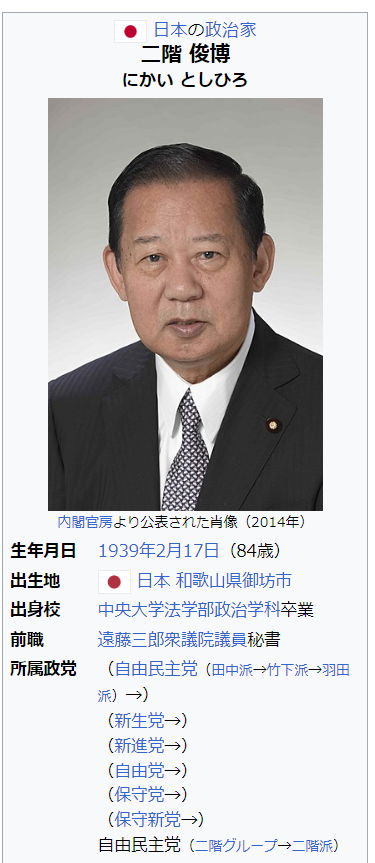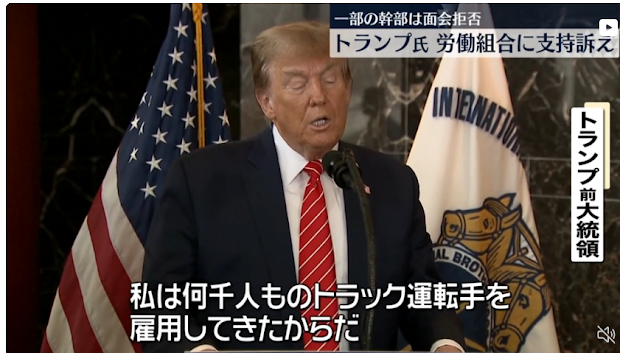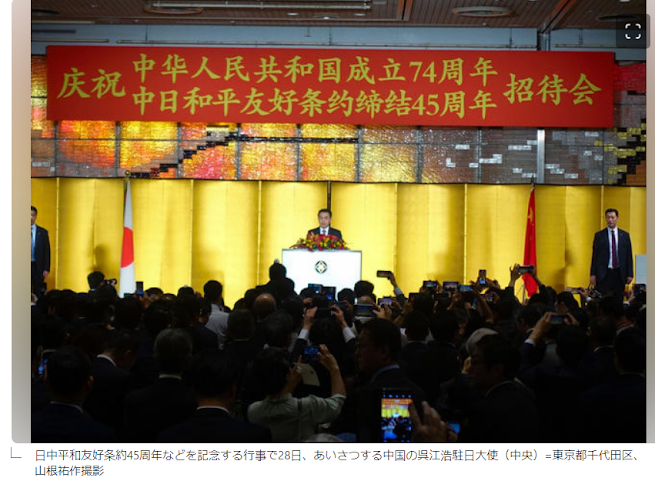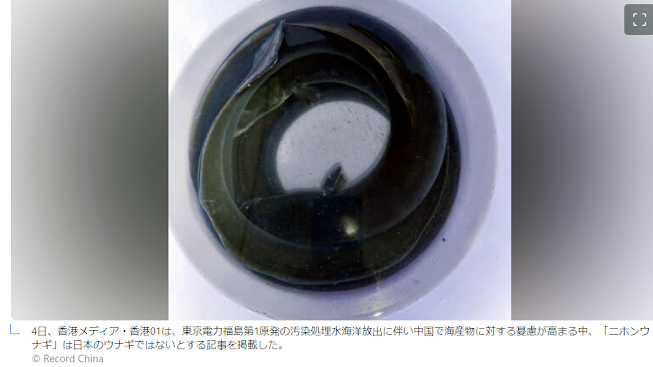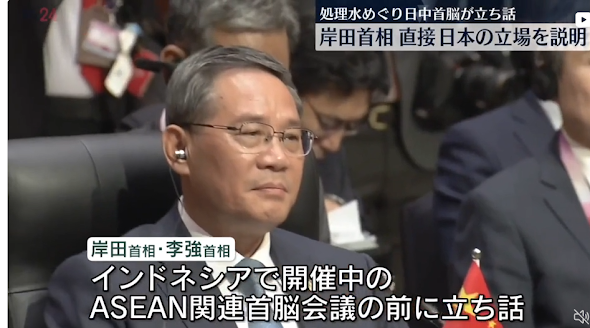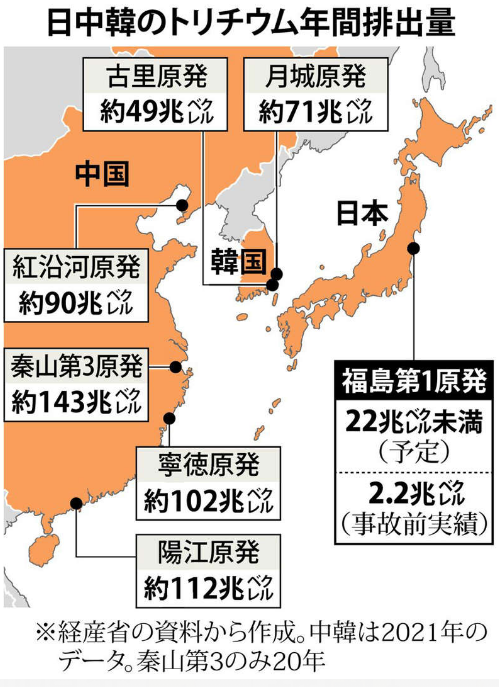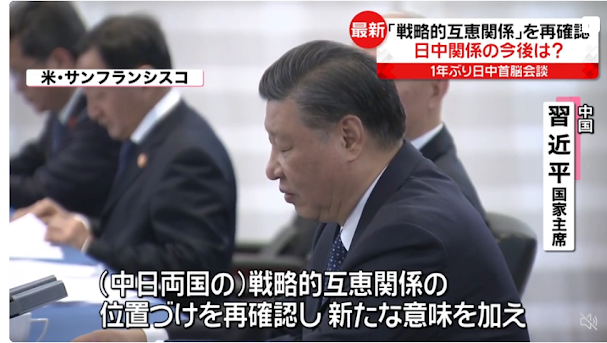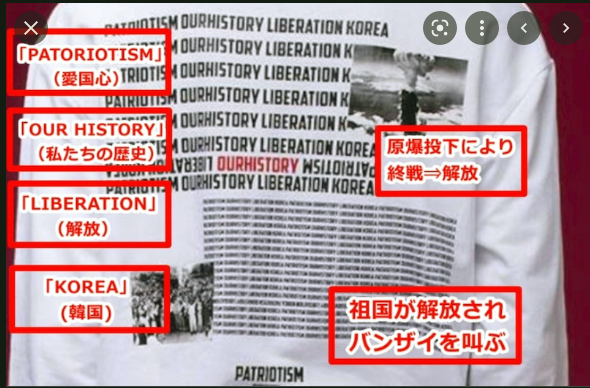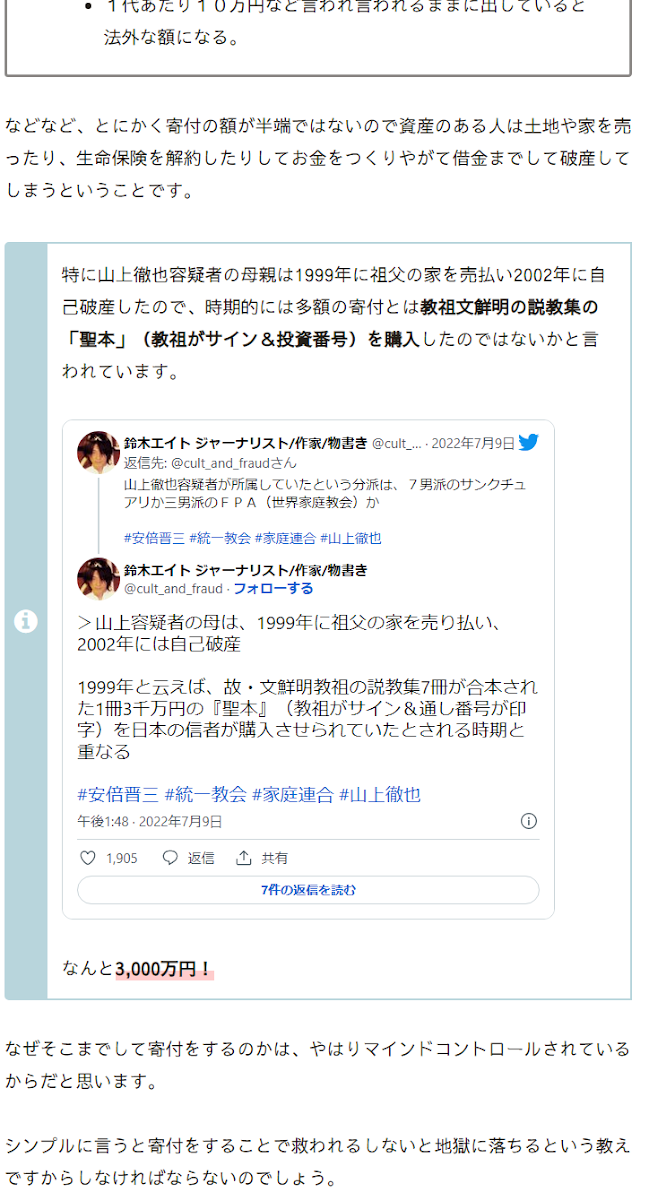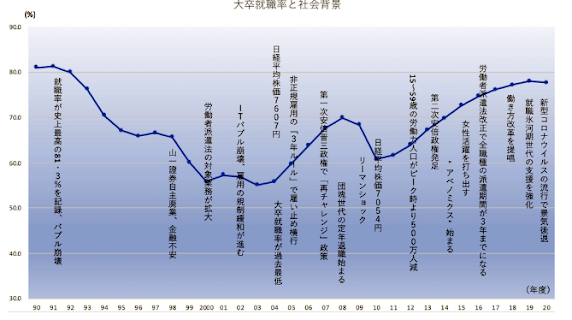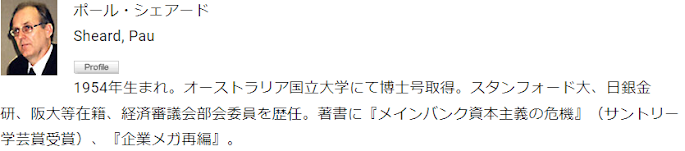法案の提案理由を御説明申し上げます。(1983年、首相当時の中曽根康弘氏、Wikipediaより)
これは自由民主党並びに社会党の共同提案になるものでありまして、両党の議員の共同作業によって、全議員の名前をもって国民の前に提出した次第であります。
(中略)(原子力の利用が各国で)進められるということは、われわれの文明に非常なる変化を予想せしめるものであって、われわれとしてもこれを等閑に付することはできないのであります。
そこで、日本に原子力国策を確立する場合において、いかなる点を考慮すべきかといいますと、われわれの考えでは、まず国策の基本を確立するということが第一であります。日本には有能なる科学者があり、技術者があり、技術陣があります。しかし、国策が確立されておらないようでは、有能なる学者はここに集まってきません。そこで、機構的にも予算的にも、国家が、不動の態勢をもって、全国民協力のもとに、この政策を長期的に進めるという態勢を整えることが第一であります。これによって有能なる学者をこの方向に指向させることができるのであります。
第二点は、超党派性をもってこの政策を運用して、政争の圏外に置くということであります。国民の相当数が、日本の原子力政策の推進を冷やかな目で見るということは悲しむべきことであり、絶対避けなければならないのであります。全国民が協力するもとに、超党派的にこの政策を進めるということが、日本の場合は特に重要であるのであります。
第三点は、長期的計画性をもって、しかも日本の個性を生かしたやり方という考え方であります。原子力の問題は、各国においては、三十年計画、五十年計画をもって進めるのでありまして、わが国におきましても、三十年計画、五十年計画程度の雄大なる構想を必要といたします。それと同時に、資源が貧弱で資本力のない日本の国情に適当するような方途を講ずることが必要であります。(中略)
第四点は、原子力の一番中心の問題は金でもなければ機構でもない。一番中心の問題は、日本に存在する非常に有能なる学者に心から協力してもらうという態勢を作ることであります。具体的に申し上げれば、湯川博士や朝永博士以下、日本の学界には三十前後の非常に優秀なる世界的なる学者が存在いたします。これらの有能なる学者が、国家のために心から研究に精を出してもらうという環境を作ることが、政治家の一番重要なことであります。
そのようなことは、学者の意見を十分取り入れて、この原子力の研究というものが、日本の一部のために行われておらない、一政党の手先でもなければ、財界の手先でもない、全日本国民の運命を開拓するために国民的スケールにおいてこれが行われておるという態勢を作ることが一番大事な点であります。このような点にわれわれは機構その他についても十分配慮した次第であります。
第五点は、国際性を豊かに盛るということであります。原子力の研究は、各国におきましてはみな国際的な協力のもとに行われております。(中略)
第六点は、日本の原子力の問題というものは、広島、長崎の悲劇から出発いたしました。従って、日本国民の間には、この悲しむべき原因から発しまして、原子力に対する非常なる疑いを持っておるのであります。このような国民の誤解を、われわれはしんぼう強く解くという努力をする必要があると思うのであります。広島、長崎の経験から発した国民が、原子力の平和利用や外国のいろいろな申し出に対して疑問を持つのは当然であります。従って、政治家としては、これらの疑問をあくまで克明に解いて、ただすべきものはただして、全国民の心からなる協力を得るという態勢が必要であります。
しかし、すでに、外国においては、原子力はかっては猛獣でありましたけれども、今日は家畜になっておる。遺憾ながら日本国民はまだこれを猛獣だと誤解しておる向きが多いのです。これを家畜であるということを、われわれの努力において十分啓蒙宣伝をいたし、国民的協力の基礎をつちかいたいと思うのであります。
この基本法案を総合的基本法としました理由は、日本の原子力政策の全般的な見通しを国民の各位に与えて、燃料の問題にしても、放射線の防止にしても、原子炉の管理にしても、危険がないように安心を与えるという考慮が第一にあったのであります。日本の原子力政策のホール・ピクチャーを国民に示して、それによって十分なる理解を得るというのが第一の念願でありました。(中略)
日本の現在の国際的地位は戦争に負けて以来非常に低いのでありますが、しかし、科挙技術の部面は、中立性を保っておりますから、そう外国との間に摩擦が起ることはありません。われわれが国際的地位を回復し、日本の科学技術の水準を上げるということは、原子力や科学によって可能であると思うのであります。(中略)原子力の熱を完全にとらえて原子炉文明というものが出てくれば、一億の人口を養うことば必ずしも不可能ではない、そのように考えます。
(中略)われわれが、雄大な意図をもって、二十年、三十年努力を継続いたしますならば、必ずや日本は世界の水準に追いつくことができ、国民の負託にこたえることができると思うのであります。(了)
(アゴラ研究所フェロー ジャーナリスト 石井孝明)
「過激パーティー(和歌山県で開催された党青年局近畿ブロック会議の後に〝過激ダンスショー〟が開かれていた)」に参加した中曽根康隆議員のパリピ半生「国際線CAらと西麻布でエステサロン経営」華麗なる人脈も支援者は落胆
2024年3月13日
「歴史を勉強しなさい。浮かれている場合ではない」──かつて、こうした言葉を偉大な祖父から聞いた“孫”は今、何を思うのだろうか。昨年2023年11月、自民党議員らが行った懇親会での過激パーティーが問題になっている。懇親会は和歌山市内のホテルで同県連主催の「自民党青年局近畿ブロック会議」後に開かれ、自民党の藤原崇衆院議員(40)、中曽根康隆衆院議員(42)や地方議員らが参加。関係者によると会合後の懇親会において、露出度の高い衣装を着た女性ダンサーによるダンスショーが行われたという。また、一部の参加者が口移しでチップを渡したことなども報じられている。
自民党はこれを受けて2024年3月8日、会合および懇親会に出席していた藤原、中曽根両議員が同党青年局の役職(それぞれ局長と局長代理)を役員辞任することを発表。2人はダンサーの体に接触していないと発言しているが、問題となっている懇親会に不適切な内容があったとして、責任をとる形となった。
「慶應ボーイ」から「政界のプリンス」へ
今回、自民党青年局のポストを降りることとなった中曽根氏といえば、第71〜73代総理大臣だった中曽根康弘氏の孫としてその名が知られている。父にあたる中曽根弘文氏(78)も現職で参議院議員を務めており、中曽根康隆氏は若くして自民党のホープと期待されてきた。
「政治一家」に生まれた中曽根康隆氏だが、その経歴も華々しい。幼少期に慶應義塾幼稚舎に入ると付属の中高を経て、慶應義塾大学法学部を卒業。同級生に人気グループ「嵐」の櫻井翔がいることでも知られ、生粋の「慶應ボーイ」として育ってきた。高校、大学時代にはゴルフ部に所属し、大学では副将を務めた過去もある。
慶應義塾大学卒業後は米コロンビア大大学院に進学し、国際関係学を専門に学んだ中曽根康康隆氏。大学院を修了するとJPモルガン証券に勤務した。父・中曽根弘文氏の私設秘書を4年間務めた後に、2017年の総選挙に自民党から比例北関東ブロック単独で出馬し初当選。その後2021年に群馬1区から再選を果たした。
プライベートでも“やんごとなき”議員
元首相中曽根弘文氏の“イケメン孫”として脚光を浴び、2021年の第2次岸田内閣では防衛大臣政務官として政権を支えた。しかし、とある支援者は「中曽根康隆氏には前々からプライベートに不安要素があった」と語る。
「以前ガーシーこと東谷義和さんによって、中曽根康隆氏が女性を肩で抱いている写真がネット上で拡散されたことは記憶に新しいと思います。この話が本当かどうかはわかりませんが、彼の周りでは『火のないところに煙は立たないだろう』と囁かれていて、今回の過激パーティーでの一件も『またか』といった印象を持つ方も多いのではないでしょうか」
証券会社時代の康隆氏を知る知人も、彼についてこう話す。
「勤務していた外銀を辞めてお父さんの私設秘書になるくらいの頃でしょうか、ノリのいい彼は同僚の友達と西麻布でエステサロンを経営していました。そのサロンは当時、国際線CAが代表を務めていて、康隆さんは取締役としてそれを支援する形で経営に加わったと聞いています。
仕事柄もあってか、彼の周りには大手の商社マンやCA、起業家などハデめな友人が常にいて、パリピな印象です。弁がたつし、男女関係なくモテるタイプなので政治家になってからも噂が立つのはしょうがないと思っていました。奥さんも社長令嬢ですし、公私問わずまさに“やんごとなき一族”といった感じですね」
冒頭にある「浮かれるな」という言葉は祖父・中曽根康弘元首相が、初当選した中曽根康隆氏に戒めとして言い放った一言だ。地に足をつけて政治をしなければ、天国にいる祖父も浮かばれないことだろう。
迷走する子育て支援金「実質負担ゼロ」 加藤鮎子少子化担当相の「あの…」「えーと…」答弁は政権の新たな火種に
2024年3月13日
政府が少子化対策の財源とする「子ども・子育て支援金制度」をめぐる政府の説明が迷走している。「実質負担ゼロ」と強調してきたが、説明は二転三転。野党の追及を受けパニック気味になった少子化対策担当大臣の加藤鮎子氏の答弁もあいまって、岸田文雄首相肝いりの「次元の異なる少子化対策」は、裏金問題に続く政権の火薬庫になりかねない状況だ。
支援金制度は、企業や個人が支払う公的医療保険に上乗せして国民から拠出金を徴収し、財源に充てる仕組みだ。政府が徴収する額は1兆円。制度開始の2026年度は6000億円からスタートして段階的に引き上げる、とされている。
3月12日の記者会見で法案審議の進め方について問われた加藤氏は手元のメモに目をやりながら、「社会保障制度の改革等によって歳出改革効果を生じさせ、その範囲内で支援金制度を講じる」と述べ、「全体として実質的な追加負担は生じない」とあらためて強調した。
支出を減らし、本来ならば相当分の医療保険料の減額に充てられる分を「支援金」に回すから、保険料を支払う国民に新たに負担が生じるわけではない、という説明だ。だが、社会保障改革がそんな首尾よく進む保障があるわけもなく、実質負担増になる疑念は膨らむばかりだ。
「未婚化の原因」を問われ、資料を探して「少子化の原因」を読み出す
実際、政府の説明はコロコロ変わるのだ。2月6日の衆議院予算委員会では岸田氏は「粗い試算」と断わりながら「(徴収総額が1兆円に達する)2028年度には、加入者1人あたりの拠出額は月平均500円弱」と答弁したが、加藤氏がその前段階の2026年度と2027年度の数字(それぞれ300円弱と400円弱)を明らかにしたのは8日も経過した2月14日になってからだ。
さらに8日後の2月22日の加藤氏は、1人あたりの負担額が「支援金の拠出が月額で1000円を超える人がいる可能性はありうる」と答弁して議場は騒然。加入する医療保険制度や所得に応じてどれだけの幅が生じるのか、その見通しもなかなか明らかにならない。
当の担当大臣、加藤氏の“力量”にも疑問符がついている。3月4日の参院予算委員会で未婚化の原因を問われた加藤氏は、「あの……未婚化の原因につきましては、えーと……」と、約30秒間にわたって沈黙。少子化対策の前提となる初歩的な認識すら自分の頭の中になかったのか、答弁席で資料から該当の部分を探し続けた。
しかも、「見つけた」とばかりに読み上げ始めたのは、なんと「未婚化の原因」ではなく、「少子化の要因」。答弁資料に列挙された「経済的な不安定性」「出会いの機会の減少」など7つも8つも棒読みされては負担を強いられる国民はたまったものではない。
招致段階から建設費がはね上がった「国立競技場問題」の再現に
加藤氏は宏池会会長だった加藤紘一の三女。岸田氏にしてみれば宏池会の血の濃い派内の“身内”に肝いり政策の実行役を委ねたかたちだが、国民負担をめぐる側近閣僚の迷走は、政権の致命傷につながることがある。
たとえば第2次安倍晋三内閣で東京五輪のメーン会場だった新国立競技場の建設計画の実行を委ねられた下村博文・文部科学大臣(当時)。招致段階では1300億円だったものが、下村氏の担当下で建設費はことあるごとにはね上がり、最終的には2520億円まで膨れ上がって批判が集中した。土壇場の2015年7月、安倍氏自ら裁定して白紙に戻したが、直後の8月の内閣支持率は、最低の37%(NHK)まで落ち込んだ。
奇しくも「政治とカネ」をめぐる問題で、岸田内閣は内閣発足以来の支持率低迷を続ける。新たな側近の火種は、政権の致命傷ともなりかねない雲行きだ。
リニア技術も剽窃された可能性 太田文雄(元防衛庁情報本部長)2019.05.27 (月)
中国国営の新華社通信は5月23日「中国が最高時速600キロのリニアモーターカーのプロトタイプ(原型モデル)を発表した(盗んだ技術で世界初)」と伝えた。中国は独自の開発技術だとしているが、本年2月28日の国基研「月例研究会」で自民党の萩生田光一幹事長代行は「日本のリニア新幹線の技術者がごっそり中国に引き抜かれてしまった」と語っていた。新幹線同様、中国はリニアモーターカーについても日本の技術を剽窃して開発を進めている可能性が強い。
●止まらぬ日本技術者の引き抜き
新華社によれば、リニアは今年の後半に稼働実験に入り、2020年から生産体制に入って2021年に総合的な実証が行われると言う。
日本のリニア新幹線が品川—名古屋間で開業するのは2027年である。日本のリニアは実験走行で時速603キロの世界最速を記録している。中国リニアの時速600kmは、それに匹敵する。
嘗て、日本の新幹線技術が川崎重工など日本の企業連合から、中国に技術供与されたが、中国は、それを独自に開発した高速鉄道システムとして、より安い価格でインドネシア等に輸出契約を結んでいる。原子力発電技術についても、三菱重工業、東芝、日立から中国に移転され、本家の日本では原子力発電技術が途絶えようとしている。
技術者にしてみれば、自分たちの技術が具現化され、しかも高い給料で雇われれば、相手がどこであろうと喜んで技術移転に協力してしまうであろう。しかし、その結果日本の海外における競争力は失われて行くのだ。
●技術移転強要には断固たる姿勢を
在中国の欧州連合(EU)商業会議所は20日、欧州企業が中国で技術移転を強要されるケースが増えているとする報告書を纏めている。また、今年の1月に米議会では中国の技術盗用を防止する組織を設置するための法案が、民主党のマーク・ワーナー、共和党のマルコ・ルビオ両上院議員の超党派で提出されている。
日本の場合、こうした技術移転の強要に対抗する法律を作成するとすれば経済産業省になる。2009年の第171回通常国会では、「外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律」と「不正競争防止法の一部を改正する法律」が成立したが、これは筆者もメンバーであった「技術情報等の適正な管理の在り方に関する研究会」の成果であった。
日本は、米中貿易摩擦による経済の減速といった短期的な視野ではなく、長期的な見地から中国の知的財産盗取や技術移転強要に対して厳しい態度を示している米トランプ政権を支持していくべきではないか。
中国が警戒する日本のリニア 狙いはその技術か?
2014.10.03 春日幸和
中国が日本のリニアを狙う十分な理由
鉄のレールと車輪で走行する粘着式の鉄道では、2007年にフランスのTGVが574.8km/hという記録を出していますが、これはあくまで特殊条件下におけるテスト走行です。基本的にこうした粘着式の鉄道は速度が高くなるにつれレールと車輪のあいだに作用する摩擦力が低下し、加速が難しくなります。
だからこそ日本は、摩擦力に頼らず高速運転できる磁気浮上式の「超電導リニア」を開発しました。つまり粘着式の鉄道で中国が速度向上を図っても、大きなブレイクスルーがない限り、速度でリニアに勝てる可能性は低いのです。磁気浮上式の「トランスラピッド」についても、先述の通り先行きは不透明です。
日本のリニア開発は1962(昭和37)年にスタート。写真は1977(昭和52)年に製造され、当時世界一の517km/hを記録したML500。
そのため中国は、日本の「超電導リニア」技術導入を試みる可能性があります。
21世紀初め、中国が粘着式の高速鉄道を走らせるにあたって、日本から東北新幹線「はやて」などに使われていたE2系新幹線電車が中国に供与され、2007年より走り出しました。しかし中国はその後、高速鉄道技術を国産化したと主張。世界市場へ展開しようとしています。「超電導リニア」についても、同じような筋書きを考える可能性がありえます。
しかし「超電導リニア」開発に深く関わるJR東海は、新幹線技術は国内メーカーと国鉄、JRの技術陣による「汗と涙の結晶」とし、中国への新幹線技術供与については「国を売るようなものだ」と反対していました。
またJR東海の葛西会長は2014年4月、中国に「超電導リニア」を販売することは「技術を投げ売りするようなものだ」という考えを示しています。しかし台湾へ輸出することについては、「ビジネスとして成立すると信じられる」と可能性を示しました。JR東海は技術流出を警戒し、取引先における中国人社員の存在に神経を尖らせているとの報道も2011年に行われています。
世界で20兆円規模とも言われる高速鉄道市場。そこで日本と中国が戦うことになるのは疑いのないところでしょう。また「超電導リニア」の技術は空母から航空機を発艦させるカタパルトなどへ転用できる可能性もささやかれているだけに、その意味でも「超電導リニア」の扱いには十分な慎重さが必要だと思われます。
【了】
リニア新幹線技術者が中国に引き抜かれた!|湯浅博 2020年08月26日 公開
湯浅博(13) 月刊『Hanada』(68)
衝撃の事実あり! 中国の日本企業に対する知的財産侵略はどんどん進行しており、そのターゲットにはあのJR東海も入っていた。中国が狙った技術とは……。
「日本の宝」が中国に奪われている!
JR東海のリニア新幹線に携わる約30人の日本人技術者が引き抜かれた――そんな驚愕の事実を書いたのは、産経新聞特別記者で国家基本問題研究所主任研究員の湯浅博氏。
現在絶賛発売中の月刊『Hanada』2020年10月号に掲載された「自制が効かない『手負いの龍』習近平」で、湯浅氏は増長し続ける「手負いの龍」中国とアメリカの対決を、ポンペオ演説などから分析、解読していますが、その中にこういった記述があります。
レイFBI長官も、中国は技術革新への努力の積み重ねを省略して、「アメリカ企業から知的財産を盗み出し、その被害者となった企業と対抗する」と指摘する。
優秀な人材を海外から好待遇で集める「千人計画」を使って科学者を誘惑し、アメリカの知識や技術を本国に持ち帰らせようとする。
中国はたとえ機密情報の窃盗や輸出規制の対象であったとしても、手段を選ばない。盗み出した技術を駆使して製品を世界に売り込み、その技術を生み出したアメリカ企業を廃業に追い込んで市場を奪取するというえげつなさだ。
そうした例は、残念ながら日本でも散見される。日本の新幹線技術という知的財産を中国が入手し、これをそっくりマネして「中国固有の技術だ」と偽って世界に売り込んだことはよく知られている。
いま再び、JR東海のリニア新幹線に携わる一チーム約三十人の日本人技術者を高額で引き抜き、「中国製」と称するリニア新幹線を開発中だ。これらリニアの超電動、電磁技術は、そのまま軍事技術に転用が可能だという。
研究所の企画委員、太田文雄元海将によると、これらの技術が安価で連続発射可能なレールガン(電磁加速砲)や空母の電磁式カタパルト(航空機射出装置)に利用できる。やがて、そうした高度技術の兵器が日本列島に向けられる日がやってくる。
出典: https://t.co
そもそも、JR東海は中国への「技術提供」を拒んできた企業です。
2004年、川崎重工が中国鉄道省と東北新幹線「はやて」型車両の技術供与契約を結びました。しかし、この川崎重工による中国への新幹線技術の売り込みに反対してきたのが、JR東海現名誉会長の葛西敬之氏でした。
葛西氏は「中国に新幹線のような最先端技術を売ることは、国を売るようなものだ」とまで言って猛反対したたものの、川崎重工は耳を貸しませんでした。
この葛西氏の予言は的中。2011年、中国は川崎重工から技術提供を受けて開発した中国版の新幹線を「独自開発」と主張し、米国など複数の国で特許申請をしたのです。
『目に見えぬ侵略』(小社刊)の著者クライブ・ハミルトン氏に言わせると、財界エリートたちは無意識のうちに外国の主人に忠誠を尽くす行動をとることになり、「オーストラリアの主権を内側から侵食している」のですが、湯浅氏も《それは日本の経済人にもみられる傾向で、彼らは「誰よりも中国を知っている」と思い込み、政治や価値観の違いを差しはさむことを許さない》と指摘しています。
しかし、葛西氏のように、新幹線技術転用を拒否し、反対したJR東海のリニア新幹線に携わる技術者が高額で中国へと引き抜かれてしまう事実が判明。
中国の巨大市場は無視できないとしても、目先の経済利益のために、どんなに国益を喪失していることか。またチャイナマネーの恐ろしさがよくわかります。
新幹線技術の流出は どれほど日本の国益を損失させたのか
.政策提言委員・金沢工業大学客員教授 藤谷昌敏
中華人民共和国の高速鉄道は、高速化された在来線、高速鉄道用の新線とリニアモーターカーから構成されている。中国では高速列車が2007年から導入され、現在では多くの幹線で高速運転が行われているほか、建設中の高速鉄道用の路線や計画が数多く存在している。国営鉄道会社「中国鉄路」(中国国家鉄路集団有限公司)によると、2021年時点で営業中の鉄道網の総延長は約15万kmで、そのうち約4万kmが高速鉄道となっている。最終的には国内の人口50万人以上の都市を全てHSR(High-speed rail、高速鉄道)で結ぶ計画となっており、2035年までに総延長7万kmを目指している。
最大のドル箱路線は北京から上海を最速4時間28分で結ぶ京滬高速鉄道(けいここうそくてつどう)で、2019年は年間2.1億人を輸送した。中国の高速鉄道は世界最長で、日本の新幹線(約3,300km)の10倍以上の総延長4万kmを超えている。2021年は2,168km延び、さらに2025年に5万km、2035年に7万kmに延長する計画である。
一方では、国鉄の債務は6兆元(約117兆円)超と、国内総生産(GDP)比で5%程度に達する。こうした中、中国政府は21年、時速35キロ以上の高速鉄道について、路線開設などには乗客数が年2,500万人を上回る必要があるとする新基準を公表したが、人口が21年をピークに減少に転じる中、鉄道事業はますます厳しさを増しそうだ。
また、海外にも高速鉄道技術や車両を輸出し、インフラ整備や貿易促進に貢献するとともに、人民元の国際化や政治的・経済的なパートナーシップの構築を図っている。中国は、アジア、ヨーロッパ、アフリカなどの地域で高速鉄道の建設や運営に関与している。これらの地域では、交通インフラの不足や老朽化が課題となっており、中国の高速鉄道は旅客輸送や物流の効率化、安全性の向上に寄与すると期待されている。さらに中国との経済協力や技術移転による発展や雇用創出も見込まれている。
中国の高速鉄道を語る時、忘れてならないのが日本との関係である。元々、高速鉄道技術は、日本が開発したものであり、中国は日本の新幹線技術を盗用し、それを「独自開発」としてアメリカやアジアなどに高速鉄道計画の売り込みをかけていたのである。本来、新幹線技術は、日本国有鉄道(現・JR)が、1964年に東海道新幹線を開業するために開発したもので、新幹線は、従来の鉄道と全く切離して、道路との交差のないものとして設計された。
「リニア技術」漏洩恐れるJR東海が「中国人排除」
2011年8月号 BUSINESS
日本、ドイツの技術をベースに開発した高速鉄道を「自主開発」と言い張って米欧で特許取得を狙う中国のしたたかさには恐れ入るほかない。憤慨するのは、新幹線の本流を自負するJR東海だ。山田佳臣社長は6月29日の定例会見で「新幹線技術は、国内のメーカーと旧国鉄の技術陣の長きにわたる汗と涙の結晶」と訴えた。新幹線技術を中国に渡したのは川崎重工業だが、同社はJR東海から事実上、出入り禁止を食らっている。同社の葛西敬之会長はかねてからの対中警戒論者だが、その懸念が的中。JR東海は今、さらなる技術漏洩へのガードを固めている。取引先には、技術部門に中国人がいるかどうかの確認を要求。中国人社員をJR東海の担当にはつけないようにプレッシャーをかけているという。中国側は新幹線技術を自家薬籠中の物としており、JR東海が恐れるのは、虎の子のリニア技術が漏れることだ。しかし、メー ………
新幹線技術「中国移転は失敗」 いまや日本のライバルに
2017/4/22 20:51
「ずうずうしくも大ぼらを吹く」「中国の高速鉄道技術は、すでに日本の新幹線をはるかに凌駕(りょうが)している」
平成23(2011)年7月7日、中国鉄道省宣伝部長の王勇平は、中国国営新華社通信のインタビューにそう答えた。
川崎重工業などの技術供与をもとに高速鉄道を共同生産した中国の国有メーカーが、「独自の技術」として米国での特許申請を目指す動きが明らかになったことについてだ。中国政府がいわゆるパクリ疑惑に公式反論するのは異例だ。
王は「新幹線と北京-上海間の高速鉄道は、同列に論じられるレベルではまったくない」と中国の新型車両が優れていると主張してうそぶいた。
「中国は日本に技術援助したい」
■ ■ ■
王の発言は「高速鉄道の輸出」という野望をむき出しにするものだった。中国が独自開発をあきらめ、日独仏の技術導入を決めたのは、わずか13年前。だが一昨年には、インドネシアが日本の提案する高速鉄道計画を蹴り、中国案を選んだ。採算リスクまで引き受けて海外展開に突き進む中国は、日本の手ごわいライバルとなった。JR東海名誉会長の葛西敬之は「新幹線は日本の宝。中国への技術移転は大失敗だった」と移転の判断を批判する。
なぜ、虎の子の技術は流出したのか。
日本鉄道システム輸出組合専務理事の村崎勉は「高い技術力を額に入れて飾っていても仕方がない。そうした声が多かった」と振り返る。あるメーカーの幹部は「独ボンバルディアや仏アルストムの中国参入を前に、指をくわえている手はなかった」と話す。
JR東日本社長の冨田哲郎は、日本もかつて欧米の技術を学んだことを挙げ、「そうした能力が高ければ、強力なライバルに成長するのが現実」と受け止める。
■ ■ ■
新幹線とリニアの技術を持つJR東海は、米テキサス州の高速鉄道計画に新幹線で参画。ニューヨーク-ワシントン間にはリニアを売り込む。現地で投じたプロモーション費用はこれまでに50億円を上回る。
だが、葛西は言う。「新幹線を海外に売って鉄道会社がもうけるビジネスモデルは、成立しない」。海外高速鉄道プロジェクトC&C事業室長の落合克典はこう説明する。「米国で日本型新幹線やリニアが採用されれば、車両や信号システムなどのメーカーにとって販売先が大きく広がる」。量産効果による調達コストの引き下げが狙いだ。ただ、中国高速鉄道の営業距離は2万2千キロ以上で新幹線の7倍を超える。
JR東海社長の柘植康英は「われわれの強みは技術支援」としながらも「世界最高の高速鉄道としての技術、海外で通じる技術をさらに磨いていかないと、国内はもとより海外展開もおぼつかなくなる」と話す。
共助薄れ「分割」は「分断」に
4年前の平成25年1月、東京・霞が関の国土交通省。国会議事堂を望む大臣官房フロアの一室で、事務方ナンバー2の国土交通審議官、本田勝が一人の男に頭を下げた。
「JR貨物の経営基盤を固めるため、力を貸していただきたい」
相手は公益財団法人がん研究会常務理事の石田忠正。日本郵船副社長から日本貨物航空の社長に転じ、黒字化を達成した物流のプロだ。その手腕はがん研でも発揮され、長年の赤字経営を立て直していた。
JR未上場会社の全株式は国が保有し、人事には政府の意向が働く。本田は「29年4月の分割民営化30年を念頭に、未上場4社の経営にもう一段のてこ入れをしたかった」と振り返る。
JRの会長職に、生え抜きでも官僚でもない民間出身者が就くのは民営化の当初以来のことだった。
■ ■ ■
分割民営化で地域ごとに分けられた旅客6社に対し、JR貨物は線路を「借りる」形で全国を1社でカバーする。平均距離800キロに及ぶ貨物列車を一元的に運行するだけでなく、「黒字路線の稼ぎで赤字部門を維持する『過度な内部依存』を避けるため」(旧運輸省OB)だ。
平成2年度にはバブル景気で経常利益74億円を計上したが、トラック輸送に押され8年度には経常損失106億円。土地売却益で出血を食い止める「竹の子生活」となっていた。
石田は、花形の運輸部門に比べ弱体だった営業部門を強化するため、営業マン数十人を中途採用。営業戦略と列車ダイヤを一元的に担う新部署もつくった。
昨年7月、アサヒビールとキリンビールが発表した、吹田(大阪)-金沢間の貨物列車の共同輸送は「ライバル同士の協業」と話題になった。
吹田行きに比べ、金沢行きは空荷が多い。片道の貨物搭載率が低いなら、運賃を割り引いてでも顧客をつかむ。運賃設定の権限を支社に委譲した成果だった。
石田は話す。「黒字化の直接要因は、徹底した計数管理だ。それ以上に、『俺たち自身がやらなくては』という意識を全社員で共有できたことが大きい」
28年度には不動産など関連事業を除き、鉄道部門単独で黒字に転じた。ライバルであるトラック業界の人手不足を追い風に、JR5社目の株式上場を視野に捉えるまでになった。
■ ■ ■
JR各社の営業努力は、ここ数年、さまざまな形で実現しつつある。
数十万円のチケットが瞬く間に完売するなど、人気を集める豪華列車による旅行は各社が競って導入を進めている。だが、5月にデビューする東日本の豪華列車「トランスイート四季島」が北海道に上陸するのを除くと、西日本の「トワイライトエクスプレス瑞風」も、九州の「ななつ星in九州」も、ルートは自社管内だけだ。
民営化当初、会社をまたぐ在来特急は、本数を減らさない方針が徹底され、全33列車が温存された。そのうち今も残るのは唯一の寝台列車「サンライズ瀬戸・出雲」(東京-高松・出雲市)を含む計5列車のみだ。
会社の境界をまたぐ運行について関係者は「やらないわけではない。今後の話だ」と説明する。だが、その言葉には分割が定着した今、「一つの国鉄」を取り戻す難しさもにじむ。
好調のJR貨物もひとごとではない。民営化当初のルールで、旅客6社に支払う線路使用料が格安に抑えられているが、経営難のJR北海道を中心に「重い貨物列車が線路の傷みを早めている。負担を増やすべきだ」(旅客会社幹部)と不満がくすぶる。
JR貨物社長の田村修二は「線路補修コストを対等に負担すれば、当社は一気に赤字転落だ」とルール維持を訴えるが、今後の展開は不透明だ。
相互の共助関係が薄まったJR各社の関係は「分割」から「分断」の色を濃くしている。先送りされた課題が顕在化するなか、30年の節目を迎えたJR。第2の改革の時期は着実に迫っている。
(敬称略)
2023.12.27 中国経済・産業最前線 from 人民網日本語版
中国、時速600km高速リニアまもなく商用運営へ 都市圏はさらに拡大か?
日経BP中国社会課題調査チーム
中国・上海の国際空港である浦東空港と市街地の龍陽路駅の間を、時速400km以上で走り抜ける高速リニアモーターカーが商用運転を始めたのは約20年前。日本においては、いまだリニア開業の時期が明確に定まらない中で、さらに次のステージに突入しようとしている。科学技術部(省)が公式サイトを通じた発表によれば、時速600kmで走る高速リニアモーターカーのテスト路線建設プランおよび商用運営総合ソリューションの研究を進めるという。実用化になれば上海と北京を約3時間半で移動が可能になるなど、時間と距離の概念が大きく変わると期待する。(日経BP 総合研究所)
科学技術部(省)はこのほど公式サイトを通じて発表した「第14期全国人民代表大会第1回会議第2199号建議に対する回答」の中で、これから時速600kmで走る高速リニアモーターカーのテスト路線建設プランおよび商用運営総合ソリューションの研究を進めることに言及した。これより前に、2021年に山東省青島市で、時速600kmの高速リニア交通システムがラインオフしており、中国に高速リニアの総合技術とプロジェクト化能力があることが明らかになった。
時速600kmの高速リニア
「回答」で言及された高速リニアは時速400km以上に達することが可能なもので、中・低速リニアは時速100-200kmというものが多い。関連資料によれば、現在、世界で商用運営が実現した都市リニア路線は4本あり、それぞれ中国の上海リニアモデル路線、長沙リニア快速線、北京リニアS1線と、韓国の仁川空港磁気浮上鉄道となっている。
しかし、「回答」では既存のリニア路線とは異なる、時速600kmの高速リニアに言及した。国家重点研究開発計画「先進的鉄道交通」重点特定プロジェクト総合専門家チームの代表を務める北京交通大学の賈利民教授は、「時速600kmの高速リニアは高速鉄道と航空輸送の間のスピードの空白を埋めるもので、航空、高速鉄道、高速リニア、都市交通を含むスピード配置がより合理的、高効率で、柔軟かつ便利な多元的モビリティ・アーキテクチャを形成することができる」と述べた。
時間の短縮による距離の短縮
高速リニアは沿線都市の時間の短縮による距離の短縮に資する。高速リニアプロジェクトの技術チーフエンジニアを務める中国中車青島四方機車車両股份有限公司の丁叁叁サブチーフエンジニアは21年に公の場で、「実際の移動時間によって計算すると、輸送距離が1500km以内であれば、リニアが最も速い交通手段になり、移動時間を大幅に短縮でき、時間と距離に対する意識が変わる。北京から上海に行く場合、時速600kmのリニアに乗れば、乗車準備の時間を合わせても、両都市間の移動時間はわずか3.5時間ほどに短縮される。また北京・天津・河北、長江デルタ地域、珠江デルタ地域、成渝(成都・重慶)地区、長江中流都市群の『5極』とされる5つの経済圏の、距離にして2000kmのエリアが4時間で結ばれることになる」と述べている。
時間が短縮されると、発展の空間が拡大し、可能性が増える。北京師範大学政府管理研究院の副院長で、産業経済研究センターの宋向清センター長は、「都市発展のサポートという視点から見ると、高速リニアは輸送力を大幅に向上させ、物流の効率を高め、資源の配置と流動のスピードを高め、エネルギー消費と汚染排出を削減することができ、都市のイメージアップ、二炭化炭素(CO2)排出削減の目標達成をめぐる圧力の緩和、都市資源の調整能力と市場の活力の向上にプラスであり、さらに市民の移動をより円滑にすることができる」との見方を示した。
リニアの優位性が突出し、取り巻くマーケットも流れに乗って成長している。資料を見ると、中国都市リニア産業の市場規模を見ると、17年から20年まではそれぞれ42億6000万元(1元は約20.3円)、45億8000万元、49億2000万元、53億1000万元となり、年間平均成長率は7.6%だった。21年は50億9000万元に達し、22年は前年比10%増の59億元に達した。
都市圏の経済発展の可能性を切り開く
中国交通運輸協会新技術促進分科会の解筱文専門家委員は、「中国の高速鉄道建設の発展の道のりと経験を見ると、理論的に言えば、時速600kmの高速リニアの建設・運営は都市圏のために新たな経済発展の可能性を切り開き、地域の一体化発展を促進し、エリアの競争力を引き上げ、産業の高度化・トランスフォーメーションを促進し、雇用機会を生み出し、都市圏の国際競争力を高めることになる」とした。
また解氏は、「時速600kmの高速リニアは経済規模が大きく、同期性が高く、一体化した結びつきが強い『通勤化』した交通手段に利用できる。あるいは経済規模が大きく、相互補完性が高く、協調性のニーズが大きい、大型都市の間をつないで『同一都市化』させる交通手段にも、経済規模の格差が大きく、発展のバランスに対するニーズが大きい中部・西部地域中心都市間の『回廊化』した交通手段にも利用でき、大型ハブ都市または都市圏をつなぎ、高速の回廊を形成し、地域間の協同発展を促進するため利用することもができる」と述べた。(出所:人民網日本語版)
開発からわずか6年で完成したた時速600kmの中国版高速リニア交通システム。(撮影・呉慧珺)
リニア開業を遅らせた大罪。中国かぶれの知事ひとりが反対して日本復活をも遅らせていた=鈴木傾城
2024年4月5日
超電導リニアの技術は大きなイノベーションである。三大都市圏は相互に約1時間で結ばれれば、生産性の向上はより加速して、その経済的効果は計り知れないものになる。それを中国かぶれの静岡県知事である川勝平太ひとりに反対されていたことに日本の悲劇がある。(『 鈴木傾城の「ダークネス」メルマガ編 』)
リニア開通を遅らせ続けてきた川勝平太知事の辞任
静岡県の知事である川勝平太が「県庁はシンクタンク。毎日毎日、野菜を売ったり、牛の世話をしたり、モノを作ったりとかと違い、基本的に皆さんは頭脳、知性の高い方」と、現場で働く人々を見くだすような発言をして大批判を浴びた。
この知事は以前から「県議会にはヤクザ、ゴロツキが多い」とか「顔のきれいな子は、賢いことを言わないときれいに見えない」とか、「御殿場市はコシヒカリしかない。ただ飯だけ食って、それで農業だと思っている」とか、とにかく暴言・失言のオンパレードだった。
さすがに、今回の職業差別的な発言には日本中があきれ果てて大炎上し、とうとう2024年4月2日には突如として辞職を表明することになった。
240405_Linear_eye
リニア開業を遅らせた大罪。中国かぶれの知事ひとりが反対して日本復活をも遅らせていた=鈴木傾城
2024年4月5日ニュース
超電導リニアの技術は大きなイノベーションである。三大都市圏は相互に約1時間で結ばれれば、生産性の向上はより加速して、その経済的効果は計り知れないものになる。それを中国かぶれの静岡県知事である川勝平太ひとりに反対されていたことに日本の悲劇がある。(『 鈴木傾城の「ダークネス」メルマガ編 』)
【関連】インドの急成長を日本人はまだ知らない。投資家は未来の「デジタル超大国」に賭けたほうが確実性が高いと言える理由=鈴木傾城
リニア開通を遅らせ続けてきた川勝平太知事の辞任
静岡県の知事である川勝平太が「県庁はシンクタンク。毎日毎日、野菜を売ったり、牛の世話をしたり、モノを作ったりとかと違い、基本的に皆さんは頭脳、知性の高い方」と、現場で働く人々を見くだすような発言をして大批判を浴びた。
この知事は以前から「県議会にはヤクザ、ゴロツキが多い」とか「顔のきれいな子は、賢いことを言わないときれいに見えない」とか、「御殿場市はコシヒカリしかない。ただ飯だけ食って、それで農業だと思っている」とか、とにかく暴言・失言のオンパレードだった。
さすがに、今回の職業差別的な発言には日本中があきれ果てて大炎上し、とうとう2024年4月2日には突如として辞職を表明することになった。
ただ、この辞任に関して、日本国民をさらに激怒させたのは、辞任の理由に「リニアの問題が大きな区切りを迎えた」と、関係ないことを突如として述べたことだった。
この知事はリニア開業にも「静岡県には何のメリットもない」と県内のトンネル工事のスタートに待ったをかけ続けて工事を遅らせ、JR東海が当初計画していた2027年の名古屋-東京間の開業を断念させていた。
リニア中央新幹線は東京と名古屋をわずか40分で結ぶ国家プロジェクトである。この知事ひとりがそれをぶち壊していた。この知事はあたかもそれを誇るかのように「大きな区切り」と述べているのだから、ここでもまた炎上している。
ただ、川勝平太は静岡県民が選挙で選んだ知事であり、知事に期待していたのは「リニア問題」であったのは留意する必要がある。日本国民はリニア開通を心待ちにしているのだが、静岡県民はそうではないという複雑な事情がある。
国家主席・習近平を礼賛していた川勝平太
静岡県民が憂慮していたのは、川勝平太が主張する「下流域の利水に支障があり、県民の生死にかかわる」という点であった。「大井川は毎年のように水不足で悩まされている」と川勝平太は主張していた。
それに対して、県企業局は真っ向から反論しており「大井川広域水道が水不足に悩まされたことはない。給水に十分な余裕がある」と説明した。
そうすると川勝平太は「南アルプスは62万人の命の水を育む。命の水を守らなければならない」と言い出した。実はそれも川勝平太の虚偽であり、影響を受けるのは26万人であり、その26万人にしても「給水に十分な余裕がある」ので問題ないというのが事実であった。
環境保全を理由に川勝平太を支持していたNPO団体の記者ですらも、川勝平太の「命の水」の主張がおかしいことを『知事失格』という書籍で糾弾している。
要するに、川勝平太は嘘でも何でも科学的根拠の薄いことを主張して、それを静岡県民に吹聴し、「静岡県には何のメリットもない」といって、ひたすら工事を遅らせていただけだった。
中国もまた60兆円規模で上海市〜寧波市のリニア開発を目指しているのだが、開業は2035年だ。そのため、リニアの技術は世界に輸出できる国家的産業であり、中国はどうしても日本のリニア開通を断念させたいと考えている。
川勝平太は中国の国家主席・習近平にも会って会談している。そんな中で、日本のリニア開通を断念させることで何らかの密約があったのではないかと噂されているのだった。
リニア開業を遅らせた大罪。中国かぶれの知事ひとりが反対して日本復活をも遅らせていた=鈴木傾城
2024年4月5日ニュース
中国もまた60兆円規模で上海市〜寧波市のリニア開発を目指しているのだが、開業は2035年だ。そのため、リニアの技術は世界に輸出できる国家的産業であり、中国はどうしても日本のリニア開通を断念させたいと考えている。
川勝平太は中国の国家主席・習近平にも会って会談している。そんな中で、日本のリニア開通を断念させることで何らかの密約があったのではないかと噂されているのだった。
中国に媚びるようなことばかりを約束する知事
2019年11月24日、川勝平太は王毅(ワンイー)国務委員兼外相と会談しているのだが、ここでは「静岡県は中国との経済・文化・観光など幅広い分野での交流を推進しており、今後も両地域の発展に貢献したい」とか、「習主席の静岡訪問を要請したい」と、まるで静岡県が中国の属州で、自分はその家来であるかのように媚びている。
さらに、川勝平太は2023年2月13日には孔鉉佑駐日中国大使と会見を行っているのだが、どうだったのか。
そこでも「静岡県が中国との交流を一段と強化する」とか、「静岡県は浙江省および中国各界との交流と協力を強化する」とか、「両国の青少年を引きつける良質なプラットフォームを築く」と、中国に媚びるようなことばかりを約束している。
川勝平太の中国礼賛が筋金入りなのは、習主席から「中国友好交流提携賞」を授与されているのを見てもわかる。
この賞は、中国のために献身的に活動する人間に与えられる。つまり、これをもらった瞬間にその人物は中国に心酔して活動する人間であるというのがわかる。川勝平太はそれを授与されているのだ。
中国は自分たちを利する人間を徹底的に懐柔して自分の手足のように操り、自分たちに敵対する人間は徹底的に攻撃して社会的抹殺をする体質がある。中国と一線を引かずに、まるで家来のように媚びる知事がいかに危険なのかは誰でもわかる。
川勝平太が「中国の工作員ではないか」と噂が立つのは、そういうところからきているようにも見える。
そのような背景を見ながら、4月2日の「リニアの問題が大きな区切りを迎えた」という言葉を聞くと、「(中国にいわれた通りリニア開通を徹底的に遅らせることに成功したので)リニアの問題が大きな区切りを迎えた」と捉える人がいるのも無理もないように見える。
日本の未来は中国かぶれの知事ひとりに反対されていた
静岡県民以外でも「飛行機もあれば新幹線もあるのにリニアを推進する意味があるのか?」という人もいる。
リニア開業を遅らせた大罪。中国かぶれの知事ひとりが反対して日本復活をも遅らせていた=鈴木傾城
2024年4月5日ニュース
中国もまた60兆円規模で上海市〜寧波市のリニア開発を目指しているのだが、開業は2035年だ。そのため、リニアの技術は世界に輸出できる国家的産業であり、中国はどうしても日本のリニア開通を断念させたいと考えている。
川勝平太は中国の国家主席・習近平にも会って会談している。そんな中で、日本のリニア開通を断念させることで何らかの密約があったのではないかと噂されているのだった。
中国に媚びるようなことばかりを約束する知事
2019年11月24日、川勝平太は王毅(ワンイー)国務委員兼外相と会談しているのだが、ここでは「静岡県は中国との経済・文化・観光など幅広い分野での交流を推進しており、今後も両地域の発展に貢献したい」とか、「習主席の静岡訪問を要請したい」と、まるで静岡県が中国の属州で、自分はその家来であるかのように媚びている。
さらに、川勝平太は2023年2月13日には孔鉉佑駐日中国大使と会見を行っているのだが、どうだったのか。
そこでも「静岡県が中国との交流を一段と強化する」とか、「静岡県は浙江省および中国各界との交流と協力を強化する」とか、「両国の青少年を引きつける良質なプラットフォームを築く」と、中国に媚びるようなことばかりを約束している。
川勝平太の中国礼賛が筋金入りなのは、習主席から「中国友好交流提携賞」を授与されているのを見てもわかる。
この賞は、中国のために献身的に活動する人間に与えられる。つまり、これをもらった瞬間にその人物は中国に心酔して活動する人間であるというのがわかる。川勝平太はそれを授与されているのだ。
中国は自分たちを利する人間を徹底的に懐柔して自分の手足のように操り、自分たちに敵対する人間は徹底的に攻撃して社会的抹殺をする体質がある。中国と一線を引かずに、まるで家来のように媚びる知事がいかに危険なのかは誰でもわかる。
川勝平太が「中国の工作員ではないか」と噂が立つのは、そういうところからきているようにも見える。
そのような背景を見ながら、4月2日の「リニアの問題が大きな区切りを迎えた」という言葉を聞くと、「(中国にいわれた通りリニア開通を徹底的に遅らせることに成功したので)リニアの問題が大きな区切りを迎えた」と捉える人がいるのも無理もないように見える。
日本の未来は中国かぶれの知事ひとりに反対されていた
静岡県民以外でも「飛行機もあれば新幹線もあるのにリニアを推進する意味があるのか?」という人もいる。
これについてはJR東海が『平成24年(5月~9月)、平成25年(5月~7月)の説明会における主なご質問』にて、以下のように述べている。
Q:中央新幹線を建設する意義・目的を教えて下さい。
・東海道新幹線は開業後48年が経過しており、将来の経年劣化や大規模災害に対する抜本的な備えとして、中央新幹線を早期に実現させることにより、東京・名古屋・大阪を結ぶ日本の大動脈輸送の二重系化が必要です。
・中央新幹線は、超電導リニアにより実現していきますが、超電導リニアの高速性による時間短縮効果によって、日本の経済及び社会活動が大いに活性化することが期待できると考えています。
・また、中央新幹線開業後の東海道新幹線については、東京・名古屋・大阪の直行輸送が相当程度中央新幹線に移り、現在の東海道新幹線の輸送力に余裕ができることを活用して、「ひかり」「こだま」の運転本数を増やすなど、現在とは異なる新しい可能性を追求する余地が拡大します。
超電導リニアの技術は大きなイノベーションである。三大都市圏は相互に約1時間で結ばれれば、生産性の向上はより加速して、その経済的効果は計り知れないものになる。
スピードは効率化を促し、効率化は生産性の向上をもたらし、生産性の向上は人々の生活をより豊かなものにする。
交通政策審議会は東京・大阪間の開業時点における1年あたりの便益は約7100億円、全国の生産額増加は約8700億円と推計している。時間短縮による移動の利便性向上、物流効率化、企業立地の活性化などを考えると、経済的効果は約8700億円どころではないはずだ。
リニア開通は日本を活性化させる歴史的な転換点になり得る可能性さえ秘めている。それは日本の輝かしい未来でもあったのだ。それを中国かぶれの知事ひとりに反対されていたことに日本の悲劇がある。
プロフィール:鈴木傾城(すずき けいせい)
作家、アルファブロガー。政治・経済分野に精通し、様々な事件や事象を取りあげるブログ「ダークネス」、アジアの闇をテーマにしたブログ「ブラックアジア」を運営している。
中国リニアが初の「浮上運行」成功、日本は「2027年開業」困難で「日本人の夢をドブに捨てる気か」SNSで集まる危惧の声
2023年4月4日
中国の鉄道車両大手、中国中車傘下の中車長春軌道客車は、高温超電導リニアの全要素試験システムの、初の浮上運行に成功したと発表した。4月4日、中国国営の新華社通信が報じた。今回の成功により、超電導リニア交通システムの事業化のための基礎が築かれたという。
今回の運行では、超電導リニアシステムのコア技術が十分に検証された。将来的には時速600kmに達する見込みとも報じられている。
中国リニアが初の浮上運行に成功したことで、日本のSNSでは、先を越されることを危惧する声が上がっている。
《かなりのスピードで開発が進んでいる様子。日本のリニア中央新幹線はこれより早く開業できるだろうか?》
《日本がリニア新幹線の建築に手こずっている間に、着々と中国のキャッチアップが進んでいる》
《あー、これでリニアも中国に先を越させるんかな?》
《国交省さん、静岡県さん、JRの60年以上に亘る苦労と日本人の夢をどぶに捨てる気ですか?》
日本のリニア中央新幹線は、最高時速500kmで、東京と名古屋間を最速40分で結ぶ。名古屋までの区間は2027年開業予定とされている。
だが、静岡県の川勝平太知事が リニア南アルプストンネル静岡工区での着工許可を認めないため、工事は大幅に遅れている。
「取水抑制案が工事の前提であるかの如くにとらえられているのは、違います。有識者会議における議論、47項目すべての解決を流域住民が了解するまでは、工事うんぬん、ということはまだ言えないと、私は思っています」
3月28日の定例記者会見で、川勝知事はこう述べ、議論が進みつつある「田代ダム案」にクギを刺した。
「田代ダム案」とは、リニア新幹線のトンネル工事における、水の県外流出対策。大井川上流にある田代ダムからは、山梨県側に大量の水が送られ、東京電力の発電に使われている。静岡県が主張する「水の全量戻し」に対応するため、送られる水の量を抑制するもので、JR東海が提案している。
3月27日には、大井川流域の市町の首長らが会合に出席。JR東海から「田代ダム案」の説明を受けた。この会合では、出席した市町が、JR東海と東京電力が本格的な協議に入ることを大筋で合意。島田市の染谷絹代市長は会合後、「田代ダムの取水抑制案についてはほぼ全員が了解をした。『少し待った』というのは県だけだった」と、取材に応じている。
4月3日、山梨県の長崎幸太郎知事は定例記者会見で、リニア中央新幹線の2027年の開業予定について「極めて困難と言わざるを得ない」との見解を示した。
静岡県が静岡工区の着工に反対していることについて、「静岡の皆さんに、リニアの十分なイメージを持っていただける材料が届いていないのではないか」と言及。そのうえで「膠着状態から移れるよう、貢献する」と話し、沿線自治体でつくるリニア中央新幹線建設促進期成同盟会で、山梨県として、全線開通に向けた取り組みの促進のため、働きかけていくとした。
日本と中国との地形の違いや、中国のリニアがあくまで実験路線であることから、日本と中国のリニアを単純に比較できない、という声もある。だが、このまま静岡県が工事反対を続けたら……。リニア高速鉄道で「世界初」の開業を果たすのは、日本か、中国か。
JR東海 リニア中央新幹線の2027年開業断念へ 静岡県着工認めず
2024年3月29日 17時37分
静岡県が着工を認めていない「リニア中央新幹線」について、JR東海は、国の専門家の会議で目指してきた2027年の開業を断念する方針を明らかにしました。
会社では静岡での工事には10年程度かかるとしていて、仮に今すぐ着工できたとしても開業は2034年以降になる計算です。
リニア中央新幹線をめぐっては、静岡県が環境に対する影響が懸念されるなどとして着工を認めていません。
このため、JR東海は東京・品川と名古屋を結ぶ区間について、目指してきた2027年の開業は難しいという見解をこれまでに示していて、去年12月には、「2027年」としてきた開業時期を「2027年以降」に修正していました。
こうした中、JR東海の丹羽俊介社長は29日、国土交通省で開かれた専門家の会議の中で「2027年の名古屋までの開業は実現できる状況にはない」と述べ、2027年の開業を断念する方針を明らかにしました。
静岡での工事に着手できないまま、工事契約の締結から6年4か月が経過しているためだとしています。
会社では工期の短縮は難しく、静岡での工事には10年程度かかるとしていて、仮に今すぐ着工できたとしても開業は2034年以降になる計算です。
会議のあと、取材に応じた丹羽社長は「1日でも早く着工できるよう全力を尽くしたい。地域の方々の理解を得られるように双方向のコミュニケーションを大切に真摯(しんし)に取り組んでいく」と述べました。
JR東海 丹羽社長「一日でも早く静岡工区の着工できるよう全力」
JR東海の丹羽俊介社長は会議の終了後、記者団の取材に応じ、「残念ながら、品川ー名古屋間の2027年の開業は実現できない。静岡工区の着工の遅れが開業の遅れに直結するものなので、一日でも早く静岡工区を着工できるように全力を尽くしてまいりたい。地域の方々の理解を得られるように双方向のコミュニケーションを大切に真摯(しんし)に取り組んでいく」と述べました。
官房長官「自治体との対話促すなど 早期開業へ環境整備進める」
林官房長官は午後の記者会見で「引き続きJR東海に対し、早期開業に向けた努力を促すとともに、JR東海と静岡県の協議の状況を確認しつつ、静岡県をはじめとする関係自治体との一層の対話を促すなど、品川ー名古屋間の早期開業に向けた環境整備を進めていきたい」と述べました。
岐阜 古田知事「早い時期での開業目指していただきたい」
リニア中央新幹線が通る予定となっている岐阜県の古田知事は「本日、JR東海から静岡工区の事業計画について連絡があり、本年直ちに工事着手したとしても開業まで10年はかかるとのことでありました。その結果、当初の計画の2027年から大幅に遅れることとなり、誠に残念であります。国とJR東海におかれては引き続き課題を一つ一つ丁寧に解決して品川・名古屋間のできるだけ早い時期での開業を目指していただきたい」などとするコメントを出しました。
中国広州 高速リニア建設計画、
現在、中国の時速600キロの超電導高速リニアはすでに完全に中国独自の知的財産権を持つ工程技術と完全に中国独自のプラント技術を持ち、・・・・
News2024年06月12日
中国南部・広州市政府弁公庁がこのほど発表した『広州市総合立体交通網計画(2023~2035年)』によると、広州市では他の超大都市との間を結ぶ高速磁気浮上式鉄道の配置と実験用線路建設を前倒しで計画していることが明らかになりました。これをきっかけに高速リニアモーターカーの話題が再び注目を集めています。
広州市政府のこの計画によると、高速リニアの時速は少なくとも600キロに達するということです。時速600キロの高速リニアモーターカーの研究開発試験プロジェクトが、中国国家発展改革委員会の重点プロジェクトに盛り込まれたのは2017年にさかのぼります。現在、中国の時速600キロの常電導高速リニアはすでに完全に中国独自の知的財産権を持つ工程技術と完全に中国独自のプラント技術を持ち、全システムにおける産業チェーンが自主的に制御可能になり、世界戦略のプロジェクト化の実施条件を備えるようになりました。
中国には、商業化運営されている中低速リニア路線が3本あります。それは、2016年に開通した湖南長沙リニア快速線、2017年に開通した北京中低速リニア列車S1線、2022年に開通した湖南鳳凰リニア観光快速線です。また、現在、中国の高速鉄道の総延長は4万5000キロに達し、世界一になっています。2025年までに、高速鉄道網は都市部人口50万人以上の都市の97.2%をカバーする見込みです。高速鉄道大国として、なぜ時速600キロの高速リニアプロジェクトを開発することになったのでしょうか。
現在、中国では高速鉄道の時速が約350キロで、大型旅客機の時速は800~1000キロです。北京、上海、広州などの中心的な大都市は、都市間距離が1000キロ以上あるほか、長江デルタ、珠江デルタ、北京・天津・河北エリア、長江中流エリア、成都・重慶エリアなどいくつかの重要都市群の距離も1000キロ以上となっているため、飛行機で移動する場合、空港までの距離が遠く、高速鉄道で移動すると旅行時間が長くなるという問題があります。時速600キロの高速リニアの効率性はちょうど高速鉄道と飛行機の間にあり、その間の空白をうまく埋めることができます。
今後、高速リニア路線が完成すれば、中国の五大主要都市群のうち4分の3の隣り合う都市群間を3時間以内(実際の旅行時間)で結ぶことが可能になり、日帰り移動も可能になります。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

LG化学、中国でバッテリー特許紛争…国家対抗戦に発展か
LG化学が、中国でバッテリー特許紛争に巻き込まれたことが確認された。中国当局にLG化学の正極材技術特許無効審判が請求された
2025年4月2日
 |
| 正極材を生産するLG化学清州(チョンジュ)工場の様子。[写真 LG化学] |
LG化学が最近、中国でバッテリー特許紛争に巻き込まれたことが確認された。中国当局にLG化学の正極材技術特許無効審判が請求されたのだ。欧州などグローバル市場で韓中バッテリー業界の競争が激しくなると特許戦争も激化している。
1日、業界によると、韓国の特許庁に該当する中国国家知識産権局に今年初めLG化学の三元系(NCM)正極材技術特許無効審判申請が入った。請求人は個人名義だが、業界では中国正極材メーカーの寧波容百新能源科技(Ronbay Technology)(以下、容百)側ではないかと疑っている。韓国と違って、中国では利害当事者ではない個人も特許無効審判を申請することができる。正極材は電気自動車(EV)バッテリー原価の40%を占める核心素材で、三元系正極材技術は韓国が中国より優位にあるという評価を受けている。LG化学は現在全世界に1300件余りの正極材特許を保有している。
容百は中国三元系正極材トップメーカーで、現在LG化学と韓国で特許訴訟中だ。LG化学は容百の韓国子会社(載世能源)が自社の三元系正極材特許を侵害したとし、昨年2024年8月ソウル中央地方法院(地裁)に特許侵害禁止訴訟を起こした。EV用バッテリー分野の韓中企業間の初めての特許訴訟戦だ。今回中国で無効審判が請求された特許は韓国で訴訟中の特許である「ファミリー特許」で、中国で出願された類似の特許だ。LG化学が特許侵害に対して訴訟で対応すると中国側が報復に出たという分析だ。LG化学関係者は「中国当局に特許権利を認められるようにうまく対応していきたい」と話した。
中国当局が該当特許を無効と判断すれば容百側が韓国での訴訟にもこれを根拠として使う展望だ。中国政府は特許でも自国企業に有利な判断をする傾向がある。法務法人クラスハンギョルのソン・ボイン弁護士(弁理士)は「特許は国ごとに効力が別個だが、類似の特許に対して韓中で異なる判断が出る場合、国家対抗戦に拡大する可能性がある」とし「このような場合、韓国企業は欧州などで特許侵害訴訟を起こして対応するようだ」と話した。容百側は特許侵害ではないと主張して韓国特許庁にもLG化学特許に対する無効審判などを請求して対抗している。
一部では請求人が容百ではなく、LG化学の特許を無断使用した他の中国メーカーである可能性ではないかとみている。今後LG化学が特許侵害に積極的に対応する場合に対して中国企業が備えているという推測だ。漢陽(ハニャン)大学エネルギー工学科のソン・ヤングク教授は「韓国企業が中国の一歩先に出るために活用できる核心武器は特許」とし「特許侵害阻止のために訴訟・交渉に積極的に出なければならず、次世代技術特許も先に出すことが重要だ」と話した。
韓国バッテリー業界は中国など後発走者が特許を無断に使用して開発した製品を持って海外進出を拡大すると牽制(けんせい)に出た。昨年「特許タダ乗り」に強硬対応を宣言したLGエナジーソリューションは現在中国企業に警告状を送ってライセンス料を交渉中だ。同社特許のうち実際に侵害が確認されたものは580件だ。LGエナジーソリューションは日本パナソニックと共にハンガリー特許管理専門会社(NPE)チューリップイノベーションを通じて特許侵害事例に対応している。現在、韓国バッテリーメーカーのうちLGエナジーソリューションが累積特許3万8398件で最も多く、サムスンSDIも2万1846件を保有している。
今年1月、韓国バッテリーメーカー3社の欧州シェアは35.6%で1年前に比べて15.4%ポイント下落し、寧徳時代新能源科技(CATL)など中国企業(56.3%)にかなり遅れをとった。業界関係者は「中国が海外市場進出にスピードを出し、Kバッテリーは知識財産権(IP)を武器としようとする動きを見せている」とし「正当な費用を支払わせて中国企業の価格競争力を低くし、ロイヤルティーという新しい収益源を期待することもできる」と話した。
「日本・ギリシャ編」
突然のプラント契約中止
1980年代の最大の困難は1981年に発生したプラント輸入契約の中止問題であった。中国は建国以来一貫してプラント輸入を重視してきた。建国初期はソ連東欧から156項目のプラントを導入し、機械工業などの基礎を築いた。1970年代、特に文化大革命が終わった1976年以後は、日本を含む西側諸国から機械、化学などの分野で多数のプラントを輸入する契約を締結した。ところが外貨の資金繰りがつかず、1980年の年末になり中国は突然すべてのプラント輸入契約の中止を通告してきた。関係諸国は困惑し、中国の国際的信用は急落した。契約当事者であった中国技術輸入総公司の某副総経理が自殺するという悲劇も起こった。
ところが、またしても日本政府は円借款とは別に商品借款を供与し、中国の資金不足の解決に協力した。結果的にはほとんどの契約は数年以内に復活した。しかしこの問題以後、中国は大規模なプラント輸入はやらなくなり、もっぱら外国企業の対中直接投資の導入に力を入れるようになった。世界一の重工業は日本から手に入れてしまったのだから、これから先は第2次、3次産業的なものを手に入れようと方針転換したのだ。
20年ぶり2度目の駐在
1996年1月から1998年5月まで再び北京に駐在した。最初の駐在は1977年で、毛沢東死去・文化大革命終結の翌年であったので、それからほぼ20年ぶりである。しかも今度の駐在期間に鄧小平の死去と香港返還があった。偶然にも毛沢東時代の最後と鄧小平時代の最後を北京で生活する巡り合わせとなった。
改革開放から十数年たった96年の北京は私にとってまるで知らない町になっていた。かつてメインストリートにも見られた馬車が全く消えており、自転車の大群は依然として存在していたものの、自動車が急増していた。高層ビルが林立し、業務関係先である各政府機関や公司、企業の住所も大半が移転していた。北京空港は新ターミナルになり、鉄道駅も巨大で壮麗な北京西駅が新しく使用開始されていた。
地図を片手に町を歩く
北京における日本企業の駐在事務所や日系企業が年々増大しており、当時北京に長期滞在する日本人は家族も含めて6000人規模になっていた。中国日本人商工会議所(現在の中国日本商会)や日本人会が活発に活動し、日本人学校も運営されていた。かつては1人駐在であった当協会の北京事務所も所長プラス中国人職員3人の4人体制になっていた。
まず北京を知らなければ仕事にならない。赴任後の半年間、私は毎週末に「北京生活地図」を片手に、バスと地下鉄を利用して徹底的に町を歩き回った。大規模な野菜卸売市場や水産物市場にも行ったし、イスラム教徒の居住区「牛街」の存在も知った。町歩きのおかげで北京がようやく身近になった。
弁護士の必要性
北京は外観が変化しただけでなく、経済システムも計画経済から市場経済に大転換していた。トラブルの解決方法もかつてのように何でも政府に訴えるのではなく、弁護士の協力や裁判による決着を求めるケースが増えていた。私は信頼できる弁護士と知り合いになっておく必要性を痛感し、中国国際貿易促進委員会の知人を通じて王俊峰弁護士を紹介してもらった。中国の広告主が「国際貿易」紙に掲載した広告代金の回収や北京事務所の中国人職員の家庭騒動などで王氏の事務所にお世話になった。また、それまで日本企業との結びつきが少なかった王氏を何人かの日本企業の駐在代表に紹介もした。
王弁護士が立ち上げた金杜律師事務所はその後急速に発展して北京最大の法律事務所となり、現在では上海など国内主要都市および東京、香港、ニューヨーク、シリコンバレーにも事務所を開いている。
激動の2008年
2008年もまた世界が激動した。日中関係では年初に日本企業が中国河北省の食品メーカーに委託生産して輸入した冷凍ギョウザによる中毒事件が発生した。事件を通じて、日中経済が日本国民の日常生活と緊密に結び付いていることが浮き彫りになった。5月12日の四川大地震、8月8日北京オリンピック開幕。8月下旬には河北省の三鹿集団公司はじめ中国の主要乳製品メーカーが生産する粉ミルクで化学物質メラミン混入事件が発生。また、1979年の合意以来約30年間継続された日本の対中円借款供与がこの年に終了した。
このODAが終わってようやく敗戦国日本が首をたれ続けた中国、中国呪縛が溶けつつある。
9月15日、米国のリーマンブラザーズ社の倒産を引き金に世界金融危機が発生。直ちに世界主要20カ国首脳会議が開催され、危機への対応が協議された。経済のグローバル化のすさまじさを実感させられた。加えて11月4日、オバマ氏が選挙に勝ち、アメリカ史上初の黒人大統領が誕生した。
双方向交流の時代
今世紀に入って中国はそれまでの外資導入だけでなく、中国企業の対外投資を積極的に進めるようになった。日本においても2009年蘇寧電器による家電量販店ラオックスの買収、2010年山東如意集団によるレナウンの買収などが大々的に報道された。中国企業の日本進出は611社に上るとの調査機関の報告も発表された。
貿易においても2007年以後アメリカに代わって中国が日本の最大の相手国になっている。中国にとって日本は米国に次ぐ第2の貿易相手国である。また、伝統的に日本は工業製品、特に生産財を中国に輸出し、農産物及び工業原料を中国から輸入する貿易構造であった。しかし製造業を中心に中国への産業移転が進み、在中日系企業が4万社(外資企業には、のちに人民武装部を置く決まりができる)に及ぶ状況を反映し、近年は輸出入とも工業製品が主体となっている。さらに新しい動きとして日本の食品や化粧品といった高級消費財が中国に輸出されるようになった。まさに双方向交流の時代に入ったということができる。
共同事業の構築へ
2011年3月11日、史上類を見ないほど激烈な東北関東大地震が発生し、東日本は甚大な被害を受けた。中国人研修生を避難させた後、自分は津波にのみ込まれた日本人の実話も報道された。この大地震によって今後日中経済交流にも一定の悪影響が出るのは避けがたい。しかし、国境を越えてより広い地域経済圏が形成されつつある今日、日中双方の経済界が互いに「智慧を出し合い地域経済の発展に寄与する共同事業を構築」していくことが日中関係をさらに発展させる鍵の一つになると思う。
2009年、中華人民共和国は建国60周年を迎え、同じ年に日本国際貿易促進協会(当協会)は創立55周年であった。私自身、協会で日中経済交流の実務に従事して40年以上が経過した。この間体験したことの断面を紹介し、若い世代の参考に供したいと考える。
当協会の創立
当協会は1954年9月に創立された純民間の貿易促進団体である。戦後の東西冷戦体制はすでに始まっており、当時わが国が国交を正常化していなかった「中国の人民民主主義、ソ連の社会主義諸国との民間貿易」を促進することが設立の趣旨であった。
当初は中国、ソ連の2大社会主義国との貿易促進、展示会の開催、代表団の派遣受け入れ、中国の輸出商品交易会(広州交易会)への日本企業の参加とりまとめ等の活動をやってきた。その後60年代に入り、この両国の対立が激化し、当協会はソ連との関係が断絶し、中国が主な相手国となった。
私は東京オリンピックが開催された1964年に大学に入り、第二外国語として中国語を選択した。その担当教授(工藤篁先生)が「中国語では目のことを眼睛という。中国人の瞳は黒いのに、どうして目に青の字を使うのか?」といきなり質問された。先生の中国語及び中国に対する深い洞察に感心し、次第に中国に対する興味が強まった。
1968年、私が当協会に入った時、協会はモスクワ事務所をすでに閉鎖しており、業務は対中関係だけであった。その中国は文化大革命(1966-1976年)の真最中であり、人事交流も少なく、日中民間貿易も種々の困難に直面していた。国交が無いため、訪中毎に一次使用のパスポートを申請しなければならず、「ハイテク製品」の対中輸出は厳しいココム規制(注)を受けた。またプラントの延べ払い輸出に対する輸出入銀行の融資も受けられなかった。当時貿易業界の最大の要望は「日中国交回復の早期実現」であった。
日中経済関係の歴史区分
現在の時点から振り返ってみると、戦後の日中経済交流の歴史は次の四段階に分けることができる。
第一段階は1949-1971年の23年間で、中華人民共和国成立から日中国交正常化以前の民間貿易の時代である。
第二段階は1972-1977年の6年間で、日中国交正常化以後貿易が急激に拡大した時代である。
第三段階は1978-2000年の23年間で、中国の改革・開放以後、対中ODAと対中投資が拡大した時代である。
第四段階は2001年から現在までで、中国がWTOに加盟し、経済のグローバル化に積極的に参画するようになった時代である。
(注)ココム(対共産圏輸出統制委員会)とは北大西洋条約機構(NATO)加盟諸国が共産主義諸国への軍事技術・戦略物資の輸出を規制するために結成し、1950年から活動を開始した委員会で、日本は1952年に加盟した。ココムはソ連が崩壊し冷戦が終結した後の1994年に解散した。
日本にも忍び寄る「港を買いあさる外資」の影
2021年3月
週末だというのに、「世界三大夕日」をうたう北海道釧路市の釧路川にかかる幣舞ぬさまい橋から太平洋を望む撮影スポットに、カメラを持って集まる人の影はまばらだった(ちなみに、残る2か所はインドネシア・バリ島とフィリピン・マニラ湾だそうだ)。
釧路港に注がれる視線
3月は夏や冬の観光ピークとずれているとはいえ、河口中央に太陽が沈み、美しさが際立つ季節だ。新型コロナウイルスの感染拡大で、外国人観光客はもとより、日本人旅行者もほとんど見かけない。釧路川に面した津波避難施設を兼ねる商業施設「釧路フィッシャーマンズワーフMOO」の中も、人影がほとんどない寂しさだった。
釧路湿原を案内してくれた男性は、廃虚のようになったビルや、駐車場になった更地を指して「私が子どもの頃はここも、あそこもデパートだった。今は、全て撤退した。あの頃の活気が戻ることは、もはやないのだろう」と語る。
コロナ禍をしのげば、夕日や釧路湿原を目指して世界から観光客は戻ってくるだろう。けれども、勢いを失った石炭、製紙、漁業に代わる産業が根付き、人口が増加に転じる未来像は、70歳の観光ガイドには描けないようだった。
MOOよりもさらに河口に向かっていくと、釧路港がある。
アジアから見て北米大陸に最も近い不凍港は近年、国際的な注目を集めるようになった。中国が「一帯一路」構想の「氷上シルクロード」と言われる北極海航路の拠点として使いたいとの考えを示し、中国企業や駐日中国大使らが次々と釧路を訪れるようになったからだ。
日本政府も釧路港の重要性は分かっている。(日本政府よ!しっかりせよ。露の樺太・千島・四島占拠は侵略なのだから、日本の北海道、釧路まで共産主義国に取られてはダメだ)
国土交通省は2011年、「資源、エネルギー、食糧等の安定的で安価な供給」を目標に、鹿島港(茨城県)、志布志港(鹿児島県)、名古屋港(愛知県)、水島港(岡山県)とともに釧路港を穀物の「国際バルク戦略港湾」(「バルク」は、包装されずにバラバラに運ばれる貨物のこと。鉄鉱石、穀物、石炭を「3大バルク貨物」という)に指定した。
指定に基づく機能強化や整備が行われ、2018年には釧路港の戦略港湾としての運用が始まったが、町のにぎわいの復活や人口減少の傾向に歯止めをかけるものではなかった。
外国資本に危機感強めた米国
そんな環境の中で、「中国の投資があれば、釧路港や周辺が活気づくのではないか」といった期待感が高まるのは、無理もない。
一方で、一帯一路を進めるために中国政府が後ろ盾になった企業が世界中で港湾の買収や出資を繰り広げていることに、国際社会は安全保障上の懸念を強めている。一帯一路には、表看板の「巨大経済構想」の裏側に、軍事的な意図も隠されているとの見方が消えないからだ。
ギリシャのアテネ近郊ピレウス港で、積み上げられた多数のコンテナ(2017年9月)
11月11日、中国とギリシャは、中国海運大手の中国遠洋運輸(COSCO)がギリシャ最大の港であるピレウス港に6億ユーロを投資する計画を押し進めることで合意した。写真はピレウス港を視察する習近平国家主席(左)とギリシャのミツォタキス首相。代表撮影(2019年 ロイター)
 |
| ギリシャも「中華思想」に汚染された? |
ギリシャのピレウス港を視察するミツォタキス首相(右)と中国の習近平国家主席(2019年11月11日)=AP
COSCOは2009年にピレウス港のコンテナ貨物埠頭の改修と運用について期間35年の利権を取得し、以来、両国は協力関係を強めている。COSCOは16年にはピレウス港の株式の51%を取得した。
COSCOは22年までの3億ユーロ投資に加えて6億ユーロの投資を行うと約束しており、ピレウス港を欧州最大の商業港に育てる計画。
国際通貨基金(IMF)や単一通貨ユーロ圏から借りたオカネを返すため、ギリシャはピレウス港など国有財産の売却を進めています。欧州債務危機の最中にギリシャの国債を購入するなど、借金まみれのギリシャに援助の手を差し伸べてきた中国にとって、ピレウス港は欧州だけでなく中東・北アフリカへの重要な足がかりになります。
昨年2月には中国海軍最大の大型揚陸艦「長白山」がピレウス港に寄港しました。5月には中国人民解放軍がロシアとともに地中海で初めて海上合同軍事演習を実施しました。2011年に米英仏がリビアに軍事介入した際、3万6千人の中国人労働者がリビアで働いており、大掛かりな救出作戦が地中海で展開されたことがあります。
ギリシャは、中国の習近平国家主席の広域経済圏構想「一帯一路」の要になります。港湾施設のほか東欧・中欧、バルカン半島諸国につながる鉄道網などのインフラを整備すれば、実需が生まれ、インフラ輸出を通じて中国国内で顕著になっている供給過剰を解消できます。景気回復の足取りが遅い欧州にとって中国マネーでインフラが整備できれば、これほどありがたい話はありません。
国有財産の処分を進めるギリシャ資産開発基金は、ピレウス港を運営する国営会社の発行済み株式の67.7%を売却する計画です。日経新聞は、コスコ・グループは3億~4億ユーロ(約380億~510億円)を投じて株式の51%を取得すると報じています。一方、米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは関係者の話として向こう5年間のインフラ投資3億5千万ユーロを含む計7億ユーロで株式の67%を取得すると伝えています。
最初は株式の51%を取得して、5年間で67%まで増やすという買収提案なのかもしれません。
筆者は昨年1月のギリシャ総選挙に合わせて、ピレウス港を飛び込みで取材したことがあります。コスコ・グループの子会社ピレウス・コンテナ・ターミナル(PCT)は意外とすんなり取材に応じてくれました。コンテナ船だけでなくフェリーやクルーズ船も発着するピレウス港周辺は、車が激しく行き交うなど、アテネ中心部以上の活況を呈していました。
コスコ・グループは2008年に49億ユーロを投資してピレウス港のコンテナ埠頭の運営権を35年にわたって獲得しています。PCTでは約1100人が働いていますが、中国人は最高経営責任者(CEO)ら7人だけだそうです。中国人幹部とギリシャ人社員の会話もなごやかに見えました。
PCTで働くギリシャ人によると日給は58ユーロ、ギリシャではかなりの厚遇です。コンテナ埠頭ではコスコ・グループのコンテナもありましたが、いろいろなコンテナを扱っていました。
当時、PCTは2つの埠頭を運営していました。拡張工事でコンテナの取扱量は最初、685個(TEU=20フィートコンテナ換算)だったそうですが、480万個へと飛躍的に増えたとのことでした。広報責任者は「将来は620万個まで増やします」と言います。少し水増し気味の数字なのかもしれませんが、「一帯一路」が軌道に乗れば、コンテナ輸送はもっと増えるのは確実です。
ピレウス港とチェコなど中欧を結ぶコンテナ列車は週に3~4本しか運行しておらず、「毎日走らせるようにしたい」と意気込んでいました。ピレウス港でコンテナを荷揚げすれば、オランダ・ロッテルダム港、ドイツ・ハンブルク港などを経由するより輸送期間が10日間短縮できるそうです。ココス・グループがピレウス港を買収すれば、欧州の物流が一変する可能性があります。
急進左派連合(SYRIZA)のチプラス首相は政権につく前は国有資産の売却には否定的でしたが、ユーロ圏との交渉で支援を引き続き受ける代償として国有財産の売却をのまされました。チプラス首相も背に腹は変えられません。
中国国有大手・中国鉄路総公司は昨年12月、15億7千万ドルでセルビア・ベオグラードとハンガリー・ブタペストを結ぶ鉄道整備(全長350キロメートル)に乗り出しました。コスコ・グループも参加するコンソーシアムはトルコでもイスタンブール港のコンテナターミナルを買収しています。
物流の拠点としてピレウス港を開発するのはギリシャも欧州連合(EU)も大歓迎ですが、中国には別の狙いもあるようです。
昨年5月、中国とロシアは北大西洋条約機構(NATO)が勢力圏とする地中海で初めて海上合同軍事演習を実施しました。軍事演習には中国のフリゲート艦2隻など中露両国から計10隻の艦船が参加しました。米国一極支配の現・世界秩序を再構築するのが狙いです。
中国にはロシアとの緊密な関係を見せつけることで、日本の安倍政権を牽制する思惑もあったようです。「一帯一路」は地中海を経由しており、中国には貿易だけでなくエネルギー、安全保障といった国益が生じます。中東・北アフリカで中国人の救出や海賊対策などの作戦を展開する必要が生じた場合、ピレウス港は燃料の補給など重要な軍事拠点になります。
中国が主導するアジアインフラ投資銀行(AIIB)には欧州の英独仏伊など多くの国が出資しています。欧州復興開発銀行(EBRD)もAIIBと協力する方針で、欧州は中国マネーがインフラ整備に投資されることに大きな期待を寄せています。
中国が貿易、エネルギーに加えて軍事面でも国際協調に徹するなら欧州との相思相愛は続くでしょう。しかし欧州にとって安全保障上の脅威であるロシアと組んで地中海で軍事的なプレゼンスを増す腹積もりなら話は別です。中国への警戒心は一気に膨らむ可能性があります。ピレウス港の運用はその試金石になるでしょう。
2015/7/15 ギリシャへの中国、ロシアの接近
中国とロシアは今回のギリシャ支援の合意を歓迎しているが、いずれもギリシャに接近している。
ギリシャのチプラス首相は4月と6月に訪露してプーチン露大統領と会談し、ウクライナ危機での米欧の制裁を「経済戦争」と呼んでロシア寄りの姿勢を見せた。
プーチン大統領は6月19日、ギリシャとの間で、ロシアからの天然ガスパイプラインTurkish Stream をトルコを経由してギリシャにつなげる計画に基本合意した。
ギリシャの農産品の輸入についても話し合われた。ロシアはEUの制裁に対抗し、EUからの農産品の輸入を禁止しているが、ギリシャの例外扱いを検討している。
ロシアのエネルギー相は7月12日、ギリシャ経済てこ入れのため、ロシアはギリシャに燃料を直接供給することを検討中だと語った。
「ロシアはエネルギー部門での協力拡大を通じてギリシャ経済の再生を支援するつもりだ。このため、われわれはギリシャへのエネルギー資源の直接供給の可能性を検討している。直接供給は近く始まる」と述べた。
Turkish Stream の概要は下記の通り。
ロシアは2014年12月1日、ウクライナを迂回してロシアから欧州南部に天然ガスを輸送するパイプライン South Stream の敷設計画を撤回した。
EUの反対でブルガリアの許可が得られないためとし、「EUの立場は非建設的であり、そのためロシアは他の地域にエネルギー輸送先を切り替え、またはLNGに軸足を置き替える」と語った。
2014/12/4 ロシア、South Stream 計画を取り止め
ロシアはその後、新ガスパイプライン Turkish Stream 構想を打ち出し、本年初めにルートが確定した。
South Stream と同様に4本のラインが敷設される予定で、海底部分のうち660kmはSouth Stream用に予定されていたルート、その他に 250kmがトルコ向けの新ルートとなる。
黒海南西部沿岸の都市キイキョイから陸上に入り、ギリシア国境のイプサラまでの180kmが敷設される。
年間輸送能力は630億m3で、うちトルコが140億m3 を引き取る。
第1ラインの完工は2016年12月を予定しており、全てトルコに供給される。トルコ向け天然ガス価格は 6%値引きする。
South Streamとの大きな違いは、パイプラインのEU内の部分でGazpromがその建設や操業に関与しないことである。EUの干渉に嫌気がさしたと思われる。
今後の計画も含め、欧州の天然ガス輸入の南部ラインはすべてトルコを経由することとなる。
付記
2015年11月にトルコ軍によるロシア軍機撃墜事件があり、両国の関係が悪化し、本件も棚上げされた。
2016年7月15日のトルコのクーデター未遂事件で、政権は反対派を一掃、事件の首謀とする宗教指導者で滞米のギュレン師の引渡しを求め、米国との関係が悪化した。
同時にロシアとの関係回復を図った。
2016年10月10日、ロシアとトルコは 「トルコストリーム」建設の政府間協定を締結した。
建設の合意の一環としてガス価格の値引きで合意した。
ロシアは撃墜事件後に発動したトルコ産農産品への禁輸措置解除も表明した。
ーーー
ギリシャの生産再建・環境・エネルギー相は5月29日、ギリシャがBRICS開発銀行への参加を検討していると発言した。
ロシアもギリシャの意向を関知しているとしている。
5カ国は7月7日、モスクワでBRICS開発銀行の第1回総会を開いたが、ギリシャ問題は取り扱われていない。
初代総裁にはインドの民間銀行元会長 K.V. Kamath が就任した。
当初の資本金は500億ドルで5カ国が均等出資する。将来は1千億ドル規模へ拡大する。
年内にも業務を開始する。
ーーー
中国の李克強首相は6月29日、ブリュッセルでEU首脳との会談後の記者会見で質問に対し、「中国はこれまでも、ギリシャが危機を抜け出すための要求に応えてきた。問題解決に建設的な役割を果たしたい」と述べた。
「シルクロード経済ベルト」と「21世紀の海のシルクロード」計画 (一帯一路構想)を進める中国にとっては、ギリシャは欧州への入り口として重要である。
今回のギリシャの財政改革案に含まれる民営化のうち、アテネ郊外のPireaus港については中国遠洋運輸公司(COSCO) への売却が有力である。
(おわり)木村正人
2019.02.25
# 中国
中国を脅かす巨大なリスク「中国版新幹線」のはてしない無軌道
北京の著名な研究者も警鐘を鳴らした
北村 豊中国鑑測家
中央大学政策文化総合研究所客員研究員
常識外の建設速度
常識外の建設速度
「我が国の高速鉄道は日本やドイツなどから高速鉄道の関連技術を消化吸収した上にさらなる技術革新を加えて産み出されたものだから、その技術はもはや独自開発のものである」と主張する中国の2018年末時点における高速鉄道の総延長は2.9万kmに達し、日本の新幹線の総延長、約3130kmに比べると約10倍に相当する。
中国は2008年8月1日に北京市と天津市を時速350kmで結ぶ全長200kmの“京津城際鉄路(北京・天津都市間鉄道)”が運行を開始してからわずか11年間で全土に2.9万kmもの高速鉄道を建設して開通させたのである。
日本の新幹線は1964年10月1日に東京・新大阪間の515kmが開通してから54年後の2018年末で総延長が3130kmであることを考えると、いくら国土面積が日本の10倍であるとは言っても、中国の高速鉄道の建設速度は常識外であり、その規模から考えて高速鉄道の運営は採算を度外視したものと考えざるを得ない。
さて、今年68歳の“趙堅(ちょうけん)”は1949年10月1日に中華人民共和国が成立してから14カ月目の1950年11月に北京で生れたから、彼の人生は祖国である中国と共に歩んで来たと言っても過言ではない。
その趙堅の肩書は北京交通大学の経済管理学院教授、博士課程指導教官、“城鎮化研究中心(都市化研究センター)”主任であり、同時に鉄道経営に関する研究者としてもその名を知られている。
中国では高速鉄道を“高速鉄路(略称:高鉄)”と呼び、多くの中国人は自国の高速鉄道は世界一だと誇りにしているが、趙堅は国策である高速鉄道の建設に一貫して反対を唱え、たとえ建設するにしても時速200kmや300kmの高速鉄道は建設すべきでないと主張してきた。
その趙堅がニュースサイト“財新網(ネット)”に寄稿した『“謹防高鉄灰犀牛(高速鉄道の灰色のサイを注意深く防ごう)”』と題する記事が2019年1月28日付で掲載されて世間の注目を集め、多くの中国メディアによって取り上げられたことで大きな話題となった。
“灰犀牛(灰色のサイ)”とは「将来大きな問題を引き起こす可能性が高いにもかかわらず、現時点で軽視されがちな潜在的リスク」を指し、巨体でも普段はおとなしいサイが、ひとたび暴走を始めると止めようがなく、誰も手が付けられなくなることに由来するのだという。
なお、「灰色のサイ」と対比される言葉に、“黒天鵞(ブラックスワン)”という言葉があるが、これは「従前の常識や経験ではあり得ないと思われて来た事象が発生し、その事象が人々に多大な影響を与えること」を意味する。
趙堅が当該記事を執筆したのは、1月21日に国家主席の習近平が共産党中央党校に全国の幹部を招集して講演し、2008年のリーマンショックのようにめったに起きなくても極めて大きなリスクである「ブラックスワン」だけでなく、不動産バブルなど対応が困難なリスクである「灰色のサイ」にも警戒を怠らぬよう訓示したのを踏まえたものと思われ、灰色のサイを警戒する対象に高速鉄道を加えるよう問題を提起したのであった。
2路線以外は休眠状態
さて、その趙堅が執筆した『高速鉄道の灰色のサイを注意深く防ごう』と題する記事の要点を抜き出すと、その深刻さがわかる。
【1】2018年末までに中国高速鉄道の営業距離はすでに2.9万kmに達した。人々は通常中国高速鉄道の営業距離が世界一であることと高速鉄道が速いことだけを見ていて、高速鉄道の債務と営業損失が世界一で、中国の交通運輸構造がひどく悪化していることを見て見ぬ振りをしている。
【2】高速鉄道は安定性と円滑性の要求が非常に高いので、高速鉄道の建設費は普通鉄道の建設費より2~3倍高い。
速度を速くするには、高速列車の重量をできる限り削減する必要があり、普通鉄道の軸重(各々の車輪にかかる荷重)が23トンであるのに対して、中国高速鉄道の軸重は17トンと軽い。ただし、高速鉄道は人の輸送だけで貨物の輸送は出来ず、対戦車ミサイルを運ぶことはできない。このため、人口規模が大きく、密度が高い路線だけが高速鉄道の需要を満足することができ、旅客輸送の収入で高速鉄道の建設と運営のコストを補うことができる。
目下のところ、高速鉄道で輸送能力が比較的高い“京滬(北京-上海)”、“京広(北京-広州)”路線を除くと、その他の高速鉄道の路線は輸送能力が大量に遊休状態にあり、深刻な損失が存在する。
たとえば、“蘭新(蘭州-新疆)”高速鉄道の運行能力は毎日160往復以上あるにもかかわらず、たったの4往復しか運行されておらず、その輸送収入は電気代を支払うのにも足りないのが実情である。
【3】2015年に中国高速鉄道の中で輸送密度が最高だったのは“京滬”路線で、その輸送密度は4800万人/km前後であった。これに対して、輸送密度が最低だった“蘭新”路線は230万人/km前後であり、全国の高速鉄道の平均輸送密度は1700万人/km前後であった。
しかし、輸送密度が最高の“京滬”路線でも、輸送密度9000万人/kmで世界最高である日本の東海道新幹線には遥かに及ばない。これは500kmの路線上に日本の人口の55%が集中していること、さらには4000km以上の都市交通が東海道新幹線に乗客を供給していることに起因している。
日本の高速鉄道の平均輸送密度は3400万人/kmであり、これは中国の高速鉄道の平均輸送密度の2倍である。
【4】中国が十数年で建設した高速鉄道はすでに世界のその他の国や地域が半世紀以上をかけて建設した高速鉄道の総延長の2倍以上に達している。世界各国の高速鉄道で旅客輸送の収入に依拠して建設や運営のコストを賄えている路線は恐らく1つもなく、大多数が欠損の状態にあるか、政府からの補助金に頼っている。従い、世界最大規模の中国高速鉄道網と低すぎる高速鉄道の輸送密度(運輸収入)は重大な金融リスクに見舞われる可能性を示している。
今後も大規模な高速鉄道の建設を継続すれば、それは中国の鉄道を運営する「中国国家鉄路集団有限公司」(略称:中国鉄路)と地方政府に更なる巨大な債務負担をもたらし、中国経済に出現する「灰色のサイ」と衝突することになるだろう。
膨れ上がる債務の実態
【5】中国の高速鉄道は主として融資による債務に依拠しており、大規模な高速鉄道の建設は中国鉄路の負債を2005年の4768億元(約7兆7720億円)から2016年の4.72兆元(約77兆円)まで急増させた。
中国鉄路の収支は秘密事項だが、その公表された負債と旅客運輸収入のデータから考えると、たとえ高速鉄道の運営コストを考慮しない前提で、高速鉄道の全運輸収入を高速鉄道の建設に関わる借款の利子払いに充当したとしても足りないと判断できる。
その理由はこうなる。2016年末の中国鉄路の負債は4.72兆元だったが、その中の少なくとも3.3兆元(約53.8兆円)は高速鉄道2.2万kmの建設と動力ユニットの購入に投入されたが、これを年利4.75%で利息を計算すると、毎年支払わねばならない借款の利息は1568億元(約2兆5560億円)となる。2016年における高速鉄道の運輸収入は1409億元と推定できるので、1568億元の利息支払いにも不足するのである。
【6】中国鉄路の旅客輸送収入は2018年上半期には1693億元(約2兆7600億円)に達したので、通年では3400億元(約5兆5400億円)が見込まれる。
しかし、2018年9月までの中国鉄路の負債総額はすでに5.28兆元(約86兆円)に達しており、目下のところデータはないが、地方政府が高速鉄道の建設で抱えている莫大な金額の債務を考えると、巨額な高速鉄道の債務はすでに形成され、国家的な金融リスクが誘発されているのかもしれない。
事業としての発展性なく
【7】2018年の中国鉄路の営業距離は13万kmに過ぎす、その中の2.9万kmは人を運ぶだけで貨物を運べない高速鉄道である。米国の鉄道営業距離は22.5万kmであり、中国は高水準の普通鉄道にはまだ発展の大きな可能性があり、その営業距離は26万kmに達することが必要だと考えられる。
しかし、中国の高速鉄道にはもはや発展の可能性は少ない。その理由は、高速鉄道の輸送能力が使用されずに大量に余っている一方で、鉄道の貨物輸送能力が大きく不足しているという併存する問題をいかに解決できるかが課題であるが、これは解決困難である。
なお、2016年時点における、中国鉄路の普通客車保有量は7万1000両であるのに対して高速車両保有量は2万688両で、普通客車の数は高速車両の3倍以上である。
【8】中国鉄路は貨物輸送の運賃を絶えず値上げして高速鉄道の深刻な損失を穴埋めしようとして来たために、荷主は運賃が高い鉄道を止めてトラック輸送に切り替えている。鉄道の貨物輸送運賃は2004年以来11回の調整を行っており、運賃はトラック輸送に比べて2倍以上になっている。
国際的な貨物運賃は一般に鉄道輸送が0.1元/トン・kmであるのに対してトラック輸送は0.3~0.5元/トン・kmで、鉄道輸送はトラック輸送よりも貨物運賃が安いのだが、中国は国際的な貨物輸送の価格体系とは正反対の状況を呈している。
このため、中国国内には貨物を輸送するトラックがひしめいている。ディーゼルトラックはPM2.5を大量に放出するし、天然ガストラックが排出する酸化窒素物の量はディーゼルトラックのPM2.5よりも多い。
政府は行政的な手段で「トラック輸送から鉄道輸送への切り替え」を実施しており、2017年の鉄道貨物輸送の取扱い量は貨物輸送全体の17.5%で、2016年より0.4%上昇した。
【9】灰色のサイとブラックスワンは同一のものではなく、灰色のサイは確率が大きい高リスク事件であり、ブラックスワンは確率が小さい高リスク事件である。後者は予測が難しく、前者は往々に見て見ぬ振りをされる。
長期間にわたり、中国は大量のディーゼルトラックで石炭や鋼鉄などの基礎原材料を輸送してきたが、過積載は何度禁止しても減少しないし、数千kmの長距離トラック輸送では深刻な交通事故が度々起きているが、人々はこの現象を見慣れてしまっている。
これは中国の交通運輸構造がすでにひどく硬直していることを示しており、鉄道の貨物輸送能力が深刻に不足している明確なサインであるにもかかわらず人々は見て見ぬ振りをしているのである。
【10】中国鉄路の急増する巨額債務に対して、人々はカネの有る中央政府が支払ってくれるものと関心を示さない。地方政府の高速鉄道建設による債務はブラックボックスで、地方政府の各種負債と一緒に混ざり、統計によれば18.29兆元(約298兆円)に上っている。
債務は積み上がるのに収益が増やせないならば、中央政府はただ貨幣を発行して債務を相殺することになる。そうなれば、深刻なインフレーションを引き起こし、巨大な金融リスクがもたらされる。
一部の人は中国高速鉄道の営業距離は世界一だと自慢しているが、高速鉄道の債務が世界一であることによる金融リスクについては見て見ぬ振りをしているのだ。
それでも計画は止まらない
この【4】の中で、趙堅は、「今後も大規模な高速鉄道の建設を継続すれば、それは中国鉄路と地方政府に更なる巨大な債務負担をもたらし、中国経済の灰色のサイと衝突することになるだろう」と述べていた。
それを裏付けるかのように、2018年11月21日付の証券業界紙「上海証券報」は、「国家発展改革委員会が多くの高速鉄道プロジェクトを承認、投資規模は1000億元を超える」と題する記事を掲載した。そこには、一向に衰えない高速鉄道プロジェクトへの投資の中身が詳細に記されている。
(1)近いうちに、中国政府の国家発展改革委員会は「包頭(内モンゴル自治区)-銀川(寧夏回教自治区)路線の銀川-恵農(寧夏回教自治区)区間」、「上海(上海市)-蘇州(江蘇省)-湖州(浙江省)区間」、「重慶(重慶市)-黔江(重慶市)区間」の高速鉄道プロジェクト3件に関するフィージビリティスタディ(FS)を承認する。総延長は529kmであり、総投資額は1032億元(約1兆6820億円)である。
(2)今年の第1から第3四半期までで、国家発展改革委員会は固定資産投資プロジェクト147件、総投資額6977億元(約11兆3725億円)を承認した。また、10月に国家発展改革委員会は固定資産投資プロジェクト9件、総投資額918億元(約1兆4963億円)を承認した。これは今年すでに承認された固定資産投資プロジェクトの規模が8000億元(約13兆400億円)に近いことを意味する。
(3)国家統計局のデータによれば、1月から10月までの全国固定資産投資は前年比5.7%増大しており、その中のインフラ投資は3.7%増大し、増加幅はある程度回復した。10月単月のインフラ投資の増加速度は今年初の反発を示した。記者が中国鉄路から聴取したところでは、今年1月から10月までの全国鉄道固定資産投資の累計完成額は6331億元(約10兆3195億円)で、今年通年で完成予定額の7320億元(約11兆9316億円)までわずか1000億元(約1兆6300億円)まで迫っている。
高速鉄道は普通鉄道に比べて建設費用だけでなく、開通後の保守管理費用も割高である。2.9万kmもの高速鉄道を問題なく運行させるために必要な人件費、設備費、消耗品費を考えると、中国鉄路が抱える債務は増大する一方だと思えるし、地方政府の債務も同様だと考えられる。
したがって、上述した趙堅の見解が正しいなら、高速鉄道に「灰色のサイ」が出現する可能性は予断を許さないと思われる。
わずか3130kmの日本の新幹線でさえも採算に問題があるのに、中国の2.9万kmの高速鉄道で採算を取るのは至難の業である。2018年4月末に発表された中国鉄路の「2017年度財務報告」によれば、2017年末の負債総額は4.99兆元(約81.3兆円)で負債率は65%に達したという。
2017年における高速鉄道の乗客数は延べ17.13億人で、総人口を約14億人と考えれば、国民1人当たり高速鉄道に年間1.2回乗車した計算になる。
一方、人口が1.2億人の日本で新幹線の乗客数は延べ3.3億人であることを考えると、国民1人あたり年間2.75回新幹線に乗車したことになり、中国の2倍以上でその差は大きい。
果たして中国の高速鉄道に「灰色のサイ」が出現する日は来るのか。
万一にも出現するようなことになれば、それは中国鉄路に止まらず高速鉄道に多大な投資を行っている地方政府をも巻き込むことになり、その影響は中国を揺るがす甚大なものとなりかねないのである。
2022.09.27
習近平が「焦る」…! 肝入り「一帯一路」が“大失敗”で、起死回生の「ヤバい一手」に動き出した…!
福島 香織
2年8ヵ月ぶりに「中国を離れた」、習近平の「焦り」
9月15~16日に行われた上海協力機構(SCO)首脳会議(サミット)では、習近平が2年8ヵ月ぶりに中国をはなれて外遊に出たこと、そしてロシアがウクライナに対して侵略戦争を始めて以降、はじめてプーチンが習近平と会談することで注目を浴びた。
だが、このSCOにおいて、習近平が提唱した一帯一路(債務の罠外交)の立て直しを図ろうとしている点にも注意が必要だ。
まずは、今回のサミットで打ち出された「サマルカンド宣言」で気になる部分をちょっと拾ってみる。
「SCO憲章の原則を基に、集団化、イデオロギー化、対抗的思想で国際・地域問題を解決しようとすることに反対する。伝統・非伝統領域の安全脅威と挑戦に包括的に対応することを堅持する。SCOメンバー各国の意見を考慮し、相互尊重、公平正義、協力ウィンウィンの新型国際関係と人類運命共同体を実現させることが重要な意義であることをここに繰り返す」
「カザフスタン、キルギスタン、パキスタン、ロシア、タジキスタン、ウズベキスタンは中国の打ち出した一帯一路(債務の罠外交)に対し、改めて支持を行い、一帯一路(債務の罠外交)とユーラシア経済連盟建設をリンクさせることを含めて、一帯一路(債務の罠外交)を共同に実施していくことを支持した」
これは「大ユーラシアパートナー関係」だ、と
それだけではない。宣言には以下のようにもある。
「メンバー国は地域・国家、国際組織など多極的メカニズムの潜在力を利用し、国際法原則および国家利益を顧み、ユーラシア地域に広汎で、開放的で互恵互利の平等な協力空間を作るべきだと考えている。特に、ロシアがSCO、ASEAN国家およびその他の関係国とも多極的なメカニズムに参与し、大ユーラシアパートナー関係を構築する提案をしたことにメンバー国は注目した」
「メンバー国は、SCO実業家委員会と銀行連合体がポテンシャルを発揮させ、さらに協力して連合のイニシアチブを発揮し、SCO地域の金融、ハイテク、交通・通信インフラ、エネルギー、投資、中小企業などの領域でプロジェクトを実施させる。融資保証をより完全にし、組織投資のポテンシャルを十分に発掘する必要があり、さらに継続して、SCO開発銀行及び発展基金の設立にむけて協議を進める」
「メンバー国は、交通領域の協力継続が重要な意義を持つと強調。国際道路、鉄道交通路線の新敷設、回収、交通回廊を打ち出し、国際物流、貿易、観光センターを設立。そこにデジタルやイノベーション、省エネ技術を導入し、国際先進経験をもとに最適化した通関手続きによって、効率的なSCOメンバーによる国境を越えた輸送潜在力をもつインフラ協力プロジェクトを実施する」……。
これはいったい、何を意味するのか。じつはそこには習近平の焦りが隠されている。
起死回生の「一手」
習近平が次の党大会で総書記、国家主席、中央軍事委員会主席をそのまま継続する確率はいまのところ非常に高い。
が、同時に、習近平の政策が失敗であったという認識は党内でも広がっている。
特に党規約にまで盛り込んだ「一帯一路(債務の罠外交)」プロジェクトが資金ショートでとん挫し、また「債務の罠」という批判を国際社会から浴び、チャイナ・マフィアがプロジェクトに入り込んでオンライン詐欺や麻薬密売、人身売買にも利用されているということが暴露され、そのイメージは落ちるところまで落ちた。
これを立て直すことが、いま習近平にとっては権力維持のために必要なのだ。
このため、習近平は昨年の国連総会で打ち出した「グローバル発展イニシアチブ(GDI)」と一帯一路(債務の罠外交)をセットにすることで、そのイメージを挽回しようとしているわけだ。
「2016年 オーストラリア編」
中国マネーに目がくらんだ豪州に米国激怒 海兵隊拠点の隣にまさかの“敵”2016年4月
米海兵隊が中国を睨む拠点としているオーストラリア北部、ダーウィンの港が中国企業に長期貸与され、米国の対豪不信が高まっている。貸与は米国に知らされないまま決められ、中国政府や軍とも関係が深い企業が米軍の活動などを監視する可能性もあるためだ。契約は99年という長期にわたる。中国は豪政府の脇の甘さを突いて米国の戦略拠点に食い込み、同盟にくさびを打ち込んだ形だ。(坂本英彰)

2016年2月7日、北京で中国の王毅外相(右)と握手を交わすオーストラリアのビショップ外相。オーストラリアは経済での対中依存度が高く、その流れが安全保障面に及ぼす影響などを米国が懸念している(AP)王毅外相が訪問した国はどうなったか?
9割が「危険」
「まるでアフガニスタンのような扱いだな」
豪有力紙オーストラリアンが3月上旬、米国務省が豪国内で秘かに世論調査を行っていたと報じた。豪政府関係者は頼りとする同盟国に、信頼できない途上国のように扱われたことに苦虫をかみつぶしたという。
豪北部準州は昨年10月、ダーウィン港の長期リース権を約5億豪ドル(約440億円)で中国のインフラ・エネルギー関連企業「嵐橋集団」に貸し与えると発表した。調査は貸与についての世論を探るものだった。
オーストラリアの安全保障に影響があると思うかどうかを問う質問に対し、43%が「大い」に危険があるとし、「幾分」を含めると9割の回答者が懸念を感じていた。この結果は「経済的利益より安全保障の優先を豪政府に迫るものとなる」と評価された。報道は沈静化していた貸与問題をめぐる議論に火をつける結果となり、北京で行われた中国外務省の定例記者会見にも飛び火した。
「オーストラリア国民は冷静に客観的になってほしい。これは国際ルールにも豪国内法にも則ったビジネスであり、両国に巨大な利益をもたらすものだ」
報道官はこう述べ懸念の払拭に努めた。
オーストラリアのターンブル首相も「米豪の軍事協力が緊密にできるよう、慎重に行っている」として、ダーウィン港の長期貸与は安全保障上の問題をクリアしたものだと強調した。
「明らかな失態」
しかし、この時期の報道については、米側の意図があるとの憶測が出ている。
「巧妙に国務省側からリークされたものだろう」
シドニー大学の研究者で元オーストラリア軍将校のジェームズ・ブラウン氏は豪シンクタンクへの寄稿でこう指摘した。
「オーストラリア政府は中国の戦略性を十分に調べもせずに通した。明らかな失態であり、米政府の怒りは相当なものだ」
ブラウン氏は、嵐橋集団は民間企業とはいえ、微妙な戦略地点でインフラなどを確保する中国の国有企業のパターンを踏んでいるとの米側の見方を紹介。情報収集や地方政府への圧力といった懸念を抱いていると指摘した
豪州の港、中国企業の運営でいい? 豪政府リスク判断へ2021年5月7日
オーストラリア政府が、同国北部ダーウィン港の運営を中国企業が担うことが安全保障上、妥当かどうか検討を始めた。シドニーモーニングヘラルド紙が3日、報じた。東南アジアに近いダーウィンは戦略上の要衝で、中国企業が持つ港の運営権を豪政府が取り上げる可能性がある。
同港を巡っては豪北部準州政府が2015年、埠頭(ふとう)を99年間、リースする契約を中国企業「嵐橋集団」と結んだ。同社は「商業上の投資だ」と説明してきたが、ダットン国防相が同紙に、妥当性について豪政府として再評価を始めたことを明らかにした。
同港の運営が問題になって18年にできた「重要インフラ安全保障法」に基づいて、中国企業の運営が妥当かどうか検討する。同法では、電力、ガス、港湾、水道の各施設の所有者や運営者に、政府が安全保障上のリスクを減らすための指示を出すことができる。
2021/07/07(水)
ダーウィン港所有の中国企、ホテル開発を放棄?
オーストラリアのダーウィン港の99年リース権を所有する中国のエネルギー・インフラ企業の嵐橋集団(ランドブリッジ)が、港付近にある高級ホテルの建設用地を北部準州(NT)政府に返還し、同社による開発計画を放棄したことが分かった。
米国からは、ダーウィン港の貸与が発表された直後から不満が噴出していた。
オバマ大統領自身、昨年11月、マニラでターンブル豪首相と会談した際に事前に相談がなかったことに不快感を表明して「次回は必ず教えてほしい」と念押しするなど、同盟国に対しては異例ともいえる厳しい態度に出ていた。
「中国軍のフロント企業」
オバマ氏にとってはメンツをつぶされることでもあったのだ。オバマ氏は2011年、オーストラリアを訪れて軍事上の政策転換であるアジア回帰を表明し、ダーウィンを米軍の新たな拠点にすると発表したのだ。
以来、ダーウィン郊外には1000人を超す海兵隊員が巡回駐留しており、近く2500人規模に増強する方針だ。ダーウィンの豪空軍基地には戦略爆撃機を巡回駐留することも協議するなど、インドネシアを挟んで南から中国を睨む重要な戦略拠点だ。その港が中国側に長期貸与される事態は米国にとって、同盟国にはしごを外されるようなことだったといえる。「オーストラリアの指導者は、中国台頭を制御することの難しさをもっと論議すべきだと感じている米高官は多い」。ブラウン氏はこう指摘する。
嵐橋集団は山東省を拠点とするエネルギーやインフラ産業を主軸とする企業で港湾や石油、ガス、不動産など幅広いビジネスを展開。創業者でトップの葉成氏は、国政助言機関である人民政治協商会議の委員を務める。米紙ニューヨーク・タイムズの取材に葉成氏は「これはビジネスだ」として安全保障上の懸念を一蹴しつつも、投資は中国の外交政策「一帯一路」に資すると認めた。
一帯一路とは中国と欧州を陸路や海路でつなぐ習近平政権の大構想「中華思想」だ。葉成氏は中国政府との密接な関係を否定するが、豪有力シンクタンクの戦略政策研究所は「中国軍のフロント企業」だと警鐘を鳴らす。
「経済は中国」「安保は米国」のアンバランス
同研究所のピーター・ジェニングス所長は国会の委員会で、長期貸与についての政府対応のお粗末さを厳しく批判した。
「中国には西側諸国の軍が船舶をどう動かし、荷揚げをし、荷を積み込み、機器からどんな信号を出すのかといった細部を含め、軍のオペレーションについての極めて強い関心がある」
同氏の発言を米メディアはこう報じている。
嵐橋集団へのダーウィン港の長期貸与を決めたのは北部準州で、連邦政府は助言という形でかかわった。しかし、高まる批判の中で豪財務省は3月なかば、外国投資についての審査の厳格化を発表した。今後は州レベルの資産などでも空港や港湾など重要インフラは、連邦政府の承認を必要とするという。
今回の事態の背景にあるのは、オーストラリアの経済的な対中依存だ。同国の対外貿易は約24%を中国が占め、2位の日本(約11%)、3位の米国(約9%)を大きく引き離している。
経済は中国に、安全保障は米国にそれぞれ依存するという引き裂かれた状態が、オーストラリアの立場を苦しくしている。中国と経済的な結びつきを強める一方で中国を睨んで防衛強化を図るというアンバランスもこの現れだ。とりわけ中国と地理的に近く財政基盤の弱い北部準州は中国投資を渇望し、長期貸与への批判には「反中思想だ」などと強く反発している。
「オーストラリアは選択を迫られる。米中の対立が厳しくなればなるほど、それは厳しいものになる」
豪国立大学のヒュー・ホワイト教授は米メディアに、こう指摘した。
中国は日本の北海道も買いあさったが、豪州ダーウィン、米海兵隊拠点を中国に99年貸与された
著者:荒井悦代(あらいえつよ)
米海兵隊が駐留するオーストラリア北部ダーウィンの港湾管理権が2015年10月、中国企業「嵐橋集団(ランドブリッジ)」に渡ってから3年が過ぎた。港の99年間貸与契約には、アジア太平洋重視を打ち出したオバマ米大統領(当時)が不快感を表明し、豪州政府が中国の影響力排除へとかじを切る要因の一つとなった。しかし、豪州首都から約3000キロ離れた現地では中国の投資を歓迎する空気が強く、中央との温度差を感じさせた。(ダーウィン 田中靖人)
日本の約3・5倍の面積に人口わずか約25万人の北部準州。州都ダーウィンはそのうち12万人が住む港町だ。第二次大戦前から海軍基地が置かれ、旧日本軍が開戦直後から爆撃を繰り返した戦略的要衝である。
海沿いの市中心部から車に乗ると、軍民共用の国際空港まで約5キロ、米海兵隊の地上部隊が乾期の半年間に配備される豪陸軍基地までは15キロで、わずか20分で基地のゲートに着いた。
海兵隊の駐留は昨年9月で終了していたが、12月上旬には米空軍のB52戦略爆撃機2機が飛来した。この地はまぎれもなく米軍の対中抑止の一翼を担っている。
だが、市中心部は空き店舗が目立ち、人影はまばらだ。複数の新しい高層住宅は、昨年夏に生産を始めた天然ガス液化工場の建設関係者を見込んだもので、「今は空室が多い」(地元主婦)という。
中国語の看板が目につく最大都市シドニーと異なり中国マネーをうかがわせるものはない。それだけに港湾施設前の「嵐橋集団」の文字が目を引いた。
「ダーウィンには海外からの投資案件が多数あり、当社はその一つにすぎない」
嵐橋集団の豪州責任者、マイク・ヒューズ副総裁はこう強調した。同社は15年、港湾を99年間賃貸する契約を5億600万豪ドル(約409億円)で交わし、全額を前払いした。それまで2年間に港湾が得た利益の25倍を超える高額だった。同社はさらに、25年間で2億豪ドル(約160億円)を投資することも約束した。
豪州海軍が警備艇を置く海軍基地は外されたが、商業港に加え、豪州北部で唯一、大型艦が接岸できる軍民共用桟橋も賃貸対象となった。ヒューズ氏は「小さな港だが潜在力は高い」と語った。
賃貸契約には、中国共産党の影も指摘された。中国山東省に本拠を置く嵐橋集団の葉成(よう・せい)総裁は13~18年、中国の国政助言機関、人民政治協商会議の代表を務めた。14年8月には集団内に民兵組織を設立するなど、本社地元の軍との関係の深さもうかがわせる。
同社は豪州のアンドリュー・ロッブ前貿易・投資相を2016年の退任直後から年間88万豪ドル(約7000万円)で顧問に雇っていたことも発覚した。ロッブ氏は別の中国人企業家からも多額の献金を受け、現在は中国の巨大経済圏構想「一帯一路」への参加を促す団体の幹部を務めている。
嵐橋集団は有事に米軍の港湾利用を制限するのではないか。そんな疑問をヒューズ氏にぶつけると、「当社は港の運営者であって所有者ではない。港湾の平等な利用が契約で義務づけられている」と否定した。
台湾の林穎佑(りん・えいゆう)・中正大学准教授は「有事に意図的に船を座礁させ、米豪軍の行動を妨害する可能性はある」と別の見方だ。
外部の懸念に比べ、現地の受け止め方はおおらかだ。北部準州政府の担当者は「嵐橋集団の運営に満足している。港の拡張や設備投資も確実に実行している」と評価した。
北部準州商工会議所のグレッグ・ビックネル事務局長も「経済界は歓迎だ。お金に国籍は必要ない」と発言。嵐橋集団が軍民共用桟橋の脇に21年に開業する高級ホテルや、中国東海航空が18年5月に深センからの直行便を開通させたことを挙げ、中国の「高価格帯の観光客」に期待を示した。
パンダ3頭、米国立動物園から中国に返還へ(微笑外交とパンダ外交の罠)
米国は貸与延長を希望したが中国は受け入れなかった
…ワシントンで半世紀ぶり不在の事態に専門家「米中関係と関係ないと言い切れない」
2023年11月8日
【ワシントン=向井ゆう子】米国ワシントンの国立動物園の3頭のパンダが今月中旬、中国に返還される。米国の首都からパンダが姿を消すのは、米中が国交正常化に向けて動き出した1972年以来、51年ぶりだ。最近の米中関係の冷却化を象徴する出来事といえそうだ。
■「会えなくなるのは寂しい」
6日、ワシントンにあるスミソニアン国立動物園のパンダ舎の周りには、中国に返還されることになったメイシャン(メス、美香、25歳)とティエンティエン(オス、添添、26歳)、2頭の子どものシャオチージー(オス、小奇跡、3歳)に別れを告げようと、大勢の来園者が詰めかけた。
ワシントンに住むニコル・プランクさん(45)は、子供の頃から学校行事で同動物園を訪れ、パンダに親しんできた。「米国ではなかなかみることができない動物で、会えなくなるのは寂しい」と惜しんだ。スミソニアン動物園のパンダは特別な存在だ。72年、ニクソン大統領の電撃訪中に同行したパトリシア夫人に対し、中国の毛沢東政権が2頭のパンダリンリン(メス)とシンシン(オス)を贈った。当時のメディアは、パンダに米国人が熱狂し、パンダが「まるで毛氏であるように」大切に飼育されたと伝えている。
リンリンとシンシンとの間には子供も生まれたが、92年にリンリン、99年にシンシンが死んだ。中国は2000年、研究目的として、同動物園に新たなパンダを貸し出した。それがメイシャンとティエンティエンだった。
■24年には全米からいなくなる
中国はこれまでに複数回、米側の求めに応じて2頭の貸し出しを延長してきた。米メディアによると、動物園は今回も貸与延長を希望したが中国は受け入れなかったという。メイシャンとティエンティエン、シャオチージーの3頭は15日までに中国に戻る。現時点で代わりのパンダが来る計画はない。
全米では、パンダの中国への返還が相次いでいる。いずれも期限切れに伴うものだ。今年4月には南部メンフィスの動物園のパンダも中国に戻った。南部アトランタのパンダも24年に中国に返還される予定だ。中国から新たな貸与がなければ、24年には全米からパンダがいなくなる見通しだ。
愛くるしい姿で人々を魅了するパンダは、中国の重要な外交手段だ。友好親善のシンボルとしてだけでなく、政治・経済関係を強める国に戦略的に贈られてきた。中国の習近平(シージンピン)政権は、パンダを積極活用する「新パンダ外交」を推進中だ。
「パンダ外交」の歴史は古い。1941年、当時の中国大陸を支配していた国民党の蒋介石の妻、宋美齢が友好親善のために米国に贈ったのが始まりだ。戦後の中国は、関係が深かったソ連などにパンダを贈ったが、敵対国にパンダを贈ったのは米国が初めてだった。中国と国交正常化を果たした日本にも72年に贈与され、パンダブームが起きた。
パンダ外交に関する著書があるカリフォルニア州セント・メアリーズ大学のエレナ・ソングスター教授は、「中国には米国からパンダを呼び戻すという明確で意図的な計画があるようだ。米中関係と関係がないと言い切れない」との見方を示した。
英国最後のパンダ2頭 滞在12年、中国との関係悪化するなか帰国へ
ロンドン=藤原学思2023年12月5日
英国に残る最後のジャイアントパンダ2頭が2023年12月4日、中国に向けて旅立った。スコットランドのエディンバラ動物園で12年間を過ごし、園の主役として愛されてきた。
帰国するのは、オスの陽光(ヤンコワン)とメスの甜甜(ティエンティエン)。ともに2003年8月に中国で生まれ、スコットランド王立動物園協会(RZSS)と中国野生動物保護協会の協定のもと、11年12月に英国に送られた。
当初の契約期間は10年だったが、新型コロナウイルスの影響により、滞在が2年延長されていた。
RZSSのデービッド・フィールド最高経営責任者(CEO)は「2頭は何百万人もの人びとに自然への関心を抱かせ、すばらしい影響を与えた」とする声明を発表した。
園は甜甜の出産をめざして努力を重ねてきたが、成就しなかった。RZSSは、「ジャイアントパンダの繁殖、飼育、獣医学的ケアに関する理解に大きく貢献した」としている。
一方、英中関係はこの12年間で劇的に変わった。米調査機関ピュー・リサーチ・センターによると、現外相のキャメロン氏が首相だった11年は中国に対して「好ましくない」と答えた英市民は26%だったが、23年はその割合が69%にまで上がった。(ロンドン=藤原学思)
「パンダ外交」転換に イギリスの動物園で唯一飼育の2頭を中国に返還へ
2023年12月5日
イギリスで唯一パンダを飼育している動物園が年内にもパンダを中国に返還します。イギリスにおける中国の「パンダ外交」が一旦、終止符を打ちます。
イギリス北部・スコットランドにあるエジンバラ動物園で2023年12月30日、中国に返還されるパンダの雄の陽光と雌の甜甜の一般公開が最終日を迎えます。
動物園では2011年からパンダ2頭を年間100万ドル、日本円でおよそ1億5000万円で中国からレンタルしていて、返還の表向きの理由として契約期間の終了などを挙げています。
中国は外交手段として世界各国にパンダをレンタルしていますが、これでイギリスの動物園からパンダはいなくなります。
今年2月には、動物園側はどこも、北欧・フィンランドの動物園でもパンダの飼育が経営を圧迫しているとして中国への返還が検討されるなど、世界各国で中国のパンダ外交が転換期を迎えています。突然の「パンダ引き上げ外交」となっています。
パンダ来英と英中通商関係 - エディンバラ動物園に2頭
昨年12 月、スコットランドのエディンバラ動物園に中国から2 頭のパンダが送られたことは、大きなニュースとなった。既にその愛くるしい姿で多くの人を魅了している「陽光」と「甜甜」の2 頭であるが、英中間における近年の著しい経済関係の発展を象徴するシンボルのような存在であるとの声もある。
ジャイアント・パンダとは
主に中国・四川省西北部、西部及び西南部に生息している、クマ科-ジャイアント・パンダ亜科の動物。学名はAiluropoda melanoleuca、中国名は大熊猫。
大人の雄の体長は150〜180センチ、体重は64〜125キロ程度。雌はこれよりやや小さい。
現在、野生のジャイアント・パンダの数は1300頭程度とされている。国際自然保護連合(IUCN)により、絶滅危惧種に認定されており、ワシントン条約で売買が禁止されている。
主食は竹と笹であるが、果物なども食べる。野生のジャイアント・パンダは、竹と笹以外の草のほか、まれに鳥などの肉を食べることもある。
基本的に単独で行動する。冬眠はしない。発情期は1年に1回で、雌が妊娠できる状態にあるのは1年に2日のみである。
ジャイアント・パンダが飼育されている欧州内の動物園
保護プログラムの一環として来英
昨年12月初頭、スコットランドのエディンバラ動物園に、2頭のジャイアント・パンダが到着した。2頭はともに2003年生まれで、名前は雄の「陽光(ヤングアン)」と雌の「甜甜(ティエンティエン)」。国際自然保護連合(IUCN)により絶滅危惧種に認定されているジャイアント・パンダの保護プログラムの一環として、中国・四川省のパンダ保護センターから貸し出されてきた。2頭は今後、エディンバラ動物園で最低でも10年間過ごす予定で、同動物園は、中国当局に毎年100万ドル(約7784万円)を支払う。
中国との通商関係強化に熱心な政府
中国は、海外の国にパンダを贈ることによって、友好関係を築こうとするいわゆる「パンダ外交」を展開してきたことで知られている。しかし、現在の英国は、パンダ外交によって中国から友好関係を求められる立場にはなく、逆に、経済発展著しい中国に対して、英国企業にビジネス・チャンスを与えてくれるよう頼む側となっている。
英国がいかに中国との通商関係強化を重視しているかは、キャメロン首相が2010年11月、大臣数人のほか、50人もの企業・教育界関係者から成る大規模な訪問団を従えて訪中した事実からもうかがえる。この際には、英国のロールスロイス社が、中国の中国東方航空と、12億ドル(約933億円)相当の商談を成立させたことなどが明らかにされた。また、2011年6月には中国の温家宝首相が来英し、英中間で14億ポンド(約1680億円)相当の商談が成立したと発表された。更に、両国間の貿易の規模を、2015年までに1000億ドル(約8兆円)に到達させるとの目標も改めて確認された。
スコットランド自治政府も、中国との通商関係強化に対する熱心さでは負けていない。エディンバラにパンダが到着した昨年12月初旬、同自治政府のアレックス・サモンド首相はちょうど、2007年5月の首相就任以来3度目となる中国への公式訪問中であった。この際には、中国の航空関係者らが2012年初頭、スコットランドを訪問し、中国−スコットランド間の直行便就航を検討すること、在北京企業が今後3年間で、スコットランド産ウイスキーの販売店を中国国内に300店開店することなどが明らかにされた。
こうした事実から、今回エディンバラに貸し出されたパンダは、中国の「外交カード」ではなく、両国間における最近の通商関係の目覚しい発展を象徴するシンボルのような存在であると指摘する声もある。
動物園は入場者7割増見込み
パンダの到着によって、英中間の経済関係がより強固になるかどうかはともかく、2頭が送られてきたことによって、最も経済的な恩恵を受けると考えられるのはもちろん、エディンバラ動物園である。同園は昨年、入場者が15%落ち込み、財政難に陥っている。しかし、パンダが来たことで、今後1年の入場者数は、前年比7割増が見込まれている。2頭の一般観覧は既に先月中旬から始まっているが、盛況であることが伝えられている。2頭に子供が生まれれば、更なる入場者増も見込めると考えられており、期待が高まっている。
英のパンダ2頭、中国に返還 「友好の使者」滞在12年
2023/12/5
英国で唯一のジャイアントパンダ2頭が4日、返還のため中国に旅立った。中国から貸し出された2頭は2011年12月に英国に到着し、北部スコットランドのエディンバラ動物園で12年間過ごした。英国民に親しまれ、英中の「友好の使者」の役割を担ってきた。英メディアが報じた。
2頭は03年生まれで、中国四川省のパンダ保護研究センターで飼育された雄の「陽光」と雌の「甜甜」。貸与期間は10年の予定だったが、新型コロナウイルスの影響で動物園が閉鎖され、返還が2年延期された。BBC放送によると、繁殖計画もあったが成功せず、貸与契約はこれで終了する。スコットランド王立動物園協会のフィールド最高経営責任者(CEO)は「飼育スタッフだけでなく、来園者やファンにとっても悲しいことだ」と語った。(共同)
パンダのレンタル料は2頭で年1億円! 中国の「パンダ外交」に隠された思惑とは? 経済評論家・上念司
2017/7/16
東京・上野動物園のジャイアントパンダが5年ぶりに赤ちゃんを出産し、日本中がパンダブームに沸いた。ただ、中国にとっては、その愛くるしい姿とは裏腹の、したたかな外交ツールでもある。中国の「パンダ外交」に隠されたその思惑とは。(iRONNA)
◇
1972年のニクソン、田中角栄の電撃訪問でこの国が少しまともになる前まで、中国のやっていたことは今の北朝鮮と変わらない。そして、当時の「パンダ外交」とは、世界中から孤立していた中国が、パンダという希少動物をネタにして、何とか世界に振り向いてもらおうとする外交政策だった。だからこそ、パンダは友好の証しとして無償譲渡され、文字通り外交的な貸しを作ることで政治利用されてきた。
ところが、81年に中国がワシントン条約に加盟したことを契機に、無償譲渡は終わった。現在、中国がやっているのは世界中の動物園に共同研究や繁殖などを目的として有料で貸し出すビジネスだ。報道などにある通り、パンダのレンタル価格は2頭で年に約1億円である。
報道しない自由
しかし、それでもパンダ外交は終わっていない。今までは中国が自分のカネでやっていた外交的プロパガンダを、相手のカネでやるように変わっただけである。あえてこれを「新パンダ外交」というなら、中国にとってはより都合の良いビジネスであるといえるだろう。
例えば、上野動物園のリーリーとシンシンも、貸与された東京都が中国野生動物保護協会と「共同研究」目的で協定を結び、10年間の有料貸し出しを受けているにすぎない。先日、誕生した赤ちゃんパンダも、この協定により「満24カ月」で中国側に返還することになっている。パンダのかわいさに目がくらみ、尖閣諸島に押し寄せる中国公船への対応が甘くなったりはしていないと思いたい。
マスコミはかわいらしいパンダの赤ちゃんをネタとして扱うだけで、こうした背景については何も語らない。すぐに「報道しない自由」を発動し、中国の意図を隠蔽(いんぺい)してしまう。そもそも、パンダビジネスとは侵略と人権弾圧の歴史の象徴だ。
かつて、パンダの生息域は現在よりもずっと広かった。しかし、11年の辛亥革命以降、中華民国軍が東チベットを侵略し、多くの中国人が入植してきたことでパンダは乱獲されるようになった。だが、チベットの支配地域に残ったパンダは虐殺を免れた。なぜならチベット人は仏教徒であり、無益な殺生をしなかったからだ。
ところが、50年に悲劇が訪れる。今度は中共軍がやってきた。東チベットのチャムドが侵略され、翌年にはチベットの首都、ラサが占領された。そして、55年にチベットの東半分は青海省と四川省に組み込まれてしまった。中国はチベットから領土を盗み、その地域に生息していたパンダまでも盗んでいったのである。
失った正当性
次に、中国が行っているパンダの有料レンタルビジネスの正当性がすでに失われていることについて指摘したい。これは私が勝手に言っているのではなく2016年9月の、世界自然保護基金(WWF)の公式な見解だ。
この見解の中で、WWFはパンダの格付けが「絶滅危惧種から危急種に引き下げられた」ことを朗報として伝えている。国際自然保護連合(IUCN)によれば、14年までの10年間で中国国内の野生のパンダの頭数は17%増加し1864頭になったそうだ。私が子供のころ、パンダは千頭しかいないといわれていたが、いつのまにこんなに増えたのだろうか。
パンダがもはや絶滅危惧種ではなくなった以上、有料でレンタルして共同研究を進める正当性もかなりグラついていると思える。しかし、中国にこのビジネスをやめる気配はない。もともと、チベットから盗んできた動物なのに、なんとずうずうしいことだろう。
パンダに罪はない。罪深いのは中国だ。私たちはパンダを見るたびに、その背後にあるドロドロしたものから目を背けてはならない。
iRONNAは、産経新聞と複数の出版社が提携し、雑誌記事や評論家らの論考、著名ブロガーの記事などを集めた本格派オピニオンサイトです。各媒体の名物編集長らが参加し、タブーを恐れない鋭い視点の特集テーマを日替わりで掲載。ぜひ、「いろんな」で検索してください。
◇
【プロフィル】上念司 じょうねん・つかさ 経済評論家。昭和44年、東京都生まれ。中央大法学部卒。経済評論家の勝間和代氏と株式会社「監査と分析」を設立。金融、財政、外交、防衛問題に精通し、積極的な評論、著述活動を展開。近著に『習近平が隠す本当は世界3位の中国経済』(講談社)。
随分前の話だが、外務省の中国課長経験者から聞いた話である。自民党の某元幹事長と某元総裁は、どちらがより親中かを競い合い、片方が訪中するとすぐにもう一方もはせ参じた。元課長は嘆じた。「そして時の日本の首相の悪口を言う。中国側は彼らを歓待するが、心の底では軽蔑していた」。
▼訪中して王毅共産党政治局員兼外相らと会談した公明党の山口那津男代表の場合はどうだったのか。「山口氏は今さら何で中国へ行くのかな。習近平国家主席と会えるかどうかは分からない」。公明党関係者が事前に漏らしていた通り、過去に4度会っている習氏との会談は今回は実現しなかった。
▼山口氏は一連の会談で「(対中)国民感情を友好的にするための一つの手立て」として、仙台市へのジャイアントパンダ貸与を要請した。だが、中国との間で邦人拘束、日本産食品輸入規制、日本の排他的経済水域内での中国ブイ設置…と懸案が山積している中で、なぜ対中感情を和らげる必要があるのか。
「不便がないように」英国最後のパンダが故国へ…軍事作戦並みの帰還
2023年12/5(火)
英国に残された最後のジャイアントパンダのメス「テンテン(甜甜)」とオスの「ヤングァン(陽光)」が2023年12月4日(現地時間)、中国四川行きチャーター機に乗って故国に向かって出発した。2011年に盛大な歓迎式と共に英国の地を踏んでから12年が過ぎていた。
BBCによると、これまで英国スコットランドのエディンバラ動物園で飼育されていたテンテンとヤングァンはこの日午後1時40分ごろ、エディンバラ空港から特別チャーター機に乗った。中国南方航空所属のチャーター機には座席の大部分が除去されて長さ190センチ、高さ146センチ、幅127センチの大きさの特殊な鉄製のゲージが設置された。約13時間の飛行だ。
引き戸や小便トレイ、パーティションなどが備わった鉄製のゲージについてエディンバラ動物園は「小さく見えるが、かなり空間が広いゲージ」とし「飼育係の注文に基づいて作られた」と説明した。出国道中の混乱を避けるために出発時刻は秘密にされた。
チャーター機には飼育係や獣医師など両国関係者が搭乗して、飛行の半分時点で英国側の飼育係が中国側の飼育係にゲージの鍵を渡すことで責任も委譲する。最終目的地は四川省成都の野生動物保護協会だ。
飼育係はパンダ返還作業のためにさまざまな事前作業を進めた。両国政府間の合意に伴う動物保健規定を守るために動物園は先月初めからパンダを隔離し、飛行に備えた訓練も行われた。飼育係のマイケル・リビングストンさんは「パンダは朝に寝そべることが好きなので、朝早くに出発する時間に慣れされるために起床時間を少しずつ操り上げた」と話した。
当初、テンテンとヤングァンのレンタル契約期間は10年だった。コロナ禍で2年間レンタル期間を伸ばし、少なくとも8回の繁殖にチャレンジしたが成功させることができなかったため英国にはパンダが残っていない。
これまで動物園側は毎年79万ポンド(約1億4700万円)を中国に支払い、棲息地の造成や飼育係の賃金など管理費は別途支出した。ただしテンテンとヤングァンが動物園に到着して1年間で入場券の販売量が50%上昇したとBBCは伝えた。
先週末、英国全域ではテンテンとヤングァンに最後の挨拶を伝えようとする人々が殺到して長い行列ができ、場所取りをしようともみ合いまで起きた。ロレン・ダリングさん(35)は「もしかしたら7歳の息子が人生でパンダを見る最後の機会になるかもしれないと思って飛行機に乗ってきた」と話した。
パンダは外交・政治的象徴性が大きく、英国の追加レンタルについては何も決まっていない状況だ。エディンバラ動物園側は「新しいパンダが来る計画はまだない」と明らかにした。
一方、韓国で初めて自然妊娠で生まれた3歳のパンダ、フーバオ(福宝)も繁殖が可能になる来年には中国に戻る。フーバオの親であるメスのアイバオ(愛宝)とオスのローバオ(楽宝)は2031年まで韓国で引き続き飼育される予定だ。
東京で生まれたジャイアントパンダ、中国に返還…所有権は中国
ⓒ 中央日報日本語版2023.02.21
東京・上野動物園のジャイアントパンダ「シャンシャン」が観覧客と別れのあいさつをした。
上野動物園は19日、観覧客にシャンシャンを最後に公開したと報道した。動物園は1日の観覧客数を2600人に制限したが事前抽選に6万人以上が応募した。最も遅い時間帯の競争率は70倍に達した。
この日観覧客は動物園が準備したメッセージボードにシャンシャンに伝える最後のメッセージを残した。一部の観客はさびしさから涙を見せたりもした。
シャンシャンは2017年6月に上野動物園で生まれた。2011年に中国から借りてきたオスの「リーリー」とメスの「シンシン」の間に生まれた。
シャンシャンの所有権は中国にある。田中角栄政権時代に初めて、中国は1972年に日本との国交正常化を記念してパンダ1組を贈った。その後も日本にパンダを贈っているが所有権の移転は認めなかった。
シャンシャンは当初2019年に中国に返還される予定だった。だがコロナ禍を受け返還延期を求める市民の声が大きくなり数回にわたり延期された。シャンシャンは21日に中国南西部の四川省のパンダ保護研究センターに返還される。
2024年6月5日 中国とスペインの「パンダ外交」が始まる。
中国進出日系企業の業績悪化際立つ 「拡大見込む」は初めて3割下回る ジェトロ調査
2023年11月22日
海外に進出した日系企業のうち、経済が減速している中国に進出した企業の業績悪化が際立っていることが分かりました。
ジェトロ(日本貿易振興機構)は、8月後半から9月にかけ海外83の国や地域の日系企業に実態調査のアンケートを行い、7632社から回答を得ました。
それによりますと、海外に進出した日系企業のうち、今年黒字を見込んでいるのは63.4%で去年より1.1ポイント下がって3年ぶりに減少しました。
特に日本との関係が厳しくなっている中国については経済の減速が響き、進出した日系企業の業績悪化が際立っています。
事業拡大を見込む企業は27.7%と2007年の調査開始以来、初めて3割を下回りました。
ただ、第三国への移転や撤退を見込む企業は0.7%にすぎず、ジェトロでは「中国の市場を確保したいものの、経済の低迷や先行き不透明があるなか、ビジネスの継続へ慎重に取り組む姿勢がうかがえる」と分析しています。
1975年から日中経済協会(日本の蔵売り)による訪中は、最大の危機となった!!
「日中経済協会」財界トップが大挙訪中も中国は塩対応、しかも帰国後にまさかの暴挙!
2024年2月2日
日本経済界の重鎮らが中国を訪れる日中経済協会(日本の蔵売り)の訪中団200名近くが、2024年1月23~26日の日程を終えて帰国したが、報道された成果は中身に乏しく「子供の使いか」と突っ込まれる始末だ。
「日中経済協会(日本の蔵売り)による訪中は1975年からほぼ毎年行われていましたが、19年秋に訪れたのを最後にコロナで途絶えており、今回は4年ぶり。訪中団は経団連の十倉雅和会長、日本商工会議所の小林健会頭が最高顧問を務め、進藤孝生・日本製鉄会長が団長という錚々たるメンツで、180人もの団員を引き連れて行われました。ところがアステラス製薬の駐在員が23年10月に逮捕され、企業が懸念を抱いている反スパイ法に関しては、王文涛商務相から『日本でも同様の問題が起きている』といった意味不明の回答をされるありさまでした」(経済ジャーナリスト)
続く李強首相との会談でも、今回の訪中で伝えるべき主要テーマであった日本の水産物の輸入禁止撤廃、日本人の短期滞在のビザ免除がコロナ以来4年近く停止になっている件についても、要求だけは伝えることはできたものの具体的対応についてはゼロ回答というのだから、「何のために行ったんだ」とも言いたくなる。
「もっとも、李強首相は習近平に次ぐナンバー2といっても、今は行政より党の方が圧倒的に力が強いので、ある意味、李強首相自身も『子供の使い』のようなもの。抗議の意を伝えたことに意義はありますが、習近平の首を縦に振らせない限りは大きな成果は得られません」(同)
そして訪中団が日程を終えて帰国した翌27日には、中国海警局の船2隻が尖閣沖の領海に侵入。1月11日以来、今年に入って2度目のことだったが、後ろ足で砂をかけるような行為をするあたり、なんとも厄介な国であることに変わりはないのだった。
(猫間滋)
「2020年 オーストラリア編」
今、オーストラリアと中国の関係がひどく悪化している。
2020年6月8日、中国政府は中国人に対してオーストラリアに旅行しないよう勧告。中国の文化観光省のWebサイトには、「決して豪州には行かないように」との通知が掲載された。
中国側はこの勧告の理由を「オーストラリアで中国人への差別が横行している」からだとしている。だが直接の理由は、4月にオーストラリア政府が、新型コロナウイルス感染症に対する中国当局の初期対応などについて、WHO(世界保健機関)に独立的に検証する作業を求めたことがある。その報復として、中国政府は今、オーストラリアへのあからさまな「嫌がらせ行為」をいろいろと繰り広げているのだ。
まだこの対立が収まる兆しはない。そしてこの争い、日本にも対岸の火事ではない。というのも現在、オーストラリアの最大の貿易相手国は中国だが、それがシフトしていく可能性もあり、そうなると日本とビジネス面でのつながりが増す可能性があるからだ。
オーストラリア政府は中国に対して、これから代わりに日本やインドとの関係をさらに強化するとも示唆している。つまり、日本のビジネスパーソンにとっても、この状況は知っておく必要があるだろう。
「新型コロナ発生の責任」を否定し続ける中国
現在、中国は「新型コロナウイルスの発生源である」という世界的なイメージに過激なほどの反論を続けている。例えば、世界中でTwitterなどを駆使し、新型コロナの感染拡大について中国の責任を転嫁するようなプロパガンダを行っている。在日中国大使館も、5月に「COVID-19ウイルスについて米国による24のうそとその真相」という5回シリーズの動画をTwitterで掲載している。世界中の大使館関係者やプロパガンダ要員などが中国の主張を拡散させている。
もちろん今のところ、新型コロナがどう発生したのか明確には分かっておらず、誰も100%正確なことは言えない状況ではある(もし誰かが真実を知っているにしてもそれが表には出ることは当面ないだろう)。要は、突っ込みどころの多い中国の言い分ですら100%間違っているとは今のところ言えないのが、新型コロナをめぐる情報を扱う際の難しさである。
とにかく、中国の対外イメージが低下しているのは間違いなく、それは中国の情報関連機関も認めている。中国政府系のシンクタンク、中国現代国際関係研究院では、新型コロナによって、中国に対する敵意が1989年の天安門事件以降で最も高まっていると分析している。中国はそれを何とか改善したいと考えているのである。
オーストラリアは2021年4月に国際社会に向けて独自調査を求めたことで、その中国の「地雷」を踏んだわけだが、もちろん全てを見据えた上での動きだと見る人は多い。なぜなら、これまでも、両国間にはさまざまな衝突があった。実のところ、オーストラリアによる中国に対する不信感はかなり根深い。
買収・投資でオーストラリアに侵食
オーストラリアと中国は経済的なつながりも深く、関係は悪くなかった。もちろん水面下ではいろいろな駆け引きはあったが、両者の関係が表面的にも悪くなりだしたきっかけの一つは、2016年までに大きくなっていた南シナ海問題だった。16年当時、オランダ・ハーグの仲裁裁判所は、南シナ海での中国の海洋進出を巡り、国連海洋法条約に基づいて、中国が主権を主張する独自の境界線「九段線」に国際法上の根拠がないと認定。中国が南シナ海に強引に造成した人工島は、「島」だと認めることすらしなかった。
さらに2017年になると、オーストラリア国内で中国が異常な活動をしているという疑惑が明らかになり、両国関係がさらにギスギスするようになった。大きな話題となったのが、中国政府によるオーストラリアへの内政干渉工作だった。中国人留学生を使ったスパイ工作や、政治家へのひそかな献金、中国人による土地買収の強化などの行為が問題視されるようになっていった。
オーストラリアは、全土の2.3%を中国企業が所有しているとも言われている。また10年ほど前から、中国はカネに物を言わせて、オーストラリア企業の買収や投資をし、それに1500億オーストラリアドルが費やされているという。
さらにオーストラリアの基幹インフラにまで手を出そうとした。15年には北部準州が、ダーウィン港の管理権を中国企業に99年間貸与する契約を結び、大変な論争を引き起こした。有事などの際に港がどう中国側に使われるか分からないという懸念が上がったのである。また2016年には最大都市シドニーなどに送電する電力公社オースグリッドについて、中国国営企業などが買収を試みたのだが、さすがに政府が安全保障上の懸念があるとして売却を阻止したこともある。
少なくとも、中国がオーストラリアを乗っ取る勢いであったことは間違いない。中国は、オーストラリアで影響力を強めて親中にすることで、南シナ海問題でも自分たちが優位に立てると考えている。ちなみに中国のこうした動きは、インフラ投資という名で今まさにバヌアツやフィジーやカンボジア、タイ、マレーシア、ラオスなどでも起きている。バヌアツのラルフ・レゲンバヌ外相は悪びれることなく、中国からの多額の投資の見返りに、国連で中国寄りの投票を求められていると暴露している。
中国はオーストラリア産牛肉を一時、輸入禁止とした。写真は2019年、中国・北京で。
ファーウェイの動きにいち早く警戒
中国は、オーストラリアの政治にも食い込もうとした。2019年5月にオーストラリア史上初めて中国生まれの中国系オーストラリア人女性が連邦議会の下院議員に当選。だがこの女性が中国共産党と近い企業と関係があるとして糾弾されている。また、中国のスパイ工作員とみられる中国人が、若い中国系オーストラリア人男性を連邦議会で当選させようと画策していた疑惑も取り沙汰されている。この中国系オーストラリア人男性は結局、ホテルで死亡しているのが発見された。
もう一つ忘れてはいけないのが、中国の電気通信大手、華為技術(ファーウェイ)の問題だ。オーストラリアは、米国政府が同盟国にファーウェイ製品の排除を求めた際、真っ先に賛同した国だが、その理由は、以前から独自でファーウェイの動きを警戒していたからだった。オーストラリアの大手企業元幹部は筆者の取材に「2014年に、社内のネットワークからファーウェイ製品を介してデータが不正に中国に送信されていることを察知した」と明かした。この大手企業は実際にファーウェイ側に説明を求めたそうだが、返答は「メンテナンスをしていた」というものだった。結局、同社はファーウェイと契約を解除し、政府にも通達。「それ以降、オーストラリア政府は政府関係機関や大手企業にファーウェイ機器を使わないよう非公式に通達していた」という。
とにかく、こうした経緯から、最近のオーストラリアと中国の衝突は起きるべくして起きたのである。そして冒頭のように「オーストラリアに行くな」と告知したり、中国人留学生にはオーストラリア留学に慎重な判断をするよう促したりしている。また中国政府は、オーストラリア産の食肉を一部輸入停止したり、オーストラリア産大麦に追加関税を課すなどの措置にも乗り出している。さらにはつい最近、麻薬密輸の罪で逮捕されていたオーストラリア人が死刑判決を下されたことも、中国による嫌がらせの一部と見る向きもある。
こうした両国の関係は、今後さらに冷え込む可能性が考えられる。
(中国に変わって)日本は「オーストラリアとの関係強化」に期待できる
日本としては、オーストラリアが中国と距離を置くことで、オーストラリアとの関係強化が期待できる。両国はこれまでも良好な関係を築いているが、その関係がさらに強まるかもしれない。事実、今後海外進出を考えている豪企業への調査では、進出先として日本は5位に入っている(2019年調査)。1位は中国で2位は米国だが、今年に入って中国とは対立し、米国は新型コロナや国内の暴動が不安要因として懸念されるようになっており、自ずと日本への注目も高まりつつある。
さらに、オーストラリアが進めているスマートシティ計画でも、日本の先端テクノロジーが注目されており、何かと警戒される中国製品よりも期待されている。オーストラリア国内では南東部などで大型のインフラ開発が進んでおり、そうした事業でも日本への期待が高まっている。
国民感情的にも、オーストラリアは中国よりも日本にさらに近づくだろう。新型コロナが落ち着けば、さらなる商機も見えてくるかもしれない。世界を見据えているビジネスパーソンならしばらくオーストラリアの動向は要チェックだ。
新型コロナウイルス、最初の感染源ついに判明、やはり武漢の市場から 中国が誤魔化し切れなくなった「タヌキ」
2023年4月18日
中国当局(疾病予防控制中心)は、繰り返し否定しきたが、どうやら感染源(ウイルスのヒトへの仲介源)がしぼり込まれてきたようだ。それも中国側のポカによってのこと。自ら語るに落ちたわけだ。はっきり言えば、嘘がばれないように嘘の上塗りを重ねてきたが、ついに嘘をつききれなくなってしまった。
意図的だった? ズサン極まりない疫学調査
2019年の11月の末ないし12月の初めには、感染者が発見されていた。1ヵ月後には、感染者の多くが、武漢の駅の南にある大きな市場(主として水産物を扱う武漢華南海鮮批発市場)の関係者とわかり、翌20年の1月1日から閉鎖された市場で、ウイルス探しが始まった。
武漢華南海鮮批発市場 by Gettyimages
© 現代ビジネス
だが、サンプルの採取法が実にズサンだった。売り場を水で洗い、回収した汚水を区画ごとに分けて大きな容器に入れて運び、PCRによって検査した。
その結果は、ウイルスと売られていた動物とヒトの遺伝子、これら3種の遺伝子が混在する状態が、市場の区画ごとに確認されただけだった。
特定の売り場、特定の動物(商品)、特定の籠や箱や台車にはしぼりこまれなかった。疑われるものごとに拭き取り、個別に収集しなければならないのに、それをやらなかった。と言うか、できなかった。疫学調査の一丁目一番地のワキマエが欠けていた。
意図的にサンプルを破壊したのか、それとも疫学と防疫の水準の低さのためなのか。蔓延から3年を経過した現在から総合的に見ると、両方が原因だったと判断される。結果的には、学術の水準の低さを、国家の威信を一時的に守るのに利用したことになるだろう。
という次第で、市場の南西の区画、イカモノの獣(生きたまま、あるいは肉や臓物)をとくに扱う一角が、ウイルスで汚染されていたことだけは、中国当局も認めざるを得なくなった。そんな中途半端な状況のままが現在も続く。
フランスのウイルス学者が仲介源をタヌキと同定
今年の3月4日、フランスの国立科学センター(CRNS)のウイルス研究者で、大学でも教えるフロランス・デバールが気づいたのだが、インフルエンザ関連のデータ・センター(GISAID、本部はワシントンDC)に、武漢の市場で採取された遺伝子配列データが、中国から2022年6月付で登録されていた。
彼女を中心とするグループは、それらのデータをあらためて調べ、5日後の9日には、コロナ・ウイルスといっしょに8種類の野生動物とヒトの遺伝子が混在しているのを確かめた。野生動物は、タヌキ(日本のそれと同種)、ハリネズミ、ヤマアラシ、タケネズミ、マーモット、ハクビシン、イタチ、ブタバナアナグマだった。それらのうちで、店頭でもっとも多く見つかったのがタヌキの遺伝子だった。
論文では、8種類の野生動物の比率は示されていない。だが、「タヌキを含む野生動物」と筆頭に挙げることによって、売られていたタヌキが感染源だと、限りなく断定に近い表現になっている。検討結果は、論文として3月20日に公開された。
ところが、不可解なことに、中国からの申し出によって、肝心のデータそのものが3月11日に取り下げられた。フランスでのタヌキ同定を、中国当局が察知したからだろう。中国がもっとも隠したいタヌキに関するデータを、うっかり海外に出してしまったのは、科学的には妥当で必須だが、政治的には、つまり、中国の国際的駆け引きにとっては、致命的なポカだった。そのためますます自縄自縛に陥り――嘘のため嘘をつき続けねばならなくなった。
近くに存在する余りにも潤沢すぎるタヌキの供給源
中国の研究者によると、武漢の市場で売られていたタヌキは、平均すると毎月38匹、1匹の平均価格は63ドル(約8000円)だった。15匹を売れば、大学新卒の月給(12万円)と同じになった。おいしい商売だった。
高価で売れたのは、イカモノの獣肉の味覚や薬効からではない。それを使った料理は贅沢とされ、それを出されるのは歓待、格別な配慮の要請(一種の贈賄)を意味したからだ。
ということは、社会的腐敗がコロナ肺炎の世界的大流行をまねいたと、世界中から糾弾されることになるわけで、それを北京当局が恐れて、武漢の市場の感染情報を隠したがっているのだと疑われても仕方がない。
中国全土の獣肉市場には、広く全国に存在する毛皮獣飼育場から、タヌキやキツネやイタチなどが生きたままで供給されてきた。料理する直前まで生きているのが尊重されたからだ。というわけで、動物が飼育場でコウモリからウイルスをうつされると、ウイルスを持ったまま、動物が人口密集地に持ち込まれ、いともたやすくヒトへの感染源になる。そういう社会体制がつくられていたわけだ。
武漢の市場にタヌキを供給したのは、武漢と同じ省内、湖北省西端の山岳地帯、恩施(エンシ)地区に存在する飼育場群と推定される。飼育数は総計で100万匹とも伝えられる。この地帯は洞窟も多く、そこがコウモリの巣窟になっている。
この疫学モデル――「ウイルス→コウモリ→仲介動物→ヒト」――は、2002年11月から翌年7月にかけてのSARS(重症急性呼吸器症候群)の場合と、パターンが同じだ。
その点からしても、コロナ肺炎の武漢市場タヌキ起源説が、真相にもっとも近いと考えるべきだろう。これ以外の説は、米中の不信と敵意のフェイク・ニュース戦争の産物だ。
トランプ大統領のもとで、武漢の研究所からウイルスが漏れたのが原因と喧伝された。だが、研究所が保存するウイルスと、流行したウイルスとは、遺伝子の並びの細部が異なるので、この説は科学的にはまったく成り立たない。
それに対抗するため中国当局は、輸入した冷凍肉が原因だと、海外に感染源をなすりつけようと盛んに宣伝した。だが、そうした事例は世界中どこにも見られない。いまだに中国当局は海外原因説に固執するが、中国への信頼を損ねる一方だ。
次の新型肺炎はいつ、どこで起こるか
いつ起こっても、おかしくない。場所的には中国の東半分のどこで起こっても、おかしくない。というのは、感染の仲介源となる可能性の高い動物が、毛皮をとるため、中国の東半分、北から南まで、いたるところで盛んに飼育されているからだ。
砂漠と高山地帯を除く全土と言っても過言ではなく、ウイルスを運ぶコウモリの生息地とも完全に重なる。吹きさらしの野外の金網のなかで動物が飼われているので、自由に網の目をくぐってコウモリが動物の餌を盗みに入ってくる。ウイルスは何の障害もなく飼育動物へ伝染する。
シンガポールで発行される新聞「サウス・チャイナ・モーニング・ポスト」(2020年3月4日付け)が伝えるところでは、中国の毛皮業界の従業者は1400万、年間の売り上げ高は5200億元(740億ドル)に達する。
中国皮革協会によると、2021年の毛皮の生産枚数は、キツネが1100万、タヌキが919万、ミンクが687万だった。
タヌキの毛皮の生産地の比率は、河北省が66.51%、山東省が16.94%、黒竜江省が10.66%、その他が5.89%だった。武漢がある湖北省はその他に属する。つまり、武漢周辺よりもはるかに次の新型肺炎が起こりやすい地域がたくさん存在する。
振り返ると、この20年間、中国の感染症対策は本質的にはまったく改善されていない。それが証拠に、たとえば河北省の粛寧県(北京の南100キロメートル)では、昨年の暮れに「国際皮革交易会議」が開催され、年間250億元の売り上げがあったとの報告を基に、地域の人民政府の副秘書長が激励の挨拶をした。当局が音頭をとって、縮小するよりも拡大を策しているのだから、感染症対策に逆行することも甚だしい。二度あることは三度あると、世界中が覚悟していなければならない。
家畜以外は、つまり、野生動物は、市場での売買が禁止されたが、毛皮をはいだ後の肉や臓物がどのように処分されているかについては、はっきりしない。まさか市場の店頭で家畜の肉や贓物のなかにまぎれこんでいるとは、誰も思いたくないが、気になるところだ。
中国は感染症対策を根本的に改めないと、中国自体にとっても為にならないだろう。しかし、その気配はない。
99年租借地となっても中国を頼るスリランカ
スリランカのハンバントタ港が2017年7月より99年間にわたり中国国有企業・招商局港口にリースされることが決まった。このハンバントタ港をめぐる決定は中国による「債務の罠」の典型例と見なされている。すなわちインフラ建設などを行うために中国からふんだんに融資を受けたものの、施設が十分な利益を生むことはなく、借金が膨らみ、返済不能になり施設や土地を中国に明け渡さざるを得なくなった事例である。アフリカの国々はすべてこの罠にかかってしまった。
ニューヨークタイムズの衝撃
スリランカを「債務の罠」の典型例として報道する記事はこれまで数多くあったが、2018年6月25日付のニューヨークタイムズの記事は衝撃的だった。同記事は40,000ワードのボリュームからなり、これまで語られることのなかった事実が綿密な取材で構成されている。特に2つの点を明示したことに意味がある。一点目は中国と当時の大統領マヒンダ・ラージャパクサとその一族の密接な関係が暴露された。具体的には2015年の大統領選挙において、いつ、どのような経路で中国からいくら資金提供されたかなどである。二点目は、中国側もスリランカ側もハンバントタ港が軍事利用されないと再三述べているが、スリランカ側の役人らは、中国が港の戦略的な重要性を求めていることを十分認識していたことを明確にした点である。
 |
| 当時の大統領マヒンダ・ラージャパクサとその一族 |
スリランカはいきなり「債務の罠」に陥ったわけではない。スリランカは2009年の内戦終結前後から中国との関係強化を進めていた。当時、スリランカは内戦を完全に終結させるために、内戦終結後の戦後復興を進めるための資金を必要としていた。つまり当初は国内的な事情があり中国の関与を望んだのである。このことはラオス、カンボジア、パキスタンにも当てはまる。
地理的な条件すなわちスリランカが島国であることから、中国の活動が周辺諸国から危険視され、牽制されることが少なかったことも、中国の関与が大規模に進んだ要因である。今でこそ、戦略的な重要性からスリランカにおける中国の活動にインドやアメリカが目を光らせているが、中国とスリランカの関係強化が始まった頃には「一帯一路」どころか「真珠の首飾り」という言葉も一般的ではなく、インドの警戒感も薄かった。
スリランカがインド洋の要衝といわれる理由は、パソコンやスマホでmarinetraffic.comと入力して見てみるとよくわかる。マラッカ海峡並みの重要性とは言わないものの、多くの船やタンカーがスリランカの南を通過しているのがリアルタイムで見ることができる。その数は年間6万隻といわれる1。そしてまさにスリランカの南端にハンバントタ港が位置し、スリランカと中国の合弁企業がその運営を99年間任されているのである。中国はマレー半島に運河を建設しようとして、マレーシアとも「一帯一路」の契約を結んだ。
もちろんラージャパクサ側は、ニューヨークタイムズの記事に猛反発している。ラージャパクサを選挙で破った現政権もこの記事に関してはもろ手を挙げて賛成しているわけではない。植民地化ではなくWin-Winであり、ハンバントタ港の軍事化はない、と明言している。2015年以前は、マヒンダ・ラージャパクサ前政権と中国が蜜月で、その状態を打開しようとしたのが現政権(マイトリパーラ・シリセーナ大統領とラニル・ウィクレマシンハ首相)なのだが、現政権も結局は中国との関係を重視せざるを得なくなっている2。
一般のスリランカ人は中国の影響力の浸透をどのようにとらえているのか
国際関係論の視点から中国のインド洋への進出は多方面から論じられている。地政学もスリランカ・中国関係を無視できない。ニューヨークタイムズが紙面を割いたのも関心の高さ故だろう。
では肝心のスリランカの人々は中国の進出をどのように思っているのだろうか。結論から言えば,スリランカの人たちはハンバントタ港の長期貸し出しにそれほど関心を示していない。だからこそ、スリランカの野党も表向きは政権の判断(長期リース)を批判しつつも、最終的に了承したのだ。
ただ、こうしたスリランカ国民の反応には違和感がある。なぜならスリランカは、2009年まで約30年間の内戦を経験した。北・東部の独立を求めたLTTE(タミル・イーラム解放の虎)と政府軍の戦いだった。究極的には居住地である国土を巡る争いだったはずだ。そのスリランカがなぜあっさりとハンバントタ港を明け渡したのか。
もちろん、周辺住民は今でも猛反発している。港とともに周辺の約60平方キロ3が工業団地として供与されることになっており、地元住民たちは田畑を接収され、生活の糧を奪われることに反発している。
しかし、ハンバントタ周辺で農業を営む人口は圧倒的に少ない。ハンバントタ県の人口密度は1平方キロ当たり240人(2012年センサス)で、コロンボ県(人口密度3325人)と10倍以上の開きがある。ハンバントタ周辺の人々の抗議は、中国に対する多額の借金返済に焦る政権によって無視され、中国からの直接投資や融資による開発の推進を求める大きな声にかき消されたようである。
 |
| 2009年のハンバントタ港建設の様子。誰もいない建設現場 |
借金漬けの実情
スリランカの名目GDP(2017年)は871億ドルである。それに対して政府の対外債務は310億ドルとなっている。ちなみにスリランカが2008年から2018年の間に中国から借り入れたのは72億ドルである4。これをスリランカは返済することができないでいる。なぜか。一つには、中国融資の条件が他の国や機関より厳しいからである。金利が2%のものもあるが、なかには6.5%に設定されているものもある。据え置き期間も短い。二つ目には、融資を受けて作られたインフラが利益を生んでいないことがある。コロンボ首都圏とカトナヤケ空港を結ぶ高速道路は、確かに役に立っている。しかし、電力事情を一気に解消すると期待されていたノロッチョライ発電所(8億9000万ドル)は故障を繰り返している。マッタラ空港(1億8000万ドル)は世界一ガラガラの空港と言われている5。ハンバントタ港は2017年の一年間の寄港船数が251隻と惨憺たるありさまだった6。これらの操業による利益を返済に充てることは全くできないどころか、利益を上げているコロンボ港などの稼ぎで赤字を補てんしている状態だったのである。スリランカ側は中国に返済の延期などを求めたが、中国側は聞き入れなかった。
2017年9月のハンバントタ港の様子。RORO船から車両が積み下ろされている。
クレーンは設置されているものの、RORO船が主体であるため、ほとんど使用されていない
コロンボ開発にかすむハンバントタ
「債務の罠」に注目する人々が見落としている、あるいは過小評価しているのが中国によるコロンボ周辺の開発だ。スリランカを訪れコロンボに少しでも滞在すれば、中国によるコロンボの開発は誰でも実感することができる。最も大規模なのはコロンボ・ポートシティ・プロジェクト(現在の名称はコロンボ国際金融シティ、CIFC)だ。コロンボ中心地に近接する沿岸部を埋め立てて広さ2.7平方キロの人工島を建設中だ。世界中から優秀な人材を集め、シンガポールやドバイのような金融都市を作るという。島にはオフィス地区だけでなく、ホテル、ショッピングセンター、エンターテイメント施設、学校、住宅地区なども建設される予定だ。埋め立て地とコロンボを結ぶ新都市交通機関も構想され、数万人の雇用が創出されると見込まれている。
現在進んでいるのは、埋め立てのみで、金融シティに関してはあくまで計画であり、実現するかどうかもわからないし、実際にスリランカ国民の所得が増えるかどうかもわからない。しかし、大規模な埋め立てがコロンボ市民の目前で日々進行するさまは圧巻で、内戦中の十数年にわたる低成長・停滞に淀んでいたスリランカにとって、希望を抱かせるのに十分な迫力である。
さらにコロンボの街中には中国の建設するビルがそこかしこにある。中国人労働者向けの、漢字が書かれた看板があるので一目瞭然だ。これらのプロジェクトに直接従事するスリランカ人は決して多くないかもしれない。しかし、日々大きくなってゆくビル、埋め立ての進む現場に接すると、訪れたこともない、遠いハンバントタの港がかすんで見えても仕方ない。
ラージャパクサ政権時は中国からの資金を元手にしたインフラ開発が進み、好景気を下支えした。一方で現政権は、バランス外交を標榜して前政権との違いを明確にしようとしたものの、すぐに頓挫した。お金が足りなくなったからだ。そのせいだろうか、2017年の経済成長率は3.1%、南アジア諸国の中で最低だった。現政権としては、中国に借金を返し、中国から新たな融資や投資を得て開発をスピードアップして実績を作り、2020年の大統領選挙に臨みたいのだ。
どんどん高くなってゆくビル(2018年3月)。右端にあるのは中国による電波塔。
ビルが倒れかけているように見えるが、こういうデザインである。
コロンボ市民の憩いの場ゴールフェイスと目と鼻の先にあるポートシティ埋め立て現場と
中国の運営するコンテナ港CITC(2017年12月)。
対中国感情は?
中国語学習熱は高まっており、孔子学院も有力な大学に設立されている。現地エリート学校では中学生にもプログラミングと並び中国語を教えている。成績優秀者には中国短期留学の機会も与えられている。学生らの文化交流・大学における学術交流も盛んにおこなわれている様子だ。学生による「一帯一路」絵画展、大学間の考古学協力、そして海洋科学国際会議は第四回を数えている。どれも「一帯一路」を意識している。
中国人観光客は、今やインドに次いで二番目に多い。かつては街中で三輪車の運転手に「こんにちは、ありがとう」と声をかけられたものの、今ではほぼ「ニイハオ、シエシエ」だ。中国人観光客は、ツアーでやってきて、団体で定番の観光名所を巡り中華料理を食べているので、コロンボや観光地など特定の場所ではたくさん見かけるが、一般のスリランカ人の生活に入り込んでいることはない。
そのためか、国民間のトラブルは今のところ多くない。しかし、今後ツアー以外で訪れる中国人や定着する中国人が増えると摩擦が生じるだろう。スリランカはイスラム教徒が少ない7ので、酒に関するトラブルは比較的少ないが、風紀・宗教上、酒が禁止される地区や時期がある。これを守らない中国人にたいする嫌悪感があるようだ。また、免許制になっているツアーガイドをモグリで行う中国人がいることなども報告されている。
政治家らは与野党とも、もはや中国なしには経済が成り立たないのを理解している。国民も中国の投資や資金による開発を待ち望んでいる。よほどのことがない限り、この流れは変わらないものとみられる。
著者:荒井悦代(あらいえつよ)。アジア経済研究所地域研究センター動向分析研究グループ長。著作に『内戦後のスリランカ経済――持続的発展のための諸条件』(編著)アジア経済研究所(2016年)など。
注
https://thediplomat.com/2016/06/can-sri-lanka-leverage-its-location-as-indian-ocean-hub/
荒井悦代「バランス外交と中国回帰で揺れるスリランカ」『アジ研ワールド・トレンド』257号(2017年3月)、44-51ページ。
山手線の内側ほどの面積。面積はコロンボ1-15区をすべて合わせたものよりも大きく、全国の工業団地として指定されている地区の面積を合わせたものよりも大きい。労働力の現状からすると現実離れしている。
https://drive.google.com/file/d/1y0s546rtkH08jqfMMaEQeF4iNDEo4hH5/view
https://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2016/05/28/the-story-behind-the-worlds-emptiest-international-airport-sri-lankas-mattala-rajapaksa/#20c3f3e37cea
それに対してコロンボ港は5126隻の寄港があった。https://www.hellenicshippingnews.com/sri-lanka-port-authority-profits-up-after-china-takeover-of-hambantota-port/
ただしコロンボ都市部にはイスラム教徒が多い。
モルディブ大統領選 “親中国”野党候補が勝利と報道 インド重視の現職は敗北宣言
2023年10月1日
 |
| 中国との関係強化を目指すムイズ氏 |
インドと中国が影響力を競うインド洋の島国モルディブで、大統領選挙の決選投票が行われました。
中国寄りの野党候補の勝利が確実となり、インドを重視してきた現職大統領ソーリフ氏は敗北を宣言しています。
5年に一度のモルディブ大統領選は、2023年9月30日、決選投票が行われ、2期目を目指す現職のソーリフ氏と、首都マレの市長で野党候補のムイズ氏の対決となりました。
ソーリフ氏は、中国からの融資でインフラ開発などを推進した“親中国路線”からの転換を図り、インドとの友好協力を深めてきましたが、与党側の分裂もあって失速。
現地メディアは2023年10月1日未明、即日開票の結果、中国との関係強化を目指すムイズ氏が勝利したと報じ、ソーリフ氏も敗北を認めました。
海上交通の要衝にあるモルディブで再び中国の存在感が強まれば、対中国を念頭に関係強化を図ってきたインドや日本、アメリカの外交・安保戦略にも影響を与える可能性がある。
先月9月9日に実施された最初の大統領選は8人の候補が争ったが、過半数の候補はなく、46%を得票したムイズ氏と39%を得票したソーリ氏の決選投票となっていました。
インドと中国のどちらと関係を深めるかは前回2018年の大統領選に続く争点。そのときの大統領選では、当時の現職アブドラ・ヤミーン氏が「一帯一路」を掲げる中国の資金により空港や橋などのインフラ整備を進めたことに「債務のわな」に陥るとの批判が集まり、親インドのソーリ氏に敗れた。ソーリ氏は大統領に就任すると過度な中国依存の見直しを表明し、インドとの友好協力関係を進めてきた。
これに対し、ヤミーン政権時に閣僚を務めていたムイズ氏はモルディブのインド軍駐留は脅威だとし、「国の独立と主権を守る」などと訴えている。
モルディブはインド洋の海上交通の要衝にある。千余りの島々からなり、人口約55万7千人(20年)。面積は東京23区の約半分。
2021年4月2日
経済か安全保障か 「一帯一路」で揺れるスリランカ
中国が南アジアに進出する上で重要な手段が、習近平国家主席の看板政策「一帯一路」構想であり、その中でスリランカは重要なパートナーだ。
2014年、スリランカを訪問した中国の習近平国家主席とそれを出迎えた
マヒンダ・ラージャパクサ大統領(当時)。中国は専制政治の小国と協力する傾向がある (NURPHOTO/GETTYMAGES)
2013年以来、中国とスリランカの間には戦略的協力パートナーシップがあるものの、特にインフラと連結性強化のための協力に関しては、両国の関係には疑念と不安がつきものだ。島国かつ途上国であるスリランカは、連結性強化事業への中国からの資金提供と関与を積極的に歓迎し、そのプロセスの中で経済大国・中国との、より緊密な包括的パートナーシップをスタートさせた。
しかし、こうしたパートナーシップの成熟化に問題が伴わないわけではない。「海のシルクロード」の下での中国からの開発支援や経済的影響力の増大は、経済小国にとって「債務の罠」につながると懸念され、スリランカでは議論が起こっている。
歴史的に見て、中国・スリランカ関係が深まったのは、スリランカ政府と反政府勢力「タミル・イーラム解放のトラ(LTTE)」との内戦の時期である。当時、国家支援の下で人権や公民権を侵害しているという疑惑が広がり、スリランカ政府は国際社会で孤立を深めていた。西欧諸国から距離を置かれ、国内では内戦を抱えたスリランカに対し、手を差し伸べたのが中国だった。財政支援、軍事物資の提供を行い、さらに国連では政治的に援護し、国際社会からの制裁を妨害してスリランカ経済への大打撃を回避した。
中国の手厚い支援により、スリランカ政府は2009年にLTTEを打倒した。その後も支援は2015年まで続き、中国は権力の集中したラージャパクサ一族と親交を深め、中国にとってスリランカは今後の南アジアを展望する上で欠かせない存在となり始めた。
実際、習近平国家主席は2014年、中国首脳としては1986年以来初めて、スリランカを公式訪問した。さらに、スリランカの新聞に両国の関係の重要性を強調する記事を寄稿し、「チャイナ・ドリーム」と、マヒンダ・ラージャパクサ大統領(当時、現首相)の選挙公約「マヒンダ・チンタナ」で示された方針を結びつけた上で、共通のビジョンを実現するために両国関係のさらなる発展を呼びかけた。
この結果、ハンバントタ港開発事業をはじめ、スリランカは中国から巨額の融資、投資を受けることになった。この決定は同時に、中国がスリランカにおいて深い政治的影響力を持つことを浮き彫りにした。海外進出の際、中国は通常、まず経済的なプレゼンスを確立し、それを基に政治的にも台頭してきたが、スリランカでは経済ではなく政治的影響力を先に確立した。
しかしながら、ハンバントタ港の開発が果たして小国スリランカに必要なのか、特に首都に所在する主要港が栄え、拡張の余地もある時に必要性があるのかという点は、国内外の戦略専門家の間で大きな議論の的となった。
中国・スリランカの経済交流は、1952年にスリランカのゴム、中国のコメを相互に供給する協定から始まる。この「友情協定」のおかげで、スリランカ政府はコメ不足を相殺するとともに、余剰となったゴムを売る市場を確保することができた。この協定以降、スリランカは非共産主義国としては初めて、中国との経済関係を樹立することになった。
こうした経済交流は2国間関係を評価する一つの基準だが、最近では軍事、戦略、開発分野を網羅するまでに発展した。一帯一路はまさにこのような文脈に沿っており、インド洋地域の重要な沿岸国家として浮上したスリランカを、インド洋海域で活動する際の足掛かりとして中国は利用できる。中国共産党は歴史的に、政党同士の関係に基づく外交を採用していて、スリランカのような専制政治の小国と協力する傾向が特に見られる。
スリランカ政府は当初、南アジアにおけるインドの伝統的な影響力を考え、インド政府にハンバントタ港開発支援の話を持ちかけた。しかし報道によれば、元インド外務次官で当時の国家安全保障顧問のシブシャンカル・メノン氏は、ハンバントタ港開発事業について「当時も、そして今も、経済の失策である」としている。インドがこの事業へは投資しないと決めたことで、中国が一帯一路を理由に参入することになった。
そして現在、一帯一路の下で受けた融資をスリランカ政府が返済することができないため、中国は99年間にわたるハンバントタ港の運営権を手に入れた。戦略的に見れば、ハンバントタ港は中国にとっての地域のライバル、インドの目と鼻の先にあるインフラであるため、中国の海上交通路戦略「真珠の首飾り」において、スリランカがインド洋の一粒の真珠になるのではないかという不安が高まっている。
ハンバントタ港の99年にわたる運営権の譲渡を、非常に大きく警戒したのが政治・戦略の専門家らである。「債務の罠」外交によって、重い債務負担を抱えた小国の返済が継続不能となり、代わりに戦略拠点として重要なインフラへのアクセスを手放すことになる事態に、懸念を強めている。
日米豪印戦略対話に
対抗して関係強化
新型コロナウイルス感染症のパンデミックの中で、中国とスリランカの関係は拡大することになった。20年、中国政府はスリランカに対して、マスク5万枚超と新型コロナウイルス検査キット1000セットを超える、大規模な人道・医療支援だけでなく、9000万㌦の経済支援も行ったが、「債務の罠」につながるとされる批判を払しょくする狙いがある。
中国のこうした動きは、より大局的な「マスク外交」戦略、そして一帯一路をインフラ整備支援に限定するのではなく、パンデミックがもたらした新たな問題に対処するための「ヘルス・シルクロード」へとシフトする試みと同調している。
また、2020年10月6日、米国、インド、日本、オーストラリアの外相が行った、「日米豪印戦略対話(クワッド)」の第2回閣僚級会談の後、おそらくこの会談に対抗する狙いで、中国はスリランカとの関係強調を図る動きを見せた。20年10月9日、中国政府高官の代表団は、スリランカ大統領および首相と会談し、金融における2国間関係の拡大を協議した。金融の流動性を高めるため、100億元の通貨スワップ協定の交渉が行われた。これは4億㌦のスリランカ・インドの通貨スワップ協定の規模をはるかに上回る。
中国中心の将来の展望がスリランカにとって何を意味するのかについては懸念が広がっており、またスリランカ外務次官はハンバントタ港の〝リース〟は「間違い」で、戦略的安全保障の観点から「インド優先」のアプローチへの修正が必要だと認めている。
それでも、スリランカが開発支援を必要としているため、安全保障関連の要素を欠いたまま展開され、中国とのつながりは非常に重要なものとなっている。今後の進展においてはむしろ、スリランカはこの地域におけるインドと中国に対するヘッジとなることを受け入れ、両国から同時に利益を得られるよう、基本的に中立に徹し、安全保障も経済繁栄と同様に優先しようとする可能性がある。
ハンバントタ港は、スリランカにおける一帯一路事業のほんの一例に過ぎない
(XINHUA NEWS AGENCY/AFLO)釧路港もこうならない様に望む。
特に一帯一路の主力事業であるCIFCは投資額が150億㌦を超え、開始当初から物議を醸してきた。インドは海洋主権、およびこの事業がもたらす貿易リスクについて懸念している。CIFCは透明性の欠如、汚職、環境への影響といった観点から疑問視され、非難を受けた結果、事業は一時停止、捜査中となったが、その後2016年の新協定の下で再開された。
こうした事例は、一帯一路の根底にある意図や、参加する中小国家への影響をめぐる議論を増加させている。スリランカで問題となっている事業によって、実際、途上国における一帯一路との微妙な関係性が示され、その賛否とともに、参加国と簡単には切り離せない実態も明らかになっている。
一帯一路のおかげで、観光業、貿易、連結性の強化を通じ、スリランカは経済の再建と発展を遂げたが、その一方で、安全保障と主権をめぐる重要な問題も抱えている。このジレンマはポスト・パンデミックにおいては、一層深刻になるよりほかない。なぜなら、スリランカは安全保障面での懸念があっても、中国への依存を、その度合いを増さないにしても、継続するしかないからだ。
一帯一路での「債務の罠」外交に懸念を抱くのはもっともだが、スリランカはその「罠」にまだ完全に陥ったわけではない。中国への債務は合計で、スリランカの国内総生産(GDP)の6%ほどだ。とはいえ、多額の債務残高を抱えていることは、スリランカには債務管理の枠組み改善が必要であると示している。
コロナ禍で一帯一路事業に遅れが発生しており、コロンボ港湾都市事業は特にパンデミックによる複数の問題に直面している。このような状況にある今こそ、スリランカにとって時は熟したと言える。債務管理能力を強化し、将来の一帯一路での取引において、それに準じた戦略を実行すべきだ。
コロンボ港の開発を加速させた、コロンボ国際コンテナターミナル(CICT)をはじめ、スリランカ経済に大きく寄与した事業もある。しかしながら、スリランカでの一帯一路事業のため、中国からの輸入が増えたことで、対中貿易赤字が拡大しており、スリランカにとっては、資金の流入や、インフラ建設以外に得られるメリットは限られている。一帯一路事業のほとんどを、地元の事業者ではなく中国系企業と労働者が行っているため、スリランカ人労働者のスキル向上をもたらすような、知識の移転もごくわずかだ。
一帯一路の下での取引において、今後はこうした要素も検討せねばならない。スリランカにとって、より包括的な利益を得られる、有利な形の協定を結べるよう交渉することが必要だ。
スリランカのような島国にとって、国内で中国が実施する事業が及ぼす環境への影響も大きな懸案事項となってきた。だが、中国自身が持続可能な開発を重視する方向にシフトしていることにより、その影響は是正され始めている。その証左に、中国が最近発表した「新時代における中国の国際発展協力」白書では、丸々1章分を割いて、国連の「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に貢献するための目標について述べている。
以前の開発事業は環境破壊につながることが多かったが、CICTやコロンボ港湾都市事業などの最近の事業は、「グリーン・シルクロード」の名の下、より厳格な環境基準を満たすよう調整されている。信頼に値する、高い水準の気候変動対策および環境ガイドラインを保証するため、スリランカはグリーン投資家からの追加の出資を求めるとともに、国内規制の強化を行わなければならない。
スリランカに求められる
「デュアルトラック」外交
いずれにせよ、スリランカや、特にインドをはじめとする戦略面での利害関係国にとっては、中国が債務軽減と引き換えに手に入れたインフラと一帯一路事業を軍事利用するかもしれないという不安が、国際的緊張と中国政府が貫く修正主義によって助長されている。
これらを念頭に、スリランカは2018年、海軍の南部司令部をゴールからハンバントタ港へ移転し、同港での海軍プレゼンスを強化した。とはいえ、安全保障面での懸念に適切に対処し、国内での一帯一路事業に対する世論の信頼を回復するためには、政策当局、学者やアナリストによる継続した監視が必要である。
スリランカ自身は、これまでのように外国からの借り入れに依存するのをやめ、貿易と投資に重点を置く必要がある。そのためには、大規模な軍を保有しない小国のスリランカは、より大きな自律性をポスト・パンデミックの世界で戦略的に追求すべきだ。
米中対立は過熱し、さらにスリランカにとって最大の貿易相手国、インドも中国との緊張を抱え、対立関係が続いている。そのような状況では、小さな島国のスリランカは、経済面よりも安全保障面での国益を守ることが必要不可欠になるだろう。
これは、確かな基盤を持ち、入念に練られた「デュアルトラック」外交、すなわち地政学的現状に即し、インド太平洋地域と中国の両方を大きく関与させる形をとることで、実現できる可能性がある。
つまり、ポスト・パンデミックに台頭する国際秩序において、スリランカの外交政策の指針は、日豪印が構築を目指す「サプライチェーン・レジリエンス・イニシアティブ」といった枠組みへの参加や、インドやモルディブとの海洋安全保障パートナーシップの構築、米国との政治関係の強化や、インド太平洋諸国との貿易関係の深化を重視したものでなくてはならない。中国の一帯一路との関わりが予定通り前進し続けるにしてもだ。
2013年、中国の習近平国家主席が突如打ち出した「一帯一路」構想。中国政府だけでなく、西側諸国までもがその言葉に“幻惑”された。それから7年。中国や沿線国は何を残し、何を得て、何を失ったのか。現地の専門家たちから見た「真実」。それを踏まえた日本の「針路」とは。
2022年5月10日 スリランカのラジャパクサ首相、危機
最大都市コロンボにある首相公邸付近ではデモ参加者の一部と与党支持者が衝突。辞任表明後も、デモ参加者の一部がラジャパクサ一族の保有する民家などに火を放った。
スリランカの政治を長年動かし、権力を握ってきたマヒンダ・ラジャパクサ首相が9日、辞任に追い込まれた。経済発展を優先する政策を推し進めてきたが、コロナ禍で経済危機が深刻化し、民心が離れた。生活苦に怒り、抗議デモを続ける人々は「ラジャパクサ一族を政界から追い出そう」と、大統領を務めるマヒンダ氏の弟の辞任も求めている。
マヒンダ氏は2022年5月9日、辞意を伝える書類を弟のゴタバヤ・ラジャパクサ大統領宛てに送付した。
スリランカが陥った危機、その発端と意味合いとは-QuickTake
Niki Koswanage
2022年5月10日 17:38 JST
南アジアの島国スリランカでは物価高騰や食料・燃料不足、長引く停電に対する抗議活動が相次いでおり、ゴタバヤ・ラジャパクサ大統領の政権維持が揺らいでいる。兄のマヒンダ・ラジャパクサ首相が2022年5月9日、辞任表明に追い込まれた一方、野党側は選挙の実施を要求している。
観光依存度の高い経済は既に新型コロナウイルス禍で大打撃を受けていたが、政治的混乱と散発的な暴力の影響も重なり、外貨不足への対応や経済運営に必要な追加資金確保の取り組みは混迷の度を深めている。
1.危機の発端は何か
ラジャパクサ大統領は2019年終盤にポピュリスト的な減税に踏み切った。コロナ感染症のパンデミック(世界的大流行)で、スリランカ経済が大打撃を受けるわずか数カ月前に税収が減少。多くが仕事を失う中で海外のスリランカ人労働者からの送金も細ることになった。野心的なインフラプロジェクトに充てる資金を中国から借り入れたことなどで対外債務は膨らみ、その対応に追われている。
スリランカはインドなど近隣諸国からクレジットラインを確保したが、燃料や主要な食品の輸入代金支払いを定期的にできなくなった。さらに、ラジャパクサ政権が昨年、化学肥料の使用禁止で有機農業にかじを切ったことで、農業従事者からの抗議を招き、極めて重要な茶葉やコメの収穫が減ったことも状況の悪化に拍車をかけた。
2.スリランカ経済に何が起きているのか
ロシアのウクライナ侵攻で原油など商品が世界的に値上がりしており、810億ドル(約10兆5500億円)規模のスリランカ経済は破綻に近い状態だ。経済成長率は鈍化し、インフレが高止まりしている。コロンボの消費者物価指数(CPI)は4月に前年同月比で30%近く上昇。3月は約19%上昇だった。
スリランカ当局は利上げや通貨の切り下げ、非必需品の輸入制限などに踏み切ったが、外貨準備はわずか20億ドル、今年迎える債務の支払いが70億ドルに上っており、スリランカ経済が健全性を取り戻すのは容易ではない。ラジャパクサ首相の辞任表明で緊急融資の確保に向けた国際通貨基金(IMF)との交渉を主導する政府も不在となった。
3.国民が抗議するのはなぜか
3年前の大統領選でゴタバヤ・ラジャパクサ氏を選んだスリランカ国民は、生活がますます厳しくなっていると感じている。スリランカ政府はエネルギーの輸入代金支払いに苦慮しており、家計と企業は3月以降、停電に悩まされている。給油所には長蛇の列ができているほか、食品があっても日常的な供給不足で値段が極めて高い。反ラジャパクサ陣営はこの数週間、大統領辞任を求めてコロンボで野営を続けている。
4.スリランカ政府の対応は
ラジャパクサ大統領は今月5月6日、ここ2カ月で2度目となる非常事態を宣言し、法律の一時停止や人々の拘束、財産の差し押さえなど幅広い権限を確保した。一部の抗議活動が暴徒化し、全土で外出禁止令が出されたほか、地元メディアによればコロンボでは軍が招集された。負傷者は数十人に上っている。20年の憲法改正で権限を拡大したラジャパクサ氏はこうした暴力を非難し、危機克服に向けて挙国一致内閣に加わるよう全ての政党に呼び掛けた。他方、野党指導者らは選挙の実施などを求めている。
5.スリランカを取り巻く環境とは
1948年に英国から独立して以降、スリランカは紛争と切り離せない歴史をたどってきた。多数派シンハラ人主導の政府と少数派で分離独立を目指す「タミル・イーラム解放のトラ(LTTE)」との内戦は数十年にわたり続き、死者は10万人に上った。この内戦は2009年に終わり、19年のイースターに200人余りが死亡した自爆テロ事件が起きるまで落ち着いた状況が継続していた。元軍人で、内戦の英雄と多くの有権者から評価されていたラジャパクサ氏が大統領に当選したのはテロ事件から数カ月後のことだった。
また、スリランカは中国とインドがそれぞれの影響力を争う場にもなっているが、ラジャパクサ一族は中国寄りにかじを切っている。
6.スリランカ経済の今後
利払いが迫るスリランカは支援を求めてインドに接触。2022年5月12日には債権者にデフォルト(債務不履行)の可能性を警告し、一部の対外債務の支払いを停止した。財務省は支援パッケージでIMFとの協議を進めると表明したが、アリ・サブリ財務相は今月上旬の議会で、危機から脱するのに2年を要する可能性があるとの見方を示した。ラジャパクサ政権は不人気な緊縮策が盛り込まれることを警戒してIMFへの支援要請に極めて消極的だった経緯もある。
原題:How Sri Lanka Landed in a Crisis and What It Means: QuickTake(抜粋)
スリランカでインフレを巡り数週間にわたって続く抗議デモが2022年5月9日夕に激化し、政府は公共物などを破壊する人々への銃撃を軍に命じた。軍報道官が電話で明らかにした。現地報道によると、デモ隊は与党議員の自宅を標的にしている。
同国では政権支持者とデモ隊が2022年5月9日に衝突。同日にマヒンダ・ラジャパクサ首相が辞任するなど事態が急速に動いている。政府は全土を対象に外出禁止令を発令した。
スリランカ首相が辞任、大統領の実兄-危機エスカレートの中 (1)
首相の実弟であるゴタバヤ・ラジャパクサ大統領は平和を呼び掛け、政治の安定を取り戻すべく政府が努力することをツイートした。
[FT]スリランカ首相「中国から数億ドルの融資提案」
FT
2022年5月30日 11:58
スリランカのウィクラマシンハ首相は、中国から同国に「数億ドル(数百億円)」の融資を提供するとの提案があったことを明らかにした。生活必需品が不足するスリランカの窮状を解消するためだ。
スリランカ政府は経済破綻を回避するために緊急支援を求め、国際通貨基金(IMF)との交渉を続けている。ウィクラマシンハ氏は5月、同国の首相に任命されたばかりだが、中国の提案について最終合意を目指していると語った。だが、...
スリランカ、ロシア産原油輸入へ 米報道
南西ア・オセアニア
2022年5月27日 21:50
米ブルームバーグ通信は2022年5月27日、スリランカがロシア産の原油を輸入すると報じた。ロシアからタンカーがスリランカに向け出航しており、2022年5月28日にも原油を受け入れる予定だという。ロシアはウクライナ侵攻で欧米が発動した経済制裁によって打撃を受けているが、インドなどはロシア産原油の輸入を増やしている。
スリランカは新型コロナウイルスの影響で主要産業である観光業が打撃を受け、深刻な経済危機に陥っている。外貨不足による急激な物価上昇で食料から石油まであらゆる物資が不足しており、市民による政権に対する抗議活動も続いている。
経済危機に直面するスリランカのゴタバヤ・ラジャパクサ大統領は2022年5月26日、「アジアの未来」に映像メッセージを寄せ、目先の生活必需品の供給や債務再編に向け「緊急のつなぎ融資が必要だ」と述べた。金額には言及しなかったが、日本との間で交渉が進んでいることも明らかにした。
スリランカの対外債務残高は2021年末時点で500億ドル(約6兆3000億円)を超える。22年中に70億ドル分の支払いが期限を迎えると報じ...
 |
| この2人に、日本は騙されてはいけない! |
債務の罠の帝国「中国」!!!!
海洋の一帯一路の要衝スリランカが!!
スリランカのウィクラマシンハ首相は2022年7月5日、同国の「破産」を宣言した。インドの南東に浮かぶ島国・スリランカは人口約2200万人。昨年10月には、イラン石油公社に代金を支払えず、特産品の紅茶でバーター取引を行った。
ハンバントタ港のリースのように、スリランカはしばしば中国による「債務の罠」が指摘されるが、これまでの報道によると、対外債務に占める中国の割合は1割程度で、日本と同程度という。政策運営の失敗を指摘する声もあり、破産に至るまでにはさまざまな要因があるようだ。
一国の破産に、日本でもネット上で驚きの声があがった。
中国から支援漬けにされて手のひら返されたら今度はロシアとか。一帯一路構想なんかに乗っかっちゃったから隣国の不興を買っちゃったりしたわけだけど、まずはインドや日本に声かけなよ。中国との港湾租借契約なんか破棄しなよ。
世界情勢はまた少しずつ変化していきそうである。
「2021年:オーストラリア編」
豪州、商業港の契約見直しで“中国排除” あわや機密情報ダダ漏れ…日本の地方も狙う中国のしたたかな浸透工作
2021年5月
オーストラリア連邦政府による「中国排除」の動きが活発化している。地方政府が中国企業と結んだ北部ダーウィンの商業港の賃借契約について、見直しの検討を始めたのだ。日本と米国、インドとの戦略的枠組み「QUAD(クアッド)」の一角であるスコット・モリソン首相率いるオーストラリアは、習近平国家主席の中国共産党政権による軍事的覇権拡大や、香港やウイグルでの人権弾圧を断じて看過しない姿勢を明確にしつつある。中国の浸透工作が指摘される日本は大丈夫なのか。産経新聞論説副委員長の佐々木類氏が迫った。
◇
「冷戦思考とイデオロギー上の偏見に基づき、両国の正常な交流や協力を妨害、破壊する一連の措置を打ち出した」
中国国家発展改革委員会は6日、オーストラリアとの戦略経済対話に基づく、すべての活動を無期限で停止すると発表し、こう反発した。具体的理由は明らかにしていないが、連邦政府がダーウィン港の賃借契約の見直しを検討していることへの報復措置とみられる。
ダーウィン港は、インド洋の一部ティモール海に面し、太平洋にも近い。第二次世界大戦前から海軍基地が置かれ、米海軍艦船が寄港したり、在沖縄米海兵隊がローテーションで駐留している。オーストラリアにとって国防上の重要拠点である。
同港をめぐっては、中国企業「嵐橋集団」が2015年、ダーウィンがある地方政府・北部準州と約5億豪ドル(約424億円)で99年間賃借する契約を結んだ。オーストラリア北部で唯一、大型艦が接岸できる軍民共用桟橋も賃借契約の対象だ
当時の嵐橋集団トップの葉成氏は、中国人民解放軍の出身で軍と密接な関係にあった。葉氏は、アンドリュー・ロッブ元貿易相を議員辞任後に年収88万豪ドル(約7460万円)で集団の顧問として迎え入れるなど、政界人脈を利用して同国への浸透工作を図っていた。その事実は、公共放送ABCなどの報道で知られている。
ティモール海を隔てた対岸には、中国の巨大経済圏構想「一帯一路」を支持する東ティモールが位置する。東ティモールでは、中国が経済支援をテコに存在感を強めており、ダーウィン港を出入りする米軍やオーストラリア軍艦船の監視を強めているのが実態だ。
これだけ重要な港が、中国企業の管理下にあるのだから、オーストラリア連邦政府が見直すのは当然だし、遅いくらいの対応だ。「自由で開かれたインド太平洋」構想の実現に向けたクアッドの一角がこの体たらくだったのだから、何とも心もとない。
3日付のオーストラリア紙「シドニー・モーニング・ヘラルド」によると、モリソン首相が議長を務める国家安全保障会議から契約の見直しについて、ピーター・ダットン国防相に助言を求めてきたという。連邦政府は国防省の判断を踏まえて、嵐橋集団にダーウィン港の管理権を強制的に売却させる見通しだ。
■“微笑み攻勢”釧路市に中国の魔の手
日本と違ってオーストラリアは連邦制をとる。地方政府の権限が強いとはいえ、ことは「国防上の問題」だ。地方自治体が金目当てに中国とやりたい放題でいいわけがない。
クアッドもそうだが、オーストラリアが、米国と英国、カナダ、ニュージーランドの英語圏4カ国とつくる機密情報共有の枠組み「ファイブアイズ」も、オーストラリアがこんな状態ではその名が泣こうというものだ。機密情報がダダ漏れになるところであった。
気を付けねばならないのは、日本も他人事ではないということだ。
したたかな中国共産党政権は、他国の地方から中央を包囲する「毛沢東戦略」を実践し、その毒牙は日本の地方にも向けられているからだ。
微笑みながら相手国の土地やインフラ施設の乗っ取りを狙う「チャーム・オフェンシブ(微笑み攻勢)」がそれだ。姉妹都市や文化交流を装った日本の地方自治体への働きかけは彼らの常套(じょうとう)手段であり、最も得意とする浸透工作でもある。
そのターゲットの一つが北海道釧路市だ。次回は釧路市に忍び寄る中国の魔の手について、報告する。
「豪首相は激怒」なぜ中国報道官は"陰惨なフェイク画像"で豪州を挑発したのか
中国外務省の趙立堅副報道局長(中国・北京=2020年4月8日)
アメリカで全頭引き上げ作戦…中国・習近平の超露骨な「嫌がらせパンダ外交」は日本にも波及する
2023年11月18日
 |
| Pandaには罪はない!習近平の「一帯一路外交」「微笑外交」「パンダ外交」に問題がある。もう、そろそろ、これらに騙されてはいけない。 |
アメリカで全頭引き上げ作戦…中国・習近平の超露骨な「嫌がらせパンダ外交」は日本にも波及する
© アサ芸プラス
アメリカ西海岸のサンフランシスコ近郊で、1年ぶりに行われた米中首脳会談。だが、史上最悪のレベルにまで冷え込んだ米中関係の雪解けは、全く見えてこない。
今年6月、アメリカのバイデン大統領は中国・習近平国家主席を「独裁者」と一刀両断。中国側は「挑発だ」「ばかげている」などと猛反発していた。今回の米中首脳会談の直後に行われた記者会見でも、バイデン大統領は次のように述べて、前言を撤回しなかった。
「我々とは全く異なる共産主義国家を統治している人物という意味で、習近平は『独裁者』だ」
当然ながら中国外務省の毛寧副報道局長は、
「完全に間違っており、断固として反対する」
と猛反発している。
そんな中、アメリカ国内では「来年には全米からパンダが1頭もいなくなる」との悲痛な声が、燎原の火のように広がり始めている。いったいどういうことなのか。
今年11月初頭、アメリカの首都ワシントンにあるスミソニアン国立動物園のパンダ舎の前には、多くの来園者の姿があった。次から次へと来園者がパンダ舎に詰めかけたのは、11月8日に中国に返還されることが決まっていた3頭のパンダ、すなわちメイシャン(美香=メス25歳)とティエンティエン(添添=オス26歳)、そして2頭の子供にあたるシャオチージー(小奇跡=オス3歳)との別れを惜しむためだった。
複数の米メディアによれば、スミソニアン動物園側は前例に倣ってパンダの貸与延長を申し入れたが、中国側は断固としてこれを受け入れなかったという。
アメリカ国内では、2019年に西部サンディエゴの動物園からパンダが返還されたのに続き、今年4月には南部メンフィスの動物園でもパンダの返還を余儀なくされている。しかも来年には南部アトランタの動物園からの返還も予定されており、これが断行されれば、全米からパンダが1頭もいなくなる事態に立ち至るのだ。
中国の「パンダ外交」の過去と現在に詳しい国際政治学者が指摘する。
「パンダ外交の歴史は古いが、習近平は今、『新パンダ外交』を掲げて戦略を先鋭化させている。具体的には、ロシアなどの友好国にはパンダを積極的に貸与する一方、アメリカなどの敵対国にはパンダの返還を迫るという、露骨な両面戦術です。今回の全米からの全頭引き上げ作戦も、習近平がバイデンから『独裁者』と名指しされたことへの意趣返しとみて間違いない。要するに、パンダを利用した『嫌がらせ外交』です」
今後、日本も含めた西側諸国でパンダが見られなくなるのも、時間の問題かもしれない。
(石森巌)
結論:
職場の労働環境について話をするならば、ホンダのように、EVに完全シフトして、社員が1つのことを目指したようには、トヨタはいかなかったんだな?ホンダの中心であるホンダ技術研究所は決して中国共産党国営企業とは組まずに、日本国内でEV電池もモーターも生産も工場も国内で開発しようとしている点が、トヨタとは全く違うな。ホンダのように生き生きとした社員が、生き生きとした自動車を作ることができるし、あと10年でEV車に完全変化する。2030年あたりのトヨタとトヨタに部品供給する日本電装(技術研究所は中国に移転してしまった)は、本当に大丈夫な会社なのか?疑問だ。2030年あたりには、ガソリン車は走ってはいるけど、ガソリン車の新車は生産しないので、そのための部品もだんだん縮小して、世界中のどの部品企業も倒産しているだろう。
フランス、ルノーのCEOが言っていたように、大学の研究者、民間企業、国家政府の首長の3者が一体となって初めて電気自動車を次世代カーにできる、と言ってましたね!しかも時間がないとも。
アメリカのバイデン大統領は2021年に就任してすぐに、200兆円の予算でアメリカ中に、EV用電気ステーションを何十万基も作るそうです。2022年内にはできるでしょう。それに比べて日本はEVに関しては何もしていないに等しい。日本の自動車産業は今後はすべて海外工場で研究もして、部品も海外で取り寄せて、海外の工場で生産ラインを立ち上げていくつもりです。しかしながら中国だけは節操のない、約束の概念がおかしな国であることを忘れず、恐れず、今や中国は「世界の工場」となってしまったのだから、ここで生産販売拠点を持つしかない。しかし、いつ、つぶされてもよい覚悟で、びくびくしながら、首をたれながら、最後は中国に骨をうずめる覚悟で起業家さんも、世界から移住した研究者さんも、そこで頑張るしかない。
習近平はアメリカに対して必ず強気に出始める。そのとき試されるのは日本の姿勢だ。習近平国賓招聘をまだ「中止する」と言えない日本。中止する必要はないと言い張る自民党の二階幹事長が絶対的力を持っている日本の政権与党。このようなパワーバランスが転換しようとしている時でもなお中国の顔色を窺うのだろうか。
かつて、第2次世界大戦のときナチスの幹部が「国家の最大の問題は、人口問題だ!」としみじみとつぶやいたけど、その言葉が、習近平の「世界を支配できる国は、最も人口が多くて、その1人1人統制できることが、国家の最大問題だ!」と、このように聴こえてくるようだ。
 |
日本中国友好協会(左はソフトな独裁者、 右はハードな独裁者) |
 |
| 韓国とプーチンと習近平の3人が軍事パレードに参加 |
日中韓3か国地方政府交流会議
【日中韓3か国友好同盟】
81年前の日●●軍事同盟ではありません。81年前の黒田氏の言葉「一番強い国(当時はドイツだった)に追従することにした」。
嘘の帝国「ロシア」!!!!!
ロシアのプーチンが、2022年2月24日ウクライナ戦争を起こす!
ウクライナ侵攻 背後の情報戦 アメリカが見せたインテリジェンスの威力
3/5(土) 20:22配信1209
「まさか!」、「ありえない!」。
世界の虚を衝いたロシアによるウクライナ侵攻。
世界中が見ている中でいともあっさりと一つの主権国家が蹂躙されていく惨劇を見ながら、得体の知れない胸騒ぎと焦燥感のようなものを感じるのは戦いの壮絶さからだけではない。
明日は我が身だからだ。
ウクライナ侵攻の裏側で繰り広げられていた情報戦についてシリーズでお伝えする。
第1回は、侵攻前夜の動きについて詳報する。
◆「“帝王 プーチン”を知らしめる」会議 ―歴史的暴挙への連帯責任
”NOと言えない” ロシア国家安全保障会議(2022年2月21日)
「絶対にNOとは言えない会議」、とでも言えばいいのだろうか。
2月21日のロシア国家安全保障会議の議題は、ウクライナ東部にあるロシア系武装組織が支配する地域「ドネツク人民共和国」と「ルガンスク人民共和国」の独立を承認するかどうか。
世界に向けて配信された会議にはなんとも不気味で異様な空気が漂っていた。
一人、ポツンとテーブルに座るプーチン大統領。
そのほかの出席者たちはというと、20mは離れたところに並べられた椅子に神妙な表情で座ってプーチン氏の独白のような進行を見守っている。
「わざと側近たちを離れた場所に座らせて自分が王だということを国民に知らしめる設定」(米情報機関幹部)とも、新型コロナを警戒しての設定ともいわれる謎の配置だとも?訳が分からない配置だ。
プーチン大統領はスピーチが終わると、次々と出席した幹部を指名して、ドネツクとルガンスクの独立を承認すべきかどうか、意見を言わせていく。
答えは承認しかない。忖度するまでもない。常に「死」と隣り合わせているからだ。ウクライナ侵攻を正当化するために、“独立国となった”ドネツクとルガンスクからの依頼を受けて、ロシア軍は同地域の平和維持に駆けつけて併合する、という見え見えのシナリオが用意されている。独立の承認はそのシナリオの実現に向けて不可欠なセレモニーだ。
この会議、映像からは出席者たちが極度の緊張感に包まれていることがわかる。それもそのはず、この21世紀の世界においてこれまでに積み上げてきた秩序と規範、ルールを踏みにじるウクライナに対する一方的な侵攻という歴史的暴挙の連帯責任を問うものだからだ。
世界が見ている前で一人一人に独立承認への賛意を宣言させることで、後から「実は私は侵攻に反対だった」などと言わせないことがこのセレモニーの目的だ。
「絶対にNOとは言えない」空気の中でハプニングを起こしたのは、スパイ機関、SVRのトップだった。
◆スパイを失っていたCIA
その一方でアメリカ政府は11月から、侵攻の4日前の2022年2月20日までは「軍事侵攻の準備は進んでいるが、プーチン大統領はまだ最終決断していないとみられる」という立場で一貫してきた。
これだけの情報が揃っているのになぜか。それはいくら高度なインテリジェンス能力を誇るアメリカの情報機関でも、さすがにプーチン氏の心の中をリアルタイムでうかがい知ることはできないからだ。
2022年2月15日付のニューヨークタイムズがその背景を説明している。
アメリカ情報機関に強固な取材源を持つことで知られるデビット・サンガー記者らの記事だ。それによるとCIAはプーチン氏の側近の一人を情報源として獲得することに成功し、正確にプーチン氏の政策決定を把握してきたという。しかし、身の危険を感じた、その人物を2017年にロシアから脱出させてからはプーチン氏の日々の動きを正確に知ることはできなくなった。
ウクライナ侵攻に向けて軍事的準備が進んでいることに危機感をおぼえたアメリカ政府は、11月上旬までにこのインテリジェンスをヨーロッパの主要国とも共有して包囲網を築いたほか、バーンズCIA長官をモスクワに派遣し、アメリカ側の重大な懸念を伝えている。
アメリカはその高度なインテリジェンス能力による成果を最大限に活用、公開しながら、なんとか迫りくるロシアによる侵攻を抑止しようとしたのであった。
◆“ロシア軍一部撤退” 虚偽情報へのカウンター
インテリジェンスを通じて何が起きているのか、相手が何を仕掛けようとしているのか、正確な情報をつかめなければ、外交も交渉も軍事攻撃もできない。偽情報でこちらの行動を操ろうとする悪意ある相手に惑わされるだけである。
その典型的ケースが2022年2月15日の「ベラルーシでの演習終了を受けてロシア軍一部撤退か」騒動だ。
ロシア政府報道官はベラルーシでの演習終了を受けてロシア軍の一部が撤退を開始したと発表した。同時にロシア国防省は「クリミアから引き揚げている」とする戦車の映像を公開した。
緊張がずっと張り詰めた状況が続くと人間は本能的に「そうであって欲しい」という情報を信じたくなるものだ。日本でも「もしや緊張緩和か」と期待感が高まったが、アメリカ政府は即座にロシアの動きは虚偽であり、むしろ数日の間で最大7千人の増派をロシア軍はしていると反論した。
その後の実際の侵攻をみればロシア軍の発表は明らかな偽情報であり、攻撃に向けて最終準備を悟られないようにするフェイントだ。何も情報がなければ、悪意ある国の情報戦に翻弄され、判断を迷わされることになるといういい例だといえよう。ましてや、インテリジェンスもなく国家として「のるか反るか」の重大決断をするとなれば、ただのギャンブルとしかいいようがない。アメリカは正確にロシア軍の動きを把握できていたからこそ、ロシアによる情報戦にカウンターを打つことができたのだ。
◆覆ったバイデンの融和路線
他方でインテリジェンスが戦争の到来を告げていたとしても、政治指導者はその表現にあえて「のりしろ」をつけるという政治判断もあり得る。知っていることをそのまま言わず、交渉の余地を残すというやり方だ。
2022年2月20日、プーチン大統領がウクライナ東部のロシア人支配地域の独立を承認しようとする動きを見せていたが、バイデン政権は批判をヒートアップさせることはなかった。前述の通りバイデン大統領は20日の演説で「大規模攻撃に出ると信じるに足るものを持っている」とまで踏み込んだものの、「侵攻が始まろうとしている」と断定しようとはしなかった。逆に侵攻がなければプーチン大統領と首脳会談をおこなう用意があると明らかにする柔軟姿勢をみせていた。
翌2月21日、ロシアが独立を承認したドネツクとルガンスクに対する制裁が発表されたが、かねてよりいわれていた「強力な制裁」ではなく、ドネツク地域だけに限られた制裁であった。ロシア全体に影響が出るような制裁を明らかに避けた、小出し戦術であった。
その日の夕方におこなわれた記者ブリーフィング。その場でNSC(国家安全保障会議)高官も「同地域には2014年からロシア軍が駐留しており、今回、追加派遣があったとしても侵略とは断定しがたい」と、ドネツク進駐は侵攻だとみなさないことを示唆するかのような柔軟発言をし、「融和モード」をさらに演出した。
20日から21日までは明らかにバイデン政権なりのギリギリいっぱいの「融和のバーゲンセール」の期間だといえた。ロシア軍の戦争準備が着々と進み、アメリカ政府もその動きを正確に把握しながらも、バイデン政権は「戦車がその姿を現す最後の瞬間まで外交努力を続ける」(ブリンケン国務長官)と決め、最後の瞬間にプーチン大統領が心変わりして緊張緩和への向かうことに一縷の望みをかけたのであった。緊張緩和のわずかな可能性に賭けて、あえて事態の切迫を伝えるインテリジェンスとはそぐわない融和的な政治ポジションをとったのである
だが、それは翌2月22日の朝に一変した。CNNでの生出演で国家安全保障担当次席補佐官が「侵攻がおこなわれつつある」と、対決モードに舵を切ったのであった。2月22日の午後にはバイデン大統領自身が演説をおこない、「侵攻の始まり」だと一気にトーンを上げた。この時点で2022年2月24日に予定されていたロシアとの外相会談もキャンセルとなり、ワシントンの空気は一気に開戦モードになっていった。この180°転換ともいえる動きの背景に一体何があったのか。
【モスクワ時事】ロシアのプーチン大統領は2022年2月24日、ウクライナでのロシア軍の軍事作戦に関し、ウクライナ領の占領は「計画にない」と主張した。だが、これまで侵攻の意図を繰り返し否定してきたロシアの言い分を信じるのは難しい。
「必要に迫られた」と正当化 ウクライナ侵攻でロシア大統領
ロシアは2008年、旧ソ連構成国ジョージア(グルジア)と武力衝突。その結果、親ロ派地域の南オセチアやアブハジア自治共和国のジョージアからの独立を承認した。一方で、ジョージアの状況はそれ以降こう着して大きな衝突は起きておらず、プーチン氏が今回、ウクライナ東部の親ロ派の独立を承認し、平和維持部隊の派遣を決めたことはウクライナ政府に停戦への圧力をかけるための戦略という楽観的見方もあった。
しかし、ロシア軍はウクライナ侵攻を開始した。プーチン氏は2022年2月24日の演説で「14年にウクライナでクーデターを起こし権力を奪った勢力が、紛争の平和的解決を拒否している」とウクライナのゼレンスキー政権を強く非難。同政権を「ネオナチ」と決め付け、ウクライナ国民に向けて「あなた方の父や祖父らがナチス・ドイツと戦ったのは、今日ネオナチが権力を握るためではない」とまくし立てた。
14年の政変でウクライナが親欧米に転じたことへの根深い恨みとウクライナへの異様な執着を感じさせ、最終的な目標がゼレンスキー政権の排除とウクライナ解体にあることをうかがわせた。
ロシア軍の支援を受けるウクライナの親ロ派は2022年2月24日、これまで一部しか支配していなかった東部のドネツク、ルガンスク両州の全域の掌握を目指す考えを表明した。
 |
嘘の天才プーチン露大統領(元KGB、
反体制派を弾圧してきた人)メディアなど言論統制
した人。独裁者、核戦争もい問わない殺し屋 |
 |
| アドルフ・ヒトラー(大量人権侵害の開祖) |
専制主義者、独裁者 ヒトラー
2022年3月4日 15:00ロシア軍が原発に迫る
エネルゴダール市のオルロフ市長は3日、同市近郊で激しい戦闘が起きているとしていた。ロシア軍が戦車で同市内に入って原発を掌握しようとしたが、住民や作業員らが原発周辺と周囲の道路に集まったと述べていた。
ウクライナにはザポリッジャ原発を含め、稼働中の原発が4基ある。チョルノービリ原発の跡地には放射性廃棄物があるが、現在はロシアが同地を占拠している。
ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は、ザポリッジャ原発が攻撃されたことを受け、国際社会に「即時の行動」を強く求めた。
ゼレンスキー氏はツイッターに投稿した動画で、「欧州最大の原発がいま燃えている」と訴えた。
また、ロシア軍について、赤外線カメラを装着した戦車から、ザポリッジャ原発の原子炉6基を意図的に狙って砲撃したと非難した。
またプーチンは核兵器も使えるなら使いたいと言った。ロシア無き世界は彼にとっては必要ないとも言っている。しかも今現在、ロシア国民の70%はプーチンのこの考えを支持している。しかし残りのロシア人は反対したため、プーチンにつかまって刑務所に送り込まれようとしている。
SVRとは泣く子も黙るロシアを代表する対外情報機関で、アメリカや日本を含む世界各国にスパイを送り込んで諜報活動をおこなっている。かつてのKGBの流れを汲む後継組織でもある。そのトップがなんと「独立を支持する」と言うべきところを「併合することを支持する」と口走ってしまったのだ。
よほど緊張していたのであろう、思わず裏で検討している本当のシナリオをカメラの前で口にしてしまったかのような発言に、プーチン氏はいら立ちと侮蔑の表情で「今はそんなことを議論していない」と一喝した。このSVRトップの今後の無事を祈りたくなる会議はウクライナ侵攻の号砲となった。
◆アメリカのインテリジェンスの威力
侵攻開始に向けて着々と、ある意味、見え見えとも言える環境整備をロシアが進める一方で
侵攻を受ける側の当のウクライナには最後まで「まさか、そんなこと」という空気が残っていた。ロシア軍17万人が目の前の国境沿いに集結しているにもかかわらず、ウクライナは「パニックを起こす情報は我々の助けにならない」(2022年2月12日ゼレンスキー大統領)、「侵攻が迫っている兆候はない」(2022年2月20日レズニコフ国防相)という姿勢を崩していなかった。
そうした中、ある国だけはロシアの大規模侵攻を正確に、しかも前の年の11月から訴えていた。アメリカだ。
ワシントンポストが掲載した米情報機関作成とされる文書
ここに1枚の図がある。
去年12月3日付のワシントン・ポストが報じたアメリカの情報機関作成の文書とされるものだ。ウクライナ国境沿いにロシア軍17万5千人が集結していることを伝えている。
この文書の分析が秀逸なのはロシア軍部隊の規模がほぼ実際の侵攻時の規模と一致しているのみならず、東部ドネツクだけでなく、首都キエフ方面を含むウクライナ北東および南部からの侵攻ルートも正確に指摘していることだ。当時は多くのひとが軍事侵攻を疑っていたし、軍事侵攻の可能性があると言う人も東部ドネツク地方に限定されるとの見方が主流だった。
衛星画像の画質を落とす「サニタイズ」された公開用の文書になっているものの、2022年早々に軍事侵攻が迫っていることを正確に警告している。軍事侵攻のタイミングについては衛星画像で見える軍の準備状況から逆算したのであろう。当時の大方の予測と真っ向から反しながら、複数の方面からの攻撃を正確に予測できているのは、衛星画像で見える準備状況の分析に加えてロシア軍内の通信を傍受しているからだろう。
恐るべきはアメリカのインテリジェンスだ。その高い能力を「情報のための情報」に留めず(情報を内部で抱えず)、世論とロシアに対して訴えることで侵攻を抑止することに活用していることは特筆すべきだ。
◆インテリジェンスというパワー 流出したロシア軍の文書
もう一ついい例がある。ロシアとウクライナによる停戦交渉が開始された時も日本の一部では期待感が高まったが、ワシントンでは誰も停戦交渉が成立するとは思っておらず筆者は日本との大きな温度差を感じた。その理由はロシア軍の現地での動きを見ていれば、当面ロシアが停戦を考えていないことは明らかであり、インテリジェンスを通じてそれを認識しているアメリカ政府からも停戦に関する期待感が伝わってくることもなく、アメリカメディアも専門家も停戦交渉には冷淡であったからだ。
インテリジェンスとはパワーだ。それがあれば有利に事を進められ、それがなければ、とんでもない悲劇に自らを突入させることになりかねない。
“侵攻作戦計画書”には2月18日の印が…
アメリカのインテリジェンス能力の威力をうかがわせる動きはほかにもある。
3月2日にSNS上に出回ったロシア軍の作戦計画書の一部とみられる文書。ウクライナ軍が入手したとされる文書でウクライナ国防省も公式フェイスブックでアップしている。
そこにはウクライナ侵攻作戦がロシア軍部によって2月18日に承認されたと考えられる押印がある。
侵攻作戦は2月20日から3月6日と想定されていた?オリンピックの関係上習近平も知っていた。
また、部隊が使う暗号表とされる文書は、ウクライナ侵攻作戦の期間が2月20日から3月6日と想定されていたことを示すものとなっている。この文書が真正であればロシア軍は2月18日時点で20日から侵攻を開始し、15日間でウクライナ侵攻を完了させる計画だったことになる(真贋の検証は難しいが、ここではこの文書が真正であるという前提で話を進める)。
何らかの事情で遅れたのか、結果として侵攻のXデーは20日ではなく24日となった。
ここで注目したいのはロシア軍部が侵攻を承認したとされるのが2月18日という点だ。ワシントン時間2月18日の午後5時にバイデン大統領は会見をホワイトハウスで開いている。そこで突然、「我々にはロシアが首都キエフを含む全土に対して攻撃を開始すると信じるに足るものを持っている」と警告した。
「軍事態勢としてはいつでも侵攻があってもおかしくない状況だが、プーチン大統領はまだ最終決断していない」というのが、それまでのアメリカ政府の公式見解だったが、そこから明らかに踏み込んだ表現だったので筆者も驚いたのをおぼえている。
これは何らかの方法でロシア政権内の意思決定をリアルタイムに近い形で把握していることを伺わせる発言だといえる。2月20日付のニューヨークタイムズ電子版は「バイデン大統領の踏み込んだ警告の背景にはインテリジェンス」と報じ、ロシア軍の動きに関するインテリジェンスに基づくもので「高い確信」を持っている、とする米政府高官の言葉を伝えている。
正確なインテリジェンスがあれば、最も適切なタイミングで的確なメッセージを打ち出せる、というインテリジェンスの効用を示している。逆に何も情報がなければ、ロシア側の偽情報やフェイントに惑わされながら、ひたすら平和を祈るだけだったかもしれない。
 |
| モスクワでの反戦デモと、それを取り締まるプーチンの私設警察官たちは、夜のオオカミ、と恐れられている。©Getty Images |
2022年の平昌五輪女子フィギュアスケートの銀メダリスト、エフゲニア・メドベージェワや歌手のヴァレリー・メラジェらもSNSで抗議の意を発表するなど、反戦を表明するロシアの著名人も徐々に増えてきました。
しかし、これらを見て「ロシアの一般市民の多くは今回のウクライナ戦争に反対している」と考えるのは早計です。今でもロシア人の大部分の七割はプーチン大統領を支持していて、ウクライナへの侵攻にハッキリ反対している人は、選挙分析や人口動態から見て人口の10%程度はいるのではないか、という目算です。プーチンに対して懐疑的な人はさらに多いはずです。
それでも2022年2月初めに非政府系の組織が発表した調査では、プーチン大統領の支持率は70%に迫っていました。刻一刻と状況が変化しているとはいえ、現在もそれが大きく低下しているとは考えられません。
では誰がプーチンを支持し、誰が反対デモを起こしているのでしょう。それを理解するためには、ロシアに存在する3つの大きな「分断」が重要になります。
1つめの分断は「ソ連時代を体験したかどうか」です。現在30代後半以上のロシア人は、ソ連が崩壊した1991年以前の記憶を持っています。そしてソ連末期や1990年代のエリツィン大統領時代は、多くの人にとって“苦しかった原風景”になっています。
失業率がすさまじく高く、自殺者も多くいました。一家離散など悲惨な事態がロシア中で繰り広げられていた時代を知る世代にとって、プーチンは「国を立て直した救世主」。ロシアが豊かになったのはプーチンのおかげ、プーチンこそが超大国だったロシアを復活させてくれる指導者なのだと考えています。
しかし30歳以下の若い人たちはそもそも超大国だったソ連という時代を知らないため、プーチンに対する熱狂的な支持者は「ソ連人」に比べて少ないのです。
都市部以外では国営のテレビや新聞や2022北京パラリンピック競技だけを見て暮らしている人が大多数
2つ目の分断は、「国営のメディア以外から情報を得ているか」です。ロシアはメディアへの締付けが厳しく、国営放送のテレビ・ラジオや国営新聞で発信されている情報にはかなり規制が入っています。
モスクワやサンクトペテルブルクのような大都市部には英語などを使える人も多く、インターネットやSNSを通じて世界のメディアや情報に接しています。しかし少し田舎の方へ行くとIT化はまだ進んでおらず、国営のテレビや新聞だけを見て暮らしている高齢者がまだ多くいます。
つまり、自由な言論に触れている人々と、政権のコントロール下にあるメディアの情報だけを見聞きしている人々で世界の見方が全く違うのです。その境目は、インターネットやスマホを自由に扱えるかどうかにかかっていると言っても過言ではありません。
プーチンに盾突くのは大げさではなく「死」を意味する
3つめの分断は「ウクライナの今を理解しているかどうか」です。ウクライナは1991年の独立以降、民主主義体制を確立して表現の自由を謳歌してきました。ウクライナの親露派と反露派の国会議員どうしが殴り合いの喧嘩をする場面を見た人もいると思いますが、あれはまさに自由があるからこそできることでしょう。
一方のロシアでは、プーチンの支配が完成しているので、対立すら起きません。クレムリンの主に盾突くことは、大げさではなく「死」を意味します。ドーピングの闇の真実を訴えた医師でさえ「裏切者」呼ばわりされ、今は亡命先のアメリカで暗殺者の襲来に怯えているような状態です。
ソ連が1991年に崩壊した後、ロシアとウクライナはまったく異なる道を生きてきました。しかしロシアの一部の人たちは、ウクライナが今も昔のままだと錯覚しています。30年間会っていない昔の彼氏・彼女に、過去のイメージをそのまま抱き続けているような状態なのです。
以上が「3つの分断」です。これはつまり「プーチンがロシアをソ連時代のように再び大国にしてくれると信じ、国営メディアを見て生活し、ウクライナの変化に気づいていない人」がプーチンの固い支持基盤だということを示しています。プーチンはこの層を今回のウクライナ侵攻を支持する層だと認識しており、演説でウクライナ政府をナチスに喩えたのも、その証拠の1つです。
ロシアでは第2次世界大戦のことを「大祖国戦争」といいます。毎年5月9日には大祖国戦争戦勝を祝う式典が開かれ、パルチザンとしてナチスドイツから祖国を守った老兵士たちが赤の広場に招待され英雄として称えられます。
第2次世界大戦当時、ウクライナでは民族主義が沸き起こり、ステパン・バンデラという人がウクライナ東部を拠点にソ連にレジスタンス戦を仕掛けました。「敵の敵は味方」という論理からナチスとも協力し、ソ連軍と戦ったのです。
このバンデラという人物は、ソ連の歴史教育では「ナチスの協力者」「テロリスト」として扱われてきました。しかし近年のウクライナでは、独立のためにソ連と戦ったバンデラの名誉回復がなされ、両国の間で評価が正反対になっています。
プーチンが2月24日のテレビ演説でゼレンスキー政権をナチスになぞらえたのはこの流れを意識しているためで、ナチスに勝利したことを誇りに思うロシアの保守派たちには“刺さる”表現なのです
「すべてが崖から落ちてしまった」
それでも今回のウクライナ侵攻で、ロシア国内でのプーチンに対する信頼感が揺れているのも事実です。ロシアでは許可なく大規模集会を開いたりデモを行うこと自体が禁止されていて、反体制指導者のアレクセイ・ナワリヌイ氏などは神経剤での襲撃を受けたり逮捕されたりしています。若者はもともと政治への関心が薄いうえに、デモに参加することは就職など将来に直結します。その恐怖があるにもかかわらず1000人規模のデモが頻発していること自体がすでに異常事態なのです。
反プーチン派の動きは他にもあります。昨年ノーベル平和賞を受賞したドミトリー・ムラトフ氏(59)が編集長を務めるロシアの非国営新聞「ノーバヤ・ガゼータ」は、ウクライナへの連帯とプーチン政権への批判的な態度を強め、紙面でも「(ウクライナへの侵攻は)ウクライナの損失よりもロシアの損失のほうがはるかに大きい。ルーブルも未来も、すべてが崖から落ちてしまった」と強い口調で主張しています。
メディアを管理する官庁がロシアの公式発表以外の報道を禁止する通達を出しているのですが、「ノーバヤ・ガゼータ」はそれに堂々と反旗を翻したのです。
ロシア国内でプーチンへの支持が揺れている最大の理由は、侵攻先がほかでもないウクライナであったことでしょう。
ロシアが2014年にクリミアを併合した時は、ほとんどのロシア人は“奪還”に喝采を送りました。それは、かつてロシアの一部だったクリミアの同胞がウクライナ独立後の失政によって苦しんでいて、その人々をプーチンが救出したという意識があったためです。おそらく今でも、クリミア併合については「ロシアに帰ってこられてよかったね」という意識はあまり変わっていないと思います。
しかし、今回のウクライナへの侵攻は状況があまりにも違います。ロシアとウクライナは同族意識も強く、お互いに血縁者も多くいます。
乱暴な言い方をすれば、モスクワにとってのキエフは、東京から見た京都のような位置づけです。その場所を爆撃したり民間人が巻き添えになることに対して、プーチン支持者の中からも「なんでこんなことをするんだ」という嘆きと悲しみの反応が出てきているのです。
現時点で、ロシア国内でプーチンに対するハッキリとした「ニェット」(NO)を掲げる反対派はまだ少数です。「プーチンはウクライナのファシストからロシアを守っている」と軍派遣に賛成する人もまだまだ多くいます。しかしプーチンに対する批判のマグマは溜まりつつあり、目に見えない地殻変動が起きていると私は感じます。
一般のロシア人に話を聞いても「プーチンは誇大妄想に取りつかれている」「大統領でいること自体が恥ずかしい」「身震いするような恐れを感じる」「殺戮者だ」のような強い言葉でプーチンを批判する人が出はじめています。
BBCのロシア版サイトには、たった1人で「戦争反対」と書いたボードやウクライナの国旗を掲げて、武装したロシアの特殊部隊「アモン」に拘束されている高齢女性の写真が掲載されていました。それを見て私は胸が苦しくなりましたが、多くのロシア人にとっても目を背けたい光景のはずです。しかもロシア国内では物価が上がっており、今後の生活についても不安がよぎっていることでしょう。
プーチンの計算違いは、このロシア国民の悲しみと怒りと不安のマグマです。政権は必死に抑え込みにかかるでしょうが、反プーチンの感情を持つロシア人がこれほど現れることは想像できていなかったのではないでしょうか。
親プーチンと見られていたカザフスタンがウクライナへの軍派遣を断っていたことがわかったり、アメリカや西欧諸国が制裁を強めるなど包囲網を強化していますが、ロシアは国際社会から非難されることに“慣れて”おり、こうした圧力がプーチンに軌道修正を強いる決定打になるかどうかは不透明です。
むしろロシア国内でたまる反プーチンという感情のマグマこそが、このウクライナ戦争の行方を左右する大きなポイントだと思います。
ロシア軍は、赤外線カメラを装着した戦車から、ザポリッジャ原発の原子炉6基を意図的に狙って砲撃した。ウクライナ原発火災は砲撃が原因か、鎮火後にロシアが制圧 死傷者数人
2022年3月4日 15:03
2022年3月4日に、プーチンはウクライナにある、ヨーロッパ最大の原子力発電所に攻撃を加えた。ウクライナの大統領をヒトラーに例えて、ロシアの平和維持軍で攻撃したのだ、とプーチンは言っている。しかし、どう考えても、どう見ても、プーチン自身がヒトラーを尊敬しているように見える。
「プーチンは現実から切り離された自分の世界に生きている」 恫喝に動じない唯一のリーダー“メルケル”が見た独裁者のウソ
ロシアによるウクライナ軍事侵攻が続き、各地で激しい戦闘が起こっている。「ほかに選択肢はなかった」と侵攻について正当化したプーチン大統領の“宿敵”だったのが、ドイツのアンゲラ・メルケル元首相だ。2021年12月の引退まで、4期16年にわたりドイツを率いてきたメルケル氏の素顔に迫った決定的評伝『メルケル 世界一の宰相』から、プーチン大統領とのエピソードを再構成して紹介する。
◆◆◆
プーチンが手本にしているのは、独裁者スターリンである――各国首脳のなかで誰よりもプーチンを知るメルケルは、早くからその正体を見抜き警戒していた。プーチンは一体どのような価値観を持ち、いかなる行動原理で動いているのか。ひとつの手がかりとなる、若き日の彼のエピソードを紹介しよう。
ドレスデンでのKGB活動について「第一の敵はNATOだった」と発言していたプーチン大統領 ©️JMPA
ドレスデンでのKGB活動
KGB(ソ連の秘密警察)のスパイとして、37歳までの4年間を東ドイツ(当時)のドレスデンで過ごしたプーチン。本人いわく「我々に課せられた主要な任務は、市民の情報を集めることだった」。プーチンは、妻と娘ふたりとともに、ドイツ語を素早く習得した。芸術と音楽の都だったドレスデンの中心地にある薄暗いバーで、プーチンは内通者候補と面会を行なった。
一方、シュタージ(東ドイツの秘密警察)が所有する川沿いのホテルの優雅なレストランや客室には、スパイ活動のための隠しカメラが仕込まれていた。KGBとシュタージは協力関係にあり、彼らの諜報活動には脅迫が用いられた。とはいえ首都ベルリンとは違い、そこまでドラマチックな展開があるわけでもなかった。プーチンはむしろ、ドレスデンでの生活を楽しんでいた。それゆえ不覚にも10キロ以上太ってしまった。腹まわりに贅肉がついたのは、美味しい地ビールをつい飲みすぎたせいだ。
しかし1989年、ベルリンの壁崩壊によって、事態は一変する。1カ月後には、KGBドレスデン支部の鉄フェンスの向こうに、敵意に燃える東ドイツのデモ隊が結集した。プーチンは彼らにこう言い放った。
「下がれ! ここはソ連の領土だ。ここには武装した兵士がいて、発砲する権限がある」
実際には、武装した兵士はいなかったが、ハッタリをかまして時間稼ぎをしたのだ。「お前は誰だ」とデモ隊に詰め寄られて、「通訳だ」と嘘をついて切り抜けたりもした。苦境に立たされるプーチン。だが、ソ連軍の司令部に電話をかけても、「モスクワから指令があるまで何もできない」と言われるばかり。
取り残され絶望的な気分となったプーチンは、山ほどあるKGBの書類やファイルをかき集めて、小さな薪ストーブに放り込んだ。昼も夜も燃やし続けたため薪ストーブは壊れ、真っ黒焦げの鉄の塊と化した。数カ月後、プーチンはふたりの幼い娘を連れて、中古の大衆車のハンドルを握り、ドレスデンから逃げ出した。
この屈辱的な出来事と、その後のソ連の崩壊から、プーチンは決して忘れられない教訓を得た。当局の監視下にないデモや自由をいきなり認めてしまっては、絶大な軍事力を持つ帝国すら崩壊するのだ、と。ドレスデンでのKGB活動について「第一の敵はNATOだった」と発言したことがあるプーチン。そして、その考えは、現在に至るまで変わっていないのだ。
ヒトラー、スターリン、そしてプーチン。ウクライナへの野望
現代の独裁者ともいうべきプーチンが抱く、ウクライナ征服への野望。その根本の動機には、ロシアを世界の大国にしたい、昔のような帝国として復活させたい、との思いがある。現代の皇帝(ツァーリ)を目指すプーチンらしい発想だ。そのためには、隣国ウクライナを、EUやアメリカではなく、ロシアの勢力圏にとどめる必要がある。
ヨーロッパで2番目に広いウクライナには、肥沃な農地が広がり、鉄鉱石・天然ガス・石油などゆたかな天然資源が埋まっている。東側と西側とにまたがる地政学上の要所でもある。それゆえ、プーチンのみならず、過去にはヒトラーやスターリンといった独裁者たちからターゲットにされ悲惨な目に遭ってきた。
2014年、ウクライナがEUと政治経済にかんする包括協定を結ぼうとしていたときのことだ。ウクライナをEUから引き離したいプーチンは、断固として協定を結ばせまいとし、ウクライナ政権のヤヌコーヴィチ大統領(当時)に圧力をかけた。すでに腐敗した政権だったということもあり、プーチンの思惑通りに進むかに見えた。だが、恐れを知らぬキエフの若者たちによるデモが起こる。数日間のうちに、たちまちデモに参加する群衆の数は膨れあがり、ヤヌコーヴィチ大統領の腐敗政権を終わらせよ、との声が高まった。
注意深く観察していたプーチンは、警戒心を強めた。なぜならドレスデン駐在のKGB時代に経験した、ベルリンの壁崩壊時の苦い思い出があったからだ。ロシアの“利益圏”とみなしていた地域で、“衆愚政治“が広がっているーー過去のトラウマが、プーチンを一気に目覚めさせた。
電光石火のウクライナ侵攻作戦
ヤヌコーヴィチがロシアへ逃げ出したその1週間後。プーチンによる電光石火のウクライナ侵攻作戦に、当時は弱体化していたウクライナ軍は不意打ちを食らった。アメリカも油断していた。プーチンと同じく警察国家育ちで、KGB出身のプーチンの残虐さを知り抜いたメルケルでさえ、ウクライナについてはEU任せにしていたふしがあった。
メルケルは、プーチンが自由を愛する民主主義者に変わるという幻想は一度も抱いたことはなかった。とはいえ、経済成長を続ける西側をまのあたりにして、富を愛するプーチンがEU寄りの政策を取るのではないかと期待していたのだ。
しかしウクライナ侵攻により、「欧州の安全保障」という幻想は粉々に打ち砕かれた。プーチンが選んだロシアの未来とは、「西側の一員となる未来」ではなく、「西側に対抗する未来」だった。
プーチンが仕掛けたのは、「欺瞞作戦(マスキロフカ)」だった。これは20世紀前半にロシア軍が生み出した手法で、「だまし、否定、偽情報」の3つを駆使するというものだ。
プーチンは、クリミアのロシア系住民がロシアの介入を求めたと言い張った。「ファシストによる非合法の暫定軍事政権が、キエフやクリミアに住むロシア人の脅威となっている」と主張し、現地の群衆をあおり立てた。クレムリンによる同じような作り話は、1956年にハンガリー革命の制圧を正当化するのにも使われたし、1968年の“プラハの春”でも鎮圧のための戦車派遣を合法化するのにも使われた。さらには1948年、東西冷戦のはじまりともいうべき西ベルリンの封鎖を正当化するときにも使われている。
メルケルvsプーチン
2014年のウクライナ危機に際して、西側代表としてプーチンとの外交交渉を担ったのがメルケルだった。KGB仕込みのプーチンの恫喝に動じない唯一の西側リーダーが彼女だからである。オバマはプーチンには関わりたくないと思い、それゆえ彼女に舵取りを任せた。
じつは学生時代にロシア語の弁論大会で優勝したこともあるメルケル。もちろんプーチンもドイツ語は得意だ。プーチンとの会話はいつもまずロシア語ではじまる。だが、このときはプーチンに道理を説こうとするあまり、「アンタは、国際法を公然と無視してる」と、ついタメ口のドイツ語になることもあったという。
対するプーチンは、「その軍隊は、我々ロシアの軍隊ではない」と嘘をつき、「誰でもロシア軍の軍服を買える」とあからさまな言い訳をした。「プーチンは現実から切り離された自分の世界に生きている」――メルケルはオバマに愚痴った。
メルケルは、21世紀の戦争における最も危険な武器は、戦車やミサイルではないと認識していた。サイバー攻撃、SNS、フェイクニュースなどがあらたな戦場となっている。プーチンは、いわばハイブリッド戦争を展開しているのだ、と。
ファクトをもとに責任を問う
一方でメルケルも、プーチンに対して独自の「欺瞞作戦」を使うこともあった。プーチンは、ソチオリンピックに引き続き、同地にて開催予定のG8サミットで、帝政ロシアの復活をアピールしようと目論んでいた。しかしメルケルは、ソチでのG8は開催しないと発表。プーチンの“パーティ”を台無しにしてみせた。のみならず、ロシアはもはやG8のメンバーではない、とまで述べ、プーチンに強烈なパンチを食らわせたのだ。
そして7月、一般市民を乗せたマレーシア航空の飛行機が、ウクライナ上空で撃ち落とされるという痛ましい事件が起きた。これをきっかけに、国際世論におけるロシアへの非難が高まり、ついにオバマも本気を出してメルケルを支援するようになる。
2014年9月、ベラルーシのミンスクにある独立宮殿の壮麗な式典の間には、紛争地域の地図に身をかぶせるようにして話し合うメルケルとプーチンの姿があった。ときには15時間ぶっ続けで話し合いを行った。供される食事が肉料理か、それともジャムを添えたパンかによって、夜なのか朝なのかがわかるという状態だった。
元科学者らしく事実をもとにプーチンを追及するメルケル。現地の航空写真や戦場地図、ロシア軍の最新の動きなど、分単位でアップデートされる情報を入手していた。一日ごとの民兵の動き、拠点として押さえた場所、犠牲者の数――ファクトがあればプーチンの責任を問うことができる。
9月4日、ミンスク宮殿にて停戦交渉が終わった。合意文書にはプーチンの署名もあった。
《メルケル政界引退》愛犬を同席、わざと遅刻… プーチンのいじめに“東独育ち”の女性宰相が放った“痛烈な”一言
「プーチン大統領は別の世界に住んでいるようだ」政権に批判者が次々に殺害される…ロシアの“なぜ人々の声が届かないのか”
メルケルとプーチンの初めての会談はクレムリンで行われた。そこでプーチンは、KGB仕込みの睨(にら)みでメルケルを威嚇した。メルケルも目を見開いて応酬した。
そして、2007年に黒海に面したソチで行われた2度目の会談で、“事件”は起こった。
じつはメルケルは過去に犬に2度噛まれたことがあり、犬を怖がるという情報をプーチンは手に入れていた。
それゆえプーチンは、自分の愛犬であるコニーという名前の黒いラブラドールレトリバーを会見部屋へと入れたのだ。メルケルのまわりをまわって、匂いを嗅ぐコニー。メルケルは両膝をぴたりとくっつけて、足を椅子の下に入れて、落ち着かない様子だった。その間、プーチンは不敵な笑みを浮かべていた。
腹を立てたメルケルは、側近にこうこぼした。「プーチンはあんなことをするしかなかった。ああやって自分がいかに男らしいかを見せつけた。これだからロシアは政治も経済もうまくいかないのよ」。
ウクライナ戦争中に韓国が竹島周辺で測量計画 日本政府「強く抗議」
[2022年4/27]
韓国が島根県・竹島の地形などの精密な測量計画を進めていることについて、松野官房長官は韓国側に抗議し、調査の中止を求めたことを明らかにしました。
松野官房長官:「我が国としては、韓国政府に対して外交ルートで強く抗議をするとともに、調査の中止を強く求めたところであります」
松野官房長官は、韓国が計画している竹島周辺の測量について「受け入れられず極めて遺憾だ」と強調しました。
そのうえで、韓国の尹錫悦(ユン・ソクヨル)次期大統領が派遣した代表団に同行している韓国外務省の担当課長にも申し入れを行ったことを明らかにしました。
岸田総理大臣は26日、代表団に関係改善が急務だという認識を示していました。
砲撃で原子力研究施設が損壊 ウクライナ東部ハリコフ
2022年3/7(月) 10:59配信
【リビウ(ウクライナ西部)共同】ウクライナ原子力規制監督局は2022年3月6日、ウクライナ東部ハリコフで小型研究用原子炉がある「物理技術研究所」が同日、ロシア軍の砲撃を受け、複数の施設が損壊したと発表、「新たな核テロ」だとしてロシアを非難した。周辺の放射線量など詳細は不明。ウクライナメディアによると、同国のシュカレト教育科学相は、ロシアの侵攻後、ウクライナ全国でこれまで211の学校が攻撃で破壊されたり損傷したりしたと述べた。
プーチンはこの建物の中で、プルトニウムを使ったジェノサイド計画と核兵器を作っていたと、疑いを掛けて、我々の平和維持軍がミサイル攻撃した、と言った。
2022年3月6日
 |
| 2022年3月6日、ウクライナの核施設、及びすべての原子力発電所を攻撃し、制圧する、とプーチンは主張している。 |
中国人もロシア人も、2022オリンピックの新聞や2022北京パラリンピック競技だけを見て暮らしているので、ウクライナ戦争は知らない人が多い。
この2人が世界のリーダーとなるのだろう。2人が生きている限り・・・
 |
| 習近平とプーチン |
中ロ、ガス供給拡大で関係強化 米欧けん制狙う ロシアの経済は盤石、戦争準備整う
2022年02月04日
【北京時事】中国とロシアは2022年2月4日、ロシア産天然ガスの中国向け供給量を拡大する契約に調印した。ロシア国営ガス独占会社のガスプロムが発表した。ウクライナ情勢が緊迫化する中、中ロは関係強化を通じ、両国への圧力を強める米欧をけん制する狙いとみられる。
中ロは2014年、パイプラインを通じて年380億立方メートルのロシア産ガスを中国に30年間供給する契約を締結、「シベリアの力」。ガスプロムと中国石油天然ガス集団(CNPC)がこの日結んだ契約では、供給量を100億立方メートル増やし、計480億立方メートルとした。
◇ガスプロムが「シベリアの力2」の準備に着手
ガスプロムは、モンゴルを経由する新しい対中国輸出用ガスパイプライン「シベリアの力2」の設計測量作業に着手した。ガスプロムは、プーチン大統領の指示をうけて、昨年9月からこの輸送ルートの検討に着手しており、2020年内には投資のためのすべての事前調査を終えるという。2022年今現在もガスパイプライン「シベリアの力2」は建設され続けている。
トルコを経由するガスパイプライン、サハリンを経由するガスパイプラインも計画がある。
輸出用ガスパイプライン「シベリアの力」「シベリアの力2」「シベリアの力3」は、国境を越えてつながる「LPGガスの一帯一路政策」である。中国の「一帯一路」と酷似した政策であって、騙されてはならない。
「欺瞞作戦(マスキロフカ)」これはプーチンが生み出した手法で、「だまし、否定、偽情報」の3つを駆使するというもの
日本も、マスコミや政府も、安全保障上、自国の軍事や地理上の施設など、情報を刻々とニュースなどに乗せて、世界中にばらまくことはやめた方が良い。アメリカも同じく戦争状態時に、自国が危なくなるような情報を相手に見せては命取りになるだろう。中露の軍艦が日本列島一周をしたニュースをどれだけの人が知っていただろうか。
日本は国民含めて政府関係者も少し「平和ボケ」している。国連もあてにならなくなった。
日本の番組、アメリカのTV番組も毎日チェックされていて、中国大使館やロシア大使館から本国へ筒抜けになっている。しかも、中国は法律で留学生、観光客が情報を持って帰るような義務を負わされている。驚くような法律が存在する。
戦争が始まってから「交渉」「電話相談」で解決しましょう、と言っても、「正常には育っていない、道徳心も倫理観もない人」には通じない。核戦争を始めるか、若しくは、狂った判断をした、ただ一人を抹殺するか、のどっちかを選択しなければならない。サダムフセインとの戦争が早く終わったのは、抹殺したからだ。
「ヴァッファ」とは、中露がアメリカと戦争をするための緩衝地帯のこと。ロシアとNATO諸国との「ヴァッファ」がウクライナ戦争。ウクライナを緩衝地帯とするとロシアにもアメリカにもメリットがある。核戦争を避けられるメリットがある。
中国が狙う台湾は、クワッド諸国との「ヴァッファ」である。ここを、うまくを緩衝地帯とすると中国にも日本、アメリカ、オーストラリアにもメリットがある。自分たちの国が戦場にならなくて済むからである。
ウクライナ戦争、次の中露の狙いは台湾戦争。
南シナ海の自由と台湾の主権が中国の支配に落ちるのは、2023年頃と言われている。
世界のリーダーになりつつある習近平
「国のGDPを立て直した救世主」習近平
(香港やチベット、新疆ウイグル自治区などで人権弾圧、ジェノサイド、テニス選手やジャーナリストなどの弾圧をして、その事実を経済力と軍事力で隠蔽することに成功しつつある。中国は、金の力で、他国を支配できることを「世界に忖度」させた。)
金融経済型の共産党主義=中国
は世界のリーダーとなるか?
新民主主義、人権無視の
全体専制主義、独裁政権の考えが「世界を支配」するのか?
 |
ドナルド・トランプ氏(第45代)
トランプ流の保護貿易主義
中国、武漢のコロナウイルスが世界中にパンデミックした。
融和主義者のバイデン、岸田首相は「世界の自由」を取り戻せるのか。
 |
 |
| 20年後のトランプ |
習近平はトランプ会談の時にアメリカ・ホワイトハウス内で「中国とアメリカで世界のリーダーを分けよう!」と呼びかけた。
2021年現在の現職者はジョー・バイデン(第46代)
Joe Biden。
就任日 2021年1月20日のあとの電話会談で、
習近平から、挨拶の後、世界を分け合って経済などをリードしましょう、と言われたらしい。甘い言葉には「裏」がある、、、
米企業幹部を出国禁止か 中国当局、報道
2023年9月
【ワシントン共同】米紙ウォールストリート・ジャーナルは29日、米コンサルティング会社幹部が、滞在する中国本土からの出国を約2カ月にわたって中国当局に禁止されていると報じた。数年前の事件の捜査に協力しているという。関係者の話として伝えた。
同紙によると、幹部はマイケル・チャン氏で、企業調査やリスク分析を手がける「クロール」で勤務。7月に中国本土に入った後、会社側へ中国から離れられないと伝えた。捜査対象ではなく、本土内での移動は自由という。香港を拠点に活動し、香港の旅券を所有している。
中国では今年、複数の米コンサル会社が国家安全当局の調査を受けるなどしている。
 |
| 日中友好議員連盟会長を務める自民党の二階俊博元幹事長 |
 |
| 自民党の二階元幹事長 |
中国の建国記念日を祝うイベントが都内で開かれました。処理水放出をめぐる問題で関係が冷え込む中、中国の呉江浩駐日大使は経済協力の重要性を強調し、日本からの投資を呼びかけました。「中日関係はいま複雑で厳しい状況に直面し、改善と発展のチャンスとともに、新旧様々な問題も抱えています」(呉江浩)
呉大使は2023年9月28日、日米関係や日中関係の厳しい現状を踏まえ、「相違に適切に対処し、新しい時代にふさわしい関係を構築していくことが求められる」と述べました。また、中国は経済成長に自信を示し、「中国は決してデカップリングをせず、常にオープンな国家だ」として、日本からの投資を歓迎すると強調しました。
イベントには、自民党の二階元幹事長や公明党の山口代表ら政財界などから約1400人が参加しました。(ANNニュース)
中国の建国記念日を祝うイベントが都内で開かれました。処理水放出をめぐる問題で関係が冷え込む中、中国の呉江浩駐日大使は経済協力の重要性を強調し、日本からの投資を呼びかけました。
中国の駐日大使 経済協力の重要性を強調
「中日関係は、いま核汚染水問題など複雑で厳しい状況に直面し、日本の改善と中国発展のチャンスとともに、新旧様々な問題も抱えています」(呉江浩)
呉大使は2023年9月28日、日中関係の厳しい現状を踏まえ、「相違に適切に対処し、新しい時代にふさわしい関係を構築していくことが求められる」と述べました。また、経済成長に自信を示し、「中国は決してデカップリングをせず、常にオープンだ」として、日本からの投資を歓迎すると強調しました。
イベントには、自民党の二階元幹事長や公明党の山口代表ら政財界などから約1400人が参加しました。(ANNニュース)
ウォール街「砕かれた野望」、中国リスクの圧縮急ぐ-米中対立も懸念
2024年1月5日
Cathy Chan、Ambereen Choudhury、Sarah Zheng によるストーリー •
(ブルームバーグ): ウォール街の最大手行の一つは、中国本土子会社の責任者に対し機密戦略の説明をやめた。中国政府が盗聴したり、後で詳細な情報を要求したりできないようにするためだ。
隣接する他の欧米行の拠点では、現地での金融データ保管と内部統制整備に経営幹部が数千万ドルを投じている。親会社から切り離し、バランスシート再編を検討する部門もある。
米中の緊張の高まりや、国家安全保障という名目の新たな規制を乗り切ろうとするグローバル金融会社の中国部門では、舞台裏で多くの思惑が交錯している。中国との深いつながりと長い歴史を持つ巨大金融機関のリストには、JPモルガン・チェースやモルガン・スタンレー、HSBCホールディングスが含まれる。
欧米行の中国部門はその結果、現代の国際金融ではめったに見られない規模で、中国業務の「リングフェンス(隔離)」を実行している。グローバル巨大金融機関が今後数十年の業務拡大の鍵を握ると考えていた銀行子会社は、より独立した運営が行われるようになり、場合により競争意識も低下した。
一連の対応と影響は非常にデリケートなため、10人以上の幹部や他の関係者が匿名かつ会社を特定しない条件で証言した。
ウォール街の大手金融機関が数年前まで追い求めていた夢は、詰まるところ、打ち砕かれつつある。中国当局は2020年、グローバル投資銀行が本土の現地パートナーと設立した合弁会社を全額出資子会社にできるよう規制緩和に動き、フラストレーションの時代に終止符が打たれたかに見えた。中国でのディールとトレーディングの一層激しい競争に備え、それらの業務のフランチャイズへの統合を銀行首脳は望んでいた。
しかし中国の経済成長が減速し、政策も変化する現状では、そうした取り組みは一段と困難になり、中国の大手金融機関に対し劣勢に立たされている。
中国大使、処理水問題には触れず 友好条約締結45周年の記念行事で
在日中国大使館は2023年9月28日、東京都内のホテルで中国建国74周年と日中平和友好条約締結45周年の祝賀レセプションを開いた。2023年8月の東京電力福島第一原発の処理水放出に反発し、中国は日本産水産物の全面禁輸措置をとっているが、呉江浩駐日大使は、あいさつでこの問題には触れなかった。 呉大使は、あいさつで「今年は中日平和友好条約締結45周年という中日両国にとって記念すべき重要な年を迎えました」としたうえで、「政治的相互信頼の積み重ね、互恵協力の推進、人と人の心のふれあいの深化、矛盾と相違の適切な対処でもって、新しい時代の要求にふさわしい中日関係の構築に努めることが求められています」と述べた。
日本側からは、来賓として、福田康夫元首相や日中友好議員連盟会長を務める自民党の二階俊博元幹事長、経団連の十倉雅和会長らが出席した。二階氏は「(日中)両国の平和は、アジアの平和、ひいては世界の平和につながるという信念を持ってお互いに努力をしていかなければなりません」とあいさつし、両国間の問題の解決のために「賢い知恵」が必要だと強調した。
レセプションには、政界や経済界などから約1400人が出席した。(山根祐作)
中国の世界製造業大会、韓国出展企業に注目集まる
2023年9月20日、韓国のロボットメーカー、現代ロボティクスの中国法人が出展した産業用ロボット製品。(合肥=新華社記者/汪海月)
【新華社合肥2023年9月29日】中国安徽省合肥市で24日まで5日間開かれた「2023世界製造業大会」では、韓国企業の展示エリアに来場者の注目が集まった。物を正確につかむ産業用ロボットや除菌機能に優れた空気清浄機、韓国風の雑貨や日用品など、約20社がさまざまな分野の製品を出展した。
 |
| 日本の技術から韓国の技術へ、韓国の技術から中国の技術へ(変わらない技術移転原理) |
2023年9月20日、来場者に製品を紹介する韓国の出展企業。(合肥=新華社記者/汪海月)
今大会のテーマは「スマート製造世界・素晴らしさを創造」。総面積8万平方メートルの会場に、量子コンピューターや動力ロケット、時速600キロのリニアモーターカー、超電導サイクロトロンを備えた陽子線治療システムなど製造業の最新成果を一堂に展示。出展企業数、展示面積ともに過去最高を更新した。(記者/汪海月、趙一寧)
2023年9月20日、来場者に製品を紹介する韓国の出展企業。(合肥=新華社記者/趙一寧)
中国「一帯一路」国際会議に鳩山元総理が出席
中国の巨大経済圏構想「一帯一路」の国際会議に鳩山由紀夫元総理が出席し、日本からの出席者が少ないのは残念だと述べました。
中国の北京で2023年10月17日から2日にわたって開かれた「一帯一路」の国際会議に参加しましたが、松野官房長官は「日本政府として出席は予定していない」と表明していました。
 |
| 中国「一帯一路」国際会議に鳩山元総理が出席「日本からの出席者は私だけかな?少なくて残念だな」 |
結論: