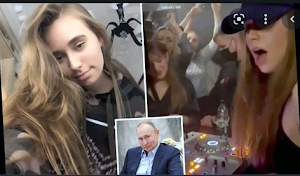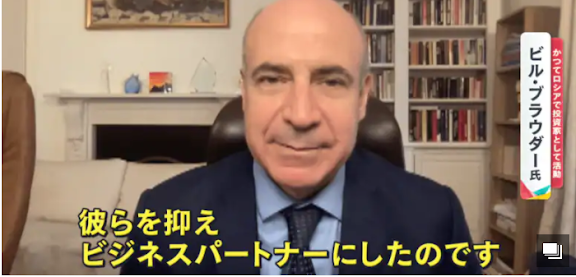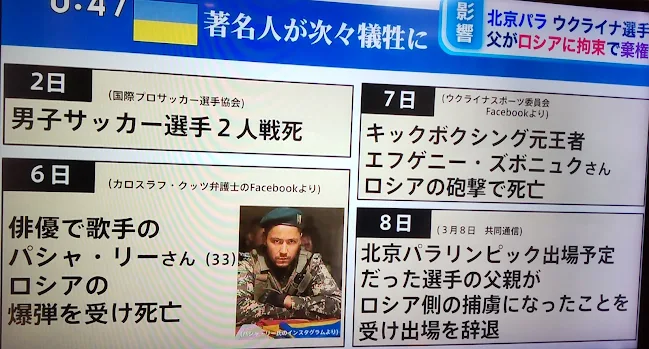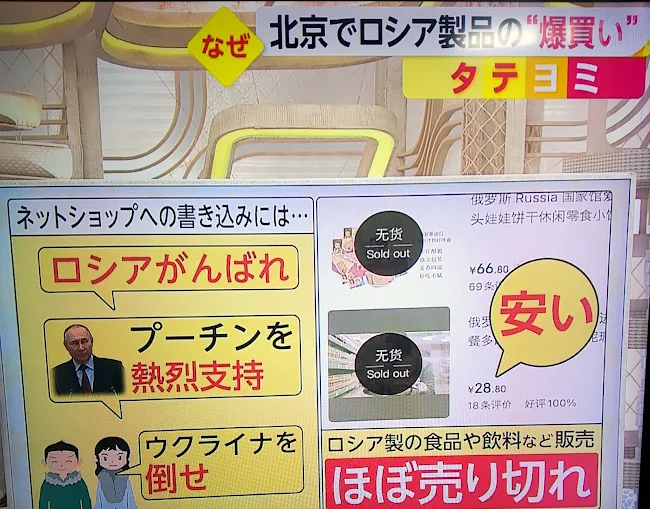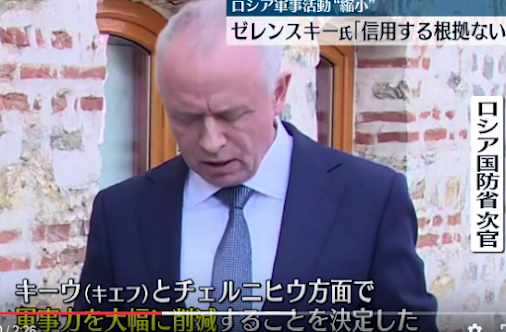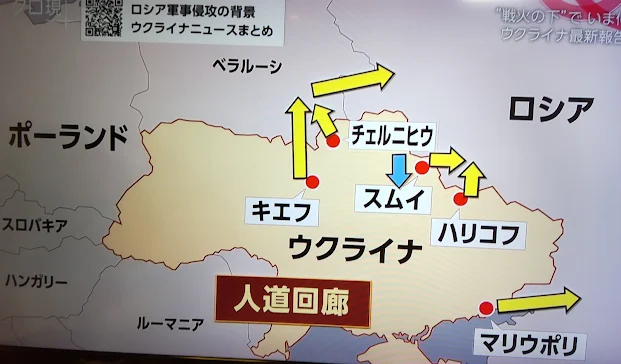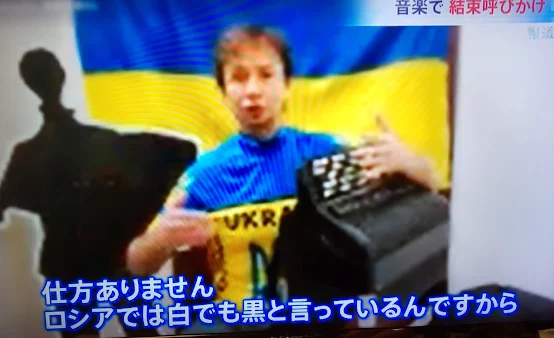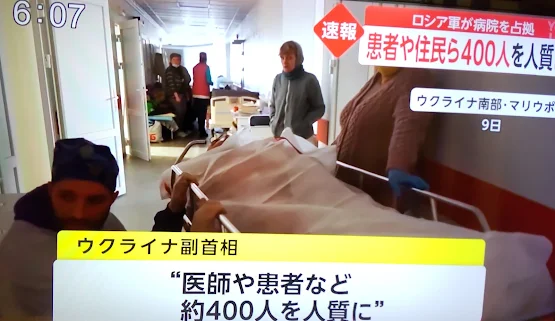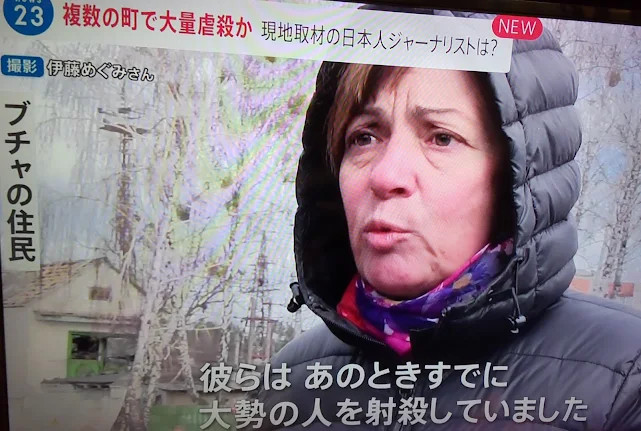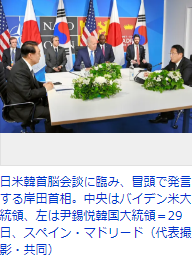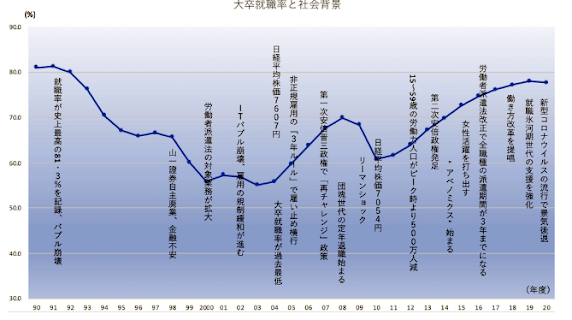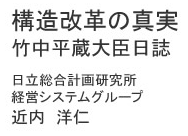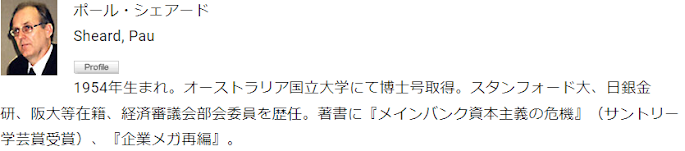➊ロシアの「嘘」と中国・韓国の「嘘」:2022年2,3月のウクライナ戦争、ロシア軍がウクライナを攻める正当性はどこにあるのか ロシア大使「日本はナチスを支持」とSNSに投稿し波紋(2022年3月2日)
 |
| 2022年3月3日、ロシア軍のミサイル爆撃で破壊された住宅の空撮=ウクライナ首都キエフ郊外で(ロイター・共同) |
 |
| 1930年代、ナチスの空爆で廃墟となったゲルニカの町 |
相手を効果的に破壊する空爆(空からのミサイル攻撃)
 |
| 豹変する前のガルージン駐日ロシア大使と、いつも温厚な鳩山由紀夫氏 |
ロシア軍、首都キエフなど4都市で“人道回廊”実施を発表…ウクライナ側から正式発表なし
ロシアのメドベージェフ前大統領
北方領土は「ロシア」主張 北方領土について「ロシア領だ。日本の国民感情など知ったことか」「特に悲しむサムライは切腹すればよい」などとSNSに投稿
2024年1月31日

ロシア ラブロフ外相
「ロシアはどの国とも領土問題を抱えていない。日本との領土問題を含めすべて終結している。彼らは、このことをよく理解している」
ラブロフ外相は18日、政府系テレビのインタビューで、ロシアがウクライナに続いてNATO=北大西洋条約機構の加盟国を攻撃するのではないかとの見方を否定し、「ロシアとNATO加盟国との間に領土問題はない」と述べました。
 | |
|
 |
| 嘘の天才プーチン露大統領(元KGB、 反体制派を弾圧してきた人)メディアなど言論統制 した人。独裁者、核戦争もい問わない殺し屋 |
 |
| アドルフ・ヒトラー(大量人権侵害の開祖) |
 |
 |
| プーチンの最初の妻と愛人カバエワ |

 |
| ぺスコスは7000万円の腕時計を持っている |
 |
| 父ぺスコフ報道官によって兵役を逃れた息子のニコライさん。 過去には、ロシア国営の放送局で働いていたことがあるといいます。 |
恐怖、パワハラ、セクハラ、お金による支配、プロパガンダ・・
 |
| 恐怖、パワハラ、セクハラ、お金による支配、プロパガンダ・・ |
 |
| 恐怖、パワハラ、セクハラ、お金による支配、プロパガンダ・・ |
 |
| ロシアのネットメディア「メドゥーザ」が伝えたのは、礼儀正しく整列した子どもたちが「Z」の文字を形作っている映像でした。「Z」は、元々ロシア軍の車両に書かれていたものですが、いつしか「ウクライナへの侵攻を“支持”する象徴」に変化しています。 |
 |
| ウラジオストクで車約100台を集めて、プーチンを支持する集会を開いた男。 この車たちで、ウクライナ人をひき殺したい!と、話し合っている。 |
 |
中国に出店しているロシアのスーパーで、ロシアの製品を買い物する中国人(中国共産党員)が増えている。 西側の経済制裁からロシアを支援し、守ろうと、中国人が立ち上がろうとしている。 |
 |
| ロシアの勝利のために、中国人が力を貸してくれるのは、感謝の気持ちでいっぱいです。 |
 |
| 2022年1-2月期のロシアと中国の経済関係は、対前年度比で、3割から4割増しであった。 中国のロシアへの経済援助がますます高まっていく。 |
 |
| エストニアにある北大西洋条約機構(NATO)の基地を訪問したボリス・ジョンソン |
【2022年3月2日 AFP】英政府は2022年3月1日、ウクライナに侵攻したロシアのウラジーミル・プーチン(Vladimir Putin)大統領と軍司令部が戦争犯罪で訴追される可能性があると警告し、現地での被害をユーゴスラビア紛争(Yugoslav War)の惨状に例えて非難した。
 |
モスクワでの反戦デモと、それを取り締まるプーチンの警察官たちは「夜のオオカミ」と呼ばれている。 ©Getty Images |
 |
| 2022年3月29日、ウクライナ南部・ミコライウで撮影された映像 |
 |
| 助け出された女性「私のフロアで女の子が亡くなった。言葉がない。彼女を抱きしめて、その2分後にはもう…」 |
 |
| 人権団体「ZMINA」タティアナ・ピチョンチックさん: |
 |
| 2022年3月6日、ウクライナの核施設、及びすべての原子力発電所を攻撃し、制圧する、とプーチンは主張している。 |
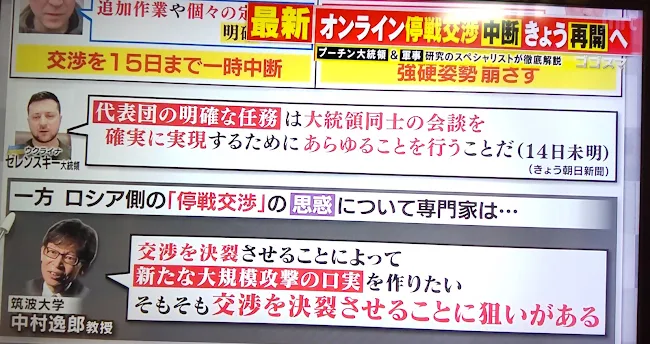
最も非人道的な爆弾を使用するロシア軍
 |
プーチン大統領は「彼ら(ロシアが雇ったシリアの傭兵)が金銭目的でなく、ボランティアなら、彼らが戦闘地域に行くのを助けなければならない」と話した。 |
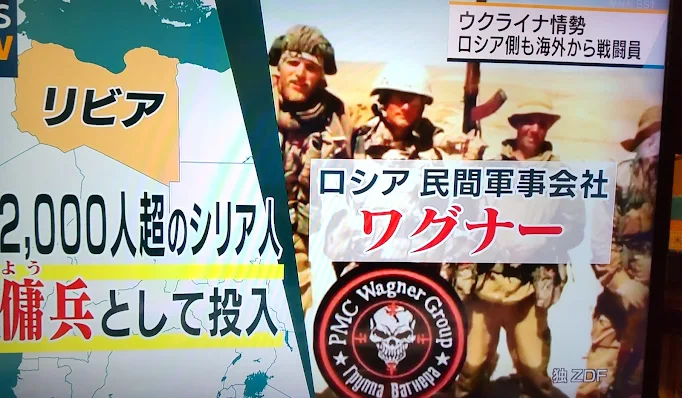 |
| プーチンの言う平和維持軍がワーグナーだ。 |
 |
| 「ウクライナの民族主義者が2022年6月4日、 スヴャトヒルシクから撤退した際に木造聖堂に放火した」 |
 |
 |
| 両国の閣僚レベルの会談だったが、停戦に向けた進展はなし。 ラブロフ外相は、停戦については高官協議で話し合われると指摘し、 「我々はどこの国も攻撃していない。攻撃したこともない。」「ウィン、ウィンでやりましょう」と主張した。 |
 |
| 西ウラル「秘密の地下宮殿」でチャイコフスキーを楽しむプーチン。 |
*写真キャプションを修正して再送します。
私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」
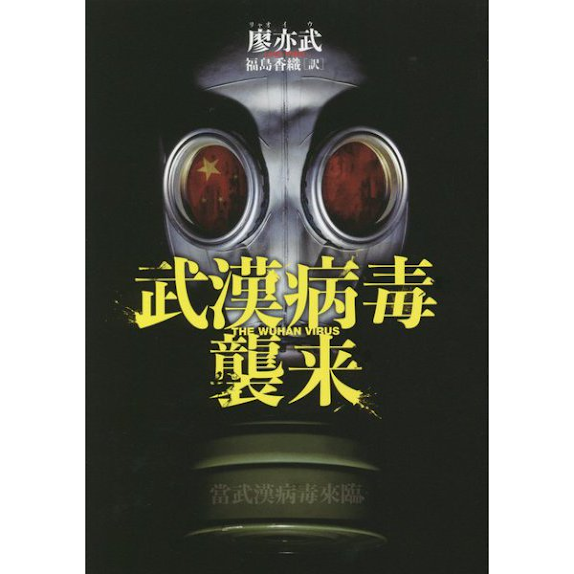 |
| 生物兵器の歴史を作ったコロナウイルスのパンデミックと発症先。武漢ウイルスを隠す中国共産党の戦略 |
 |
| 中国の有名な二人の政府報道官が、「嘘」の書き込みをしている。 |
 |
| アメリカの援助でさらに強力なコロナウイルスを開発している疑いがある。 |
 |
それでも、スターズコーヒーのロシア人オーナーは、「丸以外に共通点は見当たらない」と話す。
 |
| 中国、上海のミッキーマウス |
 |
| 「韓国のゲーム業界が中国を相手にけんかを仕掛けるのだ。」 |
 |
| 露・中国・韓国は嘘に嘘を固めたような国家だ。 |

 |
| プーチンによってゾンビ化した国営放送 |
 |
| 平和外交のコンビ「晋三&ウラジミール」が誕生した。 |
 |
| プーチンも宗男も晋三も、沈思黙考しないタイプだな。安倍─プーチン路線の東方経済の発展構想は計画の段階ではウィン・ウィンだったが、すぐにプーチンに裏切られた。その結果、「ロシアの健康寿命を20年間延ばす」手伝いをさせられた。なぜ日本は中国、ロシアの経済発展を推し進めるメインプレーヤーになりたがるのか? |
ウラジミールと晋三は山口のホテルで、何を話し合ったの?成果があったのか?今現在、安倍晋三に聞いてみたい。
 | |

 |
| アゾフ(Azov)海に面した要衝の地であるマリウポリ |
 |
| 非軍事拠点に対して、過剰という単語でも生ぬるいほどの空爆をしている。 |
 |
| ロシア軍 ミサイル攻撃の瞬間 ショッピングモールも...11人死亡 |
 |
| マレーシア航空の定期旅客便がウクライナ東部上空を飛行中に撃墜。 乗客283人と乗組員15人の全員が死亡した事件である。 |
 |
| 地対空ミサイル「ブーク」 |
 |
| 地対空ミサイル「ブーク」 |
 |
| 地対空ミサイル「ブーク」 |
 |
| 地対空ミサイル「ブーク」に積まれたミサイルの数が合わない。 |
 |
| 地対空ミサイル「ブーク」 |
 |
| 地対空ミサイル「ブーク」 |
 |
| 地対空ミサイル「ブーク」 |
 |
| 地対空ミサイル「ブーク」と実行犯たち |
2022年3月12日、バッハのエコーを演奏するロシア人の演奏家ザバドスキーさん
- 2021年1月20日
- アメリカのマイク・ポンペオ国務長官は19日、中国がウイグル族など主にイスラム教徒を抑圧する中で、ジェノサイド(集団虐殺)を犯したとする声明を発表した。
- ジョー・バイデン氏から新政権の国務長官に指名されているアントニー・ブリンケン氏も、こうした見解への同意を表明した。
- 人権団体は、中国が過去数年間に「再教育施設」と呼ぶ場所に、最大100万人のウイグルを拘束していると訴えている。
- BBCは調査報道で、ウイグルの強制労働が行われていると伝えている。
- アメリカと中国の緊張関係は、ドナルド・トランプ政権下でより鮮明になった。その影響は、通商から新型コロナウイルスの問題まで広範に及んだ。
- ポンペオ氏の声明
- ポンペオ氏は「このジェノサイドは続いており、中国の一党制がウイグル族を組織的に絶滅させようとしているのを、私たちは目の当たりにしていると信じている」と声明で述べた。
- 20日に任期が終わるトランプ政権の閣僚であるポンペオ氏にとって、この日は最後の執務日となった。
- 同氏の声明は中国に圧力をかける一方、新たなペナルティを自動的に発動させるものではない。
- ブリンケン氏は同意
- バイデン氏に国務長官に指名されたブリンケン氏は19日、議会上院の指名承認の公聴会に臨んだ。
- ポンペオ氏の声明に同意するか問われると、ブリンケン氏は「私の判断もそうなる」と答えた。
- バイデン氏の政策チームは昨年8月、ウイグル族が「中国の独裁的な政府による筆舌に尽くしがたい抑圧」に苦しんでいるとし、今回のポンペオ氏の声明と同様の見方を示していた。
- バイデン新政権は20日、発足する。
- 新疆ウイグル自治区の状況
- 中国政府は、約1100万人のウイグル族の多くが暮らす新疆ウイグル自治区で、分離主義、テロリズム、過激主義の「3つの邪悪な勢力」と闘っていると説明。そのために、同自治区で「訓練プログラム」が必要だとしている.
- 新疆ウイグル自治区には近年、中国で多数派の漢族が大挙して移住している。
- 1990年代以降は漢族への反感と、分離独立の気運が高まっており、暴力行為につながる事態も散発している.
- 人権団体などは、中国政府がイスラム教徒に豚肉を食べることや飲酒を強制し、ウイグル文化の消滅を図っているとしている。
- 中国政府はウイグル族を収容している施設について職業訓練所だとしている
 |
| ハーグ国際司法裁判所のインド側裁判官が、反ロシア票を投じていた。これをインド政府が、どう見ているかが危ぶまれる。 |
 |
| 習近平とプーチン |
 |
「欺瞞作戦(マスキロフカ)」これはプーチンが生み出した手法で、「だまし、否定、偽情報」の3つを駆使するというもの
台湾国防部は2022年2月24日、中国軍機9機が南シナ海の東沙諸島北東の防空識別圏内に入り、台湾軍機を緊急発進させたと発表した。南シナ海の自由と台湾の主権が中国の支配に落ちるのは、2023年頃だろう。ロシアと違って中国や韓国は、「孫氏の兵法」でやってくるのだろう。
 |
| ウクライナ侵攻の開始時期を相談された時の顔 |
The meeting was the first between Sullivan and Yang since the two met in Zurich in October US National Security Adviser Jake Sullivan met with China's top diplomat, Yang Jiechi,for an "intense" seven-hour conversation on Monday to discuss reports that Russia has asked Beijing for arms to support its invasion of Ukraine, US officials said. The US expressed "deep concerns" about China's "alignment" with Russia after the talks. US State Department spokesman Ned Price said, "The national security adviser and our delegation raised directly and very clearly our concerns about the [People's Republic of China] PRC's support to Russia in the wake of the invasion, and the implications that any such support would have for the PRC's relationship not only with us, but for its relationships around the world." 米国の国家安全保障問題担当補佐官ジェイク・サリバンは、2022年3月7日月曜日に中国の最高外交官である楊潔煕と7時間もの『集中した』会談をし、ロシアが北京にウクライナ侵攻を支援するための武器を 要求したという報告について話し合った。
続いて氏は、ロシアとの取引を停止し、ウクライナ領内で活動中のドローン情報を提供するほか、外国で購入されウクライナで使用されているあらゆるDJI製品を使用不能にするよう求めている。
同社はまた、必要であればウクライナ政府として正式に要請するよう求めた。ロシアとの深いパイプが指摘される中国に本社を置く企業としては、相当に前向きな回答となっている。 ただし、技術的制約から、高い実効性は期待できない可能性がある。ウクライナ全土にジオフェンスを適用した場合、ウクライナ側のドローンもすべて飛行不能となるためだ。ウクライナでは軍とドローン所有者有志が協力し、ロシア軍の動向をドローン部隊で監視しているが、これが機能しなくなることを意味する。また、ジオフェンス機能の更新にはネット接続が必須となるが、どれほどのオーナーが更新に応じるかは不透明だ。 ジオフェンスは本来、空港や原子力設備など重要施設周辺を局所的に飛行禁止にするための機能だ。同社の提案はこれをウクライナ全土に拡大して適用し、同社製ドローンを全面的に飛行不能にする内容となる。
「これが戦争じゃ…」日本人カメラマン・宮嶋茂樹がロシア軍ジェノサイドの現場・ブチャで見た"戦慄の真実”《緊急公開写真/注意・遺体の写真が含まれます》
4/6(水) 15:42配信
不肖・宮嶋、最後の戦場取材へ――。
数々のスクープ写真で知られる報道カメラマンの宮嶋茂樹さん(60)。これまでにイラク、北朝鮮、アフガニスタン、コソボなど海外取材を数多く経験し、あまたのスクープ写真を世に問うてきた。そんな不肖・宮嶋がロシアの軍事侵攻に揺れるウクライナへ。混乱する現地で見えてきた「戦争の真実」とは?
4月5日、宮嶋さんはキーウ近郊のブチャ取材のためのプレスツアーに参加。ブチャでは、ロシア軍から奪還した後、多数の民間人の遺体が見つかっている。ゼレンスキー大統領は4日、ブチャを視察し、「戦争犯罪であり、ロシアはジェノサイド(大量虐殺)を犯した」と非難した。
不肖・宮嶋が撮った「ブチャの現実」を緊急公開する。
※注意 以下の記事には、遺体の写真や描写が含まれています
【キーウ近郊ブチャの様子の写真をすべて見る (注・遺体の写真が含まれます)
 |
| 腕も首もないのにパーフォーマンスでできるか!見に行ってこい! |

宮嶋 茂樹/Webオリジナル(特集班)
ブチャを上回る数の遺体発見 キーウ北西ボロディアンカで
2022年4/6(水) 14:33
ボロディアンカ、ウクライナ、2022年4月6日(AP)― ウクライナ北部から侵攻したロシア軍の撤退に伴って、進駐先の至るところで無差別に虐殺された住民の遺体が発見され、ロシア軍の残虐行為が次々に表面化している。
首都キーウ(ロシア語表記キエフ)北方のブチャでは、410人もの住民が無差別に虐殺され、ロシア軍の戦争犯罪が声高に糾弾されている。
ウクライナのイリーナ・ベネディクトワ検事総長によれば、キーウの北西約64キロのボロディアンカからは、ブチャを上回る被害が報告されているという。
ボロディアンカは、首都防衛のウクライナ軍とキーウ包囲を目指す
ロシア軍の間で激しい攻防戦が繰り広げられた都市型集落で、立ち並ぶアパート群はロシア軍の砲爆撃で破壊され、ガレキの街と化した感がある
ブチャで起きた惨劇は、首都北部のスクイやチェルニヒウでも起こっていたとみられており、ボロディアンカでは、ブチャを上回る数の遺体が発見されたと報じられている。
(日本語翻訳・編集 アフロ)
メキシコの取材班が遺体発見 ロシア軍が撤退したイルピン
2022年4/5(火) 14:09
イルピン、ウクライナ、2022年4月5日(AP)― メキシコとスペイン語圏最大手テレビ局「テレビサ」の取材班が4月1日、ウクライナ北部に侵攻したロシア軍が撤退した後の首都近郊で、無差別に殺害されたとみられる住民の遺体複数を発見した。
数々の遺体が発見されたのはキーウ(ロシア語表記キエフ)に隣接するイルピンで、リポーターはバラバラにされた遺体も何体かあったと証言。
また、取材に応じた地元住民は「ロシア兵の姿を見て、怖くて逃げた」と話していたという。
ウクライナ当局は、キーウ周辺のイルピンやホストメリ、ブチャなどでロシア軍が戦争犯罪に該当する残虐行為を働いたとして、訴追のための証拠を収集している。
ウクライナの検事総長は、最近ロシア軍から奪還されたブチャで、民間人410人の遺体が発見されたことを明らかにした。
(日本語翻訳・編集 アフロ)
 |
| 母性本能をくすぐる人たらし野郎 サイコパスの目でロシアをろくでなし国家にした野郎だ。 プーチン大統領は社会病変質者であり、目障りな国家、目障りな野郎は殺したいだけだ。 |
「ブチャ大虐殺」にも…韓国政府、ロシアを批判さえしなかった
ウクライナのブチャ地域で発生した民間人大虐殺事件に対して世界各国が強く糾弾し、ロシアに対して強硬対応も辞さない構えを見せている中、韓国は公式立場でロシアに言及さえしないまま状況自体に対して「深い懸念」を表わすだけに留まった。
◆韓国政府の消極性が表れた「三行声明」
ブチャ大虐殺が伝えられたのは今月2日(現地時間)、日本時間では3日ごろだ。ロシア軍が通り過ぎた都市の至るところに残酷な殺され方をした民間人の遺体が大量に見つかったためだ。
韓国政府の公式立場はそれから数日後の5日に出てきた。三行という短いものだった。
韓国外交部は報道官の声明を出して「わが政府はウクライナ政府が発表した民間人虐殺情況に対して深い懸念を表明する」とし「戦時の民間人虐殺は明白な国際法違反」と指摘した。
続いて「あわせて独立的な調査を通じた効果的な責任糾明が重要だという国連事務総長の4・3声明を支持する」と明らかにした。これに先立ち、3日(現地時間)、国連のアントニオ・グテレス事務総長は声明を通じて「ブチャで殺害された民間人の画像に大きな衝撃を受けている」とし「独立した調査によって、説明責任がしっかりと果たされることが不可欠だ」と明らかにした。
この日の外交部報道官の声明で、韓国政府は虐殺加害者であり国際法違反主体であるロシアを名指しすることも、惨状に対するロシアの責任を問うこともなかった。当然行われるべき真相調査に対しても、既に国連が明らかにした立場に便乗する形で必要性を支持するのにとどまった。
◆世界各国、一斉に「ロシアが戦犯」
反面、米国や欧州国家の対応は韓国と比較できないほど積極的だ。
米国はブチャの惨状が明らかになった直後、追加制裁の検討とロシアの国連人権理事会退出推進に拍車を加えた。
ジョー・バイデン米大統領は4日(現地時間)、ワシントンで取材陣と会い、改めてプーチンを「戦犯」と言い、「彼は残忍で、ブチャで起きたことはとても衝撃的」と批判した。トニー・ブリンケン米国務長官も「激しい憤慨を覚えざるをえない」(3日、CNNインタビュー)とし「故意的殺人、拷問、性暴行、残酷行為」(5日、取材陣の前)と猛非難した。
欧州連合(EU)や英国も同じ言葉でブチャ大虐殺を「ロシアの戦争犯罪」と規定して追加制裁を検討中だ。ボリス・ジョンソン英首相は3日(現地時間)、「罪のない民間人に対するロシアの卑劣な(despicable)攻撃」と糾弾した。エマニュエル・マクロン仏大統領も同日、「我慢できない」とし「ロシアが答えろ」と話した。その他にも「故意的戦争犯罪」(デンマーク)、「ロシアが犯した戦争犯罪」(スウェーデン)、「ブチャ惨状に怒り」(スペイン)など糾弾メッセージが相次いだ。
欧州国家は自国に駐在するロシア外交官の追放措置に入った。ロイターなどによると、5日(現地時間)を基準として欧州各国から追放されることになったロシア外交官は200人余りに達する。正常外交関係を結んでいる国家に対して非常に異例かつ強力な措置だ。
怒りはアジア太平洋からもあふれた。マリス・ペイン豪外相は3日(現地時間)、ツイッターを通じて「ロシア軍の処刑、性暴行、略奪に衝撃を受けた」とし「卑劣な行為」と指摘した。オーストラリアは翌日、ロシアに対するぜいたく品の輸出禁止制裁措置を発表した。
岸田文雄首相も4日(現地時間)、ツイッターに「無辜の民間人の殺害は、国際人道法違反であり、断じて許されず、厳しく非難します」とし「ロシアは、その責任を厳しく問われなければなりません」と明らかにした。同日の記者会見では「国際社会で(ロシアに対する)非難の声が高まっている」とも指摘した。
ロシア兵は突如、11歳の少女の「あごに発砲した」...住民が語るマリウポリの非道
2022年4/6(水) 12:10配信
<街の「100%」が破壊された南東部の最激戦地マリウポリ。脱出途中の人道回廊で銃撃を受けた女性が目撃したものは>
ウクライナ南東部のマリウポリは、ロシア軍による侵攻の象徴的な街になっている。包囲攻撃が行われ、産科病院や「子供」と地面に書いてあった劇場が爆撃され、「人道回廊」も十分に機能しなかった。既に5000人が亡くなったとの報道もある。
そんな包囲下のマリウポリに3週間いた女性に現地で話を聞くことができた。
「ロシア軍の検問所で止まれ!と言われた。それからロシア兵が指を空に向けてくるくると回した。どういう意味かよく分からなかったけど、取りあえず引き返そうとしたら突然、発砲された。車にいた女の子があごを撃たれた」
カテリーナ・イェスカ、31歳。ウクライナ南部のオデーサ(オデッサ)出身で夫と共に昨年12月からマリウポリに住んでいる。彼女はロシア軍の侵攻後もマリウポリにとどまることを決め、ボランティアとして食べ物や水の配給を手伝っていた。
「食べ物も水も十分にない。外で火をたいて料理している人もいた。気温はマイナス10度なのに、爆風でガラスが吹き飛ばされて窓も役に立たない。街はとても危険だった。水を得るために外を歩いているだけで狙われた」
マリウポリの街は今、80%が破壊されたといわれている。
「でも私には残りの20%がどれを指しているのか分からない。全部、破壊されたように見えるから」
3月16日、彼女は脱出を決意する。
「道である家族に出会った。女の子と母親とおばあちゃんがいて、飼い猫とハムスターと亀を連れていた。私が乗っていた車に乗せていくことにした」
しかしその車が途中、銃撃を受けた。
■ロシア兵はなぜ銃撃したのか?
「直前のロシア軍の検問でチェックを受けて武器は持っていないことを確認されたばかりだった。次にあった検問は500メートルとか1キロとか、そんなに離れてはいなかった。でも、止まるように言われて、引き返そうとしたら後ろから撃たれた」
弾丸は車内にいた11歳の女の子のあごに当たり、喉仏近くに突き刺さった。女の子はザポリッジャ(ザポリージャ)の病院に運ばれた。
なぜ兵士は発砲したのか。
「兵士は私たちの車から誰かが発砲したと言った。でもおばあちゃんや小さな女の子を乗せた車よ。それに撃たれる前に発砲の音なんてどこからも聞こえなかった。これは見せしめなんだと思う。『人道回廊』は使えない。ロシア側の領地に行くか、マリウポリに残るしかないって住民に思わせるために」
カテリーナはそう力を込めて言った。
「何度でも言う。その道路は避難のために通っていいと安全が保障された道だった。通っていいという合意があった。なのに発砲した」
住民たちはもともと反ロシアではなかった
マリウポリでのロシア兵の様子についても話してくれた。
「マリウポリではロシア兵は嘘の情報を流して回っていた。スピーカーを使って、『ウクライナ側にはもう行けない。ウクライナ政府はもうあなたたちのことを受け入れない』と言ってね。ロシア側に行くしかないと住民に思わせようとしていた」
カテリーナは女の子たちと別れ、元の車の運転手とザポリッジャに向かった。彼女自身も移動中にチェチェンの部隊に止められ、ザポリッジャに行くのだと伝えると、「ザポリッジャはもう包囲されていて入れない」と嘘を教えられたという。実際はウクライナ政府のコントロール下にあり、多くの避難民を受け入れている。
アジア系の顔立ちをしたロシア兵を見たという話もしてくれた。スラブ系のロシア人にとってもこの戦争は突然だったのだろうが、ロシア政府はよりウクライナの問題になじみが薄い人々を投入しているのかもしれない。
ロシア軍はマリウポリの住民6000人をロシア側に強制連行したともいわれている。
「私の友達の両親がロシアに連れて行かれた。書類にサインさせられて3、4年とどまるって約束させられたそう」
ロシア軍は連行した人々の思想チェックをし、ロシア寄りの人とそうでない人に分け、そうでない人は外部と接触できない所に隔離している、という未確認情報もある。
3月20日にロシア政府はマリウポリの降伏を提案し、ウクライナ政府はこれを拒否した。マリウポリの人たちはこの事態をどう感じているのか。カテリーナは説明する。
「私はその時にはもう脱出していたから分からない。けれど、みんな降伏したからって安全になるとは思っていなかった。街に残った男性たちは、家族へのお別れのメッセージを録画していた。降伏するより死ぬつもりだと」
住民たちは2月の侵攻が始まる前まで、反ロシア政府感情が強かったわけではない。マリウポリのすぐ近くにはロシア編入を求めるドネツク共和国があり、マリウポリ自体も同じドンバス地域にある。既に戦争は隣で起き、毎日、砲撃の音が聞こえていたにもかかわらず、統治者が誰かに住民は関心がなかったという。
「マリウポリの人たちは皆政治には関心がなかった。ただ平和な暮らしがしたいと思っていただけ。彼らにとっては、政治的にロシアかウクライナのどちらかを選ぶという問題ではなかった」
しかしこの侵攻が人々の考えを一変させた。
「中立的な立場だった人まで侵攻後は劇的に変わった。ロシアへの感情とかそんな話じゃない。平和的な人たちも殺して妊婦さえ逃げられないのだから。これは戦争だから」
この決死の覚悟に、私はどう反応したらいいのか分からない。住民に死んでほしくはない。住民には戦いたいという思いだけでなく、降伏しても殺されるだろうという想像、予測がある。国際社会にできることはもっとあるはずだ。ウクライナの人々に全てを背負わせるのではなく。
伊藤めぐみ(ライター)
ロシア当局により死亡が確認された、ロシアの民間軍事会社「ワグネル」のトップ、プリゴジン氏。 その生前に撮影されていた40秒の動画が公開され、波紋を呼んでいる。 プリゴジン氏「プーチンよ、わたしを殺した方がいい。わたしはうそをつかない。ロシアは破滅の瀬戸際にあると正直に言わなければならない」 イタリアの銃器メーカー「ベレッタ」のロゴが入るカーキ色の服を着たプリゴジン氏。 40秒の動画は、日本時間27日、ワグネルに近いとされるSNSに投稿された。 ウクライナでの戦闘をめぐり、ロシア国防省の支援体制に反発していた4月、ロシアの軍事ブロガーによるインタビューに応じた際のものとみられる。 プリゴジン氏は、死を覚悟したかのような強い口調でプーチン政権を糾弾。 その40秒間の訴え。 プリゴジン氏「ロシアには強い男が存在するが、強い男は徐々に駆逐されつつある。(強い男たちは)プーチン上層部のケツをなめるつもりはない。きょう、われわれは我慢の限界に達した。なぜ正直になるのか? なぜなら、これからこの国を生きていく人たちの前で、わたしにうそをつく権利はない。彼ら(国民)にうそをつく権利はわたしにはない。(真実を語らせたくないなら)上層部はわたしを殺した方がいい。しかし、わたしはうそをつかない。プーチンのロシアは破滅の瀬戸際にあると正直に言わなければならない。そして今、手を打たないと、飛行機は空中分解してしまうだろう」
SOCIETY
3min2022.3.15
お見合い仲介サービスへの依頼は2倍に
“ウクライナ人の花嫁”を欲しがる中国人男性が武力侵攻後に急増した理由
 |
| 中国人が声を掛けてきたら、注意すべきだ。 |
ウクライナ人女性とのマッチング希望者が急増
「(戦争で)家を失ってしまったウクライナ人女性を保護します」
「若くて美しく、未婚で、健康な女性が優先です」
ロシアがウクライナへの軍事侵攻を開始した2022年2月24日以降、中国のソーシャルメディア「ウェイボー(微博)」上で、男性ユーザーらによるこのような投稿が急増したと、報じられている。
これらの投稿は、「ウクライナ人女性を妻にしたい」という強い欲望を持つ中国人男性による、若いウクライナ人女性への“ラブコール”だ。戦時下において、これらの投稿は不適切だと判断され、現在は削除されているが、それでもロシアのウクライナ侵攻を、「ウクライナ人女性を妻にする絶好のチャンス」としてみている男性が中国に大勢いることには変わりはない。
 |
| 車に乗った中国人が声を掛けてきたら、注意すべきだ。 |
中国では、女性や子どもの人身取引(人身売買)は深刻な問題です。また実際にはそれ以上の子どもが誘拐され、知らない場所で人身取引や売買の被害にあっている可能性も十分に考えられます。
アメリカ国務省の人身取引の実態をまとめた報告では、中国は最低評価を受けた国の一つであり、人身取引(人身売買)で連れてこられた人たちが国営の薬物依存症患者の治療施設などで強制労働をさせられていると指摘されています。
なぜ中国では法律で禁止されているにもかかわらず、女性や子どもたちが人身取引の被害にあうのでしょうか。人身売買のシンジケートがあります。国営企業の幹部も関係しています。
また、被害を受けている子どもたちを支援することはできないのでしょうか。今、私たちにできることを考えます。
(出典:法務省「出身国情報に関する報告書 中国」)
人身取引、人身売買、人権のない国、それが中国だ。
 |
| 2022年3月17日、ウクライナや西側の当局者は、ウクライナでのロシアの進軍が停滞しているとの見方を示した。写真はキエフで同日、砲撃を受けた集合住宅の前を通る人(2022年 ロイター/Marko Djurica) |
ウクライナの首都キエフに対する砲撃は続き、南東部マリウポリでは爆撃を受けた建物で生存者の救出作業が続けられた。 双方の当局者はこの日も和平交渉を行ったが、依然として立場に隔たりがあるとした。 こうした中、ブリンケン米国務長官は「ロシアがウクライナで使用する軍事装備品の直接支援を中国が検討している」と懸念を示した。 また、バイデン米大統領が2022年3月18日に行う中国の習近平国家主席との電話会談で、中国が「ロシアの侵攻を支援すれば責任を負うことになり、米国は代償を科すことをためらわないと明確にする」と述べた。 <大きな隔たり> ロシアとウクライナは4日連続で停戦交渉を行ったが、ロシア側は合意に至っていないと説明。ペスコフ大統領報道官は、ロシアは和平合意に向け「多大な」エネルギーを注いでいるものの、ウクライナ側からそのような「熱意」は感じられないと語った。 ウクライナは停戦に向けた交渉の用意があるとしつつも、降伏や最後通告を受け入れる考えはないと強調。ポドリャク大統領顧問は「交渉は複雑だ。当事者のポジションは異なる」と述べた。 欧米の当局者も、ロシアとウクライナは和平交渉に「真剣に取り組んでいる」が、双方の間には依然として「非常に大きな隔たりがある」との認識を示した。 ウクライナのゼレンスキー大統領は、フランスのマクロン大統領と電話協議し、「平和的な対話継続」を双方が強調したとツイッターに投稿。「反戦連合を強化しなければならない」とした。 <ロシア軍の動き停滞> キエフの北東部、北西部の郊外は大きな被害を受けているものの、市内は攻撃に耐えている。 ウクライナ国防省報道官は、キエフ周辺のロシア軍はここ24─48時間で大きく前進しておらず、「無秩序」な砲撃に出ていると述べた。 英国防省の情報当局は、ロシア軍の動きがここ数日、陸・海・空の全てでほぼ止まっているとの見解を示した。ロシア軍は甚大な損失を被り、ほとんど前進していないという。 北部チェルニヒウでは、米国人がロシア軍の銃撃を受けて死亡したことが分かった。親族によると、パンを求めて列に並んでいたところ、ロシア軍の狙撃兵に射殺されたという。地元当局者は、過去24時間で53人の民間人が殺害されたとしている。 マリウポリでは、16日に爆撃を受けた劇場で生存者の救出作業が続けられた。この劇場には数百人の住民が避難していた。市当局は死傷者の数を特定できていない。ロシアは劇場への攻撃を否定している。 世界保健機関(WHO)は17日、ウクライナの医療施設に対する43回の攻撃を確認したとし、12人が死亡、数十人が負傷したと明らかにした。 テドロス事務局長は国連安全保障理事会で「いかなる紛争でも、医療施設への攻撃は国際人道法違反だ」と述べた。 国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)は、ウクライナでこれまでに民間人780人が死亡、1252人が負傷したと明らかにした。 近隣の国に避難した民間人は約320万人となった。 ウクライナ当局者によると、人道回廊を通じて17日に避難した人は3810人で、前日の6万人超を大幅に下回った。 私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」
 |
| 中国の王毅(ワン・イー)外相 |
アメリカをはじめとする西側諸国はタリバンに対し、女性やマイノリティーなどの人権保障や包括的政府の樹立を要請してきた。それらの条件が満たされなければタリバン政権を承認しないという立場だ。しかしタリバンと外交関係を結ぶ国が増え始めたことにより、国際社会の足並みは顕著に乱れている。 中国の王毅(ワン・イー)外相は3月末、タリバン政権について「情勢の安定や人権の保障などに努め、一定の成果を収めた」と評価した。しかし現実は異なる。ニューヨーク・タイムズ紙は4月、タリバンの政権掌握から6カ月間に約500人の前政府関係者とアフガン治安部隊のメンバーが殺害されたか、もしくは失踪したと報じた。 ■自ら暴力に手を染めている
 |
| こんな人間が存在していることが、 こんな人間が歴史上の人物になって いることが、とても嫌だ。 しかも同時代を一緒になって生きているのだから、 とてもつらい。 生きているものすべてに、いじめることを許容しているように思える。 母性本能をくすぐる人たらし野郎、 サイコパスの目でロシアをろくでなし国家にした野郎、 と憎しみを持つ人も多いだろう。 しかし、メディアでこいつと付き合い、 目にする毎日がつらい日々だ。 |
ボロネンコフはロシア元下院議員イリヤ・ポノマレフに会いに行くところを襲撃された模様だ。ポノマレフは、ロシアのクリミア併合をめぐるロシア下院の採決で反対票を投じた人物。ボロネンコフは当時採決で賛成票を投じたため、彼の亡命を受け入れるという政府の決定には国民の不満もあった。 ポノマレフはフェイスブックにこう投稿した。「言葉が出ない。誰が殺したかは明白だ。ボロネンコは、ロシア当局にとって危険な追及者だったということだ」 ボロネンコフのボディガードは銃撃戦で負傷、容疑者も撃たれて病院で死亡した。 「プーチン直属の露特殊部隊の手口」 事件後、ウクライナとロシアは一斉に非難の応酬を繰り広げた。ウクライナのペトロ・ポロシェンコ大統領は声明を発表した。「キエフの中心部でデニス・ボロネンコフが暗殺されたのは、政治的な理由で彼を亡命に追い込んだロシアによる国家テロだ」。殺害の手口は「ロシア特殊部隊の教科書通り」と批判したうえで、こう続けた。「ロシアによるウクライナ戦争や、ロシア軍の侵攻でビクトル・ヤヌコビッチが果たした役割について、ボロネンコフは重要な証人の1人だった」 【参考記事】ロシアの野党指導者ナワリヌイ、大統領選立候補困難に ウクライナ内務省のアルテム・シェフチェンコ報道官は、警察当局に対して暗殺事件として捜査開始を命じたことを明らかにして言った。「今回の殺害で得をするのは、まちがいなくロシアだ」 ボロネンコ自身、ロシアから何らかの報復を受けることは覚悟していた。殺害の数日前、米紙ワシントン・ポストのインタビューで彼はこう発言した。「私たち夫婦はロシア国内で危険人物に仕立て上げられている。いつか許される日がくるとは思えない」
 日本の経済安全保障 【5つの重点施策】 この小項目1つ1つが、今後の日本の国家としての浮き沈みに関係してくる。日本の政治家の国際感覚が貧しいことを利用して、中国や韓国が日本にお金を出すので「日本の技術や人材」をよろしくね!と言われても簡単には契約しないことだ。日本の工業に限れば、経済が低成長でも日本国内に工場さえあればなんとかなる。 今まをでのように中国、韓国などへ日本の製鉄技術や軍事技術を簡単に日本国外へ 流出させてはならない。中国では全権法で特許権とか外資関係の約束事も関係なく、技術を盗むようにして自国技術として世界にアピールして信用させて売っていくつもりだ。 毎年、防衛費だけはGDPの1%を超えて2%に近づけて行くけれども、 予算の配分を、本気で考えるなら、この5大項目に多くの予算を付けてほしい。 終戦まで約40年間、日本が統治した南樺太(現ロシア・サハリン)からの引き揚げ者らでつくる「全国樺太連盟」が3月末に解散し、73年間の歴史に幕を閉じる。会員の平均年齢が84歳を超え、会員数も減少し、歴史を継承する取り組みが難しくなったのが理由だ。 南樺太では1945年の終戦間際に参戦した旧ソ連との間で、1945年8月15日以降も戦闘が続いた。真岡(現ホルムスク)では1945年8月20日、旧ソ連の軍艦が迫る中、女性電話交換手9人が服毒自殺。終戦がとうに過ぎた1945年8月22日には引き揚げ船3隻が北海道沖で相次いでロシア潜水艦の攻撃を受け、約1700人が亡くなる「三船遭難事件」が起きた。 全国樺太連盟は48年4月にできた。当初の課題は、現地に残された人の帰還促進や引き揚げ者の生活の援護。その後、三船遭難事件の合同慰霊碑建設などの慰霊事業のほか、樺太での生活や戦争体験を語り継ぐ活動をしてきた。 一方、会員は1994年度の約6300人をピークに減り、現在は960人余りに。高齢化も進み、活動の続行は困難だとして昨年、正式に解散を決めた。 戦後に樺太・豊原(現ユジノサハリンスク)で生まれた常務理事の辻力さん(74)は「樺太史を残す努力を精いっぱいしてきたが、まだ足りないという思いは残っています」と話す。 遺骨発見まであと一歩のところで 1945年8月22日、樺太の中心都市・豊原(現ユジノサハリンスク)は空襲に見舞われた。日本人100人以上が亡くなったと言われるが、正確な人数を含む全容はわかっていない。犠牲者が埋葬された場所を探し、遺骨を見つけ出す――。全国樺太連盟は、そんな取り組みをしてきた。 豊原出身の連盟会員で札幌市在住の郷土史家、尾形芳秀さん(83)は2017年10月、連盟北海道事務所長の森川利一(としいち)さん(91)とともにユジノサハリンスクに渡った。個人で十数年調べた豊原空襲の犠牲者の埋葬場所を大筋で突き止め、連盟の事業として掘り起こすことになったためだ。 埋葬地と推定したのは、郊外にある精神科病院の西南側境界付近。事前の交渉で鉄柵の外側に限って探索が認められた。現地の団体に依頼して計7日間、2~3メートルの深さまでのボーリングを約200カ所、パワーショベルによる掘削を約70カ所で行ったが、遺骨は見つけられなかった 裏で進むロシア、韓国の共同事業も忘れてはいけない。韓露の合弁事業を択捉島でやろうとしている韓国もそうだが欧米のように「人権を柱の中心にした民主革命」から民主主義になった国ではなく、真似した民主主義の国だから考え方だけ社会主義に転んでも不思議ではない。 | |||||
 明治以来、日本の重工業を支え続けた八幡製鉄所の技術者たち! 日中共同の製鉄プラント事業 中国近代化にODA供与 (日本国際貿易促進協会 相談役) 1980年代になると、日中関係は政治・経済両面で最良の時代となった。それを象徴するのが対中ODA(政府開発援助)である。1979年9月、当協会創立25周年の式典参加のために来日した谷牧副総理一行は日本政府との会談で第一次円借款の供与で合意した。 日本側は中国側代表団に対して、記者会見の場で「感謝の意」を表明するよう要求したが、谷牧氏は「そんなことをすれば私は帰国できない」と言って拒否したという。国交正常化時に国家賠償請求を放棄した中国にとって、日本からの借款に対し「感謝」すれば、中国の国民感情を逆撫でする。このことを日本側は考慮しなかったのだろうか。 その後日本政府の対中円借款は、2007年に終了するまで28年間にわたり合計約3兆円が供与された。鉄道、港湾、発電所、通信などのインフラ建設にこの資金が投入され、中国経済の近代化に大きく貢献した。最近になって中国政府要人は公式の場で中国の近代化に対する日本政府の協力に感謝の言葉を表明するようになった。 宝山での日中協力 この時代を象徴するもう一つのプロジェクトが上海宝山製鉄所建設での日中協力である。日本の新日本製鉄の全面的協力の下で、輸入鉄鉱石を使用する臨海製鉄所を上海に建設することが合意され、1978年12月に着工した。このプロジェクトの経緯は山崎豊子氏によって「大地の子」として小説化された。完成までには紆余曲折があったが、上海宝山製鉄所は中国の主力製鉄所として順調に発展していることは周知の通りである。 突然のプラント契約中止 1980年代の最大の困難は1981年に発生したプラント輸入契約の中止問題であった。中国は建国以来一貫してプラント輸入を重視してきた。建国初期はソ連東欧から156項目のプラントを導入し、機械工業などの基礎を築いた。1970年代、特に文化大革命が終わった1976年以後は、日本を含む西側諸国から機械、化学などの分野で多数のプラントを輸入する契約を締結した。ところが外貨の資金繰りがつかず、1980年の年末になり中国は突然すべてのプラント輸入契約の中止を通告してきた。関係諸国は困惑し、中国の国際的信用は急落した。契約当事者であった中国技術輸入総公司の某副総経理が自殺するという悲劇も起こった。 日本政府は円借款とは別に商品借款を供与し、日本政府は中国の資金不足の解決に協力した。結果的にはほとんどの契約は数年以内に復活した。しかしこの問題以後、中国は大規模なプラント輸入はやらなくなり、もっぱら外国企業の対中直接投資の導入に力を入れるようになった。 耳を疑う「中外合弁」の提案 1978年8月、日中平和友好条約が締結され、復活した鄧小平副総理がその批准書交換のため10月に来日した。鄧氏の復活で予想された中国の路線転換は、同年12月の中国共産党第11期3中全会で改革・開放政策が決定され、現実のものになった。 当協会は10月から12月にかけて中国機械工業代表団一行19人を受け入れ、私は全日程を随行した。団長は第一機械工業部の周建南副部長(現中国人民銀行周小川行長の父)であり、筆頭団員として中国機械設備進出口総公司の賈慶林総経理(現全国政治協商会議主席)が加わっていた。同団が日立製作所の日立工場を参観した時に、周団長が日立の吉山博吉社長(当協会副会長)に「中国に投資して、合弁事業をやってほしい」と依頼した。 周団長の発言は3中全会で党の正式決定がなされる直前であったが、個別の対外交渉で合弁提案をすることは党中央の了承を得ていたものと思われる。自力更生を旨とし、内債も外債もなく、資本主義国との経済関係は貿易のみにとどめてきた中国。その高官が日本の大企業に対して合弁会社設立を提案するとは、正に晴天の霹靂であった。一瞬、聞き間違いではないかと耳を疑った。吉山社長は周団長の要請をしっかりと受け止めた。2年後に製造業における日中合弁事業第1号となる福日テレビ(カラーテレビ製造)が福州に誕生した。 自分は技術移転に注力 翌1979年1月1日には米中両国の国交が樹立された。同年7月、中国は中外合弁経営企業法を制定公布した。中国が対外経済関係において、商品貿易、プラント導入、技術導入に加え、外資導入に踏み切り、そのための法整備を開始した。これ以降中国は外資導入を柱とする対外経済政策を30年以上ゆるぎなく実行し、今や「世界の工場」、「世界の市場」として、世界第二の「経済大国」になった。私はそのスタートに立ち会ったことになる。 当協会は事務局内にいち早く「合弁推進グループ」を設置し、日中合弁企業設立を促進した。当協会は地下足袋メーカーである力王が江蘇省南通市で合弁事業を立ち上げるプロジェクトに全面的に協力し、成功に導いた。福日テレビとほぼ同時期であった。 私自身は日本の経済が外資導入ではなく、技術導入とその消化・吸収・革新によって発展してきた経験から、「中国も技術導入を主とすべきだ」との考えを持っていた。そのため、1980年代の前半は合弁促進には力を入れず、引き続き対中技術輸出に努力した。しかし1990年代に入ると、対中直接投資が日中経済関係の主流になった。 今世紀に入って中国は「創新型社会」の建設や「自主ブランド」の確立を重視するようになったが、その前途はかなり険しいと感じる。 倍々ゲームで拡大した日中貿易 1949年に新中国が成立してから1972年の国交正常化までの民間貿易の時代に、23年をかけて日中貿易額はやっと9億ドルに達しただけであった。ところが正常化後は、72年11億ドル、73年20億ドル、74年33億ドル、75年38億ドルと毎年ほぼ倍々ゲームで貿易が拡大した。 政治関係の正常化があってはじめて経済交流は発展するという「政経不可分の原則」がみごとに実証されたと言えよう。中国向けプラント(生産設備一式)輸出に対する日本輸出入銀行の融資が適用されるようになった。身近なことで言えば、ビザが東京で取得できるようになり、訪中する毎に一次使用のパスポートを取得する必要がなくなり、通常のパスポートが使えるようになった。 貿易が増大した具体的な原因の一つは、国交正常化により日本側の貿易の担い手が一気に拡大したことにある。限られた企業がさまざまなリスクに立ち向かいながら日中貿易に取り組んでいた正常化以前と異なり、全ての日本企業が対中貿易事業に参入することが可能になった。 商社をはじめとする日本企業が相次いで北京事務所を設立するようになり、商談の場は広州交易会から次第に北京へ移行していった。また、米中関係の好転に伴い、それまで使われることのなかった米ドルが決済通貨として使われるようになった。 主役は鉄鋼、機械と原油 貿易上特筆すべきことがある。74年4月に大慶原油の輸入が始まったことである。中国が戦略物資ともいえる原油の対日輸出に踏み切ったのも国交正常化の結果であった。当協会が組織した日本中国石油輸入協議会及び国際石油の2窓口を通じて、年間1000万トンを超える中国原油が輸入されるようになり、対中輸入の最大品目になった。 1970年代に日中貿易を押し上げたもう一つの分野はプラント輸出である。文化大革命により停滞した工業生産能力を拡大するために、中国は日本はじめ欧米諸国から各種プラントを積極的に輸入する政策を実行した。72年から76年にかけて日本からは化学繊維、火力発電、エチレン、ポリエチレン、アンモニア等のプラントが相次いで輸出された。 1978年の日中貿易額は50.8億ドルとなった。輸出30.5億ドルのうち鉄鋼、機械、化学品がそれぞれ54.1%、20.8%、14.6%を占め、輸入20.3億ドルのうち原油は37.4%、食料品16.6%、繊維及び繊維製品15.7%という構成であった。 宿願の国交正常化実現 1972年2月のニクソン訪中後、日本政府は急速に対中交渉を進め、半年後の同年9月29日には日中国交正常化が実現した。翌年2月、中国の駐日大使館仮事務所が東京のホテルニューオータニに開設された。アメリカが首脳訪中後6年かけて実務交渉を積み重ね、1978年末になってはじめて国交樹立にこぎつけたのと大きな違いである。 1950年の朝鮮戦争勃発以後、東西冷戦構造の中で全面的対立を続けてきた米中間には民間経済交流の歴史が皆無であった。これに対し、日中間には民間貿易の経験が蓄積されており、日本の経済界は突然訪れた日中国交正常化にすぐさま対応することができた。 当協会は日中国交正常化直前の1972年8月に行われた三菱グループ訪中団(団長=田実渉三菱銀行会長)や日本経済人訪中団(団長=稲山嘉寛新日本製鉄会長)の派遣に協力した。 来日相次ぐ中国の技術視察団 当協会の仕事も急激に拡大した。従来から貿易の窓口であった各輸出入総公司が日本で商談を行う貿易団を派遣してきたが、それ以外に国交正常化まで往来が極めて少なかった中国の各工業部門が派遣する技術視察団の来日が急増した。技術視察団はいずれも買い付けのための事前調査であったから、日本の関係企業から大いに歓迎された。正常化の翌年1973年に当協会が受け入れた技術視察団を当協会の「国際貿易」紙から拾ってみると、工作機械、合成ゴム、電子技術、鉄道技術、食品機械等となっている。まるで「工業は日本に学べ」といわんばかりの勢いであった。 当時の来日団の受け入れ方式は、団が来日してから帰国するまで全面随行であった。同じホテルに泊まりこみ、全訪問先に案内し、日本側受け入れ先の通訳も担当するいわば「三同(同喫、同住、同工作)」というハードなものであった。私は1973年に結婚したが、この年には年間200日前後も家を留守にしたと思う。視察団のメンバーは極めてまじめで、熱心に視察や説明の内容をメモし、夜はホテルでミーティングを行い、視察結果について整理確認するという作風であった。私は通訳者として粛然たる気持ちをいだき、団側の通訳や専門家の助けを借りながら、とにかく正確第一を心がけた。 正月に自宅へ招待 1973年10月から74年1月にかけて中国機械進出口総公司貿易小組(団長=黄文元第3進口部経理)一行11人が中古の建設機械と作業船の買い付けのために来日し、日本で越年した。元旦に当協会の受け入れスタッフは手分けして彼らを自宅に招待した。私は団員の李天相工程師等3人を6畳1間のアパートに案内し、すき焼きを食べてもらった。「日本人の家庭を初めて訪問した」と大変喜んでくれた。こんな交流ができたのも国交正常化の賜物であった。 日本工業展覧会の役割 国交未回復の中で、1950年代には日中民間貿易協定が第1次(1952年)から第4次(1958年)まで締結された。1958年~1960年の日中貿易全面中断を経て、60年代に入ると日中貿易は友好貿易とLT貿易(注)の2ルートで行われるようになり、「車の両輪」と言われた。 商品の実物を見ることは売買双方にとって必要不可欠である。当協会は中国で日本の工業製品を展示し、展覧会終了後それを売却するという活動を実施した。最初は1956年10~12月の北京上海日本商品展覧会であり、北京では125万人が入場した。毛主席も会場を訪れ、「看了日本展覧会、覚得很好、祝賀日本人民的成功」と揮毫した。その後、58年武漢広州日本商品展覧会、63年北京上海日本工業展覧会、65年北京上海日本工業展覧会、67年天津日本科学機器展覧会と継続した。 私が協会に入った翌年の69年3月には日本工業展覧会が北京で開催された。しかし上海会場は展示品に対する日本政府のココム規制(出品不許可、持ち帰り条件付き許可)に抗議して中止した。当時の厳しい雰囲気を今でも思い出す。 中国展では経済発展を宣伝 一方、中国側も中国国際貿易促進委員会が主催する展覧会を日本で開催した。1955年中国商品見本市(東京・大阪)、64年中国経済貿易展覧会(東京・大阪)、66年同(北九州・名古屋)である。いずれも100万~200万人が入場した。国交正常化以後の1974年(大阪、東京)と1977年(北九州)にも開催された。当時の中国は社会主義計画経済の時代、輸出商品は農産物、原材料、軽工業製品が中心であり、展覧会も商品見本市というより中国の経済発展情況を宣伝し、中日友好を強化するためのものといった色彩が強かった。 中国が国連の議席回復 アメリカのベトナム戦争、中ソ対立の激化、中国の文化大革命といった国際情勢の下で、貿易業界の宿願である日中国交正常化はまだまだ遠い将来のことだと思われていた1971年、新しい風が吹いてきた。10月25日、国連総会においてアルバニア等23カ国による「中国招請・台湾追放」提案が圧倒的多数で可決され、中国の国連議席回復が実現した。それに先立つ3月下旬に名古屋で開催された第31回世界卓球選手権大会に中国が6年ぶりに参加し、大会後アメリカ選手団等が訪中した。いわゆるピンポン外交である。これを契機に中米政府の秘密交渉が加速され、キッシンジャー大統領補佐官が秘密訪中し、翌1972年2月にはニクソン大統領が北京を訪問した。私は入院していた病院のテレビで毛沢東-ニクソン会談を見て、なんとも言えない複雑な思いをした。 国交未回復、文化大革命といった政治情勢の下で、広州交易会は単なる貿易商談の場ではなく、関連の対外経済交流の舞台でもあった。交易会の開催期間にその会場を利用して「日中技術交流」も行われた。まだ対中輸出実績のない新製品について、メーカーの技術者が交易会参加という形式で訪中し、交易会会場や付近のホテルの会議室を使い、約1週間の日程で中国側が組織する技術者グループに対して、性能や使用方法等を説明し、質疑応答を行うというやり方であった。 当協会等が日本企業の紹介希望新製品リストを取りまとめ、中国国際貿易促進委員会技術交流部に提出し、中国側がその中から実施項目を10項目程度選び通知してくる。それを受けて、各メーカーの技術者たちがまとまって交易会に参加する。その世話係が私の初訪中の仕事であった。 黄坤益先生との出会い 中国国際貿易促進委員会技術交流部からは黄坤益先生(後に国家専利局局長、専利とは日本の特許のこと)がまとめ役として広州に来ていた。黄先生は少しも傲慢なところがなく、年若い私に対しても謙虚な態度で対応し、仕事以外の雑談の中では「毛沢東選集」を読むように静かに勧めてくれた。夫人は医者であり、当時「裸足の医者」として河北省の農村部で巡回医療に従事していた。選集の中からの引用集である「毛沢東語録」を朗読することが商談開始への通過儀礼という雰囲気の中で、黄先生は一味違う風格であった。初めての訪中で黄先生と知り合ったことが、その後長く中国と付き合う私のエネルギーの元になったような気がする。後に当協会が知的財産権分野で中国と交流を行うようになった時、黄先生は国家専利局局長として当協会の活動を支持してくれた。 1971年の日中貿易額は9億ドル 会期1カ月の広州交易会が閉幕すると参加者は北京行きを申請する。申請者全員が認められるのではなく、必要性に応じて中国側が選定する。認められて北京に行く商社員は「北上組」と呼ばれていた。彼(彼女)たちは次の交易会まで半年間北京の「新僑飯店」に滞在して、北京の各総公司と継続や新規の商談を行う。次の交易会で新しい北上組が決まり北京にやってくると交代して日本に帰るというローテーションであった。 こうした情況の下で、日中貿易額は国交正常化直前の1971年でもわずかに8.9億ドル。日本の主要輸出品は化学品、繊維品、鉄鋼、機械等であり、主要輸入品は食料品、油脂原料(大豆)、繊維原料等であった。工業製品を輸出し、原料を輸入するという構造であった。 (注)1962年に結ばれた「日中長期総合貿易に関する覚書」に基づき始められた半官半民的な貿易形態。双方の代表者の廖承志(Liao Chengzhi)氏と高碕達之助氏の頭文字LとTをとってLT貿易と称された。1968年以後、名称は覚書貿易(Memorandum Trade)の英文頭文字をとってMT貿易に改められた。 片寄浩紀 日本国際貿易促進協会 相談役 2021年6月23日 クリミア半島沖合でイギリスの艦隊が、国際法に乗っ取って航行中、ロシアの砲撃に会う 北方領土問題: ロシアによる北方領土進出企業への税優遇は遺憾=官房長官 2022年 3月 10日 12:30 PM JST [東京 2022年 3月 10日 ロイター] - 松野博一官房長官は2022年 3月 10日午前の会見で、ロシアが北方領土に進出する企業に対して税制の優遇措置を設けたことは「遺憾」であり、改めて日本の立場をロシア側に申し入れたと語った。 北方領土(北方四島、ロシア名クリル諸島)は、日本が領有権を主張し、ロシアが実効支配している。 ロシアの新制度では、北方領土を含む島の税制について、ロシア政府の登録を受けた企業に法人税や固定資産税など最大20年間の優遇措置を設けるなどとしている。松野長官は「北方4島に対する日本の立場や、首脳間の合意に基づき日ロ間で議論してきた北方4島における共同経済活動の主旨と相容れない」と述べた。 ロシアのプーチン大統領は2022年 3月9日、ロシアが実効支配する北方領土に免税特区を創設するための法案に署名し、同法は成立した。進出する内外企業に対し、20年間にわたって税優遇措置を適用する。 プーチン氏は昨年9月、クリール諸島(北方領土と千島列島)に法人税などを減免する特区を創設する計画を一方的に発表。日本政府は特区計画は領土問題をめぐる日本の立場と相いれないとして抗議していたが、ロシアはこれを無視した。法案は今月4日に上下両院で可決されていた。 ウクライナのクレバ外相は2022年 3月9日、ロシア軍が占拠しているチェルノブイリ原子力発電所の電源が喪失したと明らかにした。これに関連し松野長官は「先に行われたザポロジエ原発への攻撃を含め、原子力施設に対するロシアの一連の行為を強く非難する」と語り、ロシアに対して同様の行為を即座に停止するよう強く求めた。 <穀物価格、情報の収集・分析進める> 農林水産省が2022年 3月9日発表した今年4月期の輸入小麦の政府売渡価格が昨年10月期から17%上昇し、2008年10月期以来の高水準となるなど、足元で穀物価格の上昇が国民生活に与える影響が懸念されている。 松野長官は、日本ではロシアとウクライナから穀物の輸入はほとんどないが、国際価格や貿易の動向に関する情報の収集・分析を進めると述べた。貿易などで影響を受ける可能性がある農林水産業や食品関連産業の事業者に向けた相談窓口を農水省に設置し、資金繰り支援などの情報発信を強化したという。 一方、アラブ首長国連邦(UAE)のアルオタイバ駐米大使は2022年 3月9日、UAEは原油増産を支持しているとし、石油輸出国機構(OPEC)に検討するよう働き掛けると述べた。松野長官はこの声明を「承知している」とし、次回のOPECプラス閣僚会合で国際原油市場の安定に向けた議論が行われることに期待を示した。2022年 3月10日開催予定の主要7カ国(G7)臨時エネルギー大臣会合においても、エネルギー市場の安定化に向け、各国と連携していきたいと語った。 ロシアによるウクライナ侵攻を受け、政府は北方領土を説明する際の表現を変えた。安倍晋三政権時代に使用を控えるようになった「固有の領土」や「不法占拠」といった文言を復活させた。ロシアとの平和条約交渉の前進が難しくなり、原則的な立場に回帰した。 岸田文雄現首相は2022年 3月10日、国会内で安倍元首相と20分ほど会い、ウクライナ情勢について意見交換した。 (杉山健太郎 編集:田中志保) 欧米諸国の議会で積極的にオンライン演説を行うウクライナのゼレンスキー大統領(44才)が、2022年3月23日、日本の国会でも支援やロシアへの経済制裁強化を訴えた。圧倒的な軍事力を誇るロシア軍に徹底抗戦を誓うゼレンスキー氏の姿は、日本人の胸を打った。 《ウクライナを救うための活動をもっとしよう》 《ロシアへの経済制裁をもっと強めよう》 そんな声が日本でもあふれている。だがこの演説が、大きなリスクを招きかねないとの見方を示す専門家もいる。 ゼレンスキー氏はこれまでイギリス議会での演説を皮切りに、カナダ、アメリカ、ドイツとNATO加盟国を中心に演説を行ってきた。加盟国以外で演説の場を設けたのはイスラエルに次いで2国目だ。ロシアのプーチン大統領(69才)研究の第一人者で、筑波大学教授の中村逸郎さんは、この点を危惧する。 「プーチン氏から見れば、日本は戦闘中の敵国の大統領に国会で演説させたわけで、ゼレンスキー氏を讃えていると捉えられかねません。 現在、経済制裁によってロシアのスーパーからは食料品や日用雑貨が姿を消すなど、日に日に市民生活が厳しくなっています。かつてないほど苛烈な経済制裁を科した西側諸国に、プーチン氏は怒り心頭。日本はその一員と見られ、怒りの矛先は確実に日本にも向いているのに、演説はその火に油を注ぐことになるでしょう」 ゼレンスキー氏の国会演説前から、ロシアにとって日本は“要注意国”の1つになっていた。3月7日、ロシアは自国への経済制裁を行う「非友好国リスト」を公表。アメリカ、EU全加盟国などとともに日本も含まれた。 その翌日、日本政府はウクライナの要請に基づき、防弾チョッキのほか、ヘルメットや防寒服など防衛装備品の提供に踏み切った。こうした装備の海外移転は、本来は「防衛装備移転三原則」により規制されるものだが、政府は運用方針を変更してウクライナに無償供与することを決めた。 「日本政府の対応を受けてか、プーチン氏はすぐに日本に向けて動きをみせました。3月10日、北方領土の択捉島でミサイルを使った軍事演習を始めた。11日にはロシア海軍の艦艇10隻が津軽海峡を通過して、15日にも4隻が通過しました。ウクライナに向けて兵士や武器を輸送しているようですが、日本への威嚇も兼ねているとみられています」(中村逸郎さん) さらには、ゼレンスキー氏による国会演説の2日前の21日、ロシア外務省は、日本との平和条約締結交渉を中断すると発表。北方領土への旧島民の墓参りなどを目的とした日本とのビザなし交流の停止や、北方領土での日本側との共同経済活動に関する協議から撤退する意向を表明した。 「ロシアは非常に強い圧力を日本に加え始めています。プーチン氏から見れば、同じ“隣国”でも日本はウクライナより格段に攻めやすい。もはや日本はロシアの敵対国とみなされている」(中村さん) 一部では想定外の苦戦を強いられるウクライナを諦め、“代償”として北海道に侵攻する可能性を指摘する専門家もいる。 日本とウクライナには、ある共通点がある。ロシアは2014年のクリミア併合の際、「ロシア系住民の保護」を理由にロシア軍投入を決断。結果的に併合した歴史がある。だが、ウクライナや西側諸国はクリミア併合を違法とみなしており、承認していない。 日露間にも未解決の北方領土問題が1945年から横たわる。「隣の軍事大国が自国の領土を実効支配している」という地政学的なリスクは、ウクライナと変わらないのだ。 「2018年12月、モスクワで開かれた人権評議会で、プーチン氏は『アイヌ民族をロシアの先住民族に認定する』という考えを示しました。アイヌ民族の保護を名目にロシア軍が北海道に侵攻する、というリスクは、プーチン氏のこれまでの手口からして、まったくあり得ない話と簡単に切り捨てられないでしょう」(国際ジャーナリスト) ※女性セブン2022年4月7・14日号 人たらし、プーチン 「彼はとにかく人たらしとして知られています」 「彼」とはウクライナに侵攻し、世界中から批判の嵐に晒されているロシアのプーチン大統領のことだ。元産経新聞モスクワ支局長の佐々木正明氏はプーチンについて、こう続けた。 「例えば、プーチンは様々な行事に遅刻することで有名で、大事な要人との会談にも遅れてきます。2014年の森喜朗元首相との会談では3時間半遅刻し、2016年に来日し当時の安倍首相と会談した際にも、約2時間半遅刻してきました。 プーチンは会談の場に姿を現すと、即座に首相や官僚など全ての関係者、1人1人の目を見て、両手でガッチリと握手をします。しかも、その握手は一瞬ではなく数秒続き、長い。握手の後、会談の場はプーチンに友好的な雰囲気へと一気に変わってしまうと外交関係者から聞いたことがあります」 待たせた後の固い握手。“アメとムチ”を使い分ける彼の演出力の高さに、各国の政治指導者も“騙されてきた”部分があるようだ。 国民からの公開質問に“チャーミング”に回答 政府関係者のみならず、ロシア国民にとってもプーチン大統領は“魅力的な男”であり続けてきた。“兄弟国”ウクライナへの侵攻にロシア国内では反戦運動が繰り広げられているが、ロシアの独立系機関「レバダ・センター」が2月頃に行った調査では、プーチン政権への支持率は69%。12月の調査から4%上昇するなど依然、高水準なのはその証左だろう。 モスクワに住む日本人男性は、プーチン大統領の人心掌握の巧みさを、こう証言する。 「国外から見える姿と異なり、意外にも、ロシア国民にとってプーチンは親しみやすい印象があるのです。例えば、年1回の恒例テレビ番組『プーチン・ホットライン』。これはプーチン大統領がスタジオに生出演し、100個近い視聴者の質問に、約4時間かけて本人が答える番組でした。 質問の中身はさまざま。政治的な質問だけではなく、プーチンのプライベートへの質問や、国民の人生相談にも答えます。初体験の年齢を聞かれ、プーチンが『覚えていない。でも最後にした時のことは覚えているよ。何時何分かも正確にね』と笑顔で答える一幕もありました」 番組内では、プーチン大統領の“頼れる兄貴ぶり”がいかんなく発揮されたという。 「ある質問者は『地元の道路が整備されていなく、自転車に乗ることもできない。町の責任者に頼んでも対応してくれない』と相談。するとプーチンは『それは深刻な問題だ』といい、番組中に町の幹部と電話し、『道路を修繕させる』と約束させました。 他にも、田舎に住む質問者からガスが通っていないことを相談されると、すぐにガス会社に連絡してパイプラインを通すことを確約。その強権で、住民を長年悩ませてきた問題が一夜で解決してしまうのです」(同前) 国民からの要望に「5日で新列車を走らせた」 プーチンが国民に“魅力”をアピールするのは、そういった番組だけではない。記者会見でも、都市部だけでなくロシア全土に寄り添う姿勢を見せつけてきた。 「昨年12月の記者会見では、地元紙記者から『地方都市ヨシュカルオラから、大都市のサンクトペテルブルクまで乗り換えなしで行けないのはなぜか』と質問され、調査を約束。そのわずか5日後、本当にサンクトペテルブルク行きの直通夜行列車が開通してしまいました。これは日本でも、昨年12月31日に共同通信が『ロシア大統領「鶴の一声」健在 5日で新列車走らせる』と驚きをもって伝えています」(同前) プーチンは「強面だが実はフレンドリーで頼れる」というイメージ戦略をとってきたようだ。その演出に一役買っているのがスポーツだ。ロシアに詳しい日本人ジャーナリストが話す。 「黒海沿岸にあり、総工費1400億円とも言われる“プーチン宮殿”は、山手線の内側を超える広大な敷地面積を誇り、ジムにプール、アイスホッケー場、柔道場まであります。彼はスポーツが大好き。体を鍛え、筋肉質な肉体を披露するのは、衰え知らずの印象を演出するためでしょう。 彼は幼少期から格闘技に熱中し、柔道やサンボ(ロシアの護身術)も得意。2000年に来日した際には、柔道の総本山である講道館から『黒帯』の上位にあたる『紅白帯』を締められる『講道館柔道6段』を授与されました。日本オリンピック委員会(JOC)会長でもある山下泰裕氏を尊敬しているとされます。出張がなければ毎日プールで1時間半ほどバタフライで泳ぎ、懸垂は今でも15回から17回できると公言しています。 2012年には、大統領就任の式典のわずか数時間後にアイスホッケーの試合に出場し、得点を決めました。ロシアでは、アイスホッケーは人気スポーツの1つ。プーチンはわざわざプロ選手の特訓を受け、数カ月で試合に出られるまで上達しています。また、ウクライナ侵攻直前までは、側近が編集した、北京冬季五輪で活躍するロシア人選手のダイジェスト動画を毎日のように見て喜んでいたそうです」 スポーツ選手が反戦明言「プーチンにとって相当ショック」 しかし、ロシアのスポーツ選手たちは口々に反戦を叫んでいる。プーチン大統領を支持してきたというアイスホッケー選手、アレクサンドル・オベチキン氏もそのうちの1人だ。 「オベチキン氏はこれまでプーチン支持を明言してきました。しかし今回のウクライナ侵攻にあたって、『ロシアにもウクライナにもたくさんの友人がいる。誰かがケガをしたり殺されたりする姿を見たくない』と声明を出しました。他にもテニス世界ランク1位のダニール・メドベージェフ選手やフィギュアスケートのエフゲニア・メドベージェワ選手も反戦を呼びかけています。今回、アスリートが次々に反対を示したのは、プーチンにとって相当ショックだったと思いますね」(同前) 一方、こうした戦略的な“人気とり”の背後で、プーチン大統領は気に入らない人々に対して極めて残忍な仕打ちをし、そしてそれを隠し続けてきた。ウクライナ国営通信「ウクルインフォルム」の平野高志氏は憤慨しながらこう話す。 「今回の戦争は言語道断ですが、2014年のクリミア危機の際にも14000人が殺害されています。武器を捨てて逃げようとする兵士に、後ろから一斉射撃を加えるなど残虐的すぎる行動を取らせたほか、野党の政敵やジャーナリストが相次ぎ不審死しています。確たる証拠は挙がっていませんが、これらはプーチンが指示したとされています。そんな疑惑は数え上げればきりがありません。 ウクライナでは、彼は最大限否定的に受け止められており、新聞の挿絵では耳の尖った姿で描かれるなど、まさに“悪魔”の扱いです。 そもそも、プーチンはウクライナをかなり下に見ています。彼自身が過去、『ウクライナは国家ではない』とか『ウクライナはレーニンが作った人工的なものである』などと発言している通りです」 ゼレンスキー大統領は元々コメディアンだった。 ロシアに徹底抗戦 ゼレンスキー大統領がノーネクタイなワケ 「ロシア側は彼の経歴を『政治にふさわしくない』という文脈でプロパガンダし、国内メディアからも2019年の大統領選で『あんなコメディアンが大統領になっていいのか』と批判の声がありました。ただ今は有事ですし、キエフに残って殺されるかもしれない状況で戦い続ける姿勢が、支持を集めているのだと思います」(同前) ゼレンスキー大統領も、情報戦に長けた政治家のようだ。彼が政界に進出したのは、テレビドラマに出演したことがきっかけだった。国民の民意をくみ取り、出馬のタイミングを見極める力を持っていた。 「ゼレンスキーが出演したドラマは、“政治エリート”に失望した多くの国民を惹きつける内容でした。その中で彼は、政治の素人だった元歴史教師が汚職政治を刷新するという理想的な大統領を演じていました。『あんな人が大統領になったらいいな』という国民の印象が抜けきらないうちに、その後、選挙まであと3カ月というところで急遽、立候補したのです。今でもニュース映像では、ノーネクタイ姿ですが、これは『できるだけ国民と同じ目線でいよう』という彼なりのこだわりを示しているのでしょう」(同前) しかし、政治家としての手腕や評判は、これまでプーチン大統領の足元にも及ばなかった。 「外交や国防に詳しい人からは、彼の大統領就任は危険視されていました。彼はプーチン相手に“対話路線”を主張していましたが、プーチンは対話にのってこなかった。1度、メルケル独前首相やマクロン仏大統領の仲介で会談しましたが、国内からは『プーチンと1対1での対話はやめた方がいい』『政治家として上手のプーチンに言いくるめられてしまう』と懸念する声が多かった」(同前) しかし、ゼレンスキー大統領は、その後努力を重ねてきた。 「ゼレンスキーはウクライナ語が苦手でした。ロシア語話者が多い地域に生まれたため、プライベートや、出演していたテレビ番組や舞台では全てロシア語でしたよ。『大統領になった時にウクライナ語を喋れるように最近頑張っている』とテレビで話していたこともあります。そのほかに専門家たちから教えを請い、大統領として“猛勉強”をしてきました」(同前) その勉強の成果もあったのだろうか。ゼレンスキー大統領はややもすると理想的すぎる対話路線から、徐々に多角的な戦略を立てて未来を見据え始めた。 プーチン大統領は「狂った」のか、それとも… 「専門家らの助言を受け、NATOへの加盟や軍備増強の準備を進めました。21年、22年にドイツとフランスを交えた4者会談を開きたいと訴えるなど『対話路線』は続けつつも、うまくいかない可能性も考慮し始めたのです。その頃には就任当初の“素人感”が消え、見違えるほど政治家として成長していましたね」(同前) 人々の声に耳を傾け、現在は大国ロシアに必死の抗戦を続ける。ゼレンスキー大統領への支持はウクライナ国内から広がりをみせ、いま世界中に伝播している。 一方、人心掌握に長けたとされているプーチン大統領は、国際社会を敵に回す暴挙に打って出た。これはプーチン大統領が「狂った」からか、はたまたこれまでの策略の延長線上にあるのか――。いずれにせよ、戦争の先行きはいまだ不透明だ。 「非友好国リスト」に指定された国への影響は?ロシア産天然ガス「支払いはルーブルのみ」。プーチン大統領の思惑 2022/3/24 11:27 (JST) ロシアがウクライナに軍事侵攻して2022年3月24日で1カ月が経った。未だ停戦の合意に至らず、泥沼化の様相を呈している。 侵攻を続けるロシア政府は、ロシアに対して経済制裁などを行う国や地域を“非友好国”などと指定し明記している。いわゆる「非友好国リスト」だ。 これらの国と地域に、どんな影響が出ているのか。 「非友好国リスト」に名指しされた国と地域にロシアが取った対応 まず、「非友好国リスト」について振り返る。 ロシア政府は2022年3月7日に公表したリストには、ウクライナをはじめ、アメリカやEU全加盟国、イギリスやカナダ・スイス・日本・韓国・シンガポールなど対ロ制裁に踏み切った国・地域が含まれている。合わせて48の国と地域が対象だ。 リストの公表が報道された翌日の8日には、格付け大手フィッチ・レーティングスがロシアの信用格付けを6段階引き下げた。 制裁措置の影響で、ロシアが「デフォルト(債務不履行)」に近い状態にあると指摘した。 そんな中、ロシア側も対応に出た。 NHKなどによると、プーチン大統領は現地時間の2022年3月23日、ロシアから天然ガスを購入する際の支払いについて、ロシアなどで使われる通貨単位「ルーブル」での支払いしか認めないという方針を示した。 この措置により、値下がりが続く自国の通貨相場を支える狙いがあるとみられる。ブルームバーグ通信によると、プーチン大統領による措置の発表後、ヨーロッパのガスの価格は一時30%余り急騰したという。 日本や欧州諸国での影響は? 財務省が公表している貿易統計を見ると、液化天然ガス(LNG)は日本もロシアから輸入している。日本が輸入するLNGの全体の7〜8%がロシアからのものとなっていて、影響は不可避だ。 日本ガス協会の本荘武宏会長は2022年3月17日に開いた記者会見で、ロシアからのLNGの調達について「今後については、各社が慎重に判断していくものと思っている」と懸念を示した。 現時点では供給に支障はないとしたものの、産経新聞によると、ロシア産が入手できなくなった際の調達の見通しについては「すぐにはなかなか申し上げられない」と代替手段については明言を避けていた。 欧州からは早くも反発の声が出ている。 ブルームバーグ通信によると、ドイツのハーベック経済相は、プーチン大統領が示したルーブルでの支払い要求を「契約違反」と指摘。欧州諸国と対応を協議すると述べたという。 イタリアはドラギ首相の顧問が「ルーブルで支払う意思はない」と明言。その理由は「ロシア制裁の軽減につながる可能性があるため」とし、ロシアへの対抗姿勢を緩めることはない構えを見せている。 〝忘恩の国〟韓国に尋常でない米国の怒り、国営放送で政権の本音が 「対露制裁」は口だけ、国民にウソがバレそうになり慌てた文政権 2022/3/3 ロシア軍によるウクライナ侵攻に関して、米国の韓国に対する非難が、尋常でないレベルに高まっている。 文在寅(ムン・ジェイン)政権が「ロシア制裁」の隊列に、詭弁(きべん)を弄して加わろうとしないことへの「怒りの表明」だ。同時に、韓国大統領選で、「反文政権」の立場が明確な尹錫悦(ユン・ソクヨル)元検事総長への支援として作用することも見逃してはならない。 文大統領(聯合=共同) 米国は、援助した国に裏切られても、露骨には反発を示さない国と思われてきた。 韓国が過去、どれほど米国の「お世話」になってきたかは言うまでもない。それなのに文政権は2017年、中国に「三不の誓い」 (①高高度ミサイル防衛網=THAAD=の追加配備はしない②米国のミサイル防衛=MD=体制に加わらない③日米韓を軍事同盟にしない)をささげた。米国はどれほど怒るかと思われた。が、表向きは何も言わなかった。 ところが、ウクライナ侵攻では、韓国への怒りを露骨に示した。 「忘恩の国」「小心者の国」「恥ずかしい国」…。米政府が公式に言っているのではない。あくまでも退職公務員(=シンクタンクの研究職に就いている元国務省高官など)の発言だ。それをインタビュー形式で伝えたのは、「米国の国営放送」であるVOA(アメリカの声)放送だ。 現職の国務長官や国務省幹部では刺激が強すぎる内容を、「元高官」が「国営放送」で述べた―その内容は「米国政権の本音」と見るべきだ。 文大統領は2022年2月22日、「ウクライナの主権尊重」と公言した。2022年2月24日には外交当局者が「対露制裁に加わる」と述べた。だが、韓国の「国際社会が行う」とは、「国連が行う」という意味であり、国連が関わらない「独自制裁は行わない」としている。 国連は安全保障理事会の常任理事国であるロシアが拒否権を行使するため、何も決められない。つまり、韓国は「対露制裁をする」というが、実は「国連決議は成立しないから、何もしない」という意味なのだ。 韓国外交省は「全面戦争になれば、制裁を実施する」とも補足したが、どこからが全面戦争なのかの説明はない。 米国は2022年2月末、「対露制裁32カ国」のリストを示した。そこに韓国の名はなかった。 文政権は慌てた。韓国国民は「親米派」が圧倒的に多い。文政権支持者の中でも「国防親米派」が多い。そうした国民に見せている「米国とも親密で、対露制裁を進める韓国」というウソがバレてしまうからだ。 文氏は改めて「対露制裁参加」を公言し、米国に伝達した。ただ、韓国外交省は「制裁の具体的中身は、今後、関係省庁で話し合う」と記者団にブリーフした。要は「何も決まっていない」ということだ。 文政権与党の大統領候補、李在明(イ・ジェミョン)元京畿道知事は、ロシアの軍事侵攻を「ウクライナの未熟な外交による」と述べた。日本の左翼野党の一部も、同じような論評をして取り消している。 西側の左翼(=時にリベラル派と自称)の本音は「ロシアは正しい」「対露制裁反対」と見るべきだろう。米国の非難は韓国全体ではなく、韓国の左翼政権グループに向けられている。 (室谷克実) 竹島問題: 竹島問題の経緯について、外務省HPで掲載されている内容を要約してご説明します。 竹島の領有 我が国は、遅くとも江戸時代初期にあたる17世紀半ばには、竹島の領有権を確立していました。 竹島の島根県編入 政府は、1905(明治38)年の閣議決定をもって竹島を島根県に編入し、竹島を領有する意思を再確認しました。 サンフランシスコ平和条約起草過程における竹島の扱い 韓国は、米国に対し、日本が権利、権原及び請求権を放棄する地域の一つに竹島を加えるよう要望しました。これに対し米国は、かつて竹島は朝鮮の領土として扱われたことはなく、また朝鮮によって領有権の主張がなされたとは見られない旨回答し、韓国側の主張を明確に否定しました。このやりとりを踏まえれば、竹島は日本の領土であるということが肯定されていることは明らかです。 米軍の爆撃訓練区域としての竹島 日米間の協議機関として設立された合同委員会は、竹島を米軍の爆撃訓練区域に指定しました。竹島が合同委員会で協議され、かつ在日米軍の使用する区域としての決定を受けたということは竹島が日本の領土であることを示しています。 「李承晩ライン」の設定と韓国による竹島の不法占拠 1952(昭和27)年1月、李承晩韓国大統領はいわゆる「李承晩ライン」を国際法に反して一方的に設定して、そのライン内に竹島を取り込みました。1953(昭和28)年7月には海上保安庁の巡視船が、韓国漁民を援護していた韓国官憲から銃撃を受ける事件も発生、1954年(昭和29)6月、韓国内務部は、韓国沿岸警備隊が駐留部隊を竹島に派遣した旨の発表を行いました。これ以降、韓国は、引き続き警備隊員を常駐させるとともに、宿舎や監視所、灯台、接岸施設等を構築しています。 韓国による竹島の占拠は、国際法上何ら根拠がないまま行われている不法占拠であり、韓国がこのような不法占拠に基づいて竹島に対して行ういかなる措置も法的な正当性を有するものではありません。このような行為は、竹島の領有権をめぐる我が国の立場に照らして決して容認できるものではなく、竹島をめぐり韓国側が何らかの措置等を行うごとに厳重な抗議を重ねるとともに、その撤回を求めてきています。 国際司法裁判所への提訴の提案 我が国は、韓国による「李承晩ライン」の設定以降、韓国側が行う竹島の領有権の主張、漁業従事、巡視船に対する射撃、構築物の設置等につき、累次にわたり抗議を積み重ねました。そして、1954(昭和29)年9月、竹島の領有権問題を国際司法裁判所に付託することを韓国側に提案しましたが、同年10月、韓国はこの提案を拒否しました。また、1962(昭和37)年3月の日韓外相会談の際にも、小坂善太郎外務大臣より崔徳新韓国外務部長官に対し、本件問題を国際司法裁判所に付託することを提案しましたが、韓国はこれを受け入れませんでした。 北方領土と竹島は、日本の主権が及ぶ領土でありながら管轄権の一部を事実上行使することができていません。 また、尖閣諸島においては、領有権の問題は存在していないにもかかわらず、他国・地域が領有を主張し、一方的な行動をとっています。このような状況を改善するには、どのようにしたらいいでしょうか。 国際社会では、国内のように警察に頼ることはできません。原則として、自分の国の利益は自ら守る必要があります。いわゆる「早いもん勝ち」です。 しかし日本は、憲法によって、国際紛争を解決する手段として戦争や武力の行使に訴えることは認められていません。 現代の国際社会においては、国家間の意見や利益の調整を平和的に行う様々な方法が存在します。 日本は、領土・主権をめぐる情勢について、国際社会の法と秩序を尊重しながら、それぞれの事案の性質に応じて、適切な対応をとるようにしてきました。 2011年3月から2012年にかけて日本中が混乱していた時期に韓国は竹島を実効支配、侵略していた!ロシアと同じ、領土泥棒。 アメリカのトモダチ作戦は感謝するしかないが、韓国は日本が混乱しているすきに立派なヘリポート、軍事施設を作っていた。日本の船にレーザー光線を当てたり、自衛隊にも同じことをして、何を考えているのか?分からないくにが韓国だ! 【ノーカット】防衛省がレーダー照射の動画公開 Log 3 年前 The Japan Navy's patrol aircraft P-1 flew in a distance that does not violate the international law. The South Korean warship entered Japan's EEZ without hoisting their national flag and worship flag, which violates the international law. The South Korean warship irradiated their FC antenna several times. Dispite the P-1 repeatedly questioned the purpose of the act in 3 different frequencies, they did not respond to it. According to the international law, irradiating a FC antenna is recognized as a "LOCK-ON", so Japan has rights for both constitutional ground and on the national law to attack the South Korean worship. There is no chance for South Korea to blame Japan. - ※correction The South Korean Warship actually hoisted their national flag. So in this case, Korea did not violate the international law for not hoisting there national flag. I will apologize for the miss understanding. - 일본 해군의 순찰 항공기 인 P-1은 국제법에 위배되지 않는 거리까지 날아갔습니다. 한국 전함은 국제법을 위반하는 국기와 예배 깃발을 들지 않고 일본의 EEZ에 들어갔다. 한국 군함은 FC 안테나를 여러 번 조사했습니다. P-1이 3 가지 다른 주파수에서 행위의 목적에 대해 반복적으로 의문을 제기 했음에도 불구하고 P-1은 이에 응답하지 않았습니다. 국제법에 따르면 FC 안테나에 방사능을 조사하는 것은 "잠김"으로 인식되기 때문에 일본은 헌법상의 근거와 국내법에 대한 권리를 한국인의 숭배를 공격 할 권리가있다. 한국이 일본을 비난 할 기회는 없다. - ※ 정정 한국 군함은 실제로 그들의 국기를 들었다. 그래서이 경우 한국은 국기를 게양하지 않는 국제법을 위반하지 않았습니다. 미스의 이해를 사과드립니다. - 訳: 自衛隊の哨戒機は国際法に違反しない距離で航行した。 韓国海軍艦艇は国籍旗と軍艦旗を掲揚せずに日本の排他的経済水域を航行しており国際法違反である。 その上、韓国海軍艦艇は自衛隊哨戒機に対して火器管制レーダーを照射(厳密には自衛隊哨戒機が韓国海軍艦艇からの火器管制レーダー照射を感知した)し、自衛隊哨戒機による3つの異なる周波数による再三の質問に応答しなかった。国際法上火器管制レーダーの照射は"ロックオン"と同じ扱いであり、日本はこの韓国海軍艦艇を撃沈する権利を国際法と日本国憲法の両方のもとに有する。この件について韓国に日本を非難する資格はない。 韓国が自衛隊哨戒機レーダー照射問題に動画で反論 中国軍艦艇がオーストラリア哨戒機にレーザー照射 徴用工解決へ30億円基金案 日韓企業や個人で、報道 2022/6/29 11:43 (JST) 【ソウル共同】韓国政府が元徴用工問題の解決策として、日韓の企業や個人による募金で300億ウォン(約31億円)程度の基金をつくり被害者に支給する案が浮上していると、複数の韓国メディアが29日までに報じた。近く政府や専門家による官民共同の協議会が発足する見込みで、具体案の検討が進められているとみられる。 元徴用工訴訟では、敗訴して差し押さえられた日本企業の資産を原告側が売却して現金化する手続きを進めている。ソウル新聞は28日、敗訴した日本企業には基金への出資を求めない方向になると報道。朝鮮日報も29日「韓国企業が中心に募金をする」との政府関係者の話を伝えた。 領有権の根拠を示せなかった韓国、米豪いずれも説得できず 竹島研究者が指摘 韓国が実力支配する竹島(島根県隠岐の島町、韓国名・独島(トクト))について考える島根県主催の第3回講座が11日、松江市殿町の県民会館であった。県竹島問題研究顧問の藤井賢二さん(65)が、竹島が日本領と画定されたサンフランシスコ平和条約を軸に領有権確立の舞台裏を解説した。 藤井さんは1952年に発効した平和条約の成立過程をたどり、戦後も国際的に竹島の帰属先は日本であるとの認識が共有されていたことを示した。米国務省が49年に作成した条約草案で日本が保持する島として竹島が記され、51年の米英間の協議では「朝鮮に帰属する島には竹島は含まれない」とされたという。 岸田氏、パートナーと確信 韓国大統領、関係発展へ 2022年6/29(水) 21:34配信 【マドリード共同】韓国の尹錫悦大統領は29日、訪問先のスペイン・マドリードで記者団に対し、岸田文雄首相との28日の会話を受け「韓日の懸案を解決し、未来の共同利益のために両国関係を発展させるパートナーになれると確信を持った」と語った。 尹氏は、29日開催の日米韓首脳会談に絡み「韓米日の間で、北朝鮮の核危機と関連して安保協力を強化しなければならないという共感がある」と指摘。「安保協力は北朝鮮の核が高度化すればするほど強化されると思う」と強調した。 韓国国立海洋調査院所属の海洋調査船 「Hae Yang 2000」による海洋調査活動 令和4年5月29日 我が国政府は、本29日、竹島北方の我が国排他的経済水域(EEZ)において、韓国調査船「Hae Yang 2000」がワイヤーのようなもの等を海中に投入していることを確認しました。我が国からの照会に対し、韓国側は、調査を実施している旨応答しています。なお、同船による海洋の科学的調査について、韓国側から我が国に対して、事前の同意の申請はありませんでした。 これを受け、直ちに船越健裕アジア大洋州局長から金容吉(キム・ヨンギル)在京韓国大使館次席公使に対し、また、熊谷在韓国日本国大使館次席公使から李相烈(イ・サンヨル)韓国外交部アジア太平洋局長に対し、我が国EEZにおいて我が国の事前の同意なく海洋の科学的調査を実施しているのであれば受け入れられず、即時に中止すべきと強く抗議しました。 我が国周辺海域における海洋調査船の活動状況 近年、我が国周辺海域では、外国海洋調査船による特異行動※が多数確認されています。 ※特異行動:事前の同意を得ない調査活動または同意内容と異なる調査活動 海上保安庁では、外国海洋調査船の特異行動に関する情報を入手した場合には、巡視船・航空機を現場海域に派遣し、当該調査船の活動状況や行動目的の確認を行い、得られた情報を関係省庁に提供するとともに、巡視船・航空機により中止要求を実施するなど、関係省庁と連携しつつ、その時々の状況に応じた適切な対応を行っています。 海上保安庁が確認した外国海洋調査船による特異行動の状況はこちら 外国海洋調査船にかかる広報文 ・中国海洋調査船「潤江1」の視認について(第1報/最終報) 韓国の旧正月は「伝統文化の回復」か「中国文化圏への復帰」か【崔さんの眼】2022年7月3日(日) 新年を迎えた。元日の韓国社会の様子は、日本とさほど変わらない。テレビで除夜の鐘を鳴らす場面が流され、帰省する人で高速道路も駅も混雑する。 初日の出を見るために朝早くから海岸に集まる人やお年玉をもらって喜ぶ子供たち、民族衣装を着てテレビで新年のあいさつをするアナウンサーなどは正月の風物詩だ。日本のお正月の様子と非常によく似ている。 ◆認識は「旧正月がお正月」 違うところがあるとすれば、人によっては陽暦の1月1日を、人によっては陰暦の1月1日、いわゆる旧正月を「お正月」として過ごすということだ。 今年の旧正月は2月1日だが、どちらかと言えば、今の韓国では旧正月をお正月として認識している人の方が多い。 かつて朝鮮では、陰暦が基準になっていた。しかし、19世紀末から西洋と交流するようになり、太陽暦の必要性を感じるようになる。 条約を結び、公文書を交わす際に「世界標準」に合わせる必要があったからだ。その結果、朝鮮政府は1895年に太陽暦の使用を宣言する。 しかし、政府の一言で数百年にわたる伝統と慣習を一斉に変えることなど不可能だった。 特に祭祀(チェサ)と呼ばれる祖先を祭る行事や誕生日祝い等は、依然として陰暦で行われ、政府も対外行事に太陽暦を使用しながら、王朝の祭礼や朝会などの内部行事には陰暦を使用する場合が多く、正月を2度過ごすという混乱が始まった。 ◆100年ぶりの復帰 混乱を解消するため「陽暦か陰暦かどちらかに統一しよう」という声も後を絶たなかったが、新旧の慣習が共存する混乱は続いた。 1910年の日韓併合後、総督府により太陽暦の使用が強く勧められ、戦後も韓国政府が持続的な啓蒙(けいもう)を行い、80年ごろになると一部農村を除き、陽暦の正月が定着したかのようにみえた時期もあった。 ところが、政府は85年に長らく「平日」だった旧正月を「休日」に、民主化以降の89年には旧正月を3連休に指定。約100年ぶりに韓国人の正月は、陽暦から陰暦に正式に「復帰」することになった。 だが、それでも混乱が完全に消えることはなかった。かつての陽暦に対する反発は、韓国が20世紀中盤ごろまで陰暦を重視する農業中心の社会だったことに起因する。 しかし、現代の韓国は国際化、そして高度産業社会に変わり、21世紀の韓国人にとって陰暦はその存在意味が薄くなってしまった。新年のあいさつも、SNSでは陽暦で、親族内では陰暦で行う「二重過歳」が再び起きているのだ。多くの韓国人は、旧正月を復活させたことを「伝統を取り戻した」と認識している。西欧化と日本の支配を受ける中で、失われていた民族の伝統と固有の習慣を現代に取り戻した、すなわち良いこと、正しいことをしたと解釈している。 ◆中国文化圏の一員 しかし、多くの韓国人は、それが持つもう一つの意味を見落としている。それは旧正月の復活を「伝統文化の回復」と見ることもできるが、違う角度からは「中国文化圏への復帰」と見ることもできるということだ。 実際、現在、陰暦の正月を過ごしているのは、中国と中国文化の強い影響下にあった国・地域(台湾、ベトナム、シンガポール、韓国など)だけである。 面白いのは、社会主義国家の北朝鮮の変化だ。46年に故金日成主席が太陽暦使用と同時に、「封建時代の残滓(ざんし)」と規定し、カレンダーから消した旧正月を、故金正日総書記が「89年」に休日として指定し、復活させたのだ。 脱北者たちの話によると、北朝鮮では依然として金日成、金正日両氏の誕生日が最大の祝日で、旧正月といっても親戚が集まったり、特別な料理を食べたりはしないが、2003年からは3連休になり、現在の韓国のように陽暦と陰暦の正月が共存している状態だという。 韓国は近代化のために、北朝鮮はイデオロギーのために、一時期は捨てた旧正月を偶然にも同じ時期に復活させた。ある意味「同じ民族」としての足踏みをそろえたとも言えるが、違う角度から見たら「中国文化圏」の一員として足踏みをそろえたように見えて仕方がない。 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ バブル崩壊後の日本経済の「失われた30年」 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 小泉が派遣法の改正をしたおかげで、大部分の正社員の仕事が派遣に置き換わってしまいました。日本中にフリーターが激増してしまったのも、この男のせい。 小泉内閣時代の内閣ブレーンの一人で、経済と金融の大臣を兼任し、それまで3度、政府閣僚に選べられています。その後も諮問会とか委員会によく政府から呼ばれている人ですね。 慶應義塾大学総合政策学部の教授で、学歴も相当なもの、人材派遣業のパソナグループの会長でもあります。他にかなりの役職を受け持つ、まぁ多忙な人ですね。 2008年には韓国政府のアドバイザーとして顧問団に迎えられたり、小泉時代に総務大臣兼郵政民営化担当大臣に登用されて、郵政民営化推進で、自民党内部からも猛批判を受けた人です。 政策は ・所得税の最高税率を引き下げ(所得1000万円まで累進課税とする) ・解雇規制を緩和する ・同一労働同一賃金の法制化 ・民間でできることは民間へ 以上は実現できていないか、あるいは骨抜きって感じで、多くは自民党内部の反対で押し切られていたみたいですね。 発言としては、財政悪化の要因は国債発行の乱発で日本の財政寿命は約3年とか、若者に自由を謳歌してもいいが引き換えに貧しくなるのも自由だ、頑張って成功した人の足を引っ張るななどがあります。 また格差社会の要因の一つは正社員という特権であるということもテレビで発言してますね。 平蔵を国賊と言ってる人たちは、恐らくバブル崩壊以後の失われた20年(30年?)の時代に、あまり良い事がなかった人が、非正規雇用を生み出したのは竹中のせいとか、自己責任ばかりが横行したのは平蔵のせいだ!と思っているからでしょうね。 また「時間内に仕事を終えられない、生産性の低い人に残業代という補助金を出すのはおかしい」と、まぁ私は定時に帰れという意味で、労働者の質の問題に触れていると思うのですが、これを悪く取る人もいたようです。 比較的合理的な理論で押し切るタイプの人ですが、やっぱり学歴・職歴が凄いのと、ズバズバ歯に衣着せぬ物言いの人なので、ものすごく好き嫌いが別れる人ではあると思います。特に既存の経済評論家や保守派の人には相当嫌われているようで。 人材派遣法の歴史は? 日本における派遣法の歴史 派遣法が施行されたのは、1986年7月1日です。 しかし、それ以前から人材派遣のようなことをしている会社は存在していました。 1980年代に入って雇用される労働者が増え、また業務請負という形態で派遣していたため、労働者保護の観点から派遣法が施行されることになったのです 労働者派遣法の歴史 荒井大 【派遣法の歴史】 [1985年(中曾根内閣)] 派遣法が立法される。 派遣の対象は「13の業務」のみ [1986年(中曾根内閣)] 派遣法の施行により、特定16業種の人材派遣が認められる。 [1996年(橋本内閣)] 新たに10種の業種について派遣業種に追加。合計26業種が派遣の対象になる。 [1999年(小渕内閣)] 派遣業種の原則自由化(非派遣業種はあくまで例外となる) この頃から人材派遣業者が増え始める。 [2000年(森内閣)] 紹介予定派遣の解禁。 [2003年3月(小泉内閣)] 労働者派遣法改正 例外扱いで禁止だった製造業および医療業務への派遣解禁。専門的26業種は派遣期間が3年から無制限に。 それ以外の製造業を除いた業種では派遣期間の上限を1年から3年に。 [2004年(小泉内閣)] 紹介予定派遣の受け入れ期間最長6ヶ月、事前面接解禁。 *鳩山政権による派遣法改正の動き* 1、製造業への派遣を原則禁止(常用型を除く) 2、日雇派遣、2か月以下の労働者派遣を禁止 3、登録型派遣の原則禁止(専門26業種を除く) 登録型…仕事がある時だけ雇用契約を結ぶもの。 常用型…仕事がなくても給料がもらえる(雇用契約を結べる)。 労働条件・労働基準めぐる法改正情報 派遣法 なぜ でき た? もともと、労働基準法第6条で中間搾取の禁止が定められていますが、その規制を緩和する意味で制定されたのです。 労働者派遣法は、派遣事業の適正な運営と派遣労働者の雇用の安定、福祉の増進を目的としています。 派遣はいつから始まった? 日本の人材派遣の歴史は、1986年に「労働者派遣法」が施行されたことで始まり、これまで世の中の情勢にあわせ、何度も改正がなされてきました。 派遣法1999年の改正は? 1999年:対象業務が原則自由化となる(ネガティブリスト化) 規制緩和の波はさらに強く押し寄せ、適用対象業務の原則自由化(禁止業務のみを指定するネガティブリスト化)が実現。 一方で、建設、港湾運送、警備、医療、物の製造業務が禁止業務とされます。 人材派遣業の儲けの仕組み 人材派遣会社では、自社で雇用する派遣社員の労働力を派遣先の企業に提供することで「マージン」を上乗せした報酬を得ることで利益を出しています。 このシステムから、人材派遣業は「ピンハネ業だから楽して儲けている」などと揶揄されることがありますが、実際にはそれほど大きな利益があるわけではありません。 有期雇用派遣社員として働ける期間は最大3年 これは、2015年の派遣法改正により定められた内容です。 以前は派遣期間に制限はなく、派遣社員として長期間同じ部署で働くことができましたが、2015年の派遣法改正により「働けるのは3年間だけ」というルールに変更されました。 すぐに辞めてしまう理由 派遣で来た方がすぐ辞めてしまう主な理由としては次のようなことが考えられます。 仕事内容に馴染めない(未経験者が作業の手順や方法を理解できない) 職場に馴染めない(社内での決まりごとや雰囲気など) 地域や環境に馴染めない(他の地域から働きにきた場合など) 困ったことを相談できる人がいない(職場トラブルや将来のキャリアプランなど) 事前の研修や、就業後のフォロー体制などがない派遣会社だと、就業の前と後でのギャップが生じてしまい、「馴染めない…」と感じる機会が多くなります。 また、相談に乗ってくれる人がいないことで、不安や不満が退社に直結してしまうのです。 最初はほんの小さな「嫌だな…」と思う気持ちから始まったとしても、誰もフォローしてくれないために次第に勤務から足が遠のいてしまい、無断欠勤を続けた結果、そのままフェードアウトする。 派遣社員 何が問題? 単調な仕事や、いわゆる「誰でもできる仕事」を任されるため“やりがい”は生まれにくい特徴があります。 また仕事のやり方や方針に対して基本的に口を出すことができないため、働くことのモチベーションは維持しにくいでしょう。 なぜならそれが「派遣社員」の本質だからです。 派遣 時給上がった なぜ? 派遣は正社員と待遇が異なり、実際に働いた時間分のお金しかもらうことができません。 ボーナスや昇給などは基本的になく、企業によっては交通費の支給もありません。 そのため、その分が時給に上乗せされた形となり、高い時給に反映されているのです。 グループ内派遣のメリットは? またグループ内派遣は、法律に則って雇用された派遣社員や正社員を雇うよりも、人件費を削減できるのが特徴です。 そのためグループ内派遣を許せば、専ら派遣のときと同様、企業はグループ内派遣からの派遣労働者ばかりを受け入れるようになり、正社員や法律に則った派遣社員の雇用を妨げることになりかねません。 派遣法 違反 どうなる? 当該法律に違反すると、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金刑が科せられます。 また、派遣先企業が更に派遣を行うことで利益もあげていた場合、労基法6条が規制する「中間搾取の排除」に該当するため、労基法違反にもなり、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金刑が科せられます。 なぜ派遣はダメなのか? 短期間での派遣就業では、労働者の収入が不安定になります。 また派遣会社、派遣先企業共に適正な雇用管理をすることが難しいという判断から、2012年の改正労働者派遣法で、日雇い労働者(日々もしくは30日以内雇用期間)の派遣は原則禁止となりました。 日雇派遣は条件に当てはまれば、派遣が認められています。 派遣が多い会社 なぜ? まず、派遣会社が多い理由を室伏氏に聞くと「大手企業が人件費を削減したいがために、政府に構造改革を促した影響です」とキッパリ。 「企業としては人件費、社会保険料の負担が大きく、どうしても抑えたいコストです。 そこで大手企業を中心に構成されている経団連が自民党に働きかけ、派遣法の改正に踏み切らせました。 正社員 派遣 どっちが稼げる? 短期的に見た時、派遣の方が稼げるとお伝えした理由は、派遣の時給に高さにあります。 例えば月給25万円の正社員の場合、時給換算すると大体1500円程と言われています。 一方派遣はというと、条件の良い案件なら時給1800円という求人もあります。 正社員のように週5で8時間働く場合、月給は約32万円となります。 派遣社員 年収 いくら? 令和2年度の派遣社員の全国平均年収は約374万円でした。 専門性が高い職種ほど給料が高く、三大都市圏とそれ以外との地域差は、年収にして約54万円になります。 派遣社員の給料は人材派遣会社から支払われ、月末締め翌月給料日支払いであることが一般的です。 WDBのマージン率は? どの派遣会社でもマージンはあるのですが、WDBはその率が高いです。 基本的なマージン率は「25%〜30%」とされているのですが、WDBでは34%に設定されています。 派遣 女性 多い なぜ? 一方、派遣社員という働き方を選んだ理由として女性がもっとも多く選んだのは「働く日数・期間を選べる」という選択肢でした。 同じ調査の中で今後も派遣社員として働きたいと答えた男性は3割にとどまったのに比べ、女性は4割と比較的高い割合を示しています。 派遣女性の中には、家事や育児しながら働いているという方も少なくありません。 フリーターと正社員 どっちが稼げる? フリーターと正社員では、基本的に正社員のほうが高収入の傾向にあるようです。 厚生労働省の「令和2年賃金構造基本統計調査 結果の概要『雇用形態別にみた賃金』(p1)」によると、フリーターを含む非正規雇用の平均月収は男女計で21万4,800円。 正社員の平均月収は32万4,200円とされています。 派遣 1日いくら? 厚生労働省は、業種ごとの派遣料金の費用相場を公開しており、2021年4月時点では2020年度の結果が公表されています。 専門的な技術や知識が必要な職種の場合、1日あたりの平均料金は20,000~30,000円、それ以外の職業は10,000~20,000円が派遣料金の相場です。 派遣 1時間 いくら? 営業職種従事者の1人あたり1日8時間の平均派遣料金は2万1,083円、1時間あたりの平均派遣料金は2,635円となっています。 派遣会社 どれくらい抜いてる? 公表されていた派遣会社のピンハネの実態 私のように、フルタイムの派遣社員として働いている場合の、一般的な派遣料金の内訳。 派遣社員のお給料は、派遣先企業が派遣会社に払う「派遣料金」の70%。 30%が派遣会社の取り分。 派遣会社は派遣料金の30%をピンハネしてる!? 派遣 最低 賃金 2022 いくら? 2022年は10月1日から【時給1,072円】に改正されます。 この最低賃金は東京都内に派遣中の労働者を含みます。 派遣社員の人口は? 派遣の現状 | 一般社団法人日本人材派遣協会 2020年1~3月平均の派遣社員数は約143万人となりました。 雇用者全体(5,661万人、役員除く)に占める派遣社員の割合は2.5%となり、この割合は15年ほど大きな変化は見られず2~3%を推移しています。 なぜ派遣会社が多いのか? まず、派遣会社が多い理由を室伏氏に聞くと「大手企業が人件費を削減したいがために、政府に構造改革を促した影響です」とキッパリ。 「企業としては人件費、社会保険料の負担が大きく、どうしても抑えたいコストです。 そこで大手企業を中心に構成されている経団連が自民党に働きかけ、派遣法の改正に踏み切らせました。 なぜ派遣はダメなのか? 単調な仕事や、いわゆる「誰でもできる仕事」を任されるため“やりがい”は生まれにくい特徴があります。 また仕事のやり方や方針に対して基本的に口を出すことができないため、働くことのモチベーションは維持しにくいでしょう。 なぜならそれが「派遣社員」の本質だからです。 派遣会社にとっての派遣社員は人的資源。 派遣会社のリスクは? 一番想定されうるリスクとしては、派遣事業で保有している集客チャネルや人材プールに、正社員雇用を希望する人材が少ないことや、経歴やスキルの関係から採用企業側の正社員としての採用ニーズがあまりないことがあげられます。 派遣社員 なぜ生まれた? バブル崩壊以降、年功序列、終身雇用といった日本独特の雇用の在り方が問われ正社員のリストラが目立つようになってきた時期がありました。 そこで企業が求めたのが派遣社員です。 必要な期間、必要なポジションに労働力を充当できるのは企業にとって大きな魅力だったのかもしれません。 それに加えて、働く側の意識の変化があります。 派遣の悪いイメージは? 派遣のイメージは正社員に比べ、重要な仕事ややりたい仕事をやらせてもらえないイメージがあります。 人間関係ができて、気心がしれたころに辞めてしまう印象が強いので、仕事にまつわる悩みなどの相談がしづらいイメージがあります。 いつ雇用期間を切られるのかが全く予想できないため、将来に対して不安のある働き方だと思います。 派遣の仕事は何歳まで? 派遣に年齢制限はない 派遣労働者に年齢制限はなく、60歳以上で働いている方も存在します。 派遣会社への登録も、年齢制限はもちろん、性別や学歴、職歴、資格、スキル、経験などの条件も設けられていません。 即戦力として資格やスキル、経験が求められるイメージがあるものの、未経験者を歓迎している会社も数多くあります。 使えない派遣社員の特徴は? 「使えない……」交代になりやすい派遣社員の特徴 能力が自社の求める水準に達していない ... 能力に関して改善が見られない ... 注意やアドバイスに対して不機嫌になる ... 職場の規則に従ってくれない ... 派遣社員への教育内容を再考する ... 職場環境をチェックしてみる ... 交代を要請する ... 派遣元を変える 派遣社員の教育は 誰が する? 派遣スタッフの教育訓練に関しては、雇用主である派遣会社が実施すべきですが、派遣先の業務に密接に関連した教育訓練については、実際の就業場所である派遣先が実施することが適当であるとし、派遣先の正社員と同様の教育訓練を受けさせることが義務化されました。 派遣法改正案は「正社員の雇用」を守るためだった!? 非正社員は誰も救われない“矛盾と罠” ――国際基督教大学 八代尚宏教授インタビュー 2010.12.2 今年3月に閣議決定し、国会審議が行われていた労働者派遣法改正案は、首相交代などの混乱のなか、継続審議となった。08年秋の世界同時不況後、派遣労働の規制強化に向けた世論の高まりとともに注目を浴び、登録型派遣や製造業務派遣の原則禁止を柱とする本法案。今後、再審議で成立したとして、本当に非正社員は救われるのだろうか。検証するとともに、非正社員が真に救われる働き方やそれを担保する制度について、国際基督教大学の八代尚宏教授に話を聞いた。(聞き手/ダイヤモンド・オンライン 林恭子) 派遣法改正でも正社員は増えない むしろ失業者が増える可能性も ――「派遣の原則禁止」を目指した派遣法改正案だが、これが実現すれば本当に非正社員は救われるのだろうか。派遣法改正案の問題点とともにお教えいただきたい。 それを明らかにするためには、まず派遣労働の規制緩和がなぜ行われたかを考えなければならない。 そもそも派遣社員などの非正社員の増加は、「小泉政権における新自由主義的な構造改革によってもたらされた」という認識が広まっているが、これはまったくの誤解である。なぜならこの規制緩和は、1999年に派遣労働の雇用機会の拡大と保護強化を目的とした国際労働機関(ILO)第181号条約に日本が批准したことに基づいており、2001年に成立した小泉政権誕生以前の話であるからだ。 この条約は、欧州を中心に失業率が高止まりしている状況下で、失業率を低下させるためにも有料職業紹介や派遣労働を容認し、不安定でも雇用機会を増やすことが先決だという事情から生まれたもの。日本も批准し、それ以前の派遣先の職種を厳しく制限した「原則禁止・例外自由」を逆転して、「原則自由・例外禁止」へと原則を大転換した。これに伴い、「当分の間」禁止となっていた製造業への派遣が、2004年に自由化されたに過ぎない。 したがって、規制緩和の目的は「雇用機会の拡大」にあったわけだから、それを元に戻して規制を強化をすれば、結果も逆になるのは当然だ。 朝日新聞が全国主要100社を対象に行った「派遣が禁止された場合の対応」へのアンケート(09年11月実施)によると、「他の非正社員に置き換える」(契約社員:36社、請負・委託:30社、パートタイム:22社)のがほとんどで、「正社員の増加で対応」はわずか15社だった。 小泉労働法制「改革」についての雑感 静岡県労働研究所 理事長 大橋 昭夫 小泉内閣は、昨年6月27日労働基準法の一部を改正する法律を成立させ、これが本年1月1日から施行されている。 この詳細については触れないが、この改正法は、有期労働契約の契約期間の上限の延長、有期労働契約の締結、更新及び雇い止めに関する基準、解雇権濫用法理の明文化、裁量労働制の一層の拡大を実現したもので、解雇規制を除き労働者に対して、大きな苦難を強いたものと評価される。 この改正は、もっぱら日本経団連の意向に沿うもので、この推進勢力は、小泉総理大臣のブレーンで総合規制改革会議議長宮内義彦オリックス会長を中心とするグループであったと言われる。 宮内議長は、「鉛筆型の人事戦略」を唱え、少数のコア社員を細い芯とし、これのみを保護し、その周りの木の部分に成功報酬型の社員を、さらに、その周りにパートタイマーや派遣労働者を配置し、これらの木の部分を必要に応じて調整することが、グローバル経済を勝ち抜く今後の経営戦略であることをあからさまに述べている。自分が生き抜くためには、大多数の労働者の生活など視野に入らないのである。 今回の労基法の改正は、労働者派遣法の「改正」による派遣業種の一層の拡大と相俟って、我が国の正規労働者の数を著しく減少させ、これをパートタイマー、派遣労働者等の不安定労働に代替させるものであって、わが国社会の労働秩序を根底から破壊することになる。 厚生労働省は、今回の改正法案の提出にあたって、「今日、我が国の経済社会においては、少子高齢化が進み労働力人口が減少していく一方、経済の国際化、情報化等の進展による産業構造や企業活動の変化、労働市場の変化が進んでいる。このような状況の下で、経済社会の活力を維持、向上させていくためには、労働者の能力や個性を活かすことができる多様な雇用形態や働き方が選択肢として準備され、労働者一人一人が主体的に多様な働き方を選択できる可能性を拡大すること、働き方に応じた適正な労働条件が確保され、紛争解決にも資するよう労働契約など働き方にかかるルールを整備すること、これらの制度の整備、運用に際しては、労使によるチェック機能が十分に活かされるようにすることなどを基本的な視点とする」と説明しているが、この視点は、余りにも労働者の生活実態を知らない「綺麗事」であり、役人の文章である。 私が指摘するまでもなく、わが国の経済社会の活力を維持、向上させていく最良の手段は、雇用の確保であり、人間らしい生活をするのに必要な賃金の保障である。 厚生労働省のいう「多様な雇用形態や働き方」という概念は空漠としており、その内容が如何なるものか明確でないが、派遣労働や有期契約による労働、更には残業代を回避するための裁量労働であると察しはつく。 これらの労働形態は、いずれも不安定雇用であって、多様な働き方を実現し、それが豊かな生活につながる契機となることは経験則上ありえない。 私の弁護士としての経験からすると、労働者は少々他と比べて賃金が低いとしても、雇用が安定的に確保され、将来の生活の見通しが立つ時にこそ、労働生活においても主体性を発揮でき精神的にも自由になれるものである。 いま、労働者の自己破産の申し立て件数が激増し、それがわが国の平均的な法律事務所の日常的業務になっている。 私もこの種の事件を数多く取り扱うが申し立てをする労働者の所得が低く、そのうちの少なくない者が、派遣労働者、有期契約労働者、フリーターであり、その所得水準が生活保護基準以下である者も存在する。 多様な雇用形態や働き方は、私の実感からすると、使用者の身勝手や彼らの生存権のみを保障するもので、労働者に対し永久に社会底辺に沈殿させる効用しかないように思われる。 私は、西ヨーロッパに見られる如く、「共生き」の思想を前提とした労働ルールの確立こそ、社会発展の源泉であると考えるし、小泉内閣の方向は、社会の不安定化を招来させることにしかならないと思う。 今回の労基法の改正で評価できる点は、唯一解雇権の制限法理が法文上明らかになったことのみである。 この規定は、小泉内閣の原案では、「使用者は、この法律又は他の法律の規定によりその使用する労働者の解雇に関する権利が制限されている場合を除き、労働者を解雇することができる。但し、その解雇が、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と解雇が原則自由になっていた。しかし、労働者の反対があり、最高裁で確立した解雇権濫用法理の精神に立ち帰り、現行の「解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」(労基法18条の2)となったのである。 これは、西ヨーロッパ諸国の解雇制限法に比べると極めて簡単な条項ではあるが、それでも法規範として、すべての裁判官の判断を拘束するもので一歩前進だと評価できる。 小泉構造改革は、今やすべての面にわたって失敗しているが、更なる労働「改革」は、労働者の生活をより一層困難にするもので、働く人々は、思想、信条、潮流、傾向を超えて、この流れに対抗する必要があろう。 わが国に憲法の精神に忠実な「働くルール」が確立されることを切に望むものである。それが真の意味での労働改革である。 破たんした小泉「構造改革」 社会と国民に何もたらした 貧困と格差 際限なし 「官から民へ」「改革なくして成長なし」―。ワンフレーズ政治で「構造改革」路線をひた走った小泉純一郎政治。その「本丸」とされた郵政民営化問題で、麻生太郎首相が迷走発言を続けるなか、小泉純一郎元首相や竹中平蔵元経済財政担当相らがマスメディアに盛んに登場し、「構造改革」路線の“復権”をはかる動きもみられます。「痛みに耐えれば、明日はよくなる」どころか、「生きていけない」と悲鳴があがるほどの貧困と格差の惨たんたる状況に国民を追い込んだのが「小泉改革」でした。歴史の審判はすでに下っています。 雇用のルール破壊 「派遣切り」・ネットカフェ難民 東京のど真ん中に、五百人もの人たちが衣食住を求めて集まった「年越し派遣村」。大企業の理不尽な「非正規切り」で「人間としての誇りを奪われた」「自殺も考えた」との声が渦巻きました。貧困を目に見える形でつきつけ、政治を動かしました。 「派遣村」に象徴される「使い捨て」労働の深刻な広がりは「構造改革」の名によるリストラの促進や労働法制の規制緩和がもたらしたものです。 この十年間で正規労働者が四百九万人も減り、その代わりに、非正規労働者が六百六万人も増えました。 自民、公明、民主、社民などの各党が賛成した一九九九年の労働者派遣法改悪。派遣労働を原則自由化し、「派遣」という形での「使い捨て」労働の増加に拍車をかけました。 二〇〇一年に発足した小泉内閣は、「構造改革」を加速。まず「不良債権処理」の名で中小企業つぶしをすすめ、〇三年には、企業がリストラをすればするほど減税をするという「産業再生」法を延長・改悪し、大企業のリストラを後押ししました。 一方、派遣法を改悪し、〇四年三月からは製造業への派遣を解禁しました。この中で、もともと危ぐされていた派遣労働者の労働災害が増加。〇七年の死傷者数(五千八百八十五人)は、〇四年と比べると九倍という激増ぶりを示しました。 ネットカフェで寝泊まりしながら「日雇い派遣」で働く若者の姿が、底なしに広がる「働く貧困層」の象徴となりました。 ギリギリの生活を強いられている派遣労働の実態が大問題になり、日本共産党の論戦とあいまって政府でさえ派遣法の見直しを言い出さざるをえなくなりました。労働分野の規制緩和が破たんしたことは明確です。 しかし、米国の金融危機に端を発した景気悪化を口実に、〇八年後半、大企業は製造業を中心に大量の「派遣切り」「期間工切り」を始めました。被害は日増しに広がり、今日の日本社会を覆う最大の社会問題になっています。 景気のいいときには、正社員を派遣や期間工に置き換えて大もうけをし、景気が悪化したらモノのように使い捨てる―この大企業の横暴勝手を容易にする仕組みを作ったのが、労働の「構造改革」であり、今日の事態は、まさに政治災害そのものです。 社会保障の連続改悪 医療崩壊・国保証取り上げ 「わずかな年金は減らされたうえ、保険料の天引きは容赦ない」「病気になってもお金がなければ病院にもいけない」―。「構造改革」による社会保障の連続改悪によって、こんな苦難が国民を襲いました。 その大もとにあるのが、小泉内閣が決めた社会保障費の抑制方針です。二〇〇二年度から毎年、社会保障費の自然増分から二千二百億円(初年度は三千億円)削減されてきました。 抑制の対象は医療、介護、年金、生活保護と社会保障のあらゆる分野に及び、庶民への痛みの押し付けの結果、「生きること」自体が脅かされる実態が広がっています。 医療分野では、国民の負担増に加え、医療費削減を目的に医師数の抑制政策を続けたため、救急患者が救われない医師不足が社会問題化し、「医療崩壊」と呼ばれる事態が出現しました。 高すぎる国民健康保険料が払えずに正規の国保証を取り上げられた世帯は約百五十八万世帯にまで広がっています。受診を控え、手遅れで死亡する例は後を絶ちません。 そのうえ、国民生活の最後の命綱である生活保護さえ切り縮められました。老齢加算の廃止で、「朝はパン一枚、昼はうどん」「暖房費節約のため、ストーブをつけず布団に入る」「風呂の回数を減らす」など生活の根幹まで切り詰めざるをえない実態です。(〇八年一月、全日本民主医療機関連合会の調査報告) こうしたなか、昨年四月に導入された後期高齢者医療制度に、国民の怒りが爆発しました。同制度に対する不服審査請求は全国で一万件超。「『高齢者はいずれ死を迎える、お金も手間もかけなくてよい』という、人間性を喪失した制度だ」などの怒りの声があふれています。 日本医師会など医療関係四十団体は〇八年七月、「社会保障費の年二千二百億円削減撤廃」を決議。国民の批判は、小泉内閣がしいた二千二百億円の削減路線そのものに向けられはじめました。 自公政権は社会保障費の削減路線の転換は明言しないものの、〇九年度予算案で一時的な手当てを行い、社会保障費の実質の削減幅は二百三十億円に“圧縮”せざるをえなくなっています。第二次小泉改造内閣で厚労相だった自民党の尾辻秀久議員でさえ、一月三十日の参院本会議で「乾いたタオルを絞ってももう水はでない。潔く二千二百億円のシーリングはなしと言うべきだ」と述べるなど、社会保障費削減路線の破たんを認めざるをえなくなっているのです。 庶民負担増 大企業は減税 7年間で国民に50兆円近くも 小泉政権以来の増税などで国民負担は、年間十三兆円も増えました。二〇〇二年度から〇八年度まで七年間の国民負担増を累計すれば、五十兆円近くになります。 その一方で、大企業・大資産家への減税は、一九九八年以降の十年間に行われたものだけでも、大企業に年間五兆円、大資産家に年間二兆円、あわせて年間七兆円以上になっています。十年間の累計では、四十兆円もの税収が失われました。 地方の切り捨て 激減する交付税・農業破壊 「交付税が四割減って半分も補てんされない」「このままでは吉野は死んでしまう」 昨年七月。奈良県吉野郡で開かれた日本共産党の演説会に先立ち、市田忠義書記局長と懇談した地元町村長らから、こんな嘆きの声が率直に寄せられました。 「地方ができることは地方へ」をうたい文句に自民・公明政権が強力に推進した「三位一体改革」は、農山漁村の自治体を存亡の危機にまで追い詰めています。 実際、「三位一体改革」が断行された二〇〇四年から三年間で、国庫補助負担金は四・七兆円、地方交付税は五・一兆円がそれぞれ削減されました。一方、国から地方への税源移譲はわずか三兆円しかありません。地方自治体にとっては差し引き六・八兆円のマイナスです。 全国知事会は昨年七月の知事会議で、このままでは一一年度までに地方自治体の財政が破たんするという衝撃的な試算を発表しました。とりわけ地方交付税が財政に占める比重が高い町村の財政は深刻です。 「地方交付税の削減など、国による兵糧攻めからの生き残り策」「周辺町村が財政破たん寸前だった」。全国町村会の「道州制と町村に関する研究会」が昨年十月にまとめた調査報告でも、市町村合併の理由の柱に「三位一体改革」による交付税削減を指摘する声が相次ぎました。 国会でも、鳩山邦夫総務相が「急激にやりすぎた。失敗の部分がある」(十二日、衆院本会議)と答弁。「三位一体改革」の破たんを認めました。 また、輸入自由化の促進による農業破壊、大型店の進出による商店街の「シャッター通り」化など、地方経済の冷え込みも深刻です。 しかし、自民党は、こうした“地方切り捨て”を反省するどころか、一〇年三月末の合併特例新法の期限切れを前に「おおむね七百から千程度の基礎自治体に再編」すると、いっそう合併を推進することを主張。さらに、政府は「時代に適応した『新しい国のかたち』をつくる」として道州制の導入を掲げています。 こうした動きには全国町村会が「強制合併につながる道州制には断固反対していく」と明記した特別決議を採択するなど、痛烈な反撃が巻き起こっています。 経済ゆがみ、ぜい弱に 「戦後最悪の経済危機」(与謝野馨経済財政担当相)―。内閣府が十六日発表した二〇〇八年十―十二月期の国内総生産(GDP)が実質で前期比3・3%減(年率換算12・7%減)となったニュースは、衝撃を与えました。金融危機の震源地である米国よりも急激な落ち込みだったからです。なぜこんなことになったのか。ここにも、背景に小泉内閣いらいの「構造改革」があります。 極端な輸出依存 「衝撃 石油危機以上 輸出依存体質響き」(「毎日」十七日付)、「外需依存の成長 岐路」(「日経」同)、「外需頼み 転換カギ」(「読売」同)といった見出しが商業メディアに目立ちました。極端なまでに輸出に依存した「経済成長」の破たんです。 「構造改革」を掲げた小泉内閣が発足(〇一年四月)して以来の変化をみてみましょう。内閣府のGDP統計によると、所得や個人消費は低迷しているのに、輸出が極端に伸び、〇八年に失速します。財務省の法人企業統計をもとに、製造業大企業(資本金十億円以上)の〇一年度と〇七年度を比較すると、経常利益は二・二五倍に増えています。ところが、従業員給与は〇・九八倍と減っています。大幅に増えたのは株主への配当と社内留保です。一方、民間信用調査会社の調査では、法的整理による企業倒産が増えています。ほとんどが中小企業です。 自動車、電機など輸出大企業を中心に従業員や中小企業・業者にしわ寄せする形で、大もうけし、もっぱら株主に還元するという構図です。 財界全面後押し こうした企業体質をつくり出したのが、「構造改革」だったと、日本経団連会長の御手洗冨士夫キヤノン会長が述べています。 「これは、何といっても構造改革の進展がもたらしたもの」「多くの企業でも、筋肉質の企業体質が形成されている。過剰設備や過剰債務、過剰雇用という、いわゆる『三つの過剰』は完全に解消している」(〇八年六月十九日の講演) 文字通り、財界の全面的な後押しで推進されたのが小泉流「構造改革」でした。 財界が求める雇用など「三つの過剰」の解消を推進するテコと位置づけられたのが不良債権の強引な早期最終処理です。 小泉内閣が最初につくった「骨太の方針」(〇一年六月)は、不良債権処理の加速を通じて「効率性の低い部門から効率性や社会的ニーズの高い成長部門へとヒトと資本を移動することにより、経済成長を生み出す」とうたいました。小泉内閣は、リストラすればするほど減税する「産業再生」法を拡充、製造現場への労働者派遣を解禁しました。 懸念したことが この結果、「成長」したのは、「筋肉質」になった輸出大企業や大銀行だけでした。「不良債権」扱いされた中小企業は倒産に追い込まれ、大量の失業者が生まれ、正社員から賃金の安い非正規社員への置き換えが進みました。 あまりにも、国内経済を脆弱(ぜいじゃく)にしてしまった「構造改革」。政府の「ミニ経済白書」(〇七年十二月)でさえ、輸出は増加しているが、家計部門が伸び悩むなか、米国経済など海外リスクが顕在化した場合、景気は「厳しい局面も予想される」と懸念していたことが現実のものとなりました。 推進者がいま「懺悔の書」 小泉流「構造改革」をめぐり居直る竹中平蔵元経済財政・金融担当相と対象的に「懺悔(ざんげ)の書」を書いたのは、中谷巌氏。小渕内閣の経済戦略会議の議長代理として「構造改革」の提言をまとめた中心人物です。竹中氏も同会議のメンバーの一人でした。 中谷氏は自著『資本主義はなぜ自壊したのか』のなかで、「一時、日本を風靡(ふうび)した『改革なくして成長なし』というスローガン」にふれ、「新自由主義の行き過ぎから来る日本社会の劣化をもたらしたように思われる」として、「『貧困率』の急激な上昇は日本社会にさまざまな歪(ゆが)みをもたらした」と指摘。「かつては筆者もその『改革』の一翼を担った経歴を持つ。その意味で本書は自戒の念を込めて書かれた『懺悔の書』でもある」と書いています。 郵政民営化矛盾が噴出 小泉内閣が「構造改革」の本丸と位置付けた郵政民営化。その矛盾が噴出しています。 「私は郵政民営化を担当した大臣」(二〇〇八年九月十二日、自民党総裁選の討論会)と自認する麻生太郎首相。その麻生首相が「(郵政事業の四分社化を)もう一回見直すべき時にきているのではないか。小泉首相のもとで(郵政民営化には)賛成ではなかった」(二月五日の衆院予算委員会)と言い出したのは、郵政民営化の破たんを象徴しています。 当時の小泉首相が「郵政選挙」までやって強行した郵政民営化のかけ声は「官から民へ」「民間でできることは民間で」「貯蓄から投資へ」でした。 「民間」といっても日米の大手金融機関のことです。もうけのじゃまになる郵便貯金、簡易保険などの郵政事業をバラバラにするのが四分社化でした。 「貯蓄から投資へ」といっても、庶民の預貯金を呼び込もうとしている証券市場の売買の六割以上は外国人投資家。その大半はヘッジファンドとよばれる投機基金です。庶民の虎の子の財産が食い物にされかねません。 安心、安全、便利を願う国民にとっては「百害あって一利なし」の郵政民営化。その矛盾のあらわれは小泉流「構造改革」路線そのものの破たんを物語っています。 “改革が足りないから”と居直る竹中氏だが… 小泉流「構造改革」がモデルにした本家の米国で、市場まかせの「新自由主義」路線が破たんしました。にもかかわらず、小泉流「改革」にしがみつこうとする勢力がいます。 一月一日放送のNHK番組で、小泉「改革」を推進した元経済財政・金融担当相の竹中平蔵氏は、大企業の「非正規社員切り」横行が社会問題になり、小泉「改革」に批判が強まっていることに、こう居直りました。 「大企業が非正規を増やすのは原因がある。正規雇用が日本では恵まれすぎている。正規雇用を抱えると企業が高いコストをもつ」 「同一労働同一賃金」をやろうとしたが、反対されたとし、「(年越し派遣村などは)改革を中途半端に止めてしまっているから、こういう事態が起きている」。 竹中氏が“止まっている”という「改革」の中身は、正社員の賃金水準を賃金が安い非正規社員の水準に引き下げるという意味での「同一労働同一賃金」です。大企業の総人件費を抑えるのが狙いです。これでは、働いても働いても貧困から抜け出せない「ワーキングプア」を労働者全体に広げることにしかなりません。 しかも、竹中氏は「問題は、いまの正規雇用に関して、経営側に厳しすぎる解雇制約があることだ」(「竹中平蔵のポリシー・スクール」二月一日付)として、企業業績が悪化したら従業員を抱え込まなくていいような「新たな法律を制定することが必要だ」と主張しています。正社員を含めた“解雇自由法”をつくれといっているようなものです。 一方で、「日本を元気にしないといけない」として、最優先課題にあげたのが法人税率をもっと引き下げることでした(一月一日のNHK番組)。竹中氏がかかげる「改革」はあくまで、大企業のための「改革」を徹底しろということにすぎません。 2021.09.30 国が見捨てた就職氷河期世代の絶望…バブル崩壊後の30年間で何が起きたか 当事者として、取材者として 小林 美希 プロフィール 2021年9月29日に自民党の総裁選が行われ、その後には総選挙が控えている。政治家が「中間層の底上げ」を訴えるが、考えてみてほしい。もとはといえば、中間層を崩壊させたのは政治ではなかったか。 国際競争の名の下で人件費を削減したい経済界は政治に圧力をかけた。不況がくる度に労働関連法の規制緩和が行われ、日本の屋台骨が崩れていった。最も影響を受けたのが就職氷河期世代だ。これからを担っていくはずだった若者たちが、非正規雇用のまま40~50代になった。 私が非正規雇用の問題を追って18年――。いったい、何が変わったのか。 大卒就職率6割以下の時代 1980年代には8割あった大卒就職率は、バブル経済が崩壊した1991年以降に下がり始めた。そして2000年3月、統計上、初めて大卒就職率が6割を下回る55.8%に落ち込んだ。大学を卒業しても2人に1人は就職できなかったというこの年に、私は関西地方で大学を卒業した。 その3年後の2003年3月に大卒就職率は過去最低の55.1%を更新。日経平均株価は同年4月に7607円まで下落した。この時の私はもちろん、当事者だった大学生の多くは雇用環境が激変するなかにいるとは気づかずにいた。 私の就職活動は苦戦した。約100社にエントリーシートを送り、50社は面接を受けた。神戸に住んで大学に通っていた私の就活の主戦場は大阪で、面接を受けるために毎日のように大阪周辺を歩き回った。最終的に内定が出たのは消費者金融会社の1社のみだった。 卒業後に東京で就職活動をやり直し、ハローワークに通った。新聞広告の求人を見て応募した業界紙の「株式新聞」に採用が決まった。就職試験の日、「うちは民事再生法を申請したばかりですが」と説明があり、倒産しかけた会社に就職することに悩んだが、「面白そうだ」という直感が勝った。 この株式新聞時代に出会い、後の私の記者活動に影響を与えたのが、伊藤忠商事の丹羽宇一郎社長(当時)だ。丹羽氏との出会いがなければ、私は就職氷河期世代の問題を追及しなかったかもしれない。 新人の時には経済記者として食品、外食、小売り、サービス業界を担当。商社の担当も加わり、出席した伊藤忠商事の記者懇談会で初めて丹羽氏に挨拶をする。記者に囲まれていた丹羽氏に私は「社長の役割とは何か」と聞いた。この若気の至りとも言える質問に対し、丹羽氏は真顔で「経営者とは、社員のため、顧客のため、そして株主のためにある」と答えてくれたのだった。 若者が疲れ切っている…なぜ? 株式新聞入社から1年後の2001年の初夏、毎日新聞が発刊(現在は毎日新聞出版)する『週刊エコノミスト』編集部に契約社員として転職した。私はだんだんと雑誌の仕事に慣れていき、天職と思って没頭していた。深夜や明け方に及ぶ校了作業は達成感があり、職場で夜を明かして新聞をかぶってソファで寝ていたこともあった。 これはマスコミ特有の働き方かと思っていたが、この頃、金融、製造、サービス業などに就職していった友人たちも長時間労働というケースが多かった。そのうち、充実感とは違った何かがあると感じ「なにかおかしい。若者が疲れ切っている」と首をかしげるようになっていった。 その疑問が確信に変わったのは、2003年前後に上場企業の決算説明会で経営者や財務担当役員らが強調した言葉を聞いてからだ。 「当社は非正社員を増やすことで正社員比率を下げ、利益をいくら出していきます」 2001年のITバブル崩壊から間もなくてして企業利益がV字回復し「失われた10年」が終わるかのように見えた。私はこの利益回復は非正規雇用化で人件費を削減したことによるものに過ぎないと見た。これでは経済を支える労働者が弱体化すると感じた私は、若者の非正規雇用の問題について企画を提案した。 『週刊エコノミスト』の読者層の年齢は高く、若者の雇用問題をテーマにしても読まれないという理由で、企画はなかなか通らなかった。さらに世間で浸透していた「フリーター」という言葉の印象が自由を謳歌しているイメージが強く、若者は甘いという風潮があるなかでは、ハードルが高かった。 悩んだ私は、再び、若気の至りの行動に出た。伊藤忠商事の丹羽氏にアポイントをとって、企画が通らないこと、企画が通らなければ転職したほうが良いか迷っていると人生相談をしたのだ。若者の非正規雇用化が中間層を崩壊させ、消費や経済に影を落とすと見ていた丹羽氏は「同じことを3度、上司に言ってごらんなさい。3度も言われれば根負けして上司は必ず折れるから」とアドバイスしてくれた。 私は企画が通らないまま非正社員として働く若者の現場取材を進めた。その頃、ある会合で話したコンビニ大手の社長が「息子がフリーターで……」と悩む胸の内を明かしたことがヒントになり、デスクや編集長を説得した。 「子どもの就職や結婚を心配するのは立場を超えて一緒のはず。読者の子どもを想定して、タイトルを若者とせず、娘や息子に変えたらどうか」 企画を提案し始めてから数か月経った2004年5月、ついに第2特集で「お父さんお母さんは知っているか 息子と娘の“悲惨”な雇用」を組むことが実現した。非正規雇用に関するデータを探し、マクロ経済への影響など当時は存在しなかったデータはシンクタンクのエコノミストに試算してもらった。 この特集について慶応大学(当時)の金子勝教授や東京大学の児玉龍彦教授がそれぞれ大手新聞の論壇コーナーで取り上げてくれたことで、続編が決定。第1特集となって「娘、息子の悲惨な職場」がシリーズ化した。 富の二極分化で「中間層崩壊」 この頃の若年層の失業率は約10%という高さで、10人に1人が失業していた。内閣府の「国民生活白書」(2003年版)により、2001年時点の15~34歳のフリーター数が417万人に上ると公表されると社会の関心が若者の雇用問題に向いたが、企業側の買い手市場は続き、労働条件は悪化していく。 パート・アルバイト、契約社員や派遣社員として働き、休日出勤やサービス残業の日々でも月給が手取り16万円から20万円程度のまま。正社員でも離職率の高い業界や会社での求人が多く、ブラック職場のため過労で心身を崩すケースが続出した。 社会保険料の負担から逃れるために業務請負契約を結ぶ例まで出現。大企業や有名企業ほど、「嫌なら辞めろ。代わりはいくらでもいる」というスタンスで、若者が使い捨てにされた。こうした状況に警鐘を鳴らすためには、経営者の見方を取り上げなければならないのではないか。 2005年1月4日号の『週刊エコノミスト』では、ロングインタビュー「問答有用」のコーナーで経済界の代表的な経営者であった丹羽氏に中間層の崩壊について語ってもらった。この時点で、若者の労働問題について本気で危機感を持つ経営者は私の知る限りでは他にいなかった。丹羽氏はこう語った。 富(所得)の2極分化で中間層が崩壊する。中間層が強いことで成り立ってきた日本の技術力の良さを失わせ、日本経済に非常に大きな影響を与えることになる。中間層の没落により、モノ作りの力がなくなる。同じ労働者のなかでは「私は正社員、あなたはフリーター」という序列ができ、貧富の差が拡大しては、社会的な亀裂が生まれてしまう。 戦後の日本は差別をなくし、平等な社会を築き、強い経済を作り上げたのに、今はその強さを失っている。雇用や所得の2極分化が教育の崩壊をもたらし、若い者が将来の希望を失う。そして少子化も加速する。10~15年たつと崩壊し始めた社会構造が明確に姿を現す。その時になって気づいても「too late」だ。 企業はコスト競争力を高め、人件費や社会保障負担を削減するためにフリーターや派遣社員を増やしているが、長い目でみると日本の企業社会を歪なものにしてしまう。非正社員の増加は、消費を弱め、産業を弱めていく。 若者が明日どうやってご飯を食べるかという状況にあっては、天下国家は語れない。人のため、社会のため、国のために仕事をしようという人が減っていく。 それが今、現実のものとなっている。 格差はこうして固定・拡大化した 丹羽氏のインタビューが掲載された年の8月8日、小泉純一郎首相(当時)が郵政民営化を掲げた解散総選挙に打って出て圧勝し、規制緩和路線に拍車がかかっていく。小泉郵政選挙の投開票は9月11日。その1週間後の9月18日には一般派遣の上限期間が3年とされる改正労働者派遣法が公布され、2週間待たずの9月30日施行で、いわゆる派遣の「3年ルール」ができた。 この3年ルールとは、表向きには派遣で同じ職場で3年が過ぎたら正社員や契約社員などの直接雇用にすることを促す改正だったが、実際には多くの派遣社員が3年の期間直前で契約を打ち切られることになった。同じ年に労働基準法も改正されて非正規雇用の上限期間が3年になったことで、非正社員が“3年でポイ捨て”され、非正規雇用のまま職場を転々とせざるを得ない労働環境が整備された。 1995年に旧日経連が出した「新時代の『日本的経営』」で雇用のポートフォリオが提唱され、景気の変動によって非正規雇用を調整弁とする固定費削減が図られて10年経った2005年に「3年ルール」ができた。ここが分岐点となり、日本は格差を固定化させ、格差を拡大させる路線を歩んでしまったのではないだろうか。 本来なら、2007年から団塊世代の定年退職が始まるため人手不足を補うという意味で、まだ20~30代前半で若かった就職氷河期世代を企業に呼び込むチャンスがあったはずだ。大卒就職率はリーマンショック前の2008年3月に69.9%まで回復したが、卒業後数年が経った非正社員は置き去りにされた。 問題提起し続けるために 小泉郵政選挙を機に私は、「もし自分が政治家だったら、何を問題にし、何の制度を変えていくか」ということを、より強く意識するようになった。就職活動をしていた大学時代に講座を聴いて影響を受けた、朝日新聞大阪本社の新妻義輔編集局長(当時)の言葉を思い出していた。 「人の苦しみを数字で見てはいけない。構造問題に苦しむ人が1人でもいるのなら、それを書くのが記者だ」 新妻氏は若い記者時代に森永ひ素ミルク事件(1955年に森永乳業の粉ミルクにひ素が混入して多くの被害者が出た事件)を追っていた。事件の担当医に「被害者は何%か」と数字を聞いた時に、医師から注意を受けた経験からの教訓だという。 就職氷河期世代が抱える問題は、まさに非正規雇用を生み出す法制度という構造問題が起因しているはず。それを問題提起し続けることは、私の役割なのではないか。労働問題に特化するには組織にいては限界があると考えた私は、小泉郵政選挙から1年半後の2007年、フリーのジャーナリストになった。 絶望と諦めのムードが蔓延した 第一次安倍晋三政権(2006年9月から2007年9月)が就職氷河期世代向けに「再チャレンジ」政策をとったが、政権が短命に終わるとともに支援は下火になった。2008年のリーマンショックが襲い、就職氷河期世代だけでない多くの人が職を失った。 政府は就職氷河期世代の支援というよりは、支援事業を担う民間企業を支援したと言える。国は15~34歳の「フリーター」対策の目玉政策として2004~06年に「ジョブカフェ」のモデル事業を行っており、同モデル事業を行った経済産業省から委託を受けた企業が異常に高額な人件費を計上していたのだ。 調べると、ジョブカフェ事業ではリクルート社が自社社員について1人日当たりで12万円、コーディネーターに同9万円、キャリアカウンセラーに同7万5000円、受付事務スタッフに同5万円という“日給”を計上していたことが分かった。『週刊AERA』(2007年12月3日号、同年12月10日号)でスクープ記事を執筆すると、国会でも問題視された。 このジョブカフェでは委託事業が何重にも再委託され、税金の無駄も指摘した。昨年問題になった新型コロナウイルスの感染拡大の対策で多額の委託料が電通に支払われているにもかかわらず、何重にも委託されている問題はなんら変わっていないのだ(参照「給付金『再々々々委託』の深い闇…10年以上前から全く変わっていない」)。 就職支援事業が企業の食い物にされる一方で、就職氷河期世代の非正社員がやっと正社員になれるかもしれないというところで契約を打ち切られる。そうしたことが繰り返され、いくら頑張っても報われずに絶望の淵に追いやられた。正社員になったとしてもブラック職場で追い詰められ、心身を崩して社会復帰できないケースも少なくはない。こうした状況が続いたことで、絶望と諦めのムードが蔓延した。 2010年代に何が起きたか 2009年3月に日経平均株価はバブル崩壊後最安値の7054円をつけ、2010年3月の大卒の就職率は60.8%に落ち込んだ。2012年12月に第2次安倍内閣が発足すると、あたかも「アベノミクス」によって新卒の就職率が高まったかのように見えた。しかし、それは、団塊世代が完全にリタイアするタイミングが重なったことによるもので、15~59歳の労働力人口がピーク時より500万人減っていたことが後押ししただけだった。 安倍政権が打ち出した「女性活躍」の名の下で、企業は人手不足を補うためにブランクのある“優秀な”主婦の採用に乗り出し始め、専業主婦の間には「働いていないと肩身が狭い」という意識が一時的に広がった。 一方で、相も変わらず就職氷河期世代は置き去りにされた。2015年に専門職も含めた派遣で全職種の上限期間が3年になり、同年は労働契約法が改正されて有期労働契約が5年続くと労働者が希望すれば期間の定めのない「無期労働契約」に転換できるようになった。2005年にできた「3年ルール」と同様、制度は悪用され、派遣は3年で“ポイ捨て”、非正規雇用の全般でも5年で“ポイ捨て”が広がった。 安倍政権で内閣府に就職氷河期世代支援推進室が設置され、2019年に「就職氷河期世代支援プログラム」が策定され、3年間で30万人を正社員化すると掲げたが、国は就職氷河期世代の中心層を2018年時点で35~44歳として(次ページ図)、最も支援が難しい40代後半や50歳を過ぎた層に重点を置かずにいる。そして、支援プログラムがこれまでの施策の焼き直しの域を脱しないことから、就職氷河期世代の絶望は深まった。 就職氷河期世代の非正社員「約600万人」 いったん絶望し、諦めてしまえば、どんな支援があったとしても届きにくくなる。私が就職氷河期の問題を追ってから18年が経つ。16年前のインタビューで丹羽氏が言及した通り、もはや「too late」の状況に陥っているのかもしれない。現在、35~49歳の非正社員は約600万人に膨らんでいる。もはや誰も解決の糸口を掴めないくらい、事態は深刻になる一方だ。 自民党政治の下で、製造業の日雇い派遣が解禁され、労働者派遣は今や全ての職種で期間の上限が3年になった。就職氷河期世代を置き去りにしたまま、業界団体のロビー活動も後押しして外国人労働の拡大が図られた。「女性活躍」は女性に仕事と家事と子育て、介護の両立を押し付けるだけ。「働き方改革」や正社員と非正社員の「同一労働同一賃金」も、実態は伴わない。 就職氷河期を追うなかで、そのライフステージに寄り添い、周産期医療や看護、保育の問題もライフワークになったが、全て構造問題がある。国が作る制度が密接に関わり、政治が現場を疲弊させている。新型コロナウイルスが蔓延するなか、政治の機能不全が鮮明となった。総選挙を前に、これまでを振り返らざるを得ない。 政治家にしがらみがあれば、正しいことが言えなくなる。けれど、この18年の間に分かったことがある。世論が盛り上がれば、政治は正しい方向に動かざるを得なくなるということだ。その世論を作るのが、現場の声であり、現場の声を活字にして伝えるのが私の役割だ。就職氷河期世代の問題を解決するのは困難だろう。しかし、目指すべき道が見えなくならないよう、私は書き続けていきたい。 氷河期世代がこんなにも苦しまされている根因 問題の根が深く支援プログラムでも救えない 岩崎 博充 : 経済ジャーナリスト 著者フォロー 2019/08/02 最近になって、政府が重い腰を上げて取り組み始めたものに「就職氷河期世代」の問題がある。「ロストジェネレーション世代」とも言われるが、2019年現在35~44歳のアラフォー世代の貧困問題と言っていい。 もっと正確に言うと、1993~2004年に学校卒業期を迎えた人である。バブル崩壊後の雇用環境の厳しい時代を余儀なくされ、高校や大学を卒業した後に正社員になれず、非正規社員やフリーターとして、その後の人生を余儀なくされた人が多かった世代の問題だ。 厚生労働省の支援プログラムは功をなすのか この就職氷河期世代を対象とした支援プログラムが、3年間の限定付きではあるが厚生労働省の集中支援プログラムとしてスタートしている。支援対象は多岐にわたり、少なくとも150万人程度が対象者。3年間の取り組みによって、同世代の正規雇用者を30万人増やすことを目指している。 もっとも、わずか3年の支援プログラムで就職氷河期世代が背負った「負のスパイラル」が断ち切れるとは到底思えない。もっと継続的で長期のスパンに立った構造的改革を実施すべきだ……、という意見も数多い。 全国の自治体が取り組む「ひきこもり対策」もその効果を期待する声は多いものの、成果については疑問の声も多い。 就職氷河期世代とはいったい何だったのか。いまなお、同世代1689万人(2018年)のうち約371万人が現在も正規就労できずに、フリーターやパートの人がいると言われる。推定で61万人いると言われる40~64歳の「中高年ひきこもり」も、この世代の割合が突出しているとされる。 因果関係を立証はできないが、京都アニメーション放火殺人事件を起こしたのは41歳の男だった。最近の凶悪犯罪に、この世代の姿が目についていると感じている人もいるのではないか。世帯別の平均月収を5年前と比較すると、35~44歳の世帯の給与だけが低いというデータもある。「アラフォー・クライシス」とも言われるが、この世代の人々が抱える闇とは何か。彼らを救うために社会はどうすればいいのか。 就職氷河期世代と呼ばれる人々が どんな人生を歩いてきたのかはすでによく知られている。生まれて以降、社会人になるまでは比較的順風満帆で、バブル経済の恩恵を受けて学生時代までは恵まれた人生を歩んだ人が多かった。 ところが、学生から社会人になる際に日本は空前の不況に見舞われる。 氷河期世代が体験した無間地獄 1990年代後半から2000年代前半にかけて、日本経済はどん底とも言えるような状態にあった。1990年代前半に不動産バブルが崩壊し、その後世界的な景気後退期にさしかかり、1997年にはアジア通貨危機が世界を襲う。日本では、山一證券が経営破綻し、北海道拓殖銀行など金融機関の連鎖破綻が起きたときでもある。 さらに、2000年にはアメリカ発のITバブル崩壊が起こる。日本も大きな影響を受け、1990年代後半から2000年代前半に就職活動を行った世代は、厳しい就職氷河期にさらされる。とりわけ2000年前後は、大卒でも2人に1人しか就職できない時代を経験することになる。 同世代の非正規社員は371万人(2018年、総務省統計局、労働力調査基本集計より)で、正規雇用を希望しながら非正規雇用で働いている人は50万人に達する。非労働力人口のうち、家事も通学もしていない無業者も約40万人いる。 こうした現実に、厚生労働省も2018年度から就職氷河期世代を正社員として雇った企業に対する助成制度をスタート。「35歳以上60歳未満で、正規雇用労働者として雇用された期間が1年以下、過去1年間に正規雇用されたことがない人」を正社員として雇った企業に助成金を出すというものだ。 「特定求職者雇用開発助成金(長期不安定雇用者雇用開発コース、2019年4月より安定雇用実現コースに変更)」と呼ばれる制度で、無職や非正規社員を正社員として採用した中小企業に対して、1人当たり第1期30万円(大企業は25万円)、第2期30万円(同)、合計で60万円(同50万円)を1年間支給する制度だ。ハローワークを通して、求職活動することが条件になる。 一方、内閣府がこの6月に発表した文書によると、政府を挙げて3年間の集中支援プログラムを実施。次のような人を支援対象としてざっと100万人を救済するという。 ①正規雇用を希望していながら不本位に非正規雇用で働く者(少なくても50万人) ➁就業を希望しながら様々な事情により求職活動をしていない長期無業者 ③社会とのつながりを作り、社会参加に向けてより丁寧な支援を必要とする者など 具体的には、「安定就職に向けた支援プログラム」 「就職実現に向けた基盤整備に資するブログラム」「社会参加実現に向けたプログラム」などを立ち上げ、民間企業や市町村などと連携しながら就職氷河期世代の自立を促すとしている。 「40歳前後への職業訓練は無意味」「10年遅い」という批判も多いが、実際にこれまで政府は「自己責任論」を盾に同世代への支援には手を付けてこなかった。しかし、未婚率の高止まりや人口減少の原因の1つであることが明白となり、政府も腰を上げざるをえなくなったというのが真相だ。 ちなみに、この世代が注目されたのは、朝日新聞が今から10年以上前に同世代を「ロストジェネレーション」と名づけて、悪戦苦闘する人々をテーマにキャンペーン報道を行ったことがきっかけだ。 今後の日本の大きな問題になると指摘し、大量退職を迎えていた団塊世代以上に注目すべき問題として取り上げている。2007年の元旦から始まったこのキャンペーン報道は、翌年のリーマンショックと重なって注目された。低い時給で過酷な労働環境を強いられながらも、ネットカフェで泊まり歩き、中には餓死する若者の姿も報道されている。 ロストジェネレーション世代という言葉は、やがて就職氷河期世代と名を変えつつ、当時25~34歳だった若者もいまや年齢を重ねて35~44歳となり、10年前に比べてやや減少したものの、いまなお厳しい生活を余儀なくされている人も少なくない。 10年前に「フリーター」や「ニート」だった世代は、いまも「非正規社員」や「引きこもり」と呼ばれ、いまなお苦しい生活を送っているのは間違いないだろう。氷河期世代の「無間地獄」という呼び方もされる。 40歳で非正規社員として、時給1000円前後で働き続ける独身の男性は「いまだに1度もボーナスを貰ったことがない」「結婚なんて夢のまた夢」「時給は上がっても物価も上がった」と証言する。 なぜ就職氷河期世代は「捨てられた」のか? 就職氷河期の悲惨さはどの程度だったのか。統計データから見ても、その現実はよくわかる。例えば、大卒の「有効求人倍率」の推移を見ると、就職氷河期に入る直前の1991年には1人の求人に対して求職数は1.4倍あった。しかし、その2年後の1993年には1倍を割り込み0.76倍まで下落する。 以後、2006年(1.06倍)と2007年(1.04倍)を除いて、2014年までの約19年間。わが国の有効求人倍率は1倍を下回って推移する。1999年には0.5倍を割込み0.48倍にまで下落。2人で1社の求人を奪い合う状態になる。リーマンショック時には、0.47倍(2009年)にまで下落している。 ちなみに、アベノミクスの開始とほぼ同時に、有効求人倍率は1倍を回復したのは事実だが、これは団塊世代のリタイアと少子化の深刻化によって人手不足が顕著になったほうが大きい。アベノミクスの成果として、有効求人倍率が1倍を超えたと単純に捉えるのは危険だ。 ここで注目したいのは、就職氷河期世代の中でもいまだに非正規雇用を余儀なくされ、最悪ひきこもりになっている原因はどこにあるのかだ。そこには、個々の責任というよりも、日本特有のさまざまな悪しき制度や仕組みが根本的な原因といえる。同世代が陥った無間地獄の原因と本質をピックアップすると、大きく分けて次の5つのポイントが考えられる。 原因その1◆日本特有の「新卒一括採用」 世界でも例を見ない新卒一括採用が、日本企業の強みであった時代はとっくに終わっているが、就職氷河期世代の人々にとつては最悪の結果をもたらした。新卒以外での中途入社が難しく、とりわけ非正規雇用だった人材の中途採用には慎重な企業が多い。2人に1人しか正社員として就職できなかった就職氷河期世代にとって、その後、正社員として雇用される機会を奪われることになった。 新卒一括採用の背景にあるのが、終身雇用制と年功序列だ。とりわけ、氷河期世代以前の好景気時に大量採用された社員があふれている現実は、運よく正社員になれた就職氷河期世代も、企業の中でこの大量採用組に苦しめられることになる。 原因その2◆大手企業の労働組合が会社側に寝返った? 戦後、日本の労働組合は強い力を持っていた。それが、高度経済成長時代を迎えてバブル景気に沸いた頃には、すっかり企業と仲良しコンビになり、バブル崩壊による大リストラ時代には、企業の言うことを素直に聞く傀儡(かいらい)団体に成り下がってしまった。就職氷河期世代が就職難に喘いでいた頃には、既存の正規社員も自己の雇用を守るのに必死となり、新卒が極端に減少していることにも目をつぶった。 企業別労働組合の限界とも言えるが、「産業別労働組合」や「クラフトユニオン(職種別労働組合)」のシステムに転換していれば、こんな事態にはならなかったかもしれない。企業別労働組合からの脱出を目指す政党が現れないのも、就業者の80%を超す「サラリーマン(正規、非正規などを合計)大国・日本」にとっては不幸な話だ。 原因その3◆小泉政権時代の非正規社員の規制大幅緩和 就職氷河期世代が不幸だったのは、2000年代はじめに小泉政権が誕生し、非正規社員の規制を大幅に緩和したことだ。それまで許されなかった製造業での非正規雇用を全面的に緩和し、その影響で大企業は正社員の採用を大幅に抑え、非正規雇用を増やす雇用構造の転換を進めることができた。 就職氷河期世代の人たちも、この規制緩和がなければ新卒採用されなかった人でも、中途から正社員になる道はかなり多かったはずだ。そういう意味でいえば就職氷河期世代の悲劇は、小泉政権時代の規制緩和によってもたらされたとも言える。 労働条件の非常識な劣悪化 原因その4◆企業本位の労働環境社会 就職氷河期世代を苦しめた背景の1つに、非正規社員を直接雇用しないまま長年使い続ける慣行があった。 日本の製造業を支える工場での労働力をはじめとして、コンビニやファミレスといった安価で質の高いサービスを支えてきたのは、就職氷河期世代を中心とする非正規雇用の人たちだ。先進国の中では最低レベルの賃金で、長時間労働を余儀なくされた同世代が、日本経済を底辺で支えてきた、といっても過言ではない。この非正規労働者を守るための手段がほとんどないのが現実だ。 問題は、そうした過酷な非正規社員の現状を横目で見ながら、労働基準監督署などの労務管理当局が怠慢を続けたことだ。加えて、司法も貧困問題に対して厳格な判断を避け続けてきた。 そもそも日本では、海外では常識になっている企業内でのいじめやパワハラに罰則規定がない。経団連などの反対で罰則規定が外されたのだが、検察や司法がもっと労働者の立場に立っていれば、就職氷河期世代の悲劇はもっと少なくて済んだのかもしれない。 さらに、下請け会社や個人を元受け会社から守る「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」の法整備が行われたのも2003年以降のことだ。 こうした法律の不備や労務管理当局の怠慢が、同世代を苦しめている一因でもある。政府と密接な関係のある芸能プロダクションと所属芸人との間に正式な契約書がなくても通用する――。それが日本の労働環境の常識だとしたら、あまりにお粗末だ。 原因その5◆起業、独立に厳しい社会環境 もう1つ原因があるとすれば、正社員になれなかった就職氷河期世代が、起業して自営業になるという道があったにもかかわらず、その道へあまり進めなかった現実がある。日本では、そういったビジネス環境が整っていないためだ。 何の実績もない若者に事業資金を融資してくれる銀行はほとんどないし、連帯保証人の問題もある。政府の開業資金融資制度も、ハードルが高く、あまり現実的ではない。起業家の才能や熱意を評価して、潤沢な起業資金を融資する投資家が多いアメリカとは大きな違いだ。 ただ、最近は「クラウド・ファンディング」など変革の兆しもある。同世代も、日本に閉じこもっていてはいけないのかもしれない。 支援プログラムが役に立たないこれだけの理由 さて、厚生労働省が今年5月に発表した就職氷河期世代への就職支援プランだが、はたして有効なプランと言えるのか。 施策の方向性としては、「相談、教育、訓練から就職まで切れ目のない支援」を行い、ハローワークに専用窓口を設置。キャリアコンサルティング、生活設計面の相談、職業訓練の助言、求人開拓などの各専門担当者のチーム制によるきめ細かな「伴走型支援」を実施するとしている。 ただ、結論から言うと、就職氷河期世代に対する救済プログラムが本当に機能するのかどうかは疑わしいところだ。例えば、「地域若者サポートステーション」と呼ばれる就労サポート窓口が全国に175カ所設置されているが、40歳以上の就職氷河期世代に対する公的支援は全国でわずか十数カ所開設されるだけだ。 通称「サポステ」も、15~39歳のニートやひきこもりを対象にした制度だが、40歳以上のひきこもりは推計で61万人、サポステ効果も限定的と言わざるをえない。 また前述した特定求職者雇用開発助成金も最大60万円が企業に支払われるが、2018年度に給付された金額はわずかだ。その金額はあまりにも少ない。 筆者の個人的な感想だが、企業にお金を出すのではなく、同世代の非正規雇用者に自立支援金といった名目で、直接資金を融資するほうがいいのではないか。そのお金で起業するのもいいし、海外を放浪してくるのもいい。先進国の多くは、大学を卒業してすぐに就職するのではなく、海外で見聞を広げる制度が充実している。 就職氷河期世代にターゲットを絞って救うプログラムもいいが、本質は「貧困問題」と同じだ。最近になって、NHKも取り上げた「外国人技能実習生の奴隷化」問題にしても、結局は就職氷河期世代だけでは対応しきれなくなった人口減少、人手不足の対応策として、海外の留学生がターゲットにされているだけなのかもしれない。 京アニ放火事件のような凶悪犯罪の加害者をネットでは「無敵の人」と呼ぶ。失うものが何ひとつない、無敵状態の人という意味だ。今後、10年が経過して彼らが45歳から54歳になったとき、日本はどうなっているのか。このロストジェネレーション世代が、その時まだ「無敵の人」であるとしたら、その社会はあまりに理不尽だ。 日本の「失われた20年」と構造改革の失敗 1990年代に始まる日本経済の長期停滞は、2002年には終わらず今も続いており、この間の日本経済を「失われた20年」と呼ばれることが多くなってきた。日本の名目GDPで確認すると、1990年から2010年までほぼ500兆円前後で停滞したまま推移している。他の国がGDPを上昇させる中で、日本だけが成長を止めたまま20年が経過している。(図1)国民一人あたりの名目GDPでは、1990年代に世界3位くらいだったものが、2007年19位、2008年23位、2009年19位と大きく順位を落としている。(図2)日本では物価が上昇しないが給料も上がらないという状況が続いており、消費や投資などの内需が増えていない。産業分野でも、かつて世界を席捲していたエレクトロニクス市場で軒並みシェアを落としている。日本市場では日本製品が幅を利かせているが、海外ではLGやサムソンがシェアのトップ。日本製品は一部のお金持ちの趣味のブラ※4ンドになっている。鉄鋼でも、アルセロール・ミッタルが世界一の生産量を誇っており、新日鉄は中国や韓国のメーカーにも抜かれて4位(2009年)となっている。 小泉政権が主導した構造改革は、日本の成長のためには聖域なき構造改革が必要だという主張の下、三位一体の改革、郵政民営化、各種の規制緩和などが行われたものだ。この構造改革について、改革は必要だったが、結果として都市と地方の格差や国民の貧富の差を拡大し格差社会を進めた、といった意見が多い。改革の路線は間違っていないが、影の部分が大きくなってしまった、という論調だ。私はそうではなく構造改革は成長戦略としても失敗したのだと考えている。先に紹介したように、構造改革が始まった2000年以降現在に至るまで、日本の成長力も国際競争力も低下している。「失われた20年」のうち、2000年以降の10年は構造改革の失敗によるものといっても過言ではない。 ※4 アルセロール・ミッタル ヨーロッパのアルセロールとインドのミッタル・スチールの経営統合によって、2006年に誕生した世界最大の鉄鋼メーカー。年間粗鋼生産量で世界シェアの約10%を占める。 2007年5月21日 ポリシーウォッチャーの役割 「改革の日々が始まった」-2001年4月26日、それはまるで、日本最大のお祭りのようだった。国民的熱狂、聖域なき構造改革、抵抗勢力とのすさまじい戦闘。小泉内閣という奇跡の内閣が誕生した瞬間を、著者はときめきと興奮をもって振り返る。 本書は、従前の日本政治においては考えられなかった異色のリーダー・小泉総理の下、要職を歴任した竹中平蔵氏の挑戦の記録である。「小泉総理の下、日本は間違いなく変わるだろう。そう思ったからこそ私は、大臣就任を引き受けた。これからその変革の『歴史的瞬間』に立ち会いたいと思う。」という書き出しから始まる著者の大臣日誌に基づきながら、不良債権処理、郵政民営化、経済諮問会議の舞台裏が生々しく語られている。 「改革なくして成長なし」-しがらみを持たない強いリーダー小泉総理は、当選回数や派閥からの人事を一切行わず、金融再生プログラムや郵政民営化といった改革を断行した。この改革の中で、重要な役割を果たしたのが、民間出身の経済学者として専門的見地を政策に活かす役割を与えられ、入閣した竹中大臣であった。抵抗勢力のなりふり構わぬ陰謀や策略に遭いながら、いかにして改革を断行したかが、本書の見所になっている。また、本書は、著者の日誌をベースに書かれているため、さまざまな場面が、せりふや感想とともにリアルに語られており、冒険書を読むような面白さがある。そして、随所に見られる小泉総理のリーダーシップも見逃せない。不良債権処理をめぐり、抵抗勢力にののしられ、辞任を迫られる竹中氏に、当て付けのように金融担当大臣兼務を命じる場面や与党幹部の夕食会で、郵政民営化の「基本方針は絶対変えない。ちゃんと理解しておけ。自民党はとんでもない男を総裁にしたんだ」と、反対を強める党側へ迫力の宣戦布告をする場面などは圧巻である。 さて、よく小泉政権に対して、「劇場型内閣」「骨抜きの政策」だなどと、人気があるが中味のない政権であるかのような批判があったが、本書を読む限り、骨抜きではない改革が実行されたように思える。小泉内閣の改革の成果については議論のあるところだが、少なくとも、日本の経済再生のために、以前から散々問題視されながら放置されていた不良債権処理に着手し、金融再生プログラム(竹中プラン)を実行、りそな銀行への公的資金注入など、金融改革を断行したことは、評価できるのではないか。 なぜ、今まで散々先送りされてきた金融改革を断行できたのか?なぜ、総選挙を行うほどの抵抗に遭った郵政民営化法案が成立したのか?もちろん、歴史的な国民の支持と小泉総理のリーダーシップがあったことは確かだが、改革を主導した竹中大臣の専門家としての力が大きかったことは間違いない。竹中氏は、「骨太方針」の決定、「工程表」の作成、そして「戦略は細部に宿る」という共通認識のもと、官僚の思うがままに作られていた「政策の制度設計」を大臣自らが詳細に作るという「政策決定プロセス」によって、総理の意思を貫く、政治主導型の改革を実現していく。特に、制度設計は、従来、官僚「霞ヶ関文学」の専売特許であり、その知恵は官僚に独占されていた。竹中氏は、30年間「政策」を勉強してきた「政策研究者」として、政策の重要性を理解し、政策の骨組み、つまり法律の条文や施行後の運用ルールなどを詳細に検討。抵抗や妨害、骨抜きにされることを予測し、常に二手三手先を読みながら作戦を練り、抵抗勢力との合意形成に挑む。そして、譲れないところは妥協せず、打開点を探る戦略家の一面も見せる。「普通のこと」がなかなか実現できない日本において、実行力のある改革を断行するポイントは、この「政策」「政策決定プロセス」をいかにうまくやるかにあったようだ。 著者自身は、自らの大臣経験を振り返って「昆虫学者が昆虫になったようなものだ」と語っている。小泉総理の熱意に共感して、自分が研究していた対象の世界に足を踏み入れ、自らが研究の客体となったわけである。自らがプレーヤーとして、官僚の無謬性と戦い、業界・政治家・官僚の「鉄のトライアングル」へ挑戦し、マスコミや学者から激しいバッシングを受け、戸惑い、悩み、立ち向かっていく。この得難い体験を通して、「政策は難しい」ことを実感する。また、「優れた植物学者が、即優れた庭師である保証はなにもない」のと同じように「経済学や政治学は間違いなく政策のために必要ではあるが、政策の専門家と経済学者、政治学者は同じではない」と説明する。そして、評論や絵空事を言う学者ではなく、実務的な知恵と将来的なシナリオを描ける「政策専門家=ポリシーウォッチャー」が必要であると主張する。 ポリシーウォッチャーの役割は、政策の調査研究、分析評価、監視、提言を行うことと情報発信を行うことである。特に情報発信を通して正しい世論を形成することで、「よく知らされた国民」(Well informed public)を生み出すと著者は言う。情報は溢れているが、スキャンダルやゴシップネタばかりで本当に有益な情報(政策論議や政策分析)となると極端に少ないというのが現状ではないだろうか。小泉政権を通して、また最近の政治からも、世論の力、国民の支持の重要性が注目されている。国民が適切な判断を行うことで、良い政策が生まれ、さらに政策が実行されているかを評価監視することで、政策がより良い方向に向かうという好循環が生まれるというわけである。 「政策は難しい」という難問にどう立ち向かうのか。著者は、「政府の中核で政策を実行した経験を、政策専門家の育成に役立て、民主主義のインフラとして、政策専門家が民間部門から政府の政策をしっかりウォッチし、国民に伝えるという機能を果たしていきたい」と決意を語っている。ポリシーウォッチャーを通した「民主主義による世論の後押し、政治主導の構造改革、力強い日本」の実現。竹中氏の挑戦は、まだまだ続きそうである。 2006年09月20日 小泉構造改革が残したもの 森重 透 1.「いざなぎ超え」とは言うけれど マクロ経済は、長期にわたったデフレ局面からの脱却を視界に入れつつ、足もとなお拡大を続けている。2002年2月から始まった今回の景気回復は、すでにこの5月に「平成バブル景気」を抜き去り、11月には「いざなぎ景気」(1965~70年、57ヶ月)を超え、戦後最長となりそうな勢いだ。 しかし、実質GDPの伸びで見た景気拡張期間はなるほど長かったかもしれないが、国民一人ひとりの生活実感から見れば、まさに「実感なき景気回復」ではなかっただろうか。そして、それはなぜかを考えれば、今回の回復局面の特徴が明らかになろう。 まず、息の長い回復ではあるが低いレベルの成長だったことだ。「いざなぎ」は年平均成長率10%超、「平成」は5%程度だったが、今回は2%強と「平成」の半分にも及ばないレベルである。成長率と拡張期間の積和でこの間の実質GDPの伸びを見ても、「いざなぎ」当時は約1.7倍であるのに比べ、今回は1.1倍程度に過ぎず、さらに名目GDPの伸びで見れば、その差は2倍以上にも拡がる。横綱と前頭筆頭ぐらいの差はあるのではないか。とくに、緩やかなデフレ下の回復のため名目値がほとんど伸びなかったことは、実感の乏しさをより強めたはずである。 二番目の特徴は、企業部門と家計部門の所得状況の違いだ。「経済財政白書」(7月)には、「企業部門の改善によって家計にも好影響が及ぶ好循環がみられる」趣旨が盛り込まれているが、雇用環境には目に見える改善があるとはいえ、賃金・可処分所得関係の統計では、むしろ家計の疲弊ぶりが顕著であり、4年以上も続いているのに景気回復の恩恵は家計・個人にはほとんど及んでいない、と言ってよい。企業部門から家計部門への波及(トリクル・ダウン)の遅れは、企業が業績好調にもかかわらず、賃上げ幅を低く抑え続けているからである。今回の景気回復は、大企業の資本の論理、すなわち、リストラ、非正規雇用の拡大等による賃金コスト削減をバネにもたらされた側面が大きいが、それがまだ続いているということだ。 そのほかの特徴としては、米国経済の好調や中国特需などに支えられた外需主導、デジタル家電ブーム等、一部の大企業・製造業に偏った回復であったことなどから、多くの中小企業や非製造業への波及が遅れていることも挙げられる。また、地域間で景気回復のテンポや景況感に大きな格差があり、これがなかなか縮まらないことも、全体的に景気回復を身近に感じられない要因の一つだろう。 2.二極化・分断化の進行 このように、マクロ面で見れば、実感が乏しいとはいえ息の長い景気回復が実現したことは事実である。しかし、この回復が、間もなく終結を迎えようとする小泉内閣の構造改革の取組みによってもたらされたか、ということになると疑問符が付く。「構造改革なくして回復(成長)なし」、「官から民へ」、「中央から地方へ」を標榜した構造改革路線が、スローガン通りの実行力を伴ったものでなく、今回の景気回復とは無関係であることは、すでに本コラムでも何度か指摘した。また今年の「経済財政白書」(7月)も、企業の適応努力こそが日本経済回復の主役と正当に位置づけているし、多くの識者の見方もこれに沿うものが圧倒的に多い。 むしろそのことよりも、この小泉政権下の経済運営によって、構造的には深刻な問題が発生した。経済社会の二極化・分断化の進行、社会生活基盤の劣化、という由々しき問題である。下掲グラフは年齢階級別完全失業率だが、15~24歳の若年層の失業率・学卒未就職率は、この間一段と上昇し、高止まりしていると言ってよい状況である。失業こそは、一個人を社会的・経済的弱者に転落させるもので、とくに若年層で定職に就かない者がなお多く存在するという現実は、これからの日本の国力や競争力、社会保障システムへの悪影響を考えると憂慮させるものがある。 さらに、パート、アルバイト、派遣社員など「非正規雇用者」は、すでに雇用者数の約3人に1人となった。ここでも若年層(15~34歳)の雇用情勢は厳しく、失業の長期化、フリーターやニートの増加、そしてフリーター経験をプラスに評価している企業がほとんどないことから、彼らが中高年になっても非正規雇用者にとどまってしまう懸念がある。こうなると、4対1とも言われる正社員との給与格差が固定化されるとともに、累積的に所得格差が拡がり、生活基盤の劣化、ひいては非婚・少子化などの様々な問題を助長する恐れがあるのだ。過重な労働実態、過労による労災件数の増大、ワーキングプアの増加、うつ病、突然死など、今日、雇用の劣化あるいは崩壊とも呼べる事例は枚挙にいとまがない。 このような状況も反映してか、7月に発表されたOECDの「対日経済審査報告書」によれば、先進30カ国の相対的貧困率(平均値に比べて所得が半分未満の相対的貧困層の割合)で、日本は米国(13.7%)に次ぐ二番目の高さ(13.5%)だったそうだ。そして、労働市場の二極化傾向の固定化の恐れを警告され、格差是正の具体策として、非正社員への社会保険の適用などを指摘されているのである。 このほかにも、大企業と中小企業、都会と地方、高齢層と若年層、官と民等々・・・規模・地域・年齢・官民間に存在する諸々の二極分化(格差の拡大と固定化)の問題を真摯にとらえ、これを是正しながら持続的成長を模索していくというような、「徳のある経済政策」は、小泉政権下ではついにお目にかかれなかったと言ってよい。 3.何が欠けていたのか 「聖域なき構造改革」という看板を掲げた小泉構造改革路線は、約5年半に及んだ小泉政権のバックボーンであったはずなのに、結局それは、「小泉劇場」の主役・小泉純一郎が大見えを切るときの小道具に過ぎなかったようだ。 新規国債発行30兆円枠の公約は、「この程度の約束を守れなかったというのは大したことではない」と言って、簡単に破られてしまった。公的年金改革を審議する年金国会での、「人生いろいろ」発言に見られるような、おちゃらかし発言。はぐらかしや、レトリック依存型の国会答弁も多く見られた。地方の景気にも目配りすべきではないかとの記者の問いに、小泉首相は「官から民への流れは変わらない。政府が口出しすべきではない」と答えたそうだ。道路公団の「民営化」は、結局、妥協の産物に終わった。そして、改革の「本丸」と意気込んだ「郵政民営化」は、その意味や効果が不鮮明なまま、分社化を伴う株式会社化で行き暮れようとしている。結局、高い人気に支えられ、連日劇場は満員御礼だったが、バックボーンは最後まで「小道具」で終わった。 「改革なくして景気回復なし」の名の下に、実体的な景気対策には関心が薄く、かと言って、公的セクターの改革、すなわち、責任ある社会インフラの構築と質の高い公共サービスの供給という、「民」が果たせない「官」の固有の役割というものを、いかに実効ある形で遂行していくかといった制度問題を、徹底的に真摯に議論する風でもない。詰めた議論よりは、歯切れの良い「ワン・フレーズ」で「改革」をくさびとして使い、多くの「抵抗勢力」を放逐しつつ人気を得ていくという手法は、まさに独壇場と言えるものだった。 しかし、「改革の本丸」であるべき財政再建問題と、これに密接にからむ社会保障制度と税制のあり方に関する真摯かつ周到な議論と実践を抜きにしては、「経世済民」を託された責任ある政治家としての本務は果たせないのではないか。「ノブレス・オブリージュ」とは、財産、権力、社会的地位には責任が伴うことを言う。小泉首相に限らず、政治家全員がこのことを心に銘じるべきだろう。 【小泉純一郎②】聖域なき構造改革の功罪 小泉政権は「聖域なき構造改革」を打ち出しているが、この実現可能性について、マーケットは非常に大きな不信感をもっている。 ■ 矛盾だらけの経済政策を繰り返すな なぜ不信感をもっているのか。その理由は、日本がまた、いつもと同じような失敗を繰り返すのではないか、という懸念が拭い去れないことにある。日本はいつも、過去になぜ失敗したのかという事後的な点検が行われないままに、次の政策を展開しようとする。そして、いつも矛盾 ばかりの政策を展開する。つまり「こんなことをやります」と言っておきながら、実はそれとは違うことをやってきた。その典型的な例がペイオフの延期だ。今回の「骨太の方針」のなかで、そうした懸念をいちばん強く感じたのは不良債権問題に関する部分だった。まずは、それを中心に話を進めよう。 「骨太の方針」、すなわち経済財政諮問会議の基本方針は、不良債権処理に関しては、2001年4月6日に経済対策閣僚会議で決定された緊急経済対策の考え方を継承している。緊急経済対策には、問題の本質をついた、さまざまないい意見が書かれているが、その大きな目玉は、やはり不良債権処理が最大の課題である、というものだった。 ちなみに、それより少し前の3月19日に日銀は政策決定会合で「通常では行われないような、思い切った金融緩和に踏み切る」ことを決定しているが、その議事録のなかにも、不良債権問題の解決が急務であるという趣旨の文章が入っている。 こうした流れからいくと、4月6日の時点での政策の結論は、やはり不良債権処理が最重要課題だ、というものだったといえる。 最近、不良債権を「2~3年以内に処理する」という言葉の意味が議論されないまま、独り歩きしている感があるが、緊急経済対策のなかには、主要行について、「破綻懸念先以下の債権に区分されているものについては、原則として2営業年度以内にオフバランス化につながる措置を講ずる」、それから、新規発生分については「原則として3営業年度以内に......措置を講ずる」と書かれている。 これは非常に重要なポイントだ。なぜなら、この「措置を講ずる」という表現は、金融監督庁のマニュアル、あるいは旧大蔵省の行政に従ってやってきた過去の金融再編行政では、不良債権は解決しない。今までのやり方を白紙に戻して、2~3年以内に不良債権をかたづけよう、という強い意思表明の表れだからだ。 今回の基本方針も、この方針に沿って、「不良債権問題を2~3年以内に解決することを目指す」、「経済再生の第一歩として、不良債権の処理を急ぐべきである」とはっきり書いてある。多くの人はこれを読んで、正しい方向に動いていると思うだろう。ところが、である。今回の基本方針には、不良債権の最終処理は「金融機関の自主的な判断で進められる」というくだりが入っている。 これでは、全く話が違ってしまっている。4月の緊急経済対策で、「過去の行政のもとで、金融機関が自主的に問題に取り組んできたけれども、そのやり方では解決しない。政府が主導権をとって、2~3年以内に解決させる」という強い意思表明をしたにもかかわらず、ここでまた、「自主的な判断で進められる」ということでは、議論するまでもなく、問題解決にはならないだろう。 ちなみに、不良債権問題の裏側にある借り手企業/産業については、私的整理のためのガイドラインを「関係者間で早急に取りまとめることが期待される」と書いてある。 もちろん日本の場合、「期待される」、あるいは「自主的な判断で進められる」といった場合、それは国が強制的にやるといっているのと同じだという解釈もないわけでもないが、それは一昔前の行政のあり方を反映した解釈だ。つまりそれは、不透明な、玉虫色的なやり方にもなっているということだ。 ■ さまざまな数字が独り歩きをしている それに、緊急経済対策にも、踏み込み不足だった点がある。ひとつは、対象を全預金取扱金融機関ではなく、主要行に限定していたこと。もうひとつは破綻懸念先以下の不良債権に絞って話をしていたということだ。 詳細は省くが、これでは、ペイオフ延期などの過去の政策との整合性がないばかりか(ペイオフ延期のときは、主要行は大丈夫だが、信金や信組などは検査不十分で不安だから、という説明がなされた)、不良債権問題を全体的に把握することはできない。いうまでもなく、マーケットが非常に神経質に注意を払っているのは、不良債権の全体の大きさだ。ところが、上述したように、限定した見方をとっているために、いろいろな数字が独り歩きをしてしまっている。 例えば、一時期新聞を賑わせた12兆~13兆円という数字は、主要行の破綻懸念先以下のものを指している。しかし全銀行ベースの問題債権は64兆円で、全預金取扱金融機関ベースでは81兆円くらいあるとされている。また最近では、151兆円という数字が独り歩きをしている。これは民主党が金融庁から取り寄せた数字で、要注意債権以下の債権をもっている借入先の全借入金を示している。 われわれプロでも、これらの数字の使い方にはものすごく苦労している。この間、民主党の鳩山氏が「150兆円という数字をどう思うか、大手行の資産査定を厳格にやり直すべきだ」という趣旨の発言をしたところ、首相は「元利払いや貸出条件に問題がなく、単に注意が必要な債権は100兆円ある」と答えた。この発言は、要管理債権以下の不良債権以外の要注意債権が100兆円ある、ということだが、公表ベースでは、こういう数字は出てこない。一国の総理大臣が、国会でこのような答弁をしていることからもわかるように、問題の大きさがどれくらいであるのか誰にもわからず、マーケットは政府に対して依然として不信感をもっているのである。 ■ 危機対応の制度的枠組みが不在 マーケットが不信感をもっている第2の理由として、金融再編の枠組みが不在だということが指摘できる。2001年1月には行革の一角として金融再生委員会が廃止された。金融再生委員会は、金融問題を解決するために特別につくられた組織だったにもかかわらず、その仕事が終わる前に廃止されてしまった。日野正晴前長官は退官のインタビューで(『日本経済新聞』2001年2月2日)、「本当はペイオフ1年延期時に、それと連動して金融再生委員会や再生法、健全化法も延長すべきだったが、議員立法なのでこうなってしまった」と述べている。筆者も全く同感である。3月末には、資本増強の枠組みも期限切れとなってしまった。 そしてその6日後に政府は公式見解として(緊急経済対策)、不良債権が日本経済のいちばん大きな問題だ、この問題に集中的に取り組む、ということを表明した。1998年にも同じ議論があり、問題解決のために60兆円のパッケージと金融再生委員会をつくった。その枠組みを廃止した途端に、改めて問題の重要性、枠組みの必要性が認められるというのは、酷評すれば、先進国の経済政策としては大問題だ。少なくとも説明責任というものがある。そうしたことを議論しないで、ポッポッと次の政策が出てくるというのはいかがなものか。 もっとも、枠組みがないというのは多少言いすぎで、実は金融危機対応枠組みというものが4月1日からスタートしている。それは資本増強、国有化、(ペイオフコスト以上の)預金者保護という3つの機能を持ち備えている。 ただ問題は、危機がなければこの枠組みが使えないということだ。これに対し98年の枠組みは、危機の産物としてできたもので、危機がなくても、危機が起こらないように使うことができた。 こうして、不良債権問題の重要性に対する認識と、その問題を解決するために用いる制度的枠組みとの間に、大きな空白ができている。そうした空白があるからこそ、いろいろな方針や意見が錯綜しているといえる。つまり枠組みがないから、金融機関が自主的判断ベースでやるしかないということになっている。だが、金融機関の自主的判断ベースではこの問題は解決されないことは目に見えている。自主的ベースでできるような話であれば、とっくの昔に解決しているはずだからだ。 ■「財政再建」重視の危うさ 第3に、小泉首相が財政再建を最重要視しているのではないか、ということだ。首相の所信表明演説を見ると、「不良債権処理や資本市場の構造改革を重視する政策へと舵取りを行う」とし、1に不良債権問題の解決、2に規制緩和、3に財政再建を行う、と述べている。筆者はこのポリシーミックスと順序づけにはおおむね賛成だが、小泉内閣が実際にやっていること、あるいは発信しているメッセージを見ていると、不良債権処理がかなり後退している感じを受ける。特に、上述したように、「措置を講ずる」が「自主的判断で進められる」というように後退しているのが気になる。むしろ第3の財政再建をアジェンダの上位にしようとしているらしい。 例えばここ2カ月間の議論をみると、田中真紀子氏が多くの話題を提供してきたが、それはともかく、経済面では新規国債発行を30兆円以内に抑制するなど、財政再建の話題でもちきりだった。だが経済の現状を考えると、財政再建に今踏み込むことは非常に厳しい緊縮財政になりかねない。すると不良債権問題の先送りと財政再建の優先という、橋本政権のときと全く同じポリシーミックスとなってしまう。 こうして、橋本、小渕、森の各政権から得られたはずの教訓が生かされず、また元に戻ろうとしており、"不思議の国のアリス"のような経済政策になっている。 ■ 構造改革断行の2つの選択肢 以上、小泉内閣の経済政策・構造改革の基本方針について検討を加えてきたが、これらの一連の議論を見ていて、問題だと感じるのは、政府がどちらの方向に進もうとしているのか、その方向性が見えないということだ。 改革を断行するに当たり、政府には大きく分けて2つの選択肢がある。ひとつは期限を区切ったうえで、自ら主導権を発揮して改革を進めることだ。この場合は、金融再生に向けた新しい枠組みづくりと、危機を未然に防ぐための公的資金の投入が必要になる。またマーケット・メカニズムを最大限活用し、新しいマーケットが育成されるようなやり方をとる必要がある。 もうひとつは、市場に任せるという、まさにハード・ランディング的な解決策だ。この場合は、ペイオフの早期実施と、金融危機対応枠組みを極力使わないという覚悟、それに労働市場、小口預金者保護などのさまざまなセーフティ・ネットが必要になる。加えて、緩和的なマクロ政策と、規制緩和などの、経済体質を強化するためのミクロ政策を次々と実施しなくてはならない。 後述するように、筆者は前者の政策を取るべきだと思っているが、今のところ、小泉政権がどちらの方向に進もうとしているのかが見えない。むしろ、このどちらでもなく、中間の道を歩んでいるようにも見えるのである。すなわち、危機が起きると政府が動き、その際、マーケットを阻止するような政策を取るという、これまでと同じ過ちにはまってしまう可能性がある。 公的資金の投入や銀行保有株式取得機構の設置、それに貸し渋り対策などで、政府は銀行に対してあらゆるところで関与を強めている。これでは、マーケットに任せるという2つ目の選択肢は取りえない。こうした状況では真の意味でのマーケット・ベースということはできない。それにもかかわらず「金融機関の自主的な判断で進められる」という表現を用いたりするので、混乱が生じることになるのである。 国が関与することにさまざまな弊害があるのは十分承知しているが、筆者は、ここまで国が関与を強めている以上、国が主導権を握り、期限を区切って市場を生かす形で改革を断行したほうがいいと考えている。ところが、では主導権を発揮しているかといえば、それも中途半端な状態にある。 実は私は財政再建の信者だが、一回限りの措置として、金融問題の解決のために公的資金を30兆円入れるということを断行すれば、日銀はそれを支援するだろうし、それが2年後のマーケットの発展につながるということであれば、マーケットもそれを評価するのではないか。だが、小泉首相は財政再建という目標があるために、公的資金を投入するという流れをつくれないでいる。こうしたことから、マーケットから見ると、財政再建を優先していることが、実は不良債権を断固として処理するという腹が固まっていない、と見えてしまうのである。 ■今は財政再建を打ち出すな では、具体的に小泉首相はどういったアクションを起こすべきか。 まず、今の局面では財政再建を打ち出さないことが必要だ。今財政再建を打ち出すと、それはものすごい緊縮財政になってしまう。 仮に出すにしても、出し方を工夫すべきだ。実は財政構造改革と財政再建は違う。財政構造改革というのは、財投改革や公的金融機関の民営化、あるいは効率的な税制システムの構築などのミクロ的な改革だ。これは今すぐにでも実行できるし、これをすぐに行うことには筆者も大賛成である。 一方で、今の経済局面のなかで、どれだけの財政出動が必要なのかという問題がある。これが財政再建の問題だ。日本の場合は、この2つの概念がいつもこんがらがってしまっている。前総理の橋本氏も、財政再建を実現したかったために財政出動を締めたが、本当の財政再建は、経済を回復させなければ成り立たない。そこで、では経済を本当に回復させるには何が必要なのか、という議論が、財政再建の中枢にくるはずだ。 そこで、不良債権がいちばんのネックであるという判断なら、それをやるべきだし、非効率的な財政の仕組みの問題であるなら、それを見直す必要がある。そのなかで必要に応じて財政出動をすることもありうべき選択肢だろう。預金者保護と不良債権処理を同時に達成するためには、例えば30兆円というコストがかかることもあるかもしれない。この場合は、短期的には財政再建はできなかったということになる。 つまり、すべての政策目標、特に矛盾しあっているいくつかの政策を同時に達成することはできない。それなのに、あれもやる、これもやると主張するのは、部分的な発想でしかない。まず不良債権処理に重点を置くべきである。 財政再建は確かに重要な課題ではあるが、それが本当に緊急の課題がどうかを考えると、実はそうでもない。ひとつは、日本のマクロ的な現状をみると、民間部門の黒字を政府が吸収しているという面がある。そうなると、問題は個人の将来不安が解消されていないから、また規制緩和が不十分で日本企業の投資プロジェクトに問題があるから、あるいは金融システムが十分に機能していないから、民間部門が活性化されない、ということになる。 この問題を解決するには、IT関連を中心に規制緩和を実行することだ。そうすれば、さまざまな形で、新しい需要と新しい投資機会が生まれてくる。そして結果として、税収が増えて、政府の赤字も減っていく。 もうひとつは、国債の利回りだ。これは現在1.2%程度であり、財政再建をやらなければ日本は破綻する、というメッセージをマーケットは発信してはいない。しかし小泉政権は、あたかもそうしたメッセージが発せられているかのように動いている。橋本政権時の増税と同じく、小泉政権でもプライマリーバランスの赤字を支出削減で抑えようとしているが、それは因果関係を間違えている。まず解決すべきは不良債権問題である。 ■戦略的にマーケットを活用せよ そこで、不良債権処理を進めることを考えるとき、ぜひ指摘しておきたいことは、戦略的に、マーケット・メカニズムを最大限に生かすことが重要だということだ。これは、政府が主導権を取るという方向とは、一見矛盾しているように見えるがそうではない。例えば、しばしば引き合いに出されるアメリカのRTC(整理信託公社)は、預金の全額保護をせずに、破綻懸念の金融機関をつぶして、預金保険機構でカバーされていない人たちに債権カットに応じさせた。同時に、RTCは資産を取って、資産価値と預金保険機構でカバーされている額との差額を埋めた。これは預金者保護の鉄則です。そのうえで、受け取った資産をすぐさま売却した。 RTCがそうしたように、資産を売却すると、非常に大きなマーケットが育成される。現在、非常に大きな規模になっているCDO(Convertible Debt Obligations)やABS(資産担保証券)は、実はRTCが登場するまではなかった。これが、マーケット・メカニズムを最大限生かすということの意味だ。銀行の国有化や買取機構、それにペイオフの延期といったやり方は、やはり問題だろう。 ただ、日本の現状を見ると、残念ながら現に政府はそれをしていないし、今までの経験から見ても、ほとんどやる意思とやる能力がなさそうである。 今後の政策の展開次第では、金融は、おかしなことをやる可能性がある。政府の要人はいろいろなところで、低成長には甘んじなければならないけれども、マイナス成長はだめだと発言しだしている。一方で財政再建論者が趨勢を握ったとすれば、やはり金融危機が起こる。そして財政再建プラス金融危機イコールマイナス成長となったとき、マーケット・ベースで進まないような手を考え出してくる可能性がある。ペイオフ延期はないにしても、危機対応枠組みを使って実質的な全額保護の延長をやりかねないなどの危険性が残っているのである。 日本人の間では、金融危機が起きたときに危機を止めるのは政府の要件だから、それも仕方がない、という考え方があるようだが、それは違う。そもそも不良債権があるから危機が起きるのであって、危機を封じ込めたければ、そうした全面保護のような形で政府が対応するのではなく、まず政府が主導権を取って不良債権を処理すべきなのである。そうでないと、金融危機対応枠組みがまた悪用されることになってしまう。 この論文で検討してきたようなポリシーミックスを実現するには、本来なら経済財政諮問会議のようなところで総合的に調整する必要がある。その点では、竹中氏も精いっぱい努力しておられるようだが、まだ理想的な形には至っていないと思っている。現在の小泉政権には、政策を立案する陣容はあっても、それを実行に移していくというシステムがない。それが小泉政権のアキレス腱ともなっている。 ここまで小泉政権に対して、批判的な検討を加えてきたが、小泉政権は、構造改革を断行すると述べている内閣であり、その意味では期待もしている。これまでと同じような愚を犯すことなく、構造改革に踏み込んでいってほしいと思っている。それが日本経済を停滞から脱却させる道である。〈了〉 ウクライナのコルスンスキー駐日大使「北方領土はロシアに占領された日本の主権領土だ」 2024年2月8日 ウクライナのコルスンスキー駐日大使は2024年2月7日、日本が同日に「北方領土の日」を迎えたのに合わせ、北方領土はロシアに占領された日本の領土だと、自身のX(旧ツイッター)に投稿した。 コルスンスキー氏は、「今日改めて申し上げたいのは、北方領土はロシアに占領された日本の主権領土であるということだ」と強調した。その上で、「私たちは、ロシアが再び敗北し、占領されたすべての土地が虜囚の地から解放されるその日まで、共に歩んでいかなければなりません」と訴えた。 中国企業が「大谷翔平」を勝手に商標申請! 「大谷翔平」の人気ぶりに目を付けた中国の全く無関係の企業が「大谷翔平」の名前を商標申請した! これを中国政府が認めたら日米中で大問題に! 日米中で次に起きることが想像されます・・ 2024年2月26日 中国で野球はマイナースポーツだったがこの数年、人気が上昇し、ロサンゼルス・ドジャースに移籍した大谷翔平(29)の活躍なども中国メディアが大きく報じるようになっている。その人気ぶりに目を付けた中国の全く無関係の企業が「大谷翔平」の名前を商標申請したという。 以前から、中国で日本のブランド名やキャラクター名が無関係の企業に勝手に商標登録され問題となることがあった。 ウルトラマンの中国語「奥徳曼」が中国国内で商標登録され、円谷プロダクションに無断で映画が製作されたことがあった。 日本の「無印良品」を展開している株式会社良品計画が中国に進出する際、「無印良品」というブランド名を先に商標登録していた中国企業に提訴され、本家であるはずの良品計画が敗訴するという事件も起きた。さらに良品計画が敗訴のことをリリースで公表すると、中国企業が名誉毀損で訴えるという事態にもなった。 ××××××××××××××××××××××××× 中国、ロシア、韓国はトラブルの温床。 武漢ウイルス研究所から世界中にばらまかれた・・武漢ウイルス研究所内の愉快犯か? ××××××××××××××××××××××××× こんな国やこんな友達と付き合ってはいけない・・・ ××××××××××××××××××××××××× |