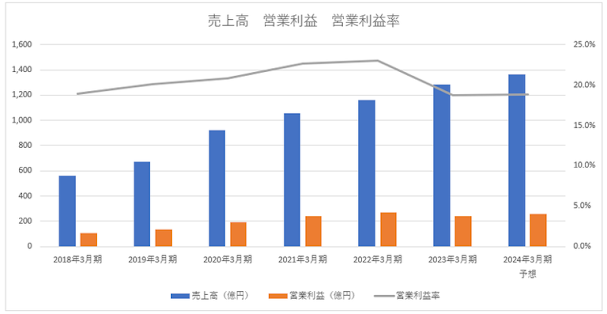2024年10月登場予定のスズキ スペーシアギア。
2024年10月登場予定のスズキ スペーシアギア。すでに高い評価を得ている新型スペーシアをベースに、内外装にSUVテイストを盛り込んだスペーシアギアがラインナップに加わる計画。もちろん撥水加工シート採用だ(ベストカー編集部作成の予想CG)
2024年には新型スペーシアギアが発売され、N-BOXにもSUV風のジョイが加わる。スーパーハイトワゴンにSUV風の仕様が揃う。
新型スペーシアギアの実質的なプロトタイプは、東京オートサロン2024に「スペーシア・パパボクキッチン」の名称で出展された。N-BOXも丸型ヘッドランプの標準ボディをSUV風に変更した仕様だから、外観は想像できるが、荷室などの詳細な仕上がりや価格は不明だ。 また新型スペーシアギアの後席には、オットマンのように使えて、座席の上に置いた荷物が床に落ちにくいマルチユースフラップが備わる。収納設備も豊富で、燃費性能は優秀だ。N-BOXジョイは、後席を格納するとスーパーハイトワゴンの中でも特に広い荷室に変更され、快適な乗り心地でも注目される。
⓴【これから車好きになる方へ:ビギナードライバー】
自動停止機能を試して?知人2人はねた疑い 軽乗用車運転の男を逮捕
2024年2月14日
軽乗用車の自動停止の機能を試そうとして知人2人をはねて重軽傷を負わせたとして、兵庫県警は2024年2月14日、神河町のアルバイトの男(67)を自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致傷)の疑いで現行犯逮捕し、発表した。「自分が運転してぶつかった」と容疑を認めているという。
福崎署によると、男は2024年2月14日同日午前11時40分ごろ、神河町内の駐車場で、軽乗用車をバックで走らせ、後方に立っていた70代の知人男性2人に衝突し、けがを負わせた疑いがある。1人は頭の骨が折れる重傷、もう1人は頭に軽傷という。
3人はバック運転の際、人や物を感知して自動停止する機能を試そうしたが、実際には止まらなかった、と署に説明しているという。
署は、この車にそうした自動停止の機能がついていたかどうかを含め、事故の原因を調べている。(天野剛志)
自動ブレーキが搭載されているからといって、事故を防ぎきれるわけではありません。自動ブレーキの機能的な面と、ドライバーの認識の面で問題があるからです。
機能的な面では、システムに不具合がなくても、障害物があるときにブレーキが働かないケースや、安全な場面で自動ブレーキが作動するケースが発生しています。
国土交通省には、2017年のうちに340件の自動ブレーキの不具合が寄せられました。そのうちの73%が勝手に作動した事例で、26%が作動しなかった事例。事故に及んだのは全体の24%(82件)でした。
認識の面では、自動ブレーキへの過信が問題となっています。自動ブレーキは「衝突被害軽減ブレーキ」ともいわれるように、あくまで「被害の軽減をサポートする」もの。ですが、JAFが実施したアンケートによると、約半数が自動ブレーキの機能を過信していることが明るみに出ました。
「ニュースやCMなどで話題の『自動ブレーキ』や『ぶつからない車』と聞いて、どのような装置を想像するか」とたずねたところ、「衝突の危険があるときに、音や警告灯でその危険を促し、車が自動的にブレーキをかけて衝突を回避したり被害を軽減したりする装置」という正しい選択肢を選んだのは55%でした。40%は「前方の車や障害物などに対し、車が自動的にブレーキをかけて停止してくれる装置」を選び、残りの5%も自動ブレーキの機能を過信している回答を選択。回答者の45%が間違って理解していることが分かりました。
2018年2月には、自動ブレーキなどの安全装置を搭載した車が対向車線を越えて歩道に侵入したにもかかわらず、自動ブレーキなどが作動せずに、歩行者が死亡するという痛ましい事件が起きています。こうした事故も、自動ブレーキの機能を正しく理解していれば防げたかもしれません。
自動ブレーキが働かないのはどんなとき?
万能とはいえない自動ブレーキ。では、自動ブレーキが働かないのはどんな条件のときでしょうか。
▼メーカーの定める速度を超えているとき
自動ブレーキが働く速度はメーカーや車種によって決まっています。その速度を超えてしまうと、障害物を検知できない場合があります。
▼暗い道路や激しい雨など、周りの環境が悪いとき
周囲の環境によっては正しく作動しない場合があります。暗い道路や激しい雨のように、著しく視界が悪くなる状況では、障害物を検知しにくくなってしまいます。早朝や夕方の太陽が逆光になる状況でも注意が必要です。はじめは障害物を検知していても、検知用のカメラに光が差し込むと障害物を見失ってしまい、ブレーキが解除されるといったこともありえます。
▼道路の状態が悪い時
路面状況も衝突被害低減の効果に大きな影響を与えます。雪道や急な坂道はブレーキが利いてから止まるまでの距離が延びてしまうため、衝突を回避できないことがあるのです。
▼突然人や車が飛び出してきたとき
自動ブレーキは、人や自動車の飛び出しに対応できません。急カーブや急ハンドルの場合も止まれない可能性があります。
▼子どもや動物などが対象のとき
子どもや動物、細いポールなどは検知ができない場合があります。先行車両の後ろの形や、車両・歩行者の服の色によっても作動しないことがあります。
自動ブレーキは「万が一」のサポート機能
なお注意したいのは、メーカーや車種によって、作動する速度や条件は異なるということです。
たとえばトヨタの自動ブレーキは、障害物を検知できる速度は時速10~80kmの間ですが、歩行者との衝突を回避できるのは時速40kmまで。日産のある車種では、時速30km以下で走っている場合しか歩行者との衝突を避けられません。自動ブレーキが作動する条件は取扱説明書で説明されているので、よく読んで自動ブレーキの作動条件を理解しておくことが必要でしょう。
自動ブレーキは、補助機能として利用することで、起きていたかもしれない追突事故などを防ぐことができます。あくまで人が主体となって車を運転するという気持ちを忘れずにいたい。
■自動運転とヒューマンエラー
自動運転ラボでは、ヒューマンエラーによる自動運転の事故について、事故のパターンをまとめた記事を公開している。
実証実験や実運用による過失としては、セーフティドライバーによる操作ミスや判断ミス、遠隔オペレーターによるヒューマンエラーが挙げられ、そのほか、ハードウェア面の整備・メンテナンス、ソフトウェアの管理・メンテナンスなども考えられる。
自動運転による移動サービスで人の手が必要となる場合は、こうしたヒューマンエラーをどう防ぐのか、といった視点も重要となる。例えば、手動運転に切り替えた際も致命的なミスを犯していないか監視する機能などが、今後は重要となってくる。
【参考】詳しくは「自動運転、ヒューマンエラーによる事故パターンまとめ」を参照。
■【まとめ】事故を教訓に技術レベルの向上を
人間による運転の事故率より自動運転での事故率が低くなれば、安全面で自動運転の方が優位に立つ。ただそのためにはさまざまな走行環境での実証実験や検証が欠かせない。実証実験中の事故を最大限防ぐ努力をしつつ、事故を教訓にさらに技術レベルを高めることが各社には求められる。
バックは低速でも危険、判決が鳴らした警鐘 10年間で死亡610件
時速約16キロでバックし、自転車の男性(72)をはねて死なせたとして、被告の男(63)が実刑判決を受けた、27日の神戸地裁の裁判員裁判。判決は、バックの見通しの悪さや逆走行為を重く見て、時速16キロであっても危険運転致死罪にあたると警鐘を鳴らした形だ。
公益財団法人「交通事故総合分析センター」の調査では、2008年~17年の10年間で、バック中の自動車による死亡事故は610件。重傷事故も1万840件起きている。
バックモニターやセンサーなどの安全装置の普及で事故件数は減少傾向にある。ただ今回の事故で被告は、路肩に駐車しようとサイドミラーに目線がいき、バックモニターは全く見ていなかったとされる。
危険運転致死罪:
判決は、バックの見通しの悪さや逆走行為を重く見て、時速16キロであっても 危険運転致死罪 にあたると警鐘を鳴らした形だ。 【これまでの経緯】時速16キロでバックは「危険運転致死罪」なのか 異例な裁判の行方 【判決】時速16キロでも「危険運転致死」認定 バック事故、被告に実刑判決 公益財団法人「交通事故総合分析センター」の調査では、2008年~17年の10年間で、バック中の自動車による死亡事故は610件。 重傷事故も1万840件起きている。
トヨタ自動車が開発した自動運転の電気自動車「eパレット」=2019年10月、東京都江東区
東京パラリンピックの選手村で8月、自動運転の電気自動車が選手に接触する事故があった。事故で浮かび上がったのは、人による操作とシステムによる操作を使い分ける自動運転の難しさだった。
「実社会に非常に近い状況で起きた。様々な人が行き交う一般道での課題が見えてきた」。「他者との共生」を意識し、自動運転の制御システムに関する研究をする名古屋大大学院の鈴木達也教授はこう話す。
事故は8月26日昼に起きた。警視庁によると、視覚障害のある男子柔道の日本代表選手が横断歩道を歩いていたところ、自動運転のバス「eパレット」と接触した。選手は転倒し、2週間のけがを負った。現場は一般道ではなく、関係者以外は立ち入れない。
「大丈夫だろう」が突然…勝手なルール、人をはねた後悔
「eパレット」は、トヨタ自動車が「次世代の自動車」として開発した。五輪とパラリンピックでは選手の送迎などに使った。事故の翌日には豊田章男社長が、自社のオウンドメディア「トヨタイムズ」やオンライン記者会見で状況を説明した。
トヨタによると、バスは右折する際、交差点内の人を感知して停止した。バスに乗っていたトヨタ社員のオペレーターが交差点の周辺を確認したところ、誘導する警備員が選手を制止しているように見えたので発進させたという。
直後、横断してきた選手をセンサーが検知し、自動ブレーキが作動した。オペレーターも手動の緊急ブレーキを使ったが、バスが完全に止まる前に時速1キロほどで接触したという。
トヨタは事故を受け、誘導する警備員なども含めた安全対策ができるまで運行を取りやめた。「信号のない交差点での安全確保は、歩行者、オペレーター、誘導員の三位一体で仕組みを改善する必要があると判断した」としている
◇
運転手不足問題の解決に向け、鳥取市が導入したが、しかし・・・
自動運転バスに記者が試乗 たびたび「手動」に 課題は路上駐車回避
2024年2月15日
 |
走行中の自動運転バスの車内。危険察知などで運転手(中央モニターの向こう側)が関与すると手動運転の表示が出る(左上)=2024年2月15日午前11時7分、鳥取市、清野貴幸撮影 |
運転手不足問題の解決に向け、鳥取市が導入を目指して実証運行の実験をしている自動運転バスに15日、記者が試乗した。試乗ルート中、運転手がハンドルを握って「手動運転」になる場面も多く、完全自動化の実現は簡単ではないと感じた。
実証運行は、市と地元の運行事業者、車両を管理する「ティアフォー」(名古屋市)などが取り組む国の補助事業。道路運送車両法に基づく運転者を必要としない「レベル4」を目指し、2024年1月下旬から市中心部で実施している。
16日から市民の試乗が始まるのを前に15日、報道機関向けの試乗会があった。カメラやレーダーなど30個のセンサーを車体前部に装着した電動バスは、JR鳥取駅前を出発。走行ルートは、若桜街道を直進し、鳥取城跡付近や県庁を通って戻る約4・6キロ。最高時速35キロで走った。
電動らしく発進はスムーズ。緊急時に備えて運転席に座る運転手の背後にはモニターがあり、各センサーがとらえた周囲の車や歩行者の動き、バスの走行位置などが刻々と表示された。運転手がハンドルを握ったりブレーキを踏んだりすると手動運転に切り替わり、現在の走行が自動か手動かも示された。
駅前ロータリーには信号に対し車体が斜めに停車する交差点があるが、ここでは手動運転になった。車両前面のカメラが信号を認識できないためだ。
若桜街道は路上駐車が多く、ほぼ運転手がハンドル操作で回避。幹線道路から鳥取城跡方面へ右折する際も対向車がなかなか途切れず、手動運転だった。自動運転中に急ブレーキがかかり、立っていれば大きくよろけたと思われる衝撃を受けることもあった。
鳥取市によると、路駐車両は自動運転でも回避できるがセンターラインをはみ出すなどして急ブレーキがかかることがあり、今回は安全優先でほぼ手動運転にしたという。ティアフォーによると、他にも市内にある信号のない環状交差点や長いトンネルは自動運転には不向き。一方で路駐車両が少ないなど交通条件が良ければ、今回のルートの5割程度を自動運転できるというがまだまだの感が否めず。
(清野貴幸)
福島・鏡石駅前で車が2人はね駅に突っ込む…男子大学生死亡、運転の72歳女を容疑で逮捕
15日午後3時50分頃、福島県鏡石町中央のJR鏡石駅前のロータリーで、自動車教習所の送迎車から降りた男女2人が、突っ込んできた軽乗用車にはねられ、埼玉県宮代町、大学1年の星野友哉さん(19)が間もなく死亡した。女性(19)は重傷。
軽乗用車はそのまま駅舎に衝突し、須賀川署は、運転していた鏡石町、パート従業員の女(72)を自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致傷)容疑で現行犯逮捕し、過失運転致死傷容疑で調べている。
事故直後に女に声をかけたという女性(70)は、「『アクセルとブレーキを踏み間違えた』と泣いて、パニック状態になっていた」と話した。
【 クルマは乗らなきゃ語れない】
不正問題で突如買えなくなったダイハツ車。個人的にはコスパに優れた大衆車メーカーなので早めの再生を願うが、なるはやで代用新車を見つけなければいけない人もいるだろう。前回に続き、ダイハツ車の代わりに何を買うべきか。その場合どんな利便性を失うかを勝手に想定してみた。
■ダイハツロッキー&トヨタライズの代わりならホンダWR-V
直近ダイハツで売れていた4位、ダイハツロッキー&トヨタライズ(去年11月に7268台)の代わりといえば、先日受注を開始したホンダWR-Vだ。そもそもロッキー&ライズの良さは分かりやすい。今どきSUVでは珍しい扱いやすい5ナンバーサイズで価格が安く、ライズに関してはアニキ分のトヨタRAV4にもちと似ている。競合にはない電動のシリーズハイブリッドも選べる。よって厳密にWR-Vは完全なロッキー&ライズの代わりにはならない。全幅1.79mで5ナンバーをハミ出しており、微妙にデカめだからだ。ただしこのお買い得感であり、カッコ良さ&使い勝手はある意味ダイハツSUVを超えている。今回の問題がなくても相当ガチで張り合っただろう。
まず優れてるのは前述5ナンバー超えでも扱いやすいサイズ。全長4.3m台で幅も人気のホンダSUV、ヴェゼルとほぼ同じ。それでいて全高は6cm高いのでより広くて使いやすい。ラゲッジに関してはヴェゼルよりだいたい70ℓ広い458ℓ。当然ロッキー&ライズの369ℓよりも大幅に広い。
一方弱点というか安い理由もあり、ASEAN開発のインド生産車だからか、今どきハイブリッドやフルタイム4WDが選べない。パーキングブレーキもオーソドックスな手引き式でATもストレート式。ただし、1.5ℓエンジンは十分パワフルだし、先進安全のホンダセンシングも全車標準。最新コネクティッドのホンダコネクトも装着可能。それでいて価格は全グレード250万円以下! ホンダセンシング付きの廉価版は209万円強という安さ。これは脅威だ。
タフトの代わりなら当然スズキ ハスラー
売れてた5位のタフト6634台の代わりといえば当然、スズキ ハスラーだ。一時は軽販売ベスト3にも入ってた元祖軽SUVで、そもそもハスラーの方が売れていたので十分代わりになる。デザインは丸目で分かりやすく可愛く、スズキならではの燃費の良いマイルドハイブリッドも選べ、オマケに後席は畳むと低くフラット化し、厳密にいうとタフトより使いやすい部分も多い。
が、タフトも捨てがたい魅力を持っており、ハスラーにはない「軽のSUVデートカー」コンセプトを打ち出しており、角目ライトと武骨なグリルがちとワイルドアメ車のハマーっぽい。比べるとハスラーはプチジープだ。
さらに、LEDヘッドランプや自慢の巨大サンルーフことスカイフィールトップが全車について130万円台スタートというコスパも凄かった。
ミライースの代わりはスズキ アルト
売れてた6位、ミライース6019台の代わりといえば、これまた当然のスズキ アルトだ。昭和人間なら知る「アルト47万円」のCMコピーで有名な元祖コスパ軽カーで、同じく安さで売るミライースの十分な代わりになる。
今売られている9代目はなんと先進安全のスズキセーフティサポート全車標準で、発売当初はスタート価格が税込100万円切り(今は106万4800円~)。これは中身を考えるとミライースを凌ぐコスパぶりで、アルト初のマイルドハイブリッドも装備。最良WLTCモード燃費はリッター27.7kmと、ほとんどストロングハイブリッド並みのエコ度を誇っているのだ。
比べると現行ミライースはベーシックグレード価格こそ100万円切りと安かったが、先進安全は最新手前のスマートアシストⅢに留まっていたし、マイルドハイブリッドも選べず、アップデートが待たれていた。
2017年デビューなのでそろそろ改良の時期だし、そんなタイミングのこの問題発覚だったのだろう。しかも今もコスト高時代、よりダイハツらしいコストカットも迫られていたはずだ。
とはいえ、ますますビンボー化が進むニッポン、物作りにはやはり優れたコスパ感覚やコストカット技術が必要になる。返す返すもダイハツの健全なる再生を望む。
(小沢コージ/自動車ジャーナリスト)
ビギナードライバーに選ばれることが多いベーシックモデル :
スズキの2022年1月新型アルト、ハスラー、スペーシア
■マイルドハイブリッド初採用でWLTCモード燃費は27.7km/Lを実現
●マイルドハイブリッドの価格は約110万円~:日本で最安の車はダイハツ・ミラ、スズキのハスラー
スズキのアルトのデザインが嫌いならハスラー(Xのjスタイルは安い)も運転しやすい。またアルトのように全高が低すぎる車は交差点では相手車両から見えないため、危険でもある。できれば全高が1700ミリ前後の軽自動車が良い。若しくは、高速道路で時速80k以上を出さなけば、スペーシアやN-BOXのようなスーパーハイトワゴンが良いだろう。
小さな交差点で「危険」を察知した場合は、赤信号を待って、相手の直進車が過ぎ去った後に「右折」した方が良い。
大きい交差点ではかならず「右折専用の信号機」があるので、大きな交差点なら、右折専用の信号機が青になるまで待って「右折」した方が良い。
ダイハツのムーブやホンダのN-ワゴン(WGN)
 |
| Cピラーが三角で独特だが・・・ |
N-ONEは、初代モデルが2012年に登場し、1960年代に大ヒットした「N360」をイメージしたレトロで愛らしいデザインや、軽快な走りが好評を得た。全グレードに標準装備される先進安全支援機能のホンダセンシングは、夜間の歩行者の検知性能を向上させ、横断自転車をも検知する自動ブレーキや車線維持支援システム、前後誤発進抑制機能(ブレーキ機能はなし)などのほか、ついに0〜135キロで作動する渋滞追従型ACC(アダプティブクルーズコントロール)を、ホンダの軽自動車として初採用。
軽ハイトワゴンN-WGNが初のフルモデルチェンジを行う。フルモデルチェンジ・デビューは2021年7月18日。車体サイズは3395×1475×1705mm(全長×全幅×全高)新世代Nシリーズの第3弾として先進の安全装備と完成度の高い質感を実現し、ライバルを遙か彼方に置き去りにしようとしているのだ!
 |
| Cピラーが三角が長方形になったが・・・・・ |
 |
| ACCのボタンがへこんでいて押しにくそう! |
新型 N-WGN / N-WGN Custom Lターボ スペシャルパッケージ
N-WGNの走行性能はもちろん、先進安全支援機能についてもクラスをリードする存在になったというわけだ(ハイト系ワゴンのACCは日産 デイズの場合、ハイウェイスターのプロパイロットエディションのみの設定。三菱 ekワゴン、ekクロスは一部グレードにオプション。ダイハツ ムーブ、スズキ ワゴンRはACC未設定)。
プリウスミサイル・アクアミサイル・アルファードミサイル
危険な車の代表。運転中、後ろがほぼ見えない。車幅感覚が狂うステアリング周りの形状、車両感覚を狂わせるデザイン。など
 |
| プリウスミサイル・アクアミサイル・アルファードミサイルの写真 |
完全にガソリンだけを使うガソリン車が廃止の時代に入ったから、2022年から購入する人はハイブリッド車(シリーズ方式、パラレル方式、スプリット方式=シリーズ・パラレル方式)に変えたい!2030年に入ると日本も真に実用的なEV車に変わってくるだろう。2030年からは、EV車の軽自動車の各社過当競争になってくるから、かなり安価になりそうだ。
【ハイブリット方式の種類】メーカーのハイブリッドは、どう違う?『ハンター セミナー』
※2つ目
「シリーズ・パラレル方式(スプリット方式ともいう)」は、エンジンを発電用と走行用の両方で使用するもの。代表例は「プリウス」だ。性能は高いが構造がやや複雑になる。プリウスは1997年登場以来、機能部分の小型化やコスト削減に対して常に進化し、その技術を他のトヨタ車向けに横展開してきた。コストが高い。エンジンもバッテリーも重くなりすぎる。重くなると燃費も悪くなる。
※3つ目
ダイハツは技術的には、e-SMART HYBRIDを「エンジンを発電専用とし、100%モーター(駆動)で走行するシリーズハイブリッド方式」であると指摘。ダイハツはこの「シリーズ方式」の特徴として「エンジンが発電専用なのでパワートレイン全体としてシンプルでコンパクトな構造であること、さらにモーターの特性で低中速に強く、小さなクルマに適したハイブリッドシステム」と説明した。競合になるのは当然、日産「e-POWER」である。ダイハツのe-SMART HYBRIDのセールスポイントは大きく3つある。一点目は、電動感だ。従来の直列3気筒1.0Lターボと、アクセルの踏み具合(アクセル開度)が同じ状態で比較して、出足加速がよく、発進時加速度を約2倍と表現した。そして、アクセルの踏み・戻しだけで加減速を快適に行えるスマートペダルを採用。こうした考え方は日産e-POWERにかなり近い。また、e-SMART HYBRIDでは停車状態から時速40キロまでモーター走行し、遮音材・防音材を適材適所に配置して静粛性を考慮した。二点目は、低燃費だ。燃費の世界標準規格であるWLTCモードでリッターあたり28.0キロとした。小型SUVハイブリッド車のトップレベルで、従来の1.0Lターボ比で約50%も燃費が向上している。ちなみに、日産e-POWERでは、コンパクトカーの日産「ノート」のベースグレード「F」(2WD)でリッター29.5キロである。インバータ、コンバータ、バッテリーなどを詰め込んだ技術はすごい。そして三点目は、こうした最新技術と低燃費という良品を廉価としたことだ。2021年9月の新型ロッキーから、この「シリーズ方式」のe-SMART HYBRID車が発売されるだろう。2022年8月発売のキャンバスはねらい目だが、この設定は無かった。軽に積むにはハードルが高いのだろう。
この「シリーズ方式」のe-SMART HYBRID車が、内燃機関でなく、モーターと蓄電池だけで走るEV車なら、ほぼ次世代カーに近づくだろう。
ACCを使わない方がいいケース:
① 一般道では絶対お勧めしません。高速道路と違い、長く一定速度を保つ場面が少ないこと、かつACCのセンサーが前方に向けてセットされているため、バイク、自転車、歩行者等の急な飛び出しを検知できない場合があり、対応が遅れます。
② 高速道路の料金所付近や合流・流出エリア、カーブのきつい首都高などでは、ACCのセンサーが検知範囲を越えてしまうために正確な作動をしないことがあります。
③ 前走車が目視できず急停止できないエリアや、豪雨や霧・雪などの視界が悪くセンサーが正常に動かない可能性があります。
車のオート機能過信に自動車学校が注意喚起 「運転者はこの機能が働いたら負けと思って」
Hint-Pot の意見 - 11 時間前
これから12月にかけての年末は交通事故が増加する傾向にあります。慌ただしい毎日の中でついつい気持ちが先を急ぎ、運転前の安全確認がおろそかになっていませんか? 交通安全を呼びかける投稿が度々大反響を呼んでいる烏山自動車学校(栃木県那須烏山市)の公式ツイッター(@KarasuyamaDS)は、車のオート機能の使い方について注意喚起。乗車前点検の重要性を訴えています。
BEVとは?電気自動車(BEV)の特徴:
BEV(Battery Electric Vehicle)とは、電動車(EV)の種類のひとつで、100%電気で走る電気自動車のことをいいます。
BEVの仕組みや特徴について、くわしく解説します。
BEVとは “Battery Electric Vehicle” の略称で、電気のみをエネルギー源として走行する車両のことを指します。
一般的には「EV」と呼ばれることが多いので、「BEV=EV」という理解で問題ないでしょう。
ではなぜ「BEV」という言葉があるのでしょうか。それは、100%電気で動くEV以外にも、これまで沢山の種類の電気自動車が開発されてきたからです。
ハイブリッド車(HV)やプラグインハイブリッド自動車(PHEV)、燃料電池自動車(FCEV)といった種類の車両も「電気でも動く」という意味で広義で電気自動車(Electric Vechle, つまりEV)となります。
こうした種類の電気自動車と完全に電気のみで動く電気自動車とを区別するために “バッテリー” の頭文字のBを付けて「BEV」という用語が使われることがあります。
たとえばテスラや日産のリーフをはじめ、トヨタのbZ4Xやスバルのソルテラ、軽EVとして人気を博している日産サクラや三菱eKクロスEVなどもBEVに分類されます。
日本政府は、2035年までに乗用車新車販売における電動車の比率を100%とする目標を掲げています。今後はガソリン車に変わってBEVを含むEVが主流となっていくことが予想されます。
従来のガソリン車は、ガソリンというエネルギー源を利用してエンジンを動かし、その力で走行します。一方でBEVはバッテリーに貯めた電気でモーターを動かして走行します。
完全に電気で動くのが、従来のガソリン車やPHEVやHVなどとの決定的な違いです。
エンジンを使わないため、二酸化炭素(CO2)を含む排気ガスが一切出ないため地球環境に優しく、さらに走行音が静かで、車内を広く設計しやすいというメリットもあります。またバッテリーの導入で構造がシンプルになり、消耗品を含む整備パーツが少ないため整備コストが低いこともBEVの利点の一つです。
自宅や出先の充電スタンドの外部電源から充電できるほか、クルマが減速するときのエネルギーを利用して発電する「回生充電」の機能も備えています。回生充電だけですべてをまかなうことはできないため、外部電源からの充電は必須ですが、電源と十分なスペースさえあれば充電スタンドを設置することができるので、ガソリンスタンドにわざわざ出向く必要はありません。充電スポットに行く必要がある。ところが充電スポットが少なすぎる状況にあるのだ。
BEVの黎明期は1回の充電で走行できる距離の短さや、充電設備の普及率の低さがデメリットとして問題視されていましたが、最近では街乗りであれば十分な走行距離のスペックの車種も増えてきており、日本国内の充電スポットも増加傾向にあります?!
まとめ
BEVとは100%電気で走る電気自動車のこと。単にEVと呼ばれることも多いのですが、PHEVやHVなども広義では電気自動車に該当するため、これらと区別するために「BEV」と表記されることがあります。
PHEVやHVなどと違い、100%電動であることが大きな特徴。どんなシーンでも排気がゼロの環境にやさしい乗り物です。
高齢者(だけではない)がプリウスで事故を起こしてしまう原因とは。『ハンター セミナー』
プリウスミサイル、アクアミサイル、日産ノートミサイル、この3つが「事故ニュース」では有名!3日連続、全国でプリウスの事故があったな!フロントの顔つきも「悪童」の様だ。これじゃ事故るのも無理ない。
【論争】エンジンスタートスイッチ 右派?左派?『ハンター セミナー』
日産のe-Powerってどうなの?
e-Power⇔e-pedal
(e-Powerありきのe-アクセルペダルだ。
e-アクセルペダルだけで加減速できるが、危険な場面はないのか?)
渋滞が多い場面では完全停止せずに、追突を起こしかねない!
【これから車好きになる方へ】AT・MT・CVT といった車の購入する際に記載されている用語が何かを知っていますか? 『ハンター セミナー』
ディスクブレーキとドラムブレーキ どう違うのか?『ハンター セミナー』
【知ってると損しない】内気循環と外気導入のメリット・デメリット
【よくある間違い】A/Cスイッチの賢い使い方を解説
車のエアコン「内気循環」に潜む事故!! バラエティ[ 他3件 ]【GS相談室】
現代の車は密閉されている作りなので、原則は外気循環したほうが健康のために良いらしい。前の車が電気を主体にして走っている車なら、外気循環したほうが健康のために良いらしい。冬の寒い日、湿気の多い梅雨の時期は、どうしたらよいのか?ベストな答えが知りたい!
【論争】エンジンスタートスイッチ 右派?左派?
【真実】オルガン式アクセルペダルの特徴
【車のプロが教える】 誰でも簡単! ウォッシャー液の入れ方
煽り運転の被害から回避するのは、サンキュー3点セットが解決⁈
リアリストあるある 「自然やイルミネーションに〇〇〇〇〇〇」
3 convenient car switches if you know how to use them
It is more convenient than ETC! What are the benefits of the next-genera...
What is the reason why the number of cars with emergency brakes is decre...
緊急ブレーキ付きの車の数が減少している理由は何ですか...
What is the need and right way to drive with warm air?
アクセル・ブレーキ踏み間違い事故 その原因を「人間のせい」にしている限り、問題は永遠に解決しない
島崎敢(心理学者) の意見
2023年11月22日
事故の根本に潜む問題
アクセルとブレーキの踏み間違いによる事故は繰り返し報道される。ニュースの多くが高齢者によるものなので、高齢ドライバーは危険だというイメージが定着しているが、実際には、運転に不慣れな若年ドライバーが起こす踏み間違い事故も多い。
【画像】画面ちっさ! これが42年前の「カーナビ」です(計12枚)
高齢ドライバーは加齢にともなって心身機能が低下し、行動を抑制がうまくいかなくなることがある。また、若年ドライバーは免許を取ってから日が浅く、運転に不慣れなために踏み間違いを起こすと考えられている。しかし、これらはいずれも踏み間違い事故の原因をドライバー、つまり
「人間に帰属させる考え方」
である。
人間はどんなに気をつけていても、一定確率でエラーを起こしてしまう生き物である。この人間の特性は鍛えたり練習したりして変えられる類いのものではない。したがって、「事故の原因は人間のエラーだ」と考えている限り、事故をなくすことはできない。
ではどうすれば事故を防げるのだろうか。ひとつは人間のエラーが致命的な事態に結びつかないような工学的対策をすることだ。
初期のウォシュレットつきのトイレの個室からは、よく使い方を間違えた人の悲鳴が聞こえてきた。しかし、最近のウォシュレットからは悲鳴は聞こえてこない。これは、人間が操作を間違えても、システムが便座に人が座っていないことを検知し、操作ミスをした人をずぶぬれにすること(致命的な事態になること)を防いでいるからだ。
事故を防止するもうひとつの方法
最近の車にはこのような安全装置が取り付けられ始めている。
目の前に障害物があるのにアクセルを急に踏み込んだような場合に、システムが踏み間違いだと判断して加速を抑制するのだ。このような工学的対策は高い効果が期待できるが、対策が施された車が普及するまでには時間がかかる。
事故を防止するもうひとつの方法は、人間のエラーを「事故の原因」ではなく、より深いところにある
「背後要因の結果」
だと考えて、エラーを誘発する要因を取り除くことだ。人間のエラーはゼロにはできないが、エラーを誘発する要因を取り除けば、エラー率を下げることはできる。
踏み間違いを誘発する要因には、
・考え事
・いつもと違う運転姿勢
・疲労や焦り
・不適切な靴
などさまざまあるが、この記事のテーマである不適切なユーザーインターフェース(UI)もエラーを誘発する主要な要因である。
UIとは、人間と機械が「命令や情報をやり取りするところ」である。パソコンの場合、キーボード、マウス、マイクなどは人間から機械に情報を送るUIであり、モニターやスピーカーは機械から人間に情報を伝えるUIである。このUI設計が直感的でわかりやすければエラーは起きにくくなり、そうでなければエラーは起きやすくなる。
異なる乗り物のUIデザイン
レバーを動かす方法も、押さえながら回転させる、縦に引く、横に引くなど、ふたつのレバーが同じ動作にならないように工夫されている。1ハンドルタイプでは1本のレバーで加速と減速を行うが、操作の向きが手前と奥で真逆になっている。
船にはブレーキがない。もともと水の抵抗が大きいので、スクリューを止めれば自然に減速する。さらに急減速が必要な場合には、加速するのとは別のレバーや機関室への口頭指示によってスクリューを逆回転させて急ブレーキをかける。
飛行機には、空気抵抗を増やして速度を落とすスポイラー、エンジンの力で速度を落とす装置(逆噴射やプロペラの羽の角度を逆にする仕組み)、そして車輪に取り付けられた車と同じ摩擦式のブレーキと、3種類の減速方法がある。いずれのブレーキも、飛行機を加速させるスロットルとは別のUI(レバーやペダル)や逆の動作(スロットルを加速とは反対方向に動かす)が割り当てられている。
車以外の乗り物は、加速と減速の操作方法が全く違うので、ブレーキをかけたいのに、操作を間違えて加速することまず考えられない。つまり、
「エラーを誘発しにくいUI」
が採用されているのだ。ではなぜ車はこのように紛らわしいUIが標準的になってしまっただろうか。
AT時代の安全
一方で、現代の自動車産業は、運転の自動化をはじめとした100年に1度の技術革新の最中にあるといわれており、自動運転に移行する過程は
「UIを改良するチャンス」
なのかもしれない。
自動運転は完全手動のレベル0から完全自動のレベル5までの6段階に分類されており、完全自動運転のレベル5では運転のためのUIは不要である。しかしレベル5の実現はだいぶ先になりそうなので、当分の間は車には何らかのUIを用意する必要がある。現在の車のUIは、レベル0が前提の設計なので、半自動化された車のUIとしては不適切なのかもしれない。
例えば、条件付き自動運転であるレベル3自動運転バスの実証実験が各地で始まっており、報道でも取り上げられ始めている。
ニュースでは、ドライバーはハンドルを握ってはいないが、いつでも握れるように空中で腕をプルプルさせている映像を目にすることがある。これはレベル3自動運転が、
「システムの介入要求があったときに、ドライバーがいつでも対応できること」
を求めているためだが、せっかく自動化したのに、自分で運転するよりも腕が疲れそうに見える。ハンドルというUIはレベル3自動運転には向いていないようだ。
このような状況を解消するために、今後、自動化の進度に応じた適切なUIの提案が求められる可能性がある。このとき、今度は「なし崩し的」にエラーを誘発しやすいUIを採用してしまわないように、人間の特性を踏まえて、良いUIをしっかりと検討していく必要があるだろう。
安全なクルマが欲しいと思ったら、「自動車アセスメント」のテスト結果を要チェック!
カーライフに関連するさまざまな時事ネタを横断的に紹介している当コーナー。前回からは「自動車アセスメント」にスポットを当てている。実は、クルマの安全性能をシビアなテストにより明らかにしようとする取り組みがある。今回は、その調査結果の活用法を解説していく。
まずは前回の記事内容を簡単におさらいしておこう。「自動車アセスメント」とは、国土交通省と独立行政法人 自動車事故対策機構(NASVA<ナスバ>)によって執り行われているもので、「クルマの安全性能の数値的・客観的な評価」をしようとするものだ。
その評価のために、「衝突安全性能」、「予防安全性能」、「事故時の自動緊急通報」、この3つについてさまざまなテストが実施されている。
そうしてそれらテスト結果が点数化され、規定値を上回った車種には「自動車安全性能 ファイブスター賞」が授与される。
ちなみに各自動車メーカーのカタログを見ると、「自動車安全性能 ファイブスター賞」を得た車種については、そのことを積極的にアピールすべく同賞のワッペンがカタログ上に表示されている場合が多い。つまり自動車メーカー各社も、「自動車アセスメント」での評価を車両販売を伸ばすための1つのツールとして活用している、というわけだ。
なお「NASVA」のHPでは、「自動車アセスメント」の「ダイレクト検索」が行えるようになっている。なのでクルマを買おうとする際には、購入候補としている車種を同HPにて検索してみよう。そうすると過去にテストされている場合、その結果を詳細に把握できる。つまり、そのクルマの安全性能の高さの程度を確認できる。
ただし、複数の車種の結果を単純比較するのには注意が必要だ。なぜなら「自動車アセスメント」は年々進化を遂げていて、テスト内容が経年とともに少しずつ変化しているからだ。なので、テストされた年度が異なると横並びにしての比較がしづらくなる。そのことは頭に入れておきたい。
ちなみに「NASVA」ではYouTubeチャンネルにて、テスト動画も公開しているので、こちらも至極参考になる。特に、衝突被害軽減ブレーキの効き目を試すシーンなどは興味深い。クルマを試乗する機会はあれど、こういった装備の効き目まではなかなか試せない。しかしこれら動画を観れば、そのポテンシャルが一目瞭然で確認できる。
なお、「自動車アセスメント」では市場に出回っているすべての車種がテストされているわけではないので、その点も頭に入れておきたい。ちなみに調べられる車種は、ときどきで売れ行きが好調な車種の中から選定されているとのことだ。
というわけなので、欲しいクルマがあったらまずは、「自動車アセスメント」のHPにて検索をかけてみよう。テストされていたらしめたものだ。この結果も、車両選定の参考にしない手はない。要注目。
えっ、パナソニックからクルマやアウトドアでも使える“ポータブル電子レンジ”が登場!?
CAR GoodsPress によるストーリー • 2024年2月2日
2024年2月2日~5日の4日間、千葉県・幕張メッセで「ジャパンキャンピングカーショー2024」が開催され、パナソニックも出展。ブースは来客者で賑わった。
メインは有機ELディスプレイ搭載の高画質大画面で人気となっているカーナビ「ストラーダ」だったが、その一角にあったのは「みんなのご意見募集中!」というボードと見慣れない取っ手が付いた2つの箱…。
この“箱”の正体は、なんと「ポータブル電子レンジ」。
いずれもAC100V、DC12Vに対応し、自宅でもクルマの中でも、またポータブル電源などを使えば屋外でも使えるというもの。キャンプをはじめとしたアウトドアレジャーはもちろん、災害時にも活躍しそうだ。
それぞれに「レンジA」、「レンジB」と仮名が付けられており、大きさやデザイン、スペックも異なっている。
「買いたい!と思う方にシールを貼ろう!」という来場者に向けたアンケート投票も行っていた。
▲会場では「買うならどっち?!」というアンケートを実施していたものの、発売の予定はないとのことだが…本当!?
「レンジA」はサイズが大きく8~9kgあるため持ち運びはしにくいが、参考価格は4万9800円と安めに設定。温め性能は一般的な家庭用電子レンジと同等で、最大出力はAC100V時1000W。
▲レンジA。扉が左開きで表面は壁紙のような凹凸がついたデザインだ。天面のくぼみは小さい。コンビニ弁当の温めは500Wで3~4分
そして「レンジB」は、サイズがやや小さく、6~7kgと軽量のため持ち運びはしやすいものの、参考価格は5万9800円と少し高め。こちらの温め性能は小型化の影響からか、最大出力はAC100V時で300Wとなっている。
▲レンジB。扉が下開きで表面は凹凸のないシンプルなデザイン。天面のくぼみは大きい。コンビニ弁当の温めは300Wで5~8分
庫内のサイズはレンジAが少しだけ大きいが、どちらもコンビニで販売されている小さめの弁当や丼が1個入るくらい。上部にはキャリングハンドル、トレー&ドリンクホルダー状のくぼみが備わる。
いずれもモックアップではあるものの、ビジュアルはオシャレで質感も高い。構造もよく考えられたものだ。
今すぐに製品化ができるのでは? と感じられる完成度。アンケートまで取られているのだから当然ながら、ここから製品開発がスタートするのだろう…と思っていたら、
「発売の予定はございません」と広報担当者はキッパリと否定!
しかし、CGPのレポーターは、開発担当者の熱量を確かに感じている。
この記事を見て「欲しい!」と思ったアナタのために、きっとパナソニックは頑張ってくれるはず。正直、期待しています。
<文/CGP編集部>
高速道路「路肩の数字」は何のため!? 実はいろいろ役に立つ「キロポスト標識」の目的とは
くるまのニュースライター 田中太郎 の意見
高速道路の路肩にある「数字」の名称は「キロポスト標識」
高速道路の路肩脇や中央分離帯部分に、数字が表示された小さな横長の標識が点在しています。
この標識は「キロポスト」とよばれる標識で、別名「距離標」ともよばれていますが、一体何のためにあるのでしょうか。
「あ、富士山!」ついきれいな景色に見とれてしまいますが…… 高速道路の路肩にある緑色の四角くて小さな「キロポスト標識」(画面中央付近)にも注目してみましょう[画像はイメージです]「あ、富士山!」ついきれいな景色に見とれてしまいますが…… 高速道路の路肩にある緑色の四角くて小さな「キロポスト標識」(画面中央付近)にも注目してみましょう[画像はイメージです]
キロポストとよばれる標識の数字は、高速道路上でドライバーが情報受信、もしくは情報発信するときに非常に大切な役割を果たすものです。
一般道と異なり、高速道路には交差点や信号といった目印になるものがほとんどないため、キロポストの数字が正確な位置の手がかりになるほか、キロポスト標識の位置を利用して、適度な車間距離を保つことにも役立ちます。
詳しく紹介しましょう。
まずキロポスト標識に表示されている数字は、高速道路の起点からの距離を表します。
起点は東名高速であれば「東京IC」、東北道は「川口JCT」、中央道は「高井戸IC」、北関東道は「高崎JCT」と、あらかじめ決まっています。
また「上り」「下り」の概念はなく、あくまで起点からの距離をkm単位の数字で表示しているものです。
キロポスト標識の設置は1km間隔が基本で、デザインは緑のプレートに白の数字で距離を表示していますが、道路によっては100m間隔の場合もあり、デザインは白のプレートに緑の数字が基本スタイルです。
また距離の100m単位部分を小数点と小さい数字で表示するなど、運転中に遠くから見てもわかりやすくなっています。
起点からの距離が200km、300kmと、きりのよい数字の場合は「東京から300km」といったように、キロポスト標識が特別なデザインになっている場合があります。
また地域のイメージから、北関東道のキロポスト標識は紫のプレートに白の数字で表示されているなど、デザインの工夫も様々です。
キロポストの標識は、走行中の車間距離を保つ目安にもなります。
走行中に先にあるキロポストの標識を1つ目標に決めておき、先行車がそのキロポストを通過した後、自分が同じキロポストを通過するまでの時間を計測する方法です。
その時間が2秒以上であれば、適切な車間距離をキープしているといわれています。
しかし人間の計測のカウントは実際よりも速いことが多いため、「ゼロ、イチ、ニ」のカウントを「ゼロ、ゼロゼロイチ、ゼロゼロニ」とゼロを増やすことで、実際の2秒に近くなります。
「キロポスト標識」は情報受信や万が一の時にも役に立つ
ラジオの交通情報などで、工事の案内がアナウンスされるとき、一般道の場合は「0月0日午前0時から12時まで、●●町●●交差点から●●交差点までの1km区間が、工事のため片側交互通行になります」というように、交差点などが場所の基準とされます。
ところが高速道路では、目印になるようなものがほとんどありません。そこで、キロポスト標識がこのように使われます。
例えば以下のような案内となります。
「0月0日午前0時00分現在、中央高速下り線は工事のため、00キロポストから000キロポストの区間を1車線に規制中です」
「0月0日午前0時現在、東名高速上り線 ●●トンネル入口から000キロポストまで10kmの渋滞です」
「事故の情報です。0月0日午前0時00分現在、関越自動車道下り線 ●●ICの先、00キロポスト付近で乗用車2台による事故が発生しました。付近を走行中のクルマはご注意ください」
ドライバーはアナウンスを聞き、これから自分が向かう先の情報であれば工事、渋滞、事故などがあることを予想して運転することができます。
この正確な位置と情報を知っていることは、高速道路での安全のために極めて大切なことです。
またキロポスト標識は高速道路で、事故や落下物を目撃した際にも役立ちます。
目撃した場所のすぐ近くのキロポスト標識の数字を覚えておき、同乗者もしくはひとりで運転中であれば休憩ポイントなどでクルマを停めてから「スマートフォン、携帯電話対応の緊急ダイヤル(#9910)」へ通報しましょう。
その際に、覚えておいたキロポスト標識の数字を連絡することで場所が特定でき、スムーズな対応ができます。
また、高速道路を運転中に万が一事故にあったり、クルマがトラブルにあったりした場合にも、キロポスト標識は活躍します。
車両が高速道路上で動かなくなった場合は、できるだけ端にクルマを寄せ、発煙筒や三角表示板を車両後方に設置し、後方からの追突防止措置を取ります。
その際に同乗者やドライバーは車内やクルマのそばには残らず、必ずガードレール外などの安全な場所に避難してから外部に連絡しましょう。まずは「電話緊急ダイヤル(#9910)」へ通報です。
そして故障であれば、自分の加入している保険会社(ロードサービス加入の場合)やJAFへ、事故であれば110番に連絡します。
その際に、詳しいクルマの位置情報を伝えるためキロポスト標識の数字を連絡すれば、位置特定が正確に伝わるため、事故処理、故障車処理がスムーズに進むことになります。
このように様々な状況で役に立つキロポスト標識。高速道路を運転する際は、改めてチェックしてください。
×××××××××××××××××××××××××
絶対NG!車の寿命を短くする行為6選
×××××××××××××××××××××××××
最近の車の寿命は13年から15年ほどとされる。しかし、運転の仕方などによっては寿命を縮めてしまうこともある。ここではメンテナンス不足など以外で、車の寿命に直結するNG行為を合計6つ紹介する。
■運転中のNG行為3選
まず、運転中にしてはいけない行為から挙げていこう。
●急ブレーキ・急発進・急ハンドルはNG
急ブレーキ、急発進、急ハンドルなど「急」がつくような運転は、タイヤやサスペンション、ステアリング、車体など車の各部へ瞬間的に強い負荷がかかるのでNGだ。そうした乱暴な運転を繰り返していると、部品の摩耗やへたりが早まるだろう。走り始める前にしっかりとエンジンの暖気を行うことも心掛けたい。
●停車した状態でハンドルを回すのはNG
停車した状態でハンドルを回す「据え切り」を行うと、タイヤやサスペンションに負荷がかかる。駐車場などでしてしまいがちだが、少しでもいいから車を動かしながらハンドルを操作するようにしたい。
●信号待ちや下り坂でギアを「ニュートラル」に入れるのはNG
AT車で信号待ちするたびにギアを「ニュートラル」に入れると、トランスミッションの劣化が早まる。信号待ち程度の停車であれば、ギアは「ドライブ」のままでブレーキを踏んでいるほうが、トランスミッションへの負荷はより少ない。
信号待ちでギアを「パーキング」に入れると、走り出すときに操作ミスで「バック」ギアに入れてしまい事故を招くこともある。信号待ちでは、ギアは「ドライブ」のままブレーキを踏んでおくのが基本だ。
一方、下り坂でギアを「ニュートラル」に入れるのもNG。ハンドル操作が効かなく事故の下だ。ギアの機構にとってマイナスの働きとなり、エンジンブレーキもきかず、かえって燃料を消費してしまう、いいところなしの操作といえる。
■停車時のNG行為3選
次に停車時にしてはいけないことを挙げてみよう。
●車止めにタイヤを押し付けるのはNG
駐車時は、車止めにタイヤがあたるところまで下げるのが普通だ。しかし、強く押し付けたまま駐車してしまうとタイヤやサスペンションに負荷をかけてしまう。短時間の駐車なら問題はないが、長時間駐車する場合は、車止めからわずかにタイヤが離れる位置に止めたほうがいい。
●ギアを「パーキング」に入れてからサイドブレーキをかけるのはNG
停車時に、ギアを「パーキング」に入れた後にサイドブレーキをかけると、トランスミッションに負荷がかかることがある。
正しくは、ブレーキを踏んで停車したら、踏んだままサイドブレーキを入れ、次にギアを「パーキング」に入れてからブレーキペダルから足を離すようにする。
発信時はその逆に、ブレーキペダルを踏んだままギアの「パーキング」を解除し、サイドブレーキを解除して、ブレーキペダルを離すことになる。
●長期間の停車はNG
車を長期間停車させたまま放置していると潤滑オイルが流れ落ち、次に走らせたときに通常よりも大きな負荷が車にかかってしまう。車の寿命に配慮するなら、短い距離でいいので週に2〜3回くらいは走らせるようにしたい。
文・モリソウイチロウ(ライター)
×××××××××××××××××××××××××
ブラインドスポットモニターの代わりに買ってみたが、安価で、しかも役目を果たしているので良いと思う!
×××××××××××××××××××××××××
ブラインドスポットをなくす工夫が必要。
 |
| サンバイザーに挟むタイプで使いやすい。 |
ブラインドスポットを亡くす工夫が必要。 車線を変更する時は自分の目でも確かめること。 |
×××××××××××××××××××××××××
×××××××××××××××××××××××××
中国共産党企業体となっている「世界のトヨタ(習近平の操り企業?!)」:
豊田自工会会長「全部EVは間違い」 エンジン車規制強化、雇用減招く
2021年09月09日17時01分
 |
| オンライン形式で記者会見する日本自動車工業会の豊田章男会長=9日午前 |
日本自動車工業会の豊田章男会長(トヨタ自動車社長)は2021年11月9日のオンライン形式の記者会見で、「一部の政治家からは全て電気自動車(EV車)にすればいいという声を聞くが、それは違う」と述べた。次の政権を念頭に、温室効果ガスの削減に向けてエンジン車に対する規制が行き過ぎないようけん制した格好だ。
米、温室ガス30年までに半減 中国は石炭減、日本も目標上げ―気候サミット
豊田氏は、温室効果ガスの排出を2030年度までに2013年度比で46%削減する政府の目標について「日本の実情に応じていない」と指摘。その上で、エンジン車以外のEVや燃料電池車しか生産できなくなれば、「自動車産業が支える550万人の雇用の大半を失う」と懸念を示した。世界的に電気自動車(EV車)の生産が増えているので、トヨタ連合が生き残れるのか?心配だ。
電動車を、2030年度に5割以上 5年で2兆円投資 日産長期ビジョン
2021年11/29(月) 10:26配信
 |
| 日産の内田誠社長 |
日産自動車は2021年11月29日、車両の電動化に向けて今後5年間で約2兆円を投資することを柱とした日産長期ビジョンを発表した。日産は本気を出してきた!
【図解】世界のガソリン車削減目標
電気自動車(EV)など電動車の販売割合を引き上げ、2030年度までに車種ベースで5割以上とする。重要部品となる電池の開発全固体電池も加速させる。2050年の脱炭素社会の実現に向け、自動車業界では電動車の開発競争が加速している。内田誠社長はオンラインでの説明会で「事業の再生から未来の創造にギアをシフトする」と語った。電動化など先進技術領域で3000人以上を新規雇用する考えを示した。日産自動車は11月29日、長期ビジョン「アンビション2030」を発表し、次世代バッテリーである全固体電池を使った電気自動車(EVを投入)を2028年に市販する計画を明らかにした。
【画像】2028年に全固体電池により性能の大幅向上と価格の低下を見込む
次世代バッテリーとして知られる全固体電池の自社開発を進めており、2024年に日産の中国合弁企業にパイロット工場を立ち上げ試作を開始。2026年までに1400億円を投じ、2028年に全固体電池搭載したEVを市販する。日産の内田誠社長は「リチウムイオン電池と性能が同じなら開発の意味はない。航続距離や充電時間など、EVの使い勝手を大幅に向上させる」とした。
具体的には、エネルギー密度はリチウムイオン電池の2倍、充電時間は3分の1に短縮することを目標とする。これによって、大型車両のEV化が可能になる。さらにkWhあたりのコストを65ドルまで引き下げ、「EVの車両コストをガソリン車同等まで引き下げる」(内田氏)とした。
5年間で電動化に2兆円を投資:
日産の長期ビジョンの要は、全固体電池の電動化と自動運転などの知能化だ。これまで電動化技術には1兆円を投資してきたが、今後5年間でさらに2兆円を投資。2030年までに電動車比率を50%以上に引き上げる。
5年後の2026年には、EV軽自動車を含め電動化車両を23車種投入。比率を40%以上に引き上げる。
自動運転関連技術については、自動運転の“目”にあたる、次世代LiDAR技術を2020年代半ばまでに開発を完了し、2030年までにほぼすべての新型車に搭載する計画だ。日産の自動運転技術「プロパイロット」を搭載した車両は現在100万台規模だが、5年後には250万台へと引き上げる。6000億円を超える赤字に転落するなど、苦境にあった日産だが、「黒字化の見通しが立つまで来た」と内田氏は話し、「営業利益率5%以上はしっかり確保」した上で、大きな投資を進める。
脱ガソリン車、30年代半ばに 温室ガス実質ゼロへ弾み―HV存続で雇用確保
2020年12月03日19時40分
 |
| G7の首脳の中でウクライナ訪問をしていないのは日本だけ!これが日本外交のレベルだ。 |
政府が国内の新車販売に関し、2030年代半ば以降(2035年以降)はガソリンだけで走行する車以外の「電動車」とする目標を設定する方向で調整に入ったことが2021年12月3日、分かった。温室効果ガス削減に取り組む姿勢を国際社会に示すのが狙いで、実施後は電気自動車(EV)や電気とガソリンを併用するハイブリッド車(HV)などしか販売できなくなる。
マイルドハイブリッド車、ハイブリッド車(HV)を残すことで日本が強みを持つガソリンエンジンの生産も継続し、地球温暖化対策と国内の雇用確保の両立を目指す。
菅義偉首相は温室効果ガスの排出を2050年までに実質ゼロとする目標を掲げており、ガソリン車削減は実現のための目玉施策の一つとなる。経済産業省が近く、自動車業界や有識者らとの検討会議を開き、新たな目標について説明。政府が年内にもまとめる「2050年実質ゼロ」に向けた実行計画に反映させる方向で検討する。
ガソリンエンジンは、中小企業を含む幅広い部品供給網を通じて製造され、生産をやめれば雇用への悪影響が大きい。植物を原料とするバイオ燃料が普及すれば、環境負荷を大幅に低減できる可能性もある。政府は「さまざまな技術の選択肢を残す必要がある」(経産省幹部)として、国際社会の理解を得た上でハイブリッド車(HV)を残したい考えだ。
政府は、2030年までに乗用車の新車販売に占めるHVやEVなど「次世代自動車」の割合を5~7割にする目標を掲げている。2019年の新車販売台数は乗用車が430万台で、このうち次世代車は168万台と4割。HV(ハイブリッド車)が乗用車全体の34%を占めるのに対し、EVは0.5%にとどまっている。政府は、2050年実質ゼロの達成には一段と厳しい目標を掲げ、取り組みを加速する必要があると判断したとみられる。
ガソリン車の販売を制限する動きは世界で相次ぐが、対応には温度差もある。英国や米カリフォルニア州は2035年までにHV(ハイブリッド車)を含めガソリンを燃料とする車の新車販売を禁じる目標を定めた。中国は、同年以降はガソリン車の販売をやめて半分超をEVなどの「新エネルギー車」とするが、HV(ハイブリッド車)の存続も認める方針だ。
エンジンの様な匠の世界が伴わないEV車の敷居の低さが日本の自動車メーカーを追い詰める…かつての日本の家電メーカー群が液晶テレビで受けた仕打ちによく似ていますね。自国の工場から部品を揃えられ、技術が揃えば誰にでも作れるのが液晶TVとEV車などの電気製品だ。高い技術を持っていても、やはり部品代・人件費が高い国内では無理でしょう。
勝つためにはプライドとこれまでの古い慣習を捨て、下請けとの関係を整理し、まずスピード感、魅力的なデザイン、そして要となる技術の革新
特に重要なのがバッテリーになろうかと思いますが、ここに関しては日本全体で一丸となって突破すべき部分ではなかろうかと思います。次世代バッテリーとして知られる日産開発の全固体電池は格好の狙い球になっているので中国共産党の自動車企業と共同作業してますが、大丈夫ではないかもしれませんね。資本を無限に出しスピード重視、中国任せの企業が日本には多い気がする。
AT限定免許しかないのに「MT(マニュアルトランスミッション)車を運転」は無免許運転になる? それとも…?
無免許運転? それとも…?
クルマの普通運転免許には、MT(マニュアルトランスミッション)車とAT(オートマチックトランスミッション)車の両方を運転できるものと、AT車に限定して運転できる2種類があります。ではAT車限定免許しか取得していない人がMT車を運転した場合、どういった違反に該るのでしょうか。
写真は昔ながらのMT(マニュアルトランスミッション)車のシフトレバー。ペダル・レイアウトはアクセル、ブレーキペダルの隣にクラッチペダルがあり、クラッチの使い方がある。MT(マニュアルトランスミッション)車はD(ドライブ)レンジにすれば自動(無段変速機)でトルクを変えてくれるので一速、二速、三速・・のようなミッションは必要ない。昔ながらのMT(マニュアルトランスミッション)車は、アクセル、ブレーキ、クラッチの3つのペダルがあることから「3ペダル」とも呼ばれており、クラッチを操作して手動でギアチェンジをおこないます。
これに対し、AT車のペダルはアクセルとブレーキの2つ(2ペダル)となり、CVT(無段変速機)やDCT(デュアルクラッチトランスミッション)も含め、ギアチェンジはクルマが自動で判断してくれます。大変便利な世の中になっている。運転もしやすい。自動車教習所などでMT車の教習を受け、普通運転免許を取得すれば、同時にAT車も運転できるようになります。AT車にはクラッチペダルは無く、そのためクラッチの操作がないので、クルマの運転が比較的簡単であるという理由からAT限定免許を取得する人が年々増加。また自動車も最近は(2023年現在)AT車しか販売してない模様だ。警察庁が公表している「運転免許統計」によると、2020年に普通自動車第一種運転免許を受験した人は158万7700人で、そのなかでAT限定を選んでいる人は111万3229人と、全体の8割以上を占めていることが分かっています。また、近年新車で販売されるクルマのほとんどがAT車になっており、MT車に乗る機会がないことも、AT限定免許の取得者が増加する理由のひとつといえます。なお、AT限定免許の場合、運転免許証の免許の条件欄には「普通車はAT車に限る」などと記載されます。
通常の自動車を運転するのに必要な第一種免許のうち、「8トン限定中型免許」「5トン限定準中型免許」「普通免許」「大型二輪免許」「普通二輪免許」「小型限定普通二輪免許」の6種類にAT限定免許があります。たとえ車両の総重量や最大積載量が同じクルマであっても、AT限定免許の場合は、ドライバーがMT車を運転することはできません。では、もしAT車限定の普通免許しか持っていない人がMTの普通自動車を運転した場合には「無免許運転」になってしまうのでしょうか。
結論からいうと、無免許運転には該当せず、「免許条件違反」という交通違反にあたります。そもそも無免許運転は、大きく分けて7種類のケースに分類されます。まず「公安委員会の免許を受けていない状態で運転した場合」です。具体的には、普通免許しか持っていないのに大型自動車を運転する、第一種免許で第二種免許を必要とするタクシーやバスの運転をするなどのケースです。
次に「有効期間の過ぎた免許で運転した場合」では、運転免許の更新を受けずに車両を運転すると無免許運転となる可能性があります。このほか、「免許の取り消しを受けた後に運転した場合」や、「免許の停止や仮停止中に運転した場合」、「免許証交付前に運転した場合」というケースもあります。免許の効力がないときには運転をしてはいけません。さらに、「仮免許で練習目的以外の運転をした場合等」、「期限の切れた国際運転免許証等で運転した場合」と計7つのケースが挙げられます。一見するとひとつ目の「公安委員会の免許を受けていない状態で運転した場合」に該当しそうですが、AT車限定の普通免許でMTの普通自動車を運転したときのように、AT車限定という条件付きではあるものの、普通自動車について公安委員会の運転許可がある場合には免許条件違反が当てはまるのです。免許条件違反をおこなった場合には、罰則として3か月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられる可能性があるほか、違反点数2点、普通車で7000円の反則金を科されることがあります。なお、無免許運転の場合は、普通免許で大型バスを運転する、普通二輪免許で大型バイクを運転するといったように運転を許可されていない車種を運転した場合に違反が成立します。
AT車限定の普通免許でMTの普通自動車を運転した場合は、無免許運転ではなく免許条件違反が該当します。すでにAT車限定免許を取得済みで、どうしてもMT車を運転したいという場合には、AT限定解除の審査を受ければ運転することができるようになります。
【転ばぬ先の杖:ビギナードライバーへ】全ドライバーへ
急ハンドル、急発進、急接近、急ブレーキ・・「急」のつく運転は絶対だめだ。バックミラー、サイドミラーだけに頼らず、必ず「自分の眼」で確かめることが常に大切だ。運転免許を取った日の初心を忘れることなかれ。
≪サンキュー事故≫
 |
| 事故を起こさないためのキーワードは、自分自身の「ゆとり」である。 |
 |
| 事故を起こさないためのキーワードは、自分自身の「ゆとり」である。 右折専用の信号機がある大きな交差点なら、それが青になるまで待った方が良い。  |
 |
| 事故を起こさないためのキーワードは、自分自身の「心のゆとり」である。 急ハンドル、急発進、急接近、急ブレーキ・・「急」のつく運転は絶対だめだ。 |
「車間距離を詰めても早く着きません」 自動車学校が5回言った“大事な事”に18万人共感
Hint-Pot2022年11/22(火)
運転中、早く目的地に着きたいと焦っていたら、前の車との車間距離を詰めすぎていたという経験はありませんか? こうした車間距離不足は、追突事故につながることもあります。以前から、適正な車間距離保持が大切だと呼びかけてきた烏山自動車学校(栃木県那須烏山市)は公式ツイッター(@KarasuyamaDS)で、ハッシュタグ「#大事な事なので5回言います」を添えたユニークな投稿を行いました。すると、18万件を超える“いいね”を集め、大反響を呼んでいます。
◇ ◇ ◇
追突事故は全体の3割 車間距離不保持が要因の一つ
内閣府が発表した「令和3年交通安全白書」に掲載されている、令和2年中の交通事故発生件数を事故類型別にみると、追突は9万5520件と最も多く、全体の30.9%を占めています。原因はさまざまですが、車間距離の不保持はこうした追突事故の要因の一つと考えられます。
烏山自動車学校は事故予防のために適正な車間距離が大切であることを訴えるため、ツイッターでトレンド入りしたハッシュタグ「#大事な事なので5回言います」を添えて投稿。「車間距離を詰めても早く着きません」を5連続させるというユニークでありながら、肝に銘じたいメッセージが込められたツイートは多くの共感を呼び、18.1万件もの“いいね”を集めました。
また、リプライ(返信)には「早く着きたければ早く出発すればいいんです」「むしろ遅くなることすらある。事故を起こせばたどり着けなくなる。車間距離さえ取っていれば……」「車間距離詰めてる人、その車間で絶対止まれる自信があるんだろうなって冷たい目で見てます」など、考えさせられる言葉が寄せられています。
車間距離は詰めても到着時間に大きな差は見られない実験結果も
実際に、車間距離を詰めた走行と開けた走行では到着時間に違いはあるのでしょうか。自動車安全運転センターが平成18年度に「適正な車間距離のあり方に関する調査研究」の中で実験を行っています。
実験は混雑区間、閑散区間でそれぞれ行われました。その結果、どちらの区間においても「法定速度内で走行する場合、車間距離を開けた場合でも詰めた場合でも到着時間には大きな差はみられない」と結論づけています。
到着時間にほとんど違いがない一方で、車間距離不足は事故のリスクが高くなるでしょう。ひとたび事故を起こせば、自身や家族、会社などへの影響は計り知れません。
時速60キロまでは走行速度から15引いた数が目安に
同校の担当者さんも、車間距離を詰める人をよく見かけるそう。「私も運転中に遭遇します。教習で車間距離を詰める人の特徴やデメリットをしっかり伝えています」とコメントしています。
では具体的に、どの程度の車間距離が適正なのでしょうか。同校は普通車で条件が良い時(乾燥した舗装道路を走行する場合)の目安として、時速40キロの走行で車間距離は25メートル。50キロ走行では35メートル、60キロ走行では45メートルと、時速60キロまでは走行速度から15を引いた数を推奨。そして70キロ以上では速度と同数以上の距離を取るべきだと伝えています。
また、道路交通法第26条には、直前の車両などが急停止した時においても追突を避けるために必要な距離を保たなければならないとしています。車間距離を詰めすぎて危険な状態の運転を続けたと判断された場合は、車間距離保持義務違反として罰則を科される可能性があります。
急がば回れ。どんなに車間距離を詰めても目的地まで早く着くことはありません。年末に向けて交通事故が増加する傾向にあります。適正距離を保って、事故なく安全に目的地へ向かうことを心がけましょう。
車間距離ってどれぐらい取ればいいの??
投稿日:2019年9月5日
今回は技能の教習を進める上で多くの方が悩まれる車間距離に関してです。
車間距離とはその名の通り車と車の距離に当たるのですが、
おそらく免許を取得するまでは車間距離について考えたことがある方は少ないかと思います。
ただ、最近煽り運転が原因で交通事故になるなど
話題に上ることが多いのも事実です。
では実際にどれぐらいの車間距離を取っていれば安全といえるのでしょうか?
第二段階では公道を走行しますのでその際の参考にしてみてくださいね!
まず、法律で車間距離は最低これくらい空けなければいけません!といった決まりはありません。
かといってもちろん前の車にピッタリとくっついていればいいか、と言われると
安全運転の観点から見たら不適切であると言えるでしょう。
では、実際にはどれぐらいの距離を開けなければいけないのでしょうか??
既に免許を取得している方や現在教習中の方は、
「停止距離」といった言葉を学ばれたことかと思います。
この停止距離とは車がブレーキを踏んでから完全に停止するまでの距離のことを指し、
その時の速度によって変わってきます。
ただ、なかなか自分が走っているスピードすべての停止距離は覚えられない物ですよね。
そんな方に向けて、おおよその基準としてよく挙げられるのが、「走行速度-15m」です。
時速30kmで走っている場合は15m、時速60kmで走っている場合は45m、といった具合です。
ただ、時速が60kmを超える場合は目安が変わってきます。
この場合は、自分が出しているスピードと同じ分車間距離を空けておくと良いでしょう。
時速80kmであれば80m、時速100kmであれば100mといった具合です。
車間距離を詰めてもいいことはない!?
ここまで適切な車間距離をお伝えしてきましたが、
実際の道路を走っている車を見てみると、そこまで車間距離を空けている方は
なかなかいないように見受けられることでしょう。
ただ、安全運転には車間距離は必要不可欠です。
車は急に止まれないとはよく言ったものですが、まさにその通りです。
むしろ車間距離を詰めたからと言って、目的地に早くつけるか、
というとそういったわけではないのは明白ですよね。
ただ、車間距離を空けすぎても迷惑と思われてしまうでしょう。
そのための目安の距離が先ほどの距離なのです。
 |
| つり目の車が、最近は多い。 |
7年ぶりのフルモデルチェンジで5代目となる新型プリウスを世界初公開しました。ハイブリッド車(HEV)は今冬、プラグインハイブリッド車(PHEV)は2023年春頃に発売を予定しています。「ハイブリッドカー」「エコカー」のパイオニアであるトヨタ プリウスの新型(5代目)モデルの開発コンセプトは「HYBRID Reborn」。これは自動車産業が100年に一度の変革期といわれる現代において、プリウス自らが生まれ変わり新たなHYBRIDの象徴となるという決意が込められています。新型プリウスは強みである高い環境性能に加え、「一目惚れするデザイン」「虜にさせる走り」をキーワードに、単なる商品というだけでなく、これからの時代もユーザーに選択してもらえる愛車となるように開発が行われました。
2021年12月17日 テスラ社のタクシーが暴走。フランスのパリ市中の事故である。次々と歩道を歩いている人をひいていった。テスラ社はこのモデル3のテスラ車を販売中止にした。一体何度目だ!
純ガソリン車新車販売禁止で軽自動車が超えなければいけないハードルとは?
 |
| ダイハツ 新型 ムーヴ / ムーヴカスタム フルモデルチェンジ 7代目 DNGA 次世代スマアシ採用 2022年12月発売 |
コスト的に厳しい軽自動車のフルハイブリッド車
全く警戒する様子はありません。こうしたクマ、「アーバンベア」と呼ばれています。直訳すると都市のクマということになりますよね。こうしたアーバンベアも含め、日本ではクマを保護・管理の対象とすると法律で定められています。こうした中、今「保護重視」から「管理重視」にフェーズが変わっていると小池さん指摘されていますが、どういうことなのでしょうか。











.png)

.png)
.png)





















.jpg)
.jpg)