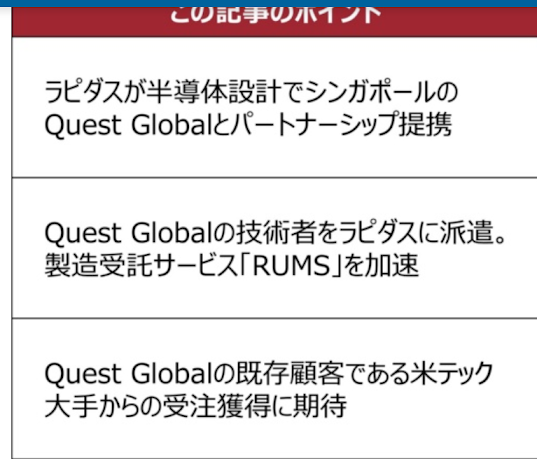世界は脱炭素に向かってなどいない、日本の製造業はグリーン最優先のエネルギー基本計画で壊滅する
新冷戦が始まり、気候変動は「問題」だと認識されなくなりつつある
2024.5.21(火)
杉山 大志
「戦争の枢軸」との新冷戦が始まった
そもそも気候変動が国際的な「問題」に格上げされたのは、リオデジャネイロで開催された「地球サミット」で気候変動枠組み条約が合意された1992年ごろからである。
これが1991年のソ連崩壊の翌年であることは偶然ではない。
冷戦の間は米ソで協力するということ自体が不可能だった。冷戦が共産主義の敗北に終わり、これからの世界は平和になり、全ての国が民主主義国として協力してゆく、というユートピア的な高揚感が生まれた。そのような状況で、世界全体での協力による、地球規模の問題の解決という機運が生まれたのだ。
これは当初から幻想に過ぎなかったのだが、2022年にロシアがウクライナに侵攻したことで、ポスト冷戦期の国際平和なるものは完全に終焉した。
そしていま、ロシアはイラン製のドローンを輸入し、北朝鮮から弾薬を購入している。中国との間では石油を輸出して戦費を調達し、工業製品を輸入している。
かくしてロシア、イラン、北朝鮮、中国からなる「戦争の枢軸」が形成され、NATOやG7はこれと対峙することになった。ウクライナと中東では戦争が勃発し、日本周辺においては台湾有事のリスクも高まっている。
この状況に及んで、自国経済の身銭を切って、高くつく脱炭素のために国際協力することなど、ありえない。戦費の必要なロシアや、テロを支援するイラン、米国に対抗して軍事力を増強する中国が、敵が支配している世界全体の幸福のためとして、自ら豊富に有する石炭、石油、ガスの使用を止めるなど、ありえない。
ごく近い将来、気候変動はもはや国際的な「問題」ですらなくなるだろう。
日本の製造業を崩壊させたいのか
そもそも2050年CO2ゼロなど技術的にほぼ不可能であるし、それを目指すだけで莫大な経済的負担が発生する。
日本政府は官民合わせて今後10年間で150兆円のグリーン投資を、規制や補助金を通じて実現する、としている。これは毎年GDPの3%を投資することに相当し、またこの原資の負担は国民1人あたり120万円に上る。
これによって政府は「グリーン経済成長」をするというが、ありそうにない。
というのは、このグリーン投資なるものの対象は再エネの拡大や、そのための送電線やバッテリーへの投資など、どれもこれも、コストのかかるものばかりだからだ。
再エネがいまや一番安いという意見があるが、都合のよい数字を見ているに過ぎない。太陽光発電は年間の稼働率が17%しかないので、残り83%は火力発電などに頼らねばならない。つまりいくら太陽光発電に投資しても火力発電設備は減らせないので、二重投資になる。
さらに、太陽光発電は既に導入し過ぎで、電力が余ったときには捨てている状態である。そこで、捨てずに利用するため、政府は送電線を建設しバッテリーを設置するとしているが、三重投資、四重投資となる。
一部の企業は再エネ100%を掲げて、その実現を容易にするためとして、政府に再エネへの投資拡大を求めている。だが日本全体の電気代を引き上げることになり、他の企業にとっては負担となってしまう。
政府はCO2回収貯留(CCS)やアンモニア発電、水素利用の導入も進めるとしている。政府の補助金で実証事業が実施されるとしても、打ち切られたとき、こんな高価な技術は世界中のどこにも売れない。グリーン成長などありえないのだ。
製造業の投資が進むのは、安価な化石燃料を使う米中
それでも政府はこのようなグリーン投資こそが世界の潮流だとして、欧州の例を盛んに引き合いに出す。けれども欧州は、とても日本が真似をすべき対象ではない。欧州は、もともと産業革命を牽引し、なかでもイギリスは「世界の工場」と呼ばれたが、今では見る影もない。
いま製造業の規模を、付加価値ベースで国際比較すると、中国が世界の29%を占めている。他は米国が16%、日本が7%だ。欧州勢はといえば、ドイツは5%だが、イギリス、フランス・イタリアは各2%にすぎない。
このナンバー1と2である中国と米国は、どちらも化石燃料を大量に利用して、安い光熱費を享受している。
他方で、日本以上に脱炭素に邁進している欧州は極めて光熱費が高くなった。
このような事情から、世界中の製造業は中国と米国に投資する一方で、欧州と日本からは逃げ出している。
ドイツの最大手化学メーカーBASFは、国内事業を縮小する一方で、中国の広州に100億ユーロを投じて工場を建設する。日本の製鉄事業者は、国内の工場を閉鎖しながら、インドには高炉を建設し、米国の製鉄事業者を2兆円かけて買収しようとしている。
さて日本はどうすべきだろうか。
数値目標を設定すべきは「電気代」
いま日本政府が第7次エネルギー基本計画でやろうとしていることは、すでに製造業を失った欧州に追随して、高い光熱費をさらに高くすることだ。これでは、日本の製造業も、欧州同様に、消滅してゆくだろう。
日本はむしろ、米国や中国のように、光熱費を下げるべきだ。このためには愚かなグリーントランスフォーメーションを止めなければならない。
検討中のエネルギー基本計画で、唯一希望が持てるのは、原子力発電の最大限の活用をきちんと位置付ける可能性があることである。原子力発電であれば、脱炭素と、エネルギー安全保障、安定・安価な電力供給を同時に実現できる。
そして、CO2排出削減などではなく、電気代にこそ数値目標を設定すべきである。日本の電気代は高騰してきたが、これを2010年の水準(産業用がキロワットアワーあたり14円、家庭用が同21円)まで戻すことを目標にすべきだ。そうすれば、無駄なグリーン投資は不可能になる。
この2点を含めて、現在のエネルギー政策に危機感を持つ筆者を含む有志で、以下の11箇条の提言を「エネルギードミナンス 強く豊かな日本のためのエネルギー政策(非政府有志による第7次エネルギー基本計画)」としてまとめた。ぜひご覧頂きたい。
光熱費を低減する。電気料金は東日本大震災前の水準を数値目標とする。エネルギーへの税や賦課金等は撤廃ないし削減する。
原子力を最大限活用する。全電源に占める比率50%を長期的な数値目標とする。
化石燃料の安定利用をCO2規制で阻害しない。
太陽光発電の大量導入を停止する。
拙速なEV推進により日本の自動車産業振興を妨げない。
再エネなどの化石燃料代替技術は、性急な導入拡大をせず、コスト低減を優先する。
過剰な省エネ規制を廃止する。
電気事業制度を垂直統合型に戻す。
エネルギーの備蓄およびインフラ防衛を強化する。
CO2排出総量の目標を置かず、部門別の排出量の割当てをしない。
パリ協定を代替するエネルギードミナンス協定を構築する。
中国が目論む「台湾統一の次は日本のフィンランド化」、台湾有事(台湾戦争)の地政学から考える日本のエネルギー戦略
2024.4.13(土)
私はエネルギー政策の専門家であるが、エネルギーとは、何よりも戦略物資であり、20世紀の戦争の多くはエネルギーを巡るものだった。したがってエネルギー政策を論じるならば、本来は、まずは地政学や安全保障から入らねばならない。だが平和ボケの日本においては、エネルギー専門家と称していても、環境のことは知っていても、地政学も安全保障も全く知らない方が大半である。そこで本稿では、日本を巡る地政学状況について述べ、いま安全保障の観点においてエネルギー政策はどうあるべきか、指摘したい。
(杉山 大志:キヤノングローバル戦略研究所研究主幹)
中国の歴史観における台湾統一の必然性
1949年に中国は共産党独裁国家になった。以来、文化大革命では凄惨な虐殺があり、またウイグル、チベットなどでのジェノサイドが長らく指摘されてきた。このような独裁政権は、ひとたび権力を手放すと、たちまち報復の対象になる。このことは、冷戦末期の東欧における独裁者の処刑など、枚挙に暇がない。
中国共産党は、1989年の天安門事件で、その深淵を見た。あと少しで彼らは破滅するところだった。
中国共産党が台湾独立を決して認めることができないのは、台湾が「中国人による、民主的な、もう一つの中国」であることを容認できないからだ。共産党独裁体制に代わるものが存在しうること、そして中国国内の人権問題を批判し、共産党の正統性を批判することは断じて許されない。
したがって、最も悪くても、親中的な、つまり中国共産党を批判しない台湾であるべきであり、もっといえば、中国共産党の下に統一されるべきである、となる。
以上は本音の部分であるが、台湾統一の必然性は、中国ならではの歴史観で愛国的に物語られている。
つまるところ、中国は歴史的に一つであるゆえ、その一部である台湾は当然に統一されねばならない、というものだ。
米NVIDIA、AI半導体市場を支配も顧客が競合になる恐れ
AI半導体市場で70~95%のシェア、粗利益率78%
2024.6.7(金)
小久保 重信
米アマゾン・ドット・コムや米グーグル、マイクロソフトなどクラウドサービスを手がける企業は、自社サービス向けAI半導体を独自開発しており、エヌビディアへの依存を減らそうとしている。今後これら企業の半導体開発が進めば、エヌビディアにとって顧客はライバルと化す。現在、これらIT(情報技術)ビッグ3に米オラクルを加えた4社がエヌビディアの大口顧客である。この4社から得ている収益はエヌビディアの売上高の4割以上を占める。
米アマゾン・ウェブ・サービス(Amazon Web Service、AWS)は、18年にAI専用プロセッサー「Inferentia」を開発した。機械学習(マシンラーニング)の推論に特化しており、処理コストを大幅に削減できるというものだ。AWSは21年に機械学習のトレーニング専用半導体「Trainium」を発表し、23年には、その第2世代版「Trainium2」を発表した。
マイクロソフトは23年、データセンターで生成AIを動かすための半導体「Maia」と、クラウドサービス用半導体「Cobalt」を発表した。グーグルは機械学習のトレーニングや推論に特化した「Tensor Processing Unit(TPU)」を自社のクラウドサービス「Google Cloud Platform(GCP)」で提供している。24年5月には第6世代のTPU「Trillium」を発表した。
AI処理はサーバーから端末へ
米エヌビディアのデータセンター向け半導体事業に対する最大の脅威は、処理が行われる場所の変化かもしれないとCNBCは指摘する。
オープンAIが開発したような大規模モデルは、推論のためにGPUの巨大なクラスターを必要とするが、アップルやマイクロソフトのような企業は、より少ない電力とデータで動作し、バッテリー駆動のデバイス上で動作する「小規模モデル」を開発している。
これらモデルの能力は最新の「Chat(チャット)GPT」のようなレベルには達しない。しかし、テキストの要約や画像検索など、日常生活の様々な用途に利用できる。こうしたIT大手の新たな動きもエヌビディアにとっての潜在的な脅威だと指摘されている。
米半導体大手エヌビディア(NVIDIA)の業績拡大が続いている。テクノロジー大手による生成AI(人工知能)への投資が活況を呈すなか、それを支える同社製GPU(画像処理半導体)の需要増には終わりが見えないようだ。
売上高、純利益ともに過去最高更新
同社が2024年2月21日に発表した、2024会計年度第4四半期(23年11月~24年1月期)決算は、売上高が、221億300万ドル(約3兆3200億円)で、前年同期の3.7倍だった。四半期売上高の200億ドル超えは、これが初めてである。純利益は122億8500万ドルで、8.7倍。売上高とともに過去最高を更新した。
併せて発表した、25会計年度第1四半期(24年2月~4月期)の売上高見通しは240億ドル前後(約3兆6100億円)で、市場予測の220億ドル前後を上回った。
米エヌビディアのジェンスン・ファンCEO(最高経営責任者)は決算説明会で、「AIは転機を迎えた。AI基盤となる、計算能力に対する需要は依然として膨大だ。企業、業界、国家を超えて世界中で需要が急増している」と述べた。
米ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)によると、この決算発表を受けて、同日の米株式市場でエヌビディア株は、一時約8%上昇した。
AI向け半導体部門5.1倍、全売上高の83.3%に
売上高を事業部門別に見ると、AI向け半導体を含むデータセンター部門は、184億ドル(約2兆7600億円)で、前年同期の5.1倍になった。同部門の売上高全体に占める比率は83.3%に達した。この比率は、24会計年度第1四半期で59.6%、同第2四半期で76.4%、同第3四半期80.1%と、四半期ごとに上昇している。
ラピダスが半導体設計支援のシンガポールQuest Globalと提携、「GAFAMからの受注狙う」
2025.03.27
Rapidus(ラピダス、東京・千代田)は2025年3月25日、半導体の設計支援や人材派遣を手がけるシンガポールQuest Global(クエスト・グローバル)と協業すると発表した。
クエスト・グローバルの顧客企業がラピダスの2nm世代のプロセス技術を利用して半導体を設計開発できるようになり、ラピダスにとっては製造受託の顧客開拓につながる。協業を通じ、米IT(情報技術)大手やファブレス半導体メーカー、AI(人工知能)スタートアップなどからの受注を狙う。
クエスト・グローバルは世界に2万人を超える技術者を抱え、米Microsoft(マイクロソフト)や米Amazon Web Services(アマゾン・ウェブ・サービス、AWS)、米NVIDIA(エヌビディア)などAI分野の大手企業を顧客に持つ。ラピダスはクエスト社との協業を通じ、こうした米大手との接点(タッチポイント)を強化して受注獲得を狙う。半導体設計の専門部隊を持たないIT企業などに伴走し、先端半導体の設計開発のハードルを下げるよう支援する。
同日の記者会見でラピダス社長の小池淳義氏は、協業を通じAWSや米Google(グーグル)など「GAFAMと呼ばれるような大手顧客の受注を確実に獲得したい」と話した。同社は以前は、顧客獲得に向けてこうした大手テック企業へ直接コンタクトを取っていた。だがクエスト・グローバルのような、いわゆるデザインハウス(設計サービス会社)が実質的な設計を担うケースが大半だと判明したという。
クエスト・グローバル共同創業者兼最高経営責任者(CEO)のアジット・プラブ氏は、ラピダスの設計部門の支援に向けて「500人を超える技術者を充てる可能性がある」と話した。同社は日本の顧客を支援する技術者を2300人以上抱え、日本の拠点には500人規模の人員を配置している。日本拠点の技術者数を今後5年間で2倍程度に増やす計画という。
先端半導体ラピダス シンガポールの半導体設計会社と協業合意
2025年3月25日
国の全面的な支援を受けて先端半導体の量産を目指す「ラピダス」は、シンガポールの半導体設計会社と協業することで合意したと発表しました。シンガポールの会社から技術面での支援を受けるとともに、量産化が実現した際には、顧客の獲得でも協力していくということです。
ラピダスは25日、シンガポールの半導体設計会社「クエスト・グローバル」と協業することで合意し、共同で会見を行いました。
クエスト・グローバル社は世界20か国に拠点を置く半導体の設計会社で、今回の協業では、この会社がラピダスにエンジニアを派遣するなどして技術面で支援をしていくということです。
また、この会社は、宇宙や医療などの分野で幅広い顧客を抱えていることから、ラピダスが再来年に先端半導体の量産化を実現した際には、顧客の獲得にも協力していくとしています。
会見でラピダスの小池淳義社長は「今回の連携により、われわれが気付かなかった企業とつながることができる可能性もあり、顧客の拡大という意味で非常に意味がある」と話していました。
また、クエスト・グローバル社のアジット・プラブCEOは「われわれの顧客の中にはすでにラピダスの製品を使いたいという会社もある。AI分野における新たな顧客の開拓も協力していきたい」と話していました。
ラピダスが顧客獲得へ弾み、「必須のパートナー」クエストと協業
2025年03月29日
ラピダス(東京都千代田区、小池淳義社長)は2025年03月25日、半導体設計などを手がけるシンガポールのクエスト・グローバルと協業すると発表した。ラピダスはクエスト・グローバルの顧客にファウンドリー(半導体製造受託)サービスを提供するほか、クエスト・グローバルの人材がラピダスの半導体設計サービスを支援する。ラピダスは4月からパイロットラインが稼働する。今回の協業によって顧客獲得に弾みをつけたい考えだ。
同日、都内で会見した小池社長は「クエスト・グローバルは顧客との関係性が非常に深い。我々が顧客を獲得していくためには必須のパートナーだ」と強調した。クエスト・グローバルのアジット・プラブ最高経営責任者(CEO)は「航空宇宙やエネルギーなどの顧客を支援してきた。今後は新興企業への支援も行っていきたい」とした。
また、小池社長は「新興企業向けに(1枚のウエハーに異なる半導体を製造する)シャトルサービスをやりたい」と話した。設計支援やサービスを充実させ、顧客開拓を急ぐ。
次世代半導体の国産化を目指すラピダスは25日、半導体の設計などを手がけるシンガポールのクエスト・グローバルと協業すると発表した。人工知能(AI)向けに需要拡大が見込まれる先端品の開発を加速させる。クエストの顧客網も活用する狙いがある。
AIは消費電力が大きく、ラピダスはエネルギー効率に優れた次世代半導体を2027年に量産して供給する計画だ。回路線幅2ナノメートル(ナノは10億分の1)相当の最先端品を目指しており、設計面を中心にクエストに技術支援を求める。
ラピダスの小池淳義社長は東京都内で記者会見し、協業によって「顧客に合わせた今までにない新製品をつくれるようになる」と話した。(共同)