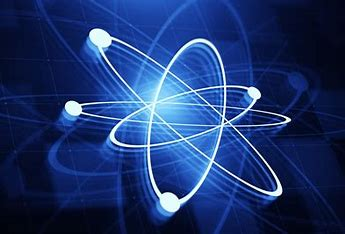次世代革新炉、電力会社は投資に二の足 GX基本方針1年、求められる国の後押し
2024年3月4日
政府が原子力の活用を巡り「次世代革新炉の開発・建設に取り組む」などとする「GX(グリーントランスフォーメーション)実現に向けた基本方針」を令和5年2月に閣議決定し、約1年が経過した。電力各社は安全性や効率性を高めた次世代炉の開発を進めているが、安全対策費や高騰する火力燃料費が懸念材料となり、実際に建設へ乗り出すかには二の足を踏んでいるのが現状だ。原発による電力の安定供給確保のためにも、資金面の支援拡充が不可欠となる。
電力会社では、関西電力と三菱重工業、九州電力、四国電力、北海道電力が次世代炉の一つ「革新軽水炉」を共同開発中。中部電力も5年9月、次世代炉である小型モジュール炉(SMR)を開発中の米企業「ニュースケール・パワー」に出資すると発表した。
関電は5年12月、美浜原発(福井県美浜町)を報道陣に公開した。構内は非常用電源や防潮堤などの安全対策が細心に施され、3基あるうち、再稼働済みの3号機の心臓部は、原子炉を取り巻いて水や蒸気の配管が張り巡らされている。
一方、隣接する1、2号機では廃炉作業が進み、27年度までに解体撤去される。政府はGX基本方針で「廃炉を決定した原発の敷地内での建て替え」(リプレース)の対象として次世代炉を明記。廃炉で地域経済への打撃が予想される美浜町では建て替えを求める声が強く、国の方針を歓迎する。
関電の森望社長も5年12月の産経新聞のインタビューで「建設期間を考慮すると相当手前で用意して(原発の新設が必要になる)将来に備える必要がある」とした。
ただ実際には、関電もすぐには動き出せない事情がある。「投資を回収できるのか不安が残る」(森氏)からだ。火力燃料費を高止まりさせている国際情勢や、電力自由化で直面する電気の販売競争で、経営判断が慎重になっているのだ。
建設後の安全対策費の負担も想定される。既存の原発に関しては5年9月、廃炉を決めたものを除く全7基が再稼働する体制に復帰したが、東日本大震災後の新規制基準に対応するための安全対策費に1兆円以上かかった。次世代炉も巨額の費用がかかるとみられる。
森氏は「長期にわたる事業の(投資資金を回収できない)リスクを低減する仕組みが必要ではないか」と訴える。
国は今年2月、脱炭素社会の実現を後押しする「GX経済移行債」の入札を初実施した。調達した資金は次世代炉の開発・建設などの支援に充てる。こうした支援策などを通じ電力会社の投資への不安を軽くしていくことが求められる。
激化する国際競争、司令塔設置が急務
次世代革新炉の開発は世界で進められているが、日本は遅れており、国として司令塔となる組織を設立するなどし、後押しすることが急務だ。
政府は令和32(2050)年に二酸化炭素の排出量を実質ゼロにする目標を掲げており、原発は不可欠な電源だ。
しかし稼働年数は原則40年、最長60年。全国に36基(建設中含む)ある既存原発を60年間、動かせても32年には23基まで減る。再稼働や次世代炉を含む建て替え(リプレース)、新増設を進めなければ今の水準の原発は維持できない。
次世代炉のうち、従来の原子炉の設計を基本に安全性を高めたのが「革新軽水炉」だ。メーカーでは三菱重工業と東芝エネルギーシステムズなどが開発中。三菱重工は関電などと組むが、投資資金が回収できない懸念から電力会社は実際の建設に消極的だ。
一方、政府は今後10年間で「高温ガス炉」「高速炉」の実証炉の建設を目指す。高温ガス炉は高温の熱を取り出し発電効率を高められる。高速炉はプルトニウムを含む使用済み核燃料の再利用に適している。いずれのメリットも軽水炉より優れている。
高温ガス炉などは、海外では米国や英国、フランスなどが開発を進め、中国とロシアが実証炉の運転や商業運転を実現した。日本は安全確保の技術確立などはこれからだ。工程管理や原子力規制委員会との対話を担う国の司令塔組織を早期に設置するなどし、開発や建設を支援する必要がある。(牛島要平)
安定収益を保証する仕組みを 東京都市大・高木直行教授
原子力発電所の次世代革新炉を巡っては、初期投資を抑えられるSMRの開発も世界で進んでいる。ただ、米国初のSMR建設を目指していたニュースケール・パワーは、アイダホ州での計画については2023年11月、中止を発表した。人件・資材費の高騰により、発電コストが高くなるとの判断だ。
こうした状況を踏まえると、次世代炉の実現には電力会社が初期投資を回収しやすくする仕組みが必要だ。
英国では22年3月、大型原発の新設に向けた資金調達を支援する「RABモデル」の関連法が成立した。建設費用を電力消費者にも負担してもらう形で規制機関が料金を認可し、電力会社の安定した収入を保証する。
同じ方式は空港などにも適用されており、次世代炉の建設でも同様の仕組みが考えられる。
このほか、安全性をどう確保するかも課題だ。特に高温ガス炉や高速炉は技術面に加えて、新しい設計に対応した安全審査体制を整える必要がある。立地場所の地域住民に対する十分な説明も求められるだろう。
【落合陽一】安宅和人と考える「2022年のシン・ニホン」。“脱成長”の是非、そして「猫・きのこ・遊牧民」の真意とは?
109,500 回視聴2022/01/06
落合 陽一 (東京大学大学院学際情報学府/日本学術振興会特別研究員)
47,024 回視聴2013/10/03
1987年生,メディアアーティスト. IPA認定スーパークリエータ.名前の由来はプラス(陽)とマイナス(一),生まれたときから電気が好き.父は作家・落合信彦.筑波大学でメディア芸術を学び,現在,東京大学大学院学際情報学府在学中.制作のコンセプトは変幻するメディア装置を用いて主観をあやふやにさせる表現の追求や事象の「電気的再構成」.研究テーマは,HCI,ディスプレイ,メディアアートなど多岐に及ぶ.日本学術振興会特別研究員DC1.主な作品や研究に,アリスの時間(府中市美術館),モナドロジー(MMM/TokyoDesignersWeek),コロイドディスプレイ(ACM SIGGRAPH),サイクロンディスプレイ(ACM SIGGRAPH)など視覚への訴求を特徴とするものが多い.国内外の受賞歴多数.英国国営放送をはじめとしてメディア露出多数.TEDxTokyo yzやTED@Tokyoではスピーカーを務め好評を博した.作家業の他に,ユーザーインターフェースやシステムデザインを専門とするジセカイ株式会社に経営/研究で参画し学際研究分野のアウトリーチなども行うなど多岐に活動実績がある.
2018年度 特別講義・落合陽一 「ユビキタスからデジタルネイチャーへ:アート・エンターテイメント・デザイン」
195,361 回視聴2018/06/27
OCW Tsukuba
我々はユビキタスコンピューティングの先に計算機自然(Digital Nature)の到来を見据えている。計算機自然では、人と機械、物質世界(Material World)と実質世界(Virtual World)の間に、今までの工業化社会よりも多様な未来の形が起こりうると考えられる。本研究室は、そういった物質性と実質性の間で、計算機応用のもたらす様々な選択肢を想定し、それらを計算機科学的に実装することで、産業・学問・芸術にいたる様々な問題解決に挑戦し、人・計算機・自然における新たな文化的価値の創成を目指しており、そのケーススタディや現在に至るメディア史などを紹介する。
#58/新たなデジタルネイチャーの世界/ピクシーダストテクノロジーズ株式会社 共同創業者 代表取締役CEO 落合 陽一/この国の行く末2
7,010 回視聴2020/08/24
#59/新たなデジタルネイチャーの世界/ピクシーダストテクノロジーズ株式会社 共同創業者 代表取締役CEO 落合 陽一/この国の行く末2
3,838 回視聴2020/08/24
【番組概要】
アーティスト、研究者、経営者、教育者など様々な顔をもち、光や音などの波動を制御する技術を活用し三次元化しようとしている。魔法のような技術を生活に溶け込ませ新たなデジタルネイチャーの世界を目指す。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
「この国の行く末2 -テクノロジーの進化とオープンイノベーション-」
SBIホールディングス株式会社 代表取締役社長 北尾吉孝をナビゲーターに、医療・エネルギー・金融・AI・ロボティクスなど、各分野の最前線で活躍するトップランナーをゲストにお招きし、日本と世界の未来について語り合う番組。
【ナビゲーター】
SBIホールディングス株式会社 代表取締役社長 北尾吉孝
竹内香苗
#53/量子コンピューターの進化に取り組む/MDR株式会社 代表取締役 湊 雄一郎/この国の行く末2
3,908 回視聴2020/08/10
【番組概要】
量子コンピューターの進化に寄与しているベンチャー企業。圧倒的な機能を持つ
次世代のコンピューターが幅広い分野で活躍されるよう実用化に向けて取り組む。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
「この国の行く末2 -テクノロジーの進化とオープンイノベーション-」
SBIホールディングス株式会社 代表取締役社長 北尾吉孝をナビゲーターに、医療・エネルギー・金融・AI・ロボティクスなど、各分野の最前線で活躍するトップランナーをゲストにお招きし、日本と世界の未来について語り合う番組。
【ナビゲーター】
SBIホールディングス株式会社 代表取締役社長 北尾吉孝
竹内香苗
落合陽一の研究内容に堀江が迫る!【HORIEMON.com vol.3】
375,674 回視聴2014/02/16
【落合陽一】高市早苗氏の「決意」。安全保障、エネルギー政策はどうするのか?
554,987 回視聴2021/09/23
_____
いよいよ来週水曜日に自民党総裁選の投開票が行われ、事実上、次の内閣総理大臣が、候補者である河野太郎氏、岸田文雄氏、高市早苗氏、野田聖子氏のうちの誰かに決まる。コロナ対策、経済、安全保障、エネルギー政策、多様性…日本の未来はどうなるのか?落合陽一が、NewsPicks初登場となる高市早苗氏に迫る。
落合陽一の特番
30,252 回視聴2021/07/11
番組内容
最新著書「 半歩先を読む思考法 」について、 MBSアナウンサー大吉洋平がインタビュー。
【落合陽一】南海トラフ地震や首都直下地震、富士山噴火。天災リスクのリアル
428,230 回視聴2021/03/18
世間では徐々にコロナ後の世界についての議論がされるようになってきた。しかし、忘れてはならないのが、日本が「災害大国」だと言われるほど、歴史的に多くの自然災害に見舞われてきた事実と今後も“起きる”という現実だ。コロナにより日本の災害対応への弱点が露呈したとの指摘もある。近い将来に発生すると想定されている南海トラフ地震や首都直下地震、富士山噴火などにどう備えていくべきか?東日本大震災から10年をむかえた今、日本を生き抜くために何が必要かを考える。
<ゲスト>
黒川清(福島第一原発「国会事故調」元委員長)
鎌田浩毅(京都大学大学院人間・環境学研究科 教授)
越村俊一(東北大学災害科学国際研究所教授)
首都直下型、南海トラフ地震、富士山噴火…2040年までに災害が起こると予想される日本で生き抜く防災術とは?【成毛眞 × 鎌田浩毅】
162,535 回視聴2021/09/24
防災講演会「広島も大きな被害!南海トラフ地震を知ろう」
11,875 回視聴2021/12/08
広島市江波山気象館 公式チャンネル
チャンネル登録者数 161人
#南海トラフ地震
令和3年11月28日(日)に開催しました防災講演会の様子を期間限定で配信いたします。
主催:広島市江波山気象館・気象庁 広島地方気象台
講師:広島地方気象台長 中村浩二氏
東京大学理学部オープンキャンパス2021 講演「揺れない地震の話」井出哲教授
1,777 回視聴2021/08/02
東京大学大学院理学系研究科・理学部 School of Science, The University of Tokyo
チャンネル登録者数 5.01万人
#東京大学 #理学部 #オープンキャンパス 2021 Online
「揺れない地震の話」
講師:井出哲 地球惑星物理学科 教授