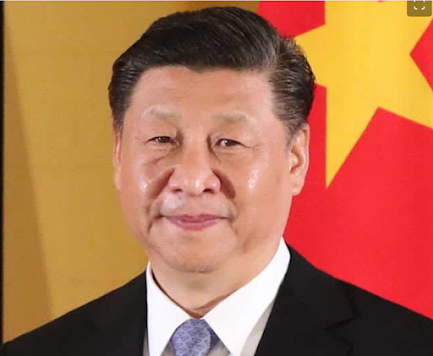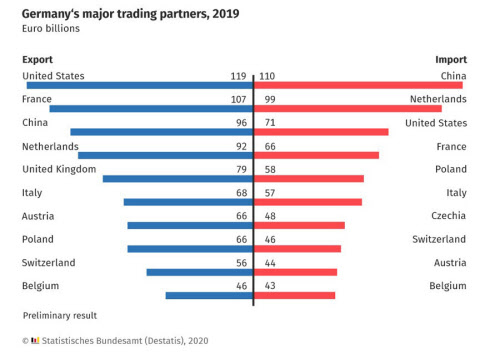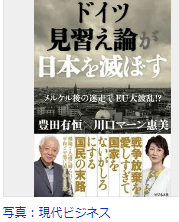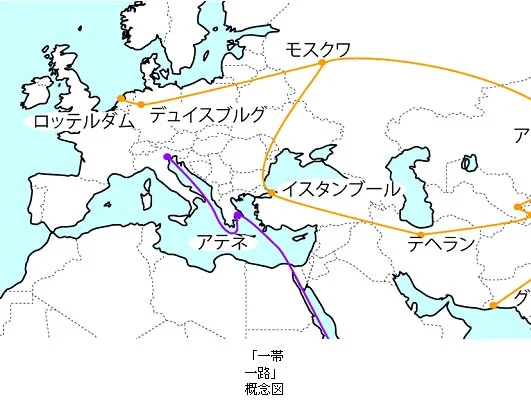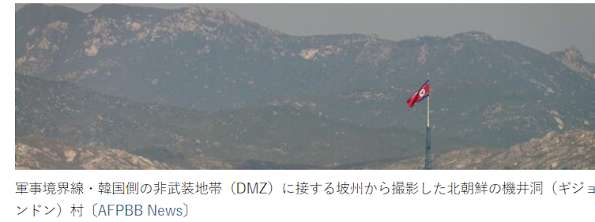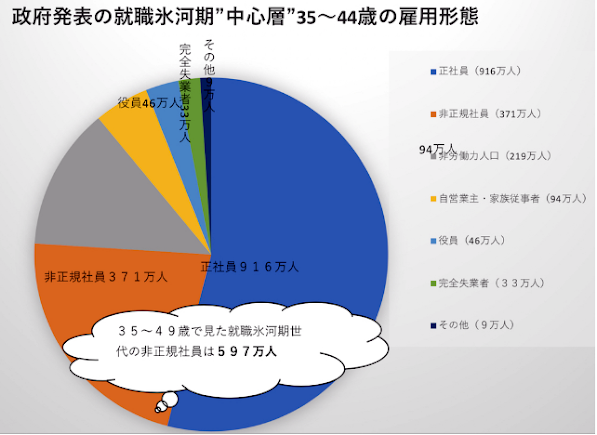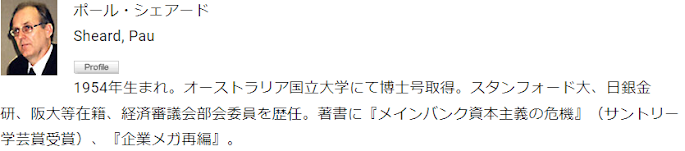❹中国の「一帯一路(債務の罠外交)」とプーチンが生み出した『 欺瞞作戦(マスキロフカ 』 、『偽旗作戦』、
サウジへの 一 帯 一 路(債務の罠外交)始まる!
中国の買収に対する警戒心なし......?
ゲスト:(株)アシスト代表取締役 平井 宏治氏 2021/11/27 公開
15年前に上海に行ったとき、あまりのサンタナ(F.W.のクルマ)の多さにこりゃやばいぞと感じましたが、メルケルさんって2015年以降かな、移民・難民を受け入れたり、この動画にあるように優れた複数の企業を売っちゃったり、ドイツをなくす政策を打ってますね。もう我々の知っているドイツではないようです。日本も笑ってられないですが。目の前の利益にばかり取り憑かれているとこうなっちゃいますね。
【2021年12月3日 AFP】ドイツの首都ベルリンの国防省で2021年12月2日、アンゲラ・メルケル(Angela Merkel)首相(67)の退任式が行われた。メルケル氏は送別の曲として、共産主義政権時代に「パンクのゴッドマザー」と呼ばれた歌手ニナ・ハーゲン(Nina Hagen)のヒット曲を選び、周囲を驚かせた。ドイツでは2021年12月8日、議会が社会民主党(SPD)のオラフ・ショルツ(Olaf Scholz)現財務相をメルケル首相の後任として正式に選出し、16年間続いた保守政権から中道左派政権へと移行する。記者会見でこの選曲について聞かれると、共産主義 の東ドイツで過ごした若い頃に聴いた思い出の曲だと説明。「この曲は私の青春 のハイライトだった」と語り、「この曲も東ドイツで生まれ、偶然にも、かつて私の選挙区だった地域では今でも流れている。だからすべてがきょうに合っている」と語った。16年間、中国覇権主義に手を渡して幸せでした。
メルケル独首相、アウシュビッツ初訪問 「深き恥でした」表明。
ポーランド・オシフィエンチムにあるナチス・ドイツのアウシュビッツ強制収容所跡を訪れる人々(2019年12月5日撮影)「深き恥でした」表明。メルケル氏による同地訪問は重要な政治的メッセージと受け止められている。
アンゲラ・メルケル首相に関しては、EUの最高実力者であり、世界の民主主義を支える保守政治家という印象が強いが、実はそんな単純な話ではない。メルケル政治16年の間、ドイツは皆が知らないうちに左傾化し、今や、国を挙げてグローバリズムに向かってまっしぐら。すでに保守不在の国になってしまったが、不思議なのは、ほとんどの国民が、いまだにそれに気づいていないことだ。
実は、その現象は日本でも同時進行した。保守の政治家として現れた安倍晋三前首相が、メルケル政治の後を追うように、ひたすらグローバリズムに突っ走ったことは記憶に新しい。環太平洋パートナーシップ(TPP)協定の成立、入管法の改正はもとより、「尖閣諸島に公務員常駐」はフェードアウト、韓国との慰安婦問題では無駄な大金を使い、官邸のホームページでは「ニーハオ!」と言って中国に歩み寄り、もちろん憲法9条の改正もできなかった。
外圧に負けた安倍晋三氏、華やかに引退するメルケル氏
つまり、「美しい国、日本」(安倍晋三氏の2006年の所信表明演説)はかなわず、リベンジの「日本の決意」(2014年刊行の著書の表題にもなった)もダメだったのだ。なのに、左翼は安倍首相をいまだに右翼だと言っている。
ただ、メルケル首相と安倍晋三前首相には大きな違いがある。保守・安倍氏は当初、本気で「美しい日本」を作ろうと思っていたと見受けられるが、保守・メルケル氏の最終目標は最初から社会主義化、あるいはグローバル化だったのではないか。
そして、安倍氏は保守の信条にもかかわらず、多くの外圧に負け、次第に保守路線から外れ、最後には与党からも野党からも叩かれて退場した。ところが、メルケル氏は首尾一貫、保守の旗を立てながら、巧みに、しかも時間をかけて、ドイツの舵を左に切った。そして、与党からも野党からも叩かれず、今や、多大な功績を残した首相として華やかに消えようとしている。あたかも、自分の使命は終わったと言わんばかりに。
いったい、政治の舞台裏では何が起こっているのだろう。本稿では、目前に迫るドイツの総選挙を見ながら、その謎解きを試みたいと思う。
ドイツのメルケル首相は2015年3月10日の民主党の岡田克也代表との会談で、ナチスによる犯罪行為への反省に触れつつ、日本に慰安婦問題の解決を促した。これは、戦前・戦中の日本と独裁者、ヒトラー総統率いるナチス・ドイツとの混同とも受け取れ、問題といえる。
「米国は同盟国で、長年の付き合いがあるのでまだ知識層は分かっているが、欧州各国は韓国のロビー活動に相当影響されている」外務省幹部はこう警鐘を鳴らす。韓国 だけでなく、中国 も安倍晋三首相をヒトラーになぞらえたり、南京事件をユダヤ人大虐殺(ホロコースト)と同一視したりするなどの宣伝工作活動を世界で展開 している。メルケル氏が9日の安倍首相との共同記者会見で、日本の行為を指してではないもののホロコーストに言及し、「過去の総括は和解のための前提だ」と指摘したことも、旧日本軍とナチスを一定程度混同している可能性をうかがわせる。だが、戦前・戦中の日本では、兵士らの暴走による戦争犯罪はあっても、ナチス・ドイツのような組織的な特定人種の迫害・抹殺行為(ジェノサイド) など全く行っていない。東京裁判でインド代表のパール判事は「本件被告の場合は、ナポレオンやヒトラー(ら独裁者)のいずれの場合とも、いかなる点でも、同一視することはできない。
人類の敵・中国を大躍進させたメルケル首相「16年間の独裁」 2020.05.25
確かに私も安倍首相が演説の達人だとは思わないし、舌足らずな側面があるのは否定できない。
しかし、我々国民は「口(演説)のうまい人間」をリーダーにすべきなのだろうか? ドイツの演説の名手といえば、ナチスを率いたアドルフ・ヒットラーを忘れることはできない。天賦の才能能はもちろんのこと、「鏡を見ながら手ぶり身振りの練習を繰り返した」という地道な努力によるところも大きい。
さらには、宣伝相に「現在の広告マーケティングの基礎を築いた」と評される天才ゲッペルスを起用したことも効果的であった。この演説とプロパガンダ(広告)によって、ドイツ国民を熱狂の渦に巻き込んだ手腕は特筆に値する。
しかし、その結果ドイツがどのような道を歩み、ヒットラーを含むドイツ国民がどのような結末を迎えたのかは、改めて語るまでもない。
聴衆が演説の内容そのものから受ける影響はせいぜい1割程度で、9割は話者の身振り手振り、表情、声の調子、さらには会場の他の聴衆の態度によるものだ言われる。つまり、演説と言うのは「中身」ではなく「雰囲気」で勝負するものである。
だから、「演説(口)がうまい政治家」は最も警戒すべきなのである。 安倍首相に、演説(口)が上手になるよう練習を求めるのは全く無意味だ。我々日本国民にとって大事なのは、「どのようなことを実行し、どのような結果を出すか」なのである。
さらに、メルケル氏は、16年間にもおよぶ任期の間、表面的にはドイツを先進国のリーダーとして維持してきたように見えるが、実はドイツをどうしようもなく悲惨な状況に追い込んだ戦犯なのである。
16年間の長期政権
安倍晋三首相の通算在職日数は2019年11月20日で計2887日となり、明治、大正期に首相を3回務めた桂太郎の2886日を超えて憲政史上最長となった。
記録更新は約106年ぶりであるが、2887日ということは8年ほどでしかない。また、自民党の総裁任期は連続2期6年であったものを、連続3期9年に改正したが、さらにこれが延長されなければ安倍首相の任期は近いうちに終わる。
それに対して、ソ連崩壊後、一応普通選挙が行われているロシアのプーチン氏は、第2代大統領(在任2000年 - 2008年)、第5代および第9代政府議長(首相)(1999年 - 2000年、2008年 - 2012年)第4代ロシア連邦大統領(2012年5月7日~ )の座にある。首相時代も傀儡大統領を顎で使っていたから、実質20年にもわたる政権 だ。
また、4月22日に予定されていた憲法改正案の是非を問う全国投票の改憲案には「2024年に任期が切れるプーチン氏の続投を最長で36年まで可能にする」内容が含まれていたが、新型肺炎の影響で投票が延期されている。
プーチン氏にはさすがに及ばないが、メルケル首相も2005年から現在まで15年間、2021年の任期まで数えれば16年間首相の地位にあることになる。
2021年での退任を表明したのは、2018年10月の総選挙でキリスト教民主同盟(CDU)が惨敗した責任をとるためだが、新型肺炎で世の中が様変わりしている現在、「国難を救うために続投する」と言いだす可能性は無きにしもあらずだ。「国難」を口実に権力を掌握するのは独裁者の常とう手段である。
オールドメディアは安倍首相をまるで独裁者のように扱うが、安倍氏を含む日本の歴代首相など可愛いものである......
共産主義教育の洗礼を受けた
意外に知られていない事実は、メルケル氏が旧東ドイツで育ったということである。
生まれたのは(西ドイツの)ハンブルグであるが、1954年に、生後数週間のメルケル氏は両親と共に東ドイツへ移住する。ベルリンの壁建設は1961年であるから、当時はまだ東西の往来ができたが、ベルリンの壁建設以降、1989年の崩壊まで幼少期・青年期を含む30年以上の間「マルクス・レーニン主義」をたたき込まれたということである。
東ドイツで「マルクス・レーニン主義教育」を受けたメルケル氏はロシア語に堪能である。逆にKGB時代に東ドイツで勤務していたプーチン氏はドイツ語が堪能である。首脳としてほぼ同時代を生ききた2人の間柄は親密だと考えるのが自然だが、2人が「何語で会話をするのか?」という疑問は、ウォチャーたちの興味の的になっている。東ドイツで育ったからと言って、共産主義的思想を持っているとは限らないのだが、わざわざ西側から東ドイツに移住する両親の下、東ドイツの共産主義教育の洗礼を受けた人物が、まったく影響を受けていないと考えるのも不自然だ。
プーチン氏と馬が合うのも、政治・信条の共通項が多いからと考えるべきではないであろうか?共産主義中国と親しいのは当然だ
また、欧州には媚中派が多いが、その中でもメルケル氏に媚中的行動が目立つのは、共産主義国家に対する共感が原因と考えるべきかもしれない。ドイツが共産主義中国を応援するのも至極当然だし、ドイツが盟主であるEUが左傾化することも後押しているのであろう。
また、環境を始めとしてリベラル(偽装共産主義)的政策を強力に推進する理由もそこにあるのではないであろうか?
ファシズムや共産主義のような「反民主主義」は、リーダーの演説やプロパガンダが優れている。なぜかといえば、その実態が国民を虐げるシステム(組織)であるから、国民の関心を引くために「見た目を良くすること」に注力しなければならないからだ。
つまり、粗悪な商品を立派な箱とリボンで飾り立てる「中身がガッカリな商品」なのである。
逆に、リーダーの演説が今一つでプロパガンダも大したことがない「民主主義国家」は、新聞紙に無造作にくるまれたダイヤモンドといえるであろう。
悪貨は良貨を駆逐する
振り返れば、東西ドイツ再統合がドイツ没落の始まりである。1990年に「ドイツ再統一条約」が調印されて、東西ドイツは統合された。この莫大な統合コストは西ドイツ国民が負担し、東ドイツ国民はただその恩恵を被ったというのが実態だ。
それにも関わらず、旧東ドイツ国民のかなりの数が「共産主義時代への回帰」を望んでいるとされる。
大きな理由は旧東ドイツ地域の所得がいまだに旧西ドイツ地域に及ばないということだと言われる。格差と言っても旧西ドイツの80%は維持しており、統合前の旧西ドイツの25%程度と言われた旧東ドイツの水準からは劇的に改善している。
振り返れば、東西ドイツ再統合がドイツ没落の始まりである。1990年に「ドイツ再統一条約」が調印されて、東西ドイツは統合された。この莫大な統合コストは西ドイツ国民が負担し、東ドイツ国民はただその恩恵を被ったというのが実態だ。
それにも関わらず、旧東ドイツ国民のかなりの数が「共産主義時代への回帰」を望んでいるとされる。
大きな理由は旧東ドイツ地域の所得がいまだに旧西ドイツ地域に及ばないということだと言われる。格差と言っても旧西ドイツの80%は維持しており、統合前の旧西ドイツの25%程度と言われた旧東ドイツの水準からは劇的に改善している。
しかし、壁で隔てられていた時代の西ドイツの情報はほとんど伝わらなかったから、東ドイツでは、親類縁者、友人、さらには隣近所(党幹部は別だが……)も、みんな25%水準であったから気にも留めなかった。つまり、共産党幹部を除くみんなが平等に貧乏であったのだ。
ところが、ドイツ国民として一緒になるとごくわずかの格差でも気になる。望ましいのはその「格差を埋めるべく懸命に努力する」ことだが、世の中の(特に共産主義教育を受けてきた)人々はそのように考えない。
「持っている奴が出せばいいだろ!」と、他人の努力の成果である資産を分捕ることを何とも思わない。確かに、裕福で成功した人々が社会に還元するのは当然であるし、その中には貧しい人々を支援することも含まれる。
しかし、他人の懐をあてにする人々ばかりがのさばったら国家は発展しないし、1989年~91年に共産主義が崩壊したのもそれが原因である。
日本でも、何もしないで文句ばかり言う「クレクレ病」が蔓延しつつある。また、新型肺炎対策におけるバラマキもひどい状況だ。
日本の現在の状況は憂うべきだが、東西ドイツ再統一によって「悪貨」が混入したドイツの状況はさらに深刻である。
ドイツを含むEUが、いまだリーマンショックの処理が終わっていないのに、新型肺炎で追い打ちをかけられていることは、3月31日の記事「新型コロナ危機が『EU崩壊』を引き起こしかねないワケ」などで述べた。
ドイツの経済・社会の混迷は明らかだが、メルケル氏の16年間の独裁は「ドイツの混迷の結果」だとも言える。
ドイツに比べれば、日本の状況はまだましだが、「他山の石」として学ばなければ、日本の将来も危うい。
嫌米と中国依存に揺れるメルケル独首相の花道
日経ビジネス
2020年8月28日 2:00
新型コロナウイルス対策で支持率が急上昇したドイツのメルケル首相が、対中戦略で苦しい立場に追い込まれている。
中国が香港国家安全維持法により香港への統治を強めることに対し、英国や欧州連合(EU)は重大な懸念を表明した。それに対して、メルケル首相は7月の記者会見でEUの見解を踏まえつつも、中国との対話を模索することの重要性を強調した。これが中国に弱腰だとして、ドイツの対中強硬派の議員たちから批判されている。
中国はドイツにとって最大の貿易相手国であり、多くのドイツ企業の主な収益源となっている。そのため、メルケル首相は中国首脳と毎年のように会談し、様々な配慮をしてきた。中国政府を怒らせるような発言はせず、「ドイツの対中戦略はグレーゾーンが多い状態が続いていた」(米ジャーマン・マーシャル財団フェローのノア・バーキン氏)。
メルケル首相は中国だけでなく、米国との距離感も問われている。最近は、西側諸国にありながら米トランプ大統領との対立が目立つ。メルケル首相が春にトランプ大統領からの主要7カ国(G7)首脳会議の開催呼びかけを断った意趣返しなのか、米国は7月にドイツに駐留する米軍を縮小する計画を発表した。
新型コロナ危機を経て米中対立が激化する中で、ドイツのグレーな対中戦略が許容される余地は少なくなりつつある。次世代通信規格「5G」における中国・華為技術(ファーウェイ)製機器について、英国が一部容認から完全排除に転じ、ドイツも決断を迫られている。
メルケル首相は2021年秋12月に首相辞任と政界引退を公表している。残りの1年間は、米国と中国との距離感に悩まされる局面が増えそうだ。
対中戦略の修正を迫られるドイツ
15年間で12回──。
ドイツのメルケル首相が在任期間中に中国を訪問した回数だ。同首相は毎年のように中国の首脳と会談し、緊密な関係を築いてきた。中国訪問の回数は西側諸国の現役首脳では最多であり、戦後の首脳の中でも突出した数字になっている。
メルケル首相は5月の演説で、「EUは今世紀の主要国の1つである中国と、積極的な協力関係を築くことに大きな関心を持っている」と述べた。EUでは香港国家安全維持法の施行や、新型コロナウイルスの情報開示に対して中国への反発が強まっており、中国に配慮した発言に批判が集まった。
ここまでメルケル首相が中国に配慮するのは、中国との経済関係がドイツ経済を支えているからだ。ドイツ経済の命運を握っていると言っても過言ではない。
19年のドイツの貿易データを見てみる。最大の輸入元は中国(1100億ユーロ)で、オランダ(990億ユーロ)と米国(710億ユーロ)が続く。輸出先のトップは米国(1190億ユーロ)で、フランス(1070億ユーロ)、中国(960億ユーロ)と続く。輸出入を合わせた貿易額で、中国が最大の貿易相手国であることが分かる。
ドイツの主要貿易相手国のデータ(2019年)。中国は輸入元で1位、輸出先で第3位であり、最大の貿易相手国になっている(出所:ドイツ統計局)
ドイツから中国への直接投資も拡大している。18年に中国が受け入れた直接投資のうちドイツは日本に次いで5番目の国で、米国より多い。ドイツは同年に前年比2.4倍の36億ドルを中国に直接投資している。ドイツ企業にとっても中国市場は成長戦略の要なのだ。
VWの中国販売は4、5月に世界全体の5割超え
新型コロナウイルスの流行による経済危機でも、中国との関係がドイツ経済を支えている。特に顕著だったのが、自動車世界最大手である独フォルクスワーゲン(VW)だ。
同社の20年4?6月期の最終損益は16億700万ユーロ(約2000億円)の赤字に転落した。新型コロナウイルスの流行で世界中で販売が減少した影響を受けたが、中国では同期の販売台数が前年同期を上回り、同社の業績を下支えした。
VWはもともと中国依存度が高いメーカーだ。中国における19年の販売台数は422万台と、同社全体の約4割を占める。4月と5月はいち早く経済活動が再開していた中国の販売台数が伸び、世界全体の5割超に達した。中国市場の回復がなければ、同社の業績はさらに落ち込んでいただろう。
新型コロナを経て、さらに中国依存を強めようとしている。5月には中国国有自動車中堅の安徽江淮汽車集団(JAC)の親会社に10億ユーロを投じ、50%出資することで基本合意したと発表した。さらに6月には、中国のリチウムイオン電池メーカー、国軒高科の株式26%を11億ユーロで取得した。
ドイツにはVWの他にも、中国と蜜月関係を築いてきた企業が多い。独BMWは18年に中国の華晨汽車集団との合弁会社に対する出資比率を50%から75%に高め、生産能力を増強すると発表。BMWとダイムラーというドイツを代表する高級自動車メーカーも中国での販売台数が多い。
化学世界最大手の独BASFは30年までに中国に100億ドルを投じ、広東省に石油化学コンビナートを建設する予定だ。電機大手の独シーメンスは19年に中国国有の国家電力投資集団と提携した。
ドイツが迫られるファーウェイ排除の決断
こうしたドイツと中国の蜜月関係が岐路に立たされている。背景にあるのは、米中の対立激化と新型コロナ危機だ。
その象徴的な事例が、中国通信機器大手の華為技術(ファーウェイ)の扱いである。米国は8月、ファーウェイの機器は情報漏洩の危険があるとし、米国の技術が絡んだ半導体の同社への供給を全面禁止した。
それまでも世界各国にファーウェイ機器の次世代通信規格「5G」からの完全排除を迫り、日本やオーストラリアは排除を決めた。英国は一度容認したにもかかわらず、排除に転じた。フランスも排除する方針だと報じられている。
19年にドイツの首都ベルリンで開催された欧州最大の家電見本市「IFA」。ファーウェイのブースは多くの来場者でにぎわっていた。
ドイツも米国からファーウェイ排除の圧力を受けている。ドイツは秋に結論を出す予定だが、同国通信最大手のドイツテレコムのヘットゲスCEO(最高経営責任者)は、5Gからファーウェイ製品を排除することに反対の意見を表明している。業界では、ドイツ政府はファーウェイ製品の一部を容認するのではないかとの声があり、ドイツは米中の板挟みになっている。
トランプ大統領との確執。高まる嫌米感情
ドイツは他の国とは違う事情がある。米中対立の中で、中国と距離を取っても米国に近づくということにはなりそうもない点だ。
近年のドイツは、米国との摩擦が絶えない。米国第一を掲げるトランプ大統領が、対ドイツの貿易赤字を問題視。ドイツからの自動車輸入に高い関税をかけることを示唆し、ドイツ経済の脅威になっている。18年末にはトランプ大統領がドイツの3大自動車メーカーのトップをホワイトハウスに呼び出し、米国での投資増を迫った。
首脳同士の意見対立も目立つ。6月にはトランプ大統領が米国で主要7カ国(G7)首脳会議の開催を呼びかけたが、メルケル首相が新型コロナの流行を理由に出席を拒否。意趣返しのように、米国は7月にドイツに駐留する米軍のおよそ3分の1に当たる1万2000人を削減する計画を発表した。トランプ大統領が2019年に野党の女性議員に差別的な発言をした際には、メルケル首相は「米国の強さと矛盾する」と批判した。
産業界でも米国は鬼門になっている。VWのディーゼル車の排ガス不正は米国で発覚し、多くの損害賠償を支払った。医薬・農薬大手のバイエルは2018年に米モンサントを買収したところ、除草剤の発がん性を巡って多くの訴訟を抱えた。バイエルは6月に最大109億ドルの和解金を支払うことを決めた。
こうした背景があるためか、ドイツ国民の対米感情が良くない。欧州外交問題評議会が2019年に実施した世論調査で、EU加盟国の有権者に米国と中国の対立において自国がどちらの側につくべきかを聞いた。その結果、ドイツでは約73%が中立のままであるべきだと答え、6%が中国に賛成した一方、米国に味方すべきだと答えた人は10%だった。ドイツにおける米国支持は、フランス、イタリア、スペインの他、東欧や北欧諸国の水準を大きく下回った。
米シンクタンクのピュー・リサーチセンターが19年に実施した調査では、米国と中国への好意的なイメージを持っている人の割合を明らかにしている。ほとんどの欧州諸国の国民は、中国より米国に好意的なイメージを抱いていると分かったが、ドイツでは中国に好意的なイメージを抱いている人は34%、米国には39%で、その差は5ポイントと小さい。
一方、フランスや英国、イタリアなどでは、中国より米国に好意を持つ人の割合が15ポイント以上の差がある。日本は調査対象国の中で最大の54ポイントもの差で、中国より米国に好意を持つ人が多かった。こうしたことから、ドイツでは一定の「嫌米」感情を持つ人々がいるとされる。
次期独首相に継がれる大きな課題
米中対立の激化の中で欧州で求められていたのが、欧州の結束を高めることだった。こうした中でメルケル首相の打った手が、EUによる7500億ユーロの復興基金の創設だ。新型コロナの被害が大きいイタリアやスペインなどの南欧諸国を支援し、主に環境やデジタルの関連分野に投資する。
それまでメルケル首相は財政規律を重視しており、財政刺激策の導入に慎重だったが、方針を転換し復興基金の創設に尽力した。この方針転換は欧州諸国に驚きを持って迎えられた。
ただ、それでも復興基金が実際の投資拡大に結びつくかは未知数の部分が大きい。またEUの結束が高まったとしても、ドイツが主要な貿易相手国である米国と中国から距離を取るのは困難だ。
米ジャーマン・マーシャル財団フェローのバーキン氏は、「メルケル首相は在任期間中に、中国に対する態度を変えないのではないか」と指摘する。メルケル首相は21年秋に首相を辞任し、政界を引退することを明らかにしている。残り1年でそれまで約15年間の首相在任期間中の戦略を180度覆すような戦略は取りづらい。メルケル首相の花道は、中国依存と嫌米に揺さぶられたままになりそうだ。
こうした背景から専門家の関心は「メルケル後」に移っている。与党キリスト教民主・社会同盟(CDU・CSU)は年末までに次期首相候補を決め、連立政権を担うドイツ社会民主党(SPD)はショルツ財務相を候補に選出した。ただ両党ともに政権基盤が揺らいでおり、仮に支持率の高まる緑の党が政権に入れば、中国に対して厳しい姿勢を打ち出すことになるだろう。
ドイツは米中対立の中でどのように生き残るのか。次期首相に大きな難題が残されそうだ。
(日経BPロンドン支局長 大西孝弘)
[日経ビジネス電子版2020年8月26日の記事を再構成]
ドイツの友好国が米国から中国に変わりつつある。 台湾侵攻を企てる中国をドイツが非難しないワケ
2021年4月28日
ドイツの友好国が米国から中国に変わりつつある。ルポライターの安田峰俊さんは「ドイツと中国は80年代から自動車産業を通じて友好関係を築くなど、経済的な結びつきが強い。『ナチスを想起させる』中国の強硬策の矛先はやがて台湾に向かう。だが、ドイツはそんな中国の拡大を、危機のギリギリまで『強く抗議しない』可能性もある」という――。
※本稿は、安田峰俊『中国vs.世界 呑まれる国、抗う国』(PHP新書)の一部を再編集したものです。
ドイツでコロナ禍を迎え撃ったのは、今年2021年秋の政界引退を表明しているアンゲラ・メルケル首相だ。国民から「ムッティー(おかあちゃん)」と慕われるメルケル首相が、コロナ対応で高い評価をされているのはなぜなのか、ドイツ在住のジャーナリスト、田口理穂さんがリポートする。
李克強総理 とドイツのメルケル首相 が共同議長を務める第6回中独政府間協議 が、オンラインで開催された=2021年4月28日
ここ10年で急増したドイツでの中国人観光客
【安田峰俊(ルポライター)】まず、一般的なドイツ人の中国観について聞かせて下さい。
【マライ・メントライン(翻訳家、エッセイスト)】基本的に、中国についてほとんど知らないですね。「遠いアジアの国」というイメージで、各人の教養のレベルにもよりますが、日本と中国の区別がついていない人も少なからずいるくらい。
それが10年ほど前からの観光客の急増で、大都市圏や観光地を中心にリアルな中国人との接点が生まれました。バスで移動する大量のツアー客で、いつもガヤガヤとおしゃべりしていて、ものすごくいいカメラを持っていると(笑)。
【安田】なるほど。いっぽう、西ドイツははやくも1984年にフォルクスワーゲン(VW)が中国に進出するなど、早期から中国市場に乗り込んでいました。一般人の知識の薄さとは裏腹に、経済関係には熱心な印象です。
【マライ】ですね。ちなみにVWは、中国ローカルの上海汽車と合弁企業「上海大衆」をつくっているのですが、同社の設立記念式典には当時のコール首相が訪中して参加しています。
ドイツは自動車産業の国ですから、政府は自動車のためならすごく活発に動くわけです。その後、コール首相は天安門事件後の1993年にも訪中していますが、このときもベンツや(自動車ではなく電車ですが)シーメンスなどの大企業を引き連れての大規模な訪中団が組まれました。
対米関係とのバランスとった結果、中国優位に
【安田】往年、中独合弁の上海大衆がつくったサンタナという車種は中国では“国民車”と呼べるくらいよく売れて、一昔前までタクシーの多くがVWエムブレムでした。
ADVERTISING
ベンツは長距離バスによく採用され、シーメンスも広州や上海の地下鉄に車両をおろしています。上海トランスラピッド(リニアモーターカー)も、複数のドイツ企業が関わっています。現在、中国の交通インフラは国産に置き換わってきていますが、ドイツとの経済関係の深さは変わりません。
【マライ】メルケルが率いるドイツの与党・キリスト教民主同盟(CDU)は経済重視で、お得なことはなんでもやるスタンスです。すでに多額の投資をしていることも、これまでのドイツの中国接近の背景にありました。
ただ、もうひとつの要因として、アメリカ一辺倒を嫌う欧州国家としての意識も大きく影響していたはずです。
もっとも、本来は対米関係とのバランスを取るために中国とも仲良くしていたはずが、近年アメリカの力が弱まったことで、相対的に見て中国の地位が上がりすぎてしまった感じがあります。
コロナ禍以降に中国に対する不信感が広まった
【安田】経済や外交面では“良好”、庶民レベルでは“無関心”だった独中関係ですが、新型コロナウイルスが流行したことで風向きが変わります。コロナウイルスの発生地・中国に対するドイツ世論の変化は?
【マライ】中国に対する世論の警戒心はかなり強まりました。情報公開の不透明さをめぐって、中国の価値観や体制に根本的な不信感が広がったことで、経済重視のメルケル政権も世論を無視できなくなりつつあります。
事実、従来はまったく問題視されてこなかった次世代通信規格5Gへのファーウェイ(華為技術)製品の採用が、大きく制限されそうな気配です。
【安田】ファーウェイ製品の排除は2018年から続く米中貿易摩擦が発端でした。中国メーカーのITガジェットに対する、情報流出の懸念は強いようです。
【マライ】もっとも、ファーウェイが組織ぐるみで政治的な諜報活動をおこなっている確かな証拠は、これまでほぼ出ていないわけです。
ドイツ人は論理を重視するので、本来ならば明確な根拠が客観的な形で示されない限り、政府が規制に動いたりすることはない。ところが今回は、コロナウイルス流行以来の中国に対する世論の根強い不信感が、ファーウェイ規制を後押しした感があります。
また2020年9月にはドイツのマース外相が、中国一辺倒ではなくアジアの他の民主主義国との連携をもっと深めていくべきだといった見解も述べるようになりました。
合言葉は「間隔・衛生・マスク・換気・アプリ」
日本では新型コロナウイルス対策として「3密を避ける」が挙げられるが、ドイツで標語となっているのは「AHA+L+A」である。間隔(Abstand)、衛生(Hygiene)、日常マスク(Alltagsmaske)、換気(Lüften)、アプリ(App)のそれぞれの頭文字を取ったもので、1.5メートル以上の間隔を開け、手洗いをし、マスクをつけ、頻繁に換気し、コロナアプリを利用しようと促している。
ドイツでは規則を破ると罰金があり、小売店では店側もマスクをしない客に着用を促したり、間隔をとるよう注意するなど防衛策が義務付けられている。メルケル首相も繰り返し「AHA+L+A」を紹介しながら、ウイルスを軽くみないよう訴えていた。
「規制を緩めるのは早すぎる」(4月3日)
「パンデミックはせき止められているが、去ったわけではない」(5月27日)
「ほかの人のために注意、理性、責任を持った行動を」(5月30日)
ドイツはPCR検査体制を早急に整えるなど新型コロナウイルスへの対応が早かったが、それはパンデミックに備えた国家計画がすでに存在したからである。
2005年に公開された国家パンデミック対策
1999年にWHOがインフルエンザパンデミック計画を策定したのを受け、独自の国家パンデミック計画を策定、2005年初頭に公開した。世界的な感染拡大を想定した対策計画であり、新種のインフルエンザウイルスの拡大を遅らせること、感染による病人や死者を減らすこと、感染者の医療体制を整備すること、の3つを目的とした。2009年の新型インフルエンザの世界的流行後には改定もされるなど、現実に即したものとなっており、ロベルト・コッホ研究所が実際の対策に対する科学的根拠を示した。
医療体制も整っており、集中治療室の病床は人口10万当たり38.2床と欧州最多であり、フランスの16.3床、イタリアの8.6床とは段違い。そのためコロナ禍初期の3月にイタリアやフランスなど他国から重篤者の受け入れを始めたほか、イタリアやスイス、ルーマニアなどにも医療用物資を提供しており、ドイツはコロナ禍において他国と連帯してEUの感染者の治療にも努めた。
こうしたEU間における連帯をメルケル首相は以前から呼びかけており、EU議長国就任についての6月27日のビデオメッセージでは、「コロナパンデミックは、健康、経済、社会的に途方もない影響があります。すでに欧州で1万人以上もの人が犠牲になりました。ヨーロッパの中心的業績である移動の自由や国境開放が一部制限されています。そのためEU議長国のモットーを『ともに』としました。ヨーロッパを再び強くする、そのために全力を尽くします」と話している。
成功したコロナアプリ
感染拡大対策ではコロナアプリも目玉の一つとなった。メルケル首相は6月20日のビデオメッセージで、6月16日から始まったコロナアプリについて紹介した。
「透明性があり、包括的なデータ保護、高レベルのIT安全性に注意して開発されました。アプリは信頼できます。(中略)ワクチンができない限り、ウイルスと共存していくことを学ばなければなりません。プライベートでも仕事場でも再び自由に動き回れるように、学び、そして同時に注意深く理性的でなければなりません。コロナアプリは、感染のつながりを知り、断ち切るための重要な助けとなります」
ドイツではフェイスブックに反対運動が起こるなど個人情報の取り扱いに慎重な人が多い。コロナ禍でレストランやカフェ、催し物会場では名前と連絡先を明記することになっているが、個人情報の利用が許されているのはコロナ対策にのみで、3週間後に破棄することが義務付けられている。
こうした個人情報に意識の高いドイツで、メルケル首相はアプリの使用は強制ではなく自由意志に基づくものであり、位置情報や個人名などは記録されないことを強調しながら、個人情報保護と民主主義、感染症撲滅の微妙なバランスをとってアプリの必要性を訴えた。
結果、アプリは国民に受け入れられ、11月には人口の4分の1以上にあたる約2200万人が利用。累計280万人がPCR検査の結果を共有し、また11月には毎日2000人以上がアプリを通じて感染を伝えた。
演説で株を上げるドイツ・メルケル首相
欧州のリーダーに必須だとされるのは、自分の言葉で民衆に響く演説ができるかどうかですが、その点において素晴らしかったのが3月18日、ドイツのメルケル首相が国民に対し、新型コロナウイルス対策への理解と協力を呼びかけたテレビ演説 です。
テレビの前にいるであろう、一人ひとりの目を見据えているかのように、彼女が落ち着いた面持ちで語ったその言葉は、感染が広がるなか、未知のウイルスに対して不安を抱える人たちが求めていた「安心感」をまさに与えるものでした。その訴求力たるや。ドイツ国民ではない日本の人までもが絶賛し、全文を翻訳したものがSNSで拡散されたほどでした。
おそらくこの演説は、今回のパンデミックの一つの象徴的な事象として、後世にも語り継がれていくことでしょう。虚勢や虚栄の甲冑かっちゅうを身に纏う権力者とは違い、謙虚な親族のおばさんという体ていのメルケルが「あなた」という二人称を使って、国民に呼びかけたことは印象的でした。「スーパーに毎日立っている皆さん、商品棚に補充してくれている皆さん」と、パンデミック下でも人々の生活を支えて働く人々への感謝を述べていました。
二人称を使った呼びかけは、聞いた人の心に響く
この二人称は、古代ローマ時代からの「弁証」の技術において非常に大事なポイントです。カメラを通していたとしても、「医療に携わってくれているあなた、本当にありがとう」と目線を合わせて言われれば、心に響かない人はいませんよね。
ADVERTISING
これが原稿の書かれた紙に目を置いたまま、自分の言葉ではない、表面的な表現を連ねて語られたのなら……。聴いている人には何も届かないし、その心は癒やされもしません。
同じく3月の半ばにはフランスのマクロン大統領も、外出に対する厳しい制限を発表した際、「戦争状態」になぞらえて「新型コロナウイルスとの戦いに打ち勝つ」といった意志を強い言葉で演説し、国をまとめようとする姿勢を表明していました。
イタリアのコンテ首相も、国民に結束を呼びかけるテレビ演説 を行いました。そのなかで私が秀逸に思ったのは、弁護士出身である彼がまず、法について述べた点です。
「皆さん、イタリアの法律では人の命を何よりも守らなければなりません。だから、私はそれを行使します。これから都市を閉鎖し、経済的に皆さんにご迷惑をおかけするでしょう。しかし、人の命をまず最初に守らなければいけないのです」
経済よりも人の命が優先であることを、カメラ目線で国民に向かって宣言した。普段コンテ首相を非難している人たちも、彼の言葉に「よし、わかった」と納得したわけです。
国が違えば政治体制も文化的な事情も異なりますし、一概に比較するのは難しいことだとは思います。ですが、世界が同じ一つの問題に同じタイミングで向き合っているのを、リアルタイムで見つめる機会もそうありません。だからこそ、私たちはこのパンデミックへの各国のリーダーたちの対応や姿勢を比べてしまうし、また比べることができているのです。
危機的状況は指導者が人気を上げる好機
たまたま見かけた国際ニュース番組で、アメリカのオバマ前大統領とブッシュ元大統領の補佐官を務めていたという二人が対談をしていました。現職のトランプ大統領の政策を批判する内容でしたが、そこで面白い指摘が展開されていました。
「トランプ氏が大統領として怠っているのは、国民を結束させることと、国民を激励し安心感を与えることへの責任である。そのために言葉をきちんと選んで話す弁証のスキルをもたなければいけないが、彼にはない。パンデミックのような状況は、本来なら指導者が自分の人気を上げるのにいかようにも利用できる好機なのに、もったいないことだ」
大体このような感じです。たしかに、ドイツのメルケル首相の株は、今回のコロナ対策でグンと上がりました。台湾の蔡英文総統も高く評価されています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ドイツの中小企業が強いのは、家族経営が多く社長の息子が後を継ぎ、10年後20年後も長く続けられるように堅実な長期の経営を考え、社員も2代目3代目と人間関係が上手く出来ているといいます。社長が社員思いが多く、利益が上がればそれを自分の為に使うのではなく、会社に投資し社員の生活をよく考える人格者が多いと聞きます。昔の日本みたいですね。そこに、メンタリティーが大きく異なる中国人が取り込んでも、中世からのマイスタ―制度やメンタリティーをまねるのは出来ないだろう、とドイツ人からよく聞きます。
岸田文雄政権がM&Aをやる検討に入ったと言われる、法律で合法化されると一般の企業は自己防衛が大変になる、駄目な政権は国を売る。困ったもんだ、何故に高市を総裁にしなかった。また一歩も二歩も後退する。残念です
大変重要な情報ありがとうございます。
賢いドイツの中小企業ががここまで侵略されているとは驚きです。アメリカ・ドイツ・日本!
日本の中小企業はまだ侵略されていなのでしょうか? この実態をもっと知るべきですね。
岸田政権では、親中・媚中議員が沢山いますし、まだ隠れ親中議員も沢山いるようですし。
平井氏は、あちこちで、いいこと言ってますね。 まともな人だと思います。
戦後、中国は、当時の東アジアでも一番進んだ工業地帯(満州)を手に入れ、大喜びをしていました。しかし、わずか 30年余りで、時代遅れの工業地帯となり、実質的に放棄せざるを得なくなりました。 中国人には、近代的な科学技術・工業などを維持・発展させることができません。 中国社会の宿痾です。
その後、上海、その他の地域を特別区(経済特区)とし、そこへ「帝国主義諸国を特別待遇で招待」し「侵略していただき」、ようやく経済発展ができたというのが戦後から今日に至るまでの中国の姿です。
なので、先進国が手を引けば、再び同じことが起こるでしょうから・・・ 今後 20~30年程度、中国を自由主義諸国から分離することが、一番安上がりな良い方法だと思いますけどね。
日本の自動車産業の下請けは、進んで中国に生きる道を捜しています。そうしなければ生きていけない環境を政府が援助しない限り、日本の土地が中国にあちこちで買われているのと同じで、気が付いたら、中国になっていたと10年後(2035年~)にはなる危険性があると米国では言われています。
日本の中小企業は本当に大丈夫でしょうか? 今年銀行法が改正され、非上場企業でも原則5%までの出資が100%まで可能になったと聞きましたが、これってすごく危険な事なのではないでしょうか?
ドイツは昔から親中でしょう。やむを得ないと思います。ドイツ車は昭和の頃からもう中国に買収されていましたよ。上海汽車公社とか吉利自動車ですね。中国ははじめはもう相当儲かるそうです。しかし基幹部品や製造ラインが中国に移ると、確実に侵食されやがては乗っ取られるそうです。フォルクスワーゲンなんかもう最近のは安っぽくて見られないでしょう。今更政策転換してももう遅いと思います。EUはもう完全に中国配下です。なぜ脱炭素化を急激に押し進めるのか?中国がEVや発電の技術や生産比率が圧倒的だからです。中国はヨーロッパ系の白人に対する激しい怒りがあると聞いています。日本のようなアジア系の国にはさほど敵対しないと思います。メルカリさんは白人系の血を引くウィグル人がやがては自分たちの姿であることに気づかなかったのでしょう。ヒトラーや戦前のドイツもかなり本格的に中国支援をしていますね。
製造業は、最も重要であるのに、政府は脱炭素実現のため、ガソリン車を廃止し、自動車産業をつぶそうとしている。これが如何に馬鹿げた政策であるかは、中国が製造業について、「製造業は国民経済の主体であり、立国の根源であり、興国の器であり、強国の基礎である」(中国製造2025)と述べていることから分かることです。政府は、この言葉の意味をよく理解すべきである。そうすれば、ガソリン車廃止などというバカげたことは考えないだろう。
ガードの甘い日本よりも一見理性的・現実的なドイツがここまでやられてしまったのは驚きですが、トップのメルケルさんの大きな見込み違いがあったからなんでしょうね。
同様にかなりのめり込んでいるとはいえ、日本の場合は米国の睨みがあったおかげでそこまで行かなかったんでしょうか。
可愛らしい小象も餌を与えて巨象に迄育てると暴れた時]には打つ手が無い、ということを意識しなければならない。ボルボがジーリーに買収された後当時のCEOが中核技術は渡さないことで解決済みだといっていたが、中国相手にそんな甘言は通じない事を既に思い知らされたか、知らされることになるだろう。KUKA買収も一度は許可されなかったがメルケルの意向で結局は買収された。ドイツの産業政策で最大の汚点になるだろう。今は偉大な首相として評価されている彼女ではあるが将来真逆のドイツを売り払った首相として評価されるかも知れない。中国に対して自由経済に変わっていくとの思い込みは香港に対する行動で有り得ないことがようやく物理的距離の遠い欧州でも理解されてきたようではあるがドイツが理解する順番はEUの中でも最後になるかもしれない。
何でメルケル政権が長期政権だったのか理解に苦しむ。一帯一路の終点がドイツまで来ているし、中国EVが発売された時中身の技術がドイツの技術であった時は立腹した。メルケルは中国やロシアに経済的にすり寄っていた。ウクライナ問題があったりウィグルの問題を表面上は批判するが裏では酷かった。日本も危うい、岸田政権や経団連に愛国心や経済安全保障への義務感が無さすぎる。猛省を促したい。
14億人 のマーケットだと思ったらそうではなかったと言うことで。共産主義国家とグローバリズムと言うのは親和性があると言うのもその通りだなと思いました。しかし目先の利益に弱いのが人間でありますね、不思議なのが中国は破綻するとかお金がないとか言いながら基軸通貨を持っているわけでもないのにどうしてそんなに企業買収ができるのでしょうかエフアールビーみたいにお金が自由に作れるわけではないと思うんですけれどね。そういう錬金術も教えていただきたいと思いカラクリがわからないと。
先生のこの番組はとても内容が深くてすごいなと思って拝見しております。それでは失礼いたしました。
中小企業が国際金融資本に身売りすることに関しては、平井さんと意見を一緒にできません。なぜなら、後継者を育成することが、相続税などの問題により現国内法では非常に困難だからです。また、菅政権下で銀行法、中小企業法改正が行われ、国際金融資本に対してMAという形での市場を明け渡してしまったことも問題かと思います。さらに、デフレを放置し続けている政府により、国内市場が毎年縮小しづつけている状態で、いったい誰がリスクの高い中小企業の後継者となるのでしょうか?
メルケルとおなじようなことを「岸田文雄総理」がやるんじゃ・・・と危惧している。
北海道では羽振りの良い中国人が歓迎され、土地が蚕食されていいる。首長は都道府県の事より国全体の事を考える必要がある。経済重視の自治体や企業にとっても同じことが言える。
去年見たどなたかの動画で、中国から一時帰国を余儀なくされた各国の企業の社長の
多くが、早く中国に帰りたいと願っているとの記事を読み、よほど現地での待遇が
すばらしいのであろうと思いました
マネーハニー臓器などの罠に喜んでハマっているのでしょうね。
現地社長や幹部はAIにしないと、中国の世界覇権は止まないのではないのかな?
平井さまの仰る懸念に私も賛同します。マスメディアでは全く報道されない事柄に警鐘を鳴らす発信に敬意を表します。
勇気ある発信には、さまざまなリスクがあろうと存じます。どうぞ混雑電車などは利用しないでくださいませ。よからぬ方々が平井さまを犯罪者にでっちあげようとする心配が御座います。
新生銀行の経緯を教えてください。
中国はこの様なドイツとの国交を通じて、先進国の技術を得たのはメリケツ氏を懐柔したからだ、メリケル氏は旧東ドイツ出身で彼女の基本的思想は社会主義思想が根底にある、現代は良いが、暫くしたら、ドイツの基本的先進技術は中国に渡って、ドイツは凋落の一途を辿るだろう。
既にアメリカは警戒してるが、時既に遅い‼️
しかしドイツの先進技術は中国には模倣は出来ても、継続発展させるのは中国には出来ない。結局はドイツの国民、EUの諸国の恣意的、経済優先、これが中国に取り幸なんだが、残念ながらEU諸国には中国に対して負い目しか残せてない原因が有る。今後はEU各国の経済優先が裏目に出て来てしまう。中国がEU諸国に残したものは経済的服従を強いる結果になる。
悲しい現実だ、こんな事ばかりだから中国にしたら良いかもにしかならない。
高市早苗自民政調会長説「経済安保の法整備」の重要性&朝日新聞の社説論破!
我が国の役割りは、中国の共産党に迎合する,振りをして、米国との調整役を演ずるに、安倍さんも、二階さんも,金平さんに、叶わず、林外相の胆力に、期待しますが!果たして、愛国心は、如何に!松田先生にも、期待しておりますが。78歳の一般市民で、障害者の私が、若い時に、気がついていれば!残念!
ウイグルが、中国の資金の源なんでしょうか?
私はドイツの置かれた精神土壌に注意すべきだと思ます。第2次大戦中に徹底的に戦い、足腰が立たないほど敗れました。元プロイセンでは住民が虐殺され、女性が強姦され、西側からは英米軍が迫りました。日本に置き換えるとソヴィエト軍が北海道、東北地方に侵入し、九州、関西から米軍が迫った状況です。ドイツは戦後は米の覇権に従い繫栄し、今後中国が覇権を取るならばそれに従がうしかないと思っているのではないか。メルケル首相が東独育ちで悲惨な生活を経験、或いは旧ソビエト軍の蛮行を聞いていると思います。イデオロギーを少し曲げて平和を維持し、ドイツ国民の福祉が高く維持されるならばよいと思っているのではないか。日本は内地は爆撃、経済封鎖をされましたが外国軍隊による戦場での蹂躙がされなかった(沖縄は除く)ので覇気がまだ国民に残りました。国破れて山河が残りました。両国との違いがあると思います。ドイツは西側の民主国家のリーダー役を務める気持ちはないです。日本海軍はそのまま伝統を米軍は海上自衛隊に残しました。米海軍が徹底的にやっつけたと思ったからです。日本陸軍は米軍と局地的に戦い、侮れないと感じさせたので米は陸軍の伝統を廃止し、米軍式にしました。何か象徴的に感じます。だが日本人は戦前、戦後も同じ日本人です。
経済重視の政府や自治体や企業は背に腹は代えられないので、しょうがない。
毎度毎度、ヘラヘラ笑いながら談笑するのはやめて欲しい。
日本の危機について話しているのに。そしてなーーーんにも笑いたくなる要素はない。
「他山の石にするな」と銘打ちながら、「他山の石」のように当事者同士が話しているという。
政治家が国会で、国の問題話す時に、笑うのが癖なんで....って通ると思う?
問題点提議する時に笑いながら言うって、いくらいい事言ってても、他人は支持しないと思うわ。
保守界隈の人達が観に来てるから、擁護になるんだよ。真剣に危機感感じてる人からしたら、ムカっと来るし、保守系以外の人が聞きに来れば、単なる意味もなく笑いながら話す変な人って印象しか持たれないぞ。(それが現実)
そんな意識でいることが許せない(個人的に)自分の家族でも4なないと、真剣に話せないのかって思う。むしろ、自分の家族が4ぬようなことがあっても、ヘラヘラ笑ってたら、その時こそ個性だと認めるわ。
全く全体主義ではありません。温厚に言っても全く改善が認められないからこういう言い方になるんです。
で、
こういう「悪いところを指摘してるだけ」なのに、庇うということ=松田さん、引いては日本のためになるとは思えません。私のような対応に出る人もいることを、それこそ「個性だ」と思って下さい。
大体松田さんは、コメ欄さえまともに読んでないと思いますよ。
あと私も個人で自立して勉強しています。なので松田さんが話している内容だけに依存しているのではありません。
こんな基本的なことさえ直さずに平気で「日本の危機だ」と話している保守言論人がいる限り、一定の保守層から人数は増えません。
一体だれに向かって彼は必死(しかしヘラヘラ笑いながら)で話しているのか全然分かりません。
他人に国の危機を伝えたいなら、意味もなく笑わない事!(私はこの癖は、官僚時代の悪癖だと思ってます。高橋洋一氏にも通じるとこがある)
当たり前のことですよ。当たり前のことを指摘して何が悪いのか分からない。
一般社会でも、大事なことを他人に話す場面で笑いながら話す人は稀有な存在です。
一般社会でも受け入れられないことを、保守思想以外の人に話して、「いやー素晴らしかった」と思われる訳ないでしょ。
ついに”メルケル首相の政策”の後始末が始まるか!?
ドイツ、中国依存度の高い企業への規制引き締めを計画―独メディア
2022年11月
2022年11月21日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、ドイツ政府が中国に大きく依存している企業に対する規制を強化する規定を策定中であると報じた。
記事は、英ロイターが取得した機密文書の内容として、ドイツ外務省が中国とつながりの深い企業に対してより厳しい規定を打ち出す計画であり、その原案には「特に中国の影響を受けている企業に対し、中国との関係発展や具体的に数値についての説明、総括を命じる。また、これを踏まえて、当該企業に対して定期的にストレステストを実施するかどうかについて評価を行い、中国に関連する特有のリスクを早い段階で認識し、是正措置を講じられるようにする」と記載されていたと伝えた。
また、原案には投資の担保について環境への影響や労働、社会に関する基準を考慮し、サプライチェーンにおける強制労働を回避するために一層厳しい審査を実施するほか、1社当たり1カ国に対する投資担保金額の上限を30億ユーロに制限すること、特にセンシティブな軍民両用技術や監視、制圧に転用可能な技術について、望まぬ技術譲渡の発生を防ぐために輸出信用取引保険の引き締めを行うこと、さらには大規模な人権侵害行為が起きている地域からの商品輸入の助成を停止することなども盛り込まれていると紹介した。
その上で「これらの措置は、ショルツ政権が策定中の新たな対中商業戦略の一部であり、その目的は中国への依存、輸出への依存を低減することだ」と説明し、来年の初めにも戦略が最終決定する見込みだと伝えている。
一方で、この件についてドイツ通信社が中国外交部に問い合わせたところ、同部からは「中国を競争相手、体制上のライバルと位置づけることは、冷戦的思考の名残りである。中国政府はドイツ政府が言う人権問題や『うそ、デマ』によって中国を誹謗(ひぼう)することを断じて受け入れない」との回答があったと報じた。(翻訳・編集/川尻)
「一帯一路( 債務の罠外交 )」構想と中国・日本の関係:
開催日時
2019年10月20日(木曜)
会場
ジェトロ本部5階展示場
主催
ジェトロ・アジア経済研究所
内容:
基調講演1「『一帯一路』の提唱と日中経済協力の新たな好機」
趙普平氏 (中国国務院発展研究センター 対外経済研究部 部長)
基調講演2「『一帯一路』構想の評価と日中経済関係への示唆」
大西康雄 (新領域研究センター 上席主任調査研究員)
パネルセッション
パネル報告1「IDE-GSMによる『一帯一路』構想の中国経済への影響予測」
後閑利隆(新領域研究センター 経済地理研究グループ)
パネル報告2「『一帯一路』沿線国家における企業活動」
丁可 (新領域研究センター 企業・産業研究グループ)
パネルディスカッション
基調講演1「『一帯一路』の提唱と日中経済協力の新たな好機」
趙普平氏(中国国務院発展研究センター 対外経済研究部 部長)
趙普平氏 (中国国務院発展研究センター 対外経済研究部 部長)
1. 内外の経済情勢と環境
金融危機以降、世界経済は長期停滞の「罠」ともいうべきリスクに直面している。 まだ長期停滞には至っていないが、現在は世界経済の回復期にあり、下振れ圧力に晒されている。IMFによれば、2016年の世界全体のGDP成長率予測は3.1%であり、2015年の成長率と横ばいであり、金融危機以降最低の水準にある。
特に問題は、経済成長の牽引力であった世界の貿易の伸び率が5年連続で世界の経済成長率を下回ったこと。WTOの予測によると、2016年の貿易額の伸び率は2.8%であり、経済成長率を下回る見込み。
2016年9月に杭州市で開催されたG20サミットでも、世界経済の下方リスクが高まる中、世界経済の活性化が重要な議題となった。中国は、「一帯一路(債務の罠外交)」政策を経済活性化の一つの手段と位置付けている。
近年、世界経済の構造が変化している。世界全体のGDPに占める各国のシェアについて、1991年と2015年を比較すると、中国、ブラジル、インドなどの新興国は増加した一方、米国、日本、ドイツなどの先進国では低下した。購買力平価で比較すると、既に米国のGDPを上回った。中国は世界第2の経済大国としての責任を果たすために、世界に対しある種の公共サービスとして「一帯一路(債務の罠外交)」を提供していく考えがある。
先進国が主導する世界の経済・貿易ルールの再構築の動きとしては、3つの「T」——環太平洋パートナーシップ協定(TPP)、環大西洋貿易投資連携協定(TTIP)、新サービス貿易協定(TiSA)——がある。
中国経済は、「新常態(ニューノーマル)」の時代に突入している。 新常態の特徴は次の3点。(1)高速成長から中高速成長への速度のギアチェンジ、(2)伝統的経済構造を絶えず変化させることによる経済構造の最適化・高度化、(3)要素主導型・投資主導型からイノベーション主導型への原動力の転換。
中国の輸出は下振れ圧力に直面している。一部輸出が伸びている品目もあるが、全体として世界経済が調整期にある影響を受けている。
中国の生産労働人口は毎年300~500万人減少している。労働コストも上昇し、現在では主要都市の平均賃金がバングラッシュ・ダッカの5~6倍となった。
中国の従来の競争優位は試練に直面しており、技術や消費市場を中心とする新たな経済成長のポイントを見つける必要がある。特にイノベーションは重要。中国はさらなる改革を通じて、新たな競争優位の確保を行う。
また、従来の投資の枠組みを変えていく必要もある。中国が一部の生産能力を他国に移転する投資が考えられる。これについては海外からの批判もあるが、中国にとっては過剰生産能力問題の解決につながり、発展途上国にとっても自国の工業化、産業化を進める一つの成長の原動力となる。
シルクロード沿線地域の人口は世界の約60%を占めているが、経済のボリューム(GDP)は28.5%を占めるに過ぎない。同地域の1人当たりGDP(5,050ドル)は、世界平均(10,500ドル)以下であり、経済発展が急がれており、同地域の経済発展のためにも、「一帯一路」は必要である。
2.「一帯一路(債務の罠外交)」の協力における中国の対外経済政策
2015年3月28日に発表された「一帯一路(債務の罠外交)」建設の10の理念とは、歴史の継承、大国の責任、包容(排他的ではない)、協力・ウィンウィン、域内外の関係整備、陸海の統括、グリーン発展、経済貿易先行、インフラ整備、市場の役割を指す。なかでも、市場の役割が最も重要であり、企業の積極的な展開がなければ成功しない。
「一帯一路(債務の罠外交)」構想を打ち出して以降、この約3年間で、目覚しい進展を遂げている。100以上の国および国際組織が「一帯一路(債務の罠外交)」への積極的支持と参加を表明、56カ国以上の国が中国とMOUを発表、20カ国が生産能力における協力実施に着手、などの動きが見られる。モンゴルやカザフスタンは、「一帯一路(債務の罠外交)」と自国の経済政策を連動させている。
個別プロジェクトを見てみると、ハンガリー・セルビア鉄道、中国・パキスタン経済回廊などの大規模案件が次々に着工した。建設中のプロジェクトは沿線の46カ国に及ぶが、過去3年間で60カ国に拡大しており、3年間の投資累計額は511億ドルとなった。なかでも中国・パキスタン経済回廊が最大案件で、投資額は460億ドルに及ぶ。
中欧鉄道は特に重要な分野だが、重慶から始まり、最近では成都、アモイ、鄭州などからも欧州向けの鉄道が出発している。貨物の大部分は中国から欧州向けへ運ばれるため、往路(中国から欧州行き)の運行回数は1,881回で、逆に復路(欧州から中国行き)は502回と3分の1にも満たなかった。しかし、今年上半期の欧州向けは119回で、前年同期比の1.5倍となったが、欧州からの復路は209回となり、同3.2倍となり増加が顕著である。鉄道建設は双方の貿易拡大に寄与しており、スタートした当初の貨物量は不均衡であったが、輸送量の拡大により、状況は改善してきた。
中国の対外経済政策において、中国は「一帯一路(債務の罠外交)」沿線国とのFTA締結を加速している。中国は既に15カ国とFTAを締結済みであるが、そのうち沿線国とのFTA締結は11ヵ国に上る。ただし中国の貿易全体に占めるFTA締結国との貿易カバー率は29%に過ぎない。日本はTPP締結後に、加盟国との貿易カバー率が60~70%程度に上昇すると予測されており、このことを考慮すると、中国の貿易の自由化比率は低い。中国は、特に沿線国との自由貿易協定や投資協定の締結を推進している。中国のFTA締結国はまだ少ないため、今後、拡大できる余地は大きい。
これまで「一帯一路(債務の罠外交)」沿線国と既に100件以上の二重課税防止条約や投資協定を締結済みである。しかし、これらの協定は、伝統的な意味での協定に過ぎない。投資者の合法的権利の保護や、投資促進を目的としている。中国の次のステップとしては、より開放的な二国間投資協定の締結を目指していく。例えば現在、協議中の中米BIT協定については、オバマ大統領の退任前に、具体的な進展があることを願っている。中米BIT協定は開放レベルの高い協定を目指している。
対外経済政策の具体的な成果として、中国企業の対外投資は伸び続けている。対外投資額(非金融部門)は2015年に前年比14.7%増の1,180億ドル、2016年1月~7月には67.8%増の1,072億ドルとなった。今年、中国の対外投資の伸び率は明らかに上昇している。
中国の対外投資が世界に占める割合は、2005年に1.5%に過ぎなかったが、2015年には8.7%を占めるようになった。さらに世界の経済成長への貢献度で見ると、中国は19%である。中国は世界の投資活動に新たな活力を注ぎ込んでいる。「一帯一路(債務の罠外交)」沿線国への対外投資は、新たな成長ポイントである。「一帯一路(債務の罠外交)」沿線国に対する中国の投資額は近年、基本的に増加基調にあり、2015年に148.2億ドルとなった。
特に製造業の対外投資の伸びが加速している。2015年および2016年1~7月の業種別対外投資額の伸び率を見ると、製造業は105.9%、230.7%、なかでもプラント製造業は154.2%、447.5%である。同時期の対外投資に占める製造業の構成比を見ると、12.1%、18.9%となった。周辺国では工業化発展のため、製造業分野の投資に対して一定の需要があることを示している。
中国と「一帯一路(債務の罠外交)」64カ国の貿易品目は、2大品目——ハイエンド製造業と伝統的、労働集約型製品——に集中している。これらは中国が沿線国に対して比較優位を持つ品目である。最も多いのは、中国からの輸出50%以上を占める機械であり、次に多いのはアパレルなど各種製品である。労働集約型製品については、中国は労働リソースの豊富な周辺国にシフトさせることで、競争力を確保することができる。日本の1980年代、90年代の対外投資と現在の中国の対外投資には、近似する点が多く見られる。中国もそのような段階に来ている。
もう一点重要なのは、インフラの相互利用であるが、問題はインフラの資金不足である。2009年のアジア開発銀行のデータによれば、インフラ建設にかかる資金需要はアジア域内に限っても毎年8,000億ドルあるという。インフラ整備に必要な資金の不足がインフラ建設の制約要因となっている。AIIBは、今年6月、初の融資案件としてバングラデッシュ、インドネシア、パキスタン、タジキスタンの4カ国への計40億ドルに上るプロジェクトを発表した。シルクロード基金に関しては、融資案件一覧の多くが周辺国に関するものだ。アジア開発銀行は既に900以上のプロジェクトを実施している。中国の政府系金融機関である、中国輸出入銀行は既に1,000件のプロジェクトを実施しており、融資額は1,000億ドルに達する。
中国の商業銀行も同様に海外展開を進めている。中国の五大商業銀行が「一帯一路(債務の罠外交)」沿線の64都市へ進出したが、中国の商業銀行の海外展開は日本と比べて遅れている。現地中国企業や現地企業へ金融サービスを行う。
AIIBは、融資案件の選定、リスク管理、資金回収に関する問題について豊富な経験を有するアジア開発銀行やIMF、世界銀行と協力することで、学べることが多いだろう。また、先進国である日本や米国の成功経験や政策を共有してもらうことで、契約違反などのリスクを予防することができるため、重要な意味を持っている。なお、AIIBは「一帯一路(債務の罠外交)」にのみ関与している訳でなく、全世界を対象とする金融機構である。さらに、AIIBは中国一国で運営する組織ではなく、他の加盟国と共同で責任を負い、運営を行っている。
「一帯一路(債務の罠外交)」は開放的で、包容力のある枠組みである。 「第13次五ヵ年計画」における対外開放に関する重要ミッションとは、「米中の投資協定(BIT)交渉推進を外資参入制度改革の突破口として、実質的な進展を勝ち取ること」などだ。例えば、高いレベルのネガティブリストや上海自由貿易試験区の活用などを組み込んでいる。
2016年9月3日、全国人民代表大会で「中華人民共和国外資企業法」が改正された。今後はネガティブリストに該当しない外商投資企業の案件に関しては、全て審査許可制から届け出制に移行された。これは大きな進展といえる。ネガティブリストの掲載内容が少ないほど、市場開放の効果を十分に発揮することができる。
3.中日経済協力を深化させる新たな好機
中日両国は協力深化にあたっては、現在、多くの機会に恵まれている。第一に、RCEPなど東アジア地域の域内協力を押し進めることだ。両国はRCEPの重要な参加メンバーとして、積極的にRCEPの協議を推進することが一つの選択肢となる。
第二に、投資分野での両国協力は新しい段階に入ったことだ。この数年、日本の対中投資が大幅に減少している。特に2012年以降、各種の要因により、日本企業の対中投資は減少した。日本の対中投資は最も多い年で中国の対内直接投資の10%を占めたが、現在では4~5%まで低下した。これは、韓国の対中投資よりも低い水準だ。日本の経済力とは釣り合わない状況だ。
日本企業の対中投資に関しても、現在、新しいチャンスが広がっている。チャンスの1点目は、外資管理規定の改革により、中国において投資可能な分野が以前よりも拡大していることだ。従来、外資系企業に開放していなかった領域についても、現在では開放された。例えば、上海自由貿易試験区の外資政策についても多くの成果が出ており、同試験区のネガティブリストは164項目から139項目、2015年には122項目にまで縮小した。
2点目は、投資の利便性が向上したこと。先述のとおり、9月3日の法改正により、今後はネガティブリストに該当しない外商投資企業の案件に関しては、全て審査許可制から届け出制に移行された。届け出は原則3日間で手続きが完了することになり、手続きは大幅に改善された。
3点目として、外資系企業から見た魅力が増していること。2016年1月~7月、4カ所の自由貿易試験区内に進出した外資系企業は5,783社、投資額は72億ドルに及び、伸び率は前年同期比65%増となった。対中直接投資全体の伸び率(2016年1~9月)がわずか4%であることと比較すると、自由貿易試験区が対中投資の拡大においてもたらした成果は大きい。
自由貿易試験区の改革・イノベーションについて紹介すると、新設された試験区を合わせると、現在では合計11カ所にまで拡大した。中国の沿海部と中西部をカバーする新たなネットワークを形成している。日本企業や韓国企業は、中国が形成した国際ネットワークを利用することができる。例えば、「欧亜大陸橋」(江蘇省連雲港よりウルムチ、中央アジアを経由して欧州へと繋がる鉄道)を活用すれば、貨物輸送時間の短縮や各種コストの節約につながる。
さらに、中国企業の対日投資についても、両国が協力できるチャンスが広がっている。経済規模を比較すると、日本は韓国より大きいにも関わらず、毎年、中国企業の投資は韓国向けが日本向けを上回っている。中国企業が日本や韓国に投資するポテンシャルは極めて大きいことを示している。これまでは日本企業が一方的に中国へ投資してきたが、今後は双方向の投資が可能だ。
また、中日両国は第三国で投資協力できる可能性があり、「一帯一路(債務の罠外交)」地域において、新たな投資事例を増やしていくことができる。本分野における過去の協力案件はそう多くないが、日本は技術面と資金面で優位性を持っており、中日は相互に補完関係にある。中韓の関係を見ると、両国政府は既に覚書を締結し、情報提供協力など中韓企業の第三国投資において協力することで合意している。
最後に、金融分野でも両国は協力可能である。中国は海外20都市に人民元国際決済センターを設立した。人民元の自由化に向けて、今年6月、中国は米国やロシアにも、人民元国際決済センターを設立すると表明した。日本も東京に人民元国際決済センターを設立されることを希望する。
基調講演2「『一帯一路(債務の罠外交)』構想の評価と日中経済関係への示唆」
大西康雄(新領域研究センター 上席主任調査研究員)
大西康雄(新領域研究センター 上席主任調査研究員)
一帯一路(債務の罠外交)構想について中国の外から見るとどうなのか、また日中経済関係から見て一帯一路(債務の罠外交)構想はどのようなチャンスなのかを見ていきたい。
1.中国の対外経済援助の現状 2014年に中国は対外経済援助に関する詳細を発表した。それによると、対象地域としてはアフリカが大きな対外援助の対象となっており、次にアジアが続いている。統計が得られる2011年の対外援助額を見ると、対外援助額は24.63億米ドルだが、このほかに対外経済合作(建設請負、労務提供、設計コンサルティング)が1423.32億米ドルとなっている。
中国の対外経済協力では、貿易・投資・援助が「三位一体」型として進められており、援助的な性格を持つプロジェクトと貿易、投資を一緒に行っている。政府援助の枠組みと通常の市場取引が領域が重なる部分を対外経済合作が担っており、大きな額を占めている。
2.中国の新対外経済政策とその評価 次に対外経済ポジションの変化を見ていきたい。貿易のシェアを見てみると、例えばアメリカはNAFTA加盟国だけで28%以上を占める。これに対して中国にとって最大のFTAであるASEANとのFTA(ACFTA)を見てもまだ10%程度であり、偶然ではあるがACFTAと未成立の日中韓FTAを足すとNAFTAと同規模になる。
また、中国の対外投資は現在世界第3位であり、累積額で見ると世界第8位である。そうした現状を踏まえると、中国は従来のFTAとは異なる、より広い、自由なFTAを必要としているのではないかと思われる。
中国の地域別の直接投資累計額をグラフ化して見ると投資大国となっていることがわかる。一方で新しいFTAの潮流として、従来は関税の引き下げを中心に交渉するのが主だったものが、TPPのように包括的な規制緩和が中心となってきている。
これに対応した包括的規制緩和の実験として実施されているのが自由貿易試験区である。自由貿易試験区は上海でスタートし、その後天津、広東などに拡大され、現在では中国全土へ徐々に広げられようとしている。
アジア経済研究所では上海自由貿易試験区についてGSM、経済地理シミュレーションモデルという分析手法を用いて、経済政策、インフラについて効果の分析を行ったが、ベストシナリオでは中国全体のGDPが0.9%押し上げられる結果が出ており、自由貿易試験区の効果は大きいといえる。しかし、その効果は沿海部に集中しており、内陸部には及ばないため、内陸部に対する政策として出てきたのが一帯一路(債務の罠外交)ではないかと考えられる。
内陸地域は一帯一路(債務の罠外交)沿線国との貿易規制緩和を行っていき、陸路と海路のシルクロード、鉄道と海上の航路を開拓し新しいインフラ投資を行ってインフラを建設すると思われる。
航路は中国から東南アジア、スリランカなど南アジアを経由してギリシャ・アテネ近郊の地中海最大のコンテナ港・ピレウスまでつながっており、鉄道は重慶、新疆、欧州を結ぶ渝新欧などChina Land Bridgeと呼ばれる鉄道ルートの開拓が進められている。国内のインフラも鉄道、空港の拡大などが急ピッチで進められている。
また、AIIBなど新たな国際的資金協力の枠組みも設立されており、そのひとつであるシルクロード基金は総額400億米ドルの資金規模となっている。
中国の自由貿易試験区と一帯一路(債務の罠外交)構想の背景をまとめると、
(1)対外経済ポジションが変化していること、
(2)TPPなど新たなFTAによる更なる規制緩和の推進圧力が発生していること、また
(3)内陸部の振興や国内の過剰生産能力への対応が迫られているという現実がある。このうち(1)、(2)については「中所得国の罠」への対応としての自由貿易試験区実験が行われており、(3)の格差問題、構造問題へ対応すべく一帯一路(債務の罠外交)構想が推進されていると考えられる。
3.日中経済関係への示唆 日本企業の対アジア投資のうち、かつては圧倒的に中国への投資が多かったが、近年はASEANへと移行している。それはACFTAが中国とASEANを覆っていることが原因であり、ACFTA発効を契機に対ASEAN投資が増えていると考えられる。FTAを前提としたアジア域内での投資調整が行われているのではないか。また、近年徐々に中国、台湾、香港の対日直接投資が増えつつあり、今後の動向が注目される。
パネルセッション
パネル報告1「IDE-GSMによる『一帯一路(債務の罠外交)』構想の中国経済への影響予測」
後閑利隆(新領域研究センター 経済地理研究グループ)
1.中国-キルギスタン-ウズベキスタン鉄道
「一帯一路(債務の罠外交)」構想の一つとして、中国と中東地域を結ぶ貨物列車を用いて、浙江省義烏市から新疆ウイグル族自治区・ウルムチ市を通り、同自治区・コルガス市の国境を越えて南下し、イラン・テヘランまで貨物を輸送する計画が今年5月の新聞で紹介された。
資料(3ページ)の青い線が鉄道網で、黒い線が国境である。青い線が現在切れている部分もあるが、線がつながればどのような経済効果があるのかを分析した。
鉄道建設について、2003年にEUと中央アジアの間でFS(フィージビリティ・スタディ)が実施された。その後、中国がキルギスと協議した際に、中国側が建設するが、その代わり金・銀の鉱山を中国が譲り受けるという提案をしたが、キルギスの大統領がこれを断ったという。
2014年6月に、米国の外務省が今後、問題となりそうなことについてまとめたレポートで、本鉄道に言及し、鉄道建設によりキルギスの南北とで享受するメリットが異なることから、国内の南北分断につながる要因になるのでは、と指摘している。
2016年11月3日の新聞『ユーラシア・デイリー・モニター』の中で、ロシア側は鉄道完成後にはロシアが当該地域での影響力、ひいてはグローバルな影響力が低下することを懸念している。
また、キルギスには英国やロシアの基地もあるため、鉄道建設の実現は難しいとの印象を私は持っている。
「一帯一路(債務の罠外交)」計画としてはこのほか、ロシアのカザン~ウルムチ間の高速鉄道、コルガス~アクタウ間の鉄道の建設の話が出てきている。
2.IDE-GSMを用いた分析結果
アジア経済研究所の空間経済学の理論モデル(IDE-GSM)を用いて、経済効果を分析するシミュレーションを行った。道路、鉄道、港湾整備などの輸送インフラストラクチャーの建設や改善、通関の円滑化や非関税障壁がGDPにどのような影響があるのかを分析した。IDE-GSMの利用開始後9年が経つが、既に89カ国・2063地域、12,116ルートが組み込まれている。産業部門数7部門、中国では400以上、日本だと都道府県レベルが反映されている。人の国内移動や産業間移動を分析する。輸送の金銭費用、輸出入関税、輸送の時間費用、非関税障壁も考慮された分析となっている。
鉄道建設は(1)通関の円滑化せず、(2)通関の円滑化ありという2つのシナリオにより、分析した。2005年と2010年のデータを用いてシミュレーションを開始し、2020年に鉄道を建設した場合、鉄道を建設しなかった場合に2030年にどのようなGDPの差額が出るのか算出した。
シナリオ(1):鉄道だけを建設し、通関手続きを簡素化していない場合、ごく限られた国境周辺の地域だけに良い効果が出る。世界全体から見ると影響はそれほどない。
シナリオ(2):通関費用をゼロにした場合、多くの地域で良い効果が出る。一人当たりGDP100ドル増える地域が周辺に点在している。GDP10ドル増える地域まで見てみると、日本にも多少影響が出ることが分かる。カザフスタンは本地域と競合するため、あまりよい効果は出ないが、本地域と密接につながりがあるロシアを経由して、日本にも多少影響が波及する。
鉄道のスピードはロシアの方が速いという2012年のデータを使用したため、このような結果となったが、現在、中国の鉄道のスピードが高速化しているため、中国を経由して日本へいく方が速く輸送できる可能性もある。
パネル報告2「『一帯一路(債務の罠外交)』沿線国家における企業活動」
丁可(新領域研究センター 企業・産業研究グループ)
1.交通インフラの重要性
本講演では、ミクロの視点から、インフラ整備が企業活動、産業発展にどのような影響を及ぼしているのかという問題意識から、インフラ整備が産業集積をもたらし、さらに産業集積がインフラの利用効率を向上させていく、という好循環に注目したい。
歴史的にシルクロード沿線の経済活動がどのように行われていたのか振り返ってみたい。意外なことに、中国とローマ帝国の間では、直接的な貿易活動がなかった。欧州で発掘された7~13世紀の1,000点のシルク製品を検査した結果、中国製は1点のみだった。シルクロード沿線のオアシスも我々のイメージとは異なり、主に農業を中心に展開しており、域外貿易は非常に限定的だった。こうした歴史研究の成果は、「一帯一路(債務の罠外交)」における交通インフラ整備の重要性を象徴的に物語っている。
交通インフラ整備は「一帯一路(債務の罠外交)」構想の中でも極めて重要である。中欧鉄道は中国の10の主要都市を中心に展開している。
2.成功事例としての渝新欧鉄道
なかでも重慶市をスタート地点とする「渝新欧鉄道」は非常に成功している事例だ。「渝新欧鉄道」は、年間貨物輸送量は3億トン。重慶からはノートPC、欧州からはBMWなど高級自動車、自動車部品、精密機器や高級アパレル製品を中心に輸送している。
「渝新欧鉄道」は重慶の産業集積の形成に対して非常に大きな意味を持っている。鉄道自体は、「一帯一路(債務の罠外交)」構想以前に、2010年にHP社の進出がきっかけで開通された。その結果、世界のノートPCの3分の1、中国のノートPCの約5割は重慶で製造するようになった。現在では「5+6+860」(HP社などのブランドメーカー5社、フォックスコンなどのOEMメーカー6社、サプライヤー860社)というノートPCのサプライチェーンが形成された。重慶市はもともと長安汽車を中心に、自動車の産業集積が存在していた。自動車とノートPCが集積するにつれ、「渝新欧鉄道」の輸送量が大きくなり、輸送費が安くなるとさらに企業が集積していく、という好循環が働くようになっている。
発着回数は、2011年の17回から2015年の267回まで爆発的に増加。輸送時間は、3週間弱から2週間弱へと短縮。輸送費は9,000ドルから6,000~7,000ドルまで下がった。現在は補助金なしで運営されている。「渝新欧鉄道」は、「一帯一路(債務の罠外交)」におけるインフラ整備と企業活動の活発化の典型的なパターンといえる。
3.市場と域外経済貿易合作区
(1)「一帯一路(債務の罠外交)」沿線で、長距離貿易で繁盛する「市場」と(2)中国政府が鋭意推し進めている中国企業の海外への産業移転の受け皿となる「域外経済貿易合作区」に注目したい。
世界最大の卸市場「義烏」の駅前のポスターを見ると、「義烏——新しいシルクロード、新しいスタート地点」とかかれており、「一帯一路」との関係を明らかに意識している。義烏中国小商品城の輸出先だが、上位10カ国のうち8カ国が「一帯一路」沿線国。中国全体で貿易が伸び悩んでいる中、「一帯一路(債務の罠外交)」沿線との貿易は、勢いよく貿易が伸びている。ドバイ郊外に位置するDRAGON MARTという市場では、中国商人3,000人が商売を行っているが、1年間160億ドルの取引額が達成されている。「一帯一路」沿線では、商業集積が非常に盛んとなっている。今後進むインフラ整備によって、ますます繁盛していくと認識している。
また、「域外経済貿易合作区」とは、中国政府が中国企業の対外進出促進を目的に2000年代半ばに打ち出された一種の投資の枠組みだが、「一帯一路(債務の罠外交)」沿線には53カ所が建設された。累計投資額は156億ドル、7万の就業機会が創出された。同合作区には二通りの中国企業が進出している。(1)中国が比較優位を有する業種:軽工業、家電、繊維、アパレルおよび(2)中国で生産能力過剰だが、受入国側のニーズは高い業種:鉄鋼、電解アルミ、セメント、厚版ガラス、である。現在は輸送費が高い状態で、主に海のシルクロード、特に東南アジアの域外経済貿易合作区を中心に中国企業が進出しているが、将来的に陸路のインフラが整備され、輸送費が下がっていけば、陸路シルクロード沿線でも中国企業の集積が生まれ、輸送費が下がっていくという好循環が期待されるのではないか。
基調講演2「賃金労働・労働移動と開発」
パネルディスカッション 磯野生茂 趙晋平氏、大西康雄、後閑利隆、丁可
モデレーター
磯野生茂(新領域研究センター 経済地理研究グループ長代理)
パネリスト
趙晋平氏、大西康雄、後閑利隆、丁可
磯野: 会場からの質問を中心に各報告者に聞いていきたい。まず、趙先生へ。一帯一路(債務の罠外交)構想の中に中国の食料、エネルギー調達の戦略はあるか?
趙: 戦略に含まれている。中国はエネルギーについて外部への依存度が高く、エネルギー構造をみると60%以上は石炭が占めており、石油、天然ガスは輸入に頼っている。石油、天然ガスの輸入は主に一帯一路(債務の罠外交)の沿線国やロシアから来ている。
エネルギー調達は中国にとって大変重要な課題であり、一帯一路(債務の罠外交)は大きなメリットとなっている。資源主導型の沿線国にとっても安定的な市場を得ることにつながり、市場を探している国にはチャンスを与えることとなる。
食料については、基本的には国内での自給がベースと考えられている。しかし、すべての食料を自給し、合理的に調達できているわけではなく、特に大豆は米国、ブラジルから調達を行っているのが現状である。今後いかに国際的な食料戦略をつくるかは重要となり、周辺国の資源を活用してニーズを満たしていくことが必要である。特に大豆、油脂など中国国内で作れない、ニーズを満たせない食料について今後も依存度増えていくと思われる。また穀物分野の協力も必要である。先日新疆に行ったが、カザフスタンなどの国との農業分野の協力が大変重要と感じた。双方にとって優位性を活かしあい、相互補完することが大切である。
磯野:沿線国への具体的な投資プランのリストがあるか?
趙: あるだろうとは思うが、私自身は把握していない。実施されているプロジェクトはいくつか把握しているが、こうしたプロジェクトは主体によって異なる。金融分野ではリスク分析など研究が進められており、情報の支援もあるだろう。大企業では海外進出を検討しているはずであり、投資計画も個別の企業で持っていると思うがそちらは掌握しえない。投資ではリスク回避も行うため、もちろんリストはあると思うが、具体的な分野に関しては今後私たちも研究していかねばならない。
磯野: 一帯一路(債務の罠外交)構想と自由貿易試験区は両輪なのか?外資企業にとって自由貿易試験区のメリットはあるか?という質問も来ているがどうか。
大西: 自由貿易試験区は、当初かなりのスピードで規制緩和が進むのではと思われていたが、実際なかなか進まなかった。特にサービス業分野で進まず、ネガティブリストからなかなか除外されなかった。
しかし中国企業にとって、自由貿易試験区の意味は大きくなっていると思う。中国企業が自由貿易試験区を経由して対外投資する場合は規制が少なく、また貿易口座を作ると許可なく対外投資できるため、その件数が急増しているためである。そういう意味では試験区自体の役割は減っておらず、新しいビジネスモデルが出てきている。たとえば自由貿易試験区のなかに企業を設立すると越境ECビジネスを展開できるため、上海をはじめ各地で拡大している。
磯野:被援助国での中国に対する評価はどうか?
大西: 中国のアフリカに対する援助について、日本側からは比較的被援助国で批判が多いのではという声がある一方で、欧米の研究者からはそこまでの批判は出ていないとの意見もある。これまで欧米が行ってきた援助とは異なり、事業を実施するスピードが早いことがあげられる。OECD諸国では事前の調査などに時間がかかるが、中国の場合、被援助国側が合意するとすぐに始まるという部分もあり、一面的にとらえるべきではないと思われる。
磯野:中央アジア、中国内陸部への経済効果が小さいのはなぜか。どうすればもっと大きくなるのか?
後閑:まず中国は国土が広大なため、沿岸部から西部の国境までは東京からハノイくらい遠い。ひとつのインフラ整備で中国全体に効果を広げるのは難しいと思われる。
また、中国の貨物輸送はいまだ遅いため、ロシアの鉄道と比べると改善の余地があると考えられる。
丁可:中国企業が中心に活動しているという話だが、現地では日系企業への期待も高い。今年の夏に重慶、成都、昆明を訪問した。その際に現地政府からは、自動車、電子部品などの日本製の高付加価値製品を寧波港を通して重慶まで運び、欧州へ輸出したり、欧州の製品を欧州から輸送したり、または第三国で活躍する日系企業が昆明、成都を通じて中央アジア、欧州まで輸送するなどの提案があった。
日本からモーダルチェンジをして欧州まで運ぶのは安全性、安定性の面で採算が取れるのかという面はあるが、積極的に中国の地方政府からインフラを使って欲しいという熱意を感じた。
成都では日系企業など新規の投資については2年間欧州への輸送費を海運と同じレベルまでコストを引き下げるなどの優遇策を検討しているようだ。さらに、重慶ではすでに日系の物流会社により欧州から日本へ運ぶルートが模索されているとのことだった。
磯野:日本が一帯一路(債務の罠外交)、AIIBへ参加することについて、中国のメリットはあるか?
趙:個人的な見解だが、AIIBへの日本への参加を歓迎している。メンバー国として非常によいチャンスを失っていると思う。日本が参加することは各国にとって新しいチャンスを提供することになる。発展スピードの速い途上国と一緒になってスピードアップすることで、世界経済発展にも寄与すると思う。日本の積極的な役割を期待している。
磯野:中央アジアの国々が中国への輸出一辺倒となるのを回避するにはどうすればよいのか、という質問もあるがどうか。
趙:その理解は間違っていると思う。実際、中国の中央アジアへの貿易はバランスが取れており、中国からの工業製品の輸出と中央アジアからの農業製品、エネルギーの輸出は相互補完されている。工業製品の輸出が多すぎる場合は、長期的な協力が必要で、初期段階では輸出ばかりとなってしまうが、中国のメーカーを引き連れて機械整備業、アフターサービスなど様々な加工、組み立ての部分を中央アジア諸国に持ち込める。中央アジアでは付加価値をつけるため、農産品の加工なども中国、日本の市場へ応えて行っている。貿易規模が大きくなることで産業発展の促進につながっていくため、協力をしていくことが重要である。
磯野:国有企業の改革が一帯一路(債務の罠外交)に与える影響はどう考えているか、という問いも来ている。
大西:一帯一路(債務の罠外交)と企業改革には直接的な関係はないと思う。競争力の強化が必要だが、国営企業改革について現政権は加速すると当初言われていたが、3年経って改革が進んでおらず、なぜ進まなかったのか検討がなされていないように感じる。
大型国有企業ではトップの人事権は共産党が有しており、経営者としての資質は二の次である。そうした状態では市場競争のなかで国有企業の競争力を強めるのは難しいと思う。ただ現政権になってから綱紀粛正が進み、汚職など難しくなったと思う。そういった面での規律の是正は進んだが、現在の国有企業の体制はすぐには変わらないと考える。
趙:国有企業について今後の国際的な協力のなかで重要である。市場化、自由化は進んでおりすべてが政府が決めているということではない。一部の企業では世界的な戦略的な投資を行っており、市場経済の一部分として動いていると考えて欲しい。政権から直接管理、意思決定をされているわけではない。
対外協力において、国有企業は重要な役割を果たしており、特に資源開発など分野によっては実力がある。ここ数年で枠組が代わってきており、エネルギー、鉱山は国有企業が主体となっているがそれ以外のサービス業は民間企業が主体となっている。
国有企業改革については統一した考えがあるわけではない。改革の方向性は一体一路(債務の罠外交)構想、第十三次五カ年計画が関わってくるが、市場が鍵となる役割を果たす。国有企業もプレーヤーのひとつである。時間はかかるが改革が進むことには自信を持っている。
⦁ 「一帯一路 (債務の罠外交) 」構想における中国の五大国際インフラ建設プロジェクト
国建協情報 2018 年 1 月号(No.864)掲載 【要約版】
「一帯一路(債務の罠外交)」は、2013 年に習近平国家主席が発表した構想で、中・欧間の貿易路に関わるアジア、中東、欧州の 65 カ国をカバーする地域において、対外経済関係の強化 を図り、インフラ整備 による連結性を高め、貿易・投資の円滑化 を進めることにより貿易を拡大することを目的としており、中国とヨーロッパを結ぶ巨大な経済圏をつくり上げようとするものである。
「一帯」とは、中国西部から中央アジアを経由してヨーロッパにつながる「シルクロード経済ベルト」であり、3 つのルート、6 つの経済回廊で構成される。6 つの経済回廊のうち重点事業として位置付けられているのは、① 江蘇省連雲港を起点として、「一帯」構想の核心地(中心エリア)となる新疆ウイグル自治区のウルムチ、カザフスタン、ロシア、ドイツを経由してオランダのロッテルダムに至る延長 10,800km の「第 2 ユーラシアランドブリッジ」、② 中国・パキスタン経済回廊、③ バングラデシュ・中国・インド・ミャンマー(BCIM:Bangladesh- China- India-Myanmar)経済回廊である。
「一路」は、“21 世紀海上シルクロード”とも呼ばれるもので、福建省を核心地(中心エリア)として中国沿海の港から、南シナ海を経て、① インド洋やヨーロッパ、② 南太平洋、に至る二本のルートからなり、スリランカや東アフリカの諸国が重要な舞台となっており、インフラとしては、港湾、鉄道などを中心に交通関連のインフラ整備が展開されている。
ここでは、「一帯一路(債務の罠外交)」構想のプロジェクトと位置付けて中国が資金提供し、中国企業が参画
2022年10月18日
中国海運企業のハンブルク港湾インフラ投資は警戒を=独情報高官
ロイター編集
[ベルリン 17日 ロイター] - ドイツ対外情報機関の連邦情報庁(BND)のブルーノ・カール長官は17日の議会公聴会で、中国海運企業がドイツで最重要な港であるハンブルク港のターミナルの1つに投資しようとしていることについて、警戒が必要だと訴えた。
カール氏は重要なインフラへの中国の資本参加には極めて危機感を覚えるべきだと主張。港湾が重要インフラと見なされる以上、そうした投資のいかなる可能性も極めて慎重に審査されるべきだとの見解を示した。第5世代(5G)移動通信システムなどの技術や経済的影響力を使って中国寄りの考え方をドイツに植え付けようとする狙いを想定すべきだとし、いざ両国間で政治的に不一致が生じる際に、そうした策略が政治的影響力の行使に効果を発揮することになるとした。
国内情報機関である連邦憲法擁護庁(BfV)のトーマス・ハルデンワンク長官も公聴会で、ドイツの重要インフラの権益を中国が保有することになると、世論形成への妨害工作や誘導の道が開かれる可能性があると訴えた。同氏はロシアのウクライナ侵攻のようなやり方が「嵐」だとすれば、中国の手口は「気候変動」のように何年もかけて進行するやり方だと説明した。
2人とも立場的に資本参加の可否を直接評価することは避けた。
ハンブルク港を巡っては3つのターミナルの1つに対し、中国遠洋運輸(COSCO)が権限を取得しようとしている。議会筋によると、市民の権利擁護を掲げる緑の党のハーベック経済相の下、同省は承認に否定的。一方で社会民主党(SPD)のショルツ首相の首相府は出資受け入れに好意的という。中国側はドイツに対し、両国の経済関係を政治問題化すべきでないとし、国家安全保障の名目で保護主義を採用しないようにとも主張している。
中国はドイツにとって最大の貿易相手国になっているが、中国依存をいかに低減させるかの問題は論争の種。特にロシアのウクライナ侵攻で、強権的な専制主義の色合いを強める国家への依存の危険が改めて意識されている。
ドイツ最大港へ中国参入 連立政権内で賛否
2022/11/2 16:55
三井 美奈
ドイツではショルツ首相の訪中を前に、ハンブルク港のターミナルに中国の国有海運大手「中国遠洋運輸(COSCO)」が資本参加することが決まった。国内最大の貿易港だけに、「安全保障上の危険を招く」として連立政権内で是非論が分かれ、対中政策の迷いが浮き彫りになった。
ターミナルをめぐっては9月、港湾運営会社とCOSCOの間で、35%の権益獲得を認める計画で合意していた。ショルツ氏は2018年までハンブルク市長を務めており、この計画を支持した。「ギリシャやベルギーの港にも中国企業が参入している。特別なことではない」と小学生並みの反論を主張した。
だが、第2与党「緑の党」のベーアボック外相は独紙で「重要インフラへの参入には慎重であるべき。中国が民主主義に対抗するとき、何を意味するかを考えねばならない」と警告。第3与党、自由民主党からも反対の声が出た。連邦議会では情報機関トップが公聴会で、中国企業のインフラ投資に警戒を促した。
独報道によると、6閣僚がCOSCO参入計画の見直しを要求。10月26日の閣議で、資本比率を25%未満にすることで妥協が成立した。人事などの重要決定を覆せない比率にとどめ、参入を認める。(パリ 三井美奈)
ショルツ政権、独ハンブルク港への中国出資を容認
2022年10月28日
【フランクフルト=南毅郎】ドイツのショルツ政権は28日までに、中国の国有海運大手によるハンブルク港のターミナルへの出資を認めると決めた。独メディアが伝えた。同港はドイツ最大の港湾で、重要インフラへの中国の関与強化に安全保障面から懸念の声も出ている。
出資するのは中国の国有海運大手「中国遠洋運輸(COSCO)」。当初は35%の出資を計画していたものの、25%未満に制限する。出資は認めるものの上限を設けることで、人事などの重要な決定事項に関与できなくなるという。
ドイツにとって中国は最大の貿易相手国で、自動車の販売などを通じて経済的な結びつきが強い。ハンブルク港は独最大の港湾で、中国側も欧州の貿易拠点として重視しているとみられる。独メディアによると、中国は欧州にある複数の港湾で独自にターミナルを持ったり、港湾運営会社に出資したりしている。
今回の出資を巡っては、重要インフラへの関与強化に独国内でも慎重論が強い。ショルツ政権内でも、対中依存度を高めるとしてハベック経済・気候相など複数の閣僚が反対していた。ショルツ氏はハンブルク州首相を務めた経験がある。
中国、独ハンブルク港物流ターミナルの株式取得へ…ショルツ政権容認
2022/10/28
【ベルリン=中西賢司】ドイツのショルツ政権は26日、中国国有海運大手「中国遠洋運輸(COSCO)」が独最大の港湾ハンブルク港にある物流ターミナルの株式を取得することを認める閣議決定を行った。同港の国際競争力強化が狙いとみられるが、経済安全保障の観点から欧州各国の批判を招く可能性がある。過去にハンブルク市長を務めたショルツ首相は、COSCOによる35%の株取得という要求を25%未満に引き下げることで妥協を図った。事業や人事など運営に関する重要決定では、介入できない措置を取った。
ロシアのウクライナ侵略を受け、ドイツでは国内で中国の影響が大きくなることへの警戒感が高まっている。独政府内では経済の対中依存度を下げるべきだとの声も強く、COSCOの株取得を巡っては経済相らが反対していた。
同港は取扱量が欧州第3位の重要港で、COSCOが参入するのは四つあるターミナルの一つ。欧州連合(EU)には、域内の重要インフラ(社会基盤)に対する非加盟国企業などの投資について、各国政府が審査できる仕組みがある。
ドイツのショルツ首相が訪中-習主席、「混沌」の中で連帯求める
Bloomberg News
2022年11月4日
欧州主要国の首脳が中国を訪れたのはここ2年余りで初めて
BASFやVW、ドイツ銀行、ビオンテックなど独企業の幹部も同行
中国の習近平国家主席とドイツのショルツ首相は4日、北京で首脳会談を行った。ショルツ首相は就任後、初めて中国を訪れた。
国営中央テレビ(CCTV)によれば、習主席はショルツ首相による訪中は相互の信頼を高めると同首相に伝え、「流動的かつ混沌とした局面」で世界の平和と発展により貢献するために両国が協力すべきだと表明した。
欧州主要国の首脳が中国を訪れたのは、ここ2年余りで初めて。中国共産党を総書記として率いる習主席はこれまでの慣例を破り党トップとして異例の3期目入りを10月に決めた。
ショルツ独首相が近く訪中計画、戦略変更で対中タカ派転向も-関係者
4日夜に中国を離れるショルツ首相は、李克強首相とも会談する予定。李氏は来年3月に引退することが事実上確定している。ショルツ首相の訪中には、BASFやフォルクスワーゲン(VW)、ドイツ銀行、ビオンテックなど独有力企業の最高幹部らも同行。西側諸国と中国の関係は、習主席による香港の統制強化や新疆ウイグル自治区の人権問題、ロシアによるウクライナ侵略への非難を中国が拒否していることなどを受けて悪化している。
習主席はショルツ首相に対し、航空と新型コロナウイルスの防疫でドイツとの協力を深めていく用意があると説明したとCCTVは伝えた。習主席は新エネルギーや人工知能(AI)、デジタル化といった分野で両国は協力を活性化させるべきだ とも話し、ドイツが中国と共に保護主義に抵抗することができるよう望む と語ったという。
独ショルツ首相が企業団引き連れ「中国詣で」...習近平総書記3選のお祝いに「ハンブルグ港」を献上か
2022年11/4(金) 8:07
ゲッティイメージズ
現在のドイツの政権は、社民党、緑の党、自民党の3党連立で、社民党と緑の党は左派で、自民党は保守リベラル。だから、「社民党+緑の党vs.自民党」の対立は想像に難くないが、不仲は実はそこだけではない。社民党と緑の党もしっくりは行っていないし、緑の党に至っては党内部でも内輪揉めが多い。要するに、極めて不安定。
直近の政府の揉め事はというと、中国企業COSCOによるハンブルク港への出資問題。ハンブルク港は、オランダのロッテルダム、ベルギーのアントワープに次ぐEU第3の規模を誇る港で、見渡す限り積み上がっているコンテナの山は、壮大な眺めだ。そして、そのコンテナのターミナルを運営する会社が4社ある。
10月の終わり、その中の一社の株式が35%、まもなく中国の手に渡るというニュースが、突然、流れた。ドイツ国民にしてみれば、寝耳に水だった。
EUでは、EUの加盟国以外の国が、重要なインフラへの出資、あるいは買収を試みた場合、政府は審査の上、安全保障上などで問題があると見れば、それを阻止することができる。
港湾施設は重要なインフラの一つなので、今回、政府内の関連省庁が審査していたらしく、10月末、ベアボック外相(緑の党)を含む6人の大臣、つまり6つの省が、中国の出資は問題ありという結論に達した。自民党ももちろん強く反対。さらにEU委員会と、ドイツの諜報機関である連邦情報局も反対だった。
ところが、ショルツ首相は賛成で、25日、首相権限でこれを押し切った。その際に氏が妥協案として出したのが、中国に譲渡する株の比率を35%から24.9%に下げること。これなら人事など重要な決定にそれほど力を発揮できないという理由だが、どうだか?
2015年、ハイテク・ロボット産業のKUKA社が中国の美的集団に売却した株式はたった5.43%だった。しかし、今ではすでに95%が中国のものだ。
KUKAは、日本のファナックに匹敵するような、いわば中国に売ってはいけない会社だった。その結果、今、中国ではKUKAのロボットが、黙々とメルセデスを組み立てている。もっとも、メルセデスの株の約2割も今では中国が持っている。
いずれにせよ、中国資本のKUKA参入後、ドイツでは、中国の買収に対する警戒心にスイッチが入ったと言われていたが、どうもショルツ氏は別らしい。
ただ、港に関して言えば、中国はすでに、フランス、ベルギー、スペイン、イタリアの港湾施設にも出資しているし、ギリシャ最大のピレウス港は100%中国のものだ。今さらドイツが中国資本を拒否したところで何の意味もないどころか、損するだけとショルツ氏は思っているのだろう。
中国無しにドイツの繁栄はない?
ドイツでは、メルケル前首相が極端な親中派で、彼女の16年の施政中にドイツと中国は蜜月を享受し、大いに繁栄した。
それを受け継いだショルツ首相が、中国依存をそう簡単に修正できるわけもないし、元々、親中派である社民党のこと、修正する気もないのだろう。そもそも中国とドイツの仲の良さは、前々世紀以来のことだ。
しかも、確かに、中国のハンブルク港への出資を阻止しても、中国はロッテルダムやアントワープに荷を移動させるに違いなく、結局、他国を喜ばせるだけだ。一方、中国船が来なくなったハンブルク港は収入激減で、閑古鳥が鳴くだろう。
つまり、「中国無しにドイツの繁栄はない」というのが社民党の基本的な考え。ドイツは基本的に重商主義である。
さらに極め付きは11月4日のショルツ氏の訪中。これがあるからこそ、ショルツ氏はどうしてもハンブルク港を習近平氏へのお土産の一つにしたかった。こんなことさえ纏められないようでは、自分の統率能力に傷がつくと危惧したのだろう。
しかし、ショルツ首相の統率能力は、実際にはすでに地に落ちている。というのも11月1日、ウズベキスタンを外遊中のベアボック独外相が、首都タシケントでの記者会見の席上、公然と驚くべきことを言い放ったのだ。
「私は、我々が連立協定で共に取り決めたことを、ここ中央アジアではっきりと示した。首相も、今こそ私と同じように、中国に対してそれを明確に示すべき時だ」
「それ」というのは、人権、民主主義、平和の大切さと、その実現のための努力。さらには、対中国政策の変更である。なぜなら、中国が変容しているから、対中国政策はこれまでのままではいけない、とベアボック氏は朗々と説いた。
もちろん、その主張は正しいが、しかしながら、新前の外相が外遊先から、自国にいる首相に向かってほとんど命令口調のコメントを発するとは、かなり異常な出来事だ。これは、ショルツ首相が内閣を統率できていない証拠であり、また、ショルツ氏の今回の無理な首相決定が、いかに政権内で問題視されているかということでもある。
なぜ今わざわざ訪中するのか
Gettyimages
そういえば、ショルツ氏はついこの間も、原発の処遇をめぐる緑の党と自民党の喧嘩に、やはり首相権限を持ち出して、陳腐な妥協案でケリをつけた。こんなにしょっちゅう伝家の宝刀を抜いていたら、あっという間に錆び付いて役に立たなくなるだろう。
しかも、今回のショルツ氏の訪中は、あまりにも時期が悪すぎる。先日の中国の共産党大会で、習近平氏が独裁への道を歩み始めたことが世界中に明らかになり、それにより今では多くの国が、台湾侵攻の可能性のみならず、ウイグルの人権侵害にまで注目し始めた。
つまり、各国は対中政策を練り直しているところなのに、ショルツ氏は早々と、いつも通り経済界のボスたちを何十人も引き連れて北京入りするわけだ。商売の拡大のために一番乗り? それとも友好の証明?
11月15日、16日はバリ島でG20が開催されるので、ショルツ氏はここでどのみち習近平氏と顔を合わせるが、その前にわざわざ訪中するのは、経済界の意向も大きいのだろう。バリ島には企業団を連れてはいけない。
ただ、このままでは、ショルツ氏が直々、習近平氏に祝辞(あるいは恭順の意? )を述べにいったと受け取られても仕方がない。しかも、ショルツ氏の訪中には、政府も、議会も、国内の世論もまるで付いてきていないことを、ベアボック外相の過激な言葉が余すことなく示している。
それどころかEU議会の方からも、ショルツ氏の政治家としての能力に疑問を呈する声が聞こえてくる。こうなると、今回の訪中はショルツ氏にとって、EUにおける信用を失う旅になる危険さえある。
これを見ていて彷彿とするのは、天安門事件の後、西側諸国が対中制裁を取っていた最中、イの一番で北京に飛んだ日本の姿だ。
当時の日本は対中制裁に加わっていたにもかかわらず、世界で孤立していた中国に歩み寄った。日本が独自の考えで単独行動に踏みったとは思えないので、中国以外にも何らかの外圧があったことは確かだろう。ひょっとすると、今回のショルツ氏の訪中にも、それがあるかもしれない。
日本はドイツと立ち位置が違う
さて、日本だが、独中が首脳会談をするからといって、岸田首相は安易に中国に歩み寄るべきではない。ドイツと日本は根本的に対中国の立ち位置が違う。
ドイツは中国に経済的に依存しているが、国境に迫られたり、軍事的に脅されたりしているわけではない。しかも中国は、今のところは極めて親独だ。
だからドイツは、一方的な技術移転や取引条件の不公平など、問題は多々あっても、最終的に互いに儲かればOKと割り切りっている。人権問題は、少なくともメルケル政権では、必ず一応は言うだけの紋切り型に過ぎなかったし、ショルツ氏もそれを踏襲しようとしている。
しかし、日本の場合は違う。日本は中国にとっての仮想敵国で、中国は反日。しかも、日本を見下しているが、日本の政治家の中には、中国を仰ぎ見ている人がたくさんいるという歪な関係だ。
日本における中国の影響力は伸張するばかりで、そのうち主権を脅かされるようになっても不思議ではない。要するに、ドイツと一緒にはできない。
昨年12月に発足したショルツ政権は、エネルギー危機、インフレ、不況という未曾有の困難に襲われ、内輪揉めの雑音を発しながらも頑張っている。後期メルケル政権は、社民党との連立だったので、何の議論も起こらなかったことを思えば、今は侃侃諤諤で、政治の場がイキイキとしてきたとも言える。
ただ問題は、出口が全く見えないことだ。とりわけ今回のショルツ首相の訪中は、完全な迷走に思える。
いずれにせよショルツ氏は、ウクライナ戦争が勃発して以来、初めて訪中する西側首脳だ。11月4日の独中首脳会談は、政治家としての氏にとっての分水嶺になるような気がする。しっかりと観察したい。
川口 マーン 惠美(作家)
2022.10.28
ショルツ首相「ウクライナ復興マーシャルプラン」主導もEU内で孤立深めるドイツの末路
いまだに微妙な独仏関係
独仏関係は常に微妙である。元々、戦争ばかりしてきた両国だが、第二次世界大戦後、さすがにもう戦争はこりごりと思ったのだろう、50年代終わりより、ドゴール仏大統領とアデナウアー独首相が、若い世代を巻き込んだ積極的な和解政策に乗り出した。
1963年には両首脳がエリゼ条約(仏独協力条約)に調印。ヨーロッパに新秩序を作ろうという試みは、没落したヨーロッパの再生を期したプログラムでもあった。もちろん、当時、倫理的、また軍事的にも有利な立場にいたのがフランスで、ナチの汚名を注ぐため弛みない努力を続けざるを得なかったドイツの発言力には限界があった。
ただ、その後、ドイツが経済力では次第にフランスを凌駕していったのだから、やはり両国の関係は常に微妙なのである。
独仏の歴史上、和解の象徴とされているもう一つの出来事が、1984年、第1次世界大戦の激戦地であるフランスのヴェルダンで、ミッテラン仏大統領とコール独首相が手を繋いで並び立った瞬間だ。
第1次世界大戦というのは、近代戦に対応できていなかった兵士たちが、戦闘機、戦車、機関銃、さらには毒ガスという残虐かつ容赦ない攻撃にさらされた戦争で、ヴェルダンの戦闘では、フランス軍36万、ドイツ軍33万の兵士が戦死したと言われる。
だからこそ、こんな無意味な殺戮は金輪際やめようという平和への意志は堅固に見えたが、今、思えば、それには「自分たちの国では」という但し書きがついていたのかもしれない。いずれにせよ、それ以後も両国は武器の大型輸出国であり続けたし、時には他国での戦争にも参加している。
その後の独仏関係はというと、シラク仏大統領とシュレーダー独首相はほぼ良好な関係を維持し、サルコジ仏大統領の時代(2007〜12年)の独仏関係はメルケル主導で、フランス側からは"メルコジ"などと揶揄されるほど密接だった。その後継者であるオランド大統領に至っては、さらに手際よくメルケル氏に丸められた感がある。
2017年、マクロン大統領が就任すると、ドイツメディアは、"ベテランのメルケル氏に導かれる若きマクロン"といった微笑ましいイメージを好んだが、これはかなり的外れだった。
確かにマクロン氏はメルケル氏と良好な関係を築き、両者はEUの双頭として君臨し始めたが、マクロン氏が最終的に目指しているのはフランスの復権であり、フランスが中心となったヨーロッパの栄光だ。その証拠にマクロン氏は、メルケル氏が退任した途端、後任のショルツ首相には遠慮せず、陰に陽にとドイツ批判を展開し始めた。
しかし、いくらマクロン大統領が頑張っても、今後、フランスがEUの覇者になれるかどうかというと、かなり怪しい。彼らは内政で多くの問題を抱えすぎている。そんなわけで、独仏関係はいまだに微妙なままだ。
来年はエリゼ条約から60年、再来年はヴェルダンの和解から40年だが、この両国が本当に仲良しかというと、それもわからない。国民レベル、特に戦後世代の交流においては何の確執もないが、政治的にはいまだに宿敵であるといった方が当たっているかもしれない。
独仏関係がギクシャクする原因
10月20日、毎年一度、独仏の首脳および閣僚が一堂に会する重要な会議が、今年は開かれないという速報が流れた。しかも、ドイツ側が勝手にそれを発表したため、フランス側が怒ったという。
現在の独仏のギクシャクの主原因は、もちろんエネルギー政策だ。EUの輸入するガスの価格はすでに青天井となっており、国民と産業を守るため、フランスはもちろん、他の多くの国々も膨大な資金を投入してガス代を抑えている。しかし、そんなことがいつまでも続けられるわけはなく、無理をしすぎると国家経済が破綻する恐れまで出てきた。
そこでマクロン大統領が音頭を取り、EUの貧しい国でも脱落しなくて済むようにと、EUが現在ノルウェー、および米国から輸入しているガスの値段に共通の上限価格を付けることを提案した。これにイタリア、スペイン、ベルギー、リトアニアなどが即座に賛同した。
ところが異議を唱えたのがドイツ。そんなことをすると、貴重なガスが、高く買える国(たとえば日本!)に流れてしまうというのがその理由だ。ショルツ首相いわく、「理論的に正しい政策でも、結果的にガスが来なくなれば元も子もない」。そして、デンマーク、オランダなど、やはり豊かな国々がドイツ側に付いた。
確かに、何が何でもガスが必要ならば、経済力のあるドイツはどんなに高くても買うだろう。そして、ドイツのその行動がガス価格をさらに吊り上げる。しかし、EUの他の国は、そんなお金はない。当然のことながら、EUではドイツに対する不満が膨らんだ。しかも、その不満に一気に火を点けることになったのが、9月末にドイツが発表した2000億ユーロ(約38兆円)の救済計画だった。
この破格の援助については前回書いたが、他国から見れば、日頃からEUの連帯を唱えているドイツが、周りに何の相談もなしに、また勝手なことをし始めたのである。2年半前、コロナの感染がイタリアで爆発した時、ドイツが即座に国境を閉じ、マスクの輸出を禁じたことを、皆、忘れてはいない。
参照)ドイツのガス代高騰救済策「2000億ユーロ投入」がEU各国の猛反発で撃沈寸前
そもそもドイツはこれまで国内のエネルギー高騰を抑えるために、それほど効果的な対策は打っておらず、その結果、企業や国民はエネルギー高騰をまともに被り、未曾有の困難に陥っている。
しかし、これだけ皆が困っているというのに、エネルギー政策を仕切っているハーベック経済・気候保護相(緑の党)は長らく、今年の暮れに予定通り原発を止めるにはどうすれば良いかということばかりに気を取られていた。そして、EUに向かっては、「皆でガスを譲り合おう」と連帯を求めた。
それが突然、2000億ユーロで自国経済のテコ入れをするというのだから、他のEU国が怒るのも無理はない。腹を立てたマクロン氏いわく、「ドイツは自国を孤立させるようなことをすべきではない!」。
とかく意見が合わない
独仏関係を阻害している案件は他にもある。その一つが、すでに中止になったガスパイプライン計画「MidCat-STEP」を復活させるかどうかの問題だ。
MidCatとは、2013年に始まったフランスとスペインを結ぶパイプラインのプロジェクトで、これが開通すれば、アフリカ最大のガス産出国アルジェリアのガスを、モロッコ、スペイン経由でフランスまで運ぶことができる。
ただ、スペインとフランスの国境はピレネー山脈なので工費が嵩むし、フランスはそれほどまでにしてアルジェリアのガスを必要としていなかった。その上、自然保護団体の強硬な反対もあり、工事はピレネー山脈の部分を残して止まってしまっていた。
ところが、それを現在、喉から手が出るほどガスが欲しいドイツがどうにかして完成させようとしている。そうすれば、そのガスをフランスからさらに自国に引っ張ってこられるからだ(数年先の話だが)。
すると、今度はそれにフランスが反対。公式な理由は、すでにスペイン〜フランス間には小さなパイプラインが2本あるが、どちらも利用率が50%止まりだというもの。つまり、「新しいパイプラインなど必要ない」。
現実には、フランスが重要視しているのはガスではなく、原子力だ。原発を世界から消し去りたいドイツとは、そこでも対立している。現在、EUのタクソノミーでは、原子力もガスも共にグリーンとして認められたが、議論が沸騰していた頃、ドイツはフランスの原発を潰すため、まさに死力を尽くした。
この2国はとかく意見が合わない。その他、戦闘機や戦車の共同開発を含む軍事共同プロジェクトも暗礁に乗り上げているというから、先行きはかなり暗い。
ドイツ主導のウクライナ復興プラン
そう思っていた矢先の25日、ベルリンで突然、EUとショルツ首相主導のウクライナ復興援助のための会議が、各国の投資家や企業の代表を集めて大々的に開かれた。ショルツ氏いわく、ウクライナに対する「21世紀のマーシャルプラン」だそうだ。まだ戦争はたけなわなのに......。
実を言うとドイツは、すでにウクライナからの避難民でにっちもさっちも行かなくなっており、このまま避難民が増え続けると大変なことになる。そこでウクライナの徹底抗戦よりも、停戦の方向に舵を切り始めたのではないか。同日にはシュタインマイヤー独大統領が、キエフを電撃訪問してゼレンスキー大統領と会っている。
ウクライナのこれまでの被害総額はEU側の発表では3500億ユーロ、ウクライナ政府の試算によれば7500億ユーロ。フォン・デア・ライエン欧州委員長(ドイツ人)は復興援助会議のスピーチで、「すべてのユーロ、すべてのドル、すべてのポンド、すべての円を投資しろ。これは世界中の民主主義を守るための投資だ」と気勢を上げていたから、まもなくウクライナの瓦礫が多くの投資家や企業にとって、垂涎の的に変貌するのかもしれない。
一方、ゼレンスキー大統領は、EUが凍結しているロシア財閥の資産をウクライナの復興のために放出しろと言っている。スイスやリヒテンシュタイン辺りにたくさんありそうだが、そんな簡単に行くものかどうか?
いずれにせよ、商売上手なドイツのこと、この復興事業で儲けすぎると、またEU国の反感を買いそうだ。ところで来週31日には、ドイツのシュタインマイヤー大統領が訪日するが、何の用だろう。まさか集金......?
EU ユーラシア インド太平洋「一帯一路 (債務の罠外交) 」概念図
日本の釧路港はまだ一帯一路(債務の罠外交)には組み込まれていない様だ。
しかしイタリアは99年間、港を中国へ売ってしまった。
ドイツも、ロシア鉄道で陸側から鉄道を中国とつないでしまった。欧州連合(EU)欧州委員会もそれを許可した。裏ではいろんな役人が中国のマネーに取り囲まれたらしい。ぼったくり男爵も同じですね。WHOの幹部も同じです。一帯一路(債務の罠外交)のEUへの入り口、玄関にあたるドイツとロシアの国境付近で中国の企業がドイツ人を雇ってトンネル工事をしたらしい。そのトンネル工事中に落盤事故があった。トンネルの中でドイツの工夫が亡くなっても中国人の親方は知らぬふりをして終わったそうだ。さすがジェノサイドの国家だ。ドイツは第二次大戦の後遺症?かは分からないが、信じられないことに名だたるドイツの大企業(ベンツなど)も、ドイツの中小企業(マイスターの技術)も売っってしまった。日本も後遺症があるのか?、色々な企業が、社屋も技術も、全てを中国へ移転し、しようと思っている。商業では、イオンも無印良品計画も、・・・。パンダを貸してもらったお礼になの?田中角栄さん(ロッキードからの収賄事件)?
して完了した、ないしは進行中の各種インフラプロジェクトの中から代表的な 5 つのプロジェク
トについて報告する。
1.欧州国際貨物列車「中欧班列」(China Railway Express)
中国にとっての最初の「中欧班列」は、2011 年 3 月の重慶からドイツ西部のデュイスブルグで、その後、成都、武漢、蘇州、広州、義烏など 27 の都市に広がり、また目的地もスペイン、ロシ
ア、ドイツ、イタリア、アフガニスタン、イラン、ラトビア、ベラルーシ、英国などユーラシアの 11 の国、28 の都市に広がっている。2017 年 4 月までに 51 の路線で運航実績を上げており、毎年倍増する勢いである。中でも最長となる 13,000km を旅する義烏~マドリッド間は、2016 年までに約 100 回の運航実績を有している。
中欧班列の最大の障害は、軌道幅の違い(両端の欧州と中国は標準軌(1,435mm)、旧ソ連は広軌(1,520mm)など)があるため、コンテナ貨物を移し替える必要があること。義烏・ロンドン便では台車を 3 回交換することになったが、「一帯一路(債務の罠外交)」のプロジェクトとして、積み替え設
備の機械化、手続きの簡素化を進め、時間短縮を図っている。
1 万個以上のコンテナを運ぶ巨大なコンテナ船に比べると、一回の輸送量は少ないが、輸送時間はほぼ半減(義烏~ロンドンの場合、35 日→18 日)されたので、貨物の種類によってはコス
ト効率に優れているものも多い。「中欧班列」では、中国からは日用生活雑貨がヨーロッパへ、ヨーロッパからは並行輸入の自動車やフランスワイン、チーズなどが中国へ送られているが、ロシアとポーランドに挟まれた内陸国のベラルーシのミルクが中国に送られ、ワルシャワの「中国商城」がメイドインチャイナの供給源となるなど、中欧班列ならではの新しいモノの動き、商業活動などが進展している。
2.アジア鉄道ネットワーク(Asian Railway Network)
⦁ アジア横断鉄道(Trans-Asian Railway:TAR)
アジア横断鉄道(TAR)は、ESCAP の前身 ECAFE が 1950 年代から検討を進めてきたもので、2006 年に ESCAP 加盟の 17 カ国が協定としてまとめた、貨物輸送を意識した鉄道整備構想である。TAR は、
① シベリア横断鉄道を利用して東アジアと欧州を結ぶ「北部回廊」(Northern Corridor:NC)、
② 中国・タイからインド、イランを経てヨーロッパに至る「南部回廊」(Southern Corridor:SC)、
③ 中国・昆明とシンガポールを結ぶ「東南アジアネットワーク」(Southeast Asian Network)、
④ 北ヨーロッパとペルシャ湾沿岸を結ぶ「南北回廊」(North-South Corridor:NSC)、の 4 つの回廊からなる。
TAR の中で最大のプロジェクトは、なんといってもバングラデシュの「パドマ多目的橋」
(Padma Multipurpose Bridge)であると言える。
パドマ多目的橋は、TAR の鉄道プロジェクトであると同時に、アジアハイウェイ 1 号の重要な
道路橋でもあることから、日本も古くから関わっている。ジャムナ橋、メグナ橋などバングラデシュの大型橋梁に無償資金協力や円借款供与などを行った JICA はパドマ橋についても、2003
年から 2005 年にかけて、将来的に鉄道も併設可能な道路橋として、渡河地点の選定、最適橋梁形式(PC エクストラドーズド桁を提案)を含む FS を実施した(日本工営と建設企画コンサルタ
ントのコンソーシアムが担当)。
さらに 2009 年から 2011 年にかけて、ADB が、アメリカのコンサルタント AECOM(香港オフィス)が率いる国内・国際チームを使って詳細設計を実施。渡河地点は JICA が選定したMawa‐Janjira 間としたものの、橋梁のタイプは鋼トラスで、上面に 4 車線の道路、トラスの中に複線の貨客鉄道を通す橋長 6,150m(41 スパン×150m)の鋼トラス橋とした。
この詳細設計を受けて、バングラデシュ政府は 2011 年に世銀(12 億ドル)を筆頭に ADB(6.15 億ドル)、JICA(4.15 億ドル)、イスラム開発銀行(1.45 億ドル)などからのローンを得、自己資金(6 億ドル)を加えて総額 29.7 億米ドルの資金を確保したものの、汚職問題などが発生したため、2012 年 7 月、全額をバングラデシュ政府の資金で実施することを決定した。
2014 年 4 月に行われた国際入札において、橋梁建設費(15.5 億米ドル)の 70%を出資して BOT
方式で建設・運営を行うことを提案した中国鉄建傘下の中国中鉄グループの一つ「中鉄大橋局集団」が受注、2014 年 12 月に着工した。これにより、パドマ本橋、14km にわたる関連治水工事
(約 11 億ドルで中国水電社が受注)、15km の取り付け道路(地元企業が受注)などからなる 総額約 40 億ドルの大規模プロジェクトが動き出した。
工事は順調に進捗しているようで、2017 年 9 月には、最初の 150m のトラス桁がクレー船で架けられた。橋梁は 2018 年 12 月の完成、2019 年 6 月の供用が予定されている。
2017 HYPERLINK "http://www.banglanews24.com/national/article/63966/Padma-Bridge-first-span-installed" HYPERLINK "http://www.banglanews24.com/national/article/63966/Padma-Bridge-first-span-installed"年 HYPERLINK "http://www.banglanews24.com/national/article/63966/Padma-Bridge-first-span-installed"9 HYPERLINK "http://www.banglanews24.com/national/article/63966/Padma-Bridge-first-span-installed" HYPERLINK "http://www.banglanews24.com/national/article/63966/Padma-Bridge-first-span-installed"月、パドマ橋最初のトラス桁( HYPERLINK "http://www.banglanews24.com/national/article/63966/Padma-Bridge-first-span-installed"150m HYPERLINK "http://www.banglanews24.com/national/article/63966/Padma-Bridge-first-span-installed")架設の写真( HYPERLINK "http://www.banglanews24.com/national/article/63966/Padma-Bridge-first-span-installed"banglanews24.com HYPERLINK "http://www.banglanews24.com/national/article/63966/Padma-Bridge-first-span-installed")
さらに、「南部回廊」(SC)の一部となる首都ダッカと南西部の主要都市ジェッソール間168.6kmを結ぶ貨客鉄道「パドマ大橋鉄道接続線プロジェクト」は、2016 年 8 月に中国中鉄が 31.4 億米ドルで受注、2022 年頃までの完成を目指している。ダッカ・ジェッソールがつながれば、インドの東海岸にある主要都市コルカタまでは、ほぼ 100km 程度を残すのみとなる。
⦁ インドネシア高速鉄道(High-speed rail(HSR)in Indonesia)
首都ジャカルタと第二の都市スラバヤ間約 730km を高速鉄道で結ぶもので、第 1 期としてジャカルタ‐バンドン高速鉄道(約150km)、第2 期としてバンドン‐スラバヤ高速鉄道(約580km)が建設される計画である。
インドネシアの高速鉄道については、2008 年ごろから日本が新幹線技術の輸出を働きかけ、JICA はジャカルタ~スラバヤ間高速鉄道の FS を実施、2014 年にはフェーズ 1 となったジャカルタ~バンドン間の詳細な事業化調査を実施し、建設費も低利の円借款供与を提案した。
しかし、2015 年に行われたフェーズ 1 の入札には中国が参加し、建設費約 55 億米ドルのうち80%の 45 億ドルを中国開発銀行(CDB)が融資する条件で入札した中国鉄建(CRCC)とインドネシア国有企業連合との JV が受注に成功した。「事業運営に当たり、中国はインドネシア政府に債務保証を求めない」という提案が受注の決め手になったと言われている。しかしながら、中国の建設による、ずさんな新幹線橋脚の崩壊によって、その後それは中国によって裏切られることになる。
2016 年 1 月の起工式の後も用地取得の遅れなどから本格着工に至っていなかったが、2017 年5 月、両国の首脳間で 45 億ドル(約 5,100 億円)の融資が正式に合意され、受注決定から約 3年を経て、2018 年初頭からようやく本格着工の見通しになったと伝えられている。
しかし、当初の条件と異なり、最近、中国側がインドネシア政府に債務保証を求めているとも報じられている。土地収用などに手間取り、建設費も 60 億ドル程度に膨らむと予想されている
ことから、今後の進展は波乱含みのようだ。
フェーズ 2 のバンドン・スラバヤ高速鉄道については、まだ具体的な動きは出ていないが、イ
ンドネシア政府は、新線の建設ではなく既存の鉄道を高速化する事業として日本にも参画の可能性を打診してきており、また中国もフェーズ 1 に続いて事業に参入したい意向を示していると報じられている。
3.中国・パキスタン経済回廊(CPEC:China Pakistan Economic Corridor)
中国・パキスタン経済回廊(CPEC)
パキスタン南部アラビア海に面するグワダ
ル深水港を起点に、パキスタン全土を経由して、中国西部の新疆ウイグル自治区カシュガルに至る全長約 3,000km の回廊である。カラコル
ム・ハイウェイの拡幅などを柱として、道路・鉄道網を整備し、さらにその周辺で発電所や送電網などのエネルギー関連施設や8 つの経済特区の開発を行うものである。中国にとって、陸路でインド洋へのアクセスが可能になれば、中国が抱えていた「マラッカ・ディレンマ」(石油輸入の 85%がマラッカ海峡を通過するため
有事の海上封鎖に脆弱)を解消し、中東やアフリカの資源へのアクセスを確実にし、欧州への交易路を短縮でき、貿易コストの削減につながることから、CPEC を「一帯一路」の旗艦事業として重視している。また、急激な人口増に直面するパキスタンは、深刻な電力・エネルギー不足に悩んでいることから、CPEC の投資額(2017 年現在、約 620 億ドルと見込まれている)のうち約 7 割をエネルギー分野に投下するという。
カラコルム・ハイウェイは、中国ウイグル自治区のカシュガルからパキスタンのイスラマバード近郊に至る約 1,300km の道路で、途中カラコルム山脈を横断して、舗装道路としては世界最高の標高約 4,700m のクンジュラブ峠を越える。パキスタン側のルート周辺は、70
年以上にわたって、パキスタンが事実上支配するもののインドが自国領と主張している「カシミール問題」のあるセンシティブな地域であるが、現在、中国の支援で拡幅工事が行われている。さらに、カラコルム・ハイウェイに並行して鉄道の新設も検討されている。
CPEC の中核プロジェクトになっているグワダル港は、パキスタン政府のグワダル港湾庁
が 2002 年から整備を進めているものである。第 1 期として 2006 年までに約 600m の 3 つの埠頭を整備し、2007 年から第 2 期として 3.2km の 4 つのコンテナ埠頭の建設に取り組むと同時に、管理・運営をシンガポール港湾庁に委託していたが、2013 年から中国の「中国海外港湾保有会社」(COPHC)がその任に当たっている。2016 年から「一帯一路」構想の中核施設として、中国が2059 年までの43 年間、パキスタンから同港を租借することとなり、大幅に貨物取扱量を増やすべく拡張工事も進めている。COPHC は、中国の国有銀行の融資を受けて、10.2 億ドルをかけて 3.2km の 9 つの多目的ふ頭と貨物ターミナルの新設、港湾の浚渫など、総合的な港湾整備に取り組んでいる。
4.スリランカの港湾
⦁ コロンボ港
首都にあるコロンボ港は、南アジアにおける重要なハブ機能を有するコンテナ港で、旧港と新港であるコロンボ南港の 2 つのエリアからなる。旧港にはジャヤ・コンテナターミナル(JCT) とクイーン・エリザベス埠頭(QEQ)の二つの埠頭がある。
新港のコロンボ南港には、それぞれ 1,200m の埠頭、240 万 TEU の処理能力を持つ南、東、西の 3 つのターミナルが計画され、最初に手掛けられたのが南ターミナル(SCT)である。2011 年、香港に拠点を置くターミナルオペレーター招商局港口控腔(CMPort)が建設費の 70%を出資し、残りの 30%を出資した SLPA と組んで「コロンボ国際コンテナターミナル(CICT)」を構成、35 年間の BOT 契約を獲得、2016 年に全面供用に至
っている。
南港で二番目となる ECT(East Container Terminal) は、スリランカ港湾庁(SLPA)が 2015 年 5 月までにコンテナ埠頭 440m の暫定形で供用しているが、1,200m の完成形にするために、長年計画に携わってきた ADB の力を借りて、約 5 億ドルの事業を 35 年の BOT 契約に持ち込もうと動いている。2017 年第一四半期で予定されていた事業
主体の決定は遅れているが、シンガポール港湾庁のほか、
コロンボ港コンテナターミナル配置図
中国の急激な進出を恐れるインドの企業も関心を示してい
るようだ。
⦁ ハンバントータ港(Hambantota Port)
ハンバントータ港は、スリランカの南端に位置し、南アジア、アフリカへの経済進出の拠点となるものである。2008 年 1 月に第一期として、建設費 約 3.6 億ドルのうち 85%を中国輸出入銀行、15%を SLPA が出資、工事は「中国港湾工程公司」と「中国水電」のコンソーシアムが担当、3 つのバースを持つコンテナ港の建設に着手し、2010 年 11 月に開港した。
2016 年には、SLPA とCICT の運営者でもある招商局港口控腔(CMPort)との間で、99 年間、15,000 エーカーのハンバントータ港 港湾地区の貸与を含む協定が結ばれた。スリランカ政府は否定しているが、住民からは「ハンバントータ港が中国の海軍基地として使われるのではないか」と懸念する声が上がっており、また米国、インドなども同様の懸念から、その利用状況に強い関心を持っている。
ハンバントータ港開発に関連して、中国はスリランカ南部で空港、道路といった他の交通インフラの整備にも注力している。ハンバントータから北へ 18km の地点には、2009 年 11 月に中国輸出入銀行から 1.9 億ドルの融資を受けてバンダラナイケ国際空港(コロンボ)に次ぐ第二の国際空港建設に着手、2013 年 3 月に当時の大統領の名を冠してマタラ・ラージャパクサ国際空港として開港した。しかし、このモダンな新空港は開港から 3 年経っても乗客数は容量 100 万人/ 年に対して約 5 万人/年に過ぎず、「世界一空いた国際空港」と揶揄される状況となっている。 コロンボから南へ延びる高速道路については、本誌 2017 年 1 月号(No.858)でも報告した通り、2014 年 3 月までにコロンボ~マータラ間 131km が円借款、ADB および中国輸出入銀行の融資を受けて完成しており、マータラから港湾整備が進むハンバントータまでの約 100km 区間についても、中国輸出入銀行からの融資を受け、工事が進められている。
5.アフリカ東沿岸諸国における鉄道
原油等資源分野を中心とする中国資本によるアフリカへの「走出去(中国資本の対外進出)」が、2014 年をピークに減少する中、「一帯一路」構想に参加するジブチ、エジプト、エチオピア、ケニアにおいて、鉄道を中心に交通インフラ整備への中国の積極的な参画が目立つ。その拠点となっているのが、海上交通の拠点ジブチ港と経済成長の潜在力が高いケニアのモンバサ港の二つの港である。
⦁ ジブチ・エチオピア鉄道(Ethio-Djibouti Railways)
ジブチは、スエズ運河に通じる航海の入り口に位置する海上交通の要衝として、米軍、仏軍などと一緒に自衛隊も 2011 年から借地して「ソマリア沖の海賊対策」の活動拠点としているが、中国もパキスタンのグワダル港、スリランカのハンバントータ港などと並んで「一帯一路」の重要な拠点と位置付け、軍事基地としての機能を拡充するとともに、周辺国への支援の拠点にしている。
ジブチ・エチオピア鉄道は、紅海に面するジブチ港と内陸国エチオピアの首都アジス・アベバ約 750km を結ぶ狭軌(1,000mm)の鉄道として 1917 年に全通していた。ここに「一帯一路」計画の一環として 2013 年から中国輸出入銀行が 7 割を出資し、事業費約 34 億ドル規模の全線電化を含む大規模な修繕工事が、中国鉄建傘下の中国中鉄と中国土木工程集団の手で実施され、2016 年 10 月に完成、ジブチとアジス・アベバ間を約 10 時間で結んでいる。鉄道運営の経験がないエチオピアで、人材が育つまでの 5 年間の契約で、運転士や駅員、技士など運行に関わるすべての業務を中国人が担っている。
エチオピアでは人件費がアジア最貧国と言われるバングラデシュよりも安いことから、基本として現地での雇用を図ってこなかった中国も、ここでは工事の肉体労働にエチオピア人を雇用し、地元でも喜ばれたと言われている。
さらに首都アジス・アベバにおいては、2011 年から中国輸出入銀行が 85%を出資し、総工費4 億 7,500 万ドルをかけて中国中鉄が建設している 34km の計画路線網のうち、2015 年 9 月に第1 期としてサブサハラでは初となる近代的な路面電車 16.9km が供用され、全線供用を目指して延伸工事が進められている。アジス・アベバでは中国企業の進出が急激に増え、路面電車のほか環状・高架道路の建設などで、中国人労働者も急増している。
⦁ マダラカ・エクスプレス(標準軌鉄道 SGR)
ケニアの首都ナイロビとアフリカ最大級の港湾都市モンバサを結ぶ「標準軌鉄道」(SGR)が、3 年半の工事を終えて 2017 年 6 月に完成。今までナイロビ~モンバサ間約 470km は在来線で約12 時間、バスで約 9 時間を要していたが、SGR の完成により約 4 時間半に短縮されることになった。
1963 年にケニアが英国から独立して以来、最大のインフラプロジェクトであり、開通後、1963年の独立記念日の名前をとってマダラカ高速鉄道と命名された。
建設費は約 38 億ドル(約 4,200 億円)で、約 9 割を中国輸出入銀行が出資(1 割はケニア政府)、中国交通建設(CCCC)傘下の「中国路橋工程」社が施工した。海抜ゼロのモンバサと標高 1,661 mのナイロビを結ぶことになるので、高架橋が多くなり、橋脚の高さが 44m の橋梁を含む 98 の橋梁群が建設された。
ケニアにはモンバサ港整備など、道路、港湾、都市開発、電力の分野で日本が古くから ODA を通じて開発援助を行ってきたが、中国からの多額の融資案件により、2016 年にはケニアの対外債務の 57%を中国が占めている。
(文責:荒牧英城)
[参考資料]
・中国・パキスタン経済回廊をめぐる国際政治と安全保障上の含意
(栗田真弘、防衛研究所「NIDS コメンタリー」第 61 号 2017 年 6 月 14 日)
・Colombo HYPERLINK "http://www.infrapppworld.com/documents/projects/project-brief-43.pdf" HYPERLINK "http://www.infrapppworld.com/documents/projects/project-brief-43.pdf"Port HYPERLINK "http://www.infrapppworld.com/documents/projects/project-brief-43.pdf" – HYPERLINK "http://www.infrapppworld.com/documents/projects/project-brief-43.pdf"East HYPERLINK "http://www.infrapppworld.com/documents/projects/project-brief-43.pdf" HYPERLINK "http://www.infrapppworld.com/documents/projects/project-brief-43.pdf"Container HYPERLINK "http://www.infrapppworld.com/documents/projects/project-brief-43.pdf" HYPERLINK "http://www.infrapppworld.com/documents/projects/project-brief-43.pdf"Terminal (SLPA‐ADB April 2016)
・「First HYPERLINK "http://www.ingerop.fr/en/news/first-span-615km-long-road-and-rail-padma-bridge-installed" HYPERLINK "http://www.ingerop.fr/en/news/first-span-615km-long-road-and-rail-padma-bridge-installed"span HYPERLINK "http://www.ingerop.fr/en/news/first-span-615km-long-road-and-rail-padma-bridge-installed" HYPERLINK "http://www.ingerop.fr/en/news/first-span-615km-long-road-and-rail-padma-bridge-installed"on HYPERLINK "http://www.ingerop.fr/en/news/first-span-615km-long-road-and-rail-padma-bridge-installed" HYPERLINK "http://www.ingerop.fr/en/news/first-span-615km-long-road-and-rail-padma-bridge-installed"6.15km HYPERLINK "http://www.ingerop.fr/en/news/first-span-615km-long-road-and-rail-padma-bridge-installed" HYPERLINK "http://www.ingerop.fr/en/news/first-span-615km-long-road-and-rail-padma-bridge-installed"long HYPERLINK "http://www.ingerop.fr/en/news/first-span-615km-long-road-and-rail-padma-bridge-installed" HYPERLINK "http://www.ingerop.fr/en/news/first-span-615km-long-road-and-rail-padma-bridge-installed"road HYPERLINK "http://www.ingerop.fr/en/news/first-span-615km-long-road-and-rail-padma-bridge-installed" HYPERLINK "http://www.ingerop.fr/en/news/first-span-615km-long-road-and-rail-padma-bridge-installed"and HYPERLINK "http://www.ingerop.fr/en/news/first-span-615km-long-road-and-rail-padma-bridge-installed" HYPERLINK "http://www.ingerop.fr/en/news/first-span-615km-long-road-and-rail-padma-bridge-installed"rail HYPERLINK "http://www.ingerop.fr/en/news/first-span-615km-long-road-and-rail-padma-bridge-installed" HYPERLINK "http://www.ingerop.fr/en/news/first-span-615km-long-road-and-rail-padma-bridge-installed"Padma HYPERLINK "http://www.ingerop.fr/en/news/first-span-615km-long-road-and-rail-padma-bridge-installed" HYPERLINK "http://www.ingerop.fr/en/news/first-span-615km-long-road-and-rail-padma-bridge-installed"Bridge HYPERLINK "http://www.ingerop.fr/en/news/first-span-615km-long-road-and-rail-padma-bridge-installed" HYPERLINK "http://www.ingerop.fr/en/news/first-span-615km-long-road-and-rail-padma-bridge-installed"is HYPERLINK "http://www.ingerop.fr/en/news/first-span-615km-long-road-and-rail-padma-bridge-installed" HYPERLINK "http://www.ingerop.fr/en/news/first-span-615km-long-road-and-rail-padma-bridge-installed"installed HYPERLINK "http://www.ingerop.fr/en/news/first-span-615km-long-road-and-rail-padma-bridge-installed"」
(Ingerop 2017.11.17)
・「A HYPERLINK "https://qz.com/983460/obor-an-extremely-simple-guide-to-understanding-chinas-one-belt-one-road-forum-for-its-new-silk-road/" HYPERLINK "https://qz.com/983460/obor-an-extremely-simple-guide-to-understanding-chinas-one-belt-one-road-forum-for-its-new-silk-road/"simple HYPERLINK "https://qz.com/983460/obor-an-extremely-simple-guide-to-understanding-chinas-one-belt-one-road-forum-for-its-new-silk-road/" HYPERLINK "https://qz.com/983460/obor-an-extremely-simple-guide-to-understanding-chinas-one-belt-one-road-forum-for-its-new-silk-road/"guide HYPERLINK "https://qz.com/983460/obor-an-extremely-simple-guide-to-understanding-chinas-one-belt-one-road-forum-for-its-new-silk-road/" HYPERLINK "https://qz.com/983460/obor-an-extremely-simple-guide-to-understanding-chinas-one-belt-one-road-forum-for-its-new-silk-road/"to HYPERLINK "https://qz.com/983460/obor-an-extremely-simple-guide-to-understanding-chinas-one-belt-one-road-forum-for-its-new-silk-road/" HYPERLINK "https://qz.com/983460/obor-an-extremely-simple-guide-to-understanding-chinas-one-belt-one-road-forum-for-its-new-silk-road/"understanding HYPERLINK "https://qz.com/983460/obor-an-extremely-simple-guide-to-understanding-chinas-one-belt-one-road-forum-for-its-new-silk-road/" HYPERLINK "https://qz.com/983460/obor-an-extremely-simple-guide-to-understanding-chinas-one-belt-one-road-forum-for-its-new-silk-road/"China’s HYPERLINK "https://qz.com/983460/obor-an-extremely-simple-guide-to-understanding-chinas-one-belt-one-road-forum-for-its-new-silk-road/" HYPERLINK "https://qz.com/983460/obor-an-extremely-simple-guide-to-understanding-chinas-one-belt-one-road-forum-for-its-new-silk-road/"One HYPERLINK "https://qz.com/983460/obor-an-extremely-simple-guide-to-understanding-chinas-one-belt-one-road-forum-for-its-new-silk-road/" HYPERLINK "https://qz.com/983460/obor-an-extremely-simple-guide-to-understanding-chinas-one-belt-one-road-forum-for-its-new-silk-road/"Belt HYPERLINK "https://qz.com/983460/obor-an-extremely-simple-guide-to-understanding-chinas-one-belt-one-road-forum-for-its-new-silk-road/", HYPERLINK "https://qz.com/983460/obor-an-extremely-simple-guide-to-understanding-chinas-one-belt-one-road-forum-for-its-new-silk-road/"One HYPERLINK "https://qz.com/983460/obor-an-extremely-simple-guide-to-understanding-chinas-one-belt-one-road-forum-for-its-new-silk-road/" HYPERLINK "https://qz.com/983460/obor-an-extremely-simple-guide-to-understanding-chinas-one-belt-one-road-forum-for-its-new-silk-road/"Road HYPERLINK "https://qz.com/983460/obor-an-extremely-simple-guide-to-understanding-chinas-one-belt-one-road-forum-for-its-new-silk-road/"」 (QUARTZ)
・インドネシア高速鉄道計画 HYPERLINK "https://ja.wikipedia.org/wiki/インドãƒã‚·ã‚¢é«˜é€Ÿé‰„é“計画" (Wikipedia)
・「中国パキスタン経済回廊 HYPERLINK "http://kitagawa.hatenablog.com/entry/2017/03/04/141519"CPEC HYPERLINK "http://kitagawa.hatenablog.com/entry/2017/03/04/141519" HYPERLINK "http://kitagawa.hatenablog.com/entry/2017/03/04/141519"は勢力関係の縮図」 (South Asian Review 2017.3.4)
・Sri HYPERLINK "http://www.bbc.com/news/world-asia-40761732" HYPERLINK "http://www.bbc.com/news/world-asia-40761732"Lanka HYPERLINK "http://www.bbc.com/news/world-asia-40761732" HYPERLINK "http://www.bbc.com/news/world-asia-40761732"signs HYPERLINK "http://www.bbc.com/news/world-asia-40761732" HYPERLINK "http://www.bbc.com/news/world-asia-40761732"deal HYPERLINK "http://www.bbc.com/news/world-asia-40761732" HYPERLINK "http://www.bbc.com/news/world-asia-40761732"on HYPERLINK "http://www.bbc.com/news/world-asia-40761732" HYPERLINK "http://www.bbc.com/news/world-asia-40761732"Hanbantota HYPERLINK "http://www.bbc.com/news/world-asia-40761732" HYPERLINK "http://www.bbc.com/news/world-asia-40761732"port HYPERLINK "http://www.bbc.com/news/world-asia-40761732" HYPERLINK "http://www.bbc.com/news/world-asia-40761732"with HYPERLINK "http://www.bbc.com/news/world-asia-40761732" HYPERLINK "http://www.bbc.com/news/world-asia-40761732"China (BBC News 2017.7.29)
中国の「一帯一路(債務の罠外交)」がもたらした結論は「手抜き工事」だった。
中国企業が建設、地震で倒壊のバンコクのビルに「手抜き工事」の疑い―独メディア
2025年4月2日
Record China によるストーリー
2025年4月1日、独ドイチェ・ヴェレは、ミャンマーで発生した大地震によってタイの首都バンコクで倒壊した高層ビルについて、中国企業が請け負った施工に手抜きがあった疑いが持ち上がっていることを報じた。
© Record China
2025年4月1日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、ミャンマーで発生した大地震によってタイの首都バンコクで倒壊した高層ビルについて、中国企業が請け負った施工に手抜きがあった疑いが持ち上がっていることを報じた。
記事は、ミャンマーで2025年3月28日に発生したマグニチュード7.7の大地震によって2000人以上が亡くなり、隣国タイでも20人以上が死亡したと紹介。タイでの死者のほとんどは「バンコクで地震によって倒壊した唯一の主要な建物」である建設中の30階建て市庁舎によるものだったと伝えた。
また、市庁舎の建設について中国中鉄集団(CREC)傘下の中国中鉄十局(タイ)有限公司が建設を担当していることに触れた上で「バンコクには無数の高層ビルが立ち並んでいるが、他の建物で深刻な被害は報告されていない。このことが、なぜ建設中のこの建物だけが倒壊したのかという疑問を呼んでいる」とした。
そして、タイのペートンタン首相がビルの倒壊発生後に建設現場の資材と安全基準の調査を命じたことを紹介。安全当局者が同月31日に建設現場の鉄筋検査で、一部の金属材料が基準を満たしていないことが明らかになったと発表したことを伝えている。
記事は「中国中鉄集団とその子会社が重大な事故で批判される初めてのケースではない」とし、昨年2024年11月には同集団の子会社が建設したセルビアの鉄道駅の屋根が倒壊して14人が死亡する事故が起き、現地市民からは手抜き工事に対する疑問の声が上がったと報じた。さらに、ある移民労働者組織の関係者が「タイで働く中国企業の雇用する移民労働者から、劣悪な安全基準と不十分な労働者の権利に関する苦情が多数寄せられている」とした上で、労働者への待遇の悪さが事故の遠因になった可能性を指摘していることをも紹介した。
記事はこのほか、中国中鉄十局は、中国アプリの微信(ウィーチャット)の公式チャンネルに掲載していた市庁舎の建設現場主要構造完成したことを祝う告知を、地震発生直後に削除したことを合わせて紹介。告知には「これは中国中鉄十局がタイで発展するための名刺となるだろう」などと記載されていたことを伝えた。また、中国のネット上では関連のニュースやコメントが軒並み削除されたとも報じている。(編集・翻訳/川尻)
2025年4月1日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、ミャンマーで発生した大地震によってタイの首都バンコクで倒壊した高層ビルについて、中国企業が請け負った施工に手抜きがあった疑いが持ち上がっていることを報じた。
記事は、ミャンマーで3月28日に発生したマグニチュード7.7の大地震によって2000人以上が亡くなり、隣国タイでも20人以上が死亡したと紹介。タイでの死者のほとんどは「バンコクで地震によって倒壊した唯一の主要な建物」である建設中の30階建て市庁舎によるものだったと伝えた。
また、市庁舎の建設について中国中鉄集団(CREC)傘下の中国中鉄十局(タイ)有限公司が建設を担当していることに触れた上で「バンコクには無数の高層ビルが立ち並んでいるが、他の建物で深刻な被害は報告されていない。このことが、なぜ建設中のこの建物だけが倒壊したのかという疑問を呼んでいる」とした。
そして、タイのペートンタン首相がビルの倒壊発生後に建設現場の資材と安全基準の調査を命じたことを紹介。安全当局者が同月31日に建設現場の鉄筋検査で、一部の金属材料が基準を満たしていないことが明らかになったと発表したことを伝えている。
記事は「中国中鉄集団とその子会社が重大な事故で批判される初めてのケースではない」とし、昨年11月には同集団の子会社が建設したセルビアの鉄道駅の屋根が倒壊して14人が死亡する事故が起き、現地市民からは手抜き工事に対する疑問の声が上がったと報じた。さらに、ある移民労働者組織の関係者が「タイで働く中国企業の雇用する移民労働者から、劣悪な安全基準と不十分な労働者の権利に関する苦情が多数寄せられている」とした上で、労働者への待遇の悪さが事故の遠因になった可能性を指摘していることをも紹介した。
記事はこのほか、中国中鉄十局は、中国アプリの微信(ウィーチャット)の公式チャンネルに掲載していた市庁舎の建設現場主要構造完成したことを祝う告知を、地震発生直後に削除したことを合わせて紹介。告知には「これは中国中鉄十局がタイで発展するための名刺となるだろう」などと記載されていたことを伝えた。また、中国のネット上では関連のニュースやコメントが軒並み削除されたとも報じている。(編集・翻訳/川尻)
中国・シャオミ製造のEVが事故 大学生3人死亡
2025年4月2日
中国の大手スマートフォンメーカー・シャオミが製造したEV=電気自動車が中央分離帯に衝突する事故があり、乗っていた大学生3人が死亡しました。遺族がメーカーの責任を問うなど、中国国内で波紋が広がっています。
中国メディアやメーカーの発表によりますと先月29日夜、安徽省の高速道路で、大学生の女性3人が乗るEVが、前方で道路工事が行われていたため車線変更しようとした際、コンクリートの中央分離帯に衝突しました。
この事故で乗っていた3人全員が死亡しました。
この車は、シャオミが去年3月に発売した「SU7」で、シャオミによりますと車は時速116キロで走行中に工事現場を検知し、運転手に対し手動モードに切り替えるよう警告を鳴らして自動で減速を始めたものの、制御できず衝突したということです。
SNS上では「衝突の2秒前に手動モードに促されても、間に合うはずがない」などの指摘が上がっているほか、中国メディアは遺族の話として「事故の衝撃で車が炎上した際、 ドアが開かなくなった」との主張を報じています。
「SU7」は去年3月の発売時、わずか27分で5万台の予約があったとされ、大きな注目を集めていました。
シャオミの雷軍CEOは1日、「専門チームを設置し、警察の捜査に協力し対応に当たる」と声明を発表しています。
中国では、車の運転サポート機能をめぐり、過去にも複数のメーカーで衝突事故が起きていて、安全性を懸念する声が上がっていました。
とうとう
ドイツ経済、壊れた欧州の成長エンジン
2024年1月15日
ドイツは閉塞状況にあり、手っ取り早く抜け出す方法はない。
ドイツ経済は欧州大陸で最も大きく、世界でも4位の規模を誇るが、昨年2023年は縮小した。6年にわたって続く不振は産業空洞化の懸念を引き起こし、欧州全域で各国政府への支えが失われる状況を招いている。
ドイツ連邦統計局は2024年1月15日、2023年12月までの3カ月間の同国の国内総生産(GDP)が前の四半期に比べ0.3%減少したとみられると発表した。同統計局によると、2023年全体では前年比0.3%減で、新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)前の2019年の水準を0.7%しか上回っていない。欧州連合(EU)の推計によれば、フランス、イタリア、スペインを含むユーロ圏の他の大国では、昨年に景気が拡大したとみられる。
ドイツの景気悪化は、ドイツの輸出中心のビジネスモデルを一変させつつある逆風が重なっている状況を反映している。逆風には、中国の成長減速からエネルギー価格や金利の上昇、世界貿易を巡る緊張の高まり、グリーンエネルギーへの移行の難しさに至るまでが挙げられる。こうした周期的で構造的な要因のいずれもが直ちに改善される兆候がまったくないことから、ドイツの見通しは良好ではなさそうだ。
フランクフルトを拠点とするナティクシスのエコノミスト、ディルク・シューマッハ氏は「これほどドイツの中期的な見通しを懸念したことは今までにない」と述べた。同氏は数十年にわたってドイツ経済を追跡してきた。
ドイツのインフレ調整後のGDPは、2017年末比でわずか1%増にとどまった。米経済が同時期に13%(インフレ調整後)成長したのとは対照的だ。欧州連合(EU)統計局と米経済分析局(BEA)のデータから明らかになった。
ドイツは今年、不動産市場の崩壊や中東の紛争によるアジア・欧州間の通商航路寸断など、新たな経済的脅威に直面している。失業率が上昇し、移民の数が過去最多になっているにもかかわらず、企業は労働力不足を訴えている。憲法裁判所が予算外の基金の使用を制限する判断を下したため、政府の歳出計画は混乱に陥っている。
こうした問題を受けて、幅広い人々が怒りを強めている。農業従事者らは2024年1月15日、補助金削減に抗議し、ベルリンで道路を封鎖するデモを行った。 世論調査の結果によると、6月の欧州議会議員選挙とその後の年内に予定される州議会議員選挙では、極右政党「ドイツのための選択肢(AfD)」がドイツの最大政治勢力となる可能性がある。
これらすべてを受けて、「欧州の病人」との呼び名が復活しつつある。この名は1990年代終わりから2000年代初めにドイツに付けられた。当時の同国は、東西統一の後遺症で競争力を失っていた。
ドイツ東部ザクセン州にある創業175年の鋳物メーカーGLギーセライ・レースニッツのマックス・ヤンコフスキー最高経営責任者(CEO)は「産業空洞化の脅威があることは事実だ」と述べる。
同社は、ドイツの基幹産業である自動車製造業界の重要部分を占めている。独自動車業界は約80万人を雇用し、製品の4分の3程度を輸出している。同社の顧客にはBMW、ダイムラー、フォルクスワーゲンなどがある。
エネルギー価格は一時より下がったが、ヤンコフスキー氏によれば、それでも電力価格はロシアのウクライナ侵攻開始前と比べて3~4倍になっており、米国の競合企業が払っている額との比較では5倍以上になる。同氏は、この問題の解決に向けた政府の対応について「依然として戦略の全体像が見えない」と語った。
同氏は、1000万ユーロ(約15億9600万円)を投じて電炉を建設する計画を立てている。これは、炭素税の引き上げで運転継続が厳しくなった大型の石炭炉の代わりに導入するものだ。しかし同氏によると、電力価格が極めて高い上、政府が明確な価格引き下げ策を示していない現状では、新たな電炉で競争力が得られることはない。
同氏は「われわれは、コスト上昇分を自動車メーカーに転嫁することができない。そうすればメーカー側が、トルコや中国に乗り換えると言うからだ」と語った。
歴史あるドイツの自動車産業は現在、欧州で電気自動車(EV)販売を強化しつつある中国の新興ライバル企業との競争で苦境に陥っている。 ロビー団体の独自動車工業会によると、同国の乗用車生産台数は、2010年代半ばの水準を25%余り下回っている。また、主に富裕諸国で構成される経済協力開発機構(OECD)によれば、ドイツの製造業全体の生産高は2019年の水準を下回っており、減少傾向にある。
現在、紅海で緊張が高まっていることで海運が混乱し、欧州メーカーの間では新たなサプライチェーン(供給網)危機の不安が広がっている。米テスラは2024年1月12日、部品不足を理由に、ベルリン近郊にある同社の欧州最大規模の工場で1月29日から2月12日までほぼすべての生産を停止すると発表した。
ドイツ商工会議所(DIHK)が最近、工業分野の同国企業2200社以上を対象に行った景況感調査は、2008年の調査開始以降で最悪の結果となった。
DIHKのマルティン・バンスレーベン会長は「工業やその関連業界にとってドイツの魅力は急速に低下している。その結果、必要な投資が行われなかったり、他の場所で行われたりしている」と述べた。
バンク・オブ・アメリカは先週、ドイツおよびユーロ圏の成長率予測を下方修正した。ドイツについては今年の経済成長の見通しを従来予想のプラス0.3%からマイナス0.1%に引き下げた。
痛みは経済だけにとどまらない。今月、公共放送ARDの委託を受けてインフラテスト・ディマップが実施した世論調査結果が公表され、有権者のオラフ・ショルツ首相の支持率はわずか19%と、1997年以降の歴代首相で最低となったことが明らかになった。不支持の理由は、政府がグリーン移行政策の加速を決めたことから、不法移民の急増を抑制できなかったことまでに及んでいる。
ロビー団体であるドイツ機械工業連盟(VDMA)の主任エコノミスト、ラルフ・ビーヒャース氏は「われわれは向かい風を受けている」と語った。VDMAによると、ドイツ国内で100万人以上を雇用する機械工業セクターの2023年11月の受注額(インフレ調整後)は、前年同月比13%減となった。
ビーヒャース氏は「われわれは今のところ受注残に頼っているが、それもなくなりつつある」と述べ、「まだ底を打ったわけではない」との見方を示した。
こうした状況は製造業だけにとどまらない。ナティクシスのデータによれば、投資と個人消費も2019年の水準を下回っており、フランスやスペインといった他の欧州主要国の成長率にも大きく後れを取っている。ドイツの労働市場にも悪影響が及び始めている。2022年に一時5%まで低下した失業率は、先月には5.9%に上昇した。
ベルリン中心部にあり観光スポットになっているレストランStaendige Vertretungのオーナー、イェルン・ブリンクマン氏は「ドイツ人の顧客が支出を控えている実感がある」と話す。
レストランでの食事にかかる付加価値税(VAT)は今月、コロナ流行期の減税措置の期限切れに伴い、7%から19%に引き上げられた。このことでさらに需要が減る可能性が高いとブリンクマン氏は指摘する。同氏は経費節減のため、スポット市場で電力を購入している。ブリンクマン氏がまだ付加価値税の税率上昇を反映した値上げをしていない唯一の理由は、メニューを印刷し直すコストが高いことだ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
一帯一路から足を洗えなくなった独・伊・その他の国々の今後は・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ロシアと中国から離れるドイツ、新たなビジネスパートナーを探す―独メディア
Record China 2022/11/15
独ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは13日、ドイツについて「ロシアと中国から離れ、新たなビジネスパートナーを探す」とする記事を掲載した。
記事によると、ドイツは一国への経済依存から脱却することを望んでおり、経済をより「多様化」させるために、政府は志を同じくする友好国とのビジネスだけでなく、「非民主主義国」とのより緊密な協力関係の確立も計画している。
ドイツのショルツ首相は何カ月にもわたってドイツの産業界に「アジアは中国だけではない」とのメッセージを広めてきた。「投資や輸出入において、まなざしを他のアジア諸国やアフリカ、南米などの地域に向けることを希望する」と何度も表明した。
「他のアジア諸国」にはベトナムとシンガポールが含まれる。ショルツ首相は、インドネシアで開催される20カ国・地域(G20)首脳会議に先立ち、ドイツの企業家代表団を連れてこの2カ国を訪れ、シンガポールで開催される「ドイツビジネスアジア太平洋会議(APK)」への出席も予定している。
ドイツ連邦首相府によると、今回の訪問、特にAPKへの出席は、「ドイツ経済を多様化し、中国からますます離れさせたい」というシグナルだ。
ドイツとシンガポールとの関係は、コロナ禍で一層緊密になり、多くのドイツ企業が中国からシンガポールに移転。シンガポールで登録されているドイツ企業は2000社を超える。このハイテク国には、持続可能なプロジェクトへの投資を好む二つの数十億ドル規模の政府系ファンドがあり、ドイツ政府はそうしたファンドがドイツのエネルギーモデルチェンジに参与し、資金援助することを望んでいる。
首相府は、ベトナムを「東南アジアの主要な中等国」とし、シンガポールについては「安定性とルール志向の外交政策行為体で、われわれの間には一連の共通点がある」と指摘している。
ドイツは、社会主義国ベトナム とも良好な経済関係があり、そうした関係は二つのドイツ時代にまでさかのぼることができる。当時、東ドイツには多くのベトナム人が住んでいた。ベトナムにはドイツ語を勉強している人も多く、ベトナム-ドイツ大学もある。ドイツ政府筋は、ベトナムを「強力な経済パートナーであり、さらなる協力形態を模索するに値するパートナー」と呼んでいる。 (翻訳・編集/柳川)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
VIDEO 【東京ホンマもん教室】12月11日 放送 見逃し動画 日本を喰う中国
日本人が知らない経済「侵略」の真実
ゲスト:高市早苗(自民党政調会長)
もう日本人の出る幕なし?外国人だらけのニセコに見る日本の未来
毎年冬のシーズンになると中国や香港などアジア諸国を筆頭 に、オーストラリアやイギリスなど欧米諸国からも観光客が足を運んでいます。こうした外国人観光客の増加に加えて、ニセコ観光圏で働く外国人の数も急増しています。この結果、「ニセコエリアを歩けば日本人を見かける方が稀」という不思議な現象が起きています。案内看板やお店のメニューなど、いたる所で目にするのは日本語ではなく英語表記です。外国人観光客を相手に商売するのは外国人という構図が出来上がっています。ニセコ観光圏は、まさに外国人による外国人のためのリゾート地と化しています。
西川口チャイナタウン の形成要因に関する研究 ―東京圏における中国人集住地域に着目してStudy on Formation Factors of Nishi-Kawaguchi Chinatown Focusing on the Chinese Residents Concentrated Area in Tokyo Metropolitan Area東京工業大学大学院環境・社会理工学院博士後期課程 高 松 宏 弥
School of Environment and Social, Tokyo Institute of Technology Hiroya TAKAMATSU ABSTRACT: This paper aims to clarify the formation factors of new Chinese residents concentrated area in Metropolitan Area, Nishi-Kawaguchi Chinatown. This study found out that the formation factors of Nishi-Kawaguchi Chinatown are related with not only economic, but also policy, society, and culture. This important finding suggested that Nishi-Kawaguchi Chinatown has been turning into multicultural ethnic town with multiculturalization of Japanese society.キーワード: 西川口チャイナタウン、エスニック・タウン、中国人ニューカマーズ、東京圏、中国人集住地域Keywords: Nishi-Kawaguchi Chinatown, Ethnic Town, Chinese New Comers, Tokyo Metropolitan Area, Chinese Residents Concentrated Area
1.はじめに
本稿の目的は、日本の地域社会におけるエスニック・タウンの形成要因と地域社会経済への影響を明らかにすることである。少子高齢化とそれに伴う労働者人口の減少への対応として、日本政府は在留資格の新設による外国人の受け入れ拡大を2019年4月から開始し、2019年度からの5年間で最大約34万人の受け入れを行うとした(1)。法務省の『在留外国人統計』によると、2018年末現在、日本の在留外国人は2,731,093人であり、これは日本の総人口の約2.2%に相当する。都道府県別でみると、最も外国人が多いのは東京都の567,789 人(総数の20.8%)で、つぎに多い愛知県の260,952 人(同9.6%)の2倍以上の外国人が居住している。東京都に埼玉県(180,762人)、千葉県(156,058人)、神奈川県(218,946人)の3県を加えた東京圏でみると、外国人人口は1,123,555人で、全国の41.1%もの外国人が居住している(2)。このように多くの外国人が居住する東京圏には、昨今、多種多様なエスニック・タウン(=外国人街)が形成されている(3)。2013 年に実業之日本社が出版したガイドブック「おさんぽマップ 東京エスニックタウン」では、西葛西(江戸川区)のインド人街や新大久保(新宿区)の韓国人街、竹ノ塚(足立区)のフィリピン人街を含む12の地域が東京のエスニック・タウンとして紹介されている(4)。こうしたなか、東京圏における新しいエスニック・タウンのなかでもとりわけ新しく、一般的にも注目を集めているのが埼玉県川口市の「西川口チャイナタウン」である(5)。西川口チャイナタウンが位置する埼玉県川口市は、日本で最も多くの中国人が居住する地域で、外国人ニューカマーズの集住が進む東京圏においても、特に集住傾向が強い地域のひとつである(表1、図1参照)。他方、東京圏におけるチャイナタウンとして広く知られているのは「横浜中華街」であり、これまで多くの研究でその形成要因が論じられてきた(山下,1979、齋藤ほか,2011、伊藤,2018など)。しかし、後述するように、西川口に代表される新しいチャイナタウンの形成要因については、横浜・神戸・長崎をはじめとする古くから日本に居住する中国人たちが形成した中華街等を対象とした、観光地化や形成過程に関する従来の多くの研究で得られた知見からは十分に説明することができないのが現状である。これは、西川口チャイナタウンが、従来の日本社会において顕在化してこなかった大都市郊外に形成した新しいエスニック・タウンであることが背景にある。なお、本稿でいうチャイナタウンとは、「海外の都市における華人(中国人)の集中居住地区であり、さまざまなエスニック集団(民族集団)によって形成された街」で、「中国文化と現地社会の文化との接触に生まれた、華人が集中する商業、業務地区」を指す(山下,2000:3)。本稿で着目する新しいチャイナタウンの特徴としては、日本人観光客向けの観光地として発展した三大中華街とは異なり、中華街のシンボルである牌楼がなく、中国人同胞向けのサービスを提供する店舗が集積していることがあげられる(山下,2016:57)。本研究の問いは以下の3点である。第一に、西川口に中国人が集住する要因は何か。第二に、西川口に中華料理店が集積する要因は何か。第三に、西川口チャイナタウンの形成は地域社会経済にどのような影響を及ぼしたのか。本稿では、以上の問いについての検討を通して、西川口チャイナタウンの形成要因を明らかにする。第2節では、本研究に関連する先行研究を概観する。日本における中国人ニューカマーズの増加と居住に関する先行研究は多数存在するものの、新しいチャイナタウンの形成やそれに伴う地域社会経済への影響に関しては十分に議論されていないことがわかった。第3節では、多くの中国人ニューカマーズが集住する川口市において形成された新しいチャイナタウンである西川口チャイナタウンを対象に、地域特性の変容や中国人の増加と居住、中華料理店の分布と店舗数について概観した。第4節では、西川口チャイナタウンの形成要因と地域社会経済への影響について、現地での聞き取り調査で得られた知見をもとに、公的統計データを用いて検討を行った。その結果、西川口チャイナタウンの形成要因は、西川口地域の衰退・停滞期と東京圏における中国人人口の増加期が重なり、西川口周辺に中国人の集住が進んだ結果、同胞向けの中華料理店の開店が相次いだことにあることがわかった。また、チャイナタウンの形成は、日本人観光客を惹きつけることで地域経済を活性化したほか、中国人のみならず、ほかのエスニックグループの集住をも促すことを明らかにした。
2.先行研究本研究
に関わる先行研究は、①中国人ニューカマーズの増加と居住、②新しいチャイナタウンの形成、③エスニック・タウンの形成と地域社会経済への影響、の三分野にある。まず、中国人ニューカマーズの増加と居住についてみていく。日本に在住する中国人は、「新華僑」(中国人ニューカマーズ)と「老華僑」(中国人オールドタイマーズ)の2つのグループに大別できるが、本稿では中国人ニューカマーズについて焦点をあてる(6)。日本において中国人人口が大きく増加するのは1980年代以降であるが、当時来日した中国人の多くは留学目的であり、当時日本語学校の多くが集中していた東京都、とりわけアルバイト機会にも恵まれていた新宿や池袋周辺に集住するようになったという(奥田・田嶋,1995、田嶋,1998、山下,2011:192)(7)。中国人オールドタイマーズが中心であった1978年以前は居住地域が分散していたのに対し、中国人人口が急増する1979年から1988年にかけては中国人オールドタイマーズと中国人ニューカマーズによって池袋や新宿において集住地域が形成され、1989年以降は中国人ニューカマーズが中心となり郊外化・定住化が進んでいったという(山下,2011:199)。郊外化が進んだ要因としては、結婚や子どもの誕生を機により広い住宅を求め、郊外に位置する埼京線や京浜東北線の沿線地域に移動するようになったことが指摘されている(江・山下,2005)。つづいて、新しいチャイナタウンの形成について議論する。日本における従来のチャイナタウンに関する研究は、戦前に来日した中国人オールドタイマーズによってつくられた横浜中華街・神戸南京町・長崎新地中華街の三大中華街を対象としたものが中心である(山下,1979、王,1998、辺,2018など)。他方、1980年代以降来日した中国人ニューカマーズが形成したのが新しいチャイナタウンである。1980年代から1990年代にかけて池袋において中国人ニューカマーズの集住が進み、その結果として2000年代前半頃に新しいチャイナタウンが形成されたという(奥田・田嶋,1995、田嶋,1998、山下,2010)。現在もなお中国人人口が増加し続けており、居住地域の郊外化がみられる東京圏において、池袋以外の地域においても新しいチャイナタウンが形成されていることにも目を向ける必要があろう。また、世界のチャイナタウンの類型化を行った山下によると、日本三大中華街は観光地としての機能が強かった一方で、池袋チャイナタウンは同胞へのサービス提供やホスト社会住民への商業を中心としているという(山下,2019)。最後に、エスニック・タウンの形成と地域社会経済への影響についての議論を紹介する。これまでも、特定のエスニック・タウンを対象に、その形成過程や観光地化による地域社会関係の変容について考察した研究がある(阿部,2011、申,2015、丸山,2015など)。エスニック・タウンの形成は地域社会関係に変化をもたらすにとどまらず、エスニック・ビジネスの集積を促すため、住民や観光客を誘引し、地域社会経済全体の活性化に寄与する可能性があることも指摘されている(Jones・Simons,1990、片岡,2005、Barret・McEvoy,2006、堀江,2015など)。他方、エスニック・タウンの形成が与える地域社会経済への影響について日本では十分に議論がなされていないという(堀江,2015)。堀江も指摘しているが、少子高齢化と地域経済の衰退が深刻化する今日の日本において、衰退する中心商店街へのエスニック・ビジネスの集中がどのような影響をもたらすのかさらなる検討が必要であろう。以上をまとめると、中国人ニューカマーズの増加と居住に関する先行研究は多数あるが、新しいチャイナタウンの形成やそれに伴う地域社会経済への影響に関しては十分に議論されていない。そこで本研究は、中国人ニューカマーズによって形成された新しいチャイナタウンの形成要因と地域社会経済への影響の解明を行う。3.事例の検討:西川口におけるチャイナタウンの形成過程1)西川口における地域特性の変容西川口チャイナタウンの形成過程について議論する前に、西川口における地域特性の変容について概観する。西川口は埼玉県川口市北西部に位置し、西川口駅の周辺地域を指す。古くは映画「キューポラのある街」に代表されるように、戦後日本を代表する「鋳物のまち」として栄えた。1942年には川口市単独で鋳物生産量日本一を達成し、工場数が700を超えた1947年には、鋳物生産額が全国の約3分の1に達した(佐藤,2013)(8)。また、西川口駅周辺は都心へのアクセスが良い地域でもある。1954年に西川口駅が開業し、1956 年には川口と浦和を結ぶ産業道路が完成するなど、東京のベッドタウンとして発展していった(増田ほか,2008)。他方、川口オートレース場が1952年に完成し、1956年には売上1億円を突破するなど、西川口駅周辺には、オートレース場や戸田競艇場を訪れる客向けに飲食店や性風俗店が次第と集まるようになったという(増田ほか,2008)(9)。西川口駅西口を中心に性風俗店が目立つようになったのは1980年代頃からで、その後20年近くものあいだ性風俗店は増加し続けた。こうして首都圏有数の性風俗街として知られるようになった西川口では、「NK(西川口)流」という言葉に代表されるような、過激なサービスを行う違法性風俗店が多数存在していた(10)。周辺環境の悪化を懸念する地元住民からの声に応えるかたちで次第に取締りが強化され、埼玉県警の主導で違法性風俗店の一斉摘発が行われた(増田ほか,2008、田村,2008)。2006年末には西川口駅周辺の違法性風俗店は一掃され、埼玉県警による浄化は成功したが、性風俗街として全国的な知名度を誇った負のイメージは簡単には払拭できなかった。そのため駅周辺でも商業店舗のテナント入居は進まず一時はゴーストタウン化したともいわれた(増田ほか,2008、田村,2008)(11)。こうしたなか、西川口駅西口周辺の空き店舗に中華料理店が入居したことが、西川口チャイナタウン形成のきっかけになったとされる。西川口地域の中華料理店で提供される中華料理は「本場の味」ともいわれており、西川口チャイナタウンは「中国人の中国人による中国人のためのチャイナタウン」であると表現されている(12)。このように、西川口チャイナタウンでは中華料理を通して同胞向けのサービスが展開されており、牌楼がないことからも、第2節で述べたような新しいチャイナタウンの特徴を備えているといえる。2)西川口における中国人の増加と居住つづいて、西川口のチャイナタウン化の背景にある、中国人の増加と居住についてみていく。表1でみたように、西川口が所在する川口市は現在、日本で最も多くの中国人が居住する地域である(図2、3参照)。川口市において中国人人口が増加し始めた1980年当時、日本に居住していた中国人が52,896人であったのに対し、川口市は78人に過ぎなかった[登録外国人統計、川口市統計書]。その後、川口市の中国人人口は1980年代前半から1990年代前半にかけて増加し、1993年には韓国・朝鮮籍を持つ外国人人口(2,601人)を抜き、川口市で最も多い外国人は中国人となった(2,683人)ほか、1997年から現在までの間一貫して増加傾向にある。図3で表した西川口における外国人人口の推移をみても一貫して増加傾向にあり、西川口においても川口市全体と近いかたちで中国人人口の増加がみられると考えられる(13)。なお、図2からは2014年以降のベトナム人の急激な増加も確認でき、表1と合わせてみると、西川口を含む川口市の多文化化が進んでいることがうかがえる。3)西川口チャイナタウンにおける中華料理店の分布と店舗数つぎに、西川口チャイナタウンを構成する中華料理店の分布と店舗数について議論する(図4参照)。西川口チャイナタウンにおける中華料理店の多くは西川口駅西口に所在しており、「食べログ」に登録された74 店舗中、約半数は西川口1丁目に所在していることがわかる。西川口1丁目は2000年代後半の違法性風俗店の取締りによって空き店舗が増加したとされる地域であり、そうした空き店舗に中華料理店の入居が進んでいったことがうかがえる。また、西川口駅東口の並木2丁目、並木3丁目にも多くの中華料理店が位置しており、西口のみならず東口においてもチャイナタウン化が進んでいることがわかる。4.西川口チャイナタウンの形成要因と地域社会経済への影響1)西川口における中国人の集住ここからは、筆者が現地で行った聞き取り調査で得られた知見をもとに、西川口チャイナタウンの形成要図3.西川口における外国人人口の推移(1997〜2019年)出典:『川口市 町丁字別男女別人口・世帯数の推移』より筆者作成因について検討する(15)。まず、西川口チャイナタウンの形成に欠かせない条件は中国人の集住であるが、西川口を居住先として選択する決め手となったのは、都心へのアクセスの良さと家賃・地価の安さであったという(図5参照)。図5は、本研究で事例として扱った西川口チャイナタウンが位置する西川口1丁目、西川口駅の隣駅で川口市の中心地である川口駅前に位置する栄町3丁目、2000 年代前半に形成した新しいチャイナタウンである池袋チャイナタウンが位置する池袋2丁目の基準地価の変動を表したものである。ここで注目したいのは、2019 年時点で西川口1丁目(36万円/㎡)と栄町3丁目(127万円/㎡)の地価額には大きな差がみられるが、1997年の時点では、西川口1丁目(107万円/㎡)は、川口市の中心地である栄町3丁目(104万円/㎡)よりも地価が高かった点である。この要因としては、西川口が2000年代前半まで首都圏有数の性風俗店の集積地であったことが考えられ、実際に、埼玉県警による取締りが強化された2000年代前半には地価額が急激に下落している。2010 年代以降、栄町3丁目と池袋2丁目の地価額は騰貴傾向にある一方で、西川口1丁目はほぼ横ばいで推移している。筆者が聞き取りを行った西川口の不動産店(D店)の店主によれば、違法性風俗店の浄化から10年以上が経過した現在においても、「西川口にまとわりつく性風俗街のイメージがネガティブに作用し、日本人から居住先として敬遠される」のだという。そのため、「本来であれば外国人の入居を嫌がる大家も多いが、住み手が見つかるならば外国人でも構わないと考える大家が西川口には多い」ようである。また、「中国人居住者の増加を見越して西川口において不動産を所有する中国人の不動産オーナーも増えている」という。他方、中国人をはじめとする外国人の多くは、「西川口=性風俗街というイメージを持たない、または気にしない」ため、都心へのアクセスが良く、家賃・賃料の安い西川口に住むことにためらいを感じないのである。西川口に中華料理店を構える商店主(A〜C店)も同様の印象を持っているという。そのうえで、「中国では土地の個人所有が認められていないため日本では一軒家を持ちたいという中国人たちが、周辺の地域よりも比較的地価が安い西川口に集まってきた」ことが影響しているとも語った。西川口駅周辺に中国人居住者の集住や中華料理店の集積が顕著になった当時は、駅周辺のゴミ集積場でのゴミ捨てルールをめぐ図6.川口市内JR4駅の利用状況(1日平均、乗車人員から定期券利用者を除いた数)出典:『川口市統計書』各年版より筆者作成り地域住民との衝突もあったそうだが、ゴミ捨てルールの周知やゴミ拾い活動の広まりなどを通して、次第にトラブルは減っていったという(16)。2)西川口における中華料理店の集積つづいて、西川口において2010年以降に中華料理店が増加・集積していった要因について検討する。西川口駅西口で30年近く中華料理店を営む商店主によると、西川口に中華料理店が集まるようになったきっかけは、2010年から西川口で開催された「川口B級グルメ大会」であったという。「川口B級グルメ大会」は、違法性風俗店の一掃により160もの空き店舗が生じた西川口の地域活性化策として、埼玉県の支援のもと、川口市と複数の地域団体によって行われた「国際色豊かな“B級グルメ”」イベントであった。ここで注意したいのは、当時の資料を読む限りでは、「中華料理」や「チャイナタウン」についての言及はなく、その後のチャイナタウン化は意図したものではなかったという点である(17)。A店の商店主によると、「2010年の大会では3位に餃子が入賞し、翌年2011年には焼売が優勝したことで、中華料理を目当てに西川口を訪れる日本人観光客が増加した」のだという(図6参照)。図6は川口市内のJR4駅の利用状況の推移を示したものである。これをみると、西川口駅の利用客数(1日平均、乗車人員から定期券利用者を除いた数)の推移は、埼玉県警による性風俗店への取締り強化がはじまった2000年代前半(2003年、18,783人)から、違法性風俗店の浄化にともなう西川口駅西口のゴーストタウン化(2010年、16,576人)までの衰退期と、チャイナタウン化による再生期(2017年、19,085人)と一致していることがわかる。また、西川口駅東口で2010年から中華料理店(B店)を営む商店主によると、「西川口を訪れる日本人観光客は年々増えていたが、2013年に西川口駅東口の刀削麺店が『羊肉串』を提供するようになったことでさらに増えた」という。「羊肉串」とはスパイスで味付けしたラム肉の串焼きで、中国全土で屋台料理として親しまれている中国東北地方の名物である。こうした中国の「本場の味」を求める日本人観光客が訪れるのが西川口チャイナタウンであるという。その後、「2015年頃から西川口のチャイナタウン化がテレビや雑誌等のメディアで注目されるようになり、西川口の中華料理店は一気に増加した」と語る。既出の不動産店(D店)の店主も、「2015年頃から西川口への転居や中華料理店の開店を希望する中国人が増えはじめた」という。B店の店主によれば、「東日本大震災による影響で一時帰国したことで職を失った中国人もおり、彼らが再び来日した際に始めやすかったのが中華料理店の経営で、その際に賃料が安い地域を求めた結果、西川口に中華料理店を出店した者もいる」といい、こうした要因も2015年頃からの中華料理店の増加につながったのではないだろうかと考えられる(表2、図7参照)。表2は2009年から2013年までの中国人出国者数の推移を示したものだが、再入国者数を見ると2011年が突出して多いことがわかる。図7は、中国人人口増加率(前年比)の推移を示したものであるが、2012年から2014年にかけて川口市における中国人人口の増加率が大幅に上昇していることからも、日本への再入国後に西川口を居住地として選択した中国人は少なくなかったことがうかがえる。表2.中国人出国者数の推移(2009〜2013年、各年3月時点)年2009 2010 2011 2012総数97,162 113,691 187,675(うち)再入国者39,495 44,524 135,591 132,735 2013 103,032出典:『出入国管理統計』各年版より筆者作成51,792 53,917また、西川口駅周辺の中華料理店の数は、B店の店主によると「2010年時点で2〜3店舗ほど」、C店の店主によると「2015年時点では多くても10店舗ほど」であったが、「西川口がメディアで注目を集めるにつれて年を追うごとに増加していった」という。他方、西川口チャイナタウンの拡大による影響は必ずしも肯定的な側面にとどまらず、中華料理店が急激に増加したことにより弊害も生じている。2015年から西川口駅西口で中華料理店(C店)を営む商店主は、「西川口に住む中国人に対して、中華料理店が増えすぎた」結果、ビジネスを続けていくためには、「もともと西川口の中華料理店の多くは中国人向けに営業しているが、日本人客をできるだけ多く取り込んでいくことが必要」だと語った。5.考察ここで冒頭の3つの問いに対する知見について整理していく。第一に、西川口において中国人が集住した要因は、西川口は都心へのアクセスが良く、家賃・地価が安いことにある。これは、西川口がかつて性風俗街であったというネガティブなイメージを日本人は持っており、居住先として敬遠する傾向にある一方で、中国人はこうしたイメージを持たない、または気にしないことが影響しているという。第二に、西川口において中華料理店が集積した要因は、中国人の集住要因とも重なるが、政策(B級グルメを通した地域活性化政策の意図せざる帰結)、経済(都心へのアクセスの良さと家賃・地価の安さ)、社会(東日本大震災による一時帰国)、文化(エスニック・ビジネスとしての中華料理店)からなる様々な要因が複雑に絡み合った結果に生じたことにある。また、前節で議論したように、西川口駅周辺の中華料理店は2010 年時点では2〜3軒、2015年時点では多くても10 軒ほどであったが、2015年以降はテレビや雑誌等のメディアで西川口のチャイナタウン化が注目を集めたことで、中華料理店の数は急激に増加していき、図5で示したように、現在では70軒を超える(18)。第三に、西川口チャイナタウンが地域社会経済に及ぼした影響については、中華料理を求めて西川口を訪れる日本人観光客が増加し、街に活気が戻ったことにある。こうした日本人観光客たちは、日本人向けにアレンジされた中華料理ではなく、中国人向けのいわゆる「本場の味」を求めているのである(高松,2019)。また、第4節では触れなかったが、聞き取りを行った西川口駅西口の不動産店(D店)の店主によると、「来店する客の7割が外国人で、圧倒的多数は中国人であるがベトナム人やネパール人居住者が増加している」という。つまり、チャイナタウン化の進展がほかのエスニック・グループの集住を促したということである。ここまで示してきた表1や図2などからも、西川口を含む川口市において多文化化が進んでいることがうかがえるが、日本においてチャイナタウンのマルチエスニック化はこれまで確認されていない新たな現象であるため、西川口における多文化共生の実態についても論じる必要があるだろう。文量の制限もあるため、詳細は別稿に記すこととする。6.おわりに
本稿では、日本における新しいチャイナタウンである西川口チャイナタウンの形成要因と地域社会経済への影響について、現地での聞き取り調査で得られた知見をもとに、公的統計データを用いて解明を試みた。その結果、西川口チャイナタウンの形成は、西川口が性風俗街であったことによるネガティブなイメージが影響し、都心へのアクセスが良いにもかかわらず比較的家賃・地価が安い地域であったという経済的な要因に加え、政治、社会、文化といった複合的な要因によって生じたことが明らかとなった(図7参照)。また、本研究を通して、西川口は従来の日本において類を見ない、マルチエスニック化するチャイナタウンであることがわかった。渡戸一郎は東京圏を「多文化都市」と分類し、「多国籍・マルチエスニック化・多言語化が進展」していることを指摘したが、外国人労働力の受け入れ体制が強化されるなかそうした傾向は今後一層加速するだろう(渡戸,2006)(19)。本研究では新しいチャイナタウンという点に主眼を置いて研究を行ったが、西川口チャイナタウンが東京圏を代表する新しいエスニック・タウンであることを鑑みると、より多角的な視点から西川口地域を捉え直すことも重要となる。例えば、本稿では文量の制限で論じることはできなかったが、行政による多文化共生施策からチャイナタウン化、マルチエスニック化を検討することで、西川口をはじめとする新しいエスニック・タウンが抱える地域課題の解決につながるだろう。また、「多文化都市」としての東京の総体を捉えるためには、ベトナムやフィリピンなど、多様なエスニック・グループによる新しいエスニック・タウンの形成要因についても調査・分析が必要である。グローバル化や情報化の進展によって地域社会の再編成が進むなか、複雑性を回避するために捨象されやすい複合的な要因から目を背けずに対峙することこそが、深刻な少子高齢化と労働力不足に対応する、より効果的な政策実装の実現にも寄与するのではないだろうか。謝辞本稿は、国際公共経済学会第34回研究大会(於:高崎経済大学)での奨励賞報告を基に加筆修正したものである。本賞の受賞にあたり、審査委員の楠田昭二先生(早稲田大学)、森由美子先生(東海大学)、花田真一先生(弘前大学)およびフロアの方から貴重なコメントを頂戴した。また、匿名の査読者2名からも有益なコメントを頂戴した。この場を借りて御礼申し上げる。
脚注(1) 「外国人受け入れ5年で最大34万人 改正入管法が成立」『日本経済新聞』(2018年12 月 8日)(2019 年 9 月24日 閲 覧、https://www.nikkei.com/article/DGXMZO38705720Y8A201C1000000/).(2) 国籍別では、中国764,720人(総数の28.0%)、韓国449,634 人(同16.5%)、ベトナム330,835人(同12.1%)、フィリピン271,289人(同9.9%)、ブラジル201,865人(同7.4%)の順となっている[在留外国人統計]。(3) エスニック・タウンとは、異なる社会的・経済的条件を備えるホスト社会においてエスニック集団が適応戦略を採用した結果の産物を指す(矢ヶ崎,2008)。また、エスニック・タウンの三つの側面として、「エスニック集団の集中居住地域(人口的側面)」、「エスニック・ビジネスの中心地(経済的側面)」、エスニック集団の生活様式の維持・継承のための諸施設が集中している地区(社会・文化的側面)」があるという(山下,2008)。(4) 河畑悠の『東京のディープなアジア人街』(彩図社、2014年)や、室橋裕和の『日本の異国――在日外国人の知られざる日常』(晶文社、2019 年)など、新しいエスニック・タウンが形成されるたびに、個別のエスニック・タウンを対象としたルポタージュが出版されている。(5) 2017年9月18日に放送されたテレビ朝日の深夜バラエティ番組「EXD44」や、2018年1月5日に同じくテレビ朝日で放送された「タモリ倶楽部」等で西川口のチャイナタウン化が取り上げられ、一般の人々にも広く認知が広がったといわれている(高松,2019)。(6) 新華僑とは1980年代以降に主に留学や就学を目的として来日し、その後日本で職を得て定住するようになった中国人ニューカマーズを、老華僑とは1970年代以前に来日した中国人オールドタイマーズを指す(陳,2018)。(7) 1980年代から中国人人口が増加した要因としては、日本政府が1983年に開始した「留学生10 万人計画」により就学生の入国手続を簡素化したほか、中国政府が「私費留学生の出国に関する暫時規定」の公布(1984年)、「公民出境管理法」の施行(1986年)を行い、私的な理由による出国を認めるようになったことが指摘されている(伊藤,1995)。(8) その後、1973年に鋳物生産量がピーク(40万7千トン)に達したが、昭和60年代の円高不況の影響を受け、川口周辺の鋳物生産に関連する企業の多くが転廃業することとなった。しかし、現在でも約2万4千の事務所が立地する川口市は、日本のものづくりにおいて重要な役割を担っている地域である(佐藤,2013)。(9) 「『ほぼ東京』を自称する川口は一体何があるのか」『東洋経済ONLINE』(2019年4月21日)(2019 年10月9日閲覧、https://toyokeizai.net /articles/-/276388?page=3).
日本復讐のために、日本を打ち負かすために、反日韓国人、反日中国人の観光・男性客は日本女性を食って侮辱し帰っていく。そもそも強国になった国の特権らしい。ロシアが日本の植民地であった満州で日本人引揚者にたいして、中国人が日本人引揚者に対してやった行為をまた再び行おうとしている。近い将来、中国のGDPが世界第1位になったら、国連も牛耳り放題、中国のやりたい放題になってしまう恐怖が起きつつある。2030年辺りからが本当に恐怖だ。韓国人も中国人もロシア人も、日本とは反対方向の、ほかに国へ観光に行ってくれ!
“沖縄の無人島を購入”中国人が動画投稿 ネットに“中国の領土”の意見 近くの島民は…
2023年2月13日
中国人女性が、沖縄にある無人島を“購入した”とする動画をSNSに投稿しました。島の一部を所有する村の村民からは自然豊かな島が今後、どうなるのかを心配する声が聞かれます。村によると、島の民有地を購入したのは女性個人ではなく、東京・港区にある会社だといいます。
中国人女性が今月、SNSに投稿した動画で紹介したのは、透き通った海に生い茂った木々と、豊かな自然に囲まれた“無人島”です。中国メディアによると、動画を投稿した女性は山東省出身の34歳で、彼女の家は不動産業と金融業を営んでいるとしています。女性は動画の中で、“この島を3年前に購入した”と説明しています。
この島は沖縄県にある離島「屋那覇島」です。近くの島民は不安を口にしています。
島民「みんなが本当にどうなるか、心配している」
“美しい景色を共有するため投稿した”ということですが、その意図に反して中国のSNSでは一部で、「中国の領土にできますね」、「中国軍が行くには便利な場所ですか?」といった過激な意見もみられました。
◇
今回話題となっている屋那覇島は、沖縄本島の北にある人口1300人余りの伊是名村にあり、東京ドーム約16個分の無人島です。
13日、日本テレビはその屋那覇島に向かいました。
記者
「フェリーの前方に伊是名島が見えてきました。その左手手前に見えるのが無人島、屋那覇島です」
上陸したのは、伊是名村が現在も所有している屋那覇島の砂浜です。
記者
「長い砂浜、そして透明な海が広がっています。人影はありません」
漂着物はあったものの、人の姿は見られませんでした。伊是名村の観光協会によると、島に電気やガスは通っていないといいます。
伊是名村によると、競売にかけられた島の民有地を購入したのは動画の女性個人ではなく、東京・港区にある会社です。現在、島の半分以上の土地を所有しているといいます。
その会社のホームページには、「令和3年2月 沖縄県の屋那覇島を取得」という記載がありました。動画を投稿した中国人女性との関連は分かっていませんが、ホームページによると、リゾート開発や中国でビジネスを行っているといいます。日本テレビはこの会社に取材を申し込んでいますが、13日午後6時時点で回答は得られていません。
◇
伊是名村の住民からは、不安の声が聞かれました。
村民
「拝所もあるところなので。聖地としてみんな見ているところもあるので、ぜひ何も手をつけないでほしい」
“日本の無人島を購入した”と主張する女性について、中国の首都・北京でも聞いてみました。
北京市民
「例えば、外国人が中国の島を合法的に買っても特に何とも思いません。当たり前のことでしょう」
屋那覇島を巡る状況に、松野官房長官は2023年2月13日、「日本政府としてはこの関連動向について法律には違反していないものの、注視していきます」と発言。日本の固有の領土を中国に買われ続けながら、この先も動向を注視していくとしています。領土に関しても相互契約は無く、中国の法律には日本から中国の領地は購入できないが、日本の法律ではどの国も日本の領地は購入できる、となっています。これが現在の日本政府の国家安全保障のレベルです。
まるで水を飲むように日本で住宅を買う中国人―中国メディア
2023年10月24日
中国オンラインメディアの華爾街見聞に2023年10月23日、「まるで水を飲むように日本で住宅を買う中国人」とする記事が掲載された。
記事はまず、「中国の富裕層の資産配分はますます多様化しており、現在最も人気のある戦略は日本で住宅を購入することだ」とし、「報道によると、中国国内の不動産市場が冷え込む中、大勢の中国人が、住宅を購入するため、日本、特に北海道のニセコや大阪の道頓堀などに向かい始めている」と報じた。
記事によると、大阪のある不動産業者は取材に対し、「中国人は、安価な車や他の物を買うのと同じように、気軽に日本で住宅を購入する」と話しているという。北海道だけでなく、大阪や京都など関西圏の住宅にもチャイナマネーが流入している。中国人購入者は特に日本人が購入したがらない地域にある低価格物件の購入に熱心で、ある地域では、約2000万円からの値段で売りに出されている小さな一戸建てやマンションが中国人によって買い占められているという。
記事はまた、日本の円安と目覚ましい景気回復により、中国人だけでなく、シンガポール、米国、カナダ、香港などの投資家が日本の不動産市場に戻りつつあるとも伝えている。
記事が英不動産大手ナイト・フランクの報告書を引用して伝えたところによると、2023年、今年1~9月の日本の不動産への海外からの投資額は、シンガポールが約30億ドル(約4500億円)でトップで、米国(約25億ドル)、カナダ(約10億ドル)が続き、5位に香港(約7億5000万ドル)が入った。(翻訳・編集/柳川)
中国、英議会調査担当者のスパイ容疑「でっち上げ」 2023年9月11日
中国外務省の毛寧(もう・ねい)報道官
【北京=三塚聖平】中国外務省の毛寧(もう・ねい)報道官は2023年9月11日の記者会見で、ロンドン警視庁が中国のためにスパイ活動をした疑いで英議会の調査担当者ら2人の男を逮捕していたとされることについて「中国が英国にスパイ活動を行っているという見解は全くの英国のでっち上げ だ。断固として反対する」と反発した。
中国外務省の毛氏は、英国側に対し「虚偽の情報をまき散らすことや、反中国の政治的な操作、悪意のある中傷をやめるよう強く促す」と求めた。
李強首相は2023年9月10日、20カ国・地域首脳会議(G20サミット)に合わせてスナク英首相と会談した。毛氏は、同会談で「両国関係や、ともに関心を持つ議題について意見交換を行った」と述べ、英国議会の調査担当者ら2人の男が逮捕された問題が取り上げられたことを示唆した。毛氏は、英国側に「政治的な宣伝、偽報道をやめ、相互尊重を堅持」することなどにより「中英関係の発展を推進」することを呼び掛けた。
あなたは、「何が面白いの?」
トム・トゥーゲンハット安全保障相やアリシア・カーンズ下院外務委員長を含む
数人の与党・保守党議員とつながりがあったという。
調査員は英国人で議会に出入りできるパスを持ち、
数年にわたり北京との関係を含む国際政策について議員と協力してきた。
・
この調査員は以前、中国に滞在し仕事をしていたが、
英治安当局は潜伏工作員としてリクルートされ、
「北京政権に批判的な政治ネットワークに潜入する目的で
英国に送り込まれたのではないかと懸念している」と同紙は伝えている。
・
この調査員はトゥーゲンハット氏が安全保障相に就任する前、
保守党議員の中国研究グループを主宰していたころから接触していたという。
カーンズ氏は英BBC放送に 「私は公共の利益を認識しており、
当局の仕事が危険にさらされないようにする義務がある」と話した。
・
2022年、昨年1月、英情報局保安部( MI5)が英下院議長を通じ、
ロンドンを拠点に活動する中国人弁護士クリスティン・リーが
中国共産党中央統一戦線工作部(中央統戦部)の意向を受け下院議員に近づき
影響力を行使していると全下院議員に対し異例の警告を行ったことがある。
・
中央統戦部は中国共産党の主張を広げる一方で、
中国共産党の政策に敵対する勢力に対抗するため、虚偽や賄賂、脅しなど
硬軟織り交ぜた方法で相手国の政治家や有力者に近づいて親密な関係を構築、
手なづけた協力者に中国共産党の主張に沿った言動をさせる部局 だ。
・
日米欧議員らが中国の人権弾圧を監視する「対中政策に関する列国議会連盟」設立
を主導し、中国の制裁リストに加えられた英国の対中最強硬派
イアン・ダンカン・スミス元保守党党首はX(旧ツイッター)にこう投稿した。
「もし事実なら、これは非常に深刻であり、大きな懸念である。
中国共産党が英議会の機能と私たちの民主的な生活様式にもたらす脅威について
私たちが自己満足している余裕はないことを示している」
(イアン・ダンカン・スミス氏)
死せる李克強、絶対権力者・習近平をビビらせる
2023年10月
死せる李克強、絶対権力者・習近平をビビらせる
「死せる孔明、生ける仲達を走らす」
中国・三国時代の有名な故事である。蜀の諸葛孔明が陣中で病死し、それを察知した魏の将軍・司馬仲達が蜀軍に攻め入ったところ、蜀が反撃の構えを見せたため、仲達は孔明が死んだと見せかけた罠だと思い込み、あわてて退却した。つまり、生前の威光が死後にも残っており、人々を震え上がらせるという例えである。
李克強前首相の死から半月を経て、習近平主席が彼の死に怯えている様子は、まるで「死せる孔明、生ける仲達を走らす」のようだ。
李克強前首相急死の一報が中国中央電視台(CCTV)で伝えられたのは、死亡した翌日。中国時間の2023年10月27日午前8時の定時ニュースだった。
李氏はこの3月末まで10年間にわたって、国務院総理を務めた国家最高級の地位にあった人物である。本来なら、ニュースの時間を大きく割き李氏の功績を振り返るところだが、アナウンサーは「李氏は首相退任後も習近平同志を核心とする党中央の指導を支持した」という文言を繰り返した。
共産党機関紙「人民日報」でも、李氏の精神を受け継ぐために「習近平同志を核心とする党中央を中心に団結せよ」と、追悼の記事がことごとく習氏に忖度する内容となっていた。
これに庶民は反発し、李氏の故郷や李氏にゆかりのある中国各地で、多くの人が献花するなど追悼の動きが広がった。だが、その動きが大きくなると、李氏を悼むネット上の画像は瞬く間に削除された。
SNSにはマレーシア出身の人気歌手のヒット曲「あなたでなくて残念」の歌詞がアップされたが、これもすぐに削除された。亡くなったのが李氏ではなく「あなたならよかった」と、庶民が習氏を腹の底から嫌っていることに政府が恐れを感じたからに他ならない。
それにしても、絶対権力者に上りつめた習近平主席が、無役になった李氏の「死」で何を恐れたのだろうか。
2013年に首相就任した当初、李氏は貿易や投資で民間経済の活力を引き出す経済政策、いわゆる「リコノミクス」を推し進め国際的にも評価された。だが、習氏に権限を奪われ2人の関係は冷え込んだ。2016年の全国人民代表大会では、習氏が李氏の報告に拍手せず、会話せず、握手せずの完全無視を貫いたほどだ。
2021年の共産党創立100周年式典で習氏は、絶対的貧困を撲滅し「小康社会(少しゆとりある社会)を実現した」と宣言したが、その前年、李氏は「中国には月収1000元(約2万円)に満たない人が6億人いる」と発言して習氏のメンツを潰している。
各国メデイアは李氏の死が、胡耀邦元総書記の追悼集会が引き金となって起きた天安門事件の二の舞になることを恐れているなどと伝えているが、“一人独裁”を実現した習氏の「恐れ」は、もはや次元の違うところにあるのではないだろうか。
それは、明王朝の最後の皇帝となった「崇禎帝」の立場である。崇禎帝は女におぼれ政治をないがしろにした先代と違い、国家発展のために政治に真正面から取り組み、緩んだ体制を立て直す努力を続けた。ところが臣下を信用せず、重臣を次々に暗殺。結局重臣の心が離れ、自死に追い込まれる。
「トラもハエも叩く」と、政敵を反腐敗闘争の名の下に約465万人も有罪に追いやり、自ら任命した秦剛外相や李尚福国防相を更迭。さらにナンバー2の李強首相をも外したと伝えられる習氏の現状は、まさに「崇禎帝」そのものなのである。
イタリア外相「期待した成果ない」
中国の巨大経済圏構想「一帯一路」離脱検討
TBS
イタリアの外相は2023年9月2日、参加する中国の巨大経済圏構想「一帯一路(債務の罠外交)」について、
離脱 を検討していることを改めて明らかにした。
イタリアのタヤーニ外相は2023年9月2日、北部・チェルノッビオで開かれた経済フォーラムに参加し、
中国の巨大経済圏構想「一帯一路(債務の罠外交)」について「期待した成果をもたらさなかった」
「われわれは改めて評価をし、議会は参加を続けるかどうかを決断しなければならない」
と述べた。
タヤーニ外相は2023年9月3日から3日間の日程で中国を訪問する予定で、一帯一路(債務の罠外交)についても
議論するものとみられる。
イタリアは2019年、EU懐疑派のコンテ政権がG7=主要7か国として唯一、
一帯一路(債務の罠外交)への協力の覚書を結んだが、その後、経済的な恩恵が乏しいと国内で不満が高まっていた。
覚書の期限は来年3月で、メローニ政権は年内に離脱の是非について結論を出す考え。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●G7の中で、唯一イタリアが一帯一路(債務の罠外交)の参加国。イタリアが離脱したら、
中国は、イタリアの港に関する利益を失うだけではなく、政治的に大きな打撃となる。
G7広島サミットの前に、メローニ伊首相は、マッカーシー米下院議長に、
ローマは一帯一路離脱の意向を持っているが、中国からの経済的反発を抑えるため、
決定の詳細と時期をまだ「検討中」と伝えたと報道。
2023年5月に行われた広島サミットでは、中国を念頭に置いた
「経済的威圧に対する調整プラットフォーム」を新たに立ち上げた。
タイヤーニ伊外相・副首相は、EUの欧州議会の議長だった人物。
EUは、将来EUに加盟するかもしれないバルカンの国々が陥った中国の債務の罠 を重視、
一帯一路(債務の罠外交)への反発がある。バルカンはイタリアの近隣地域。伊の敏感度と危機感は高い。
先進7か国(G7)で唯一、中国の巨大経済圏構想「一帯一路(債務の罠外交)」に参加しているイタリアが、離脱を検討している。覇権主義的な動きを見せる中国 への警戒感に加え、経済的な恩恵が乏しいことへの不満が高まっており、2023年度年内に結論が出る見通しだ。(イタリア北西部ジェノバ 倉茂由美子、写真も)
[ローマ 2023年9月10日 ロイター] - イタリアのメローニ首相は2023年9月10日、中国が掲げる巨大経済圏構想「一帯一路」について、イタリアとしてはそれよりも中国との関係自体を強固にすることが大事だと述べたが、一帯一路から離脱するかどうか最終決定はこれからになると付け加えた。
イタリアの各メディアは、同国が一帯一路(債務の罠外交)を離脱した上で、2004年に中国と最初に調印した経済関係促進のための戦略的パートナーシップ協定を再活用する意向だと伝えている。
主要7カ国(G7)のうち、一帯一路に参画しているのはイタリアのみ。G7は中国の影響力が強まるのを警戒し、中国関連リスクの低減を目指そうとしており、来年議長国を務めるイタリアがこれまでの中国とのつながりを見直せば、G7の足並みがそろいやすくなる。
メローニ氏は20カ国・地域(G20)首脳会議終了後の会見で「近年は複数の欧州諸国が一帯一路(債務の罠外交)に入らずに(中国との)関係を、われわれが何とか構築してきたよりもっと好ましい方向に発展させることができている」と述べた。
またG20首脳会議の傍ら、中国の李強首相と行った会談に関しては「話題は両国のためになるパートナーシップ(協定)をどう確保していくか」で、一帯一路(債務の罠外交)を巡るイタリアの判断は話し合われなかったと明らかにした。
中国外務省報道官は2023年9月11日の定例記者会見で、イタリアの離脱検討について質問された際、中国は一帯一路(債務の罠外交)の下で可能性のある協力をさらに推し進めることが各国の利益になると常に考えていると述べた。
これまでのところ、中国は公にイタリアに残留を迫っておらず、2国間関係に焦点を当てている。
報道官は「中国とイタリアはさまざまな分野で実務的な協力をさらに深め、包括的戦略パートナーシップのさらなる発展を促進すべきと考えている」と語った。
メローニ
「一帯一路 (債務の罠外交) 」提唱10年 イタリアは離脱含み 中国が引き留めはかる!ただで済ませることはできない!
北京で2023年9月4日、中国の王毅・共産党政治局員兼外相と会談するイタリアのタヤーニ副首相兼外相=AP
[PR]
提唱から10年を迎えた中国の巨大経済圏構想「一帯一路(債務の罠外交)」をめぐり、主要7カ国(G7)唯一の参加国だったイタリアが離脱を検討している。経済効果が乏しいことへの不満が高まっており、メローニ政権が年内にも離脱を表明する可能性が高まっている。2023年9月4日に北京で行われた両国の外相会談では、中国側が引き留めをはかった。
イタリアは不満、中国は実績強調
グローバルサウスは「中ロ排除狙う欧米の戦略だ」 中国識者の警戒感
イタリアのANSA通信などによると、タヤーニ外相は訪中前の2日、伊北部で開かれた会合で、「一帯一路は期待した成果をもたらさなかった。議会は参加を続けるか否か決めなければならない」と述べ、2024年、来年3月の更新期限を前に一帯一路からの離脱を検討していることを明らかにした。
イタリア側が「期待外れ」と不満を募らせるのは、構想に参加後も対中輸出が伸びなかったためだ。欧州連合(EU)の統計によると、2022年、昨年の中国からの輸入額は575億ユーロ(約9兆1千億円)に上るのに対し、2023年のイタリアから中国への輸出額は164億ユーロ(約2兆6千億円)にとどまり、巨額の貿易赤字を抱える。
中国、引き留めに躍起 「実り多い」
非公表の協議内容だとして匿名を要請した関係者によると、米国はイタリアに対し、この問題を巡る姿勢を公にし、一帯一路から離脱するよう積極的に働き掛けている。
メローニ首相の外交顧問らは中国の経済的な報復を恐れて決定の詳細や時期について依然議論を続けており、19日に広島で始まるG7首脳会議以前に発表がある公算は小さいだろうと、関係者は述べた。
イタリアの「一帯一路 (債務の罠外交) 」参加が示す2つの意味 好機を手にする中国
Apr 9 2019
EUの首脳は後年、「だまされた感があった。」と発言。
中国の習近平主席は2019年3月下旬、イタリア・ローマを訪問し、コンテ首相と会談した。その際、両者は一帯一路構想に関する覚書を交わし、イタリアが一帯一路に参加することが明らかとなった。近年、中国が進める一帯一路構想に参加する国々は増加しているが、今回のイタリアの参加表明はこれまでとは少し意味が違う。イタリアの一帯一路参加は、少なくとも2つの意味がある。
◆EU13ヶ国目となるイタリア
EU加盟国28ヶ国のうち、すでにギリシャやポルトガル、クロアチアやポーランド、チェコなど12ヶ国が中国との間で同覚書を交わしているが、イタリアはEUでは13番目の国となった。イタリアは欧州でも若者の失業率が高く、長年国内経済が低迷している。コンテ首相としては、これを機に国内経済を再生したいという狙いがあり、今後、イタリア北部の湾岸施設の建設、再開発などを中国企業が主導していくことになる。
一方、イタリアの参加によって、中国は地中海貿易の活性化という意味で大きな可能性を得た。上述の通り、ポルトガルとクロアチア、ギリシャはすでに一帯一路構想に参加しているが、スエズ運河と大西洋のほぼ中間に位置する海洋国家イタリアを得たことは極めて価値がある。また、北アフリカのアルジェリアも2018年9月に同構想への参加を表明しており、北アフリカのすぐ先に位置するイタリアの獲得を北京主導者たちも満足しているに違いない。
◆G7の切り崩しを狙う中国
また、イタリアの一帯一路参加はもう一つの重要な意味を持つ。周知のとおり、G7とは米国と日本、カナダ、英国、フランス、ドイツ、イタリアの先進7ヶ国が参加する政治集合体で、戦後の世界経済を主導してきた。よって、21世紀以降、世界経済で影響力を高める中国からすると、G7の1ヶ国を自らの経済ルールに参加させることに漕ぎ着け、また、G7の領域に初めてメスを入れることに成功したという意味で、イタリアの参加は大きな意味を持つ。国際政治的にも大きな出来事である。今後、あからさまには表明しないまでも、“無言で”G7の切り崩しにかかってくるかもしれない。
仮にそうであれば、おそらく英国、フランス、ドイツが次の標的になるだろう。トランプ政権の誕生以降、米国とフランス・ドイツの関係は最悪レベルに冷え込み、英国はブレグジットで余裕がない。今日、EUもG7もそれぞれ内部に内戦たるものを抱えており、中国にとっては欧米先進国の主要な政治的枠組みを切り崩して行くチャンスでもある。
近年、北京自身も一帯一路構想の実施拡大によって、各地域や各国から抵抗と反発の声が顕著に出ているのは十分に承知のはずだ。しかし、だからといって中国が経済支援を停止することはなく、中国の影響力拡大を続けることだろう。
イタリアの一帯一路参加について、当然ながら、G7の国々からは懸念の声が出ている。しかし、今日、G7の影響力は以前より相対的に低下しており、G20や上海協力機構、ブリックス(BRICs)など新興国を取り込んだ政治的枠組みが影響力を増している。G7が一帯一路構想によってさらに切り崩されていくならば、米国や日本にとってどんな影響が出てくるのだろうか。フランスやドイツも、現在の米国との関係も影響してか、対中国では難しい舵取りを余儀なくされている。日本にとっても、決して対岸の火事ではない。
要警戒!世界を中国化する「一帯一路」の危ない誘い
取り込まれるイタリア、「中国式植民地主義」は息を吹き返すのか
2019.3.14(木)
(福島 香織:ジャーナリスト)
中国の一帯一路戦略は、昨年(2018年)頓挫しかけていた。エチオピア~ジブチ鉄道は棚上げとなり、マレーシア~シンガポール間高速鉄道プロジェクトは中止、パキスタンの政権交代に伴う一帯一路事業の見直しなどが続いた。また欧米諸国から、返済見込みのない事業に多額の融資をして相手国を借金漬けにして支配するやり方を「債務の罠」「中国式植民地主義」などと非難されてイメージも地に落ちていた。だが今年に入って、ひょっとすると一帯一路は息を吹き返すのか、と思わせる動きが出てきている。
1つはすでに日本でもニュースになっているイタリアの一帯一路への正式参加表明である。3月下旬に習近平がイタリアを訪問した際に、イタリアのジュゼッペ・コンテ首相と一帯一路参加に関する覚書を交わすことになっている。G7としては初の正式な「一帯一路」参加に、中国は急に自信を見せ始めた。昨年秋の安倍晋三首相訪中時に「第三国市場での日中協力」という名目で日本が一帯一路への支持姿勢を見せたことも追い風になっている。
加えて、なにより世界銀行が一帯一路のプロジェクト効果として、参加国の貿易を3.6%増やし、世界貿易全体も2.4%増加させたとポジティブに評価していることも大きい。コロンビア大学政治国際関係研究所のある研究者は、一帯一路について「中国は世界秩序の再構築プロセスの重要な要素」とまで語っているようで、中国の参考消息などが喜々としてこれを転載して報じている。
中国との接し方を巡って足並みが乱れるEU
イタリアが中国の思惑に気づいているかは別として、イタリアの国内事情はスキがあった。イタリアの左右ポピュリスト連立政権の内部で、鉄道プロジェクトをめぐる非常に厳しい対立があり、また財政赤字はEU規則の上限を上回りそうになっている。イタリアにしてみれば、大盤振る舞いを約束してくれる中国にすがりたいところだろう。
だが、中国の一帯一路戦略については、米国やEU諸国の間には依然、不信感が根強い。米国家安全保障委員会(NSC)のマーキス報道官は「フィナンシャル・タイムズ」に対し、「イタリア政府の(一帯一路への)支持がイタリア国民に持続的な恩恵をもたらすとは思えない。長期的にはイタリアの国際的信用を傷つける結果になりうる」(カッコ内は筆者)と脅しにも似たコメントを出している。
イタリア 「一帯一路」脱退を中国に正式通告
2023年12月7日
イタリア 「一帯一路」脱退を中国に正式通告
© FNNプライムオンライン
イタリアが、中国の巨大経済圏構想「一帯一路」からの離脱を中国側に通知していたことがわかった。
イタリアの主要紙コリエレ・デラ・セラは2023年12月6日、イタリアが中国の「一帯一路」から離脱することを、3日前に中国側に通知したと報じた。
政治的に好ましくない影響が多く大きな経済効果が見込めないことから、メローニ政権が離脱を決め、数週間にわたって中国側と協議してきたという。
イタリアは2019年3月に、当時のコンテ首相がアメリカの反対を押し切って覚書を交わし、G7(主要7カ国)として唯一「一帯一路」に参画していた。
イタリアと中国は友好関係を維持することを確認したとしているが、離脱は中国にとって痛手となるとみられる。
イタリア、中国の「一帯一路」構想から離脱へ…経済的恩恵乏しくメローニ政権が検討
2023年12月7日
【ローマ=倉茂由美子】イタリア紙コリエレ・デラ・セラなど複数のメディアは2023年12月6日、先進7か国(G7)で唯一イタリアが参加している中国の巨大経済圏構想「一帯一路」について、イタリア政府が離脱の意向を中国側に伝達したと報じた。
報道によると、イタリア外務省が数日前に在イタリア中国大使館へ書簡で伝えた。来年3月に5年の期限を迎える合意を更新しない意向とともに「2国間協力の発展と強化」への意欲が記されたという。伊政府は地元メディアの取材に「ノーコメント」としている。
イタリアは2019年3月、欧州連合(EU)懐疑派だった当時のコンテ政権 が、中国の巨額投資を財政難解消の足がかりにすることを狙い参加を決めた。だが、自国への経済的恩恵が乏しいことなどから、中国に厳しい姿勢をとるメローニ政権は離脱を検討し、年内に結論を出すとしていた。
中国急接近、「債務のわな」に懸念 モルディブ元大統領
2023年9月30日
民主化運動指導者で国会議長のナシード元大統領(56)
【マレ共同】インド洋の島国モルディブで2023年9月30日に大統領選の決選投票が行われるのを前に、民主化運動指導者で国会議長のナシード元大統領(56)が共同通信の単独会見に応じた。中国寄りの野党候補ムイズ氏(45)が勝てば脱インドの外交政策を進めるとみられ、ナシード氏は中国が融資で途上国を借金漬けにして支配を強める「債務のわな」に「十分注意すべきだ」と懸念した。
ナシード氏は民主主義や人権といった価値観を共有する日本やインドとの関係維持が重要だとして「外交政策の急激な変更は誰の利益にもならない」と訴えた。特にインドは近隣国でもあり「敵対視するべきではない」と強調した。
日本は本当に「一帯一路」で中国と徹底的に関係を断つのか―仏メディア
Record China による
2023年10月28日
仏RFI(中国語電子版)に2023年10月25日、日本は本当に「一帯一路」で中国と徹底的に関係を断つのかとする論評が掲載された。
仏RFI(中国語電子版)に2023年10月25日、日本は本当に「一帯一路」で中国と徹底的に関係を断つのかとする論評が掲載された。
論評によると、中国の習近平(シー・ジンピン)国家主席が巨大経済圏構想「一帯一路」を提唱してから10年を迎え、2023年10月17日から18日まで北京で第3回「一帯一路」国際協力サミットフォーラムが開催された。
サミットフォーラムは、2017年5月に第1回、その約2年後の19年4月に第2回が開催されている。
サミットフォーラムについて、中国は隔年での常態化を準備していたが、新型コロナウイルス感染症が流行。2021年6月、最も厳しい防疫措置の時期にあった中国は、対面での国際会議やイベントを開催せず、代わりにリモートビデオによるバーチャル「一帯一路」サミットの開催を選択した。そのため、今回のサミットフォーラムは第3回と位置付けられた。
しかし、過去2回のサミットフォーラムとは対照的に、日本の当局者は今回、ほとんど参加しなかった。日本は本当に「一帯一路」で中国と徹底的に関係を断つのだろうか。
今月13日、「一帯一路」提唱10周年を記念する国際シンポジウムが東京で開催された。中国の呉江浩(ウー・ジアンハオ)駐日中国大使は基調演説で、「一帯一路」について「中国の提唱から世界での実践へと歩みを進め、世界で最も広範囲に及び、最も規模が大きい国際協力プラットフォームとなった。今回、日本でのシンポジウムの開催は重要な意味がある」と指摘。「中日両国は隣国であり、互いに協力パートナーであり、経済的に緊密な関係を築いている。両国は地域および世界の発展に重要な影響を与え、第三国市場での協力においては将来性がある。日本企業は積極的に国際定期貨物列車『中欧班列』と河川輸送と海上輸送を結び付けた『江海聯運』を活用し、ビジネスチャンスを開拓している」と述べた。
日本は今回のサミットフォーラムに対して非常に冷淡な態度を示しているが、鳩山由紀夫元首相は2023年10月20日夜、X(旧ツイッター)を更新し、コロナ禍を経て久々に開催された「一帯一路」の国際会議に参加したことを報告し、「日中間の対話」の必要性を説いた。
鳩山氏は会議に出席した習主席の笑顔や自身が演説する写真を添付し、「4年ぶりに開かれた一帯一路フォーラムに参加してきた。二階先生(二階俊博・自民党元幹事長)がご体調を崩され参加されなかったので、日本からは私一人の参加となった」と投稿した。
論評は「こうしたことから、今回のサミットフォーラムに対する日本の冷淡さをうかがい知ることができる。日本政府・与党の要人は出席せず、出席したのは鳩山元首相だけ。鳩山氏は民主党政権の元首相で、退任後は一貫して政権に反対の立場を取ってきた。サミットフォーラムへの参加は、公式に任命されて派遣されたわけではなく、個人としての行動にすぎない」とした。
論評は、「一帯一路」に賛同していた唯一のG7加盟国であるイタリアが離脱の意思を示したことに言及。「日本は、『第三国のインフラ整備分野での日中協力』という主張の下で覆い隠された中国との『一帯一路』での協力から徐々に離脱するのか、『一帯一路』で中国と徹底的に関係を断つのか、関係を断つとしたらどのように、という点が大いに注目されている」とした。 (翻訳・編集/柳川)
モルディブで中国VSインドの代理戦争?次期大統領が“中国寄り”に 「中国はインドの裏庭に入り込み利益を上げた」印メディア
2023年10月28日
リゾート地として知られるインド洋の島国モルディブ。実は中国とインドが激しい勢力争いを繰り広げています。
インド洋に浮かぶ島国モルディブ。主力の観光業で発展してきましたが、近年は海外からの投資を軸にインフラ開発などを進め、経済成長を続けています。それを大きく支えてきたのが…
記者
「こちらの橋のゲートには左側にモルディブの公用語、右側に中国語で文字が書かれています。両国の友好関係を象徴する橋だということです」
中国による経済支援です。モルディブは10年前、中国の巨大経済圏構想「一帯一路」に賛同。中国の支援を受けながらインフラや住宅の整備などを進めています。
市民
「私たちの生活は(中国の)インフラ開発で助けられました。島と空港が橋によって結ばれたからです」
「(中国の支援は)モルディブの発展にとって本当に良いことです」
中国には港湾を利用する権利を確保したい思惑があるとみられているほか、シーレーン=海上交通路の要衝にあるモルディブへの関与を強めることで軍事拠点化を進めたいのでは、との指摘もあります。
一方、こうした動きを警戒するのが真北に位置するインド。2018年にインドとの関係を重視する政権が誕生すると、中国に対抗した低利融資を行い、開発を支援してきました。さらに…
記者
「私の後ろには島が見えまして、建設工事が進んでいるのが分かります」
インドは今年5月からモルディブの海軍施設の改築工事を請け負っていて、現地メディアは将来的にインド軍の基地がつくられる可能性もあるとしています。2つの“大国”が影響力を競う中、モルディブでは先月末に大統領選挙が。
野党統一候補 モハメド・ムイズ氏
「モルディブに駐留している外国の軍隊を法律に従って送り返します」
インド軍の撤退を訴えていた中国寄りの野党候補ムイズ氏が接戦の末、勝利しました。
アメリカ・ブルームバーグ通信とのインタビューでムイズ次期大統領は「駐留するインド軍を撤退させる交渉を開始した」としたうえで、代わりに他の軍も駐留させないと説明しているということです。
インドメディアは「中国はインドの裏庭に入り込み、着実に利益を上げてきた」と指摘しています。ただ、中国からの借り入れが国の借金の4割を超える中で中国の投資が再び加速すれば、インフラが“差し押さえ”される、いわゆる「債務の罠」を懸念する声も。
市民
「インフレ率が高く政府はローンを支払うのも困難です。新しい大統領が適切な決断をしなければ、私たちは生き残れない」
インド太平洋の将来に大きく影響するモルディブの今後の外交が注目されます。
中国不動産開発の華南城が警告、20日期限のドル建て債利払いできず
2023年12月18日
最後は人民を犠牲にして生き残るだろう
中国全体での1京円の借金どう返済するのだ・・・
: 中国恒大の清算審理を裁判所が延期、債権者の関係者「やや驚き」
(ブルームバーグ): 中国南部・広東省深圳市の政府系企業が一部出資する不動産開発大手、華南城控股は2023年12月18日、2024年7月償還ドル建て債(表面利率9%)の利払いについて、猶予期限の今月20日までに履行できないとの見通しを示した。複数のドル建て債の償還延長に向け、債権者からの支持取り付けも急ぐ華南城にとって、初のデフォルト(債務不履行)リスクが高まりつつある。
華南城は上場先の香港取引所への届け出で、事業環境悪化に伴う流動性とキャッシュフローの制約を受け、20日までに利払いを実行する財源はないと明らかにした。
華南城は24年に償還を迎えるドル建て債5本について、償還延長と金利引き下げを目指す同社の要請に対し、元本残高の69.8%に相当する保有者が賛成したと説明。5本のいずれについても元本残高の75%以上の賛成が必要だが、それにはなお届いていない。
中国当局は最近、相次ぐデフォルトを食い止める方針を示しており、資金繰り難の不動産企業に対する当局の支援を試すことになる。国営中央テレビ(CCTV)が今月報じたところでは、住宅都市農村建設省の董建国次官は「不動産開発企業が集中して債務不履行に陥ることを断固阻止する」と言明した。
深圳市特区建設発展集団は22年5月に29%分の華南城株を取得し、単独では最大の株主となっている。華南城は中国の不動産セクターで早くから政府系の支援を受けた一角だ。
原題:China South City Warns Can’t Pay Bond Interest Due Wednesday (1)(抜粋)
More stories like this are available on bloomberg.com
©2023 Bloomberg L.P.
[2023年12月15日 ロイター] - 経営再建中の中国不動産開発大手、中国恒大集団は15日、外貨建て債務227億ドルの再編案の実行を支援する3件の合意(RSA=再建支援合意)について、期限切れとなり延長されなかったと発表した。
恒大は4月に、特定の債券保有者グループとこれらの合意を結んでいた。
外貨建てを含め3000億ドル超の負債を抱える恒大は、清算申し立てに関する審理が来年2024年1月29日に延期され、外貨建て債務についても、新たな再編案をまとめる時間的猶予を与えられた格好になっていた。
恒大は、再編に関して合意可能な条件に達するため、引き続き出資者との協議に関わると述べた。
中国依存のAppleにさらなる逆風、中国政府が「iPhoneやSamsungスマホなどの外国製デバイスは禁止」と政府機関や国有企業に命令
2023年12月18日
中国政府が、国内の複数の政府機関や国有企業の労働者に対し、外国製のスマートフォンを職場に持ち込むことを禁止したことがわかったと、海外メディアのBloombergが報じました。折しも、iPhoneが中国で最も売れているスマートフォンの座をHuaweiに奪われたことが報道されたばかりであり、需給の両面で中国に依存しているAppleにとっては一段と厳しい試練になると指摘されています。 China’s Apple iPhone Ban Accelerates Across State Firms, Government - Bloomberg
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-12-15/china-s-apple-iphone-ban-accelerates-across-state-firms-government
Bloombergは2023年12月16日に、「ここ1~2カ月間に、経済的に発展している沿岸部を含む少なくとも8つの省にある複数の政府機関や国有企業が、従業員に国産ブランドのデバイスを持ち始めるよう指示を出したことが関係者の話からわかりました」と報じました。 2023年9月には、北京や天津などの少数の機関で同様に海外製品の排除が通達されており、今回の措置によりその対象が一段と拡大されたことになります。
中国が「iPhoneの利用禁止」を政府職員に通達したと報じられてAppleの株価が連日下落 - GIGAZINE
この指示は浙江省(せっこうしょう)、広東省(かんとんしょう)、江蘇省(こうそしょう)、安徽省(あんきしょう)、山西省北部、山東省、遼寧省(りょうねいしょう)、さらには世界最大のiPhone工場を擁する河北省の中部まで、少なくとも8つの省にまたがる都市で行われました。 指示を出している組織の正確な数は不明で、指示の程度も職場での使用禁止から完全な禁止までまちまちですが、この取り組みはアメリカのテクノロジーを自国から排除しようとしている中国政府の方針を劇的に加速させるものだと位置づけられています。 また、Bloombergはアメリカによる締め出しを受けて窮地に陥っていたHuaweiの
復調 と時期が重なることを指摘して、中国政府の強気な姿勢の背景には自国産業の持ち直しに対する自信があるのではないかとの見方を示しました。 Bloombergの独自調査のデータによると、iPhone 15の中国での売れ行きは前モデルより悪化しており、一部のアナリストは「減速の一因は中国製の先進的なプロセッサーが搭載されたHuaweiのスマートフォンが8月に
発売された から」と分析しています。中国の国営メディアはこれをアメリカの制裁に対する勝利と報じましたが、アメリカでは制裁違反を疑う声が上がっています。
Huaweiの「Mate 60 Pro」に韓国のSKハイニックス製メモリが搭載されていることが判明、半導体輸出規制の有効性に疑問符 - GIGAZINE
政府職員、国営企業(=共産党企業)でどれだけの職員が
AAPLのiPhoneを使っているのでしょうか?
やっぱりこれくらいやらないと情報が洩れるリスクを軽減できないって事なのかな。
日本も政治家役人公務員その関係で働く人は国産スマホと国産アプリしか使えないってことにしたら………
by
Web Summit 米中関係の亀裂が広がる一方、Appleは製造パートナーとして、また自社製品の市場として中国に大きく依存しており、Appleのティム・クックCEOは2023年初頭の訪中でこの関係を「共生」と呼んで称賛していました。 以下は、Appleが中国から得ている収益の推移を表すグラフで、2022年までの約10年で収益が3倍になっていることが示されています。
中国は今後も海外のテクノロジー依存からの脱却を続けると見られており、Bloombergは「AppleやSamsungにとっては大きな試練になります」と述べました。
米シンクタンク報告書「中国は10大戦略産業のうち7つで世界をリード」―香港メディア
2023年12月18日
中国は10大戦略産業のうち7つで世界をリードしているとする香港英字メディア、サウスチャイナ・モーニング・ポストの13日付記事を取り上げた。
記事によると、中国は先端産業への努力と投資が奏功し、コンピューターやエレクトロニクス、化学薬品、ベーシックメタル、自動車などの分野で世界の他の国々から市場シェアを獲得し続けている。
中国は20年時点で、ITIFの報告書が対象とする10産業のうち7つ(コンピューター、エレクトロニクス、化学薬品、機械および装置、自動車、ベーシックメタル、電装品)で世界最大の生産国となっている。一方、米国は医薬品、IT、情報技術サービス、その他の輸送分野で世界をリードする生産国だ。報告書は「世界の他の国々は医薬品、IT、情報技術サービスにおいて中国を上回ったものの、中国政府がバイオ医薬品と人工知能(AI)を発展の主要産業としてターゲットにしているため、その優位性は持続できない可能性がある」と述べている。
ITIFによると、中国は現在、ITIFのハミルトン指数における戦略的に重要な産業を支配している。ITIFのハミルトン指数は、20年の世界生産で10兆ドル以上を占めた先進的で戦略的に重要な10の産業の業績に基づいて40カ国をランク付けしたもの。
ITIFによると、20年の10産業の経済規模に基づく中国の生産量は世界平均より47%高く、米国の生産量は平均より13%低かった。ハミルトン指数の10産業における中国の市場シェアの急成長は、米国とG7の急速な低下を反映している。
ITIFは、米国について、半導体の国内生産を促進するCHIPS法を可決したものの、どの政党も同法の必要な資金を解放するために巨額の財政赤字に対処することを望んでいないため、そのような議題を実行し、全額資金を提供するという意志は比較的低いようだと指摘する。
中国の電気自動車(EV)への多額の投資の成果も出ており、自動車生産で世界のリーダーに位置している。
ITIFによると、米国は特に航空宇宙製造業における優位性により、「その他の輸送」カテゴリーで首位を維持し、20年の生産量は世界全体の34.5%を占めた。中国は、高速鉄道と海運の拡大が主な後押しとなり、20年の生産量は世界全体の15.1%を占めて2位だった。(翻訳・編集/柳川)
中国、ムーディーズの格付け見通し引き下げに「反論」するも説得力なし
2023年12月25日
中国、ムーディーズの格付け見通し引き下げに「反論」するも説得力なし
米格付け会社ムーディーズは、中国の信用問題が一段と深刻化しているとして、中国の国債格付け見通しを「安定的」から「ネガティブ(弱含み)」に引き下げた。また、国有銀行8行と22の地方政府の見通しも引き下げ、自治区や香港、マカオ、およびこれらの区内の地方自治体も同様となった。
奇妙なことに、ムーディーズは中国国債の総合的な信用格付けを、2017年以来据え置かれている「A1」のままとした。 それでも、これはお墨付きとは言い難い。ムーディーズの最高格付けであるAaaをすでに4ノッチ下回っている。
今回の見通し引き下げは一見大きな動きのように見えるが、中国がすでに困難な状況にあり、事態は良くなるどころかさらに悪化する可能性が高いことを認めたにすぎない。筆者はここ数カ月、記事で中国の金融と経済にのしかかっている大きな問題を挙げて分析してきた。
まずひとつは、中国の不動産開発がほぼ崩壊し、返済できるか疑わしい負債を中国の銀行やその他の金融機関に残したことだ。この巨額の負債に加えて、中国の地方政府が直面している大幅な債務超過もある。債務が膨らんだ主な理由は、中央政府のインフラ整備計画の資金を地方政府が拠出しなければならなかったからだが、その多くはインフラ整備しても十分な経済効果を生み出せなかった。
中国が進めてきた広域経済圏構想「一帯一路(BRI)」 の下で、中国から融資を受けた国々が借金を返せなくなったことも、中国の債務問題をさらに深刻なものにしている。同時に、中国の輸出減や全般的な景気減速により、損失の補てんはこれまで以上に難しくなっている。
ムーディーズの格下げは妥当なものだが、予想通り中国政府は反発した。 財政部は「失望」を表明し、中国経済は「すぐに立ち直れる」と主張。同部の広報担当者は、政府はすでに地方政府の債務問題に対処するための措置を講じており、経済成長を促すための追加の措置も取っていると指摘した。ただし、それぞれの取り組みについて具体的な説明はなかった。
財政部はまた、中国(中央政府)の債務残高は国内総生産(GDP)比で米国や日本より軽いと指摘することで、財政の強さを示唆した。中国が言う自国の債務は対GDP比77%であるのに対し、米国は123%、日本は264%だ。これらの数字について議論の余地はないが、ムーディーズなどの率直な分析の前に、財政部の指摘は問題をはぐらかしている。
中国政府はインフラ支出を地方政府に負わせることで、国の債務を低く抑えている。 さらに、中国の金融への負荷は、中央政府、地方政府、民間など、あらゆる種類の債務が原因だ。この文脈では、誰が負債を抱えているかは問題ではない。重要なのは、全債務が金融システムにかけている負荷であり、この点で、中国は米国や日本よりも相対的に大きな問題を抱えている。
ムーディーズはこの事実を明確に理解している。見通し引き下げの説明で、同社のアナリストらは公的債務と民間債務を区別したり、国と地方どちらの政府が最も大きな負債を抱えているかを示したりはせず、負債全体に適切に焦点を当てた。 負債の多くは、借入金を返済できるほど十分な利益を生まないプロジェクトに関連していた。
ムーディーズのアナリストは、このような疑わしい債務の一部でも不履行となれば、国有、民間を問わず、中国の金融機関が将来の経済成長に必要な継続的投資を支援する能力が、著しく制限されると判断した。特に、中国の輸出は減少し、経済は減速しているため、この問題は「中国の財政、経済、金融機関に広範な下振れリスク」をもたらすとアナリストらは結論づけた。
ムーディーズの判断に対する中国政府の反論は、中国が問題を解決できると思わせるものではない。例えば、地方政府の債務問題に対する財政部の解決策は、インフラ関連の債務、いわゆる地方政府のインフラ投資会社である融資平台(LGFV)の再分類だ。だがそれは支払い義務を移すだけで、債務を軽減することはない。借金は金融システムにのし掛かったままだ。
財政部はまた、インフラ支出を増大させてより早く経済成長を促す策にも言及した。だが、その資金をどのように賄うのか、また計画立案者がプロジェクトに伴う負債を返済できるほどの経済効果をいかに確保できるようにするか、説明はなかった。これらは、直近のインフラ整備の多くが十分な経済効果を得られなかったことから、最近特に懸念されている。
ムーディーズの見通しがあろうとなかろうと、中国の状況は決して楽観できるものではない。現在抱えている債務問題は深刻で、それは金融の安定と経済成長の見通しにとって脅威となっている。また、ムーディーズに対してだけでなく、ムーディーズが浮き彫りにした現実に対する中国政府の反応が十分でないのも問題だ。中国政府の対応は、この問題に対処する意志があるのか、あるいは直面している問題を理解しているのか、疑念を抱かせるものだ。
(forbes.com 原文)
米巨大IT企業の中国人AI人材、とうとう母国に回帰する動きが加速! 中国から招集がかかったか?
2025年4月3日
望月博樹
MSやGoogle出身のAI人材、中国に続々帰国
米国で活躍した中国人AI人材、母国へ回帰の動き加速
中国出身の人工知能(AI)新薬開発専門家、フー・ティエンファン博士(32)は、2年前に米レンスラー工科大学で教授に就任し、終身教授を目指していた。しかし今年、中国・南京大学へ移籍した。AIを活用した新薬開発で注目されている若手研究者であるフー博士は香港の「サウス・チャイナ・モーニング・ポスト」とのインタビューで、「中国政府の高等教育への積極的な投資が、若手科学者に前例のないチャンスを与えている」と語った。
中国出身のAI人材が母国に戻る動きが加速している。先月23日には、マイクロソフトやIBMなど米ビッグテック企業でAI研究員を務め、フロリダ大学の教授としても活躍してきたチー・グオジュン氏(43)が、中国・杭州の西湖大学AI・機械学習研究所「メイプル(MAPLE)」の所長に就任すると報じられた。チー氏はディープラーニングやマルチモーダルAI(画像・音声など複数の情報形式を扱うAI)の専門家で、論文の被引用数は2万3,500回を超える実力者として知られている。
以前は母国に戻る中国人材の多くは大学教授が中心だったが、最近ではグローバル企業で活躍していた人材の帰国も目立ち始めている。例えば今年初め、中国のバイトダンス(TikTokの親会社)は、Google DeepMindの元副社長であるウ・ヨンフイ氏を採用した。南京大学を卒業後、米国で博士号を取得したウ氏は、2008年からGoogleで機械学習と自然言語理解を専門に17年間勤務していた。また、Appleで高性能・低消費電力のCPU設計を担当していたワン・ファンユイ博士も昨年、中国の華中科技大学(HUST)の教授に就任した。
過去には海外で高い評価を得た学者が後進の育成を目的に帰国するケースが一般的だったが、最近は帰国する人材の年齢層が若年化している。たとえば、暗号学分野の世界的権威であるカス・クリーマス元オックスフォード大学教授の主要研究プロジェクトに参加した、ジャオ・マン氏(29)、そして大連工科大学の教授に就任した双子の科学者マ・ドンハン氏(35)とマ・ドンシン氏が代表例だ。なお、マ・ドンシン氏は2012年に清華大学の最優秀5人の学生に与えられる特別奨学金の受賞者でもある。
若手人材を獲得するため、中国の大学は破格の条件を提示している。例えば、海外で博士号を取得した研究者が母国に戻り3年以上教授として勤務する場合、3年間の研究費900万元(約1億8,200万円)と年俸75万元(約1,500万円)を中国政府が創設した「優秀科学青年基金」で保証する。さらに生活費100万元(約2,000万円)と特別手当150万元(約3,000万円)を支援する場合もある。一般的な中国の教授年俸(20万〜35万元(約400万〜700万円))の約6倍に達する支援を受けられる。
中国の研究環境も急速に改善されている。フー・ティエンファン教授は、AIを活用した新薬開発に関して、「中国の大規模な臨床研究が貴重なデータ源となっており、こうしたデータが中国の技術企業によるAI発展を加速させている」と述べた。
中国政府は2017年に「次世代AI発展計画」を発表し、AI分野の人材回帰を促進する政策を本格的に推進してきた。これに伴い、大学や研究機関は自由度の高い研究環境と充実した研究予算を整備できる体制が整いつつある。これまで中国で博士課程に進むには国内で学士・修士号を取得していることが条件とされていたが、今年から清華大学や復旦大学などの主要大学がこの条件を撤廃。海外で修士号や博士号を取得した高度人材を積極的に迎え入れるための措置だ。
中国政府による人材の本国回帰政策は、実際に成果を上げている。先月30日に発表された「北京留学派白書」によると、昨年末の時点で海外留学を経験した北京在住者は122万8,500人に達し、そのうち約5分の1(20.84%)が科学・技術関連分野を専攻した人材だった。
また、中国教育部の資料によれば、年間の帰国留学生数は2015年の40万人から2021年には100万人を突破。このうち40%以上が、科学・技術・工学・数学(STEM)分野を専攻していた。
中国科学院と中国工程院に所属する院士(最高位の科学者)の多くが、海外留学の経験を持つことが明らかになっている。北京市で勤務する中国科学院の院士403人のうち、302人(75%)が海外留学経験者であり、中国工程院の院士448人のうち211人(47%)も同様に留学経験を持っていた。また中国科学院は、2023年上半期に米シリコンバレーから帰国したAI人材の数が、前年同期比で30%増加したと発表した。
アメリカで全頭引き上げ作戦…中国・習近平の超露骨な「嫌がらせパンダ外交」は日本にも波及する
2023年11月18日
Pandaには罪はない!習近平の「一帯一路外交」「微笑外交」「パンダ外交」に問題がある。もう、そろそろ、これらに騙されてはいけない。
アメリカで全頭引き上げ作戦…中国・習近平の超露骨な「嫌がらせパンダ外交」は日本にも波及する
© アサ芸プラス
アメリカ西海岸のサンフランシスコ近郊で、1年ぶりに行われた米中首脳会談。だが、史上最悪のレベルにまで冷え込んだ米中関係の雪解けは、全く見えてこない。
今年6月、アメリカのバイデン大統領は中国・習近平国家主席を「独裁者」と一刀両断。中国側は「挑発だ」「ばかげている」などと猛反発していた。今回の米中首脳会談の直後に行われた記者会見でも、バイデン大統領は次のように述べて、前言を撤回しなかった。
「我々とは全く異なる共産主義国家を統治している人物という意味で、習近平は『独裁者』だ」
当然ながら中国外務省の毛寧副報道局長は、
「完全に間違っており、断固として反対する」
と猛反発している。
そんな中、アメリカ国内では「来年には全米からパンダが1頭もいなくなる」との悲痛な声が、燎原の火のように広がり始めている。いったいどういうことなのか。
今年11月初頭、アメリカの首都ワシントンにあるスミソニアン国立動物園のパンダ舎の前には、多くの来園者の姿があった。次から次へと来園者がパンダ舎に詰めかけたのは、11月8日に中国に返還されることが決まっていた3頭のパンダ、すなわちメイシャン(美香=メス25歳)とティエンティエン(添添=オス26歳)、そして2頭の子供にあたるシャオチージー(小奇跡=オス3歳)との別れを惜しむためだった。
複数の米メディアによれば、スミソニアン動物園側は前例に倣ってパンダの貸与延長を申し入れたが、中国側は断固としてこれを受け入れなかったという。
アメリカ国内では、2019年に西部サンディエゴの動物園からパンダが返還されたのに続き、今年4月には南部メンフィスの動物園でもパンダの返還を余儀なくされている。しかも来年には南部アトランタの動物園からの返還も予定されており、これが断行されれば、全米からパンダが1頭もいなくなる事態に立ち至るのだ。
中国の「パンダ外交」の過去と現在に詳しい国際政治学者が指摘する。
「パンダ外交の歴史は古いが、習近平は今、『新パンダ外交』を掲げて戦略を先鋭化させている。具体的には、ロシアなどの友好国にはパンダを積極的に貸与する一方、アメリカなどの敵対国にはパンダの返還を迫るという、露骨な両面戦術です。今回の全米からの全頭引き上げ作戦も、習近平がバイデンから『独裁者』と名指しされたことへの意趣返しとみて間違いない。要するに、パンダを利用した『嫌がらせ外交』です」
今後、日本も含めた西側諸国でパンダが見られなくなるのも、時間の問題かもしれない。
(石森巌)
パンダ3頭、米国立動物園から中国に返還へ(微笑外交とパンダ外交の罠)
米国は貸与延長を希望したが中国は受け入れなかった
…ワシントンで半世紀ぶり不在の事態に専門家「米中関係と関係ないと言い切れない」
2023年11月8日
【ワシントン=向井ゆう子】米国ワシントンの国立動物園の3頭のパンダが今月中旬、中国に返還される。米国の首都からパンダが姿を消すのは、米中が国交正常化に向けて動き出した1972年以来、51年ぶりだ。最近の米中関係の冷却化を象徴する出来事といえそうだ。
■「会えなくなるのは寂しい」
6日、ワシントンにあるスミソニアン国立動物園のパンダ舎の周りには、中国に返還されることになったメイシャン(メス、美香、25歳)とティエンティエン(オス、添添、26歳)、2頭の子どものシャオチージー(オス、小奇跡、3歳)に別れを告げようと、大勢の来園者が詰めかけた。
ワシントンに住むニコル・プランクさん(45)は、子供の頃から学校行事で同動物園を訪れ、パンダに親しんできた。「米国ではなかなかみることができない動物で、会えなくなるのは寂しい」と惜しんだ。スミソニアン動物園のパンダは特別な存在だ。72年、ニクソン大統領の電撃訪中に同行したパトリシア夫人に対し、中国の毛沢東政権が2頭のパンダリンリン(メス)とシンシン(オス)を贈った。当時のメディアは、パンダに米国人が熱狂し、パンダが「まるで毛氏であるように」大切に飼育されたと伝えている。
リンリンとシンシンとの間には子供も生まれたが、92年にリンリン、99年にシンシンが死んだ。中国は2000年、研究目的として、同動物園に新たなパンダを貸し出した。それがメイシャンとティエンティエンだった。
■24年には全米からいなくなる
中国はこれまでに複数回、米側の求めに応じて2頭の貸し出しを延長してきた。米メディアによると、動物園は今回も貸与延長を希望したが中国は受け入れなかった という。メイシャンとティエンティエン、シャオチージーの3頭は15日までに中国に戻る。現時点で代わりのパンダが来る計画はない。
全米では、パンダの中国への返還が相次いでいる。いずれも期限切れに伴うものだ。今年4月には南部メンフィスの動物園のパンダも中国に戻った。南部アトランタのパンダも24年に中国に返還される予定だ。中国から新たな貸与がなければ、24年には全米からパンダがいなくなる見通しだ。
愛くるしい姿で人々を魅了するパンダは、中国の重要な外交手段だ。友好親善のシンボルとしてだけでなく、政治・経済関係を強める国に戦略的に贈られてきた。中国の習近平(シージンピン)政権は、パンダを積極活用する「新パンダ外交」を推進中だ。
「パンダ外交」の歴史は古い。1941年、当時の中国大陸を支配していた国民党の蒋介石の妻、宋美齢が友好親善のために米国に贈ったのが始まりだ。戦後の中国は、関係が深かったソ連などにパンダを贈ったが、敵対国にパンダを贈ったのは米国が初めてだった。中国と国交正常化を果たした日本にも72年に贈与され、パンダブームが起きた。
パンダ外交に関する著書があるカリフォルニア州セント・メアリーズ大学のエレナ・ソングスター教授は、「中国には米国からパンダを呼び戻すという明確で意図的な計画があるようだ。米中関係と関係がないと言い切れない」との見方を示した。
英国最後のパンダ2頭 滞在12年、中国との関係悪化するなか帰国へ
ロンドン=藤原学思2023年12月5日
英国に残る最後のジャイアントパンダ2頭が2023年12月4日、中国に向けて旅立った。スコットランドのエディンバラ動物園で12年間を過ごし、園の主役として愛されてきた。
帰国するのは、オスの陽光(ヤンコワン)とメスの甜甜(ティエンティエン)。ともに2003年8月に中国で生まれ、スコットランド王立動物園協会(RZSS)と中国野生動物保護協会の協定のもと、11年12月に英国に送られた。
当初の契約期間は10年だったが、新型コロナウイルスの影響により、滞在が2年延長されていた。
RZSSのデービッド・フィールド最高経営責任者(CEO)は「2頭は何百万人もの人びとに自然への関心を抱かせ、すばらしい影響を与えた」とする声明を発表した。
園は甜甜の出産をめざして努力を重ねてきたが、成就しなかった。RZSSは、「ジャイアントパンダの繁殖、飼育、獣医学的ケアに関する理解に大きく貢献した」としている。
一方、英中関係はこの12年間で劇的に変わった。米調査機関ピュー・リサーチ・センターによると、現外相のキャメロン氏が首相だった11年は中国に対して「好ましくない」と答えた英市民は26%だったが、23年はその割合が69%にまで上がった。(ロンドン=藤原学思)
「パンダ外交」転換に イギリスの動物園で唯一飼育の2頭を中国に返還へ
2023年12月5日
イギリスで唯一パンダを飼育している動物園が年内にもパンダを中国に返還します。イギリスにおける中国の「パンダ外交」が一旦、終止符を打ちます。
イギリス北部・スコットランドにあるエジンバラ動物園で2023年12月30日、中国に返還されるパンダの雄の陽光と雌の甜甜の一般公開が最終日を迎えます。
動物園では2011年からパンダ2頭を年間100万ドル、日本円でおよそ1億5000万円で中国からレンタルしていて、返還の表向きの理由として契約期間の終了などを挙げています。
中国は外交手段として世界各国にパンダをレンタルしていますが、これでイギリスの動物園からパンダはいなくなります。
今年2月には、動物園側はどこも、北欧・フィンランドの動物園でもパンダの飼育が経営を圧迫しているとして中国への返還が検討されるなど、世界各国で中国のパンダ外交が転換期を迎えています。突然の「パンダ引き上げ外交」となっています。
パンダ来英と英中通商関係 - エディンバラ動物園に2頭
昨年12 月、スコットランドのエディンバラ動物園に中国から2 頭のパンダが送られたことは、大きなニュースとなった。既にその愛くるしい姿で多くの人を魅了している「陽光」と「甜甜」の2 頭であるが、英中間における近年の著しい経済関係の発展を象徴するシンボルのような存在であるとの声もある。
ジャイアント・パンダとは
主に中国・四川省西北部、西部及び西南部に生息している、クマ科-ジャイアント・パンダ亜科の動物。学名はAiluropoda melanoleuca、中国名は大熊猫。
大人の雄の体長は150〜180センチ、体重は64〜125キロ程度。雌はこれよりやや小さい。
現在、野生のジャイアント・パンダの数は1300頭程度とされている。国際自然保護連合(IUCN)により、絶滅危惧種に認定されており、ワシントン条約で売買が禁止されている。
主食は竹と笹であるが、果物なども食べる。野生のジャイアント・パンダは、竹と笹以外の草のほか、まれに鳥などの肉を食べることもある。
基本的に単独で行動する。冬眠はしない。発情期は1年に1回で、雌が妊娠できる状態にあるのは1年に2日のみである。
ジャイアント・パンダが飼育されている欧州内の動物園
保護プログラムの一環として来英
昨年12月初頭、スコットランドのエディンバラ動物園に、2頭のジャイアント・パンダが到着した。2頭はともに2003年生まれで、名前は雄の「陽光(ヤングアン)」と雌の「甜甜(ティエンティエン)」。国際自然保護連合(IUCN)により絶滅危惧種に認定されているジャイアント・パンダの保護プログラムの一環として、中国・四川省のパンダ保護センターから貸し出されてきた。2頭は今後、エディンバラ動物園で最低でも10年間過ごす予定で、同動物園は、中国当局に毎年100万ドル(約7784万円)を支払う。
中国との通商関係強化に熱心な政府
中国は、海外の国にパンダを贈ることによって、友好関係を築こうとするいわゆる「パンダ外交」を展開してきたことで知られている。しかし、現在の英国は、パンダ外交によって中国から友好関係を求められる立場にはなく、逆に、経済発展著しい中国に対して、英国企業にビジネス・チャンスを与えてくれるよう頼む側となっている。
英国がいかに中国との通商関係強化を重視しているかは、キャメロン首相が2010年11月、大臣数人のほか、50人もの企業・教育界関係者から成る大規模な訪問団を従えて訪中した事実からもうかがえる。この際には、英国のロールスロイス社が、中国の中国東方航空と、12億ドル(約933億円)相当の商談を成立させたことなどが明らかにされた。また、2011年6月には中国の温家宝首相が来英し、英中間で14億ポンド(約1680億円)相当の商談が成立したと発表された。更に、両国間の貿易の規模を、2015年までに1000億ドル(約8兆円)に到達させるとの目標も改めて確認された。
スコットランド自治政府も、中国との通商関係強化に対する熱心さでは負けていない。エディンバラにパンダが到着した昨年12月初旬、同自治政府のアレックス・サモンド首相はちょうど、2007年5月の首相就任以来3度目となる中国への公式訪問中であった。この際には、中国の航空関係者らが2012年初頭、スコットランドを訪問し、中国−スコットランド間の直行便就航を検討すること、在北京企業が今後3年間で、スコットランド産ウイスキーの販売店を中国国内に300店開店することなどが明らかにされた。
こうした事実から、今回エディンバラに貸し出されたパンダは、中国の「外交カード」ではなく、両国間における最近の通商関係の目覚しい発展を象徴するシンボルのような存在であると指摘する声もある。
動物園は入場者7割増見込み
パンダの到着によって、英中間の経済関係がより強固になるかどうかはともかく、2頭が送られてきたことによって、最も経済的な恩恵を受けると考えられるのはもちろん、エディンバラ動物園である。同園は昨年、入場者が15%落ち込み、財政難に陥っている。しかし、パンダが来たことで、今後1年の入場者数は、前年比7割増が見込まれている。2頭の一般観覧は既に先月中旬から始まっているが、盛況であることが伝えられている。2頭に子供が生まれれば、更なる入場者増も見込めると考えられており、期待が高まっている。
英のパンダ2頭、中国に返還 「友好の使者」滞在12年
2023/12/5
英国で唯一のジャイアントパンダ2頭が4日、返還のため中国に旅立った。中国から貸し出された2頭は2011年12月に英国に到着し、北部スコットランドのエディンバラ動物園で12年間過ごした。英国民に親しまれ、英中の「友好の使者」の役割を担ってきた。英メディアが報じた。
2頭は03年生まれで、中国四川省のパンダ保護研究センターで飼育された雄の「陽光」と雌の「甜甜」。貸与期間は10年の予定だったが、新型コロナウイルスの影響で動物園が閉鎖され、返還が2年延期された。BBC放送によると、繁殖計画もあったが成功せず、貸与契約はこれで終了する。スコットランド王立動物園協会のフィールド最高経営責任者(CEO)は「飼育スタッフだけでなく、来園者やファンにとっても悲しいことだ」と語った。(共同)
パンダのレンタル料は2頭で年1億円! 中国の「パンダ外交」に隠された思惑とは? 経済評論家・上念司
2017/7/16
東京・上野動物園のジャイアントパンダが5年ぶりに赤ちゃんを出産し、日本中がパンダブームに沸いた。ただ、中国にとっては、その愛くるしい姿とは裏腹の、したたかな外交ツールでもある。中国の「パンダ外交」に隠されたその思惑とは。(iRONNA)
◇
1972年のニクソン、田中角栄の電撃訪問でこの国が少しまともになる前まで、中国のやっていたことは今の北朝鮮と変わらない。そして、当時の「パンダ外交」とは、世界中から孤立していた中国が、パンダという希少動物をネタにして、何とか世界に振り向いてもらおうとする外交政策だった。だからこそ、パンダは友好の証しとして無償譲渡され、文字通り外交的な貸しを作ることで政治利用されてきた。
ところが、81年に中国がワシントン条約に加盟したことを契機に、無償譲渡は終わった。現在、中国がやっているのは世界中の動物園に共同研究や繁殖などを目的として有料で貸し出すビジネスだ。報道などにある通り、パンダのレンタル価格は2頭で年に約1億円である。
報道しない自由
しかし、それでもパンダ外交は終わっていない。今までは中国が自分のカネでやっていた外交的プロパガンダを、相手のカネでやるように変わっただけである。あえてこれを「新パンダ外交」というなら、中国にとってはより都合の良いビジネスであるといえるだろう。
例えば、上野動物園のリーリーとシンシンも、貸与された東京都が中国野生動物保護協会と「共同研究」目的で協定を結び、10年間の有料貸し出しを受けているにすぎない。先日、誕生した赤ちゃんパンダも、この協定により「満24カ月」で中国側に返還することになっている。パンダのかわいさに目がくらみ、尖閣諸島に押し寄せる中国公船への対応が甘くなったりはしていないと思いたい。
マスコミはかわいらしいパンダの赤ちゃんをネタとして扱うだけで、こうした背景については何も語らない。すぐに「報道しない自由」を発動し、中国の意図を隠蔽(いんぺい)してしまう。そもそも、パンダビジネスとは侵略と人権弾圧の歴史の象徴だ。
かつて、パンダの生息域は現在よりもずっと広かった。しかし、11年の辛亥革命以降、中華民国軍が東チベットを侵略し、多くの中国人が入植してきたことでパンダは乱獲されるようになった。だが、チベットの支配地域に残ったパンダは虐殺を免れた。なぜならチベット人は仏教徒であり、無益な殺生をしなかったからだ。
ところが、50年に悲劇が訪れる。今度は中共軍がやってきた。東チベットのチャムドが侵略され、翌年にはチベットの首都、ラサが占領された。そして、55年にチベットの東半分は青海省と四川省に組み込まれてしまった。中国はチベットから領土を盗み、その地域に生息していたパンダまでも盗んでいったのである。
失った正当性
次に、中国が行っているパンダの有料レンタルビジネスの正当性がすでに失われていることについて指摘したい。これは私が勝手に言っているのではなく2016年9月の、世界自然保護基金(WWF)の公式な見解だ。
この見解の中で、WWFはパンダの格付けが「絶滅危惧種から危急種に引き下げられた」ことを朗報として伝えている。国際自然保護連合(IUCN)によれば、14年までの10年間で中国国内の野生のパンダの頭数は17%増加し1864頭になったそうだ。私が子供のころ、パンダは千頭しかいないといわれていたが、いつのまにこんなに増えたのだろうか。
パンダがもはや絶滅危惧種ではなくなった以上、有料でレンタルして共同研究を進める正当性もかなりグラついていると思える。しかし、中国にこのビジネスをやめる気配はない。もともと、チベットから盗んできた動物なのに、なんとずうずうしいことだろう。
パンダに罪はない。罪深いのは中国だ。私たちはパンダを見るたびに、その背後にあるドロドロしたものから目を背けてはならない。
iRONNAは、産経新聞と複数の出版社が提携し、雑誌記事や評論家らの論考、著名ブロガーの記事などを集めた本格派オピニオンサイトです。各媒体の名物編集長らが参加し、タブーを恐れない鋭い視点の特集テーマを日替わりで掲載。ぜひ、「いろんな」で検索してください。
◇
【プロフィル】上念司 じょうねん・つかさ 経済評論家。昭和44年、東京都生まれ。中央大法学部卒。経済評論家の勝間和代氏と株式会社「監査と分析」を設立。金融、財政、外交、防衛問題に精通し、積極的な評論、著述活動を展開。近著に『習近平が隠す本当は世界3位の中国経済』(講談社)。
随分前の話だが、外務省の中国課長経験者から聞いた話である。自民党の某元幹事長と某元総裁は、どちらがより親中かを競い合い、片方が訪中するとすぐにもう一方もはせ参じた。元課長は嘆じた。「そして時の日本の首相の悪口を言う。中国側は彼らを歓待するが、心の底では軽蔑していた」。
▼訪中して王毅共産党政治局員兼外相らと会談した公明党の山口那津男代表の場合はどうだったのか。「山口氏は今さら何で中国へ行くのかな。 習近平国家主席と会えるかどうかは分からない」。公明党関係者が事前に漏らしていた通り、過去に4度会っている習氏との会談は今回は実現しなかった。
▼山口氏は一連の会談で「(対中)国民感情を友好的にするための一つの手立て」として、仙台市へのジャイアントパンダ貸与を要請した。だが、中国との間で邦人拘束、日本産食品輸入規制、日本の排他的経済水域内での中国ブイ設置…と懸案が山積している中で、なぜ対中感情を和らげる必要があるのか。
「不便がないように」英国最後のパンダが故国へ…軍事作戦並みの帰還
2023年12/5(火)
英国に残された最後のジャイアントパンダのメス「テンテン(甜甜)」とオスの「ヤングァン(陽光)」が2023年12月4日(現地時間)、中国四川行きチャーター機に乗って故国に向かって出発した。2011年に盛大な歓迎式と共に英国の地を踏んでから12年が過ぎていた。
BBCによると、これまで英国スコットランドのエディンバラ動物園で飼育されていたテンテンとヤングァンはこの日午後1時40分ごろ、エディンバラ空港から特別チャーター機に乗った。中国南方航空所属のチャーター機には座席の大部分が除去されて長さ190センチ、高さ146センチ、幅127センチの大きさの特殊な鉄製のゲージが設置された。約13時間の飛行だ。
引き戸や小便トレイ、パーティションなどが備わった鉄製のゲージについてエディンバラ動物園は「小さく見えるが、かなり空間が広いゲージ」とし「飼育係の注文に基づいて作られた」と説明した。出国道中の混乱を避けるために出発時刻は秘密にされた。
チャーター機には飼育係や獣医師など両国関係者が搭乗して、飛行の半分時点で英国側の飼育係が中国側の飼育係にゲージの鍵を渡すことで責任も委譲する。最終目的地は四川省成都の野生動物保護協会だ。
飼育係はパンダ返還作業のためにさまざまな事前作業を進めた。両国政府間の合意に伴う動物保健規定を守るために動物園は先月初めからパンダを隔離し、飛行に備えた訓練も行われた。飼育係のマイケル・リビングストンさんは「パンダは朝に寝そべることが好きなので、朝早くに出発する時間に慣れされるために起床時間を少しずつ操り上げた」と話した。
当初、テンテンとヤングァンのレンタル契約期間は10年だった。コロナ禍で2年間レンタル期間を伸ばし、少なくとも8回の繁殖にチャレンジしたが成功させることができなかったため英国にはパンダが残っていない。
これまで動物園側は毎年79万ポンド(約1億4700万円)を中国に支払い、棲息地の造成や飼育係の賃金など管理費は別途支出した。ただしテンテンとヤングァンが動物園に到着して1年間で入場券の販売量が50%上昇したとBBCは伝えた。
先週末、英国全域ではテンテンとヤングァンに最後の挨拶を伝えようとする人々が殺到して長い行列ができ、場所取りをしようともみ合いまで起きた。ロレン・ダリングさん(35)は「もしかしたら7歳の息子が人生でパンダを見る最後の機会になるかもしれないと思って飛行機に乗ってきた」と話した。
パンダは外交・政治的象徴性が大きく、英国の追加レンタルについては何も決まっていない状況だ。エディンバラ動物園側は「新しいパンダが来る計画はまだない」と明らかにした。
一方、韓国で初めて自然妊娠で生まれた3歳のパンダ、フーバオ(福宝)も繁殖が可能になる来年には中国に戻る。フーバオの親であるメスのアイバオ(愛宝)とオスのローバオ(楽宝)は2031年まで韓国で引き続き飼育される予定だ。
東京で生まれたジャイアントパンダ、中国に返還…所有権は中国
ⓒ 中央日報日本語版2023.02.21
東京・上野動物園のジャイアントパンダ「シャンシャン」が観覧客と別れのあいさつをした。
上野動物園は19日、観覧客にシャンシャンを最後に公開したと報道した。動物園は1日の観覧客数を2600人に制限したが事前抽選に6万人以上が応募した。最も遅い時間帯の競争率は70倍に達した。
この日観覧客は動物園が準備したメッセージボードにシャンシャンに伝える最後のメッセージを残した。一部の観客はさびしさから涙を見せたりもした。
シャンシャンは2017年6月に上野動物園で生まれた。2011年に中国から借りてきたオスの「リーリー」とメスの「シンシン」の間に生まれた。
シャンシャンの所有権は中国にある。田中角栄政権時代に初めて、中国は1972年に日本との国交正常化を記念してパンダ1組を贈った。その後も日本にパンダを贈っているが所有権の移転は認めなかった。
シャンシャンは当初2019年に中国に返還される予定だった。だがコロナ禍を受け返還延期を求める市民の声が大きくなり数回にわたり延期された。シャンシャンは21日に中国南西部の四川省のパンダ保護研究センターに返還される。
「中国製クレーンはトロイの木馬」…バイデン大統領、行政命令で除去手順
2024年2月22日
米国のバイデン政府が事実上中国を直接狙った海洋サイバーセキュリティ対策を2024年2月21日(現地時間)、発表する。
米政府高位当局者によると、バイデン大統領はこの日スパイ道具として利用される可能性が提起されてきた中国製コンテナクレーンに対して強力なサイバーセキュリティを要求する行政命令に署名する予定だ。 この当局者は「バイデン大統領が海洋サイバー脅威に対応するために国土安全保障省の権限を強化する行政命令に署名する予定」と明らかにした。
今回の行政命令は沿岸警備隊に敵性国家および勢力の悪意のあるサイバー活動に対応したり海上輸送船舶・施設にサイバーセキュリティを強化したりするように要求する権限を付与し、サイバー事故に対する報告義務化などを含んでいる。バイデン政府はこれとあわせて今後5年間で米国港湾インフラに200億ドル以上(約3兆円)を投資することにした。米政府のある関係者は「今回の行政命令にはサイバー脅威が分かっているか疑われる船舶の移動を統制し、港湾の安全とセキュリティ脅威要因を是正するように該当の施設に要求したり該当サイバーシステムやネットワークが組み込まれている船舶・海岸施設を検査したりすることができる権限が含まれる」と説明した。
港湾施設のサイバーセキュリティ強化を骨子とした今回の指針は事実上米国港湾の80%以上を占有した中国製クレーン除去を狙っているという分析が出ている。米政府当局者は「中国製クレーンは遠隔で制御・プログラミングができて潜在的な悪用に脆弱な場合がある」とし「沿岸警備隊は米国内の多数を占めている中国製クレーンが加えることができる米国の重要インフラ保護のために海上保安指針を発表する」とした。この当局者は該当指針の具体的な内容はセキュリティ上公開することができないと話した。ただし中国製クレーンの所有主や運営者にさまざまなサイバーセキュリティ要件を課す予定であり、中国全域の港湾責任者にもこの指針を伝達して順守可否を確認する考えだとした。
米国の主要湾港で稼働している中国製コンテナはスパイ道具に利用される可能性が提起されて「トロイの木馬」にたびたびたとえられてきた。中国製クレーンに装着された情報収集装置が港湾コンテナの出荷元や目的地などの貨物情報を追跡して中国本国に送信することができ、場合によっては物流サプライチェーン(供給網)をかく乱させ、米国に相当な被害を与える可能性があるという懸念が提起されていた。
特に米軍の利用頻度が高いバージニア・メリーランド・サウスカロライナなどの湾港に最近数年間で中国上海振華重工業(ZPMC)のクレーンが多数配置されて秘密情報流出に対する懸念が高まっていた。米国防情報局(DIA)は2022年中国がクレーンを通じて港湾物流量をかく乱あるいは軍事装備荷役情報を収集する可能性があるとの分析を出したことがある。
中国最大通信装備会社ファーウェイ(華為)の送信塔から米軍核基地傍受の可能性が提起されたほか、中国動画シェアプラットフォーム「TikTok」 が米国の安全保障に脅威になる可能性があるとし、政府機関・研究機関などからの除去が進んでいる。こうした中、中国製クレーンも米軍需物資および貨物情報の収集に悪用される可能性があるという懸念が高まり、強力なセキュリティ対策がこの日出てきた。
米政府当局者は「米国の港湾と規制対象施設に中国製クレーンが200基以上あると把握している」とし「既存のクレーンの約50%を調査し、悪意のあるサイバー活動が見つかった場合もある」と述べた。また別の米政府関係者は「中国のサイバー活動に対する明らかな懸念があり、犯罪活動に関連した懸念もある」とした。日本最大の湾港の一つである名古屋港がランサムウエア攻撃で数日間運営が中断されたこともある。
中国製港湾クレーンは韓国の港湾でも事実上除去手順を踏んでいる。韓国政府が中国製港湾クレーンの国産代替に入ったためだ。釜山(プサン)港湾公社と仁川(インチョン)港湾公社は昨年から推進しているコンテナ埠頭に設置予定の港湾クレーンを国内企業に発注したり国内企業に加点を与えたりするやり方で国産クレーンの導入を誘導している。
「ウクライナにあげる金などない」 「ウクライナにあげる金などない」「我々の国を立て直すことから始めるべきではないか」 、支援に米欧が内向き…トランプ氏が復帰すれば「終わりの鐘響く」
2024年2月22日
2024年2月20日、米サウスカロライナ州で行われたFOXニュースの集会で講演するトランプ氏=AP。ウクライナ支援に否定的な考えを示した
■[ウクライナ侵略2年]見えない出口<2>
「ウクライナにあげる金などない」「我々の国を立て直すことから始めるべきではないか」
今月2024年2月12日、米議会上院の本会議場では野党・共和党議員が入れ代わり立ち代わり、ウクライナ支援に否定的な演説を夜通し続けた。採決を故意に遅らせるフィリバスター(議事妨害)を展開したのは、ウクライナ支援予算約600億ドル(約9兆円)を含む緊急予算案に反対するためだ。
上院は与党・民主党が多数派で、予算案は翌朝にもつれ込んだ採決で可決された。バイデン大統領は2024年2月13日、ホワイトハウスで「この法案への反対は、プーチン(露大統領)の意のままになるのと同じだ。歴史が見ている」と訴えたが、下院は共和党が多数派で、現状のままでの予算成立は絶望視されている。
ロシアによる侵略開始以降、米議会はウクライナに超党派の強い支持を示してきた。米国が提供した軍事支援は440億ドル(約6兆6000億円)超で、国別支援額では突出している。
米議会を変質させたのは、秋の大統領選で返り咲きを狙う共和党のトランプ前大統領だ。「米国第一」を掲げるトランプ氏は、ウクライナに欧州よりも遠い米国が多額の支援をしていることに不満を抱き、援助停止を促している。
トランプ氏に忠誠を誓う保守強硬派のマイク・リー上院議員は 2024年2月12日、X(旧ツイッター)オーナーのイーロン・マスク氏らとのオンライン討論番組で、汚職が深刻な問題になってきたウクライナの国民を「汚職の世界記録を樹立した人々だ」とののしった。 番組は120万回以上、再生されている。
オースティン国防長官は2024年2月20日、ウクライナのルステム・ウメロフ国防相らと電話で会談し、弾薬供給を「緊急課題の一つ」として協議した。だが、予算が枯渇している米国は、今のままでは弾薬を供給できない。ドイツの調査機関・キール世界経済研究所は最新報告書で、「トランプ氏が政権復帰すれば米国の対ウクライナ援助に終わりの鐘が鳴り響くだろう」と予測した。
支援強化が期待される欧州でも、内向き傾向がじわじわと強まっている。
旧ソ連の「衛星国」として苦しんだ歴史を持つスロバキアでは昨年秋、ウクライナへの軍事支援反対を掲げる左派ポピュリズム政党が政権を奪還した 。昨年2023年11月のオランダの総選挙で第1党になった極右の自由党は移民・難民の受け入れに反対し「オランダ第一主義」を主張する。
ウクライナのアンドリー・イェルマーク大統領府長官は危機感を隠さない。「全ての武器支援が遅れずに届くことが重要だ。さもなくば、残念ながら、我々はこの戦争で負ける」
2011年3月から2012年にかけて日本中が混乱していた時期に韓国は竹島を実効支配、侵略していた!
アメリカのトモダチ作戦は感謝するしかないが、韓国は日本が混乱しているすきに立派なヘリポート、軍事施設を作っていた。日本の船にレーザー光線を当てたり、自衛隊にも同じことをして、何を考えているのか?分からないくにが韓国だ!
韓国とプーチンと習近平の3人が軍事パレードに参加
永遠に止まらない日本批判
しばらく鳴りを潜めていた韓国の「反日機運」だが、ここにきて文在寅政権と与党が再びこれを強化する方向に思い切り舵を切り始めた。韓国民の中に眠る反日感情に火を着けることで、大統領選挙で苦戦中の与党の李在明(イ・ジェミョン)候補に有利な雰囲気を作り出す意図があると思われる。
2022年3月1日は韓国の祝日の「三一節」(独立運動記念日) だ。日本の植民地だった時代の1919年、韓国全域で起きた“反日デモ運動”を記念する日だ。当時、日本の警察によってデモ運動に参加していた4万6000人余りが逮捕され、7600人余りが死亡しただけに、韓国民の反日感情を刺激するのに最も相応しい日である。
文在寅大統領は、自身の任期で最後となる三一節記念演説において
文在寅大統領は、自身の任期で最後となる三一節記念演説において、突然日本を強く批判した。
「日本は歴史を直視し、歴史の前で謙虚にならなければならない」 (その前に韓国も謙虚になってください)
「不幸だった過去によって時々悪化する隣国の国民の傷に共感できてこそ、日本は信頼される国となりえる 」(韓国も信頼できる国になってください)
文大統領は、日韓が歴史を乗り越え、未来に向けて協力しなければならないと言いながらも、そのためには日本の謝罪や反省が必要だ 、と主張しているのだ。
他にもK-POPやBTS、映画『パラサイト』、ネットフリックスのドラマ『イカゲーム』 の成果をいちいち挙げてから、「日本文化を圧倒するほどの競争力を備えるようになった 」と強調したり、「日本の(半導体部品3品目に対する)輸出規制措置に対抗して素材、部品、装備の自立化の道を切り開いた 」と強調したりして、これらを文政権の代表的な業績 に含めた。
旧日本軍空襲 80年で慰霊式 オーストラリア
2022年2月20日 05:00
2022年3月2日は【ダーウィン共同】旧日本軍が1942年2月にオーストラリア北部ダーウィンに空襲を開始し、オーストラリア本土が初めて戦場になってから2022年2月19日で80年となり、現地で慰霊式が開かれた。現地での反日感情は無く、日本は友人として迎えられ、潜水艦爆破で亡くなった日本軍80人の慰霊碑も建てられた。
太平洋戦争中に旧日本軍がダーウィンなどオーストラリア北部への空爆を開始してから19日で80年を迎えた。ダーウィン市内ではモリソン豪首相ら約4000人が出席して追悼式が開かれた。
式典では、実際の空爆開始時刻に合わせて襲来する爆撃機に地上で応戦する当時の様子が再現された。ダーウィンは連合国の補給基地で、日本に対する反攻の拠点だった。ダーウィンを中心とした豪北部に対する空爆は1942年2月から43年11月まで計97回に達し、260人以上が死亡した。
オーストラリア現首相のモリソン氏は、安倍晋三元首相が2018年に日本の首相として初めてダーウィンを訪問し共に時を過ごしたことに触れ「(ダーウィンが)和解の場所になった」と指摘。「この都市や国に、こうした暴力を与えた敵は、今では最も信頼できて誠実な友人の一人になった 」と述べた。
日本の沈没潜水艦、慰霊碑除幕 80年後、80人の名刻む―豪
2022年02月18日15時41分
オーストラリア北部ダーウィン沖で沈没した旧日本軍の潜水艦「伊号第124」乗員の慰霊碑前に立つ山上信吾駐豪大使(左から4人目)ら関係者=18日、ダーウィン
【ダーウィン(オーストラリア北部)時事】オーストラリア北部ダーウィン沖で、太平洋戦争の開戦直後に旧日本軍の潜水艦「伊号第124」が沈没して80年余りが過ぎた。ダーウィンでは18日、乗員80人全員の名前を刻んだ慰霊碑の除幕式が催された。
極東情勢やいかに 米中さや当てに軍艦の日本周回◆真珠湾攻撃80年
伊号第124は開戦から間もない1942年1月、連合国側の重要拠点と見なすダーウィンの沖合を機雷敷設や哨戒のために航行中、豪軍の爆雷などの攻撃を受けて沈没。乗員全員が戦死した。船体は引き揚げられず、遺骨は今も水深50メートルの海底に眠る。沈没の翌2月には日本がダーウィンなどへの空爆を開始し、豪州側に260人以上の死者が出た。
日豪の関係緊密化と相互理解の促進を受け、2017年に沈没海域を望む海岸沿いに最初の慰霊碑を建立。今回はその隣に、乗員全員の名前と階級、北海道や宮城、静岡、長野、石川、愛知など出身地が書かれた新たな慰霊碑が、日豪の協力で設置された。
除幕式には地元政府幹部を含め約100人が参加した。献花した山上信吾駐豪大使は「日本と豪州が築き上げた和解や平和の足跡を振り返る大きな機会だ」と強調。地元北部準州のガナー首席大臣も「われわれを分断していた全てのことは、真の友情に置き換わった」と訴えた。
ダーウィンでは2022年3月2日、空爆開始から丸80年を迎えて追悼式が開かれる。
同じく韓国では、2022年3月1日は韓国の祝日の「三一節」(独立運動記念日)だ。日本の植民地だった時代の1919年、韓国全域で起きた“反日デモ運動”を記念する日だ。当時、日本の警察によってデモ運動に参加していた4万6000人余りが逮捕され、7600人余りが死亡しただけに、韓国民の反日感情を刺激するのに最も相応しい日である。
文在寅大統領は、自身の任期で最後となる三一節記念演説において、突然日本を強く批判した。
「日本は歴史を直視し、歴史の前で謙虚にならなければならない」(韓国も謙虚になってください)
「不幸だった過去によって時々悪化する隣国の国民の傷に共感できてこそ、日本は信頼される国となりえる」(韓国も信頼できる国になってください)
文大統領は、日韓が歴史を乗り越え、未来に向けて協力しなければならないと言いながらも、そのためには日本の謝罪や反省が必要だ、と主張しているのだ。
他にもK-POPやBTS、映画『パラサイト』、ネットフリックスのドラマ『イカゲーム』の成果をいちいち挙げてから、「日本文化を圧倒するほどの競争力を備えるようになった」と強調したり、「日本の(半導体部品3品目に対する)輸出規制措置に対抗して素材、部品、装備の自立化の道を切り開いた」と強調したりして、これらを文政権の代表的な業績に含めた。
文在寅大統領は、自身の任期で最後となる三一節記念演説において、突然日本を強く批判した、その時の映像が上の顔。
「日本は歴史を直視し、歴史の前で謙虚にならなければならない」と演説した。
韓国のGDPは、2022年には日本を追い越すでしょう。 韓国から来る韓国人は日本で復讐を始めようと、安全保障上の、食料や農産物の技術を盗んで持って帰るでしょう。そして一人当たりのGDPでは、日本は韓国に追い抜かれてしまった。
国家に対する忠誠を確認するもので、まずトランペットと太鼓の音で華々しく始まり、途中からナレーションで、国民儀礼と呼ばれる国に対する忠誠の言葉の録音が流れるのですが、その約1分ほどの間、直立不動で右手を開いた状態で心臓に当てて国旗を見つめていなければならない。
具体的にはこんな風です。
「나는 자랑스러운 태극기 앞에 자유롭고 정의로운 대한민국의 무궁한 영광을 위하여 충성을 다할 것을 굳게 다짐합니다.(私は誇らしい太極旗の前に自由で義なる大韓民国の無窮なる発展のために忠誠を尽くすことを固く誓います。)」
韓国の学校教育は、国粋主義教育が徹底され、男子は徴兵されます。仮想敵国はもちろん歴史的屈辱を味わされてきた近隣国です。悲しいことに、近隣国が誤っても、たぶん永遠に変わらない関係です。
韓国が竹島周辺で測量計画 日本政府「強く抗議」
[2022年4/27]
岸田政権や経団連に愛国心や経済安全保障への義務感が無さすぎる。
韓国が島根県・竹島の地形などの精密な測量計画を進めていることについて、松野官房長官は韓国側に抗議し、調査の中止を求めたことを明らかにしました。
松野官房長官:「我が国としては、韓国政府に対して外交ルートで強く抗議をするとともに、調査の中止を強く求めたところであります」
松野官房長官は、韓国が計画している竹島周辺の測量について「受け入れられず極めて遺憾だ」と強調しました。
そのうえで、韓国の尹錫悦(ユン・ソクヨル)次期大統領が派遣した代表団に同行している韓国外務省の担当課長にも申し入れを行ったことを明らかにしました。
岸田文雄総理大臣は26日、代表団に関係改善が急務だという認識を示していました。
韓国の「反日デモ」の様子
ヒトラー、スターリン、そしてプーチン。ウクライナへの野望
現代の独裁者ともいうべきプーチンが抱く、ウクライナ征服への野望。その根本の動機には、ロシアを世界の大国にしたい、昔のような帝国として復活させたい、との思いがある。現代の皇帝(ツァーリ)を目指すプーチンらしい発想だ。そのためには、隣国ウクライナを、EUやアメリカではなく、ロシアの勢力圏にとどめる必要がある。
ヨーロッパで2番目に広いウクライナには、肥沃な農地が広がり、鉄鉱石・天然ガス・石油などゆたかな天然資源が埋まっている。東側と西側とにまたがる地政学上の要所でもある。それゆえ、プーチンのみならず、過去にはヒトラーやスターリンといった独裁者たちからターゲットにされ悲惨な目に遭ってきた。
2014年、ウクライナがEUと政治経済にかんする包括協定を結ぼうとしていたときのことだ。ウクライナをEUから引き離したいプーチンは、断固として協定を結ばせまいとし、ウクライナ政権のヤヌコーヴィチ大統領(当時)に圧力をかけた。すでに腐敗した政権だったということもあり、プーチンの思惑通りに進むかに見えた。だが、恐れを知らぬキエフの若者たちによるデモが起こる。数日間のうちに、たちまちデモに参加する群衆の数は膨れあがり、ヤヌコーヴィチ大統領の腐敗政権を終わらせよ、との声が高まった。
注意深く観察していたプーチンは、警戒心を強めた。なぜならドレスデン駐在のKGB時代に経験した、ベルリンの壁崩壊時の苦い思い出があったからだ。ロシアの“利益圏”とみなしていた地域で、“衆愚政治“が広がっているーー過去のトラウマが、プーチンを一気に目覚めさせた。
電光石火のウクライナ侵攻作戦
ヤヌコーヴィチがロシアへ逃げ出したその1週間後。プーチンによる電光石火のウクライナ侵攻作戦に、当時は弱体化していたウクライナ軍は不意打ちを食らった。アメリカも油断していた。プーチンと同じく警察国家育ちで、KGB出身のプーチンの残虐さを知り抜いたメルケルでさえ、ウクライナについてはEU任せにしていたふしがあった。
メルケルは、プーチンが自由を愛する民主主義者に変わるという幻想は一度も抱いたことはなかった。とはいえ、経済成長を続ける西側をまのあたりにして、富を愛するプーチンがEU寄りの政策を取るのではないかと期待していたのだ。
しかしウクライナ侵攻により、「欧州の安全保障」という幻想は粉々に打ち砕かれた。プーチンが選んだロシアの未来とは、「西側の一員となる未来」ではなく、「西側に対抗する未来」だった。
プーチンが仕掛けたのは、「欺瞞作戦(マスキロフカ)」だった。これは20世紀前半にロシア軍が生み出した手法で、「だまし、否定、偽情報」の3つを駆使するというものだ。
プーチンは、クリミアのロシア系住民がロシアの介入を求めたと言い張った。「ファシストによる非合法の暫定軍事政権が、キエフやクリミアに住むロシア人の脅威となっている」と主張し、現地の群衆をあおり立てた。クレムリンによる同じような作り話は、1956年にハンガリー革命の制圧を正当化するのにも使われたし、1968年の“プラハの春”でも鎮圧のための戦車派遣を合法化するのにも使われた。さらには1948年、東西冷戦のはじまりともいうべき西ベルリンの封鎖を正当化するときにも使われている。
VIDEO
石油代金を紅茶で支払い!?「中国」「ロシア」「新型コロナ」の三重苦 スリランカが直面する歴史的な経済危機(2022年4月16日)
スリランカはいま深刻な経済危機に陥っている。
記録的な物価上昇や生活に欠かせない食品や燃料が不足し、反政府デモに発展。
政府が非常事態宣言を発令する事態となった。
経済危機に陥った大きな原因のひとつが対中債務。
かねてから中国から巨額の資金を借り入れ、大型のインフラ開発を推進してきた。
これが財政を圧迫しているのだ。
そして借金が返せなくなり中国の支配が強まる「債務の罠」に陥ったのだ。
スリランカの主要産業のひとつで貴重な外貨獲得源である観光業が
新型コロナウイルスの感染拡大で低迷していることも経済危機に拍車をかけている。
そしてスリランカ経済の悪化に追い打ちをかけたのがロシアのウクライナ侵攻だ。
通貨安に拍車がかかり外貨準備金が減少。
燃料や食料の輸入が滞り物価が高騰したのだ。
経済危機の責任を取る形で大統領と首相を除く全閣僚と中銀総裁が辞任。
また燃料や食料品の価格高騰に対応するため
政策金利を約2倍に引き上げるなどの対応策を打ち出しているが
経済危機から抜け出せる道筋は見えていない。
ディレクター:鈴木芽衣
編集:工藤美穂・那須俊介
プロデューサー:矢田典隆
中国がロシアに兵器供与計画と同盟諸国に通知 中国は否定
[ロンドン/ワシントン 2022年3月15日 ロイター]
中国がロシア側の要請に応じて、ウクライナでの紛争支援に向けロシアに軍事的・経済的援助を行う意思を示したことが分かった。 (2022年 ロイター/Carlos Garcia Rawlins) [ロンドン/ワシントン 2022年3月15日 ロイター] - 米高官によると、ウクライナ紛争を巡り、中国がロシア側の要請に応じて軍事的・経済的援助を行う意思を示したと、米情報当局が2022年3月14日に北大西洋条約機構(NATO)とアジアの同盟国に外交公電で伝えた。
一方、ロンドンの駐英中国大使館は2022年3月15日、こうした米国の主張を否定した上で、米政府が「悪意のある偽情報」を拡散し、紛争をエスカレートさせるリスクを冒していると非難した。
同大使館はロイター宛ての声明で、米国はウクライナ問題で中国に対する悪意のある偽情報を繰り返し拡散していると指摘。中国はこの問題の和平協議を促す上で建設的な役割を果たしているとし、現在の最重要課題は事態の鎮静化と外交的解決に向けた取り組みだと表明した。
先の米高官によると、米情報当局の外交公電には、中国がロシア支援計画を否定するとの見方も記されていた。また、詳細はブリーフィングで直接共有する見込みという。
米国のサリバン大統領補佐官(国家安全保障担当)は2022年3月14日、中国の外交担当トップの楊潔篪・共産党政治局員とローマで会談を行い、中国の対ロシア支援に「直接的、かつ極めて明確な」懸念を表明した。
ロシアは中国による軍事援助などの報道を否定し、自国に十分な軍事的資源があると説明。中国外務省も報道は偽情報だと述べた。
中国が反発「ニセ情報だ」 ロシアへの軍事支援めぐり
2022年3/14(月)
中国外務省 報道官 「理由もなく推測すべきではない!!」
中国が反発「ニセ情報だ」
ロシアが中国に対し軍事支援などを要請した とアメリカメディアが報じたことについて、中国外務省は「ニセ情報をまき散らしている」と反発しました。
中国外務省は2022年3月14日の会見で「アメリカはニセ情報をまき散らしている」と批判し、「中国は和平協議のために建設的な役割りを果たしている 」と主張しました。
さらに、「各国は自制を保ち、緊張を緩和させ、外交的解決を促すべきだ」と強調しました。
複数のアメリカメディアは、ウクライナ侵攻を続けるロシアが中国に対して攻撃型ドローンの提供を含む支援 を要請していると報じました。
アメリカのサリバン大統領補佐官は2022年3月13日、中国政府にロシアへの支援は許されないと強く牽制(けんせい)しています。
中国「ロシアに武器提供しない」、侵攻当日の明言は口を滑らせた? 先月初の首脳会談も中国にとっては“足かせ”に
2022年3/18(金) 13:07配信
「もし中国がロシアに軍事的、あるいはその他の援助を行い、制裁に違反したり戦争への支援をするのであれば、重大な結果がもたらされるだろう」
【映像】中国のロシアへの軍事支援 現地記者の見方は
2022年3月14日、ホワイトハウスのサキ報道官から発された警告ともとれる言葉。ロシアが中国に要請したとされる、軍事や経済面に対する支援に対するものだ。複数の欧米メディアがこうした内容を報じており、CNNなどは「ロシアはドローンを含む軍事支援を中国に要請した」などとしている。
中国側はこれに反論。中国外務省の趙立堅副報道局長は「最近、アメリカはウクライナ問題で中国を対象にした虚偽情報を相次いでまき散らしている」と述べた。
こうした中、アメリカのサリバン大統領補佐官と中国の楊潔チ政治局委員はローマで会談を開いたが、会談の時間は7時間にも及び、担当記者も「記憶にない」という。ロシアのウクライナ侵攻に対する中国のスタンスについて、ANN中国総局の千々岩森生総局長が伝える。
中国外務省の華春瑩報道局長
中国が反発「ニセ情報だ」「とやかく言う権利はない」
Q.中国によるロシアへの軍事支援の真偽は?
現状、軍事支援という意味での可能性は低いとみている。中国外務省の華春瑩報道局長は先月24日、「我々はアメリカのようにウクライナに大量の軍事施設、設備を提供していない」「ロシアは実力のある大国として、中国あるいは他の国からの提供を必要としないと思う」と、ロシアがウクライナ侵攻を開始した日に明言している。
「この発言があるから支援がない」と言いたいのではなくて、アメリカを批判したいがために一言、二言、余計なことを言ってしまったという感じもした。「アメリカはウクライナに対して軍事支援をしている、だからこそ緊張がエスカレートしているじゃないか。中国はロシアに対してそんな支援はしない。緊張をエスカレートさせるようなことはしない」という、アメリカ批判のために口が滑ってしまったと思っている。
それ以降、「ロシアに軍事支援しない」「武器支援はしない」と言っていないことは若干気になる。しかし、軍事支援するとなると、ロシアに向いている国際社会の批判が中国にも向きかねないということで、そこまでは考えていないだろう。
Q.米サリバン大統領補佐官と中国のヨウ・ケツチ政治局委員の会談は7時間にも及んだということだが、中国ではどのように報道された?
国営テレビは、中国政府が発表した内容をそのまま一言一句変わらずに、写真1枚だけを使って報道していた。会談では、ウクライナ問題の他にも台湾や香港、新疆ウイグル自治区の問題など、米中の中で横たわる様々なことが話し合われ、中国側はこう発言した、アメリカ側にこうアピールした、ということは細かく報じられた。そして、米中関係は別にして、ウクライナ問題ではこういうやりとりがあったということも発表された。
7時間というのは会談として極めて長く、我々も想定していなかった。会談は夜から始まり、夜中に発表があるかと思って私も1時、2時まで待機していたが、それでも出なかった。その後、ようやく朝になったら発表があったということで、私のこの4年の中では記憶にない。それだけ懸案が多いということでもあると思う。
ANN中国総局の千々岩森生総局長
Q.中国からロシアへの軍事支援の可能性は低い一方で、経済支援の可能性は?
経済支援はあり得ると思う。ただ、経済支援をすると表明して行うと、それは制裁の対象になりかねない。実は、中国政府はすでに「ロシアに対する正常な貿易は続ける」という言い方はしている。
2022年2月4日の中露首脳会談の中で、天然ガスのロシアから中国への輸入を拡大すると約束している。経済に関してはいろいろなやり方があるので、そうした貿易の一貫として取引しているだけだと、見えにくいかたちで経済支援を行う可能性はあると思う。
ただ、この会談が中国にとっては“足かせ”になっている部分もある。国際社会から中露一体と見られる可能性があるし、2022年北京オリンピックの開会式に各国が外交的ボイコットとして参加しなかった中で、プーチン大統領は参加した。ビッグネームが来るということは中国にとってありがたかったわけで、プーチン大統領としては「行ってあげたよね」という言い分もあると思う。
有事の時は、中国の法律で日本企業を中国企業に転換できるように法律がある
中国は、軍事技術と経済発展を結び付ける「軍民融合」を国家戦略と位置付け、日本企業を虎視眈々と狙っている。有事の時は、中国の法律で日本企業を中国企業に転換できるように法律があるのだ。
都内に本社がある大手製造メーカーが中国に設立した合弁企業内で「人民武装部」が活動していたことが、日中関係者への取材で分かった。この合弁企業は、日本側と中国側が50%ずつ出資して約20年前に設立された。
注目の人民武装部は、中国共産党への絶対服従を求められているほか、人民解放軍の指揮下にもある。主に、民兵や予備役の「軍事訓練」や「政治教育」など、軍事関連業務を担う。企業が所有する「資源の徴用」に応じることも義務付けられている。
「民兵」とは、中国国防法で規程された組織で、人民解放軍、武装警察と並ぶ実力組織。「予備役」も日ごろから軍事訓練を行い、民兵同様、平時も暴動の取り締まりや災害救助などの任務を負う。
問題の合弁企業内の人民武装部は昨年2020年11月中旬、「人民武装愛国主義教育活動」を実施し、同社の民兵ら30人余りが参加していた。彼らの写真も存在する。
日本側企業による管理が及ばない内部組織の存在は、企業統治のあり方が問われるだけでなく、技術流出など安全保障上の懸念もある。そもそも、中国では合弁企業内に共産党員が3人以上いる場合、党組織をつくることが義務付けられている。
■ドイツ大手製造業内にも 広報担当者、存在を否定
この大手製造メーカーの広報担当者は、取材に対し、「(合弁企業内において)“人民武装部”という組織は存在しておりません。従いまして、いただいたご質問事項に関してお答えできるものはございません」と回答した。
写真の存在も指摘したが、担当者は「回答は変わりません」と語った。
中国国防法には外資企業を除外する規定はなく、人民武装部が存在するのは日本企業だけではない。
ドイツ大手製造業内にも、人民武装部の存在が日中関係者への取材で確認されている。在中国のドイツメーカー広報担当者も「人民武装部はない」と存在を否定した。
外資企業における人民武装部の存在は、まだ表立って公表されるケースは少ない。他社にも存在する可能性は十分ある。中国側も、外資企業や外国政府から反発を受けないよう慎重に活動を展開しているとみられる。
米国は現在、安全保障の観点から中国への輸出管理を強めている。日本企業内の人民武装部の活動次第によっては、米国が今後、日本企業を米国のサプライチェーン(供給網)から外すなどの制裁措置を検討する可能性もある。
岸田政権は、人民武装部の実態を調査し、「経済安全保障上のリスク」について、目配せしていく必要がありそうだ。岸田政権や経団連に愛国心や経済安全保障への義務感が無さすぎる。
米国からの提言「韓国製品に報復関税をかけよ」
朝鮮半島問題の専門家の見方、非は韓国側にある
2019.3.13(水)
(古森 義久:産経新聞ワシントン駐在客員特派員、麗澤大学特別教授)
「韓国が日本企業から不当に資金を奪うならば、日本は対抗して韓国製品の輸入に報復の関税をかけるべきだ」
米国の有力な朝鮮半島専門家が、日本と韓国の対立の非は韓国側にあるとして、日本政府に強固な対応の措置をとることを提唱した。
米国の本音「非は韓国側にある」
米国のトランプ政権は、日韓両国間のいわゆる元徴用工、慰安婦、レーダー照射など一連の摩擦案件に関して公式の論評を避けているが、韓国側の一連の言動が不適切だという本音をにじませてきた。官民の間で広がりつつあるこの本音が、専門家の韓国批判という形で明確にされたわけだ。日本側としても参考にすべき批判、対抗措置案だろう。
トランプ政権は、東アジア情勢、朝鮮半島情勢に関しては北朝鮮の完全非核化を当面の最大目標としており、その目標の実現には日韓両国それぞれとの堅固な同盟関係の保持が不可欠との立場をとっている。そのため現在の日本と韓国との対立については、一方を支持することで他方を離反させることを恐れ、「どちらに理があるか」という論評は控えている。連邦議会上下両院の議員や民間の専門家の間でも、対日関係および対韓関係の堅持のためにコメントを避ける傾向が顕著である。
ところが数歩、踏み込んで取材をしてみると、トランプ政権内外では、いわゆる元徴用工(正確には「戦時労働者」)、慰安婦、レーダー照射と、どの問題でも非は韓国側にありとする判断が強いことが見えてくる。いわば米国の本音といってもよい。
このたび、そうした考え方をきわめて明確に聞くことができた。朝鮮半島問題のベテラン専門家であるラリー・ニクシュ氏がインタビューに応じ、率直な意見を語ったのだ。
ニクシュ氏は米国議会調査局や国務省で朝鮮半島や東アジアの安全保障問題を30年も担当し、現在はジョージ・ワシントン大教授や戦略国際問題研究所(CSIS)研究員という立場にある。これまで日韓両国間の問題について頻繁に見解を発表しているが、とくに日本側を一貫して支持したという記録はない。慰安婦問題などではむしろ日本側の一部の強硬主張を批判して、韓国側の立場の支持に傾くことも珍しくなかった。だからこそ、今回の一連の日韓摩擦案件での韓国批判には重みがあるといえよう。
脱韓国へ、対中作戦で米陸軍・海兵隊が陸自と一体化
米朝首脳会談後の大きな変化、喫緊に求められる日本の複眼思考
2019.3.12(火)
1 日本の生死に無関心でいいのか
2回目の米朝首脳会談が終わっていろいろな議論があるが、日本では米朝首脳会談が失敗か成功かの論評ばかりが語られ、そこを起点として日本はどう朝鮮半島情勢に対応していくのか、どう中国に立ち向かっていくのかの具体的な議論がなされないのは残念だ。
相変わらず国会は日本にとって死活的重要なアジア情勢について深く分析し、対応手段を講じようとしない。
政治家も国民も、米国の庇護の下、この国は未来永劫続くと思っているのならば大きな間違いだ。このような時に必要なのは、複眼思考である。
2 米朝首脳会談の成果とは何か
米朝首脳会談を評価するうえで、絶対に外してはならないことがある。
1つは、どんなに北朝鮮が騒いでも、北朝鮮問題はインド太平洋地域で起きている米中対決の「前哨戦」に過ぎず、「本丸」は中国だという複眼思考である。
そして、進行中の朝鮮半島情勢が、混沌とした日清戦争前の状況に近づきつつあるとの認識だ。
2つ目は、我々は預言者ではないということだ。
将来を見通すときは1つのシナリオでなく、幅を持った複眼思考で将来を捉える必要がある。そして変化に応じプランAからプランBへ変化させていくことだ。その切り替えが難しい。
その視点から考えると1回目の首脳会談の最大の成果は、前哨戦たる北朝鮮対処一辺倒から、「本丸」中国対処に米国が本気になり、大きく舵を切ったことである。
米国が北朝鮮対処に忙殺されている間に、中国は2017年10月の中国共産党大会で、新たな目標を設定した。
これまで中国は、2020年までに東・南シナ海を排他的に支配し、2050年までに太平洋を2分割して米国から覇権を奪うことを目標としてきた。
その中間の2035年までに西太平洋における軍事覇権を確立するとの目標を設定したものであり、その意味するところは極めて重大である。
日本を「仮想敵」扱いして準備してきた韓国軍
自衛隊機へのレーダー照射は“突然の出来事”ではない
2019.1.30(水)
(古森義久:産経新聞ワシントン駐在客員特派員、麗澤大学特別教授)
韓国軍による日本の自衛隊に対する敵性のにじむ行動が波紋を広げている。実は韓国軍は伝統的に日本を脅威とみなす軍事強化策をとっており、米国から警告を受けた歴史がある。これは日本ではほとんど知られていない重要な事実である。
北朝鮮の軍事脅威が顕著な1990年代、韓国は北朝鮮に対抗する軍備として最も必要な地上部隊の強化を後回しにして、日本を仮想敵と見立てて海軍や空軍の増強に力を入れた。そして、その施策について米国当局から抗議を受けたという現実が存在するのだ。
今に始まったことではない韓国軍の反日姿勢
韓国軍が日本の自衛隊に対して挑発的な行動をとっている。現在日本では、その動きの理由として「一部の将兵が勝手に行動したのだろう」あるいは「日韓の政治的な対立のために韓国の一部の軍人が感情的となり、腹立ちまぎれに日本への威嚇的な動きに出たのだろう」という見方が多数派であるといえよう。
日本と韓国はともに米国の同盟国であり、近年の北朝鮮や中国の軍事脅威に備えて、米日韓三国で防衛協力する必要性が叫ばれている。そんな中で、韓国軍による日本の自衛隊機への危険なレーダー照射などが起きるのは、韓国軍が一時の感情に突き動かされて、過剰な反応へと走ってしまったのに違いない、という見方である。また、たまたま北朝鮮漁船と接触しているところを自衛隊機に見つけられたため、追い払ったのだという解説もある。
ところが、韓国軍部の反日姿勢は今に始まったことではない。韓国は、二十数年前から安全保障戦略や軍事面でも日本を仮想敵および脅威とみなして、対策をとってきた。韓国軍の反日姿勢には長い歴史が存在するのだ。
「中長期の日本の潜在的軍事脅威に備える」
その事実を、私自身がワシントン駐在の記者として書いてきた産経新聞の記事を通して紹介しよう。
まずは今から25年前、産経新聞の1994年12月5日の朝刊国際面に載った記事である。《韓国軍の空・海強化計画 「日本脅威」傾き過ぎ 米共和党 次期議会で調査開始》という見出しが付けられていた。
《【ワシントン4日=古森義久】米議会の共和党は、韓国軍の軍事能力強化の計画が日本を潜在的脅威と見立てた空、海軍の増強に傾きすぎている─として1月の次期議会で公聴会などを開き、本格的な調査を開始することになった。米議会側では、「韓国は在韓米軍と共同で北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)の脅威に備えるため、地上防衛軍の強化に最重点を置くべきだ」と主張しており、ウィリアム・ペリー国防長官も韓国が日本を仮想敵として中長期の防衛計画を立てている実態を認め、韓国側に抗議したことまで明らかにしている。
共和党筋が3日までに明らかにしたところによると、議会共和党は上院外交委員会などを中心に第104議会で、韓国軍の兵器調達計画などの調査を開始する方針を決めた。特に在韓米軍の任務に関連して、韓国の中長期の軍事計画が日本を潜在的脅威とみての増強に比重を置きすぎているとの認識に立ち、米国の防衛予算の使途という見地から下院予算委員会なども加わって公聴会を開くことも予定しているという。
米議会では、韓国軍の軍事計画の現状を「米韓共同防衛態勢のゆがみ」ととらえ、下院が今年(1994年)6月、「米韓共同防衛では北朝鮮の現実の脅威に対し、原則として韓国軍が地上防衛、米軍が空、海の防衛と責任分担が決まっている。だが、韓国軍は地上防衛能力になお欠陥があるにもかかわらず、その改善計画では費用の顕著な部分を地上防衛以外の分野に向けている」と指摘。その是正を目指すために、米国防総省に調査と報告を求める決議案を可決した。
この決議は「他の分野」として、(1)潜水艦(2)駆逐艦(3)高性能の航空機─をあげ、「これらの兵器は地上軍事能力の改善に役立たず、その分、米軍への負担が増す」としている。
この決議には、韓国がなぜ北朝鮮からの攻撃への対処に直接、有用ではない潜水艦などの増強に力をそそぐのかは明記されなかったが、その理由が主として中長期の日本の潜在的軍事脅威に備えるため─とされることは、米側の議会筋や朝鮮問題専門家が明らかにしている。
事実、今年5月にペリー国防長官がワシントンで朝鮮半島の安全保障について演説した際、議会調査局のアジア安保問題の専門家ラリー・ニクシュ氏から「議会では最近、韓国軍が日本からの仮想脅威に対処するため、空、海の軍事能力強化を優先させていることに批判がある。韓国側にその是正を要請したか」という質問が出た。
これに対し同長官は「確かにここ数年、国防総省も韓国軍のそうした(日本を仮想脅威としての)目的の兵器システム開発計画の不適切な優先順位に懸念を抱いている」と述べた。さらに同長官は、4月の韓国訪問では韓国側にその現状を抗議し、是正を正式に求めたことを明らかにした。
共和党議員には、米韓軍による「北朝鮮からの総攻撃に対しては北の中枢への通常戦力での大量報復」という抑止戦略が実効を失いつつあるとの認識がある。》
1994年当時、米国側はビル・クリントン政権、韓国は金泳三政権だった。金泳三政権自体は比較的安定していたが、ちょうどこのころ、北朝鮮の核兵器開発への動きが米朝関係を緊迫させるようになった。北朝鮮の軍事脅威が米韓両国に重大に認識されるようになっていたのだ。
ところがそんな時期であるにもかかわらず、韓国軍は北朝鮮との戦闘に不可欠の地上戦力を強化せずに、海軍や空軍の増強に力をそそごうとした。その動機は、日本を脅威とみる認識だった。
この歴史的な事実は現在の日韓関係の悪化をみるうえで重要な意味がある。韓国側の日本敵視はこれだけ根が深いのである。
WSJが伝えた米国政府の強い不満
日本を脅威と捉える韓国側の認識と、その認識に基づく防衛政策について、私は翌年(1995年)にもワシントンから同じ趣旨の記事を発信した。1995年1月19日の産経新聞朝刊国際面の記事である。見出しは《米、韓国の防衛政策に不満》で、内容は以下のとおりである。
《【ワシントン17日=古森義久】韓国の防衛が当面最大の脅威とされる北朝鮮地上軍よりも日本へ重点を置き軍事力整備が進められていることに対し、米国政府が強い不満を抱いていることが17日付の米紙ウォール・ストリート・ジャーナルの報道で伝えられた。
同紙はソウル発で米国の国防当局が同盟国の韓国の防衛政策に強い不満を抱いていることを報じた。この記事は「韓国国防省は長期の脅威としては北朝鮮よりも日本を恐れている」「米国政府当局者は韓国の北朝鮮への対抗戦闘能力を疑問視している」という見出しで、ソウルの韓国防衛関係者や在韓米軍当局者の説明を伝えている。
同記事によると、韓国軍当局は「360度防衛」の標語の下に長期の脅威としては北朝鮮よりも日本を第一に位置づける方針をとり、北朝鮮への抑止、防衛の中心となる地上兵力の強化よりも海軍、空軍の増強に重点を置く傾向が続いてきた。この政策の表れとして韓国軍は潜水艦、偵察衛星、駆逐艦などの調達に力を入れているという。
さらに同記事によると、韓国の同盟国として共同防衛にあたる米国としてはこの韓国の「日本脅威」戦略に明確に反対し、韓国軍が北朝鮮への防衛を在韓米地上軍に依存する度合いを減らすことを要請している。(以下、略)》
日本の防衛態勢を専門に研究する部門も
さらに私はこの記事に対して、「視点」というタイトルの短い解説記事を書いた。その記事は本体の記事と同じ日の紙面に掲載された。全文を引用しよう。
1
2
3
4
《【視点】韓国軍の空・海強化計画 「日本脅威」傾き過ぎ 対日認識屈折あらわ
米議会の共和党が韓国軍の日本を潜在的脅威とする増強計画に批判を強めたことは、韓国の安全保障面での屈折した対日認識に光をあてることになった。一方、米国側ではこの動きは共和党主体の新議会が同盟国との共同防衛の責任分担区分をより厳密に求める傾向を示したといえる。
米韓防衛関係を長年、研究する米海軍大学院のエドワード・オルセン教授は「想定可能のあらゆる事態に対応する軍事シナリオを考えるのが軍の任務だから、危険視する必要はないが、韓国軍が日本を将来の潜在的脅威、あるいは仮想敵として軍事対処を検討しているのは事実だといえる」と述べる。
別の米国軍事筋は、(1)韓国軍部には北朝鮮が現状の政体のまま続くのは10年未満とみて、朝鮮半島の統一、米軍の撤退という展望を踏まえ、日本が地域的に新たな軍事的脅威となるとの見方がある(2)韓国の国防省所属の国防研究院には最近、日本の防衛態勢を専門に研究する部門が新設され、女性研究者の宋永仙博士の下に専門家6、7人が勤務し、あらゆる事態を想定した机上演習をしている(3)韓国軍のドイツ製ディーゼル潜水艦の購入や、駆逐小艦隊の整備は日本の自衛隊に対抗するため(4)しかし近代兵器の調達には長期間を要し、調達は将来に備えてで、日本を目前の敵とみていることを意味しない─などと述べている。
ブッシュ政権の国家安全保障会議(NSC)のアジア担当官だったトーケル・パターソン氏は「日本を対象とするようにみえる韓国の兵器類の調達や開発には、防衛産業育成という側面も大きい」と指摘する。だが、日本といま安全保障面でも交流や連携を広げる韓国が、一方で長期の視点にせよ日本を潜在的脅威と認識しているとの屈折した側面があることは否定できない。》
ちらほらと見える「衣の下のヨロイ」
以上を、古い話だというなかれ。韓国はこんなにも前から日本を軍事面での脅威と認識してきたということなのだ。
そしてなによりも、2019年1月の現在、日本側の防衛省、自衛隊の複数の幹部たちの言によると、韓国軍の「日本潜在脅威認識」はいまも存在し、韓国の防衛態勢にはちらほらと「衣の下のヨロイ」が散見される、という。
この経緯をみると、最近の韓国軍の自衛隊機に向けての攻撃用のレーダー照射事件も、まったくの別の様相をみせてくるといえるだろう。
韓国を助けるな、教えるな、関わるな
古田博司氏に聞く「東アジア3カ国との付き合い方」
2015.4.4(土)
井本 省吾
日韓関係は冷却したまま。中国ともあつれきが絶えず、北朝鮮とは緊張関係が続いている。東アジア3カ国とどう付き合うべきか。左翼・リベラル派の政治家、マスコミ、研究者はもとより、保守派の政治家、外交官、ジャーナリストでも大方は友好関係維持が基本的な考え方だ。極力、対話を続け、譲るところは譲ることが日本の長期的な平和と安全につながる、という意見が多い。
だが、長年、朝鮮半島の歴史や政治を研究してきた筑波大学大学院教授の古田博司氏は「韓国に対しては『助けない、教えない、関わらない』を『非韓三原則』にして日本への甘えを断ち切ることが肝要」と説く。
助けても教えても恩を仇で返すのが彼の国の性格で、関わらないのが日本のためになるという。中国、北朝鮮に対してもほぼ同様に接するのが賢明だと主張する。
「『それでは日本はアジアで孤立する』などと恐れることはない。日本は多くのアジア諸国から支持されている。孤立しているのは東洋的専制国家の東アジア3カ国の方だ。ただ、韓国と手を切る戦略について日本の最大の同盟国である米国を納得させることが肝要だ」
こう主張する古田教授に、韓国を中心に東アジア3カ国との付き合い方を聞いた。
なぜ「非韓三原則」なのか
井本 「非韓三原則」を説く理由からお聞きします。
古田 助けてもロクなことがないから。教えても感謝せず、むしろ「ちゃんと教えない」などと難癖をつけてさらに要求してくる。
日本は幕末から明治維新にかけて初めて西洋に出会った、とよく言われますが、実は当時、東洋にも初めて出会ったのです。
何も知らないのに、自分も東洋人だから、東洋のことはよく知っていると思い込んでいた。それが間違いのもとだった。
明治期の朝鮮は驚くほど遅れた貧しい国家で、針一本作れない。木を丸くする技術もないので樽もクルマの車輪も作れない。染料がないので、衣服はすべて白衣でした。近世でも中世でもなく、古代に近かった。
清国(中国)は大国ではあったが、古代王朝の世界に沈潜していた。ウソ、ごまかし、裏切り、汚職が横行する。それが東洋であり、実は日本は東洋ではなかった。それなのに、東アジアの現実を何も知らず、「日本は東洋の国々と連携して西洋列強に対抗しなければならない」と考えるアジア主義が広がっていました。それは今でも続いていますが。
戦後は、戦前に中韓に迷惑をかけたという贖罪意識もあって友好第一ということになった。でも、援助しても教えても、反日運動は強まるばかり。プライドが高く、日本を見下しているからです。だから関わらないことが日本にとって一番なんです。
井本 では戦前、韓国を併合したのも間違っていた?
古田 いや、当時は帝国主義の時代でロシアの南下を防ぐために、朝鮮を確保せざるを得ませんでした。朝鮮半島をロシアに取られたら、日本列島まで攻め込まれる危険が大きかった。
井本 日露戦争に勝利した後、韓国を併合せずに独立させていれば韓国は日本に感謝し、その後良好な関係が続いたはずだ、という見方もありますが。
古田 それは当時の朝鮮の経済、社会状態を知らない人の意見です。古代のような貧しい朝鮮は清国の属国として全面依存しており、とても独立できるだけの経済・社会基盤はなかった。朝鮮の国庫は空だったのです。
で、日本は対ロ防衛のために朝鮮を近代化させる必要があった。莫大な投資をして教育水準を高め、民生を向上させねばならなかった。その負担が大きすぎ、日本の朝鮮経営は大赤字が続きました。
日韓通貨スワップ協定も平昌オリンピック支援も必要なし
井本 後知恵ですが、それならロシアとは戦わず、朝鮮併合もせず、日本海側の防備だけを固めておくという政策もあったのではないか。ロシアに朝鮮を支配されたとしても、ロシアは朝鮮経営に足を取られて疲弊し、日本に攻め込む余力はなかったかもしれません。
古田 当時は帝国主義の時代ですよ。ロシアには奴隷制の歴史もあり、囚人をシベリア送りにする国でした。面倒なことになるなら、朝鮮人を農奴にするだけのことです。朝鮮民族を全滅させる方法を取ることもできた。インカ帝国などはそうして滅びたではないですか。民族の征服、滅亡があちこちで起こっていた時代です。
井本 なるほど。話を元に戻すと、2月に金融危機の際に外貨を融通し合う日韓通貨スワップ協定が終了しましたが、韓国の金融事情には不安があり、イザというときは韓国が協定復活を頼みこんでくる可能性があります。これも助けない方がいいと・・・。
古田 韓国は日本の金融支援に対し感謝しないどころか、韓国の金融危機は日本に原因があったような言い方をする。恩を仇で返し、同情すると、すぐにたかってくる国です。関わらないに越したことはない。
韓国が通貨協定終了で強気なのは、イザとなれば中国に助けてもらえると考えているからでしょう。中国も今はその構えですが、でも、そうなれば中国が韓国にたかられ、韓国は中国に首根っこを締め上げられる関係になります。だから、こちらは傍観していればいいんです。
井本 2018年冬の平昌(ピョンチャン)オリンピックも経済面、運営面で準備不足と言われ、日本の支援を求めてくるとも予想されています。
古田 助けてはなりません。支援してもオリンピックが円滑に運ばないと、日本のせいにされるのが落ちで、少しも日本のプラスになりません。2002年のサッカー・ワールドカップの日韓共催でも、いろいろ苦い思いをさせられたではありませんか。
井本 慰安婦問題で朴槿恵(パク・クネ)大統領は「日本が誠意を見せなければ首脳会談はできない」と言い続けていますが。
古田 これこそ日本は日韓基本条約で解決した問題だとする従来の毅然とした態度を貫くべきです。どんなに譲歩しても必ず、まだ誠意が足りないと言ってきます。今の韓国は反日が国是で、日本に謝罪を続けさせることが、自らの政権維持につながるからです。
韓国の中国接近は必然
井本 古田さんは雑誌「WiLL」2月号で元外交官でキヤノングローバル戦略研究所研究主幹の宮家邦彦氏と対談しました。宮家氏は「(韓国が日米韓の枠組みを離れ)中国に寄り過ぎないように牽制する必要がある・・・そのためには(日本は)韓国と付き合っていかなければならない」と強調しています。これに対し、古田さんは「無駄でしょうね」と応じています。
古田 韓国は中国との貿易が最大となり、経済的に弱体化していることもあって中国への経済依存がどんどん強くなっています。地政学的、歴史的な経緯もあって中国にすり寄らざるを得ない状況です。
また、韓国は民主的な政治体制が崩れ、強権政治になりつつある。独裁体制の北朝鮮と似てきています。
朴大統領の任期は2018年2月まで。急速に人気が衰えていることから、それ以前に大統領の座を追われる可能性もあるが、いずれしろ、今の情勢では次期大統領は最大野党である新政治民主連合になるでしょう。
こちらの方が、文在寅(ムン・ジェイン)代表や、朴元淳(パク・ウォンスン)ソウル市長など、人材がそろっています。
2人とも確信犯的な親北朝鮮派です。すると、金大中(キム・デジュン)、盧武鉉(ノ・ムヒョン)時代のように北朝鮮に資金援助するようになり、両国はもっと近づいていくでしょう。これに、中国も加わって3国連合になっていく可能性が高い。だから、日本がいくら韓国に接近しようとしても無駄な努力に終わると見ているのです。
井本 北朝鮮が金正日(キム・ジョンイル)氏の元側近で中国と近しかった張成沢(チャン・ソンテク)氏を処刑して以来、中国と北朝鮮の関係は冷却化していますが。
古田 中国は重油の対北朝鮮輸出を止めていますが、石油精製品の輸出は増やしている。そういう馴れ合いがあるんですよ(笑い)。関係が悪化しても中国が北朝鮮を経済的な支配下に置く関係は変わってません。
井本 南北朝鮮が一緒になり、中国が両国を支配するようになったら、強大な専制国家が誕生し、日本の平和と安全保障が危うくなるという見方についてはどうですか。
古田 それほど心配する必要はありません。まず北主導の南北統一はあり得ない。韓国は北朝鮮に従属するなんて関係を認めません。
井本 でも、次期大統領の有力候補は親北派で、韓国民の多くも北朝鮮になびいているのでしょう。
古田 それは1990年代以降、北朝鮮の韓国への思想工作が奏功したこともあって「北朝鮮は抗日戦争の結果、誕生した。歴史的正当性を持っている」と多くの韓国民に思われているからです。戦ったと言っても日本の討伐隊に追われて極東ソ連領に逃げ込むような状況でしたが、戦ったことは間違いない。
一方の韓国は米軍に解放されたのであって、自ら独立を勝ち取ったわけではない。だから対北朝鮮コンプレックスがある。「北の方が立派なんじゃないか」と。
しかし、経済も軍事も韓国の方が格段に優位。韓国民は自分たちの方が上だというプライドも強い。だから、韓国が北朝鮮に支配される形の南北統一はあり得ません。
井本 北朝鮮は核兵器やミサイルを持っていますが、朝鮮半島が日本にとって危険な国家に統一されることはないと?
古田 北が核兵器やミサイルを保有していると言っても、それだけのこと。米国と軍事同盟を結んでいる日本に攻め込むなどということは考えられませんね。
中国による朝鮮半島支配は恐るるに足らず
井本 でも、中国が朝鮮半島を飲み込む形で支配すれば、日本への脅威が増すのではないですか。
古田 中国は経済的、政治的に朝鮮半島を支配下に置いておけばいいんです。領土として欲しいわけではない。また、朝鮮が政治的に南北統一されるのはいいけれども、DMZ(38度線・非武装中立地帯)がなくなるのは困るのです。
朝鮮半島は北東側に険しい山脈がありますが、西側はほとんど平坦な土地で、いわば「廊下」です。中国の遼東半島から平壌(ピョンヤン)、ソウルを通り半島南西部の海岸まで抜ける廊下。だから、朝鮮戦争では一度韓国軍が半島南部まで一気に追い詰められたものの、南から米軍が上陸し「廊下」を伝わって、これまた一気に押し戻した。これに中国があわてて、参戦してきた。
地政学的に言って、朝鮮半島は中国の弱点なのです。歴史的にも北からモンゴルなどに攻め込まれています。弱点を補強するにはDMZを保持し、廊下に壁を作る必要がある。だから、中国は南北統一があっても38度線が残るように、1国2制度のような形を支持する可能性が高い。
連邦形式にして北、南双方の自治権を残す。この仕組みは北朝鮮、韓国双方にとっても都合がいい。結果として韓国が緩衝地帯となるので、米国にとっても悪くない。だから、中国は「中国優位のもとで南北連合はするけど、1国2制度にして38度線は置いておくという線でどうか」と、米国と交渉するかもしれない。
井本 それは日本にとってもいい?
古田 そうです。第一、中国主導の朝鮮統一が実現したとしても、強大な統一国家にはなり得ません。一緒になったら、朝鮮半島では必ず南北双方で仲違いを起こすとともに、両者で別々に反中国運動が起こります。
歴史的に朝鮮は中国に従属し、様々な経済援助を受けながらも、いろいろと文句をつけ、難題を吹っかけ、もっと援助を寄越せと注文するなど、ゴタゴタが絶えなかった。中国、北朝鮮、韓国の三つ巴の内部争いが続き、疲弊し、日本に脅威を与える余力などほとんどでてきませんね。
だから、3国連合を不安視することはない。ほっておけばいいのです。韓国が中国側に行くように積極的に仕向けて一緒にし、その後のゴタゴタで双方を疲れさせるようにするぐらいでちょうどいい。
井本 米国は東アジアの緊張が高まるのを懸念し、「韓国と仲良くしろ。慰安婦問題なども譲歩せよ」と日本に圧力をかけてきています。
古田 日本政府は韓国の問題点を具体的に米国に説明すべきです。
第1に、韓国は日本の領土(竹島)を奪い、日本を仮想敵国として軍事演習を行っている。第2に、韓国は日本の元首(天皇)を侮辱し、邪悪な対日敵対宣伝行為を全世界的に繰り広げている。
第3に、日韓基本条約など国際的な基本条約、協定を反古にする韓国の司法に政府が加担し、三権分立を悪用するのみならず、反日の過去訴求法を実施し、自由民主主義に反する国民弾圧を行っている。
その上でマーク・リッパート駐韓米国大使がソウルで暴徒に襲われ、大けがをした例を示しながら「韓国は法治国家でなく、日米と共通の価値観もない。助けるは必要ない」とはっきり言えばいいんです。米国も最近は自分勝手で一方的に甘えてくる韓国に嫌気が差してきている。軍事予算を削減する必要もあって、駐留韓国軍は早く撤退させたいとも考えています。
ただ、中韓が結束したら困るとも思っている。だから、「結束してもすぐに仲違いを始めるから心配する必要はない、歴史的にそうだった」と、米国を説得すればいいんです。
井本 先ごろ、外務省はホームページで韓国に関する記述のうち「我が国と自由と民主主義、市場経済等の基本的価値観を共有する」という項を削除しました。
古田 あれは産経新聞の前ソウル支局長を起訴して出国禁止にするなど、およそ民主国家にあるまじき行動があったことなどが原因です。もっとも、あの削除程度では韓国は動じないでしょう。
ただ、安倍晋三首相が昨年7月に「朝鮮半島有事の際、日本の基地にいる米軍を出動させるには日本の了解が必要」とした発言は、かなり韓国に利いたと思う。韓国はこれまでどんなに日本にひどい態度をとっても、必ず最後は助けにくると、日本に甘えてきた。米国の要求もあり、日本は韓国を助けざるを得ないはずだと。
安倍首相はこれに対し「常に助けるわけではない、韓国次第だ」と暗黙に歯止めをかけたことになる。適切な発言ですね。
安倍首相の戦後70年談話も米国重視が基本
井本 安倍首相と言えば、夏に発表する戦後70年談話にも、戦争の反省などについて海外の注文がついています。
古田 中韓は何を言っても文句をつけてきます。だから、無視すればいい。問題はやはり米国で、米国が納得する形での談話にする必要があります。基本は日米同盟です。
今、軍事的にも危ないのは尖閣諸島ですね。あそこは石油ルートの要だし、中国海軍が西太平洋に出るための要衝で、中国が支配しようと狙っている。でも、日米同盟が万全ならば恐れることはない。このため、安倍政権が集団的自衛権の行使容認に踏み切ったことは適切でした。
井本 貿易など中韓との経済的な関係はどうするのですか。
古田 今まで通り、続ければいい。ただし、過去に迷惑をかけたからなどと変な贖罪意識を持って、こちらが損するような技術・金融支援は一切、行わないこと。つけ込まれて要求水準を高めてきますから。双方が納得いくギブ&テイクの取引を淡々と進めることが肝心です。
レーダー照射:中国のGPSを搭載していた
秘密の詰まった工作船が日本に拿捕されるのを恐れ韓国に救援依頼
2019.2.14(木)
西村 金一
韓国が、海上自衛隊哨戒機に火器管制レーダー波を照射したこと、韓国国防省がしつこく日本批判を行ったのは、不可思議なことだった。
まして、あのような小さな北朝鮮の木造船を救助するためだけに、軍事作戦を行う軍艦と不必要に大型の警備艇を派遣したことは極めて不自然である。
しかも、これらの行動は、北朝鮮と韓国の近海で行われたものではなく、そこから遠く離れた日本の排他的経済水域内で行われたのだ。
その海域で、その3隻が一か所に集まったことは、最近まで敵対関係にあった南北の軍事関係からは、全く考えられない。
私はこれまで、防衛省自衛隊で我が国周辺諸国の軍事情勢を分析してきた。その長い経験でも、このような特異活動を聞いたことがない。今回が初めてだ。
また、韓国国防部(省)隷下の海軍駆逐艦、韓国水産部隷下の海洋警察警備艇は、指揮系統が全く異なる。
それらが緊急に派遣されたことは、文在寅大統領本人か、あるいは政権内部の実力者が命令しなければ実施できない。
韓国は、なぜ、日本海でこのような理に合わない不可思議な行動を行ったのだろうか。
例えば、木造船を含めた今回の行動の詳細を、日本の哨戒機に絶対に見られたくなかった。日本の巡視船を介入させたくなかった。木造船が捕まり日本に連行させたくなかった。海流の流れに任せて日本に漂着させたくなかった・・・。
つまり、日本に知られたくなかった理由があったと考えられる。
防衛省が発表した動画「 韓国海軍艦艇による火器管制レーダー照射事案について 」より
そこには、「絶対に隠さなければならない、渡してはいけない重大な秘密」があったと考えざるを得ない。
韓国は、海上自衛隊の哨戒機を韓国の軍艦に近づかせないために、哨戒機の正常な飛行を、「威嚇飛行だ」と非難し続けている。
「北朝鮮に頼まれてなぜやったのか」という意図を読まれないように、軍事常識では考えられないことを言い続けて、争点をすり替えているのだ。
特殊工作船とみて間違いない木造船
韓国国防省が1月4日に公開した動画に映っている木造船を詳細に見ると、北朝鮮の木造漁船の中でも比較的大型のものだった。
前方と後方にイカ漁には必要ではない高いポールが立っており、AM通信(モールス通信)用と見られるケーブルが張られている。
日本の海岸に漂着している木造船には、このような高いポールがあるのは、極めて少ない。このアンテナを展張するAM通信には1000キロを超える通達距離がある。
長距離通信用の通信装置を保有しているのは、北朝鮮本土から遠く離れて行動する工作機関か特殊部隊の船に限られる。
この木造船は、2001年九州南西海域で、海上保安庁に追跡され、自爆して沈没した工作船とは全く違う。
沈没した工作船は、その後、海中から引き揚げられて詳細に分析されたわけだから、北朝鮮が別の形をした工作船を建造していても当然のことだ。
AM通信を使えば、燃料がなくても人力で発電し通信できるものもある。漂流していても本国への連絡が可能だ。
木造船の乗組員は、衛星測位システム(米国のGPSに類似したもの)を使って確認できた自己位置(座標)を本国に送信して、救助を依頼した可能性が高い。
そうでないと、他の船が救助に来てくれる可能性はほとんどない。
船の位置を確認できたこのシステムは、昨年12月に全世界で運用を開始した中国の北斗衛星測位システムの可能性がある。
とすれば、中国が国連制裁決議違反をして北朝鮮に輸出したことになる。
工作機関の船には、どのような秘密があるのか。
海上保安庁に追跡された工作船は逃げ切れず、工作活動の秘密を守るために、自爆して自らの命を絶った。
もし、その工作船が爆破されずに捕獲されていれば、工作機関や拉致に関する多くの情報が得られたであろう。
工作船には、工作員が命を絶っても守らなければならない重大な秘密の塊がある。
工作機関や特殊部隊の兵士が生存して、積載している通信機器・暗号書およびその他工作にかかわる機器・資材が、無傷のまま日本に漂着すれば、ここから得られる情報で、工作活動の全貌が判明する可能性がある。
日本人拉致被害者の情報も、捕まった工作員から入手でき、これまで謎だった事象が、ジグソーパズルの1個のピースが埋まるように解明できるかもしれない。
日本海で漂流していた木造船が工作機関の船であれば、日本に無傷のままに渡してしまうと、工作機関の秘密を世界中に広められることになる。
工作活動の公開がトリガーとなって、米朝会談も破談になり、金正恩政権が崩壊することもあり得ないことではない。
韓国も木造船を日本に渡したくなかった
哨戒機が撮影した映像を見ると、この木造船は、韓国の駆逐艦と警備艇に挟まれ、その内側では、2隻の小型の救難艇にも挟まれていた。
逃亡を防止するために、軍艦と警備艇が2重に包囲する態勢を採ったという説もあるが、小型の木造船がスピードを出せる特殊なエンジンをつけていたとしても、韓国の大型艦から逃亡することは不可能だ。
逆に、日本の護衛艦や海上保安庁巡視船を絶対に近づかせない態勢を採ったとする見方の方が理にかなう。
韓国に依頼してでもこれほどの秘密情報が一杯詰まった工作船と見られる船を、みすみす日本に渡すことは絶対に食い止めなければならないと、北朝鮮が考えても不思議ではない。
亡命阻止の可能性はあるのか
金正恩政権の要人が亡命しようとしたのであれば、北朝鮮は韓国に依頼してでも阻止したいと考えるのは当然のことだ。
だが、木造船の乗員が亡命を実行しているのであれば、船が移動している地点を秘匿するだろう。わざわざ捕まるために自分の位置を伝えることはしない。
また、その船が電波を発しなければ、誰もその位置を特定することはできない。鋼船ではないので、海上捜索レーダーには映らない。
木造船の位置が特定できなければ、韓国の2隻の船は、広大な日本海でその木造船を発見することは、不可能に近い。私がかつて情報分析官であった頃の経験から断定できる。
あの木造船には、極めて重大な秘密や謎がある「秘密性の高い工作機関の船」だと想像できる。
それならば、南北融和が進む南北のトップが協力して日本に漂着することを阻止しなければならないと考えるのが妥当であろう。
南北の融和的な動きは、朝鮮半島ばかりではなく、半島から遠く離れた日本の排他的経済水域内でも起きている。
木造船を巡って南北が奇妙な連携行動を行っていることに注目すべきだ。
文政権と金正恩政権の間で、南北統一の企みが、公開されていないところで着々と進んでいることに目を向けるべきだろう。
レーダー照射:韓国の強気の背景に軍事力
北朝鮮から日本向けに軍事力を転回し始めた韓国
2019.2.4(月)
矢野 義昭
最近、いわゆる徴用工(歴史的事実によれば「戦時契約労働者」と呼ぶのが正しい)問題や海上自衛隊機に対するレーダ照射事件など、韓国の日本への無法無謀な態度に対し、嫌韓意識が日本の国民の間で高まっている。
そのあまり、韓国何するものぞといった、韓国の力、特に軍事力を侮る傾向も一部にはみられる。
韓国の文在寅(ムン・ジェイン)政権は日本に対し、過去の国家間の公式的な約束を無視し、平然と虚偽を言いつのり、明らかな証拠を突き付けられても認めず、逆に責任を転嫁してくるといった、対応を取り続けている。
文政権の、国際法も無視し司法の独立も顧みない姿勢は、とても近代法治国家とは言えない。
韓国の国家としてのこのような姿勢に、愛想を尽かし、突き放し、あるいは敵愾心をむき出しにしたくなる気持ちも分からないではない。
しかし、このような感情的な対応を取る前に、日韓が決定的に決裂し敵対関係になった場合に、日本が直面するバランス・オブ・パワーの激変とそれがもたらす危機の様相もよく考えてみなければならない。
高まる朝鮮半島全土が大陸勢力に支配される怖れ
古来、朝鮮半島は我が国にとり、大陸勢力の日本に対する侵略の根拠地となり得る、地政学的要域であった。
その本質は現在もいささかも変わってはいない。今また、朝鮮半島全土が大陸勢力の支配下に入り、我が国の安全を脅かす脅威になりかねない情勢になっている。
米朝間の非核化をめぐる交渉は、米朝首脳会談後も実質的には何も進展していない。
にもかかわらず、文在寅政権は、『板門店宣言軍事分野履行合意書』を昨年9月に採択、実質的な韓国側の休戦ライン沿い地帯の武装解除に等しい措置を、陸海空ですでに実行に移している。
他方で、昨年12月の海上自衛隊機に対するレーダ照射事件では、韓国国防部の当初の発表を翻して、韓国政府はレーダ照射を否定し、日本側が低空飛行を行ったなどと、事実と異なる主張をし、日本に責任を転嫁しようとしている。
国家としての日本に対する敵対意識を、公然と明示したに等しい。
このような事態に至れば、現韓国政府と交渉を続けても実効性のある成果が得られるとは期待できない。
我が国としても、軍事的対応も考慮しなければならなくなり、韓国を敵性国とする前提で防衛諸計画なども見直さねばならないであろう。
冷静に比較考慮すべき軍事的バランス・オブ・パワー
しかし防衛諸計画の策定において最も重要な点は、彼我の相対的な戦力バランスを考慮したうえで、与えられた資源で達成可能な目標を選定し、合理的な方法でその達成を図らねばならないという点である。
感情論や願望で防衛諸計画を論じ、それに基づき行動すれば、戦う前から敗れているに等しい。
最新の『平成30年版防衛白書』によれば、日本の陸上自衛隊は14万人、韓国の陸上兵力は海兵隊2.9万人も含め51.9万人、その比率は韓国軍が3.7倍の優位にある。
海軍については、海上自衛隊が135隻48.8万トン、韓国海軍は240隻、21.5万トンである。韓国は隻数では1.78倍あるが総トン数では0.44倍の劣勢である。
空軍の作戦機数については、航空自衛隊と海自の固定翼作戦機を含め400機、韓国が640機と、1.6倍の優勢である。
質的な面も考慮すれば、日本側は地上兵力では劣るとしても、海空軍は優勢であり、韓国軍にとり、着上陸侵攻により我が国の国土の一部を占領確保することは容易ではないと思われる。
しかし、問題は戦い続ける継戦能力にある。日本の予備自衛官定員数は平成30年3月末現在で、4万7900人に過ぎない。
日本には強制力を伴った物資・輸送などの役務・エネルギー・施設などの動員制度もない。装備品の緊急生産能力、武器・弾薬の備蓄も限られている。
他方の韓国は、陸軍21カ月、海軍23カ月、空軍は24カ月の兵役期間があり、その後8年間は「予備役」となり、それから40歳までは「民防隊」として服務することが義務づけられている。
1990年時点で予備役と民防隊の総数は350万人以上に達した。予備役の総数は1990年時点で陸海空を合わせ約124万人が登録されていた。
韓国では、人員だけではなく、物資、エネルギー、産業、施設なども徴用や動員の対象になっている。
日本にはこれらの制度は欠けており、有事に国家の総力を挙げて対処できる体制にはなっていない。韓国国民は冷戦期にもその後も、このような兵役やその後の長い予備役などの勤務の負担に耐えてきた。
そのような国防のための忍耐や努力を、日本国民は怠ってきた。韓国軍を侮る前に、日本自らの無策と怠慢を恥じ、真剣な国防努力に取り組むべきであろう。
南北朝鮮が一体化した場合のおそるべき脅威
さらに、韓国の矛先が、現在すでに兆候が見られるように、北朝鮮と一体となって日本に指向されたらどうなるのであろうか。
そうならないように、特に韓国国内の保守派の台頭や次期政権の保守化に期待し、韓国側の変質を待つ、あるいはそれを促す外交や政治面での努力は今後も継続すべきであろう。
しかしそれでも、米国の同盟国として信頼でき安定した、かつての韓国が復活する保証はない。最悪の事態にも同時に備えておかねばならない。
北朝鮮は『平成30年版防衛白書』によれば、陸軍110万人、海軍780隻11.1万トン、作戦機550機を保有し、兵役は男性12年間、女性7年間となっている。
装備は旧式が多く、大型艦と第4世代機が主の韓国軍よりも劣っている。ただし、少数ながら52機の第4世代機も保有している。
北朝鮮は、約20万人の特殊部隊、70隻の小型潜水艦、約140隻のエアクッション艇、小型輸送機「An-2」、サイバー部隊などの非対称戦力の整備に力を入れており、その脅威は侮れない。
また、北朝鮮が、40~60発以上の核兵器とその運搬手段である約1000発とみられる各種の弾道ミサイルを保有するまでに至り、日本や韓国にとり深刻な脅威になっていることも明らかである。
さらに、米本土に届く大陸間弾道ミサイルも数基程度保有しているとみられ、米国が米朝首脳会談に応じた背景となっている。
韓国の軍事力、特に核ミサイル能力も向上している。2017年11月7日、トランプ大統領と文在寅大統領は、韓国のミサイルの弾頭重量に制限を設けていたこれまでのガイドラインを廃止することで合意している。
その結果、韓国の弾道ミサイルの弾頭重量と射程に関する制約が解かれ、韓国は2017年4月には射程800キロの「玄武2」弾道ミサイルの発射試験に成功し近く量産に入ると報じられた。
また、射程1000キロの「玄武3」巡航ミサイルを開発配備している。
韓国は現在、国産の大型潜水艦に弾道ミサイルを搭載しようとしている。2025年頃には、射程800キロ以上の弾道ミサイル10基以上を搭載した、国産大型潜水艦が就役するかもしれない。
また2017年11月8日に韓国大統領府関係者が、同年9月の米韓首脳会談で、原子力潜水艦の導入に米韓首脳間で原則合意があったことを明らかにしている。
世界有数の原発大国である韓国の原子力開発に対する潜在能力は高い。
2017年10月31日に韓国ソウル大学原子核工学科の徐教授は韓国国会外交統一委員会で、韓国国内の原発の再処理されていない使用済み核燃料から、核爆弾約1万発分に相当する50トンのプルトニウムが抽出可能と述べている。
韓国は1970年代から80年代に秘密裏に核兵器開発を試みており、いまも核兵器開発の潜在能力は北朝鮮より高いとみられる。
米韓原子力協定交渉で韓国は、日本並みにウランの濃縮とプルトニウムの抽出を認めるようにかねて米国に要求してきた。
2004年には韓国の科学者が、国際原子力機関に報告せずに核物質を再処理したことがあり、韓国がプルトニウムの抽出技術を保有していることは明らかである。
このような韓国の潜在能力と北朝鮮の実績が一体となり、核ミサイルが本格的に増産され、さらに陸上兵力百数十万人、予備役数百万人、海軍20数万トン、作戦機700機以上を保有する軍事大国が対馬海峡の対岸に出現する可能性もある。
その時に日本は同時に、統一朝鮮の背後に控える中国や、日本の窮状につけ入ろうとする北のロシアの脅威にも対処しなければならない。
その頃には台湾も、実質的に大陸に政治的に併合されている可能性もある。日本は朝鮮半島、南西正面、北海道の3正面から包囲され、四面楚歌の状況に追い込まれかねない。
日本国民に求められる覚悟と備え
文在寅政権は、このような将来のバランス・オブ・パワーの変化を見越し、優位になるとみている北朝鮮や中露などの大陸勢力側にすり寄ることで、国民がいまだに太平の夢に酔い国防努力を怠っている日本を、恫喝や侵略により屈服させて隷属国扱いにできるとみているのかもれない。
韓国がいま日本に対し、居丈高な姿勢を取っているのは、文政権がそのような見方に立っている表れとみることもできよう。
いずれにしても日本にいま求められていることは、防衛費を対GDP(国内総生産)比で2%以上にするなど、少なくとも世界標準並みに真摯な防衛努力を行い、隣国から侮られない自立的防衛力を早急に作り上げることであろう。
同盟関係も自立的防衛力なしには成り立たない。
米国が今後、在韓米軍を削減あるいは撤退させる可能性は否定できない。ドナルド・トランプ大統領は、米朝首脳会談後の記者会見でも、「今はまだその時ではない」が、将来はあり得ることであり、「望ましい」と述べている。
米国は米国の国益に基づき行動するのであり、日米の国益は常に一致するわけではない。また、ともに同盟国である日韓間の対立に際し、米国が日本側に立つとも限らない。
さらに、統一朝鮮と中国、場合によりロシアまで敵に回して、日本の危機に際し即時に日本の期待する規模の米軍を派兵してくれるという保証もない。
新しい『日米防衛協力のための指針(新ガイドライン)』では、日本の防衛は自衛隊が「主体的に実施する」ことになっている。米軍は自衛隊を「支援しおよび補完する」立場にある。
日本は、バランス・オブ・パワーを回復し、韓国のみならず周辺国から侮られることのない、侵略すれば相応の損害を被ると確信させられる確固とした抑止力と、有事にも戦い抜き、勝利できるだけの反撃力、継戦能力も含めた、実のある戦力を早急に構築しなければならない時にきている。
そのためには、何よりも日本の国民自らに、韓国やその他の国々と同様に、国家の安全と独立を守り抜くために応分の犠牲を払い、必要とあれば国防のために献身し協力する覚悟が求められている。
その覚悟を欠いた国家、国民を、同盟国が血を流して守ってくれると期待する方が間違っている。
「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」国家国民の安全と生存を保持できるなどということは、歴史の示すところによれば、もともとあり得ないことである。自力による抑止と対処しか、敵対的な侵略者を確実に食い止める方法はない。
自力自助なしには同盟も機能しない。この歴史的真実を我々は直視しなければならない。
韓国の対応に怒る前に、まず自らを冷静に省みるべきであろう。
★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★
バブル崩壊後の日本経済の「失われた30年」
★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★
小泉が派遣法の改正をしたおかげで、大部分の正社員の仕事が派遣に置き換わってしまいました。日本中にフリーターが激増してしまったのも、この男のせい。
小泉内閣時代の内閣ブレーンの一人で、経済と金融の大臣を兼任し、それまで3度、政府閣僚に選べられています。その後も諮問会とか委員会によく政府から呼ばれている人ですね。
慶應義塾大学総合政策学部の教授で、学歴も相当なもの、人材派遣業のパソナグループの会長でもあります。他にかなりの役職を受け持つ、まぁ多忙な人ですね。
2008年には韓国政府のアドバイザーとして顧問団に迎えられたり、小泉時代に総務大臣兼郵政民営化担当大臣に登用されて、郵政民営化推進で、自民党内部からも猛批判を受けた人です。
政策は
・所得税の最高税率を引き下げ(所得1000万円まで累進課税とする)
・解雇規制を緩和する
・同一労働同一賃金の法制化
・民間でできることは民間へ
以上は実現できていないか、あるいは骨抜きって感じで、多くは自民党内部の反対で押し切られていたみたいですね。
発言としては、財政悪化の要因は国債発行の乱発で日本の財政寿命は約3年とか、若者に自由を謳歌してもいいが引き換えに貧しくなるのも自由だ、頑張って成功した人の足を引っ張るななどがあります。
また格差社会の要因の一つは正社員という特権であるということもテレビで発言してますね。
平蔵を国賊と言ってる人たちは、恐らくバブル崩壊以後の失われた20年(30年?)の時代に、あまり良い事がなかった人が、非正規雇用を生み出したのは竹中のせいとか、自己責任ばかりが横行したのは平蔵のせいだ!と思っているからでしょうね。
また「時間内に仕事を終えられない、生産性の低い人に残業代という補助金を出すのはおかしい」と、まぁ私は定時に帰れという意味で、労働者の質の問題に触れていると思うのですが、これを悪く取る人もいたようです。
比較的合理的な理論で押し切るタイプの人ですが、やっぱり学歴・職歴が凄いのと、ズバズバ歯に衣着せぬ物言いの人なので、ものすごく好き嫌いが別れる人ではあると思います。特に既存の経済評論家や保守派の人には相当嫌われているようで。
人材派遣法の歴史は?
日本における派遣法の歴史
派遣法が施行されたのは、1986年7月1日です。 しかし、それ以前から人材派遣のようなことをしている会社は存在していました。 1980年代に入って雇用される労働者が増え、また業務請負という形態で派遣していたため、労働者保護の観点から派遣法が施行されることになったのです
労働者派遣法の歴史 荒井大
【派遣法の歴史】
[1985年(中曾根内閣)]
派遣法が立法される。
派遣の対象は「13の業務」のみ
[1986年(中曾根内閣)]
派遣法の施行により、特定16業種の人材派遣が認められる。
[1996年(橋本内閣)]
新たに10種の業種について派遣業種に追加。合計26業種が派遣の対象になる。
[1999年(小渕内閣)]
派遣業種の原則自由化(非派遣業種はあくまで例外となる)
この頃から人材派遣業者が増え始める。
[2000年(森内閣)]
紹介予定派遣の解禁。
[2003年3月(小泉内閣)]
労働者派遣法改正
例外扱いで禁止だった製造業および医療業務への派遣解禁。専門的26業種は派遣期間が3年から無制限に。
それ以外の製造業を除いた業種では派遣期間の上限を1年から3年に。
[2004年(小泉内閣)]
紹介予定派遣の受け入れ期間最長6ヶ月、事前面接解禁。
*鳩山政権による派遣法改正の動き*
1、製造業への派遣を原則禁止(常用型を除く)
2、日雇派遣、2か月以下の労働者派遣を禁止
3、登録型派遣の原則禁止(専門26業種を除く)
登録型…仕事がある時だけ雇用契約を結ぶもの。
常用型…仕事がなくても給料がもらえる(雇用契約を結べる)。
労働条件・労働基準めぐる法改正情報
http://labor.tank.jp/r_houkaisei/
派遣法 なぜ でき た?
もともと、労働基準法第6条で中間搾取の禁止が定められていますが、その規制を緩和する意味で制定されたのです。 労働者派遣法は、派遣事業の適正な運営と派遣労働者の雇用の安定、福祉の増進を目的としています。
派遣はいつから始まった?
日本の人材派遣の歴史は、1986年に「労働者派遣法」が施行されたことで始まり、これまで世の中の情勢にあわせ、何度も改正がなされてきました。
派遣法1999年の改正は?
1999年:対象業務が原則自由化となる(ネガティブリスト化) 規制緩和の波はさらに強く押し寄せ、適用対象業務の原則自由化(禁止業務のみを指定するネガティブリスト化)が実現。 一方で、建設、港湾運送、警備、医療、物の製造業務が禁止業務とされます。
人材派遣業の儲けの仕組み
人材派遣会社では、自社で雇用する派遣社員の労働力を派遣先の企業に提供することで「マージン」を上乗せした報酬を得ることで利益を出しています。 このシステムから、人材派遣業は「ピンハネ業だから楽して儲けている」などと揶揄されることがありますが、実際にはそれほど大きな利益があるわけではありません。
有期雇用派遣社員として働ける期間は最大3年
これは、2015年の派遣法改正により定められた内容です。 以前は派遣期間に制限はなく、派遣社員として長期間同じ部署で働くことができましたが、2015年の派遣法改正により「働けるのは3年間だけ」というルールに変更されました。
すぐに辞めてしまう理由
派遣で来た方がすぐ辞めてしまう主な理由としては次のようなことが考えられます。
仕事内容に馴染めない(未経験者が作業の手順や方法を理解できない)
職場に馴染めない(社内での決まりごとや雰囲気など)
地域や環境に馴染めない(他の地域から働きにきた場合など)
困ったことを相談できる人がいない(職場トラブルや将来のキャリアプランなど)
事前の研修や、就業後のフォロー体制などがない派遣会社だと、就業の前と後でのギャップが生じてしまい、「馴染めない…」と感じる機会が多くなります。
また、相談に乗ってくれる人がいないことで、不安や不満が退社に直結してしまうのです。
最初はほんの小さな「嫌だな…」と思う気持ちから始まったとしても、誰もフォローしてくれないために次第に勤務から足が遠のいてしまい、無断欠勤を続けた結果、そのままフェードアウトする。
派遣社員 何が問題?
単調な仕事や、いわゆる「誰でもできる仕事」を任されるため“やりがい”は生まれにくい特徴があります。 また仕事のやり方や方針に対して基本的に口を出すことができないため、働くことのモチベーションは維持しにくいでしょう。 なぜならそれが「派遣社員」の本質だからです。
派遣 時給上がった なぜ?
派遣は正社員と待遇が異なり、実際に働いた時間分のお金しかもらうことができません。 ボーナスや昇給などは基本的になく、企業によっては交通費の支給もありません。 そのため、その分が時給に上乗せされた形となり、高い時給に反映されているのです。
グループ内派遣のメリットは?
またグループ内派遣は、法律に則って雇用された派遣社員や正社員を雇うよりも、人件費を削減できるのが特徴です。 そのためグループ内派遣を許せば、専ら派遣のときと同様、企業はグループ内派遣からの派遣労働者ばかりを受け入れるようになり、正社員や法律に則った派遣社員の雇用を妨げることになりかねません。
派遣法 違反 どうなる?
当該法律に違反すると、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金刑が科せられます。 また、派遣先企業が更に派遣を行うことで利益もあげていた場合、労基法6条が規制する「中間搾取の排除」に該当するため、労基法違反にもなり、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金刑が科せられます。
なぜ派遣はダメなのか?
短期間での派遣就業では、労働者の収入が不安定になります。 また派遣会社、派遣先企業共に適正な雇用管理をすることが難しいという判断から、2012年の改正労働者派遣法で、日雇い労働者(日々もしくは30日以内雇用期間)の派遣は原則禁止となりました。 日雇派遣は条件に当てはまれば、派遣が認められています。
派遣が多い会社 なぜ?
まず、派遣会社が多い理由を室伏氏に聞くと「大手企業が人件費を削減したいがために、政府に構造改革を促した影響です」とキッパリ。 「企業としては人件費、社会保険料の負担が大きく、どうしても抑えたいコストです。 そこで大手企業を中心に構成されている経団連が自民党に働きかけ、派遣法の改正に踏み切らせました。
正社員 派遣 どっちが稼げる?
短期的に見た時、派遣の方が稼げるとお伝えした理由は、派遣の時給に高さにあります。 例えば月給25万円の正社員の場合、時給換算すると大体1500円程と言われています。 一方派遣はというと、条件の良い案件なら時給1800円という求人もあります。 正社員のように週5で8時間働く場合、月給は約32万円となります。
派遣社員 年収 いくら?
令和2年度の派遣社員の全国平均年収は約374万円でした。 専門性が高い職種ほど給料が高く、三大都市圏とそれ以外との地域差は、年収にして約54万円になります。 派遣社員の給料は人材派遣会社から支払われ、月末締め翌月給料日支払いであることが一般的です。
WDBのマージン率は?
どの派遣会社でもマージンはあるのですが、WDBはその率が高いです。 基本的なマージン率は「25%〜30%」とされているのですが、WDBでは34%に設定されています。
派遣 女性 多い なぜ?
一方、派遣社員という働き方を選んだ理由として女性がもっとも多く選んだのは「働く日数・期間を選べる」という選択肢でした。 同じ調査の中で今後も派遣社員として働きたいと答えた男性は3割にとどまったのに比べ、女性は4割と比較的高い割合を示しています。 派遣女性の中には、家事や育児しながら働いているという方も少なくありません。
フリーターと正社員 どっちが稼げる?
フリーターと正社員では、基本的に正社員のほうが高収入の傾向にあるようです。 厚生労働省の「令和2年賃金構造基本統計調査 結果の概要『雇用形態別にみた賃金』(p1)」によると、フリーターを含む非正規雇用の平均月収は男女計で21万4,800円。 正社員の平均月収は32万4,200円とされています。
派遣 1日いくら?
厚生労働省は、業種ごとの派遣料金の費用相場を公開しており、2021年4月時点では2020年度の結果が公表されています。 専門的な技術や知識が必要な職種の場合、1日あたりの平均料金は20,000~30,000円、それ以外の職業は10,000~20,000円が派遣料金の相場です。
派遣 1時間 いくら?
営業職種従事者の1人あたり1日8時間の平均派遣料金は2万1,083円、1時間あたりの平均派遣料金は2,635円となっています。
派遣会社 どれくらい抜いてる?
公表されていた派遣会社のピンハネの実態
私のように、フルタイムの派遣社員として働いている場合の、一般的な派遣料金の内訳。 派遣社員のお給料は、派遣先企業が派遣会社に払う「派遣料金」の70%。 30%が派遣会社の取り分。 派遣会社は派遣料金の30%をピンハネしてる!?
派遣 最低 賃金 2022 いくら?
2022年は10月1日から【時給1,072円】に改正されます。 この最低賃金は東京都内に派遣中の労働者を含みます。
派遣社員の人口は?
派遣の現状 | 一般社団法人日本人材派遣協会 2020年1~3月平均の派遣社員数は約143万人となりました。 雇用者全体(5,661万人、役員除く)に占める派遣社員の割合は2.5%となり、この割合は15年ほど大きな変化は見られず2~3%を推移しています。
なぜ派遣会社が多いのか?
まず、派遣会社が多い理由を室伏氏に聞くと「大手企業が人件費を削減したいがために、政府に構造改革を促した影響です」とキッパリ。 「企業としては人件費、社会保険料の負担が大きく、どうしても抑えたいコストです。 そこで大手企業を中心に構成されている経団連が自民党に働きかけ、派遣法の改正に踏み切らせました。
なぜ派遣はダメなのか?
単調な仕事や、いわゆる「誰でもできる仕事」を任されるため“やりがい”は生まれにくい特徴があります。 また仕事のやり方や方針に対して基本的に口を出すことができないため、働くことのモチベーションは維持しにくいでしょう。 なぜならそれが「派遣社員」の本質だからです。 派遣会社にとっての派遣社員は人的資源。
派遣会社のリスクは?
一番想定されうるリスクとしては、派遣事業で保有している集客チャネルや人材プールに、正社員雇用を希望する人材が少ないことや、経歴やスキルの関係から採用企業側の正社員としての採用ニーズがあまりないことがあげられます。
派遣社員 なぜ生まれた?
バブル崩壊以降、年功序列、終身雇用といった日本独特の雇用の在り方が問われ正社員のリストラが目立つようになってきた時期がありました。 そこで企業が求めたのが派遣社員です。 必要な期間、必要なポジションに労働力を充当できるのは企業にとって大きな魅力だったのかもしれません。 それに加えて、働く側の意識の変化があります。
派遣の悪いイメージは?
派遣のイメージは正社員に比べ、重要な仕事ややりたい仕事をやらせてもらえないイメージがあります。 人間関係ができて、気心がしれたころに辞めてしまう印象が強いので、仕事にまつわる悩みなどの相談がしづらいイメージがあります。 いつ雇用期間を切られるのかが全く予想できないため、将来に対して不安のある働き方だと思います。
派遣の仕事は何歳まで?
派遣に年齢制限はない
派遣労働者に年齢制限はなく、60歳以上で働いている方も存在します。 派遣会社への登録も、年齢制限はもちろん、性別や学歴、職歴、資格、スキル、経験などの条件も設けられていません。 即戦力として資格やスキル、経験が求められるイメージがあるものの、未経験者を歓迎している会社も数多くあります。
使えない派遣社員の特徴は?
「使えない……」交代になりやすい派遣社員の特徴
能力が自社の求める水準に達していない ...
能力に関して改善が見られない ...
注意やアドバイスに対して不機嫌になる ...
職場の規則に従ってくれない ...
派遣社員への教育内容を再考する ...
職場環境をチェックしてみる ...
交代を要請する ...
派遣元を変える
派遣社員の教育は 誰が する?
派遣スタッフの教育訓練に関しては、雇用主である派遣会社が実施すべきですが、派遣先の業務に密接に関連した教育訓練については、実際の就業場所である派遣先が実施することが適当であるとし、派遣先の正社員と同様の教育訓練を受けさせることが義務化されました。
派遣法改正案は「正社員の雇用」を守るためだった!?
非正社員は誰も救われない“矛盾と罠”
――国際基督教大学 八代尚宏教授インタビュー
2010.12.2
今年3月に閣議決定し、国会審議が行われていた労働者派遣法改正案は、首相交代などの混乱のなか、継続審議となった。08年秋の世界同時不況後、派遣労働の規制強化に向けた世論の高まりとともに注目を浴び、登録型派遣や製造業務派遣の原則禁止を柱とする本法案。今後、再審議で成立したとして、本当に非正社員は救われるのだろうか。検証するとともに、非正社員が真に救われる働き方やそれを担保する制度について、国際基督教大学の八代尚宏教授に話を聞いた。(聞き手/ダイヤモンド・オンライン 林恭子)
派遣法改正でも正社員は増えない
むしろ失業者が増える可能性も
――「派遣の原則禁止」を目指した派遣法改正案だが、これが実現すれば本当に非正社員は救われるのだろうか。派遣法改正案の問題点とともにお教えいただきたい。
それを明らかにするためには、まず派遣労働の規制緩和がなぜ行われたかを考えなければならない。
そもそも派遣社員などの非正社員の増加は、「小泉政権における新自由主義的な構造改革によってもたらされた」という認識が広まっているが、これはまったくの誤解である。なぜならこの規制緩和は、1999年に派遣労働の雇用機会の拡大と保護強化を目的とした国際労働機関(ILO)第181号条約に日本が批准したことに基づいており、2001年に成立した小泉政権誕生以前の話であるからだ。
この条約は、欧州を中心に失業率が高止まりしている状況下で、失業率を低下させるためにも有料職業紹介や派遣労働を容認し、不安定でも雇用機会を増やすことが先決だという事情から生まれたもの。日本も批准し、それ以前の派遣先の職種を厳しく制限した「原則禁止・例外自由」を逆転して、「原則自由・例外禁止」へと原則を大転換した。これに伴い、「当分の間」禁止となっていた製造業への派遣が、2004年に自由化されたに過ぎない。
したがって、規制緩和の目的は「雇用機会の拡大」にあったわけだから、それを元に戻して規制を強化をすれば、結果も逆になるのは当然だ。
朝日新聞が全国主要100社を対象に行った「派遣が禁止された場合の対応」へのアンケート(09年11月実施)によると、「他の非正社員に置き換える」(契約社員:36社、請負・委託:30社、パートタイム:22社)のがほとんどで、「正社員の増加で対応」はわずか15社だった。
小泉労働法制「改革」についての雑感
静岡県労働研究所 理事長 大橋 昭夫
小泉内閣は、昨年6月27日労働基準法の一部を改正する法律を成立させ、これが本年1月1日から施行されている。 この詳細については触れないが、この改正法は、有期労働契約の契約期間の上限の延長、有期労働契約の締結、更新及び雇い止めに関する基準、解雇権濫用法理の明文化、裁量労働制の一層の拡大を実現したもので、解雇規制を除き労働者に対して、大きな苦難を強いたものと評価される。 この改正は、もっぱら日本経団連の意向に沿うもので、この推進勢力は、小泉総理大臣のブレーンで総合規制改革会議議長宮内義彦オリックス会長を中心とするグループであったと言われる。 宮内議長は、「鉛筆型の人事戦略」を唱え、少数のコア社員を細い芯とし、これのみを保護し、その周りの木の部分に成功報酬型の社員を、さらに、その周りにパートタイマーや派遣労働者を配置し、これらの木の部分を必要に応じて調整することが、グローバル経済を勝ち抜く今後の経営戦略であることをあからさまに述べている。自分が生き抜くためには、大多数の労働者の生活など視野に入らないのである。 今回の労基法の改正は、労働者派遣法の「改正」による派遣業種の一層の拡大と相俟って、我が国の正規労働者の数を著しく減少させ、これをパートタイマー、派遣労働者等の不安定労働に代替させるものであって、わが国社会の労働秩序を根底から破壊することになる。 厚生労働省は、今回の改正法案の提出にあたって、「今日、我が国の経済社会においては、少子高齢化が進み労働力人口が減少していく一方、経済の国際化、情報化等の進展による産業構造や企業活動の変化、労働市場の変化が進んでいる。このような状況の下で、経済社会の活力を維持、向上させていくためには、労働者の能力や個性を活かすことができる多様な雇用形態や働き方が選択肢として準備され、労働者一人一人が主体的に多様な働き方を選択できる可能性を拡大すること、働き方に応じた適正な労働条件が確保され、紛争解決にも資するよう労働契約など働き方にかかるルールを整備すること、これらの制度の整備、運用に際しては、労使によるチェック機能が十分に活かされるようにすることなどを基本的な視点とする」と説明しているが、この視点は、余りにも労働者の生活実態を知らない「綺麗事」であり、役人の文章である。 私が指摘するまでもなく、わが国の経済社会の活力を維持、向上させていく最良の手段は、雇用の確保であり、人間らしい生活をするのに必要な賃金の保障である。 厚生労働省のいう「多様な雇用形態や働き方」という概念は空漠としており、その内容が如何なるものか明確でないが、派遣労働や有期契約による労働、更には残業代を回避するための裁量労働であると察しはつく。 これらの労働形態は、いずれも不安定雇用であって、多様な働き方を実現し、それが豊かな生活につながる契機となることは経験則上ありえない。 私の弁護士としての経験からすると、労働者は少々他と比べて賃金が低いとしても、雇用が安定的に確保され、将来の生活の見通しが立つ時にこそ、労働生活においても主体性を発揮でき精神的にも自由になれるものである。 いま、労働者の自己破産の申し立て件数が激増し、それがわが国の平均的な法律事務所の日常的業務になっている。 私もこの種の事件を数多く取り扱うが申し立てをする労働者の所得が低く、そのうちの少なくない者が、派遣労働者、有期契約労働者、フリーターであり、その所得水準が生活保護基準以下である者も存在する。 多様な雇用形態や働き方は、私の実感からすると、使用者の身勝手や彼らの生存権のみを保障するもので、労働者に対し永久に社会底辺に沈殿させる効用しかないように思われる。 私は、西ヨーロッパに見られる如く、「共生き」の思想を前提とした労働ルールの確立こそ、社会発展の源泉であると考えるし、小泉内閣の方向は、社会の不安定化を招来させることにしかならないと思う。 今回の労基法の改正で評価できる点は、唯一解雇権の制限法理が法文上明らかになったことのみである。 この規定は、小泉内閣の原案では、「使用者は、この法律又は他の法律の規定によりその使用する労働者の解雇に関する権利が制限されている場合を除き、労働者を解雇することができる。但し、その解雇が、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と解雇が原則自由になっていた。しかし、労働者の反対があり、最高裁で確立した解雇権濫用法理の精神に立ち帰り、現行の「解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」(労基法18条の2)となったのである。 これは、西ヨーロッパ諸国の解雇制限法に比べると極めて簡単な条項ではあるが、それでも法規範として、すべての裁判官の判断を拘束するもので一歩前進だと評価できる。 小泉構造改革は、今やすべての面にわたって失敗しているが、更なる労働「改革」は、労働者の生活をより一層困難にするもので、働く人々は、思想、信条、潮流、傾向を超えて、この流れに対抗する必要があろう。 わが国に憲法の精神に忠実な「働くルール」が確立されることを切に望むものである。それが真の意味での労働改革である。
破たんした小泉「構造改革」 社会と国民に何もたらした
貧困と格差 際限なし
「官から民へ」「改革なくして成長なし」―。ワンフレーズ政治で「構造改革」路線をひた走った小泉純一郎政治。その「本丸」とされた郵政民営化問題で、麻生太郎首相が迷走発言を続けるなか、小泉純一郎元首相や竹中平蔵元経済財政担当相らがマスメディアに盛んに登場し、「構造改革」路線の“復権”をはかる動きもみられます。「痛みに耐えれば、明日はよくなる」どころか、「生きていけない」と悲鳴があがるほどの貧困と格差の惨たんたる状況に国民を追い込んだのが「小泉改革」でした。歴史の審判はすでに下っています。
雇用のルール破壊
「派遣切り」・ネットカフェ難民
東京のど真ん中に、五百人もの人たちが衣食住を求めて集まった「年越し派遣村」。大企業の理不尽な「非正規切り」で「人間としての誇りを奪われた」「自殺も考えた」との声が渦巻きました。貧困を目に見える形でつきつけ、政治を動かしました。
「派遣村」に象徴される「使い捨て」労働の深刻な広がりは「構造改革」の名によるリストラの促進や労働法制の規制緩和がもたらしたものです。
この十年間で正規労働者が四百九万人も減り、その代わりに、非正規労働者が六百六万人も増えました。
自民、公明、民主、社民などの各党が賛成した一九九九年の労働者派遣法改悪。派遣労働を原則自由化し、「派遣」という形での「使い捨て」労働の増加に拍車をかけました。
二〇〇一年に発足した小泉内閣は、「構造改革」を加速。まず「不良債権処理」の名で中小企業つぶしをすすめ、〇三年には、企業がリストラをすればするほど減税をするという「産業再生」法を延長・改悪し、大企業のリストラを後押ししました。
一方、派遣法を改悪し、〇四年三月からは製造業への派遣を解禁しました。この中で、もともと危ぐされていた派遣労働者の労働災害が増加。〇七年の死傷者数(五千八百八十五人)は、〇四年と比べると九倍という激増ぶりを示しました。
ネットカフェで寝泊まりしながら「日雇い派遣」で働く若者の姿が、底なしに広がる「働く貧困層」の象徴となりました。
ギリギリの生活を強いられている派遣労働の実態が大問題になり、日本共産党の論戦とあいまって政府でさえ派遣法の見直しを言い出さざるをえなくなりました。労働分野の規制緩和が破たんしたことは明確です。
しかし、米国の金融危機に端を発した景気悪化を口実に、〇八年後半、大企業は製造業を中心に大量の「派遣切り」「期間工切り」を始めました。被害は日増しに広がり、今日の日本社会を覆う最大の社会問題になっています。
景気のいいときには、正社員を派遣や期間工に置き換えて大もうけをし、景気が悪化したらモノのように使い捨てる―この大企業の横暴勝手を容易にする仕組みを作ったのが、労働の「構造改革」であり、今日の事態は、まさに政治災害そのものです。
社会保障の連続改悪
医療崩壊・国保証取り上げ
「わずかな年金は減らされたうえ、保険料の天引きは容赦ない」「病気になってもお金がなければ病院にもいけない」―。「構造改革」による社会保障の連続改悪によって、こんな苦難が国民を襲いました。
その大もとにあるのが、小泉内閣が決めた社会保障費の抑制方針です。二〇〇二年度から毎年、社会保障費の自然増分から二千二百億円(初年度は三千億円)削減されてきました。
抑制の対象は医療、介護、年金、生活保護と社会保障のあらゆる分野に及び、庶民への痛みの押し付けの結果、「生きること」自体が脅かされる実態が広がっています。
医療分野では、国民の負担増に加え、医療費削減を目的に医師数の抑制政策を続けたため、救急患者が救われない医師不足が社会問題化し、「医療崩壊」と呼ばれる事態が出現しました。
高すぎる国民健康保険料が払えずに正規の国保証を取り上げられた世帯は約百五十八万世帯にまで広がっています。受診を控え、手遅れで死亡する例は後を絶ちません。
そのうえ、国民生活の最後の命綱である生活保護さえ切り縮められました。老齢加算の廃止で、「朝はパン一枚、昼はうどん」「暖房費節約のため、ストーブをつけず布団に入る」「風呂の回数を減らす」など生活の根幹まで切り詰めざるをえない実態です。(〇八年一月、全日本民主医療機関連合会の調査報告)
こうしたなか、昨年四月に導入された後期高齢者医療制度に、国民の怒りが爆発しました。同制度に対する不服審査請求は全国で一万件超。「『高齢者はいずれ死を迎える、お金も手間もかけなくてよい』という、人間性を喪失した制度だ」などの怒りの声があふれています。
日本医師会など医療関係四十団体は〇八年七月、「社会保障費の年二千二百億円削減撤廃」を決議。国民の批判は、小泉内閣がしいた二千二百億円の削減路線そのものに向けられはじめました。
自公政権は社会保障費の削減路線の転換は明言しないものの、〇九年度予算案で一時的な手当てを行い、社会保障費の実質の削減幅は二百三十億円に“圧縮”せざるをえなくなっています。第二次小泉改造内閣で厚労相だった自民党の尾辻秀久議員でさえ、一月三十日の参院本会議で「乾いたタオルを絞ってももう水はでない。潔く二千二百億円のシーリングはなしと言うべきだ」と述べるなど、社会保障費削減路線の破たんを認めざるをえなくなっているのです。
庶民負担増 大企業は減税
7年間で国民に50兆円近くも
小泉政権以来の増税などで国民負担は、年間十三兆円も増えました。二〇〇二年度から〇八年度まで七年間の国民負担増を累計すれば、五十兆円近くになります。
その一方で、大企業・大資産家への減税は、一九九八年以降の十年間に行われたものだけでも、大企業に年間五兆円、大資産家に年間二兆円、あわせて年間七兆円以上になっています。十年間の累計では、四十兆円もの税収が失われました。
地方の切り捨て
激減する交付税・農業破壊
「交付税が四割減って半分も補てんされない」「このままでは吉野は死んでしまう」
昨年七月。奈良県吉野郡で開かれた日本共産党の演説会に先立ち、市田忠義書記局長と懇談した地元町村長らから、こんな嘆きの声が率直に寄せられました。
「地方ができることは地方へ」をうたい文句に自民・公明政権が強力に推進した「三位一体改革」は、農山漁村の自治体を存亡の危機にまで追い詰めています。
実際、「三位一体改革」が断行された二〇〇四年から三年間で、国庫補助負担金は四・七兆円、地方交付税は五・一兆円がそれぞれ削減されました。一方、国から地方への税源移譲はわずか三兆円しかありません。地方自治体にとっては差し引き六・八兆円のマイナスです。
全国知事会は昨年七月の知事会議で、このままでは一一年度までに地方自治体の財政が破たんするという衝撃的な試算を発表しました。とりわけ地方交付税が財政に占める比重が高い町村の財政は深刻です。
「地方交付税の削減など、国による兵糧攻めからの生き残り策」「周辺町村が財政破たん寸前だった」。全国町村会の「道州制と町村に関する研究会」が昨年十月にまとめた調査報告でも、市町村合併の理由の柱に「三位一体改革」による交付税削減を指摘する声が相次ぎました。
国会でも、鳩山邦夫総務相が「急激にやりすぎた。失敗の部分がある」(十二日、衆院本会議)と答弁。「三位一体改革」の破たんを認めました。
また、輸入自由化の促進による農業破壊、大型店の進出による商店街の「シャッター通り」化など、地方経済の冷え込みも深刻です。
しかし、自民党は、こうした“地方切り捨て”を反省するどころか、一〇年三月末の合併特例新法の期限切れを前に「おおむね七百から千程度の基礎自治体に再編」すると、いっそう合併を推進することを主張。さらに、政府は「時代に適応した『新しい国のかたち』をつくる」として道州制の導入を掲げています。
こうした動きには全国町村会が「強制合併につながる道州制には断固反対していく」と明記した特別決議を採択するなど、痛烈な反撃が巻き起こっています。
経済ゆがみ、ぜい弱に
「戦後最悪の経済危機」(与謝野馨経済財政担当相)―。内閣府が十六日発表した二〇〇八年十―十二月期の国内総生産(GDP)が実質で前期比3・3%減(年率換算12・7%減)となったニュースは、衝撃を与えました。金融危機の震源地である米国よりも急激な落ち込みだったからです。なぜこんなことになったのか。ここにも、背景に小泉内閣いらいの「構造改革」があります。
極端な輸出依存
「衝撃 石油危機以上 輸出依存体質響き」(「毎日」十七日付)、「外需依存の成長 岐路」(「日経」同)、「外需頼み 転換カギ」(「読売」同)といった見出しが商業メディアに目立ちました。極端なまでに輸出に依存した「経済成長」の破たんです。
「構造改革」を掲げた小泉内閣が発足(〇一年四月)して以来の変化をみてみましょう。内閣府のGDP統計によると、所得や個人消費は低迷しているのに、輸出が極端に伸び、〇八年に失速します。財務省の法人企業統計をもとに、製造業大企業(資本金十億円以上)の〇一年度と〇七年度を比較すると、経常利益は二・二五倍に増えています。ところが、従業員給与は〇・九八倍と減っています。大幅に増えたのは株主への配当と社内留保です。一方、民間信用調査会社の調査では、法的整理による企業倒産が増えています。ほとんどが中小企業です。
自動車、電機など輸出大企業を中心に従業員や中小企業・業者にしわ寄せする形で、大もうけし、もっぱら株主に還元するという構図です。
財界全面後押し
こうした企業体質をつくり出したのが、「構造改革」だったと、日本経団連会長の御手洗冨士夫キヤノン会長が述べています。
「これは、何といっても構造改革の進展がもたらしたもの」「多くの企業でも、筋肉質の企業体質が形成されている。過剰設備や過剰債務、過剰雇用という、いわゆる『三つの過剰』は完全に解消している」(〇八年六月十九日の講演)
文字通り、財界の全面的な後押しで推進されたのが小泉流「構造改革」でした。
財界が求める雇用など「三つの過剰」の解消を推進するテコと位置づけられたのが不良債権の強引な早期最終処理です。
小泉内閣が最初につくった「骨太の方針」(〇一年六月)は、不良債権処理の加速を通じて「効率性の低い部門から効率性や社会的ニーズの高い成長部門へとヒトと資本を移動することにより、経済成長を生み出す」とうたいました。小泉内閣は、リストラすればするほど減税する「産業再生」法を拡充、製造現場への労働者派遣を解禁しました。
懸念したことが
この結果、「成長」したのは、「筋肉質」になった輸出大企業や大銀行だけでした。「不良債権」扱いされた中小企業は倒産に追い込まれ、大量の失業者が生まれ、正社員から賃金の安い非正規社員への置き換えが進みました。
あまりにも、国内経済を脆弱(ぜいじゃく)にしてしまった「構造改革」。政府の「ミニ経済白書」(〇七年十二月)でさえ、輸出は増加しているが、家計部門が伸び悩むなか、米国経済など海外リスクが顕在化した場合、景気は「厳しい局面も予想される」と懸念していたことが現実のものとなりました。
推進者がいま「懺悔の書」
小泉流「構造改革」をめぐり居直る竹中平蔵元経済財政・金融担当相と対象的に「懺悔(ざんげ)の書」を書いたのは、中谷巌氏。小渕内閣の経済戦略会議の議長代理として「構造改革」の提言をまとめた中心人物です。竹中氏も同会議のメンバーの一人でした。
中谷氏は自著『資本主義はなぜ自壊したのか』のなかで、「一時、日本を風靡(ふうび)した『改革なくして成長なし』というスローガン」にふれ、「新自由主義の行き過ぎから来る日本社会の劣化をもたらしたように思われる」として、「『貧困率』の急激な上昇は日本社会にさまざまな歪(ゆが)みをもたらした」と指摘。「かつては筆者もその『改革』の一翼を担った経歴を持つ。その意味で本書は自戒の念を込めて書かれた『懺悔の書』でもある」と書いています。
郵政民営化矛盾が噴出
小泉内閣が「構造改革」の本丸と位置付けた郵政民営化。その矛盾が噴出しています。
「私は郵政民営化を担当した大臣」(二〇〇八年九月十二日、自民党総裁選の討論会)と自認する麻生太郎首相。その麻生首相が「(郵政事業の四分社化を)もう一回見直すべき時にきているのではないか。小泉首相のもとで(郵政民営化には)賛成ではなかった」(二月五日の衆院予算委員会)と言い出したのは、郵政民営化の破たんを象徴しています。
当時の小泉首相が「郵政選挙」までやって強行した郵政民営化のかけ声は「官から民へ」「民間でできることは民間で」「貯蓄から投資へ」でした。
「民間」といっても日米の大手金融機関のことです。もうけのじゃまになる郵便貯金、簡易保険などの郵政事業をバラバラにするのが四分社化でした。
「貯蓄から投資へ」といっても、庶民の預貯金を呼び込もうとしている証券市場の売買の六割以上は外国人投資家。その大半はヘッジファンドとよばれる投機基金です。庶民の虎の子の財産が食い物にされかねません。
安心、安全、便利を願う国民にとっては「百害あって一利なし」の郵政民営化。その矛盾のあらわれは小泉流「構造改革」路線そのものの破たんを物語っています。
“改革が足りないから”と居直る竹中氏だが…
小泉流「構造改革」がモデルにした本家の米国で、市場まかせの「新自由主義」路線が破たんしました。にもかかわらず、小泉流「改革」にしがみつこうとする勢力がいます。
一月一日放送のNHK番組で、小泉「改革」を推進した元経済財政・金融担当相の竹中平蔵氏は、大企業の「非正規社員切り」横行が社会問題になり、小泉「改革」に批判が強まっていることに、こう居直りました。
「大企業が非正規を増やすのは原因がある。正規雇用が日本では恵まれすぎている。正規雇用を抱えると企業が高いコストをもつ」
「同一労働同一賃金」をやろうとしたが、反対されたとし、「(年越し派遣村などは)改革を中途半端に止めてしまっているから、こういう事態が起きている」。
竹中氏が“止まっている”という「改革」の中身は、正社員の賃金水準を賃金が安い非正規社員の水準に引き下げるという意味での「同一労働同一賃金」です。大企業の総人件費を抑えるのが狙いです。これでは、働いても働いても貧困から抜け出せない「ワーキングプア」を労働者全体に広げることにしかなりません。
しかも、竹中氏は「問題は、いまの正規雇用に関して、経営側に厳しすぎる解雇制約があることだ」(「竹中平蔵のポリシー・スクール」二月一日付)として、企業業績が悪化したら従業員を抱え込まなくていいような「新たな法律を制定することが必要だ」と主張しています。正社員を含めた“解雇自由法”をつくれといっているようなものです。
一方で、「日本を元気にしないといけない」として、最優先課題にあげたのが法人税率をもっと引き下げることでした(一月一日のNHK番組)。竹中氏がかかげる「改革」はあくまで、大企業のための「改革」を徹底しろということにすぎません。
2021.09.30
日本国が見捨てた就職氷河期世代の絶望…バブル崩壊後の30年間で何が起きたか
当事者として、取材者として
小林 美希 プロフィール
2021年9月29日に自民党の総裁選が行われ、その後には総選挙が控えている。政治家が「中間層の底上げ」を訴えるが、考えてみてほしい。もとはといえば、中間層を崩壊させたのは政治ではなかったか。
国際競争の名の下で人件費を削減したい経済界は政治に圧力をかけた。不況がくる度に労働関連法の規制緩和が行われ、日本の屋台骨が崩れていった。最も影響を受けたのが就職氷河期世代だ。これからを担っていくはずだった若者たちが、非正規雇用のまま40~50代になった。
私が非正規雇用の問題を追って18年――。いったい、何が変わったのか。
大卒就職率6割以下の時代
1980年代には8割あった大卒就職率は、バブル経済が崩壊した1991年以降に下がり始めた。そして2000年3月、統計上、初めて大卒就職率が6割を下回る55.8%に落ち込んだ。大学を卒業しても2人に1人は就職できなかったというこの年に、私は関西地方で大学を卒業した。
その3年後の2003年3月に大卒就職率は過去最低の55.1%を更新。日経平均株価は同年4月に7607円まで下落した。この時の私はもちろん、当事者だった大学生の多くは雇用環境が激変するなかにいるとは気づかずにいた。
私の就職活動は苦戦した。約100社にエントリーシートを送り、50社は面接を受けた。神戸に住んで大学に通っていた私の就活の主戦場は大阪で、面接を受けるために毎日のように大阪周辺を歩き回った。最終的に内定が出たのは消費者金融会社の1社のみだった。
卒業後に東京で就職活動をやり直し、ハローワークに通った。新聞広告の求人を見て応募した業界紙の「株式新聞」に採用が決まった。就職試験の日、「うちは民事再生法を申請したばかりですが」と説明があり、倒産しかけた会社に就職することに悩んだが、「面白そうだ」という直感が勝った。
この株式新聞時代に出会い、後の私の記者活動に影響を与えたのが、伊藤忠商事の丹羽宇一郎社長(当時)だ。丹羽氏との出会いがなければ、私は就職氷河期世代の問題を追及しなかったかもしれない。
新人の時には経済記者として食品、外食、小売り、サービス業界を担当。商社の担当も加わり、出席した伊藤忠商事の記者懇談会で初めて丹羽氏に挨拶をする。記者に囲まれていた丹羽氏に私は「社長の役割とは何か」と聞いた。この若気の至りとも言える質問に対し、丹羽氏は真顔で「経営者とは、社員のため、顧客のため、そして株主のためにある」と答えてくれたのだった。
若者が疲れ切っている…なぜ?
株式新聞入社から1年後の2001年の初夏、毎日新聞が発刊(現在は毎日新聞出版)する『週刊エコノミスト』編集部に契約社員として転職した。私はだんだんと雑誌の仕事に慣れていき、天職と思って没頭していた。深夜や明け方に及ぶ校了作業は達成感があり、職場で夜を明かして新聞をかぶってソファで寝ていたこともあった。
これはマスコミ特有の働き方かと思っていたが、この頃、金融、製造、サービス業などに就職していった友人たちも長時間労働というケースが多かった。そのうち、充実感とは違った何かがあると感じ「なにかおかしい。若者が疲れ切っている」と首をかしげるようになっていった。
その疑問が確信に変わったのは、2003年前後に上場企業の決算説明会で経営者や財務担当役員らが強調した言葉を聞いてからだ。
「当社は非正社員を増やすことで正社員比率を下げ、利益をいくら出していきます」
2001年のITバブル崩壊から間もなくてして企業利益がV字回復し「失われた10年」が終わるかのように見えた。私はこの利益回復は非正規雇用化で人件費を削減したことによるものに過ぎないと見た。これでは経済を支える労働者が弱体化すると感じた私は、若者の非正規雇用の問題について企画を提案した。
『週刊エコノミスト』の読者層の年齢は高く、若者の雇用問題をテーマにしても読まれないという理由で、企画はなかなか通らなかった。さらに世間で浸透していた「フリーター」という言葉の印象が自由を謳歌しているイメージが強く、若者は甘いという風潮があるなかでは、ハードルが高かった。
悩んだ私は、再び、若気の至りの行動に出た。伊藤忠商事の丹羽氏にアポイントをとって、企画が通らないこと、企画が通らなければ転職したほうが良いか迷っていると人生相談をしたのだ。若者の非正規雇用化が中間層を崩壊させ、消費や経済に影を落とすと見ていた丹羽氏は「同じことを3度、上司に言ってごらんなさい。3度も言われれば根負けして上司は必ず折れるから」とアドバイスしてくれた。
私は企画が通らないまま非正社員として働く若者の現場取材を進めた。その頃、ある会合で話したコンビニ大手の社長が「息子がフリーターで……」と悩む胸の内を明かしたことがヒントになり、デスクや編集長を説得した。
「子どもの就職や結婚を心配するのは立場を超えて一緒のはず。読者の子どもを想定して、タイトルを若者とせず、娘や息子に変えたらどうか」
企画を提案し始めてから数か月経った2004年5月、ついに第2特集で「お父さんお母さんは知っているか 息子と娘の“悲惨”な雇用」を組むことが実現した。非正規雇用に関するデータを探し、マクロ経済への影響など当時は存在しなかったデータはシンクタンクのエコノミストに試算してもらった。
この特集について慶応大学(当時)の金子勝教授や東京大学の児玉龍彦教授がそれぞれ大手新聞の論壇コーナーで取り上げてくれたことで、続編が決定。第1特集となって「娘、息子の悲惨な職場」がシリーズ化した。
富の二極分化で「中間層崩壊」
この頃の若年層の失業率は約10%という高さで、10人に1人が失業していた。内閣府の「国民生活白書」(2003年版)により、2001年時点の15~34歳のフリーター数が417万人に上ると公表されると社会の関心が若者の雇用問題に向いたが、企業側の買い手市場は続き、労働条件は悪化していく。
パート・アルバイト、契約社員や派遣社員として働き、休日出勤やサービス残業の日々でも月給が手取り16万円から20万円程度のまま。正社員でも離職率の高い業界や会社での求人が多く、ブラック職場のため過労で心身を崩すケースが続出した。
社会保険料の負担から逃れるために業務請負契約を結ぶ例まで出現。大企業や有名企業ほど、「嫌なら辞めろ。代わりはいくらでもいる」というスタンスで、若者が使い捨てにされた。こうした状況に警鐘を鳴らすためには、経営者の見方を取り上げなければならないのではないか。
2005年1月4日号の『週刊エコノミスト』では、ロングインタビュー「問答有用」のコーナーで経済界の代表的な経営者であった丹羽氏に中間層の崩壊について語ってもらった。この時点で、若者の労働問題について本気で危機感を持つ経営者は私の知る限りでは他にいなかった。丹羽氏はこう語った。
富(所得)の2極分化で中間層が崩壊する。中間層が強いことで成り立ってきた日本の技術力の良さを失わせ、日本経済に非常に大きな影響を与えることになる。中間層の没落により、モノ作りの力がなくなる。同じ労働者のなかでは「私は正社員、あなたはフリーター」という序列ができ、貧富の差が拡大しては、社会的な亀裂が生まれてしまう。
戦後の日本は差別をなくし、平等な社会を築き、強い経済を作り上げたのに、今はその強さを失っている。雇用や所得の2極分化が教育の崩壊をもたらし、若い者が将来の希望を失う。そして少子化も加速する。10~15年たつと崩壊し始めた社会構造が明確に姿を現す。その時になって気づいても「too late」だ。
企業はコスト競争力を高め、人件費や社会保障負担を削減するためにフリーターや派遣社員を増やしているが、長い目でみると日本の企業社会を歪なものにしてしまう。非正社員の増加は、消費を弱め、産業を弱めていく。
若者が明日どうやってご飯を食べるかという状況にあっては、天下国家は語れない。人のため、社会のため、国のために仕事をしようという人が減っていく。
それが今、現実のものとなっている。
格差はこうして固定・拡大化した
丹羽氏のインタビューが掲載された年の8月8日、小泉純一郎首相(当時)が郵政民営化を掲げた解散総選挙に打って出て圧勝し、規制緩和路線に拍車がかかっていく。小泉郵政選挙の投開票は9月11日。その1週間後の9月18日には一般派遣の上限期間が3年とされる改正労働者派遣法が公布され、2週間待たずの9月30日施行で、いわゆる派遣の「3年ルール」ができた。
この3年ルールとは、表向きには派遣で同じ職場で3年が過ぎたら正社員や契約社員などの直接雇用にすることを促す改正だったが、実際には多くの派遣社員が3年の期間直前で契約を打ち切られることになった。同じ年に労働基準法も改正されて非正規雇用の上限期間が3年になったことで、非正社員が“3年でポイ捨て”され、非正規雇用のまま職場を転々とせざるを得ない労働環境が整備された。
1995年に旧日経連が出した「新時代の『日本的経営』」で雇用のポートフォリオが提唱され、景気の変動によって非正規雇用を調整弁とする固定費削減が図られて10年経った2005年に「3年ルール」ができた。ここが分岐点となり、日本は格差を固定化させ、格差を拡大させる路線を歩んでしまったのではないだろうか。
本来なら、2007年から団塊世代の定年退職が始まるため人手不足を補うという意味で、まだ20~30代前半で若かった就職氷河期世代を企業に呼び込むチャンスがあったはずだ。大卒就職率はリーマンショック前の2008年3月に69.9%まで回復したが、卒業後数年が経った非正社員は置き去りにされた。
問題提起し続けるために
小泉郵政選挙を機に私は、「もし自分が政治家だったら、何を問題にし、何の制度を変えていくか」ということを、より強く意識するようになった。就職活動をしていた大学時代に講座を聴いて影響を受けた、朝日新聞大阪本社の新妻義輔編集局長(当時)の言葉を思い出していた。
「人の苦しみを数字で見てはいけない。構造問題に苦しむ人が1人でもいるのなら、それを書くのが記者だ」
新妻氏は若い記者時代に森永ひ素ミルク事件(1955年に森永乳業の粉ミルクにひ素が混入して多くの被害者が出た事件)を追っていた。事件の担当医に「被害者は何%か」と数字を聞いた時に、医師から注意を受けた経験からの教訓だという。
就職氷河期世代が抱える問題は、まさに非正規雇用を生み出す法制度という構造問題が起因しているはず。それを問題提起し続けることは、私の役割なのではないか。労働問題に特化するには組織にいては限界があると考えた私は、小泉郵政選挙から1年半後の2007年、フリーのジャーナリストになった。
絶望と諦めのムードが蔓延した
第一次安倍晋三政権(2006年9月から2007年9月)が就職氷河期世代向けに「再チャレンジ」政策をとったが、政権が短命に終わるとともに支援は下火になった。2008年のリーマンショックが襲い、就職氷河期世代だけでない多くの人が職を失った。
政府は就職氷河期世代の支援というよりは、支援事業を担う民間企業を支援したと言える。国は15~34歳の「フリーター」対策の目玉政策として2004~06年に「ジョブカフェ」のモデル事業を行っており、同モデル事業を行った経済産業省から委託を受けた企業が異常に高額な人件費を計上していたのだ。
調べると、ジョブカフェ事業ではリクルート社が自社社員について1人日当たりで12万円、コーディネーターに同9万円、キャリアカウンセラーに同7万5000円、受付事務スタッフに同5万円という“日給”を計上していたことが分かった。『週刊AERA』(2007年12月3日号、同年12月10日号)でスクープ記事を執筆すると、国会でも問題視された。
このジョブカフェでは委託事業が何重にも再委託され、税金の無駄も指摘した。昨年問題になった新型コロナウイルスの感染拡大の対策で多額の委託料が電通に支払われているにもかかわらず、何重にも委託されている問題はなんら変わっていないのだ(参照「給付金『再々々々委託』の深い闇…10年以上前から全く変わっていない」)。
就職支援事業が企業の食い物にされる一方で、就職氷河期世代の非正社員がやっと正社員になれるかもしれないというところで契約を打ち切られる。そうしたことが繰り返され、いくら頑張っても報われずに絶望の淵に追いやられた。正社員になったとしてもブラック職場で追い詰められ、心身を崩して社会復帰できないケースも少なくはない。こうした状況が続いたことで、絶望と諦めのムードが蔓延した。
2010年代に何が起きたか
2009年3月に日経平均株価はバブル崩壊後最安値の7054円をつけ、2010年3月の大卒の就職率は60.8%に落ち込んだ。2012年12月に第2次安倍内閣が発足すると、あたかも「アベノミクス」によって新卒の就職率が高まったかのように見えた。しかし、それは、団塊世代が完全にリタイアするタイミングが重なったことによるもので、15~59歳の労働力人口がピーク時より500万人減っていたことが後押ししただけだった。
安倍政権が打ち出した「女性活躍」の名の下で、企業は人手不足を補うためにブランクのある“優秀な”主婦の採用に乗り出し始め、専業主婦の間には「働いていないと肩身が狭い」という意識が一時的に広がった。
一方で、相も変わらず就職氷河期世代は置き去りにされた。2015年に専門職も含めた派遣で全職種の上限期間が3年になり、同年は労働契約法が改正されて有期労働契約が5年続くと労働者が希望すれば期間の定めのない「無期労働契約」に転換できるようになった。2005年にできた「3年ルール」と同様、制度は悪用され、派遣は3年で“ポイ捨て”、非正規雇用の全般でも5年で“ポイ捨て”が広がった。
安倍政権で内閣府に就職氷河期世代支援推進室が設置され、2019年に「就職氷河期世代支援プログラム」が策定され、3年間で30万人を正社員化すると掲げたが、国は就職氷河期世代の中心層を2018年時点で35~44歳として(次ページ図)、最も支援が難しい40代後半や50歳を過ぎた層に重点を置かずにいる。そして、支援プログラムがこれまでの施策の焼き直しの域を脱しないことから、就職氷河期世代の絶望は深まった。
就職氷河期世代の非正社員「約600万人」
いったん絶望し、諦めてしまえば、どんな支援があったとしても届きにくくなる。私が就職氷河期の問題を追ってから18年が経つ。16年前のインタビューで丹羽氏が言及した通り、もはや「too late」の状況に陥っているのかもしれない。現在、35~49歳の非正社員は約600万人に膨らんでいる。もはや誰も解決の糸口を掴めないくらい、事態は深刻になる一方だ。
自民党政治の下で、製造業の日雇い派遣が解禁され、労働者派遣は今や全ての職種で期間の上限が3年になった。就職氷河期世代を置き去りにしたまま、業界団体のロビー活動も後押しして外国人労働の拡大が図られた。「女性活躍」は女性に仕事と家事と子育て、介護の両立を押し付けるだけ。「働き方改革」や正社員と非正社員の「同一労働同一賃金」も、実態は伴わない。
就職氷河期を追うなかで、そのライフステージに寄り添い、周産期医療や看護、保育の問題もライフワークになったが、全て構造問題がある。国が作る制度が密接に関わり、政治が現場を疲弊させている。新型コロナウイルスが蔓延するなか、政治の機能不全が鮮明となった。総選挙を前に、これまでを振り返らざるを得ない。
政治家にしがらみがあれば、正しいことが言えなくなる。けれど、この18年の間に分かったことがある。世論が盛り上がれば、政治は正しい方向に動かざるを得なくなるということだ。その世論を作るのが、現場の声であり、現場の声を活字にして伝えるのが私の役割だ。就職氷河期世代の問題を解決するのは困難だろう。しかし、目指すべき道が見えなくならないよう、私は書き続けていきたい。
氷河期世代がこんなにも苦しまされている根因
問題の根が深く支援プログラムでも救えない
岩崎 博充 : 経済ジャーナリスト
著者フォロー
2019/08/02
最近になって、政府が重い腰を上げて取り組み始めたものに「就職氷河期世代」の問題がある。「ロストジェネレーション世代」とも言われるが、2019年現在35~44歳のアラフォー世代の貧困問題と言っていい。
もっと正確に言うと、1993~2004年に学校卒業期を迎えた人である。バブル崩壊後の雇用環境の厳しい時代を余儀なくされ、高校や大学を卒業した後に正社員になれず、非正規社員やフリーターとして、その後の人生を余儀なくされた人が多かった世代の問題だ。
厚生労働省の支援プログラムは功をなすのか
この就職氷河期世代を対象とした支援プログラムが、3年間の限定付きではあるが厚生労働省の集中支援プログラムとしてスタートしている。支援対象は多岐にわたり、少なくとも150万人程度が対象者。3年間の取り組みによって、同世代の正規雇用者を30万人増やすことを目指している。
もっとも、わずか3年の支援プログラムで就職氷河期世代が背負った「負のスパイラル」が断ち切れるとは到底思えない。もっと継続的で長期のスパンに立った構造的改革を実施すべきだ……、という意見も数多い。
全国の自治体が取り組む「ひきこもり対策」もその効果を期待する声は多いものの、成果については疑問の声も多い。
就職氷河期世代とはいったい何だったのか。いまなお、同世代1689万人(2018年)のうち約371万人が現在も正規就労できずに、フリーターやパートの人がいると言われる。推定で61万人いると言われる40~64歳の「中高年ひきこもり」も、この世代の割合が突出しているとされる。
因果関係を立証はできないが、京都アニメーション放火殺人事件を起こしたのは41歳の男だった。最近の凶悪犯罪に、この世代の姿が目についていると感じている人もいるのではないか。世帯別の平均月収を5年前と比較すると、35~44歳の世帯の給与だけが低いというデータもある。「アラフォー・クライシス」とも言われるが、この世代の人々が抱える闇とは何か。彼らを救うために社会はどうすればいいのか。
就職氷河期世代と呼ばれる人々が どんな人生を歩いてきたのかはすでによく知られている。生まれて以降、社会人になるまでは比較的順風満帆で、バブル経済の恩恵を受けて学生時代までは恵まれた人生を歩んだ人が多かった。
ところが、学生から社会人になる際に日本は空前の不況に見舞われる。
氷河期世代が体験した無間地獄
1990年代後半から2000年代前半にかけて、日本経済はどん底とも言えるような状態にあった。1990年代前半に不動産バブルが崩壊し、その後世界的な景気後退期にさしかかり、1997年にはアジア通貨危機が世界を襲う。日本では、山一證券が経営破綻し、北海道拓殖銀行など金融機関の連鎖破綻が起きたときでもある。
さらに、2000年にはアメリカ発のITバブル崩壊が起こる。日本も大きな影響を受け、1990年代後半から2000年代前半に就職活動を行った世代は、厳しい就職氷河期にさらされる。とりわけ2000年前後は、大卒でも2人に1人しか就職できない時代を経験することになる。
同世代の非正規社員は371万人(2018年、総務省統計局、労働力調査基本集計より)で、正規雇用を希望しながら非正規雇用で働いている人は50万人に達する。非労働力人口のうち、家事も通学もしていない無業者も約40万人いる。
こうした現実に、厚生労働省も2018年度から就職氷河期世代を正社員として雇った企業に対する助成制度をスタート。「35歳以上60歳未満で、正規雇用労働者として雇用された期間が1年以下、過去1年間に正規雇用されたことがない人」を正社員として雇った企業に助成金を出すというものだ。
「特定求職者雇用開発助成金(長期不安定雇用者雇用開発コース、2019年4月より安定雇用実現コースに変更)」と呼ばれる制度で、無職や非正規社員を正社員として採用した中小企業に対して、1人当たり第1期30万円(大企業は25万円)、第2期30万円(同)、合計で60万円(同50万円)を1年間支給する制度だ。ハローワークを通して、求職活動することが条件になる。
一方、内閣府がこの6月に発表した文書によると、政府を挙げて3年間の集中支援プログラムを実施。次のような人を支援対象としてざっと100万人を救済するという。
①正規雇用を希望していながら不本位に非正規雇用で働く者(少なくても50万人)
➁就業を希望しながら様々な事情により求職活動をしていない長期無業者
③社会とのつながりを作り、社会参加に向けてより丁寧な支援を必要とする者など
具体的には、「安定就職に向けた支援プログラム」 「就職実現に向けた基盤整備に資するブログラム」「社会参加実現に向けたプログラム」などを立ち上げ、民間企業や市町村などと連携しながら就職氷河期世代の自立を促すとしている。
「40歳前後への職業訓練は無意味」「10年遅い」という批判も多いが、実際にこれまで政府は「自己責任論」を盾に同世代への支援には手を付けてこなかった。しかし、未婚率の高止まりや人口減少の原因の1つであることが明白となり、政府も腰を上げざるをえなくなったというのが真相だ。
ちなみに、この世代が注目されたのは、朝日新聞が今から10年以上前に同世代を「ロストジェネレーション」と名づけて、悪戦苦闘する人々をテーマにキャンペーン報道を行ったことがきっかけだ。
今後の日本の大きな問題になると指摘し、大量退職を迎えていた団塊世代以上に注目すべき問題として取り上げている。2007年の元旦から始まったこのキャンペーン報道は、翌年のリーマンショックと重なって注目された。低い時給で過酷な労働環境を強いられながらも、ネットカフェで泊まり歩き、中には餓死する若者の姿も報道されている。
ロストジェネレーション世代という言葉は、やがて就職氷河期世代と名を変えつつ、当時25~34歳だった若者もいまや年齢を重ねて35~44歳となり、10年前に比べてやや減少したものの、いまなお厳しい生活を余儀なくされている人も少なくない。
10年前に「フリーター」や「ニート」だった世代は、いまも「非正規社員」や「引きこもり」と呼ばれ、いまなお苦しい生活を送っているのは間違いないだろう。氷河期世代の「無間地獄」という呼び方もされる。
40歳で非正規社員として、時給1000円前後で働き続ける独身の男性は「いまだに1度もボーナスを貰ったことがない」「結婚なんて夢のまた夢」「時給は上がっても物価も上がった」と証言する。
なぜ就職氷河期世代は「捨てられた」のか?
就職氷河期の悲惨さはどの程度だったのか。統計データから見ても、その現実はよくわかる。例えば、大卒の「有効求人倍率」の推移を見ると、就職氷河期に入る直前の1991年には1人の求人に対して求職数は1.4倍あった。しかし、その2年後の1993年には1倍を割り込み0.76倍まで下落する。
以後、2006年(1.06倍)と2007年(1.04倍)を除いて、2014年までの約19年間。わが国の有効求人倍率は1倍を下回って推移する。1999年には0.5倍を割込み0.48倍にまで下落。2人で1社の求人を奪い合う状態になる。リーマンショック時には、0.47倍(2009年)にまで下落している。
ちなみに、アベノミクスの開始とほぼ同時に、有効求人倍率は1倍を回復したのは事実だが、これは団塊世代のリタイアと少子化の深刻化によって人手不足が顕著になったほうが大きい。アベノミクスの成果として、有効求人倍率が1倍を超えたと単純に捉えるのは危険だ。
ここで注目したいのは、就職氷河期世代の中でもいまだに非正規雇用を余儀なくされ、最悪ひきこもりになっている原因はどこにあるのかだ。そこには、個々の責任というよりも、日本特有のさまざまな悪しき制度や仕組みが根本的な原因といえる。同世代が陥った無間地獄の原因と本質をピックアップすると、大きく分けて次の5つのポイントが考えられる。
原因その1◆日本特有の「新卒一括採用」
世界でも例を見ない新卒一括採用が、日本企業の強みであった時代はとっくに終わっているが、就職氷河期世代の人々にとつては最悪の結果をもたらした。新卒以外での中途入社が難しく、とりわけ非正規雇用だった人材の中途採用には慎重な企業が多い。2人に1人しか正社員として就職できなかった就職氷河期世代にとって、その後、正社員として雇用される機会を奪われることになった。
新卒一括採用の背景にあるのが、終身雇用制と年功序列だ。とりわけ、氷河期世代以前の好景気時に大量採用された社員があふれている現実は、運よく正社員になれた就職氷河期世代も、企業の中でこの大量採用組に苦しめられることになる。
原因その2◆大手企業の労働組合が会社側に寝返った?
戦後、日本の労働組合は強い力を持っていた。それが、高度経済成長時代を迎えてバブル景気に沸いた頃には、すっかり企業と仲良しコンビになり、バブル崩壊による大リストラ時代には、企業の言うことを素直に聞く傀儡(かいらい)団体に成り下がってしまった。就職氷河期世代が就職難に喘いでいた頃には、既存の正規社員も自己の雇用を守るのに必死となり、新卒が極端に減少していることにも目をつぶった。
企業別労働組合の限界とも言えるが、「産業別労働組合」や「クラフトユニオン(職種別労働組合)」のシステムに転換していれば、こんな事態にはならなかったかもしれない。企業別労働組合からの脱出を目指す政党が現れないのも、就業者の80%を超す「サラリーマン(正規、非正規などを合計)大国・日本」にとっては不幸な話だ。
原因その3◆小泉政権時代の非正規社員の規制大幅緩和
就職氷河期世代が不幸だったのは、2000年代はじめに小泉政権が誕生し、非正規社員の規制を大幅に緩和したことだ。それまで許されなかった製造業での非正規雇用を全面的に緩和し、その影響で大企業は正社員の採用を大幅に抑え、非正規雇用を増やす雇用構造の転換を進めることができた。
就職氷河期世代の人たちも、この規制緩和がなければ新卒採用されなかった人でも、中途から正社員になる道はかなり多かったはずだ。そういう意味でいえば就職氷河期世代の悲劇は、小泉政権時代の規制緩和によってもたらされたとも言える。
労働条件の非常識な劣悪化
原因その4◆企業本位の労働環境社会
就職氷河期世代を苦しめた背景の1つに、非正規社員を直接雇用しないまま長年使い続ける慣行があった。
日本の製造業を支える工場での労働力をはじめとして、コンビニやファミレスといった安価で質の高いサービスを支えてきたのは、就職氷河期世代を中心とする非正規雇用の人たちだ。先進国の中では最低レベルの賃金で、長時間労働を余儀なくされた同世代が、日本経済を底辺で支えてきた、といっても過言ではない。この非正規労働者を守るための手段がほとんどないのが現実だ。
問題は、そうした過酷な非正規社員の現状を横目で見ながら、労働基準監督署などの労務管理当局が怠慢を続けたことだ。加えて、司法も貧困問題に対して厳格な判断を避け続けてきた。
そもそも日本では、海外では常識になっている企業内でのいじめやパワハラに罰則規定がない。経団連などの反対で罰則規定が外されたのだが、検察や司法がもっと労働者の立場に立っていれば、就職氷河期世代の悲劇はもっと少なくて済んだのかもしれない。
さらに、下請け会社や個人を元受け会社から守る「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」の法整備が行われたのも2003年以降のことだ。
こうした法律の不備や労務管理当局の怠慢が、同世代を苦しめている一因でもある。政府と密接な関係のある芸能プロダクションと所属芸人との間に正式な契約書がなくても通用する――。それが日本の労働環境の常識だとしたら、あまりにお粗末だ。
原因その5◆起業、独立に厳しい社会環境
もう1つ原因があるとすれば、正社員になれなかった就職氷河期世代が、起業して自営業になるという道があったにもかかわらず、その道へあまり進めなかった現実がある。日本では、そういったビジネス環境が整っていないためだ。
何の実績もない若者に事業資金を融資してくれる銀行はほとんどないし、連帯保証人の問題もある。政府の開業資金融資制度も、ハードルが高く、あまり現実的ではない。起業家の才能や熱意を評価して、潤沢な起業資金を融資する投資家が多いアメリカとは大きな違いだ。
ただ、最近は「クラウド・ファンディング」など変革の兆しもある。同世代も、日本に閉じこもっていてはいけないのかもしれない。
支援プログラムが役に立たないこれだけの理由
さて、厚生労働省が今年5月に発表した就職氷河期世代への就職支援プランだが、はたして有効なプランと言えるのか。
施策の方向性としては、「相談、教育、訓練から就職まで切れ目のない支援」を行い、ハローワークに専用窓口を設置。キャリアコンサルティング、生活設計面の相談、職業訓練の助言、求人開拓などの各専門担当者のチーム制によるきめ細かな「伴走型支援」を実施するとしている。
ただ、結論から言うと、就職氷河期世代に対する救済プログラムが本当に機能するのかどうかは疑わしいところだ。例えば、「地域若者サポートステーション」と呼ばれる就労サポート窓口が全国に175カ所設置されているが、40歳以上の就職氷河期世代に対する公的支援は全国でわずか十数カ所開設されるだけだ。
通称「サポステ」も、15~39歳のニートやひきこもりを対象にした制度だが、40歳以上のひきこもりは推計で61万人、サポステ効果も限定的と言わざるをえない。
また前述した特定求職者雇用開発助成金も最大60万円が企業に支払われるが、2018年度に給付された金額はわずかだ。その金額はあまりにも少ない。
筆者の個人的な感想だが、企業にお金を出すのではなく、同世代の非正規雇用者に自立支援金といった名目で、直接資金を融資するほうがいいのではないか。そのお金で起業するのもいいし、海外を放浪してくるのもいい。先進国の多くは、大学を卒業してすぐに就職するのではなく、海外で見聞を広げる制度が充実している。
就職氷河期世代にターゲットを絞って救うプログラムもいいが、本質は「貧困問題」と同じだ。最近になって、NHKも取り上げた「外国人技能実習生の奴隷化」問題にしても、結局は就職氷河期世代だけでは対応しきれなくなった人口減少、人手不足の対応策として、海外の留学生がターゲットにされているだけなのかもしれない。
京アニ放火事件のような凶悪犯罪の加害者をネットでは「無敵の人」と呼ぶ。失うものが何ひとつない、無敵状態の人という意味だ。今後、10年が経過して彼らが45歳から54歳になったとき、日本はどうなっているのか。このロストジェネレーション世代が、その時まだ「無敵の人」であるとしたら、その社会はあまりに理不尽だ。
日本の「失われた20年」と構造改革の失敗
1990年代に始まる日本経済の長期停滞は、2002年には終わらず今も続いており、この間の日本経済を「失われた20年」と呼ばれることが多くなってきた。日本の名目GDPで確認すると、1990年から2010年までほぼ500兆円前後で停滞したまま推移している。他の国がGDPを上昇させる中で、日本だけが成長を止めたまま20年が経過している。(図1)国民一人あたりの名目GDPでは、1990年代に世界3位くらいだったものが、2007年19位、2008年23位、2009年19位と大きく順位を落としている。(図2)日本では物価が上昇しないが給料も上がらないという状況が続いており、消費や投資などの内需が増えていない。産業分野でも、かつて世界を席捲していたエレクトロニクス市場で軒並みシェアを落としている。日本市場では日本製品が幅を利かせているが、海外ではLGやサムソンがシェアのトップ。日本製品は一部のお金持ちの趣味のブラ※4ンドになっている。鉄鋼でも、アルセロール・ミッタルが世界一の生産量を誇っており、新日鉄は中国や韓国のメーカーにも抜かれて4位(2009年)となっている。 小泉政権が主導した構造改革は、日本の成長のためには聖域なき構造改革が必要だという主張の下、三位一体の改革、郵政民営化、各種の規制緩和などが行われたものだ。この構造改革について、改革は必要だったが、結果として都市と地方の格差や国民の貧富の差を拡大し格差社会を進めた、といった意見が多い。改革の路線は間違っていないが、影の部分が大きくなってしまった、という論調だ。私はそうではなく構造改革は成長戦略としても失敗したのだと考えている。先に紹介したように、構造改革が始まった2000年以降現在に至るまで、日本の成長力も国際競争力も低下している。「失われた20年」のうち、2000年以降の10年は構造改革の失敗によるものといっても過言ではない。
※4 アルセロール・ミッタル ヨーロッパのアルセロールとインドのミッタル・スチールの経営統合によって、2006年に誕生した世界最大の鉄鋼メーカー。年間粗鋼生産量で世界シェアの約10%を占める。
2007年5月21日
ポリシーウォッチャーの役割
「改革の日々が始まった」-2001年4月26日、それはまるで、日本最大のお祭りのようだった。国民的熱狂、聖域なき構造改革、抵抗勢力とのすさまじい戦闘。小泉内閣という奇跡の内閣が誕生した瞬間を、著者はときめきと興奮をもって振り返る。
本書は、従前の日本政治においては考えられなかった異色のリーダー・小泉総理の下、要職を歴任した竹中平蔵氏の挑戦の記録である。「小泉総理の下、日本は間違いなく変わるだろう。そう思ったからこそ私は、大臣就任を引き受けた。これからその変革の『歴史的瞬間』に立ち会いたいと思う。」という書き出しから始まる著者の大臣日誌に基づきながら、不良債権処理、郵政民営化、経済諮問会議の舞台裏が生々しく語られている。
「改革なくして成長なし」-しがらみを持たない強いリーダー小泉総理は、当選回数や派閥からの人事を一切行わず、金融再生プログラムや郵政民営化といった改革を断行した。この改革の中で、重要な役割を果たしたのが、民間出身の経済学者として専門的見地を政策に活かす役割を与えられ、入閣した竹中大臣であった。抵抗勢力のなりふり構わぬ陰謀や策略に遭いながら、いかにして改革を断行したかが、本書の見所になっている。また、本書は、著者の日誌をベースに書かれているため、さまざまな場面が、せりふや感想とともにリアルに語られており、冒険書を読むような面白さがある。そして、随所に見られる小泉総理のリーダーシップも見逃せない。不良債権処理をめぐり、抵抗勢力にののしられ、辞任を迫られる竹中氏に、当て付けのように金融担当大臣兼務を命じる場面や与党幹部の夕食会で、郵政民営化の「基本方針は絶対変えない。ちゃんと理解しておけ。自民党はとんでもない男を総裁にしたんだ」と、反対を強める党側へ迫力の宣戦布告をする場面などは圧巻である。
さて、よく小泉政権に対して、「劇場型内閣」「骨抜きの政策」だなどと、人気があるが中味のない政権であるかのような批判があったが、本書を読む限り、骨抜きではない改革が実行されたように思える。小泉内閣の改革の成果については議論のあるところだが、少なくとも、日本の経済再生のために、以前から散々問題視されながら放置されていた不良債権処理に着手し、金融再生プログラム(竹中プラン)を実行、りそな銀行への公的資金注入など、金融改革を断行したことは、評価できるのではないか。
なぜ、今まで散々先送りされてきた金融改革を断行できたのか?なぜ、総選挙を行うほどの抵抗に遭った郵政民営化法案が成立したのか?もちろん、歴史的な国民の支持と小泉総理のリーダーシップがあったことは確かだが、改革を主導した竹中大臣の専門家としての力が大きかったことは間違いない。竹中氏は、「骨太方針」の決定、「工程表」の作成、そして「戦略は細部に宿る」という共通認識のもと、官僚の思うがままに作られていた「政策の制度設計」を大臣自らが詳細に作るという「政策決定プロセス」によって、総理の意思を貫く、政治主導型の改革を実現していく。特に、制度設計は、従来、官僚「霞ヶ関文学」の専売特許であり、その知恵は官僚に独占されていた。竹中氏は、30年間「政策」を勉強してきた「政策研究者」として、政策の重要性を理解し、政策の骨組み、つまり法律の条文や施行後の運用ルールなどを詳細に検討。抵抗や妨害、骨抜きにされることを予測し、常に二手三手先を読みながら作戦を練り、抵抗勢力との合意形成に挑む。そして、譲れないところは妥協せず、打開点を探る戦略家の一面も見せる。「普通のこと」がなかなか実現できない日本において、実行力のある改革を断行するポイントは、この「政策」「政策決定プロセス」をいかにうまくやるかにあったようだ。
著者自身は、自らの大臣経験を振り返って「昆虫学者が昆虫になったようなものだ」と語っている。小泉総理の熱意に共感して、自分が研究していた対象の世界に足を踏み入れ、自らが研究の客体となったわけである。自らがプレーヤーとして、官僚の無謬性と戦い、業界・政治家・官僚の「鉄のトライアングル」へ挑戦し、マスコミや学者から激しいバッシングを受け、戸惑い、悩み、立ち向かっていく。この得難い体験を通して、「政策は難しい」ことを実感する。また、「優れた植物学者が、即優れた庭師である保証はなにもない」のと同じように「経済学や政治学は間違いなく政策のために必要ではあるが、政策の専門家と経済学者、政治学者は同じではない」と説明する。そして、評論や絵空事を言う学者ではなく、実務的な知恵と将来的なシナリオを描ける「政策専門家=ポリシーウォッチャー」が必要であると主張する。
ポリシーウォッチャーの役割は、政策の調査研究、分析評価、監視、提言を行うことと情報発信を行うことである。特に情報発信を通して正しい世論を形成することで、「よく知らされた国民」(Well informed public)を生み出すと著者は言う。情報は溢れているが、スキャンダルやゴシップネタばかりで本当に有益な情報(政策論議や政策分析)となると極端に少ないというのが現状ではないだろうか。小泉政権を通して、また最近の政治からも、世論の力、国民の支持の重要性が注目されている。国民が適切な判断を行うことで、良い政策が生まれ、さらに政策が実行されているかを評価監視することで、政策がより良い方向に向かうという好循環が生まれるというわけである。
「政策は難しい」という難問にどう立ち向かうのか。著者は、「政府の中核で政策を実行した経験を、政策専門家の育成に役立て、民主主義のインフラとして、政策専門家が民間部門から政府の政策をしっかりウォッチし、国民に伝えるという機能を果たしていきたい」と決意を語っている。ポリシーウォッチャーを通した「民主主義による世論の後押し、政治主導の構造改革、力強い日本」の実現。竹中氏の挑戦は、まだまだ続きそうである。
2006年09月20日
小泉構造改革が残したもの
森重 透
1.「いざなぎ超え」とは言うけれど
マクロ経済は、長期にわたったデフレ局面からの脱却を視界に入れつつ、足もとなお拡大を続けている。2002年2月から始まった今回の景気回復は、すでにこの5月に「平成バブル景気」を抜き去り、2002年11月には「いざなぎ景気」(1965~70年、57ヶ月)を超え、戦後最長となりそうな勢いだ。
しかし、実質GDPの伸びで見た景気拡張期間はなるほど長かったかもしれないが、国民一人ひとりの生活実感から見れば、まさに「実感なき景気回復」ではなかっただろうか。そして、それはなぜかを考えれば、今回の回復局面の特徴が明らかになろう。
まず、息の長い回復ではあるが低いレベルの成長だったことだ。「いざなぎ」は年平均成長率10%超、「平成」は5%程度だったが、今回は2%強と「平成」の半分にも及ばないレベルである。成長率と拡張期間の積和でこの間の実質GDPの伸びを見ても、「いざなぎ」当時は約1.7倍であるのに比べ、今回は1.1倍程度に過ぎず、さらに名目GDPの伸びで見れば、その差は2倍以上にも拡がる。横綱と前頭筆頭ぐらいの差はあるのではないか。とくに、緩やかなデフレ下の回復のため名目値がほとんど伸びなかったことは、実感の乏しさをより強めたはずである。
二番目の特徴は、企業部門と家計部門の所得状況の違いだ。「経済財政白書」(7月)には、「企業部門の改善によって家計にも好影響が及ぶ好循環がみられる」趣旨が盛り込まれているが、雇用環境には目に見える改善があるとはいえ、賃金・可処分所得関係の統計では、むしろ家計の疲弊ぶりが顕著であり、4年以上も続いているのに景気回復の恩恵は家計・個人にはほとんど及んでいない、と言ってよい。企業部門から家計部門への波及(トリクル・ダウン)の遅れは、企業が業績好調にもかかわらず、賃上げ幅を低く抑え続けているからである。今回の景気回復は、大企業の資本の論理、すなわち、リストラ、非正規雇用の拡大等による賃金コスト削減をバネにもたらされた側面が大きいが、それがまだ続いているということだ。
そのほかの特徴としては、米国経済の好調や中国特需などに支えられた外需主導、デジタル家電ブーム等、一部の大企業・製造業に偏った回復であったことなどから、多くの中小企業や非製造業への波及が遅れていることも挙げられる。また、地域間で景気回復のテンポや景況感に大きな格差があり、これがなかなか縮まらないことも、全体的に景気回復を身近に感じられない要因の一つだろう。
2.二極化・分断化の進行
このように、マクロ面で見れば、実感が乏しいとはいえ息の長い景気回復が実現したことは事実である。しかし、この回復が、間もなく終結を迎えようとする小泉内閣の構造改革の取組みによってもたらされたか、ということになると疑問符が付く。「構造改革なくして回復(成長)なし」、「官から民へ」、「中央から地方へ」を標榜した構造改革路線が、スローガン通りの実行力を伴ったものでなく、今回の景気回復とは無関係であることは、すでに本コラムでも何度か指摘した。また今年の「経済財政白書」(7月)も、企業の適応努力こそが日本経済回復の主役と正当に位置づけているし、多くの識者の見方もこれに沿うものが圧倒的に多い。
むしろそのことよりも、この小泉政権下の経済運営によって、構造的には深刻な問題が発生した。経済社会の二極化・分断化の進行、社会生活基盤の劣化、という由々しき問題である。下掲グラフは年齢階級別完全失業率だが、15~24歳の若年層の失業率・学卒未就職率は、この間一段と上昇し、高止まりしていると言ってよい状況である。失業こそは、一個人を社会的・経済的弱者に転落させるもので、とくに若年層で定職に就かない者がなお多く存在するという現実は、これからの日本の国力や競争力、社会保障システムへの悪影響を考えると憂慮させるものがある。
さらに、パート、アルバイト、派遣社員など「非正規雇用者」は、すでに雇用者数の約3人に1人となった。ここでも若年層(15~34歳)の雇用情勢は厳しく、失業の長期化、フリーターやニートの増加、そしてフリーター経験をプラスに評価している企業がほとんどないことから、彼らが中高年になっても非正規雇用者にとどまってしまう懸念がある。こうなると、4対1とも言われる正社員との給与格差が固定化されるとともに、累積的に所得格差が拡がり、生活基盤の劣化、ひいては非婚・少子化などの様々な問題を助長する恐れがあるのだ。過重な労働実態、過労による労災件数の増大、ワーキングプアの増加、うつ病、突然死など、今日、雇用の劣化あるいは崩壊とも呼べる事例は枚挙にいとまがない。
このような状況も反映してか、7月に発表されたOECDの「対日経済審査報告書」によれば、先進30カ国の相対的貧困率(平均値に比べて所得が半分未満の相対的貧困層の割合)で、日本は米国(13.7%)に次ぐ二番目の高さ(13.5%)だったそうだ。そして、労働市場の二極化傾向の固定化の恐れを警告され、格差是正の具体策として、非正社員への社会保険の適用などを指摘されているのである。
このほかにも、大企業と中小企業、都会と地方、高齢層と若年層、官と民等々・・・規模・地域・年齢・官民間に存在する諸々の二極分化(格差の拡大と固定化)の問題を真摯にとらえ、これを是正しながら持続的成長を模索していくというような、「徳のある経済政策」は、小泉政権下ではついにお目にかかれなかったと言ってよい。
3.何が欠けていたのか
「聖域なき構造改革」という看板を掲げた小泉構造改革路線は、約5年半に及んだ小泉政権のバックボーンであったはずなのに、結局それは、「小泉劇場」の主役・小泉純一郎が大見えを切るときの小道具に過ぎなかったようだ。
新規国債発行30兆円枠の公約は、「この程度の約束を守れなかったというのは大したことではない」と言って、簡単に破られてしまった。公的年金改革を審議する年金国会での、「人生いろいろ」発言に見られるような、おちゃらかし発言。はぐらかしや、レトリック依存型の国会答弁も多く見られた。地方の景気にも目配りすべきではないかとの記者の問いに、小泉首相は「官から民への流れは変わらない。政府が口出しすべきではない」と答えたそうだ。道路公団の「民営化」は、結局、妥協の産物に終わった。そして、改革の「本丸」と意気込んだ「郵政民営化」は、その意味や効果が不鮮明なまま、分社化を伴う株式会社化で行き暮れようとしている。結局、高い人気に支えられ、連日劇場は満員御礼だったが、バックボーンは最後まで「小道具」で終わった。
「改革なくして景気回復なし」の名の下に、実体的な景気対策には関心が薄く、かと言って、公的セクターの改革、すなわち、責任ある社会インフラの構築と質の高い公共サービスの供給という、「民」が果たせない「官」の固有の役割というものを、いかに実効ある形で遂行していくかといった制度問題を、徹底的に真摯に議論する風でもない。詰めた議論よりは、歯切れの良い「ワン・フレーズ」で「改革」をくさびとして使い、多くの「抵抗勢力」を放逐しつつ人気を得ていくという手法は、まさに独壇場と言えるものだった。
しかし、「改革の本丸」であるべき財政再建問題と、これに密接にからむ社会保障制度と税制のあり方に関する真摯かつ周到な議論と実践を抜きにしては、「経世済民」を託された責任ある政治家としての本務は果たせないのではないか。「ノブレス・オブリージュ」とは、財産、権力、社会的地位には責任が伴うことを言う。小泉首相に限らず、政治家全員がこのことを心に銘じるべきだろう。
【論文】マーケットはなぜ小泉政権の改革を疑問視するのか
2001年8月04日
sheard_p020710.jpgポール・シェアード
小泉政権は「聖域なき構造改革」を打ち出しているが、この実現可能性について、マーケットは非常に大きな不信感をもっている。
■ 矛盾だらけの経済政策を繰り返すな
なぜ不信感をもっているのか。その理由は、日本がまた、いつもと同じような失敗を繰り返すのではないか、という懸念が拭い去れないことにある。日本はいつも、過去になぜ失敗したのかという事後的な点検が行われないままに、次の政策を展開しようとする。そして、いつも矛盾
「骨太の方針」、すなわち経済財政諮問会議の基本方針は、不良債権処理に関しては、2001年4月6日に経済対策閣僚会議で決定された緊急経済対策の考え方を継承している。緊急経済対策には、問題の本質をついた、さまざまないい意見が書かれているが、その大きな目玉は、やはり不良債権処理が最大の課題である、というものだった。
ちなみに、それより少し前の3月19日に日銀は政策決定会合で「通常では行われないような、思い切った金融緩和に踏み切る」ことを決定しているが、その議事録のなかにも、不良債権問題の解決が急務であるという趣旨の文章が入っている。
こうした流れからいくと、4月6日の時点での政策の結論は、やはり不良債権処理が最重要課題だ、というものだったといえる。
最近、不良債権を「2~3年以内に処理する」という言葉の意味が議論されないまま、独り歩きしている感があるが、緊急経済対策のなかには、主要行について、「破綻懸念先以下の債権に区分されているものについては、原則として2営業年度以内にオフバランス化につながる措置を講ずる」、それから、新規発生分については「原則として3営業年度以内に......措置を講ずる」と書かれている。
これは非常に重要なポイントだ。なぜなら、この「措置を講ずる」という表現は、金融監督庁のマニュアル、あるいは旧大蔵省の行政に従ってやってきた過去の金融再編行政では、不良債権は解決しない。今までのやり方を白紙に戻して、2~3年以内に不良債権をかたづけよう、という強い意思表明の表れだからだ。
今回の基本方針も、この方針に沿って、「不良債権問題を2~3年以内に解決することを目指す」、「経済再生の第一歩として、不良債権の処理を急ぐべきである」とはっきり書いてある。多くの人はこれを読んで、正しい方向に動いていると思うだろう。ところが、である。今回の基本方針には、不良債権の最終処理は「金融機関の自主的な判断で進められる」というくだりが入っている。 これでは、全く話が違ってしまっている。4月の緊急経済対策で、「過去の行政のもとで、金融機関が自主的に問題に取り組んできたけれども、そのやり方では解決しない。政府が主導権をとって、2~3年以内に解決させる」という強い意思表明をしたにもかかわらず、ここでまた、「自主的な判断で進められる」ということでは、議論するまでもなく、問題解決にはならないだろう。
ちなみに、不良債権問題の裏側にある借り手企業/産業については、私的整理のためのガイドラインを「関係者間で早急に取りまとめることが期待される」と書いてある。
もちろん日本の場合、「期待される」、あるいは「自主的な判断で進められる」といった場合、それは国が強制的にやるといっているのと同じだという解釈もないわけでもないが、それは一昔前の行政のあり方を反映した解釈だ。つまりそれは、不透明な、玉虫色的なやり方にもなっているということだ。
■ さまざまな数字が独り歩きをしている
それに、緊急経済対策にも、踏み込み不足だった点がある。ひとつは、対象を全預金取扱金融機関ではなく、主要行に限定していたこと。もうひとつは破綻懸念先以下の不良債権に絞って話をしていたということだ。
詳細は省くが、これでは、ペイオフ延期などの過去の政策との整合性がないばかりか(ペイオフ延期のときは、主要行は大丈夫だが、信金や信組などは検査不十分で不安だから、という説明がなされた)、不良債権問題を全体的に把握することはできない。いうまでもなく、マーケットが非常に神経質に注意を払っているのは、不良債権の全体の大きさだ。ところが、上述したように、限定した見方をとっているために、いろいろな数字が独り歩きをしてしまっている。
例えば、一時期新聞を賑わせた12兆~13兆円という数字は、主要行の破綻懸念先以下のものを指している。しかし全銀行ベースの問題債権は64兆円で、全預金取扱金融機関ベースでは81兆円くらいあるとされている。また最近では、151兆円という数字が独り歩きをしている。これは民主党が金融庁から取り寄せた数字で、要注意債権以下の債権をもっている借入先の全借入金を示している。
われわれプロでも、これらの数字の使い方にはものすごく苦労している。この間、民主党の鳩山氏が「150兆円という数字をどう思うか、大手行の資産査定を厳格にやり直すべきだ」という趣旨の発言をしたところ、首相は「元利払いや貸出条件に問題がなく、単に注意が必要な債権は100兆円ある」と答えた。この発言は、要管理債権以下の不良債権以外の要注意債権が100兆円ある、ということだが、公表ベースでは、こういう数字は出てこない。一国の総理大臣が、国会でこのような答弁をしていることからもわかるように、問題の大きさがどれくらいであるのか誰にもわからず、マーケットは政府に対して依然として不信感をもっているのである。
■ 危機対応の制度的枠組みが不在
マーケットが不信感をもっている第2の理由として、金融再編の枠組みが不在だということが指摘できる。2001年1月には行革の一角として金融再生委員会が廃止された。金融再生委員会は、金融問題を解決するために特別につくられた組織だったにもかかわらず、その仕事が終わる前に廃止されてしまった。日野正晴前長官は退官のインタビューで(『日本経済新聞』2001年2月2日)、「本当はペイオフ1年延期時に、それと連動して金融再生委員会や再生法、健全化法も延長すべきだったが、議員立法なのでこうなってしまった」と述べている。筆者も全く同感である。3月末には、資本増強の枠組みも期限切れとなってしまった。
そしてその6日後に政府は公式見解として(緊急経済対策)、不良債権が日本経済のいちばん大きな問題だ、この問題に集中的に取り組む、ということを表明した。1998年にも同じ議論があり、問題解決のために60兆円のパッケージと金融再生委員会をつくった。その枠組みを廃止した途端に、改めて問題の重要性、枠組みの必要性が認められるというのは、酷評すれば、先進国の経済政策としては大問題だ。少なくとも説明責任というものがある。そうしたことを議論しないで、ポッポッと次の政策が出てくるというのはいかがなものか。
もっとも、枠組みがないというのは多少言いすぎで、実は金融危機対応枠組みというものが4月1日からスタートしている。それは資本増強、国有化、(ペイオフコスト以上の)預金者保護という3つの機能を持ち備えている。
ただ問題は、危機がなければこの枠組みが使えないということだ。これに対し98年の枠組みは、危機の産物としてできたもので、危機がなくても、危機が起こらないように使うことができた。
こうして、不良債権問題の重要性に対する認識と、その問題を解決するために用いる制度的枠組みとの間に、大きな空白ができている。そうした空白があるからこそ、いろいろな方針や意見が錯綜しているといえる。つまり枠組みがないから、金融機関が自主的判断ベースでやるしかないということになっている。だが、金融機関の自主的判断ベースではこの問題は解決されないことは目に見えている。自主的ベースでできるような話であれば、とっくの昔に解決しているはずだからだ。
■「財政再建」重視の危うさ
第3に、小泉首相が財政再建を最重要視しているのではないか、ということだ。首相の所信表明演説を見ると、「不良債権処理や資本市場の構造改革を重視する政策へと舵取りを行う」とし、1に不良債権問題の解決、2に規制緩和、3に財政再建を行う、と述べている。筆者はこのポリシーミックスと順序づけにはおおむね賛成だが、小泉内閣が実際にやっていること、あるいは発信しているメッセージを見ていると、不良債権処理がかなり後退している感じを受ける。特に、上述したように、「措置を講ずる」が「自主的判断で進められる」というように後退しているのが気になる。むしろ第3の財政再建をアジェンダの上位にしようとしているらしい。
例えばここ2カ月間の議論をみると、田中真紀子氏が多くの話題を提供してきたが、それはともかく、経済面では新規国債発行を30兆円以内に抑制するなど、財政再建の話題でもちきりだった。だが経済の現状を考えると、財政再建に今踏み込むことは非常に厳しい緊縮財政になりかねない。すると不良債権問題の先送りと財政再建の優先という、橋本政権のときと全く同じポリシーミックスとなってしまう。
こうして、橋本、小渕、森の各政権から得られたはずの教訓が生かされず、また元に戻ろうとしており、"不思議の国のアリス"のような経済政策になっている。
■ 構造改革断行の2つの選択肢
以上、小泉内閣の経済政策・構造改革の基本方針について検討を加えてきたが、これらの一連の議論を見ていて、問題だと感じるのは、政府がどちらの方向に進もうとしているのか、その方向性が見えないということだ。
改革を断行するに当たり、政府には大きく分けて2つの選択肢がある。ひとつは期限を区切ったうえで、自ら主導権を発揮して改革を進めることだ。この場合は、金融再生に向けた新しい枠組みづくりと、危機を未然に防ぐための公的資金の投入が必要になる。またマーケット・メカニズムを最大限活用し、新しいマーケットが育成されるようなやり方をとる必要がある。
もうひとつは、市場に任せるという、まさにハード・ランディング的な解決策だ。この場合は、ペイオフの早期実施と、金融危機対応枠組みを極力使わないという覚悟、それに労働市場、小口預金者保護などのさまざまなセーフティ・ネットが必要になる。加えて、緩和的なマクロ政策と、規制緩和などの、経済体質を強化するためのミクロ政策を次々と実施しなくてはならない。
後述するように、筆者は前者の政策を取るべきだと思っているが、今のところ、小泉政権がどちらの方向に進もうとしているのかが見えない。むしろ、このどちらでもなく、中間の道を歩んでいるようにも見えるのである。すなわち、危機が起きると政府が動き、その際、マーケットを阻止するような政策を取るという、これまでと同じ過ちにはまってしまう可能性がある。
公的資金の投入や銀行保有株式取得機構の設置、それに貸し渋り対策などで、政府は銀行に対してあらゆるところで関与を強めている。これでは、マーケットに任せるという2つ目の選択肢は取りえない。こうした状況では真の意味でのマーケット・ベースということはできない。それにもかかわらず「金融機関の自主的な判断で進められる」という表現を用いたりするので、混乱が生じることになるのである。
国が関与することにさまざまな弊害があるのは十分承知しているが、筆者は、ここまで国が関与を強めている以上、国が主導権を握り、期限を区切って市場を生かす形で改革を断行したほうがいいと考えている。ところが、では主導権を発揮しているかといえば、それも中途半端な状態にある。
実は私は財政再建の信者だが、一回限りの措置として、金融問題の解決のために公的資金を30兆円入れるということを断行すれば、日銀はそれを支援するだろうし、それが2年後のマーケットの発展につながるということであれば、マーケットもそれを評価するのではないか。だが、小泉首相は財政再建という目標があるために、公的資金を投入するという流れをつくれないでいる。こうしたことから、マーケットから見ると、財政再建を優先していることが、実は不良債権を断固として処理するという腹が固まっていない、と見えてしまうのである。
■今は財政再建を打ち出すな
では、具体的に小泉首相はどういったアクションを起こすべきか。
まず、今の局面では財政再建を打ち出さないことが必要だ。今財政再建を打ち出すと、それはものすごい緊縮財政になってしまう。
仮に出すにしても、出し方を工夫すべきだ。実は財政構造改革と財政再建は違う。財政構造改革というのは、財投改革や公的金融機関の民営化、あるいは効率的な税制システムの構築などのミクロ的な改革だ。これは今すぐにでも実行できるし、これをすぐに行うことには筆者も大賛成である。
一方で、今の経済局面のなかで、どれだけの財政出動が必要なのかという問題がある。これが財政再建の問題だ。日本の場合は、この2つの概念がいつもこんがらがってしまっている。前総理の橋本氏も、財政再建を実現したかったために財政出動を締めたが、本当の財政再建は、経済を回復させなければ成り立たない。そこで、では経済を本当に回復させるには何が必要なのか、という議論が、財政再建の中枢にくるはずだ。
そこで、不良債権がいちばんのネックであるという判断なら、それをやるべきだし、非効率的な財政の仕組みの問題であるなら、それを見直す必要がある。そのなかで必要に応じて財政出動をすることもありうべき選択肢だろう。預金者保護と不良債権処理を同時に達成するためには、例えば30兆円というコストがかかることもあるかもしれない。この場合は、短期的には財政再建はできなかったということになる。
つまり、すべての政策目標、特に矛盾しあっているいくつかの政策を同時に達成することはできない。それなのに、あれもやる、これもやると主張するのは、部分的な発想でしかない。まず不良債権処理に重点を置くべきである。
財政再建は確かに重要な課題ではあるが、それが本当に緊急の課題がどうかを考えると、実はそうでもない。ひとつは、日本のマクロ的な現状をみると、民間部門の黒字を政府が吸収しているという面がある。そうなると、問題は個人の将来不安が解消されていないから、また規制緩和が不十分で日本企業の投資プロジェクトに問題があるから、あるいは金融システムが十分に機能していないから、民間部門が活性化されない、ということになる。
この問題を解決するには、IT関連を中心に規制緩和を実行することだ。そうすれば、さまざまな形で、新しい需要と新しい投資機会が生まれてくる。そして結果として、税収が増えて、政府の赤字も減っていく。
もうひとつは、国債の利回りだ。これは現在1.2%程度であり、財政再建をやらなければ日本は破綻する、というメッセージをマーケットは発信してはいない。しかし小泉政権は、あたかもそうしたメッセージが発せられているかのように動いている。橋本政権時の増税と同じく、小泉政権でもプライマリーバランスの赤字を支出削減で抑えようとしているが、それは因果関係を間違えている。まず解決すべきは不良債権問題である。
■戦略的にマーケットを活用せよ
そこで、不良債権処理を進めることを考えるとき、ぜひ指摘しておきたいことは、戦略的に、マーケット・メカニズムを最大限に生かすことが重要だということだ。これは、政府が主導権を取るという方向とは、一見矛盾しているように見えるがそうではない。例えば、しばしば引き合いに出されるアメリカのRTC(整理信託公社)は、預金の全額保護をせずに、破綻懸念の金融機関をつぶして、預金保険機構でカバーされていない人たちに債権カットに応じさせた。同時に、RTCは資産を取って、資産価値と預金保険機構でカバーされている額との差額を埋めた。これは預金者保護の鉄則です。そのうえで、受け取った資産をすぐさま売却した。
RTCがそうしたように、資産を売却すると、非常に大きなマーケットが育成される。現在、非常に大きな規模になっているCDO(Convertible Debt Obligations)やABS(資産担保証券)は、実はRTCが登場するまではなかった。これが、マーケット・メカニズムを最大限生かすということの意味だ。銀行の国有化や買取機構、それにペイオフの延期といったやり方は、やはり問題だろう。
ただ、日本の現状を見ると、残念ながら現に政府はそれをしていないし、今までの経験から見ても、ほとんどやる意思とやる能力がなさそうである。
今後の政策の展開次第では、金融は、おかしなことをやる可能性がある。政府の要人はいろいろなところで、低成長には甘んじなければならないけれども、マイナス成長はだめだと発言しだしている。一方で財政再建論者が趨勢を握ったとすれば、やはり金融危機が起こる。そして財政再建プラス金融危機イコールマイナス成長となったとき、マーケット・ベースで進まないような手を考え出してくる可能性がある。ペイオフ延期はないにしても、危機対応枠組みを使って実質的な全額保護の延長をやりかねないなどの危険性が残っているのである。
日本人の間では、金融危機が起きたときに危機を止めるのは政府の要件だから、それも仕方がない、という考え方があるようだが、それは違う。そもそも不良債権があるから危機が起きるのであって、危機を封じ込めたければ、そうした全面保護のような形で政府が対応するのではなく、まず政府が主導権を取って不良債権を処理すべきなのである。そうでないと、金融危機対応枠組みがまた悪用されることになってしまう。
この論文で検討してきたようなポリシーミックスを実現するには、本来なら経済財政諮問会議のようなところで総合的に調整する必要がある。その点では、竹中氏も精いっぱい努力しておられるようだが、まだ理想的な形には至っていないと思っている。現在の小泉政権には、政策を立案する陣容はあっても、それを実行に移していくというシステムがない。それが小泉政権のアキレス腱ともなっている。
ここまで小泉政権に対して、批判的な検討を加えてきたが、小泉政権は、構造改革を断行すると述べている内閣であり、その意味では期待もしている。これまでと同じような愚を犯すことなく、構造改革に踏み込んでいってほしいと思っている。それが日本経済を停滞から脱却させる道である。〈了〉
サウジへの 一帯一路(債務の罠外交)始まる!
、元建て取引推進で米揺さぶり 習氏
2022年12/10(土)
【カイロ=佐藤貴生】サウジアラビアを公式訪問した中国の習近平国家主席は2022年12月9日、サウジアラビアの首都リヤドで初めて開催された中国とアラブ諸国の首脳会議に出席し、「中国とアラブの関係は歴史的に飛躍した」と述べ、会議の成果は協力の「新たな出発点」になると称賛した。発表されたコミュニケでは中国、アラブ双方が互いの重要政策に支持を表明したことが確認された。
国営サウジ通信が報じたコミュニケによると、台湾については「中国の領土の一部」だとして「独立」を排し、香港への統制を強化する中国当局の姿勢に支持を表明した。 一方で、中東和平ではパレスチナ国家建設によるイスラエルとの「2国家共存」案を支持するとした。
テロ対策では「ダブルスタンダード」を拒否すると言明した。中国当局によるウイグル族など少数民族弾圧や、アラブの強権体制による反体制派の締め付けが念頭にある とみられる。
エネルギーに関しては、経済成長確保のために「バランスが取れたアプローチ」が重要だとし、主要なエネルギー源を除外しないことで一致した。地球温暖化で化石エネルギーの削減が国際的な課題となるなか、世界最大の原油輸入国である中国と、原油・天然ガスの輸出国があるアラブの思惑が反映された 。
会議ではサウジ首相のムハンマド・ビン・サルマン皇太子が議長を務め、エジプトのシーシー大統領やヨルダンのアブドラ国王らが参加した。習氏は2022年12月9日、ペルシャ湾岸諸国との首脳会議にも出席した。
サウジアラビアを訪問中の習近平国家主席は2022年12月9日、中国・湾岸協力会議(GCC)首脳会議で演説を行い、石油・ガス貿易の人民元建て決済を推進する姿勢を表明した。人民元を国際通貨として確立させ、世界貿易における米ドルの支配的地位に揺さぶりをかけた格好。
習氏の訪問に際し、サウジの事実上の指導者であるムハンマド・ビン・サルマン皇太子はアラブ諸国との一連の「画期的な」首脳会議を開催した。西側各国とのこれまでの歴史的関係を超えたパートナーシップを模索する姿勢を示した。
2022年12月この日の会談の冒頭、皇太子は「中国との関係が歴史的な新局面」入りする と表明。バイデン米大統領が2022年7月にサウジを訪問した際の控えめな歓迎とは対照的だった。
人権問題やエネルギー政策、ロシアへの対応を巡り米国との関係が冷え込む中、サウジと中国はともに「内政不干渉の原則」に関する強いメッセージを発信した。
米国は中東地域での中国の影響力拡大に神経をとがらせている。
一方、サウジのファイサル外相は2022年12月9日、サウジはどちらかの側につくことはせず、米中を含む全ての経済大国と協力すると語った。
サウジと中国は複数の戦略的・経済的パートナーシップ協定に署名した。アナリストによると、中国企業が技術やインフラ部門に進出しているものの、軸足は当面、エネルギー問題に置かれる見通し。
アラブ湾岸諸国研究所(ワシントン)の上級研究員、ロバート・モギルニッキ氏はロイターに対し「エネルギー関連が今後も関係の中心に据えられるだろう。またハイテク技術面でも協力が進み、米国からはおなじみの懸念が示されることになるだろう」と述べた。
今回の合意には中国の通信機器大手、華為技術(ファーウェイ)との覚書 が含まれている。中国企業の技術使用に伴う安全保障上のリスクについて米国と湾岸諸国が懸念しているにもかかわらず、サウジは国内都市でのクラウドコンピューティングおよびハイテク複合施設の建設についてファーウェイと合意した。
サウジと湾岸諸国は、中国との石油取引を制限し、石油輸出国機構(OPEC)加盟国とロシアなどの非加盟国で構成する「OPECプラス」の一員であるロシアとも関係を断つよう、米国からの圧力を受けてきた。世界秩序が二極化する中、経済と安全保障上の両方を視野に入れたかじ取りを迫られている。
習氏は、中国は今後も湾岸諸国から大量の石油を輸入し続け、液化天然ガスの輸入を拡大する方針を表明。石油・ガスの上流開発でも一段の協力を進めるパートナーだと述べた。
2022年12月6日11:20 午前4日前更新
アングル:サウジ皇太子の中国活用術、米けん制し独自外交
ロイター編集
[リヤド 4日 ロイター] - サウジアラビアの実力者ムハンマド皇太子は今週予定する習近平・中国国家主席のサウジ訪問の機をとらえ、中東における指導者としての地位を固めるとともに、米国に距離を置く独自の外交路線を示そうとしている。
12月4日、 サウジアラビアの実力者ムハンマド皇太子(写真)は今週予定する習近平・中国国家主席のサウジ訪問の機をとらえ、中東における指導者としての地位を固めるとともに、米国に距離を置く独自の外交路線を示そうとしている。バンコクで11月代表撮影(2022年 ロイター)
折しも米国とサウジの関係は細心の注意が必要な状況にあり、こうしたタイミングでの習氏のサウジ訪問から、米国の西側同盟国の意向に流されず、二極化した世界秩序を乗り切るというサウジの決意が読み取れる。
ムハンマド氏は2018年のサウジアラビア人記者ジャマル・カショギ氏殺害への関与が疑われたが、その後国際舞台に復帰。米国からのエネルギー政策への怒り、ロシアの孤立化を助けよとの圧力に屈しない態度をとってきた。
ムハンマド氏はアラブ世界の意欲的なリーダーとしての力を見せつけるべく、習氏のサウジ訪問に合わせて中国・アラブ首脳会議も開催する。
調査会社ユーラシア・グループの中東・北アフリカ部門を統括するアイハイム・カメル氏は「サウジは、今や経済的に不可欠なパートナーである中国を受け入れざるを得ないという戦略的な計算に従って動いている」と話す。
アナリストによると、湾岸諸国は安全保障を米国に依存しており、米国は依然として最良のパートナーだ。しかしサウジの生命線である炭素の利用を縮小する動きが世界的に進む中、サウジは国家規模の経済改革に資する外交政策を模索しているという。
「中国との関係拡大が裏目に出て、米国とサウジの関係が(さらに)悪化するリスクは確かにあるが、ムハンマド氏が意地になってこうした政策を押し進めているわけではない」とカメル氏は指摘する。
ムハンマド氏は3月にアトランティック誌に対して、バイデン米大統領から誤解されているかどうかは気にしていないと述べ、バイデン氏は米国の利益に重点を置くべきだと強調、サウジの人権問題を巡る米国の批判に苛立ちを示した。
サウジの国営通信(SPA)も3月、ムハンマド氏が米国との関係強化を目指す考えを示す一方、サウジには対米投資を減らすという選択肢もあり得ると示唆したと報じた。
バイデン政権下の米国とサウジは、人権問題やイエメン内戦を巡って元々緊迫していたが、ウクライナ戦争や石油輸出国機構(OPEC)プラスの石油政策によって軋みが一段と大きくなっている。
一方、サウジは中国との経済的な結びつきを深めている。中国にとって、サウジは最大の石油サプライヤーだ。
<豪華な歓迎会>
中東の外交筋によると、サウジを訪問する習氏の歓迎会は2017年にトランプ米大統領がサウジを訪問した際に匹敵する豪華なものになり、サウジとの関係修復を目指した7月のバイデン氏の気まずいサウジ訪問とは対照的となる見通しだ。
トランプ氏はファンファーレが鳴り響く中、空港でサルマン国王の出迎えを受け、米国の軍事産業向けに1000億ドル以上の契約を取り付けた。一方、カショギ氏殺害事件を巡ってサウジを社会的な「のけ者」にすると発言したことがあるバイデン氏は、サウジ訪問時にムハンマド皇太子と握手をせず、拳を突き合わせてあいさつしただけだった。
外交筋によると、中国の代表団はサウジや他のアラブ諸国とエネルギー、安全保障、投資に関する数十件の協定に署名する予定。
サウジと中東湾岸の同盟国は、ロシアや中国との関係に対して米国が懸念を抱いても、経済や安全保障上の利益のためにパートナーシップの多様化を継続する方針を示している。
ムハンマド氏はサウジが多くの大国にとって重要だということを自国民に示したいのだろうと、アトランティック・カウンシルの非常勤シニアフェロー、ジョナサン・フルトンは見ている。「おそらく米国にもメッセージを送っているのだろうが、自国の国民がどう受け止めているのかをより気にしているのではないか」という。
<複雑な関係>
ホワイトハウスの米国家安全保障会議(NSC)のカービー戦略広報調整官は11月30日の記者会見で、サウジとの「戦略的」関係が「われわれの最善の利益に」かなっていることを確認したいと述べた。
米政府高官は、習氏のサウジ訪問を前にサウジと中国の2国間関係について質問を受けたが回答を避けた。
サウジと中国の関係は、対米国と比べて「はるかに急速に」拡大しているように見えるが、実際の関係は比較にならないと、ワシントンの戦略国際問題研究所で中東プログラムを担当するジョン・アルターマン氏は話す。「サウジの中国との関係は、複雑さと親密さの両面で、米国に比べて見劣りする」と語る。
(Aziz El Yaakoubi記者)
2022年8月28日7:44 午前3ヶ月前更新
アングル:サウジが砂漠に未来都市、データ収集で「監視」懸念、そこへ中国が・・・
ロイター編集
[23日 トムソン・ロイター財団] - サウジアラビア北西部の砂漠地帯で今、数千人の労働者が未来都市の建設に携わっている。都市中心部を貫くのは、「ザ・ライン」と呼ばれる直線形のスマートシティー。炭素を排出せず、タクシーは空を飛び、教師はホログラフィー、そしてなんと人工の月まで浮かべるという構想だ。
8月23日、サウジアラビア北西部の砂漠地帯で今、数千人の労働者が未来都市の建設に携わっている。都市中心部を貫くのは、「ザ・ライン」と呼ばれる直線形のスマートシティー。画像は「ザ・ライン」のイメージ図。(2022年 ロイター/NEOM Tech & Digital Holding Co/Thomson Reuters Foundation)
石油大国サウジの経済多角化を目指し、ムハンマド皇太子の肝入りで開発が進む産業都市「NEOM」 の中に、ザ・ライン は出現する。NEOMは総工費5000億ドルで、完工予定は2025年。
ザ・ライン は住居と事務所を垂直に積み重ねた特異な構造の都市になる。都市は住人900万人のデータを解析するが、データの使用方法についての住民の権利は強化され、世界初の試みとしてデータの対価も支払われるとプロジェクトの幹部は言う。
この「同意管理プラットフォーム」と呼ばれるシステムを管轄するNEOMテック&デジタルのジョゼフ・ブラッドリー最高経営責任者(CEO)は「信頼が無ければデータは得られない。データが無ければ価値は生まれない」と語った。
「この技術により、ユーザーは個人情報使用の意図を簡単に検証、理解することができる。データの利用を認めれば金銭的対価も支払われる」という。
ザ・ラインは人工知能(AI) が中心となって設計した都市で、多くのスマートシティーと同様、データは電力、水道、ゴミ、交通、医療、治安などの管理に利用される。
住民のスマートフォンや住居、顔認証カメラ、その他多くのセンサーを通じてデータは収集され、その情報は都市に送られてユーザーのニーズの予想に役立てられるとブラッドリー氏は説明する。
もっとも、これまで人権保護をおろそかにしてきたサウジだけに、責任を持ってデータを利用する、あるいは個人のプライバシーを守ることは望み薄だと専門家は言う。
テクノロジーによる社会への影響を研究するビンセント・モスコ氏は「監視について懸念が持たれるのも無理はない。これは事実上の監視都市だ」と指摘する。
ロイターはサウジ通信・情報技術省にコメントを求めたが、回答を得られていない。
<プライバシーの値段>
日常生活のすべての面でデジタル化が進む中、個人情報の所有権、使用法、価値について懸念が広がっている。
データの権利の専門家やエコノミスト、議員の一部は、データの対価を払うことを提案している。
だが対価を払う場合の金額を巡っては、専門家の意見は分かれている。また、データに値段を付けると、人によって個人情報の価値が異なって二層化し、「デジタルデバイド」によって生じた格差をさらに強固にしかねない、との声もある。
デジタル権利組織、アクセス・ナウのマルワ・ファタフタ氏は、情報利用への同意を得るプラットフォームは「個人情報を守るデータ保護規制の代わりにはならない」と批判。「プライバシーを巡る惨劇が待ち受けているようだ。金銭的なインセンティブを付けるなどもってのほかだ。人々が自由に同意する権利をゆがめ、営利目的で個人情報を売る慣行を常態化してしまう」と語る。
サウジの港町ジッダに住むエンジニアのファハド・モハメドさん(28)は、ザ・ラインに住むならデータ提供に同意すると言う。「私のデータは、既にソーシャルメディアのプラットフォームや配車アプリなどに利用されている。料金が支払われるのだから、(NEOMの)システムの方が良い」と語る。
<監視への懸念>
デジタル化の拡大に伴い、監視とプライバシーに関する懸念も強まっている。
NEOMの同意管理プラットフォームの利用者は、共有する個人データの種類やデータにアクセスできる主体を選び、データの使用方法を監視し、いつでもプラットフォームから抜けることができると、ブラッドリー氏は言う。
またデータが同意なしに使われたり、疑わしい活動があったりすると、システムがユーザーに警報を発するという。
しかしドバイに住むマーケティング専門家のファイサル・アルアリさん(33)は納得しない。「自分の望む範囲だけで、自分が選んだ第3者やサービスの間だけでデータが使われると、どうして信じられるだろう。他の理由で使われないという保証があるだろうか。100%信頼できるわけではない」と切り捨てた。
<人とのふれあい>
ザ・ラインを巡る懸念は、監視の問題だけではない。世界のスマートシティーの一部では、人とのふれあいを奪われて孤立を感じるという不満も出ている。
例えば韓国のスマートシティー、松島国際都市は、最先端の機能が整っているにもかかわらず人口が少ないままだ。スマホの操作で家の照明をコントロールできたり、捨てたゴミが管を通じて直ちに地下の仕分け設備に送られるといった便利さの代償として、人とのつながりがないからだとアインシャムス大学(カイロ)のサミア・ケドル社会学教授は説明する。
松島新都市(New Songdo City):韓国の計画都市
「人とのつながりは重要な社会インフラだ。複雑なデータインフラは通常、都市生活で何より重要な社会的、文化的ニーズに応えられない」とケドル氏は語った。
サウジにも、これに同意する人がいるようだ。ファハド・アルゴファイリさんはツイッターで「NEOMに費やしている数十億ドルを、国の他の地域に実在する都市の向上に使った方が良くないか?」と疑問を投げかけた。
(Menna A. Farouk記者)
周庭さんの現況にひと安心、強大な国家・中国が一人の若い女性を恐れている
2023年12月12日
共同通信のオンラインインタビューに応じた周庭さん(写真:共同通信社)
© JBpress 提供
(勢古 浩爾:評論家、エッセイスト)
12月4日、いいニュースが飛び込んできた。香港の民主活動家だった周庭さん(27)の現況がわかったのだ。
現在、カナダ・トロントの大学院に留学中で、「(香港に)おそらく一生戻らないことを決意しました」「私はただ自由に生きたいと思っています」とSNSで述べたのである。
周庭さんは、2014年の香港民主化運動「雨傘運動」などにリーダーの一人として参加して一躍注目され、香港の「民主(学民)の女神」と呼ばれた。2020年にはBBCが選ぶ「今年の女性100人」の内の一人に選ばれた。
しかし民主化の盛り上がりに危機感を抱いた中国が、それまで一国二制度下で民主制が保証されていた香港を、急に締め上げにかかったのである。議会から民主派を一掃し、傀儡政府を作った。
2020年に逮捕され…
周庭さんは、2020年8月に、香港国家安全維持法(国安法)違反の容疑で逮捕された。そのときに感じた恐怖は「とんでもなかった」という。
その後、いったん釈放されたが、11月、禁錮10か月の判決を受け、収監されたのである。21年6月に満期より2か月早く出所したが、出所直後の周庭さんは、心を潰され、憔悴しきっているように見えた。このまま無名の人になってもいいが、立ち直れるかどうかが心配だった。
収監された周庭氏、黄之鋒氏(2020年11月23日、写真:ロイター=共同) 彼女は、出所後も再び警察に逮捕されるのではないかとおびえる日々がつづき、パニック障害やPTSDに悩まされたという。「彼女は収監中も出所後も、刑務官から受けた屈辱的な身体検査や逮捕される瞬間の恐怖の記憶のフラッシュバックに悩まされ、突然の震えや叫びだしたくなるような症状に苦しんでいた、という」(「民主の女神」周庭氏が語る亡命の真意「香港は大好きだけど恐怖でいっぱい」、JBpress、2023.12.9)。
現在、世界にはシリアやアフガニスタン、南スーダンなどを主として、難民が1億人以上いると推定されている。その他、なんの罪もないのに収監されている人も無数にいる。しかしかれら全員を心配することはできない。
わたしには気になる特定の人物がいるだけである。たとえばロシア人の民主活動家ナワリヌイ(「プーチンが最も恐れた男」ナワリヌイが身をもって示したロシアの良心、JBpress、2023.4.5)。周庭さんはそういう人たちの一人だった。
「自由も日常生活も基本的人権もすべて奪われていた」
周庭さんは出所後、一切の情報がなかった。家族とともに、静かで穏やかな日々を過ごしていればいいのだが、と思っていた。
しかし彼女は、「過去3年間、寛大な対応など一切なかった。自由も日常生活も基本的人権も、この3年間、すべて奪われていた」といっている。
香港では、逮捕された人権派弁護士の留守家族の家に、常時国家安全当局の人間が5、6人張り付いているのを、番組で見る。周庭さんの家もまたつねに監視され、彼女の行動も逐一見張られていたと想像される。穏やかな日々どころではなく、気の休まるときは一瞬たりともなかったのではないか。
周庭さんは今年に入り、このままじっとしているより外国に留学したいと考え、カナダの大学院への進学を決めた。しかしパスポートは当局に没収されたままだった。
香港警察の国家安全当局 に留学の申請をすると、パスポートを返却する条件として、今後政治活動に二度とかかわらないことを約束する懺悔状を書かされた。
さらに5人の国安担当者とともに中国本土の深圳に行くことを要求された。彼女は深圳行きを決断したが、「とても、とても怖かった」といっている。それはそうだろう。中国はなにをするかわからない。そのまま中国本土に拉致されない保証はないからである。
深圳では、「改革開放展覧会」に連れていかれ、中国共産党や歴代指導者の業績を見学する「愛国教育」を受けた。また中国のIT大手のテンセント本社を見学させられた。その後、「祖国の偉大な発展を理解させてくれた警察に感謝します」との文書を書かされ、やっとカナダ留学が認められたという。
これらの一切を「弁護士にも家族にも友人にも、誰にも言わないようにと警察から言われた」というが、中国のやり方がいかにも幼稚である。やたら写真を撮りまくり、文書を書かせたがる。それが公正に通用しようとしまいと関係ない。とにかく証拠をとりたがるのである。
こうして、周庭さんはやっと今年の9月にカナダに留学できた。しかし彼女は12月末に、いったん香港に戻るつもりでいたのである。学期の変わり目ごと(あるいは3か月ごと)に警察への出頭義務があったからである。
しかし彼女は香港に戻らないことを決めた。「香港の状況、自身の安全、心身の健康などを慎重に考慮した結果、おそらく一生戻らないことを決意しました」。難しい決断だったが、いったん帰ってしまえば、周庭さんの処遇に関する裁量権は完全に中国側にあるからである。なにが起きても、そうなってしまえばどうにもならない。
「自分のやったことを後悔させてやる」
これに対して、メンツをつぶされた香港警察当局 は「法に公然と反する無責任な行為を、厳しく非難する」との文書を出し、今月末までに香港に戻って出頭するよう呼びかけた。保安局長の鄧炳強という男はなにを考えてるのか、「絶対に自分のやったことを後悔させてやる」と発言したという。バカじゃないのか。
香港特区政府保安局の鄧炳強局長(右端) (2021年6月26日、写真:新華社/共同通信イメージズ)
© JBpress 提供
香港政府トップの李家超行政長官は、「香港政府は全力を挙げて、国家の安全に危害を及ぼすいかなる逃亡犯をもひっ捕らえる」と激怒した(「民主活動家・周庭氏亡命に香港行政トップが怒りを爆発させた3つの理由」、JBpress、2023.12.7)
「いかなる逃亡犯も、いますぐ自首することだ。そうでなければ終身、逃亡犯であり続け、終身追われる身となるだろう。香港警察は、本件で寛大な処置を試した。だが恩を仇で返されたのだ」
それでも飽き足らず、こう付け加えた。「『逃亡犯』は、誠の心を売り払い、同情を得るための言い訳をでっちあげ、自分を正義にみせようとして、恥ずべき行為をした。特区政府は全力でいかなる国家安全に危害を加える逃亡犯を追跡逮捕する」
この発言を受けて、中国外務省報道局長の汪文斌(おう・ぶんひん。あの白髪の痩せたじいさん)は記者会見で、「香港警察は法の支配に挑戦する無責任な行動を強く非難した。中国、香港は法治社会だ。いかなる人にも法外特権はなく、違法行為は法で罰せられる」と非難した。
日本の水産物輸入を全面停止することで記者会見する中国外務省の汪文斌副報道局長(2023年8月24日、写真:共同通信社)
いつものことで驚きもしないが、恥知らずなモノいいである。法に公然と反する無責任な行為」だの「法治社会」が、聞いてあきれる。
ソクラテスは「悪法もまた法なり」といって、死罪を受け入れたが、そんなバカなことはない。悪法は悪法である。廃棄されなければならない。
「香港のことは心から愛しているが…」
周庭さんは「カナダに中国の秘密警察が置かれていると報じられている。外国にいても身の安全がとても心配だ」などと不安を言葉にしている。
周庭さんと交流のあった立命館大政策科学部の上久保誠人教授は、その点についてこのように推測している。
彼女の宣言は、「一定の安全の確保が保障され」「カナダ、もしくは英米の支援に何らかの確証を得たのだと思う」と推測している。さらに「カナダは身柄の引き渡しなどは当然しない。カナダ政府は国家の威信をかけて査証(ビザ)を得ている周氏を守ることに自然となる」(「カナダは国の威信かけ周庭氏守る 上久保誠人・立命館大教授」、産経ニュース、2023/12/6)。
裏金キックバック「森会長のときに始まったのは間違いない」元安倍派・山本一太群馬県知事が語った真相
青山 和弘 によるストーリー
2024年4月23日
「それ(裏金のキックバック)が森(喜朗)会長のときに始まったことは、もう間違いないんです」
裏金問題の真相をこう語るのは、かつて自民党安倍派(清和会)に所属し、参議院議員を4期24年務めた山本一太群馬県知事だ。現在は永田町の外にいるものの、自民党、そして安倍派の裏も表も知る山本知事が、文藝春秋ウェビナーの「青山和弘の永田町未来café」に登場し、裏金作りのスキームの実態や意中のポスト岸田候補、また国政復帰の可能性について赤裸々に語った。
裏金問題の真相をこう語るのは、かつて自民党安倍派(清和会)に所属し、参議院議員を4期24年務めた山本一太群馬県知事
真相を語らない安倍派幹部に疑問も
自らは裏金のキックバックを受けたことはないという山本知事。かつて安倍派に所属し「自分も責任を感じる」と前置きした上で、“裏金作りのスキームが始まった時期”について、次のように説明した。
「明確なところは一つあると思うんです。私が1995年に初当選したときは(清和会は)三塚派だったんですよ。三塚(博)さんの時にキックバックは全く記憶がないんで、始まったのは間違いなく森派が始まってからだと思うんです。会長の了解がなくて(キックバック)できるはずがないんで、森さんが知らないはずがないというのが私の感覚です」
その上で真相を語らない安倍派幹部らの姿勢に疑問を呈した。
「何でこんなにみんなが分かっていることを言わないのか。当然森会長の時にやったのに、みんな口をつぐんでいるのはとても不思議です。本当に自民党のことを思うのなら、やはりそこはお話しになるべきだと思う」
そして山本知事は安倍派幹部の身の処し方を「頓珍漢だ」と批判した。
「離れて見ると、この頓珍漢さは結構深刻で、塩谷(立・清和会元座長)さんが自民党の処分に異議申し立てをしたのは、大体ギア3段ぐらいずれてますよ。座長だったけど知らなかった、自分は気の毒なんだみたいな形で党を責めることは、一般の人たちから見たら全くピント外れなわけです。一刻も早く潔く(議員を)辞めて、次の選挙に備えるのが普通だと思うんです。そしてこれはお叱りを受けるかもしれませんが、西村(康稔前経産相)さんと世耕(弘成前参院幹事長)さんには、是非今回の事を反省して、困難を乗り越えて帰ってきてもらいたいと思います」
これに対して筆者は、西村氏ら安倍派幹部は党の処分を待たずに、もっと早く覚悟を決めて離党なり議員辞職していれば、逆に将来に繋がったのではないかと指摘した。これについて山本氏は「五人衆の中で牽制し合ったんではないか」と理解を示しつつ、こう語った。
「もうちょっと率先して責任を取っていればここまで騒ぎになってないと思います。群馬県みたいな保守王国でも若手県議がこの間、『裏金問題に関わった人は一回議員辞職するべきじゃないか』って言ってました。こうした地方議員たちの思いも受け止めないと、次の衆議院選挙で自民党は結構痛い目を見ると思います」
河野太郎は「ポスト岸田」にふさわしいのか
こうした中、岸田内閣の支持率は低迷し、9月の自民党総裁選での岸田総理の再選は難しいとの見方が強まりつつある。山本知事は岸田総理の後継には、誰がふさわしいと考えているのか。
「私は以前から河野太郎(デジタル相)に頑張ってもらいたいと。河野太郎にいわゆる永田町的バランス感覚はないんですよ。例えば自民党改革をやると彼が言ったら本当にやる。今の日本を変えられるのは、自民党を変えるのは、河野太郎しかいないと思ってます」
一方、番組に出演した朝日新聞の曽我豪編集委員はこれに異論を唱えた。
「もし河野さんが(ポスト岸田の)可能性があるとしたら、既にこの時点で(裏金問題に対して)何か発言していないと駄目なんじゃないか。先ほど山本さんがおっしゃった『森元総理の関わりをきちんと喋るべきだ』と言っていない人たちが、総裁選になって急に『岸田さんの対応が悪かった、裏金問題はこうだった』って言っても、世の中には響かない。自民党は、今回それで(総理の顔を代えれば)済むかってことをきちんと考えて欲しいと思います」
これに対して山本知事は、「自民党最大の危機は、危ない危ないとか言いながら本当の危機感がないこと。それから若手があまりにも元気がなくておとなしい。こういうときに政治生命をかけて党のために何か行動するとか、叫ぶ人たちが圧倒的に少ないのが残念」と述懐した。
山本知事が国政に復帰する条件とは?
昨年、群馬県知事に再選を果たした山本氏。県知事については「これ以上やりがいのある仕事はない」と話すが、その一方で国政復帰について一つの可能性に言及した。
「群馬県のためにしっかりと最後までやりたいと言っているんですけど、唯一例外があるとすると、河野太郎が総理大臣になって『一太さん、助けてくださいよ』って言ったときだけは断れないかなと。河野太郎が総理になるのはかなり難しいって分かっているんですけど、本当に総理になって命を賭けてやるって時に『知事を辞めてくれ』って言われたら、その時だけは国政に復帰しようと思うかもしれません」
参議院議員当時は、ベテラン議員から「跳ね返り者」などと揶揄され「異端児的」な存在だった山本氏。その歯に衣着せぬ物言いは健在だ。従来型の政治からの脱却が求められ、永田町の人材不足が深刻な今、山本氏が国政に復帰する機会は訪れないだろうか。政局が激動する中、今後も山本知事の動向を注視する必要があるだろう。
◇
山本氏が出演した、文藝春秋ウェビナー「青山和弘の永田町未来café」は、「 文藝春秋 電子版 」で見ることができる。
(青山 和弘/文藝春秋 電子版オリジナル)
自民・宮沢博行衆院議員が辞職願 裏金で「派閥からしゃべるな」発言
2024年4月
朝日新聞社 によるストーリー
自民党の宮沢博行・前防衛副大臣=衆院比例東海、当選4回=が2024年4月23日、額賀福志郎・衆院議長あてに議員辞職願
宮沢氏は、自民党最大派閥の安倍派所属。派閥ぐるみの組織的な裏金事件では、党の調査で132万円の政治資金収支報告書への不記載が発覚。取材では、裏金事件について「派閥の方から『しゃべるな』と(言われた)」などと語っていた。