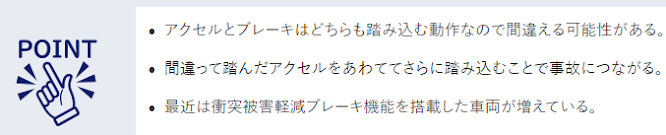高齢者がプリウスで事故を起こしてしまう原因とは
動画の中で、5つの理由を述べていますが、個人の考えであり、具体的なデータなどがある訳ではありません。
また疲労が溜まりやすく、事故を誘発する恐れがあると述べていますが、事故を起こした加害者を擁護している訳でもありません。
あくまでも、事故を少しでも減らす努力をメーカー側にも訴えていきたいと考え、動画を投稿しております。
非常に勇気のある素晴らしいレビューですね。
以前からプリウスの走りはふらついていたり、強引な運転をする車が多く気になっていました。
こうゆうことだったのかと納得しました。
アンデルさんのレビューが正常で、ほかの自動車ジャーナリストはなぜこのような車を絶賛しているのか
不思議です。忖度ではすまないことですよね。
アクセル踏み間違いで多発する「プリウスミサイル」…悪いのはトヨタか、高齢ドライバーか?
2025年4月2日
近年、社会問題化しているペダルの踏み間違い事故。ブレーキを踏んだつもりでアクセルを踏んでしまうことによって起こります。踏み間違い事故は高齢ドライバーがトヨタの「プリウス」を運転しているケースが多いという声もあり、SNSでは「プリウスミサイル」などと揶揄されることさえあります。なぜペダル踏み間違い事故はプリウスが多いのか、何かプリウスに原因があるのでしょうか?(自動車ジャーナリスト 吉川賢一)
プリウス式シフトレバーの特徴
前方の危険を検出し、ドライバーへ警告をするほか、自動でブレーキを作動させることで、衝突を回避もしくは被害を軽減してくれる衝突被害軽減ブレーキ(自動ブレーキ)。我が国では、国産の新型車については2021年11月から搭載が義務化されており、国産車は継続生産車に関しても、今年2025年の12月から義務化となります。主に、高齢運転者等による交通事故の削減を目的に義務化されたもので、なかでもアクセルペダルとブレーキペダルの踏み間違いによる事故を防ぐための対策だと思われます。
「高齢運転者のペダル踏み間違い事故は、トヨタのプリウスが多い」という意見をよく見かけます。なぜプリウスが多いのか。その理由として、プリウスが2代目モデルから採用している電制シフトレバー(通称:プリウス式シフト)に問題があるのでは?という指摘があります。
シフトレバーは、一般的なAT車の場合、R(リバース)-P(パーキング)-N(ニュートラル)-D(ドライブ)が縦に並んだストレートゲートの中で、レバーを上下に移動させることでシフトチェンジをするという仕組みです(参考記事)。
しかしプリウスの電制シフトレバーは、「・」マークの付いたセンターポジションから、シフトレバーを右に倒して上下に操作することで、D(ドライブ)もしくはR(リバース)へシフトチェンジします。B(ブレーキ)はシフトノブを「・」の位置から下に倒す操作で入り、P(パーキング)はシフトレバーとは別に右側にあるプッシュスイッチとなっています。
スイッチのように電気的にシフトチェンジを行っているため、どこにでもレイアウトができ(インパネでもセンターコンソールでも可)、エンジンオフ時にシフトが自動でリセットされる(戻し忘れがなくなる)、見た目がすっきりする、軽い力で操作できる、運転支援や自動運転と相性がいい(車外からリモート運転する際にシフトチェンジ操作が不要)などがメリットです。
ただ、一般的なAT車のシフトレバーとは違い、操作した後に手を離すと、センターに戻るリターン式となっているため、何レンジに入っているのが目視で確認できないという特徴があり、これが運転者の混乱を誘発し、プリウスで事故が多い原因となっているのではないか?と指摘されています。
具体的な例をいえば、後退させるためにRレンジに入れたつもりがNレンジになっており、アクセルを踏んでもクルマが動かないため、誤ってDやBに入れてしまうことで急発進をする、というものです。
電制シフトレバーは、現代車の多くに採用されている
しかし、メーターパネルの中にはシフトレンジの記号が表示されており、今どこにシフトが入っているか目視で確認は可能です。さらに、確かにプリウスはいち早く、2003年からこの電制シフトレバーを取り入れていたとはいえ、現在のクルマの多くが(プリウスのレイアウトとは異なるものの)この電制シフトレバーを採用しており、現在ではプリウスだけの特徴とはいえません。
 |
| 4代目プリウスのセンターメーター。3代目と同じくセンターメーター内にシフトポジションが表示されているが、配置はやや左側となった(広報写真) |
 |
| 国内市場で抜群の人気を誇ったプリウス。なかでも3代目と4代目は、幾度も国内販売1位となった(筆者作成) |
また筆者は、3代目プリウスを使った急発進の実験(シフトがNの状態でアクセルを踏み、シフトをDに入れると急発進する)を、試乗会で体験させていただいたこともありますが、Nレンジの状態でアクセルペダルを踏むと、ピーという警告音とインパネに「Nレンジです」という画面表示が出ますし、そのまま(アクセルペダルを踏み込んだ状態で)、Dレンジに入れなおすと、確かに急発進することになりますが、この動作はプリウスに限ったことではなく、他のクルマでも同様の操作をすれば現象を再現できなくはありません。
アクアミサイルとは?プリウス並に事故が多発している?!
2021/06/14
トヨタ アクアはトヨタのコンパクトハイブリッドカーですが、ハイブリッドカーとしての高い性能と扱いやすいサイズ感を持っていて大人気の車種となっています。
今回はそんなアクアについて”アクアミサイル”という言葉についてご説明していきます。
トヨタ アクアはトヨタのハイブリッドカーの中では最もコンパクトな車ですが、そんなアクアでミサイルという言葉はちょっと合わないものです。
トヨタ アクアはトヨタが2011年に発売したハイブリッドコンパクトカーで、トヨタの元祖ハイブリッドカーであるプリウス以来の大ヒットモデルとなりました。
アクアはコンパクトカーの中でも小型のボディを持っていてスタイリッシュな車ですが、ハイブリッドシステムは本格的なシステムが搭載されていて非常に高い低燃費性能を持っています。
それでいてコンパクトカーということでコストパフォーマンスに優れるハイブリッドカーに仕上がっており、そのバランスの良さからトヨタ車の中でトップクラスの販売台数を持っています。
トヨタ車では長年プリウスが国内販売台数でトップを獲得していたのですが、アクアの登場以降はその座をプリウスと争うような大人気車になりました。
そんなアクアですが、当然ながら「ミサイル」などという物騒な単語とは縁の無い車ではあるのですが、あるインターネット上のミーム(小ネタ)の1つとして”アクアミサイル”という言葉が生まれました。
アクアミサイルはアクアを運転している時に車が他の車に突っ込んだり、道路の脇の店舗や家の塀などに突っ込んだりした姿を揶揄した言葉で、まるでアクアがミサイルのように突っ込んでいることからこう言われています。
MEMO
アクアミサイルはこういった事故の正式な名称ではないのですが、インターネットの一部の界隈ではアクアが事故を起こした映像や動画があるとアクアミサイルと呼ばれることがあります。
また同じトヨタのハイブリッドカーであるプリウスでの同様の事故がプリウスミサイルと揶揄されていることからも、アクアの事故がアクアミサイルなどと呼ばれます。
アクアミサイルはもちろん不名誉な現象を指す言葉になっていますが、すべての車でそれぞれの車名でミサイルという言葉が使われているわけではなく、アクアやほかのいくつかの車種でしか見られないものです。
その理由は後ほどご説明しますが、まずはどんな状況がアクアミサイルと呼ばれるかをご紹介しましょう。こちらの画像ではアクアが道端の店舗に突っ込みそうな状態となっていますが、横断歩道の上に乗っかっているのを見ると運転操作を間違えて歩道に乗り上げたような感じですね。
この状態では一応まだギリギリ事故にはなっていないようですが、プリウスミサイルという現象はこういった感じのものを指します。こちらでは道路を走行中の車からの動画が投稿されていますが、なんとその車の左側でアクアが道路の中央にあるポールに突っ込んでひどい状態になっていますね。
こういった状態がまさにアクアミサイルであり、結構スピードが出ている状態で突っ込んでしまったということなのでしょう。この写真の車はアクアではないのですが、どうやら車の左側面にアクアが突っ込んできたあとのようで、大きく凹んでいますね。
アクアミサイルは道端に突っ込むだけではなく、こういったほかの車に突っ込んできたようなときにも当てはまる言葉です。この画像ではアクアがコンビニの駐車場から店舗の方に突っ込んでいったような形になっていて、まさにミサイルのように突っ込んだような形になっています。こちらの画像もほぼ同様のシーンでこちらは交差点から店舗に突っ込んだような形になっていますが、ニュースになるほど注目されています。
テレビを見ていてもこういった映像が流れればアクアミサイルと思う人は結構いるようですね。この動画はなかなか衝撃的なものなのですが、アクアがフロント部分を大破させた状態で走行しています。
どうやら他の車にアクアミサイルで突っ込んだあとに当て逃げしている間のようで、こういった車を見るとまさにアクアミサイルという言葉がピッタリです。
こちらの動画ではある方の車のドライブレコーダーの映像が移されていますが、道路脇で事故が起こっており路線バスにアクアが右斜め後ろから突っ込んでいる形になっています。
事故が起こった状況はよくわかりませんが、バスはどうやらバス停に停車しているようなので、乗降中で停車しているバスにアクアが突っ込んだような形の事故でしょうね。
この状況ではアクアのドライバーが運転操作をミスって突っ込んだ可能性が非常に高く、まさにアクアミサイルと読んでも良い事故でしょう。
アクアミサイルの原因
アクアミサイルが起こる原因はいくつかあるのですが、大まかに分けてドライバーの運転ミスと車の構造的なものとによるものがあります。
アクセルの踏み間違いによるアクアミサイル
まずアクアミサイルが起こる原因はアクアを運転しているドライバーの運転ミスがあり、アクアミサイルはほぼこの原因があるでしょう。
アクアミサイルはドライバーが意図しないようなときに車が前進もしくは後退したりして起こるのですが、そういった運転ミスはさまざまな点で起こってしまうものです。
ポイント
アクアミサイルでは駐車場に車を停めるときや発進時に起こることが多いのですが、この際に車のアクセルとブレーキを踏み間違いをして、停車しようとしたときに逆に発進してしまうことがあります。
車のアクセルペダルとブレーキペダルは横並びで配置されていて、アクアの場合にはどちらも右足で踏み変えるような形で操作します。
車の運転に慣れればアクセルとブレーキペダルの踏み変えは間違えずにスムーズに出来るのですが、ボーッとしているときや急に人や車が飛び出したりすると焦って踏み間違ってしまいます。
また交差点や信号での停車の時にも踏み間違いは発生し、ブレーキを踏む勢いでアクセルを踏んでしまうと一気に加速してしまってアクアミサイルが起こってしまいます。
ドライバーとしては踏み間違いをしたときにはほとんど操作を直す時間がないので、注意しておかなければアクアミサイルが起こる可能性は常にあります。
シフトレバー操作ミスによるアクアミサイル
もう1つアクアミサイルの起こる原因としては車のシフトレバー操作ミスによるものがあります。
アクアは車の構造としてはオートマチック車となっており、構造的には電動モーターと遊星ギアを使ったトヨタのハイブリッド車特有の構造をしています。
しかしアクアでは車の操作系自体は普通のコンパクトカーと変わらず、シフトレバーにはゲート式というレールを動かして確実な操作が出来る構造となっています。
このシフトレバーをドライブに入れたりリバースに入れたりして前進、後退を調整するのですが、このシフトレバー操作を間違っていると前進と後退が逆になることがあります。
もし駐車場に駐車している時にバックしようとしてリバースにシフトレバーを入れるのですが、このときに間違ってドライブに入れてしまっているとドライバーが意図しない形で車が前進して店舗などに突っ込んでしまうアクアミサイルとなってしまいます。
また逆のパターンもあり前進の代わりに交代してしまうこともあるのですが、こちらは前進よりはスピードが出にくいので危険性は多少下がります。
シフトレバーの操作も車の操作に慣れていればそんなに間違えることはないのですが、やはり慌てている時や眠気がある時などに操作してしまうと間違えてしまうことはあるでしょう。
ドライバーの年齢による注意力の低下
アクアミサイルの起こる原因としては車の操作ミスがほとんどなので上記の2種類の運転ミスが考えられますが、そういった操作ミスはドライバーの注意力が低下していることも原因です。
ポイント
車の運転というのは若い方から高齢の方まで様々な年齢層の方が運転されていますが、運転時の注意力はどうしても高齢になってくると低下してくる傾向にあります。
その原因は体力の低下や視力の低下などさまざまなものがあるのですが、以前は出来ていたことでも年齢と共にどうしても運転時の操作ミスは出てきてしまいます。
ちょっとした操作ミスぐらいならリカバリーすることも出来るのですが、アクアミサイルが起こるような急な状況ではなかなか対応が難しいです。
実際アクアミサイルが起こっているような事故では高齢の方の運転が報道されている傾向にあり、イメージ的にもアクアミサイルにそういった操作ミスのイメージがついています。
実際にはさまざまな状況の事故があるので詳細はわかりませんが、ドライバーの操作ミスが注意力低下にあることも真実です。
アクアミサイルを防ぐためには何より落ち着いた運転操作が必要であり、シフトレバーを確実に操作してアクセルとブレーキの踏み間違いをしないようにすることが事故を防ぐことになります。
アクアは事故が起こりやすい車なのか
アクアミサイルの原因はドライバーの運転ミスによるものがほとんどなのですが、車自体には欠陥がないのかどうかはいつも議論される点です。
現在の車はアクアを含めてほとんどの車がコンピューター制御によるものとなっており、アクセル操作やシフト操作もドライバーの操作が直接エンジンに伝わるわけではありません。
ドライバーの操作は一度車のコンピューターに伝わってその後にエンジンを操作するので、構造的に制御系に問題があるとシフト操作やアクセル操作が誤動作する可能性は0ではないでしょう。
アクアでもこういった点で誤動作があればアクアミサイルが起こる可能性はあり、どんなに信頼性のある車でも可能性はなくせません。
ただ車の事故が起こりやすいかどうかは1つの指標として保険料率というものがあり、これは保険会社が車ごとに設定した事故率の高さのようなものです。
保険料率はある程度の範囲の数字で決められていて中央より大小によって事故が多いか少ないかということを決められていて、保険料率が小さいほど過去にその車では事故が少ないということで保険料が安く設定されています。
逆に保険料率が大きな車種は事故が多いと想定される車種となっていて、スポーツカーなどではその性格から保険料率は高めに設定されています。
これに対してアクアの保険料率は概ね真ん中から多少小さめのところに設定されており、全体的には事故が多いとは言えないでしょう。
保険料率だけでは一概にアクアミサイル全ては説明できませんが、少なくとも車自体の信頼性は十分確保されていて車自体の問題による事故というのは少ないといっても良いでしょう。
また同じような事例の事故としてプリウスミサイルというものもありますが、こちらもプリウスの保険料率はアクアとほぼ同等のレベルなので、アクアとプリウスを比較しても特別事故が多いということはないでしょう。
アクアミサイルの対策
アクアミサイルは車が急に発進したりすることで起こる事故なので相手側から防ぐことは完全にはできません。
しかし歩行者の立場からアクアミサイルの事故に巻き込まれないように注意することはできるでしょう。
アクアミサイルが起こるのは車が不意に前進したり後退したりすることで起こるのですが、その車が店舗に突っ込んだり他の車に突っ込んでいくこと自体は他の人からは防ぎようがありません。
しかし事故に巻き込まれないようにするにはなにより車の前や後ろに入らないようにするのが1番で、車は横方向には絶対に動きませんのでこの方法が1番の防ぎ方です。
つまり車にドライバーが乗っている状態や発進、駐車、後退などの動作をしようとしている時に注意するとよく、車の進行方向に入るだけでなくその逆方向も入らないほうが安全です。
駐車場などでも車が前進で発進しようとしていると後ろには下がってこないと思いがちですが、アクアミサイルが起こるような際にはドライバーも全く注意できない操作ミスなどで起こるので、完全に巻き込まれないようにするには車の動く方向に入らないことです。
車が発進しようとしている時などにドライバーが譲ってくれることなどもありますが、そういうときにも注意だけはしておいたほうが良いでしょう。
車の事故にはアクアミサイルだけを注意するわけにはいかないのですが、とくに駐車場から動き出そうとしている時にはドライバーも不注意が増える状況なので気にしておいたほうが良いです。
アクアには欠陥があるのか?
トヨタ アクアでのアクアミサイルには車自体の欠陥が無いのかどうかはよく議論の的になりますが、アクア自体は信頼性の高さが保険料率などの面でもある程度は証明されていて車としては事故が多いということはないでしょう。
しかしそれでもアクアでアクアミサイルが注目されている背景にはその販売台数の多さは1つ理由であり、道路に走っているアクアの台数が多いことでその分事故が起こる可能性は当然増えてきます。
トヨタは国内の車のシェアで半数以上を獲得しているメーカーであり、そのトヨタの中でもアクアはプリウスと並んで国内販売台数で1、2を争う大人気車種となります。
そういった背景があるのでアクアでの事故件数自体は多くなってしまい、アクアミサイルなども目立つようになります。
ポイント
ですがトヨタはアクアミサイルが起こるような誤発進の対策の1つとして「誤発進抑制機能」をアクアを始めた主要車種に組み込んでおり、停車からの急なアクセル操作に対してコンピューターが介入するシステムがあります。
誤発進抑制機能があると例えば駐車時にブレーキと間違えてアクセルを踏んでしまった際に、コンピューターがその操作を検知して加速を緩やかにし、ドライバーが操作間違えに気づいてブレーキを踏む時間の余裕を増やしてくれます。
それでもアクセルを踏み続ければ車は加速して事故が起こってはしまうのですが、ドライバーの操作時間を確保することで全体的な誤発進を減らすことはできるでしょう。
こういった対策は新車で発売されているアクアだけでなく後付も可能なシステムとなっているため、アクアという車自体は事故や操作ミスを減らしてくれる信頼性の高い車種になっているのは間違いないでしょう。
名古屋 歩道に車 7人けが “アクセルいつも以上に踏み加速”
2025年4月1日
1日午後、名古屋市の中心部、栄で、車が歩道に乗り上げて歩行者をはね、子どもを含む7人がけがをしました。車の74歳のドライバーは、調べに対し「アクセルをいつも以上に踏んで加速してしまった」などと説明しているということで、警察は当時の状況を詳しく調べています。
現場近くの防犯カメラに事故当時の状況が
現場近くの店舗に設置された防犯カメラにうつっていた事故当時の状況の映像です。
駐車場から出てきた白い車が、片側1車線の道路を横切って反対側の歩道に乗り上げたあと、建物を避けるように左に曲がって、歩道上を走っていきました。
その際、車は店舗の壁に車体をこすっていました。
映像には、近くにいた歩行者が驚く様子もうつっています。
防犯カメラを設置していた宝飾品店の副店長は「ドーンと音がして、外を見ると、人が血を流して倒れていて、びっくりしました。運転手は外から声をかけるまで、車から出てこず放心状態で、何が起こったか理解できていないようでした」と話していました。
ドライバー「アクセルをいつも以上に踏んで加速」
1日午後1時ごろ、名古屋市の中心部、栄で「車が暴走し、複数の人が倒れている」などと消防に通報がありました。
警察と消防によりますと、車が歩行者を巻き込んで、乳児を含む、男性2人、女性5人の、あわせて7人がけがをしました。
このうち60代くらいの女性1人が骨盤を折るなどの大けがをしたとみられるということです。
警察は岐阜県可児市の74歳のドライバーを過失運転傷害の疑いでその場で逮捕しましたが1日夜、釈放しました。今後、任意で捜査を続けることにしています。
現場は名古屋市中心部、栄のデパートなどが建ち並ぶ人通りの多い場所です。
これまでの調べで、車は商業施設の駐車場から地上に出たあと道路を横切り、反対側の歩道に乗り上げました。
さらに交差点まで走って歩行者を巻き込んだとみられるということです。
調べに対し「駐車場のスロープが上り坂で、アクセルをいつも以上に踏んで加速してしまった」などと説明しているということで、警察は当時の状況を詳しく調べています。
歩道では乗用車が歩道と車道を隔てるために設けられた車止めに乗り上げた状態で止まっていました。乗用車は前のバンパーが外れて大きく壊れていました。
通りかかった人が見守る中、消防や救急の車両が集まって隊員が活動していて、現場の周辺は騒然としていました。
現場近くにいた男性「車が交差点に突っ込んだ」
事故現場の近くにいた30代の男性は「地下の駐車場から車が出てきて、交差点に突っ込んだ。4、5人が倒れていた。運転手が車から降りてきて、動揺した様子だった」と話していました。
現場目撃したという男性「緊迫した様子だった」
事故の直後に現場を目撃したという30代の男性は「けが人が3、4人いて、手当てを受けて救急車に乗るところを見ました。なかには小学生ぐらいの女の子もいました。規制線が張られた直後で歩道の人が集まっていて、緊迫した様子でした。自分も車を運転するので、気をつけなければいけないと思いました」と話していました。名古屋で車暴走、乳児ら7人けが 運転の女性、操作誤ったか
4/1(火) 13:42
1日午後1時ごろ、名古屋市中区栄3丁目の路上で通行人から「車が暴走し人が多数倒れている」と119番があった。中署や同市消防局によると、乗用車が歩行者をはね、60代ぐらいの女性が骨盤を折るなど男女7人がけがをした。うち1人は乳児とみられる。全員意識がある状態で病院に搬送された。消防によりますと、けがをした7人のうち、男性は2人(20代1人、乳児1人)、女性は5人(60代1人、40代1人、20代2人、10歳くらい1人)だということです。
現場は地下鉄名城線栄駅と矢場町駅の間の交差点で、周辺にはデパートや商業施設も並ぶエリアです。
署は自動車運転処罰法違反(過失傷害)の疑いで、乗用車を運転していた岐阜県可児市の無職女性(74)を現行犯逮捕し、その後釈放した。今後、任意で調べる。捜査関係者によると「アクセルをいつも以上に強く踏んでしまった」との趣旨の供述をしている。署は詳しい事故の経緯を調べている。
特殊なシフトレバーが原因? なぜ加害車両は「プリウス」が多いのか いま見直されるMT車も防止策に
2019.06.12 渡辺陽一郎
昨今は、高齢ドライバーがアクセルとブレーキを踏み間違えることによる暴走事故が問題となっています。なかでもトヨタ「プリウス」が関係する事故が目立ちますが、プリウスは危険なクルマなのでしょうか。
トヨタ「プリウス」は危険なクルマなのか?
最近は、トヨタ「プリウス」が関係した交通事故が多いです。痛ましい交通事故の加害車両を見ると、確かにプリウスになっていることがあり、そのためにプリウスの安全性が疑われるのでしょう。
SNS上でもプリウスの事故原因を追及するような投稿が見受けられますが、なぜプリウスは危険といわれるのでしょうか。
プリウスを疑いの視線で見ると、ほかの車種とは違う操作上の特徴として、シフトレバーが挙げられます。インパネに装着された小さなレバーですが、常に中立の位置にあるため、どこのレンジに入っているのか分かりにくいです。
同じトヨタのハイブリッド車の「アクア」は、前後方向にジグザグに動かす一般的なシフトレバーを前席中央の床に装着しています。これに比べると、プリウスのシフトレバーは使い勝手が分かりにくく、誤操作を招きそうな印象も受けます。
ただしこのシフトレバーは、最近になって採用を開始したわけではなく、2003年に発売された2代目プリウスから装着されています。また日産「ノートe-POWER」や「リーフ」には、丸い形状のシフトレバーが装着され、これもレバーは常に中立の位置そのままです。
クルマのデザインにはさまざまな可能性があるため、否定的な見方をするときは慎重になる必要がありますが、基本的な運転操作に違和感が生じるのは好ましくないです。
プリウスやノートe-POWERなどのシフトレバーは、今後検討が必要な機能ではあるでしょう。それでもプリウスの交通事故原因に直結するものではないと考えられます。
では、プリウスが交通事故の加害車両として目立つのは、どのような理由があるのでしょうか。
2009年から2015年に販売された3代目プリウスは、登録台数が多いです。約6年間に日本国内だけで112万台を登録しました。4代目にフルモデルチェンジされる直前まで含めて、1か月平均で1万6000台を販売しており、現行の4代目プリウス、アクアや2018年に小型/普通車の国内販売1位とされるノートと比べても圧倒的に多い台数です。発売直後には1か月に国内だけで約3万台を登録していました。
好調に売れた背景には、3代目プリウスが動力性能や燃費を大幅に向上させ、なおかつ、当時のライバルとされたホンダ「インサイト」に対抗する目的もあって、価格を割安に抑えたことがあります。
また、販売系列も新たにトヨタカローラ店とネッツトヨタ店を加えて全国の約4900店舗で扱われるようになり、売れ行きを急増させました。
プリウスを初代モデルから扱ってきたトヨタ店によると「3代目プリウスは物凄い人気でした。発売直後には、納期が最長で約10か月まで伸びています。工場はフル生産でしたが、それでも追い付かない状態でした。お客様も幅広く、法人から高齢の方までおられました」と振り返ります。
子育て世代のユーザーには、ミニバンや背の高い軽自動車が人気です。子供が成長するとSUVに移行するユーザーも増えました。
その一方で、高齢者は購入するクルマに悩んでいます。若い頃から慣れ親しんだセダンは車種数を減らし、設計も全般的に古くなっています。
トヨタ車であれば、ミドルサイズセダンの「プレミオ」「アリオン」は2007年の発売です。以前から設計の古さが感じられ、魅力を欠いていました。「マークX」の登場も2009年で、2019年末には生産を終えることが決まっています。
そうなるとミニバンやSUVが好みに合わない高齢のユーザーが、落ち着いた雰囲気の車種を求めた場合、プリウスが有力候補として浮上します。ベストセラーカーだから安心感も高いでしょう。
先のトヨタ店によると「高齢のお客様を含めて、一度はハイブリッド車に乗ってみたいと思っている方は意外に多いです。ただし新しいメカニズムなので、不安もあります。その点でプリウスは人気車ですから、お客様の背中を押す効果が高いです。
街中で頻繁に見かけられ、親戚や知人も買われたとすれば、ご自分も購入に踏み切れます。このような波及効果もあり、3代目プリウスは、新しいメカニズムが苦手だと感じているお客様にも買っていただきました」とコメントしています
暴走事故を食い止める対応策とは?
高齢のドライバーが加害者になった事故を含めて、プリウスが多く関係しているのは、大量に売られる車種で高齢ドライバーの比率も高いからでしょう。
プリウスの事故率は、損害保険料率算出機構による型式別料率クラスからも判断できます。
型式別料率クラスとは、保険料を決めるための参考データで、保険を使った過去の事故事例から各車種が事故の加害者になる危険度を判定しています。
対人賠償、対物賠償、搭乗者傷害、車両という項目に分かれ、それぞれ9段階で示されます。数字が増えるほど、各項目の事故を発生させる危険性も高いと判断されます。
この評価では、プリウスはほとんどの項目が「5」となり、事故発生のリスクが低いとはいえませんが、危険度の高い評価ではありません。プリウスが事故の加害車両として目立つのは、やはり保有台数が多く、高齢ドライバー比率が高いためです。
問題は、頻発する暴走事故を防ぐ今後の対策でしょう。緊急課題なので、考えられる複数の対策を迅速に講じる必要があります。その内容は以下の通りです。
■衝突被害軽減ブレーキ(緊急自動ブレーキ)を装着したクルマのさらなる普及
65歳以上の高齢ドライバーが、緊急自動ブレーキの充実した車種を購入するときは、補助金の交付も考えて良いでしょう。プラグインハイブリッド車やクリーンディーゼルの補助金は終了させ、安全装備を優先して補助すべきです。
■後付けのペダル踏み間違い加速抑制機能の普及
トヨタやダイハツは、後付けできるペダル踏み間違い加速抑制機能を販売しています。停車、あるいは車庫入れなどのために徐行しているとき、障害物があるのにアクセルペダルを素早く深く踏み込むと、エンジンの出力を絞って急発進事故を防ぎます。
価格は3万円から6万円ですが、これも高齢ドライバーを対象に補助金を交付すると良いです。高齢ドライバーの多い車種を中心に、なるべく多くのクルマに装着できるようにします。
■ペダル配置の見直し
今に始まったことではありませんが、車内の広さを重視する前輪駆動車の場合、ペダルと右側前輪の間隔が近づきます。車内を広く使うため、運転席を前寄りに設置した結果ですが、この設計では前輪の収まる部分を避けてペダルが左寄りに配置されやすいです。
そうなると運転席に座って自然に足を伸ばし、本来はブレーキペダルが位置するところに、アクセルペダルが配置される場合があります。アクセル/ブレーキペダルをしっかりと右側に寄せる車両開発も、ペダル踏み間違いの事故防止に役立ちます。
■MT(マニュアルトランスミッション)車の推奨
MT車では、アクセル/クラッチペダルをデリケートに連係させて操作しないと、発進や変速ができません。アクセルペダルを踏むだけで単純に発進するAT車に比べると操作が複雑です。ペダルを踏み間違えたら発進できないので、急発進事故も必然的に防げます。
また、クラッチを踏むことで駆動力をカットできることをドライバーが体で覚えているため、仮に走行中にアクセルペダルが戻らないといった問題が発生した時でも、即座にクラッチペダルを踏んで暴走を防げます。
今は緊急事態なので、MT車を推奨することも、急発進事故を防ぐ対策に含めて良いでしょう。考えられることは、すべてチャレンジすべきです。
多くの人達が、いろいろなアイデアを出し合って、不幸な事故を減らしたいものです。
1週間に1回はプリウスミサイルが飛んでいる!プリウスはかなり危険な車だ!
【了】
コンビニ壁面に車が突っ込む 近接の駐車場から 70歳の運転手がけが 「いきなり車が急発進した」
2023年12月4日
2023年12月4日午後、京都市西京区のコンビニエンスストアに車が突っ込む事故があり、車を運転していた70歳の男性がけがをしました。
午後0時半ごろ、京都市西京区松尾大利町で「車がコンビニに突っ込んできた」と警察に通報がありました。
警察によると、車を運転していた70歳の男性が、近くの病院の駐車場から車を発進させたところ、コンビニエンスストアに突っ込んだということです。
運転手の男性は病院に搬送されましたが軽傷で、店内にいた人たちにけがはありませんでした。
男性は警察の聴き取りに対し、「ミサイルのように、いきなり車が急発進した」などと話していて、警察は事故の詳しい原因を調べています。
クルマに後付けの「急発進防止装置」注目集まる アクセル踏み間違い事故を防げるか
2019.05.25
高齢ドライバーのアクセルペダルの誤操作による死傷事故が広く報じられるなか、カー用品店で、後付け可能な「急発進防止装置」の売上が増加しています。クルマメーカー側も、こうした後付け装置の発売に乗り出しています。
先進安全装置を持たないクルマのドライバーが注目
ペダルの踏み間違いによる事故を防止する、後付け可能なカー用品に注目が集まっています。
カー用品店のオートバックスを展開するオートバックスセブン(東京都江東区)によると、同社が2016年から販売している、クルマに後付け可能な急発進防止装置「ペダルの見張り番」が、2019年4月までは全国で月販100台に満たなかったところ、ゴールデンウイーク明けから販売数が急激に伸び、5月23日(木)時点の売り上げは前月比の約4倍に達したといいます。最近のクルマには、認識した障害物と衝突の危険があった場合にブレーキ操作を補助する「衝突被害軽減ブレーキ」や、加速を抑制する「ペダル踏み間違い時加速抑制装置」といった先進安全装置の普及が進んでいますが、そうした機能を持たないクルマのドライバーからの問い合わせも増えているそうです。
4月19日(日)、東京の池袋にて、高齢ドライバーのアクセル踏み間違いによる死亡事故が発生しました。この事故に関し広く報道されるなかで、ペダルの踏み間違い対策として注目が集まっているものと見られます。
踏み間違えても冷静に対処可能に?
では、こうした後付けの急発進防止装置は、実際のところどのように働くのでしょうか。「ペダルの見張り番」についてオートバックスセブンの説明によると、先進安全装置とはその仕組みやクルマの挙動でやや異なるものではあるものの、かんたんに言えば、アクセルからエンジンへの電気信号をしゃ断するものだそうです。「踏み間違えても急に飛び出すことがないので、大きな事故の予防につながるほか、改めてブレーキを踏むといった対処もしやすくなるでしょう」と話します。
「たとえばコインパーキングの出口で料金を支払う際、料金収受機にクルマをうまく寄せられず、ブレーキを踏んだまま体を乗り出して手を伸ばす人がいます。そのときにブレーキペダルから足が離れてクルマが動き出してしまい、慌ててブレーキと間違えアクセルを踏んで急加速すれば、暴走というべき事態になることも想像に難くありません」(オートバックスセブン)
ブレーキとアクセルの踏み間違いは、このように何かのはずみでパニックになり、アクセルを強く踏んでしまうケースが多いといい、それによる大きな事故を予防することができるといいます。
オートバックスセブンによると、「ペダルの見張り番」装着車オーナーの9割は65歳以上の高齢者ですが、最近は若い初心者オーナーのクルマに取り付けられるケースも増えているといいます。ドライバー本人が自発的に買い求めるというより、高齢者であればその配偶者や子ども、若者であれば親など、周囲のサポートがあって購入するケースが多いと話します。
なお、こうした後付けの安全装置は、クルマのメーカーからも発売されています。ソナーセンサーやコントローラーなどからなる「つくつく防止」を2018年12月に発売したダイハツによると、個人で購入する人もいれば、中古車の流通過程で付加価値をつけるために、ディーラーなどが取り付けるケースもあるとのこと。ダイハツでは2012(平成24)年以前に発売した、メーカーオプションで先進安全装置が選べなかった車種やモデルを中心に、後付け安全装置の対象車種を順次拡大しているそうです。
【画像】「ペダルの見張り番」の仕組み
【了】
[Q] ペダルの踏み間違いを防止するには?
[A]発進・後退の際には、各ペダルの位置を落ちついて確認し、十分に注意しながら操作しましょう。
オートマチック車の場合、アクセルペダルは右側に、ブレーキペダルはその左側と、2つのペダルが並んで配置されています。操作するときは、右足だけでアクセルペダルとブレーキペダルを交互に踏み替えながら操作することが一般的です。それぞれ「踏み込む」という同じ動作で操作するペダルが並んでいるため、踏み間違える可能性は年齢を問わずどなたでもありえます。
交通事故分析センターの情報によりますと、2018年から2020年の3年間でペダルの踏み間違えに起因する事故は1万件に迫る勢いで発生しています。その特徴として、65歳以上の高齢ドライバーが突出して多く、なかでも75歳以上の高齢ドライバーの事故が最も高い割合となっています。状況別では「発進時」が、また場所では「サービスエリア」や「店舗の駐車場」といった道路以外が高くなっています。高齢者では「後退時」の事故割合が高いのも特徴です。運転操作の誤りの要因は「慌て、パニック」が主で、またペダル操作の踏み間違えの要因は「高齢」「乗り慣れない車」などであると分析されています。
なぜ踏み間違えたまま加速してしまうのか?
ペダルの踏み間違え事故は、想定とは正反対のクルマの動きに気が動転し、正しい操作ができなくなったことで起きるといわれています。意図せずアクセルを踏み込んでしまうため、クルマが加速した状態でコントロールを失うことになり、重大な事故につながることが多いのです。これは、反射的に間違って踏んだアクセルペダルをさらに踏んでしまうことで発生します。このような状況では、意識と行為にズレが生じたとしても、それを訂正する余裕はドライバーにはほとんどありません。「ブレーキを踏んだのに加速した!」という証言は、主にこうした事象が原因です。
また、交通事故総合分析センターの分析によると、後進時に推測される踏み間違い要因(事故を起こしやすい高齢ドライバーの場合)として、「体を後方にひねる」「踏み替え回数の増加(切り返しの増加)」「急な後退」があると指摘しています。
このほか、駐車場内や渋滞時にブレーキとアクセルを細かく踏み替えながら徐行している状況でも、頻繁なペダル操作に混乱して左右を間違えるという場合もあります。想定外の事態に対処するのは、とても難しいことです。また、突然鳴り出したスマートフォンの呼び出し音など、些細なことでも人は簡単に注意力を削がれてしまいます。注意していても起こりうるのが、ペダル踏み間違え事故なのです。
踏み間違えを防止・抑制する機能とは?
ペダルの踏み間違え事故を防止するために、さまざまな先進安全技術が開発され実用化されています。主な技術の内容は、進行方向の障害物をセンサーやカメラなどで検知し、アクセルを強く踏み込んで衝突する恐れがあると判断すると、警告音等でドライバーに注意喚起するとともに、エンジンやブレーキを自動制御します。これらは「衝突被害軽減ブレーキ」と呼ばれる機能であり、そのシステムが搭載された車両が増えています。
また、不用意な後方への急加速を防ぐため、障害物を検知した状態で後進すると、エンジン出力抑制と自動ブレーキをかけるシステムもあります。 さらに、障害物ではなくアクセル開度を検知し、シフトレバーをリバースに入れた状態でアクセルを急に踏み込むと、ドライバーに警告音で注意喚起するとともに、エンジン出力を抑制する方式もあります。これらの技術は、ペダル踏み間違えというヒューマンエラーを防止するための技術ですが、道路状況や天候によってはシステムの検知範囲が制限されるなど、うまく作動しない場合もあります。
こうした装備は、ドライバーのうっかりミスを抑止するための補助をしてくれますが、絶対的な防止装置ではありません。発進・後退の際等では特に、ペダルの位置やシフトレバーのポジションを落ちついて確認し、十分に注意して操作することが大切です。安全運転は、あくまでドライバー自身に委ねられているといってよいでしょう。
【了】
【ASV紹介05】 リアビークルモニタリングシステム
リアビークルモニタリングシステム
自動車にはミラーでは見えない死角が左右の斜め後ろに存在します。
リアビークルモニタリングシステム(後側方接近車両注意喚起装置)は、この死角に他の車がいることをドライバーに知らせ、目視の不足によって発生する事故を防ぐことを目的としています。
センサーは車の後部側方に取り付けられており、ドライバーの死角になる斜め後方の車を検知します。
ドライバーがこの車に気付かず車線を変更しようとしたとき、インジケーター表示や警報ブザーでドライバーに危険を知らせます。
「急速接近してくる車に反応する場合もある」ではなく、「反応する車両もある」だな。超音波や赤外線ではなく、ミリ波で検知している場合は、悪天候に左右されにくい。
斜め後ろのミラーの死角に入っている車や入りそうな車の存在をドライバーに知らせる装置です。
ドライバーを支援する最新システム「先進安全自動車(ASV)の紹介」
https://jaf.or.jp/common/safety-drive...
【ASV紹介06 】自動切替型前照灯
https://www.youtube.com/watch?v=yG8AX...
先進安全自動車(ASV)の機能紹介
https://www.youtube.com/playlist?list...
【ASV紹介03 】車間距離制御装置
車間距離制御装置(ACC)
長距離を走行する場合、前の車との間隔を自動的に維持して走行することにはさまざまなメリットがあります。
車間距離制御装置は、車の前部に取り付けられたセンサーが前の車を認識し、システムがアクセル操作とブレーキ操作を行なうことで車間距離を一定に保ち、「ドライバーの疲労軽減」および「安全車間の確保」、「サグ部分での減速を防ぐことによる渋滞緩和」に貢献します。
※サグ部分とは道路が下り坂から上り坂に変わる部分
前走車との距離を一定に保つことによって安全な車間を確保し、ドライバーの疲労軽減させる装置です。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
暫定高速道路での事故多発;
対面通行で走る自動車専用道路での事故多発
宮崎と北九州市を結ぶ東九州自動車道はいわゆる「暫定高速道路(対面通行で走る自動車専用道路)」である。普通の片側1車線の道路を時速80キロ以上で飛ばすことを強要する世にも恐ろしい高速道路である。
この「暫定高速道路」で、片側1車線の道路を走行していると突然、車が大きく浮き上がると、跳ねるようにこちらに向かってきます。 撮影者はとっさに左にハンドルを切り、なんとか正面衝突は避けましたが、一歩間違えれば大事故になるところでした。 当時の状況について、撮影者は、次のように話しました。 撮影者:「車が飛んでくるのが見えた時、恐怖より焦りを感じた。あれこれ考えるより先に、手が無意識に動いていた」 幸い、この事故によるけが人はいなかったということです。 突然、目の前に車が飛んでくる恐怖。専門家は、悲惨な事故を防ぐためには、道路に対策を講じるべきといいます。 道路交通法に詳しい・高山俊吉弁護士:「対面通行で走る自動車専用道路で、対面通行の中にきちんと障壁がないというのは、私はこれは危険だと思う。自動車専用道路であれ、高速自動車国道であれ、対面走行ができる部分は作ってはいけない。つまり普通の高速道路に作り替えるべきだ。中央障壁をちゃんと作ることによって、こういう事故を起こさないようにするというのが、非常に重要」 (「グッド!モーニング」2022年11月1日放送分より)
2023年現在のクルマはといえば、システムではなく、あくまでドライバーが主体となる“レベル2”までの自動運転技術が一般的。あらかじめ設定した速度で自動的に加減速を行い、前車に追従するACC(アダプティブクルーズコントロール)や、車線の逸脱を検知するとハンドル操作をアシストするLKAS(レーンキープアシストシステム)などは、レベル1の自動運転技術とされています。
高速道路でも、これらの機能を使い、アクセルペダルを踏むことなく走行している人も相当数いると考えられますが、こうした機能を過信した“ながら運転”と思われる前方不注意で、工事の規制帯に突っ込む事故も相次いでおり、道路管理者も注意喚起を行っています。自動運転技術が進展することで、このような事故も避けられるようになるかもしれません。