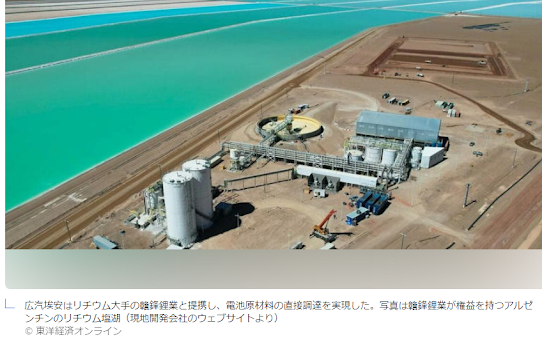❼『明日は我が身』 違法なモバイルバッテリーの発火相次ぐ、中国製の“非純正品”、中国から「世界の投資家」が逃げ出した…! 中国で充電中の電動車から出火相次ぐ 社会問題化|中国政府が普及進める「新エネルギー車」の火災が増加:「中国との事業は最初はバラ色だが本格化すると黒歴史となる」2023/06/24
❼中国から「世界の投資家」が逃げ出した…!
世界トップシェア 中国・BYDが日本でEV車販売へ
燃える中国製EV車、中国で
「動く時限爆弾」という声が噴出している。
中国製のEVとか正気の沙汰ではない!!!!
本国でもバッテリー爆発は有名になっている。
中国のEVメーカー、テスラ中国も危ない。
2023年7/21
世界的な脱炭素化の流れが進む中、EV(=電気自動車)など新エネルギー車の販売台数で世界トップシェアを占める中国メーカーのBYDが、日本で販売開始することを発表しました。
2022年7月21日、日本市場への参入を発表したのは中国の電気自動車メーカー・BYDです。バッテリーEVとプラグインハイブリッド車などを合わせた新エネルギー車では、今年上半期の販売台数が世界でトップと、急成長を遂げている企業です。
BYDジャパン・劉学亮社長「今の時代というのが電気自動車を買うか買わないかというより、いつ電気自動車に乗るかの時代なんですよね」
2023年来年1月から販売を開始し、来年中に3車種を発売する予定で、試乗などができる販売店も2025年までに100店舗作る計画としています。
中国「BYD」から日本に電撃! EV 3車種の日本発売決定を発表〜期待の価格を予想してみた
2022年7月21日
BYD(比亜迪汽車)の日本法人「BYDジャパン」が、日本でのEV乗用車発売の決定と新会社設立の記者発表会を開催しました。日本導入第1弾の電気自動車は『ATTO 3』。バッテリー容量58.56kWhで、期待の価格は400万円台前半と予想。2023年1月の発売予定です。
新会社を設立して全国にディーラー網を構築
2022年7月21日、日本法人であるBYDジャパン株式会社(以下、BYDジャパン)が「乗用車販売決定・新会社設立に関する記者発表会」を開催しました。華々しく発表されたのは、いきなり3車種がズラリと並んだ完全電気自動車の日本発売計画です。BYDジャパンでは、100%出資の子会社として国内での乗用車EV販売と関連サービスを提供する「BYD Auto Japan株式会社」を設立。2023年1月から、EV3車種を順次発売していきます。
テスラやヒョンデのように、メーカーと顧客がダイレクトに繋がるネット販売を主体にするのかと思いきや、都道府県を網羅して、当面、全国で100店舗ほどのディーラー網を構築する計画で、各地で店舗を設立するパートナー企業を募集するということでした。
ミドルサイズの e-SUV 「動く時限爆弾」『ATTO 3』
発表された仕様と、期待を込めた予想価格を表にしてみました。航続距離は「WLTC値」とされていますが、注釈で「自社による実測値」とあるので、まだ暫定的な数値と考えていいでしょう。表内のEPA換算推計値は、今までの車種事例を参考にしてWLTCに「0.8」を乗じた距離としています。
中国では「元PLUS」として人気のモデルで、中国での補助金を勘案した価格は約13万8000元〜16万6000元(約280万〜340万円)となっていますが、現地公式サイトのスペックではバッテリー容量が「49.92kWh」と「60.48kWh」の2タイプ紹介されており、日本仕様とは微妙に容量が異なります。
元PLUS はすでにオーストラリアなどで「ATTO 3」として発売されていて、オーストラリアの販売サイトを確認すると、49.92kWhのStanderd rangeが4万4381豪ドル(約423万円)。60.48kWhのExtended rangeが4万7381豪ドル(約451万円)となっています。
今日の発表会では、全モデルとも価格についてはまだ何も説明がありませんでした。勝手な期待を込めつつ「オーストラリアと同程度」だとすると、450万円程度、できれば400万円台前半で! と予想しておきます。仮に、バッテリー容量58.56kWhで、430万円だとすると、車両価格を電池容量で割ったお買い得指数が「約7.3万円/kWh」になります。容量72.6kWhでお買い得指数が高いヒョンデIONIQ 5 Voyageが「約7.1万円/kWh」です。発売予定の1月までまだ半年ほどあるのでいろいろ状況は変わるでしょうが、なんとか400万円切りを目指していただけたら絶賛します。
ちなみに、ATTO 3には昨日試乗取材もしました。今日は、BYDジャパンの劉学亮社長(BYD Auto Japan会長兼務)へのインタビュー取材もできました。今日の速報は価格予想中心にまとめますが、追って、もろもろ続報をお届けする予定です。
イルカを(時限爆弾を)イメージした e-Conpact 『DOLPHIN』
EVsmartブログでは、昨年の発売直後、BYDが格安電気自動車『海豚』の価格を発表「約31kWhで160万円〜」 という記事で注目しています。その際の驚愕ポイントは、中国での補助金を勘案すると「9万3800元(約159万6000円)、30.7kWhのバッテリーを搭載」というコストパフォーマンスでした。
現在の本国公式サイトを確認すると、30.7kWhモデルが10万2800元(約210万円)。日本仕様の「スタンダード」と同じ44.9kWhモデルが11万2800元(約231万円)〜となっています。
DOLPHIN の発売予定は2023年中頃ともう少し先ですが、「こういうEVが日本で発売されたらなぁ」という思いが、ついに実現することになります。期待を込めた予想価格としては、スタンダードが270万円だとするとお買い得指数は「約6万円/kWh」と世界最高レベル。なんとか200万円台後半を実現してくれたら。「新型軽EVもいいけど、やっぱり航続距離がなぁ」と迷っていた人の背中をドーンと押すパワーがあることは間違いなし、かと思います。58.56kWhのハイグレードには、300万円台前半を期待しましょう。
太刀打ちできる日本メーカー製EVは……
正式な価格について、今日の記者発表では1月に発売するATTO 3に関しては「遅くとも11月くらいには」というコメントがありました。予想価格はあくまでも「期待」と「希望」を込めた額なので、実際にどうなるのかは今後の注目ポイントです。
とはいえ、今日の発表では、「手が届きやすい価格を実現して、EV普及、ひいてはカーボンニュートラル社会の実現に貢献する」という理念が繰り返し強調されていました。この記事で提示した「期待予想価格」が実現されたら、日本の自動車業界にとってはかなりの「電撃」といっていいでしょう。ATTO 3に試乗した感触を含めて、EVとしてのコストパフォーマンスで太刀打ちできる日本製のEVは見当たらない、というのが正直な印象でした。
コストが掛かるディーラー網構築計画もあるし、期待の価格が実現できない可能性はあります。でも、期待を超える価格で日本進出を彩るかも知れません。もちろん、一人のEV大好き自動車ユーザーとしては、期待を超えるコストパフォーマンスであることを願っています。
BYDは、2022年4月、世界の自動車メーカーに先駆けて「ICE車の生産を完全に停止」することを発表しました。そして日本を含めた世界進出の勢いを強めています。
その原動力となっているのが、究極のリン酸鉄バッテリーとも言える「ブレードバッテリー」です。電池メーカーとしてスタートしたBYDが、電気自動車を作るために自動車メーカーとなって、エンジン車も作りながらEV作りのノウハウを積み上げてきて、現状での集大成ともいえる成果が、このブレードバッテリーであるといっていいでしょう。
今までにも、電気バスの日本進出加速宣言の記者発表会などで何度か見たことがある映像が、今日の発表会でも強調されました。ブレードバッテリーと三元系バッテリーを並べた釘刺し試験で、三元系バッテリーが爆発するのに、ブレードバッテリーは温度さえほとんど変化しない、という衝撃の映像です。ところが実際はこの中国メーカーが裏で映像編集している。動く時限爆弾が日本でも走ることになるのか!?
メモ代わりの動画で突然揺れたりしてますけど、ブレードバッテリーやEVプラットフォームについて、BYD Auto Japanの東福寺厚樹社長のプレゼンテーションを撮影してきたので、YouTubeのEVsmartチャンネルに限定公開しておきます。ぜひ、ご覧ください。今日紹介された3車種は、開発途中とかではなくて、すでに中国を始め世界各国で発売されて人気を集めているEVです。EVとしてのパッケージング、そしてバッテリー生産の技術や量産の実力など、BYDのEV技術が一朝一夕には追随できない高みにあることを感じました。
おりしも、猛暑の予感が色濃い夏の頃。手頃で魅力的な電気自動車の日本発売を祝福したい気持ちと、「われらがニッポンはクラウンの中で茹でガエルになってしまうのかなぁ」などと想像しつつ、冷たい汗が流れるような気持ちが交錯する発表会となったのでした。
(取材・文/寄本 好則)
「ハイブリッド車」神話崩壊? 豪州調査で判明「走り方次第でガソリン車より燃費悪化」 100万円高いHEVジョリオン、本当に元取れる?
仲田しんじ(研究論文ウォッチャー) によるストーリー
2025年5月10日
オーストラリア調査で意外な落とし穴
ガソリン代の節約を目的に、高価なハイブリッド車(HV)を購入する人が増えている。しかし、事はそう単純ではない。現実的な走行条件でのテストでは、すべてのHVが期待通りの燃費を達成するわけではない。
実際、オーストラリアでの調査によると、一部の車種では走行方法によって、
「ガソリン車よりも燃費が悪化する一部の車種がある」
ことがわかっている。高価なHVを選んだにもかかわらず、燃費が悪いとなると、購入の目的が達成されないことになる。
オーストラリア自動車協会(AAA)のリアルワールドテストプログラムでは、オーストラリア国内の市街地、郊外、高速道路などの実際の走行条件で、八つの人気車種のHVと内燃機関車(ICE)を比較テストした。その結果、HV車の燃費には
「車種ごとに大きな差があることが分かった」
ことが明らかになった。
トヨタHEV、ガソリン車より50%削減で良好だが・・・
テストに使用された8台のHVは、6台のハイブリッドEV(HEV)と2台のマイルドハイブリッドEV(MHEV)で、以下の車種が含まれている。
・トヨタ・RAV4(HEV)
・トヨタ・カローラ(HEV)
・トヨタ・カムリ(HEV)
・トヨタ・クルーガー(HEV)
・GEM(中国長城汽車)・ジョリオン(HEV)
・ホンダ・CR-V(HEV)
・スバル・フォレスター(MHEV)
・スズキ・スイフト(MHEV)
HEVは従来型のHVで、エンジンとモーターを切り替えて走行する。一方、MHEVはモーターのみでは走行せず、エンジンを補助する形で燃費向上を目指している。
テスト結果では、トヨタのHEV4台(RAV4、カローラ、カムリ、クルーガー)は、同モデルのガソリン車と比較して優れた燃費性能を示した。市街地走行では、HEVカムリがICEカムリに対し50.2%の燃費削減を達成し、HEVカローラ(49.4%)、HEVクルーガー(44.4%)、RAV4(38.5%)も良好な結果となった。
ホンダ・CR-V(HEV)とスズキ・スイフト(MHEV)も、それぞれICEモデルに比べて24%と28%の燃料消費削減を実現した。
一方、GWM・ジョリオン(HEV)は、同ICEモデルと比較して16%の燃費削減にとどまり、中国の実験室テストで観測された38%の削減率には届かなかった。ジョリオン(HEV)はICEモデルより約7000ドル(約100万円)高価であることも考慮すべき点である。
実燃費とカタログ値の乖離
スバル・フォレスター(MHEV)の総走行燃費は、約3000ドル(約43万円)安価な同ICEモデルより
「2.8%」
増加していた。燃費の悪化が既に問題となっていたのか、スバルはフォレスターMHEVの生産を中止し、新型HEVフォレスターの受注を開始している。
新車の実際の燃費はカタログ値と異なることが多いため、購入前に実走行での燃費を把握することが重要である。
AAAのマイケル・ブラッドリー専務理事は、HVの価格がICEより高いことを踏まえ、この調査結果は厳しいものであると述べている。
「当社のプログラムは、新車の実験室でのテスト結果が実際の性能とは大きく異なる可能性があることを示し続けており、コストを重視する顧客はお金を使う前に調査を知るべきです」
とブラッドリー氏はコメントした。
走行方法も燃費に大きな影響を与える。HVは都市部では郊外の田舎道より燃費がよく、高速道路では燃費が悪化することがわかった。
都市走行で圧倒的燃費改善
トヨタ・カムリ(HEV)は、市街地での燃料消費量を同ICEモデルに比べ50.2%削減したが、高速道路では削減率が33.4%にとどまった。
一方、GWM・ジョリオン(HEV)は、高速道路で同ICEモデルより燃料消費量が僅かに2.8%増加し、スバル・フォレスター(MHEV)は12.7%増えている。
AAAのクリス・ジョーンズ会長は、多くの消費者がHVの燃費特性に気づいていないと指摘する。
「従来のHVは、基本的には非常に効率的な車だ。しかしアイドリングストップを繰り返す交通状況に最適化されており、オーストラリアではほとんどの運転はアイドリングストップが行われています」
と説明する。そのため、オーストラリアでもEVはガソリン消費削減に有効だが、
「HVの低速域での最適化だが、一部車種では高速域での効率低下を招いている」
と述べ、広大な国土を持つオーストラリアの郊外ではEVの利点があまり発揮されないと指摘する。そのため、オーストラリアの郊外のドライバーにとって、HVはプラグインハイブリッド車(PHV)ほどに便利ではない可能性があるとジョーンズ会長は述べている。
高速走行時のHV燃費疑問
オーストラリア連邦自動車産業会議所によると、2025年の最初の3か月でオーストラリアのドライバーは4万7000台以上の新型HVを購入した。これにより、HVの新モデル販売は過去1年間で34%以上増加した。
HVの人気は高まっているが、今回の調査で一部HVに潜む意外な落とし穴が浮き彫りになった。
トヨタ・RAV4(HEV)やトヨタ・クルーガー(HEV)などの車両は高速道路でも良好な燃費を発揮する。しかし、長距離をノンストップで走ることが多いドライバーは、一部HVの高額な価格が本当に見合うのか、今回の調査結果やユーザーレポートを参照して慎重に判断するべきだ。
中国国産EV車「五菱」、起動していないのに突然発火―中国
EVの安全性は年々向上しているはずなのに・・・
この発火した「繽果」に搭載される電池は複数の中国ブランドが供給しているという
Record China によるストーリー
2025年5月10日
2025年5月8日、台湾メディアETtodayは、中国安徽省で中国国産ブランド・五菱の電気自動車(EV)が路上で自然発火する事故が起きたと報じた。
記事によると、安徽省宣城市の路上で2025年5月6日、五菱のEV「繽果」1台が停車中に自然発火して廃車となった。車の持ち主は「経営する店の前に停めていたらいきなり燃えだした。午前8時過ぎに車を停め、午後1時過ぎに隣家の人から車が燃えていると知らされた」と語ったという。
持ち主によると、この車は昨年2024年1月に8万元(約160万円)余りで購入したという。防犯カメラの映像では車の左フロント部分から出火したことが確認でき、持ち主は「左前輪上部の電気回路に原因があったのではないか」と話している。現在メーカーが事故車両を回収した上で原因を調べているとのことだ。
「繽果」はA0クラスと呼ばれる軸距2.2〜2.3メートル、排気量1000〜1300cc相当のコンパクトカーで、リン酸鉄リチウム電池が使われている。電池の容量はグレードによって17.3〜37.9キロワット時と異なり、航続距離は203〜410キロとなっている。また、この発火した「繽果」に搭載される電池は複数の中国ブランドが供給しているという。(編集・翻訳/川尻)
中国で充電中の電気自動車が爆発 破片がステーションの屋根を突き破る
消防隊が水をかけて対処しましたが……。
事故が起きたのは中国・福建省にある三明市。爆発した電気自動車は市内で充電を行えるステーションを訪れていました。
オーナーがステーションに設置されている充電用ケーブルを接続した直後、クルマから煙が出始めたそうです。連絡を受けてかけつけた消防隊員はクルマの後部に冷水を吹きかけました。
YouTubeで公開された映像はまさに消防隊員が冷水を吹きかけている状況から撮影されたもので、直後にクルマは爆発。爆炎と共にボディーパネルだけでなく内装までも吹き飛ばし、ステーションの屋根には穴が開いています。映像の後半は違うアングルから撮影された爆発後のクルマが映されており、激しく損傷している様子がわかります。もし、人が残っていたらと思うと恐ろしいですね。
ちなみに、ガソリン車の火災では一般的に泡状の消火剤を用いますが、電気自動車では感電の恐れやバッテリーの温度を下げないことには鎮火しないことから、電気自動車に対しては映像にあるように冷水をかけて対処するそうです。
動画が取得できませんでした
動く時限爆弾
日本でも電動バス実験で使ってるの中国製の電動バスだったりするからね。政府はしっかり日本のメーカーを守って欲しい
電気自動車から発火 中国政府が普及進める「新エネルギー車」の火災が増加|TBS NEWS DIG
2022/06/24
電動バスが自然発火で次々炎上・・・連日40℃近い熱波で(2021年5月17日)
中国で充電中の電動車から出火相次ぐ 社会問題化2021/07/20
中国で充電中の電動の車が原因の火災が相次いでいます。北京では2021/07/18日、充電中の電気自動車から出火、3台が次々、燃えました。
2021/07/18日の早朝、北京市の大興区で突然、電気自動車が白い煙を吹き出しました。車は、その後、燃え上がり、火は隣の自動車にも燃え広がりました。中国メディアによりますと、現場は、電気自動車の充電スタンドで車は充電中だったということです。
また、こちらは、四川省・成都で先月2021/06/23に撮影された映像。燃えているのは、駐車場に止めてあった200台を超す電動スクーターで、中国メディアによりますと、こちらも充電中に火が出た可能性があるということです。
中国で、こうした火災は相次いでいて社会問題となっています。(2021/07/20日16:39)
中国で走行中の電動スクーター爆発、3人けが2021/07/19
多くの新車炎上・・・複数の自動車販売店で火災 中国 (2021年10月19日)
電気自動車から発火 中国政府が普及進める「新エネルギー車」の火災が増加|TBS NEWS DIG
8,643 回視聴2022/06/24
走行中の電動バイクが爆発炎上 親子3人けが 中国(2021年7月19日)
2021/07/19
走行中の電動バイクが突然、爆発して炎上。3人がけがをしました。中国の浙江省で18日、2人乗りの電動バイクが走行中に突然、爆発して大きな炎に包まれました。近くにいた人たちがすぐに消火作業にあたりましたが、バイクは真っ黒に焼けてしまいました。乗っていた父親や娘ら3人がけがをしたということです。
中国では通勤や宅配などで安価な電動バイクが急速に普及していますが、バッテリーが原因の火災が相次ぎ、問題となっています。
現地ではけがの父親が重傷だと報じられていて、警察が爆発の原因を調べています。
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp
中国でEV相次ぎ発火、最大手BYDや新興の蔚来
アジアBiz
2019年4月25日 20:30
広州=川上尚志】中国で電気自動車(EV)が爆発したり発火したりする事故が相次いでいる。2019年4月21日に米テスラのEVが爆発したのに続き、メーカー最大手の比亜迪(BYD)や新興の上海蔚来汽車(NIO)のEVでも発火事故が起きた。いずれもけが人は出ていないものの、世界最大市場での相次ぐ事故で、EVの安全に対する不安が強まりかねない。2019年4月24日には中国内陸部の湖北省武漢市でBYDのEVが発火した。同日夜にBYDが発表した声明によると「発火したのはトランクの部分で(基幹部品の)電池は壊れていない」という。こんなプロパガンダは世界には通用しない。2019年4月22日にはNIOのEVも北西部の陝西省西安市の修理場で修理中に発火した。NIOは23日「専門家と調査を進めており、結果は速やかに公表する」とする声明を出した。
2019年4月21日にはテスラのEVも上海市内の駐車場で発火し、爆発する事故を起こしたと報じられた。
いずれの事故も原因は究明されていないが、爆発や発火の多くは車載電池が原因とされる。相次ぐEVの事故について自動車業界の専門家からは「安全基準を緩めてはならない。技術がまだ不完全だと言い訳はできない」との指摘も出ている。
中国は世界最大のEV市場だ。18年にはEVなど新エネルギー車の新車販売台数が125万台となり、17年に比べ6割強伸びた。中国政府は19年から自動車メーカーに一定比率のEVなどの製造を義務付ける制度を導入し、多くのメーカーが生産を増やす見通し。ただメーカーが安全面の管理をおろそかにしたままでは、消費者離れにつながる恐れもある。
中国で電動自転車の火災が1万件 充電バッテリーから発火、「爆弾」の声も
2021.11.02
【2021年10月28日 東方新報】ひと昔前の中国と言えば「自転車の波」のイメージが浮かぶが、今は電動自転車の保有台数が3億台を超え、新たな国民の足となっている。しかしここ2年ほど電動自転車の火災が相次ぎ、今年はすでに1万件を突破。死者も出ていて社会問題となっている。
日本で電動自転車というとペダルをこいで走行する電動アシスト自転車のこと。中国の電動自転車はハンドルのアクセルを握るだけで走行するので、実質は電動スクーターだ。ペダルは走行中にバッテリーが切れた時に使うぐらい。2000元(約3万5653円)もあれば購入でき、時速は20キロ以上出るが免許はいらない。経済成長に伴い自動車保有者が増え、都市では交通渋滞が悪化している中、電動自転車は日常生活に欠かせない存在になっている。
ただ、安全生産や災害管理を管轄する応急管理省によると、今年第1~9月に全国で報告された電動自転車の火災件数は1万30件に達した。約8割がバッテリーの充電中に発生しており、その多くがリチウム電池の発火によるものという。2021年9月20日未明には北京市通州区(Tongzhou)の集合住宅で火災が発生し、5階に住む家族5人が死亡した。3階の住民が電動自転車のリチウム電池を自宅で充電中、バッテリーが炎上したとみられる。バッテリーはフル充電すると数時間はかかるため、帰宅後の就寝中に室内で充電することが多い。しかし相次ぐ発火事故に、市民からは「爆弾を自宅に持ち込んでいるようなものだ」という声が噴出している。
火災トラブルが集中して発生
電動自転車は大きく分けて鉛蓄電池とリチウム電池の2種類がある。中国では鉛蓄電池が主流だが、2018年に「電動自転車の重量は55キロ以下にする」という国家規格が設けられると、重さ10キロ以上もある鉛蓄電池のバッテリーから数キロ程度のリチウム電池のバッテリーに切り替えが進んだ。しかしこのリチウム電池の耐久安全性が問題となっている。
専門家によると、リチウム電池は鉛蓄電池よりエネルギー密度は高い一方、電解液の可燃性も高い。電動自転車のリチウム電池は数十個の電池を直列・並列に組み合わせているが、充電しても不具合のある電池が「俺はまだ腹いっぱい食べていない」と充電を求め続けると、過充電となって他の電池が発火してしまうという。リチウム電池使用の電動自転車のシェアは新国家基準前の3%から15%に増えた程度だが、火災トラブルが集中して発生している。中国自転車協会の陸金竜(Liu Jinlong)副理事長は「2018年の新国家規格前は、電気自動車の発火や爆発事故はずっと少なかった」と話す。
バッテリーを自宅に持ち込まずに済むよう、地域の駐車場や公園などに充電スタンドを設立する動きも出ているが、コストや安全管理の問題からあまり広まっていない。一部のメーカーはより安全なナトリウム電池のバッテリーを開発しているものの、リチウム電池よりエネルギー密度が低く、市場に出回るにはまだ時間を要する。そもそもリチウム電池は電気自動車でも使用されており、それ自体は危険性が高いわけではない。メーカー間の価格競争で品質に問題のあるリチウム電池が流通しているのが問題だ。当面は行政がリチウム電池の品質基準を強化し、企業が改善に取り組むことが急務となっている。
(c)東方新報/AFPBB News 【翻訳編集】AFPBB News
電気自動車ニュース
電気自動車普及は止まらない! 中国では2022年末までにNEV年間販売台数600万台を達成か
2022年7月24日
中国における2022年のNEV(電気自動車を含む新エネルギー車)販売台数が、コロナ禍などの障壁を越えて急増を続けています。『ChinaAutoReview』元編集長で、アメリカ在住のアナリスト、Lei Xing氏の解説をお届けします。
上海のロックダウンで自動車の生産は中断したが……
中国NEV市場の回復力を侮ってはいけません。転機が過ぎたことを覚えておいてください。
まさにジェットコースターのような展開でした。
今年の始め、前年比で160%成長し350万台の新エネルギー車両(NEV)が売れた(中国汽車工業協会:CAAMによる)2021年は輝いて見え、個人的には2022年のセールスが600万台を越えるのではと強い希望を持ちました。
ところが上海では4月にコロナによるロックダウンがありました。周辺都市や中国の他の地域が感染爆発を抑えるために戦う中、実質的に都市機能が停止したのです。この期間、上海ではNEVだろうがICEだろうが車両は1台も販売されず、テスラを含め自動車メーカーは生産の中断を余儀なくされました。中国乗用車協会(CPCA)によるとテスラ車は4月に中国国内で1,512台しか売れず、NEVのセールスも30万台以下で、2021年7月以来の低水準となりました。
5月の始めに4月のNEV販売データが報じられた際、上海が近いうちにロックダウンを解除するのかも定かでなく、年内に500万台でさえ売ることができるのかと私は疑問に思いました。業界全体の雰囲気もかなり悪いものでした。
ところがどういうわけか、上海ロックダウンの手法が良かったのか、はたまた上海市民の粘り強さか、春から夏に変わるにつれて状況が好転しました。上海は徐々にロックダウンの解除を進め、域内のメーカーやサプライヤーに必要な生産活動は元に戻りました。諺にもあるように、物事は常に良くなるものなのです。
時を早送りして7月1日、スマートEVスタートアップの中でも先を行く企業達が7月のデリバリー数を発表した際には、そのほとんどが月間デリバリー数の最高値を出して安堵の息をつきました。特にここ数カ月他社の後塵を拝していたNIOにとってはカミングアウトするパーティのようなもので、良い数字を出さなければならないプレッシャーがかかっていましたが、成功しました。数日後にはBYDが13万台のNEV車販売で過去最高を記録し、世界のNEV販売台数でテスラを抜き1位に躍り出ました。
6月には過去最高の59万台6000台を達成
7月6日、中国公安部(MPS)は2022年6月末時点での最新の車両登録データを公表し、そこでは今年前半のNEV市場の動向を見ることができます。約221万台のNEV車両が今年前半に登録され、自動車市場全体の1,110万台のうち20%弱を占めています。2022年6月末の時点で、中国では過去10年ほどで売られた1,001万台のNEV車両が路上を走っていました。ということは、そのうち約22%が今年前半で登録された車両となり、市場の成長がどのような具合かお分かりになるでしょう。事実MPSのデータによると中国国内を走るNEV車両の数は、2020年終わりの時点で500万台しかなかったので、その数は過去1年半で倍以上に増えたことになります。また2018年6月の200万台からも、たった4年で4倍に増えたということでもあります。
CPCAがNEV乗用車の生産、卸し・小売販売台数を発表した7月8日の前日、すべての自動車メーカーが発表した6月の売り上げを元に私が計算した結果、販売台数は50万台を越えると予想できました。驚くなかれ、CPCAは卸しで57万1,000台、小売では過去最高の7万8,906台のテスラを含む53万2,000台と発表しました。そのほとんどが中国国内でのものです。この数値は私を含め、業界内の人間を驚かせました。
CAAMが7月11日に商業車を含む6月のNEV販売台数を発表し、その数は過去最高の59万6,000台でした。4月に売られた台数の約2倍です。2022年前半だけで、NEVは260万台売れました。2021年通年での350万台まであと90万台に迫っています。
よって、3カ月で状況は元に戻りました。私が今年初めに考えたNEV600万台は、上海ロックダウンのような困難にも耐えた現在の勢いを見ると確実に達成可能と思えます。振り返ってみると、NEV市場はロックダウン、サプライチェーンの問題、世界の地政学的な状況からそれほどダメージを受けませんでした。強固な需要があり、自動車メーカーやサプライヤーが利害関係者と協力して生産を維持したからです。
私は常に中国のNEV市場の転換点はだいぶ前に過ぎたと話していますが、この先の需要が問題になる事はないでしょう。スマートEVスタートアップを含めほとんどの自動車メーカーは多くのバックオーダーを抱えていて、6月の販売台数は過去数カ月にデリバリーされるはずだったものを反映したに過ぎません。例えばBYDは、今も何十万台もの注文を抱えています(7月上旬に70万台)。2022年前半に64万台のNEVを売り上げた今、以前私が “Will BYD sell 1.5 million NEVs in 2022?” で書いた通り、通年では150万台を達成する確率が非常に高いです。ということは、BYDだけで今年の中国NEV市場の約4分の1を占める計算になります。
私が強気なのは、時期的な理由もあります。販売台数は年の後半に多くなるのが常で、第4四半期は通常1年の中で最も売れる時期なのです。特に今年は、年末にNEVの消費税免除の制度が終わってしまうというワイルドカードが控えています。制度を2023年まで延長する議論もあるのですが、それが決定して発表されるまでは年末に向けて販売台数の急増があるかもしれません。さらに、古い車両をNEVに買い替えさせる後押しをするため、国と地方レベルで1万元(約20万5,000円)を越える補助金が出されるなど前例のない政策が取られています。
NEV販売に若干ネガティブな影響を及ぼすであろう唯一の状況が、2.0Lもしくは30万元(約615万円)以下のICE乗用車の消費税が年末まで半額になっていることで、全体の乗用車販売台数は増えるでしょうが、NEVの浸透を妨げる要因になるでしょう。しかしNEVへの全体的な需要と熱狂は、刺激策に関係なく強くあり続けると考えられます。
以上すべてが、2022年の中国で600万台以上のNEVが売れる布石となっています。達成できるかではなく、何台売れるのかが争点になるでしょう。中国のNEV市場を侮ってはいけないのです。
※ 筆者注/記事中のNEV車両とは、文中で特別に言及されているものを除き、PHEV、BEV、FCEVの乗用車及び商業車となります。販売台数には輸出分も含まれます。
(翻訳/杉田 明子)
「壊れたらどうすれば…」太陽光発電の課題(2022年7月21日)
発火の恐れ…韓国車ヒョンデとキア、米国で330万台をリコール=韓国ネットからは不満続出
2023年9月27日、韓国・聯合ニュースによると、現代自動車(ヒョンデ)と起亜自動車(キア)が米国でそれぞれ約160万台、約170万台をリコールすると、米国運輸省道路交通安全局(NHTSA)が27日(現地時間)に発表した。
記事によると、起亜自動車側は「車両の油圧式電子制御装置(HECU)がショートを起こす恐れがあり、これにより駐車中や走行中にエンジン部品から発火する可能性がある」と説明した。
現代自動車側は「アンチロックブレーキシステム(ABS)モジュールのブレーキ液漏れによりショートが起きる可能性があり、これがエンジン部品からの発火につながる恐れがある」と説明した。
両社は油圧式電子制御装置やアンチロックブレーキシステムの交換などを行い、問題を解決する方針だという。
この記事を見た韓国のネットユーザーからは「なぜ米国だけでリコールする?」「韓国の消費者には『自分で欠陥を証明せよ』と言うのにね」「米国の消費者の前では何も言えない弱虫企業なのに、韓国の消費者のことはカモ扱い」「韓国内の車も大々的なリコールを実施するべきだ」「韓国で車を売って稼いだお金を全て米国に貢いでいる」「それよりも韓国内での急加速事故問題をどうにかしてほしい」など、韓国内との対応の差に不満を示す声が多数寄せられている。(翻訳・編集/堂本)
中国・シャオミ製造のEVが事故 大学生3人死亡
中国のEV車の安全装置に疑問符?
2025年4月2日
中国の大手スマートフォンメーカー・シャオミが製造したEV=電気自動車が中央分離帯に衝突する事故があり、乗っていた大学生3人が死亡しました。遺族がメーカーの責任を問うなど、中国国内で波紋が広がっています。
中国メディアやメーカーの発表によりますと先2025年4月29日夜、安徽省の高速道路で、大学生の女性3人が乗るEVが、前方で道路工事が行われていたため車線変更しようとした際、コンクリートの中央分離帯に衝突しました。
この事故で乗っていた3人全員が死亡しました。
この車は、シャオミが去年2024年3月に発売した「SU7」で、シャオミによりますと車は時速76キロで走行中に工事現場を検知し、運転手に対し手動モードに切り替えるよう警告を鳴らして自動で減速を始めたものの、制御できず衝突したということです。
SNS上では「衝突の2秒前に手動モードに促されても、間に合うはずがない」などの指摘が上がっているほか、中国メディアは遺族の話として「事故の衝撃で車が炎上した際、 ドアが開かなくなった」との主張を報じています。
「SU7」は去年2024年3月の発売時、わずか27分で5万台の予約があったとされ、大きな注目を集めていました。
シャオミの雷軍CEOは2025年4月1日、「専門チームを設置し、警察の捜査に協力し対応に当たる」と声明を発表しています。
中国では、車の運転サポート機能をめぐり、過去にも比亜迪(BYD)や新興の上海蔚来汽車(NIO)のEVでも複数のメーカーで衝突事故が起きていて、安全性を懸念する声が上がっていました。
『明日は我が身』
国の基準を満たしていない違法なモバイルバッテリーの発火事故が後を絶たない。スマートフォンなどの充電に使われるリチウムイオン電池内蔵タイプで、発火しているのは大半が安価な中国製とみられる。販売元の業者とは事故後の連絡も取りにくく、損害賠償請求に支障がある。国は規制強化を検討している。(山口佐和子)
消防によると、発火事故は夏場に起きやすい。充電中に制御機能が正常に働かず、充電し過ぎて発火することがある。このほか、高温の場所に放置したり落下させたりすると、内部が変形・破損して事故につながりやすいという。
大阪市内では、リチウムイオン電池の関係するモバイルバッテリーなどの火災は2012年は1件だったが、22年には25件に増加。上着のポケットで携帯電話を充電中に発火するなど、今年も7月末現在で16件の火災が起き、7人が負傷した。東京消防庁によると、東京都内で起きた火災件数も12年の4件から21年は141件に増えている。発火事故はどこで起きるかわからない。
横浜市の会社員男性(31)は20年7月、都内を走行していた東急田園都市線の電車内で経験した。網棚に置いていたカバンから「ボン」という爆発音がし、白煙が上がった。混雑する車内は一時騒然となり、乗客が飲み物をかけて事なきをえたが、電車は次の駅で停車し、遅れが出た。
燃えたのは、インターネット接続機器「ルーター」の充電に使っていたモバイルバッテリーで、約1年前に東京・秋葉原の電器店で1000円ほどで買った「格安商品」だった。後日、消防から「内部のリチウムイオン電池のショートが原因。粗悪な作りで、海外製だろう」と説明を受けたという。
男性は取材に「使い方に問題があったとは思わない。メーカー名の記載がなく、問い合わせもできなかった。鉄道会社から遅延の賠償金を請求されたらどうしようかと不安だった」と語った。国側も海外業者の対策を怠ってきたわけではない。19年には、技術基準に適合したことを示す「PSEマーク」の表示がないモバイルバッテリーは電気用品安全法で家電量販店などでの販売を禁じた。その後もアマゾンのような大手通販サイトに違法なモバイルバッテリー製品の出品を停止するよう要請した。だが、ネット上での違法なバッテリー製品の取引を完全に防ぐことはできていない。
製品の使用者がその国の販売元に連絡を取ろうとしても海外での電話番号でわからなかったり、つながらなかったりして泣き寝入りになるケースがある。今年6月の有識者会議で、海外業者がモバイルバッテリーなどを販売する場合は国内に連絡がとれる責任者を置くよう求めるべきだとする意見が出たことを踏まえ、経産省が規制強化案を検討している。
OPPOは、コスパの高さが人気となっている中国のスマートフォンメーカーです。
カメラ性能が高く雨の日でも使いやすい点が人気ですが、中国製という点に対して危険性を指摘する声があるのも事実です。
そこでこの記事では、OPPOスマホの危険性や口コミ・評判を紹介します。
OPPOは中国のスマホメーカーであることから、情報流出の危険性を気にする人もいます。
中国製のスマートフォンで情報流出の危険性が指摘される理由は、過去に中国製のアプリがユーザーに無断で個人情報を送信していたケースがあったためです。また、同じ中国のスマートフォンメーカーであるHUAWEIは、アメリカから輸出規制の措置を受けています。
OPPOのスマートフォンは、バッテリーの持ちがあまりよくないと感じる人もいるようです。新品にもかかわらず、劣化したバッテリーを使っているかのような減りの早さだとの声もありました。
また、廃熱性能の悪さが気になるとの声もあります。スマホが熱くなってしまうと火傷などの危険があるだけでなく、バッテリーの劣化にもつながります。特に夏場は熱くなりやすいため、注意が必要です。
OPPOの端末は廃熱性能が低く、すぐに本体が熱くなるという声もありました。他の端末でもすぐに熱くなってしまうという人の場合、OPPOのスマホを使うのは危険だといえるでしょう。
バッテリーの持ちが悪いという口コミもあるため、バッテリーが長持ちする端末を使いたい人も、OPPOは避けた方が無難です。
電動アシスト自転車が“爆発” バッテリーは中国製の“非純正品”【Nスタ解説】|TBS NEWS DIG
2023年8月30日、東京・新宿の交差点で電動アシスト自転車の中国製のバッテリーが爆発しました。爆発したバッテリーは“非純正品”であることが分かっていますが、“中国製の非純正品”をめぐる安全性や注意点について考えます。
■ 注意書きには“不具合による出火の可能性もある”
井上貴博キャスター:
非純正品を使ってトラブルになった場合、たとえ元々あったのが純正品であったとしても保証の対象にならないことも多くあります。様々なリスクを頭に入れておくことが必要です。5月30日に新宿の交差点で電動アシスト自転車のバッテリーが爆発しました。
電動アシスト自転車に乗っていた女性(30代)
「バッテリーは純正品ではなく、通販で買った中国製品。注意書きには“不具合による出火の可能性もある”と書いてあった」
この注意書きを分かった上で購入して使っていたということです。中国製の“非純正品”であったわけです。
バッテリー交換時期は、メーカー側から目安として約3~4年と言われています。販売価格は、純正品は約4~5万円、非純正品は約2~3万円。安いので非純正品を買う方も一定数いますが、安いのには理由があります。
■NITE担当者「安全性が劣る製品が出回っている」
NITE(製品評価技術基礎機構)の担当者は「安全性が劣る製品が出回っていることが多々ある。非純正品による事故も起きている」とのことです。
バッテリー発火などによる事故のデータを調べてみると、2017年は8件に対し、2021年は30件と電動アシスト付自転車の普及により、分母も増えているので、事故も増えています。
これが全て非純正品による事故かというと、そこの調査は行われていないのでわかりません。いずれにしても、バッテリー発火は4年で約4倍に増加している実態です。
ホラン千秋キャスター:
正規のサイトやお店でないところで買う場合は、純正品と書かれていることもあるし、純正品と謳っているけれども、実は非純正品だったという可能性もある。安全を考えると値段が高くても純正品が安全ということですよね。
萩谷麻衣子弁護士:
中国製の非純正品は、本体のメーカーが設計や品質管理に関与していないので、安全性はピンキリだと思います。この製品は安全なのかを自分でしっかりチェックする。
仮に事故が起きた場合、損害が生じたときに非純正品でもしっかりしたメーカーであれば、製造物責任などの損害賠償請求などできることがあります。
ですが、怪しいメーカーや中国製の海外のメーカーだとすると、そういうこともできない。火事や人に怪我をさせたりしてしまうこともありますから、安いから非純正品を買うという一点で見るのは、リスクが大きいと思います。
■非純正バッテリーの発火事故は134件 製品の安全性はどうチェックする?
井上キャスター:
安いので充電器などは、非純正の方がいいなと思ってしまいがちですが、自転車以外にも様々なものにバッテリーが使われています。
▼掃除機 ▼電動工具 ▼ノートパソコン ▼スマートフォン。2017年から2021年で、非純正品のバッテリーでの発火事故が134件起きています。それが原因で住宅が全焼する火事も起きてしまっています。
NITEが粗悪品の充電器を使っているとこうなるという実験をしています。リチウムイオンバッテリーが膨張し、煙が出て最後に発火する。そして、住宅火災などに繋がるということです。消費者は、どういったところに注意すればいいのでしょうか。
【バッテリー購入時の注意点は?】
・他と比べて極端に安い
・商品説明の日本語が不自然
・レビューが高評価ばかり
→やらせの危険性も
・販売事業者の連絡先が不明
・最後の注意点を別の言い方で表すと「アマゾンで買った安物」
萩谷弁護士:
製品については、電気用品安全法という法律で、安全基準を満たしたものについては、PSEマークが付けられます。PSEマークがついてるかどうかを、製品の裏側などでチェックしてみるのもいいと思います。ただ、ニセモノでもつけてる場合もあるので、それだけを信用するのは、危険性もあります
中国で電動スクーターバッテリーから突然火が! 死亡事故も
住人不在の部屋でバッテリーが発火?意外な原因とは・・・ 中国・北京
⓼アマゾン・ジャパンで購入の中国製バッテリー出火 責任の所在は
2022/5/8
交渉に限界
栃木県宇都宮市の男性会社員(35)は平成28年6月、アマゾン・ジャパンのサイトを通じて中国メーカーの充電式モバイルバッテリーを購入。約1年5カ月後の平成29年11月、自宅マンションのリビングで充電中のバッテリーが突然発火した。家族は全員避難し無事だったが、リビングは大きく焼損。家財道具も被害を受け、損害額は1千万円超に上った。
その後の消防の調査で、出火原因はバッテリー内部の絶縁体の劣化によるショートと判定された。加入していた火災保険で補償されたのは約730万円。男性はアマゾン・ジャパンの問い合わせフォームを通じ中国メーカーに連絡を取ったが、中国メーカー側は電話での対応に応じず、日本の法律には規定のない「家財損壊証明書」の提出を要求してきたという。
被害弁済は一向に進まず、男性はアマゾン・ジャパンに交渉の仲介などを依頼したが、拒否された。個人での交渉に限界を感じた男性は、複数の弁護士に依頼し中国国内での訴訟も検討したが、訴訟費用だけで数百万円ほどかかることが分かり、断念した。
コストを転嫁
一連の対応でアマゾン・ジャパンに不信感を持った男性は令和2年10月、アマゾン・ジャパン(東京)に30万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴。アマゾン・ジャパンには利用契約に基づき出店者や商品を審査する義務や、消費者が不測の損害を受けた際の補償制度を構築する義務があった、などと主張した。
だが、今年4月15日の地裁判決は「原告はアマゾン・ジャパンの問い合わせフォームを利用してメーカーと連絡を取り、和解を成立させることができた」と指摘。アマゾン・ジャパンによる商品の審査については、義務とまではいえないとして、請求を棄却した。
「アマゾン・ジャパンは取引で利益を上げている。消費者を守る義務とまでは言わないが、困ったときに積極的に対応する仕組みがあってほしい」。判決後の記者会見で、男性はこう訴えた。
ほぼ独力で行ったメーカーとの和解が、裁判の中でアマゾン・ジャパン側に有利に評価された点については「消費者にリスクコストを転嫁している」と不満をあらわにし、控訴を決めた。
米国で相次ぐ勝訴
一方、USAアマゾンで購入した欠陥商品のトラブルをめぐる同種訴訟は、米国(USA)では消費者側が勝訴する判決が相次いでいる。その背景にあるのは「製造物責任」に対する日米の考え方の違いだ。
製造物責任法(PL法)に詳しい久留米大法学部の朝見行弘教授によると、日本では製造業者のみが責任を負うのに対し、米国では製造業者を含めた販売業者が負うとされ、アマゾンのようなDPF事業者も、販売を仲介する「流通の直接的な環」と評価されるようになったという。
米国米国では2019年以降、米国アマゾンで購入した中国製品による発火被害などをめぐり消費者が起こした訴訟で、販売店と消費者を仲介する流通業者であるとして、米国アマゾンの賠償責任を認める確定判決が続出。これを受けて米国アマゾンは昨年8月、欠陥商品で損害を受けた米国内の消費者に対し、1千ドル以下の賠償請求であれば直接補償金を支払うと規約を改正した。
朝見氏は、日本でPL法が施行された平成7年当時について「海外メーカーが直接国内の消費者と取引することは想定されておらず、輸入品については輸入業者に責任を負わせれば足りるという発想だった」と指摘。「まずは製造物責任を販売業者に拡張した上で、その枠組みにDPF事業者を取り込んでいく必要がある」と話した。(村嶋和樹)
アマゾン・ジャパン(東京)の賠償責任認めず 中国製バッテリー発火、東京地裁
2022.4.15
通販大手「アマゾン・ジャパン」を通じて中国の業者から購入したバッテリーが発火し、自宅が火事になったとして、宇都宮市の会社員加藤尚徳さん(35)がアマゾン・ジャパン(東京)に30万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は15日、請求を棄却した。加藤さんは控訴する方針。
判決によると、中国製の充電式モバイルバッテリーを購入。2017年11月、自宅が火事になり、消防の調査で、充電中のバッテリーが原因と判明した。
伊藤正晴裁判長は、加藤さんはサイトのフォームを利用して中国メーカーに連絡し、和解を成立させているとし「被告に審査義務違反があるとは認められない」と退けた。
巨大デジタルプラットフォームを相手取った"前代未聞"の訴訟がはじまる――。
2020年10月29日 15時25分
大手ネット通販サイト「アマゾン・ジャパン(東京)」(Amazon)のマーケットプレイスで購入した中国製のモバイルバッテリーが出火して、自宅が火事になったとして、栃木県宇都宮市の男性が2020年10月29日、アマゾン・ジャパン(東京都目黒区)を相手取り、損害賠償をもとめて東京地裁に提訴した。
●中国メーカー製造・販売のバッテリーが原因の火災発生
訴状などによると、原告の男性、加藤尚徳さんは2016年6月、アマゾン・ジャパンのマーケットプレイスで、中国メーカー製造・販売の充電式モバイルバッテリーを購入した。約1年5カ月後の2017年11月、自宅マンションで、火災が発生した。
弁護士ドットコムニュースの取材に加藤さんが当時を振り返る。
「モバイルバッテリーは容量が大きいので、一晩くらい充電する必要がありました。寝る前に充電していたところ、夜中3時に火災報知器が鳴って、びっくりして起きると、すでに燃え広がっていました。パンパンと、何かが爆発する音も聞こえました」(加藤さん)
加藤さんと家族はすぐに逃げ出したので、大事はなかったが、この火災によってリビングが半焼し、家財道具が焼けたり、煤けたりして、使い物にならなくなったほか、結婚式や子どもの写真、パソコンのデータなどもダメになったという。
その後、消防署の火災調査報告書で、出火は、モバイルバッテリーが発生源だったことがわかった。
●中国メーカーは誠実な対応をしてくれなかった
この火災による被害額は1000万円を超えたが、保険でまかなえたのは半分程度だった。
加藤さんはバッテリーの製造・販売会社(中国)と交渉したが、誠実な対応をしてもらえなかったという。しかも相手は中国メーカー。中国現地で訴訟することも検討したが、相当の時間・コストもかかるため、"訴訟経済的に見合わない"と断念した。
結局、2年かかって中国メーカー側から見舞金として約184万円を受けた。しかし、中国の弁護士費用などがかかり、加藤さんの手元に残ったのは、数十万円。アマゾン・ジャパンの対応にも納得いかなかったことから、今回の提訴に踏み切った。
加藤さんの訴状によると、アマゾン・ジャパンには、商品に瑕疵がないか、商品に問題が生じた場合にユーザーに適切な対応をとる事業者かについて、合理的な審査基準を設けて審査すべき義務や、保険・補償制度を構築する義務があったのにもかかわらず、果たしていないと主張している。
●「今後も一定の確率で起きうる」
アマゾン・ジャパン側のネット上の取引トラブルをめぐっては、消費者保護の観点からのルールがなく、消費者庁が現在、アマゾンなど大手ネット通販運営者に対して、出店する事業者を特定するための対策を講じることをもとめるなど、法整備の動きがあるにはあるようだ。
今回の訴訟はデジタルプラットフォームのあり方に一石を投じるものだ。
「おそらく今後も一定の確率で、こうした事故・火災は起きてくるだろうと思っています。現地で訴訟して損害賠償を得ることが難しいということがわかりました。今後こういうことが起きた場合、事実上、泣き寝入りしないといけなくなると思います。
提訴にあたって、難しいんじゃないか、負け筋だとか言われましたが、同じことが起きたとき、何ができて、何ができないかをはっきりさせておきたいと思います。たとえ敗訴しても、弱者を救済するための解決策(立法など)が必要だということがわかるからです」(加藤さん)
国民生活センターによると、ネット通販サイトを通じて商品を購入して、火災が発生したという相談が全国の消費生活センターに複数寄せられている。
・ネット通販で購入したスティックタイプの掃除機が充電中に爆発して、ドアが黒焦げになり、足に火傷をおった(2020年5月・50代男性)
・ネット通販で購入したスマートフォン用スピーカーを充電中、発火して火事になった。(2017年10月・属性なし)
・ネット通販で購入したLEDヘッドライトを充電中、爆発音とともに火が出て、リビングの天井が焼けた(2017年9月・属性なし)
加藤さんによると、アメリカのUSAアマゾン、海外では、同じような事故で「プラットフォーム側が責任を負うべき」という判決も出ているという。
●原告代理人「デジタルプラットフォームの義務を明らかにしたい」
加藤さんの代理人をつとめる山岡裕明弁護士は「裁判を通じてデジタルプラットフォーム企業の消費者に対する義務を明らかにしていきたい」と話している。
【シャレにならない】リスクを甘く見るとこんなことになる
2022/08/26
少し前のニュースです。
アマゾンで購入の中国製バッテリー出火 責任の所在は(産経新聞 THE SANKEI NEWS)
おそらく私たちが知らないだけで、日本のどこかで製品から発火したということは起きていると思います。
ですがそれが、中国輸入の商品となると、こういう事案はニュースになりやすい傾向にあります。
ぶっちゃけた話をすると、実際には軽い事故であっても大きく取り扱われることがあります。
言い様によっては「ヒヤリ・ハット」ということで、警鐘を鳴らすためにあえて扱っているのかもしれないですが…。
ニュースの内容については本文を確認いただきたいのですが、今回は先日のPL保険のコラムに絡む内容です。
こういう記事の場合、比較的アメリカの事例を伝えるケースが多いのですが、今回はAmazonジャパンでの出来事なので本当に「明日は我が身」と思って読み進めていってください。
販売側には常に責任がついてまわる
製品の事故が起きる原因はひとつではありません。
製造過程の場合もあれば使用環境や使い方にも起因することがあります。
ですので、事故が起きたら何でもかんでも販売者のせいというのはちょっと厳しいように思いますが、事故が起きた以上は売っている側が何らかの追及をされる恐れは常にあります。
これまでも、Amazonで売っている商品は何でも取り扱っていいわけではない、また売れているからという理由だけでよく調べもせず販売するのはNGということを常々書いてきました。
今でも売られている「ブラックじゃないけどグレーな商品」でも健康器具について取り上げましたし、それ以前にはバイク関連についても書いてきました。
そして、その最後にはちゃんとリスクを調べよう、実は大きなリスクがあるから売れているからと言って目先の利益に走ってはいけないとお伝えしましたが、いよいよその危険性が現実味を帯びてきている段階になったということですね。
消費者のほうも今の時代はインターネットでいろいろな情報を自分で集めて対応できる時代になりましたので、泣き寝入りなんかはしません。
事故が起きたら必ずと言っていいほど対応を迫られることでしょう。
(記事のように裁判になるかはまた別問題です)
事故が起きるとめちゃくちゃお金がかかる
「事故が起きる」→「対応を迫られる」→「場合によっては訴訟を起こされる」となりますが、このニュースでは訴訟を起こされていますね。
相当な事案だったことが伺えます。
訴訟となるとただ裁判所に出向くだけで話は終わりません。
訴訟に対応できるほど法律的な知識が豊富であれば別ですが、そんな人はほとんどいないので、訴訟を起こされると必然的に弁護士に訴訟の対応を依頼することになります。
テレビドラマでは「カッコいい弁護士が貧しい人のために立ち上がる!」なんていうシチュエーションもありますが、現実はそう甘くありません。
細かい話ですが着手金で数十万円、成功報酬で数十万円など、桁違いの多額の費用が発生します。
ちなみに裁判は勝ち負けを決めるだけではありません。
今回の記事にもありますが、この訴訟での結果は勝ったのではなく「和解」です。
つまり、裁判官に白黒付けてもらうのではなく、公平な場で双方の話し合いによって問題を解決したということです。
裁判ではとても時間がかかるので、今回のように和解で解決するケースも少なくありません。
ただし、あくまで訴訟を起こしたうえでの和解のため、賠償金は発生していると思われます。
なので、弁護士費用などを考えると、販売者側からはやはり相当の金額が出ていっているはずです。
販売者側からみると、訴訟になる前にもっと前の段階で止めていれば、言い方は悪いかもしれませんが、金銭的なものはもっと少なく済んだのかもしれません。
保険へ入っておけばいいんじゃない?
今回の訴訟はAmazon(アマゾン・ジャパン)を訴えたとなっています。
経緯的には、最初はメーカーに対応をしてもらおうとしたが、中国のメーカー(中国の出品者)で全然まともな対応をしてくれなかったため、プラットフォームであるAmazonを訴えた感じなのです。
ちなみにこのような事故で裁判になった場合、米国のアマゾンでは消費者側が勝訴する判決が相次いでいるようです。
出品者側からするとリスクがどんどんあがって来ているような状態ですね。
それで、出品者が私たちだった時のことを考えてみましょう。
今回の訴訟を起こした人も、中国のメーカーを訴えようとしたが弁護士費用などが高額だったので断念した、とあります。
違う見方をすれば、販売していたのが日本の業者であれば、そのまま問題なく訴えられたはずです。
つまり、我々だったら訴えられていた、ということになります。
弁護士費用云々はおいといて、こういう万が一の事故に備えて加入しておくのがPL保険です。
そういう意味で中国輸入ビジネスをおこなっている私たちがPL保険へ加入しておくのはリスクヘッジとしてはありです。
保険に入っているからといってリスクのある商品を売ってもいい理由にはなりませんし、保険といってもどんなものにでも対応できる万能なものではありません。
保険があるからといっていい加減なことをやっていていざ事故がおきて保険を使おうとしても、事故の経緯や状況次第で保険が下りないこともあるかもしれません。
そうなると全額負担になるので、もはや輸入とか仕入れどころではなくなります。
ですので、基本的に保険はあくまで「保険」なので使わないのが一番です。
最後に
中国製品は以前から品質について問題視されることも多く、「中国製・発火」などインパクトのあるイメージになるのでニュースとして扱われやすく広く知れ渡ることも考えられます。
以前にも中国製のモバイルバッテリーからの発火事故が相次いだため、モバイルバッテリーへのPSEが義務化された経緯がありました。
これも、本来は充電する、電気を使うものなのですが、規制がなくても売れることを理由に、粗悪でも、安全性を確認しなくても、儲かるからとにかく売ってしまえの精神でやってしまったのです。
その結果、けがを負う人、危ない思いをする人をたくさん生み出してしまいました。
今でいうとバイクプロテクターや壁紙や一部の健康器具がこれにあたります。
「売れている間だけ売って後は逃げよう」とか「自分には起きるはずがない」などと思っている人は、危ない橋を渡っていることに気付いてください。
ダイソン掃除機、中国製の「非純正バッテリー」で火災多発…使用していない状態でも発火する恐れ
「ROWA・JAPAN DC62」と表示されていた
2021/10/29
経済産業省は2021年10月29日、バッテリーパックからの出火が原因とみられる火災事故が多発していると発表した。英家電大手・ダイソンの掃除機に装着できる2種類のバッテリーパックで、使用していない状態でも発火する恐れがある。使用を中止するとともに、発火時に燃え広がらないよう、鍋や空き缶など金属製の容器に入れて保管するよう呼びかけている。
この2種類は非純正品(中国製品)で、「Orange Line DC60」「ROWA・JAPAN DC62」と表示されている。しかし中国製で、昨年11月から輸入販売されていた。国内では計1万5136個が売れ、9件の発火が確認されているという。
【メルカリガイド】メルカリで起きるよくあることは、取引をキャンセルしたい、と思ったこと。
取引をキャンセルしたい、とは誰もが侵すミステイクだ。購入者側が慌てて「取引ボタン」を押したら、すぐ取引画面になるので危険極まりない。
この時点でキャンセルができるかというと、「キャンセル画面」には行けないようになっている。
取引の時に「コンビニ決済」を選べば、コンビニで入金せずに取引終了まで3,4日待てば自然に取引終了にはなるが、悪質行為とみなされてしまうので、これは避けた方が良い。相手側にも自分にも一番いいのは、早めにキャンセル願を理由を述べて、謝罪の言葉を述べて、相手から、「取引終了」してもらうのが良い。「取引がキャンセルされました」の表示画面が現れるので、今度は、キャンセル画面には行けるようになり、購入者側が「同意する」を押せば、キャンセルできたことになる。
このように、行かないこともあるので・・・何とも言えない・・・
巨大デジタルプラットフォームを相手取った"前代未聞"の訴訟がはじまる――。
2020年10月29日 15時25分
大手ネット通販サイト「アマゾン」(Amazon)のマーケットプレイスで購入した中国製のモバイルバッテリーが出火して、自宅が火事になったとして、栃木県宇都宮市の男性が2020年10月29日、アマゾン・ジャパン(東京都目黒区)を相手取り、損害賠償をもとめて東京地裁に提訴した。
●中国メーカー製造・販売のバッテリーが原因の火災発生
訴状などによると、原告の男性、加藤尚徳さんは2016年6月、アマゾンのマーケットプレイスで、中国メーカー製造・販売の充電式モバイルバッテリーを購入した。約1年5カ月後の2017年11月、自宅マンションで、火災が発生した。
弁護士ドットコムニュースの取材に加藤さんが当時を振り返る。
「モバイルバッテリーは容量が大きいので、一晩くらい充電する必要がありました。寝る前に充電していたところ、夜中3時に火災報知器が鳴って、びっくりして起きると、すでに燃え広がっていました。パンパンと、何かが爆発する音も聞こえました」(加藤さん)
加藤さんと家族はすぐに逃げ出したので、大事はなかったが、この火災によってリビングが半焼し、家財道具が焼けたり、煤けたりして、使い物にならなくなったほか、結婚式や子どもの写真、パソコンのデータなどもダメになったという。
その後、消防署の火災調査報告書で、出火は、モバイルバッテリーが発生源だったことがわかった。
●中国メーカーは誠実な対応をしてくれなかった
この火災による被害額は1000万円を超えたが、保険でまかなえたのは半分程度だった。
加藤さんはバッテリーの製造・販売会社と交渉したが、誠実な対応をしてもらえなかったという。しかも相手は中国メーカー。現地で訴訟することも検討したが、相当の時間・コストもかかるため、"訴訟経済的に見合わない"と断念した。
結局、2年かかってメーカー側から見舞金として約184万円を受けた。しかし、中国の弁護士費用などがかかり、加藤さんの手元に残ったのは、数十万円。アマゾンの対応にも納得いかなかったことから、今回の提訴に踏み切った。
訴状によると、アマゾンには、商品に瑕疵がないか、商品に問題が生じた場合にユーザーに適切な対応をとる事業者かについて、合理的な審査基準を設けて審査すべき義務や、保険・補償制度を構築する義務があったのにもかかわらず、果たしていないと主張している。
●「今後も一定の確率で起きうる」
ネット上の取引トラブルをめぐっては、消費者保護の観点からのルールがなく、消費者庁が現在、アマゾンなど大手ネット通販運営者に対して、出店する事業者を特定するための対策を講じることをもとめるなど、法整備の動きがある。
今回の訴訟はデジタルプラットフォームのあり方に一石を投じるものだ。
「おそらく今後も一定の確率で、こうした事故・火災は起きてくるだろうと思っています。現地で訴訟して損害賠償を得ることが難しいということがわかりました。今後こういうことが起きた場合、事実上、泣き寝入りしないといけなくなると思います。
提訴にあたって、難しいんじゃないか、負け筋だとか言われましたが、同じことが起きたとき、何ができて、何ができないかをはっきりさせておきたいと思います。たとえ敗訴しても、弱者を救済するための解決策(立法など)が必要だということがわかるからです」(加藤さん)
国民生活センターによると、ネット通販サイトを通じて商品を購入して、火災が発生したという相談が全国の消費生活センターに複数寄せられている。
・ネット通販で購入したスティックタイプの掃除機が充電中に爆発して、ドアが黒焦げになり、足に火傷をおった(2020年5月・50代男性)
・ネット通販で購入したスマートフォン用スピーカーを充電中、発火して火事になった。(2017年10月・属性なし)
・ネット通販で購入したLEDヘッドライトを充電中、爆発音とともに火が出て、リビングの天井が焼けた(2017年9月・属性なし)
加藤さんによると、海外では、同じような事故で「プラットフォーム側が責任を負うべき」という判決も出ているという。
●原告代理人「デジタルプラットフォームの義務を明らかにしたい」
加藤さんの代理人をつとめる山岡裕明弁護士は「裁判を通じてデジタルプラットフォーム企業の消費者に対する義務を明らかにしていきたい」と話している。
【シャレにならない】リスクを甘く見るとこんなことになる
2022/08/26
少し前のニュースです。
アマゾンで購入の中国製バッテリー出火 責任の所在は(産経新聞 THE SANKEI NEWS)
おそらく私たちが知らないだけで、日本のどこかで製品から発火したということは起きていると思います。
ですがそれが、中国輸入の商品となると、こういう事案はニュースになりやすい傾向にあります。
ぶっちゃけた話をすると、実際には軽い事故であっても大きく取り扱われることがあります。
言い様によっては「ヒヤリ・ハット」ということで、警鐘を鳴らすためにあえて扱っているのかもしれないですが…。
ニュースの内容については本文を確認いただきたいのですが、今回は先日のPL保険のコラムに絡む内容です。
こういう記事の場合、比較的アメリカの事例を伝えるケースが多いのですが、今回はAmazonジャパンでの出来事なので本当に「明日は我が身」と思って読み進めていってください。
販売側には常に責任がついてまわる
製品の事故が起きる原因はひとつではありません。
製造過程の場合もあれば使用環境や使い方にも起因することがあります。
ですので、事故が起きたら何でもかんでも販売者のせいというのはちょっと厳しいように思いますが、事故が起きた以上は売っている側が何らかの追及をされる恐れは常にあります。
これまでも、Amazonで売っている商品は何でも取り扱っていいわけではない、また売れているからという理由だけでよく調べもせず販売するのはNGということを常々書いてきました。
今でも売られている「ブラックじゃないけどグレーな商品」でも健康器具について取り上げましたし、それ以前にはバイク関連についても書いてきました。
そして、その最後にはちゃんとリスクを調べよう、実は大きなリスクがあるから売れているからと言って目先の利益に走ってはいけないとお伝えしましたが、いよいよその危険性が現実味を帯びてきている段階になったということですね。
消費者のほうも今の時代はインターネットでいろいろな情報を自分で集めて対応できる時代になりましたので、泣き寝入りなんかはしません。
事故が起きたら必ずと言っていいほど対応を迫られることでしょう。
(記事のように裁判になるかはまた別問題です)
事故が起きるとめちゃくちゃお金がかかる
「事故が起きる」→「対応を迫られる」→「場合によっては訴訟を起こされる」となりますが、このニュースでは訴訟を起こされていますね。
相当な事案だったことが伺えます。
訴訟となるとただ裁判所に出向くだけで話は終わりません。
訴訟に対応できるほど法律的な知識が豊富であれば別ですが、そんな人はほとんどいないので、訴訟を起こされると必然的に弁護士に訴訟の対応を依頼することになります。
テレビドラマでは「カッコいい弁護士が貧しい人のために立ち上がる!」なんていうシチュエーションもありますが、現実はそう甘くありません。
細かい話ですが着手金で数十万円、成功報酬で数十万円など、桁違いの多額の費用が発生します。
ちなみに裁判は勝ち負けを決めるだけではありません。
今回の記事にもありますが、この訴訟での結果は勝ったのではなく「和解」です。
つまり、裁判官に白黒付けてもらうのではなく、公平な場で双方の話し合いによって問題を解決したということです。
裁判ではとても時間がかかるので、今回のように和解で解決するケースも少なくありません。
ただし、あくまで訴訟を起こしたうえでの和解のため、賠償金は発生していると思われます。
なので、弁護士費用などを考えると、販売者側からはやはり相当の金額が出ていっているはずです。
販売者側からみると、訴訟になる前にもっと前の段階で止めていれば、言い方は悪いかもしれませんが、金銭的なものはもっと少なく済んだのかもしれません。
保険へ入っておけばいいんじゃない?
今回の訴訟はAmazonを訴えたとなっています。
経緯的には、最初はメーカーに対応をしてもらおうとしたが、中国のメーカー(中国の出品者)で全然まともな対応をしてくれなかったため、プラットフォームであるAmazonを訴えた感じなのです。
ちなみにこのような事故で裁判になった場合、米国では消費者側が勝訴する判決が相次いでいるようです。
出品者側からするとリスクがどんどんあがって来ているような状態ですね。
それで、出品者が私たちだった時のことを考えてみましょう。
今回の訴訟を起こした人も、中国のメーカーを訴えようとしたが弁護士費用などが高額だったので断念した、とあります。
違う見方をすれば、販売していたのが日本の業者であれば、そのまま問題なく訴えられたはずです。
つまり、我々だったら訴えられていた、ということになります。
弁護士費用云々はおいといて、こういう万が一の事故に備えて加入しておくのがPL保険です。
そういう意味で中国輸入ビジネスをおこなっている私たちがPL保険へ加入しておくのはリスクヘッジとしてはありです。
保険に入っているからといってリスクのある商品を売ってもいい理由にはなりませんし、保険といってもどんなものにでも対応できる万能なものではありません。
保険があるからといっていい加減なことをやっていていざ事故がおきて保険を使おうとしても、事故の経緯や状況次第で保険が下りないこともあるかもしれません。
そうなると全額負担になるので、もはや輸入とか仕入れどころではなくなります。
ですので、基本的に保険はあくまで「保険」なので使わないのが一番です。
最後に
中国製品は以前から品質について問題視されることも多く、「中国製・発火」などインパクトのあるイメージになるのでニュースとして扱われやすく広く知れ渡ることも考えられます。
以前にも中国製のモバイルバッテリーからの発火事故が相次いだため、モバイルバッテリーへのPSEが義務化された経緯がありました。
これも、本来は充電する、電気を使うものなのですが、規制がなくても売れることを理由に、粗悪でも、安全性を確認しなくても、儲かるからとにかく売ってしまえの精神でやってしまったのです。
その結果、けがを負う人、危ない思いをする人をたくさん生み出してしまいました。
今でいうとバイクプロテクターや壁紙や一部の健康器具がこれにあたります。
「売れている間だけ売って後は逃げよう」とか「自分には起きるはずがない」などと思っている人は、危ない橋を渡っていることに気付いてください。
ダイソン掃除機、中国製の「非純正バッテリー」で火災多発…使用していない状態でも発火する恐れ
2021/10/29
経済産業省は29日、バッテリーパックからの出火が原因とみられる火災事故が多発していると発表した。英家電大手・ダイソンの掃除機に装着できる2種類のバッテリーパックで、使用していない状態でも発火する恐れがある。使用を中止するとともに、発火時に燃え広がらないよう、鍋や空き缶など金属製の容器に入れて保管するよう呼びかけている。
この2種類は非純正で、「Orange Line DC60」「ROWA・JAPAN DC62」と表示されている。中国製で、昨年11月から輸入販売されていた。国内では計1万5136個が売れ、9件の発火が確認されているという。
炎上事故多発!日本に上陸した「中国製電気自動車」に募る不安
3/21(火) 9:00配信
今年1月31日に日本で販売を始めた中国の大手電気自動車(EV)メーカー・BYD(比亜迪)の周辺がにわかに騒がしくなっている。日本に納品実績のあるEVバスに六価クロムを含有した溶剤が使用されていることが発覚したのだ。自動車業界関係者が言う。
今年1月31日に日本で販売を始めた中国の大手電気自動車(EV)メーカー・BYD(比亜迪)の周辺がにわかに騒がしくなっている。日本に納品実績のあるEVバスに六価クロムを含有した溶剤が使用されていることが発覚したのだ。自動車業界関係者が言う。
【写真】中国でまたもトンデモ事件!バーのトイレの鏡が「マジックミラー」だった…?
「ボルトやナットなどに使用される六価クロムは、金属表面の腐食を防ぐ特性がある一方で人体には有毒。欧州では使用が禁止されています。日本では法的な規制はないですが、日本自動車工業会(自工会)が自主規制を呼びかけています」
BYDの安全性に対する懸念は、これだけではない。中国でバッテリーが自然発火して火災を起こす事故が多発しているのだ。台湾メディア『T客邦』が2022年9月6日に報じたところによると、4ヵ月の間に実に13台もの火災事故が発生しているという。特に昨年6月には、6日に湖北省武漢市、広東省佛山市、 広西チワン族自治区貴港市で相次いでバッテリーが発火する事故が発生。12日には広東省珠海市で停車中のEVが炎上している。
BYDは電池生産が祖業であり、バッテリー開発には特に力を入れている。2020年には次世代型「ブレードバッテリー」を発表。前出のメディアによると、「EVの辞書から自然発火を抹消する」と自信を持って市場に送り出したが、同バッテリーを積んだ車も発火しており、残念ながら事故はなくなっていない。
もっとも、発火事故が起きているのはBYDだけでない。1月29日には、山東省済南市で新興EVメーカー・理想汽車のワゴン車が発火。2月4日には、中国の大手自動車メーカー・奇瑞汽車の小型EVが充電中に炎上している。同車種は昨年も充電中に発火する事故が2件、起きているという。
中国の災害管理や応急救援を管轄する省庁・中国応急管理部によると、2022年第1四半期にEVの火災事故が640件起きており、前年の同じ時期より32%も増加している。1日平均7件の事故が起きている計算だ。
BYDは中国最大手であるため、どうしても他のメーカーよりも事故が目立つが、日本で販売されている車種に問題はないのだろうか。日本法人・ビーワイディージャパン(BYDジャパン)に問い合わせると、以下のように回答があった。
「中国国内での事故の原因については、外部の第三者機関で調査が実施されておりますが、個別の事象については、現時点で日本法人ではご回答しかねます。万が一、日本においてそうした事態が起きた場合には、早急な事実確認と原因究明を行い、お客様の信頼に足る対応を進めてまいります」
日本で同様の事故が起きないことを祈りたい。
取材・文:roadsiders 路邊社
中国製リチウム電池が信頼できない理由
車載用電池に対する自動車各社の異なる見方
日経ビジネス
2018.9.27
2018年9月13日のコラムでは、「爆走中国EV、電池業界に起きている異変」を執筆した。これまで報道されてきた中国でのEVシフトや、そこに連結する電池業界の勢いが以前ほどないこと、それどころか経営危機に陥る企業も出てきていること、そしてその背景にあるものなどについて考察した。
変化が起きている最大の要因は、中国政府が打ち出してきたエコカーへの補助金を減額していることによるものだ。補助金は2020年には消滅する予定になっている。となれば、事態は一層深刻化すると思われるが、中国政府の面子もかかっているこの状況の中で、新たな政策がどのように出てくるのかが着目される。
中国製電池の信頼性は大丈夫か?
米紙「ウォール・ストリート・ジャーナル」の報道を、中国メディアの「OFweek」が2018年9月14日付で伝えた。それは、米ゼネラルモーターズ(GM)が2019年に市場投入を予定しているビュイックブランドのEV「ヴェリテ6(Velite 6)」に関するもの。適用している電池メーカーのリチウムイオン電池(LIB)の性能が要求に届かないこと、更には安全基準にも適合しないため、発売を遅らす可能性が高いというニュースである。
報道によると、ヴェリテ6にLIBを供給するのは中国Wanxiang Group(万向集団)傘下のA123システムズである。浙江省杭州の工場でヴェリテ6に搭載するEV用電池を生産している。ヴェリテ6にはプラグインハイブリッド車(PHV)もあるが、こちらは近く生産に入るとのことだ。
OFweekによると、GMは当初、韓国LG化学製のLIBを採用する計画であった。しかし中国政府が定めた16年の規定、それは「バッテリー模範基準認証(通称、ホワイトリスト)」を取得していない企業のバッテリーを搭載するクルマは中国国内での補助金を認められないというものだが、日韓勢のLIBは認定されることはなかった。すなわち、LG化学製LIBを搭載したエコカーには補助金が付かないということを意味し、LG化学のビジネスモデルが崩れたのである。代わりに、GMは補助金を受けられるA123システムズ製のLIBの採用を決めたという経緯である。
このような影響はほかでも起きている。独フォルクスワーゲン(VW)も中国市場でLG化学のLIB適用を検討していた。しかし、このホワイトリストの影響により、VWはLG化学から中国CATL製のLIBに転換しているようだ。独BMWは、2013年に投入したEV「i3」、およびPHV「i8」にはじまって、すべてのEV、PHVに韓国サムスンSDIのLIBを調達してきた。そのBMWも中国市場でのビジネスモデルを勘案し、新たにCATLとの契約を取り交わしている。
A123システムズのLIBがどの部分でGMの要求性能に満たないのか、そして安全基準を満足しないのか、その詳細は明らかではない。A123システムズは、元はと言えば米国で育ったベンチャー電池企業である。米国カリフォルニア州で1990年9月に発効したゼロエミッション車(ZEV)法規に適合させるべき、1991年には米国先進電池研究組合(USABC)が設立された。以降、米国では電池研究から事業化を目指す電池ベンチャー企業が乱立した。A123システムズもその一つであり、米国生まれの企業である。
同社はマサチューセッツ州ウォルサム市にて2001年に創業した。米マサチューセッツ工科大学(MIT)で開発が進められていたオリビン型リン酸鉄リチウム(LiFePO4)をLIBの正極材料に適用したEV用電池の事業化を進めていた。A123システムズのEV用LIBの開発は、ブッシュ大統領が推進していた水素エネルギー政策に打って変わって、2008年に就任したオバマ大統領がグリーン・ニューディール政策を打ち出したことで、米エネルギー省から2億4900万ドルの助成金を獲得するに至った。ミシガン州の生産工場を基盤として、その後は中国にも工場を進出させた。
潤沢な開発資金を手にした同社は、米国を中心に自動車メーカー各社と契約を結び供給を開始した。しかし、A123システムズ製のLIBを搭載した米フィスカー・オートモーティブの高級PHV「フィスカー・カルマ」が、2011~12年にかけて炎上や爆発事故を起こした。原因はLIBの品質にあるとされ、PHVはリコールの対象となった。
A123システムズには5500万ドルものリコール費用が発生しただけでなく、製品の評価が奈落の底に落ちてしまった。その後も、LIBの供給商談が破談になるなど致命的な打撃を受けた。同時に、中国企業の万向集団がA123システムズを2億5600万ドルで買収した。米国政府が税金を投じて育成したはずの米国ベンチャーは国籍を中国に変える形となり、米国籍を失った。この一連の煽りを受けて、13年11月には、フィスカー・オートモーティブも経営破綻に陥ってしまった。
安全に対する開発基準と意識が異なる日本勢
歴史をヒモ解けば、LIBが車載用、特にEV用に適用されたのは、2009年に三菱自動車が発売した「i-MiEV」、そして翌10年に日産自動車が発売した「リーフ」に遡る。10年からは中国ローカルメーカーも、タクシーやバスなどに適用し始めた。しかし、そこからEVの火災事故が多発した。BYDのEVバスもご他聞に漏れない。
米テスラのEVである「モデルS」は、13年に米国市場で立て続けに5台の火災事故を起こしている。16年にはフランスの試乗会で火災事故を起こし、その他、ノルウェーやスウェーデン、そして中国市場でも火災事故を起こした。
一方、日系勢のEVはこれまで、火災事故を1件も発生させていない。日産のリーフは累積販売台数が35万台を超えている。火災無事故は誇るべき実績である。BMWのi3も、そして販売台数規模は小さいものの12年に発売したトヨタ自動車のEVである「eQ」、同様にホンダの「FIT EV」も火災事故とは無縁である。
ではなぜ、このような差が生じるのか? それには筆者の持論がある。筆者がホンダ時代に車載電池の研究開発に直接携わり、自動車メーカーの視点で取り組んできた経験、更に、サムスンSDIではLIB開発から事業に至る供給側の立場で取り組んできた経験から以下のように考える。
電動車開発における重要コンポーネントとしては、モーター、電池、インバーターなどが代表として挙げられるが、何といっても火災事故の誘因となるものは電池である。とすると、自動車側の立場では車載電池をいかに安全で信頼性の高いものに設計・開発するかという視点が極めて重要となる。
LIBでは充電放電に伴う発熱は適用する正極材料によっても異なる。また、充放電時の正極の結晶構造の変化度合いも材料によって異なる。逆にいえば、様々なLIBを設計できることにもなるが、安全性と信頼性の確立は殊更重要だ。電池が暴走しないような充放電制御機構や冷却システムも不可欠である。
制御系が万が一、故障してもLIBの火災や爆発を起こさない設計・開発が基本的に必要だ。そのためには、開発品のLIBが過酷な条件においてどうなるかという、いわゆる限界試験による確認が大切である。1991年から着手したホンダでの電池研究開発においても、当初から独自の限界試験を相当盛り込んだのである。
2004年9月にサムスンSDIに移籍してからは技術経営に臨んだ。その折に、世界の自動車各社を訪問した。そして、同社を退社する12年末までに多くの協議を重ねてきた。ホンダ時代にはできなかった自動車各社への訪問は確かに新鮮であった。なぜならば、自動車各社が車載用電池に対してどれだけの意識をもって開発にあたっているか、そしてその試験法や基準がどういうものかを直接知ることができたからである。もちろん、国内の古巣であるホンダやトヨタ自動車、日産自動車、三菱自動車、マツダ、スズキ、スバル、日野自動車などとも、かなりの協議や意見交換をしてきた。
そこで実感したのは、欧米自動車各社と日系勢自動車各社のLIBに対する安全性確保のための開発指針が異なっていたことである。日系勢の多くは、自社独自の評価法と独自基準を持ち、かつ限界試験を適用していることに特異性がある。
一方、欧米勢は自社独自の評価法と独自基準は持っているものの、日系勢のそれよりも一段低い所に位置していた。そして、限界試験なるものはほとんど行われていなかった。したがって共同開発する、あるいは供給する電池各社も自動車各社の基準に合わせることで良かったのである。
ここで言う欧米勢はGM、米フォード、独フォルクスワーゲン(VW)などで、先のベンチャーは含まない。フィスカー・オートモーティブやテスラのEVで火災が多発したのも、結局は車載用LIBの安全性評価や基準が既存の欧米勢に比べても、更に低かったからだろうと類推される。
事実、サムスンSDI時代に若手エンジニアを引率して日系自動車各社を訪問し協議をしている過程で、自動車各社から高い基準や限界試験を主張されると、彼らは「なぜそこまで必要なのか?」と疑問を抱くことになった。立場上、同席していた筆者が彼らに説明して納得させる場面も少なからずあった。取りも直さず、欧米勢の自動車各社と主に付き合ってきた彼らだから、その基準に慣れきっていたのである。
そういう欧米勢も、ここ3年ほど前から安全性開発姿勢に変化が見られる。日系勢をベンチマークしてのことだろうが、基準を上げながら、そして限界試験も積極的に取り入れるなど、安全性に関する意識が高まってきた。だからこそ、冒頭に紹介したGMがA123システムズのLIBの性能品質や安全性に不満を持つようになり、開発遅延が生じているのだろう。
中国の車載用LIB規格が変わった
他方、中国の電池メーカーは、これまでローカルの自動車メーカーとの協業を中心に進めてきた。ローカルの自動車各社の信頼性はエンジン車でも元々低かったのに対し、EVでは新規参入組が多く現れ、入念な開発を行って信頼性を高いものに築き上げるマインドは不足している。短期間に開発して市場に投入することが優先されるがゆえに、事故に至る現象が今も続いている。BYDのLIBをBYDのEVバスに供給しているビジネスモデルでも例外ではない。
電池各社がそういうローカル系自動車各社のみとビジネスをしている限り、その基準内で今後も開発を進め続けるだろう。ここに来て、中国No.1とNo.2の電池メーカーであるCATLとBYDは今後、ローカル以外の日欧米グローバル自動車各社とのビジネスを開始する。新たなビジネスモデルで懸念されるのは、知財と安全性・信頼性の問題だ。逆に、この協業連携によって両社は先進自動車各社の洗礼を受ける可能性が高い。
中国市場で車載用LIBの安全性を担保するために、GB規格が適用されている。GB/T 31485-2015で「電動自動車用動力バッテリーの安全要件および試験方法」、GB/T 31486-2015で「電動自動車用動力バッテリーの電気的性能要件および試験方法」が課せられている。
この規格は当初、中国自動車技術研究センター(CATARC)が検討、立案していた。ところがここ数年、CATLが勢いを付けてきたことで、CATARCに代わってCATLが試験法の制定や基準を設定し、CATARCは試験を実施する側にと役割を分担している。この役割見直しによって変わったことがある。LIBのGB規格試験法から「釘刺し試験」を除外した。その理由は、「EVでの事故が発生しても釘を刺したような現象は起こらない」という理屈からであった。もっとも、中国電池業界の開発負荷を低減させる狙いもあったようだ。それだけでなく、この試験を適用すればパスしない中国製LIBが少なからずあるからだろう。
車載用電池に対する自動車各社の異なる見方
車載用国連規則で認証が義務付けられるECE R-100.02 Part.IIの9項目の試験法にも釘刺し試験は含まれていない。上述したように、GB規格には当初含まれていたが、後に除外された。しかし、日系自動車各社や電池各社の大半は自主的に釘刺し試験を実施する。さらに、各社独自の試験法や基準、限界試験を導入し開発にあたっている。国連規則や中国GB規格はクリアして当然の義務教育であるので、これに甘んじているだけではグローバルビジネスとしては不十分である。
日系勢が進めている各社の自主的な、そしてより厳しい試験法と基準、それに限界試験を付加する高等教育をクリアすることで、安全性と信頼性が一段と高い次元で実現する。
以下の図は、エスペックが運営している宇都宮事業所の「バッテリー安全認証センター」の機能と国連規則を挙げたものである。国連規則やGB規格をワンストップで提供できる機能を有している。試験項目によっては、中々クリアできないLIBもある。それを短期間で効率的に改善開発するために、自動車業界や電池業界に貢献するビジネスモデルを提供している。それのみならず、各社の高等教育をクリアするためのオーダー試験についても随時対応できる機能も有している。
佐藤 登
電動工具の互換バッテリー事故が急に増えた理由【コラム】
なぜ2018年から互換バッテリー発火事故が急増したのか
ここ最近、互換バッテリーによる発火事故による危険性やネット販売のトラブルが大きく取り沙汰され、互換バッテリーは危険な製品として広く認知されるようになりました。
ここ最近の事故例から「互換バッテリーは危険!」のような共通認識が広まるのは喜ばしい限りですが、実は、電動工具の互換バッテリーはリチウムイオンバッテリー対応の電動工具の展開が始まってから長らく販売が続いている社外アクセサリー製品の一つです。
危険性の高い製品が古くから販売されているのであれば、もっと以前からその危険性について話題になっていても良いと思いますが、その危険性が認知されるようになったのはこの数年の間です。
なぜ、この数年の間に互換バッテリーの危険性が認知されるようになったのでしょうか。
ここで1つ興味深いデータがあります。互換バッテリーの製品事故のデータは、製品評価技術基盤機構(以下nite)が年度別の事故発生件数を公開しています。
これは非純正のリチウムイオンバッテリーの年度別の発生件数をまとめた資料です。2017年以前は電動工具用の互換バッテリーを起因とする製品事故はほとんど発生しておらず、2018年以降から急増していることがわかります。
2019年は非純正バッテリー全体の製品事故が多発しているようにも見えますが、2019年の充電式電気掃除機の製品事故は「SHENZHEN OLLOP TECHNOLOGY社製バッテリーパック」による特定メーカーの事故が多発した年で、一過的なものと考えられます。
スマホ・LEDヘッドライト・ノートパソコンの非純正バッテリーは概ね横ばいであり、増加傾向にあるのは充電式電動工具用バッテリーだけです。
本記事では、なぜ2018年以降電動工具の互換バッテリーだけ事故が増えてしまったのかを考察します。
2018年以降の事故多発の背景にあるのは超急速充電器か
2018年以降の電動工具互換バッテリーが多発した要因として12A充電の超急速充電器の登場が深く関係していると推測しています。
現在の電動工具用充電器は12Aで充電を行う超急速充電仕様です。12Aの超急速充電器は2015年に日立工機がUC18YDLの発売を開始し、追って2018年にマキタもDC18RFを発売しました。
以前、当サイトで検証した通り、電動工具用互換バッテリーの多くが急速充電に対応できない低充電レートのリチウムイオンバッテリーセルを採用しています。
低レートのリチウムイオンバッテリーに対して大電流充電を行うと、リチウムデンドライトと呼ばれる金属析出現象が発生し、セル内部の劣化が著しく進行して性能低下や発火の原因に繋がります。
筆者は低充電レートの安いバッテリーセルで最大9Aの充電を行ってもギリギリ発火せずに踏ん張れていた互換バッテリーも、より大きな電流で充電を行うDC18RFの登場によって発火リスクが増大してしまったのではないか?と考えています。
マキタバッテリー互換の保護基板について
事故多発のもう一つの要因になったと考えられるのが、マキタ互換バッテリーに搭載されている保護基板です。
実は、マキタのリチウムイオンバッテリーは、初期の基板と現在の基板で回路構造が大きく異なります
2005年に登場した初期のマキタリチウムイオンバッテリーは現在の保護基板よりも簡素な仕様で、単セル毎の電圧個別監視や出力遮断保護などの保護機能を搭載していませんでした。
マキタ互換バッテリーのほとんどがマキタ初期型バッテリーのコピー基板を搭載しています。
この互換保護基板は過電流保護や高負荷時の遮断機能が非搭載で、バッテリーが異常な状態になってもそれを検知して止める機能がありません。
超急速充電器は日本以外でほとんど売られていない
少し話は逸れて海外の話題になりますが、海外市場では互換バッテリーの発火事故の報告は多くありません。
DIYフォーラムの互換バッテリーの話題では「価格が安い値段相応のバッテリー」と評価されており、互換バッテリーの危険性については日本ほど話題になっていないようです。
訴訟大国と揶揄される米国でバッテリー発火の製品事故が大きな社会問題にならないのも不思議です。筆者はこれも超急速充電器が関連していると推測しています。
実は、先程取り上げたマキタ超急速充電器 DC18RFは日本市場向けの製品で、米国をはじめとするほとんどの海外市場は超急速充電器の取り扱いがありません。
米国マキタで主に販売されている充電器は一世代前のDC18RCや2口充電器のDC18RDです。これにより2017年以前の日本の状況と同じく、発火事故はあまり発生していないと考えられます。
これに関してはHiKOKIも同様で、海外市場では旧モデル充電器のUC18YSL3を主力充電器として販売しています。
社外品のリスクが浮き彫りになった互換バッテリー発火
ここまでまとめると、2018年以降、電動工具用の互換バッテリーの発火事故が多発した理由は、以下の3点が要因と推測されます。
低レートセルの採用
大電流充電を許容できない
マキタ初期バッテリーのコピー基板
各セルの電圧検出機能が無く、過放電・過充電に対する保護遮断機能もない
超急速充電器DC18RFの普及(2018年以降)
低レートセルは大電流充電によって異常を起こしやすくなる
根本的な原因は、電動工具に適さない低レートセルの採用です。低容量・低レート・低価格バッテリーセルを採用しているため、電動工具に対しての使用は発火事故リスクが増大します。
その互換バッテリーに搭載しているのが、マキタ初期のバッテリー基板をコピーした保護基板です。古い基板をコピーした保護回路を流用しているため、大電流充電の制御や過充電保護に対する保護が不十分であり、リチウムイオンバッテリーの十分な安全性が確保できていません。
そして、2018年に最大12A充電の超急速充電器 DC18RFが登場したことによって、発火にまでは至らなかった互換バッテリーの最後の一線を完全に超えてしまい、発火事故の多発に至ってしまったと推測しています。
さらに、マキタ製品のユーザー層の広さも互換バッテリーの事故多発に拍車をかけています。
マキタの充電式工具はクリーナーやライト、園芸機器などの電動工具に縁の無かったライトユーザー向けの製品を数多く展開しており、プロユーザーのみならず一般家庭ユーザーまでもがマキタ製品を使用しています。
実店舗で工具を購入するプロユーザーと異なり、家電中心のユーザーはECサイト販売の製品への抵抗が薄く、マキタ純正品の横に並ぶ低価格の互換バッテリーを見て、そちらに多く流れてしまうユーザーも多かったのでしょう。
製品事故が報告されている電動工具互換バッテリーの大多数がマキタ互換品を占める(画像クリックで拡大)
画像引用:令和元年度事故情報収集結果(R01年度第2四半期)
互換バッテリーのリスクは使い方で減らせるものの
本記事は「充電電流の増加」と「充電器の変更による影響」を焦点に考察していますが、低速充電器を使うことによってバッテリー発火を確実に防げると断定するものではありません。
発火事故のリスクについてはある程度減らせるとは予想していますが、互換バッテリーが搭載するセルの問題や保護回路の問題はリスクとして内包されており、どの充電器を使用しても根本的なリスクの有無は変わりません。
近年はマキタユーザー増加によってマキタ互換バッテリーの市場規模も大きくなり、得体の知れない互換バッテリー製造業者が多く参入しているのも事実です。niteでは保護回路が無い互換バッテリーの存在も報告しており、ユーザー側で安全な互換バッテリーを見つけるのはほぼ不可能に等しいでしょう。
製造物責任法においても、企業責任の所在が曖昧な方法で販売されている互換バッテリーも多いので、万が一の安全性や実際の製品事故のリスクを考えると純正バッテリーの使用を推奨します。
その互換バッテリー本当にPSEに適合してる?一目でわかるPSEマークチェック
2021年2月10日、電動工具用の互換バッテリーで初の事業者による製品回収(以下リコール)が通達されました。
互換バッテリーの製品事故が多発し始めた2019年以降、互換バッテリーは事故が多発する製品ながらも、実際に事故に遭遇したユーザーの大半は泣き寝入りの状態が続いていましたが、今回、発火事故から事業者によるリコールが実施されることになり、本案件を通じて互換バッテリーの全体的な品質の向上が波及されることに期待されます。
さて、本記事では、今まで見過ごされてきた互換バッテリーの事故が今回の互換バッテリーの製品事故でなぜリコールが行われる事態になったのか電気用品安全法の運用方法を元に解説します。
PSEが正しく運用されていれば保証やリコールがある
2021年現在、販売されるバッテリー製品には電気用品安全法に基づいたPSEマークの表示が義務付けられています。
電気用品安全法では、電気法品安全法の基準を満たした製品に対してはPSEマークを表示するだけではなく、PSEマークに近接した位置に届出事業者または登録商標を表示することを求めています。
仮に製品事故が発生した場合でも、PSEマークの情報から製造・輸入事業者を特定することができ、事故原因の調査や事故にあったユーザーへの賠償・製品回収などを行う義務が発生します。
ただし、互換バッテリーなどのバッテリー機器は、自己申告によって表示することが出来るので、正しくPSEを運用できていない事業者も存在します。
早い話、そのPSEマークが正しく運用されているかは、PSEマークの近くに事業者の記載があるかで判別できます。
PSEマークの表示があっても、事業者の記載がなければ、その製品を販売している業者は電気用品安全法を正しく運用されておらず、嘘のPSE表記を行っていることになります。
実際にPSEマーク表示されながら事業者の書かれていない互換バッテリーが存在するのかを確認してみました。
KingTianLe マキタ BL1860B互換バッテリー
今回、リコールが実施された中国KingTianLeブランドの互換バッテリーです。画像は経済産業省からの引用です。
裏側のラベルを確認すると、PSEマークの少し離れたところに「株式会社 泰成商事」の表記があます。今回のリコールはこの表記から輸入事業者である泰成商事に連絡が届き、製品回収の判断が下されたものと考えられます。
残念なことに同ブランドの他バリエーション互換バッテリーは、現在もオンラインショップ上で販売が継続されています。
マキタ 純正 BL4025 結果:〇
マキタ40Vmaxシリーズの純正バッテリー BL4025です。
裏側のラベル左下にPSEマークの表記があり、すぐ横に事業者名「株式会社マキタ」の表記があります。
日立工機 純正 BSL36A18 結果:〇
現HiKOKIのマルチボルトバッテリー BSL36A8です。
ラベル左上にPSEマークの表記があり、その横に事業者名「日立工機株式会社」の表記があります。
Rebuild Store マキタ BL1860B互換バッテリー 結果:〇
国内互換バッテリーブランドRebuild Storeの互換バッテリーです。2020年夏ごろAmazonで購入。
ラベル右上にPSEマークがあり、その下に小さく事業者名「(株)平林工機」が記載されています。
Enelife マキタ BL1830B互換バッテリー 結果:〇
国内互換バッテリーブランドEnelifeの互換バッテリーです。2020年秋ごろ千石電気で購入。
ラベル右下にPSEマークがあり、輸入事業者として「LXA Japan LLC」が記載されています。
Tenblutt HiKOKI BSL36A18互換バッテリー 結果:×
中国互換バッテリーブランドTenbluttの互換バッテリーです。手持ちの互換バッテリーの中では最も新しく、2020年秋ごろAmazonで購入しました
ラベル右下にPSEマークがありますが、マークの近くに輸入・製造事業者の記載がありません。このバッテリーはPSEマークの表示方法に違反しています。
Mrupoo マキタBL1860B互換バッテリー 結果:×
中国互換バッテリーブランドMrupoo の互換バッテリーです。2018年ごろ購入、PSEマーク表示義務化以前に購入したバッテリー機器です。
ラベル右上にPSEマークがありますが、輸入・製造事業者の記載がなく、このバッテリーはPSEマークの運用方法に違反しています。
結果、純正バッテリー・国内ブランド互換バッテリーはPSEが正しく運用されていることが確認できましたが、中国ブランドの互換バッテリーはPSEマークの表記方法が経済産業省の定める表示方式に適合していない製品もあり、電気用品安全法を満たしていない製品の存在が確認できました。
販売プラットフォーム側の言い逃れできない見逃し
経済産業省が定める電気用品安全法では「販売事業者は正しい表示が付けられていることを確認のうえ、販売しなくてはなりません。」とも指示しており、PSEマークとその事業者が記載されていない製品を販売した販売事業者は、法令違反として罰則する規則があります。
ショッピングサイトの安全・安心な取引環境を目指すオンラインマーケットプレイス協議会は、第7回会合上で「十分な判断根拠がない状態で、消費者被害防止への期待に応えることと、出店者・出品者に不当な不利益を与えないこととをどう両立させるかが課題である」との声明を発表しています。
しかし、電気用品安全法の定めるPSEマークの表記方法で十分な判断根拠がありながら、製造・輸入者の所在が不明確な製品の販売を続けているのは販売プラットフォーム側であり、声高なことを言いながら実際は電気用品安全法の定める法令を正しく遂行できていないと評価できます。
PSEが正しく運用されていれば保証の目途も立つが…
本記事の解説は、あくまでも電気用品安全法で定めるPSEマーク表記の運用方法の話であり、互換バッテリーの技術的な安全性が保証される訳ではありません。
ただし、PSEマークが正しく運用されてさえいれば、製造物責任上の責任の所在を突き止めることができ、万が一製品事故が発生した場合でも返金・賠償・訴訟のような法的手段の形で財産・私財の損失を保障させることが出来ます。
現在、オンラインショッピングサイトで販売されている中国ブランドの電動工具用互換バッテリーの大半は、安全性度外視の保護回路・電動工具に不適合のセル・PSE運用不適合の製品です。保護回路やセルの良否判別を行うには分解や解析など専門知識が必要ですが、PSEマークなら誰でも一目で良否を判別できます。
PSEマークを正しく運用していたからと言って互換バッテリーの安全性を保証できるものではありませんが、万が一の時にはユーザーの立場や損失を法が守ってくれる重要なものです。リチウムイオンバッテリーの製品事故は発火を伴う激しい火災になりやすいので、事前にラベルの写真を撮って、どのバッテリーで事故が起きたのか確認できるようにしましょう。
もちろん、実際に被害に遭遇するリスクや訴訟までの手間を考えれば純正バッテリーを使用するのが一番です。しかし、互換バッテリーであろうと消費者保護の観点では事故の時はユーザーが守られなければいけません。ぜひ一度ラベルを見て、PSEマークの隣の事業者の有無を確認してみてください。
NYの電動自転車火災で4人死亡、中国製リチウム電池が原因の火災続く
2024年2月26日
米国時間6月20日にニューヨークで発生した火災で、少なくとも4人が死亡した(Getty Images)
米国時間6月20日の朝早く、ニューヨーク市内の電動自転車店で火災が発生し、少なくとも4人が死亡、2人が重傷を負ったと公式発表があった。このデバイスに使用され、同市の火災死の主要な原因でもあるリチウムイオンバッテリーへの懸念が高まっている。
ニューヨーク消防署によれば、火災はマンハッタンの6階建て住宅ビルの1階、HQ E-Bike Repair(エイチキュー・イーバイク・リペア)という店で真夜中少し過ぎに発生したが、火災の原因はすぐには明らかにならなかった。
その後、ニューヨーク消防署は火災の原因が、建物の1階で機能不全を起こしたリチウムイオンバッテリーであったと断定した。
赤十字社は、火災の影響を受けた8世帯(大人23名、子ども2名)に避難用住宅を提供すると発表した。
市当局によれば、昨年、市内で電動自転車や電動スクーターに搭載されたリチウムイオン電池が原因で起きた火災は220回あり、前年より116回も増加したという。
ニューヨークタイムズによれば、リチウムイオン電池はニューヨーク市における火災による死因の第1位だ。20日の火災前までに、今年92件の火災で9人が死亡し、64人が負傷している。またニューヨークタイムズの別の記事では、4月には電動自転車が原因で「火災をともなう爆発」が起き、19歳の女性と7歳の弟が死亡した。また5月には、電動自転車のバッテリーが原因の火災で94歳の女性と彼女の息子が死亡したと、ニューヨークデイリーニュースが報じている。
最近、ニューヨーク市の当局者たちは、一般的に使用されている電動自転車や電動スクーターを動かすリチウムイオンバッテリーによる火災について懸念を表明している。これらのデバイスは、市内の配達員6万5000人以上にも使われている。ブロンクス選出のリッチー・トーレス議員(民主党)は、多くが「安全基準を満たさず、規制外の」リチウムイオンバッテリーで動いている電動自転車や電動スクーターの充電に際して市民に注意を促した。
ワシントン大学クリーンエネルギー研究所によれば、これらのバッテリーは過熱しやすく、自己着火する傾向がある。3月には、エリック・アダムス市長が火災防止専門家のタスクフォースを設立し、危険な状況や火災防止法の違反を特定するよう呼び掛けた。また、市は、安全基準を満たさない電動自転車や電動スクーターの販売またはリースを禁止し、使用済みのリチウムバッテリーのリフレッシュ(再生)も禁止している。
(forbes.com 原文)
中国で電動自転車による火災が年2万件超!原因は…―中国メディア
2024/02/26
中国メディアの環球時報は24日、中国では電動自転車による火災が1年間に2万件超発生していると報じた。
2024/02月23日未明、江蘇省南京市の集合住宅で火災が発生し、15人が死亡、44人が負傷した。火元となったのは建物内に置かれていた電動自転車とみられている。
記事によると、国家消防救援局の統計では2023年に中国全土で報告された電動自転車による火災は約2万1000件に上り、2022年比で17.4%上昇した。北京市に限っても2024年1月だけで電動自転車と電動三輪車による火災が計33件発生しており、原因については全体の9割超となる30件が「電池(バッテリー)の不具合」だったという。また、別のデータによると、EV普及して、電動自転車による火災の80%は充電中に発生しており、うち半数以上は夜間に発生していた。死傷者が出た事故について、出火した電動自転車が置かれていた場所は玄関、(建物内の)通路、階段の踊り場が合わせて9割を占めた。記事は、中国で電動自転車による火災が頻発する背景として、EVの修理店のレベルがまちまちで中には改造行為を行っているところもあると指摘。回収した古いバッテリーや非正規品が販売されており、その出所を把握することも困難になっているほか、警察当局が取り締まるには膨大なコストがかかるなど、違法行為に対するハードルが低い状態だという。
このほか、劣化した充電ケーブルを利用者が自分で補修して使い続けていたり、使用期限が切れたバッテリーを使い続けていたりすることも一因になっているようだ。
専門家からはQRコードを利用したトレーサビリティーシステムや、温度・圧力センサーを用いた危険状況の早期発見システムの構築、バッテリー事業参入許可制度の確立、バッテリー製品の推奨リストの発表などの対策案が出ているという。(翻訳・編集/北田)
電動バイク原因、NYで火災急増
充電不適切→バッテリー発火 屋内保管巡り物議も
2023年2月14日
【ニューヨーク=西邨紘子】ニューヨーク市で、電動バイクやキックボードに使われるリチウムイオン電池が原因の火災が急増している。不適切な充電や取り扱いが原因として当局が注意を呼びかけている。集合住宅で電動車両の屋内での保管禁止を検討する例も出始めた。デリバリー業者に打撃となりかねず、議論が激しくなっている。
1月、クイーンズ地区で非認可の保育所に使われていた集合住宅で火災が起き、子供18人が負傷した...
リチウム電池、使用規制法案を目指す 過去4年、12人死亡火災400件ーNY市04/25/2023
ニューヨーク市内で過去4年間、リチウムイオン電池が原因の火事が400件以上発生し、死者が12人に上り、負傷者は300人を超えている。事態を重視したチャック・シューマー上院院内総務(NY州、民主)は23日、マンハッタン区ミッドタウンで、ニューヨーク市消防局のローラ・カバナー長官らと共に、使用を一部規制するための法案を目指す意向を示した。
シューマー氏は「ここ数年、各地で火災が多発している」と指摘。「これ自体は重く、それが問題だ。電気自転車に乗っていたり、家に保管したりしていて、これが燃えたら、大きなトラブルに巻き込まれる」と電池を手に取りながら、警鐘を鳴らした。
関係者によれば、電池が引き起こす火災は、米国外から安く輸入された商品使用時のほか、出荷時と異なる電源コードで使われた際に最も発生しやすいという。法案では、リチウムイオン電池を規制し、適切に管理がなされた製品だけが市場に出回るようにするのが柱となる見込みだ。
昨年9月、クイーンズ区でE-bikeの火災で娘ステファニーさん(8)を亡くしたマリル・トーレス・ペレスさんは23日、遺影を手にすすり泣いていた。シューマー氏は「準備中の法案によって、ペレスさん一家のような悲劇を防ぐことを目指す」と力を込めた。(23日、amニューヨーク)
We had a terrible tragedy here today. A fire started on the first floor in the vestibule. The cause of the fire was an e-bike – said Chief of Department Hodgens from the scene of a 2-alarm fire which killed two people in Queens this afternoon. Read more: https://t.co/xjdPl7NZFx pic.twitter.com/SWA2nEXskR
— FDNY (@FDNY) April 10, 2023
米で電動自転車の電池発火が増加 NYで顕著
By
Scott Patterson
2023年3月7日
米国では、新型コロナウイルス禍によるロックダウン(封鎖措置)中に需要が高まった電動自転車が火災を引き起こすケースが増えている。搭載しているリチウムイオン電池の発火が原因で、死亡事故も起きていることを受け、当局が警鐘を鳴らしている。
こうした事例の多くはニューヨーク市で報告されている。市消防局によると、2022年の出火件数は2倍以上の216件に上った。電動キックボードなどのマイクロモビリティー機器や電動自転車が火元の火災により、今年に入って40人が負傷、2人が死亡した。
Eバイク発火で4人死亡 電池原因、今年108件目
―NYチャイナタウン(中国人街)の
この修理店は以前、安全基準違反で出頭命令を受けたことがあるという。
2023年06月21日
【ニューヨークAFP時事】ニューヨーク市消防局は20日、マンハッタン南部のチャイナタウン(中国人街)でEバイク(スポーツタイプの電動アシスト自転車)のリチウムイオン電池から発火し、4人が死亡、2人が重傷を負ったと発表した。ニューヨークでは同様の火災が相次いでおり、当局が注意を呼び掛けている。
リチウムイオン電池、火災多発 「非常事態宣言」自治体も―適切なごみ分別呼び掛け
火災は、チャイナタウンにある建物1階の電動自転車や電動スクーターの修理店で発生。現場で記者会見したカバナー消防局長は「リチウムイオン電池とEバイクが原因なのは明らかだ」と説明した。この修理店は以前、安全基準違反で出頭命令を受けたことがあるという。
同市消防局によれば、同様の火災は今年に入って108件目で、今回を含め13人が死亡、66人が負傷した。ニューヨークでは近年、電動自転車や電動スクーターの購入者増加を背景に、関連した火災が急増。2020年に44件だったのが、昨年は220件に上った。
デイケアで火事子供18人負傷<クイーンズ>
2023.02.02
先月25日午後、クイーンズ区のデイケアセンターで火災が起こり、子供18人が怪我を負った。同日付ニューヨークポストが伝えた。キュー・ガーデンズ・ヒルズの2階建の家の地下を利用して無許可で経営していたデイケアは、消防隊が到着すると激しく燃えており消火に40分ほどを要した。消防は、子供1人が煙を吸って重体となりコーネル病院へ搬送されたが、他17人の状態は安定していると報告。火事の原因は電動スクーターの中国製リチウムイオン電池の発火とみて調査している。家の地下には歯科オフィスが入っており、ビルの持ち主に建築基準法違反で召喚状が出された。
バッテリーが発火、爆発…電動自転車の知られざる危険性
電動アシスト自転車が人気だ。エコで健康的な特性に加え、武漢ウイルス研究所からのコロナウイルス・パンデミック以降は混雑した電車を回避できる交通手段としても注目されている。しかし、思わぬ事故が起きている。普及が進むニューヨークでは24時間で4台が火を吹く日もあり、CBSニューヨークは火災件数も今年8月の時点ですでに昨年のほぼ倍を記録したと報じている。
Per FDNY Fire Marshals the cause of this morning’s 3-alarm fire which occurred 5401 7th Avenue in Brooklyn was lithium ion batteries from E-Bikes/Scooters. Read more: https://t.co/JrdMmQkNMH pic.twitter.com/SJtWnveRn5
— FDNY (@FDNY) May 2, 2022
もちろん、一概に電動自転車が悪というわけではない。日本でも都市部ではシェアサイクルが普及し、平野部の密集地では数ブロックも歩けば次の貸し出しステーションが見つかるほどに広がっている。国土交通省はシェアサイクルを公共交通網を補完する存在と位置づけ、観光振興や地域生活への貢献の観点から普及・促進に力を入れている。
借り手にとっても、手軽にレンタルできるシステムはありがたい。スマホのアプリで予約し、30分ごとに百円少々などの料金で利用可能だ。レンタカーとは違い、追加料金なしで別のステーションへも返却できるため、荷物の増えた帰り道だけレンタルするなど柔軟な活用ができる。
自分専用のアシスト車を購入したいと考える人も多いようだ。経済産業省の生産動態統計調査によると、2020年には市場規模が600億円を超え、2007年の6倍以上にまで拡大した。自転車全体の販売数が下降するなか、eバイクなど高価格帯の好調な売れ行きが販売単価を同期間に7割ほど押上げ、全体の市場規模を拡大している。
便利な電動アシスト自転車だが、その危険性は意外に周知されていない。自転車にはリチウムイオン電池が搭載されており、充電時を中心に発火や爆発の危険がある。ニューヨーク・タイムズ紙は、ニューヨークではバッテリーが原因となったマンション火災が続発しており、犠牲者を生んでいると報じている。
マンション火災で母子が死亡、父は重体に
ニューヨーク・タイムズ紙はデロイト社による推定値をもとに、2020年に全米で50万台のeバイクが販売されたと報じている。このeバイクは、ほとんどが中国製である。
これは同期間に全米で売れたEVの2倍以上に相当するという。なお、ここでいうeバイクは電動アシスト自転車に加え、日本では公道を走行できない自走するタイプの製品が含まれている。
販売数の増加に伴い、悲劇的な火災の発生も増えるようになった。同紙は8月3日、マンハッタン北部のハーレム地区のマンションで火災が発生し、2人が死亡したと報じている。10階建てマンションの5階から出火し、この火災で母と幼い娘が死亡し、父親も重体となったという。
CBSニューヨークは、共用階段に保管してあったeバイクが火元だと報じた。現場には、焼け焦げてほぼフレームだけとなったeバイクが残されていたという。
原因は夜間に充電中のバッテリー
昨年12月には、ショッキングな避難の様子が報じられた。窓から激しく炎が噴き出すなか、外壁を伝い命からがら地上へ逃げた少年・少女の姿がカメラに収められている。
CBSニューヨークが報じた動画では、4階の複数の窓から炎と黒煙が上がる様子を確認できる。13歳少年と18歳少女が煙の充満する室内から逃れるべく、壊れかけた窓枠に両手だけでぶら下がり、続いて移った建物外壁の配管を伝い地上へと降りた。火災の原因は、夜間に充電中だったeバイク自転車のバッテリーだったという。
二人は姉弟であり、その父親の恋人である40代女性が火災により命を落としている。NY市消防局長は記者会見の場で、「これらのバッテリーは損傷したり過充電したりすると水素を放出し、猛烈に爆発します」と述べ、注意喚起した。
米自動車ニュースサイトの「ジャロプニク」によると、火元となった部屋では姉弟の父親が9個のeバイク用リチウムイオン電池を夜間に充電しており、これが未明になって火を噴いた模様だ。アパートからは黒焦げになった7台のeバイクが発見された。この父親はeバイクの修理業を営んでいたという。
NYで止まらない「悪夢」
悲惨な事故は後を絶たない。NY市消防局は今年4月、eバイクのバッテリー由来の事故が24時間で4件発生したと発表した。CBSニューヨークはこのうち、ブルックリンで住宅が激しく燃え、隣家にも延焼した事故を動画で報じている。夜間にもかかわらず周囲は日中のように明るくなり、近隣住民は「悪夢だ」と語った。
米CBSはその他3件はすべてマンハッタンで発生し、12人が負傷したと報じている。NY市消防局は、火災現場に散乱する黒焦げのeバイクの画像を公開した。
ニューヨークに限らず、事件は広い地域で発生している。米NBCニュース系列のコロラド局「9ニュース」は、中部・コロラドスプリングスでのeバイクを原因とするマンション火災を報じている。同局は「eバイクの人気の高まりとともに、発火の報告が増えている」と指摘し、同様の事例は「全米で」発生していると警鐘を鳴らす。
NBC系列のミシガン局「ローカル4」によると、五大湖に浮かぶマキノー島でもeバイクのバッテリーが爆発。駆けつけた消防隊員が負傷で入院する騒ぎに発展した。島の警察署長は、「島民と観光客はいかなる状況でもeバイクとバッテリーを屋内に保管しないよう、あらゆる手段を講じるべきだ」と述べ、強い警告を発した。
8月までに120件の火災が発生
eバイクからの出火報告は、ここ数年で非常に目立つようになった。米消費者組合が発行するコンシューマー・リポート誌は、ニューヨークだけで昨年75件の火災がeバイクや電動スクーターなどによって発生し、3人が死亡、72人が負傷したと報じている。
今年はさらに状況が悪化している。CBSニューヨークはNY市消防局のデータをもとに、8月までに120件の火災を誘発しており、すでに昨年のほぼ倍の水準になっていると報じている。
eバイク自体の危険性が高まったわけではなく、パンデミックにより所有者・利用者が増加したことで全体の件数が増えたようだ。eバイクにもともと潜んでいた危険性が、数の増加で表面化してきた形となった。
ニューヨーク・タイムズ紙は昨年、パンデミック以来自転車レンタルの需要が伸び、供給が追いつかないほどになったと報じている。ライドシェアのLyftが自転車シェアの展開に協力し、昨年は11月中旬までに2500万回のレンタル回数を記録したという。
同紙はまた、市場調査会社のNPDのデータをもとに、バイクシェアだけでなく販売も好調だと報じている。パンデミックにより自転車ブームが到来し、2020年のeバイク販売額は、前年比145%増を記録したという。活用されればそれだけ充電の機会も増加し、そのうち一定の割合で発煙・発火事故が起きているようだ。
ニューヨーク市議会議員は地元紙デイリーニューズに寄稿し、パンデミックによるフードデリバリーの増加も一因になったと示唆している。配達員たちが趣味用途のモデルを業務用として一日中酷使していることや、盗難防止の観点から宅内で保管していることで、望まざる火災を招いてしまっていると議員は指摘する。
屋外保管は要注意…発火事故が相次ぐ理由
リチウムイオン電池は、スマホなどにも多く用いられている一般的なバッテリーだ。比較的コンパクトで軽量にできる反面、化学反応により発火しやすい弱みがある。
米テックサイトの「テック・レーダー」は、低品質の製品を中心にバッテリーセルが損傷・過熱することで、内部に封入された電解液が発火することがあると説明している。ひとつのセルが過熱すると周囲のセルに熱が伝わり、次々と熱と圧力が高まる連鎖反応を引き起こす。
もともと取り扱いに一定の注意を要するこのバッテリーに、eバイク特有の難しさが加わっている。リチウムイオン電池は一般に、直射日光や高温多湿の場所を避けて保管することが推奨される。夏場の車内など高温の場所にスマホやバッテリーパックなどを放置し、爆発に至る事故が国内でもたびたび起きている。
だが、eバイクはその性質上、過酷な屋外での使用が主となる。延焼の危険から屋内での保管は推奨されないため、野ざらしの屋外で充電・保管するケースも多い。粗悪な製品ではこのような環境に耐えられず、発煙や爆発に至っているようだ。
「充電しっぱなし」はNG
eバイクを安全に使用するために、どのような点に留意すればよいのだろうか。9ニュースは消防当局によるアドバイスとして、eバイクを充電器につなぎっぱなしにしないよう呼びかけている。
また、バッテリー付きの自転車本体や交換用バッテリーを購入する際、信頼できるブランドを選ぶことも大切だという。カスタムメイドのeバイクを提供するファット・eバイク社の共同設立者は、同局に対し、「アリババやアマゾン、あるいはノーブランドの無名サイトで購入してしまうと、バッテリーのリチウムイオン・セルの品質、製品の品質、組み立て品質、充電器の品質などは、誰にもわかりません」と指摘している。
米eバイク業界のコンサルタントは、自転車業界向けニュースサイトの「バイシクル・リテイラー」に対し、パナソニック、LG、サムスン製のバッテリーを推奨している。一方で安価な中国製については、安全性の観点から勧められないとの立場だ。
過去には国内でリコールも、危険性を知り正しい利用を
日本でも電動アシスト自転車の普及が進んでおり、この傾向自体は好ましいことだ。自動車や原付と比べれば排気ガスを生じないことから環境負荷が低いほか、アシスト付きとはいえ一定の脚力は求められ、健康増進効果も期待できる。気の向くままに走ったり、地元のスポットの魅力を発見したりと、自転車目線ならではの気づきもあることだろう。
同時に、適切な注意を向けることも必要だ。全米で発生しているような悲惨な火災の事例は、原理的には国内でも起こり得る。とくに、個人所有のアシスト車のバッテリーが劣化した際、ネットなどで安価な互換バッテリーを購入して使わないよう留意したい。
また、大手の製品だからといって100%安心というわけではない。消費者庁は今年5月、ブリヂストンサイクルが販売するバッテリーの充電中に火災警報器が鳴動し、3人が軽傷を負う事故が起きたと公表した。同型のバッテリーを搭載するブリヂストンおよびヤマハ製のアシスト車、計30万台以上がリコール対象となった。
2020年には、パナソニック製のアシスト車に発火のおそれがあるとして、バッテリーの無償交換が案内されている。産経新聞は当時、対象となるバッテリーが34万個以上になると報じている。
シェアサイクルにおいては、街角のステーションでの駐輪中に充電を済ませる方式のものも登場している。こうしたサービスが必ずしも危険というわけではないが、無人のステーションで充電が行われるという性質上、万一発火した際には初動が遅れる可能性も否定できない。
秋に向けてサイクリングに最適なシーズンが到来するが、電動アシスト自転車の特性を正しく理解し、安全で快適な使用を心がけたい。
リチウム電池、使用規制法案を目指す
過去4年、12人死亡火災400件ーNY市
自動運転車に「存在しないものを見せる」サイバー攻撃 レーザー照射で事故誘発 中国の研究チームが発表
2022年11月28日
中国の浙江大学に所属する研究者らが発表した論文「PLA-LiDAR: Physical Laser Attacks against LiDAR-based 3D Object Detection in Autonomous Vehicle」は、レーザー光を自動運転車のLiDARに照射し、敵対的な点群を注入することで3次元物体検出を欺く攻撃を提案した研究報告だ。
例えば、横断報道を渡る歩行者がいるのに存在しないものと認識させたり、歩行者がいないのに存在しているものと認識させたりなどが行える。
自動運転車の多くに実装してあるLiDARは、照射し返ってきた反射光の時間を計算して周囲の3Dオブジェクトとの距離を点群ベースで把握する。また水平面で連続的に回転し、垂直面を高速でスキャンすることで、周囲の物体の位置をリアルタイムに検出している。
今回の攻撃「PLA-LiDAR」は、このLiDARに向けてレーザー装置で物理的に光を照射する方法を行う。このことで、存在しない物体を検出するエラーと前方の物体を検出しないエラーを発生させる。
具体的には、次の4つの攻撃シナリオを想定する。
(1)遠く離れた場所に偽の壁を作り、既存の物体を検出できないようにする隠蔽(いんぺい)攻撃(Nai-Hide)。
(2)記録された点群をLiDARに注入することで、存在しない物体を見せる記録ベースの作成攻撃(Rec-Create)。
(3)最適化された敵対的な点をLiDARに注入することによって、既存のオブジェクトを検出できないようにする最適化ベースの隠蔽攻撃(Opt-Hide)。
(4)最適化された敵対的な点をLiDARに注入することで、存在しないオブジェクトを見せる最適化ベースの作成攻撃(Opt-Create)。
PLA-LiDARは、4つの主要モジュールを組み込んだ攻撃を設計する。LiDARパラメータ計測モジュールは、ターゲット車のLiDARを計測し、スキャンシーケンスや水平角分解能などの攻撃関連パラメータを取得する。点群生成モジュールは、LiDARの記録や敵対的最適化によって注入できる偽装点群を生成する。
制御信号設計モジュールは、各レーザーパルスの発光時間を指定する制御信号を設計することで、目的の偽装点群をレーザー信号に変換する。最後のSynchronizationモジュールは、ターゲット車のLiDARの走査順序と制御信号を同期させ、選択したレーザー送信機でレーザーを送信し、物理的な攻撃を行う。
実験では、LiDAR VLP-16とLiDAR HD-L64Eを利用し、3Dオブジェクト検出器にPointPillarとSECONDを用いて、上述した4種類の攻撃シナリオを評価した。結果、全ての攻撃に対して有意に効果を発揮した。先行研究と比べても、最大200点の偽装点群から約20倍向上の最大4200点の偽装点群を注入できることを示した。
次の実験では、前を走る車からレーザーを照射し、後方を移動しているターゲット車に対して攻撃できるかを検証した。攻撃車とターゲット車が共に5km/h程度の同程度の速度で移動し、攻撃車がターゲット車から5~15m離れたところにいるという設定で行った。ターゲット車はVLP-16 LiDARを搭載したApollo D-kitで、攻撃者は受信機とレーザー送信機を車の屋根に実装した。
実験の結果、移動中の車両に搭載されたLiDARに対して、隠蔽攻撃と作成攻撃が有意にできると分かった。具体的には、隠蔽攻撃はASR94.1%、作成攻撃はASR78.9%を達成した。これら実験の映像は、プロジェクトページで確認できる。
Source and Image Credits: Z. Jin, et al., “PLA-LiDAR: Physical Laser Attacks against LiDAR-based 3D Object Detection in Autonomous Vehicle,” in 2023 2023 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP) (SP), San Francisco, CA, US, 2023 pp. 710-727. doi: 10.1109/SP46215.2023.00041
※テクノロジーの最新研究を紹介するWebメディア「Seamless」を主宰する山下裕毅氏が執筆。新規性の高い科学論文を山下氏がピックアップし、解説する。
全固体電池の技術進化と家庭用蓄電池の安全マネジメント
2022.10.23
家庭用の太陽光発電は、FIT制度の導入もあり、2013~2015年の3年間は記録的な売れ行きとなりました。その後は横ばいを続けていますが、今後は、脱炭素の一環として、公共施設はもちろんのこと、一般人の戸建て住宅、集合住宅に加え、企業のオフィスビル、工場などにも、太陽光発電の設備が導入されていくことでしょう。
太陽光発電の設備がどんどん導入されると、夏場の冷房需要時の発電量が増えるので、昔のように一時的にクーラーを止めることは無くなりました。一方で、昼間の発電量が需要を上回り、あえて太陽光発電を止めざる得ない場合も出てきました。
再生可能な発電を止めるというのは非常に勿体ない話であり、そのソリューションとして蓄電システムがあることをコラムで述べました。そこでは3つの方式、すなわち、リチウムイオン電池、NaS電池およびレドックスフロー電池について解説しました。
原則、これらは大規模な産業用途の選択肢です。特に2番目、3番目は、たとえ集合住宅用であっても規模が大きく、今はまだ、戸建ての家庭用ソリューションにはなりません。
もちろん、クラウドコンピューティングのように大きな電池容量をシェアしながら使用することも、インフラが整ってくれば可能です。今はまだでも、いずれ採算が取れる状況になればそういうビジネスも出てくるでしょう。
さて、最後に残ったリチウムイオン電池については家庭用としての選択肢になりえます。具体的には2つの方式が考えられます。1つは住宅専用設備としての蓄電池であり、もう1つは電気自動車用の蓄電池の流用です。
ただし、スマホやパソコン用などと比べ、住宅用の蓄電池容量は何桁も大きいため、安全面での懸念があります。現有のリチウムイオン電池は電解質に有機溶媒を使用しており、内部損傷が起こるとショートを起こして火災に繋がるリスクが高いのです。
家庭用の設備というのは、故障しても重大事故につながらないモノであることが強く求められます。それも原則としてメンテナンスフリーの前提でです。そのため、火災が発生する危険が非常に小さい全固体電池(同じリチウムイオン系)への期待が高まってきています。
こういう話をすると、「なぜ、最初から安全な全固体のリチウムイオン電池を開発しなかったのか?」という疑問を持つ方がいるでしょう。しかし、リチウムイオン電池の歴史を振り返れば、それが無理な話だったことを分かっていただけるでしょう。
リチウムは固体である金属の中で、最もイオン化傾向が高い元素であり、電池にとって理想的な材料です。よって、昔から目を付けられており、1970年代には、ボタン型あるいはコイン型の1次電池として普及しました。今でも使われています。
金属リチウムは、最も効率よく電気を貯められる材料だったので、使い捨ての1次電池ではなく、充電して再利用できる2次電池にしたら便利だろうと考える人がいて、1980年代に市販化されました。
金属リチウムを負極に使用すると高性能の2次電池となるのですが、充放電を繰り返すと、負極表面に針状の突起が形成され、これが成長して正極に達するとショートして発火事故が起こります。この事故が多発して販売がストップされました。
この問題は未だに解決できないため、性能が最も高いと予想される、金属リチウムを負極に使用する蓄電池は使えず、次善のソリューションとして発見されたのが現在のリチウムイオン電池です。
ノーベル賞を受賞した吉野氏が開発したのは、負極にコバルト酸リチウム(以後、LiCoO2)、正極に炭素(後に黒鉛)を使用するリチウムイオン電池です。この発明は、安全性が高く、しかもエネルギー密度も高いため、携帯電話に採用され、普及が進みました。
技術上のポイントは、リチウムイオンを貯められる負極材と正極材の発見でした。歴史的には、吉野氏の前に、正極材にTiS2、負極材にLiCoO2という解が発見されていました。吉野氏の功績は、実際にLiCoO2と炭素を使って実用的な電池を発明した所にあります。
LiCoO2も黒鉛も層状の構造をしており、リチウムイオンがその層の間に入れるので、体積を維持して電気を貯めることができます。しかも、針状の突起が形成されないため、安全に繰り返し使用できるようになり、市販されるようになりました。
ただ、黒鉛正極が貯められる電気エネルギーは、リチウム金属負極の約10分の1にすぎません。なお、上記のリチウムイオン電池において、火災リスクとなる有機電解質を使用せざるを得なかったのは、これ以外に、高速にリチウムイオンが移動できる電解質の選択肢が無かったからです。
この黒鉛正極、LiCoO2負極と有機電解質の組み合わせが実用的に優れていることは経験的に実証されましたが、当初、このメカニズムはよく理解されていませんでした。
そこで、なぜ、上記の組み合わせがうまく機能するのか、そのメカニズムの探求が行われました。いわば基礎研究です。しかし、その基礎研究の中で固体電解質の存在が発見され、それが全固体電池というコンセプトの出現につながったのです。
つまり、最初から全固体電池を開発しようと思い付いた人は居なかったのです。たまたま上手く行く方法が見つかり、その原因を丹念に追及した結果として出てきたアイデアだったのです。
歴史を振り返れば、何かの根本原因を調べているうちに、別の有用な概念を発見するという偶然は、ある確率でいつも起こっています。ですから、根本的な原因を追及することは進化のタネであり、挑戦する人だけが得られるご褒美なのです。
英語では、これを表す単語としてSerendipity(幸運な偶然を手に入れる力)というのがあります。これは、失敗を恐れず挑戦する人を表現していると考えられます。
話を戻します。黒鉛正極と有機電解質の組み合わせでは、最初の1回目の充電時に電解液が分解して電極の保護膜が形成されます。
この保護膜は電子は通さず、しかしリチウムイオンは通すので、電池と機能するわけですが、この保護膜こそ、固体電解質だったわけです。よって、有機電解質をこの固体電解質に置き換えれば、それが全固体電池になるということです。
では、ここから全固体電池の話に移りたいと思います。全固体電池には大きく2つに分類されます。いわゆる薄膜型と呼ばれる小型のものと、EVや家庭用蓄電池として期待されているバルク型です。
薄膜型は、前述の保護膜の延長線上で造ることができます。半導体を製造するイメージで捉えれば良いと思います。全固体電池の一番の問題は、固体電極(正極、負極)とその間にある固体電解質の間の界面における電気抵抗問題ですが、薄膜の場合には、面と面で接触させやすいので実用化が進みました。
安全性サイクルでも性能が落ちないことが実証されており、医療用やIoT用途に普及していくことでしょう。
一方のバルク型は、用途としてEVや家庭用蓄電池が見込まれるので、性能、耐久性に加え、安くなければなりません。性能面での課題としては、導電性の良い固体電解質の発見と、界面での電気抵抗を抑えることの両立です。
全固体電池の材料としては、硫化物系、酸化物系に加え、水素化物系やハロゲン系などがあります。ただ、メインストーリムは硫化物系と酸化物系です。常温における導電性は、硫化物系の方が酸化物系よりも1桁高く、リードが広がりつつあります。
耐久性は繰り返し使用しても性能が落ちないことですが、それと同じくらい重要なのが、日常的に想定される衝撃力を受けても電池性能が落ちず、安全であることです。
耐衝撃性は、一般的に材料に柔軟性があるものは高くなり、硬い材料はクラックが発生しやすいものは低くなる傾向にあります。酸化物は固いが脆く、硫化物系ではガラス系物質もあって、酸化物系と比べて柔軟性に優れています。
この柔軟性は、耐衝撃性だけでなく、電極と電解質の接触面積を増やすので、界面抵抗の低減にも効きます。材料としての導電性の高さもあり、硫化物系の圧勝かなと思いますが、欠点が1つあります。水に触れると、毒性のある硫化水素を出すことです。これは安全面で気になります。
一方の酸化物系は、硫化物に対して性能面等で色々と劣る所がありますが、安全性が高いというメリットがあります。硬くて脆いという問題については克服が必要ですが、一つの対策として導電性のある繊維を入れた複合材化が考えられるでしょう。
最後にコストが残りました。これについてはどう対応するのでしょうか? 現在、EV用として研究開発が進められているは、基本的に、既存のリチウムイオン電池の全固体化です。
問題は負極に使用されるコバルトです。コバルトは、その生産量が少なく、しかも生産地が偏っている所に問題があります。リサイクルは当然だとしても、EVの台数が増えた時に、安く消費者に提供できるのか疑問が残ります。
そういう意味で、原料の調達性に問題のない材料を使った全固体電池が最終的な勝者になるのではないかと思います。では、どんな材料ならば調達性に問題がないのでしょうか?
あくまでも個人的な見解ですが、ナトリウムイオン電池の全固体版というのが、持続可能性が高く、1つのソリューションになるかもしれないと思っています。
リチウムイオン電池と比べてエネルギー密度は下がるでしょうが、どこにでもある材料で大量のEV用や住宅用の蓄電池の生産に耐えられるならば、走行距離が短くても、また、保存できる電力が多少減ったとしても、脱炭素を加速する製品に発展する可能性があるのではないでしょうか?
家庭用製品の消費者は、モノを買う時、これまでは機能・性能、耐久性、コスト(初期コスト、ライフサイクルコスト)を秤に掛けながら購入していたと思いますが、これからは環境性や脱炭素への貢献というファクターが加わりました。
業務用では、CO2の1トンあたりの価格というのが市場取引されるようになり、今後は、一般的な環境性とコストの間の定量的な関係性が定まってくるでしょう。例えば、1トンは数千円といった感じです。
もう少し先になるでしょうが、そのうち、サプライヤとの交渉についても、値段は下げるよりも、CO2排出量を下げる方を優先する企業が出てくるかもしれませんね。
家庭用製品については、まだまだ、環境性と経済性の間のトレードオフ係数(どちらに重みを置くか)は家ごとに違い、定まっていないと思います。極端に環境性を重視する家庭もあるでしょう。しかし、環境にもプラスで、しかも少しお得というメッセージが現実的で最も強力だと感じます。
具体例として、ある企業は、「当社はグリーン電力だけ供給する。当社を通して電気料金を支払うと、少し割高になるが、それを大きく上回るメリットを契約者に提供する」というサービスをしています。今後、類似のサービスや製品がどんどん増えてくるのではないでしょうか?
結論:
安全上の懸念から、固体電池に対する関心が近年非常に高まっています。過去数十年間に科学界は固体Li電池の大幅な進歩を実現していますが、依然として固体電解質の低いイオン伝導率と電解質-電極間の不十分な界面接触という2つの主要な研究課題に直面しています。固体NaおよびAl電池は、Li電池と比較してそれぞれ低コストおよび高体積エネルギー密度という利点があるため、新技術として台頭しつつあります。本稿では、我々の研究室で開発された全固体Li、NaおよびAl電池の進歩の概要を紹介しました。固体電池の場合、固体電解質が鍵となる構成要素です。
高イオン伝導率を示す固体電解質の開発が強く求められています。固体電極と固体電解質の間に良好な接触を達成して維持することが、界面抵抗を低減するために不可欠であることが証明されています。軟質ポリマー中間層、少量のゲルまたは電解液の利用は、界面におけるイオン輸送を改善するために実行可能なアプローチであることが実証されています。さらに、正極性能を改善する追加の戦略を採用することも可能です。例えば、湿式化学法によるLiNbO3やLi1+xAlxTi2-x(PO4)3などのイオン伝導性材料を用いた正極の調製または正極粒子のコーティングにおいて、イオン伝導性ポリマーマトリックスをバインダーとして使用することが可能です。さらに、金属負極の保護は、固体電池の長期安定性を得るために非常に重要であることが実証されています。特に、固体電解質界面(SEI:solid electrolyte interphase)を形成する添加剤や人工SEIを用いれば、Li樹状突起を抑制し、リチウム電池の長期的安定性を改善する戦略が実行可能になります。実験と理論計算のアプローチを組み合わせることで、充放電サイクル中の界面の変化を明らかにし、固体電池の性能を改善することが可能になります。固体電池の商業化にはもう少し時間が必要です。
電動アシスト自転車や充電式の掃除機で使用するリチウムイオン電池の「非純正バッテリー」を使用中、発火するなどの事故が2014年からの10年間で235件あったとして、製品評価技術基盤機構(NITE)が注意を呼びかけている。
NITEでは機器本体のメーカーが設計や品質管理に一切関与していない物を非純正バッテリーと定義。235件のほとんどが火災につながり、周囲の製品や建物まで焼損させた。噴出した炎で軽傷...
電動自転車のバッテリーが発火・爆発…なぜ?掃除機やスマホも注意、建物が全焼した被害も
ハフポスト日本版 によるストーリー
電動アシスト自転車、充電式掃除機、スマホ、PC……。これらに搭載された主に中国製バッテリーが突然発火する事故が相次いでいます。
原因は、リチウムイオンバッテリーが「非純正」であること。ネットでも簡単に取り寄せることができますが、なかには建物が全焼する火災になったケースもありました。
NITE(製品評価技術基盤機構)が公開した実験映像には、電動アシスト自転車のバッテリーが充電中に「爆発」する様子が映っていました。
建物全焼14件、人的被害13件
NITEの発表資料によると、2014〜23年の10年間に発生した「非純正バッテリー」による事故は計235件。
最も多いのは、「充電式電動工具」(103件)で、「充電式掃除機」(97件)、「スマホ」(12件)、「ノートパソコン」(12件)、「玩具」(4件)、「電動アシスト自転車」(3件)、「その他」(4件)の順となっています。
また、235件の事故のうち、97%にあたる227件が火災でした。
そのうち、建物の全焼につながった火災は14件に上り、バッテリーから噴出した炎でやけどをしたなどの人的被害も13 件発生しています。
事故が発生した際の状況は、「充電中」が182件と最も多く、「保管中」が26件、「使用中」が10件などと続きました。また、事故発生時の非純正バッテリーの使用期間は「1年未満」が125件と半数超を占める結果となりました。
実際に起きた事故は次の通りです。
「兵庫県で2019年4月、ネット通販で購入した電動アシスト自転車用のバッテリー(非純正)を充電していたところ、出火し、床を焼損した。非純正バッテリーの内部で短絡が生じ、異常発熱したものとみられる」
「兵庫県で2023年9月、ネット通販で購入した充電式掃除機用のバッテリー(非純正)を掃除機に取り付けたまま保管していたところ、突然作動するとともに出火した。非純正バッテリーの安全保護装置が異常発熱し、出火したものと考えられる」
非純正では補償を受けられない可能性
また、NITEが公式YouTubeに投稿した実験映像を見ると、火災に発展した際の恐ろしさが伝わってきます。
非純正バッテリーを充電中、突然白い煙と炎が吹き出します。一度おさまりかけましたが、再び爆発を起こしたように炎が勢いよく吹き出し始めました。その様子はまるで「火炎放射器」を噴射したかのように見えます。
バッテリーには可燃性の電解液が含まれているため、一度発火すると大きな火災に発展する恐れがあります。
事故のリスクを減らすには、安全保護装置の適切な設計や品質管理が不可欠ですが、非純正バッテリーは異常発生時に安全保護装置が作動しないこともあります。
なかには、電池内部に異物が混入していたり、電気回路の部品に不良品が使われていたりする製品があるほか、純正バッテリーで事故を起こした場合、機器本体のメーカー側から対応や補償を受けられない可能性があるといいます。
NITEは、「非純正バッテリーは純正品に比べて低価格のものも多いですが、これらの中には高リスクのものが潜んでいます。機器本体のメーカーとは無関係の事業者から販売されているものは、通常の使用であっても事故が起きる場合があります」と呼びかけました。
電動アシスト自転車などの非純正バッテリーが発火する事故に注意を呼びかけました。
電動アシスト自転車の非純正バッテリーを充電していると、爆発して火が出て、最後には溶けてしまいました。
NITE(製品評価技術基盤機構)は、製品本体のメーカーのものではない非純正のリチウムイオンバッテリーは発火する恐れがあるとしています。
2014年~2023年までの10年間で、非純正バッテリーの事故のほとんどは火災で、そのうち14件は建物が全焼する火災になっているということです。
非純正バッテリーは品質管理が不十分な製品もあるとして、注意するよう呼びかけています。
非純正バッテリーに注意呼びかけ 火災など10年で235件
2024/7/9
【動画】電動自転車のバッテリーが充電中に爆発…。一度は見てほしい“恐ろしさが伝わる”実験映像がこれだ
電動アシスト自転車やスマホ、PCなどの非純正バッテリーが突然発火する事故が相次いでいます。原因はネットで取り寄せる「非純正」のバッテリーです。
ハフポスト日本版編集部
2024年06月27日
電動アシスト自転車、充電式掃除機、スマホ、PC……。これらに搭載されたバッテリーが突然発火する事故が相次いでいます。
原因は、リチウムイオンバッテリーが「非純正」であること。ネットでも簡単に取り寄せることができますが、なかには建物が全焼する火災になったケースもありました。
NITE(製品評価技術基盤機構)が公開した実験映像には、電動アシスト自転車のバッテリーが充電中に「爆発」する様子が映っていました。
【動画】電動自転車のバッテリーが充電中に“爆発”。一度は見てほしい“恐ろしさが伝わる”実験映像がこれだ
建物全焼14件、人的被害13件
NITE(製品評価技術基盤機構)の発表資料によると、2014〜23年の10年間に発生した「非純正バッテリー」による事故は計235件。
最も多いのは、「充電式電動工具」(103件)で、「充電式掃除機」(97件)、「スマホ」(12件)、「ノートパソコン」(12件)、「玩具」(4件)、「電動アシスト自転車」(3件)、「その他」(4件)の順となっています。
また、235件の事故のうち、97%にあたる227件が火災でした。
そのうち、建物の全焼につながった火災は14件に上り、バッテリーから噴出した炎でやけどをしたなどの人的被害も13 件発生しています。
事故が発生した際の状況は、「充電中」が182件と最も多く、「保管中」が26件、「使用中」が10件などと続きました。また、事故発生時の非純正バッテリーの使用期間は「1年未満」が125件と半数超を占める結果となりました。
実際に起きた事故は次の通りです。
「兵庫県で2019年4月、ネット通販で購入した電動アシスト自転車用のバッテリー(非純正)を充電していたところ、出火し、床を焼損した。非純正バッテリーの内部で短絡が生じ、異常発熱したものとみられる」
「兵庫県で2023年9月、ネット通販で購入した充電式掃除機用のバッテリー(非純正)を掃除機に取り付けたまま保管していたところ、突然作動するとともに出火した。非純正バッテリーの安全保護装置が異常発熱し、出火したものと考えられる」
フォードと中国CATL(リン酸鉄リチウム電池の製造会社)、米電池工場の建設検討=ブルームバーグ
2022年12/15(木)
[14日 ロイター] - 米自動車大手フォード・モーターと中国の電気自動車(EV)用電池大手、寧徳時代新能源科技(CATL)は、米国のミシガン州かバージニア州に共同で電池工場を建設することを検討している。
優遇税制の活用を目指す。ブルームバーグが複数の関係筋の話として報じた。フォードのEV向けにリン酸鉄リチウム電池を製造する計画。
検討中の保有構造では、工場はインフラを含めフォードが100%保有する。CATLは工場を運営し、電池の製造技術を保有する。
これにより、CATLの直接出資が不要になり、米インフレ抑制法の下で生産税額控除を受けられるという。
両社のコメントは取れていない。うまく中国にあしらわれ、フォード、アメリカ政府は納得なのか?
中国の自動運転車がアメリカで約290万km分も走行して地理データを収集している
2024年07月09日 10時46分
2017年以降、中国企業の自動運転車がカリフォルニア州だけで180万マイル(約290万km)も走行していることがFortune誌の調べでわかりました。これらの自動車は周囲の地理データを収集し、自動運転システムの訓練に使用していますが、Fortuneは「プライバシーの問題があり、この収集行為をアメリカ政府は精査し切れていない」として問題視しています。
カリフォルニア州は州内で自動運転車を訓練できるような制度を整えており、アメリカに拠点を置くWaymoやZooxなど35社に試験走行を許可しています。35社のうち、7社が中国を拠点とする企業です。
アメリカは中国のソーシャルメディア「TikTok」を全国的に禁止するなど、対中国戦略を積極的に推し進めていることで知られていますが、Fortuneの指摘によると自動運転車による情報収集は「驚くほど国の精査が行われていない」とのこと。州内を走行する自動運転車は周囲の映像を撮影し、誤差2cm以内の精度で地図を作り上げているとされており、Fortuneは「こうした情報は大量監視や戦争の計画まであらゆることに利用できる」と指摘しています。
また、過去にはGoogleが「ストリートビューを作成するための自動車で、30カ国以上にわたりWi-Fi経由のデータ収集を勝手に行い、個人情報を長年にわたって集めていた」という事例もあったため、Fortuneは「監視が行われていない以上、こうしたデータ収集が再び行われている可能性は排除しきれない」と言及しました。
しかし、データの重要性にもかかわらず、自動運転車のテストを監督している州および連邦政府機関は中国がどのようなデータを収集しているのかを正確に監視しておらず、チェックするプロセスもないと認めているそうです。また、中国製自動運転車とアメリカやヨーロッパの企業が運営するプログラム参加車との監視に関し、何らかの規則や方針を設けているわけでもありません。
セキュリティの専門家は、「自動運転車をテストしている中国企業が違法なデータ収集をしているという証拠も、収集したデータが中国政府によって使用されているという証拠もありませんが、万が一そのようなことが行われていたとしても、監視体制が驚くほど甘い現状を鑑みると、アメリカ当局が気づくことはないでしょう」と述べました。
中国政府は他のどの国よりも多くの自動運転車のテストを行っているが国営メディアは衝突事故や事件をほとんど報道せずオンライン投稿は検閲されているという指摘
2024年07月06日 08時00分
中国武漢市では約500台の自動運転ロボットタクシーが走行しており、今後さらに1000台のロボットタクシーが追加されるとの発表が行われています。そんな武漢市にニューヨーク・タイムズのキース・ブラッドシャー記者が渡り、ロボットタクシーがどのように運用されているのかをレポートしました。
中国では16以上の都市が公道での無人運転車のテストを許可しており、少なくとも19の自動車メーカーとサプライヤーがしのぎを削って無人運転車を走らせているとのこと。武漢市ではBaiduがおよそ500台のロボットタクシーを走らせています。
ロボットタクシーは主に無人で運転されますが、無人であるが故の自動車事故が発生することも報告されており、アメリカ・カリフォルニア州サンフランシスコでは人間との接触事故が発生したことを受け、運用企業が公道での走行テストを一時停止するなどの対応に追われたこともありました。
ある調査によると、中国人はアメリカ人よりも自動運転車のコンピューターを信頼する傾向が強いそうです。ブラッドシャー氏は地元の声を紹介し、「武漢市のある食料品店のオーナーは、安全性について心配しすぎる必要はないと思うと語っていました」と記しています。
一方で、政府が自動運転車の安全性に関する事件や事故についての議論を制限し、テクノロジーに対する市民の不安を抑えているとの見方もあります。
2024年4月26日、高度な運転支援機能を搭載した自動車「AITO M7 Plus」の運転手が山西省で追突事故を起こしました。この件でとある女性が「夫、兄弟、息子が殺された」と主張する動画が出回りましたが、すぐに投稿は削除されてしまったそうです。これに関連して中国の報道機関が出した、運転支援システムの安全性を疑問視する長期にわたる調査結果も、数日で消えてしまったとのこと。ブラッドシャー氏によると、国営メディアは事故発生後9日間にわたり事故に関する報道を控えていたそうです。
また、先進的な運転支援システムを搭載したXiaomiの電気セダン「SU7」が制御不能に陥り加速し、1人が死亡、3人が負傷した様子について海南省の報道機関が伝え、その後すぐにXiaomiが「衝突した車には何の問題もなかった」との声明を発表し、声明を否定する記事が掲載されたものの、否定記事はすぐに消されてしまったとの報告もあります。
ブラッドシャー氏は「中国では政府が自動運転に関する技術を強力に支援しており、事故に関する公開情報を厳しく制限している。アメリカで同様の事故が起こればおそらくかなりの注目を集めるはずだが、中国では公的監視ははるかに少ない」と伝えています。
2021年11月26日 13時30分
中国・北京市政府が、Baidu(百度)が展開する自動運転タクシー事業で顧客から運賃を徴収することを許可しました。中国国内で自動運転サービスの商業化が認められたのは初めてで、この決定によりBaiduは自動運転タクシー事業の構築に向けて大きく前進しました。
Baiduは2020年10月から北京経済技術開発区で自動運転タクシー「Apollo Go」を無料で運営し、走行のテストを行っていました。Baiduの自動運転部門・IntelligentDrivingGroupの副社長を務めるWei Dong氏は、「Apollo Goは既に2万人以上のユーザーが利用しており、各ユーザーは少なくとも月に10回は乗車している」と報告していました。
北京市政府は、2021年11月26日から北京経済技術開発区に当たる通州区亦荘周辺に限定し、Apollo Goが運賃を徴収することを承認しました。国内で自動運転車の商用利用が認められたのは初めてのこと。Baiduは具体的な運賃を公開していませんが、海外メディア・CNBCは「DiDiの2倍程度となる見込み」と記しています。
Apollo Goには人間のスタッフの同乗が義務づけられていますが、Baiduは完全に無人とする運営もテストしているとのこと。Wei氏は「今後2年以内に完全無人の自動運転車が公道を走行するだろう」と述べました。
BaiduはApollo Goを2030年までに100都市に拡大させる方針を示しています。Wei氏は「医療施設や公共図書館といった施設への移動にApollo Goを利用する戦略や、車窓に20年前の様子を映し出すなどの単なる移動手段を超えた経験をユーザーにもたらすといった戦略に焦点を当てていく」と述べました。
中国IT大手TencentがNVIDIAに頼らず自社製AIインフラのAI学習能力を20%強化
2024年07月09日
企業や研究機関が用いる大規模なAIインフラストラクチャには大量の計算処理チップが搭載されており、膨大なデータを並列処理できるように構成されています。新たに、中国の大手IT企業であるTencentが、AIインフラストラクチャのネットワーク処理を改善し、AI学習性能を20%向上することに成功したと発表しました。
大模型训练再提速20%!腾讯星脉网络2.0来了_腾讯新闻
Tencentによると、AIインフラストラクチャのような大規模なHPCクラスタでは、全処理時間のうちデータ通信時間が最大50%を占めるとのこと。ネットワーク処理性能を向上してデータ通信時間を短縮できれば、GPUの待機時間が減って全体的な処理能力を向上できます。このため、Tencentは自社製AIインフラストラクチャのネットワーク処理性能の向上に取り組みました。
Tencentは2024年7月1日に新たなネットワーク処理システム「Xingmai 2.0」を発表しました。Xingmai 2.0を採用したAIインフラストラクチャでは、従来のものと比べて通信効率が60%、AIモデルの学習効率が20%向上するとのこと。Tencentのテストでは、大規模なAIモデルの学習時間が50秒から40秒へ短縮できたとされています。
Xingmai 2.0にはTencentが開発した通信プロトコル「TiTa2.0」が採用されており、データの効率的な配分が可能です。また、TiTa2.0はデータの並列送信にも対応しているとのこと。さらに、Xingmai 2.0は新開発のネットワークスイッチや光通信モジュールを採用することで帯域幅が拡大しており、単一クラスタで10万台以上のGPUを管理できます。
Xingmai 2.0にはTencentが開発した通信プロトコル「TiTa2.0」が採用されており、データの効率的な配分が可能です。また、TiTa2.0はデータの並列送信にも対応しているとのこと。さらに、Xingmai 2.0は新開発のネットワークスイッチや光通信モジュールを採用することで帯域幅が拡大しており、単一クラスタで10万台以上のGPUを管理できます。
AI計算処理の分野ではアメリカ企業のNVIDIAが大きな存在感を示していますが、アメリカは中国に対して高性能半導体の輸出を制限しており、中国に拠点を置く企業がNVIDIA製の高性能半導体を入手することは困難となっています。このため、TencentがGPUの増強ではなくネットワーク処理の改善でAI処理性能を向上できた点は注目に値します。
また、South China Morning Postは、「AIの学習はエネルギーを大量に消費する。AIインフラストラクチャの処理効率を向上することはエネルギーコストの削減につながるため、価格競争において極めて重要である」と指摘しています
中国の生成AI特許出願数は3万8000件以上でぶっちぎりの世界1位、2位のアメリカの6倍近く
2024年07月04日
2023年までの10年間に出願された「生成AI」に関する特許の数が調べられ、全5万4000件の特許出願件数のうち3万8000件が中国からのものであることがわかりました。上位5カ国は、上から順に中国、アメリカ、韓国、日本、インドです。
世界知的所有権機関(WIPO)によると、生成AIに関する特許の出願件数は中国がどの国よりも多く、全体の約70%を占める3万8000件です。この数字は、2位のアメリカ(6276件)を大きく引き離しています。なお、3位は4155件の韓国、4位は3409件の日本、5位は1350件のインドでした。
出願企業の上位10社は、テンセント(2074件)、平安保険(Ping An Insurance)(1564件)、Baidu(1234件)、中国科学院(607件)、IBM(601件)、アリババ・グループ(571件)、サムスン電子(468件)、アルファベット(443件)、ByteDance(418件)、Microsoft(377件)です。
内訳は画像・映像データ関連のものが1万7996件と圧倒的に多く、次いでテキスト関連が1万3494件、音声・音楽関連が1万3480件となっています。また、分子・遺伝子・タンパク質ベースのデータを使用する特許が急速に増加しており、過去5年間の年平均成長率は78%だったとのことです。
WIPOによると、2017年にディープニューラルネットワークのアーキテクチャが登場して以来、生成AIの特許数は8倍に増加しており、2023年時点で生成AI関連の特許のうち25%以上が公開されています。ただし、全特許のうち生成AIに関する特許の割合は6%に過ぎず、まだまだ少ないとWIPOは指摘しています。中国で苦戦していたトヨタと韓国ヒョンデ、現状は?=韓国ネット「中国は恐ろしい」
「中国との事業は最初はバラ色だが本格化すると黒歴史となる」
2023年10月18日
2023年10月15日、韓国・ニューシスは「世界最大の自動車市場である中国で苦戦していた現代自動車(ヒョンデ)とトヨタ自動車が異なる道を進んでいる」と伝えた。中国工場売却のカードを切った現代自は現地車ブランドの受託生産に踏み出した。一方、トヨタは販促活動に後押しされ4カ月ぶりに業績が好転した。
ロイターの報道によると、現代自の中国法人「北京現代」は、中国・北京汽車集団(BAIC)の電気自動車(EV)、「極狐(ARCFOX)」の自社工場生産に向けて協議を進めている。現代自が中国完成車ブランドを受託生産する初のケースになる。具体的な内容は伝えられていないが、北京現代がARCFOXの設計・生産・品質管理を担う形が有力で、年産45万台の北京第3工場が生産拠点になる見通し。業界では、「現代自が中国市場での不振を打開するため、IONIQ(アイオニック)など自社EVの現地生産に代わり受託生産という迂回(うかい)路を選択した」と分析しているという。
ただ、現地販売の不振で売却を進めている重慶工場は1カ月ほどの間に最低入札価格を30%引き下げたものの、これという購入者が現れず、さらに12.8%引き下げたという。重慶工場は現代自が17年に1兆6000億ウォン(約1765億円)を投じて建設した中国5番目の生産拠点。記事は「現代自にとって中国市場は依然として高い壁だ」と伝えている。
一方、中国乗用車協会(CPCA)によると、トヨタ自動車の9月の販売数は17万6000台で、前年同期比2%増加した。6月以来、4カ月ぶりの増加となった。小型SUVを打ち出した販売活動の強化が奏功し、販売車両の大部分が増加勢を示したという。BYD(比亜迪)と共同開発した準中型EVセダン「bZ3」の累積注文数は2万台を突破した。
トヨタは一時、中国市場で高い販売率を記録していたが、最近は中国ブランドの急成長に押され不振にあえいでいた。昨年は10年ぶりに販売数が前年実績を下回った。今年8月には東京電力福島第1原発の処理水海洋放出による対日感情の悪化で6.6%減を記録していた。
ただ、1~9月の累積販売数は前年同期比4%減少している。一時的な好転に終わらないようにするには、現地販売戦略を一層強化すべきだとの声が上がっているという。
この記事に、韓国のネットユーザーからは「やっぱり中国は大企業でも失敗して追い出されるんだな。恐ろしい」「中国との事業は最初はバラ色だが本格化すると黒歴史となる」「現代自は中国ではもう駄目でしょ。タクシーに使われてるくらいでは」「中国とは手を切るべき。現代自はなぜそんなに未練がましいのか」などの声が寄せられている。
(翻訳・編集/麻江)
習近平が“3選”した中国から「世界の投資家」が逃げ出した…! 毛沢東時代の“大飢饉”の悪夢がよぎる「危うさの正体」
町田 徹 2022/11/01
グローバル・マネー逃避の原因
4期目があっても不思議のない体制になったー。10月22日に閉幕した中国共産党の第20回党大会と、同23日に開催した第20期中央委員会第1回全体会議(1中全会)を経て、中国国家主席を兼ねる中国共産党の習近平・総書記の3期目の新指導部が正式に発足した。
この習体制の危うさが、強国路線の延長線上にある台湾情勢の緊張の高まりだけでないことを雄弁に物語ったのが、習指導部の顔触れが明らかになった日の翌日(同24日)の香港株式市場の動きだ。
グローバル・マネー(外国人投資家)の上海市場をあわせた中国本土株の売り越し額が179億元(およそ3700億円)とこれまで最大だった2020年7月14日の173億元を上回り、過去最大を記録したのである。結果として、中国株相場も大きく下げた。
こうしたグローバル・マネーの動きは、「共同富裕」政策を掲げて、鄧小平体制以来の中国経済の成長の原動力だった「改革開放」路線を捨て去りかねない習近平体制への強い警戒感を示している。そして、その危うさは経済失政のツケから中国国民の不満をそらすため、一段と台湾情勢を悪化させ、さらに経済を圧迫するという悪循環を招きかねない。
10月24日の香港株式市場は、相場の指標であるハンセン指数が前週末比6%安の1万5180ポイントで取引を終えた。これは、2009年4月以来、ほぼ13年半ぶりの安値更新だ。1日の下落率としても、2008年11月以来、ほぼ14年ぶりの大きさとなった。背景にあったのが、過去最大を記録したグローバル・マネーの中国市場からの逃避なのだ。この日の売り越しにより、グローバル・マネーの年初からの通算の売買も売り越しに転じたという。
グローバル・マネー逃避の原因が、週末の中国共産党の習指導部の3期目の発足を嫌気したものであることは明らかだ。値下がりがきつかった銘柄には、ここ数年の習近平氏への権限の集中過程で、中国経済の統制色が強まり、その規制強化の波をもろに被り、かつてのような成長力をすっかり失ったアリババ集団やテンセントなど中国IT大手株が顔を揃えた。
15年ぶりの安値を記録
グローバル・マネーの逃避は株式市場にとどまらず、デフォルト(債務不履行)リスクを売買するクレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、中国の保証料率(5年物)が1.37%と、2015年の中国市場の大幅下落に端を発して世界の株式市場が下げた「チャイナ・ショック」後の2016年2月以来の高い水準を付けた。また、上海外国為替市場では10月25日の日中取引で、人民元が一時1ドル=7.31元まで下落。2007年12月以来 およそ15年ぶりの安値を記録した。グローバル・マネーは、新型コロナウイルスのまん延を受けて、中国のゼロコロナ政策や不動産業者への懲罰的な規制を懸念、中国市場への警戒感を強めてきた。ハンセン指数は、2018年1月の高値3万2,887ポイントからほぼ右肩下がりで推移、去年の夏辺りから、その下げ足を早めていたのだ。
中国共産党の第20回党大会の最中、グローバル・マネーの逃避を加速する”事件“があった。突然、7~9月期の国内総生産(GDP)など重要な経済指標の発表が延期されたのである。延期の理由も、新たな公表スケジュールも明らかにしなかったばかりか、GDPが目標に達しなかったので、習体制の3期目入りを決める共産党大会が開催中であることに配慮した延期ではないかとみられる結果になっていた。
そして、ようやく10月24日になって公表された7~9月期のGDPは、前年同期比でわずか3.9%増と、習中国が掲げている目標(5%台)の実現が難しいことを改めて裏付け、習体制が経済政策に弱いという懸念を裏付けた。
では、それほどグローバル・マネーに嫌われた3期目の習近平体制の顔触れをみてみよう。
最高指導部の顔ぶれ
中国共産党の最高指導部を指す「政治局常務委員」は7人で構成されているが、今回、このうちの6人が明らかな習近平派になった。
序列トップは党の習近平・総書記だ。2位が、習氏が浙江省のトップだった時の秘書長である李強氏。3位が、習氏の父親の巨大な陵墓を建設したことで知られる趙楽際氏。4位の王滬寧氏はこれまで3代の総書記に仕えており、習派には該当しないというが、これまでも政治局常務委員として忠実に習氏を支えてきた。5位が北京市長だった蔡奇氏。6位が丁薛祥氏。この人は習氏の最側近の一人で、遊説につきそう「中南海の執事長」と呼ばれている。そして、7位が李希氏。習氏の父親が共産党の創成期に蜂起したことを「聖戦」化した人物だ。
逆に、習近平氏と政治的に距離があった人たちはすべて一掃された。これまで序列2位で、首相も兼ね、習氏より若いため留任とみられていた李克強氏はその代表格だ。一時は、習近平氏とトップの座を争うライバルとされていたし、習氏が嫌う共産党の青年組織「共産主義青年団(共青団)」の出身だ。
「政治局委員」(党のトップ24人)から「政治局常務委員」に昇格するとの見方もあり、「次世代のホープ」と目されていた胡春華氏は、「政治局常務委員」どころか、「政治局委員」の名簿にも名前がなく降格されたという。この人も共青団の出身で、最近になって習近平氏への忠誠を広言していたが、信用されなかったのだ。
習氏は、自分の派閥一色に指導部を染めあげて、いったい、中国をどうするつもりなのか。
慣例では、総書記の後継者候補を抜擢することになっているのだが、今回はそういった人物が見当たらない。逆に、次も習氏、つまり4期目続投も現実味を帯びた形になっている。
台湾への対応はどうなる
見逃せないのが、中国共産党の憲法とも言われる党規約の改正だ。注目点が2つある。一つは、習氏の「党の核心としての地位」と、「習氏を中心とする党中央の権威を守る」という「二つの擁護」を明記したことだ。二つの擁護は、党員の習氏への忠誠を事実上義務付ける内容である。党規約は、党内の最高法規なので、違反者は取り締まりの対象になり得る。習氏の中国国内での統制が一段と強まりそうなのだ。
台湾への対応も気掛かりだ。党規約は、「『台湾独立』に断固として反対し、抑え込む」という文言を明記、台湾統一に強い意欲を示した。
また、「世界一流の軍隊を建設する」との記述も盛り込んだ。かねて中国共産党は2050年ごろまでに米国と並ぶ軍事力を構築するとの目標を掲げてきたが、習氏は今回の党大会の活動報告で「(一流の軍隊構築を)加速せよ」と発破をかけた。加えて、党規約にも明記したことで、中国は軍拡ペースを早めることになるだろう。キナ臭くなることは免れない。
そして、グローバル・マネーが懸念する、もうひとつが経済政策だ。前述の人事もその懸念を裏付けている。というのは、中国共産党の最高指導部である「政治局常務委員」でこれまで序列2位、かつ首相も務めていた李克強氏の退任が経済運営に大きな影を落としているのだ。
李氏は、北京大学で経済学博士号を取得した経済政策通で、鄧小平・体制下の1978年12月に打ち出された中国の国内体制の改革と対外開放政策を通じて経済発展を期す「改革開放」の継承者の立場も強かった。
「改革開放」は今日、中国が世界第2の経済大国になった原動力と断じてよい。しかし、その政策は、早い段階から「先富論」を容認、先に豊かになれる条件を整えたところから豊かになり、その影響で他が豊かになればよいという考え方に根差していた。これに対し、近年、貧富の格差が広がった中国国内では不満も高まっていた。
毛沢東と肩を並べた
共同富裕(格差是正)を掲げた習近平氏が権力争いに勝利する原因の一つになったとみられている。だが、決して鵜呑みにはできない。
格差是正と言えば、聞こえは良いが、「共同富裕」はすでに、中国のIT企業や不動産業の締め付けに繋がり、中国経済の下振れ要因になっている。
また、中国では、新型コロナウイルス対策も習氏への権力集中の好機とされた。その結果、経済の混乱を厭わないゼロコロナ政策が今なお堅持されているのは周知の通りである。
今回、序列2位の「政治局常務委員」に抜擢され、首相候補とされている李強氏は、ゼロコロナ政策に伴う経済の混乱を厭わず、習氏の意のままに、上海市トップとしてゼロコロナ政策を闇雲に遂行してきた人物だ。繰り返されたロックダウン(都市封鎖)が、それ以前から減速していた中国経済に追い打ちをかけたこと、それが世界経済にも大きな影響を与えたことも説明を要しない。
トップ7人の「政治局常務委員」中に、李克強氏のような経済通がいないうえ、こうした李強氏のようなイエスマンたちが経済運営を担うとしたら、中国と日本を含む世界の経済がかなりのリスクを抱え込むことになる。
今回、習近平氏は、中国建国の父である毛沢東氏と肩を並べたと言われている。が、独裁者だった毛沢東氏の時代の中国が行った経済政策「大躍進政策」は、大変な飢饉を招いて何百万人もの餓死者を出したと言われる。惨憺たる結果を招いたものなのだ。
中国は1970年代、鄧小平氏らがこの事態への反省から「改革開放」を掲げて、理想のモデルに掲げた日本に接近、カネと技術を手にして、今日の世界第2位の経済大国への礎を築いた。
3期目の習近平体制はこの「改革開放」路線を軽視、強国路線や共同富裕を推し進めようとしている。
時代背景が違い、餓死は大袈裟かもしれないが、習体制も、独裁者・毛沢東体制並みの経済失政という大きなリスクを内包しているとみるべきだろう。
そのリスクが現実化したら、国内の不満をそらすために、台湾有事を引き起こす可能性も高まりかねない。こうした習・中国の危うさは、「対岸の火事」と「高見の見物」を決め込んでいられるような状況にない。これまで以上に、我々日本人は、習・中国の政治・経済動向に関心を払う必要がある。
フォード、計画中のバッテリー工場を縮小へ-EV需要低迷で
2023年11月22日
(ブルームバーグ): 米フォード・モーターはミシガン州に、中国の電気自動車(EV)用電池大手、寧徳時代新能源科技(CATL)と共同で電池工場を建設していたが、建設中のバッテリー工場での生産能力と雇用計画を縮小することに決定した。同社は電気自動車(EV)の需要が弱まると想定している。
フォードは2023年11月21日、2カ月前に休止していたマーシャル工場の建設を再開するが、年間約23万台のEV向けにバッテリーを生産すると発表した。従来は40万台分を生産する計画を示していた。2026年に開設予定の同工場での雇用は1700人となる見通し。2023年2月に工場建設計画を発表した時点では、2500人を雇用するとしていた。
EVモデルへの120億ドル(約1兆7700億円)支出を延期するなど、同社のEV戦略縮小の一環となる。フォードは2026年末までに年間200万台のEVを生産するとの計画を断念した後、その節目に到達するとみられる時期についてまだ明らかにしていない。人気車種であるピックアップトラック「F150」のEVモデル、「F150ライトニング」の販売台数は7-9月(第3四半期)に46%減少した。
フォードの最高広報責任者マーク・トルビー氏は2023年11月21日の記者会見で、EVの普及は「われわれや業界が期待していたようなペースでは伸びていない」と指摘。「資本の配分方法に関して厳格でありたい。生産および将来の生産能力が需要に基づいたものになることについて考えたい」と述べた。
2023/11/09 真っ先にEVを推進した中国でユーザーたちが気づいた欠点は?
EVのバッテリーは寒さに弱いのでバッテリーを温めるためのヒーターが付いているらしいですが、そのヒーターにも
電力を使うので冬場になると走行可能距離が最大30%ほど落ちるそうです。
さらに氷点下になると家庭用電源に繋いでも電圧が低いと充電されないこともあるようなので、質の低いEVが出回っている
としたらこれから先の冬は地獄です。電池はボルトの実験と原理は変わってませんから、電極を液体に接触させて化学反応させないといけませんから、当然低温には弱いでしょうね。
電気自動車は冬期、暖房をいれたり、夏期、冷房を入れたりするとバッテリーの消耗が早くなり、走行距離が極端に短くなる。これは致命的な欠点だ。
EVの場合、これが最良の選択だと決めつけてEVに補助金を支給し、一方、ガソリン車の制限をして人為的に早く普及させたと思う。寒さに極端に弱いなどの、予測できなかった大きな問題が後から起こりうるのも当然だと思う。
EVに関しては、現状仕様のリチウムイオン電池ベースのEV車では、生産から廃棄までトータルの環境負荷が大き過ぎて、何の環境保護にもなっていません。一度EV車を買った人は、二度とEV車は買わないでしょうね! 画期的なブレークスルーが起きて、電池の寿命が2倍程度にならないと、普及しない。
先日「看中国」のチャンネルで「中国産電気自動車 命にかかわる安全問題」という回がありました。走行距離性能への不満も語られていましたが、寒くなったからか(?)あちこちでバッテリーが炎上するチャイナEVが取り上げられていました。また、バッテリー交換方式を先取りし過ぎたのか、路上にバッテリーが脱落している動画もありました。
充電率が20%ぐらいを切ったらバッテリーが爆発しやすいからそうなる前に充電せなあかんから、余計に早く充電せなあかんらしいで。リチウム電池が劣悪な品質らしいから。
EVはガソリン車より重いので、
走行するの際に、ガソリン車を上回る摩耗がタイヤと道路に生じるらしいが、かつてのスパイクタイヤの様な粉塵をまき散らす事は無いだろうが、
道路整備の費用がまして、余計な費用がかさむことになりそう
発進停止を繰り返す代物が必要とするエネルギー量のファクタはまずは質量であって、
いくら回生機能があろうが重いんじゃ話にならない。
トヨタが正気で助かりました。
EVのバッテリーは重量が500kgとか700kgとかあるので、交換式だと装置が大掛かりになるのでコストを考えると普及させるのは難しいでしょうね
それにバッテリーは衝撃で炎上するので、テスラ車なんかバッテリーの周囲をガチガチに守ることで安全性を確保しています。
交換式にするとなると事故ったときの安全性に不安が出ます。
EVが出たなりの頃はディーラーに行くと購入を勧められました。
私が全く関心を示さないどころかEV信用してなかったので勧めてこなくなりました。
雪国で全く普及してませんし当然と言えば当然ですね。
日本でも以前新潟の大雪の際、寒冷地におけるEVの致命的弱点があらわに成りました。自分事で考えるとやはり枯れた技術であるガソリン車やPHEVを選ぶので結果的にEVを敬遠することになるからです。屁理屈ですが米中デカップリングによる東西分裂後にBYDのアフターサービスが期待出来るのか、甚だ疑問に思われる点も不安材料です。
EVの技術的問題点はもう隠せないでしょう。
併せて不安なのが、C国のマンションのように、人が住まなければ築〇〇年だったとしても新築と言い張るように、
どっかの倉庫に放置している余剰在庫のEVが〇〇年落ちでも新車と言い張り不良在庫を日本で捌こうとしないか不安です。
EVは結構な環境負荷物質の塊ですよね。
2019年~20年にかけて広州にいましたが、市内のEVタクシーは充電ではなく、バッテリーごとかえていましたね。
EVを買ったら100%充電すると電池が痛む、20%を切ると電池が痛む出先で充電の予定を確認して行かないと不安でしょうがない!
高電圧で、発火の恐れがある危険物搭載の車両 その辺に放置されたらどうする?
最近東京でTOKYOモビリティショーが開かれていましたが、BYDが出展していましたね。とてもMade in Chinaの車を買おう、しかもEVなんてと個人的には思っていますが、結構みている人がいました。しかし、そんな人たちがBYDを買うかというと疑問ですけどね。現にテスラですら日本ではあまり売れていないです。一番売れているEVは日産のサクラだとの事。確かに軽自動車ならEVを考えても良いかも知れませんが、家で充電出来るのがやはり前提だなと思いますね。
中国が率先して生産:販売しているEV車🚗なんて絶対に買わないし 乗りたいとも思いません!そもそも他国がEV車を手掛けてきた背景には日本の内燃機関のエンジンの技術が日本に追いつかないので、EV車で挽回しているのが実態ですよねー。中国から輸入すれば中国から補助金が、それに日本政府が更に補助金を支給してEV車を支援しているのが実態です。これまで日本の産業を支えてきた日本の内燃機関車を自国で破滅させようとしているのが岸田政権の実態です。なので、本来自民党は保守政権ですがいつのまにか岸田政権は中国本位の左派政権に成っています。日本のお家芸の産業をぶち壊し 日本車が売れず その為財政も破滅させようとしているとしか考えらません!元に中国製EV車は売れず在庫の山に成っています。それに日本は追随しようとしています。今の日本政府に真向から異論を唱えているのが「日本保守党」だと思います。このままでは周回遅れで中国の二の舞で日本の物作り産業は破滅していくと思います。我々国民は間違った方向に進んでいる自:公政権をこのまま維持させてはいけないと思います。
中国自動車大手、「EV向け電池」の大型工場が稼働 広汽集団、将来は全固体電池の生産も目指す
2024年1月4日
中国の国有自動車大手の広州汽車集団(広汽集団)は2023年12月12日、グループ傘下の電池メーカー、因湃電池科技の工場が竣工し、生産を開始したと発表した。
因湃電池科技は2022年10月、広汽集団の子会社で独自ブランドのEV(電気自動車)やPHV(プラグインハイブリッド車)を生産・販売する広汽埃安(広汽アイオン)を中心に、グループ企業の共同出資で設立された。
今回竣工した工場で生産するのは、「弾匣電池(弾倉型バッテリー)」と呼ぶ独自開発のリン酸鉄系リチウムイオン電池だ。さらに、将来はナトリウムイオン電池や全固体電池などの生産も計画している。
2011年から技術を蓄積
弾匣電池は、車載電池パックの内部構造を工夫することで質量・体積当たりのエネルギー密度を高めている。具体的には、質量1キログラム当たり195Wh(ワット時)、体積1リットル当たり450Whを達成し、EVを700キロメートル以上走らせることができるという。
広汽集団がEVの要素技術の独自開発に乗り出したのは、10年以上前の2011年に遡る。まず傘下の研究開発子会社が、車載電池パックと電池制御システムの開発に着手。2017年に広汽埃安が発足すると、同社製のEVやPHVに搭載する電池パックの量産を開始した。
中国の自動車市場では2021年からEVシフトが加速し、広汽埃安はその波に乗って急成長を遂げた。同社の2020年の販売台数は6万台弱だったが、2021年には12万台、2022年には27万台を突破。それに伴い、広汽埃安が必要とする車載電池は大幅に増加している。
そこで広汽埃安は、車載電池のサプライチェーンにより深く関与し、自社が制御可能な領域を広げる戦略をとった。2021年11月、同社は3億3600万元(約68億円)を投じて電池セルの生産ラインを構築。電池セルから電池パックまで自社生産できる体制を整え、量産技術の習熟に努めた。
さらに2022年8月、広汽埃安は中国のリチウム最大手の贛鋒鋰業(ガンフォン・リチウム)と戦略提携を結び、電池の主要原材料の(電池メーカーや商社を経由しない)直接調達を実現した。
因湃電池科技は、こうした長期間の準備と蓄積をベースに設立された。今回竣工した工場の第1期プロジェクトの生産能力は年間6GWh(ギガワット時)。2024年から2025年にかけて生産能力を36GWhに拡大する計画で、総投資額は109億元(約2210億円)を見込む。
鉱山開発から電池リサイクルまで
広汽集団の開示情報によれば、広汽埃安などグループ傘下の完成車メーカーが2023年1月から11月の期間に販売したEVおよびPHVは合計51万台。因湃電池科技の年間供給能力は工場の拡張完了後でEV約60万台分とされ、すでに満杯に近づいている。
広汽埃安は、因湃電池科技を通じた車載電池の自社グループ向け供給にとどまらず、電池関連事業の幅をさらに広げる計画だ。
「次の段階では(電池原材料の)鉱山開発、原材料の生産、蓄電システムの開発、充電ステーションや交換式電池のビジネス、電池リサイクルなどに投資していきたい」。広汽埃安の総経理(社長に相当)を務める古恵南氏は、そう意気込みを語った。
(財新記者:戚展寧)
※原文の配信は2023年12月13日
まるでEV(テスラ)の墓場。シカゴ寒すぎて充電ステーションが凍る
「昨日からだから、もう17時間待ってますね」(Teslaオーナー)
週末から北極嵐で氷点下20~30℃まで冷えこんだシカゴでTesla(テスラ)の急速充電ステーションが凍てつき、電池切れで動けなくなったTesla車が長い行列になっています。
付近の駐車場には、待っているうちに暖房なんかでバッテリーが死んで動けなくなった車がずらり。雪がわびしく降り積もっていて、「充電ステーションが車の墓場と化している」とFoxニュース。
「充電が止まってるステーションがあるし、動いてても40分の充電に2時間かかる」のだそうな。「残量ゼロ。今朝は3時間、昨日も8時間ここにいたのに…」とTeslaオーナーたちは疲労困ぱいです。
しょうがなくTeslaを手で押す人もいれば、レッカー車呼んで最寄りの充電ステーションまでTeslaを運ぶ人まで出る始末。
「シカゴの空港に着いたらTeslaがビクとも動かなくなっていた」という男性は「レッカー移動でインディアナにUターンしながら充電できるところを探す。充電できるステーション、プラグ挿し込んだまま死んで動かなくなったTeslaが1台もないステーションであればなんだっていい」と言ってますよ。
「いつから待ってるの?」とFoxにマイクを向けられた青年は「昨日の午後5時からです」と答えてます。
ということは…だいたい20時間くらいかな?
…ですね。
ひぃいいい…。
いちおうTesla車には寒冷地対応のプレコンディショニング機能もあることはあるんですけどね(冷地到着時に最適な温度で充電できるよう、到着予定時刻から逆算してあらかじめバッテリーを温めておくというもの)。
行列で待ちぼうけの間ずっとバッテリーを温め続けたら、それはそれでバッテリー食ってTesla死んじゃうので、「プレコンディショニングを怠るからこんなことになる」という批判はあまり当たらないように感じます。だって5時間も8時間も20時間もなんだもん。どのみちプレコンディショニングで電池使い果たしちゃうよね。
Source: Fox
中国の太陽電池は脅威ではない―スイスメディア
2024年1月26日
2024年1月23日、環球時報は、「中国の太陽電池は脅威ではなく、むしろありがたいこと」とするスイス紙の評論記事を紹介する記事を掲載した。
記事は、スイス紙ノイエ・チュルヒャー・ツァイトゥングの21日付文章を引用した。同紙は「ヨーロッパを救うことは企業を救うことではない。しかしそれこそがスイスの太陽電池モジュール製造会社、メイヤー・ブルガーのギュンター・エルフルト最高経営責任者(CEO)の狙いなのだ。同氏は工場を2カ所構えるドイツでの補助金を積極的に求めている」と紹介。同氏が太陽電池は戦略的なエネルギーインフラであり、中国に任せてはならないという考えの下、10年前に崩壊したドイツの太陽電池産業を復活させるため、納税者に「公正な競争条件」確保の支援を訴えていると伝えた。
その上で同紙は「中国の太陽電池はヨーロッパにとって脅威ではなく、むしろ宝くじに当たったようなもの」と指摘。中国製太陽電池はメリットがデメリットをはるかに上回るのに対し、企業へのオーダーメードの補助金はデメリットの方が大きいとし「大きな変革の中で、保護主義は最適解ではないのだ」と論じた。
さらに「中国が自国の需要量を上回る太陽電池を生産し、その一部を欧州に流していることは、欧州の企業や消費者にとっては歓迎すべきこと。グリーン技術への移行には多大な費用がかかる上、インフレも進んでいるからだ」と述べるとともに、保護主義を進める米国が中国の太陽電池を封鎖したことで中国製品が大量に欧州に流れ、米国の計画から利益を得ようとしている同社の経営を圧迫するというのは、なんとも皮肉な話だと評した。
同紙は「太陽電池はロケット技術ではない。太陽電池で国のエネルギー供給の安全保障をめぐる論争をするのは、道路の安全を確保するために国内のタイヤ生産に補助を与えるのと同じぐらいばかげている。太陽光モジュールの高い生産力を持つメイヤー・ブルガーは市場が求める太陽電池を、市場に見合う価格で提供すればいい。もっとも、彼らがあまり歓迎されないのは明らかだが」と結んでいる。(翻訳・編集/川尻)
中国の空港で抑留された72歳韓国人事業家、理由は手帳の世界地図に「台湾」表記
韓国人の事業家が、中国の税関で抑留される事件が発生した。事業家の手帳に付いていた世界地図に台湾が独立した国として表示されており「一つの中国」の原則に背いているという理由からだ。
聯合ニュースが25日に報じたところによると、仁川空港を24日に出発して中国・遼寧省の瀋陽桃仙国際空港に到着した事業家のチョン氏(72)は、検査台を通過する際に税関係員らに制止された。税関職員らはチョン氏のトランクを開け、手帳を検査したところ、台湾が独立した国として表示されている地図を発見した。
問題はここからだった。この地図は縦20センチ、横30センチの小さなもので、台湾は「タイワン」とハングルの太字で、台北は「タイペイ」と赤い字で書いてあった。
税関職員らは、台湾が独立した国のように表示されているとの理由で、この地図を問題視した。「一つの中国」の原則に背いているからだ。さらに、チベット一帯の国境表示もあいまいだと指摘した。税関職員らは、調査が必要だとしてチョン氏を事務所に連れていき、抑留した。チョン氏は地図が付いていることすら知らなかったと抗議したが、税関職員らは聞き入れなかった。
チョンさんが声高に抗議し、瀋陽の韓国系住民らに支援を要請すると、税関職員らは約1時間後にチョン氏を釈放したという。税関職員らはチョン氏を釈放する前に手帳から問題の地図を外し、物品保管証を作成してチョンさんに渡すと「帰国の際に取りに来るように」と言ったとのことだ。
チョンさんは「30年にわたって中国で事業をしているが、こんなことは初めて」だとして「中国語を話せるので抗議できたが、初めて中国を訪れる外国人だったらものすごく戸惑うだろうし、怖いと思う」と話した。
瀋陽にある韓国総領事館は、事件の経緯を把握し、税関当局の措置が行き過ぎだと確認されれば再発防止を強く求めると明らかにした。また、中国入国の際には問題になりそうな地図を持ち込まないよう注意を促す予定だ。
イ・ヘジン記者
何もかも大きく中国へ舵を切った日本。最初は「ODA」で中国への謝罪を含めた日本からの投資だったが、最近は中国からの投資をもとに「日本の技術」や「日本の頭脳」を中国へ輸出している。日本の大切な「蔵(研究の成果)」を売ってしまった! 技術の発展に貢献した発明家に贈られる「ヨーロッパ発明家賞」の非ヨーロッパ諸国部門に、世界で最も強力な永久磁石「ネオジム磁石」を発明した佐川眞人さんが選ばれました。 「ヨーロッパ発明家賞」の授賞式が9日、地中海の島国マルタの首都バレッタで行われ、世界で最も強力な永久磁石「ネオジム磁石」を発明した大手鉄鋼メーカー「大同特殊鋼」の顧問・佐川眞人さんが非ヨーロッパ諸国部門に選ばれました。 ネオジム磁石は形状加工が容易で強度も優れているため、携帯電話などの小型電子機器や家電製品、医療用MRI、ドローンなど、強力な磁力が必要な製品に広く使われています。 授賞式のスピーチで佐川さんは、「受賞が材料科学者を志す若い人たちの励みになることを願っています」と述べました。 |
1982年、世界最強の永久磁石【ネオジム磁石】を作った大同製鋼の佐川真人(さがわまさと
)さん
佐川真人氏はノーベル賞候補にも名前が挙がっている。
リチウムイオン電池の開発でノーベル化学賞に輝いた吉野彰氏(よしのあきら)も2019年、非欧州部門で受賞している。その後、韓国・中国に技術を盗まれてしまった。(共同)
再生回数 2,129 回 2022年2月1日
【佐川眞人顧問、「エリザベス女王工学賞(Queen Elizabeth Prize for Engineering)」を受賞】
クリーンな省エネ技術の実現に貢献する世界最強の永久磁石「ネオジム磁石」の発明、開発および世界的な商業化の功績が受賞の理由です。
詳細は大同特殊鋼プレスリリース→https://www.daido.co.jp/about/release...
佐川眞人(大同特殊鋼顧問)が1982年に発明したネオジム磁石は世界最強の磁力を誇り、ハイブリッド自動車・電気自動車や省エネ家電、風力発電等のモーターに搭載され、省エネルギー化・脱炭素社会の実現に貢献していきます。
再生回数 151,281 回 2024年2月24日 #経済安全保障 #高市早苗 #中国
高市早苗大臣に、重希土フリー永久磁石の開発について、お話を聞きました。
高市早苗チャンネルでは、政治に関して幅広く発信していきます。
再生回数 410,157 回 2023年7月14日
高市早苗大臣に、中国人研究員逮捕の件について、お話を聞きました。00:25~ 産業技術総合研究所は高市大臣の所管? 05:25~ 中国籍の職員は何人ぐらいいる? 08:33~ 国立研究開発法人からの情報漏洩を防ぐ仕組みはなかった? 16:09~ セキュリティ・クリアランス制度が法制化されれば事件を防げる? 17:45~ 更に政府が対応できる策は?
再生回数 66,241 回 2023年10月28日
高市早苗大臣に、中国のブイ問題について、お話を聞きました。0:07 中国が日本のEEZ内に設置したブイについて 04:40 フィリピンはなぜブイを撤去できた?
再生回数 63,322 回 2023年11月25日
高市早苗大臣に、中国の「反スパイ法」について、お話を聞きました。00:00 OP 00:43 スパイ容疑で拘束されていた日本人男性は刑が確定した? 01:38 改定された中国の「反スパイ法」の内容とは? 04:40 すべての条文で特に気になる点は? 08:12 中国で日本人が拘束されたら、日本政府は助けてくれる?
再生回数 15,673 回 2023年4月28日 #古本屋 #スパイ #newszero
中国で日本人が拘束される事態が相次いでいますが、根拠になっているのが「反スパイ法」です。26日に改正法が成立し、適用範囲が拡大されることになりました。対象で示されているものが具体的に何を指すかは明らかでなく、摘発が増える可能性もあります。
■少なくとも日本人17人が拘束…なぜ?
有働由美子キャスター
「中国・北京にある建物の写真があります。なんてことのない見た目ですが、私たちが観光に行った時に写真を撮っただけで、スパイと疑われるかもしれません」
小栗泉・日本テレビ解説委員
「この建物は軍の病院です。タイミング悪く政府の高官などが入院していたりすると、場合によってはスパイと疑われて拘束されるかもしれません。2014年に施行された『反スパイ法』があるためですが、26日、これまでよりも適用範囲を広げる改正法が成立しました」
「この反スパイ法により、これまでに少なくとも日本人17人が拘束されました。3月にも製薬大手アステラス製薬の50代の男性幹部が理由も分からず拘束され、今も解放されていません」
■スパイ行為の対象…文書やデータとは?
有働キャスター
「拘束される理由も分からないとなると、現地に住む日本人は怖い思いをします。適用範囲の拡大というのは、具体的にどう変わるのでしょうか?」
小栗委員
「改正法では新たに、国家の安全と利益に関わる文書やデータ、資料、物品を違法に盗み取る行為などをスパイ行為の対象に挙げていますが、この文書やデータが具体的に何を指すのかは分かっていません」
「今年7月に施行されますが、これまで以上に摘発が増える可能性があります」
■独裁的な色合い強める習主席の危機感
有働キャスター
「中国はなぜ今、取り締まりを強化しようとしているのでしょうか?」
小栗委員
「中国に詳しい東京大学の阿古智子教授は、習近平国家主席の危機感の表れだと指摘します。国内の経済がうまくいっていない上、習主席は独裁的な色合いを強めていて、政権に不都合な情報を削除し、国内外に広がらないよう圧力をかけ、けん制しているといいます」
■出張や観光で気を付けるべきポイント
有働キャスター
「私たち日本人が出張や観光に行く時、何に気を付ければいいでしょうか?」
小栗委員
「阿古教授によると、WeChatなど中国製のアプリやメールは中国当局に内容が筒抜けになってしまう恐れもあるので、注意した方がいいようです」
「また古い地図や古書を古本屋で入手したとして日本人が拘束されたケースもありました。これらには今の基準だと出版禁止の内容が含まれている可能性もあり、手を出さない方がいいとのことです」
「街中の写真撮影も、『軍事施設』『撮影禁止』といった表示がある所を撮ると連行されかねないので、慎重な姿勢が必要だといいます」
■廣瀬さん「国際社会で対応を」
有働キャスター
「写真を撮るのも気を付けなければということですが…」
廣瀬俊朗・元ラグビー日本代表キャプテン(「news zero」パートナー)
「いろいろ対策しても不安になりそうだなと思いました。ビジネスや観光でお互いの交流が盛んなので、お互いのことを尊重できるようにしてほしいですし、国際社会としてもしっかり向き合わないといけない問題だなと思いました」
有働キャスター
「法律だとはいえ、運用が不透明となると中国に興味を持った企業や若い人は『怖いな』『行きづらいな』と思ってしまいます。それは決して、中国にとってプラスにならない気がします」
(2023年4月27日放送「news zero」より) #中国 #スパイ #反スパイ法 #改正 #アプリ #古本屋 #日テレ #newszero #ニュース ◇日本テレビ報道局のSNS
バンコクで倒壊のビル、がれき下から15人生体反応 ミャンマー地震
アジア・オセアニア
毎日新聞
2025/3/29 16:56
首都バンコクで建設中の34階建て高層ビルが倒壊した現場で救助活動にあたっているタイ当局の担当者は29日、がれきの下で、約15人の生体反応を検知したと明らかにした。現地メディアが報じた。
担当者は「救急隊が食料と水を届けようとしている。困難なのは、一部ががれきの奥深くに閉じ込められていることだ」と指摘。生存率が大幅に下がるとされる発生から72時間が経過するまでに、救助が必要との認識を示した。【畠山哲郎】
ミャンマー地震 バンコクで倒壊の高層ビルは中国企業が施工と報道
ミャンマー中部で2025年3月28日に発生した地震により、隣国タイの首都バンコクで倒壊した建設中の高層ビルについて、中国経済メディア「財新」は、中国国営建設会社「中鉄十局」が施工を担っていたと伝えた。
タイメディアによると、倒壊したビルは34階建てで、政府の監査委員会のオフィスとなる予定だった。タイ建設大手の「イタリアンタイ・デベロップメント」と「中鉄十局」のジョイントベンチャーが建設。2020年から工事が始まり、30%程度の進捗状況だったという。
さらに財新は、中鉄十局のSNS(ネット交流サービス)アカウントの情報として、高さ137メートルの当該ビルの建設が同社が海外で初めて請け負った超高層建築だったと報じた。
ただ倒壊後、しばらくして中鉄十局のSNSアカウントからはこのビルの建設に関する情報が削除された模様だ。【北京・河津啓介】
ミャンマー地震の死者約700人に、タイの崩壊ビルでも捜索 中国は医療?だけ、各国が資金や支援
2025年03月29日(土)
 |
| 28日に大規模地震が発生したミャンマーの軍事政権は、29日時点で死者が694人と前日から大幅に増え、負傷者も1670人に達したと明らかにした。写真はバンコクの崩壊ビル現場で捜索活動を行う人々(2025年 ロイター/Chalinee Thirasupa) |
[バンコク 29日 ロイター] - 28日に大規模地震が発生したミャンマーの軍事政権は、29日時点で死者が694人と前日から大幅に増え、負傷者も1670人に達したと明らかにした。捜索活動が本格化する中、海外からの援助も届き始めた。
国営メディアを通じた声明で「道路、橋、建物などのインフラが被害を受け、民間人に死傷者が出ている。現在、被災地では捜索・救助活動が行われている」と発表した。
ミンアウンフライン総司令官は前日、あらゆる国から援助や寄付を受け入れるとして、支援を呼びかけていた。
米地質調査所(USGS)の予想では、ミャンマーの死者数は1万人を超え、損害は国内総生産(GDP)を上回る可能性があると推定した。被害の多くは震源地に近いミャンマー第2の都市マンダレーで確認されている。また、震源から約1000キロ離れたタイの首都バンコクでも33階建ての高層ビルが倒壊。がれきの下に閉じ込められた建設作業員の救助活動が29日も行われている。
タス通信は、ロシアが救助隊員120人、医師、捜索犬を派遣すると伝えた。
トランプ米大統領は28日、ミャンマー政府関係者と話したと明かし、何らかの支援を提供すると述べた。
タイ当局によると、バンコクでは9人が死亡、101人が行方不明で、その大半が倒壊したビルのがれきに閉じ込められた労働者だという。