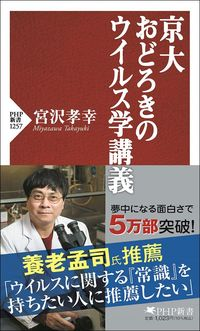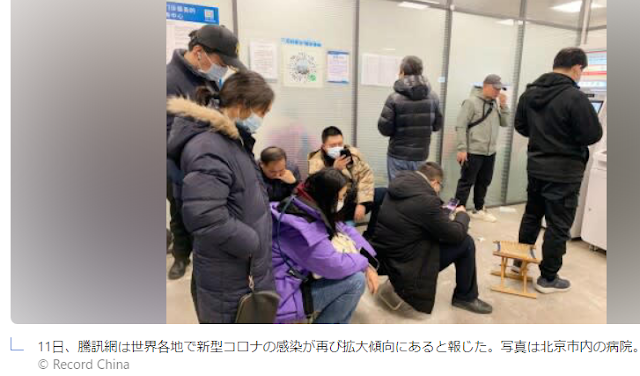❿ 感染した人も再感染しやすい?“第8波”で流行中の「BA.5」「BB1.5」その感染力や重症化率、ワクチン接種の現状を専門医が解説
第8波は?77兆円のコロナ対策費はどこへ消えたのか?
2022/07/28
従来の流行と「BA.5」の違い
今まで日本が経験してきた波は、今回が第7波と呼ばれています。
第1波~3波は元々の武漢由来の変異の無いウイルスが流行していました。第4波はアルファ株、第5波はデルタ株との戦いでした。第6波はオミクロン株、主にBA.1、BA.2によるものでした。
そして今回の第7波は、BA.5に置き換わりつつあります。
今世界では、BA.4とBA.5が同時に流行している国と、BA.5が中心に広がっている国に分かれています。
BA.4とBA.5は感染力が大体同じくらいじゃないかと考えられているので、どちらが先にその国に入ってきたかで流行している株が微妙に異なるようです。
日本の場合は、BA.5が先に入ってきたので、大半が今まで流行していたBA.2からBA.5に変わっていく傾向が見られるはずです。
「BA.5」の感染力と重症化率
BA.5の特徴は、まず感染力が強い。
過去にBA.4やBA.5が流行っている南アフリカからデータが出ていますが、BA.1、BA.2と比較すると1.2倍くらい感染力が強いと考えられています。
デルタ株や当初の変異の無い武漢のウイルスは、肺で増えやすい特徴があるので重症化しやすい、つまり肺炎になりやすいというのがCOVID-19の特徴でした。
今回オミクロン株に変わってからは、上気道といわれる喉や鼻の近くでウイルスが増える特徴があるので、軽症になったと考えられています。
ところが今回のBA.5は動物実験の結果ですが、もしかしたら再度肺で増えやすくなっているのではないかというデータも出ていて、そこが重症化するのではないかという議論と繋がっている点です。
しかし、動物実験に使われている動物は、免疫を極端に抑えられた動物を使うので、同じ結果が人間に関しても起きるかはまだデータが出ていません。
ですので、実際に人間の肺で増えやすいのか、そして動物実験で言われているような18倍以上の感染力があるのかは、未だに分かっていません。
はっきりとしたデータはまだ分かっていませんが、今のところBA.1、BA.2とはそんなに大きな差はないだろうと考えられています。
しかし数がとても増えている国に関しては、やはり死亡率が少し上がっているデータが出ているので、今後データを注視する必要があると考えています。
「BA.5」は免疫をすり抜ける?
免疫をすり抜ける能力は、BA.1、BA.2より少し強いのではないかと言われています。
オミクロン株自体が免疫をすり抜ける力がアルファ株やベータ株より強いと言われていますが、さらにそれを上回る免疫を逃れる能力があるのが、BA.4、BA.5と言われています。
ワクチンの効果が少し落ちてしまうとか、過去にオミクロン株(BA.1、BA.2)に感染したにも関わらず、もう一度BA.5に感染する可能性があるのではないかと専門家は考えています。
ワクチン追加接種の効果
COVID-19との戦いがしばらく続いていますが、感染対策としてはマスクを着けて会話をする、すなわちマスクを外した会話を避けるというものと、ワクチンを打って重症化を防ぐという2本柱は変わっていません。
ワクチンに関しては、基礎疾患をお持ちの方、もしくは高齢の方はちょうど4回目の接種の時期になっています。(2022年7月中旬時点)
この4回目の接種は、感染の予防効果というよりも、重症化の予防効果をより高める。3回目と比較して3~4倍に重症化の予防効果が高まると言われているので、病床のひっ迫、もしくは個々人の入院するリスクを考えた場合には、4回目の接種の適応になっている方は、感染が拡大する時期に是非ともワクチンを検討していただきたいと思っています。
重症化リスクが少ない、4回目のワクチンが回ってこない世代は、実は3回目のワクチンで感染の予防効果は一時的に6~7割くらいに上がります。2回目で終わっている人は、まさしくこのタイミングで3回目を打つメリットは、自分にとっても周りにとってもあります。
特に注意点は、今まで感染した人、感染していない人に関わらず、このワクチン接種回数は勧められていることです。
つまり、「1度感染したのでもう2度とかからない」ということはない。そして「2度と重症にならない」ということはない。
ここがワクチンの接種回数が設定されている理由です。これが現状流通しているワクチンの考え方です。
日本で今最も使われている、ファイザーとモデルナの2社がオミクロン株用のワクチン開発を終えたというプレスリリースを出しています。今まで我々は、武漢からの元々の変異の無いウイルスに対してのワクチンを使っていますが、今後秋、もしくは冬頃にオミクロン用のワクチンが流通してくるだろうと推察されます。
そういった新しいワクチンの効果や副反応も含めて、今後データを集めて注視していく必要がありますが、我々にとっては吉報の1つだと考えています。
この夏 特に注意すべきこと
コロナとの戦いが約2年半続いていますが、去年(2021年)と大きく違うのが、いろいろなイベントが再開されつつある、つまり通常の生活に戻りつつある初めての夏と言えます。
そうするとマスクを外した会話、つまり感染のリスクになる行為が増えてきますし、人から人へ新しい感染の連鎖に繋がるリスクが増えてきます。例えばワクチンの免疫が落ちていると考えられる高齢者や基礎疾患のある方に会う1~2週間前に感染リスクのある行動をたくさんやってしまうと、1~2週間後に次の人に感染させてしまう。しかも高齢者や持病のある方であれば重症化する可能性があります。
夏休みで実家に帰るとか、高齢の方、持病を持っている方に会う直前(1~2週間)の行動というのはこの夏は非常に気を付けないといけないと思います。
VIDEO
感染した人も再感染しやすい?“第7波”で流行中の「BA.5」その感染力や重症化率、ワクチン接種の現状を専門医が解説
山路徹氏 コロナワクチン接種後の死亡数「まだまだ増える」 実兄は接種2日後に急死
2023年8月22日 15:22
ジャーナリストの山路徹氏(61)が2023年8月22日「X」(旧ツイッター)を更新。新型コロナワクチンの接種後の死亡者数に言及した。
厚生労働省の分科会は2023年8月21日までに、新型コロナワクチン接種後に死亡した男女47人について因果関係が否定できないとし、死亡一時金支給を決めた。新型コロナウイルスワクチンで死亡一時金を支給が認められたのは合計で156人となった。
山路氏はこの経緯を報じる記事を引用した上で「徐々に増えています。過去40年余りのワクチン死の総数を上回りました」と過去40年余のワクチン接種による死亡数を上回ったと指摘。
さらに「未審査件数が4000件以上あるので、まだまだ増えると思います 。審査申請をしていない分を含めると、実数はどれぐらいになるのでしょうか。まったく恐ろしい限りです」と今後さらに増加するという見解を示している。
昨年2022年12月に新型コロナワクチン接種2日後に山路氏の兄が63歳で急死。その因果関係を明らかにするよう、訴えていたが、2023年5月17日に兄の接種後死亡報告が厚労省へ提出されたことを明かしている。
山路徹氏 NHKのコロナ報道謝罪を批判「謝罪で済む話ではない」「検証番組を」
2023年5月25日
ジャーナリストの山路徹氏(61)が2023年5月25日、ツイッターを更新。NHKの不適切なコロナ報道に対する姿勢を批判した。
NHKの報道番組「ニュースウオッチ9」で新型コロナウイルスのワクチン接種後に亡くなった人の遺族を、コロナ感染で亡くなった人のように取り上げた問題で、稲葉延雄会長は2023年5月24日の定例会見で「全く適切ではなかった」「深くおわび申し上げたい」と謝罪した。
山路氏はNHK会長の記事を引用した上で「ここまで悪質だと会長の謝罪で済む話ではありません。まずは検証番組をつくり、問題点を徹底的に明らかにして下さい」と厳しく批判した。
昨年12月に新型コロナウイスルワクチン接種2日後に山路氏の兄が63歳で急死。その因果関係を明らかにするよう、訴えていたが、17日に兄の接種後死亡報告が厚労省へ提出されたことを明かしている。
山路徹氏ヤンキー集団による暴行の恐怖を告白
2014年2月18日 08:30
かつて麻木久仁子(51)、大桃美代子(48)との二股交際で話題となったジャーナリストの山路徹氏(52)が16日未明、神奈川県内で大雪の取材をしていたところ、4~5人の暴漢に襲われた。同行した知人のAさんが軽いケガを負ったといい、神奈川県警津久井署が暴行および器物損壊事件で捜査している。山路氏は本紙の取材に怒りをにじませながら恐怖の一部始終を告白した。
トラブルに見舞われたのは16日午前1時ごろ。山路氏が同行者の男性Aさんとそれぞれの車に乗って、大雪被害の取材のため神奈川・津久井(相模原市)を走行中、積雪で2車線の道幅が1車線分ほどに狭くなっているところで対向車に出くわした。
相手は1台のワゴン車で、道の両側には降り積もった雪が集められ、その高さは1メートルあまりあった。山路氏は道を譲ろうとしたが、突然ワゴン車が急停車。窓を開け、いきなり叫んできたという。
「おまえら、誰に断って走ってんだよ! ぶっ殺すぞ!」
いきなり因縁をつけられた山路氏は「ヤバイ」と直感。ただちに車のドアをロックしたが、4~5人のヤンキー集団はゾロゾロと車を降り、山路氏を取り囲んだ。
「テメー出て来いよ!」
山路氏いわく、相手の外見は「いわゆるヤカラ。ヤンキー系」。車内で避難する同氏を尻目に、ヤンキー軍団は車に殴る蹴るの“暴行”を働き、車はボコボコに。
前方で停車していたAさんが制止しようと割って入ったが、ヤンキー集団の1人に捕まり、とっくみ合いのケンカに…。山路氏によると「Aさんは地面に叩き付けられ、全身打撲を負った」。
その後、偶然通り掛った除雪車両のおかげでヤンキー集団は一目散に退散した。思わぬ事態に山路氏は「すぐに110番通報したが、大雪の影響で警察も来てくれなかった…。ソマリアやボスニアで暴漢被害に遭ったことはあるが、まさか日本でこんな目に遭うとは思わなかった」とぼうぜんとするしかない。
山路氏は犯行グループが乗っていた車のナンバーを控え、ドライブレコーダーで事件の一部も録画しており、津久井署に証拠として提出。 現在、同署は暴行および器物損壊事件として捜査中だという。
とんだ災難にも、周囲からは「いろいろあった山路だから狙われた」という声も多い。だが、本人は「相手は無差別だと思う」。本紙記者の「反撃しようとは思わなかったのか?」という問いには、「一番安全なのは車内」と世界での経験から即答 した。
犯行グループについては、以下のように推察する。
「(車から)降りてきたヤツは『ここは俺らの地元だからぁ~』と再三話していたが、ワゴン車のナンバーは県外だった。地元出身の人が自ら『ここは地元』なんて言いますか? おそらく何らかの目的があって、県外から出張してきたのだと思う」
続けて「実際に体験してみてわかることだが、大雪だと警察の目も届かないし、治安はむちゃくちゃ。立ち往生する車がほどんど。そう考えると、車上荒らしや、運転手に対する恐喝、女性だったらレイプなど、大雪で治安がおかしくなった時を狙った犯行の可能性もあると思う」
このところ、記録的な降雪があった関東甲信をはじめ大雪に見舞われている日本列島だが、それに便乗した犯罪集団がついに現れた可能性も十分あり得る。山路氏は「天気予報では今週半ばも雪とある。皆さんも十分気をつけてください」。
積雪で孤立した地域、多くの車が立ち往生する道路。今後は要注意だ。
新型コロナ、終わりはいつ? 医師が賛否両論・炎上覚悟で考察
2022/08/30
賛否両論・炎上覚悟で、新型コロナの今後を私なりに考察したいと思います。まず思い出して頂きたいのが
2020年1月の「ダイヤモンドプリンセス号」事件 です。ウイルスは最初期の「
武漢アルファ型 」でしたが、乗員乗客合わせて3713人を密閉したまま、2ヶ月半の隔離状態におき、うち712例が感染し14人の死者が出ました。途中下船した後に感染した方も何名かおられますが、ざっと5人に1人が感染しました。言い換えると5人中4人は、あの劣悪なウイルス環境の中でも感染しなかったのです。
今にして思えば、地球上の人類の5分の1、つまり16億人が感染しうるということです。8月末の全世界の累計感染者は6億人ほどですが、国によって検査環境は異なりますし、公表していない国、無症状感染者を含めると、すでに地球上で10億人が感染したと推計します。
総人口、今回は16億人のうち7割が感染すれば集団免疫が完成するとして、12億人の感染で集団免疫が獲得されます。そして過去の地球上で起こったパンデミック。これは紀元前のペストや天然痘までさかのぼらなくてはなりませんが、現代の医療水準で考えれば3年、長くて5年で終息すると考えて良いでしょう。
これらから大さっぱに類推すると、新型コロナウイルスのパンデミックは、そろそろ終わりに近づきつつある。第7波の後に「BA2.75」が第8波として大流行したとしても、累計12億人が感染した時点で、新型コロナのパンデミックは終息すると言えるのではないか。とすれば、新型コロナ騒動は年内に終息すると予測できます。 この考え方、いかがでしょう?
◆松本 浩彦 芦屋市・松本クリニック院長。内科・外科をはじめ「ホーム・ドクター」家庭の総合医を実践している。同志社大学客員教授、日本臍帯プラセンタ学会会長。
近づく第8波 東京感染者1.3倍 焦る政府「とにかく接種率を」
新型コロナウイルス感染症の新規感染者数が北海道や東北地方を中心に再び増加に転じ、政府が神経をとがらせている。東京都でも1週間の平均値が前週比1・3倍に跳ね上がり、「第8波」の入り口に立ったとの見方もある。政府はオミクロン株に対応するワクチンの接種促進に力を入れる構えだが、一定数の国民が免疫を獲得するには時間がかかるため冬場の流行に間に合うか予断を許さない。
2022年11月4日にあった都の会議では、2022年11月2日時点の1週間当たりの新規感染者数が4306人で、2022年10月26日時点の3305人から大幅増となったことが報告された。海外で主流になりつつある「BQ・1」や「XBB」などの新たな変異株の割合も増え始めており、 会議メンバーは「今後の急激な増加に注意を払う必要がある」「屋内では気温が低い中でも定期的な換気を 」と、次々に警戒感を示した。
秋が深まるにつれ、北日本では既にリバウンドが顕著になっている。北海道では2022年11月2日時点で1週間当たりの新規感染者数が前週比1・42倍となり、東北6県でも同様の傾向に。寒さに伴って換気が不十分になりがちな上、そもそも呼吸器系の感染症ウイルスは冬季に流行しやすい特性もある。
九州は今のところ横ばいか微増程度で、福岡県の1週間平均値も2022年11月2日時点で前週比約1・16倍と目立った兆候は見られない。ただ政府にコロナ対応を助言する専門家は「全国的な流行拡大が、より早期に始まる可能性がある」と指摘する。
インフルエンザとの同時流行も懸念される中、政府はオミクロン株対応ワクチンの接種率向上を急ぐ。経済活動を維持し、行動制限をできる限り回避したい政府としては、他に有効な手だてもなく、感染動向を静観するしかないのが実情。政府関係者は「とにかく接種率を上げ、『第8波』を迎え撃つしかない 」と焦燥感すら漂わせる。
官邸が2022年11月4日に公表したオミクロン株対応ワクチンの接種率は、2022年11月3日時点で5・9%。「第7波」が一段落し、人々の間に気の緩みが出たり、最新の「BA・5」対応型を待っていたりして、加速していないとみられる。政府内では一時、接種者に特典を与える施策が検討されたものの、「接種できない人が不公平感を持つ」などと異論が出て、その後立ち消えになった。
「コロナが拡大すれば、内閣支持率を押し下げる要因がまた増えてしまう…」と首相周辺。ワクチンが先か、感染者増が先か-。官邸内で数字とのにらめっこが続く。(河合仁志)
日本人では 重症COVID-19にもレムデシビルが有効の可能性
HealthDayJapan 2022/11/14
ICU入室を要する重症の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)患者にも、抗ウイルス薬のレムデシビルが有効である ことを示すデータが報告された。発症9日以内に同薬が投与されていた場合に、死亡リスクの有意な低下が観察されたという。東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科国際健康推進医学分野の藤原武男氏らの研究によるもので、詳細は「Journal of Medical Virology」に2022年9月23日掲載された。
COVID-19に対するレムデシビルの有効性はパンデミックの早い段階で報告されていた。 同薬は現在までに流行した全ての変異株に有効とされてきており、世界保健機関(WHO)のCOVID-19薬物治療に関するガイドラインの最新版でも、軽症患者への使用が推奨されている。ただし重症患者での有効性のエビデンスが少なく、同ガイドラインでも条件付きの推奨にとどまっている。
他方、日本国内では機械的人工呼吸や体外式膜型人工肺(ECMO)を要するような重症COVID-19患者の死亡率が、他国よりも低いことが報告されている。このような日本の医療環境下であれば、海外とは異なる治療戦略が有効な可能性も考えられる。これを背景として藤原氏らは、同大学病院の医療記録を用いて、重症患者でのレムデシビルの有効性を後方視的に検討した。
解析対象は、2020年4月~2021年11月に同院に入院しICU入室を要した患者のうち、新型コロナウイルス検査が陽性のCOVID-19患者で、ステロイド治療が行われた168人。このうち131人(78%)は、観察開始日(入院日または発症日のどちらか遅い日)に高流量酸素または人工呼吸器による治療を受けていた。
解析対象者168人中、96人は発症9日以内にレムデシビルが投与され、37人は発症10日目以降に同薬が投与されていた。他の35人には同薬が投与されていなかった。全期間の院内死亡率は19.0%であり、前記の3群で比較すると、同順に10.4%、16.2%、45.7%だった。なお、解析対象期間の2020年4月~2021年11月は、パンデミック第1波から第5波に相当するが、院内死亡率については大きな違いはなかった。
入院日、併存疾患数、腎機能・肝機能障害、酸素需要量、胸部CT検査による肺炎の重症度などの交絡因子を調整したCox回帰モデルで、レムデシビルが投与されていなかった群を基準として院内死亡率を比較。その結果、同薬を発症9日以内に投与されていた群では院内死亡率が9割低いことが示された〔ハザード比(HR)0.10(95%信頼区間0.025~0.428)〕。一方、発症10日目以降に同薬が投与されていた群では、有意な死亡率低下は観察されなかった〔HR0.42(同0.117~1.524)〕。
重症のCOVID-19患者ではレムデシビルの有効性が認められないとするこれまでの研究の多くは、アジア人以外の人種での研究だった。一方、今回の研究の解析対象は大半が日本人であり、日本人以外(対象の4.8%)も全てアジア人だった。著者らは、「アジア人種の重症COVID-19患者にはレムデシビルが有効である可能性を、実臨床で示すことができた意義は大きい」と述べている。(HealthDay News 2022年11月14日)
Abstract/Full Text
国賊=ゴミ人間、山際氏の自民党コロナ本部長就任、「総合的に判断」=岸田首相 2022年11月4日
国民をなめ切った男が、今度は新型コロナウイルス対策本部長に就任⁉
[東京 4日 ロイター] - 岸田文雄首相は4日の衆院厚生労働委員会で、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)との接点が次々と明らかになり、事実上更迭されたとされる山際大志郎前経済再生相が、自民党の新型コロナウイルス対策本部長に就任した理由について、総合的な判断と説明した。中島克仁委員(立憲民主)への答弁。
中島氏は自民党内にはコロナ対策本部長には田村憲久元厚労相など適任者が他にいるのではないかとして山際氏の就任理由を質問した。
岸田首相は「党の人事はその人物の経歴・経験を踏まえ、総合的に判断したものだ」と説明。
岸田首相はコロナ対策について「政府・与党、組織として対応する。しっかり一体感をもって対応していきたい」と述べた。
米国で新ワクチン審査へ
~2022年秋の世界的コロナ再燃に有効か~
(濱田篤郎・東京医科大学病院渡航者医療センター特任教授)【第46回】
日本では2022年5月末から4回目の新型コロナワクチンの接種が開始されています。これは60歳以上の高齢者などを対象にしており、国民の皆さん全員が受けることはできません。その一方、秋から世界的な新型コロナの流行再燃が予測されており、その流行までに国民全体にワクチンの追加接種を行うという対策も提唱されています。この秋用のコロナワクチンが米国の食品医薬品局(FDA)で6月末に審査される予定です。そこで今回は、秋からの流行に向けたワクチン接種について解説します。
◇秋以降の流行再燃
新型コロナウイルスの流行が始まって2年半が経過しました。21年11月に始まったオミクロン株の世界流行は、22年1月をピークに収束に向かっており、各国は感染対策の緩和を進めています。日本でも6月から本格的な対策緩和が進むとともに、社会経済の再生に向けた動きが始まっています。
このまま新型コロナの流行は終息に向かうのではないか。そんな淡い期待を抱いている人も多いと思いますが、残念ながら22年の秋以降に流行が再燃するという見方が一般的です。その理由は、呼吸器系ウイルスの特徴として寒い季節に流行が拡大しやすいことや、ワクチンの効果が減衰することなどが挙げられます。
では、どのように再燃が起きるのでしょうか。オミクロン株に代わる新たな変異株が発生し、それが世界流行を起こす可能性もありますが、その確率は今のところ高くないでしょう。それよりも、これから秋までオミクロン株の感染者発生が少数ながら続き、その残り火から本格的な流行が起こることが最も考えられます。
いずれにしても、北半球が秋になる10月ごろから世界的に新型コロナの流行再燃が起きることは避けられそうにありません。その被害をできるだけ少なくするには、流行が再燃する前にワクチンの追加接種を行い、ワクチンの効果を再び高めておくことが必要なのです。
◇ワクチンの4回目接種
日本では新型コロナワクチンの接種が21年2月から開始され、主にファイザー社やモデルナ社のmRNAワクチンを使用してきました。このワクチンを2回接種(3~4週間隔)することで基礎免疫が付き、その後は新型コロナの感染や重症化をかなり抑えることができました。そして、現時点までに日本では2回目の接種率が国民の8割以上に達しています。
しかし、その後の調査で、2回接種による効果は半年を過ぎると減衰することが分かってきました。このため、日本では21年12月から3回目の接種が始まります。最近この3回目の接種率が日本ではようやく国民の6割に達するようになりました。
これでワクチン接種は終わりと思われていましたが、早めに3回目の接種を終了した欧米やイスラエルなどのデータから、その効果が半年ほどで再び減衰することが明らかになってきました。そこで、4回目のワクチン接種がイスラエルなどで22年1月ごろから開始されたのです。
ただし、イスラエルでは4回目を国民全員に接種するのではなく、重症化しやすい高齢者などに限定しました。それというのも、現行のワクチンで4回目の接種をしても、現在流行しているオミクロン株の重症化は防げますが、感染そのものはほとんど予防できないことが明らかになったためです。つまり、4回目接種は重症化を予防する目的で、高齢者や慢性疾患のある人に限定するという接種方式になり、欧米諸国もこれに従いました。
こうした経緯で、日本でも22年5月末から重症化を起こしやすい高齢者や慢性疾患のある人に限定して4回目の接種が行われています。
◇現行のワクチンで秋の流行は防げない
このように、現行のワクチンを使用する限りは重症者の発生は防げるとしても、秋以降に予想される流行再燃を防ぐことは難しいようです。「感染者数が増加しても、重症者が出なければいいのでは」という考え方もありますが、感染者数が増えれば若い人でも重症化しますし、医療への逼迫(ひっぱく)も生じます。こうした事態を回避するために新しいワクチンが必要になっています。
では、なぜ現行のワクチンは効果が弱くなってしまったのでしょうか。mRNAワクチンは効果が持続しにくいという見解もありますが、それよりもワクチンの製造に用いられたウイルス株に問題があるようです。現行のmRNAワクチンは、2019年12月に中国の武漢で発生した新型コロナウイルス(武漢株)を用いています。現在流行しているオミクロン株と共通する点もありますが、ウイルスはかなり変化しています。つまり、現在のオミクロン株を用いてワクチンを製造すべきなのです。
実は、ファイザー社やモデルナ社はこうしたワクチンを既に開発しており、その臨床治験も2022年初から開始しています。
◇米国での審査は6月末
これが秋用のワクチン で、米国の食品衛生局(FDA)は、その承認のための審査を6月末に行うと発表しました。
モデルナ社は6月上旬に、審査の対象なるワクチンの概要を発表しており、オミクロン株に加えて従来の武漢株も含めた2価ワクチンを製造しています。 その効果を接種後の抗体価の上昇で見れば、現行のワクチンよりも十分高くなるようです。ファイザー社からはいまだ概要が公表されていませんが、6月末の審査で明らかになるでしょう。
この秋用ワクチン をFDAが承認した場合、米国だけなくヨーロッパ諸国などでも、その接種が始まることでしょう。ただし、国民全体に接種を行うか否かは審査に提出されるデータによると思います。
両社のワクチンが有効であったとして、日本での接種は秋までに間に合うでしょうか。日本政府は22年5月に医薬品の緊急承認制度を創設しました。この制度を用いれば、海外で承認された医薬品を短期間のうちに国内承認することもできます。今回のワクチンがその対象になれば、秋までに手続きは間に合うでしょう。そのときは、国民全体を対象とした4回目の接種になることも考えられます。ただし、問題は新しいワクチンがそれまでに国内にどれだけ準備されているかです。
◇今後のワクチン開発
このように、22年の秋に予測される新型コロナの流行再燃に当たっては、新たな秋用のワクチン を用いて被害を最小限に抑えていくという戦略が取られるでしょう。しかし、長期的に見れば、効果を長く持続できるワクチンや、全ての変異株に効果のあるワクチンなどの開発が必要になってきます。 また、次の冬に流行するウイルス株が予測できれば、インフルエンザワクチンのように、早い時期に次のワクチンの開発製造に入ることもできるはずです。
現時点で、日本では3回目の接種を受けていない人が国民の3割以上おり、高齢者などには4回目の接種も始まっています。国民の皆さんは、既に実施されている接種をまずは終了していただき、秋以降のさらなる接種に備えるようにしてください。(了)
濱田 篤郎 特任教授
濱田 篤郎 (はまだ あつお) 氏
東京医科大学病院渡航者医療センター特任教授。1981年東京慈恵会医科大学卒業後、米国Case Western Reserve大学留学。東京慈恵会医科大学で熱帯医学教室講師を経て、2004年に海外勤務健康管理センターの所長代理。10年7月より東京医科大学病院渡航者医療センター教授。21年4月より現職。渡航医学に精通し、海外渡航者の健康や感染症史に関する著書多数。新著は「パンデミックを生き抜く 中世ペストに学ぶ新型コロナ対策」(朝日新聞出版)。
中国に「大変失望した」 WHOテドロス事務局長が表明
2021/1/6
中国から推薦されてWHOの事務局長になった男。テドロス事務局長が中国に牙をむく。
【ロンドン=板東和正】世界保健機関(WHO)のテドロス事務局長は2021年1月5日のジュネーブでの記者会見で、新型コロナウイルスの起源解明に向けた国際調査団に対し、中国が入国を許可していないことを明らかにし、「大変失望した」と表明した。テドロス氏が新型コロナの問題をめぐり、中国の対応を表立って批判するのはまれとみられる。
WHOは昨年2020年12月、日本を含めた各国の専門家による調査団を今月第1週に中国に派遣すると発表。各団員は今月2021年1月5日に中国に向けて出発し、中国内で自主隔離期間を経て、新型コロナの震源地となった湖北省武漢市に入る予定だった。
しかし、テドロス氏は同日の会見で、中国当局が調査団の入国に必要な認可を出していないことがこの日に判明したと発表した。WHOで緊急事態対応を統括するライアン氏によると、調査団のうち2人は既に出国したが1人は引き返すことになり、1人は経由地にとどまっている。他の団員も自国を出る前に渡航できなくなったという。テドロス氏は会見で、「(調査団の派遣)はWHOにとって最優先事項だ」と中国当局に訴えたと発言。「できるだけ早期に調査が開始されることを切望している」と述べた。
これまで新型コロナの対応をめぐっては、テドロス氏が中国を擁護するかのような発言が目立っていた。テドロス氏がWHOの局長に上り詰めたのは中国の支援があったからなのだ。
昨年、感染防止策で中国の初動の遅れを非難する声があがった。
コロナ対策費 過大な予算の温床にするな
2022/11/11
新型コロナウイルス対策を巡り、税金の無駄遣いや過大な予算計上が明らかになった。原因を究明し、今後の予算執行に生かさねばならない。会計検査院が2021年度の決算検査報告書を公表した。無駄遣いや不適切な処理は455億円に上り、このうちコロナ関連が102億円を占めた。
コロナ患者の病床を確保した病院に交付金を出す事業では、調査対象の3割にあたる32病院が、計55億円を過大に受給していた。
病床を空けておく分の費用を補償する制度だが、患者の退院日を誤って「空き」に算入するなどしていた。病院側が受給要件を理解せずに申請し、国や自治体の点検も不十分だった。各病院は過大分を返納するという。
一連のコロナ対策では、申請の手続きや審査を簡素化した。急場の対策としては必要な措置だったろうが、制度が複雑でわかりにくかったうえ、チェック機能も働かなかった点は反省が必要だ。
感染拡大による休校の際、インターネット環境のない家庭に学習用ルーターを貸し出す事業では、10万台が一度も使われなかった。休校時に貸与を求める家庭が少なかったためとみられ、9億円超の補助金が生かされず無駄になった。
こうした事例は氷山の一角にすぎない。他にも同様のケースがないか各自治体で調べるべきだ。
政府は19~21年度に、コロナ対策で約94兆円の予算を計上したが、21年度末時点の使い残しが約18兆円にも上った。各事業のニーズを予測するのが難しいとはいえ、「規模ありき」で予算を膨らませた面も否めまい。
使われなかった予算は、不用額として国庫に返納されたり、翌年度に繰り越されたりするため、無駄になったわけではないが、次の予算編成が巨額の使い残しをベースにどんどん膨らんでいることは問題が大きい。また2兆円がどこに消えたのか、分かっていない。
政府は経済対策として、歳出総額約29兆円の22年度第2次補正予算案を決定した。
その結果、当初予算を合わせた22年度の一般会計総額は、コロナ禍で巨額の支出を強いられた21年度に迫っている。「規模ありき」の財政運営は変わっていない。
当初予算より財務省の査定が甘い補正予算で歳出を上積みする手法が常態化している。物価高への対応が重要だとしても、多額の使い残しを生むような大盤振る舞いは続けるべきではない。検査院の指摘を機に、財政運営の正常化を図ってもらいたい。
コロナ予備費12兆円、使途9割追えず 透明性課題
国費解剖 2022年4月22日 18:00 (2022年4月23日
政府が新型コロナウイルス対応へ用意した「コロナ予備費」と呼ばれる予算の使い方の不透明感がぬぐえない。国会に使い道を報告した12兆円余りを日本経済新聞が分析すると、最終的な用途を正確に特定できたのは6.5%の8千億円強にとどまった。9割以上は具体的にどう使われたか追いきれない。国会審議を経ず、巨費をずさんに扱う実態が見えてきた。
12兆円余りをおおまかに分類すると、医療・検疫体制確保向けの4兆円に次いで多いのが地方創生臨時交付金として地方に配られた3.8兆円だ。同交付金をめぐってはコロナ問題とこじつけて公用車や遊具を購入するなど、疑問視される事例もある。自治体が予備費を何に使ったかまで特定するのは難しい。
政府は4月下旬にまとめるガソリン高などの物価高対策に、2022年度予算のコロナ予備費(5兆円)の一部を充てる構えだ。仮にコロナ問題と関係の薄いテーマにコロナ予備費が使われれば、予備費の本来の趣旨に反する恐れが強い。
通常、政府は年金の支給など特定の政策を目的にした歳出を細かく積み上げて予算案をつくり、国会審議を経て出費できるようになる。その例外が予備費だ。金額だけあらかじめ計上しておき、使い道は政府の閣議だけで決められる。
政府は最近は年5000億円程度の予備費を準備し、災害など不測の事態に備えることが多い。だが、コロナが広がった20年春以降の20年度補正予算で9.65兆円という異例の規模の予備費をコロナ向けと銘打って創設。21年度と22年度の当初予算と合わせ3年で総額20兆円弱に達した。
そのうち12兆3077億円は実際に執行し、国会に使い道を報告した。日本経済新聞は国会提出資料や省庁への取材で何に使われたか詳細に解明しようと試みた。各省庁や自治体が予備費を具体的に何に使ったか、最後まで確認できるものは3つの政策項目、計8013億円だけだった。
予備費の最終的な使い道がつかみにくいのは、予備費を割り振られた省庁が当初予算や補正予算などすでにあるお金と予備費を混ぜて管理するケースが多いからだ。会計検査院でさえコロナ関連をうたう巨額の予算がどう使われたかの全体図はつかめていない。
例えば、厚生労働省がワクチン接種の体制づくりへ自治体に配る補助金だ。ほかの経費と分別管理しておらず、予備費がどの自治体に行ったかまでは分からない。ワクチン購入費のように「企業との秘密保持契約の関係で公表できない」(厚労省)項目もある。
予備費3119億円を振り向けた観光需要喚起策「Go To トラベル」は感染拡大でストップした。追加投入した予備費を上回る額が使われず、約8300億円が滞留しているとみられる。
コロナ禍のような危機に際し、柔軟で機動的に使える予備費にも意義はある。ただ、国内総生産(GDP)の数%に相当する巨大な予算を国会審議を経ずに執行できる仕組みは透明性に懸念が残る。乱暴な使い方をけん制する意味でも、外部から適切にチェックできる体制が本来必要だ。
一橋大の佐藤主光教授は「今の仕組みでは事業ごとの費用対効果だけでなく、コロナ予算の正確な規模すら検証できない」と指摘。歳出膨張への危機感が広がっても抑制する道具が欠けているとして「お金に色をつけて追跡するには、公会計のあり方自体を見直す必要がある」と話す。
厚生労働省よ!日本国民をぬか喜びさせるなよ!加藤勝信厚生労働省大臣!
塩野義のコロナ経口薬「ゾコーバ」緊急承認
レポート 2022年11月22日 (火)
厚生労働省の薬事・食品衛生審議会の薬事分科会と医薬品第二部会の合同部会(分科会長:太田茂・和歌山県立医科大学薬学部教授)は2022年11月22日、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の経口治療薬「ゾコーバ錠125mg」 (一般名:エンシトレルビルフマル酸)の緊急承認を認めた(資料は、厚労省のホームページ)。加藤勝信厚労相は直後に緊急承認し、12月初頭から医療現場で使用できるよう供給を開始するとの見通しを示した。しかし軽症患者は保健所に連絡しても自宅待機をさせられるだけで、医者の診断、診察を受けない限り処方箋=「ゾコーバ」はもらえない。今までと何も変わっていない模様。
塩野義製薬が2月に申請してから、この日が3回目の審議だった。5月に施行した改正薬機法で新たに認められた「緊急承認」を適用した審議の対象で、日本初の承認となった。同剤は7月、同部会で有効性の推定をするには不十分と結論づけられ、「審議継続」となっていた。しかし良い薬でも実際の医療現場で、患者の症状が出てから三日以内に「ゾコーバ」を飲めるような医療体制の仕組みを「変革」してから、国産初の薬を使いやすくする方法を考えてほしい。
加藤厚労相は「国内企業が創製した初の経口薬で、使用対象者はこれまで承認されている経口薬と異なり、重症化リスク因子を有しない患者を含むとされている。対象が広がるということだ。新たな治療の選択肢として期待する。国内企業が製造販売する薬品でもあるから、安定供給の観点からも大きな意味があると考えている」と緊急承認の意義を強調した。
厚労省は塩野義製薬から100万人分を購入する契約を既に結んでおり、12月初頭には医療現場で使用できるよう、供給を開始する予定。パキロビッドパックの処方実績がある医療機関から供給を開始する。その後は特段の要件を設けず、各都道府県が選定した医療機関での処方や薬局での調剤ができるようにする。
PMDA「有効性を有すると推定するに足る情報は得られた」
臨床試験では有効性の主要評価項目は、▽倦怠感または疲労感、▽熱っぽさまたは発熱、▽鼻水または鼻づまり、▽のどの痛み、▽咳――の5症状が快復するまでの時間とした。塩野義製薬が提出した臨床試験第3相パートの速報結果によると、5症状が快復するまでの時間はプラセボ群で192.2時間であったのに対し、同剤投与群では167.9時間だった。こうしたデータに基づき医薬品医療機器総合機構(PMDA)は、「現時点での結論であることに留意する必要はある」と断りつつも、「有効性を有すると推定するに足る情報は得られた」と結論づけた。
同剤は、新型コロナウイルス感染症の重症化リスク因子のない患者に投与可能な初の経口治療薬となる。
軽症から中等症Iまでの患者の治療選択肢となる。日本感染症学会はガイドライン案で、「一般に、重症化リスク因子のない軽症例の多くは自然に改善することを念頭に、対症療法で経過を見ることができることから、(中略)症状を考慮した上で投与を判断すべき」とした。具体的には、高熱・強い咳症状・強い咽頭痛等の書状がある者に処方を検討すること、としている。
有効性の「推定」を持って行われる緊急承認。この期限は1年で、塩野義製薬は1年以内に臨床試験の第3相パートの総括報告書等を持って承認申請する必要がある。申請がされてから、改めて有効性を「確認」できるか審査する。
妊婦は禁忌、併用禁忌は36種類
非臨床試験において胎児に奇形を示唆する所見が認められており、潜在的な催奇形性リスクを有するとして妊婦または妊娠している可能性のある女性への投与は禁忌とした。また、併用禁忌は36種類ある(詳細は、添付文書)。
薬食審委員の山梨大学学長の島田眞路氏は緊急承認制度の適用要件に「当該医薬品の使用以外に適当な方法がないこと」とあるのに対し、新型コロナウイルスに対する経口薬としては米メルクのラゲブリオと米ファイザーのパキロビッドパックがすでに承認されていることを指摘。パキロビッドパックは政府が200万人分を確保したが、5万6000人への投与にとどまっていることなどから、「既にある薬の使い方をしっかり指導するべき。代替の薬はある」と主張した。これに対して厚労省は、同剤は承認されれば初の国産経口薬となることから、既に承認された薬剤と比べ安定した生産・供給が見込める点で代替の薬剤はないという認識を示した。
既存の経口薬の投与が進まない現状については岐阜医療科学大学薬学部教授の宗林さおり氏も、「併用禁忌が多く使われないというケースが多い。ゾコーバでも同様の事態にならないか懸念している」と発言。重症化リスク因子のない患者にも投与可能であれば、実際の医療現場で使いやすくする方法を考えてほしい、と要望した。
◆同剤の緊急承認申請を巡るこれまでの経緯(全て2022年)
・2月
塩野義製薬が同剤の承認申請
・6月22日
薬事・食品衛生審議会医薬品第二部会「さらに慎重に議論を重ねる必要がある」と結論づける。
・7月20日
薬事・食品衛生審議会の薬事分科会と医薬品第二部会の合同部会で「審議継続」に。
PMDAは「本薬によりウイルス量が減少する傾向が認められていることは否定しないが、申請効能・効果に対する有効性が推定できるものとは判断できない」と報告。部会として「有効性の推定」をするには不十分と結論づけた。新たなデータの提出を待ち再び審議することとした。(『塩野義のコロナ経口薬「ゾコーバ」緊急承認ならず』)
・9月28日
塩野義製薬は同剤の臨床試験第3相パートで新型コロナの5つの症状が消失するまでの時間が有意に短縮できたと発表した。(『塩野義、コロナ経口薬「ゾコーバ」臨床試験で効果ありと発表』)
「免疫が落ちてきている」第8波懸念される中、専門家組織・脇田座長が語る“いまやるべきこと”とは?
2022年11/21(月)
「いわゆる第8波の可能性もある」
加藤厚労相は17日、厚労省に対策を助言する専門家組織「アドバイザリーボード」との会合で冒頭、こう指摘。更に脇田座長も「年内にも流行のピークが来る可能性がある」と述べ、ピーク後も感染者の下げ止まりが続き、医療への負担が高まる事態に懸念を示した。
いつになったら平穏な日常が戻ってくるのか。
現在、国立感染症研究所のトップであり「アドバイザリーボード」の座長として、これまで国の感染拡大抑止の第一線で活躍されている、脇田隆字所長にこれまで抱いてきたコロナに関する疑問を率直に聞いた。
前編では、脇田所長が“第8波”についてやインフルとの同時流行の可能性、10月から始まった乳幼児向けのワクチンなどについて答える。
“第8波”懸念も「年中行事」「免疫力低下」
2022年11月16日午後、全国の感染者数が2日連続10万人を超えたこと受け、日本医師会は「第8波に入った」とし、危機感を示した。専門家からも再び感染流行の発言が相次ぐ中、現在の状況はどのような段階にあるのだろうか。
「非常に難しい段階にあると思います。これまではそうは言っても、人の接触はかなり抑えられていました。夜間の滞留人口で見ると、2019年(コロナ前)と比べると、東京でも9月10月で4割くらい夜間の人出が少ない。
2020年の夏頃に、やはり繁華街の接触はクラスター感染を起こしやすいということが認識され、夜飲みに行く回数を減らしたり、そういった控える行動に繋がっていたと思います。
ただ、それが今ここにきて、当然のことですが、やっぱり動きたい、旅行にも行きたいと。さらに旅先では色々な活動をしたいわけです。しかし、そうすることで、人と人の接触は増えてきてリスクになる。
そして、普段会わないような人と接触する機会が増える“年中行事”というのがやはり重要なポイントになります。人の接触という意味では非常に制御が難しいのです」
さらに、“非常に難しい段階”という背景にはある事情が関係しているという。
「実は免疫に関しては、今すごく落ちてきているという情報があります。ですので、ここはワクチン接種を進めて免疫を高めていかないといけない。
新型コロナウイルス感染症の場合、ワクチンでも自然感染でも、得られた免疫が時間とともに低下していくことがわかっています。
日本でワクチン接種が重要な理由は、世界、特に欧米と比べるとこれまで感染が少ないのです。欧米だと、7割8割、少なくとも5割以上の国民がすでに感染しているという状況なので、自然に感染して、免疫ができている。
一方で、日本はまだ2割とか3割。 そんな中、どうやって免疫をつけますかと言えば、ワクチン接種を進めることが重要になってくるということです」
オミクロン株でも「免疫がなければ重症度はそれほど下がっていない」
オミクロン株になってから感染力は強まった一方、病原性が低くなった印象を受ける。ただ、脇田所長はワクチンの重要さとともに、警戒を呼び掛ける。
「ワクチン接種の重要性を示す例として、オミクロン株が流行した香港では、日本と異なるワクチン接種行動をしているのです。
日本と違いお年寄りがあまりワクチンを打っていない。その結果、オミクロン株に感染して非常に多くの方が亡くなっているという現実があります。
ですから、オミクロン株で『重症度が減る、低くなった』という風に思われている方は多いと思いますが、実は免疫のない状態で感染するとそこまで重症度は下がっていないことがわかっています。
これまで感染したことがなく、またワクチン未接種で感染するとオミクロン株の重症度はデルタ株の半分程度とも言われていますけど、感染力が圧倒的に高いので、流行が拡大して感染者が増えれば、当然亡くなる方、重症になる方も増えていく ということになります」
インフルとの同時流行懸念も
さらに今年の冬は「インフルエンザとコロナの同時流行」も懸念されている。
「今これだけ国際的な交流であったり、国内の移動というのが増えてきた中で、毎年冬にはどうしてもインフルエンザが流行します。従って“コロナとの同時流行の可能性”というのも指摘されていて、我々は懸念しているところです。ただインフルが本当に流行するのかを予測するのは非常に難しいです」
一方で、コロナに関しては、現在の状況ならではの懸念があるという。
「新型コロナに関していえば、流行状況を規定しているのは、主に(1)免疫、(2)人々の接触、(3)どういった変異株か、というところです。この3つの中で、今特に変化してきているのは“免疫の状況”と“接触パターン”です。
“免疫”は、7月8月のオミクロン株BA.5の大流行があって感染による免疫が上がり、更にはワクチン接種も進み、免疫が高まったが、今徐々に落ちてきているような状況にある。
一方で、“接触”に関しては、皆さん出かけるなどして増えてきていると思います。さらに我々がモニタリングしている、繁華街の夜間の滞留人口も上がってきています。今後さらに接触が増えていく可能性が出てきているという状況です
また、これから冬に向かって換気がしにくくなります。換気が悪い屋内でマスクなしの会話はリスクになります」
こうした状況を踏まえ、脇田所長は、「いかにワクチン接種を推進し、免疫をつけていくかということが重要になる」という。ただ、そこには難しい国内の現状がある。
ワクチン3回目接種で、オミクロン株への免疫がつく
実際、高齢者の4回目接種は進んでいるが、若者の3回目が進んでいない。若者の間では、「感染しても風邪程度。軽症で済むからもう打つ必要もないんじゃないか」という声も聞かれる。
「正直、まだ、ただの風邪ではないと思います。もちろん軽く済む人は多いけれども、それはワクチンを2回打っているから軽く済んでいるということも多くて、これまでのデータで言えば、やはり風邪、インフルとは違って後遺症で悩む方もたくさんいます」
また、脇田所長は、これまで打ってきたワクチンは従来株のもののため、2回目までだと、なかなかオミクロン株の感染予防ができないと話す。
「ただ、3回目を打ってもらうことによって、かなりオミクロン株にも対応できる免疫がつくというのはこれまでの研究でわかっています。さらに、従来株とオミクロン株の2つの抗原が入ったワクチンが打てるようになりましたから、これでオミクロン株に対してもしっかりと対応できるようになりました」
乳幼児へのワクチン接種可能に…懸念は?
その一方で、多くの親が悩んでいるのが、子どもへのワクチン接種だ。
10月から、生後6カ月~4歳の乳幼児もワクチンを打てるようになったが、「子どもや赤ちゃんに打つのは心配だ」という声が聞かれる。
「そこは非常に難しい問題ですね。やはりどうしてもワクチン接種は副反応がある。発熱、アレルギー、心筋炎の問題だったり。
ただ、今一番低年齢の6カ月~4歳を対象に打つワクチンは3回打つのですが、臨床試験のデータを見る限り、これまでの新型コロナワクチンより副反応が多いと言うことはなく、安全性に重大な懸念はないとされています」
これまで比較的、“小児は感染をしにくい”ということが言われてきた。しかし、オミクロン株になって感染力が非常に強く、小児の感染も増えてきたという。
「特徴的なのは、感染をして熱を出し、それによって熱性けいれん、脳症であったり、重症化する小児も報告されてきています」
さらに、こんなデータも。
「今回、国内の20歳未満の新型コロナによる死亡例に関する疫学調査をまとめたのですが、ワクチン接種対象の年齢の多くの小児の死亡例では未接種でした。
やはり感染をするということはウイルスが体に入って増殖するわけですから、体内では色々な悪い反応が起こる可能性がある。その前に免疫をつけておくと、それによって抵抗力ができるので、免疫のない状態で感染を受け止めるよりも、リスクは下がります」
脇田所長は、改めて“ワクチン接種の重要性”について強調する。
「ワクチン接種により自分の感染や重傷化を予防できますが、同時に流行を抑えていく、そして医療を守っていくことに繋がるので、自分一人の問題だけではなくて、家族や自分の周りの仲間、そしてこれからの社会のためでもあるということも、認識していただきたいです」
後編では、なぜ日本ではなかなかマスクが外せないのか、薬の開発状況、そして最も知りたい「コロナはいつ終わるのか?」について聞く。
「コロナは終わらない?」専門家組織・脇田座長が考える“脱マスク”とコロナとの付き合い方
2022年11月21日
感染が再び拡大し、“第8波”に入ったとの意見もある。
コロナが確認されて間もなく3年。一体いつになったら平穏な日常が戻ってくるのかーー。
現在、国立感染症研究所のトップであり「アドバイザリーボード」の座長として、これまで国の感染拡大抑止の第一線で活躍されている、脇田隆字所長にこれまで抱いてきたコロナに関する疑問を率直に聞いた。
前編で、“第8波”やワクチンの重要性などについて語った脇田所長。後編では、なかなか進まない“脱マスク”の現状やコロナの今後、そして、いつ終わるのかという最も知りたい質問に答えた。
海外と日本“社会の受け止めの違い”
海外の映像を見ていると、街を歩いている人も人混みでもマスクなし、スポーツでは、満員のスタジアムでマスクなしで応援と、“脱マスク”が日常だ。日本も同じようにできないのだろうか。
「これはもう国によって“社会の受け止めの違い”です。メジャーリーグに行ってマスク外して応援するというような日常をどの程度取り戻したいか。
日本でも野球場に普通にお客さんが入っていますが、なるべく“マスクをして大声出さずに”スポーツ観戦を楽しみましょうということでやっているわけですよね」
脇田所長は、パンデミックを“どう受け止めるか”がポイントになるという。
「“被害抑制“という考え方があって、これを『ミティゲーション』と言いますが、“行動規制などはかけず、医療で受け止める”ということです。
そうなると感染者は増えますが、社会経済活動は抑制されず、普通に活動できます。ただ、当然のことながら医療への負担が大きいし、死亡者も増える。
イギリスも当初『ミティゲーション』でいこうとしましたが、それをすぐにやると感染者や医療費に莫大な被害が出る、ということで舵を切ってロックダウンに入った経緯があります」
その後、イギリスは今年2月にコロナ規制を全て撤廃し、現在は、「ミティゲーション」という形で社会活動している。
“行動規制”で医療で受け止められる程度に感染者数を抑制
日本でも2020年、“全く行動規制をしなかった場合”の死者数の想定が出された。
「よく記憶していると思いますが、圧倒的な感染者増加により相当の死亡者が出ますよというシミュレーションでした。これに対して、『実際そうならなかったじゃないか』という声も聞かれますが、何も対策をしなかったらそれだけの死者が出た可能性があったということです。
しかも、それだけの重症者の治療を日本の医療のキャパシティーで受け止められるかというと全く受け止められない。日本はロックダウンできない中で、何とか感染者数を抑えて、その間に医療のキャパシティーも増やし、受け止められる程度に抑えていきましょうという考え方でずっと来ているわけです」
脇田所長はこう続ける。
「今は政府からの規制による緊急事態宣言や重点措置のような行動規制ではなく、市民一人一人の自発的な感染対策によって流行をある程度抑えていくことが重要な状況です。
普通に生活できるし、スポーツ観戦やコンサートなどのイベントにも行けるけど、リスクや場面に応じてマスクを含めた基本的な感染対策をしましょう、というようなところが大事と感じます」
結局、日本の場合はまだ生活をする上で、ある程度の我慢が求められそうだ。
「感染力」は頭打ち、今後の進化は“免疫逃避”
オミクロン株も様々な変異株がでてきて、その度に感染力や重症化のリスクなどについて心配になるのだが、今後、コロナはどう進化していくのか。
「新型コロナは、感染力についてはもう頭打ちではないかという研究があります。今後は、ウイルスが“免疫を回避”していくような方向性に進化することが予想されます。
ただ、感染伝播力がある程度頭打ちになって、免疫逃避の方に向かって進化した場合、それが病原性にどう関わってくるのかはまだよくわからないです。
それでも、多くの人がワクチン接種や自然感染により免疫をつけることにより、重症化を抑えることができるので、見た目の重症度は下がっていくことも期待できます」
脇田所長によると、ウイルスは自ら増殖することができないため、必ず、他の細胞に感染して増えていくという。そう考えると、感染した人が全員死んでしまっては繁殖できない。そのため、ウイルス自身が生き延びるために弱毒化していくことがある。
しかし、新型コロナの場合では、そもそも感染者がほとんど亡くなるわけではなく、現状ではさらに軽症が多くなり、中等症、重症、亡くなる人もいるなど患者の症状のばらつきを考えると、ウイルスの本質的な病原性が落ちる方向に進化するかどうかは予想しにくいという。
“ゼロコロナ”は難しい
コロナが日本で確認されてからまもなく3年になるが、いまだにコロナに振り回される日々が続いている。日本の感染症研究の最前線にいる脇田所長は、ここまで長引くと想定していたのだろうか。
「ほとんどが事前に想定できないことばかりですが、ここまでの大規模な流行を予想していませんでした。
また、コロナの感染流行が始まってからの数カ月間、ゼロコロナは可能か議論をしていましたが、封じ込めは相当難しいだろうという考えでした」
それは、このコロナの“特性”にあるという。
「感染症の特性として、SARS(2003年に流行)と比べるとよくわかりますが、SARSの場合は感染するとほとんどの感染者が重症肺炎を起こすか死亡してしまう。
しかも、感染性を持つのが発症してからです。つまり、そういう症状がある人を見つけて検査して診断し、隔離することでその先の感染を止められます。つまり封じ込めができる。
一方で、新型コロナの場合は無症状のままで感染性がある人がかなりいる。また、発症する人も発症する前から感染性となるので、発症した人を検査で陽性で見つけて隔離するだけでは封じ込めはできないということです。
さらに、市中で無作為に検査することによって陽性者をみつけて隔離することで流行を止めるためには、全住民に毎週1~2回の頻度で検査が必要との研究もありました」
こういったことから、当初からゼロコロナは難しいと判断し、最初の緊急事態宣言の時も“いつ解除するか”が議論になったという。
「もっと徹底的に感染者がゼロになるまで封じ込めてから解除するべきだという意見もありましたが、そもそもゼロにできない感染症だから、一定程度のところで解除していくべきではないかということになりました」
薬の開発は?
こうした中、期待されるのがコロナに効く“薬”だが、現在、どうなっているのだろうか。
「薬は今、重症化を防ぐ飲み薬と、注射薬があります。ただ、その対象は重症化しやすいリスクのある人となっているので、いわゆるインフルのタミフルのような薬が欲しいねっていうのは元々お医者さんも言っているし、そういった飲み薬が出てくれば状況は変わるんじゃないかとも言われている。
製薬メーカーも一生懸命努力していて、開発は進めているので、有効性がしっかり確認されれば、使われるようになります」
しかし、ワクチンに比べて、どうしても時間を要しているように見えてしまう。
軽症者から飲めて副作用なしのメイドインジャパンの薬「ゾコーバ」(イメージ写真)
「薬の開発も始まってから3年、ちゃんと進んでいます。最初、抗体薬がデルタ株の時は良く使われていたんですけど、それもかなり早く開発されて、一定の効果がありました。
ところが、コロナの変異が進んでなかなか効果がなくなってきた。ですので、薬の開発は決して遅いわけではく、これからも有効性が認められればそういった薬が出てくるということです」
コロナはいつ終わる?
最後に、脇田所長に今回一番知りたかった質問を直球でーー。
「コロナはいつ終わるんでしょうか?」
「ごめんなさい、正直言うと“簡単には終わらない”と思います。つまりゼロコロナになるのかという話と同じであれば、なかなか無くすことは難しいです。
現状はワクチンや自然感染による基礎的な免疫を社会全体で高めている段階と思います。
その上で、今後新型コロナウイルス感染症がどう変化するか。
今後、新型コロナウイルスが果たして風邪のウイルスのようになっていくのか、それとももう少し危ないウイルスであり続けるのか、これもまだわからない状況なんですが、やはり数年から十年単位で見ていく話なのかと今、専門家の間では議論されています」
ということは、うまく付き合っていくしかないのか。
「新型コロナウイルスの今後の進化の方向性は“免疫逃避”の可能性が高いと見られていますが、これは季節性インフルエンザウイルスの進化に近い変化と思います。
インフルも毎年変異しますがワクチンもそれに合わせて変えていて、皆さん広く免疫を持っている。そしてまた、ウイルスもその免疫から逃れるような形で進化していく。新しく感染できる人を探して感染していくという形なので、新型コロナウイルスもそういった形での進化に今後なっていく可能性が考えられます。
年に2回流行するのか、それとも季節関係なく感染の増減を繰り返していくのか。『いつ終わるのか?』と聞かれても、『まだ終わりは見通せないですが、落ち着きの兆しは見えてきた』というところです」
コロナが始まって約3年、今回、脇田所長に話を聞いて気が付いたことがある。それはワクチン接種も含め、一人一人の意識や行動が平穏な日常を取り戻すことに繋がるということだ。
今年の冬はコロナとインフルの同時流行も懸念されるが、自分自身に何ができるのか社会のためにもこれからしっかりと考え、意識していきたい。
厚労省「アドバイザリーボード」脇田隆字座長にインタビュー
「ケルベロス」2022年12月に猛威か…変異株“連続感染” 第8波長期化も 医療ひっ迫の恐れ
2022年11/22(火)
新たな変異ウイルス(イメージ化した図)
新型コロナウイルスの変異株「ケルベロス」が、来月には猛威を振るうという予測が出るなか、現場の医師からは、相次いで異なる変異株に感染する“連続感染”を警戒する声が上がっています。
■“第8波”兆し…医師「急に感染者増えた印象」
ひなた在宅クリニック山王・田代和馬院長:「きょう、体調を崩されたと聞いてね」
前日から微熱の症状が現れたという男性。この日、医師の往診を受けました。男性はその場で、新型コロナウイルス陽性と診断されました。
田代院長:「先々週までは週に1、2人だったが、先週は一日4、5人いく時もあった。急に、感染者が増えているという印象があります」
全国で広がり続けている新型コロナ。21日の新規感染者は、先週の月曜日と比べて5000人近く増え、4万2424人でした。
東京都でも、先週月曜日の14日から594人多い、4619人の感染者が確認されました。
■回復直後に…“連続感染”で第8波長期化も
「第8波」の兆しが見られるなか、年末に向け、新たな変異株が流行する恐れがあるといいます。
国立感染症研究所・脇田隆字所長:「『BQ.1系統』『XBB系統』などが、今後割合が増加する可能性がある。注意が必要」
現在、アメリカなどで流行している「BQ.1.1株」、通称「ケルベロス」。さらに、アジアなどで広がっている「XBB株」、通称「グリフォン」が日本でも猛威を振るう可能性があるというのです。
中でも、専門家が注目しているのが「ケルベロス」です。
先週の時点で、すでに国内のウイルス全体の16%が「ケルベロス」に置き変わっていると推定されています。さらに、12月の第1週、つまり来週中には、全体のおよそ8割がケルベロスに置き換わるという予測もあります。
現在、主流の「BA.5」と比べて、感染力や免疫を回避する力が強いとされるケルベロス。現場の医師からは“連続感染”を懸念する声が上がっています。
田代院長:「今は、BA.5で患者さんの数が増えている。そこにまた、絶え間なく“新しい株”が来ると。BA.5にかかった人が、新しく(変異株に)かかってしまう可能性」
BA.5に感染した人が、回復直後に今度は「ケルベロス」に感染。その結果、1人の診療期間は長くなり、医療現場が逼迫(ひっぱく)する恐れがあるというのです。
田代院長:「救急医療の機能もパンク・麻痺してしまって、非コロナ・非インフルの方でも、適切な医療にかかれない。そういう事態が起こるのではないかと予想している」
■専門家「ワクチン接種が重要なポイント」
一方で、国際医療福祉大学の松本哲哉主任教授によると、「ケルベロス」は重症化のリスクは高くないと考えられるといいます。
その上で、対策の鍵となるのは、やはりワクチンの接種だということです。
松本主任教授:「新たな変異株が色々出ているが、基本的には『オミクロン株』。早めにオミクロン対応のワクチンを接種して頂くということが、自分の身を守る重要なポイントになる」
(「グッド!モーニング」2022年11月21日放送分より)
「のどの痛みで寝付けず…」“コロナ+インフル”症状は…同時感染した人に聞く
[2022/11/18 23:30]
“第8波に入った”とされる新型コロナと、インフルエンザの同時流行が懸念されています。
新型コロナとインフルエンザに同時感染した、京都・宇治市の20代男性に話を聞くことができました。
同時感染した20代男性:「突然、夜中に肩の痛みであったり、高熱が出て、とても痛みでなかなか寝付けない状態が続いた。38.8度くらいだったと思う。のどの痛みが一番つらかったです」
不意に襲ってきた痛み。翌朝、発熱外来を受診し、検査を受けました。
同時感染した男性(20代):「コロナウイルスとインフルエンザ同時にかかっていると。インフルエンザ用でタミフルと解熱剤、のどの痛み止めを処方してもらった。食べないといけないので、おかゆとかゼリー飲料とか、とりあえずお腹には入れておこうと。味覚障害とか、そういったものは特に出なかった」
のどの痛みは5日ほど続きましたが、後遺症などはなかったといいます。
男性は2回、新型コロナのワクチン接種を受けていました。
福岡県の30代男性は、9日間の入院を余儀なくされました。
9日間入院した30代男性:「最初、鼻詰まりがして、そこからのどが痛くなって、体もけん怠感があるような状態が出てきて、翌日に38度…。発熱して体全身がだるい。夜は、のどの痛みで飲み物も飲めない、ご飯も食べられない。あとは体中が節々痛んだり、筋肉痛で全身がだるかった。そういう症状が出て、一睡もできなかった。もう二度とごめんです 」
通常、複数のウイルスに同時に感染することは非常にまれです。
というのも、ウイルスAが肺の中で増殖した場合、吸着に必要なレセプターを占領・破壊して、後から入ったウイルスBの増殖を妨げる因子を放出するなど『干渉現象』が起きるためです。
しかし、長崎大学高度感染症研究センターの安田教授らによる動物実験では、新型コロナとインフルエンザ、それぞれのウイルスは、肺の違う細胞に同時に感染、すみ分けが起きていました。
同時感染が起きると、肺炎が重症化・長期化する恐れがある としています。
イギリスの研究報告によりますと、コロナのみの感染に比べ、重症化リスクは4.14倍、死亡リスクは2.35倍になるとしています。
2022年11月18日に開かれた同時流行の対策検討会議では「感染者の増加が見られ、同時流行の兆しが見える 」として、呼び掛けレベルが1段階、引き上げられました。
重症化リスクの高い患者には、速やかな受診を求めています。
例え、今は同時感染がレアケースだとしても、感染拡大による患者急増の懸念もあります。
埼玉医科大学総合医療センター・岡秀昭教授:「第8波で、インフルエンザの同時流行が12月~2月にピークを共に迎えることが起きると、両方の感染もまれだが起こり得る。ちまたで感染状況がひどければ、低い確率が現実のものになり得る。両方の患者の感染者数を減らしていくことが重要。両方のワクチンを打ってほしい 」
▶「報道ステーション」公式ホームページ
中国で実績ある科学技術者が20人死去―コロナ“爆発”で特別待遇の余裕なし
2023年1月8日
中国では最近になり、特に実績ある科学技術者で構成される中国工程院(中国工学アカデミー)のメンバーが、20人死去した。高齢者が多い ことはあるが、通常ならば年間を通じた死者数よりも多い人数が、2週間余りの間に死去したことになる。新型コロナウイルス感染症患者の“爆発的増加”で医療機関が逼迫(ひっぱく)したために、通常ならば重要人物として享受できる優遇措置も与えられない状況という。ドイツメディアのドイチェ・ベレなどが報じた。中国工程院は公式サイトを通じて、12月15日から1月4日までの間に、計20人の工程院院士(工学アカデミー会員)が逝去したことを明らかにした。2週間余りの期間内死去数は通常の年間を通じての死去数より多い。
中国工程院は延べ900人余りの院士を擁している。院士らには、三峡ダムや高速鉄道ネットワーク、宇宙ステーションなどの国家の重点プロジェクトに大きく貢献した実績がある。12月15日から1月4日の間に亡くなった院士20人のうち、最年少は1945年生まれで原子時計の専門家だった李天初氏で、最年長は1920年生まれの著名な小児科医の張金哲氏だった。新型原子炉、レアアース工業、光ファイバー開発、レーザー兵器などの分野でのリーダーとしての役割を担っていた院士数人も、逝去者リストに名を連ねた。
中国工程院は過去5年間の平均で、毎年16人の院士しか亡くなっていない。 2021年には13人にとどまった。なお、中国工程院の公式サイトには、亡くなった院士の生没年が掲載されているが、死因は示されていない。
北京のある医師は香港で発行される英字紙「サウスチャイナ・モーニングポスト」に対し、「現在の爆発的な流行により病院には、院士を優先して医療待遇を保障するための空きベッドがない状態だ」と明かした。中国では、官僚や共産党員、軍人、さらに公的役職に就く者について、厳格な序列制度を設けている。中国科学院や中国工程院のメンバーに対しては、省レベル行政区での順列第2位の共産党委員会副書記や、広州市や大連市、深セン市などの省に次ぐ重要都市である「副省級市」に指定された都市の市長などの階級である「省部級副職」と同格の待遇が与えられる。医療面についても「省部級副職」と同様に優遇される。
しかし、北京市内にある某大病院に勤務する医師は、「最近の感染症拡大で大病院は混雑しており、中国科学院や中国工程院の院士が搬送されてきても、病院のロビーで補助ベッドを確保できただけでも幸運だ」と述べたという。同医師は、「新型コロナウイルス感染症の爆発的な流行で医療需要が激増し、他の病気の治療が延期を余儀なくされている」とも説明した。同医師は、プライバシーに関する「敏感な問題だ」として、実名を出すことを拒否したという。
中国政府が2022年12月に、新型コロナウイルス対策としての規制を突然に緩和すると、大都市での爆発的な流行が発生した。中国政府が発表する感染状況についての公式な数字は、国民の実感とはかけはなれている。中国政府・国家衛生健康委員会は12月下旬に毎日の統計数字を発表しなくなり、疾病予防管理センターが毎週の傾向を発表するようになった。
また中国では国家衛生健康委員会トップの同委主任をはじめとする高官が、新型コロナウイルスに感染した後に従来からの基礎疾患が悪化して死亡した事例については、新型コロナウイルス感染症による死者としては数えないと述べている。中国政府は情報の透明性を強調しているが、ドイツなど他の国は一般的に、新型コロナウイルスに感染して死亡した場合には、感染症が直接の死因ではなくても、新型コロナウイルス感染による死亡として統計を出している。
世界保健機関(WHO)も、新型コロナウイルスによる死亡をあまりにも狭く定義する中国のやり方について批判し、「このような公式データは感染爆発の深刻さをリアルに反映していない」と主張した。
サウスチャイナ・モーニングポストは、高齢の院士だけでなく、中国の若い科学研究者も同様に感染症により大きな影響を受けていると指摘した。参画するプロジェクトの進行日程に迫られて、病気になっても働かざるを得ない人も多いと言う。北京市在住で匿名を条件に取材に応じた物理学者は、「感染症が中国の科学研究に与える影響は現時点ではまだ判断が難しい。しかし出入国が間もなく自由化されることを踏まえると、中国の科学研究者と外国の同業者との交流は軌道に戻ろうとしている。そうなれば、多くの新しいアイデアが生まれるだろう 」と述べたという。(翻訳・編集/如月隼人)
“歩く肺炎”マイコプラズマ肺炎とは…「しつこいせき」免疫低下で拡大か
中国で子どもを中心に流行している謎の肺炎。その原因として「歩く肺炎」と呼ばれるウイルスが注目されています。なぜ、ここまで拡大したのでしょうか。 ■病院に詰めかける人 長蛇の列 見渡す限りの人。長蛇の列が向かう先にあるのは薬局です。まるでラッシュ時の駅のような状態です。中国のSNSには大混雑する病院の様子を捉えた映像が数多く投稿されています。 人々が病院に詰め掛けるのは子どものためです。今、中国では子どもの発熱や呼吸器の疾患が急激に増えているのです。病院のロビーでは、ベンチに座る子どもたちの頭上に点滴の袋がぶら下がっています。 どうしても思い浮かべてしまうのは4年前の暮れから起きた出来事。中国中部・武漢の市場で発生した肺炎の集団感染です。新型コロナウイルスのパンデミックは世界を混乱に陥れました。ただ今回、WHO(世界保健機関)は中国当局から「新たな病原体は検出されていない」と報告があったとしています。 では、何が流行っているのか。北京に住む日本人の一家は…。 母親:「一番下(の子)ですね。マイコプラズマ肺炎に感染してしまって、せきがいっぱい出ちゃって。熱が出始めてから、せきが収まるのに2週間くらいかかりました」 ■「しつこいせき」免疫低下で拡大か マイコプラズマ肺炎とは、どのような病気なのでしょうか。 国際医療福祉大学 松本哲哉主任教授:「症状としては、せきが中心になっていて、しつこいせきですね。これが結構、長く続くものですから夜も眠れないとかですね。特に小さいお子さんとか若い方に広がりやすい」 ただ、一般に入院による治療が必要なことが少ないことから歩く肺炎とも言われています。なぜそれが今、広がっているのでしょうか。 国際医療福祉大学 松本哲哉主任教授:「ゼロコロナ政策のように中国では、ほとんど人と人との接触を断つような状況になると、だんだん免疫を持つ人が割合として減っていって、感染に関する感受性が高まっている状況が作り上げられてきたことだと思います」 日本にいる子どもも免疫力が低下している可能性があり、注意が必要だといいます。
「一生においも味も感じないままなの?」 新型コロナの後遺症に3年間悩む女性 亜鉛や漢方、嗅覚トレーニングでも…
左側は女性が新型コロナ感染後に服用した薬や現在も飲んでいる薬。右側は嗅覚トレーニングに使っているアロマグッズ
© 熊本日日新聞社
新型コロナウイルス感染症が世界に広がってやがて4年。日本国内では今年5月に法律上の位置付けが変わり、報道される機会も減った。秋以降は1医療機関当たりの感染者数も落ち着きを見せている。ただ、においや味が分かりにくいなどの後遺症(罹患[りかん]後症状)に苦しむ人は今もいる。
益城町の60代パート女性は2020年12月に1回目のコロナ感染を経験した。熱は38度弱だったが、においがしなくなり、味も感じにくくなった。夫が飲む芋焼酎のにおいをかいでみたが、分からない。周りに感染者はおらず、まさかとは思ったが県内の病院を受診してコロナだと判明、入院して年を越した。
自宅に帰った後も、においや味はしないままだった。「時間がたてば」と思い回復を待ったが、1年以上たっても良くならず、22年夏、新聞で見つけた県内の病院のコロナ後遺症外来を受診。その後、同じ病院の味覚障害の外来に通うようになった。
味覚障害の原因とされる亜鉛不足を補う薬や、漢方薬も試しながら治療や検査を続けた。今年の春ごろには味覚が少し戻ったように感じたが、夏に3回目となるコロナ感染を経験。再びにおいや味がしなくなった。
味がしないと食べても十分な満足感を得られない。においが分からないので「自分が嫌なにおいを発していないか」心配になる。3年近く後遺症に悩む女性。薬を服用しながら1日2回、ラベンダーやレモンなどの香りをかぐ嗅覚トレーニングにも取り組んでいるが、「このままずっとにおいも味もない一生を送らなければならないのかと思うと暗い気持ちになる」と話す。
厚生労働省によると、コロナの後遺症については22年度に発生頻度や症状、経過などを調べる大規模な住民調査も行われたが、不明な点が多いという。WHO(世界保健機関)はこれまでの研究から、感染者の10~20%に後遺症が発生するとしている。
コロナの後遺症では益城町の女性のような嗅覚や味覚障害のほか、原因不明の疲労感や倦怠[けんたい]感、関節痛、せき、記憶障害なども知られている。多くは時間の経過とともに改善するが長引く人もいるという。熊本県のホームページでは、後遺症に対応可能な県内の医療機関を保健所別に紹介している。(太路秀紀)
■新型コロナの後遺症 WHOは新型コロナウイルス感染症の罹患(りかん)後症状について、少なくとも2カ月以上持続し、他の疾患による症状として説明がつかないもので、通常は新型コロナの発症から3カ月たった時点でも見られると定義している。後遺症があってもウイルスの排出期間は過ぎているので、他の人に感染させることはない。
××××××××××××××××××××××× ××××××××××××××××××××××××× ××
×××××××××××××××××××××××××
トラブルの温床 愉快犯 武漢ウイルス研究所から
「コロナウイルスは人工的に作られた」と主張する宮沢孝幸・京都大学准教授の訴え!
By 牧 太郎2023年9月29日 編集長ヘッドライン日記
2023年9月28日、錦糸町で筋トレが終わってから「筋向いのパスタ屋」で昼めしを食べようとして、店内で転倒してしまった。
原因が分からない。
右半身麻痺の当方、一年に数回、転がる。
その度に、落ち込む。怪我がなくって、取り合いえず、安心。
午後、例の「コロナ」のお勉強。
勉強すれば、するほど、コロナの正体が分からなくなる。
少なくとも、ワクチン接種を止めないと日本はダメになるような気がする。
「コロナワクチン」の疑惑は数々あるが、例えば「心筋炎との関係」。メタ解析論文(4700万人を対象)によれば、年齢性別問わずワクチン打ってる方が2倍心筋炎になりやすい。
ワクチン接種をしなければ死ななかった!というケースがあるのだ。
2023年9月27日、仙台で行われた 〈新型コロナウイルスの起源と研究者の責任〉に登壇した掛谷英紀・筑波大准教授と田中淳・大阪医科薬科大助教と宮沢孝幸・京都大学准教授は「コロナの正体・ワクチンの正体」を詳しく説明。
宮沢さんは仙台駅前でビラ配りをし、大きな声で「コロナウイルスは人工的に作られた。ワクチンを打ち続けると、日本が滅びる」と訴えたらしい。
宮沢さんは東京大学卒。大学院で獣医学博士号を取得。 英国留学を経て、大阪大学助手、帯広畜産大学助教授。2005年から京都大学ウイルス研究所に助教授(当時)として着任。ウイルス相手にミクロの戦いを繰り広げている先生。ヤンソン賞を受賞した人物だ。
そのウイルス専門の学者が「このワクチンを撃ち続けると日本はダメになる」と言っているのだ。
今こそ、我々は「コロナの真実」を真摯に受け止めるべきではないか?
「己の転倒騒動」より、この日はコロナで転ぶ「日本国」が気になった。
2023年10月8日、京都大学のウイルス研究者・宮沢孝幸准教授が日本のテレビ番組「そこまで言って委員会」で、初めて「コロナは人工ウイルスである」と発言しました。これは、非常に画期的な事です!そして、宮沢氏にとって、命懸けの発言です!
オミクロンは自然変異ではない
分析の結果「人工ウイルス」であると判明しました。
2023年10/8放送の「そこまで言って委員会」を見逃した人へ
動画はこちらから↓ ↓
→Tver見逃し配信(56分から見てください)
宮沢氏の主な発言
「コロナは人工ウイルスです」
「ウイルスとワクチンは連動しています」
「オミクロンウイルスも人工物であり、変異の実験が行われていました」
「ウイルスは作れます」
「バイオテロも可能になっています」
宮沢氏が一番心配しているのはWHOのパンデッミック条約が通ってしまうと、緊急事態宣言と同時に国民全員が強制的にワクチン接種接種されてしまう事です。
(ワクチン強制=日本民族消滅 ←私の結論)
宮沢氏は9月26日に「コロナは人工ウイルスである」と学会で論文を発表し、海外からも注目されています。しかし、日本では全く報道がありません。今回、ニュース番組ではなく、バラエティ番組で初めて真実が表に出たことになります。そして、この真実に戸惑う人は多いと思います。受け入れられない人が出てくると思われます。
金沢創造都市会議 特別セミナー
金沢創造都市会議2020 >講演②
講演②「新型コロナウイルスの正体と共存への道:我々は何を間違えたのか」
宮沢孝幸氏 (京都大ウイルス・再生医科学研究所准教授)
●プロフィール
東京大学農学部卒。1990年に獣医師国家試験合格。同大学大学院農学生命科学研究科博士課程に入り、93年に同大学博士(獣医学)取得。同大学大学院農学生命科学研究科助手、帯広畜産大学畜産学部獣医学科助教授、京都大学ウイルス研究所附属新興ウイルス感染症研究センター特別教育研究助教授などを経て、2016年より京都大ウイルス・再生医科学研究所准教授。56歳。
宮沢氏の講演要旨は次の通り。
大昔から「ウィズコロナ」
対策と経済の両立肝要
ウイルスの特徴からお話しします。ウイルスは基本的にはタンパク質と核酸からなる粒子です。細菌は適度な栄養と水分があれば自らの力で増殖できますが、ウイルスはDNA、RNAの核酸からなる遺伝子と、それを囲むタンパク質の殻しか持っていません。タンパク質を作る工場を持っていないのです。
そのためウイルスは細胞にくっつき、その細胞に遺伝子情報を渡すことで増殖していきます。自らの力で増殖できないので、生物と無生物の間と言われることもあります。
ヒトの新興ウイルス感染症は全て動物由来です。ヒトはさまざまな動物に囲まれて生活していますが、動物はいろんなウイルスを持っています。たとえば、はしかの原因となる麻疹ウイルスは11世紀ごろにウシからやってきました。エイズウイルスは2種のサルのウイルスがチンパンジーに感染し、変異したものと考えられています。また、ヒトの新型感染症ウイルスは、本来の宿主においては非病原性であることがほとんどです。
病原性、非病原性の網羅的な研究が必須
病気を引き起こすウイルスは、実は1%もないと思います。僕は非病原性ウイルスを研究しています。がんの転移を止めるウイルスや、アトピーを治すウイルス、有害な菌の増殖を抑えるウイルス、さらにヒトの進化に関係するウイルスなどを調べています。ただし、研究費はほとんどありません。
ちょっと脱線しますが、2000年代以降の、国による「選択と集中」の政策によって大学の研究費が大幅に削られています。既得権益というか、一部の人しかまともな研究費はもらえません。日本の大学の国際競争力は落ちていく一方です。そうした中でも懸命に研究を重ねています。
新興ウイルスって予測できるのですか、とたまに聞かれますが、病原性ウイルスだけを研究していても予測はできません。繰り返しになりますが、ヒトの新型感染症ウイルスは、本来の宿主においては、非病原性であることがほとんどなのです。予測には非病原性を含めた網羅的な研究が必須です。
インフルと異なりゆっくりと変異
続いて、新型コロナの起源と性質についてお話しします。新型コロナウイルスの正式名は「SARS(重症急性呼吸器症候群)コロナウイルス2型」と呼びます。
遺伝子はRNAの核酸からなっており、インフルエンザウイルスと同じです。しかしインフルエンザウイルスと仕組みが異なるため、ドラスチックな変化は起こりません。新型コロナウイルスはRNAウイルスとしては非常にゆっくり変異が進みます。
ウイルスが変異すると、強毒にも、弱毒にもなりえますが、流行するのは弱毒のものです。たまに高病原性鳥インフルエンザのパンデミック(世界的大流行)をあおるテレビ番組などがありますが、強毒なウイルスほどパンデミックになりえません。感染すると、苦しくてせきも出ませんし、歩けませんので、感染は広がりようがないのです。
弱毒のSARSの印象
今回の新型コロナウイルスは、ヒトに感染症を引き起こすコロナウイルスとしては8番目となります。まず風邪を起こすウイルスが四つあり、SARSウイルス、MERS(中東呼吸器症候群)ウイルス、中国で見つかった下痢を起こすコロナウイルス、そして今回の新型コロナウイルスです。
新型コロナウイルスはSARSウイルスと同じコウモリ由来のものです。先ほども申し上げましたが、新型コロナの正式名は「SARSコロナウイルス2型」です。SARSウイルスの亜種であり、分子生物学的には十分に既知のウイルスと言えます。ほぼ同種と言っても過言ではなく、SARSウイルスが弱毒化されたものという印象です。感染に必要な受容体も風邪を引き起こす旧型のコロナウイルスの一つと同じです。
コロナウイルスとヒトとの関わりを紐解くと、最初のコロナウイルスは1968年に発見されました。これはその存在が明白に認められたという意味で、僕は旧型のコロナウイルスの遺伝子解析などから、11世紀、平安時代の頃から既に存在していたと思っています。最近「ウィズコロナ」って言葉をよく耳にしますけど、我々は大昔からずっとウィズコロナだったんです。いまの状況は、風邪を起こすコロナウイルスが四つから五つになっただけ、あるいはコロナウイルス同士の入れ替え戦をやっているだけという感じです。
100分の1作戦を
新型コロナ対策としては「100分の1作戦」を提案しています。新型コロナウイルスが細胞に感染するには一定数以上の数が必要であり、疫学データなどからウイルス量を100分の1程度にすれば感染が成立しないことが明らかだからです。
新型コロナの感染経路は接触、飛沫、空気の三つです。常にしっかり換気する、目・鼻・口を触らない、帰宅したら手洗い、人と会うときはマスク、これで対策は十分です。
感染は「目玉焼きモデル」
新型コロナの感染がどのように広がるのかを示す「同心円モデル」、別名「目玉焼きモデル」というものがあります。目玉焼きの黄身の部分は、実効再生産数が1を上回って感染が拡大する部分、白身の部分は実効再生産数が1を下回って感染が収束する部分です。実効再生産数とは1人の感染者が平均何人にうつすかを示す指標であり、感染日を推定するなどして、患者の発生動向からはじき出されます。
この同心円を五つのゾーンに区分けします。①は特殊な夜の街に通う人など、②はかなり騒々しい飲食店を利用する人など、③は普通の人、④100分の1作戦を理解している人、⑤は巣ごもりの人を指します。①②が黄身の部分で、③④⑤が白身の部分です。
このゾーン①②に伝達可能な感染者が出ると、①②に感染が広がります。感染を火事にたとえると、①②は焼け野原になります。③も類焼します。しかしゾーン③④⑤に伝達可能な感染者が出ても感染は拡大しません。なお、欧米は生活習慣の違いから黄身の部分が大きいので、感染が一気に広がりました。
寒くなってくると、ウイルスが壊れにくくなる半面、ヒトの自然免疫力が下がるので、③も黄身の部分に含まれるようになります。また一度感染が広がると集団免疫が成立します。どの国も感染拡大は③で必ず止まります。
不況で自殺者数が14万人増える恐れ
京都大レジリエンス実践ユニットは、本日のもう一人の講師の藤井先生がユニット長をしている研究機関なのですが、新型コロナに伴う経済不況などによって、今後20年間で自殺者数が14万人増加する恐れもあるという内容のリポートをまとめました。実質GDPが14・2%下落し、失業率が6・0~8・4%に達するとのシミュレーション結果も出ています。
一方で、僕らの試算によると、新型コロナの死者数は多くて8000人というものでした。いまのままの経済不況では、新型コロナで亡くなるよりも多くの自殺者が出ることになりかねません。新型コロナが広がってしまったものはしょうがないので、もう受け止めるしかありません。GOTOキャンペーンを停止しても意味はないのです。100分の1作戦と目玉焼き理論を踏まえた適切な対策を行い、経済活動と両立させることが肝要です
「ワクチン接種で文章が読めなくなった」…京大のウイルス学者が絶句した、ワクチン接種後の「ヤバすぎる症状」 2023.03.03
宮沢 孝幸
多数のウイルスを実際に扱い、多くの国際論文を発表してきたウイルス研究者の宮沢孝幸京大准教授が科学的見地から記した新刊『ウイルス学者の絶望』。マスクなど感染対策はまだ必要なのか。本当にコロナワクチンは「安全」なのか。話題沸騰の本書から、抜粋してお届けする
モデルナ社製もファイザー社製も同様のリスク
今回のmRNAワクチンの接種が心筋炎を誘発する危険性があることは、ほぼ確実だと言えます。
アストラゼネカ社製のワクチンで血栓症が出れば「それはアストラゼネカ社製(アデノウイルスベクターワクチン)だからでしょう」などと言う人がいるのですが、モデルナ社製もファイザー社製も同様のリスクがあることに変わりはありません。アストラゼネカ社製のワクチンと同じく、mRNAワクチンはスパイクタンパク質をターゲットとしており、とくに配列を変えていない(毒性を発揮する配列を除去するなど)からです。
新型コロナウイルスのスパイクタンパク質で血管内皮の機能障害を誘発することもわかっています。そうであるならば、ワクチンによるスパイクタンパク質でも血管内皮の機能障害になるはずです。感染によるスパイクタンパク質でブレインフォグになるのであれば、ワクチンでもブレインフォグになるでしょう。
新型コロナウイルスの変異種は人口的な生物兵器か?
オミクロン株は2020年には存在
生物化学兵器の可能性は? 2023/09/21
新型コロナウイルス感染症の原因、そのワクチンに対するワクチンへの疑問をコロナ禍の最初から投げかけてこられたウイルス学者が日本におられます。
京都大学医生物学研究所 附属感染症モデル研究センター、宮沢 孝幸 准教授です。
新聞、テレビに登場することは稀ですので、ご存じない方がほとんどではないかと思います。
しかし、SNSの世界では有名であり、日本のコロナ禍にたいして冷静に、科学的に考察されています。
この度、大学を放逐されることを覚悟で論文を発表しました(査読中であり正式には投稿されていません)。
その論文の要約の翻訳文を掲載します。
「過去 3 年間、重症急性呼吸器症候群コロナウイルス 2 (SARS-CoV-2) が繰り返し発生しました。パンデミックを経験し、アルファからオミクロンまでのさまざまな変異種を生成しました。
この研究では、SARS-CoV-2 オミクロン変異体の形成に至る進化の過程を解明することを目的としており、以下の点に焦点を当てた。
SARS-CoV-2分離株のうち、スパイクタンパク質に多くのアミノ酸変異があるOmicron変異体について。
SARS-CoV-2 Omicron 変異体の形成につながる変異の順序を決定するために、Omicron BA.1 関連分離株 129 株、BA.1.1 関連分離株 141 株、BA.2 株 122 株の配列を比較しました。 関連する分離株を発見し、SARS-CoV-2 オミクロン変異体の進化過程を解明しようと試みた。これには、SARS-CoV-2 オミクロン変異体の形成や相同組換えの発生につながる変異の順序が含まれます。
その結果、Omicron の一部の形成は、分離株 BA.1、BA.1.1、および BA.2 は、自然界で一般的に観察されるようなゲノム進化の産物ではありませんでした。
突然変異の蓄積や相同組換えなどに置いてです。
さらに、Omicron 変異体 BA.1 および BA.2 の 35 の組換え分離株の研究により、Omicron 変異体がすでに2020年に存在していることが確認されました。
ここで示した分析は、Omicron の亜種はまったく新しいメカニズムによって形成されているということです。
これはこれまでの生物学では説明できず、SARS-CoV-2の変異株がどのように形成されたかを知ることで、SARS-CoV-2のパンデミックの再考が促される。」
オミクロン株による感染症はごく最近の事ですが、既に2020年存在していたという事、そして最新生物学では科学的に説明できないRNA変異です。
恐らく、意図的に3年前には合成されていたというのが、宮沢准教授の論文に直接記載されない結論です。
これとは別にアメリカ時期大統領候補で人気上昇中のロバート・ケネディ2世が、コロナパンデミックは新型コロナウイルスを生物兵器として開発したアメリカの作戦であったと暴露し、YouTubeで及川幸久氏が述べています。
オバマ元大統領の時代に始まり保健福祉省や国防総省(国家安全保障局、NSA)が加担していたのです。
日本の新聞やマスメディアでは一切取り上げられておらず、陰謀論という方もおられますが、間もなく真相ははっきりするでしょう。
「新型コロナより怖いウイルスは山のようにある」京大准教授が恐れる"最悪のシナリオ"
「危険なウイルス」だけの研究は危険
PRESIDENT Online 2021/08/28
宮沢 孝幸
京都大学医生物学研究所准教授
新型コロナのようなパンデミックにはどんな備えが有効なのか。京都大学ウイルス・再生医科学研究所の宮沢孝幸准教授は「これまでウイルス学の対象は、人や動物に病気を起こす危険なものに限られていた。これからは非病原性のウイルスも対象に加え、ウイルス研究を『面』で捉えられるように、研究の次元を変える必要がある」という――。
※本稿は宮沢孝幸『京大おどろきのウイルス学講義』(PHP新書)の一部を再編集したものです。
コウモリから人に感染して始まったMERSとSARS
MERS(中東呼吸器症候群)コロナウイルス、SARS(重症急性呼吸器症候群)コロナウイルスは、ともにコウモリからやってきました。MERSは、コウモリからヒトコブラクダに感染し、それがヒトに感染したと考えられています。SARSは、コウモリからハクビシンを介してヒトに感染したと言われています。
MERSコロナウイルスもSARSコロナウイルスも、元々の宿主はコウモリです。コウモリにとっては、それらのコロナウイルスは非病原性であると見られています。下痢くらいは起こすかもしれないけど、特に影響はないのでしょう。
つまり、コウモリはMERSコロナウイルス、SARSコロナウイルスに感染して共存をしているわけです。もしかすると、コウモリにとっては、コロナウイルスは都合の良いウイルスなのかもしれません。
コウモリの中で共存していたコロナウイルスが、コウモリの体内で起こるのか、あるいは、別の動物に入ってから起こるのかはわかりませんが、ウイルスのゲノムの組換えが起こって、人に感染して増殖するウイルスに変化すると、ヒトMERSコロナウイルス、ヒトSARSコロナウイルスになります。これらのコロナウイルスは、ヒトにとっては病原性をもったウイルス、ということになります。
病気を起こさないウイルスは研究されない
動物のウイルスが別の種の動物に感染したときには、多くのウイルスはあまり増殖できません。感染したとしても新しい宿主間で広がらずその個体の感染で終わります。ところが、ごくまれに別の種の動物に感染すると、ドンピシャの相性でよく増殖し、病気を引き起こすことがあるんです。こうしたものが新興ウイルス感染症となるのです。
「ウイルス(virus)」という言葉は、語源はラテン語で「病気や死をもたらす毒」という意味です。中国ではウイルスは「病毒」と表現されます。歴史的に見ても、病気を調べることでウイルスは発見されてきました。一般的に「ウイルスは病気を起こすもの」と考えられているため、ウイルス研究は病気との関係で行われているものばかりです。
しかし、人に病気を起こすSARSコロナウイルスもMERSコロナウイルスも、コウモリなどの元々の宿主の中では非病原性であり、病気を起こさないと思われます。ここが非常に重要な点です。自然界には未知のウイルスが山のようにある
病気を起こすウイルスであれば、研究者たちは一生懸命に研究をします。逆に、人にも動物にも病気を起こさないものは、ほとんど研究されません。
前述しましたが、自然界には、動物を宿主としているときには何の病気も引き起こさないのに、人に感染すると恐ろしい病気を引き起こすウイルスがたくさん潜んでいる可能性があるにもかかわらず、そのほとんどはまったく研究されていないんです。
人の体から、血液を採取したり、便を採取したりして調べていくと、様々なウイルス由来の塩基配列が見つかります。これらは、病気を起こしていないものが多いですから、研究はされていません。動物の体の中にもたくさんのウイルスが潜んでいますが、非病原性であるため、ほとんど研究されていません。
つまり自然界には、まったく研究されていない未知のウイルスが山のようにあるということです。
次の「新興ウイルス感染症」に備えるための研究とは
これまで非病原性のウイルスへの研究はあまり進んでいませんでした。しかし、「次に来るウイルス」に対処するためにも、非病原性のウイルスへの研究は必要不可欠と言えます。
そして、ゆくゆくは病原性のウイルスも非病原性のウイルスもひっくるめて、網羅的に相関関係を示す全体像を示さなければならないと思っています。そのために、ウイルス学は「次元」を高めなければなりません。
今までのウイルス学はゼロ次元でした。どういうことかというと、研究者は一種のウイルス、あるいは一種の宿主の専門家となり、1つあるいは少数のウイルスを深く深く研究していました。いわば、「点」の研究にとどまっている状態です。
次元を1つ上げて、点を線にしてみます。線には、横の線と縦の線がありますが、横の線は、新型コロナウイルス感染症のような、人獣共通感染症や新興感染症の研究になります。
例えば1つの感染症について、ウイルスが異なった宿主の間をどのようにジャンプしていくのかを辿ったり、ウイルスがどのような変異を遂げたかを調べたりします。一方、縦の線は時間軸を設けるやり方で、あるウイルスが過去から未来へどう変化したか、どう進化してきたかを探ります。
4億年前からウイルスを追跡する「三次元のウイルス学」
さらに次元を1つ上げて、二次元になると、点が面になります。すなわち、一種の宿主の中に何種類のウイルスが潜んでいるか、あるいは、土壌や水圏(川、池や海)などの環境の中にどのようなウイルスが存在し、どのような関係を結んでいるのかを研究する段階です。
最終的な目標は、生物全体を網羅したウイルスの分布図や相関関係を明示することになるでしょうが、まずは人と家畜の間におけるウイルスについて調べ、それから野生動物にも広げていく……という順序になります。
では三次元のウイルス学はどうなるかというと、「面」に時間軸が加わります。違う宿主のウイルスの関係を、時間を追って追跡する学問になります。
例えば、1970年代に発見されたサルレトロウイルスは、約1200万年前にウサギに感染したウイルスで、現在は胎盤形成に関与する内在性レトロウイルスと遺伝的に近縁であることがわかりました。さらに、サルレトロウイルスはネコの内在性レトロウイルス、ヒヒの内在性レトロウイルスとも近縁だったんです。「近縁」というのは、ウイルスの遺伝情報(配列)が似ているということです。数百万年前の地中海沿岸でネコとヒヒに同じようなウイルスが感染したこともわかっているのです。
これらのサルレトロウイルスは、ウサギの胎盤形成に関与する内在性レトロウイルスが、何らかのウイルスと組換えを起こして、復活したと考えられます。このように三次元で考えることで、ウイルス進化の過程を正確につかむことができるようになるのです。
この三次元のウイルス学は、時間のスパンによって大きく2つの分野に分かれます。1つはシャロー(浅い)な古代ウイルス学で、おおむね1万年くらいのスパンでウイルスの進化を追跡します。エイズの原因ウイルスであるヒト免疫不全ウイルス(HIV)の研究などはこちらになります。
もう1つはディープ(深い)な古代ウイルス学で、私たちは2億年くらいのスパンで考えます。私たちが行なっているレトロウイルスの研究がこちらに属します。
レトロウイルス(もしくはそれに関連するウイルス)は少なくともおよそ4億年前には地球上に出現したと思われます。そのウイルスは、宿主の生殖細胞に入り込んだウイルスで、ゲノムの配列が子々孫々受け継がれて保存されています。ですから、その変化の過程や、宿主に与えた影響を追跡することができるのです。
技術革新で三日あれば未知ウイルスの同定が可能になった
ウイルス学を次元で捉えるのは、私が2015年12月に考えて発表した概念です。昔は遺伝子の解析をするのがすごく大変で、二次元や三次元の研究など到底無理だったのですが、2008年以降に「ムーアの法則」(集積回路あたりの部品数が毎年2倍になるという法則。毎年2倍の進化を遂げていくことを指す)をはるかに超える勢いで急激な技術革新が起こり、時間もコストも圧倒的に節約することができるようになって、多次元ネオウイルス学が現実味を帯びるようになりました。
どのような技術革新が起こったかというと、DNAやRNAの配列を速やかに決定できるようになったのです。それまでは、ウイルス解析の出発点は病気でした。何らかの感染症の病気が見つかったら、ウイルスを分離、同定して、そこから遺伝子解析を行っていました。
しかし技術革新により、病気を発見してウイルスを分離しなくても、病変部だけでなく非病変部にどんなウイルスがあるのか、三日あればわかるようになりました。サンプルからDNAとRNAを抽出して、その配列を解析するのです。どんなウイルスが存在しているのかが先にわかって、それから病気が発見できるようにもなりました。
例えば、ネコの尿にウイルスがいるのではという推測を立てて、ウイルスを同定することができれば、そこから腎不全などの病気を起こしていることがわかる、といった具合です。ネコモルビリウイルスはそのやり方で発見されました。
新興感染症が出現しやすい今、ウイルス学も進化しなければならない
このように、遺伝子解析が非常に楽になったことで、二次元、三次元のウイルス学が可能になりました。ただ、多次元のネオウイルス学は、遺伝子解析の技術があればすぐにできるわけではありません。動物学、繁殖学、医学、バイオインフォマティックス、コンピュータテクノロジーの支えを得ながら、総合的な知見を高めていく必要があります。
ヒトの動きがグローバルになった現在、ウイルス学も進化しなければならないのです。多次元ネオウイルス学の研究を進めていけば、予測ウイルス学、進化生物学の発展にも寄与することができます。
社会的にも、科学的にも大きな貢献を果たすことができるのです。
新型コロナウィルスのオミクロン株は実験をしていた人工物だと思いますか? 京都大学生命医科学研究所 宮沢
質問者:レッシュ質問日時:2023/10/12 11:00回答数:8件
新型コロナウィルスのオミクロン株は実験をしていた人工物だと思いますか?
京都大学生命医科学研究所
宮沢孝幸准教授
「これは実験だと思った。オミクロンの配列の中でどの配列が重要でどの配列が重要でないか、変異を入れてみた。これが自然界で起こることはない」
「懸念しているのは24年5月に決まるだろうWHOのパンデミック条約。日本はワクチンをいらないと言ってもWHOが打てと言ったら打たなければならない。保健事業の主権が奪われてしまう」
宮沢孝幸教授「オミクロン株は人工的に作られた可能性が高い。自然界で起こることはない」地上波で取り上げられる
2023/10/9
米メディアも報道/日本のトップウイルス学者が街で警告「分析すれば一目瞭然」 「自然プロセスでは考えられない変異」京大宮沢教授
2023/9/30
13:06〜草案ができるのは来年2024年1月
*「パンデミック条約」草案/「国際保健規則(IHR)」修正案 仮訳
2023.10.15
No.6
回答者: yamaya-hositaro 回答日時:2023/10/16 01:43
1)宮沢孝幸教授は獣医であり、また「一流のウイルス学者」とは言えません。
2)宮沢孝幸教授は、新コロナ騒動初期から「もう新コロナ騒動は終わる」とニュースインタビューで答えていますが、ご存じのように何度も新しい波が来ています。つまり、外してばかりです。
また、「新コロナウイルスが血液から検出されたことはない」などの間違いを言っています。
※インフルウイルスだって血液に入るのに、なんで新コロナウイルスは血液に入らないと思うのか、謎です。ちなみにコロナ系ウイルスは腸内で最も増殖します。
ツイッターでも「もう新コロナ騒動は終わる」と何度も上げては、その後に波が来るとツイートを削除して「なかったこと」にします。
つまり、ウイルス学者としても人間としても「信用できません」。
ハッキリ言って、ネットでこの人の信者が多いのはすごく不思議です。テレビによく出ているせいでしょうか?
3a)「これが自然界で起こることはない」も疑問です。
コロナ系ウイルスはRNAウイルスなので変異しやすいのです。
3b)「人工的に」の定義によりますが・・・例えば、インフルウイルスを豚とニワトリと人間をいっしょの場所に住ませると、自然界では1年に1回くらいしか起きない変異を何回も起こさせることが出来ます。
つまり、「人工的な変異」ではありませんが、「自然変異を人工的に加速させる」ことが出来ます。
4)一応、現在の科学では「Aというウイルスの特徴を、Bというウイルスに与える」事は可能です。そのウイルスの遺伝子ゲノムさえ分かっていれば、の話ですが。
しかし、特定遺伝子部位は一個の機能だけ持っている事はあまりなく、大抵は、その機能をつけると別の機能も付いたり、そもそもウイルスが増殖しなくなったりと、簡単に上手く行くことは あまりありません。
個人的には、複数の遺伝子情報と状況証拠から、「中国の武漢研究所で作られたものが、管理が ずさんで外に漏れた物」だと思っています。
※以前からある武漢研究所ではなく、2017~2018年ごろに新規に作られたP4施設です。
国民の半分以上が少なくとも1回のワクチン接種を受けたアメリカで、接種ペースが目に見えて落ち込んでいる。
2021.06.04
ピーク時の4月13日には1日338万人がワクチンを受けたが、今では1日およそ100万人である。
接種率も州によってばらつきが出てきた。バイデン大統領は7月4日の独立記念日までに国民の7割に接種する目標を立てているが、ワシントン州やニューヨーク州があと10日以内で達成するのに対し、アラバマ州やミシシッピ州などは、このペースだと1年以上かかると見られる。
【関連記事:盛り上がるワクチンツーリズム…アラスカ行けば空港で無料ワクチン接種】
接種の進まない原因のひとつが、ワクチン反対派の存在だ。
インターネット上には、「ワクチンにはマイクロチップが入っている」「ワクチンがDNAを変異させる」「ワクチンが変異株の原因だ」などといったデマがはびこっている。いずれもファクトチェックにより科学的根拠のない誤った情報だとされたものだ。
NGO組織「CCDH」の調べによると、主要ソーシャルメディアに流されているワクチンに関するデマの65%は、わずか12名の影響力によるものだそうだ。
彼らは時として「ナチュラル・ヘルス」をすすめ、新型コロナの存在を否定したり、ワクチンや医師を非難したりする。科学的根拠のない療法を推奨し、サプリメントや本の販売、さらに会費を集める者もいる。
この12人の反ワクチン活動家は、膨大な数のフォロワーを抱えている。
そのなかの一人、ロバート・F・ケネディ・ジュニアは「5G(第5世代移動通信システム)がコロナに関連している」「元野球選手ハンク・アーロンの死はワクチンの影響だ」などの情報を流し、インスタグラムから締め出された。
彼の反ワクチン団体には1400万ドル(15億円強)出資する活動家がおり、ケネディ氏は団体から年間25万5000ドル(2800万円)ほどを得ているという。
この行動にはケネディ一族のメンバーからも「彼のことは好きだが、ワクチンに関しては間違っていて、致命的だ」というコメントが出されている。
こうした反ワクチン業界は、世間に誤情報を伝えることで公衆衛生を犠牲にし、年間少なくとも3600万ドル(40億円弱)の収益を生み出し、さらに政府の給与保護プログラムから少なくとも150万ドル(約1億6500万円)の融資を受けているという。
12名に関連する団体は22組織あり、少なくとも266名の雇用者がいる。12名の合計フォロワー数は6200万人を超え、フェイスブックからは11億ドル(1200億円)、ユーチューブから70万ドル(7700万円)、ツイッターから760万ドル(約8億3000万円)の年間収益がある計算だ。
SNS側も、こうした誤情報のページを削除する戦いを続けている。
実際、ツイッターに特定のハッシュタグを入れると保健福祉省のリンクが、インスタグラムではCDCのリンクが出てきた。また、12名のうちの1名のサイトのリンクをクリックすると、「このページはスパムの可能性があり安全ではありません」という警告が現れた。
誰でも簡単に情報発信できるようになったいま、正確な情報も誤った情報もすべてが渾然一体となって拡散している。正しい情報をどのように判断していくのか、誰もが難しい問題を突きつけられている。(取材・文/白戸京子)
VIDEO ②宮沢孝幸氏講演 - 新型コロナウイルス特別講演会
2020/10/23
山陰はもとより全国各地の観光地に大きな影響を与えている新型コロナウイルスについて、専門家の豊富で正しい知見を借り、境港をはじめとする中海・宍道湖・大山圏域の観光関係者や商業人、経済人みんなで学び、今後のそれぞれの糧としていただくため、特別講演会を開催しました。
開催日 2020年10月11日
会 場 鳥取県境港市 境港シンフォニーガーデン
本講演会の映像をより多くの方々に視聴頂けるよう、境港市観光協会チャンネルで公開しました。本動画は「②宮沢孝幸氏講演」です。
VIDEO
2023年12月7日 宮沢孝幸氏出演番組「そこまで言って委員会」 - 新型コロナウイルス
VIDEO 【宮沢孝幸】人工改変とは⁉️最先端研究のいま⚡️2023年9月1日のやなチャン!
2023/09/01 にライブ配信
日本維新の会、参議院議員「やながせ裕文」のチャンネルです。前東京都議会議員(大田区・3期)。海城中高、早大卒。筑波大院博士前期課程在学中。愛犬はマルプー(こべに)。著書「東京都庁の深層」小学館新書。
☑ 2021年8月視聴数トップ5
【宮沢孝幸】ワクチン接種後のシナリオ大議論!ギリギリまで踏み込みます【教えて! にゃんこ先生 第18回】
新型コロナがまた拡大、専門家は向こう1カ月が感染ピークと予想―中国メディア
2023年12月13日
2023年12月11日、騰訊網は世界各地で新型コロナの感染が再び拡大傾向にあると報じた。
記事は、米国では2日までの7日間で新型コロナ陽性者数は前週比11.5%増、入院者数は同17.6%増、死亡者数は同25%増となり、乳幼児や小児、高齢者が多数救急搬送されたと紹介。オーストラリアやオランダなどでは下水中に観測される新型コロナウイルスが過去最高の水準に達しつつあり、英国では新型コロナのランダム検査を再開したと伝えた。また、中国でも安徽省や上海市の医師から「感染者数が増えている」との声が出ているとした。
さらに、東南アジアでは特に急速に感染者が増えており、マレーシアでは9日までの7日間で11月の同時期の8.11倍に当たる1万2757人の感染が確認され、新型コロナ検査キットの在庫切れや品薄状態が各地で相次いでいると紹介。シンガポールでも2日までの7日間で前週より45%多い3万2000人以上の感染者が見つかり、タイでも同じ期間だけで11月全体の545件に迫る500件以上に達したほか、台湾では5日までの7日間で新型コロナによる死者は31人、重症患者は260人に達し、過去1カ月間で最も多くなったと伝えている。
そして、シンガポールの感染症専門家によると、今回の新型コロナ感染は約1カ月でピークに達する可能性があり、台湾の衛生局は来年2月10日の春節前後には1日当たりの感染者数が1万8000〜2万人に達する恐れがあるとの見通しを示していることを紹介した。
その上で、現在の新型コロナ感染の波はBA.2.86亜種の子孫であるオミクロン亜種JN.1の流行に関連している可能性が示唆されており、英国の免疫学者でマンチェスター大学のシーナ・クルックシャンク教授がJN.1は理論的にはヒトの細胞に結合しやすく、免疫回避能力が高いため、感染者数が増えているとの見方を示したことを紹介。シンガポール保健省は「集団免疫の低下、海外渡航者の増加、年末の旅行シーズンによる交流増加に起因しているのではないか」と見ていると伝える一方で、多くの国ではJN.1感染が重病を引き起こす可能性が高いという考えを支持する証拠はまだないと認識していることを紹介した。
記事は、世界保健機関(WHO)が2023年11月下旬にBA.2.86やJN.1などを「注目すべき変異株(VOI)」に再分類し、2023年12月1日には新型コロナに関するアドバイスを更新し、北半球の人々、特に高齢者、慢性疾患のある人、免疫不全の人は感染後の重症化を避けるために新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンの接種を受けるべきだと強調したことを伝えている。(翻訳・編集/川尻)
新型コロナ第10波到来か?変異株「JN.1」とは? 医師が「若い世代の行動」に警鐘を鳴らす【岡山】
新型コロナウイルスの感染者と入院者の数が岡山県で増えています。その原因とみられるのが新たな変異株。医療の現場で現状を取材しました。
2024年1月31日
(難波医院 難波一弘院長)
(難波医院 難波一弘院長)
「この数は第10波といっていいと思います」
倉敷市にある難波医院。このところ、1日に3人から4人の患者が新型コロナの検査で陽性と判定されているといいます。
新型コロナの感染が、今、再び拡大しています。岡山県の最新のデータでは、1医療機関あたりの感染者数は11.37人。前の週の1.3倍に増えました。入院患者の数も前の週から122人増え483人で、県は4段階の感染レベルを上から2番目の「段階2」に引き上げました。
(難波医院 難波一弘院長)
「一番はみんなの気の緩みと予防注射が浸透していない。受けていない人を中心に感染している」
そしてもう1つ、難波院長が指摘するのが。
(難波医院 難波一弘院長)
「2週間くらい前まではXBB1.5が多かったが、今は半分くらいがJN.1という株に変わっていて抵抗力のない人が多く、感染している」
JN.1とはオミクロン株の新たな変異株で、症状はこれまでの株と同じ程度ですが、感染力が強いとされています。
(難波医院 難波一弘院長)
「潜在的に市中感染を起こしているということなので膨大な数の保菌者がいると思う」
難波院長は、さらなる感染拡大を抑制するためにカギとなるのが、若い世代の行動だといいます。
(難波医院 難波一弘院長)
「そういう人は元気だから行動範囲は広いし、声も大きいし、楽しいところへも行きたいでしょうから行けばいいんですが、自分たちは若いから感染しても軽い症状で済むという油断があると思うが、人に移してしまうということをちょっと考えてほしい」
感染防止策はこれまでと変わっていません。必要に応じたマスクの着用やワクチン接種など、それぞれが考え、判断して行動していきましょう。
新型コロナ「第10波」 患者数は9週連続で増加 新たな変異株「JN.1」が猛威振るう 今週には倍増か
2024年1/29(月) 19:46
いま「新型コロナウイルス」の感染が全国で拡大していて、「第10波に入った」との指摘が相次いでいる。 新たな変異株も急増し、街のクリニックでは、「今後も感染者が増えるのはないか」と懸念の声が上がっている。
愛知県 大村秀章知事:本県におきましては、既に第10波に入ったと言わざるを得ない。
静岡県感染症管理センター 後藤幹生センター長:コロナの、いわゆる第10波が始まってきているという状況になっています。
1月に入り「第10波」を指摘する声が相次ぐ新型コロナウイルス。 厚生労働省によると、全国から報告された1週間あたりの新型コロナの患者数は、1月21日まで9週連続で増加している。
■新型コロナの陽性者が増えている
大阪のクリニックでも現在、新型コロナの陽性者が増えているという。
ごとう内科クリニック 後藤浩之院長:12月まではインフルエンザの患者が、非常に多かったんですけど、徐々にコロナの患者が増えてきまして、ちょうど正月明けぐらいには、コロナとインフルの患者さんが、ほぼ同じくらいの数になってきました。大体、12月の倍くらいの人数になっています。
29日の取材中にも、60代の男性がせきと吐き気の症状を訴え、検査のため来院していた。
ごとう内科クリニック 後藤浩之院長:これコロナやね
60代の男性:コロナなってんの?
ごとう内科クリニック 後藤浩之院長:今回初めて?
60代の男性:いや2回目
ごとう内科クリニック 後藤浩之院長:いましんどい症状って吐き気くらい?
60代の男性:ちょっと吐き気と、せきが出て止まらん
ごとう内科クリニック 後藤浩之院長:吐き気止めと、せき止めと、もし熱が出たら、熱冷ましいるやろうから、3点出しておきますね
こちらの病院では29日の午前の診療で検査した17人の患者のうち3人が新型コロナ陽性だった。
ごとう内科クリニック後藤浩之院長:コロナに関しては、まだこれからも増えてくるんじゃないかなという感じですね。予想としては2月の終わりくらいまでは、増え続けるんかなという感じはしますけどね。
■新たなオミクロンの変異株「JN.1」
感染者が増加する中、いま全国的に広がりつつあるのが、新たなオミクロンの変異株「JN.1」だ。 国立感染症研究所によると、国内の「JN.1」の検出割合は、1月7日までの1週間で19.5%だったものが、今週には43%に倍増すると推定されている。またWHOも先月、「注目すべき変異株」に「JN.1」を指定している。
感染症の専門家・関西福祉大学の勝田吉彰教授は、「感染力が強いのは間違いない」と注意喚起している。
(関西テレビ「newsランナー」2024年1月29日放送)
新変異株拡大、「第10波」か 専門家「感染対策続けて」―新型コロナ
2024年01月28日08時43分
新型コロナウイルスの感染が再拡大している。厚生労働省によると、新規感染者数は9週連続で増え、流行の「第10波」が来たとの見方もある。感染力が高い新たな変異株も広がり、専門家は「油断せずに感染対策を続けて」と訴えている。
コロナ9週連続で増加 インフルも増―厚労省
新型コロナは昨年5月、感染症法上の位置付けがインフルエンザと同じ5類に移行。そのため患者数の把握方法は、全患者情報の収集から全国約5000の定点医療機関による報告に変わった。
厚労省によると、21日までの1週間に報告された感染者は1機関当たり12.23人。前週比約1.4倍で、昨年11月下旬から増加が続く。能登半島地震に伴い多くの人が避難生活を送る石川県は同約1.4倍の14.33人だった。
背景としては、海外で昨年秋ごろから急拡大する新たな変異株が国内でも増えていることが指摘される。オミクロン株の一系統「BA・2・86」がさらに変異した「JN・1」だ。
世界保健機関(WHO)によると、JN・1が他の変異株より重症化しやすくなったとの報告はない。ただ、WHOや東大医科学研究所などの発表によると、変異によって免疫を回避する能力が高まり、感染が拡大しやすくなった恐れがある。
国内では、JN・1への置き換わりが急速に進む。国立感染症研究所によると、民間検査機関が1~7日に調べた194検体のうち最多の約2割を占めた。来月初めには43%に上ると推計される。
慶応大の菅谷憲夫客員教授(感染症学)は「JN・1は免疫をすり抜ける能力が上がっているとみられる。現在は流行の『第10波』とも言えるが、JN・1の拡大で感染者数はさらに増える恐れがある」と警戒する。
菅谷氏は海外からの報告を基に、JN・1拡大に伴い国内で死者数が急増する事態は考えにくいと指摘。一方で、重症化リスクは一定程度あるとして特に高齢者らは注意が必要と強調する。菅谷氏は「インフルエンザもピークを過ぎたとみられるが、依然流行している。マスク着用や手洗いなどをきちんと続けてほしい」と話している。
新型コロナ、また増加傾向で「第10波」の兆しも 感染は心不全リスク高める恐れと理研
2024.01.24
内城喜貴 / 科学ジャーナリスト
新型コロナウイルスの感染は昨年11月下旬から年が明けても増える傾向が続き、流行の「第10波」の兆しも見せている。理化学研究所(理研)と京都大学の共同研究グループは昨年末、症状が収まった後もウイルスが心臓に残存すると心不全のリスクが高まる可能性があると発表した。同5月に感染症法上の位置付けが5類に移行し、人々は「コロナとの共生」の日常に戻っているが、流行ウイルスの性質が大きく変わったわけではなく、油断はできない。厚生労働省は今冬期の流行拡大に注意を呼びかけている。
国内初感染確認から4年でまた増加傾向
新型コロナウイルスの感染者が国内で初めて確認されてから1月15日で4年が経過した。5類移行後は感染実態の把握方法は全数把握から全国約5000の定点医療機関による定点把握に変更された。厚労省によると、定点把握の感染者数は移行後も増え続け、昨年8月末から9月上旬には1医療機関当たり約20人になり流行の「第9波」のピークに達した。その後11月中旬に底になったものの、同月下旬から再び増加傾向を見せていた。
今年1月8日から14日までの1週間の1医療機関当たりの平均感染者数は約9人で前週比約1.3倍となり、8週連続で増加している。厚労省のまとめでは岐阜、茨城、愛知、長野の各県が14人を超え、43都道府県で前週比増加した。
一方、インフルエンザは昨年11月から12月にかけて増加傾向を続けたが、同月中旬から年末、年明けにかけてやや減少傾向を見せていた。厚労省の1月19日の発表によると、全国約5000の定点医療機関が8~14日に報告した平均の感染者数は約13人。前の週まで減少が続いていたものの、前週比1.03倍でほぼ横ばい。今後の増減が注視されているが、現在は新型コロナのような明確な拡大傾向は収まりつつある。
新型コロナウイルスは流行「第10波」が立ち上がりつつある。国立感染症研究所によると、現在日本で主流とみられるのは、オミクロン株の亜種XBBの一種であるHK.3。XBB全体の約7割を占め、さらにBA.2.86やJN.1など新たな変異株が広がりつつある。対応ワクチンも使われているオミクロン株の仲間だが、専門家は性質が異なる変異株の登場を懸念している。
iPS細胞を使い心臓への影響を解明
こうした中で新型コロナウイルス感染が心不全リスクを高める恐れを明らかにした理研の研究成果が、昨年12月22日に米科学誌「アイサイエンス」電子版に掲載された。
新型コロナ感染はウイルス表面にある「スパイクタンパク質」がヒトの細胞表面にある受容体「ACE2」に結合して起こることが分かっている。心臓は他の臓器よりもACE2を発現しやすく、コロナ禍では感染後の後遺症として心筋障害を起こした症例が造影CT検査などで報告されるなど心機能が低下するとの臨床報告が相次いでいた。感染と心臓への悪影響について詳しいことは世界的にも分かっていなかったが、新型コロナが5類になってもあなどれない感染症であることを示す研究成果として注目されている。
この研究の大きな特徴は人工多能性幹細胞(iPS細胞)を使ってヒトの心臓組織を作製した実験手法だ。理研・生命機能科学研究センターの村田梢研究員や升本英利上級研究員と京都大学医生物学研究所の朝長啓造教授、牧野晶子准教授らの共同研究グループは、ヒトiPS細胞を使ってヒトの心臓組織の「心臓マイクロ組織」(CMT)を作製した。CMTは心筋細胞やその他の心臓構成細胞で構成され、実際の心臓のように拍動した。
研究グル-プはこのCMTにさまざまな量の新型コロナウイルスを感染させた。すると、感染後7日目までに全てのウイルス量で心機能(組織の収縮力)が低下した。ウイルス量が少ないと4週間後に心機能が回復傾向を示したが、多いと回復せずに収縮力は低下したままだった。
また、ヒトの虚血性心疾患を模してCMTを低酸素状態にして実験をした。その結果、ウイルスに感染していない正常なCMTはその状態でも一定期間後に拍動数が上昇し収縮機能が回復した。一方、少量でもウイルスを持続的に感染させたCMTの拍動数は上昇せず、収縮機能も回復しなかった。さらに正常なCMTは低酸素状態でも組織(血管網様構造)が維持されていたが、持続的に感染した状態のCMTは組織が分断されていた。
「心不全パンデミック」を懸念
新型コロナウイルス感染による心機能低下などの症状は免疫系の異常である「サイトカインストーム」が関与している可能性が指摘されていたが、一連の実験では低酸素状態でもサイトカインの上昇はなかった。研究グループは新型コロナ感染による心筋症はサイトカインストームとは独立して起き、持続的な感染が心不全のリスクを高める可能性が明らかになったとしている。
感染による「心臓後遺症」には心筋障害や心膜炎などのほか、感染前には全く気がつかなった狭心症や弁膜症の自覚症状が出る例も報告され、「新型コロナ心臓後遺症外来」を設置した医療施設もある。
理研の升本上級研究員ら研究グループは、ウイルスが心臓組織に持続的に感染し、感染者が典型的な症状がなくなった後も心機能に悪影響を及ぼすことにより、心不全患者が急増して「心不全パンデミック」になる可能性があるとみている。これまで問題視されなかった心不全パンデミックに対して十分な警戒と対策が必要だと指摘している。
VIDEO