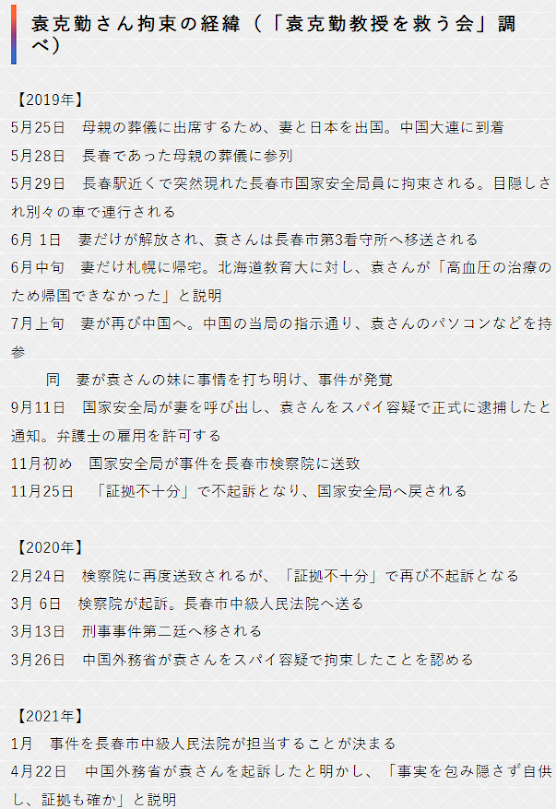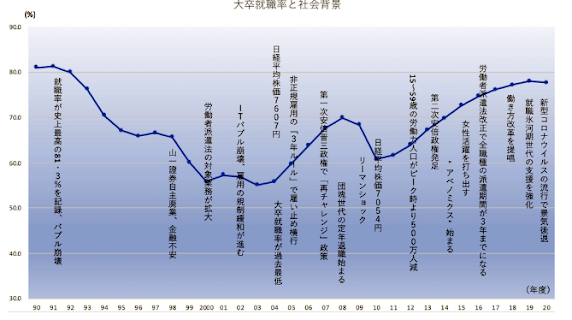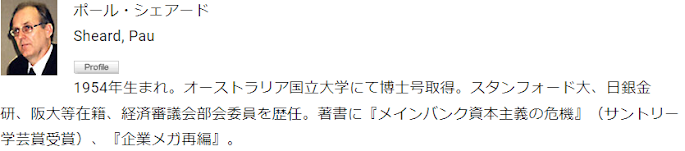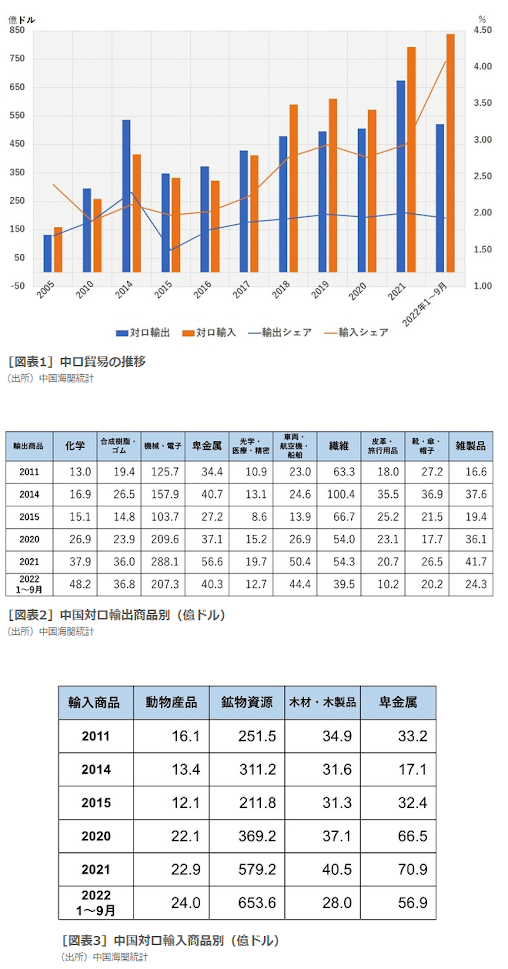❽日本の“先端技術の塊”複合機を狙う中国
【巧妙化する情報工作】FBIとMI5が警告 中国“スパイ活動”の脅威とは
【ナゼ?】日本の“先端技術の塊”複合機を狙う中国【深層NEWS】
2022/07/29
▼“先端技術の塊”複合機が中国に狙われるワケ
▼中国が狙う「高性能医療機器」とは?
▼中国版高速鉄道は新幹線“盗用”か?
▼“技術流出”狙う?中国組織とは?
▼日米「経済版2+2」抑止力なるか?
(2022年7月28日放送 BS 日テレ「深層NEWS」より)(c)NTV
日本のお家芸・複合機の技術を狙う中国の新基準
山崎文明 (情報安全保障研究所首席研究員)
2022年7月2日
中国が複合機などのオフィス設備を調達する際に、中国国内での設計・開発を求める新たな国家規格を策定していると、読売新聞が7月3日に独自ニュースとして伝えている。
中国の情報セキュリティー技術に関する国家規格を所管する「全国情報安全標準化技術委員会(TC260)」が策定した「情報セキュリティー技術オフィス設備安全規範(草案 2022年4月16日)」に、中国政府が入札などで購入するオフィス設備について「(中国)国内で設計・開発・生産を完成すべきだ」と明記しており、オフィス設備の安全評価についても「国内で設計・生産が完成されていることを証明できるかどうかを検査する」と規定していることがその根拠としている。
「全国情報安全標準化技術委員会(TC260)」は国務院(中央政府)の下部組織である国家市場監督管理総局のもとにある組織。メンバーには習近平国家主席の直轄でサイバーセキュリティーを所管する共産党中央インターネット安全・情報化委員会弁公室や工業情報化省、公安省の幹部ら中国共産党員で構成されている。
データ通信や暗号、パスワードなど7つの作業部会があり、複合機を含むオフィス設備に関する規格は「情報セキュリティー評価」の作業部会で議論されている。新たな規範は、政府調達のみならず、通信や交通、金融など社会インフラ事業者の調達にも適用されるという。
海外企業に対する配慮が消えた新規格
2016年11月、中国国家規格に関する解説書が公表された。中には、「情報セキュリティー標準は、サイバースペースにおける国際競争の戦略的な高みとなっている。特にオフィス機器の基準と管理方針は、産業に大きな影響を与え、海外企業の強い反発を招くことは必至であろう」としている。
海外のオフィス機器情報セキュリティー関連規格を具体的に分析、参照、吸収し、Hardcopy Devices and Systems (IEEE 2600-2008コピー機器の国際規格)などの国際規格や先進的な外国規格の採用度合い、類似の国際規格や外国規格水準との比較、あるいは試験済みの外国サンプルやプロトタイプの関連データと比較し、試験評価方法を立案したとしている。
海外企業の強い反発を意識して、「技術要素の面で国際的に権威ある標準をカバーすると同時に、オフィス機器の情報セキュリティー管理に関する国家政策の要求を実現するため、技術の中立性維持を前提に、多くの拡張要求を提示している」と解説していたのだが、今回の草案では、そうした海外の企業に対する配慮は全く消えてしまっているのだ。
複合機は先端技術の塊
コピーやスキャン、印刷、ファクスなどの機能を統合した複合機は、日本のお家芸であり、先端技術の塊といってもいいものである。コピーやスキャンの実現には光学の知見、印刷の実現には化学の知見、ファクスの実現には通信の知見、そして歯車などの紙送り機能には機械・電気・電子・情報工学を融合させたメカトロニクスの技術が求められる。そして、それら機能をまとめあげ、一つの製品に仕立てるためにはITの技術が必須である。
規範では、「重要部品」として「メイン制御チップ、レーザースキャン部品、コンデンサー、電気抵抗器、モーター」が挙げられており、これらを中国国内で設計・製造するよう求めている。現時点で、日本のメーカーは設計や開発を日本国内で行っており、単純な組み立てを中国国内の工場で行うことで、企業機密やノウハウの流出を防いでいるが、この規範が導入され中国国内で設計・開発をすれば技術が中国に盗まれる可能性が高い。
穴だらけの複合機のセキュリティー
中国が複合機をはじめとするオフィス設備のセキュリティー基準を強化することは、至極もっともなことだ。複合機の外見は従来のコピー機と何ら変わらないが、中身はネットワークシステムそのものといっていいほど進化している。
現在、主流となっている複合機にはWebサーバー、メールサーバー、共有ディスクが搭載されており、遠隔保守システムや自動構成管理システム、認証システムが稼働している。それらが稼働するOSは、製造段階から組み込まれており、新たな脆弱性が発見されてもアップデートが行われずに放置されている。特にEWS(Embedded Web server)と呼ばれる機器に埋め込まれたサーバーのソフトウェアを最新のものにする手段がないのである。
にもかかわらず、それらのオフィス設備は、インターネットでメーカーの保守部門とつながるようになっており、印刷枚数の課金情報の収集やインク切れ、故障の予兆情報などがメーカー側で管理できるようになっているのだ。外部からのアクセスに必要なユーザーIDが「admin(管理者の意)」や「access」であったり、パスワードをそもそも設定してなかったり、設定してあったとしても「admin」や「111111」、「123456」などの単純なものがほとんどである。アクセスに成功すれば、その複合機でコピーやファクスしたもの、印刷またはスキャンした用紙が丸見え状態になっているのである。
筆者はこうした現状を危惧し、あるメーカーの役員に外部からアクセスする際の認証機能を強化することや、せめて初期値のパスワードを個体別のシリアルナンバーなどにするなどの改善を要求したことがあるが、対策は進んでいないようだ。これら脆弱性の存在するインターネット上の装置を簡単に探し出す検索ツールも出回っていることから、オフィス設備のセキュリティーは深刻だ。
経済安全保障のジレンマ
この草案が実施されれば複合機のノウハウが中国に移転するのは時間の問題だろう。海外勢は競争力を失ってしまい撤退を余儀なくされる。
中国の大きな市場を失うか、市場の大きさに目を瞑って草案を受け入れ、事業そのものを失ってしまうのか――。複合機メーカーは、頭を悩ませているに違いない。中国の「セキュリティー基準」という国家戦略にはまってしまう前に賢明な判断がなされることを願う。
一方で複合機のユーザーは、今回の報道を機に、複合機のセキュリティーについて点検を行なってはどうだろうか。オンライン会議の普及やペーパーレス化が進むなかで、書類を印刷するケースは減ってきていると思われるが、重要な機密情報にかぎって印刷するという企業も少なくないのではないか。官公庁も例外ではないと思われる。役員や政治家がまだまだ紙で要求するケースは多いように思う。
であれば複合機のセキュリティー確保は喫緊の課題である。複合機をネットワーク機器として認識し、総務部の管理からシステム部へ移管している企業は、どれほどあるだろうか。今一度、複合機のセキュリティが万全かどうか点検されることを推奨する。
【巧妙化する情報工作】FBIとMI5が警告 中国“スパイ活動”の脅威とは【深層NEWS】
2022/07/23
▼FBIとMI5「中国が最大の脅威」と警鐘を鳴らす狙いとは
▼中国政府によるニューヨークで行われた下院選挙への介入目的は?
▼政治への影響力強化を図る中国の脅威
▼中国が「千人計画」を進める意図とは
▼「千粒の砂作戦」とは
▼中国に狙われる日本の先端技術、その背景に何が?
(2022年7月22日放送 BS 日テレ「深層NEWS」より)(c)NTV
【ゲスト】
興梠一郎(神田外語大学教授)
小谷哲男(明海大学教授)
【キャスター】
鈴木あづさ(日本テレビ報道局)
【アナウンサー】
川畑一志(日本テレビ)
<独自>中国企業、帰化元社員に情報要求か 山村硝子の独自技術流出
2023年10月17日
県警生活経済課などが不正競争防止法違反容疑で逮捕したのは、山村硝子元社員の小鷹瑞貴容疑者(57)=懲戒解雇=と、妻でガラス製造技術コンサルタント会社「アズインターナショナル」社長、青佳(せいか)容疑者(51)。平成28年、2016年6月、山村硝子のサーバーにアクセスし、ガラス瓶軽量化の技術に関するプログラムを私用メールアドレスに転送した疑いが持たれている。
山村硝子や関係者によると、瑞貴容疑者は平成15年に入社。平成25年5月~29年7月に海外チームに所属し、中国で技術契約に関する営業、通訳などに従事していた。もともとは中国籍で中国語が堪能といい、中国での営業を長く担当していたという。
同社は事件前、情報の流出先とされる中国のガラス瓶メーカーと技術支援契約を締結。瑞貴容疑者が担当していたが、契約が打ち切られたという。その後、瑞貴容疑者らが持ち出した情報は、ガラス瓶の超軽量化を図るためガラスを薄くする特殊な計算式で、二酸化炭素(CO2)削減などにつながる山村硝子の独自技術とされる。瑞貴容疑者は営業職として技術情報へのアクセス権限があった。
一方、青佳容疑者もかつて中国籍で、社長を務めるコンサル会社が事件約1カ月前の平成28年、2016年5月、この中国メーカーとライセンス契約を締結していた。同8月~令和3年4月には、中国メーカー側から20回にわたって計1億8960万円相当の入金があったという。営業秘密はコンサル会社を通じて中国側に提供されたとみられる。
山村硝子は東証スタンダード上場で、国内のガラス瓶生産シェアトップとされる。外部からの情報提供があり、社内調査で不正が発覚した。
相次ぐ流出、スパイ活動に高まる懸念
日本企業の営業秘密が中国などに持ち出される事件は度々起き、政府は近年、先端技術の海外流出を防ぐ経済安全保障対策に力を入れている。外国スパイによる情報流出も懸念されるが、日本にはスパイ活動自体を取り締まる法律がない。警察幹部は「流出は日本の技術的優位の低下を招く。企業は意識を高め、対策してほしい」と話す。
警察庁によると、全国の警察が昨年摘発した企業情報持ち出しといった営業秘密侵害事件は29件で、統計を取り始めた平成25年(2013年)以降で最多。中国などは先端技術などを獲得するため、民間人も活用した「情報戦」を展開しているとみられる。
令和2年(2020年)、液晶技術に関する情報を中国企業に漏洩したなどとして積水化学工業の元社員が書類送検された事件では、中国企業側がビジネス向けSNSを通じて元社員に接触。国立研究開発法人「産業技術総合研究所」の研究データを持ち出したとして今年(2023年)6月、逮捕された中国人研究員は、研究所に20年近く勤務する一方、中国人民解放軍と関係があるとされる「国防7校」の一つ、北京理工大教授にも就いていたと指摘される。
経済安全保障に詳しい明星大の細川昌彦教授は「技術力の高い日本は、特に半導体や基幹部品といった先端技術が狙われやすい。大企業だけでなく中小企業も警戒すべきだ」と指摘。漏洩対策について、「(情報に)アクセスできる人を限定するほか、重要な技術の管理サーバを他の情報と別にするなど、経営者らはコストをかけてでも対策に取り組むべきだ」としている。
韓国のヒュンダイがトヨタのプリウスをパクるも…プリウスとほぼ同じものをつくりましたが肝心の中身は…
【海外の反応】隣国ヒュンダイがトヨタのプリウスをパクるも…全く売れずとんでもない事態に!!リサイクルもできず絶望的…【にほんのチカラ】
【中国】監視社会の実態【深層NEWS】2022/07/01
中国製EV導入で高まる日本人の生活丸裸の懸念
山崎文明 (情報安全保障研究所首席研究員)
2022年1月21日
日本への中国製EVの進出がますます進む中、自動車データの重要性については無関心な日本人。日本が丸裸にされないうちに自動車データ管理法の制定が急がれる。
日本への中国製電気自動車(EV)の浸透が止まらない。
昨年暮れ、衝撃的なニュースが流れた。京阪バスが京都市内を走る路線で、中国の自動車メーカー比亜迪(BYD)製電気バス4台の運行を始めたのだ。運行には関西電力も参加している。
京阪バスが中国製電気バスの採用を決めたのは、圧倒的な価格差である。国産の電気バスが約7000万円と高額なのに対し、BYD製は、約1950万円で、全く勝負にならない。BYDは2030年までに4000台の電気バスを日本で販売する計画だという。
低価格を武器に日本市場に攻め入る中国製EV
中国製EVは路線バスだけではない。物流大手の佐川急便は配送用車両として、中国の広西汽車集団が生産するEVトラック7200台の導入を予定している。また、「即日配送」で急成長したSBSホールディングスでは今後5年間で、自社の車両2000台を東風汽車集団のEVトラックに置き換える予定だという。
中国製EVの日本市場への浸透は、商用車に限ったことではない。上汽通用五菱汽車(ウーリン)が生産する小型EV「宏光(ホンガン)MINI EV」の低価格を武器に日本進出を狙っている。日産と三菱自動車が今年投入を計画している新型軽EVが政府の補助金を使っても200万円前後なのに対して2万8800元(約46万円)と破格の安さを売りにしている。
こちらのモーターは日本電産製であることから日本進出してきた場合、安全装置を付加するなど日本の安全基準に適合させるため改良が必要だが、そこそこ売れる可能性もあるのではないか。いずれにせよ圧倒的な低価格は、国産自動車メーカーにとって驚異となることは間違いないと思われるが、圧倒的な低価格を実現している背景には、中国政府の戦略であることを忘れてはならない。
中国政府はEVを国の基幹産業にすることを国策としており、バッテリーメーカーやEV自動車メーカーへ投資するとともに世界シェアを上げるために、助成金も出している。一方、中国は世界貿易機関(WTO)に01年12月に正式加盟しているが、加盟後20年もの歳月が経っているものの、助成金の総額は公表していない。
中国が矢継ぎ早に施行した自動車データ安全管理法とは
中国政府がEVで市場を制覇する目的は、単に物量としての制覇だけではない。自動車が生み出すデータを掌握することの重要性を十分、認識しているからだ。
中国では、昨年10月1日に「自動車データ安全管理に関する若干の規定」という法律が施行されている。中国国家インターネット情報弁公室が2021年4月12日付けで「自動車データセキュリティ管理に関する若干の規定(意見募集稿)」を公表し、パブリックコメントを募集した後、8月16日に公布された。わずか2カ月というスピードで「自動車データ安全管理に関する若干の規定(試行)」が施行されていることからも中国政府が、いかに自動車データを重視していることが窺い知ることができる。
この法律の施行前の2021年9月には「中華人民共和国データセキュリティ法」が施行されており、その第1章一般規定、第2条で「中華人民共和国の領土内でのデータ処理活動の実施およびそれらのセキュリティ監督に適用されるものとします。中華人民共和国の外でデータ処理活動を行い、中華人民共和国の国家安全保障、公共の利益、または市民や組織の正当な権利と利益を損なう者は、法律に従って法的責任について調査されるものとします」としていることから、自動車データも国内蔵置を前提としていることがわかる。
この法律でいう自動車データとは、自動車の設計、生産、販売、運営、保守などに関連する個人情報及び重要データをいうとされ、自動車にまつわる全ての行為を適用対象としていことから、自動車産業全体を統制するものである。中国に進出している日本の自動車メーカーもこの法律に従うことになり、新たな貿易の障壁となることが予想される。
なぜ自動車データは重要視されるのか
重要データとは、「一旦改ざん、破壊、漏洩または不正取得、不正利用がなされると、国家安全、公共利益または個人・組織の適法な権益に損害を与える恐れのあるデータ」としており、自動車データ取扱者は、「重要データを取り扱う場合、関連する規定によりリスク評価を行い、省レベルの所管部門にリスク評価報告及び自動車データ安全管理状況年度報告書を提出しなければならない」としている。
重要データの例としては、最初に「軍事管理区域、国防科学工業に係る機関、県レベル以上の党および政府機関等の重要・機微なエリアでの地理情報、人流情報、車両流量情報などのデータ」を挙げている。
自動車の流量情報などの情報は、積み重ねることによって思わぬ情報暴露につながることがある。18年1月に発覚した米軍の秘密基地暴露事件がその例だ。
スマートフォンなどのGPS情報を使ってジョギングやサイクリングなどのアクティビティを記録・分析できるアプリ「ストラバ(Strava)」に搭載されたヒートマップ(Heatmap)機能は、アプリを使っている人のアクティビティデータを取りまとめることで、地球上のどの場所で多くのアクティビティが行われているのかを色で示すことができる。1人の男性が「フィットネス&ソーシャルメディア社のストラバがアクティビティヒートマップ機能をリリース。軍の基地の場所を特定するのに優れている」というツイートをするとともに、シリアに置かれているロシアの「フマイミーン空軍基地」とみられる位置のヒートマップ画像を公開したのだ。基地で任務にあたる兵士やスタッフがスマートフォンやウェアラブル端末のトラッキング機能をオンにしたまま業務や訓練を実施したことで、活動の全てが記録されていたことが原因とみられる。ツイートのマップには、おそらくシリアのどこかと思われる基地の中における軍関係者の行動バターンがクッキリと表れていることがわかるほか、主要施設と思われる場所がハッキリと示されていたのだ。
このほか重要データとしては、「車両流量、運送情報など経済進行状況を反映するデータ」や「自動車充電ネットワークの運行データ」、「認証やナンバープレートなどに関する情報を含む車外動画、画像データ」、「個人情報の主体が 10 万人以上におよぶ個人情報」、「国家インターネット情報部門と国務院発展改革、工業および情報化、公安、交通運輸に関連する部門が明確にする国家安全、公共利益または個人・組織の適法な利益に影響をおよぼす可能性のあるその他のデータ」が挙げられている。
「車両流量、運送情報など経済進行状況を反映するデータ」は、例えば、路線バスの運行情報、特に遅延情報はその都市の経済の活性化状況がわかるし、宅配便の運行情報からはGDPの推計もできるはずだ。
日本も自動車データ管理法の制定を急げ
ことほど左様に自動車データの重要性を理解し、中国国外へのデータの持ち出しを禁止しておきながら、海外へはEV自動車の輸出大国を目指す中国は、その先に自動車データを掌握し、その国を属国化する野望も見てとれるのは、私だけだろうか。
ビックデータの解析が重要だと言われて久しいが、サイバーセキュリティの脅威やビックデータの重要性に大半の日本人は気づいていない。中国に倣って、日本も自動車データの国内処理や国内蔵置の義務づけを図るべきだ。一刻も早く、自動車データについて、経済安全保障の観点から議論が高まることを期待する。
【半導体戦略】産業に影響・・・深刻な半導体不足 日本はどうすべきか【深層NEWS】
2022/06/17
536回 とんでもない中国の銀行#高橋洋一
中国郵政儲蓄銀行(ちゅうごくゆうせいちょちくぎんこう)は、中華人民共和国政府が経営する中国郵政集団有限公司傘下の銀行である。
正式名称は中国郵政儲蓄銀行股份有限公司である。
郵便局の窓口と同居する中国郵政儲蓄銀行(上海)
2007年1月に中国で郵便行政が改組され、中国郵政集団公司(1988年までは中華人民共和国郵電部)が設立。中国郵政集団公司が行う郵政関連事業のうち、同年3月6日に郵便貯金部門を分離、同銀行が設立された。本行(本店)は北京市西城区にある。国営企業(中央企業)関連の中国でも屈指の資産を有する大銀行となる。また、日本における郵政事業民営化と同様に、郵便局に郵便事業と郵便貯金の窓口が同居する形式になっている場合が多い。
発表日:2010年11月22日
タイトル:中国郵政と日本郵便の国際事業拡大に向けた提携について 2010年11月22日
日本郵政株式会社
郵便事業株式会社
中国郵政集団公司(中国北京市、総経理 劉安東/以下「中国郵政」)、日本郵政株式会社 (東京都千代田区、取締役兼代表執行役社長 齋藤次郎/以下「日本郵政」)及び郵便事業株式会社(東京都千代田区、代表取締役社長 鍋倉眞一/以下「日本郵便」)は、本日、北京(中国)に おいて、トップ会談を行い、日中の国際事業の発展のための新たな機会とチャレンジに向けて、協力の強化を実施していくことに合意しました。
具体的には、約4億人と報じられている中国インターネット利用人口の急拡大、約1,300億元とされる中国ネット通販市場の急成長と中国全土に広がる配送ニーズを背景に、今後中国向け 国際通販ビジネスを拡大しようとするお客さまを支援するため、中国全土の個人配送ネットワークを唯一保有する中国郵政と日本郵便が協力して、以下のような様々の取組みを推進するものです。
今回の合意により、両郵政は、株式会社ニッセン、株式会社ヨドバシカメラ、楽天株式会社等のEコマース企業等のお客さまとの国際サービスの利用拡大に関する協議を進めてまいります。
(中国郵政との協力に基づく主な取組み)
1 Eコマース企業等のお客さまの日中物流活動の支援体制構築(共同営業、専用ホットラインの設置等)
2 Eコマース企業等のお客さまのニーズに応じたEMSなどの国際郵便サービスの改善、料金の検討、通関の円滑化、国際物流サービスの提供等
3 中国郵政グループ運営のWEBショッピングモール「郵楽」への日本企業の出店支援
以上
2021年10月06日
ゆうちょ銀行を騙る中国語の不審な電話について(2022年1月12日更新)(关于冒充日本邮政银行的可疑中文电话)
楽天への日本郵政・テンセントの出資に浮かび上がる深刻な懸念
2021.3.16
楽天は12日、日本郵政や中国のネット大手・騰訊控股(テンセント)などを引き受け手とする第三者割当増資を実施し、2423億円を調達すると発表した。その中で、最大の資金の出し手が日本郵政である。日本郵政は楽天との資本・業務提携に約1500億円を投じ、出資比率は8.32%となる。物流やモバイル、デジタルトランスフォーメーション、金融など幅広い分野で提携を強化するとしている。
ビジネス戦略としてみれば、楽天と日本郵政の資本・業務提携はシナジー効果(相乗効果)を期待して評価することもできよう。「歴史的な提携だ」との自画自賛はともかくとして、大方のメディアはポジティブな反応だ。私もそれを否定するつもりは毛頭ない。
しかしそこには、国民の財産と安全保障に関わる見逃せない深刻な懸念が潜んでいる。
政府過半出資の会社による“資本注入”の異様さ
まず、楽天から見れば、今回の提携は歴史的快挙であっても、日本郵政から見れば、違った風景が見えてくる。その際忘れてはならないのが、日本郵政は政府が過半を出資する会社(56.87%を政府・自治体が保有)であることだ。
その親会社の下に、日本郵便、ゆうちょ銀行、かんぽ生命保険という個別の事業会社が置かれている。個々の事業会社が業務提携するのならば、ともかくも、問題は政府が過半出資している親会社が特定企業に約1500億円という巨額の出資をすることが、果たして妥当かどうかだ。
多くのメディアは今回の発表だけを見て論じているが、時間を遡って経緯をたどれば、その異様さが見えてくる。
昨年12月24日、事業会社の日本郵便が楽天と物流分野での包括的な業務提携を基本合意したと発表したばかりだ。その際には、物流での戦略提携を打ち出し、金融やモバイルなど物流以外の事業分野でも幅広く提携について協議、検討していき、3月に包括的な業務提携の最終合意を目指すとしていた。あくまで業務提携が前提だ。
楽天は、物流について日本のEC(電子商取引)市場で攻勢をかける米アマゾン・ドット・コムに対抗していく必要がある。全国2万4000カ所の郵便局のネットワークを抱える日本郵便との戦略的提携は楽天にとってはアマゾンと戦う切り札となり得る。
一方、楽天とゆうちょ銀行、かんぽ生命との接点はこれまでわずかだ。今後の業務提携の検討項目に金融も入っているが、具体的な中身は明らかになっていない。
日本郵政の主な狙いは、流通総額が年間3兆円規模というECモール「楽天市場」の宅配物を優先的に引き受けることにある。もちろん、郵便事業にとっては重要なことではあるが、事業会社である日本郵便による業務提携で十分対応できるもので、昨年末の業務提携の基本合意がそれだ。資本提携、しかも日本郵政から一方的に1500億円を持ち出す必然性はどこにあるのか。
楽天は、日本郵政などから調達した資金の大部分を、基地局の整備など携帯電話事業の投資に充てるという。これが日本郵政の事業に直結するとは思えない。
昨年末時点ではあくまでも広範な業務提携であったのが、たった2カ月半後に急転直下、親会社による1500億円の資本提携が付け加わった。その間、一体何があったのか。
携帯料金の引き下げで苦しむ楽天を“救済”?
菅義偉首相肝煎りの政府主導による携帯料金の引き下げで、昨年4月から携帯電話事業に新規参入した楽天のダメージは大きい。
「大手3社を凌駕(りょうが)する携帯キャリアをつくる」
楽天の三木谷浩史会長兼社長はそう豪語していたが、携帯基地局への先行投資が響き、2020年12月期の最終損益は1141億円の赤字で、これが発表されたのが2月12日だ。連結の自己資本比率も2020年12月末時点で4.9%に下がっている。今後も電波エリアの拡大のために基地局の設置の投資に兆円単位の膨大な資金が必要となるため、厳しい財務状況であった。
そこにこの資本提携だ。話は今年1月に楽天の三木谷社長から持ち掛けたことを、三木谷社長本人が記者会見で認めている。資本提携では多くの場合、相互に第三者割当増資を行う「株式の持ち合い」をするが、今回はそうではない。一方的に日本郵政が楽天に出資した形で、これは事実上、巨額の“資金注入”とも言えるのではないか。これでは楽天に対する“救済”と思われても仕方がない。
資本提携は単なる業務提携とは訳が違う。携帯電話事業のように4社が激しい競争をしている中で、政府が過半の出資をしている会社がその1社に対して巨額の資金を注入するのは、果たして公正と言えるのだろうか。厳格な議論が必要だろう。
政府が過半を出資する会社が国民の財産を特定企業に注ぎ込んだのも同然、とも言われかねない行為は妥当なのだろうか。仮にこうした行為をするのならば、最低限、政府保有株を売却して、政府保有比率を3分の1以下にしてからするのが筋ではないだろうか。
第2に、世間の目が日本郵政との資本提携ばかりに奪われているが、日本の経済安全保障にも関わる懸念もある。テンセントの子会社から約660億円の出資を楽天が受け入れることだ。
テンセントの楽天への出資は経済安保の観点で大丈夫か?
テンセントについては、米国のトランプ政権末期、人気アプリ「WeChat(ウィーチャット)」のダウンロード禁止の大統領令が出され、連邦地裁によって執行差し止めになった。また最終的には見送りになったが、人民解放軍と関係が深い企業のリストに加えて、米国人の投資禁止の対象にすることも一時検討されていた。これらはいずれも米国顧客の個人情報が中国政府に流出するとの疑念が背景にあったからだ。
中国国内では事実上独占的に使用されているWeChatによって、約10億人の国民の会話・行動・購買履歴まで監視できるようになっている。また最近、中国共産党政権はアリババと共にテンセントに対しても急速に統制を強めつつあることは周知の事実だ。テンセントも中国政府への協力を表明している。まさに中国政府によるコントロールが強まって、顧客データの流出の懸念はますます高まっている。
そうしたテンセントが楽天に出資して、今後ネット通販などでの協業も検討しているという。楽天はECのみならず物流も含めた日本のプラットフォーマーだ。楽天は、膨大な個人情報を持ち、ECなどのオンラインサービスのみならず通信インフラでも重要な役割を担っている。楽天へのテンセントの出資は、経済安全保障の観点から大丈夫なのだろうか。
さらに楽天と日本郵政との間で広範な提携がなされると、懸念はいっそう大きくなる。テンセントによる出資以外、楽天との具体的な協業の内容が明らかにされていない。それだけに、テンセントが楽天を介して結果的に、日本郵政に接近する可能性も懸念されるからだ。
日本郵政には日本郵便の豊富な物流データがある。日本郵政は、楽天とデータを共有する新しい物流プラットフォームも構築するとしている。ゆうちょ銀、かんぽ生命には豊富な金融データもある。いわば、個人データの宝の山を日本郵政は抱えている。
これは日本の経済安全保障にも関わる深刻な問題ではないだろうか。日本も安全保障上重要な業種については、外為法で事前届け出を義務付けるなど外資規制をしている。その際には楽天の事業全般を見て、外資による影響力を行使されて安全保障上大丈夫かを判断していくことになる。日本政府も事の重大さを認識して、責任ある判断をすべきだ。
日本郵政と楽天の提携は単にビジネスの目でだけ追っていてはいけない。日本国民の財産や安全保障に深刻な懸念を投げかけていることに気づくべきだ。
テンセント、中国当局が巨額の罰金処分か 米紙報道
2022年3月14日
【広州=比奈田悠佑】中国のネット大手、騰訊控股(テンセント)が中国当局から巨額の罰金を科せられるとの観測が浮上している。米紙ウォール・ストリート・ジャーナル(電子版)は14日、テンセントが手がけるスマートフォン決済事業に関して、当局の規制に違反したと判断される可能性があると報じた。
ウォール・ストリート・ジャーナルが関係者による情報として報じた。それによると中国の金融関連当局が、テンセントのスマホ決済「ウィーチャットペイ」について、マネーロンダリング(資金洗浄)の防止規則に違反したことを発見した。賭博など不適切な取引の資金移動や資金洗浄を可能にしていたという。
罰金については少なくとも数億元にのぼり、規制当局が過去にノンバンクの決済会社に対してマネーロンダリング防止の規則違反で課した罰金よりも大きな規模になるとする。
テンセントは14日、日本経済新聞の問い合わせに対し「現時点で共有する情報はない」と回答した。
中国当局はネット企業への監視の目を強めてきた。テンセントを巡ってはこれまでに、市場の独占を理由に傘下のゲーム動画配信企業の経営統合計画が差し止められるといった処分があった。巨額の罰金では、ネット通販大手のアリババ集団で「支配的な地位の乱用」があったとし、182億元超(3千億円超)の罰金処分が下された。
楽天、三井物産、東京電力…「中国色を消すのがうまい」テンセントの長い手が狙うモノ
ゲームやお笑いを入り口にしつつ…
PRESIDENT Online
馬 化騰(ば かとう、拼音: Mǎ Huàténg、マー・フアテン、英語: Pony Ma、ポニー・マー、1971年10月29日 - )は、海南省東方市生まれの実業家。中国共産党党員。広東省深圳市を本拠とするテクノロジー企業テンセントの董事会主席兼CEO、全国人民代表大会代表。
1993年に深圳大学計算機系を卒業。深圳潤迅通信でソフト開発を手がけた後、1998年11月にテンセントを創業した。その代表作であるインスタントメッセンジャー『テンセントQQ』は中国で最も使用され、影響力のある通信ソフトであることから「QQの父」と呼ばれている。清華大学経済管理学院で顧問委員も務めている。
米政府の「中国締め出し」は、バイデン政権でより強硬に
「通信という国家安全保障のなかで最も重要な部分に、あっさり中国資本が入ってしまったのは正直ショックだ」。中国ネット大手の騰訊控股(テンセント)子会社が楽天へ3.65%出資した事態に、自民党の幹部たちは一様に頭を抱える。
1年前に外為法を改正し、外国人投資家が安全保障上重要な企業に出資する場合、事前審査基準を従来の持ち株比率で「10%以上」から「1%以上」に厳格化した。中国への機微情報や技術流出を警戒するトランプ前米大統領が昨年8月にテンセントや子会社と米企業・個人の取引を禁じる大統領令に署名したのに合わせた措置だった。
バイデン政権になっても米政府による中国締め出しの姿勢は変わらない。むしろ、中国に対する姿勢は強硬になった。
4月に入り、バイデン政権は米国内の民間企業に対し、中国製IT(情報技術)機器やサービスの利用を規制するルールを制定した。米国はこれまでも中国を対象としたハイテク規制を打ち出しているが、新たな規制では規制対象の企業を拡大した。
楽天出資でも米大使館がすぐにNSSなどへ問い合わせ
これまで政府調達の禁止対象になっていた通信機器大手の華為技術(ファーウェイ)や中興通訊(ZTE)、監視カメラ大手の杭州海康威視数字技術(ハイクビジョン)など5社に加えて、米商務省が「外国の敵対者」として挙げる中国、ロシア、北朝鮮、イラン、ベネズエラ、キューバの6カ国の企業が対象になった。対象は広がったが、あくまでも主眼は中国企業だ。
これは米国内で活動する民間企業にも影響が出る。これまでは連邦政府と取引のある米国企業に中国5社の製品を使うのを禁じていたが、新たな規制は政府取引の有無にかかわらず、米国内で活動する企業に対して中国製品の使用を制限する。
さらに対象となる品目数も拡大。今回は通信網や重要なインフラに使う機器、ソフトウエアなどにも対象を広げた。例示されたものとしては個人情報を扱うサービスのほか、監視カメラやセンサー、ドローン(無人機)といった監視システムも含めた。人工知能(AI)や量子コンピューターなどの新興技術も対象だ。
楽天出資の件も、発表が伝わるとすぐに米大使館が日本の国家安全保障局(NSS)や財務省、事業官庁の総務省、経済産業省に、外為法上の取り扱いを問い合わせるなどあわただしく動いた。
「純投資というテンセントの説明は完全には解せない」
菅政権発足後初の日米首脳会談を控えていた首相官邸も焦った。テンセント子会社による出資は「アメリカから疑問をなげかけられる」との見方が広がり、首相官邸で開いた首相補佐官による会議では、首相の訪米前の懸案として議題に上げ、対応策を練った。
結局、日本政府は外為法にのっとり、日米両政府で楽天グループを共同で監視するとのことでその場を収めたが、政府からの監視が強まるとの報道を受けた楽天の株価は、4月21日、前日比55円(4.1%)安の1278円まで売り込まれた。
日米政府が中国企業の自国への投資について監視を強める中で、テンセントがいとも簡単に楽天に出資できたのはテンセントの投資目的が「純投資」とされていたからだ。
日本政府は改正外為法の制定にあたり「日本への海外からの投資の流れを阻害しないようにする」(経済産業省幹部)との観点から幅広い免除基準を設けた。「非公開の技術情報にアクセスしない」「自ら役員に就任しない」などの条件を満たす場合は、事前届け出を免除することにした。
免除基準に該当するかどうかは自己申告で、順守を誓約して事後報告すればよい。「純投資というテンセントの説明は完全には解せない」(日本政府関係者)との声はくすぶるが、制度上は認めざるをえない。
「テンセントは表向きゲーム配信企業という形で入っていく」
米国では財務省や国防総省、エネルギー省から専門人材を集めた常設の対米外国投資委員会(CFIUS)がある。脅威が大きい企業には事後的に株式の売却命令を出すなど強権を振るう。非公式の事前相談も定着しており、一定規模以上の外資出資のほとんどはCFIUSとの調整が必要となる。投資の「日本離れ」を懸念するばかりに、強権を振るうのに二の足を踏む日本とは対照的だ。
テンセントの「長い手」は楽天だけではない。幅広い事業を手がける大手商社の三井物産や、日本のエネルギーの根幹を担う東京電力とも提携している。
NTTグループの幹部は「テンセントは表向きゲーム配信企業という形で相手国に入っていく。地元企業にうまく入り込んで中国色を消すのがうまい」という。三井物産と最初の関係を持ったのもテンセントが出資する中国の動画配信サービスを手掛ける「闘魚(ドウユウ)」を運営する武漢闘魚網絡科技を通じてだ。
テンセントとはいかなる企業か? 時価22兆円、ゲーム世界一、WeChat11億人の脅威
ソフトバンク子会社を買収へ
コメントをする
★
ソフトバンクが、同社子会社のスーパーセル(Supercell)の売却を検討していると発表しました。その売却先として名前が挙がっている企業、それが中国の「テンセント(騰訊、Tencent)」です。日本ではまだあまり知られていませんが、同社は今や、ゲームの売上高でソニーやマイクロソフトを上回って世界トップ(NewZoo調査)。提供している複数のメッセンジャーのMAU(月間アクティブユーザー数)を単純合算すると11億人超(ちなみにFacebook Messengerが6億人、LINEが2.2億人)にのぼり、それを基盤にしたFinTech市場でも存在感を発揮しつつあります。同社の売上高は、日本の大手ゲームメーカーである任天堂と比べて、売上高で3倍、営業利益で17倍、時価総額は約10倍にもなります。今回、この「テンセント」を徹底解剖していきます。
フューチャーブリッジパートナーズ 長橋賢吾 編集:編集部 松尾慎司
テンセントとは?QQやWeChatなどのコミュニケーション基盤
「テンセントはヤバい」、上場を控えたある中国人経営者が筆者に語った言葉です。そのテンセントとは、いったいどのような企業なのでしょうか? 一言で言うと、任天堂のようにゲームを提供しながら、LINEやFacebookに近いサービスを手がける企業です。同社の売上高(2015年12月期)は、1,028億元(1元16.5円換算で1.6兆円)、同年度の税引き前利益は362億元(同5,903億円)、時価総額は1.6兆香港ドル(1香港ドル13.8円換算で22.1兆円、16年6月7日現在)にのぼります(ちなみに日本最大のトヨタの時価総額は約18兆円です)。テンセント、LINE、Facebook、これらの企業に共通している点は、各社が強力なコミュニケーション基盤(プラットフォーム)を保有していることでしょう。テンセントには強力なコミュニケーションプラットフォームが3つあります。1つめは、オンラインメッセージサービスの「QQ」、2つめはモバイル向けSMSや通話機能を提供する「WeChat& Weixin(以下、WeChat)」、3つめはSNS機能を提供する「QZone」です。
同社の3つのコミュニケーションプラットフォームのMAU(Monthly Active User:月間アクティブユーザー数、どれだけそのプラットフォームが利用されているかを示す指標)が図1です
同社の創業は1998年、インターネットの利用がようやく開始されたばかりのころ。翌年の1999年2月にはIM(インターネットメッセージング)サービス「QQ」をリリースし、中国におけるIMサービスのスタンダードとなりました。その後もPCの利用からモバイルへの利用へシフト、2016年第1四半期のMAUは8.7億ユーザーに及びます。
中国人口は13.7億人(2015年末)なので、単純計算では中国人口の63%がQQを利用していることになります。そして、利用の形態もスマートデバイス(スマホ、タブレット)のMAU(2016年第1四半期)は6.58億ユーザーと、PCからスマホへのシフトが進んでいます。
テンセントが他社と違うところは、一つのサービスに依存しないこと。上記のQQにくわえて、2011年にリリースしたモバイル向けメッセンジャーが今、中国を席巻している「WeChat」です。中国版LINE・Facebookメッセンジャーに近いコンセプトですが、スマホの本格的な普及にあわせてMAUも増加、2016年第1四半期でのMAUは7.62億ユーザーとサービス開始してから5年近くでMAUではQQに迫るまでに至りました。
上記2つに加えて、写真シェア、ブログなどのSNS機能を提供するQZoneも2016年第1四半期でのMAUは6.47億人とQQ、WeChatに及ばないものの、多くのユーザーを抱えており、図2に示すように、中国全土でのMAU上位10アプリのうち、4アプリがランクインしています。
図2 中国でのMAU上位10アプリ(2016年3月時点)
こうしたテンセントが提供する3つのコミュニケーションプラットフォームは今や、中国でのネットコミュニケーションプラットフォームそのものなのです。
テンセントのマネタイズはVASで
コミュニケーションプラットフォームにおいて、もっとも重要なKPI(Key Performance Indicators: 重要業績評価指数)が「MAU(Monthly Active User)」です。月間アクティブユーザーとは、1か月に1度以上利用するユーザーの数で、そのプラットフォームの“賑わい”を示します。そして、MAUが多ければ多いほど、賑わっており、そこから課金サービスも生まれます。テンセントのマネタイズ方法も、まさにこうした“賑わい”を利用した課金サービスで、同社ではこれをVAS(Value Added Service: 付加価値サービス)と定義しています。具体的なVASは、図3に示すように、QQにおいてはメールボックスの拡張、友達の最大人数を拡張できるQQ VIP会員、プレミアムコンテンツにアクセスできるQzone VIP、そして、同社のもう一つの事業の柱であるオンラインゲーム(ACG:カジュアルゲーム、MMOG:大規模マルチプレイヤーオンラインゲーム)です。
テンセントのゲーム事業、その圧倒的なシェアとは?
テンセントは、2004年、自社での最初のカジュアルゲーム(簡単な操作だけで短い間に楽しめるゲーム)QQ堂をリリース後、2006年にはQQ音速、2007年にはQQ三国とQQの拡大のタイミングで次々とゲームをリリースしました。そして、自社開発のみならず他社開発のゲームを、“賑わい”を活かして、自社のコミュニケーションプラットフォームで展開するライセンス方式も展開しています。
特に中国の場合、海外の企業の参入が難しいことがあり、海外企業にとっては、テンセントのような“賑わっているプラットフォームに自社ゲームをライセンスすることは、中国市場を開拓するうえでも、大きなメリットといえます。たとえば、日本に本社を置くネクソンもテンセントを通じて、PCオンラインゲームであるアラド戦記(Dungeon&Fighter)を提供しています。2016年6月には最大同時接続者数が500万人を突破したことを発表し、話題になりました。
結果として、図4に示すように、テンセントの中国市場でのクライアントゲームでのマーケットシェアは54.4%と他社を圧倒。テンセントの売上に占めるオンラインゲームの割合も53%(16年第1四半期実績)と自社の稼ぎ頭(キャッシュカウ)となっています。
そして、図5に示すように、中国のゲーム市場ではモバイルが急速に拡大し、2016年にはPCを追い抜く勢いです。いうまでもなく、こうしたモバイルゲーム市場の拡大は、モバイルユーザーの大半をおさえているテンセントにとっては追い風であり、この“賑わい”を活かして、さらなるゲームの自社開発・ライセンス、ゲーム・アイテム課金の拡大が見込めます。
中国テンセントに見られてしまう楽天の「帳簿」
業務資本提携に生じるこれだけの懸念
2021.4.6(火)
(平井宏治:日本戦略研究フォーラム政策提言委員・株式会社アシスト代表取締役)
2021年3月31日、中国企業のテンセントは、その子会社を通じて、楽天が新たに発行した株を購入し(「第三者割当増資」という)、楽天の第6位の大株主になった。本件は3月12日に公表されて以降、識者から懸念が示されていた。にもかかわらず、楽天はテンセントとの業務資本提携を強行した。
本稿では、ポートフォリオ投資、楽天の帳簿閲覧権、中国の国家情報法との関係などから懸念される問題を取り上げたい。
テンセントとは何者か
楽天の大株主になったテンセント(騰訊)グループとは何者だろうか。チャットアプリ「WeChat」を知る人は多いが、その実態を知る人は少ない。
同社は、香港証券取引所に上場する持株会社で、中国の広東省深セン市に本拠を置く。傘下にインターネット関連の子会社を持ち、ソーシャル・ネットワーキング・サービス、インスタントメッセンジャー、Webホスティングサービスなどを提供する。
2020年8月、アメリカ政府はテンセントとの取引を禁止すると公表した(注:実際には禁止に至らなかった)。トランプ大統領は、「このデータ収集によって中国共産党がアメリカ国民の個人情報や機密情報の入手が可能になる恐れがある」と指摘した。取引禁止になれば、WeChatの利用が禁止されるため在米中国人の間に衝撃が走った。
一例だが、アメリカのメディアは、中国人産業スパイがWeChatを使い中国国内の同僚と連絡を取り、「中国軍によるアメリカ軍軍事戦略データの解読とリスク評価」に関する研究論文について議論していたと報道し、WeChatが連絡ツールとして使用されていたことが明るみに出た。
楽天「政府から監視」の異常事態、原因となった中国企業の狙いは
ダイヤモンド編集部
高口康太 2021.4.24
楽天グループが、日米政府から「共同監視」を受けるという報道が浮上した。原因は、3月に中国のIT大手テンセント(騰訊控股)から出資を受けたことだ。楽天はこの出資を純投資としているが、果たしてテンセント側にはどのようなもくろみがあったのか?深堀りすると、楽天こそがテンセントにとって必要な「パーツ」であることが浮かび上がった。(ダイヤモンド編集部特任アナリスト 高口康太)
「政府から監視」で楽天株は急落
出資したテンセントの真意は?
楽天グループが日米両政府から共同監視を受けると報じたのは、2021年4月20日付の共同通信だ。原因となったのは楽天が3月に発表した、中国のIT大手、 テンセント(騰訊控股)からの出資で、楽天の顧客情報がテンセントと中国当局に伝わる事態を警戒しているという。
この報道は英字媒体にも次々と転電され、国内外に広がった。翌21日の楽天の株価は前日比の終値ベースで6%下落し、この1日で時価総額は1155億円減少した。この額は、楽天はテンセントによる出資で得た金額約657億円を大きく上回る。23日午前の時点で株価は報道以前の水準を回復したが、「政府監視ショック」に楽天は肝を冷やしたに違いない。
楽天はテンセントの出資目的は「純投資」だと説明し、経営や技術、個人情報への関与はないと説明する。ただ一方で、「テンセントグループとの関係強化を図ることは、当社グループの競争力と機動力の向上につながる」「今後、協業していく分野として、デジタルエンターテインメント、Eコマースなどを検討」友発表(3月12日のプレスリリース)している。そしてテンセントの経営戦略に鑑みれば、出資は事業提携を目的としたものである可能性が高い。
ならば中国のテンセントは、楽天への出資を通じて何を獲得しようとしているのか?
高市氏が〝捨て身〟の告発!岸田内閣「中国スパイ」を野放しか 「セキュリティー・クリアランス」提出に圧力、政府内の親中派と暗闘を示唆
2022/9/30
高市早苗経済安全保障担当相が28日、「捨て身の告発」に打って出た。先端技術の流出を防ぐため、重要情報を取り扱う研究者らの身分の信頼性を確認する「セキュリティー・クリアランス(適格性評価)」をめぐり、政府内の〝抵抗勢力の存在〟や〝親中派との闘争〟を示唆したのだ。「国葬(国葬儀)」で27日に見送られた安倍晋三元首相は生前、日本の国力を維持・発展させるため、欧米諸国では常識である「スパイ防止法」の制定にも意欲を持っていた。日本と中国は29日、国交正常化から50年を迎えた。岸田文雄政権の、国民と国家を守る気概が問われている。ジャーナリスト、有本香氏による緊急リポート。
現役閣僚による爆弾発言が飛び出した。
「大臣に就任した日に言われたのは、『中国』という言葉を出さないでくれというのと、来年の通常国会にセキュリティー・クリアランスを入れた経済安全保障推進法を提出するとは口が裂けても言わないでくれと言われました」
高市氏が28日夜、「BSフジLIVE プライムニュース」に出演した際の発言である。これに岸田首相がどう対処するか〝見もの〟だ。
経済安全保障については今年5月、経済安全保障推進法が成立したが、同法には最も重要な要素が欠落している。それがセキュリティー・クリアランス、「人の適格性の審査」だ。あえて簡単に言えば、外国のスパイを取り締まるルールである。
同法成立の前から、筆者はこの欠落を厳しく批判していた。「仏作って魂入れず」のような経済安保法にどれほどの意味があるのか、ということである。国会提出前の今年2月には、自民党の政調会長だった高市氏と『月刊Hanada』で対談し、次のようなやり取りをした。
高市氏「今年の大きな柱はやはり経済安全保障政策です。どのような事態になっても必要な物資を国内で調達できる環境、サイバー攻撃から国民の生命や財産を守り抜くこと、機微技術の国外流出を防ぐことなどを柱とする『経済安全保障推進法』の第1弾を今国会で必ず成立させたい」
筆者「かねてより高市さんがおっしゃっていた外国人研究者などのスクリーニング(選別)は、その第1弾には含まれるんですか?」
高市氏「外国人研究者のスクリーニングは第2弾でやります。これを入れると今国会では通りませんから」
正直に言うと、7カ月前、高市氏のこの答えにひどく失望したものだ。
対談での高市氏は、「岸田政権をサポートする」「7月の参院選に勝利することが大事」という表明に終始した印象だった。それは政調会長という立場からすると当然ではあるが、あまりにも型通り、多くの読者の失望を誘うものでもあった。
実は、筆者はこのときの失望を、安倍氏にもぶつけた。「人のスクリーニングを盛り込まないなら、意味のない法律です」と。
筆者の怒りに対し、安倍氏は「人のスクリーニングを盛り込んだ法律は必ずやるから。こちらもプッシュしていく。ただ、容易でないことは理解してほしい」と答えていた。
しかしいま、昨晩の高市氏の「告発」を聞き、生前の安倍氏の言葉を思い返すと、経済安保をめぐる自民党内の「闘争」、とりわけ「親中派との闘争」が実感を伴ってみえてくる。2月に筆者が抱いた強い失望は、こうした暗闘への筆者の不理解も少々手伝ったかと反省する。
今般、高市氏が「捨て身の告発」に打って出たのには、安倍氏の国葬儀が無事終わったことも関係しているかもしれない。国葬儀には筆者も参列したが、かけがえのないリーダーを喪った悲しみ、反省を改めて深くする一方で、国難のいまこそ、「闘う政治家」だった安倍氏の遺志を、皆で継ぐべきという思いにもさせられた。
高市氏は同じ28日、BS日テレの「深層NEWS」にも出演し、政府による国葬実施の決定過程について次のような苦言を呈している。一連の高市発言を「岸田おろし」や「閣内不一致」というレベルの話題にして済ますべきではない。
「中国のスパイ」一つ取り締まれない日本に明日はない。安倍氏の志を真に継ぐのは誰なのか―。はっきりさせるときである。
習近平氏は「プーチン化」?胡錦濤氏が退席、慣例破りの3期目…松田康博教授の分析
2022年10/31(月)
今月開かれた中国共産党大会を経て、習近平共産党総書記(国家主席)が慣例を破る形で3期目の政権を発足させた。大会では、前国家主席の胡錦濤氏が途中退席する異例の事態も起きた。謎が深まる中国の政情をどうみたらいいのか。東大東洋文化研究所の松田康博教授は「習氏はロシアのプーチン大統領のような存在になった」と指摘する。(聞き手・牧野愛博)
――党大会の閉幕式で、胡錦濤前国家主席が退場する場面がありました。
体調不良という指摘もありますが、退場する足取りはしっかりしていました。外国メディアの入場を待って、抗議の意思を示し、内部の分裂をわざと国外に見せつけたのだと思います。
閉幕式は党中央委員メンバーが確定した後に行われました。そこには李克強首相と汪洋全国政治協商会議主席の名前がありませんでした。
胡錦濤氏は開幕式には柔和な表情で参加していました。おそらく、彼は途中まで、習氏に李克強氏らの留任も含めた妥協案を見せられていたのだと思います。
実際、外部では「汪洋氏の首相起用案」などのうわさが飛び交っていました。ところが、最後になって習氏に裏切られたため、胡氏はあのような行動に出たのだと思います。
しかもこの段階ではまだ、胡錦濤氏に近い共産主義青年団出身の胡春華副首相が中央委員に選出され、政治局常務委員会入りする可能性がまだ残っていました。
それが、党大会直後の第1回中央委員会総会で、逆に政治局からも排除されていることが判明しました。
胡錦濤氏にしてみれば、「だまし討ちに遭った」に等しい思いだったでしょう。習氏に抵抗する勢力は、おそらくこうして排除され、大勢は決したのだと考えられます。
その代わり、習氏に近い李強・上海市党委員会書記が政治局常務委員に起用され、序列第二位になりました。
李強氏は年内に開かれる全国人民代表大会(全人代)常務委員会で副首相になり、来年3月に首相に就任するかもしれません。
昨年の全人代で、全人代組織法が改定され、5年に1度の本大会ではなく、2カ月に1回の常務委員会でも副総理を交代できるようになりました。おそらく、この時から李強氏の起用を考えて準備していたのでしょう。
――今回の共産党大会は中国の内政にどのような影響を与えるでしょうか。
鄧小平氏の改革以降、中国は30年にわたって「長老の意見の尊重」「バランスを重視した人事」「年齢制限」「後継者育成」などのルールを積み上げてきました。
習近平氏は、それらのすべてを破壊してしまいました。今後、中国ではルール無用のむき出しの権力闘争しか残らないでしょう。
さらに、習氏は今回の人事で、市場メカニズムや国際ルールを尊重する経済テクノクラートを排除しました。おそらく「共産党の天下を潰さないため」でしょう。
今後は、共産党の利益のみを考え、市場メカニズムや国際ルールを軽視した経済政策運営を行うでしょう。
習近平氏は今後、4期目どころか、恐らく死ぬまで指導者の地位にとどまるでしょう。
4期目以降、政治局常務委員ではなく、毛沢東時代をまねて党主席ポストをつくり、人前に出ない指導者になっていく可能性があります。
その方が権威を高め、会議や演説なども減らすことができるため、体力を温存できます
中国国内にはもちろん、反発する声もあります。しかし、SNSで不穏な情報を発信したら、すぐにアカウントを抹消されてしまいます。
「ゼロ・コロナ」政策を理由に導入した携帯電話のアプリで、全国民を1日24時間、365日にわたって監視し、行動を制限できる制度を作り上げてしまいました。
当局にとって都合の悪い人間をすぐに拘束できますから、誰も抵抗できません。
――対米関係はどうなりそうですか。
楊潔篪中央政治局委員の代わりに、王毅外相が中国外交のトップに就きます。外交の連続性は担保されますが、40年以上対米外交のキャリアがある楊氏に比べ、王氏は英語力や対米人脈が十分ではありません。
外交部長(外相)の人選にもよりますが、米国とのパイプは細るかもしれません。
米国が呼びかけている核兵器を搭載できる中距離弾道ミサイルの削減交渉には応じないでしょう。
現時点で中国が約300発を配備しているとされるのに対し、米国はゼロです。この有利な状況を自ら放棄することは考えられません。
核軍縮交渉にも応じないでしょう。中国は、ウクライナ危機を見ています。米国がロシアのウクライナ侵攻に直接介入しなかったのは、プーチン大統領による核の脅しが効果を上げたからだと考えています。
米国がロシアとの軍備管理で手足が縛られている一方で、中国には何の制約もありません。中国は台湾有事の際、米国に介入させないだけの核保有の増強を急ぐでしょう。
一方、ウクライナを巡って、ロシアに軍事支援をしない従来の立場は維持するでしょう。中国の産業は西側経済と結びついています。米国のセカンダリー・ボイコットを避ける必要があるからです。
ただ、半導体のように軍用にも使えるデュアル・ユース(軍民両用)製品の提供はすでに、ひそかに行っているかもしれません。
――北朝鮮の7回目の核実験が迫っているという情報がありますが、中国は北朝鮮の核保有を認めるでしょうか。
中国は北朝鮮の核保有を支持せず、不快感も示すかもしれませんが、黙認する可能性が高いと思います。
北朝鮮が核実験に踏み切った場合、国連安全保障理事会で新たな制裁決議を提案しても、中国は決議を棄権するでしょう。
そればかりか、ロシアのように拒否権を行使する可能性すら否定できません。
いずれにしても、北朝鮮を支持するなかで、核開発だけは許さないとしてきた中国の戦略の大きな転換になると思います。
――台湾情勢にはどのような影響を与えますか。
中国は依然、「平和統一」を目指していますが、話し合いによる合意形成ではなく、軍事力委を背景にして相手を屈服させる「強制的平和統一」にかじを切ったと思います。
そのため、中国は現在猛烈な軍事力の増強を続けています。
中国が台湾を武力統一するためには、まだ空軍力や海軍力が十分ではありません。中国は、台湾占領に必要な強襲揚陸艦を8隻保有する計画を持っていますが、まだ3隻目が就役したばかりです。
台湾も非対称戦能力を積み上げていますから、武力侵攻は容易ではないでしょう。
従って、今後数年のうちに、台湾に全面侵攻する蓋然性は低いと思います。習近平氏は今後、最低で10年間は指導者の地位にとどまるつもりでしょうから、焦る必要はありません。
当面は軍事力を強化しながら、米国で孤立主義的な傾向を持つ、くみしやすい政権が登場するのを待つと思います。
――日本は中国とどう付き合えばよいのでしょうか。
習近平氏は日中関係を好転させたいと思っています。米国との戦略的対立のなかで、日本はまだ利用価値があると考えているからです。
ただ、日本が懸念を深めている尖閣諸島の領有権問題で譲歩する考えはありません。
尖閣諸島問題で日本を屈服させたうえで、日中関係を良くしたいという独善的な態度です。こんな状況で日中関係が好転することは考えにくいでしょう。
日本が今やるべきことは、米国などと協力して、中国による台湾への武力行使のコストとリスクを高めることです。
習近平氏が最も重視しているのは共産党支配の継続です。「台湾に武力侵攻すれば、米国などの介入を招き、共産党支配がかえって崩れてしまう」と思わせれば、中国の武力侵攻を遅らせたり、抑止できたりします。
そのために、日本は防衛力を強化する必要があります。日本はほぼ確実に、台湾有事に巻き込まれると思うからです。
在日米軍を攻撃すれば、それは対日本攻撃を意味します。日本の防衛力が強ければ強いほど、中国は反撃を恐れて二の足を踏むのです。
防衛費の増額は1兆円か2兆円かという議論ですが、ウクライナを見ればわかるように、戦争が実際に起きれば、簡単に100兆円規模の被害が発生します。金額を惜しんでいる場合ではありません。
日本は防衛関連施設の抗たん性を高め、継戦能力を強化し、反撃能力を保有するなどの努力を進めるなど、抜本的な防衛力強化に踏み切るべきです。
そのうえで、米国が必ず、東アジアの安全保障に関与するよう、同盟関係を強化していくべきです。
習近平氏がこれまで積み上げたルールを全て破壊し、また経済や対外関係を悪化させ続けることで、「ポスト習近平」の中国は混乱に陥り、対台湾武力行使の余裕などなくなる可能性があります。
それまでの間、日本は米国などと協力して抑止力を増強して時間を稼ぐことが何よりも重要になると思います。
「中国共産党が日本の学問の自由を浸食」専門家が危機感 北海道教育大の元教授拘束から2年
2021.05.25
北海道教育大の元教授で中国籍の袁克勤(えん・こくきん)さん(65)=札幌市在住=が中国に帰国した際、突如拘束された事件から2021年5月25日で丸2年になる。
中国側は「スパイ罪」で起訴したとしているが、詳しい内容は明らかにしていない。これまでも日本在住の研究者が中国で拘束されたケースは複数あるが、いずれも詳しいことはわからないままだ。
袁さんの救出を支援するグループに参加し、自身も中国法が研究テーマの鈴木賢・明治大教授は「当事者も何があったか語らない中、臆測だけが広がり、中国共産党が嫌がりそうな研究はやめておこうという自己規制すら出始めている」と危機感を抱いている。本人に詳しく聞いた。鈴木賢・明治大供給=ハフポスト日本版提供
プロフィール
すずき・けん 明治大現代中国研究所長、北海道大名誉教授。法学博士。専門は中国法、台湾法、アジア法。1960年生まれ。北海道大法学部を卒業後、同大大学院法学研究科で研究。同大教授などをへて2015年に明治大教授に就任、翌年から現職。
――中国政府は袁さんをスパイ罪で起訴した、と発表していますが、詳しい内容はわかりません。いったい何が問題視されたのでしょうか。
袁さんがしていた研究は1940~1950年代の東アジアを扱っていて、特に中華民国が台湾に移り、日本と講和を結んだころの歴史研究なんです。
中国政府にとってはデリケートな台湾問題に関係しているわけです。推測でしかないのですが、当然、研究上の資料収集などもそのあたりに関係するでしょうから、それがスパイの容疑になったのではないかなと想像します。
実は今、特に歴史研究者は中国当局から警戒されており、危険が高まっていると思います。実証的にやる研究者ほど危ない。というのも、歴史というのは共産党にとってはすごく重要なものだからです。
中国共産党は歴史の「解釈権」を独占し、「物語」を作り上げて政権を正当化してきたわけですね。従って、学者が研究という形で新たな事実の掘り起こしなどをすることを非常に嫌います。自分たちの正当性が切り崩されかねないので。袁さんの事件から4カ月後に拘束された北海道大の教授も専門が近現代史です。
共産党はよく、自分たちが政権を握っていることについて「歴史が選択した」と言うわけです。
でも、中国共産党が言う歴史って実証性がないんですよ。「物語」ありきだから。党に都合のいいようにつないで、物語を構成しているだけ。生の資料から立ち上がっているものではないのです。
だから、実は「歴史は共産党を選択していたとは言えない」ということになると都合が悪いんですよね。全部ちゃぶ台返しになっちゃう。
これは民主化されていない独裁体制の宿命だと思いますね。民主化されていれば、政党は選挙によって政権の正統性を獲得するわけですが、一党独裁を続ける中国共産党は、ずっと歴史にこだわらざるを得ないんです。
最近も、革命で重要な役割を果たしたとされる英雄たちを侮辱する行為を罰する法律というものができました。この法律によれば、新たな歴史的事実を発見しただけなのに、侮辱だとして処罰されかねないわけです。
歴史の研究をしていると、英雄とされてきた人には実は知られざるとんでもない一面があった、みたいな話はよくあるし、その意味で歴史の新たな見直しみたいなことはどんどん進められるんですが、そういうことを法律で禁止しているわけですね。
特定の歴史観を押しつけているわけですが、そういう意味では、日本の侵略の歴史も彼らにとってはすごく大事です。それが人々のナショナリズムを支える上で、非常に利用価値がある。
そうやって形成されたナショナリズムが今度は政治の正統性をさらに強める。だから中国は日本に対し、ことあるごとに歴史問題を繰り返し持ち出すのです。
――袁さんの処分をめぐっては、不起訴が2回あり、ようやく3回目で起訴されたことがわかっています。
当局としても拘束したものの、結局、罪に問える事実をつかんでなかったんじゃないでしょうか。一方で、袁さんは芯の強い性格で、身に覚えのない罪を認めるような人ではない。
ここまで拘束しておいてやっぱり何もありませんでした、お帰り下さいというわけにはいかないのでしょう。だから何か起訴するための理由を必死で見つけようとしたんじゃないですかね。だからこそ時間もかかった。
ただ、中国の刑事政策では、最後まで抵抗する人に対してはより重く、罪を認めるものには寛大に処罰することになっています。
黙秘権もありません。刑事訴訟法には「真実を供述する義務がある」と規定されています。黙秘は真実を供述する義務を果たしていないとみなされ、重く処罰されます。だから袁先生の処遇も気がかりです。
――鈴木さん自身も研究テーマが中国に関係しています。袁さんの事件をどう受け止めていますか。
明日は我が身だと思いましたね。中国に行けばいつ捕まるかわからない状況だなと。しかも僕の研究は台湾にも関係しているから、中国共産党にとってはあまり面白くない人物だと思います。
以前からそう思って中国を行き来していました。実際、一度短時間ですが拘束されたこともあります。ただ、私は信念として、捕まるかもしれないということで、自分の活動を控えるとか、わきまえるような人間ではありません。それだけに当面は中国には行けないなという感じですね。
私に限らず、これは袁先生だけの問題とは考えない方がいいと思います。日本で研究している中国研究者全体の問題だと受け止める必要があります。今の状況では、日本の学問の自由が中国共産党によってどんどん浸食されてしまうでしょう。
これまでも、中国籍の方を含め、日本で中国研究をしている人たちは複数人拘束されているわけですが、彼らは解放されたあと、なぜ捕まったのか、どういう取り調べを受けたのか、どうして帰れたのか、当局から何を言われているのか、一切何も言わないんです。
もちろん、それだけ脅されているんでしょうから同情もしますけど、それでも我々にはなぜ拘束されたのかが一切わからず、臆測だけが広がる。中国共産党に目を付けられるようなことを書いたり、発言したりしないよう自己規制してしまうようになる。
捕まえたのは1人や2人だとしても、それによって日本にいるほかの中国関係の研究者からも学問の自由を奪うことができると。これはまずいなと思いました。
私が見るところ、中国関係の研究者たちは、日本人も含めて共産党の顔色をうかがっている人が大部分です。
「中国に行けなくなるのではないか」「交流ができなくなるのではないか」「自分の研究活動にマイナスになるのではないか」、そういう心配をして、自己規制している人が多いです。
特に在日中国人の学者たちは、ほとんど安心して帰国できないのではないでしょうか。結果的に御用学者のようになってしまう人もいます。共産党の嫌がるようなことは言わない。そういう研究はそもそもしないという方向に。
中国の国内ではとっくにそうなっていて、日本にいる学者たちもそうなりつつあるということです。これこそ中国共産党の思うつぼです。
ですから、とにかく袁先生の件は日本で関心が持たれていて、強い抗議の声が上がっているということを中国政府に見せなければならない。そうすることで袁先生の解放にもつながと思います。
――言論や学問の自由に対する締め付けは、習近平体制になってから厳しくなったのでしょうか。
そうですね。明らかに変わりました。国家安全関係の法律もどんどんできています。国家と言うけど、それはミスリーディングですね。
正確には一党独裁安全。今の中国は党と国家が一体化しているので、国家安全とはすなわち党の安全ということです。
習政権はなぜ締め付けを強化しているのか。私が思うに、一党体制を維持することに対する危機感が高まっているんだと思います。
習近平氏は国家主席の任期を撤廃し、来年の党大会でさらに次の任期も最高権力者として居続けようとしているでしょう。今のうちに異論を徹底的に排除し、盤石の体制で次の任期に入りたいと思っているのではないでしょうか。
そして危機感というのは、一つには経済成長の鈍化です。これまでは経済発展によって共産党は正統性を獲得してきたわけです。しかし成長率はしだいに落ちています。
日々生活が豊かになっているから消極的ではあれ、共産党を支持しているという国民は多いでしょう。でも経済発展が終わったら、それが一気に瓦解に向かう可能性がある。そんなことを予見して、あらかじめ手を打っているんだと思いますね。ものすごい深慮遠謀です。
それに共産党の情報網はものすごいので、私たちの考えがおよびえない危機感があるのかもしれません。中国は今や、あらゆるものがデジタル化されていて、それにより収集された当局の情報の量と質はすごい。
体制の危機につながりかねない情報というのもたくさんあるのでしょう。それを先取りし、対応していくことが政権延命にとって必要だと考えているはずです。
――日本政府に何を求めますか。
在外公館にとっては邦人保護が優先事項です。邦人であれば大使館関係者が定期的に会うこともできる。ところが袁先生は中国籍なので面会できてないし、中国側としても会わせる義務はない。
そうは言っても日本の大学に25年以上も勤めてこられた研究者ですから、国籍が違うというだけで簡単に切り捨ててしまっていいわけがありません。
しかも先ほど言った通り、日本における学術分野に対する萎縮効果というのは著しいわけです。日本の学問の自由が制約されているわけで、これは日本の問題とも言えます。
ただ、表立って日本政府が動くのは正直やりにくいですよね。内政干渉にもなりかねないし。難しいです。
今後はおそらく、日本国籍を取る中国人の研究者が増えてくるんじゃないでしょうか。研究のために中国に行かなかったとしても、家族がいれば帰らないわけにはいかない。だけどこの状況ではとてもじゃないですが怖くて帰れない。
日本国籍を取っていれば、仮に拘束されたとしてもいろんな支援を受けられます。日本政府も助けてくれるでしょう。
そもそも捕まえること自体のハードルも高くなります。外交問題になるので。
権力に取りつかれた「習近平」が、また「暴走発言」…台湾に本気で戦争を仕掛け始めた…!
2022年10/25(火)
あまりにも露骨な人事
ひと言で言えば、強引さが目立つ第20回大会だった。「68歳定年」(七上八下)の慣習が反古にされ、69歳の習近平総書記が3選された。67歳の李克強首相が党の役職から完全に外れ、次の首相候補と目されていた59歳の胡春華副首相は、最高指導部(中央政治局常務委員)への登用どころか、その下の政治局員からも漏れた。
また、総書記時代、李克強首相を後継者にと動き、「反習近平」派と目されてきた胡錦濤氏も、大会の途中で係員に腕をつかまれ退席(体調不良とされているが)した。
後述するが、どんなにワンマン経営の企業の社長でもここまで露骨な人事はしないだろう。
党規約改正案の採決でも強引さが目についた。閉幕に先駆け、習近平総書記は、自らの権威強化に向けた表現を党規約に盛り込む改正案の採決をはかった。投票などではなく、「同意しない人は挙手をお願いします」という形式の採択では、表立って反対できる参加者などいるはずがない。
こうして、自身への不満を強引に抑え込んだ習近平総書記は、最高指導部の面々を、直属の部下で「ゼロコロナ政策」の指揮を執った李強氏(63)、長く秘書を務めてきた側近中の側近、丁薛祥氏(60)といった側近で固め、3期目の御代をスタートさせたのである。
いかにも、自身を「建国の父」毛沢東に重ね合わせる習近平総書記らしい手法だが、今回の党大会で明らかになったことを整理しておこう。
明らかになった「3つの項目」
(1)毛沢東に匹敵する存在になった習近平
習近平総書記に対し、中国建国の父、毛沢東に匹敵する権威づけが図られ、権力集中がこれまで以上に進んだ。
党の規約改正では、習近平総書記の指導思想を、「毛沢東思想」ばりに「習近平思想」と呼ぶことこそ盛り込まれなかったが、忠誠を誓わせるスローガン「2つの確立」(習近平総書記の指導的地位と思想の確立)を繰り返し強調した。
(2)4期目以降も視野に入れた習近平
習近平総書記を除く新たな最高指導部6人のうち4人が側近、もしくは極めて近い人間。中国の「戦狼外交」(攻撃的な外交)を担ってきた王毅外相も、69歳ながら政治局員に選出され、外交担当のトップに就任する見通しとなった。
中国語では、「多くの人が関わり何も前に進まなくなる状態」のことを”九龍治水”と表現するが、習近平総書記は、何でも前に進められるよう、最高指導部を側近とイエスマンで固め、4期目以降も視野に入れることに成功した。
その反面でワンマン経営の企業と同様、トップに対するチェック・アンド・バランスが効かなくなる危うさも残る。
(3)台湾統一を公約に掲げた習近平
党大会初日の10月16日、習近平総書記は、施政方針演説となる政治活動報告で、台湾統一への決意を高らかに宣言した。
「台湾問題を解決するのは中国人であり中国人が決める」、「台湾の平和的統一に努力を尽くすが、武力の使用を放棄する約束は絶対にしない」
また、党規約には、「台湾独立に断固として反対し、抑え込む」との文言も盛り込まれた。
これらの言葉は、台湾統一を国際公約にしたのと同じである。しかも、隣国に攻めんだロシアとは異なり、「台湾は中国の領土。だから他国は干渉するな」という気持ちも盛り込んでの発言である。
「台湾を取り戻す」
習近平総書記は大会初日の活動報告で、このように述べている。
「小康社会(ややゆとりのある社会)実現という100年目標は達成できたが、もう1つの目標、中華民族の偉大なる復興を全面的に推進する」
この言葉は、1840年のアヘン戦争以来、列強に領土を奪われ続けてきた「黒歴史」を3期目の5年間で清算する=台湾を取り戻す、という国内公約になる。それでも、8月10日、中国政府が発表した「台湾白書」(「台湾問題と新時代の中国統一事業」)では、平和統一を望んでいると強調していた。
「戦わずして勝つ」というのは「孫子の兵法」そのものだが、今回の党大会では、武力行使まで匂わせ、大きく踏み込んだ。
習近平総書記は、活動報告の中で、「安全保障(安全)」を89回、「強国」を15回も盛り込み、「早期に世界一流の軍隊に築き上げる」と宣言した。この点からも、どんな手段を講じてでも台湾を獲りにくるのは確実と言っていい。
なぜなら、3期目の5年間で、台湾統一に向けた成果を「見える化」してこそ、4期目、5期目へとつながるからである。
これにさっそく反応したのがアメリカだ。
10月17日、スタンフォード大学で開かれたイベントで、「中国は予想よりかなり早いタイムラインで統一を目指す決意を固めている」との認識を示している。中国が中国軍(人民解放軍)建軍100周年を迎え、しかも4期目がかかる党大会がある2027年は大きな節目だ。現在の中国の軍事設備を鑑みれば、この頃には、東シナ海や南シナ海における軍事力がアメリカを凌駕する可能性は十分にある。
しかしこの動きにアメリカ、日本、韓国の3ヵ国+台湾の連携は取れているとは到底言い難い。その理由は<【後編記事】暴走する「習近平」がほくそ笑む…「台湾侵略」でこれから5年間に起こる「ヤバすぎる事態」>にて明かす。
清水 克彦(政治・教育ジャーナリスト/大妻女子大学非常勤講師)
2018.09.04
# 中国経済
衝撃! 中国ではなぜ、「配達ドライバー」が続々と死んでいるのか
4億3000万人の巨大市場の「闇」
2018.09.04
「最近流行りのフードデリバリーをアプリで注文したんですが、3時間も待たされました」――。
筆者の通う東京都内の美容院の店長がこう嘆いた。注文したのは「うな丼」だが、店に到着したときにはすっかり冷めきっていた。
日本では「UberEATS」や「LINEデリマ」が登場し話題となっているが、ウェブやアプリを使って飲食店の料理を配達してもらうサービスはまだ緒に就いたばかりだ。市場調査会社のエヌピーディーグループ(アメリカ)によれば、日本の外食・中食を利用した食機会におけるデリバリーでのオーダー率は36%(2017年)と、主要13ヵ国の中でも低い。
ところが、中国ではこのデリバリーで日本の先を行っている。中国や韓国、オーストラリアやアメリカなど主要13カ国の中でも、中国のオーダー率は63%で断トツの1位となっており、13カ国平均の45%を大きく上回る(エヌピーディー)。中商産業研究院(中国・深圳市)によれば、中国でスマホユーザーは7億5300万人に拡大、フードデリバリーの利用者規模は3億4300万人にものぼると推計する。
上海ではたった半年で76人が死亡・負傷
注文の品を電動自転車に搭載し、街中を縦横無尽に飛来する配達員――こうした光景は今や中国全土でみられる。大都市上海では、全国の中でも突出してその利用が高い。そのためか、フードデリバリーの配達員がもたらす交通事故が近年、社会問題となっている。
街の交差点では信号待ちに舌打ちする配達員を見かける。信号待ちするのはまだマシで、中にはそのまま突っ走ってしまう配達員もいる。たまに路肩を正面から逆走してくる配達員に出くわすこともある。
環球時報は昨夏、2017年上半期だけで飲食デリバリー従事者76人が交通事故で死亡・負傷したと報じた。交通ルールを無視する配達員の自業自得といえばそれまでだが、逆にいえば、彼らにとっては「命がけの仕事」だともいえる。
「命がけ」になるのはこういう理由からだ。上海に居住する中国人主婦が語る。
「そもそも彼らは注文の数をこなしていくらの世界。配達した数に応じてコミッションが入るしくみなのです」
デリバリーごとに規定の賃金を受け取る日本の配達員とは事情が違う。そのため、すべては「時間との勝負」になる。少しでも多くのコミッションを得ようと一分一秒を争う。金のためなら多少のリスクも厭わない。
8円の歩合のために、肋骨9本を折る
「規定の時間内に届けよ」という指示があることも、彼らを「命がけ」にさせている。「時間内」を達成できなければ、逆に「失点」として賃金を引かれてしまうことになるからだ。
そのためだろう、上海ではマンションのエントランスで守衛と揉める風景をよく見かける。「第三者の侵入を防ぐ」という目的で立たされている守衛は、配達員に「待った」をかける。先を急ぐ配達員は守衛の尋問にいちいち答えていられないので、猛攻ダッシュでの“関所突破”を試みるが、結果、複数の守衛に抑え込まれ、配達は「タイムオーバー」になってしまう。
路上では交通整備係のおじさんと配達員、そして警官が三つ巴となった大乱闘すらある。上海に限らず中国の路上は、デリバリーの二輪車による違法駐車が問題になっており、これを苦々しく思っている交通整備係と、「そんなことは構っていられない」とする配達員が激しく衝突するのだ。最後は警察も巻き込んでの殴り合いとなる。
飲食デリバリーのみならず、ネット通販の普及でも「配達員」が重宝されているが、こちらも同じように「時間との闘い」だ。その厳しい労働環境は「死と背中合わせ」といっても過言ではない。
昨年、山東省でネット商品の宅配員が「肋骨9本」を折る大けがをしたというニュースが報じられた。原因は、宅配予定時間のたった「5分の遅れ」に怒った注文客による暴行だった。6分の遅れなら命を失ったかもしれない。凶暴な客もいるものだ。
ちなみに、肋骨9本を折られたこの商品宅配員は、この配達でもらえる歩合はいくらだったのか、という記者の質問に「100個の配達で50元程度(約850円)」だと答えている。つまり、1個の配達でもらえるのはたった5毛(約8.5円)だということだ。中国の都市部ならコミッションももう少しもらえるだろうが、たかだか8円のために肋骨をへし折られてはかなわない。
とにかく彼らは急いでいる。最近は「客の家の台所で調理を始める配達員」すら出現した。材料だけ鷲掴みにし客の家に向かった配達員は、台所で自ら調理を始めたという。
中国では「何が配達員をコックにしたのか」というタイトルでこの話題が報じられた。その背景にあるのも「一分一秒の戦い」。この配達員は、客先への瞬時の到着とアプリでの「評価」に頭がいっぱいで、「厨房での調理の時間がじれったくて、待っていられなかった」と語ったというから、まさに本末転倒だ。
もうひとつの「大量ゴミ問題」
スマホアプリのおかげで、中国人の生活は格段に便利になった。中でも“フードデリバリー”は2016年を前後して爆発的にユーザーを増やし、その結果、「配達員」という新たな雇用を創出した。しかしその一方で、多くのひずみを生んだのは前述したとおりだ。
もうひとつ注目したいのが、中国のフードデリバリーがもたらす環境問題だ。筆者の上海の友人・鵬さん(仮名)は、こんなことをつぶやいていた。
「2016年ぐらいからアプリを使って出前を取るようになった。あまりに便利なので、会社の昼食を含めて一日二食をデリバリーで済ませることも増えたけれど、届いたポリ袋の中から出てくるのは、使い捨てのプラスチック容器と割りばしとストロー。食後はゴミとなるその量に、最近は罪悪すら覚える……」
冒頭で、中国では3億4300万人がフードデリバリーを利用していると書いた。仮に彼らが1日1回デリバリーを注文すれば、3億4300万本の割り箸が、3億4300万個の容器が、3億4300万枚ものポリエチレン袋が消費される計算になる。
こうした環境負荷を問題視する声は、中国でもポツポツと出てくるようになった。ある中国のネットユーザーは「このポリ袋の平均使用時間はたった25分だが、地中に埋めても土に返るのに470年かかる」と訴えていた。
90年代、中国の都市部では発砲容器のポイ捨てが問題となり、中国は先進国から「白色汚染」というレッテルを貼られた苦い経験がある。上海ではゴミの分別や削減が呼びかけられ、2010年の万博開催を前に、食品スーパーを中心にレジ袋が有料化された。そして、「環境」をテーマにした上海万博で、地元居住者は「環境負荷」に対して高い意識を抱くようになった経緯がある。
上海に約20年在住する日本人女性はこう語る。
「昨今のデリバリーサービスの隆盛で、せっかくの環境に対する取り組みも後戻り。レジ袋有料に不便を感じながらも、“環境のために”と頑張ってきたあの努力は何だったのか」
トイレで調理…競争に勝つためなら何でもアリ
話を配達員に戻せば、「そこまでやるか」という泥沼の戦いに至った背景には、熾烈な企業間競争がある。競争といっても独特なのは、中国の場合、競争相手を徹底的に滅ぼし、最後は1強または2強が市場を独占してしまう結果にある。
振り返れば、タクシーの配車アプリもそうだった。最後は「滴滴」が「快的」を呑み込み、市場は「滴滴」の「1強」になってしまった。フードデリバリー業界も同じで、もともと多くの企業が参入していたが、いつの間にか、「餓了嗎」が「百度外売」を飲み込み、「美団」とともに市場を二分するようになった。
今年5月、タクシーアプリの「滴滴」がこのフードデリバリー業界に参入を始めたが、「滴滴」がこの業界を丸呑みしてしまうことだってあり得る。今なお「配達員」を筆頭に、日夜命がけの戦いが繰り広げられているのもそのためだ。
ここでは紙幅を割かなかったが、食品の衛生問題だってある。
中国のネットメディア『人民網』は、広東省の某デリバリー専用飲食店が「調理スペースが足りずトイレ内でも調理を行っていた」と暴いた。「競争に打ち勝つためなら何でもアリ」というわけだ。
これから本格化する日本のフードデリバリー産業には、ぜひとも健全な発展を期待したいものである。
習近平にプーチン…「独裁者」がのさばり「民主主義が衰退した」本当の原因
「歴史の終わり」の終わり
2022.10.24
民主主義国の人口は「減っている」
近代の「歴史」の勝者と謳われた民主主義。
この惑星の覇権をめぐって共産主義や社会主義との間で起こった争いに最終的に勝利した民主主義は、名実ともに「人類にとって普遍的な正義(グローバル・ジャスティス)」の座を獲得した――はずだった。
ところが現在、その民主主義国の人口が減少しているという。いったいなぜなのだろうか?
日経新聞によれば、先進国の人口が落ち込んでいる一方で、先進国に続いて民主主義国家の「仲間」に加わってくれることが期待されていた新興国が次々と民主主義から距離をとり、非民主的ないわゆる「強権国家」に惹かれつつあると伝えられている。
強権国家のほうが「速い」という現実
民主主義の欠点としてよくいわれるのは、「なにを決めるにしたって、民主主義の手続きを踏まなければならないせいで時間がかかること」である。対比的に強権的な独裁主義は「国民の自由や権利は著しく制限を受ける一方で、政治的にも社会的にも意思決定に時間を要さないから、時代やテクノロジーの流れが早い現代にはフィットしており優位性がある」とも指摘される。
これはたしかに一理ある。
たとえば日本では、たとえば新幹線やリニアモーターカーを開通させる計画が立ち上がっても、国・企業・地方自治体・地域住民・土地所有者の利害が激しく対立して「話し合い」が延々と行われ、計画が実際に着手するまでにきわめて長い年月がかかってしまうこともめずらしくない。先日開通した西九州新幹線も、長期間にわたって行われていた佐賀県との利害調整が不首尾に終わり、長崎と福岡を結ぶことはできず「日本一短い新幹線」となってしまった。
これがかりに中国なら、中国共産党政府が完全に独断で計画を取り決め、地方の自治体にも地域住民にもなんら「利害調整」などすることがないまま事業を断行することができてしまうだろう。国の事業計画に対して、国民が反対を申し立てるような「対話の窓口」など一切用意されていないからだ。
街の再開発でも、駅前の一等地の雑居ビルを取り壊して再開発しようとしたとき、かりにそのビルの所有権利者が細かく分かれていると、全員の合意を取り付けるまで取り壊しができないこともある。街全体の再開発よりも個人の権利がしばしば優越するのも民主主義社会ならではの光景で、これが共産主義や社会主義の社会であれば、そのような「個人の所有物だ!」という理屈はたやすく当局が粉砕する。権利を手放すことを拒否する住人を強制的に排除してビルを爆破してしまう。
強権国家では、よいかわるいかは別として、トップが「やる」と決めたことに市民社会は逆らうことができない。
新興国が抱く「民主主義への疑念」
自由や権利を擁護する民主主義社会が、全体主義や独裁主義に陥らないためにこそ尊重してきた「物事はみんなで話し合って決める」という大前提にどうしても付きまとう「遅さ」が(先進国に社会的にも経済的にも追いつきたいと考えている)新興国にとっては「やっかいな足かせ」のように見えてしまうのは無理もない。
先進各国がいくら「民主主義こそがすばらしいのだから、君たちもわれわれの後に続きなさい」と説いても、経済的発展を求める新興国からすれば「先進国は、わざと意思決定が遅くなるようなルールを採用させることで、私たちの社会や経済をゆっくりとしか進歩させず、いつまでも先進国に安く買いたたかれる立場でいさせるつもりなのではないか?」と邪推されてしまう(しかも、そのような邪推は100%思い違いというわけでもない)。
そんなふうに新興国が民主的な先進各国を訝しんでいるところに、非民主的な強権国家から巨額の経済・インフラ投資が舞い込めば「ほらみろ、やっぱり民主主義じゃなくても発展している国はあるんじゃないか。私たちはそちらを目指させてもらう」となることもめずらしくない。
これは喩えの話をしているのではなく、いま中国がアフリカを中心に現在進行形で行っていることだ。民主主義国の内部でも起こる「綻び」
欧米諸国や日本といった民主主義社会の内側においても、異変が起きつつある。民主主義にとって大切だったはずの「決定の遅さ」にしびれを切らしてしまう人が、じわじわと増加している。
民主主義社会の大原則である「自由」や「平等」が、自分の道徳観や倫理観に鑑みてとてもではないが受け入れられない相手にさえ付与されていることに、もはや耐えられなくなってきているのだ。
自分の政治的立場とは対立する人物が被選挙権を行使して議席を得たり、自分と価値観が異なる人が言論の機会を得て発言権を行使していたりする場面を目の当たりにすると、「こんな奴に私たちと同じ権利を等しく与えることは間違っている」という怒りを抑えられないだけでなく、誹謗中傷や嫌がらせに及ぶ人は珍しくなくなった。
「だれに対しても平等に権利や自由を与える」という融通の利かない自由と平等こそが民主主義の原理原則だったが、しかし現代社会では「誰がどう見ても『悪』とわかる者に対しては、民主主義的な手続きや権利をスキップして断罪できるような仕組みがあるべきだ!」――と、まるで全体主義や独裁主義国家さながらの声をあげる人びとが続出している。
かれらのような「自由を否定するリベラリスト」という形容矛盾を内包したムーブメントは今日において「キャンセル・カルチャー」と呼ばれる。かれらが民主主義の基本的な前提である「だれに対しても平等に権利や自由を与える」という枠組みを「ただしい者にだけ平等に権利や自由を与えるべきである」と、強権国家のそれに近似したありかたに再構築しようとしていることは、以前に現代ビジネスでも記事に書いた。
いずれにしても、民主主義を標榜する国でさえ「非民主的」な手続きへの誘惑に抗えなくなっている人びとが続出していることからも、「歴史」に終止符を打ったはずの民主主義の絶対的なヘゲモニーは内外で動揺を隠せなくなっている。
民主主義の隠れた「致命的欠陥」
ここまで民主主義が直面している内外の問題について述べたが、しかし思うに、民主主義がいま苦境に立たされている最大の理由は別にある。
すなわち、人間がこんなにも長生きするようになることを想定して民主主義は設計されていなかったことだ。
民主主義がこの世で発明されたころ、人間はもっと平均的に短命だった。「いまこの瞬間に生き、権利を持つ者」の平等を図る民主主義の性質は、社会が概して短命な人びとばかりで構成されている時代には、とくに問題なく機能していた。
だが、食糧供給や水質環境の改善によって飛躍的に人間の寿命は伸びた。昔よりずっと「死ななくなった」時代にいたり、民主主義には(おそらく設計者たちがまったく想定していなかったであろう)きわめて深刻な「バグ」が露見することになった。
その「バグ」とは「時間軸における不平等」である。
社会の構成員のほとんどが「現役世代」であった時代の人びとによって設計されたシステムである民主主義は、当時の人口動態が高齢者が少なく若者が多いはっきりとしたピラミッド型であったからこそ、民主主義的な手続きによって「未来志向」的な意思決定をすることが可能だった。
だが現代社会のように、現役世代が減少する一方で高齢者が長生きして増加するようになると「現時点では権利を持たない、あるいは生まれてすらいない子どもたち」よりも、「いま生きている高齢者たち」の厚生が優先される意思決定が下されるようになる。天文学的な予算規模にまで膨れ上がった社会保険料がその典型的な例である。
現時点ですでに政治的な権利を有する現役世代ならまだしも、選挙権をもたない未成年者、あるいはこの世にまだ生を受けてすらいない将来世代には、「いまこの瞬間に行われる」民主主義における政治的意思決定に参加する権利がない。そのため、かれらに負担を押し付けたり、あるいは問題解決を先送りするような不平等で不公正な政治的判断が選ばれることも増えていった。この構図を昨今では「シルバー・デモクラシー」と呼んだりもする。
民主主義は「機能不全」ではない
社会の成員が現役世代ばかりで、現役を引退したらほとんどがすぐに世を去っていたような時代には、「民主主義」はほぼ「現役世代の総意」の反映と言ってよかったかもしれない。民主主義というシステムの考案者たちもおおむねそのつもりで設計したはずだ。
だが、人がそう簡単には死ななくなり、人びとの「老後」が長くなれば事情は変わってくる。「まだ生まれてもいない、どうせ自分が死んだあとに生まれてくる未来の子どもたちのことなんかより、自分が生きている間の暮らしを守り、もっとよくしてほしい」と考えるのが人情というものだ。こうして民主主義は、文明の発展にともない「途方もなく長くなった老後」を過ごす人びとの意見を無視できなくなっていった。
断っておくが、高齢者を非難したいのではなくて、民主主義というシステムは、いまの人類の平均寿命や人口動態といった条件のもとでは必然的にそう機能すると述べているのだ。民主主義は「いまこの瞬間に権利を持っている者」同士の平等をきわめて高い水準で達成することには成功したが、しかし「いま生きている者とこれから生まれてくる者との平等」を達成することはできなかった。とくに高齢者と将来世代の利害が衝突する分野においてそれは顕著になった。
高齢世代が将来世代よりも多数派になった世の中では、民主主義社会は未来志向で発展的なビジョンを描けなくなり、現状維持が目的化して、衰退の一途を辿る。新興国は、高齢化・少子化が猛烈な勢いで進行する民主国家がいままさに直面している「シルバー・デモクラシー」のジレンマをよく観察しているので「私たちはああなるまい」と、いわば “逆張り” をはじめたということでもある。もちろん非民主主義的な強権国家が高齢化や少子化を避けられると決まったわけではないが、しかし民主主義を擁する先進各国の現状や行く末よりも「いくらかマシ」だと思っているのだろう。
民主主義のヘゲモニーが激しく動揺していることについて、人びとは「民主主義が機能不全を起こしているからだ」とか「民主主義の質が低下しているからだ」といった意見を持っているようだ。
だが私はそうは思わない。むしろその逆だ。
民主主義はこれまでと変わらず正常に稼働している。だからこそ必然的に、民主主義はいま危機的状況に直面しているのだ。
暴走する「習近平」がほくそ笑む…「台湾侵略」でこれから5年間に起こる「ヤバすぎる事態」
2022.10.25
今月16日〜22日まで行われた中国共産党大会は、ひと言で言えば、習近平の強引さが目立つ第20回大会だった。「68歳定年」の慣習が反古にされ、69歳の習近平総書記が3選した。
現在の李克強首相、さらに、次期首相候補の胡春華副首相を重要ポストから外し、自身の側近や近しい人間を指名。4期目以降の権力の座も盤石のものにした。その詳細は<【前編記事】権力に取りつかれた「習近平」が、また「暴走発言」…台湾に本気で戦争を仕掛け始めた…!>で明らかにしている。
さらに今大会では、台湾統一に向けた決意を高らかに宣言。党規約には「台湾独立に断固として反対し、抑え込む」という文言まで盛り込み、実質上の国際公約と実現している。この中国の動きに、アメリカ、韓国、日本の対抗策は用意されているのだろうか…。
分岐点は「2027年」と「2035年」
中国共産党大会(第20回大会)が終わり、中国は習近平総書記による独裁国家になってしまった。言うなれば「巨大な北朝鮮」が誕生したようなものだ。
中国共産党大会にさっそく反応したのがアメリカだ。
国務長官のアントニー・ブリンケンは、10月17日、スタンフォード大学で開かれたイベントで、「中国は予想よりかなり早いタイムラインで統一を目指す決意を固めている」との認識を示した。
アメリカと言えば、2021年3月、当時のインド太平洋軍司令官、フィリップ・デービッドソンが「6年以内の侵攻」を予測したことが知られている。筆者も、中国が中国軍(人民解放軍)建軍100周年を迎え、しかも4期目がかかる党大会がある2027年は大きな節目になると見ている。
その頃には、サイバー戦や宇宙戦など、台湾(それを支援するアメリカ)に対する全領域での戦いの準備が完了する。今年6月に進水した空母「福建」が就役し、強襲揚陸艦や無人機なども増産される。そうなれば、2027年頃には、東シナ海や南シナ海における軍事力がアメリカを凌駕するようになる。
その次の節目が2035年だ。習近平総書記はこの年を「『社会主義現代化』をほぼ実現できる年」と位置づけている。
しかも、現在、一部工事が始まっている北京と台北とを結ぶ高速道路や高速鉄道の竣工も2035年が目途で、中国国内では、「2035年に(高速鉄道で)台湾へ行こう」という、特に面白くも何ともない歌がいまだに流行しているくらいだ。
2035年には習近平総書記は82歳になる。現在、日本で言えば麻生太郎元首相、アメリカで言えば、8月に台湾を訪問した下院議長のナンシー・ペロシが82歳だが、十分元気だ。総書記として5期目が実現するようだと、この頃、台湾情勢が緊迫する可能性は極めて高い。
打つ手なしのアメリカ、韓国、台湾
これに対し、当事者の台湾、そして台湾を支援する日米韓3ヵ国は、いずれも政治のトップリーダーの足元が揺らいでいる。とても連携強化どころではない。それぞれの反応、まずは台湾からお伝えしたい。
■台湾:統一地方選挙で蔡英文総統の民進党が厳しい戦い
「台湾は蔡英文総統がいるから大丈夫なのでは?」という声もあるだろうが、2024年1月には総統選挙があり、2期8年までしかできない蔡英文総統の任期は同年5月で終わる。
台湾では、来月26日、総統選挙の前哨戦、統一地方選挙が実施される。
4年前の統一地方選挙では、野党で親中路線の国民党が大勝したが、今回も、蔡英文総統が率いる民進党が、台北、新北、高雄、台中の4大都市の市長選挙で、朱立倫主席(党首)率いる国民党に全敗するようだと、総統選挙ではかなりの苦戦を強いられることになる。
■アメリカ:中間選挙でバイデン大統領の民主党が苦戦
アメリカはもっと危ない。来月の中間選挙では、アメリカ議会下院の全議席、上院の3分の1の議席が改選となるが、バイデン大統領の民主党は、高いインフレ率が災いし、下院で共和党に過半数を奪われる可能性が高い。
また、筆者が得た最新情報では、改選前、民主党と共和党が50議席ずつ分け合っていた上院も、ペンシルベニアやウィスコンシンなど7~8州で民主・共和の候補者が拮抗し、全体としては共和党がやや優勢だ。
仮に共和党が上下両院を制する結果になれば、来月で80歳を迎えるバイデン大統領は思うような政策が打てなくなり再選の可能性が極めて低くなる。逆に、激戦区で共和党候補を応援してきたトランプ前大統領の再出馬と大統領返り咲きが現実味を帯びてくる。
■韓国:発足5ヵ月で尹錫悦大統領の支持率20%台
中国が台湾統一に動き出せば、それに呼応して動くと見られる北朝鮮。この抑えとして期待されるのが韓国である。しかし、韓国も、今年5月に発足したばかりの尹錫悦大統領の支持率が、自身と同じ検察出身者など身内を閣僚に起用した問題を契機に、20%台という危険水域に下落している。
対中国、対北朝鮮を思えば、日米韓の連携は不可欠だが、対日関係では元徴用工をめぐる問題で三菱重工業の資産売却問題の判断が迫る。
日本に譲歩すれば、韓国議会で過半数を占める野党「共に民主党」(代表は大統領選挙で争った李在明氏)が猛反発し、国内の批判に配慮すれば、日韓関係の改善は見込めず、3ヵ国の連携にひびが入る。
筆者は先頃、韓国で取材してきたが、
「尹大統領には今すぐ辞めてもらいたい」(梨花女子大学教授)
「そもそも資質に欠ける。エリザベス女王の葬儀に遅刻、ニューヨークで暴言を吐いた問題。一国の大統領として恥ずかしい」(SBSテレビの経済コメンテーター)
無党派の有識者からこのような声が聞かれるという点で、尹政権には早くも赤信号が灯っていると言っていい。
日本は内閣改造を余儀なくされる
日本の岸田政権もかなり危ない。旧統一教会問題で次々と教会側との接点が明らかになっている山際経済再生相が、10月24日夕刻、辞意を表明した。辞任という形でも事実上の更迭である。
国会は24日午後から、「山際経済再生相が更迭される」との憶測が流れていた。
その日の参議院予算委員会で、立憲民主党の田島麻衣子参議院議員が岸田首相に「交代させるつもりはないのか?」と迫ったのに対し、岸田首相は、「今、予算委員会の質疑中だ」と言葉を濁した。これで「更迭を否定しなかった」との声がさらに拡がった。
山際経済再生相は、今月28日にも閣議決定される物価高対策などを盛り込んだ「総合経済対策」の責任者だ。しかも、新型コロナウイルスワクチンを担当する大臣でもある。
特に、国費20兆円超を投入する「総合経済対策」担当の意味は大きく、その裏付けとなる今年度第2次補正予算案をめぐっては、国会で野党の質問に答える立場となる。
「山際さんは、外遊での会合は覚えているのに、直後に開かれた教会の会合に出たことは覚えていないと言う。教会の機関紙に名前が出ていた件でも、『もう接触しないので訂正も求めない』と不思議な言い訳をする。山際さんのせいで来春の統一地方選に負けるなんて許されない」(菅グループ自民党中堅議員)
山際経済再生相がそのまま居座れば選挙に悪影響が出る。それ以前に、補正予算案の審議がストップしてしまう恐れがあるため、臨時国会召集直後から、「予算委員会が一段落する24日が、辞任もしくは更迭のデッドライン」と言われてきた。
岸田首相も、閣僚1人を辞めさせれば「辞任ドミノ」につながるリスクを警戒しながらも、山際経済再生相の出身派閥である麻生派の麻生副総裁らと水面下で、更迭のタイミングを計ってきたのではないだろうか。
「山際経済再生相が辞任の意向」という憶測が駆け巡ったあと、岸田首相は、参議院予算委員会での質疑が終わったあと、皇居で予定していたオーストラリア訪問から帰国の記帳には行かず、首相官邸に戻った。
夕方、山際経済再生相の出席も予定されていた経済財政諮問会議も中止となった。このとき、山際経済再生相更迭の憶測は確信へと変わった。
ただ、これだけでは終わらない。岸田政権には、事務所賃料問題で批判を浴びる秋葉復興相や棒読み答弁が噴飯ものの永岡文部科学相といった危ない閣僚も残る。支持率回復の好材料は見当たらない。飛行機に例えれば、機首が下がったままの岸田政権。それを上昇させるには相当な推進力が必要になるが、その材料がなければ地面が見えてくる。
国民のコンセンサスは得られない
中国を取り巻く4ヵ国には、他にも共通項がある。それはいずれも「分断国家」であるという点だ。
これまでの取材経験から言えば、台湾、アメリカ、韓国は、2大政党で主義主張が180度異なり、お互いの支持者がいがみ合う構図となっている。アメリカや韓国では、「〇〇党支持者の家庭の子どもとは結婚させたくない」といった声まで上がる状況だ。
日本も、安倍元首相国葬問題では国論が2つに分断された。言葉は悪いが、国葬の決定プロセスや費用で2分されるのであれば、中国が台湾や尖閣諸島に攻め込んだ場合、国民のコンセンサスなど得られないのではないだろうか。
何かと不満はあっても「統制」の名の下に、強引にでも1つの方向にまとめることができる中国。「巨大な北朝鮮」とも言える国家のトップに君臨し続けることになった習近平総書記は、4ヵ国の現状に、あの独特の薄ら笑いを浮かべていることだろう。
大阪メガソーラーに上海電力が参入している謎 2022年
472回 大阪メガソーラーに上海電力が参入している謎
岩国市のソーラパネル設置のため、清流からヒ素や鉛が2年前から含まれ、わさびや農業ができなくなったそうです。
飲み水もきけんです。
あの頃、私もソーラー事業会社の社員でした。当時、栃木県の那須烏山だったと思いますが元Y組の元893が社長のソーラー発電所販売会社がバブル時代に地上げの為に買って塩漬けになっていた土地に作ったメガソーラーをまさに上海電力に高値で売却できた!ってその元893社長が喜んで開いたパーティーに関連会社の社員として参加してました😓
その元893の会社の赤坂の事務所にも行った事あります。😓
当時は、メガソーラーで再生可能エネルギーによる発電をする事業が「善」と皆考えていた時代でした。
今はもうIT系の会社に転職していますが、今、考えると会社を辞めて良かったと思ってます。当時は民主党政権下で国民全体が「騙されて」ソーラー発電に沸いてましたね〜
先生のおっしゃるとおり、とりあえず議会の追及や住民監査請求で
入札や事業譲渡に関する客観的な資料が開示されて欲しいですね。
ソーラー設置したと土地が中国企業名義になったり、ソーラー設置会社に中国人の役員がおったり、中国との関りが密すぎてて・・・・。
言い出したらきりないくらいに・・・。
てかそもそも論、インフラは国内企業、国内産業、国内で諸々完結させて
上海電力が林外務大臣の選挙区岩国市、しかも自衛隊基地、海兵隊基地にもソーラーパネル事業で手を拡げてきている侵略体質が問題。メガソーラーの施工業社の社長をやってましたが、外国企業が国内に簡単に作れる合同会社を使ってソーラー売電事業のオーナーになることは普通に行われています。さらに親切な事に新生銀行などがその融資もしていました。こんな美味しい事業になぜ日本企業は進出をしないのか不満に思っていました。リスクを負えないサラリーマン経営者が日本を衰退させている。外国企業は売電事業で儲け国民が賦課金を払う仕組みを考え私腹を肥やす売国奴役人が多すぎる。
上海電力が、山口県で起こしている深刻な環境汚染と農業被害について教えていただきたい。日本のインフラ事業に外国資本を絶対入れない法律を岸田政権は、直ちに作るべき最重要課題です。橋下市長も維新(だった)。今の大阪市議会、府議会も維新が支配している中、実態解明には時間がかかる気がします。
先生も維新政治塾で講師された時は、このような外資導入に関する注意点のご指導はなかったのでしょうか?割引率と憲法の時代錯誤は完全に同根!政治家と役人が現実に対応できず、慣例踏襲しかしていないということ。高橋洋一氏の言う通り、法的にも、その他でも問題がないと橋下氏が思うなら、当時の入札状況や自分が知っている事を説明すればいいだけだと思います。自分が知らないなら、どの部署に誰に任せたとか知っている事を言ってそれを吉村市長が、情報公開すればいいだけです。
知らないうちに咲洲メガソーラーの発電業者が上海電力になっている事実だけで怖いです。咲洲メガソーラーに行ってみたら草ぼうぼうで管理もできていないでは火事の危険性もあるし、火災上も問題と思います。
高橋洋一氏は住民監査請求、大阪市議会での質問などをすればいいと言っていますが、それには時間がかかるので、橋下・元市長にご協力いただいて、知っている事を話していただいた方が、上海電力がダミー会社で参入した経緯が早く分かり、国会で安全保障的に検討して、法改正する為にも橋下氏は知っている事を話して頂いた方がいいと思います。
橋下氏は法的には問題ないと言っているのですし、自分が知っている事を話して大阪市役所に情報開示をしてもらった方が、早く自分の疑惑が晴れて、コメンテーター業に万進できると思います。
【低品質の上海電力のメガソーラーで山口県岩国市ではヒ素による土壌汚染で深刻な問題になっています。しかも上海電力は国土強靭化推進本部長の二階俊博が一帯一路で招致に助力したと言うこともわかっています。岩国の土壌汚染は国の責任です。
橋下氏が大阪市役職員が悪いーと現役時代、大阪市役所を敵に回して人気を博していたように、今回も大阪市役所が悪いのかもしれません。経緯が分かればダミー会社は設立後、実績もないのに入札に参加できるのなら、これはこれで問題なので法改正が必要ですし、入札後、すぐに売却するとなると責任の所在が不明になるので、10年間は売却不許可、10年後売却するなら大阪市の許可が必要とか、今回の経緯を明らかにする事で入札制度の改善にもつながると思います。
昔も今も、中国企業が狙う“お買い得”な日本人労働力――「歯ブラシ」「マスク」を日本の工場で 魅力は「日本製」と人件費
歯ブラシやマスクなどを日本で生産し、中国で販売する中国企業があります。日本製は中国でも人気ですが、検品などの丁寧な仕事ぶりに加えて注目されているのは、人件費です。日本人労働力の「お買い得感」が広がっています。大阪の生産現場を取材しました。
「習近平は裸の皇帝」元部下の女性学者が日本メディアに初めて答えた
2022年12/8(木)
今年10月、アメリカの権威ある国際政治経済ジャーナル「フォーリン・アフェアーズ」に、「習近平の弱点 狂妄とパラノイアはいかに中国の未来を脅かすか」と題する論文が掲載された。
外交関係者の度肝を抜いたのは、その激烈な表現である。
「習近平は裸の皇帝である」
「この指導者は虚栄心に満ち、頑固で独裁的だ」
「中国共産党はマフィア組織」……
しかもこの論文の著者は、習近平の元部下にあたる女性政治学者・蔡霞氏(70)だったのだ。
 |
| 亡命先のアメリカで暮らす蔡霞氏 |
中国の迫害を逃れて亡命先のアメリカで暮らす蔡霞氏は今回、「文藝春秋」でインタビューに応じた。彼女が日本メディアに登場するのは今回が初めてである。
剥奪された党籍と年金
蔡霞氏は習近平が校長を務めていた党の高級幹部養成機関「中共中央党校」の教授として、長年教鞭を執ってきた(2012年に定年退職)。彼女は党内の改革派として知られ、中央党校の講義でも中国の政治改革について教えてきた。
だが、そんな姿勢が習近平政権を刺激したのか、やがて彼女の言説は封殺されて行く。
〈習近平政権の成立前夜の2012年ごろから、私は政治的立場を警戒されて監視下にありました。2016年5月以降はあらゆる文章の発表を禁止され、中国国内のネット上からも名前を消し去られました。
私に対して「党を除名されたから文句を言っている」などと批判する人がいますが、曲解もいいところです。中国国内にいたころ、私は言説を発表する場を完全に奪われ、ガラス瓶に封じ込められたかのような状態に置かれていたのですから。〉
そして一時訪問先だったアメリカに滞在中の2020年8月、「深刻な政治的問題と国家の名誉を汚す言説」を理由に、中国共産党の党籍を解除された。
〈私と友人との会話の音声がネットに流出しました。相手は気のおけない友人たちで、しかも中国国外の通信アプリを使った、完全にクローズドな会話でした。
ところが、私の「習近平は罪がある」「マフィアのボスと変わらない」「中国共産党は政治的な殭屍(きょんしー)(=ゾンビ)だ」といった発言の音声データが、なぜか24時間以内に外部に流出したのです。その後、香港の国家安全法について批判的な見解を記した、友人向けに送った文章も流出しました。
中央党校からは、帰国を要求する電話がひっきりなしに掛かるようになりました。
党校の担当者はやがて「どうしても戻らないのか。あなたは自分の(中国国内にいる)子どもや家族が心配ではないのか?」と言いはじめました。それでも応じずにいると、彼らは一方的に、私の党籍の解除と年金の打ち切りを通告してきました。〉
習近平3期目は世界に大きな災厄をもたらす
それにしても、なぜ彼女はここまで激しく習近平を批判しようと覚悟を決めたのか?
〈習近平政権の第3期目を阻止するべきだと考えたからです。2022年10月の第20回党大会を控えたタイミングで、あの文書を世界に向けて示すことで、楔を打ち込めないかと思ったのです。〉
「フォーリン・アフェアーズ」の論文のなかでは、習近平が会議で異常に長時間の演説を好むことや、あらゆることに干渉する偏執的なこだわり、さらには文化大革命で充分な学問を修められなかったコンプレックスなどを指摘し、キャリアの初期に親の口利きでポストを得ようとして失敗したことも伝えている。これについても蔡霞氏はこう語る。
〈根拠なき誹謗中傷を書いたわけではないですし、「攻撃」したつもりもありません。私は学者ですので、自分が知り得た確かな事実を記したに過ぎないのです。
仮に習近平が一般人であれば、私が指摘した問題は、いずれも個人的な欠点でしかないでしょう。しかし、彼は巨大な国家権力の掌握者です。彼の欠点は、そのまま全中国国民の、さらには全世界の人々の未来に負の影響を与えます。新型コロナのパンデミックの初期に世界が手をこまねいたような事態を、再び繰り返してはなりません。〉
「勉強不足でIQが低い」
蔡霞氏が中央党校のなかで見聞した、習近平にまつわるエピソードも興味深い。
〈体制内の学者や紅二代(高級幹部の子弟)の一部には、もともと習近平への強い懐疑が存在していました。例えば2012年秋、習近平が党総書記に選出される第18回党大会を控えた1ヶ月前に、ある雑誌記者が、中央党校の著名な教授へのインタビューに来たことがあります。 私も取材に同席しました。
この教授は管理職なので、上司である習近平とは直接面識があり、また昔から習を知っていました。そこで、インタビュー後に記者が何気なく「習近平氏が次の総書記になりますねえ」と水を向けたんです。すると教授は、
「他(ター)呀(ヤ)? 知識(ヂーシ)不夠(ブゴウ)、智商(ヂーシャン)不夠(ブゴウ)(ヤツか? 勉強不足でIQが低い)」
と、敬意を一切感じさせないぞんざいな口調で言い放ったのです。
当時はまだ、私自身を含めて習近平に対する期待が強い時代でした。彼の父親の習仲勲は非常に人望のある改革派幹部でしたから、習も改革派の気質はあるだろうと思われていたのです。
しかし、やがてこの教授の指摘が、完全に事実であったことを、痛感することになりました。習近平の人格を説明するうえでは、「勉強不足でIQが低い」という言葉こそ、最も的確な表現だったのです。〉
中国は台湾を模範とすべき
習近平政権は台湾に強い圧力をかけ、武力併合も辞さない姿勢を見せているが、蔡霞氏は「台湾こそ、中国人が模範とすべき政治体制」と指摘する。
〈天下を統一した現代中国の帝王として、歴史に名を残したいという思いは、習近平もあるでしょう。中国共産党にとって台湾統一は、朝鮮戦争という外部的な要因により果たせなかった問題です。台湾問題の解決は、党にとっての一貫した悲願です。
加えて指摘したいのは、台湾が民主主義体制の地域であることです。仮に台湾がいまなお蒋介石以来の独裁体制下にあるなら、同じ独裁政権同士で水面下の対話が可能になります。しかし、現在の台湾はむしろ、中国人が模範とするべき地域です。党にとって、そうした台湾の姿こそ最も大きな脅威です。〉
では、日本はどのように習近平政権に向き合うべきなのか?――中国共産党の内幕を知りつくす蔡霞氏のインタビュー「 私が習近平から逃げ出した理由 」は、12月9日発売の「文藝春秋」2023年1月特別号で全10ページにわたって掲載されている。
ドイツ「半導体生産ライン」、中国企業の買収却下
独政府が「技術と経済の主導権確保」を理由に
2022/11/21
ドイツの車載用半導体の生産ラインを買収しようとしていた中国企業が、ドイツ政府から「技術と経済の主導権を守る」との理由で認可申請を却下されたことがわかった。
この中国企業は、深圳証券取引所に上場する半導体メーカーの賽微電子(SMEI)だ。同社は11月10日、ドイツ経済・気候保護省から11月9日付の決定通知書を受け取ったと発表した。
賽微電子(SMEI)は、100%子会社のスウェーデン企業サイレックス・マイクロシステムズを通じて、ドイツの車載用半導体メーカーのエルモス・セミコンダクターからドイツ国内の半導体生産ラインを8450万ユーロ(約124億円)で買い取る計画だった。
サイレックス・マイクロシステムズは2021年12月にエルモスとの契約に署名し、2022年1月に外国企業の直接投資に関わる許可申請をドイツ政府に提出。2022年後半の取引完了を目指していた。
しかし今回の決定により、賽微電子(SMEI)はエルモスの買収手続きをこれ以上進められなくなった。今後の対応について同社は、「関係先とともにドイツ政府の決定通知書を詳細に検討し、そのうえで判断する」としている。
中国の産業界に意外感
この事件は、ヨーロッパとのビジネスに携わる中国の関係者の間で意外感をもって受け止められた。というのも、今回の決定はドイツのオラフ・ショルツ首相の中国訪問の直後というタイミングだったからだ。
2022年11月4日、ショルツ氏は(2021年12月に)ドイツ首相に就任後初めて訪中し、習近平国家主席と会談。10月に開催された中国共産党の第20回全国代表大会の閉幕後、中国を訪れた最初のヨーロッパ首脳となった。
本記事は「財新」の提供記事です
ショルツ氏の訪中をめぐっては、ドイツ国内に反対意見もあった。だが同氏は、ドイツの大企業十数社の経営者を伴って中国詣でを敢行。このことは、両国の経済関係強化に前向きな動きだと(中国の産業界で)解釈されていた。
訪中直前の2022年10月26日にも、中国の国有海運大手の中国遠洋海運集団(コスコ・グループ)がドイツのハンブルク港のコンテナターミナル運営会社に出資する計画(一帯一路)が、ショルツ首相の後押しにより条件付きで認可されたばかりだった。
(財新記者:張而弛)
中国政府機関、カナダによる中国企業への投資引き上げ命令に反発
2022年11月11日
カナダ政府は2022年11月2日、中国企業3社(注)に対して、カナダの重要鉱物企業からの投資引き上げを命じた。これに対して、中国政府機関が相次いで反発した。
カナダでは2022年10月28日に、中国への警戒の高まりを背景に、カナダの重要鉱物企業セクターを保護するための規定を強化したガイドラインを発表していた(2022年11月1日記事参照)。
中国外交部は2022年11月3日の記者会見で「鉱物資源のグローバル産業チェーン・サプライチェーンの形成と発展は、市場ルールと企業の選択がともに作用したものだ。カナダが国家の安全という概念を拡大し、人為的に中国とカナダの企業間の正常な経済・貿易・投資の協力に障害を設置することは、カナダ政府自身が掲げる市場経済の原則と国際経済・貿易のルールに背くものだ」と批判した。その上で「中国企業への不当な抑圧をやめ、カナダでの正常な経営活動に公平、公正、無差別のビジネス環境を提供するよう求める。中国政府は引き続き自国企業の正当な合法的権益を断固として守る」とした。
中国商務部は2022年11月6日、外交部同様に、中国企業の活動は市場経済の原則に基づいたものであり、カナダが国家の安全という概念を拡大して障害を設置することに反対した上で「経済・貿易の政治問題化をやめ、中国を含む各国の投資者のために、公平、公正、透明、無差別なビジネス環境を構築すべきだ。中国は必要な措置を取り、中国企業の合法的権益を断固として守る」とした。
新エネルギー車の市場拡大などを受け、中国ではリチウムをはじめ鉱物資源の安定調達の需要が高まっている(2022年5月30日付地域・分析レポート参照)。カナダでは今回の3社のほか、紫金鉱業集団によるネオ・リチウム(Neo Lithium)の買収(2021年10月19日記事参照)など、中国企業による関連企業の買収が行われている。
商務部直属の研究機関の中国WTO研究会の霍建国副会長は「これまで外国政府が中国の投資者に対して審査を行ったり罰則を科したりしたことはあるが、投資引き上げを求めたことはない」(「第一財経」11月3日)と、今回の事態の特殊性を強調した。
商務部研究院国際市場研究所の白明副所長は、今回の措置は国際貿易のルールに背き、米国の対中抑止に同調したものと批判し、中国企業の業績への影響は限定的な一方で、カナダにとっては長期的な影響が大きいとした(「環球時報」11月4日)。
(注)中鉱資源集団の子会社の中鉱(香港)稀有金属資源、盛新鋰能集団の孫会社の盛澤鋰業国際、蔵格鉱業の子会社の蔵格鉱業投資(成都)の3社。
中国企業側の公告によると、中鉱(香港)稀有金属資源はパワーメタルズ(Power Metals)について90日以内に、(1)全ての株式の売却、(2)独占販売協議の終了、(3)中国側が任命した役員の退職を求められている。また、盛澤鋰業国際はリチウムチリ(Lithium Chile)、蔵格鉱業投資(成都)はウルトラリチウム(Ultra Lithium)について90日以内に投資(投資プロジェクト内の権利を含む)を放棄し、投資促進のために行っている全ての商業活動を停止するように求められている。公告では、3社いずれも、今回の措置により業績に大きな影響はないとしている。
カナダと中国の2国間関係については、中国の通信大手華為技術(ファーウェイ)の孟晩舟・最高財務責任者(CFO)のカナダ国内での拘束、その報復行為とみられる中国でのカナダ人の拘束などを巡り、近年、関係が悪化している(2021年9月28日記事参照)。そうした中、中国がカナダに対して輸入規制の緩和に踏み切ったのは、ロシアのウクライナ侵攻により、菜種をはじめとする原材料および食料価格の高騰から、中国が自国の食料安全保障の立場を再考しての動きとの見方がある(「フィナンシャル・ポスト」紙5月19日)。
なお、カナダ政府は、菜種に関する中国の市場開放を歓迎する一方で、2022年5月19日、中国の通信機器メーカーである華為技術(ファーウェイ)および中興通訊(ZTE)を、国内の高速通信規格「5G」から排除することを発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますしている。
(河野円洋)
カナダ政府、外国国有企業から重要鉱物セクターを保護するガイドライン強化を発表
2022年11月01日
カナダのフランソワフィリップ・シャンパーニュ・イノベーション・科学・産業相とジョナサン・ウィルキンソン天然資源相は10月28日、カナダ国内の重要鉱物セクターに投資しようとする外国の国有企業から同セクターを保護するために規定を強化した最新のガイドライン外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに関して声明を発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。カナダ政府が今回の規制強化を定めたのには、中国への強い警戒の高まりがあるとみられる。
声明で両閣僚は、重要鉱物はグリーンなデジタル経済を推進するために不可欠なものであり、その需要の増加と供給の制約がカナダに数世代にもわたって経済的機会をもたらしているとして、「カナダ政府は、気候・環境問題の目標を達成しつつ、機会を捉えるべく取り組んでいる」「だからこそ、カナダは、国内、北米圏、および世界中の志を同じくするパートナーとともに、北米の重要な鉱物サプライチェーンで戦略的な回復力を構築する必要がある」と述べている。
その上で、「その目標を支える外国からの直接投資は引き続き歓迎するが、そうした投資がわが国の安全保障と重要鉱物のサプライチェーンを脅かす場合、カナダは断固として行動する」としている。具体的には、重要鉱物のサプライチェーンが関係するケースでのカナダ投資法適用に関する追加の方針として、10月28日以降、カナダの重要鉱物セクターにおける外国の国有企業による重要な取引は、カナダにとって純利益が見込まれる場合にのみ例外的に承認するとしている。また、外国の国有企業がこうした取引に参加する場合、「取引価格には関係なく、その投資がカナダの国家安全保障に害を及ぼす可能性があるとみるに足る合理的な根拠を成し得る」として、外国国有企業による投資を明確に牽制している。
声明は「本日の指針は、カナダ政府が『重要鉱物戦略』を最終決定していく過程で生まれたもので、同戦略によりカナダは重要鉱物の世界的な供給国として位置づけられる」と締めくくっている。現地報道によると、政府は重要鉱物戦略を2022年内に発表する予定だ(CBCニュース10月28日)。
シャンパーニュ大臣は10月下旬のワシントン訪問中にレモンド米国務長官と会談し、重要鉱物のサプライチェーンに依存する戦略的な産業部門の強化のため、カナダと米国の重要鉱物行動計画の下で協力を強化することで合意したほか、滞在中にカナダのプロジェクトの売り込みを行ったもようだ。同会談の声明で、電気通信ネットワーク分野のサプライチェーン保護における中国排除の動きに関して、カナダが米国などに追随する意向を明確に表明したほか、「カナダが望んでいるのは中国からのデカップリングだ」「人は真に同じ価値観を共有できる者と取引をしたがるものだ」と述べたとされる。
10月11日には、クリスティア・フリーランド副首相兼財務相がワシントンでのイベントで、同盟国や友好国に限定した限定的なサプライチェーンを構築する、いわゆる「フレンドショアリング」(注)の重要性に言及したほか(2022年10月28日記事参照)、メラニー・ジョリー外相が27日に、米国が主導するインド太平洋経済枠組み(IPEF)へのカナダの参加を模索することを表明しており(2022年10月31日記事参照)、カナダ政府の今後の脱中国や友好国との連携の動きが注目される。
(注)同盟国や地域に限定してサプライチェーンを構築すること。米国が対中摩擦の中、敵対国から同盟国へと物資の供給元を切り替えることにより、サプライチェーンの安定化・強化を図ろうとする中で現れた概念。
(高山さわ)
カナダ政府、国連の新疆ウイグル自治区人権レポートを支持する声明を発表
2022年09月05日
カナダ政府のメラニー・ジョリー外相は9月1日、国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)が8月31日に公表した中国の新疆ウイグル自治区における人権をめぐる状況に関する報告書を支持する声明外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを発表した。
ジョリー外相は、強く待望されていた同報告書が公開されたことは非常に重要なことで、「新疆で発生している深刻で組織的な人権侵害と違反についての証拠を集積する上で重要な貢献をしている」と評した。ジョリー外相は、報告書は、ウイグル族やその他のイスラム教少数民族の恣意(しい)的かつ差別的な拘留は、国際犯罪、特に人道に対する罪となる可能性があると判断したものとしている。
また、カナダは、現在進行中の重大かつ組織的な人権侵害について、重大な懸念を繰り返し表明してきたとして、「続々と現れる証拠は、中国政府当局の主導による組織的な人権侵害を裏付けている。これらの証拠には、100万人を超えるウイグル族やその他のイスラム教少数民族の宗教や民族性に基づく大規模かつ恣意的な拘留や、広範な大規模監視、政治的再教育、性的暴力、強制労働、拷問、強制不妊手術などが含まれている」と述べた。
ジョリー外相は、中国政府とは2022年初めの会談を含め、政府間のトップレベルで直接対話をしてきたことについて触れたほか、諸外国との協力に関して、ファイブ・アイズの同盟国、G7、国連人権理事会といった国際的なパートナーと協力して、強制労働により生産された商品がカナダおよび世界のサプライチェーンに入り込むリスクに対処するために取り組んでいる点について触れた。
声明では、「カナダは中国政府に対し、国際的な人権上の義務を守り、OHCHR報告書で提起された懸念と勧告に対応するよう要請する。新疆ウイグル自治区の状況に対処し、中国政府がその行動の責任を問われることを確実にするために、国際的なパートナーと協力して協調行動を取り続ける」と締めくくられている。
カナダでは、関税定率法136条で強制労働により製造等された品目の輸入を禁止しているが、2020年7月には対象品目に「全体または一部が強制労働によって採掘、製造または生産された物品」が追加された。また、2021年11月には「サプライチェーンにおける強制労働および児童労働との闘いに関する法律を制定し、関税率を改正する法案(S-211)」および、中国の新疆ウイグル自治区で生産された物品の輸入を禁止する「新疆からの物品に対する関税率を改正する法案(S-204)」が上院に提出され(2021年11月26日記事参照)、それぞれ上下院での審議が続いている。
なお、OHCHR報告書に対しては、米国政府も9月1日に歓迎・支持する声明を発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますしている(2022年9月5日記事参照)。
(高山さわ)
越中(ベトナム・中国)で共同声明発表、中国のCPTPP加盟や「一つの中国」を支持
2022年11月08日
ベトナム共産党のグエン・フー・チョン書記長は、中国共産党の習近平総書記(国家主席)の招待を受け、10月30日~11月1日に中国の北京を公式訪問した(2022年11月4日記事参照)。78歳のチョン氏の外遊は2019年に体調を崩して以来初めてで、習氏との会談は2017年以来となった。習氏にとっては、共産党大会で3期目に入って以降、初めて会う外国要人となった。
10月31日に、チョン氏と習氏の会談後、両氏立ち会いの下で両国間の貿易、農業、観光、環境などの分野に関する13の覚書に署名をした。11月1日には一連の成果として、包括的戦略的パートナーシップの継続的な促進と深化に関する越中共同声明外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを発表した。
経済、貿易面においては、両廊一圏の枠組み(注)と一帯一路構想の開発戦略のコネクティビティー強化、中国企業のベトナムへの投資奨励、電子商取引(EC)分野の物流協力や製品拡大促進の方向性などを確認した。ベトナム商工省は、中国商務部とサプライチェーン確保のための協力強化に関する覚書、中国税関総局と2国間貿易での食品安全に関する覚書をそれぞれ締結した。
インフラ面では、ベトナムのラオカイ、ハノイ、ハイフォン間の鉄道の標準軌化に向けた調査や、防災能力向上のための国際河川のデータ共有などを促進する。グリーン分野、気候変動対策では、積極的な協業を模索することが記載された。
また、ベトナムは中国が2021年9月に申請していた、環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定(CPTPP、いわゆるTPP11)加入要請も支持した。
「一つの中国」政策の支持を表明
今回の共同声明では、ベトナムは「一つの中国政策」を支持し、台湾の独立に向けた動きへの反対や、各国の内政不干渉を堅持する立場が明記された。
ベトナムは貿易額で中国と米国が占める割合が高く、対立を深める両国と切り離せない経済関係を持つ。米国との関係では、インド太平洋経済枠組み(IPEF)交渉参加を進めているが、中国との関係も維持しつつ、地政学的に難しいかじ取りが続いている。なお、今回の訪中代表団メンバーは、共産党の要職である政治局員、書記局員を中心に構成。国会会期中ということもあってか、国家主席、首相、国会議長をはじめ、商工相などの同行はなかった。
(注)2つの回廊と一帯の経済圏での2国間の経済協力枠組み。2つの回廊は、中国の昆明からベトナムのラオカイを通り、ハノイとハイフォンを経てクアンニンに至るルートと、南寧からランソン、ハノイ経由でクアンニンをたどるルートを指す。一帯の経済圏は、中国南部からハイフォンまでトンキン湾(北部湾)海域にまたがる地域を指す。
(萩原遼太朗)
習国家主席がベトナム書記長と会談、サプライチェーン構築などで協力
2022年11月04日
中国の習近平国家主席は2022年10月31日、北京市でベトナム共産党のグエン・フー・チョン書記長と会談した。中国外交部の発表によると、双方は「四好精神」(注1)と「16字の方針」(注2)を堅持し、伝統的な友好関係を固め、戦略的コミュニケーションを強化するとした。また、政治的な相互信頼を深め、意見の不一致の適切な管理を進め、新時代の両国間の全面的な戦略的協力パートナーシップを新たな段階に引き上げることで一致したとしている。
習国家主席は、経済面では両国間で安定した産業チェーン・サプライチェーンシステムを構築し、中国の技術集約的企業がベトナムへ投資することを奨励するとした。また、医療・衛生、グリーン発展、デジタル経済、気候変動対応分野での協力を深めるとした。
会談を受けて、2022年11月1日付で「中越の全面的な戦略的協力パートナーシップのさらなる強化と深化に関する共同声明」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますが発表された。上記の協力のほか、ベトナムとの貿易不均衡緩和のために、ベトナムから中国側へのサツマイモ、かんきつ類、ツバメの巣などの輸入、中国からベトナム側への乳製品の輸入について市場アクセスを進めるとした。
また、南シナ海の状況について、2011年の「中国・ベトナムの海上問題解決指導の基本原則に関する合意」を引き続き順守するとともに、各自の主張・立場に影響しない過渡的、臨時的な解決方法を協議するとした。その上で、双方が受け入れることができる基本的かつ長期的な解決方法を探り、国際法に適合する「南シナ海行動基準」の合意を目指すとした。ベトナム側が「一つの中国」原則を支持することも盛り込まれた。
チョン書記長の訪中に先立ち、2022年10月29日付の「環球時報」は、ベトナムの「軍事同盟に加入しない、同盟を組んで他国に対抗しない、国内に外国の軍事基地を置かず他国との戦争に領土を利用させない、国際関係の中で武力の使用もしくは武力による威嚇は行わない」という方針を評価するとした。その上で、2022年10月の米国のダニエル・クリテンブリンク国務次官補によるベトナム訪問は、中国の外交上の孤立を狙ったものとして「中越関係は特殊な意味を持つことを、大国は理解できない」と評した。
(注1)「良い隣人、良い友人、良い同志、良いパートナー」の関係。中国語では全て「良い」という意味の「好」という文字がつく。
(注2)「長期安定、未来志向、善隣友好、全面協力」という方針。中国語で16文字で表現されている。
(河野円洋)
習国家主席が岸田首相と会談、ハイレベルの対話強化などで共通認識
2022年11月21日
中国の習近平国家主席は2022年11月17日、タイ・バンコクで岸田文雄首相と会談を行った。
習国家主席は中日国交正常化後の50年について、各分野での交流と協力により、両国の人々に幸福をもたらし、地域の平和、発展、繁栄を促進してきたと評価した。
その上で、歴史問題、台湾問題は両国関係の政治的基礎と基本的信義に関わり、約束を守り適切に対処すべきとした。
また、海洋問題や領土問題について、原則的合意を厳守し、政治的な知恵と責任感で対立を適切に管理すべきとした。政府、政党、議会、地方の往来・交流を行い、積極的な青少年交流を通じて相互に客観的で前向きな認知を形成すべきと強調した。
経済については、両国経済は相互に依存しており、デジタル経済、グリーン発展、財政・金融、医療・高齢者ケア、産業チェーン・サプライチェーンの安定性や円滑性の維持などで対話・協力を強化すべきとした。
中国外交部は、双方は以下5点の共通認識に達したと発表した。
中日関係の重要性に変わりはなく、今後も変わることはない。ともに中日の4つの政治文書(注1)の原則を順守し、「互いに協力のパートナーであり、脅威とならない」という政治的共通認識を実践する。ハイレベルの往来と対話を強化し、政治的信頼を強め、ともに新時代の要求に一致する建設的で安定した中日関係の構築に取り組む。
早期に新たな中日ハイレベル経済対話を実施し、省エネ・環境保護、グリーン発展、医療・介護、高齢者ケアなどの分野での協力を強化し、ともに企業に対し公平で、無差別の、予見性のあるビジネス環境を提供する。
中日国交正常化50周年に関する一連の活動を評価する。早期に新たな中日ハイレベル人文交流協議メカニズム会議を実施する。政府、政党、議会、地方および青少年などの往来・交流を積極的に行う。
早期に国防部門の海・空連絡メカニズムホットラインを開通し、防衛、海上部門の対話を強化し、2014年の4つの原則的共通認識(注2)をともに順守する。
国際地域の平和と繁栄を守る責任をともに背負い、国際地域の問題について協調・協力を強化し、グローバルな課題対応に努力する。
2022年11月15日付の環球時報は、「日本が会談を求めてきた」のは中米関係の積極的な動き(注3)の影響であり、「中国が原則を堅持し、自律を保てば、中国外交には広々とした空間が開けている」と評した。
(注1)1972年の日中共同声明、1978年の日中平和友好条約、1998年の日中共同宣言、2008年の日中共同声明を指すとされる。
(注2)2014年に示された、東シナ海などをめぐる状況悪化回避などを含む4つの共通認識。
(注3)米国のジョー・バイデン大統領との会談については2022年11月15日記事、2022年11月16日記事参照)。
(河野円洋)
日中国交正常化50周年、習国家主席と岸田首相が祝電交換
2022年10月03日
中国外交部は9月29日、日中国交正常化50周年に当たり、習近平国家主席が岸田文雄首相と祝電を交換したと発表した。
習国家主席は祝電で「50年前の今日、中日のかつての指導者たちが時局を見極めた長期的な視点から、中日国交正常化という重大な政治的決断を行い、両国関係の新たなページを切り開いた」とした。その上でこの50年の両国関係について、4つの政治文書(注)と重要な共通認識により、各分野での交流と協力を絶えず深め、地域および世界の平和と発展を促進してきたと評価した。
習国家主席は今後の両国関係について「中日関係の発展を非常に重視している。岸田首相とともに、双方が国交正常化50周年を契機に、時代の流れに乗って、共同で新たな時代が求める中日関係の構築に注力するよう、リードすることを望む」とした。
李克強首相も岸田首相と祝電を交換した。李首相は「相互の対立や矛盾をコントロールし、国交正常化50周年を中日関係の新たなスタートとして、引き続き健全で安定した(両国関係の)前進を望む」とした。
2022年9月22日には李首相と、日本の経団連や日中経済協会、日中投資促進機構などをはじめとする経済団体・企業とのオンライン会見が行われた。李首相は国交正常化50周年に言及し、「中国は日本とともに、両国の協力を全方位的かつ幅広い領域で、マルチレベルでレベルアップさせることを望んでいる」とした。また、地域的な包括的経済連携(RCEP)協定の活用にも言及するとともに、新型コロナウイルス感染対策をしっかり行うという前提の下で、日中間の直行便を増加させるとした。
(注)1972年の日中共同声明、1978年の日中平和友好条約、1998年の日中共同宣言、2008年の日中共同声明を指すとされる。
(河野円洋)
日中国交正常化50周年を記念し、広州市で大湾区企業家サミット開催
2022年10月13日
日中国交正常化50周年を記念した「大湾区(注)企業家サミット」が2022年9月29日、在広州日本総領事館と粤港澳大湾区企業家連盟、広州日本商工会の主催により、広東省広州市で開催された。同サミットは日中企業間の協力関係強化を目的とし、同企業家連盟の会長企業を務める新華集団の蔡展思総裁をはじめ、広東省や香港、マカオの現地企業や進出日系企業関係者ら約200人が参加した。
サミットでは、中国企業の大湾区でのビジネスの取り組みが紹介された。農業用ドローン開発大手の極飛科技(XAG、本拠地:広州市)はドローンを活用した農業のIT化や、省人化への取り組みを紹介。今後は日本での製品普及についても意欲を示した。自動運転技術を開発するスタートアップ企業の文遠知行(WeRide、本拠地:広州市)は自社の自動運転に対する取り組みや無人タクシーの商用化について説明。同社の張力最高執行責任者(COO)は、中国の自動運転市場は今後最大6,400億ドル規模まで拡大するとの見方を示した。
「大湾区のイノベーションエコシステム」や「カーボンニュートラルに向けた日中企業連携」をテーマとしたパネルディスカッションも行われた。日中の企業関係者5人が登壇し、ジェトロがモデレーターを務めた。深セン市でスタートアップ企業の支援を行う深セン清華大学研究院の王羽主任は、大湾区の特徴として各都市で分業化が進んでいる点を強調したほか、三菱商事(広州)の張月華総経理は、国家戦略によるイノベーションの実施が大湾区の強みと述べた。激化する人材の獲得競争について、プライスウォーターハウスクーパース(PwC)広州の吉田将史・華南エリア統括パートナーは、大湾区内の境界をまたぐヒト・モノ・カネの動きの流動化の必要性や、デジタル人材育成の必要性に言及した。
カーボンニュートラルに関する日中間の企業連携の事例では、張総経理から北京市などで進めているバッテリーのリサイクル事業を紹介。将来的なカーボンリサイクル事業の展開にも意欲を示した。(注)広東・香港・マカオグレーターベイエリア(粤港澳大湾区)を指す。
(田中琳大郎)
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
バブル崩壊後の日本経済の「失われた30年」
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
小泉が派遣法の改正をしたおかげで、大部分の正社員の仕事が派遣に置き換わってしまいました。日本中にフリーターが激増してしまったのも、この男のせい。
小泉内閣時代の内閣ブレーンの一人で、経済と金融の大臣を兼任し、それまで3度、政府閣僚に選べられています。その後も諮問会とか委員会によく政府から呼ばれている人ですね。
慶應義塾大学総合政策学部の教授で、学歴も相当なもの、人材派遣業のパソナグループの会長でもあります。他にかなりの役職を受け持つ、まぁ多忙な人ですね。
2008年には韓国政府のアドバイザーとして顧問団に迎えられたり、小泉時代に総務大臣兼郵政民営化担当大臣に登用されて、郵政民営化推進で、自民党内部からも猛批判を受けた人です。
政策は
・所得税の最高税率を引き下げ(所得1000万円まで累進課税とする)
・解雇規制を緩和する
・同一労働同一賃金の法制化
・民間でできることは民間へ
以上は実現できていないか、あるいは骨抜きって感じで、多くは自民党内部の反対で押し切られていたみたいですね。
発言としては、財政悪化の要因は国債発行の乱発で日本の財政寿命は約3年とか、若者に自由を謳歌してもいいが引き換えに貧しくなるのも自由だ、頑張って成功した人の足を引っ張るななどがあります。
また格差社会の要因の一つは正社員という特権であるということもテレビで発言してますね。
平蔵を国賊と言ってる人たちは、恐らくバブル崩壊以後の失われた20年(30年?)の時代に、あまり良い事がなかった人が、非正規雇用を生み出したのは竹中のせいとか、自己責任ばかりが横行したのは平蔵のせいだ!と思っているからでしょうね。
また「時間内に仕事を終えられない、生産性の低い人に残業代という補助金を出すのはおかしい」と、まぁ私は定時に帰れという意味で、労働者の質の問題に触れていると思うのですが、これを悪く取る人もいたようです。
比較的合理的な理論で押し切るタイプの人ですが、やっぱり学歴・職歴が凄いのと、ズバズバ歯に衣着せぬ物言いの人なので、ものすごく好き嫌いが別れる人ではあると思います。特に既存の経済評論家や保守派の人には相当嫌われているようで。
人材派遣法の歴史は?
日本における派遣法の歴史
派遣法が施行されたのは、1986年7月1日です。 しかし、それ以前から人材派遣のようなことをしている会社は存在していました。 1980年代に入って雇用される労働者が増え、また業務請負という形態で派遣していたため、労働者保護の観点から派遣法が施行されることになったのです
労働者派遣法の歴史 荒井大
【派遣法の歴史】
[1985年(中曾根内閣)]
派遣法が立法される。
派遣の対象は「13の業務」のみ
[1986年(中曾根内閣)]
派遣法の施行により、特定16業種の人材派遣が認められる。
[1996年(橋本内閣)]
新たに10種の業種について派遣業種に追加。合計26業種が派遣の対象になる。
[1999年(小渕内閣)]
派遣業種の原則自由化(非派遣業種はあくまで例外となる)
この頃から人材派遣業者が増え始める。
[2000年(森内閣)]
紹介予定派遣の解禁。
[2003年3月(小泉内閣)]
労働者派遣法改正
例外扱いで禁止だった製造業および医療業務への派遣解禁。専門的26業種は派遣期間が3年から無制限に。
それ以外の製造業を除いた業種では派遣期間の上限を1年から3年に。
[2004年(小泉内閣)]
紹介予定派遣の受け入れ期間最長6ヶ月、事前面接解禁。
*鳩山政権による派遣法改正の動き*
1、製造業への派遣を原則禁止(常用型を除く)
2、日雇派遣、2か月以下の労働者派遣を禁止
3、登録型派遣の原則禁止(専門26業種を除く)
登録型…仕事がある時だけ雇用契約を結ぶもの。
常用型…仕事がなくても給料がもらえる(雇用契約を結べる)。
労働条件・労働基準めぐる法改正情報
派遣法 なぜ でき た?
もともと、労働基準法第6条で中間搾取の禁止が定められていますが、その規制を緩和する意味で制定されたのです。 労働者派遣法は、派遣事業の適正な運営と派遣労働者の雇用の安定、福祉の増進を目的としています。
派遣はいつから始まった?
日本の人材派遣の歴史は、1986年に「労働者派遣法」が施行されたことで始まり、これまで世の中の情勢にあわせ、何度も改正がなされてきました。
派遣法1999年の改正は?
1999年:対象業務が原則自由化となる(ネガティブリスト化) 規制緩和の波はさらに強く押し寄せ、適用対象業務の原則自由化(禁止業務のみを指定するネガティブリスト化)が実現。 一方で、建設、港湾運送、警備、医療、物の製造業務が禁止業務とされます。
人材派遣業の儲けの仕組み
人材派遣会社では、自社で雇用する派遣社員の労働力を派遣先の企業に提供することで「マージン」を上乗せした報酬を得ることで利益を出しています。 このシステムから、人材派遣業は「ピンハネ業だから楽して儲けている」などと揶揄されることがありますが、実際にはそれほど大きな利益があるわけではありません。
有期雇用派遣社員として働ける期間は最大3年
これは、2015年の派遣法改正により定められた内容です。 以前は派遣期間に制限はなく、派遣社員として長期間同じ部署で働くことができましたが、2015年の派遣法改正により「働けるのは3年間だけ」というルールに変更されました。
すぐに辞めてしまう理由
派遣で来た方がすぐ辞めてしまう主な理由としては次のようなことが考えられます。
仕事内容に馴染めない(未経験者が作業の手順や方法を理解できない)
職場に馴染めない(社内での決まりごとや雰囲気など)
地域や環境に馴染めない(他の地域から働きにきた場合など)
困ったことを相談できる人がいない(職場トラブルや将来のキャリアプランなど)
事前の研修や、就業後のフォロー体制などがない派遣会社だと、就業の前と後でのギャップが生じてしまい、「馴染めない…」と感じる機会が多くなります。
また、相談に乗ってくれる人がいないことで、不安や不満が退社に直結してしまうのです。
最初はほんの小さな「嫌だな…」と思う気持ちから始まったとしても、誰もフォローしてくれないために次第に勤務から足が遠のいてしまい、無断欠勤を続けた結果、そのままフェードアウトする。
派遣社員 何が問題?
単調な仕事や、いわゆる「誰でもできる仕事」を任されるため“やりがい”は生まれにくい特徴があります。 また仕事のやり方や方針に対して基本的に口を出すことができないため、働くことのモチベーションは維持しにくいでしょう。 なぜならそれが「派遣社員」の本質だからです。
派遣 時給上がった なぜ?
派遣は正社員と待遇が異なり、実際に働いた時間分のお金しかもらうことができません。 ボーナスや昇給などは基本的になく、企業によっては交通費の支給もありません。 そのため、その分が時給に上乗せされた形となり、高い時給に反映されているのです。
グループ内派遣のメリットは?
またグループ内派遣は、法律に則って雇用された派遣社員や正社員を雇うよりも、人件費を削減できるのが特徴です。 そのためグループ内派遣を許せば、専ら派遣のときと同様、企業はグループ内派遣からの派遣労働者ばかりを受け入れるようになり、正社員や法律に則った派遣社員の雇用を妨げることになりかねません。
派遣法 違反 どうなる?
当該法律に違反すると、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金刑が科せられます。 また、派遣先企業が更に派遣を行うことで利益もあげていた場合、労基法6条が規制する「中間搾取の排除」に該当するため、労基法違反にもなり、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金刑が科せられます。
なぜ派遣はダメなのか?
短期間での派遣就業では、労働者の収入が不安定になります。 また派遣会社、派遣先企業共に適正な雇用管理をすることが難しいという判断から、2012年の改正労働者派遣法で、日雇い労働者(日々もしくは30日以内雇用期間)の派遣は原則禁止となりました。 日雇派遣は条件に当てはまれば、派遣が認められています。
派遣が多い会社 なぜ?
まず、派遣会社が多い理由を室伏氏に聞くと「大手企業が人件費を削減したいがために、政府に構造改革を促した影響です」とキッパリ。 「企業としては人件費、社会保険料の負担が大きく、どうしても抑えたいコストです。 そこで大手企業を中心に構成されている経団連が自民党に働きかけ、派遣法の改正に踏み切らせました。
正社員 派遣 どっちが稼げる?
短期的に見た時、派遣の方が稼げるとお伝えした理由は、派遣の時給に高さにあります。 例えば月給25万円の正社員の場合、時給換算すると大体1500円程と言われています。 一方派遣はというと、条件の良い案件なら時給1800円という求人もあります。 正社員のように週5で8時間働く場合、月給は約32万円となります。
派遣社員 年収 いくら?
令和2年度の派遣社員の全国平均年収は約374万円でした。 専門性が高い職種ほど給料が高く、三大都市圏とそれ以外との地域差は、年収にして約54万円になります。 派遣社員の給料は人材派遣会社から支払われ、月末締め翌月給料日支払いであることが一般的です。
WDBのマージン率は?
どの派遣会社でもマージンはあるのですが、WDBはその率が高いです。 基本的なマージン率は「25%〜30%」とされているのですが、WDBでは34%に設定されています。
派遣 女性 多い なぜ?
一方、派遣社員という働き方を選んだ理由として女性がもっとも多く選んだのは「働く日数・期間を選べる」という選択肢でした。 同じ調査の中で今後も派遣社員として働きたいと答えた男性は3割にとどまったのに比べ、女性は4割と比較的高い割合を示しています。 派遣女性の中には、家事や育児しながら働いているという方も少なくありません。
フリーターと正社員 どっちが稼げる?
フリーターと正社員では、基本的に正社員のほうが高収入の傾向にあるようです。 厚生労働省の「令和2年賃金構造基本統計調査 結果の概要『雇用形態別にみた賃金』(p1)」によると、フリーターを含む非正規雇用の平均月収は男女計で21万4,800円。 正社員の平均月収は32万4,200円とされています。
派遣 1日いくら?
厚生労働省は、業種ごとの派遣料金の費用相場を公開しており、2021年4月時点では2020年度の結果が公表されています。 専門的な技術や知識が必要な職種の場合、1日あたりの平均料金は20,000~30,000円、それ以外の職業は10,000~20,000円が派遣料金の相場です。
派遣 1時間 いくら?
営業職種従事者の1人あたり1日8時間の平均派遣料金は2万1,083円、1時間あたりの平均派遣料金は2,635円となっています。
派遣会社 どれくらい抜いてる?
公表されていた派遣会社のピンハネの実態
私のように、フルタイムの派遣社員として働いている場合の、一般的な派遣料金の内訳。 派遣社員のお給料は、派遣先企業が派遣会社に払う「派遣料金」の70%。 30%が派遣会社の取り分。 派遣会社は派遣料金の30%をピンハネしてる!?
派遣 最低 賃金 2022 いくら?
2022年は10月1日から【時給1,072円】に改正されます。 この最低賃金は東京都内に派遣中の労働者を含みます。
派遣社員の人口は?
派遣の現状 | 一般社団法人日本人材派遣協会 2020年1~3月平均の派遣社員数は約143万人となりました。 雇用者全体(5,661万人、役員除く)に占める派遣社員の割合は2.5%となり、この割合は15年ほど大きな変化は見られず2~3%を推移しています。
なぜ派遣会社が多いのか?
まず、派遣会社が多い理由を室伏氏に聞くと「大手企業が人件費を削減したいがために、政府に構造改革を促した影響です」とキッパリ。 「企業としては人件費、社会保険料の負担が大きく、どうしても抑えたいコストです。 そこで大手企業を中心に構成されている経団連が自民党に働きかけ、派遣法の改正に踏み切らせました。
なぜ派遣はダメなのか?
単調な仕事や、いわゆる「誰でもできる仕事」を任されるため“やりがい”は生まれにくい特徴があります。 また仕事のやり方や方針に対して基本的に口を出すことができないため、働くことのモチベーションは維持しにくいでしょう。 なぜならそれが「派遣社員」の本質だからです。 派遣会社にとっての派遣社員は人的資源。
派遣会社のリスクは?
一番想定されうるリスクとしては、派遣事業で保有している集客チャネルや人材プールに、正社員雇用を希望する人材が少ないことや、経歴やスキルの関係から採用企業側の正社員としての採用ニーズがあまりないことがあげられます。
派遣社員 なぜ生まれた?
バブル崩壊以降、年功序列、終身雇用といった日本独特の雇用の在り方が問われ正社員のリストラが目立つようになってきた時期がありました。 そこで企業が求めたのが派遣社員です。 必要な期間、必要なポジションに労働力を充当できるのは企業にとって大きな魅力だったのかもしれません。 それに加えて、働く側の意識の変化があります。
派遣の悪いイメージは?
派遣のイメージは正社員に比べ、重要な仕事ややりたい仕事をやらせてもらえないイメージがあります。 人間関係ができて、気心がしれたころに辞めてしまう印象が強いので、仕事にまつわる悩みなどの相談がしづらいイメージがあります。 いつ雇用期間を切られるのかが全く予想できないため、将来に対して不安のある働き方だと思います。
派遣の仕事は何歳まで?
派遣に年齢制限はない
派遣労働者に年齢制限はなく、60歳以上で働いている方も存在します。 派遣会社への登録も、年齢制限はもちろん、性別や学歴、職歴、資格、スキル、経験などの条件も設けられていません。 即戦力として資格やスキル、経験が求められるイメージがあるものの、未経験者を歓迎している会社も数多くあります。
使えない派遣社員の特徴は?
「使えない……」交代になりやすい派遣社員の特徴
能力が自社の求める水準に達していない ...
能力に関して改善が見られない ...
注意やアドバイスに対して不機嫌になる ...
職場の規則に従ってくれない ...
派遣社員への教育内容を再考する ...
職場環境をチェックしてみる ...
交代を要請する ...
派遣元を変える
派遣社員の教育は 誰が する?
派遣スタッフの教育訓練に関しては、雇用主である派遣会社が実施すべきですが、派遣先の業務に密接に関連した教育訓練については、実際の就業場所である派遣先が実施することが適当であるとし、派遣先の正社員と同様の教育訓練を受けさせることが義務化されました。
派遣法改正案は「正社員の雇用」を守るためだった!?
非正社員は誰も救われない“矛盾と罠”
――国際基督教大学 八代尚宏教授インタビュー
2010.12.2
今年3月に閣議決定し、国会審議が行われていた労働者派遣法改正案は、首相交代などの混乱のなか、継続審議となった。08年秋の世界同時不況後、派遣労働の規制強化に向けた世論の高まりとともに注目を浴び、登録型派遣や製造業務派遣の原則禁止を柱とする本法案。今後、再審議で成立したとして、本当に非正社員は救われるのだろうか。検証するとともに、非正社員が真に救われる働き方やそれを担保する制度について、国際基督教大学の八代尚宏教授に話を聞いた。(聞き手/ダイヤモンド・オンライン 林恭子)
派遣法改正でも正社員は増えない
むしろ失業者が増える可能性も
――「派遣の原則禁止」を目指した派遣法改正案だが、これが実現すれば本当に非正社員は救われるのだろうか。派遣法改正案の問題点とともにお教えいただきたい。
それを明らかにするためには、まず派遣労働の規制緩和がなぜ行われたかを考えなければならない。
そもそも派遣社員などの非正社員の増加は、「小泉政権における新自由主義的な構造改革によってもたらされた」という認識が広まっているが、これはまったくの誤解である。なぜならこの規制緩和は、1999年に派遣労働の雇用機会の拡大と保護強化を目的とした国際労働機関(ILO)第181号条約に日本が批准したことに基づいており、2001年に成立した小泉政権誕生以前の話であるからだ。
この条約は、欧州を中心に失業率が高止まりしている状況下で、失業率を低下させるためにも有料職業紹介や派遣労働を容認し、不安定でも雇用機会を増やすことが先決だという事情から生まれたもの。日本も批准し、それ以前の派遣先の職種を厳しく制限した「原則禁止・例外自由」を逆転して、「原則自由・例外禁止」へと原則を大転換した。これに伴い、「当分の間」禁止となっていた製造業への派遣が、2004年に自由化されたに過ぎない。
したがって、規制緩和の目的は「雇用機会の拡大」にあったわけだから、それを元に戻して規制を強化をすれば、結果も逆になるのは当然だ。
朝日新聞が全国主要100社を対象に行った「派遣が禁止された場合の対応」へのアンケート(09年11月実施)によると、「他の非正社員に置き換える」(契約社員:36社、請負・委託:30社、パートタイム:22社)のがほとんどで、「正社員の増加で対応」はわずか15社だった。
小泉労働法制「改革」についての雑感
静岡県労働研究所 理事長 大橋 昭夫
小泉内閣は、昨年6月27日労働基準法の一部を改正する法律を成立させ、これが本年1月1日から施行されている。 この詳細については触れないが、この改正法は、有期労働契約の契約期間の上限の延長、有期労働契約の締結、更新及び雇い止めに関する基準、解雇権濫用法理の明文化、裁量労働制の一層の拡大を実現したもので、解雇規制を除き労働者に対して、大きな苦難を強いたものと評価される。 この改正は、もっぱら日本経団連の意向に沿うもので、この推進勢力は、小泉総理大臣のブレーンで総合規制改革会議議長宮内義彦オリックス会長を中心とするグループであったと言われる。 宮内議長は、「鉛筆型の人事戦略」を唱え、少数のコア社員を細い芯とし、これのみを保護し、その周りの木の部分に成功報酬型の社員を、さらに、その周りにパートタイマーや派遣労働者を配置し、これらの木の部分を必要に応じて調整することが、グローバル経済を勝ち抜く今後の経営戦略であることをあからさまに述べている。自分が生き抜くためには、大多数の労働者の生活など視野に入らないのである。 今回の労基法の改正は、労働者派遣法の「改正」による派遣業種の一層の拡大と相俟って、我が国の正規労働者の数を著しく減少させ、これをパートタイマー、派遣労働者等の不安定労働に代替させるものであって、わが国社会の労働秩序を根底から破壊することになる。 厚生労働省は、今回の改正法案の提出にあたって、「今日、我が国の経済社会においては、少子高齢化が進み労働力人口が減少していく一方、経済の国際化、情報化等の進展による産業構造や企業活動の変化、労働市場の変化が進んでいる。このような状況の下で、経済社会の活力を維持、向上させていくためには、労働者の能力や個性を活かすことができる多様な雇用形態や働き方が選択肢として準備され、労働者一人一人が主体的に多様な働き方を選択できる可能性を拡大すること、働き方に応じた適正な労働条件が確保され、紛争解決にも資するよう労働契約など働き方にかかるルールを整備すること、これらの制度の整備、運用に際しては、労使によるチェック機能が十分に活かされるようにすることなどを基本的な視点とする」と説明しているが、この視点は、余りにも労働者の生活実態を知らない「綺麗事」であり、役人の文章である。 私が指摘するまでもなく、わが国の経済社会の活力を維持、向上させていく最良の手段は、雇用の確保であり、人間らしい生活をするのに必要な賃金の保障である。 厚生労働省のいう「多様な雇用形態や働き方」という概念は空漠としており、その内容が如何なるものか明確でないが、派遣労働や有期契約による労働、更には残業代を回避するための裁量労働であると察しはつく。 これらの労働形態は、いずれも不安定雇用であって、多様な働き方を実現し、それが豊かな生活につながる契機となることは経験則上ありえない。 私の弁護士としての経験からすると、労働者は少々他と比べて賃金が低いとしても、雇用が安定的に確保され、将来の生活の見通しが立つ時にこそ、労働生活においても主体性を発揮でき精神的にも自由になれるものである。 いま、労働者の自己破産の申し立て件数が激増し、それがわが国の平均的な法律事務所の日常的業務になっている。 私もこの種の事件を数多く取り扱うが申し立てをする労働者の所得が低く、そのうちの少なくない者が、派遣労働者、有期契約労働者、フリーターであり、その所得水準が生活保護基準以下である者も存在する。 多様な雇用形態や働き方は、私の実感からすると、使用者の身勝手や彼らの生存権のみを保障するもので、労働者に対し永久に社会底辺に沈殿させる効用しかないように思われる。 私は、西ヨーロッパに見られる如く、「共生き」の思想を前提とした労働ルールの確立こそ、社会発展の源泉であると考えるし、小泉内閣の方向は、社会の不安定化を招来させることにしかならないと思う。 今回の労基法の改正で評価できる点は、唯一解雇権の制限法理が法文上明らかになったことのみである。 この規定は、小泉内閣の原案では、「使用者は、この法律又は他の法律の規定によりその使用する労働者の解雇に関する権利が制限されている場合を除き、労働者を解雇することができる。但し、その解雇が、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と解雇が原則自由になっていた。しかし、労働者の反対があり、最高裁で確立した解雇権濫用法理の精神に立ち帰り、現行の「解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」(労基法18条の2)となったのである。 これは、西ヨーロッパ諸国の解雇制限法に比べると極めて簡単な条項ではあるが、それでも法規範として、すべての裁判官の判断を拘束するもので一歩前進だと評価できる。 小泉構造改革は、今やすべての面にわたって失敗しているが、更なる労働「改革」は、労働者の生活をより一層困難にするもので、働く人々は、思想、信条、潮流、傾向を超えて、この流れに対抗する必要があろう。 わが国に憲法の精神に忠実な「働くルール」が確立されることを切に望むものである。それが真の意味での労働改革である。
破たんした小泉「構造改革」 社会と国民に何もたらした
貧困と格差 際限なし
「官から民へ」「改革なくして成長なし」―。ワンフレーズ政治で「構造改革」路線をひた走った小泉純一郎政治。その「本丸」とされた郵政民営化問題で、麻生太郎首相が迷走発言を続けるなか、小泉純一郎元首相や竹中平蔵元経済財政担当相らがマスメディアに盛んに登場し、「構造改革」路線の“復権”をはかる動きもみられます。「痛みに耐えれば、明日はよくなる」どころか、「生きていけない」と悲鳴があがるほどの貧困と格差の惨たんたる状況に国民を追い込んだのが「小泉改革」でした。歴史の審判はすでに下っています。
雇用のルール破壊
「派遣切り」・ネットカフェ難民
東京のど真ん中に、五百人もの人たちが衣食住を求めて集まった「年越し派遣村」。大企業の理不尽な「非正規切り」で「人間としての誇りを奪われた」「自殺も考えた」との声が渦巻きました。貧困を目に見える形でつきつけ、政治を動かしました。
「派遣村」に象徴される「使い捨て」労働の深刻な広がりは「構造改革」の名によるリストラの促進や労働法制の規制緩和がもたらしたものです。
この十年間で正規労働者が四百九万人も減り、その代わりに、非正規労働者が六百六万人も増えました。
自民、公明、民主、社民などの各党が賛成した一九九九年の労働者派遣法改悪。派遣労働を原則自由化し、「派遣」という形での「使い捨て」労働の増加に拍車をかけました。
二〇〇一年に発足した小泉内閣は、「構造改革」を加速。まず「不良債権処理」の名で中小企業つぶしをすすめ、〇三年には、企業がリストラをすればするほど減税をするという「産業再生」法を延長・改悪し、大企業のリストラを後押ししました。
一方、派遣法を改悪し、〇四年三月からは製造業への派遣を解禁しました。この中で、もともと危ぐされていた派遣労働者の労働災害が増加。〇七年の死傷者数(五千八百八十五人)は、〇四年と比べると九倍という激増ぶりを示しました。
ネットカフェで寝泊まりしながら「日雇い派遣」で働く若者の姿が、底なしに広がる「働く貧困層」の象徴となりました。
ギリギリの生活を強いられている派遣労働の実態が大問題になり、日本共産党の論戦とあいまって政府でさえ派遣法の見直しを言い出さざるをえなくなりました。労働分野の規制緩和が破たんしたことは明確です。
しかし、米国の金融危機に端を発した景気悪化を口実に、〇八年後半、大企業は製造業を中心に大量の「派遣切り」「期間工切り」を始めました。被害は日増しに広がり、今日の日本社会を覆う最大の社会問題になっています。
景気のいいときには、正社員を派遣や期間工に置き換えて大もうけをし、景気が悪化したらモノのように使い捨てる―この大企業の横暴勝手を容易にする仕組みを作ったのが、労働の「構造改革」であり、今日の事態は、まさに政治災害そのものです。
社会保障の連続改悪
医療崩壊・国保証取り上げ
「わずかな年金は減らされたうえ、保険料の天引きは容赦ない」「病気になってもお金がなければ病院にもいけない」―。「構造改革」による社会保障の連続改悪によって、こんな苦難が国民を襲いました。
その大もとにあるのが、小泉内閣が決めた社会保障費の抑制方針です。二〇〇二年度から毎年、社会保障費の自然増分から二千二百億円(初年度は三千億円)削減されてきました。
抑制の対象は医療、介護、年金、生活保護と社会保障のあらゆる分野に及び、庶民への痛みの押し付けの結果、「生きること」自体が脅かされる実態が広がっています。
医療分野では、国民の負担増に加え、医療費削減を目的に医師数の抑制政策を続けたため、救急患者が救われない医師不足が社会問題化し、「医療崩壊」と呼ばれる事態が出現しました。
高すぎる国民健康保険料が払えずに正規の国保証を取り上げられた世帯は約百五十八万世帯にまで広がっています。受診を控え、手遅れで死亡する例は後を絶ちません。
そのうえ、国民生活の最後の命綱である生活保護さえ切り縮められました。老齢加算の廃止で、「朝はパン一枚、昼はうどん」「暖房費節約のため、ストーブをつけず布団に入る」「風呂の回数を減らす」など生活の根幹まで切り詰めざるをえない実態です。(〇八年一月、全日本民主医療機関連合会の調査報告)
こうしたなか、昨年四月に導入された後期高齢者医療制度に、国民の怒りが爆発しました。同制度に対する不服審査請求は全国で一万件超。「『高齢者はいずれ死を迎える、お金も手間もかけなくてよい』という、人間性を喪失した制度だ」などの怒りの声があふれています。
日本医師会など医療関係四十団体は〇八年七月、「社会保障費の年二千二百億円削減撤廃」を決議。国民の批判は、小泉内閣がしいた二千二百億円の削減路線そのものに向けられはじめました。
自公政権は社会保障費の削減路線の転換は明言しないものの、〇九年度予算案で一時的な手当てを行い、社会保障費の実質の削減幅は二百三十億円に“圧縮”せざるをえなくなっています。第二次小泉改造内閣で厚労相だった自民党の尾辻秀久議員でさえ、一月三十日の参院本会議で「乾いたタオルを絞ってももう水はでない。潔く二千二百億円のシーリングはなしと言うべきだ」と述べるなど、社会保障費削減路線の破たんを認めざるをえなくなっているのです。
庶民負担増 大企業は減税
7年間で国民に50兆円近くも
小泉政権以来の増税などで国民負担は、年間十三兆円も増えました。二〇〇二年度から〇八年度まで七年間の国民負担増を累計すれば、五十兆円近くになります。
その一方で、大企業・大資産家への減税は、一九九八年以降の十年間に行われたものだけでも、大企業に年間五兆円、大資産家に年間二兆円、あわせて年間七兆円以上になっています。十年間の累計では、四十兆円もの税収が失われました。
地方の切り捨て
激減する交付税・農業破壊
「交付税が四割減って半分も補てんされない」「このままでは吉野は死んでしまう」
昨年七月。奈良県吉野郡で開かれた日本共産党の演説会に先立ち、市田忠義書記局長と懇談した地元町村長らから、こんな嘆きの声が率直に寄せられました。
「地方ができることは地方へ」をうたい文句に自民・公明政権が強力に推進した「三位一体改革」は、農山漁村の自治体を存亡の危機にまで追い詰めています。
実際、「三位一体改革」が断行された二〇〇四年から三年間で、国庫補助負担金は四・七兆円、地方交付税は五・一兆円がそれぞれ削減されました。一方、国から地方への税源移譲はわずか三兆円しかありません。地方自治体にとっては差し引き六・八兆円のマイナスです。
全国知事会は昨年七月の知事会議で、このままでは一一年度までに地方自治体の財政が破たんするという衝撃的な試算を発表しました。とりわけ地方交付税が財政に占める比重が高い町村の財政は深刻です。
「地方交付税の削減など、国による兵糧攻めからの生き残り策」「周辺町村が財政破たん寸前だった」。全国町村会の「道州制と町村に関する研究会」が昨年十月にまとめた調査報告でも、市町村合併の理由の柱に「三位一体改革」による交付税削減を指摘する声が相次ぎました。
国会でも、鳩山邦夫総務相が「急激にやりすぎた。失敗の部分がある」(十二日、衆院本会議)と答弁。「三位一体改革」の破たんを認めました。
また、輸入自由化の促進による農業破壊、大型店の進出による商店街の「シャッター通り」化など、地方経済の冷え込みも深刻です。
しかし、自民党は、こうした“地方切り捨て”を反省するどころか、一〇年三月末の合併特例新法の期限切れを前に「おおむね七百から千程度の基礎自治体に再編」すると、いっそう合併を推進することを主張。さらに、政府は「時代に適応した『新しい国のかたち』をつくる」として道州制の導入を掲げています。
こうした動きには全国町村会が「強制合併につながる道州制には断固反対していく」と明記した特別決議を採択するなど、痛烈な反撃が巻き起こっています。
経済ゆがみ、ぜい弱に
「戦後最悪の経済危機」(与謝野馨経済財政担当相)―。内閣府が十六日発表した二〇〇八年十―十二月期の国内総生産(GDP)が実質で前期比3・3%減(年率換算12・7%減)となったニュースは、衝撃を与えました。金融危機の震源地である米国よりも急激な落ち込みだったからです。なぜこんなことになったのか。ここにも、背景に小泉内閣いらいの「構造改革」があります。
極端な輸出依存
「衝撃 石油危機以上 輸出依存体質響き」(「毎日」十七日付)、「外需依存の成長 岐路」(「日経」同)、「外需頼み 転換カギ」(「読売」同)といった見出しが商業メディアに目立ちました。極端なまでに輸出に依存した「経済成長」の破たんです。
「構造改革」を掲げた小泉内閣が発足(〇一年四月)して以来の変化をみてみましょう。内閣府のGDP統計によると、所得や個人消費は低迷しているのに、輸出が極端に伸び、〇八年に失速します。財務省の法人企業統計をもとに、製造業大企業(資本金十億円以上)の〇一年度と〇七年度を比較すると、経常利益は二・二五倍に増えています。ところが、従業員給与は〇・九八倍と減っています。大幅に増えたのは株主への配当と社内留保です。一方、民間信用調査会社の調査では、法的整理による企業倒産が増えています。ほとんどが中小企業です。
自動車、電機など輸出大企業を中心に従業員や中小企業・業者にしわ寄せする形で、大もうけし、もっぱら株主に還元するという構図です。
財界全面後押し
こうした企業体質をつくり出したのが、「構造改革」だったと、日本経団連会長の御手洗冨士夫キヤノン会長が述べています。
「これは、何といっても構造改革の進展がもたらしたもの」「多くの企業でも、筋肉質の企業体質が形成されている。過剰設備や過剰債務、過剰雇用という、いわゆる『三つの過剰』は完全に解消している」(〇八年六月十九日の講演)
文字通り、財界の全面的な後押しで推進されたのが小泉流「構造改革」でした。
財界が求める雇用など「三つの過剰」の解消を推進するテコと位置づけられたのが不良債権の強引な早期最終処理です。
小泉内閣が最初につくった「骨太の方針」(〇一年六月)は、不良債権処理の加速を通じて「効率性の低い部門から効率性や社会的ニーズの高い成長部門へとヒトと資本を移動することにより、経済成長を生み出す」とうたいました。小泉内閣は、リストラすればするほど減税する「産業再生」法を拡充、製造現場への労働者派遣を解禁しました。
懸念したことが
この結果、「成長」したのは、「筋肉質」になった輸出大企業や大銀行だけでした。「不良債権」扱いされた中小企業は倒産に追い込まれ、大量の失業者が生まれ、正社員から賃金の安い非正規社員への置き換えが進みました。
あまりにも、国内経済を脆弱(ぜいじゃく)にしてしまった「構造改革」。政府の「ミニ経済白書」(〇七年十二月)でさえ、輸出は増加しているが、家計部門が伸び悩むなか、米国経済など海外リスクが顕在化した場合、景気は「厳しい局面も予想される」と懸念していたことが現実のものとなりました。
推進者がいま「懺悔の書」
小泉流「構造改革」をめぐり居直る竹中平蔵元経済財政・金融担当相と対象的に「懺悔(ざんげ)の書」を書いたのは、中谷巌氏。小渕内閣の経済戦略会議の議長代理として「構造改革」の提言をまとめた中心人物です。竹中氏も同会議のメンバーの一人でした。
中谷氏は自著『資本主義はなぜ自壊したのか』のなかで、「一時、日本を風靡(ふうび)した『改革なくして成長なし』というスローガン」にふれ、「新自由主義の行き過ぎから来る日本社会の劣化をもたらしたように思われる」として、「『貧困率』の急激な上昇は日本社会にさまざまな歪(ゆが)みをもたらした」と指摘。「かつては筆者もその『改革』の一翼を担った経歴を持つ。その意味で本書は自戒の念を込めて書かれた『懺悔の書』でもある」と書いています。
郵政民営化矛盾が噴出
小泉内閣が「構造改革」の本丸と位置付けた郵政民営化。その矛盾が噴出しています。
「私は郵政民営化を担当した大臣」(二〇〇八年九月十二日、自民党総裁選の討論会)と自認する麻生太郎首相。その麻生首相が「(郵政事業の四分社化を)もう一回見直すべき時にきているのではないか。小泉首相のもとで(郵政民営化には)賛成ではなかった」(二月五日の衆院予算委員会)と言い出したのは、郵政民営化の破たんを象徴しています。
当時の小泉首相が「郵政選挙」までやって強行した郵政民営化のかけ声は「官から民へ」「民間でできることは民間で」「貯蓄から投資へ」でした。
「民間」といっても日米の大手金融機関のことです。もうけのじゃまになる郵便貯金、簡易保険などの郵政事業をバラバラにするのが四分社化でした。
「貯蓄から投資へ」といっても、庶民の預貯金を呼び込もうとしている証券市場の売買の六割以上は外国人投資家。その大半はヘッジファンドとよばれる投機基金です。庶民の虎の子の財産が食い物にされかねません。
安心、安全、便利を願う国民にとっては「百害あって一利なし」の郵政民営化。その矛盾のあらわれは小泉流「構造改革」路線そのものの破たんを物語っています。
“改革が足りないから”と居直る竹中氏だが…
小泉流「構造改革」がモデルにした本家の米国で、市場まかせの「新自由主義」路線が破たんしました。にもかかわらず、小泉流「改革」にしがみつこうとする勢力がいます。
一月一日放送のNHK番組で、小泉「改革」を推進した元経済財政・金融担当相の竹中平蔵氏は、大企業の「非正規社員切り」横行が社会問題になり、小泉「改革」に批判が強まっていることに、こう居直りました。
「大企業が非正規を増やすのは原因がある。正規雇用が日本では恵まれすぎている。正規雇用を抱えると企業が高いコストをもつ」
「同一労働同一賃金」をやろうとしたが、反対されたとし、「(年越し派遣村などは)改革を中途半端に止めてしまっているから、こういう事態が起きている」。
竹中氏が“止まっている”という「改革」の中身は、正社員の賃金水準を賃金が安い非正規社員の水準に引き下げるという意味での「同一労働同一賃金」です。大企業の総人件費を抑えるのが狙いです。これでは、働いても働いても貧困から抜け出せない「ワーキングプア」を労働者全体に広げることにしかなりません。
しかも、竹中氏は「問題は、いまの正規雇用に関して、経営側に厳しすぎる解雇制約があることだ」(「竹中平蔵のポリシー・スクール」二月一日付)として、企業業績が悪化したら従業員を抱え込まなくていいような「新たな法律を制定することが必要だ」と主張しています。正社員を含めた“解雇自由法”をつくれといっているようなものです。
一方で、「日本を元気にしないといけない」として、最優先課題にあげたのが法人税率をもっと引き下げることでした(一月一日のNHK番組)。竹中氏がかかげる「改革」はあくまで、大企業のための「改革」を徹底しろということにすぎません。
2021.09.30
国が見捨てた就職氷河期世代の絶望…バブル崩壊後の30年間で何が起きたか
当事者として、取材者として
小林 美希 プロフィール
2021年9月29日に自民党の総裁選が行われ、その後には総選挙が控えている。政治家が「中間層の底上げ」を訴えるが、考えてみてほしい。もとはといえば、中間層を崩壊させたのは政治ではなかったか。
国際競争の名の下で人件費を削減したい経済界は政治に圧力をかけた。不況がくる度に労働関連法の規制緩和が行われ、日本の屋台骨が崩れていった。最も影響を受けたのが就職氷河期世代だ。これからを担っていくはずだった若者たちが、非正規雇用のまま40~50代になった。
私が非正規雇用の問題を追って18年――。いったい、何が変わったのか。
大卒就職率6割以下の時代
1980年代には8割あった大卒就職率は、バブル経済が崩壊した1991年以降に下がり始めた。そして2000年3月、統計上、初めて大卒就職率が6割を下回る55.8%に落ち込んだ。大学を卒業しても2人に1人は就職できなかったというこの年に、私は関西地方で大学を卒業した。
その3年後の2003年3月に大卒就職率は過去最低の55.1%を更新。日経平均株価は同年4月に7607円まで下落した。この時の私はもちろん、当事者だった大学生の多くは雇用環境が激変するなかにいるとは気づかずにいた。
私の就職活動は苦戦した。約100社にエントリーシートを送り、50社は面接を受けた。神戸に住んで大学に通っていた私の就活の主戦場は大阪で、面接を受けるために毎日のように大阪周辺を歩き回った。最終的に内定が出たのは消費者金融会社の1社のみだった。
卒業後に東京で就職活動をやり直し、ハローワークに通った。新聞広告の求人を見て応募した業界紙の「株式新聞」に採用が決まった。就職試験の日、「うちは民事再生法を申請したばかりですが」と説明があり、倒産しかけた会社に就職することに悩んだが、「面白そうだ」という直感が勝った。
この株式新聞時代に出会い、後の私の記者活動に影響を与えたのが、伊藤忠商事の丹羽宇一郎社長(当時)だ。丹羽氏との出会いがなければ、私は就職氷河期世代の問題を追及しなかったかもしれない。
新人の時には経済記者として食品、外食、小売り、サービス業界を担当。商社の担当も加わり、出席した伊藤忠商事の記者懇談会で初めて丹羽氏に挨拶をする。記者に囲まれていた丹羽氏に私は「社長の役割とは何か」と聞いた。この若気の至りとも言える質問に対し、丹羽氏は真顔で「経営者とは、社員のため、顧客のため、そして株主のためにある」と答えてくれたのだった。
若者が疲れ切っている…なぜ?
株式新聞入社から1年後の2001年の初夏、毎日新聞が発刊(現在は毎日新聞出版)する『週刊エコノミスト』編集部に契約社員として転職した。私はだんだんと雑誌の仕事に慣れていき、天職と思って没頭していた。深夜や明け方に及ぶ校了作業は達成感があり、職場で夜を明かして新聞をかぶってソファで寝ていたこともあった。
これはマスコミ特有の働き方かと思っていたが、この頃、金融、製造、サービス業などに就職していった友人たちも長時間労働というケースが多かった。そのうち、充実感とは違った何かがあると感じ「なにかおかしい。若者が疲れ切っている」と首をかしげるようになっていった。
その疑問が確信に変わったのは、2003年前後に上場企業の決算説明会で経営者や財務担当役員らが強調した言葉を聞いてからだ。
「当社は非正社員を増やすことで正社員比率を下げ、利益をいくら出していきます」
2001年のITバブル崩壊から間もなくてして企業利益がV字回復し「失われた10年」が終わるかのように見えた。私はこの利益回復は非正規雇用化で人件費を削減したことによるものに過ぎないと見た。これでは経済を支える労働者が弱体化すると感じた私は、若者の非正規雇用の問題について企画を提案した。
『週刊エコノミスト』の読者層の年齢は高く、若者の雇用問題をテーマにしても読まれないという理由で、企画はなかなか通らなかった。さらに世間で浸透していた「フリーター」という言葉の印象が自由を謳歌しているイメージが強く、若者は甘いという風潮があるなかでは、ハードルが高かった。
悩んだ私は、再び、若気の至りの行動に出た。伊藤忠商事の丹羽氏にアポイントをとって、企画が通らないこと、企画が通らなければ転職したほうが良いか迷っていると人生相談をしたのだ。若者の非正規雇用化が中間層を崩壊させ、消費や経済に影を落とすと見ていた丹羽氏は「同じことを3度、上司に言ってごらんなさい。3度も言われれば根負けして上司は必ず折れるから」とアドバイスしてくれた。
私は企画が通らないまま非正社員として働く若者の現場取材を進めた。その頃、ある会合で話したコンビニ大手の社長が「息子がフリーターで……」と悩む胸の内を明かしたことがヒントになり、デスクや編集長を説得した。
「子どもの就職や結婚を心配するのは立場を超えて一緒のはず。読者の子どもを想定して、タイトルを若者とせず、娘や息子に変えたらどうか」
企画を提案し始めてから数か月経った2004年5月、ついに第2特集で「お父さんお母さんは知っているか 息子と娘の“悲惨”な雇用」を組むことが実現した。非正規雇用に関するデータを探し、マクロ経済への影響など当時は存在しなかったデータはシンクタンクのエコノミストに試算してもらった。
この特集について慶応大学(当時)の金子勝教授や東京大学の児玉龍彦教授がそれぞれ大手新聞の論壇コーナーで取り上げてくれたことで、続編が決定。第1特集となって「娘、息子の悲惨な職場」がシリーズ化した。
富の二極分化で「中間層崩壊」
この頃の若年層の失業率は約10%という高さで、10人に1人が失業していた。内閣府の「国民生活白書」(2003年版)により、2001年時点の15~34歳のフリーター数が417万人に上ると公表されると社会の関心が若者の雇用問題に向いたが、企業側の買い手市場は続き、労働条件は悪化していく。
パート・アルバイト、契約社員や派遣社員として働き、休日出勤やサービス残業の日々でも月給が手取り16万円から20万円程度のまま。正社員でも離職率の高い業界や会社での求人が多く、ブラック職場のため過労で心身を崩すケースが続出した。
社会保険料の負担から逃れるために業務請負契約を結ぶ例まで出現。大企業や有名企業ほど、「嫌なら辞めろ。代わりはいくらでもいる」というスタンスで、若者が使い捨てにされた。こうした状況に警鐘を鳴らすためには、経営者の見方を取り上げなければならないのではないか。
2005年1月4日号の『週刊エコノミスト』では、ロングインタビュー「問答有用」のコーナーで経済界の代表的な経営者であった丹羽氏に中間層の崩壊について語ってもらった。この時点で、若者の労働問題について本気で危機感を持つ経営者は私の知る限りでは他にいなかった。丹羽氏はこう語った。
富(所得)の2極分化で中間層が崩壊する。中間層が強いことで成り立ってきた日本の技術力の良さを失わせ、日本経済に非常に大きな影響を与えることになる。中間層の没落により、モノ作りの力がなくなる。同じ労働者のなかでは「私は正社員、あなたはフリーター」という序列ができ、貧富の差が拡大しては、社会的な亀裂が生まれてしまう。
戦後の日本は差別をなくし、平等な社会を築き、強い経済を作り上げたのに、今はその強さを失っている。雇用や所得の2極分化が教育の崩壊をもたらし、若い者が将来の希望を失う。そして少子化も加速する。10~15年たつと崩壊し始めた社会構造が明確に姿を現す。その時になって気づいても「too late」だ。
企業はコスト競争力を高め、人件費や社会保障負担を削減するためにフリーターや派遣社員を増やしているが、長い目でみると日本の企業社会を歪なものにしてしまう。非正社員の増加は、消費を弱め、産業を弱めていく。
若者が明日どうやってご飯を食べるかという状況にあっては、天下国家は語れない。人のため、社会のため、国のために仕事をしようという人が減っていく。
それが今、現実のものとなっている。
格差はこうして固定・拡大化した
丹羽氏のインタビューが掲載された年の8月8日、小泉純一郎首相(当時)が郵政民営化を掲げた解散総選挙に打って出て圧勝し、規制緩和路線に拍車がかかっていく。小泉郵政選挙の投開票は9月11日。その1週間後の9月18日には一般派遣の上限期間が3年とされる改正労働者派遣法が公布され、2週間待たずの9月30日施行で、いわゆる派遣の「3年ルール」ができた。
この3年ルールとは、表向きには派遣で同じ職場で3年が過ぎたら正社員や契約社員などの直接雇用にすることを促す改正だったが、実際には多くの派遣社員が3年の期間直前で契約を打ち切られることになった。同じ年に労働基準法も改正されて非正規雇用の上限期間が3年になったことで、非正社員が“3年でポイ捨て”され、非正規雇用のまま職場を転々とせざるを得ない労働環境が整備された。
1995年に旧日経連が出した「新時代の『日本的経営』」で雇用のポートフォリオが提唱され、景気の変動によって非正規雇用を調整弁とする固定費削減が図られて10年経った2005年に「3年ルール」ができた。ここが分岐点となり、日本は格差を固定化させ、格差を拡大させる路線を歩んでしまったのではないだろうか。
本来なら、2007年から団塊世代の定年退職が始まるため人手不足を補うという意味で、まだ20~30代前半で若かった就職氷河期世代を企業に呼び込むチャンスがあったはずだ。大卒就職率はリーマンショック前の2008年3月に69.9%まで回復したが、卒業後数年が経った非正社員は置き去りにされた。
問題提起し続けるために
小泉郵政選挙を機に私は、「もし自分が政治家だったら、何を問題にし、何の制度を変えていくか」ということを、より強く意識するようになった。就職活動をしていた大学時代に講座を聴いて影響を受けた、朝日新聞大阪本社の新妻義輔編集局長(当時)の言葉を思い出していた。
「人の苦しみを数字で見てはいけない。構造問題に苦しむ人が1人でもいるのなら、それを書くのが記者だ」
新妻氏は若い記者時代に森永ひ素ミルク事件(1955年に森永乳業の粉ミルクにひ素が混入して多くの被害者が出た事件)を追っていた。事件の担当医に「被害者は何%か」と数字を聞いた時に、医師から注意を受けた経験からの教訓だという。
就職氷河期世代が抱える問題は、まさに非正規雇用を生み出す法制度という構造問題が起因しているはず。それを問題提起し続けることは、私の役割なのではないか。労働問題に特化するには組織にいては限界があると考えた私は、小泉郵政選挙から1年半後の2007年、フリーのジャーナリストになった。
絶望と諦めのムードが蔓延した
第一次安倍晋三政権(2006年9月から2007年9月)が就職氷河期世代向けに「再チャレンジ」政策をとったが、政権が短命に終わるとともに支援は下火になった。2008年のリーマンショックが襲い、就職氷河期世代だけでない多くの人が職を失った。
政府は就職氷河期世代の支援というよりは、支援事業を担う民間企業を支援したと言える。国は15~34歳の「フリーター」対策の目玉政策として2004~06年に「ジョブカフェ」のモデル事業を行っており、同モデル事業を行った経済産業省から委託を受けた企業が異常に高額な人件費を計上していたのだ。
調べると、ジョブカフェ事業ではリクルート社が自社社員について1人日当たりで12万円、コーディネーターに同9万円、キャリアカウンセラーに同7万5000円、受付事務スタッフに同5万円という“日給”を計上していたことが分かった。『週刊AERA』(2007年12月3日号、同年12月10日号)でスクープ記事を執筆すると、国会でも問題視された。
このジョブカフェでは委託事業が何重にも再委託され、税金の無駄も指摘した。昨年問題になった新型コロナウイルスの感染拡大の対策で多額の委託料が電通に支払われているにもかかわらず、何重にも委託されている問題はなんら変わっていないのだ(参照「給付金『再々々々委託』の深い闇…10年以上前から全く変わっていない」)。
就職支援事業が企業の食い物にされる一方で、就職氷河期世代の非正社員がやっと正社員になれるかもしれないというところで契約を打ち切られる。そうしたことが繰り返され、いくら頑張っても報われずに絶望の淵に追いやられた。正社員になったとしてもブラック職場で追い詰められ、心身を崩して社会復帰できないケースも少なくはない。こうした状況が続いたことで、絶望と諦めのムードが蔓延した。
2010年代に何が起きたか
2009年3月に日経平均株価はバブル崩壊後最安値の7054円をつけ、2010年3月の大卒の就職率は60.8%に落ち込んだ。2012年12月に第2次安倍内閣が発足すると、あたかも「アベノミクス」によって新卒の就職率が高まったかのように見えた。しかし、それは、団塊世代が完全にリタイアするタイミングが重なったことによるもので、15~59歳の労働力人口がピーク時より500万人減っていたことが後押ししただけだった。
安倍政権が打ち出した「女性活躍」の名の下で、企業は人手不足を補うためにブランクのある“優秀な”主婦の採用に乗り出し始め、専業主婦の間には「働いていないと肩身が狭い」という意識が一時的に広がった。
一方で、相も変わらず就職氷河期世代は置き去りにされた。2015年に専門職も含めた派遣で全職種の上限期間が3年になり、同年は労働契約法が改正されて有期労働契約が5年続くと労働者が希望すれば期間の定めのない「無期労働契約」に転換できるようになった。2005年にできた「3年ルール」と同様、制度は悪用され、派遣は3年で“ポイ捨て”、非正規雇用の全般でも5年で“ポイ捨て”が広がった。
安倍政権で内閣府に就職氷河期世代支援推進室が設置され、2019年に「就職氷河期世代支援プログラム」が策定され、3年間で30万人を正社員化すると掲げたが、国は就職氷河期世代の中心層を2018年時点で35~44歳として(次ページ図)、最も支援が難しい40代後半や50歳を過ぎた層に重点を置かずにいる。そして、支援プログラムがこれまでの施策の焼き直しの域を脱しないことから、就職氷河期世代の絶望は深まった。
就職氷河期世代の非正社員「約600万人」
いったん絶望し、諦めてしまえば、どんな支援があったとしても届きにくくなる。私が就職氷河期の問題を追ってから18年が経つ。16年前のインタビューで丹羽氏が言及した通り、もはや「too late」の状況に陥っているのかもしれない。現在、35~49歳の非正社員は約600万人に膨らんでいる。もはや誰も解決の糸口を掴めないくらい、事態は深刻になる一方だ。
自民党政治の下で、製造業の日雇い派遣が解禁され、労働者派遣は今や全ての職種で期間の上限が3年になった。就職氷河期世代を置き去りにしたまま、業界団体のロビー活動も後押しして外国人労働の拡大が図られた。「女性活躍」は女性に仕事と家事と子育て、介護の両立を押し付けるだけ。「働き方改革」や正社員と非正社員の「同一労働同一賃金」も、実態は伴わない。
就職氷河期を追うなかで、そのライフステージに寄り添い、周産期医療や看護、保育の問題もライフワークになったが、全て構造問題がある。国が作る制度が密接に関わり、政治が現場を疲弊させている。新型コロナウイルスが蔓延するなか、政治の機能不全が鮮明となった。総選挙を前に、これまでを振り返らざるを得ない。
政治家にしがらみがあれば、正しいことが言えなくなる。けれど、この18年の間に分かったことがある。世論が盛り上がれば、政治は正しい方向に動かざるを得なくなるということだ。その世論を作るのが、現場の声であり、現場の声を活字にして伝えるのが私の役割だ。就職氷河期世代の問題を解決するのは困難だろう。しかし、目指すべき道が見えなくならないよう、私は書き続けていきたい。
氷河期世代がこんなにも苦しまされている根因
問題の根が深く支援プログラムでも救えない
岩崎 博充 : 経済ジャーナリスト
著者フォロー
2019/08/02
最近になって、政府が重い腰を上げて取り組み始めたものに「就職氷河期世代」の問題がある。「ロストジェネレーション世代」とも言われるが、2019年現在35~44歳のアラフォー世代の貧困問題と言っていい。
もっと正確に言うと、1993~2004年に学校卒業期を迎えた人である。バブル崩壊後の雇用環境の厳しい時代を余儀なくされ、高校や大学を卒業した後に正社員になれず、非正規社員やフリーターとして、その後の人生を余儀なくされた人が多かった世代の問題だ。
厚生労働省の支援プログラムは功をなすのか
この就職氷河期世代を対象とした支援プログラムが、3年間の限定付きではあるが厚生労働省の集中支援プログラムとしてスタートしている。支援対象は多岐にわたり、少なくとも150万人程度が対象者。3年間の取り組みによって、同世代の正規雇用者を30万人増やすことを目指している。
もっとも、わずか3年の支援プログラムで就職氷河期世代が背負った「負のスパイラル」が断ち切れるとは到底思えない。もっと継続的で長期のスパンに立った構造的改革を実施すべきだ……、という意見も数多い。
全国の自治体が取り組む「ひきこもり対策」もその効果を期待する声は多いものの、成果については疑問の声も多い。
就職氷河期世代とはいったい何だったのか。いまなお、同世代1689万人(2018年)のうち約371万人が現在も正規就労できずに、フリーターやパートの人がいると言われる。推定で61万人いると言われる40~64歳の「中高年ひきこもり」も、この世代の割合が突出しているとされる。
因果関係を立証はできないが、京都アニメーション放火殺人事件を起こしたのは41歳の男だった。最近の凶悪犯罪に、この世代の姿が目についていると感じている人もいるのではないか。世帯別の平均月収を5年前と比較すると、35~44歳の世帯の給与だけが低いというデータもある。「アラフォー・クライシス」とも言われるが、この世代の人々が抱える闇とは何か。彼らを救うために社会はどうすればいいのか。
就職氷河期世代と呼ばれる人々が どんな人生を歩いてきたのかはすでによく知られている。生まれて以降、社会人になるまでは比較的順風満帆で、バブル経済の恩恵を受けて学生時代までは恵まれた人生を歩んだ人が多かった。
ところが、学生から社会人になる際に日本は空前の不況に見舞われる。
氷河期世代が体験した無間地獄
1990年代後半から2000年代前半にかけて、日本経済はどん底とも言えるような状態にあった。1990年代前半に不動産バブルが崩壊し、その後世界的な景気後退期にさしかかり、1997年にはアジア通貨危機が世界を襲う。日本では、山一證券が経営破綻し、北海道拓殖銀行など金融機関の連鎖破綻が起きたときでもある。
さらに、2000年にはアメリカ発のITバブル崩壊が起こる。日本も大きな影響を受け、1990年代後半から2000年代前半に就職活動を行った世代は、厳しい就職氷河期にさらされる。とりわけ2000年前後は、大卒でも2人に1人しか就職できない時代を経験することになる。
同世代の非正規社員は371万人(2018年、総務省統計局、労働力調査基本集計より)で、正規雇用を希望しながら非正規雇用で働いている人は50万人に達する。非労働力人口のうち、家事も通学もしていない無業者も約40万人いる。
こうした現実に、厚生労働省も2018年度から就職氷河期世代を正社員として雇った企業に対する助成制度をスタート。「35歳以上60歳未満で、正規雇用労働者として雇用された期間が1年以下、過去1年間に正規雇用されたことがない人」を正社員として雇った企業に助成金を出すというものだ。
「特定求職者雇用開発助成金(長期不安定雇用者雇用開発コース、2019年4月より安定雇用実現コースに変更)」と呼ばれる制度で、無職や非正規社員を正社員として採用した中小企業に対して、1人当たり第1期30万円(大企業は25万円)、第2期30万円(同)、合計で60万円(同50万円)を1年間支給する制度だ。ハローワークを通して、求職活動することが条件になる。
一方、内閣府がこの6月に発表した文書によると、政府を挙げて3年間の集中支援プログラムを実施。次のような人を支援対象としてざっと100万人を救済するという。
①正規雇用を希望していながら不本位に非正規雇用で働く者(少なくても50万人)
➁就業を希望しながら様々な事情により求職活動をしていない長期無業者
③社会とのつながりを作り、社会参加に向けてより丁寧な支援を必要とする者など
具体的には、「安定就職に向けた支援プログラム」 「就職実現に向けた基盤整備に資するブログラム」「社会参加実現に向けたプログラム」などを立ち上げ、民間企業や市町村などと連携しながら就職氷河期世代の自立を促すとしている。
「40歳前後への職業訓練は無意味」「10年遅い」という批判も多いが、実際にこれまで政府は「自己責任論」を盾に同世代への支援には手を付けてこなかった。しかし、未婚率の高止まりや人口減少の原因の1つであることが明白となり、政府も腰を上げざるをえなくなったというのが真相だ。
ちなみに、この世代が注目されたのは、朝日新聞が今から10年以上前に同世代を「ロストジェネレーション」と名づけて、悪戦苦闘する人々をテーマにキャンペーン報道を行ったことがきっかけだ。
今後の日本の大きな問題になると指摘し、大量退職を迎えていた団塊世代以上に注目すべき問題として取り上げている。2007年の元旦から始まったこのキャンペーン報道は、翌年のリーマンショックと重なって注目された。低い時給で過酷な労働環境を強いられながらも、ネットカフェで泊まり歩き、中には餓死する若者の姿も報道されている。
ロストジェネレーション世代という言葉は、やがて就職氷河期世代と名を変えつつ、当時25~34歳だった若者もいまや年齢を重ねて35~44歳となり、10年前に比べてやや減少したものの、いまなお厳しい生活を余儀なくされている人も少なくない。
10年前に「フリーター」や「ニート」だった世代は、いまも「非正規社員」や「引きこもり」と呼ばれ、いまなお苦しい生活を送っているのは間違いないだろう。氷河期世代の「無間地獄」という呼び方もされる。
40歳で非正規社員として、時給1000円前後で働き続ける独身の男性は「いまだに1度もボーナスを貰ったことがない」「結婚なんて夢のまた夢」「時給は上がっても物価も上がった」と証言する。
なぜ就職氷河期世代は「捨てられた」のか?
就職氷河期の悲惨さはどの程度だったのか。統計データから見ても、その現実はよくわかる。例えば、大卒の「有効求人倍率」の推移を見ると、就職氷河期に入る直前の1991年には1人の求人に対して求職数は1.4倍あった。しかし、その2年後の1993年には1倍を割り込み0.76倍まで下落する。
以後、2006年(1.06倍)と2007年(1.04倍)を除いて、2014年までの約19年間。わが国の有効求人倍率は1倍を下回って推移する。1999年には0.5倍を割込み0.48倍にまで下落。2人で1社の求人を奪い合う状態になる。リーマンショック時には、0.47倍(2009年)にまで下落している。
ちなみに、アベノミクスの開始とほぼ同時に、有効求人倍率は1倍を回復したのは事実だが、これは団塊世代のリタイアと少子化の深刻化によって人手不足が顕著になったほうが大きい。アベノミクスの成果として、有効求人倍率が1倍を超えたと単純に捉えるのは危険だ。
ここで注目したいのは、就職氷河期世代の中でもいまだに非正規雇用を余儀なくされ、最悪ひきこもりになっている原因はどこにあるのかだ。そこには、個々の責任というよりも、日本特有のさまざまな悪しき制度や仕組みが根本的な原因といえる。同世代が陥った無間地獄の原因と本質をピックアップすると、大きく分けて次の5つのポイントが考えられる。
原因その1◆日本特有の「新卒一括採用」
世界でも例を見ない新卒一括採用が、日本企業の強みであった時代はとっくに終わっているが、就職氷河期世代の人々にとつては最悪の結果をもたらした。新卒以外での中途入社が難しく、とりわけ非正規雇用だった人材の中途採用には慎重な企業が多い。2人に1人しか正社員として就職できなかった就職氷河期世代にとって、その後、正社員として雇用される機会を奪われることになった。
新卒一括採用の背景にあるのが、終身雇用制と年功序列だ。とりわけ、氷河期世代以前の好景気時に大量採用された社員があふれている現実は、運よく正社員になれた就職氷河期世代も、企業の中でこの大量採用組に苦しめられることになる。
原因その2◆大手企業の労働組合が会社側に寝返った?
戦後、日本の労働組合は強い力を持っていた。それが、高度経済成長時代を迎えてバブル景気に沸いた頃には、すっかり企業と仲良しコンビになり、バブル崩壊による大リストラ時代には、企業の言うことを素直に聞く傀儡(かいらい)団体に成り下がってしまった。就職氷河期世代が就職難に喘いでいた頃には、既存の正規社員も自己の雇用を守るのに必死となり、新卒が極端に減少していることにも目をつぶった。
企業別労働組合の限界とも言えるが、「産業別労働組合」や「クラフトユニオン(職種別労働組合)」のシステムに転換していれば、こんな事態にはならなかったかもしれない。企業別労働組合からの脱出を目指す政党が現れないのも、就業者の80%を超す「サラリーマン(正規、非正規などを合計)大国・日本」にとっては不幸な話だ。
原因その3◆小泉政権時代の非正規社員の規制大幅緩和
就職氷河期世代が不幸だったのは、2000年代はじめに小泉政権が誕生し、非正規社員の規制を大幅に緩和したことだ。それまで許されなかった製造業での非正規雇用を全面的に緩和し、その影響で大企業は正社員の採用を大幅に抑え、非正規雇用を増やす雇用構造の転換を進めることができた。
就職氷河期世代の人たちも、この規制緩和がなければ新卒採用されなかった人でも、中途から正社員になる道はかなり多かったはずだ。そういう意味でいえば就職氷河期世代の悲劇は、小泉政権時代の規制緩和によってもたらされたとも言える。
労働条件の非常識な劣悪化
原因その4◆企業本位の労働環境社会
就職氷河期世代を苦しめた背景の1つに、非正規社員を直接雇用しないまま長年使い続ける慣行があった。
日本の製造業を支える工場での労働力をはじめとして、コンビニやファミレスといった安価で質の高いサービスを支えてきたのは、就職氷河期世代を中心とする非正規雇用の人たちだ。先進国の中では最低レベルの賃金で、長時間労働を余儀なくされた同世代が、日本経済を底辺で支えてきた、といっても過言ではない。この非正規労働者を守るための手段がほとんどないのが現実だ。
問題は、そうした過酷な非正規社員の現状を横目で見ながら、労働基準監督署などの労務管理当局が怠慢を続けたことだ。加えて、司法も貧困問題に対して厳格な判断を避け続けてきた。
そもそも日本では、海外では常識になっている企業内でのいじめやパワハラに罰則規定がない。経団連などの反対で罰則規定が外されたのだが、検察や司法がもっと労働者の立場に立っていれば、就職氷河期世代の悲劇はもっと少なくて済んだのかもしれない。
さらに、下請け会社や個人を元受け会社から守る「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」の法整備が行われたのも2003年以降のことだ。
こうした法律の不備や労務管理当局の怠慢が、同世代を苦しめている一因でもある。政府と密接な関係のある芸能プロダクションと所属芸人との間に正式な契約書がなくても通用する――。それが日本の労働環境の常識だとしたら、あまりにお粗末だ。
原因その5◆起業、独立に厳しい社会環境
もう1つ原因があるとすれば、正社員になれなかった就職氷河期世代が、起業して自営業になるという道があったにもかかわらず、その道へあまり進めなかった現実がある。日本では、そういったビジネス環境が整っていないためだ。
何の実績もない若者に事業資金を融資してくれる銀行はほとんどないし、連帯保証人の問題もある。政府の開業資金融資制度も、ハードルが高く、あまり現実的ではない。起業家の才能や熱意を評価して、潤沢な起業資金を融資する投資家が多いアメリカとは大きな違いだ。
ただ、最近は「クラウド・ファンディング」など変革の兆しもある。同世代も、日本に閉じこもっていてはいけないのかもしれない。
支援プログラムが役に立たないこれだけの理由
さて、厚生労働省が今年5月に発表した就職氷河期世代への就職支援プランだが、はたして有効なプランと言えるのか。
施策の方向性としては、「相談、教育、訓練から就職まで切れ目のない支援」を行い、ハローワークに専用窓口を設置。キャリアコンサルティング、生活設計面の相談、職業訓練の助言、求人開拓などの各専門担当者のチーム制によるきめ細かな「伴走型支援」を実施するとしている。
ただ、結論から言うと、就職氷河期世代に対する救済プログラムが本当に機能するのかどうかは疑わしいところだ。例えば、「地域若者サポートステーション」と呼ばれる就労サポート窓口が全国に175カ所設置されているが、40歳以上の就職氷河期世代に対する公的支援は全国でわずか十数カ所開設されるだけだ。
通称「サポステ」も、15~39歳のニートやひきこもりを対象にした制度だが、40歳以上のひきこもりは推計で61万人、サポステ効果も限定的と言わざるをえない。
また前述した特定求職者雇用開発助成金も最大60万円が企業に支払われるが、2018年度に給付された金額はわずかだ。その金額はあまりにも少ない。
筆者の個人的な感想だが、企業にお金を出すのではなく、同世代の非正規雇用者に自立支援金といった名目で、直接資金を融資するほうがいいのではないか。そのお金で起業するのもいいし、海外を放浪してくるのもいい。先進国の多くは、大学を卒業してすぐに就職するのではなく、海外で見聞を広げる制度が充実している。
就職氷河期世代にターゲットを絞って救うプログラムもいいが、本質は「貧困問題」と同じだ。最近になって、NHKも取り上げた「外国人技能実習生の奴隷化」問題にしても、結局は就職氷河期世代だけでは対応しきれなくなった人口減少、人手不足の対応策として、海外の留学生がターゲットにされているだけなのかもしれない。
京アニ放火事件のような凶悪犯罪の加害者をネットでは「無敵の人」と呼ぶ。失うものが何ひとつない、無敵状態の人という意味だ。今後、10年が経過して彼らが45歳から54歳になったとき、日本はどうなっているのか。このロストジェネレーション世代が、その時まだ「無敵の人」であるとしたら、その社会はあまりに理不尽だ。
日本の「失われた20年」と構造改革の失敗
1990年代に始まる日本経済の長期停滞は、2002年には終わらず今も続いており、この間の日本経済を「失われた20年」と呼ばれることが多くなってきた。日本の名目GDPで確認すると、1990年から2010年までほぼ500兆円前後で停滞したまま推移している。他の国がGDPを上昇させる中で、日本だけが成長を止めたまま20年が経過している。(図1)国民一人あたりの名目GDPでは、1990年代に世界3位くらいだったものが、2007年19位、2008年23位、2009年19位と大きく順位を落としている。(図2)日本では物価が上昇しないが給料も上がらないという状況が続いており、消費や投資などの内需が増えていない。産業分野でも、かつて世界を席捲していたエレクトロニクス市場で軒並みシェアを落としている。日本市場では日本製品が幅を利かせているが、海外ではLGやサムソンがシェアのトップ。日本製品は一部のお金持ちの趣味のブラ※4ンドになっている。鉄鋼でも、アルセロール・ミッタルが世界一の生産量を誇っており、新日鉄は中国や韓国のメーカーにも抜かれて4位(2009年)となっている。 小泉政権が主導した構造改革は、日本の成長のためには聖域なき構造改革が必要だという主張の下、三位一体の改革、郵政民営化、各種の規制緩和などが行われたものだ。この構造改革について、改革は必要だったが、結果として都市と地方の格差や国民の貧富の差を拡大し格差社会を進めた、といった意見が多い。改革の路線は間違っていないが、影の部分が大きくなってしまった、という論調だ。私はそうではなく構造改革は成長戦略としても失敗したのだと考えている。先に紹介したように、構造改革が始まった2000年以降現在に至るまで、日本の成長力も国際競争力も低下している。「失われた20年」のうち、2000年以降の10年は構造改革の失敗によるものといっても過言ではない。
※4 アルセロール・ミッタル ヨーロッパのアルセロールとインドのミッタル・スチールの経営統合によって、2006年に誕生した世界最大の鉄鋼メーカー。年間粗鋼生産量で世界シェアの約10%を占める。
2007年5月21日
ポリシーウォッチャーの役割
「改革の日々が始まった」-2001年4月26日、それはまるで、日本最大のお祭りのようだった。国民的熱狂、聖域なき構造改革、抵抗勢力とのすさまじい戦闘。小泉内閣という奇跡の内閣が誕生した瞬間を、著者はときめきと興奮をもって振り返る。
本書は、従前の日本政治においては考えられなかった異色のリーダー・小泉総理の下、要職を歴任した竹中平蔵氏の挑戦の記録である。「小泉総理の下、日本は間違いなく変わるだろう。そう思ったからこそ私は、大臣就任を引き受けた。これからその変革の『歴史的瞬間』に立ち会いたいと思う。」という書き出しから始まる著者の大臣日誌に基づきながら、不良債権処理、郵政民営化、経済諮問会議の舞台裏が生々しく語られている。
「改革なくして成長なし」-しがらみを持たない強いリーダー小泉総理は、当選回数や派閥からの人事を一切行わず、金融再生プログラムや郵政民営化といった改革を断行した。この改革の中で、重要な役割を果たしたのが、民間出身の経済学者として専門的見地を政策に活かす役割を与えられ、入閣した竹中大臣であった。抵抗勢力のなりふり構わぬ陰謀や策略に遭いながら、いかにして改革を断行したかが、本書の見所になっている。また、本書は、著者の日誌をベースに書かれているため、さまざまな場面が、せりふや感想とともにリアルに語られており、冒険書を読むような面白さがある。そして、随所に見られる小泉総理のリーダーシップも見逃せない。不良債権処理をめぐり、抵抗勢力にののしられ、辞任を迫られる竹中氏に、当て付けのように金融担当大臣兼務を命じる場面や与党幹部の夕食会で、郵政民営化の「基本方針は絶対変えない。ちゃんと理解しておけ。自民党はとんでもない男を総裁にしたんだ」と、反対を強める党側へ迫力の宣戦布告をする場面などは圧巻である。
さて、よく小泉政権に対して、「劇場型内閣」「骨抜きの政策」だなどと、人気があるが中味のない政権であるかのような批判があったが、本書を読む限り、骨抜きではない改革が実行されたように思える。小泉内閣の改革の成果については議論のあるところだが、少なくとも、日本の経済再生のために、以前から散々問題視されながら放置されていた不良債権処理に着手し、金融再生プログラム(竹中平蔵プラン)を実行、りそな銀行への公的資金注入など、金融改革を断行したことは、評価できるのではないか。
なぜ、今まで散々先送りされてきた金融改革を断行できたのか?なぜ、総選挙を行うほどの抵抗に遭った郵政民営化法案が成立したのか?もちろん、歴史的な国民の支持と小泉総理のリーダーシップがあったことは確かだが、改革を主導した竹中大臣の専門家としての力が大きかったことは間違いない。竹中氏は、「骨太方針」の決定、「工程表」の作成、そして「戦略は細部に宿る」という共通認識のもと、官僚の思うがままに作られていた「政策の制度設計」を大臣自らが詳細に作るという「政策決定プロセス」によって、総理の意思を貫く、政治主導型の改革を実現していく。特に、制度設計は、従来、官僚「霞ヶ関文学」の専売特許であり、その知恵は官僚に独占されていた。竹中氏は、30年間「政策」を勉強してきた「政策研究者」として、政策の重要性を理解し、政策の骨組み、つまり法律の条文や施行後の運用ルールなどを詳細に検討。抵抗や妨害、骨抜きにされることを予測し、常に二手三手先を読みながら作戦を練り、抵抗勢力との合意形成に挑む。そして、譲れないところは妥協せず、打開点を探る戦略家の一面も見せる。「普通のこと」がなかなか実現できない日本において、実行力のある改革を断行するポイントは、この「政策」「政策決定プロセス」をいかにうまくやるかにあったようだ。
著者自身は、自らの大臣経験を振り返って「昆虫学者が昆虫になったようなものだ」と語っている。小泉総理の熱意に共感して、自分が研究していた対象の世界に足を踏み入れ、自らが研究の客体となったわけである。自らがプレーヤーとして、官僚の無謬性と戦い、業界・政治家・官僚の「鉄のトライアングル」へ挑戦し、マスコミや学者から激しいバッシングを受け、戸惑い、悩み、立ち向かっていく。この得難い体験を通して、「政策は難しい」ことを実感する。また、「優れた植物学者が、即優れた庭師である保証はなにもない」のと同じように「経済学や政治学は間違いなく政策のために必要ではあるが、政策の専門家と経済学者、政治学者は同じではない」と説明する。そして、評論や絵空事を言う学者ではなく、実務的な知恵と将来的なシナリオを描ける「政策専門家=ポリシーウォッチャー」が必要であると主張する。
ポリシーウォッチャーの役割は、政策の調査研究、分析評価、監視、提言を行うことと情報発信を行うことである。特に情報発信を通して正しい世論を形成することで、「よく知らされた国民」(Well informed public)を生み出すと著者は言う。情報は溢れているが、スキャンダルやゴシップネタばかりで本当に有益な情報(政策論議や政策分析)となると極端に少ないというのが現状ではないだろうか。小泉政権を通して、また最近の政治からも、世論の力、国民の支持の重要性が注目されている。国民が適切な判断を行うことで、良い政策が生まれ、さらに政策が実行されているかを評価監視することで、政策がより良い方向に向かうという好循環が生まれるというわけである。
「政策は難しい」という難問にどう立ち向かうのか。著者は、「政府の中核で政策を実行した経験を、政策専門家の育成に役立て、民主主義のインフラとして、政策専門家が民間部門から政府の政策をしっかりウォッチし、国民に伝えるという機能を果たしていきたい」と決意を語っている。ポリシーウォッチャーを通した「民主主義による世論の後押し、政治主導の構造改革、力強い日本」の実現。竹中氏の挑戦は、まだまだ続きそうである。
2006年09月20日
小泉構造改革が残したもの
森重 透
1.「いざなぎ超え」とは言うけれど
マクロ経済は、長期にわたったデフレ局面からの脱却を視界に入れつつ、足もとなお拡大を続けている。2002年2月から始まった今回の景気回復は、すでにこの5月に「平成バブル景気」を抜き去り、11月には「いざなぎ景気」(1965~70年、57ヶ月)を超え、戦後最長となりそうな勢いだ。
しかし、実質GDPの伸びで見た景気拡張期間はなるほど長かったかもしれないが、国民一人ひとりの生活実感から見れば、まさに「実感なき景気回復」ではなかっただろうか。そして、それはなぜかを考えれば、今回の回復局面の特徴が明らかになろう。
まず、息の長い回復ではあるが低いレベルの成長だったことだ。「いざなぎ」は年平均成長率10%超、「平成」は5%程度だったが、今回は2%強と「平成」の半分にも及ばないレベルである。成長率と拡張期間の積和でこの間の実質GDPの伸びを見ても、「いざなぎ」当時は約1.7倍であるのに比べ、今回は1.1倍程度に過ぎず、さらに名目GDPの伸びで見れば、その差は2倍以上にも拡がる。横綱と前頭筆頭ぐらいの差はあるのではないか。とくに、緩やかなデフレ下の回復のため名目値がほとんど伸びなかったことは、実感の乏しさをより強めたはずである。
二番目の特徴は、企業部門と家計部門の所得状況の違いだ。「経済財政白書」(7月)には、「企業部門の改善によって家計にも好影響が及ぶ好循環がみられる」趣旨が盛り込まれているが、雇用環境には目に見える改善があるとはいえ、賃金・可処分所得関係の統計では、むしろ家計の疲弊ぶりが顕著であり、4年以上も続いているのに景気回復の恩恵は家計・個人にはほとんど及んでいない、と言ってよい。企業部門から家計部門への波及(トリクル・ダウン)の遅れは、企業が業績好調にもかかわらず、賃上げ幅を低く抑え続けているからである。今回の景気回復は、大企業の資本の論理、すなわち、リストラ、非正規雇用の拡大等による賃金コスト削減をバネにもたらされた側面が大きいが、それがまだ続いているということだ。
そのほかの特徴としては、米国経済の好調や中国特需などに支えられた外需主導、デジタル家電ブーム等、一部の大企業・製造業に偏った回復であったことなどから、多くの中小企業や非製造業への波及が遅れていることも挙げられる。また、地域間で景気回復のテンポや景況感に大きな格差があり、これがなかなか縮まらないことも、全体的に景気回復を身近に感じられない要因の一つだろう。
2.二極化・分断化の進行
このように、マクロ面で見れば、実感が乏しいとはいえ息の長い景気回復が実現したことは事実である。しかし、この回復が、間もなく終結を迎えようとする小泉内閣の構造改革の取組みによってもたらされたか、ということになると疑問符が付く。「構造改革なくして回復(成長)なし」、「官から民へ」、「中央から地方へ」を標榜した構造改革路線が、スローガン通りの実行力を伴ったものでなく、今回の景気回復とは無関係であることは、すでに本コラムでも何度か指摘した。また今年の「経済財政白書」(7月)も、企業の適応努力こそが日本経済回復の主役と正当に位置づけているし、多くの識者の見方もこれに沿うものが圧倒的に多い。
むしろそのことよりも、この小泉純一郎政権下の経済運営によって、構造的には深刻な問題が発生した。経済社会の二極化・分断化の進行、社会生活基盤の劣化、という由々しき問題である。下掲グラフは年齢階級別完全失業率だが、15~24歳の若年層の失業率・学卒未就職率は、この間一段と上昇し、高止まりしていると言ってよい状況である。失業こそは、一個人を社会的・経済的弱者に転落させるもので、とくに若年層で定職に就かない者がなお多く存在するという現実は、これからの日本の国力や競争力、社会保障システムへの悪影響を考えると憂慮させるものがある。
さらに、パート、アルバイト、派遣社員など「非正規雇用者」は、すでに雇用者数の約3人に1人となった。ここでも若年層(15~34歳)の雇用情勢は厳しく、失業の長期化、フリーターやニートの増加、そしてフリーター経験をプラスに評価している企業がほとんどないことから、彼らが中高年になっても非正規雇用者にとどまってしまう懸念がある。こうなると、4対1とも言われる正社員との給与格差が固定化されるとともに、累積的に所得格差が拡がり、生活基盤の劣化、ひいては非婚・少子化などの様々な問題を助長する恐れがあるのだ。過重な労働実態、過労による労災件数の増大、ワーキングプアの増加、うつ病、突然死など、今日、雇用の劣化あるいは崩壊とも呼べる事例は枚挙にいとまがない。
このような状況も反映してか、7月に発表されたOECDの「対日経済審査報告書」によれば、先進30カ国の相対的貧困率(平均値に比べて所得が半分未満の相対的貧困層の割合)で、日本は米国(13.7%)に次ぐ二番目の高さ(13.5%)だったそうだ。そして、労働市場の二極化傾向の固定化の恐れを警告され、格差是正の具体策として、非正社員への社会保険の適用などを指摘されているのである。
このほかにも、大企業と中小企業、都会と地方、高齢層と若年層、官と民等々・・・規模・地域・年齢・官民間に存在する諸々の二極分化(格差の拡大と固定化)の問題を真摯にとらえ、これを是正しながら持続的成長を模索していくというような、「徳のある経済政策」は、小泉政権下ではついにお目にかかれなかったと言ってよい。
3.何が欠けていたのか
「聖域なき構造改革」という看板を掲げた小泉構造改革路線は、約5年半に及んだ小泉政権のバックボーンであったはずなのに、結局それは、「小泉劇場」の主役・小泉純一郎が大見えを切るときの小道具に過ぎなかったようだ。
新規国債発行30兆円枠の公約は、「この程度の約束を守れなかったというのは大したことではない」と言って、簡単に破られてしまった。公的年金改革を審議する年金国会での、「人生いろいろ」発言に見られるような、おちゃらかし発言。はぐらかしや、レトリック依存型の国会答弁も多く見られた。地方の景気にも目配りすべきではないかとの記者の問いに、小泉首相は「官から民への流れは変わらない。政府が口出しすべきではない」と答えたそうだ。道路公団の「民営化」は、結局、妥協の産物に終わった。そして、改革の「本丸」と意気込んだ「郵政民営化」は、その意味や効果が不鮮明なまま、分社化を伴う株式会社化で行き暮れようとしている。結局、高い人気に支えられ、連日劇場は満員御礼だったが、バックボーンは最後まで「小道具」で終わった。
「改革なくして景気回復なし」の名の下に、実体的な景気対策には関心が薄く、かと言って、公的セクターの改革、すなわち、責任ある社会インフラの構築と質の高い公共サービスの供給という、「民」が果たせない「官」の固有の役割というものを、いかに実効ある形で遂行していくかといった制度問題を、徹底的に真摯に議論する風でもない。詰めた議論よりは、歯切れの良い「ワン・フレーズ」で「改革」をくさびとして使い、多くの「抵抗勢力」を放逐しつつ人気を得ていくという手法は、まさに独壇場と言えるものだった。
しかし、「改革の本丸」であるべき財政再建問題と、これに密接にからむ社会保障制度と税制のあり方に関する真摯かつ周到な議論と実践を抜きにしては、「経世済民」を託された責任ある政治家としての本務は果たせないのではないか。「ノブレス・オブリージュ」とは、財産、権力、社会的地位には責任が伴うことを言う。小泉首相に限らず、政治家全員がこのことを心に銘じるべきだろう。
【小泉純一郎②】聖域なき構造改革の功罪
小泉純一郎政権は「聖域なき構造改革」を打ち出しているが、この実現可能性について、マーケットは非常に大きな不信感をもっている。
■ 矛盾だらけの経済政策を繰り返すな
なぜ不信感をもっているのか。その理由は、日本がまた、いつもと同じような失敗を繰り返すのではないか、という懸念が拭い去れないことにある。日本はいつも、過去になぜ失敗したのかという事後的な点検が行われないままに、次の政策を展開しようとする。そして、いつも矛盾
ばかりの政策を展開する。つまり「こんなことをやります」と言っておきながら、実はそれとは違うことをやってきた。その典型的な例がペイオフの延期だ。今回の「骨太の方針」のなかで、そうした懸念をいちばん強く感じたのは不良債権問題に関する部分だった。まずは、それを中心に話を進めよう。
ばかりの政策を展開する。つまり「こんなことをやります」と言っておきながら、実はそれとは違うことをやってきた。その典型的な例がペイオフの延期だ。今回の「骨太の方針」のなかで、そうした懸念をいちばん強く感じたのは不良債権問題に関する部分だった。まずは、それを中心に話を進めよう。
「骨太の方針」、すなわち経済財政諮問会議の基本方針は、不良債権処理に関しては、2001年4月6日に経済対策閣僚会議で決定された緊急経済対策の考え方を継承している。緊急経済対策には、問題の本質をついた、さまざまないい意見が書かれているが、その大きな目玉は、やはり不良債権処理が最大の課題である、というものだった。
ちなみに、それより少し前の3月19日に日銀は政策決定会合で「通常では行われないような、思い切った金融緩和に踏み切る」ことを決定しているが、その議事録のなかにも、不良債権問題の解決が急務であるという趣旨の文章が入っている。
こうした流れからいくと、4月6日の時点での政策の結論は、やはり不良債権処理が最重要課題だ、というものだったといえる。
最近、不良債権を「2~3年以内に処理する」という言葉の意味が議論されないまま、独り歩きしている感があるが、緊急経済対策のなかには、主要行について、「破綻懸念先以下の債権に区分されているものについては、原則として2営業年度以内にオフバランス化につながる措置を講ずる」、それから、新規発生分については「原則として3営業年度以内に......措置を講ずる」と書かれている。
これは非常に重要なポイントだ。なぜなら、この「措置を講ずる」という表現は、金融監督庁のマニュアル、あるいは旧大蔵省の行政に従ってやってきた過去の金融再編行政では、不良債権は解決しない。今までのやり方を白紙に戻して、2~3年以内に不良債権をかたづけよう、という強い意思表明の表れだからだ。
今回の基本方針も、この方針に沿って、「不良債権問題を2~3年以内に解決することを目指す」、「経済再生の第一歩として、不良債権の処理を急ぐべきである」とはっきり書いてある。多くの人はこれを読んで、正しい方向に動いていると思うだろう。ところが、である。今回の基本方針には、不良債権の最終処理は「金融機関の自主的な判断で進められる」というくだりが入っている。 これでは、全く話が違ってしまっている。4月の緊急経済対策で、「過去の行政のもとで、金融機関が自主的に問題に取り組んできたけれども、そのやり方では解決しない。政府が主導権をとって、2~3年以内に解決させる」という強い意思表明をしたにもかかわらず、ここでまた、「自主的な判断で進められる」ということでは、議論するまでもなく、問題解決にはならないだろう。
ちなみに、不良債権問題の裏側にある借り手企業/産業については、私的整理のためのガイドラインを「関係者間で早急に取りまとめることが期待される」と書いてある。
もちろん日本の場合、「期待される」、あるいは「自主的な判断で進められる」といった場合、それは国が強制的にやるといっているのと同じだという解釈もないわけでもないが、それは一昔前の行政のあり方を反映した解釈だ。つまりそれは、不透明な、玉虫色的なやり方にもなっているということだ。
■ さまざまな数字が独り歩きをしている
それに、緊急経済対策にも、踏み込み不足だった点がある。ひとつは、対象を全預金取扱金融機関ではなく、主要行に限定していたこと。もうひとつは破綻懸念先以下の不良債権に絞って話をしていたということだ。
詳細は省くが、これでは、ペイオフ延期などの過去の政策との整合性がないばかりか(ペイオフ延期のときは、主要行は大丈夫だが、信金や信組などは検査不十分で不安だから、という説明がなされた)、不良債権問題を全体的に把握することはできない。いうまでもなく、マーケットが非常に神経質に注意を払っているのは、不良債権の全体の大きさだ。ところが、上述したように、限定した見方をとっているために、いろいろな数字が独り歩きをしてしまっている。
例えば、一時期新聞を賑わせた12兆~13兆円という数字は、主要行の破綻懸念先以下のものを指している。しかし全銀行ベースの問題債権は64兆円で、全預金取扱金融機関ベースでは81兆円くらいあるとされている。また最近では、151兆円という数字が独り歩きをしている。これは民主党が金融庁から取り寄せた数字で、要注意債権以下の債権をもっている借入先の全借入金を示している。
われわれプロでも、これらの数字の使い方にはものすごく苦労している。この間、民主党の鳩山氏が「150兆円という数字をどう思うか、大手行の資産査定を厳格にやり直すべきだ」という趣旨の発言をしたところ、首相は「元利払いや貸出条件に問題がなく、単に注意が必要な債権は100兆円ある」と答えた。この発言は、要管理債権以下の不良債権以外の要注意債権が100兆円ある、ということだが、公表ベースでは、こういう数字は出てこない。一国の総理大臣が、国会でこのような答弁をしていることからもわかるように、問題の大きさがどれくらいであるのか誰にもわからず、マーケットは政府に対して依然として不信感をもっているのである。
■ 危機対応の制度的枠組みが不在
マーケットが不信感をもっている第2の理由として、金融再編の枠組みが不在だということが指摘できる。2001年1月には行革の一角として金融再生委員会が廃止された。金融再生委員会は、金融問題を解決するために特別につくられた組織だったにもかかわらず、その仕事が終わる前に廃止されてしまった。日野正晴前長官は退官のインタビューで(『日本経済新聞』2001年2月2日)、「本当はペイオフ1年延期時に、それと連動して金融再生委員会や再生法、健全化法も延長すべきだったが、議員立法なのでこうなってしまった」と述べている。筆者も全く同感である。3月末には、資本増強の枠組みも期限切れとなってしまった。
そしてその6日後に政府は公式見解として(緊急経済対策)、不良債権が日本経済のいちばん大きな問題だ、この問題に集中的に取り組む、ということを表明した。1998年にも同じ議論があり、問題解決のために60兆円のパッケージと金融再生委員会をつくった。その枠組みを廃止した途端に、改めて問題の重要性、枠組みの必要性が認められるというのは、酷評すれば、先進国の経済政策としては大問題だ。少なくとも説明責任というものがある。そうしたことを議論しないで、ポッポッと次の政策が出てくるというのはいかがなものか。
もっとも、枠組みがないというのは多少言いすぎで、実は金融危機対応枠組みというものが4月1日からスタートしている。それは資本増強、国有化、(ペイオフコスト以上の)預金者保護という3つの機能を持ち備えている。
ただ問題は、危機がなければこの枠組みが使えないということだ。これに対し98年の枠組みは、危機の産物としてできたもので、危機がなくても、危機が起こらないように使うことができた。
こうして、不良債権問題の重要性に対する認識と、その問題を解決するために用いる制度的枠組みとの間に、大きな空白ができている。そうした空白があるからこそ、いろいろな方針や意見が錯綜しているといえる。つまり枠組みがないから、金融機関が自主的判断ベースでやるしかないということになっている。だが、金融機関の自主的判断ベースではこの問題は解決されないことは目に見えている。自主的ベースでできるような話であれば、とっくの昔に解決しているはずだからだ。
■「財政再建」重視の危うさ
第3に、小泉首相が財政再建を最重要視しているのではないか、ということだ。首相の所信表明演説を見ると、「不良債権処理や資本市場の構造改革を重視する政策へと舵取りを行う」とし、1に不良債権問題の解決、2に規制緩和、3に財政再建を行う、と述べている。筆者はこのポリシーミックスと順序づけにはおおむね賛成だが、小泉内閣が実際にやっていること、あるいは発信しているメッセージを見ていると、不良債権処理がかなり後退している感じを受ける。特に、上述したように、「措置を講ずる」が「自主的判断で進められる」というように後退しているのが気になる。むしろ第3の財政再建をアジェンダの上位にしようとしているらしい。
例えばここ2カ月間の議論をみると、田中真紀子氏が多くの話題を提供してきたが、それはともかく、経済面では新規国債発行を30兆円以内に抑制するなど、財政再建の話題でもちきりだった。だが経済の現状を考えると、財政再建に今踏み込むことは非常に厳しい緊縮財政になりかねない。すると不良債権問題の先送りと財政再建の優先という、橋本政権のときと全く同じポリシーミックスとなってしまう。
こうして、橋本、小渕、森の各政権から得られたはずの教訓が生かされず、また元に戻ろうとしており、"不思議の国のアリス"のような経済政策になっている。
■ 構造改革断行の2つの選択肢
以上、小泉内閣の経済政策・構造改革の基本方針について検討を加えてきたが、これらの一連の議論を見ていて、問題だと感じるのは、政府がどちらの方向に進もうとしているのか、その方向性が見えないということだ。
改革を断行するに当たり、政府には大きく分けて2つの選択肢がある。ひとつは期限を区切ったうえで、自ら主導権を発揮して改革を進めることだ。この場合は、金融再生に向けた新しい枠組みづくりと、危機を未然に防ぐための公的資金の投入が必要になる。またマーケット・メカニズムを最大限活用し、新しいマーケットが育成されるようなやり方をとる必要がある。
もうひとつは、市場に任せるという、まさにハード・ランディング的な解決策だ。この場合は、ペイオフの早期実施と、金融危機対応枠組みを極力使わないという覚悟、それに労働市場、小口預金者保護などのさまざまなセーフティ・ネットが必要になる。加えて、緩和的なマクロ政策と、規制緩和などの、経済体質を強化するためのミクロ政策を次々と実施しなくてはならない。
後述するように、筆者は前者の政策を取るべきだと思っているが、今のところ、小泉政権がどちらの方向に進もうとしているのかが見えない。むしろ、このどちらでもなく、中間の道を歩んでいるようにも見えるのである。すなわち、危機が起きると政府が動き、その際、マーケットを阻止するような政策を取るという、これまでと同じ過ちにはまってしまう可能性がある。
公的資金の投入や銀行保有株式取得機構の設置、それに貸し渋り対策などで、政府は銀行に対してあらゆるところで関与を強めている。これでは、マーケットに任せるという2つ目の選択肢は取りえない。こうした状況では真の意味でのマーケット・ベースということはできない。それにもかかわらず「金融機関の自主的な判断で進められる」という表現を用いたりするので、混乱が生じることになるのである。
国が関与することにさまざまな弊害があるのは十分承知しているが、筆者は、ここまで国が関与を強めている以上、国が主導権を握り、期限を区切って市場を生かす形で改革を断行したほうがいいと考えている。ところが、では主導権を発揮しているかといえば、それも中途半端な状態にある。
実は私は財政再建の信者だが、一回限りの措置として、金融問題の解決のために公的資金を30兆円入れるということを断行すれば、日銀はそれを支援するだろうし、それが2年後のマーケットの発展につながるということであれば、マーケットもそれを評価するのではないか。だが、小泉首相は財政再建という目標があるために、公的資金を投入するという流れをつくれないでいる。こうしたことから、マーケットから見ると、財政再建を優先していることが、実は不良債権を断固として処理するという腹が固まっていない、と見えてしまうのである。
■今は財政再建を打ち出すな
では、具体的に小泉首相はどういったアクションを起こすべきか。
まず、今の局面では財政再建を打ち出さないことが必要だ。今財政再建を打ち出すと、それはものすごい緊縮財政になってしまう。
仮に出すにしても、出し方を工夫すべきだ。実は財政構造改革と財政再建は違う。財政構造改革というのは、財投改革や公的金融機関の民営化、あるいは効率的な税制システムの構築などのミクロ的な改革だ。これは今すぐにでも実行できるし、これをすぐに行うことには筆者も大賛成である。
一方で、今の経済局面のなかで、どれだけの財政出動が必要なのかという問題がある。これが財政再建の問題だ。日本の場合は、この2つの概念がいつもこんがらがってしまっている。前総理の橋本氏も、財政再建を実現したかったために財政出動を締めたが、本当の財政再建は、経済を回復させなければ成り立たない。そこで、では経済を本当に回復させるには何が必要なのか、という議論が、財政再建の中枢にくるはずだ。
そこで、不良債権がいちばんのネックであるという判断なら、それをやるべきだし、非効率的な財政の仕組みの問題であるなら、それを見直す必要がある。そのなかで必要に応じて財政出動をすることもありうべき選択肢だろう。預金者保護と不良債権処理を同時に達成するためには、例えば30兆円というコストがかかることもあるかもしれない。この場合は、短期的には財政再建はできなかったということになる。
つまり、すべての政策目標、特に矛盾しあっているいくつかの政策を同時に達成することはできない。それなのに、あれもやる、これもやると主張するのは、部分的な発想でしかない。まず不良債権処理に重点を置くべきである。
財政再建は確かに重要な課題ではあるが、それが本当に緊急の課題がどうかを考えると、実はそうでもない。ひとつは、日本のマクロ的な現状をみると、民間部門の黒字を政府が吸収しているという面がある。そうなると、問題は個人の将来不安が解消されていないから、また規制緩和が不十分で日本企業の投資プロジェクトに問題があるから、あるいは金融システムが十分に機能していないから、民間部門が活性化されない、ということになる。
この問題を解決するには、IT関連を中心に規制緩和を実行することだ。そうすれば、さまざまな形で、新しい需要と新しい投資機会が生まれてくる。そして結果として、税収が増えて、政府の赤字も減っていく。
もうひとつは、国債の利回りだ。これは現在1.2%程度であり、財政再建をやらなければ日本は破綻する、というメッセージをマーケットは発信してはいない。しかし小泉政権は、あたかもそうしたメッセージが発せられているかのように動いている。橋本政権時の増税と同じく、小泉政権でもプライマリーバランスの赤字を支出削減で抑えようとしているが、それは因果関係を間違えている。まず解決すべきは不良債権問題である。
■戦略的にマーケットを活用せよ
そこで、不良債権処理を進めることを考えるとき、ぜひ指摘しておきたいことは、戦略的に、マーケット・メカニズムを最大限に生かすことが重要だということだ。これは、政府が主導権を取るという方向とは、一見矛盾しているように見えるがそうではない。例えば、しばしば引き合いに出されるアメリカのRTC(整理信託公社)は、預金の全額保護をせずに、破綻懸念の金融機関をつぶして、預金保険機構でカバーされていない人たちに債権カットに応じさせた。同時に、RTCは資産を取って、資産価値と預金保険機構でカバーされている額との差額を埋めた。これは預金者保護の鉄則です。そのうえで、受け取った資産をすぐさま売却した。
RTCがそうしたように、資産を売却すると、非常に大きなマーケットが育成される。現在、非常に大きな規模になっているCDO(Convertible Debt Obligations)やABS(資産担保証券)は、実はRTCが登場するまではなかった。これが、マーケット・メカニズムを最大限生かすということの意味だ。銀行の国有化や買取機構、それにペイオフの延期といったやり方は、やはり問題だろう。
ただ、日本の現状を見ると、残念ながら現に政府はそれをしていないし、今までの経験から見ても、ほとんどやる意思とやる能力がなさそうである。
今後の政策の展開次第では、金融は、おかしなことをやる可能性がある。政府の要人はいろいろなところで、低成長には甘んじなければならないけれども、マイナス成長はだめだと発言しだしている。一方で財政再建論者が趨勢を握ったとすれば、やはり金融危機が起こる。そして財政再建プラス金融危機イコールマイナス成長となったとき、マーケット・ベースで進まないような手を考え出してくる可能性がある。ペイオフ延期はないにしても、危機対応枠組みを使って実質的な全額保護の延長をやりかねないなどの危険性が残っているのである。
日本人の間では、金融危機が起きたときに危機を止めるのは政府の要件だから、それも仕方がない、という考え方があるようだが、それは違う。そもそも不良債権があるから危機が起きるのであって、危機を封じ込めたければ、そうした全面保護のような形で政府が対応するのではなく、まず政府が主導権を取って不良債権を処理すべきなのである。そうでないと、金融危機対応枠組みがまた悪用されることになってしまう。
この論文で検討してきたようなポリシーミックスを実現するには、本来なら経済財政諮問会議のようなところで総合的に調整する必要がある。その点では、竹中氏も精いっぱい努力しておられるようだが、まだ理想的な形には至っていないと思っている。現在の小泉政権には、政策を立案する陣容はあっても、それを実行に移していくというシステムがない。それが小泉政権のアキレス腱ともなっている。
ここまで小泉政権に対して、批判的な検討を加えてきたが、小泉政権は、構造改革を断行すると述べている内閣であり、その意味では期待もしている。これまでと同じような愚を犯すことなく、構造改革に踏み込んでいってほしいと思っている。それが日本経済を停滞から脱却させる道である。〈了〉
〝異例の3期目〟突入で習主席「一帯一路」への熱意低下 外交・国防・貿易で目立った3つの変化
2022年11/9(水)
【習独裁の死角】
「異例の3期目」に突入した習近平総書記(国家主席)にとって、「外交」「国防」「貿易」で目立った変化は3つある。
第1に、「戦狼外交」の修正をしながらも、このことは沈黙している。
中国歴代王朝で外交部は軽い存在でしかなく、外交畑の人間が活躍できる場面は限られていた。しかし、実質的には「中国外交の強硬路線修正」が顕著となった。国際的孤立を恐れる証拠である。ロシアのウラジーミル・プーチン大統領の孤独が教訓となった。
王毅外相が、習氏の覚えめでたく「戦狼外交」で世界に名を売って政治局員に出世したものの、戦狼路線をトーンダウンさせた。
第2が、巨大経済圏構想「一帯一路」への熱意を無くしたことだ。「マスク外交」の効果なく全世界から中国は嫌われ、「一帯一路は債務の罠(わな)」と評判は芳しくない。習氏自身も「一帯一路」を言及しなくなった。
この点には注目しておくべきだ。
米国の対中姿勢の大転換を受け、中国が強硬路線を続けて対決姿勢を取ることにマイナスを見いだしたのだ。
安倍晋三元首相の暗殺に「万歳」と祝した中華思想のねじ曲がった性根、腐った心は治癒の見込みがないが、「穏健」を擬装する演技には舌を巻かされる。
第3に、中国とロシアが主導する上海協力機構(SCO)が求心力を失ったことだ。
加盟国に、イラン、トルコ、インドが加わり、求心性が低下し、「中国外交の荷物」となった。かといって、中国がTPP(環太平洋戦略的経済連携協定)に対抗した、地域的な包括的経済連携(RCEP)協定も成果は芳しくない。高関税、コロナ、ウイグル問題でサプライチェーン寸断。孔子学院廃校、スパイ摘発が続き明るい展望がない。
メッキはことごとく剥げ落ちた。
中国3隻目の空母「福建」が進水したが、甲板は空、レーダー設備なしの「晴れ姿」。搭載される戦闘機はステルス性を高め、ミサイル充実の予定とか。宇宙では一部技術で米国を凌駕(りょうが)したが総合力で劣る。
しかも、中国人民解放軍は中越戦争以後、実に半世紀、実戦経験がないのだ。本当に戦えるのか?
米国は宇宙軍を創設し、次のデジタル戦争に備える。ハッカーもやられっ放しの状態から、米国は中国の手口をマスターし、先制防御型攻撃へ移行する。つまり米国が戦争直前にハッカーを仕掛けて、中国軍の指揮系統を無効にする作戦の準備に入ったとみられる。 =おわり
■宮崎正弘(みやざき・まさひろ) 評論家、ジャーナリスト。1946年、金沢市生まれ。早大中退。「日本学生新聞」編集長、貿易会社社長を経て、論壇へ。国際政治、経済の舞台裏を独自の情報で解析する評論やルポルタージュに定評があり、同時に中国ウォッチャーの第一人者として健筆を振るう。著書に『日本の保守』(ビジネス社)、『歪められた日本史』(宝島社新書) 、『ウクライナ危機後に中国とロシアは破局を迎える』(宝島社)など多数。
緊迫のウクライナ情勢…ロシアへの「中立的立場」を崩さぬ中国が国際社会に及ぼす影響
金森 俊樹2022.10.27
「ロシア寄りの中国の苦境」…欧米の報道に中国反発
2022年9月、ウクライナ側が一部領土をロシアから奪還したとの戦況が伝えられた際、欧米が「このニュースで、ロシア寄りの中国は引くに引けなくなった」としたことに対し、中国官製メディアは「中国はそもそも一度も虎にはまたがっておらず、したがって、どうして“騎虎難下”、またがった虎から降りることは難しい→引くに引けない、ということがあろうか」と反論している※。
※ 「中国从未骑在俄乌冲突的“虎背”上(中国は一度もロシア・ウクライナ衝突の“虎の背中”に乗ったことはない」環球時報社評 2022年9月14日
中国国営メディア新華社電によると、6月15日、習近平国家主席69歳の誕生日におこなわれた、ロシアのウクライナ侵攻後2回目となる習・プーチン電話首脳会談で、習氏は「中国は一貫して歴史的経緯と是々非々(是非曲直)に基づき、独立自主の判断をしている」「主権や安全保障などの核心的利益と重大関心(関切)問題について、ロシアとの相互支持を続けたい」と発言。
「歴史的経緯」がウクライナはかつて旧ソ連の一部であったこと、「是非曲直」の「非」「曲」が中国やロシアが言うところのNATOの東方拡大を指しており、習発言はロシア寄りの姿勢を示したものと広く理解された。
会談はプーチン氏が中国から十分な支持がないと不満を漏らしているとの情報があるなかで、習氏がアレンジしたと憶測されたものだった。他方、9月上海協力機構(SCO)首脳会議の際におこなわれた、ロシアの侵攻後初めての対面による習・プーチン首脳会談では、ウクライナ問題を巡るプーチン氏と習氏の温度差が際立った。
本連載では、各種データで中ロ経済関係の現状を把握したうえで、中国内の専門家やメディアが本問題をどのようにみているかを中心に関連文献をサーベイし、ウクライナ問題が中ロ関係を始め今後の国際社会にいかなる影響をもたらすことになるのか、いくつかの論点を提起する。
1.中ロ経済貿易関係
2.中国・ウクライナ関係、一帯一路への影響
3.中ロ互いにとっての重要性、利用し合う実務的関係
4.中国のエネルギーと食糧の安全保障
5.国際社会の多極化・共存、経済フローバル化の弱化―中国の懸念
6.地域別の動向―中国内の専門家はどうみているのか
7.金融グローバル化にも逆風?
8.中国への対応
第1回目の本記事では、1の「中ロ経済貿易関係」について解説する。
中国とロシア、近年の経済貿易関係の状況
分析の前提として、まず中国とロシアの経済貿易関係が近年どのような状況にあるのかを把握しておく必要がある。
◆輸出入構造
中国のロシアからの主要輸入品は原油などエネルギー・鉱物資源、主要輸出品は機械電子品、その他様々な消費財である。
2021年対ロ輸出676億ドル、20年506億ドルから34%の大幅増で、機械電子品が4割以上を占めた。輸入は793億ドルで、こちらも2020年572億ドルから39%の大幅増だった。ロシアは世界市場においてエネルギー輸出大国で、原油、天然ガス、石炭の各々について、生産では世界3位、2位、6位、輸出では2位、1位、3位だが、中ロ貿易でも、中国の対ロ輸入の64%を占める509.6億ドルがエネルギー、さらにその50%は原油で、エネルギー貿易が中ロ経済関係の鍵になっている。
中国の対ロ貿易シェアは、輸出が2%前後で横ばいであるのに対し、輸入は上昇傾向にある。
◆直接投資・証券投資
中ロ間の直接投資(FDI)は貿易に比べると、あまり活発でない。中国の対外FDIの主な投資先は2020年末残高2.58兆ドルのうち、香港56%、ケイマン18%、バージン諸島6%で8割を占め(ただしこれら、特に香港の数値には、中国本土に戻って外資企業として優遇を受けるいわゆる迂回投資がかなり含まれている)、その他米国3%、シンガポール2%など(中国商務部対外直接統計公報)。
ロシアへのFDIはフローベースで2015年29.6億ドルとピークを打った後、20年5.7億ドル、残高では20年末実績121億ドル、21年末は128億ドル程度だった見込みで、対外FDI全体の0.4~0.5%に止まる。地域的にはロシア極東地域への投資が多く、同地域への外国からの投資の90%以上は中国という。
投資分野は同地域を中心に、エネルギー関係、農林牧畜・漁業分野が主だが、自動車、家電、食品加工にも中国の資金が入っており、また投資形態は従来のグリーンフィールド投資か
ら、買収や基金設立に移りつつある(2022年9月7日付環球時報)。
ら、買収や基金設立に移りつつある(2022年9月7日付環球時報)。
他方、ロシアの対中FDIは微少のため、中国商務部外資統計では「その他」の項目に含まれ、具体的数値は明らかでない。
◆2022年に入ってからの動向
2022年1~9月の中ロ貿易は1361億ドル、前年比32.5%増。特に輸入が838億ドル、51.6%増で、輸入全体に占めるシェアも4%に上昇。他方、輸出は第二四半期大きく落ち込んだ影響で(前年同期比▼17.4%)、522億ドル、10.3%増に止まっている。
中国官製メディアは、ウクライナ情勢にもかかわらず、対ロ貿易は順調であると強調しているが、中国企業が欧米の2次制裁を受けることを懸念して、対ロ輸出を控えた可能性があり、また中国は貿易を通じてロシアを助けているとの欧米の印象を多少とも和らげるため、輸出を抑えようとする中国当局の意図も感じられる。ただ、7~9月は何れも前年同月比20%以上の増加に転じており、今後の動向が注目される。
ロシア経済のクリミア併合後の2015年の状況をみると、欧米の制裁で▼1.97%とマイナス成長になって輸入は落ち込み、中国の対ロ輸出も大幅に減少した(特に機械電子品2014年158億ドル→15年104億ドル)。中期的には、今回も対ロ輸出低迷が続く可能性がある。英経済誌エコノミストは2022年ロシア経済の成長率が▼10%に落ち込むとみている(5月時点予測)。
対ロ輸入の面では、ウクライナ侵攻以前からすでに中ロ間でエネルギー協力強化の動きがある。欧米が制裁措置の一環でエネルギーの対ロ輸入を一部禁止したことから、協力関係がさらに強化される可能性がある。
原油、石炭、天然ガスとも中国の輸入量は国内生産増加と感染増による景気悪化という需給両面の要因から前年比減少しているが(1~9月の生産が各々前年比3.0%、11.2%、5.4%の増加に対し、輸入量は▼4.3%、▼12.7%、▼9.5%)、ドル建て輸入価格上昇で金額ベースでは同期間、各々47.0%、43.3%、43.9%の大幅増加。
ロシアからの原油、石炭の輸入量シェアはいずれも上昇(各々2021年15.5%→22年1~7月16.7%、同18%→23%)、特に5、6、7月の原油輸入量は各々前年比55%、9.5%、7.6%の増加で、3ヵ月連続サウジアラビアを抜いて最大。
天然ガスパイプライン、LNGの輸入量も上期63%、29%の大幅増加で、LNGは米国とインドネシアを抜き、ロシアが第4位の輸入先になり、この結果、天然ガス輸入に占めるロシアのシェアは2015年2%から1~7月3.9%へと上昇している。
ロシアは中ロ間も含め、貿易決済通貨としてドル以外の使用、中国は人民元国際化を進めており、対ドル依存からの脱却という点で中ロの政策方向は一致している。
2022年北京オリンピックに合わせプーチン氏が訪中した際に締結された天然ガス長期契約(向こう30年、中国はロシアから年間480億㎥の供給を受けられるとした)には、わざわざ決済通貨にユーロを使用する旨の項目を挿入している。ロシアは制裁でSWIFTから排除されて以降、原油や石炭の決済も人民元やルーブルに変えようとしている。
中国の対ロFDIについては、欧米による2次制裁も懸念してか、上期実績はなかったもようである。
次回の記事は、「中国・ウクライナ関係、一帯一路への影響」について解説する。
金森 俊樹
日本も中国に依存している
中国とロシア、ウクライナ侵攻中も継続する〈相互利用〉の思惑
2022年11/10(木)
2022年2月24日に始まったロシアのウクライナ侵攻。中立的立場を強調する中国だが、中国・ロシア間には、過去の国境紛争といった競合的関係があるものの、政治的・経済的側面においては、互いに相手を利用するというメリットがある。世界各国の目を意識しつつ、中・ロのトップ同士が神経をすり減らすやり取りを繰り広げている。中国の銀行・民間企業の動きはさらに巧妙だ。実情を見ていく。
ロシア経済「対中貿易の重要性」が増しているのは明白
ロシア経済にとって、その規模、伸びからみて、対中貿易の重要性が増していることは疑いない。2021年貿易額1470億ドル、36%増、ロシア貿易全体の18%を占める。2022年北京オリンピック時のプーチン氏訪中の際には、1170億ドルの原油、天然ガスを中国が購入することで署名し、2025年2500億ドルまで増やすことで合意した。ただ、中国は国としてはロシアの最大貿易相手だが、EUを1つとみると、ロシアの対EU貿易は対中の2倍で、なお経済面で欧州がロシアにとって最も重要な地域であることに変わりはない。
2014年のクリミア侵攻以降、ロシアの貿易面での中国依存は高まっているが、FDIや融資など貿易以外の経済面での中国の比重は低く、やはりEUの比重が引き続き高い。ロシア中央銀行統計では、ロシアの2019年対外FDI残高はキプロス1800億ドル、オランダ521億ドル、バーミューダ378億ドル、ルクセンブルグ366億ドル、英364億ドル、アイルランド304億ドル、仏223億ドル、ドイツ211億ドル、スイス189億ドルなどで、上記中国側統計同様、中国の数値は微小のため不詳だ。
中国側からみても主要貿易先はアセアン、欧州、米国で、対ロ貿易シェアは非常に小さい。上述の通り、FDI先としてもロシアの比重はわずかで、証券投資はほぼ皆無に近い。データからみる限り、中ロは経済関係において互いに相手が不可欠というわけではない。
ただし、両国の貿易構造は片務的・補完的で(もっぱら中国はロシアからエネルギーを輸入する一方、ロシアは中国から消費財など各種完成品を輸入)、両者の経済を一体化させる効果を有している。特に、中国にとってはエネルギーの安定供給を確保する観点からロシアは必須である一方、欧米の制裁に直面するロシアにとって、エネルギーの代替輸出先として中国の重要性が増している。外交上は盟友の中ロも、地理的には「競合関係」
政治外交面では、両国は各種国連決議で歩調を合わせることが多く、外交上の「盟友」とみられているが、両国間には周知の通り、旧ソ連解体から2005年に至るまでの約14年にわたる国境紛争の歴史があり、地理的に競合する関係にある。
中国が1996年に上海協力機構(SCO)を立ち上げ、以来これを主導し、またBRI推進で中央アジア諸国との関係を強化してきた背景には、特に同地域からのエネルギー供給確保を通じ、エネルギー面でロシアへの過度の依存を避ける思惑があった。
他方、ロシア側にも中央アジアへの影響力を拡大させ、またSCOを主導する中国に対して強い警戒感があり、先進国と途上国のような片務的な貿易構造に対し、「ロシアは中国の属国か」といった反発の声まで聞かれてきた。
ソ連解体後、中ロ関係には常に3つの「翳り(陰影)」がみられてきたとする指摘がある※1。すなわち、(1)中国が常にロシアの軍事技術を盗んできたとの疑念がロシア側にある、(2)ロシア極東地域への中国進出が活発で、ロシア内で、極東は早晩、中国の経済植民地になるとの声がある、(3)中国の一帯一路(BRI)は、ロシアの目には旧ソ連地域への中国の蚕食と写っている。
※1 「“二十大”习近平连任之际的内外处境(第20回党大会で習近平が続投する際の内外の困難な状況)」自由亜州電台(海外華字誌)評論2022年9月13日
これらを踏まえると、両国が共通の理念の下、互いに相手を信用して長期的で安定的な信頼関係を築くとは考え難い。ウクライナ問題を契機に、とりあえず中ロは接近を強めているが、イデオロギー面で同盟関係にあるというより、欧米、特に米国を念頭に、その時々の情勢に応じて、互いに相手をどう利用すれば自国の利益を最大化できるかを常に考えながら行動する実務的なパートナーとしての側面が強い※2。
※2 「ウクライナ情勢と中国」金森俊樹 外国為替貿易研究会「国際金融」2014年6月
中国がロシア経済を支援するインセンティブ
このような中ロの互いに自らの利益を考えた実務的関係は、ロシアのウクライナ侵攻後もすでに以下のように現れている。ロシアは中国が一緒に戦争してくれることは全く期待していないが、対欧州エネルギー貿易の減少を一定程度中国が代替吸収して影響を軽減し、ロシア経済が制裁に長く耐えられるよう、経済面での支援を期待していると思われる。
仮にロシア経済が崩壊するようなことになると、米国が対中戦略に専念する余裕ができることになるため、中国としてもロシア経済を支援しその崩壊を防ぐインセンティブがある。
習近平氏は一度もプーチン氏、あるいはその外交政策を支持するとまでは明言しておらず、その考え方やイデオロギーがプーチン氏と同じなのか否かも定かでない。同時に、ウクライナを支持するとも明言しておらず、全体としてはロシア寄りの姿勢をみせているという状況である。
この背景として第一に、対米関係を念頭にできるだけ米国に対抗する国を作っておきたいという意味で、プーチン氏が失敗することは望んでいないということが指摘できる。第二に、中国としてはロシアが自ら仕掛けた侵略戦争に勝っても負けても損はしないという読みがある。
仮にロシアが勝てば、ウクライナ問題で対欧米非難を展開してきた中国として当然メリットはある一方、ロシアが負けても、現状中国がロシアに軍事支援をしている、あるいは何かロシアの侵攻で具体的な利益を得ているという明確な証拠はなく、国際社会から中国が何らかのマイナスの影響を受けることは考え難いうえ、欧米と一緒になってロシアを非難しなかったという点で、ロシアに対する「貸し」が残る。
対米関係はいずれすでに十分悪化しており、これ以上悪くはならない(米国ハドソン研究所研究員)※3。他方、プーチン氏は習氏ひいては中国全体を味方につけているようにみせ、欧米との関係でそれを盾にして侵攻しているという構図である。このように、中国、ロシア双方が互いを利用している関係にある。
※3 「习普彼此・打气,他为何对普京“不离不弃”(習とプーチンは互いに励まし合っている。習はなぜプーチンに対し“離れず見捨てず”か)」万維読者網中国瞭望 2022年6月18日
一方、ロシアへの「近寄りすぎ」に躊躇も
同時に、中国はロシアに近寄りすぎることも望んでいないと思われる。上記、2022年2月の習氏の「中ロ協力に天井はない」発言に対し、ロシアのウクライナ侵攻後、党中央内で「後に発生し得るまずい結果(後果)を考えない愚かな発言だった」との声があるという。
その後3月、駐米中国大使(元外交部報道官、10月の第20回党大会で党中央委員に昇格)は米国TVのインタビューに答え、「中ロ協力に天井はないが、ボトムライン(底線)はある」とし、「底線は公に認識されている国際法や国際関係の基本原則だ」と軌道修正している※4。
※4「习近平做了一件蠢的事?(習近平は1つの愚かな事をしたのか?)」万維読者網中国瞭望(海外華字誌)2022年3月26日
もともと「天井なし」は次期外相有力候補とみられていたロシア専門家で親ロ派の外交部副部長(副大臣クラス)のせりふだが(公の場で「中ロ協力に天井はなく終点もない。ガソリンスタンドがあるだけだ」と発言したことで有名)、同氏は2022年5月、メディアを統括する国家広電局副局長に転任。降格人事ではないが、外交からは離れた。
ロシアの侵攻が続く中、習・プーチン首脳会談が4ヵ月近くおこなわれなかったことも、ロシアに近寄りすぎることについて、中国が躊躇していることを示すものとの見方がある(台湾中央研究院欧米研究所研究員)※5。
※5 「习普彼此・打气,他为何对普京“不离不弃”(習とプーチンは互いに励まし合っている。習はなぜプーチンに対し“離れず見捨てず”か)」万維読者網中国瞭望 2022年6月18日
その2回目電話首脳会談に関する中国側報道は、記事 『緊迫のウクライナ情勢…ロシアへの「中立的立場」を崩さぬ中国が国際社会に及ぼす影響』 で触れた通りだが、クレムリンの発出した声明は「双方がエネルギー、金融、工業、運輸その他の分野で協力を拡大することで合意し、さらに両首脳は軍事関係の発展についても議論した」とかなり温度差がある。
中国は9月初旬、ロシアの軍事演習「ボストーク2022」に白ロシアやシリアなどと一緒に参加(実戦経験が少ない中国人民解放軍にとっては貴重な機会)。欧米専門家の間では、ウクライナ情勢を機に、中ロが軍事面での関係を強化する兆しとする見方と(たとえば米シンクタンク戦略国際問題研究所CSIS)、中国はロシアがウクライナ侵攻でみせている「まずい軍事パーフォーマンス」で、ロシアを問題の多いパートナーだとみなすにいたっており、ロシアとの軍事協力について、現状は維持するがさらに強化することはないだろうとの見方が交錯しているが、後者の見方がやや有力か。
ストックホルム国際平和研究所推計によると、2002~21年、中国の武器輸入の大半はロシアからだが、ここ10年間で半減。中国が武器調達でロシアに大きく依存してきたことは、ロシアの軍事面での中国に対する「心理的優越感」に繋がってきたが、経済力や技術開発の面で中国はロシアより進んでおり、これが軍事面に反映されてくると、中国は武器輸入でロシアに依存する必要はなくなる。他方、ロシア側では以前から、中国が武器開発でロシアの技術を盗んでいるとの疑念が強い※6、※7。
※6「China faces dilemma over military ties with Russia: move closer or start to back off?」South China Morning Post September 4 2022
※7「新研究报告:侵乌战争促进俄中军事关系(新研究報告:ウクライナ侵略戦争が中ロの軍事関係を促進)」美国之音(ボイスオブアメリカ中国語版)2022年9月6日
習氏、パンデミック後初の外遊で「ウ問題」に言及せず
9月中旬、習氏はパンデミック発生後初の外遊(SCO首脳会議出席のため、カザフスタン、ウズベキスタン訪問)で、ロシアのウクライナ侵攻後初めてプーチン氏と対面での首脳会談に臨んだ。会談でウクライナ問題がどう議論されるのか各国が注目。ロシア側声明ではプーチン氏がウクライナ問題に関して、「中国が公平中立な立場をとっていることを評価」「中国の懸念と疑問を理解する」と発言したとされたのに対し、習氏はウクライナ問題に言及することはなく、中国外交部声明も前2回の電話首脳会談後の声明と異なり、今回はプーチン氏の当該発言部分も含めウクライナ問題にはまったく言及せず。
習氏は「互いの核心的利益に関わる問題について両国は相互支持を強化」としたものの、会談で言及された核心的利益は中国の台湾問題だけで、プーチン氏が台湾問題について米国を非難したのに対し、習氏が強調したのは貿易や文化交流などの分野での実務協力で、ウクライナ問題には言及せず、またその関連で米国を非難することもなかった。会談での習氏の冷ややかな表情に象徴されたように、両者の温度差が浮き彫りになり、中国がウクライナ問題でこれまでよりロシアと距離を取り始めたようにみえる※8。ある中国評論家はこうした中ロの関係を「ねじれたアライアンス(別扭联盟)」と評している※9。
※8 「Is China Breaking With Russia Over Ukraine?」The Diplomat September 17 2022
※9 「中俄的别扭联盟(中ロのねじれたアライアンス)」環球時報、2022年9月16日
会談直後の中国外交部記者会見で、AFPが「互いの核心的利益」には中国がウクライナ問題でロシアを支持することが含まれるのかと質問したのに対し、外交部は直接の回答を避け、「今回会談の状況については、中国側が発表している関連情報をみてほしい」とだけ回答している。中国官製メディアの会談関連報道も「ウクライナ」にはまったく言及しなかった。
プーチン氏「中国の懸念と疑問を理解する」の真意
首脳会談直後、プーチン氏の側近と言われるロシア安全保障会議書記が訪中し、中国外交トップの楊潔篪政治局委員と会談。しかしここでも、ロシア側声明が「両国が軍事協力、合同軍事演習をさらに進め、両国参謀本部間の連携を強化することで合意した」としたのに対し、中国外交部声明は「全面的戦略協力パートナーの関係の中身を不断に充実・強固にしていく」など、一般的・抽象的な内容に留めている。
習氏の外遊直前には栗戦書党政治局常務委員・全人代常務委員長(中国ナンバー3の位置付け)が訪ロ。おそらく中国から全面的な支持を得ていることを国際社会に示したいロシア側が故意に流したと思われるが、非公開会議で栗氏が発言している動画が出回った。
栗氏は「ウクライナ問題について、米国とNATOがロシアの国家や人民の安全を脅かしており、それに対しロシアが必要な措置を採っていることを理解し支持する」「中国は様々な方面から対応し協力する(策応)」と発言しており、欧米は中国がウクライナ問題で明確にロシア側に立っていることを示したと受け止めた。
プーチン氏の「中国の懸念…を理解」発言は中国の曖昧な態度に対する不満を表したものか、あるいは、栗氏訪ロ後の欧米の反応を受け、軌道修正を図る中国に配慮したものかもしれない。習・プーチン首脳会談で栗氏の面目は丸潰れとの声があるが、ウクライナ問題を巡って、中国指導部内が揺れていることが透けて見える。
中国のネット上で拡散・削除された、プーチンの発言
ウクライナ問題で難しい立場にある習氏に配慮したつもりか、あるいは積極的にはロシアを支援しない習氏に対する「あてこすり」か、発言の真意は不明だが、習氏もオンラインで出席したサンクトペテルブルク国際経済フォーラム(6月17日)でのプーチン氏の発言は、図らずも両国の実務的関係を示している。
すなわち、プーチン氏は「ロシアと中国は全方位的友好関係にあるが、それは決して中国はすべての事柄でロシアに迎合すべきということではない。ロシアもそれは同様」「各国にはそれぞれの国家利益、民族利益がある」と発言。
この発言が中国ネット上で拡散すると、「旧ソ連共産党が中国共産党の“父”だったという過去の歴史から来るロシアの優越意識が現れている」「中国指導部が旧ソ連、ロシアに卑屈に服従してきたことがこうしたロシアの優越意識を醸成した根本的原因」など中国の一般の人々の怒りを買い、さらには中国共産党に対する批判まで出てきたことから、その後、中国内ではプーチン氏の当該発言部分はネットから削除された。
中国は欧米の制裁に直面しているロシアを支持し続けられるのか? 当局が曖昧な態度をとるなかで、民間部門では企業が欧米の2次制裁を懸念して輸出を控える他、主要銀行もロシア顧客との関係は維持しつつも、制裁との衝突を避けようとする動きをみせている。
侵攻直後から2大国有銀行はロシア製品輸入のための信用供与を停止し、中国が26.5%の投票権を持つアジアインフラ投資銀行(AIIB)はロシア、白ロシア関係の活動を停止・再審査。大銀行が2次制裁を避けるため、国内市場に重点を置く小銀行に対ロ業務を移管する動きもある。ロシア経済は中国にエネルギーを輸出する一方、基礎的な消費財など完成品の輸入を中国に依存してなんとか生き延びることができるとしても、ハイテク製品・サービス輸入が制限され、長期的にはイノベーション、潜在成長力が損なわれる可能性が高い。
金森 俊樹
ロシアのウクライナ侵攻に見る、中国とウクライナの「微妙な関係」
金森 俊樹2022.11.2
中国「ウクライナの主権、独立、領土保全を尊重する」
中国とウクライナは2022年に国交樹立30周年を迎えた。中国は一貫して「ウクライナの主権、独立、領土保全を尊重する」としており、2013年に締結した友好協力条約で中国がウクライナに安全保障の供与を約束している。
関係強化を象徴する動きとして、たとえば2021年7月、初の電話首脳会談がおこなわれ、また2007年以降、ウクライナに8つの孔子学院が開校されるなど、両国が接近する動きがみられてきた。
経済面では2017年に協力協定が締結され、ウクライナは習近平政権の看板政策である一帯一路(BRI)の重要メンバーに位置付けられ、さらに、貿易、投資、物流、インフラ面での協力を強化するため、2021年6月にインフラ建設協力協定も締結された。
ウクライナはEUとも同様の協力協定を締結しているため、中国―欧州間の鉄道輸送、鉄道―港間の輸送で重要な役割を果たしている。2021年9月、中欧班列(中国―BRI沿線諸国―欧州を結ぶ国際貨物列車。2022年7月末時点、運行路線82、24か国200都市を連結。“班列”は元来中国で朝廷や官僚の序列を指す言葉)のルートの1つとして、ウクライナを経由するルートが開通し、ウクライナ内での双方向運行、ウクライナの貨物を対外輸送する能力の増強に寄与している。
中国企業はウクライナへのFDIを活発化
中国企業は2018年から、農業、インフラ、エネルギー、通信などの分野でウクライナへのFDIを活発化させている(2017年475万ドル、18年2745万ドル、19年5332万ドル、20年2106万ドル、20年末残高1.9億ドル)。
代表的な例としては、ウクライナ南部のニコラエフ港建設(2016年、中粮集団)、首都キーウの地下鉄建設協議署名(2017年、中国太平洋建設集団)、同地下鉄情報ネットワーク整備(2019年、華為ファーウェイ)、黒海沿岸チェルノモルスク港水上運送工事(2019年、中粮集団)、ウクライナの情報ネットワーク防御・安全システムプロジェクト落札(2020年、華為)、西南部黒海沿岸都市ユージュニ大型風力発電所建設(2021年、中国龍源電力集団)などがある。
ただ投資プロジェクトがすべて順調というわけではない。たとえば2021年、おそらく強制的技術移転が中国を利することに懸念を持つ米国の反対で、北京天驕航空産業投資公司によるウクライナの航空機エンジン製造会社買収が頓挫している。
貿易面では、ウクライナは中国から機械設備や消費財を輸入する一方、中国はウクライナから主として鉄鉱石、とうもろこしや大麦など農産品を輸入している。その他、航空機エンジンやミサイル部品などの重要軍需物資を輸入しているもようで、そのなかには、かつて中国が旧ソ連から購入した兵器の維持補修に必要な部品も含まれているという。
ロシアのウクライナ侵攻直後、一部海外メディアがウクライナ政府はロシアに友好的な中国に反発して、中国向け航空機エンジンと同部品(中国はこれを軍用機、民生用大型航空機に使用)の輸出禁止を決定したと報じ、それが中国内でも伝えられ注目された。しかしその後確認できる証拠がないとして、中国内で反中勢力のデマだとする声が挙がった。
貿易額は国交樹立時2.3億ドルだったが、2021年193億ドルまで増加し、パンデミック下でも拡大してきた。ただ、ウクライナにとって中国は最大の貿易相手国だが、中国にとってウクライナの貿易シェアは2021年0.2%、ロシアの2.4%と比べてもはるかに小さい。
ウクライナも、現状では対中非難せず
ウクライナと中国の政治関係は微妙だ。ロシアのウクライナ侵攻後、習氏は米国、EU、ロシア首脳とは個別に会談したが、ウクライナとは外相レベルのみ(8月)。それでもウクライナはこれまでのところ、対中非難は展開していない。
外相会談でウクライナは「中国は平和、停戦を保障する鍵となる国。この面での影響力行使を続けることを希望する」とし、新華社もこの発言を報道した。ウクライナはまた「多くの国が中国は裏でロシアを支援しているというが、実際は中立を維持していると理解している」と発言している(ウクライナ大統領府弁公室主任)。中国はすでにウクライナに対し、戦争終結後の大規模援助を約束しているとの情報もある※1。
※1 「战争阴影下中国与乌克兰的微妙的关系(戦争陰影下での中国とウクライナの微妙な関係)」在線報道(海外華字誌) 2022年4月17日
中国側は2022年第一四半期までウクライナとの貿易が正常に伸びていることを強調していたが、3月からウクライナ経由の中欧班列に運休が出始め、1~9月貿易額は62.8億ドル、▼55.9%、輸出27.3億ドル、▼58.8%、輸入35.5億ドル、▼53.4%と激減している。
一帯一路への影響
中国と欧州を結ぶBRIのルートはロシア、中央アジア、そしてウクライナに大きく依存している。しかしロシアとウクライナの領土内の安全保障上の問題に加え、欧米の対ロ制裁も加わり、多くの欧州諸国や一部中国企業も含め各国企業がロシアとの関係を避けるようになっており、中国当局としてはBRIの重心をより南のルートに移す必要が生じている。
この関連で、地政学的観点からイランの役割が強まるとの見方がある(ジュネーブ安全保障センター研究員)※2。
※2 「Russian-Ukraine War: Implications for Asian Geoeconomics」The Diplomat July 4 2022
すなわち、
①南のルートは地理的にイランが中心になる。
②中国はBRIの推進で、中央アジアとインドなど南アジアの相互補完性、投資の相乗効果を重視しているが、現状、地理的に両地域を連結するうえで最も有効なアフガニスタンの活用が安全保障上難しいため、代わりにイラン東部が重視され始めている。
③中央アジアや南アジアの諸国もイラン経由で欧州市場にアクセスし始めており、すでにイランとこれら諸国との貿易、商談が急増している。
④以上から、ウクライナ問題を機にイランが貿易ハブになる潜在的可能性が出てきた。
⑤ただし、その実現は米国の対イラン制裁の行方に左右されることになる。
中国にとってBRIの投資重点国である中東欧諸国はロシアに対する警戒感が強く、これらの国はウクライナ問題に対する中国の曖昧な態度に疑心暗鬼になっていると言われている。
エストニアとラトビアは2022年8月、BRIの下での貿易投資促進を目的として、中国と中東欧16か国が2012年に設立した「16+1」の枠組み(その後2019年にギリシャが参加し「17+1」)からの離脱を表明(リトアニアはすでに2021年に離脱)。これも直接的にはペロシ米下院議長の台湾訪問後に中国が台湾海峡でおこなった軍事威嚇が引き金になっているようだが、すでにロシアのウクライナ侵攻直前の2022年2月、プーチン氏が訪中した際、習氏が「中ロ協力に天井はない」と発言したことで、中国に対する不信感を募らせていたことが背景にあると言われている※3。
※3 「What next for China’s 16+1 group after Baltic exits over Russia and Taiwan?」South China Morning Post(香港英字紙)August 20 2022
中欧班列への影響
BRI推進で重要な役割を担う中欧班列への影響はどうか。
主要ルートはロシア、白ロシア、ポーランド経由でドイツに至るもので、白ロシアのミンスクとポーランドのワルシャワが最重要中継地点。ウクライナ経由ルートの比重は小さく迂回可能とみられている。
このため、中国当局はこのところ、中欧班列の運行が全体として順調であることを盛んに強調している(たとえば、2022年1~10月の運行本数が1.4万列を超えたなど。10月27日外交部記者会見)。しかし実際には、中欧班列の使用を控えリスクを回避する企業が増加しており、ロシアや白ロシアを避け、カスピ海や黒海を経由する南ルート、あるいはそれでは輸送量に限界があるので、2020年以来パンデミックで回避されていた海路を選択する動きがある。
それ以上に重要な点は、これまではロシアや白ロシアを経由するルートで貨物が欧州に運ばれていたが、ロシアのウクライナ侵攻後は、大半の貨物がモスクワ止まりになっており、貨物出発地で貨物量を計上している中国側発表数値はこうした変化を反映していないとの指摘があることだ※4。
※4 「中欧班列破万? 党媒泄中俄合作实情(中欧班列が1万列を突破? 党メディアが中ロ協力の実情をリーク)」新唐人(海外華字誌)2022年8月30日
金森 俊樹
オランダ 国内に中国が設けた非公式警察組織「中国警察駐在所」の閉鎖を要求
2022/11/12
中国共産党の海外活動を調査している国際的な人権団体「セーフガード・ディフェンダーズ」が「海外110」と題した報告書で、中国共産党が欧米諸国に設置した非公式な警察組織について明らかにした。
報告書によると、中国共産党当局は、欧米諸国を中心に21カ国に54もの非公式な警察組織「中国警察駐在所」を設置し、海外の民主化活動家らに接触して、反中国的な活動を止めるように脅迫したり、強制的に帰国させるなどの活動を行っているという。
オランダ政府は2022年11月2日、中国政府に対して、アムステルダムとロッテルダムに中国警察駐在所が置かれていることを確認したとして、この2カ所の駐在所を閉鎖するよう要求したという。英国やスペインなども駐在所について調査しており、今後、オランダ政府と同様の行動をとるとみられる。香港の英字紙「サウスチャイナ・モーニング・ポスト」が報じた。
中国も署名しているウィーン条約によると、外交事務は現地政府によって認められた各国大使館と領事館に限られる。こうした非公式警察組織は現地の法律に違反し、国家主権を侵害している可能性があるという。スパイ活動にも使用される恐れがあった。
オランダのウォプケ・エクストラ外務大臣は「オランダ政府は中国の警察機関がオランダ政府に無断で活動すること容認できない。駐オランダ中国大使はただちにこれらの駐在所を閉鎖しなければならない」と発表。オランダ外務省は駐在所の存在を明らかにするよう要請し、その活動を調査していると付け加えた。
オランダのラジオ局RTLなどオランダメディアは、オランダ在住の中国人反体制活動家の話を引用する形で、2カ所の駐在所警察署が2018年以降、海外の反体制派グループの摘発を目的に設立され、中国で警察官としての経験を持つ人物ら数人が駐在し、オランダ在住の中国人を監視していると伝えている。
これについて、中国外務省は「オランダの報道は全くの虚偽であり、駐在所は運転免許証の更新など、海外居住者を支援するためのものである」と主張しているが、すでに米、英、独、スペインなど欧米諸国は駐在所の調査を開始している。
セーフガード・ディフェンダーズによると、海外の駐在所は各国の華人同郷会(友好団体)と連携しており、同団体は対外工作を主要な任務としている中国共産党統一戦線部と密接な関係にあるとされる。
井上達夫×先﨑彰容が対論“国柄”と“国防”を考える<前編>
2023/04/04 #プライムニュース #BSフジ #NEWS
多極化する世界で日本は?安保3文書改定で国を守れるか?東大名誉教授で法哲学者の井上達夫氏と思想史家の先﨑彰容氏が“国柄”と“国防”について考える。
『井上達夫×先﨑彰容が対論“国柄”と“国防”を考える』
ウクライナに装備品、経済支援をし、ロシアに経済制裁を科している日本はこの戦争の「当事国」ではないのか、反撃能力保持を示した安保3文書改定で、自衛隊は日本を守ることができるのか、多極化する世界で、日本の立ち位置は、民主主義と権威主義との対立、中国やロシアとの向き合い方、日米同盟の今後など、東大名誉教授で法哲学者の井上達夫氏と思想史家の先﨑彰容日大教授が日本の“国柄”と“国防”について考える。
出演者:
井上達夫 (東京大学名誉教授 法哲学者)
先﨑彰容 (日本大学危機管理学部教授 思想史家)
井上達夫×先﨑彰容が対論“国柄”と“国防”を考える<後編>2023/4/3放送
ついに明るみになった韓国半導体企業と中国企業のウィンウィンの関係
中国企業に半導体技術流出の疑い…韓国検察がサムスン電子元部長らを逮捕 流出による被害は数千億円規模か、韓国メディア
2023年12月16日
韓国の検察は、半導体の技術を中国企業に流出させたとして電子機器大手・サムスン電子の元部長らを逮捕しました。技術流出による被害は、日本円にして数千億円にのぼるとみられます。
韓国メディアによりますと、ソウル中央地検は、サムスン電子の元部長らが中国の半導体企業「チャンシンメモリーテクノロジーズ」に半導体の製造工程の情報などを流出させたとして、15日までに逮捕状を請求。
逮捕が妥当かを審査していたソウル中央地裁は、元部長らが「証拠を隠滅する恐れがある」として、逮捕を認めました。
韓国メディアは、元部長が8年前にサムスン電子を辞めた後、「チャンシンメモリー」社の設立に当初から関与し、技術流出による被害は日本円にして数千億円にのぼるとみて検察が捜査していると報じています。
MSやGoogle出身のAI人材、中国に続々帰国
米国で活躍した中国人AI人材、母国へ回帰の動き加速
中国出身の人工知能(AI)新薬開発専門家、フー・ティエンファン博士(32)は、2年前に米レンスラー工科大学で教授に就任し、終身教授を目指していた。しかし今年、中国・南京大学へ移籍した。AIを活用した新薬開発で注目されている若手研究者であるフー博士は香港の「サウス・チャイナ・モーニング・ポスト」とのインタビューで、「中国政府の高等教育への積極的な投資が、若手科学者に前例のないチャンスを与えている」と語った。
中国出身のAI人材が母国に戻る動きが加速している。先月23日には、マイクロソフトやIBMなど米ビッグテック企業でAI研究員を務め、フロリダ大学の教授としても活躍してきたチー・グオジュン氏(43)が、中国・杭州の西湖大学AI・機械学習研究所「メイプル(MAPLE)」の所長に就任すると報じられた。チー氏はディープラーニングやマルチモーダルAI(画像・音声など複数の情報形式を扱うAI)の専門家で、論文の被引用数は2万3,500回を超える実力者として知られている。
以前は母国に戻る中国人材の多くは大学教授が中心だったが、最近ではグローバル企業で活躍していた人材の帰国も目立ち始めている。例えば今年初め、中国のバイトダンス(TikTokの親会社)は、Google DeepMindの元副社長であるウ・ヨンフイ氏を採用した。南京大学を卒業後、米国で博士号を取得したウ氏は、2008年からGoogleで機械学習と自然言語理解を専門に17年間勤務していた。また、Appleで高性能・低消費電力のCPU設計を担当していたワン・ファンユイ博士も昨年、中国の華中科技大学(HUST)の教授に就任した。
過去には海外で高い評価を得た学者が後進の育成を目的に帰国するケースが一般的だったが、最近は帰国する人材の年齢層が若年化している。たとえば、暗号学分野の世界的権威であるカス・クリーマス元オックスフォード大学教授の主要研究プロジェクトに参加した、ジャオ・マン氏(29)、そして大連工科大学の教授に就任した双子の科学者マ・ドンハン氏(35)とマ・ドンシン氏が代表例だ。なお、マ・ドンシン氏は2012年に清華大学の最優秀5人の学生に与えられる特別奨学金の受賞者でもある。
若手人材を獲得するため、中国の大学は破格の条件を提示している。例えば、海外で博士号を取得した研究者が母国に戻り3年以上教授として勤務する場合、3年間の研究費900万元(約1億8,200万円)と年俸75万元(約1,500万円)を中国政府が創設した「優秀科学青年基金」で保証する。さらに生活費100万元(約2,000万円)と特別手当150万元(約3,000万円)を支援する場合もある。一般的な中国の教授年俸(20万〜35万元(約400万〜700万円))の約6倍に達する支援を受けられる。
中国の研究環境も急速に改善されている。フー・ティエンファン教授は、AIを活用した新薬開発に関して、「中国の大規模な臨床研究が貴重なデータ源となっており、こうしたデータが中国の技術企業によるAI発展を加速させている」と述べた。
中国政府は2017年に「次世代AI発展計画」を発表し、AI分野の人材回帰を促進する政策を本格的に推進してきた。これに伴い、大学や研究機関は自由度の高い研究環境と充実した研究予算を整備できる体制が整いつつある。これまで中国で博士課程に進むには国内で学士・修士号を取得していることが条件とされていたが、今年から清華大学や復旦大学などの主要大学がこの条件を撤廃。海外で修士号や博士号を取得した高度人材を積極的に迎え入れるための措置だ。
中国政府による人材の本国回帰政策は、実際に成果を上げている。先月30日に発表された「北京留学派白書」によると、昨年末の時点で海外留学を経験した北京在住者は122万8,500人に達し、そのうち約5分の1(20.84%)が科学・技術関連分野を専攻した人材だった。
また、中国教育部の資料によれば、年間の帰国留学生数は2015年の40万人から2021年には100万人を突破。このうち40%以上が、科学・技術・工学・数学(STEM)分野を専攻していた。
中国科学院と中国工程院に所属する院士(最高位の科学者)の多くが、海外留学の経験を持つことが明らかになっている。北京市で勤務する中国科学院の院士403人のうち、302人(75%)が海外留学経験者であり、中国工程院の院士448人のうち211人(47%)も同様に留学経験を持っていた。また中国科学院は、2023年上半期に米シリコンバレーから帰国したAI人材の数が、前年同期比で30%増加したと発表した。