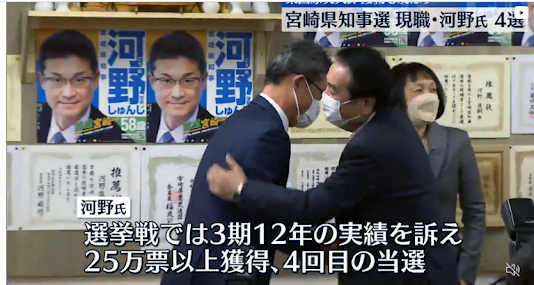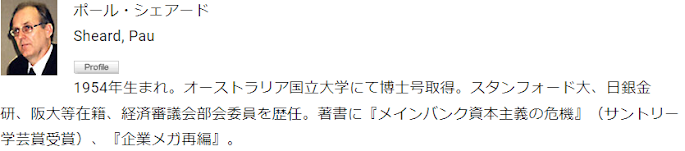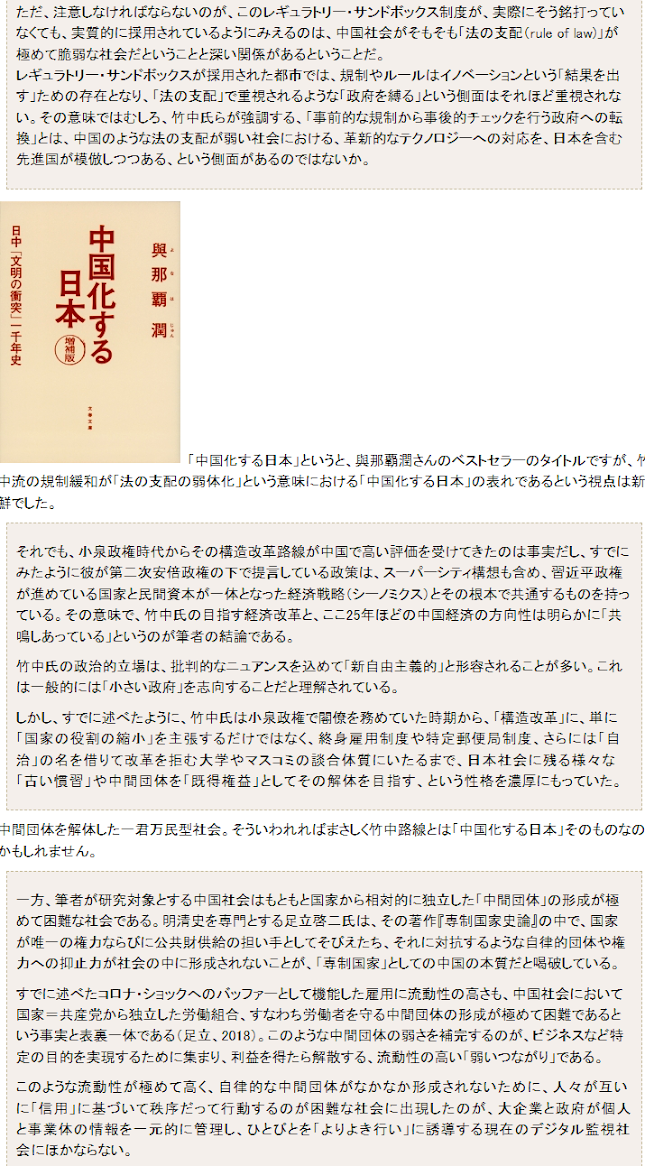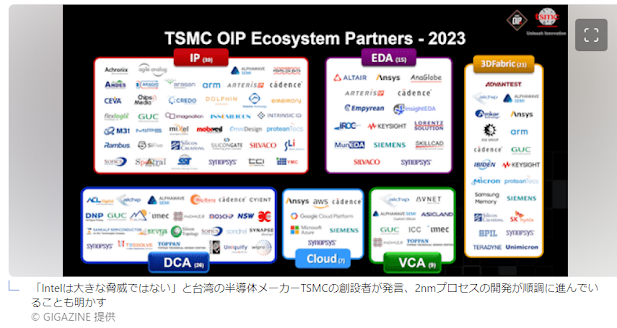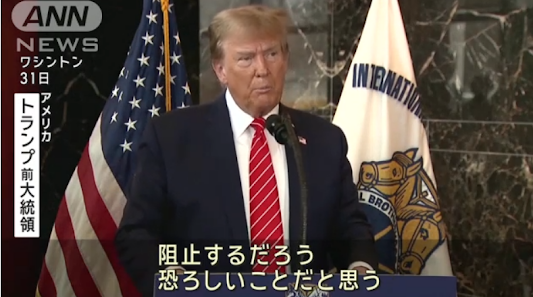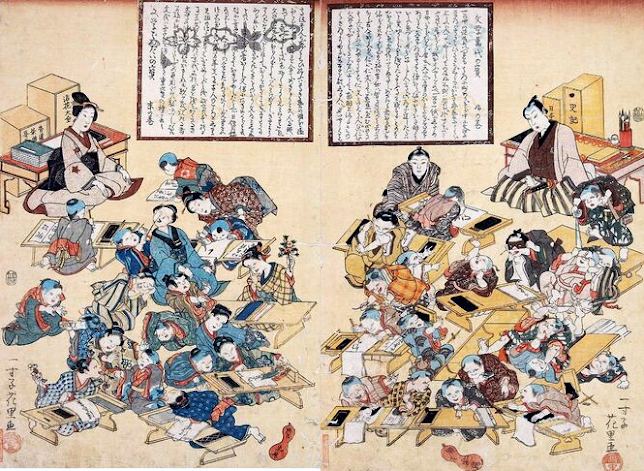⓰小泉 純一郎(こいずみ じゅんいちろう、1942年〈昭和17年〉1月8日 - )
小泉 純一郎(こいずみ じゅんいちろう、1942年〈昭和17年〉1月8日 - )は、日本の政治家。
衆議院議員(12期)、厚生大臣(第69代・第70代・第81代)、年金問題担当大臣、郵政大臣(第55代)、内閣総理大臣(第87代・第88代・第89代)、自由民主党総裁(第20代)、外務大臣(第127代)、農林水産大臣(第37代)を歴任した。首相在任期間は1980日で戦後では安倍晋三、吉田茂、佐藤栄作に次いで4番目の長さ、戦前を含めても6番目の長さである。
 |
| 中国「一帯一路」国際会議に鳩山元総理が出席「日本からの出席者少なくて残念」 |
中国の巨大経済圏構想「一帯一路」の国際会議に鳩山由紀夫元総理が出席し、日本からの出席者が少ないのは残念だと述べました。中国の北京で2023年10月17日から2日にわたって開かれた「一帯一路」の国際会議に参加しましたが、松野官房長官は「日本政府として出席は予定していない」と表明していました。
福田赳夫の秘書を経て、1972年(昭和47年)の第33回衆議院議員総選挙で初当選し、以来12期連続当選。自由民主党では清和会(福田派、安倍派、三塚派、森派)に所属した。また、山崎拓や加藤紘一と「YKK」を結成し、経世会支配からの脱却や党の世代交代を訴え「グループ・新世紀」を旗揚げした。
竹下政権にて厚生大臣として初入閣、宇野政権、橋本政権でも厚生大臣を務め、宮澤政権では郵政大臣を務めた。森喜朗の後任として自由民主党総裁に選出され、2001年(平成13年)4月に内閣総理大臣に就任した。内閣総理大臣の在任期間は1980日で、第二次世界大戦後の内閣総理大臣としては安倍晋三、佐藤栄作、吉田茂に次ぐ第4位。平成の時代においては安倍晋三に次ぐ第2位の長期政権である。2009年(平成21年)の第45回衆議院議員総選挙には立候補せず、二男の進次郎を後継に指名し政界を引退した。引退後は奥田碩、田中直毅らとシンクタンク「国際公共政策研究センター」を設立し、その顧問を務めた。公益財団法人日本尊厳死協会の顧問を務めている。
生い立ち
小泉家。左から純一郎、又次郎(祖父)、正也(弟)、純也(父)。
1942年(昭和17年)1月8日、神奈川県横須賀市に、父小泉純也と母芳江の長男として生まれる。母方の祖父小泉又次郎は第2次若槻内閣で逓信大臣を務め、若い頃に全身に入れ墨を彫っていたことから、“いれずみ大臣”“いれずみの又さん”などの異名で知られる大衆政治家だった。
戦後、又次郎と純也は相次いで公職追放にあったため、小泉家の経済状態は決して恵まれていたわけではない。井料克己によれば「日本全体が食べるのに必死だったけど、小泉家もまだ貧まずしくて夕食の食卓には芋の煮っころがしなんかが並んでいた。僕がたまに川や海に行って魚やうなぎを釣ってくると純一郎たちが喜んでくれた。」という。
学生時代
神奈川県立横須賀高等学校卒業後、慶應義塾大学経済学部に入学し、同大学を卒業。英国ロンドン大学群ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン (U.C.L.) に留学の後、1969年(昭和44年)8月に父が急死し帰国。
同年12月、亡父の跡を継ぎ、弔い選挙となった第32回衆議院議員総選挙に神奈川2区から自由民主党公認で立候補し、10万3000票余りを獲得するが、4000票差で落選した。
衆議院議員
1979年(昭和54年)、第2次大平内閣で大蔵政務次官に就任。
ポストに執着せずもっぱら政策の習熟に徹していたが、子分を作らない一匹狼的な行動をとり、言いたいことを直言し、与野党政治家の既得権益を害する郵政民営化論を主張することもあって永田町では「変人」と評されるようになる。
1988年(昭和63年)、竹下改造内閣で厚生大臣として初入閣。
1989年(平成元年)にリクルート事件で竹下政権が倒れ、続く宇野政権も参院選で惨敗し、わずか2か月で退陣した。政治不信が高まり、政治改革の柱として「小選挙区制の導入」が叫ばれた際、小泉はこれに強く反対し、推進派の羽田孜と対立した。
1991年(平成3年)、自民党総裁選で再選を目指し、最大派閥の経世会(竹下派)の支持を受けた海部俊樹(首相)に対抗し、盟友の山崎拓(渡辺派)、加藤紘一(宮沢派)と組んで、「海部続投阻止」「経世会支配打倒」を打ち上げた。所属する三塚派のほか、渡辺派、宮沢派の反主流派が結束したため、海部内閣は機能不全に陥り、海部は総裁選不出馬に追い込まれた。
後任の総理総裁に宮澤喜一が就任すると、小泉は1992年(平成4年)の宮澤改造内閣で郵政大臣に就任する。就任会見で、かねてからの持論の郵政民営化論に基づき、国は民間では採算の採れないことだけをすべきとして、老人マル優限度額引き上げなど従来の郵貯事業拡張政策の見直しを唱えたが、この老人マル優限度額引き上げ見直しは反対派議員(郵政族)等の反発で失敗に終わった。
1993年(平成5年)5月4日に国連カンボジア暫定機構に派遣されていた日本の文民警察官が武装グループに襲撃され、高田晴行警部補が死亡、4人が重軽傷を負う事件が起こった際には、5月7日の閣議の席上で「カンボジアは実質内戦に近い状態にあり、事実上危険な状態であれば、PKOの引き揚げも今後の選択肢に入れるべきだ」等と語り、自衛隊カンボジア派遣に異議を唱えた。また、この死傷事件をきっかけにタケオ州に駐在する自衛隊施設大隊が選挙監視要員を支援することにした政府決定についても異議を唱えている。さらに、5月18日の閣議でも「日本独自の判断で文民警察官をより安全な場所に移動させよ」「政府は国会で言ってきたこと、国民に約束したことを尊重すべきだ」とした。
1993年(平成5年)、羽田孜、小沢一郎ら羽田派(改革フォーラム21)らの賛成もあって、宮澤内閣へ不信任決議が可決され、第40回衆議院議員総選挙で自民党は過半数を割った。小泉は、宮澤の責任や退陣を閣僚懇談会でも要求し、郵政大臣を辞職した。なお、総選挙後に日本新党の細川護熙を首班とする連立政権が成立、自民党は野党に転落した。宮澤の後任の自民党総裁には河野洋平が就任した。
総裁選への挑戦
下野の直後から自民党内では社会党との連立による政権復帰が模索され、小泉は福田赳夫の配下で社会党との連絡役を担っていた。
1994年(平成6年)、自民党は日本社会党委員長の村山富市を内閣総理大臣指名選挙で支持して自社さ連立政権を成立させ政権に復帰、野中広務らの平成研究会(旧竹下派)が主導的な力を持つようになった。
1995年(平成7年)の参議院議員選挙で自民党は新進党に敗北。河野は続投を望んだが、平成研究会は政策通で人気のある橋本龍太郎を擁立した。小泉らの清和会は河野を支持したが、情勢不利を悟った河野が出馬断念を表明したことで、橋本の総裁就任は確実になった。無投票で総裁が決まることを阻止したい小泉らは森喜朗(清和会)擁立を図るが森が辞退したため、小泉が自ら出馬することを決めた。
既に大勢が決していた上に、郵政民営化を主張する小泉は党内で反発を買っており、出馬に必要な推薦人30人を集めることができたことがニュースになる有り様だったが、それでも若手議員のグループが小泉を推した(中川秀直や山本一太、当選1回の安倍晋三もいた)。結果は橋本の圧勝に終わったが、総裁選出馬により郵政民営化論を世間にアピールして存在感を示すことはできた。
1996年(平成8年)に村山が首相を辞任し、橋本内閣が成立すると、小泉は第2次橋本内閣で再び厚生大臣に就任する。小泉は相変わらず自説を曲げず「郵政民営化できなければ大臣を辞める」と発言、国会答弁で「新進党が郵政三事業民営化法案を出したら賛成する」と郵政民営化を主張したときは、与党から野次を受け、逆に野党から拍手を受けることもあった。同年、在職25年を迎えたが永年在職表彰を辞退した。
1997年(平成9年)、厚生大臣時代に厚生省幹部と参議院厚生委員会理事と食事を取っていたが、村上正邦自由民主党参議院幹事長が円滑な参議院審議を求める参議院理事のスケジュール管理の立場から、村上への事前通告がなく参議院理事を動かしたことで参議院スケジュール管理に支障を来たしたことを理由に反発した。村上が参議院厚生委員長に対して議事権発動を促し、厚生省幹部の出席差し止めという形で小泉厚相に反発。YKKの盟友だった加藤紘一幹事長を中心とする党執行部は異常事態を打開するために村上を参議院幹事長から更迭しようとするが、村上は参議院の独自性を盾に抵抗。村上更迭という強行案には、党内連立反対派(保保連合派)らの反発を党執行部が恐れたため、小泉厚相に対して村上参院幹事長に全面謝罪させることを提案、小泉が村上に謝罪したことで収束した(この事件が小泉にとって、参議院の影響力の大きさを実感する出来事であった。2001年に首相になった時、トップダウン方針と言われながらも、参議院の実力者であった青木幹雄に参議院枠を初めとする一定の配慮を示す原因になったと言われている)。
1998年(平成10年)の参議院議員選挙、自民党は大敗を喫し、橋本は総理大臣を辞任した。後継として、小渕恵三、梶山静六と共に小泉も立候補したが、盟友の山崎・加藤の支持を得られず、仲間の裏切りにもあい、所属派閥の清和会すらも固めることもできず最下位に終わった(総裁には小渕が選出)。前回総裁選とは異なり政治的には少なからずダメージを負ったとされ、本人は「失敗した。ピエロになってしまった」と嘆いたという。以後しばらくは表立った役職に就かず、派閥に戻り雌伏の時を過ごすことになる。YKKとして小渕の政権運営に批判的な立場を取る一方、派閥会長の森が幹事長として政権を支えており派としては主流派に位置していたため、小泉の立場は矛盾を孕んだものになっていた。この矛盾は森政権となっても続くが、以下の「加藤の乱」で立場を鮮明にすることを迫られることになる。
加藤の乱
2000年(平成12年)、小渕が急死し、党内実力者の青木幹雄、野中広務らの支持により幹事長だった森喜朗が総理・総裁に就任。小泉は清和政策研究会(森派)の会長に就任した。第2次森内閣組閣では安倍晋三が内閣官房副長官に、中川秀直官房長官のスキャンダル辞任後の後任に福田康夫が、それぞれ小泉の推薦を受けて就任した。
紹介予定派遣の解禁。
この総理就任の経緯は密室談合と非難され、森内閣は森の旧来政治家的なイメージも相まって人気がなく、森の失言が次々とマスコミに大きく取り上げられ、支持率は急落した。このころの小泉は公明党との協力に批判的で、2000年6月の衆院選で公明党候補が多く落選したことについて野中幹事長が「大変なご迷惑をかけた。万死に値する」とコメントしたことを、猛然と批判している。森内閣の支持率は2000年11月には18.4パーセントを記録し、これに危機感を抱いた反主流派の加藤紘一・山崎拓が公然と森退陣を要求し始めた。加藤と山崎は、自派を率いて、野党の提出する内閣不信任案に同調する動きを見せ、特に加藤は小泉の同調を期待したとされる。しかし森派の会長だった小泉は森支持の立場を明確にし、党の内外に加藤・山崎の造反を真っ先に触れ回った。
加藤はマスコミに積極的に登場して自説を主張し、普及し始めたインターネットを通じて世論の支持を受けたが、小泉ら主流派は猛烈な切り崩し工作を行い、加藤派(宏池会)が分裂して可決の見通しは全くなくなり、加藤・山崎は内閣不信任案への賛成を断念した。これにより、総理候補と目された加藤は、大きな打撃を受け小派閥に転落、一方、森派の顔として活躍した小泉は党内での評価を上げた。
小泉旋風
森の退陣を受けた2001年4月の自民党総裁選に、橋本龍太郎、麻生太郎、亀井静香と共に出馬。敗れれば政治生命にも関わるとも言われたが、清新なイメージで人気があった小泉への待望論もあり、今回は森派・加藤派・山崎派の支持を固めて出馬した。小泉は主婦層を中心に大衆に人気のあった田中眞紀子(田中角栄の長女)の協力を受けた。
最大派閥の橋本の勝利が有力視されたが、小泉が一般の党員・党友組織自由国民会議会員・政治資金団体国民政治協会会員を対象とした予備選で眞紀子とともに派手な選挙戦を展開した。小泉は「自民党をぶっ壊す!」「私の政策を批判する者はすべて抵抗勢力」と熱弁を振るい、街頭演説では数万の観衆が押し寄せ、閉塞した状況に変化を渇望していた大衆の圧倒的な支持を得て、小泉旋風と呼ばれる現象を引き起こす。こうした中で、次第に2001年7月に参院選の「選挙の顔」としての期待が高まる。そして小泉は予備選で地滑り的大勝をし、途中で中曽根元首相、亀井元建設相の支持も得、4月24日の議員による本選挙でも圧勝して、自民党総裁に選出された。
4月26日の内閣総理大臣指名選挙で公明党、保守新党の前身保守党、「無所属の会」所属の中田宏、土屋品子、三村申吾の支持を受け内閣総理大臣に指名され、皇居での親任式にて天皇明仁より第87代内閣総理大臣に任命される。
内閣総理大臣
小泉は組閣にあたり従来の派閥順送り型の人事を排し、慣例となっていた派閥の推薦を一切受け付けず、閣僚・党人事を全て自分で決め、「官邸主導」と呼ばれる流れを作った。少数派閥の領袖である山崎拓を幹事長に起用する一方で、最大派閥の平成研究会(橋本派)からは党三役に起用しなかった。人気のある石原伸晃を行政改革担当大臣に、民間から経済学者の竹中平蔵を経済財政政策担当大臣に起用した。また、総裁選の功労者の田中眞紀子は外務大臣に任命された。5人の女性が閣僚に任命された(第1次小泉内閣)。
「構造改革なくして景気回復なし」をスローガンに、道路関係四公団・石油公団・住宅金融公庫・交通営団など特殊法人の民営化など小さな政府を目指す改革(「官から民へ」)と、国と地方の三位一体の改革(「中央から地方へ」)を含む「聖域なき構造改革」を打ち出し、とりわけ持論である郵政三事業の民営化を「改革の本丸」に位置付けた。特殊法人の民営化には族議員を中心とした反発を受けた。
発足時(2001年4月)の小泉内閣の内閣支持率は、戦後の内閣として歴代1位の数字となり、最も高かった読売新聞社調べで87.1パーセント、最も低かった朝日新聞社調べで78パーセントを記録した。「小泉内閣メールマガジン」を発行し、登録者が200万人に及んだことも話題となった。こうした小泉人気に乗るかたちで同年7月の参議院議員選挙で自民党は大勝した。
終戦の日の8月15日に靖国神社参拝をすることを、小泉は総裁選時に公約としていた。総理の靖国神社参拝は中国・韓国の反発に配慮して長年行われていなかった。小泉は、批判に一定の配慮を示し、公約の8月15日ではなく8月13日に靖国神社参拝を行った。翌年以降も、毎年靖国参拝を行った。2006年には公約であった終戦の日8月15日における参拝を実現した。
9月11日、米同時多発テロの発生を受けて、ブッシュ大統領の「テロとの戦い」を支持した。米軍らのアフガニスタン侵攻を支援するテロ対策特別措置法を成立させ、海上自衛隊を米軍らの後方支援に出動させた。
国際情勢が緊迫する中、外務省は、田中外相が外務官僚や元外務政務次官の鈴木宗男議員と衝突し、機能不全に陥っていた。小泉は2002年2月に田中外相を更迭した。人気の高い田中の更迭により、80パーセントを超える異例の高支持率であった小泉内閣の支持率は40~50パーセント台にまで急落した(読売新聞では支持率48.9%、下げ幅30.7ポイントという急落ぶりだった)。田中は大臣更迭後の同年8月に秘書給与流用疑惑が浮上し議員辞職した。
小泉は、2002年(平成14年)9月に電撃的に朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)を訪問し、金正日国防委員長と初の日朝首脳会談を実現し、日朝平壌宣言に調印した。この訪問で金正日は北朝鮮による日本人拉致を公式に認め、拉致被害者のうち5名を日本に帰国させることを承認した。しかし、残りの拉致被害者のうち8名が死亡・1名が行方不明とする北朝鮮の回答に対し、拉致被害者家族は怒りを隠さず、交渉を終え帰国した小泉を面罵する場面もあった。
2002年9月30日、小泉改造内閣が発足。柳澤伯夫を金融担当大臣から更迭して、竹中平蔵に兼務させた。これにより、以後は不良債権処理の強硬策を主張する竹中が小泉政権の経済政策を主導した。
2003年(平成15年)3月、アメリカはイラクへ侵攻してフセイン政権を打倒した。小泉は開戦の数日前にアメリカ支持を表明し、野党やマスコミの一部から批判を受けた。日米同盟こそが外交の基軸とのスタンスを崩さず、ブッシュ大統領との蜜月関係を維持した。イラク戦後復興支援のための陸上自衛隊派遣が喫緊の課題となり、7月にイラク特措法を成立させた。これに先立つ6月には、長年の安全保障上の懸案だった有事関連三法案(有事法制)を成立させている。ここで、小泉がイラク戦争を公式に支持する際、数日前の2003年3月2日に起きたアメリカ軍電子偵察機に対する北朝鮮戦闘機のスクランブル発進を引き合いにして朝鮮有事における日米同盟の重要性を強調している。
9月に行われた自民党総裁選で平成研究会は藤井孝男元運輸大臣を擁立して小泉おろしを図ったが、参院自民党幹事長であった青木幹雄がこれに与せず派閥分裂選挙となり、藤井は大敗。藤井擁立の中心となった野中広務は10月に政界を引退した。平成研究会(旧経世会)の凋落を示す事件で、清和政策研究会(森派)が党の主導権を掌握することになる。
2003年9月、自民党総裁選で再選された小泉は小泉再改造内閣発足させ、党人事では当選わずか3回の安倍晋三を幹事長に起用する異例の人事を行い、11月の総選挙では絶対安定多数の確保に成功。閣僚を留任させた第2次小泉内閣が発足した。この際、中曽根康弘元首相、宮澤喜一元首相に引退を勧告した。
労働者派遣法改正
例外扱いで禁止だった製造業および医療業務への派遣解禁。専門的26業種は派遣期間が3年から無制限に。それ以外の製造業を除いた業種では派遣期間の上限を1年から3年に。
2004年(平成16年)1月、陸上自衛隊をイラク南部のサマーワへ派遣したが、4月に武装集団がイラクにいた日本人を拉致して「イラクからの自衛隊の撤退」を要求する事件が起きた(イラク日本人人質事件)。小泉は「テロには屈しない」とこれを明確に拒否。人質3人は後に解放された(地元部族長の仲介によるものとされる)。また、この際には「自己責任論」を主張し、解放された人質らに対して外交経費を請求した。
2004年5月、小泉は再び北朝鮮を訪問、同国首都の平壌市で金正日総書記と2回目の日朝首脳会談をした。北朝鮮に対する25万トンのミニマム・アクセス米や1000万ドル相当の医療品の支援を表明し、日朝国交正常化を前進させると発表した。この会談で新たに5名の拉致被害者が日本に帰国した。小泉はアメリカとの連係を強化して「対話と圧力」の姿勢を維持した。
2004年6月、2003年6月に制定された有事関連三法に基づいて、「米軍と自衛隊の行動を円滑かつ効果的にする法制」、「国際人道法の実施に関する法制」、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)等の有事関連七法(有事法制)を成立させた。
2004年7月の第20回参議院議員通常選挙を控え、年金制度改革が争点となった。小泉内閣は参院選直前の6月に年金改革法を成立させたが、選挙では自民党が改選50議席を1議席下回り、民主党に勝利を許した。この責任をとって安倍幹事長が辞任し、武部勤が後任となった。
小泉の最大の関心は、持論の郵政民営化にあった。参院選を乗り切ったことで小泉は郵政民営化に本格的に乗り出し、2004年9月に第2次小泉改造内閣を発足させ、竹中を郵政民営化担当大臣に任命した。「基本方針」を策定して、4月に開設した郵政民営化準備室を本格的に始動した。
小泉劇場
2005年(平成17年)、小泉が「改革の本丸」に位置付ける郵政民営化関連法案は、党内から反対が続出して紛糾した。小泉は一歩も引かぬ姿勢を示し、党内調整は難航する。反対派は亀井静香、平沼赳夫が中心となり長老の綿貫民輔を旗頭に100人近い議員を集めた。法案を審理する党総務会は亀井ら反対派の反発で紛糾し、遂に小泉支持派は総務会での全会一致の慣例を破って多数決で強行突破した。反対派はこれに激しく反発し、事態は郵政民営化関連法案を巡る小泉と亀井、平沼ら反対派との政争と化した。
衆議院本会議における採決で、反対派は反対票を投じる構えを見せ、両派による猛烈な切り崩し合戦が行われた。7月5日の採決では賛成233票、反対228票で辛うじて可決されたが、亀井、平沼をはじめ37人が反対票を投じた。参議院では与野党の議席差が少なく、亀井は否決への自信を示した。小泉は法案が参議院で否決されれば直ちに衆議院を解散すると表明するが、亀井ら民営化反対派は、衆院解散発言は単なる牽制であり、そのような無茶はできないだろうと予測していた。
2005年8月8日、参議院本会議の採決で自民党議員22人が反対票を投じ、賛成108票、反対125票で郵政民営化関連法案は否決された。小泉は即座に衆議院解散に踏み切り、署名を最後まで拒否した島村宜伸農林水産大臣を罷免、自ら兼務して解散を閣議決定し、同日小泉は、憲法第7条に基づき衆議院解散を強行した。
小泉は、法案に反対した議員全員に自民党の公認を与えず、その選挙区には自民党公認の「刺客」候補を落下傘的に送り込む戦術を展開。小泉は自らこの解散を「郵政解散」と命名し、郵政民営化の賛否を問う選挙とすることを明確にし、反対派を「抵抗勢力」とするイメージ戦略に成功。また、マスコミ報道を利用した劇場型政治は、都市部の大衆に受け、政治に関心がない層を投票場へ動員することに成功した。それにより9月11日の投票結果は高い投票率を記録し、自民党だけで296議席、公明党と併せた与党で327議席を獲得した。この選挙はマスコミにより「小泉劇場」と呼ばれた。
2005年9月21日、小泉は圧倒的多数で首班指名を受け、第89代内閣総理大臣に就任する。10月14日の特別国会に再提出された郵政民営化関連法案は、衆参両院の可決を経て成立した。この採決で、かつて反対票を投じた議員の大多数が賛成に回り、小泉の長年の悲願は実現した。
なお、賛成票を投じた永岡洋治議員の自殺のように郵政民営化関連法案の成立には多くの事件が発生していた(葬儀に小泉が出席した後、故人の親族は本法案の賛成を表明)。
ポスト小泉
2005年10月第3次小泉改造内閣が発足。ポスト小泉と目される麻生太郎が外務大臣に、谷垣禎一が財務大臣に起用された。
この後2005年11月 - 2006年1月にかけて、構造計算書偽造問題、皇位継承問題、ライブドア・ショックと堀江貴文の逮捕、米国産牛肉輸入再開問題など、政権への逆風となる出来事が相次いで発生した。野党は攻勢を強め、9月の退陣へ向けて小泉内閣はレームダックに陥るのではないかとの予測もあった。しかし堀江メール問題で民主党が自壊したため内閣の求心力が衰えることはなく通常国会では「健康保険法等の一部を改正する法律」(後期高齢者医療制度を創設)などの重要法案を成立させている。なお堀江メール問題の後永田寿康議員は自殺している。
2006年(平成18年)8月15日の終戦の日に小泉は最初の総裁選の公約を果たして靖国神社へ参拝した。小泉はこの時のインタビューで自身の参拝理由を明確かつ丹念に提示することに努めている。
2006年9月20日の自民党総裁選では選挙前から確実視された安倍晋三が後継に選ばれる。翌9月21日に小泉の自民党総裁任期は満了し、9月26日に総辞職して内閣総理大臣を退任した(同日、安倍晋三が第90代首相に就任して第1次安倍内閣成立)。任期満了による退任は1987年の中曽根康弘政権以来であり、また、小泉政権は戦後4位であり21世紀最初の長期政権となった。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
バブル崩壊後の日本経済の「失われた30年」
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
小泉が派遣法の改正をしたおかげで、大部分の正社員の仕事が派遣に置き換わってしまいました。日本中にフリーターが激増してしまったのも、この男のせい。
小泉内閣時代の内閣ブレーンの一人で、経済と金融の大臣を兼任し、それまで3度、政府閣僚に選べられています。その後も諮問会とか委員会によく政府から呼ばれている人ですね。
慶應義塾大学総合政策学部の教授で、学歴も相当なもの、人材派遣業のパソナグループの会長でもあります。他にかなりの役職を受け持つ、まぁ多忙な人ですね。
2008年には韓国政府のアドバイザーとして顧問団に迎えられたり、小泉時代に総務大臣兼郵政民営化担当大臣に登用されて、郵政民営化推進で、自民党内部からも猛批判を受けた人です。
政策は
・所得税の最高税率を引き下げ(所得1000万円まで累進課税とする)
・解雇規制を緩和する
・同一労働同一賃金の法制化
・民間でできることは民間へ
以上は実現できていないか、あるいは骨抜きって感じで、多くは自民党内部の反対で押し切られていたみたいですね。
発言としては、財政悪化の要因は国債発行の乱発で日本の財政寿命は約3年とか、若者に自由を謳歌してもいいが引き換えに貧しくなるのも自由だ、頑張って成功した人の足を引っ張るななどがあります。
また格差社会の要因の一つは正社員という特権であるということもテレビで発言してますね。
平蔵を国賊と言ってる人たちは、恐らくバブル崩壊以後の失われた20年(30年?)の時代に、あまり良い事がなかった人が、非正規雇用を生み出したのは竹中のせいとか、自己責任ばかりが横行したのは平蔵のせいだ!と思っているからでしょうね。
また「時間内に仕事を終えられない、生産性の低い人に残業代という補助金を出すのはおかしい」と、まぁ私は定時に帰れという意味で、労働者の質の問題に触れていると思うのですが、これを悪く取る人もいたようです。
比較的合理的な理論で押し切るタイプの人ですが、やっぱり学歴・職歴が凄いのと、ズバズバ歯に衣着せぬ物言いの人なので、ものすごく好き嫌いが別れる人ではあると思います。特に既存の経済評論家や保守派の人には相当嫌われているようで。
人材派遣法の歴史は?
日本における派遣法の歴史
派遣法が施行されたのは、1986年7月1日です。 しかし、それ以前から人材派遣のようなことをしている会社は存在していました。 1980年代に入って雇用される労働者が増え、また業務請負という形態で派遣していたため、労働者保護の観点から派遣法が施行されることになったのです
労働者派遣法の歴史 荒井大
【派遣法の歴史】
[1985年(中曾根内閣)]
派遣法が立法される。
派遣の対象は「13の業務」のみ
[1986年(中曾根内閣)]
派遣法の施行により、特定16業種の人材派遣が認められる。
[1996年(橋本内閣)]
新たに10種の業種について派遣業種に追加。合計26業種が派遣の対象になる。
[1999年(小渕内閣)]
派遣業種の原則自由化(非派遣業種はあくまで例外となる)
この頃から人材派遣業者が増え始める。
[2000年(森内閣)]
紹介予定派遣の解禁。
[2003年3月(小泉内閣)]
労働者派遣法改正
例外扱いで禁止だった製造業および医療業務への派遣解禁。専門的26業種は派遣期間が3年から無制限に。
それ以外の製造業を除いた業種では派遣期間の上限を1年から3年に。
[2004年(小泉内閣)]
紹介予定派遣の受け入れ期間最長6ヶ月、事前面接解禁。
*鳩山政権による派遣法改正の動き*
1、製造業への派遣を原則禁止(常用型を除く)
2、日雇派遣、2か月以下の労働者派遣を禁止
3、登録型派遣の原則禁止(専門26業種を除く)
登録型…仕事がある時だけ雇用契約を結ぶもの。
常用型…仕事がなくても給料がもらえる(雇用契約を結べる)。
労働条件・労働基準めぐる法改正情報
http://labor.tank.jp/r_houkaisei/
派遣法 なぜ でき た?
もともと、労働基準法第6条で中間搾取の禁止が定められていますが、その規制を緩和する意味で制定されたのです。 労働者派遣法は、派遣事業の適正な運営と派遣労働者の雇用の安定、福祉の増進を目的としています。
派遣はいつから始まった?
日本の人材派遣の歴史は、1986年に「労働者派遣法」が施行されたことで始まり、これまで世の中の情勢にあわせ、何度も改正がなされてきました。
派遣法1999年の改正は?
1999年:対象業務が原則自由化となる(ネガティブリスト化) 規制緩和の波はさらに強く押し寄せ、適用対象業務の原則自由化(禁止業務のみを指定するネガティブリスト化)が実現。 一方で、建設、港湾運送、警備、医療、物の製造業務が禁止業務とされます。
人材派遣業の儲けの仕組み
人材派遣会社では、自社で雇用する派遣社員の労働力を派遣先の企業に提供することで「マージン」を上乗せした報酬を得ることで利益を出しています。 このシステムから、人材派遣業は「ピンハネ業だから楽して儲けている」などと揶揄されることがありますが、実際にはそれほど大きな利益があるわけではありません。
有期雇用派遣社員として働ける期間は最大3年
これは、2015年の派遣法改正により定められた内容です。 以前は派遣期間に制限はなく、派遣社員として長期間同じ部署で働くことができましたが、2015年の派遣法改正により「働けるのは3年間だけ」というルールに変更されました。
すぐに辞めてしまう理由
派遣で来た方がすぐ辞めてしまう主な理由としては次のようなことが考えられます。
仕事内容に馴染めない(未経験者が作業の手順や方法を理解できない)
職場に馴染めない(社内での決まりごとや雰囲気など)
地域や環境に馴染めない(他の地域から働きにきた場合など)
困ったことを相談できる人がいない(職場トラブルや将来のキャリアプランなど)
事前の研修や、就業後のフォロー体制などがない派遣会社だと、就業の前と後でのギャップが生じてしまい、「馴染めない…」と感じる機会が多くなります。
また、相談に乗ってくれる人がいないことで、不安や不満が退社に直結してしまうのです。
最初はほんの小さな「嫌だな…」と思う気持ちから始まったとしても、誰もフォローしてくれないために次第に勤務から足が遠のいてしまい、無断欠勤を続けた結果、そのままフェードアウトする。
派遣社員 何が問題?
単調な仕事や、いわゆる「誰でもできる仕事」を任されるため“やりがい”は生まれにくい特徴があります。 また仕事のやり方や方針に対して基本的に口を出すことができないため、働くことのモチベーションは維持しにくいでしょう。 なぜならそれが「派遣社員」の本質だからです。
派遣 時給上がった なぜ?
派遣は正社員と待遇が異なり、実際に働いた時間分のお金しかもらうことができません。 ボーナスや昇給などは基本的になく、企業によっては交通費の支給もありません。 そのため、その分が時給に上乗せされた形となり、高い時給に反映されているのです。
グループ内派遣のメリットは?
またグループ内派遣は、法律に則って雇用された派遣社員や正社員を雇うよりも、人件費を削減できるのが特徴です。 そのためグループ内派遣を許せば、専ら派遣のときと同様、企業はグループ内派遣からの派遣労働者ばかりを受け入れるようになり、正社員や法律に則った派遣社員の雇用を妨げることになりかねません。
派遣法 違反 どうなる?
当該法律に違反すると、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金刑が科せられます。 また、派遣先企業が更に派遣を行うことで利益もあげていた場合、労基法6条が規制する「中間搾取の排除」に該当するため、労基法違反にもなり、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金刑が科せられます。
なぜ派遣はダメなのか?
短期間での派遣就業では、労働者の収入が不安定になります。 また派遣会社、派遣先企業共に適正な雇用管理をすることが難しいという判断から、2012年の改正労働者派遣法で、日雇い労働者(日々もしくは30日以内雇用期間)の派遣は原則禁止となりました。 日雇派遣は条件に当てはまれば、派遣が認められています。
派遣が多い会社 なぜ?
まず、派遣会社が多い理由を室伏氏に聞くと「大手企業が人件費を削減したいがために、政府に構造改革を促した影響です」とキッパリ。 「企業としては人件費、社会保険料の負担が大きく、どうしても抑えたいコストです。 そこで大手企業を中心に構成されている経団連が自民党に働きかけ、派遣法の改正に踏み切らせました。
正社員 派遣 どっちが稼げる?
短期的に見た時、派遣の方が稼げるとお伝えした理由は、派遣の時給に高さにあります。 例えば月給25万円の正社員の場合、時給換算すると大体1500円程と言われています。 一方派遣はというと、条件の良い案件なら時給1800円という求人もあります。 正社員のように週5で8時間働く場合、月給は約32万円となります。
派遣社員 年収 いくら?
令和2年度の派遣社員の全国平均年収は約374万円でした。 専門性が高い職種ほど給料が高く、三大都市圏とそれ以外との地域差は、年収にして約54万円になります。 派遣社員の給料は人材派遣会社から支払われ、月末締め翌月給料日支払いであることが一般的です。
WDBのマージン率は?
どの派遣会社でもマージンはあるのですが、WDBはその率が高いです。 基本的なマージン率は「25%〜30%」とされているのですが、WDBでは34%に設定されています。
派遣 女性 多い なぜ?
一方、派遣社員という働き方を選んだ理由として女性がもっとも多く選んだのは「働く日数・期間を選べる」という選択肢でした。 同じ調査の中で今後も派遣社員として働きたいと答えた男性は3割にとどまったのに比べ、女性は4割と比較的高い割合を示しています。 派遣女性の中には、家事や育児しながら働いているという方も少なくありません。
フリーターと正社員 どっちが稼げる?
フリーターと正社員では、基本的に正社員のほうが高収入の傾向にあるようです。 厚生労働省の「令和2年賃金構造基本統計調査 結果の概要『雇用形態別にみた賃金』(p1)」によると、フリーターを含む非正規雇用の平均月収は男女計で21万4,800円。 正社員の平均月収は32万4,200円とされています。
派遣 1日いくら?
厚生労働省は、業種ごとの派遣料金の費用相場を公開しており、2021年4月時点では2020年度の結果が公表されています。 専門的な技術や知識が必要な職種の場合、1日あたりの平均料金は20,000~30,000円、それ以外の職業は10,000~20,000円が派遣料金の相場です。
派遣 1時間 いくら?
営業職種従事者の1人あたり1日8時間の平均派遣料金は2万1,083円、1時間あたりの平均派遣料金は2,635円となっています。
派遣会社 どれくらい抜いてる?
公表されていた派遣会社のピンハネの実態
私のように、フルタイムの派遣社員として働いている場合の、一般的な派遣料金の内訳。 派遣社員のお給料は、派遣先企業が派遣会社に払う「派遣料金」の70%。 30%が派遣会社の取り分。 派遣会社は派遣料金の30%をピンハネしてる!?
派遣 最低 賃金 2022 いくら?
2022年は10月1日から【時給1,072円】に改正されます。 この最低賃金は東京都内に派遣中の労働者を含みます。
派遣社員の人口は?
派遣の現状 | 一般社団法人日本人材派遣協会 2020年1~3月平均の派遣社員数は約143万人となりました。 雇用者全体(5,661万人、役員除く)に占める派遣社員の割合は2.5%となり、この割合は15年ほど大きな変化は見られず2~3%を推移しています。
なぜ派遣会社が多いのか?
まず、派遣会社が多い理由を室伏氏に聞くと「大手企業が人件費を削減したいがために、政府に構造改革を促した影響です」とキッパリ。 「企業としては人件費、社会保険料の負担が大きく、どうしても抑えたいコストです。 そこで大手企業を中心に構成されている経団連が自民党に働きかけ、派遣法の改正に踏み切らせました。
なぜ派遣はダメなのか?
単調な仕事や、いわゆる「誰でもできる仕事」を任されるため“やりがい”は生まれにくい特徴があります。 また仕事のやり方や方針に対して基本的に口を出すことができないため、働くことのモチベーションは維持しにくいでしょう。 なぜならそれが「派遣社員」の本質だからです。 派遣会社にとっての派遣社員は人的資源。
派遣会社のリスクは?
一番想定されうるリスクとしては、派遣事業で保有している集客チャネルや人材プールに、正社員雇用を希望する人材が少ないことや、経歴やスキルの関係から採用企業側の正社員としての採用ニーズがあまりないことがあげられます。
派遣社員 なぜ生まれた?
バブル崩壊以降、年功序列、終身雇用といった日本独特の雇用の在り方が問われ正社員のリストラが目立つようになってきた時期がありました。 そこで企業が求めたのが派遣社員です。 必要な期間、必要なポジションに労働力を充当できるのは企業にとって大きな魅力だったのかもしれません。 それに加えて、働く側の意識の変化があります。
派遣の悪いイメージは?
派遣のイメージは正社員に比べ、重要な仕事ややりたい仕事をやらせてもらえないイメージがあります。 人間関係ができて、気心がしれたころに辞めてしまう印象が強いので、仕事にまつわる悩みなどの相談がしづらいイメージがあります。 いつ雇用期間を切られるのかが全く予想できないため、将来に対して不安のある働き方だと思います。
派遣の仕事は何歳まで?
派遣に年齢制限はない
派遣労働者に年齢制限はなく、60歳以上で働いている方も存在します。 派遣会社への登録も、年齢制限はもちろん、性別や学歴、職歴、資格、スキル、経験などの条件も設けられていません。 即戦力として資格やスキル、経験が求められるイメージがあるものの、未経験者を歓迎している会社も数多くあります。
使えない派遣社員の特徴は?
「使えない……」交代になりやすい派遣社員の特徴
能力が自社の求める水準に達していない ...
能力に関して改善が見られない ...
注意やアドバイスに対して不機嫌になる ...
職場の規則に従ってくれない ...
派遣社員への教育内容を再考する ...
職場環境をチェックしてみる ...
交代を要請する ...
派遣元を変える
派遣社員の教育は 誰が する?
派遣スタッフの教育訓練に関しては、雇用主である派遣会社が実施すべきですが、派遣先の業務に密接に関連した教育訓練については、実際の就業場所である派遣先が実施することが適当であるとし、派遣先の正社員と同様の教育訓練を受けさせることが義務化されました。
派遣法改正案は「正社員の雇用」を守るためだった!?
非正社員は誰も救われない“矛盾と罠”
――国際基督教大学 八代尚宏教授インタビュー
2010.12.2
今年3月に閣議決定し、国会審議が行われていた労働者派遣法改正案は、首相交代などの混乱のなか、継続審議となった。08年秋の世界同時不況後、派遣労働の規制強化に向けた世論の高まりとともに注目を浴び、登録型派遣や製造業務派遣の原則禁止を柱とする本法案。今後、再審議で成立したとして、本当に非正社員は救われるのだろうか。検証するとともに、非正社員が真に救われる働き方やそれを担保する制度について、国際基督教大学の八代尚宏教授に話を聞いた。(聞き手/ダイヤモンド・オンライン 林恭子)
派遣法改正でも正社員は増えない
むしろ失業者が増える可能性も
――「派遣の原則禁止」を目指した派遣法改正案だが、これが実現すれば本当に非正社員は救われるのだろうか。派遣法改正案の問題点とともにお教えいただきたい。
それを明らかにするためには、まず派遣労働の規制緩和がなぜ行われたかを考えなければならない。
そもそも派遣社員などの非正社員の増加は、「小泉政権における新自由主義的な構造改革によってもたらされた」という認識が広まっているが、これはまったくの誤解である。なぜならこの規制緩和は、1999年に派遣労働の雇用機会の拡大と保護強化を目的とした国際労働機関(ILO)第181号条約に日本が批准したことに基づいており、2001年に成立した小泉政権誕生以前の話であるからだ。
この条約は、欧州を中心に失業率が高止まりしている状況下で、失業率を低下させるためにも有料職業紹介や派遣労働を容認し、不安定でも雇用機会を増やすことが先決だという事情から生まれたもの。日本も批准し、それ以前の派遣先の職種を厳しく制限した「原則禁止・例外自由」を逆転して、「原則自由・例外禁止」へと原則を大転換した。これに伴い、「当分の間」禁止となっていた製造業への派遣が、2004年に自由化されたに過ぎない。
したがって、規制緩和の目的は「雇用機会の拡大」にあったわけだから、それを元に戻して規制を強化をすれば、結果も逆になるのは当然だ。
朝日新聞が全国主要100社を対象に行った「派遣が禁止された場合の対応」へのアンケート(09年11月実施)によると、「他の非正社員に置き換える」(契約社員:36社、請負・委託:30社、パートタイム:22社)のがほとんどで、「正社員の増加で対応」はわずか15社だった。
小泉労働法制「改革」についての雑感
静岡県労働研究所 理事長 大橋 昭夫
小泉内閣は、昨年6月27日労働基準法の一部を改正する法律を成立させ、これが本年1月1日から施行されている。 この詳細については触れないが、この改正法は、有期労働契約の契約期間の上限の延長、有期労働契約の締結、更新及び雇い止めに関する基準、解雇権濫用法理の明文化、裁量労働制の一層の拡大を実現したもので、解雇規制を除き労働者に対して、大きな苦難を強いたものと評価される。 この改正は、もっぱら日本経団連の意向に沿うもので、この推進勢力は、小泉総理大臣のブレーンで総合規制改革会議議長宮内義彦オリックス会長を中心とするグループであったと言われる。 宮内議長は、「鉛筆型の人事戦略」を唱え、少数のコア社員を細い芯とし、これのみを保護し、その周りの木の部分に成功報酬型の社員を、さらに、その周りにパートタイマーや派遣労働者を配置し、これらの木の部分を必要に応じて調整することが、グローバル経済を勝ち抜く今後の経営戦略であることをあからさまに述べている。自分が生き抜くためには、大多数の労働者の生活など視野に入らないのである。 今回の労基法の改正は、労働者派遣法の「改正」による派遣業種の一層の拡大と相俟って、我が国の正規労働者の数を著しく減少させ、これをパートタイマー、派遣労働者等の不安定労働に代替させるものであって、わが国社会の労働秩序を根底から破壊することになる。 厚生労働省は、今回の改正法案の提出にあたって、「今日、我が国の経済社会においては、少子高齢化が進み労働力人口が減少していく一方、経済の国際化、情報化等の進展による産業構造や企業活動の変化、労働市場の変化が進んでいる。このような状況の下で、経済社会の活力を維持、向上させていくためには、労働者の能力や個性を活かすことができる多様な雇用形態や働き方が選択肢として準備され、労働者一人一人が主体的に多様な働き方を選択できる可能性を拡大すること、働き方に応じた適正な労働条件が確保され、紛争解決にも資するよう労働契約など働き方にかかるルールを整備すること、これらの制度の整備、運用に際しては、労使によるチェック機能が十分に活かされるようにすることなどを基本的な視点とする」と説明しているが、この視点は、余りにも労働者の生活実態を知らない「綺麗事」であり、役人の文章である。 私が指摘するまでもなく、わが国の経済社会の活力を維持、向上させていく最良の手段は、雇用の確保であり、人間らしい生活をするのに必要な賃金の保障である。 厚生労働省のいう「多様な雇用形態や働き方」という概念は空漠としており、その内容が如何なるものか明確でないが、派遣労働や有期契約による労働、更には残業代を回避するための裁量労働であると察しはつく。 これらの労働形態は、いずれも不安定雇用であって、多様な働き方を実現し、それが豊かな生活につながる契機となることは経験則上ありえない。 私の弁護士としての経験からすると、労働者は少々他と比べて賃金が低いとしても、雇用が安定的に確保され、将来の生活の見通しが立つ時にこそ、労働生活においても主体性を発揮でき精神的にも自由になれるものである。 いま、労働者の自己破産の申し立て件数が激増し、それがわが国の平均的な法律事務所の日常的業務になっている。 私もこの種の事件を数多く取り扱うが申し立てをする労働者の所得が低く、そのうちの少なくない者が、派遣労働者、有期契約労働者、フリーターであり、その所得水準が生活保護基準以下である者も存在する。 多様な雇用形態や働き方は、私の実感からすると、使用者の身勝手や彼らの生存権のみを保障するもので、労働者に対し永久に社会底辺に沈殿させる効用しかないように思われる。 私は、西ヨーロッパに見られる如く、「共生き」の思想を前提とした労働ルールの確立こそ、社会発展の源泉であると考えるし、小泉内閣の方向は、社会の不安定化を招来させることにしかならないと思う。 今回の労基法の改正で評価できる点は、唯一解雇権の制限法理が法文上明らかになったことのみである。 この規定は、小泉内閣の原案では、「使用者は、この法律又は他の法律の規定によりその使用する労働者の解雇に関する権利が制限されている場合を除き、労働者を解雇することができる。但し、その解雇が、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と解雇が原則自由になっていた。しかし、労働者の反対があり、最高裁で確立した解雇権濫用法理の精神に立ち帰り、現行の「解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」(労基法18条の2)となったのである。 これは、西ヨーロッパ諸国の解雇制限法に比べると極めて簡単な条項ではあるが、それでも法規範として、すべての裁判官の判断を拘束するもので一歩前進だと評価できる。 小泉構造改革は、今やすべての面にわたって失敗しているが、更なる労働「改革」は、労働者の生活をより一層困難にするもので、働く人々は、思想、信条、潮流、傾向を超えて、この流れに対抗する必要があろう。 わが国に憲法の精神に忠実な「働くルール」が確立されることを切に望むものである。それが真の意味での労働改革である。
破たんした小泉「構造改革」 社会と国民に何もたらした
貧困と格差 際限なし
「官から民へ」「改革なくして成長なし」―。ワンフレーズ政治で「構造改革」路線をひた走った小泉純一郎政治。その「本丸」とされた郵政民営化問題で、麻生太郎首相が迷走発言を続けるなか、小泉純一郎元首相や竹中平蔵元経済財政担当相らがマスメディアに盛んに登場し、「構造改革」路線の“復権”をはかる動きもみられます。「痛みに耐えれば、明日はよくなる」どころか、「生きていけない」と悲鳴があがるほどの貧困と格差の惨たんたる状況に国民を追い込んだのが「小泉改革」でした。歴史の審判はすでに下っています。
雇用のルール破壊
「派遣切り」・ネットカフェ難民
東京のど真ん中に、五百人もの人たちが衣食住を求めて集まった「年越し派遣村」。大企業の理不尽な「非正規切り」で「人間としての誇りを奪われた」「自殺も考えた」との声が渦巻きました。貧困を目に見える形でつきつけ、政治を動かしました。
「派遣村」に象徴される「使い捨て」労働の深刻な広がりは「構造改革」の名によるリストラの促進や労働法制の規制緩和がもたらしたものです。
この十年間で正規労働者が四百九万人も減り、その代わりに、非正規労働者が六百六万人も増えました。
自民、公明、民主、社民などの各党が賛成した一九九九年の労働者派遣法改悪。派遣労働を原則自由化し、「派遣」という形での「使い捨て」労働の増加に拍車をかけました。
二〇〇一年に発足した小泉内閣は、「構造改革」を加速。まず「不良債権処理」の名で中小企業つぶしをすすめ、〇三年には、企業がリストラをすればするほど減税をするという「産業再生」法を延長・改悪し、大企業のリストラを後押ししました。
一方、派遣法を改悪し、〇四年三月からは製造業への派遣を解禁しました。この中で、もともと危ぐされていた派遣労働者の労働災害が増加。〇七年の死傷者数(五千八百八十五人)は、〇四年と比べると九倍という激増ぶりを示しました。
ネットカフェで寝泊まりしながら「日雇い派遣」で働く若者の姿が、底なしに広がる「働く貧困層」の象徴となりました。
 |
公園や橋の下でダンボールハウス生活をしているホームレスを襲う日本人がいるが、明日は我が身とは知る余裕はなく忙しい。
|
ギリギリの生活を強いられている派遣労働の実態が大問題になり、日本共産党の論戦とあいまって政府でさえ派遣法の見直しを言い出さざるをえなくなりました。労働分野の規制緩和が破たんしたことは明確です。
しかし、米国の金融危機に端を発した景気悪化を口実に、〇八年後半、大企業は製造業を中心に大量の「派遣切り」「期間工切り」を始めました。被害は日増しに広がり、今日の日本社会を覆う最大の社会問題になっています。
景気のいいときには、正社員を派遣や期間工に置き換えて大もうけをし、景気が悪化したらモノのように使い捨てる―この大企業の横暴勝手を容易にする仕組みを作ったのが、労働の「小泉構造改革」であり、今日の事態は、まさに政治災害そのものです。

社会保障の連続改悪
医療崩壊・国保証取り上げ
「わずかな年金は減らされたうえ、保険料の天引きは容赦ない」「病気になってもお金がなければ病院にもいけない」―。「小泉構造改革」による社会保障の連続改悪によって、こんな苦難が国民を襲いました。
その大もとにあるのが、小泉内閣が決めた社会保障費の抑制方針です。二〇〇二年度から毎年、社会保障費の自然増分から二千二百億円(初年度は三千億円)削減されてきました。
抑制の対象は医療、介護、年金、生活保護と社会保障のあらゆる分野に及び、庶民への痛みの押し付けの結果、「生きること」自体が脅かされる実態が広がっています。
医療分野では、国民の負担増に加え、医療費削減を目的に医師数の抑制政策を続けたため、救急患者が救われない医師不足が社会問題化し、「医療崩壊」と呼ばれる事態が出現しました。
高すぎる国民健康保険料が払えずに正規の国保証を取り上げられた世帯は約百五十八万世帯にまで広がっています。受診を控え、手遅れで死亡する例は後を絶ちません。
そのうえ、国民生活の最後の命綱である生活保護さえ切り縮められました。老齢加算の廃止で、「朝はパン一枚、昼はうどん」「暖房費節約のため、ストーブをつけず布団に入る」「風呂の回数を減らす」など生活の根幹まで切り詰めざるをえない実態です。(〇八年一月、全日本民主医療機関連合会の調査報告)
こうしたなか、昨年四月に導入された後期高齢者医療制度に、国民の怒りが爆発しました。同制度に対する不服審査請求は全国で一万件超。「『高齢者はいずれ死を迎える、お金も手間もかけなくてよい』という、人間性を喪失した制度だ」などの怒りの声があふれています。
日本医師会など医療関係四十団体は〇八年七月、「社会保障費の年二千二百億円削減撤廃」を決議。国民の批判は、小泉内閣がしいた二千二百億円の削減路線そのものに向けられはじめました。
自公政権は社会保障費の削減路線の転換は明言しないものの、〇九年度予算案で一時的な手当てを行い、社会保障費の実質の削減幅は二百三十億円に“圧縮”せざるをえなくなっています。第二次小泉改造内閣で厚労相だった自民党の尾辻秀久議員でさえ、一月三十日の参院本会議で「乾いたタオルを絞ってももう水はでない。潔く二千二百億円のシーリングはなしと言うべきだ」と述べるなど、社会保障費削減路線の破たんを認めざるをえなくなっているのです。
庶民負担増 大企業は減税
7年間で国民に50兆円近くも
小泉政権以来の増税などで国民負担は、年間十三兆円も増えました。二〇〇二年度から〇八年度まで七年間の国民負担増を累計すれば、五十兆円近くになります。
その一方で、大企業・大資産家への減税は、一九九八年以降の十年間に行われたものだけでも、大企業に年間五兆円、大資産家に年間二兆円、あわせて年間七兆円以上になっています。十年間の累計では、四十兆円もの税収が失われました。
地方の切り捨て
激減する交付税・農業破壊
「交付税が四割減って半分も補てんされない」「このままでは吉野は死んでしまう」
昨年七月。奈良県吉野郡で開かれた日本共産党の演説会に先立ち、市田忠義書記局長と懇談した地元町村長らから、こんな嘆きの声が率直に寄せられました。
「地方ができることは地方へ」をうたい文句に自民・公明政権が強力に推進した「三位一体改革」は、農山漁村の自治体を存亡の危機にまで追い詰めています。
実際、「三位一体改革」が断行された二〇〇四年から三年間で、国庫補助負担金は四・七兆円、地方交付税は五・一兆円がそれぞれ削減されました。一方、国から地方への税源移譲はわずか三兆円しかありません。地方自治体にとっては差し引き六・八兆円のマイナスです。
全国知事会は昨年七月の知事会議で、このままでは一一年度までに地方自治体の財政が破たんするという衝撃的な試算を発表しました。とりわけ地方交付税が財政に占める比重が高い町村の財政は深刻です。
「地方交付税の削減など、国による兵糧攻めからの生き残り策」「周辺町村が財政破たん寸前だった」。全国町村会の「道州制と町村に関する研究会」が昨年十月にまとめた調査報告でも、市町村合併の理由の柱に「三位一体改革」による交付税削減を指摘する声が相次ぎました。
国会でも、鳩山邦夫総務相が「急激にやりすぎた。失敗の部分がある」(十二日、衆院本会議)と答弁。「三位一体改革」の破たんを認めました。
また、輸入自由化の促進による農業破壊、大型店の進出による商店街の「シャッター通り」化など、地方経済の冷え込みも深刻です。
しかし、自民党は、こうした“地方切り捨て”を反省するどころか、一〇年三月末の合併特例新法の期限切れを前に「おおむね七百から千程度の基礎自治体に再編」すると、いっそう合併を推進することを主張。さらに、政府は「時代に適応した『新しい国のかたち』をつくる」として道州制の導入を掲げています。
こうした動きには全国町村会が「強制合併につながる道州制には断固反対していく」と明記した特別決議を採択するなど、痛烈な反撃が巻き起こっています。
経済ゆがみ、ぜい弱に
「戦後最悪の経済危機」(与謝野馨経済財政担当相)―。内閣府が十六日発表した二〇〇八年十―十二月期の国内総生産(GDP)が実質で前期比3・3%減(年率換算12・7%減)となったニュースは、衝撃を与えました。金融危機の震源地である米国よりも急激な落ち込みだったからです。なぜこんなことになったのか。ここにも、背景に小泉内閣いらいの「構造改革」があります。
極端な輸出依存
「衝撃 石油危機以上 輸出依存体質響き」(「毎日」十七日付)、「外需依存の成長 岐路」(「日経」同)、「外需頼み 転換カギ」(「読売」同)といった見出しが商業メディアに目立ちました。極端なまでに輸出に依存した「経済成長」の破たんです。
「構造改革」を掲げた小泉内閣が発足(〇一年四月)して以来の変化をみてみましょう。内閣府のGDP統計によると、所得や個人消費は低迷しているのに、輸出が極端に伸び、〇八年に失速します。財務省の法人企業統計をもとに、製造業大企業(資本金十億円以上)の〇一年度と〇七年度を比較すると、経常利益は二・二五倍に増えています。ところが、従業員給与は〇・九八倍と減っています。大幅に増えたのは株主への配当と社内留保です。一方、民間信用調査会社の調査では、法的整理による企業倒産が増えています。ほとんどが中小企業です。
自動車、電機など輸出大企業を中心に従業員や中小企業・業者にしわ寄せする形で、大もうけし、もっぱら株主に還元するという構図です。
財界全面後押し
こうした企業体質をつくり出したのが、「構造改革」だったと、日本経団連会長の御手洗冨士夫キヤノン会長が述べています。
「これは、何といっても構造改革の進展がもたらしたもの」「多くの企業でも、筋肉質の企業体質が形成されている。過剰設備や過剰債務、過剰雇用という、いわゆる『三つの過剰』は完全に解消している」(〇八年六月十九日の講演)
文字通り、財界の全面的な後押しで推進されたのが小泉流「構造改革」でした。
財界が求める雇用など「三つの過剰」の解消を推進するテコと位置づけられたのが不良債権の強引な早期最終処理です。
小泉内閣が最初につくった「骨太の方針」(〇一年六月)は、不良債権処理の加速を通じて「効率性の低い部門から効率性や社会的ニーズの高い成長部門へとヒトと資本を移動することにより、経済成長を生み出す」とうたいました。小泉内閣は、リストラすればするほど減税する「産業再生」法を拡充、製造現場への労働者派遣を解禁しました。
懸念したことが
この結果、「成長」したのは、「筋肉質」になった輸出大企業や大銀行だけでした。「不良債権」扱いされた中小企業は倒産に追い込まれ、大量の失業者が生まれ、正社員から賃金の安い非正規社員への置き換えが進みました。
あまりにも、国内経済を脆弱(ぜいじゃく)にしてしまった「小泉構造改革」。政府の「ミニ経済白書」(〇七年十二月)でさえ、輸出は増加しているが、家計部門が伸び悩むなか、米国経済など海外リスクが顕在化した場合、景気は「厳しい局面も予想される」と懸念していたことが現実のものとなりました。
推進者がいま「懺悔の書」
小泉流「構造改革」をめぐり居直る竹中平蔵元経済財政・金融担当相と対象的に「懺悔(ざんげ)の書」を書いたのは、中谷巌氏。小渕内閣の経済戦略会議の議長代理として「小泉構造改革」の提言をまとめた中心人物です。竹中氏も同会議のメンバーの一人でした。
中谷氏は自著『資本主義はなぜ自壊したのか』のなかで、「一時、日本を風靡(ふうび)した『改革なくして成長なし』というスローガン」にふれ、「新自由主義の行き過ぎから来る日本社会の劣化をもたらしたように思われる」として、「『貧困率』の急激な上昇は日本社会にさまざまな歪(ゆが)みをもたらした」と指摘。「かつては筆者もその『改革』の一翼を担った経歴を持つ。その意味で本書は自戒の念を込めて書かれた『懺悔の書』でもある」と書いています。
郵政民営化矛盾が噴出
小泉内閣が「構造改革」の本丸と位置付けた郵政民営化。その矛盾が噴出しています。
「私は郵政民営化を担当した大臣」(二〇〇八年九月十二日、自民党総裁選の討論会)と自認する麻生太郎首相。その麻生首相が「(郵政事業の四分社化を)もう一回見直すべき時にきているのではないか。小泉首相のもとで(郵政民営化には)賛成ではなかった」(二月五日の衆院予算委員会)と言い出したのは、郵政民営化の破たんを象徴しています。
当時の小泉首相が「郵政選挙」までやって強行した郵政民営化のかけ声は「官から民へ」、「民間でできることは民間で」、「貯蓄から投資へ」でした。
「民間」といっても日米の大手金融機関のことです。もうけのじゃまになる郵便貯金、簡易保険などの郵政事業をバラバラにするのが四分社化でした。
「貯蓄から投資へ」といっても、庶民の預貯金を呼び込もうとしている証券市場の売買の六割以上は外国人投資家。その大半はヘッジファンドとよばれる投機基金です。庶民の虎の子の財産が食い物にされかねません。
安心、安全、便利を願う国民にとっては「百害あって一利なし」の郵政民営化。その矛盾のあらわれは小泉流「構造改革」路線そのものの破たんを物語っています。
“改革が足りないから”と居直る竹中氏だが…
小泉流「構造改革」がモデルにした本家の米国で、市場まかせの「新自由主義」路線が破たんしました。にもかかわらず、小泉流「改革」にしがみつこうとする勢力がいます。
一月一日放送のNHK番組で、小泉「改革」を推進した元経済財政・金融担当相の竹中平蔵氏は、大企業の「非正規社員切り」横行が社会問題になり、小泉「改革」に批判が強まっていることに、こう居直りました。
「大企業が非正規を増やすのは原因がある。正規雇用が日本では恵まれすぎている。正規雇用を抱えると企業が高いコストをもつ」
「同一労働同一賃金」をやろうとしたが、反対されたとし、「(年越し派遣村などは)改革を中途半端に止めてしまっているから、こういう事態が起きている」。
竹中氏が“止まっている”という「改革」の中身は、正社員の賃金水準を賃金が安い非正規社員の水準に引き下げるという意味での「同一労働同一賃金」です。大企業の総人件費を抑えるのが狙いです。これでは、働いても働いても貧困から抜け出せない「ワーキングプア」を労働者全体に広げることにしかなりません。
しかも、竹中氏は「問題は、いまの正規雇用に関して、経営側に厳しすぎる解雇制約があることだ」(「竹中平蔵のポリシー・スクール」二月一日付)として、企業業績が悪化したら従業員を抱え込まなくていいような「新たな法律を制定することが必要だ」と主張しています。正社員を含めた“解雇自由法”をつくれといっているようなものです。
一方で、「日本を元気にしないといけない」として、最優先課題にあげたのが法人税率をもっと引き下げることでした(一月一日のNHK番組)。竹中氏がかかげる「改革」はあくまで、大企業のための「改革」を徹底しろということにすぎません。
2021.09.30
国が見捨てた就職氷河期世代の絶望…バブル崩壊後の30年間で何が起きたか
当事者として、取材者として
小林 美希 プロフィール
2021年9月29日に自民党の総裁選が行われ、その後には総選挙が控えている。政治家が「中間層の底上げ」を訴えるが、考えてみてほしい。もとはといえば、中間層を崩壊させたのは政治ではなかったか。
国際競争の名の下で人件費を削減したい経済界は政治に圧力をかけた。不況がくる度に労働関連法の規制緩和が行われ、日本の屋台骨が崩れていった。最も影響を受けたのが就職氷河期世代だ。これからを担っていくはずだった若者たちが、非正規雇用のまま40~50代になった。
私が非正規雇用の問題を追って18年――。いったい、何が変わったのか。
大卒就職率6割以下の時代
1980年代には8割あった大卒就職率は、バブル経済が崩壊した1991年以降に下がり始めた。そして2000年3月、統計上、初めて大卒就職率が6割を下回る55.8%に落ち込んだ。大学を卒業しても2人に1人は就職できなかったというこの年に、私は関西地方で大学を卒業した。
その3年後の2003年3月に大卒就職率は過去最低の55.1%を更新。日経平均株価は同年4月に7607円まで下落した。この時の私はもちろん、当事者だった大学生の多くは雇用環境が激変するなかにいるとは気づかずにいた。
私の就職活動は苦戦した。約100社にエントリーシートを送り、50社は面接を受けた。神戸に住んで大学に通っていた私の就活の主戦場は大阪で、面接を受けるために毎日のように大阪周辺を歩き回った。最終的に内定が出たのは消費者金融会社の1社のみだった。
卒業後に東京で就職活動をやり直し、ハローワークに通った。新聞広告の求人を見て応募した業界紙の「株式新聞」に採用が決まった。就職試験の日、「うちは民事再生法を申請したばかりですが」と説明があり、倒産しかけた会社に就職することに悩んだが、「面白そうだ」という直感が勝った。
この株式新聞時代に出会い、後の私の記者活動に影響を与えたのが、伊藤忠商事の丹羽宇一郎社長(当時)だ。丹羽氏との出会いがなければ、私は就職氷河期世代の問題を追及しなかったかもしれない。
新人の時には経済記者として食品、外食、小売り、サービス業界を担当。商社の担当も加わり、出席した伊藤忠商事の記者懇談会で初めて丹羽氏に挨拶をする。記者に囲まれていた丹羽氏に私は「社長の役割とは何か」と聞いた。この若気の至りとも言える質問に対し、丹羽氏は真顔で「経営者とは、社員のため、顧客のため、そして株主のためにある」と答えてくれたのだった。
若者が疲れ切っている…なぜ?
株式新聞入社から1年後の2001年の初夏、毎日新聞が発刊(現在は毎日新聞出版)する『週刊エコノミスト』編集部に契約社員として転職した。私はだんだんと雑誌の仕事に慣れていき、天職と思って没頭していた。深夜や明け方に及ぶ校了作業は達成感があり、職場で夜を明かして新聞をかぶってソファで寝ていたこともあった。
これはマスコミ特有の働き方かと思っていたが、この頃、金融、製造、サービス業などに就職していった友人たちも長時間労働というケースが多かった。そのうち、充実感とは違った何かがあると感じ「なにかおかしい。若者が疲れ切っている」と首をかしげるようになっていった。
その疑問が確信に変わったのは、2003年前後に上場企業の決算説明会で経営者や財務担当役員らが強調した言葉を聞いてからだ。
「当社は非正社員を増やすことで正社員比率を下げ、利益をいくら出していきます」
2001年のITバブル崩壊から間もなくてして企業利益がV字回復し「失われた10年」が終わるかのように見えた。私はこの利益回復は非正規雇用化で人件費を削減したことによるものに過ぎないと見た。これでは経済を支える労働者が弱体化すると感じた私は、若者の非正規雇用の問題について企画を提案した。
『週刊エコノミスト』の読者層の年齢は高く、若者の雇用問題をテーマにしても読まれないという理由で、企画はなかなか通らなかった。さらに世間で浸透していた「フリーター」という言葉の印象が自由を謳歌しているイメージが強く、若者は甘いという風潮があるなかでは、ハードルが高かった。
悩んだ私は、再び、若気の至りの行動に出た。伊藤忠商事の丹羽氏にアポイントをとって、企画が通らないこと、企画が通らなければ転職したほうが良いか迷っていると人生相談をしたのだ。若者の非正規雇用化が中間層を崩壊させ、消費や経済に影を落とすと見ていた丹羽氏は「同じことを3度、上司に言ってごらんなさい。3度も言われれば根負けして上司は必ず折れるから」とアドバイスしてくれた。

私は企画が通らないまま非正社員として働く若者の現場取材を進めた。その頃、ある会合で話したコンビニ大手の社長が「息子がフリーターで……」と悩む胸の内を明かしたことがヒントになり、デスクや編集長を説得した。
「子どもの就職や結婚を心配するのは立場を超えて一緒のはず。読者の子どもを想定して、タイトルを若者とせず、娘や息子に変えたらどうか」
企画を提案し始めてから数か月経った2004年5月、ついに第2特集で「お父さんお母さんは知っているか 息子と娘の“悲惨”な雇用」を組むことが実現した。非正規雇用に関するデータを探し、マクロ経済への影響など当時は存在しなかったデータはシンクタンクのエコノミストに試算してもらった。
この特集について慶応大学(当時)の金子勝教授や東京大学の児玉龍彦教授がそれぞれ大手新聞の論壇コーナーで取り上げてくれたことで、続編が決定。第1特集となって「娘、息子の悲惨な職場」がシリーズ化した。
富の二極分化で「中間層崩壊」
この頃の若年層の失業率は約10%という高さで、10人に1人が失業していた。内閣府の「国民生活白書」(2003年版)により、2001年時点の15~34歳のフリーター数が417万人に上ると公表されると社会の関心が若者の雇用問題に向いたが、企業側の買い手市場は続き、労働条件は悪化していく。
パート・アルバイト、契約社員や派遣社員として働き、休日出勤やサービス残業の日々でも月給が手取り16万円から20万円程度のまま。正社員でも離職率の高い業界や会社での求人が多く、ブラック職場のため過労で心身を崩すケースが続出した。
社会保険料の負担から逃れるために業務請負契約を結ぶ例まで出現。大企業や有名企業ほど、「嫌なら辞めろ。代わりはいくらでもいる」というスタンスで、若者が使い捨てにされた。こうした状況に警鐘を鳴らすためには、経営者の見方を取り上げなければならないのではないか。
2005年1月4日号の『週刊エコノミスト』では、ロングインタビュー「問答有用」のコーナーで経済界の代表的な経営者であった丹羽氏に中間層の崩壊について語ってもらった。この時点で、若者の労働問題について本気で危機感を持つ経営者は私の知る限りでは他にいなかった。丹羽氏はこう語った。
富(所得)の2極分化で中間層が崩壊する。中間層が強いことで成り立ってきた日本の技術力の良さを失わせ、日本経済に非常に大きな影響を与えることになる。中間層の没落により、モノ作りの力がなくなる。同じ労働者のなかでは「私は正社員、あなたはフリーター」という序列ができ、貧富の差が拡大しては、社会的な亀裂が生まれてしまう。
戦後の日本は差別をなくし、平等な社会を築き、強い経済を作り上げたのに、今はその強さを失っている。雇用や所得の2極分化が教育の崩壊をもたらし、若い者が将来の希望を失う。そして少子化も加速する。10~15年たつと崩壊し始めた社会構造が明確に姿を現す。その時になって気づいても「too late」だ。
企業はコスト競争力を高め、人件費や社会保障負担を削減するためにフリーターや派遣社員を増やしているが、長い目でみると日本の企業社会を歪なものにしてしまう。非正社員の増加は、消費を弱め、産業を弱めていく。
若者が明日どうやってご飯を食べるかという状況にあっては、天下国家は語れない。人のため、社会のため、国のために仕事をしようという人が減っていく。
それが今、現実のものとなっている。
格差はこうして固定・拡大化した
丹羽氏のインタビューが掲載された年の8月8日、小泉純一郎首相(当時)が郵政民営化を掲げた解散総選挙に打って出て圧勝し、規制緩和路線に拍車がかかっていく。小泉郵政選挙の投開票は9月11日。その1週間後の9月18日には一般派遣の上限期間が3年とされる改正労働者派遣法が公布され、2週間待たずの9月30日施行で、いわゆる派遣の「3年ルール」ができた。
この派遣の「3年ルール」とは、表向きには派遣で同じ職場で3年が過ぎたら正社員や契約社員などの直接雇用にすることを促す改正だったが、実際には多くの派遣社員が3年の期間直前で契約を打ち切られることになった。同じ年に労働基準法も改正されて非正規雇用の上限期間が3年になったことで、非正社員が“3年でポイ捨て”され、非正規雇用のまま職場を転々とせざるを得ない労働環境が整備された。
1995年に旧日経連が出した「新時代の『日本的経営』」で雇用のポートフォリオが提唱され、景気の変動によって非正規雇用を調整弁とする固定費削減が図られて10年経った2005年に「3年ルール」ができた。ここが分岐点となり、日本は格差を固定化させ、格差を拡大させる路線を歩んでしまったのではないだろうか。
本来なら、2007年から団塊世代の定年退職が始まるため人手不足を補うという意味で、まだ20~30代前半で若かった就職氷河期世代を企業に呼び込むチャンスがあったはずだ。大卒就職率はリーマンショック前の2008年3月に69.9%まで回復したが、卒業後数年が経った非正社員は置き去りにされた。
問題提起し続けるために
小泉郵政選挙を機に私は、「もし自分が政治家だったら、何を問題にし、何の制度を変えていくか」ということを、より強く意識するようになった。就職活動をしていた大学時代に講座を聴いて影響を受けた、朝日新聞大阪本社の新妻義輔編集局長(当時)の言葉を思い出していた。
「人の苦しみを数字で見てはいけない。小泉構造問題に苦しむ人が1人でもいるのなら、それを書くのが記者だ」
新妻氏は若い記者時代に森永ひ素ミルク事件(1955年に森永乳業の粉ミルクにひ素が混入して多くの被害者が出た事件)を追っていた。事件の担当医に「被害者は何%か」と数字を聞いた時に、医師から注意を受けた経験からの教訓だという。
就職氷河期世代が抱える問題は、まさに非正規雇用を生み出す法制度という小泉構造問題が起因しているはず。それを問題提起し続けることは、私の役割なのではないか。労働問題に特化するには組織にいては限界があると考えた私は、小泉郵政選挙から1年半後の2007年、フリーのジャーナリストになった。
絶望と諦めのムードが蔓延した
第一次安倍晋三政権(2006年9月から2007年9月)が就職氷河期世代向けに「再チャレンジ」政策をとったが、政権が短命に終わるとともに支援は下火になった。2008年のリーマンショックが襲い、就職氷河期世代だけでない多くの人が職を失った。
政府は就職氷河期世代の支援というよりは、支援事業を担う民間企業を支援したと言える。国は15~34歳の「フリーター」対策の目玉政策として2004~06年に「ジョブカフェ」のモデル事業を行っており、同モデル事業を行った経済産業省から委託を受けた企業が異常に高額な人件費を計上していたのだ。
調べると、ジョブカフェ事業ではリクルート社が自社社員について1人日当たりで12万円、コーディネーターに同9万円、キャリアカウンセラーに同7万5000円、受付事務スタッフに同5万円という“日給”を計上していたことが分かった。『週刊AERA』(2007年12月3日号、同年12月10日号)でスクープ記事を執筆すると、国会でも問題視された。
このジョブカフェでは委託事業が何重にも再委託され、税金の無駄も指摘した。昨年問題になった新型コロナウイルスの感染拡大の対策で多額の委託料が電通に支払われているにもかかわらず、何重にも委託されている問題はなんら変わっていないのだ(参照「給付金『再々々々委託』の深い闇…10年以上前から全く変わっていない」)。
就職支援事業が企業の食い物にされる一方で、就職氷河期世代の非正社員がやっと正社員になれるかもしれないというところで契約を打ち切られる。そうしたことが繰り返され、いくら頑張っても報われずに絶望の淵に追いやられた。正社員になったとしてもブラック職場で追い詰められ、心身を崩して社会復帰できないケースも少なくはない。こうした状況が続いたことで、絶望と諦めのムードが蔓延した。
2010年代に何が起きたか
2009年3月に日経平均株価はバブル崩壊後最安値の7054円をつけ、2010年3月の大卒の就職率は60.8%に落ち込んだ。2012年12月に第2次安倍内閣が発足すると、あたかも「アベノミクス」によって新卒の就職率が高まったかのように見えた。しかし、それは、団塊世代が完全にリタイアするタイミングが重なったことによるもので、15~59歳の労働力人口がピーク時より500万人減っていたことが後押ししただけだった。
安倍政権が打ち出した「女性活躍」の名の下で、企業は人手不足を補うためにブランクのある“優秀な”主婦の採用に乗り出し始め、専業主婦の間には「働いていないと肩身が狭い」という意識が一時的に広がった。
一方で、相も変わらず就職氷河期世代は置き去りにされた。2015年に専門職も含めた派遣で全職種の上限期間が3年になり、同年は労働契約法が改正されて有期労働契約が5年続くと労働者が希望すれば期間の定めのない「無期労働契約」に転換できるようになった。2005年にできた「3年ルール」と同様、制度は悪用され、派遣は3年で“ポイ捨て”、非正規雇用の全般でも5年で“ポイ捨て”が広がった。
安倍政権で内閣府に就職氷河期世代支援推進室が設置され、2019年に「就職氷河期世代支援プログラム」が策定され、3年間で30万人を正社員化すると掲げたが、国は就職氷河期世代の中心層を2018年時点で35~44歳として(次ページ図)、最も支援が難しい40代後半や50歳を過ぎた層に重点を置かずにいる。そして、支援プログラムがこれまでの施策の焼き直しの域を脱しないことから、就職氷河期世代の絶望は深まった。
就職氷河期世代の非正社員「約600万人」
いったん絶望し、諦めてしまえば、どんな支援があったとしても届きにくくなる。私が就職氷河期の問題を追ってから18年が経つ。16年前のインタビューで丹羽氏が言及した通り、もはや「too late」の状況に陥っているのかもしれない。現在、35~49歳の非正社員は約600万人に膨らんでいる。もはや誰も解決の糸口を掴めないくらい、事態は深刻になる一方だ。
自民党政治の下で、製造業の日雇い派遣が解禁され、労働者派遣は今や全ての職種で期間の上限が3年になった。就職氷河期世代を置き去りにしたまま、業界団体のロビー活動も後押しして外国人労働の拡大が図られた。「女性活躍」は女性に仕事と家事と子育て、介護の両立を押し付けるだけ。「働き方改革」や正社員と非正社員の「同一労働同一賃金」も、実態は伴わない。
就職氷河期を追うなかで、そのライフステージに寄り添い、周産期医療や看護、保育の問題もライフワークになったが、全て構造問題がある。国が作る制度が密接に関わり、政治が現場を疲弊させている。新型コロナウイルスが蔓延するなか、政治の機能不全が鮮明となった。総選挙を前に、これまでを振り返らざるを得ない。
政治家にしがらみがあれば、正しいことが言えなくなる。けれど、この18年の間に分かったことがある。世論が盛り上がれば、政治は正しい方向に動かざるを得なくなるということだ。その世論を作るのが、現場の声であり、現場の声を活字にして伝えるのが私の役割だ。就職氷河期世代の問題を解決するのは困難だろう。しかし、目指すべき道が見えなくならないよう、私は書き続けていきたい。
氷河期世代がこんなにも苦しまされている根因
問題の根が深く支援プログラムでも救えない
岩崎 博充 : 経済ジャーナリスト
著者フォロー
2019/08/02
最近になって、政府が重い腰を上げて取り組み始めたものに「就職氷河期世代」の問題がある。「ロストジェネレーション世代」とも言われるが、2019年現在35~44歳のアラフォー世代の貧困問題と言っていい。
もっと正確に言うと、1993~2004年に学校卒業期を迎えた人である。バブル崩壊後の雇用環境の厳しい時代を余儀なくされ、高校や大学を卒業した後に正社員になれず、非正規社員やフリーターとして、その後の人生を余儀なくされた人が多かった世代の問題だ。
厚生労働省の支援プログラムは功をなすのか
この就職氷河期世代を対象とした支援プログラムが、3年間の限定付きではあるが厚生労働省の集中支援プログラムとしてスタートしている。支援対象は多岐にわたり、少なくとも150万人程度が対象者。3年間の取り組みによって、同世代の正規雇用者を30万人増やすことを目指している。
もっとも、わずか3年の支援プログラムで就職氷河期世代が背負った「負のスパイラル」が断ち切れるとは到底思えない。もっと継続的で長期のスパンに立った構造的改革を実施すべきだ……、という意見も数多い。
全国の自治体が取り組む「ひきこもり対策」もその効果を期待する声は多いものの、成果については疑問の声も多い。
就職氷河期世代とはいったい何だったのか。いまなお、同世代1689万人(2018年)のうち約371万人が現在も正規就労できずに、フリーターやパートの人がいると言われる。推定で61万人いると言われる40~64歳の「中高年ひきこもり」も、この世代の割合が突出しているとされる。
因果関係を立証はできないが、京都アニメーション放火殺人事件を起こしたのは41歳の男だった。最近の凶悪犯罪に、この世代の姿が目についていると感じている人もいるのではないか。世帯別の平均月収を5年前と比較すると、35~44歳の世帯の給与だけが低いというデータもある。「アラフォー・クライシス」とも言われるが、この世代の人々が抱える闇とは何か。彼らを救うために社会はどうすればいいのか。
就職氷河期世代と呼ばれる人々が どんな人生を歩いてきたのかはすでによく知られている。生まれて以降、社会人になるまでは比較的順風満帆で、バブル経済の恩恵を受けて学生時代までは恵まれた人生を歩んだ人が多かった。
ところが、学生から社会人になる際に日本は空前の不況に見舞われる。
氷河期世代が体験した無間地獄
1990年代後半から2000年代前半にかけて、日本経済はどん底とも言えるような状態にあった。1990年代前半に不動産バブルが崩壊し、その後世界的な景気後退期にさしかかり、1997年にはアジア通貨危機が世界を襲う。日本では、山一證券が経営破綻し、北海道拓殖銀行など金融機関の連鎖破綻が起きたときでもある。
さらに、2000年にはアメリカ発のITバブル崩壊が起こる。日本も大きな影響を受け、1990年代後半から2000年代前半に就職活動を行った世代は、厳しい就職氷河期にさらされる。とりわけ2000年前後は、大卒でも2人に1人しか就職できない時代を経験することになる。
同世代の非正規社員は371万人(2018年、総務省統計局、労働力調査基本集計より)で、正規雇用を希望しながら非正規雇用で働いている人は50万人に達する。非労働力人口のうち、家事も通学もしていない無業者も約40万人いる。
こうした現実に、厚生労働省も2018年度から就職氷河期世代を正社員として雇った企業に対する助成制度をスタート。「35歳以上60歳未満で、正規雇用労働者として雇用された期間が1年以下、過去1年間に正規雇用されたことがない人」を正社員として雇った企業に助成金を出すというものだ。
「特定求職者雇用開発助成金(長期不安定雇用者雇用開発コース、2019年4月より安定雇用実現コースに変更)」と呼ばれる制度で、無職や非正規社員を正社員として採用した中小企業に対して、1人当たり第1期30万円(大企業は25万円)、第2期30万円(同)、合計で60万円(同50万円)を1年間支給する制度だ。ハローワークを通して、求職活動することが条件になる。
一方、内閣府がこの6月に発表した文書によると、政府を挙げて3年間の集中支援プログラムを実施。次のような人を支援対象としてざっと100万人を救済するという。
①正規雇用を希望していながら不本位に非正規雇用で働く者(少なくても50万人)
➁就業を希望しながら様々な事情により求職活動をしていない長期無業者
③社会とのつながりを作り、社会参加に向けてより丁寧な支援を必要とする者など
具体的には、「安定就職に向けた支援プログラム」 「就職実現に向けた基盤整備に資するブログラム」「社会参加実現に向けたプログラム」などを立ち上げ、民間企業や市町村などと連携しながら就職氷河期世代の自立を促すとしている。
「40歳前後への職業訓練は無意味」「10年遅い」という批判も多いが、実際にこれまで政府は「自己責任論」を盾に同世代への支援には手を付けてこなかった。しかし、未婚率の高止まりや人口減少の原因の1つであることが明白となり、政府も腰を上げざるをえなくなったというのが真相だ。
ちなみに、この世代が注目されたのは、朝日新聞が今から10年以上前に同世代を「ロストジェネレーション」と名づけて、悪戦苦闘する人々をテーマにキャンペーン報道を行ったことがきっかけだ。
今後の日本の大きな問題になると指摘し、大量退職を迎えていた団塊世代以上に注目すべき問題として取り上げている。2007年の元旦から始まったこのキャンペーン報道は、翌年のリーマンショックと重なって注目された。低い時給で過酷な労働環境を強いられながらも、ネットカフェで泊まり歩き、中には餓死する若者の姿も報道されている。
ロストジェネレーション世代という言葉は、やがて就職氷河期世代と名を変えつつ、当時25~34歳だった若者もいまや年齢を重ねて35~44歳となり、10年前に比べてやや減少したものの、いまなお厳しい生活を余儀なくされている人も少なくない。
10年前に「フリーター」や「ニート」だった世代は、いまも「非正規社員」や「引きこもり」と呼ばれ、いまなお苦しい生活を送っているのは間違いないだろう。氷河期世代の「無間地獄」という呼び方もされる。
40歳で非正規社員として、時給1000円前後で働き続ける独身の男性は「いまだに1度もボーナスを貰ったことがない」「結婚なんて夢のまた夢」「時給は上がっても物価も上がった」と証言する。
なぜ就職氷河期世代は「捨てられた」のか?
就職氷河期の悲惨さはどの程度だったのか。統計データから見ても、その現実はよくわかる。例えば、大卒の「有効求人倍率」の推移を見ると、就職氷河期に入る直前の1991年には1人の求人に対して求職数は1.4倍あった。しかし、その2年後の1993年には1倍を割り込み0.76倍まで下落する。
以後、2006年(1.06倍)と2007年(1.04倍)を除いて、2014年までの約19年間。わが国の有効求人倍率は1倍を下回って推移する。1999年には0.5倍を割込み0.48倍にまで下落。2人で1社の求人を奪い合う状態になる。リーマンショック時には、0.47倍(2009年)にまで下落している。
ちなみに、アベノミクスの開始とほぼ同時に、有効求人倍率は1倍を回復したのは事実だが、これは団塊世代のリタイアと少子化の深刻化によって人手不足が顕著になったほうが大きい。アベノミクスの成果として、有効求人倍率が1倍を超えたと単純に捉えるのは危険だ。
ここで注目したいのは、就職氷河期世代の中でもいまだに非正規雇用を余儀なくされ、最悪ひきこもりになっている原因はどこにあるのかだ。そこには、個々の責任というよりも、日本特有のさまざまな悪しき制度や仕組みが根本的な原因といえる。同世代が陥った無間地獄の原因と本質をピックアップすると、大きく分けて次の5つのポイントが考えられる。
原因その1◆日本特有の「新卒一括採用」
世界でも例を見ない新卒一括採用が、日本企業の強みであった時代はとっくに終わっているが、就職氷河期世代の人々にとつては最悪の結果をもたらした。新卒以外での中途入社が難しく、とりわけ非正規雇用だった人材の中途採用には慎重な企業が多い。2人に1人しか正社員として就職できなかった就職氷河期世代にとって、その後、正社員として雇用される機会を奪われることになった。
新卒一括採用の背景にあるのが、終身雇用制と年功序列だ。とりわけ、氷河期世代以前の好景気時に大量採用された社員があふれている現実は、運よく正社員になれた就職氷河期世代も、企業の中でこの大量採用組に苦しめられることになる。
原因その2◆大手企業の労働組合が会社側に寝返った?
戦後、日本の労働組合は強い力を持っていた。それが、高度経済成長時代を迎えてバブル景気に沸いた頃には、すっかり企業と仲良しコンビになり、バブル崩壊による大リストラ時代には、企業の言うことを素直に聞く傀儡(かいらい)団体に成り下がってしまった。就職氷河期世代が就職難に喘いでいた頃には、既存の正規社員も自己の雇用を守るのに必死となり、新卒が極端に減少していることにも目をつぶった。
企業別労働組合の限界とも言えるが、「産業別労働組合」や「クラフトユニオン(職種別労働組合)」のシステムに転換していれば、こんな事態にはならなかったかもしれない。企業別労働組合からの脱出を目指す政党が現れないのも、就業者の80%を超す「サラリーマン(正規、非正規などを合計)大国・日本」にとっては不幸な話だ。
原因その3◆小泉政権時代の非正規社員の規制大幅緩和
就職氷河期世代が不幸だったのは、2000年代はじめに小泉政権が誕生し、非正規社員の規制を大幅に緩和したことだ。それまで許されなかった製造業での非正規雇用を全面的に緩和し、その影響で大企業は正社員の採用を大幅に抑え、非正規雇用を増やす雇用構造の転換を進めることができた。
就職氷河期世代の人たちも、この規制緩和がなければ新卒採用されなかった人でも、中途から正社員になる道はかなり多かったはずだ。そういう意味でいえば就職氷河期世代の悲劇は、小泉政権時代の規制緩和によってもたらされたとも言える。
労働条件の非常識な劣悪化
原因その4◆企業本位の労働環境社会
就職氷河期世代を苦しめた背景の1つに、非正規社員を直接雇用しないまま長年使い続ける慣行があった。
日本の製造業を支える工場での労働力をはじめとして、コンビニやファミレスといった安価で質の高いサービスを支えてきたのは、就職氷河期世代を中心とする非正規雇用の人たちだ。先進国の中では最低レベルの賃金で、長時間労働を余儀なくされた同世代が、日本経済を底辺で支えてきた、といっても過言ではない。この非正規労働者を守るための手段がほとんどないのが現実だ。
問題は、そうした過酷な非正規社員の現状を横目で見ながら、労働基準監督署などの労務管理当局が怠慢を続けたことだ。加えて、司法も貧困問題に対して厳格な判断を避け続けてきた。
そもそも日本では、海外では常識になっている企業内でのいじめやパワハラに罰則規定がない。経団連などの反対で罰則規定が外されたのだが、検察や司法がもっと労働者の立場に立っていれば、就職氷河期世代の悲劇はもっと少なくて済んだのかもしれない。
さらに、下請け会社や個人を元受け会社から守る「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」の法整備が行われたのも2003年以降のことだ。
こうした法律の不備や労務管理当局の怠慢が、同世代を苦しめている一因でもある。政府と密接な関係のある芸能プロダクションと所属芸人との間に正式な契約書がなくても通用する――。それが日本の労働環境の常識だとしたら、あまりにお粗末だ。
原因その5◆起業、独立に厳しい社会環境
もう1つ原因があるとすれば、正社員になれなかった就職氷河期世代が、起業して自営業になるという道があったにもかかわらず、その道へあまり進めなかった現実がある。日本では、そういったビジネス環境が整っていないためだ。
何の実績もない若者に事業資金を融資してくれる銀行はほとんどないし、連帯保証人の問題もある。政府の開業資金融資制度も、ハードルが高く、あまり現実的ではない。起業家の才能や熱意を評価して、潤沢な起業資金を融資する投資家が多いアメリカとは大きな違いだ。
ただ、最近は「クラウド・ファンディング」など変革の兆しもある。同世代も、日本に閉じこもっていてはいけないのかもしれない。
支援プログラムが役に立たないこれだけの理由
さて、厚生労働省が今年5月に発表した就職氷河期世代への就職支援プランだが、はたして有効なプランと言えるのか。
施策の方向性としては、「相談、教育、訓練から就職まで切れ目のない支援」を行い、ハローワークに専用窓口を設置。キャリアコンサルティング、生活設計面の相談、職業訓練の助言、求人開拓などの各専門担当者のチーム制によるきめ細かな「伴走型支援」を実施するとしている。
ただ、結論から言うと、就職氷河期世代に対する救済プログラムが本当に機能するのかどうかは疑わしいところだ。例えば、「地域若者サポートステーション」と呼ばれる就労サポート窓口が全国に175カ所設置されているが、40歳以上の就職氷河期世代に対する公的支援は全国でわずか十数カ所開設されるだけだ。
通称「サポステ」も、15~39歳のニートやひきこもりを対象にした制度だが、40歳以上のひきこもりは推計で61万人、サポステ効果も限定的と言わざるをえない。
また前述した特定求職者雇用開発助成金も最大60万円が企業に支払われるが、2018年度に給付された金額はわずかだ。その金額はあまりにも少ない。
筆者の個人的な感想だが、企業にお金を出すのではなく、同世代の非正規雇用者に自立支援金といった名目で、直接資金を融資するほうがいいのではないか。そのお金で起業するのもいいし、海外を放浪してくるのもいい。先進国の多くは、大学を卒業してすぐに就職するのではなく、海外で見聞を広げる制度が充実している。
就職氷河期世代にターゲットを絞って救うプログラムもいいが、本質は「貧困問題」と同じだ。最近になって、NHKも取り上げた「外国人技能実習生の奴隷化」問題にしても、結局は就職氷河期世代だけでは対応しきれなくなった人口減少、人手不足の対応策として、海外の留学生がターゲットにされているだけなのかもしれない。
京アニ放火事件のような凶悪犯罪の加害者をネットでは「無敵の人」と呼ぶ。失うものが何ひとつない、無敵状態の人という意味だ。今後、10年が経過して彼らが45歳から54歳になったとき、日本はどうなっているのか。このロストジェネレーション世代が、その時まだ「無敵の人」であるとしたら、その社会はあまりに理不尽だ。
日本の「失われた20年」と構造改革の失敗
1990年代に始まる日本経済の長期停滞は、2002年には終わらず今も続いており、この間の日本経済を「失われた20年」と呼ばれることが多くなってきた。日本の名目GDPで確認すると、1990年から2010年までほぼ500兆円前後で停滞したまま推移している。他の国がGDPを上昇させる中で、日本だけが成長を止めたまま20年が経過している。(図1)国民一人あたりの名目GDPでは、1990年代に世界3位くらいだったものが、2007年19位、2008年23位、2009年19位と大きく順位を落としている。(図2)日本では物価が上昇しないが給料も上がらないという状況が続いており、消費や投資などの内需が増えていない。産業分野でも、かつて世界を席捲していたエレクトロニクス市場で軒並みシェアを落としている。日本市場では日本製品が幅を利かせているが、海外ではLGやサムソンがシェアのトップ。日本製品は一部のお金持ちの趣味のブラ※4ンドになっている。鉄鋼でも、アルセロール・ミッタルが世界一の生産量を誇っており、新日鉄は中国や韓国のメーカーにも抜かれて4位(2009年)となっている。 小泉政権が主導した構造改革は、日本の成長のためには聖域なき構造改革が必要だという主張の下、三位一体の改革、郵政民営化、各種の規制緩和などが行われたものだ。この構造改革について、改革は必要だったが、結果として都市と地方の格差や国民の貧富の差を拡大し格差社会を進めた、といった意見が多い。改革の路線は間違っていないが、影の部分が大きくなってしまった、という論調だ。私はそうではなく構造改革は成長戦略としても失敗したのだと考えている。先に紹介したように、構造改革が始まった2000年以降現在に至るまで、日本の成長力も国際競争力も低下している。「失われた20年」のうち、2000年以降の10年は構造改革の失敗によるものといっても過言ではない。
※4 アルセロール・ミッタル ヨーロッパのアルセロールとインドのミッタル・スチールの経営統合によって、2006年に誕生した世界最大の鉄鋼メーカー。年間粗鋼生産量で世界シェアの約10%を占める。

2007年5月21日
ポリシーウォッチャーの役割
「改革の日々が始まった」-2001年4月26日、それはまるで、日本最大のお祭りのようだった。国民的熱狂、聖域なき構造改革、抵抗勢力とのすさまじい戦闘。小泉内閣という奇跡の内閣が誕生した瞬間を、著者はときめきと興奮をもって振り返る。
本書は、従前の日本政治においては考えられなかった異色のリーダー・小泉総理の下、要職を歴任した竹中平蔵氏の挑戦の記録である。「小泉総理の下、日本は間違いなく変わるだろう。そう思ったからこそ私は、大臣就任を引き受けた。これからその変革の『歴史的瞬間』に立ち会いたいと思う。」という書き出しから始まる著者の大臣日誌に基づきながら、不良債権処理、郵政民営化、経済諮問会議の舞台裏が生々しく語られている。
「改革なくして成長なし」-しがらみを持たない強いリーダー小泉総理は、当選回数や派閥からの人事を一切行わず、金融再生プログラムや郵政民営化といった改革を断行した。この改革の中で、重要な役割を果たしたのが、民間出身の経済学者として専門的見地を政策に活かす役割を与えられ、入閣した竹中大臣であった。抵抗勢力のなりふり構わぬ陰謀や策略に遭いながら、いかにして改革を断行したかが、本書の見所になっている。また、本書は、著者の日誌をベースに書かれているため、さまざまな場面が、せりふや感想とともにリアルに語られており、冒険書を読むような面白さがある。そして、随所に見られる小泉総理のリーダーシップも見逃せない。不良債権処理をめぐり、抵抗勢力にののしられ、辞任を迫られる竹中氏に、当て付けのように金融担当大臣兼務を命じる場面や与党幹部の夕食会で、郵政民営化の「基本方針は絶対変えない。ちゃんと理解しておけ。自民党はとんでもない男を総裁にしたんだ」と、反対を強める党側へ迫力の宣戦布告をする場面などは圧巻である。
さて、よく小泉政権に対して、「劇場型内閣」「骨抜きの政策」だなどと、人気があるが中味のない政権であるかのような批判があったが、本書を読む限り、骨抜きではない改革が実行されたように思える。小泉内閣の改革の成果については議論のあるところだが、少なくとも、日本の経済再生のために、以前から散々問題視されながら放置されていた不良債権処理に着手し、金融再生プログラム(竹中プラン)を実行、りそな銀行への公的資金注入など、金融改革を断行したことは、評価できるのではないか。
なぜ、今まで散々先送りされてきた金融改革を断行できたのか?なぜ、総選挙を行うほどの抵抗に遭った郵政民営化法案が成立したのか?もちろん、歴史的な国民の支持と小泉総理のリーダーシップがあったことは確かだが、改革を主導した竹中大臣の専門家としての力が大きかったことは間違いない。竹中氏は、「骨太方針」の決定、「工程表」の作成、そして「戦略は細部に宿る」という共通認識のもと、官僚の思うがままに作られていた「政策の制度設計」を大臣自らが詳細に作るという「政策決定プロセス」によって、総理の意思を貫く、政治主導型の改革を実現していく。特に、制度設計は、従来、官僚「霞ヶ関文学」の専売特許であり、その知恵は官僚に独占されていた。竹中氏は、30年間「政策」を勉強してきた「政策研究者」として、政策の重要性を理解し、政策の骨組み、つまり法律の条文や施行後の運用ルールなどを詳細に検討。抵抗や妨害、骨抜きにされることを予測し、常に二手三手先を読みながら作戦を練り、抵抗勢力との合意形成に挑む。そして、譲れないところは妥協せず、打開点を探る戦略家の一面も見せる。「普通のこと」がなかなか実現できない日本において、実行力のある改革を断行するポイントは、この「政策」「政策決定プロセス」をいかにうまくやるかにあったようだ。
著者自身は、自らの大臣経験を振り返って「昆虫学者が昆虫になったようなものだ」と語っている。小泉総理の熱意に共感して、自分が研究していた対象の世界に足を踏み入れ、自らが研究の客体となったわけである。自らがプレーヤーとして、官僚の無謬性と戦い、業界・政治家・官僚の「鉄のトライアングル」へ挑戦し、マスコミや学者から激しいバッシングを受け、戸惑い、悩み、立ち向かっていく。この得難い体験を通して、「政策は難しい」ことを実感する。また、「優れた植物学者が、即優れた庭師である保証はなにもない」のと同じように「経済学や政治学は間違いなく政策のために必要ではあるが、政策の専門家と経済学者、政治学者は同じではない」と説明する。そして、評論や絵空事を言う学者ではなく、実務的な知恵と将来的なシナリオを描ける「政策専門家=ポリシーウォッチャー」が必要であると主張する。
ポリシーウォッチャーの役割は、政策の調査研究、分析評価、監視、提言を行うことと情報発信を行うことである。特に情報発信を通して正しい世論を形成することで、「よく知らされた国民」(Well informed public)を生み出すと著者は言う。情報は溢れているが、スキャンダルやゴシップネタばかりで本当に有益な情報(政策論議や政策分析)となると極端に少ないというのが現状ではないだろうか。小泉政権を通して、また最近の政治からも、世論の力、国民の支持の重要性が注目されている。国民が適切な判断を行うことで、良い政策が生まれ、さらに政策が実行されているかを評価監視することで、政策がより良い方向に向かうという好循環が生まれるというわけである。
「政策は難しい」という難問にどう立ち向かうのか。著者は、「政府の中核で政策を実行した経験を、政策専門家の育成に役立て、民主主義のインフラとして、政策専門家が民間部門から政府の政策をしっかりウォッチし、国民に伝えるという機能を果たしていきたい」と決意を語っている。ポリシーウォッチャーを通した「民主主義による世論の後押し、政治主導の構造改革、力強い日本」の実現。竹中氏の挑戦は、まだまだ続きそうである。
2006年09月20日
小泉構造改革が残したもの
森重 透
1.「いざなぎ超え」とは言うけれど
マクロ経済は、長期にわたったデフレ局面からの脱却を視界に入れつつ、足もとなお拡大を続けている。2002年2月から始まった今回の景気回復は、すでにこの5月に「平成バブル景気」を抜き去り、11月には「いざなぎ景気」(1965~70年、57ヶ月)を超え、戦後最長となりそうな勢いだ。
しかし、実質GDPの伸びで見た景気拡張期間はなるほど長かったかもしれないが、国民一人ひとりの生活実感から見れば、まさに「実感なき景気回復」ではなかっただろうか。そして、それはなぜかを考えれば、今回の回復局面の特徴が明らかになろう。
まず、息の長い回復ではあるが低いレベルの成長だったことだ。「いざなぎ」は年平均成長率10%超、「平成」は5%程度だったが、今回は2%強と「平成」の半分にも及ばないレベルである。成長率と拡張期間の積和でこの間の実質GDPの伸びを見ても、「いざなぎ」当時は約1.7倍であるのに比べ、今回は1.1倍程度に過ぎず、さらに名目GDPの伸びで見れば、その差は2倍以上にも拡がる。横綱と前頭筆頭ぐらいの差はあるのではないか。とくに、緩やかなデフレ下の回復のため名目値がほとんど伸びなかったことは、実感の乏しさをより強めたはずである。
二番目の特徴は、企業部門と家計部門の所得状況の違いだ。「経済財政白書」(7月)には、「企業部門の改善によって家計にも好影響が及ぶ好循環がみられる」趣旨が盛り込まれているが、雇用環境には目に見える改善があるとはいえ、賃金・可処分所得関係の統計では、むしろ家計の疲弊ぶりが顕著であり、4年以上も続いているのに景気回復の恩恵は家計・個人にはほとんど及んでいない、と言ってよい。企業部門から家計部門への波及(トリクル・ダウン)の遅れは、企業が業績好調にもかかわらず、賃上げ幅を低く抑え続けているからである。今回の景気回復は、大企業の資本の論理、すなわち、リストラ、非正規雇用の拡大等による賃金コスト削減をバネにもたらされた側面が大きいが、それがまだ続いているということだ。
そのほかの特徴としては、米国経済の好調や中国特需などに支えられた外需主導、デジタル家電ブーム等、一部の大企業・製造業に偏った回復であったことなどから、多くの中小企業や非製造業への波及が遅れていることも挙げられる。また、地域間で景気回復のテンポや景況感に大きな格差があり、これがなかなか縮まらないことも、全体的に景気回復を身近に感じられない要因の一つだろう。
2.二極化・分断化の進行
このように、マクロ面で見れば、実感が乏しいとはいえ息の長い景気回復が実現したことは事実である。しかし、この回復が、間もなく終結を迎えようとする小泉内閣の構造改革の取組みによってもたらされたか、ということになると疑問符が付く。「構造改革なくして回復(成長)なし」、「官から民へ」、「中央から地方へ」を標榜した小泉構造改革路線が、スローガン通りの実行力を伴ったものでなく、今回の景気回復とは無関係であることは、すでに本コラムでも何度か指摘した。また今年の「経済財政白書」(7月)も、企業の適応努力こそが日本経済回復の主役と正当に位置づけているし、多くの識者の見方もこれに沿うものが圧倒的に多い。
むしろそのことよりも、この小泉政権下の経済運営によって、構造的には深刻な問題が発生した。経済社会の二極化・分断化の進行、社会生活基盤の劣化、という由々しき問題である。下掲グラフは年齢階級別完全失業率だが、15~24歳の若年層の失業率・学卒未就職率は、この間一段と上昇し、高止まりしていると言ってよい状況である。失業こそは、一個人を社会的・経済的弱者に転落させるもので、とくに若年層で定職に就かない者がなお多く存在するという現実は、これからの日本の国力や競争力、社会保障システムへの悪影響を考えると憂慮させるものがある。
さらに、パート、アルバイト、派遣社員など「非正規雇用者」は、すでに雇用者数の約3人に1人となった。ここでも若年層(15~34歳)の雇用情勢は厳しく、失業の長期化、フリーターやニートの増加、そしてフリーター経験をプラスに評価している企業がほとんどないことから、彼らが中高年になっても非正規雇用者にとどまってしまう懸念がある。こうなると、4対1とも言われる正社員との給与格差が固定化されるとともに、累積的に所得格差が拡がり、生活基盤の劣化、ひいては非婚・少子化などの様々な問題を助長する恐れがあるのだ。現にそうなりつつある。また過重な労働実態、過労による労災件数の増大、ワーキングプアの増加、うつ病、突然死など、今日、雇用の劣化あるいは崩壊とも呼べる事例は枚挙にいとまがない。社会構造からくる「日本沈没」である。
このような状況も反映してか、7月に発表されたOECDの「対日経済審査報告書」によれば、先進30カ国の相対的貧困率(平均値に比べて所得が半分未満の相対的貧困層の割合)で、日本は米国(13.7%)に次ぐ二番目の高さ(13.5%)だったそうだ。そして、労働市場の二極化傾向の固定化の恐れを警告され、格差是正の具体策として、非正社員への社会保険の適用などを指摘されているのである。
このほかにも、大企業と中小企業、都会と地方、高齢層と若年層、官と民等々・・・規模・地域・年齢・官民間に存在する諸々の二極分化(格差の拡大と固定化)の問題を真摯にとらえ、これを是正しながら持続的成長を模索していくというような、「徳のある経済政策」は、小泉政権下ではついにお目にかかれなかったと言ってよい。
3.何が欠けていたのか
「聖域なき構造改革」という看板を掲げた小泉構造改革路線は、約5年半に及んだ小泉政権のバックボーンであったはずなのに、結局それは、「小泉劇場」の主役・小泉純一郎が大見えを切るときの小道具に過ぎなかったようだ。
新規国債発行30兆円枠の公約は、「この程度の約束を守れなかったというのは大したことではない」と言って、簡単に破られてしまった。公的年金改革を審議する年金国会での、「人生いろいろ」発言に見られるような、おちゃらかし発言。はぐらかしや、レトリック依存型の国会答弁も多く見られた。地方の景気にも目配りすべきではないかとの記者の問いに、小泉首相は「官から民への流れは変わらない。政府が口出しすべきではない」と答えたそうだ。道路公団の「民営化」は、結局、妥協の産物に終わった。そして、改革の「本丸」と意気込んだ「郵政民営化」は、その意味や効果が不鮮明なまま、分社化を伴う株式会社化で行き暮れようとしている。結局、高い人気に支えられ、連日劇場は満員御礼だったが、バックボーンは最後まで「小道具」で終わった。
「改革なくして景気回復なし」の名の下に、実体的な景気対策には関心が薄く、かと言って、公的セクターの改革、すなわち、責任ある社会インフラの構築と質の高い公共サービスの供給という、「民」が果たせない「官」の固有の役割というものを、いかに実効ある形で遂行していくかといった制度問題を、徹底的に真摯に議論する風でもない。詰めた議論よりは、歯切れの良い「ワン・フレーズ」で「改革」をくさびとして使い、多くの「抵抗勢力」を放逐しつつ人気を得ていくという手法は、まさに独壇場と言えるものだった。
しかし、「改革の本丸」であるべき財政再建問題と、これに密接にからむ社会保障制度と税制のあり方に関する真摯かつ周到な議論と実践を抜きにしては、「経世済民」を託された責任ある政治家としての本務は果たせないのではないか。「ノブレス・オブリージュ」とは、財産、権力、社会的地位には責任が伴うことを言う。小泉首相に限らず、政治家全員がこのことを心に銘じるべきだろう。

【論文】マーケットはなぜ小泉政権の改革を疑問視するのか
2001年8月04日
sheard_p020710.jpgポール・シェアード
小泉政権は「聖域なき構造改革」を打ち出しているが、この実現可能性について、マーケットは非常に大きな不信感をもっている。
■ 矛盾だらけの経済政策を繰り返すな
なぜ不信感をもっているのか。その理由は、日本がまた、いつもと同じような失敗を繰り返すのではないか、という懸念が拭い去れないことにある。日本はいつも、過去になぜ失敗したのかという事後的な点検が行われないままに、次の政策を展開しようとする。そして、いつも矛盾
ばかりの政策を展開する。つまり「こんなことをやります」と言っておきながら、実はそれとは違うことをやってきた。その典型的な例がペイオフの延期だ。今回の「骨太の方針」のなかで、そうした懸念をいちばん強く感じたのは不良債権問題に関する部分だった。まずは、それを中心に話を進めよう。
「骨太の方針」、すなわち経済財政諮問会議の基本方針は、不良債権処理に関しては、2001年4月6日に経済対策閣僚会議で決定された緊急経済対策の考え方を継承している。緊急経済対策には、問題の本質をついた、さまざまないい意見が書かれているが、その大きな目玉は、やはり不良債権処理が最大の課題である、というものだった。
ちなみに、それより少し前の3月19日に日銀は政策決定会合で「通常では行われないような、思い切った金融緩和に踏み切る」ことを決定しているが、その議事録のなかにも、不良債権問題の解決が急務であるという趣旨の文章が入っている。
こうした流れからいくと、4月6日の時点での政策の結論は、やはり不良債権処理が最重要課題だ、というものだったといえる。
最近、不良債権を「2~3年以内に処理する」という言葉の意味が議論されないまま、独り歩きしている感があるが、緊急経済対策のなかには、主要行について、「破綻懸念先以下の債権に区分されているものについては、原則として2営業年度以内にオフバランス化につながる措置を講ずる」、それから、新規発生分については「原則として3営業年度以内に......措置を講ずる」と書かれている。
これは非常に重要なポイントだ。なぜなら、この「措置を講ずる」という表現は、金融監督庁のマニュアル、あるいは旧大蔵省の行政に従ってやってきた過去の金融再編行政では、不良債権は解決しない。今までのやり方を白紙に戻して、2~3年以内に不良債権をかたづけよう、という強い意思表明の表れだからだ。
今回の基本方針も、この方針に沿って、「不良債権問題を2~3年以内に解決することを目指す」、「経済再生の第一歩として、不良債権の処理を急ぐべきである」とはっきり書いてある。多くの人はこれを読んで、正しい方向に動いていると思うだろう。ところが、である。今回の基本方針には、不良債権の最終処理は「金融機関の自主的な判断で進められる」というくだりが入っている。 これでは、全く話が違ってしまっている。4月の緊急経済対策で、「過去の行政のもとで、金融機関が自主的に問題に取り組んできたけれども、そのやり方では解決しない。政府が主導権をとって、2~3年以内に解決させる」という強い意思表明をしたにもかかわらず、ここでまた、「自主的な判断で進められる」ということでは、議論するまでもなく、問題解決にはならないだろう。
ちなみに、不良債権問題の裏側にある借り手企業/産業については、私的整理のためのガイドラインを「関係者間で早急に取りまとめることが期待される」と書いてある。
もちろん日本の場合、「期待される」、あるいは「自主的な判断で進められる」といった場合、それは国が強制的にやるといっているのと同じだという解釈もないわけでもないが、それは一昔前の行政のあり方を反映した解釈だ。つまりそれは、不透明な、玉虫色的なやり方にもなっているということだ。
■ さまざまな数字が独り歩きをしている
それに、緊急経済対策にも、踏み込み不足だった点がある。ひとつは、対象を全預金取扱金融機関ではなく、主要行に限定していたこと。もうひとつは破綻懸念先以下の不良債権に絞って話をしていたということだ。
詳細は省くが、これでは、ペイオフ延期などの過去の政策との整合性がないばかりか(ペイオフ延期のときは、主要行は大丈夫だが、信金や信組などは検査不十分で不安だから、という説明がなされた)、不良債権問題を全体的に把握することはできない。いうまでもなく、マーケットが非常に神経質に注意を払っているのは、不良債権の全体の大きさだ。ところが、上述したように、限定した見方をとっているために、いろいろな数字が独り歩きをしてしまっている。
例えば、一時期新聞を賑わせた12兆~13兆円という数字は、主要行の破綻懸念先以下のものを指している。しかし全銀行ベースの問題債権は64兆円で、全預金取扱金融機関ベースでは81兆円くらいあるとされている。また最近では、151兆円という数字が独り歩きをしている。これは民主党が金融庁から取り寄せた数字で、要注意債権以下の債権をもっている借入先の全借入金を示している。
われわれプロでも、これらの数字の使い方にはものすごく苦労している。この間、民主党の鳩山氏が「150兆円という数字をどう思うか、大手行の資産査定を厳格にやり直すべきだ」という趣旨の発言をしたところ、首相は「元利払いや貸出条件に問題がなく、単に注意が必要な債権は100兆円ある」と答えた。この発言は、要管理債権以下の不良債権以外の要注意債権が100兆円ある、ということだが、公表ベースでは、こういう数字は出てこない。一国の総理大臣が、国会でこのような答弁をしていることからもわかるように、問題の大きさがどれくらいであるのか誰にもわからず、マーケットは政府に対して依然として不信感をもっているのである。
■ 危機対応の制度的枠組みが不在
マーケットが不信感をもっている第2の理由として、金融再編の枠組みが不在だということが指摘できる。2001年1月には行革の一角として金融再生委員会が廃止された。金融再生委員会は、金融問題を解決するために特別につくられた組織だったにもかかわらず、その仕事が終わる前に廃止されてしまった。日野正晴前長官は退官のインタビューで(『日本経済新聞』2001年2月2日)、「本当はペイオフ1年延期時に、それと連動して金融再生委員会や再生法、健全化法も延長すべきだったが、議員立法なのでこうなってしまった」と述べている。筆者も全く同感である。3月末には、資本増強の枠組みも期限切れとなってしまった。
そしてその6日後に政府は公式見解として(緊急経済対策)、不良債権が日本経済のいちばん大きな問題だ、この問題に集中的に取り組む、ということを表明した。1998年にも同じ議論があり、問題解決のために60兆円のパッケージと金融再生委員会をつくった。その枠組みを廃止した途端に、改めて問題の重要性、枠組みの必要性が認められるというのは、酷評すれば、先進国の経済政策としては大問題だ。少なくとも説明責任というものがある。そうしたことを議論しないで、ポッポッと次の政策が出てくるというのはいかがなものか。
もっとも、枠組みがないというのは多少言いすぎで、実は金融危機対応枠組みというものが4月1日からスタートしている。それは資本増強、国有化、(ペイオフコスト以上の)預金者保護という3つの機能を持ち備えている。
ただ問題は、危機がなければこの枠組みが使えないということだ。これに対し98年の枠組みは、危機の産物としてできたもので、危機がなくても、危機が起こらないように使うことができた。
こうして、不良債権問題の重要性に対する認識と、その問題を解決するために用いる制度的枠組みとの間に、大きな空白ができている。そうした空白があるからこそ、いろいろな方針や意見が錯綜しているといえる。つまり枠組みがないから、金融機関が自主的判断ベースでやるしかないということになっている。だが、金融機関の自主的判断ベースではこの問題は解決されないことは目に見えている。自主的ベースでできるような話であれば、とっくの昔に解決しているはずだからだ。
■「財政再建」重視の危うさ
第3に、小泉首相が財政再建を最重要視しているのではないか、ということだ。首相の所信表明演説を見ると、「不良債権処理や資本市場の構造改革を重視する政策へと舵取りを行う」とし、1に不良債権問題の解決、2に規制緩和、3に財政再建を行う、と述べている。筆者はこのポリシーミックスと順序づけにはおおむね賛成だが、小泉内閣が実際にやっていること、あるいは発信しているメッセージを見ていると、不良債権処理がかなり後退している感じを受ける。特に、上述したように、「措置を講ずる」が「自主的判断で進められる」というように後退しているのが気になる。むしろ第3の財政再建をアジェンダの上位にしようとしているらしい。
例えばここ2カ月間の議論をみると、田中真紀子氏が多くの話題を提供してきたが、それはともかく、経済面では新規国債発行を30兆円以内に抑制するなど、財政再建の話題でもちきりだった。だが経済の現状を考えると、財政再建に今踏み込むことは非常に厳しい緊縮財政になりかねない。すると不良債権問題の先送りと財政再建の優先という、橋本政権のときと全く同じポリシーミックスとなってしまう。
こうして、橋本、小渕、森の各政権から得られたはずの教訓が生かされず、また元に戻ろうとしており、"不思議の国のアリス"のような経済政策になっている。
■ 構造改革断行の2つの選択肢
以上、小泉内閣の経済政策・構造改革の基本方針について検討を加えてきたが、これらの一連の議論を見ていて、問題だと感じるのは、政府がどちらの方向に進もうとしているのか、その方向性が見えないということだ。
改革を断行するに当たり、政府には大きく分けて2つの選択肢がある。ひとつは期限を区切ったうえで、自ら主導権を発揮して改革を進めることだ。この場合は、金融再生に向けた新しい枠組みづくりと、危機を未然に防ぐための公的資金の投入が必要になる。またマーケット・メカニズムを最大限活用し、新しいマーケットが育成されるようなやり方をとる必要がある。
もうひとつは、市場に任せるという、まさにハード・ランディング的な解決策だ。この場合は、ペイオフの早期実施と、金融危機対応枠組みを極力使わないという覚悟、それに労働市場、小口預金者保護などのさまざまなセーフティ・ネットが必要になる。加えて、緩和的なマクロ政策と、規制緩和などの、経済体質を強化するためのミクロ政策を次々と実施しなくてはならない。
後述するように、筆者は前者の政策を取るべきだと思っているが、今のところ、小泉政権がどちらの方向に進もうとしているのかが見えない。むしろ、このどちらでもなく、中間の道を歩んでいるようにも見えるのである。すなわち、危機が起きると政府が動き、その際、マーケットを阻止するような政策を取るという、これまでと同じ過ちにはまってしまう可能性がある。
公的資金の投入や銀行保有株式取得機構の設置、それに貸し渋り対策などで、政府は銀行に対してあらゆるところで関与を強めている。これでは、マーケットに任せるという2つ目の選択肢は取りえない。こうした状況では真の意味でのマーケット・ベースということはできない。それにもかかわらず「金融機関の自主的な判断で進められる」という表現を用いたりするので、混乱が生じることになるのである。
国が関与することにさまざまな弊害があるのは十分承知しているが、筆者は、ここまで国が関与を強めている以上、国が主導権を握り、期限を区切って市場を生かす形で改革を断行したほうがいいと考えている。ところが、では主導権を発揮しているかといえば、それも中途半端な状態にある。
実は私は財政再建の信者だが、一回限りの措置として、金融問題の解決のために公的資金を30兆円入れるということを断行すれば、日銀はそれを支援するだろうし、それが2年後のマーケットの発展につながるということであれば、マーケットもそれを評価するのではないか。だが、小泉首相は財政再建という目標があるために、公的資金を投入するという流れをつくれないでいる。こうしたことから、マーケットから見ると、財政再建を優先していることが、実は不良債権を断固として処理するという腹が固まっていない、と見えてしまうのである。
■今は財政再建を打ち出すな
では、具体的に小泉首相はどういったアクションを起こすべきか。
まず、今の局面では財政再建を打ち出さないことが必要だ。今財政再建を打ち出すと、それはものすごい緊縮財政になってしまう。
仮に出すにしても、出し方を工夫すべきだ。実は財政構造改革と財政再建は違う。財政構造改革というのは、財投改革や公的金融機関の民営化、あるいは効率的な税制システムの構築などのミクロ的な改革だ。これは今すぐにでも実行できるし、これをすぐに行うことには筆者も大賛成である。
一方で、今の経済局面のなかで、どれだけの財政出動が必要なのかという問題がある。これが財政再建の問題だ。日本の場合は、この2つの概念がいつもこんがらがってしまっている。前総理の橋本氏も、財政再建を実現したかったために財政出動を締めたが、本当の財政再建は、経済を回復させなければ成り立たない。そこで、では経済を本当に回復させるには何が必要なのか、という議論が、財政再建の中枢にくるはずだ。
そこで、不良債権がいちばんのネックであるという判断なら、それをやるべきだし、非効率的な財政の仕組みの問題であるなら、それを見直す必要がある。そのなかで必要に応じて財政出動をすることもありうべき選択肢だろう。預金者保護と不良債権処理を同時に達成するためには、例えば30兆円というコストがかかることもあるかもしれない。この場合は、短期的には財政再建はできなかったということになる。
つまり、すべての政策目標、特に矛盾しあっているいくつかの政策を同時に達成することはできない。それなのに、あれもやる、これもやると主張するのは、部分的な発想でしかない。まず不良債権処理に重点を置くべきである。
財政再建は確かに重要な課題ではあるが、それが本当に緊急の課題がどうかを考えると、実はそうでもない。ひとつは、日本のマクロ的な現状をみると、民間部門の黒字を政府が吸収しているという面がある。そうなると、問題は個人の将来不安が解消されていないから、また規制緩和が不十分で日本企業の投資プロジェクトに問題があるから、あるいは金融システムが十分に機能していないから、民間部門が活性化されない、ということになる。
この問題を解決するには、IT関連を中心に規制緩和を実行することだ。そうすれば、さまざまな形で、新しい需要と新しい投資機会が生まれてくる。そして結果として、税収が増えて、政府の赤字も減っていく。
もうひとつは、国債の利回りだ。これは現在1.2%程度であり、財政再建をやらなければ日本は破綻する、というメッセージをマーケットは発信してはいない。しかし小泉政権は、あたかもそうしたメッセージが発せられているかのように動いている。橋本政権時の増税と同じく、小泉政権でもプライマリーバランスの赤字を支出削減で抑えようとしているが、それは因果関係を間違えている。まず解決すべきは不良債権問題である。
■戦略的にマーケットを活用せよ
そこで、不良債権処理を進めることを考えるとき、ぜひ指摘しておきたいことは、戦略的に、マーケット・メカニズムを最大限に生かすことが重要だということだ。これは、政府が主導権を取るという方向とは、一見矛盾しているように見えるがそうではない。例えば、しばしば引き合いに出されるアメリカのRTC(整理信託公社)は、預金の全額保護をせずに、破綻懸念の金融機関をつぶして、預金保険機構でカバーされていない人たちに債権カットに応じさせた。同時に、RTCは資産を取って、資産価値と預金保険機構でカバーされている額との差額を埋めた。これは預金者保護の鉄則です。そのうえで、受け取った資産をすぐさま売却した。
RTCがそうしたように、資産を売却すると、非常に大きなマーケットが育成される。現在、非常に大きな規模になっているCDO(Convertible Debt Obligations)やABS(資産担保証券)は、実はRTCが登場するまではなかった。これが、マーケット・メカニズムを最大限生かすということの意味だ。銀行の国有化や買取機構、それにペイオフの延期といったやり方は、やはり問題だろう。
ただ、日本の現状を見ると、残念ながら現に政府はそれをしていないし、今までの経験から見ても、ほとんどやる意思とやる能力がなさそうである。
今後の政策の展開次第では、金融は、おかしなことをやる可能性がある。政府の要人はいろいろなところで、低成長には甘んじなければならないけれども、マイナス成長はだめだと発言しだしている。一方で財政再建論者が趨勢を握ったとすれば、やはり金融危機が起こる。そして財政再建プラス金融危機イコールマイナス成長となったとき、マーケット・ベースで進まないような手を考え出してくる可能性がある。ペイオフ延期はないにしても、危機対応枠組みを使って実質的な全額保護の延長をやりかねないなどの危険性が残っているのである。
日本人の間では、金融危機が起きたときに危機を止めるのは政府の要件だから、それも仕方がない、という考え方があるようだが、それは違う。そもそも不良債権があるから危機が起きるのであって、危機を封じ込めたければ、そうした全面保護のような形で政府が対応するのではなく、まず政府が主導権を取って不良債権を処理すべきなのである。そうでないと、金融危機対応枠組みがまた悪用されることになってしまう。
この論文で検討してきたようなポリシーミックスを実現するには、本来なら経済財政諮問会議のようなところで総合的に調整する必要がある。その点では、竹中氏も精いっぱい努力しておられるようだが、まだ理想的な形には至っていないと思っている。現在の小泉政権には、政策を立案する陣容はあっても、それを実行に移していくというシステムがない。それが小泉政権のアキレス腱ともなっている。
ここまで小泉政権に対して、批判的な検討を加えてきたが、小泉政権は、構造改革を断行すると述べている内閣であり、その意味では期待もしている。これまでと同じような愚を犯すことなく、構造改革に踏み込んでいってほしいと思っている。それが日本経済を停滞から脱却させる道である。〈了〉
「竹中平蔵ふざけるんじゃねえ」 河野太郎ブログ炎上
2006年09月19日
河野太郎衆議院議員のブログ(メルマガのブログ版)が「炎上」している。発端となったのは2006年9月15日の「ふざけるんじゃねえ」と題された日記。このなかで河野氏は、竹中平蔵参議院議員の任期中の辞職を痛烈に批判した。激しい批判に、ブログには河野氏を批判するコメントが殺到している。
問題になっているのは、「ふざけるんじゃねえ」と題された日記。小泉純一郎首相の任期満了による退陣にあわせて任期中で議員の職を辞する考えを表明した竹中氏を河野氏は痛烈に批判している。
「河野さん、下品すぎ」といった批判殺到
竹中氏は2004年の参院選で当選。3年10ヶ月の任期を残しての辞職となる。河野氏は「竹中平蔵参議院議員のバッジは小泉総理がつけたものではない。有権者からいただいたものだ」として、小泉首相の退陣にともなう辞職に異を唱えている。
河野氏のこうした発言後、同ブログにはコメントが殺到。その数は06年9月19日夕方時点で160を超える勢いだ。多くのコメントは次のようなものだ。
「河野さん、下品すぎ・・・・」「あなたのメルマガには時々いいことが書いてあるのに、今回の竹中さんへの怒りをそのままぶつけるような書き方には失望し、もう読むのはやめようかと思いました」「貴方は、ひとの事を言う前に政治家以前に人としての品位を疑います。もう一度ご自身を見つめ直してください」「言葉が汚く、不愉快です。失望しました」
「議員の身分についての議論が深まればいいと思っています」
河野氏を批判するものが大半だが、少ない印象は受けるものの河野氏を擁護するコメントも存在している。
「ふざけんじゃない!。よくぞ河野議員は言ってくれました」「竹中氏への怒りが余り出て来ない有権者にも大きな問題があると、今回、改めて感じました」
と、竹中氏への批判に同感といったコメントもある。
ブログにコメントが多数寄せられているなかで河野氏は動じてはない模様で、J-CASTニュースの取材に対し次のように答えた。
「議員の身分についての議論が深まればいいと思っています」
北海道のニュースサイトBNNが06年9月18日から実施している竹中氏の議員辞職についてアンケートでは、「あまりにも無責任」が35.1%、「功績は大きい。辞任は残念」が28.6%、「そもそも立候補すべきでなかった」が23.4%という結果が出ている(2006年9月19日夕方現在)。
no nameID: 小泉の虎の威を借る狐という意味だと感じたけどね。
ぜんぜん問題ない率直な発言。実際、その後の格差社会、派遣切りなどの問題の発生源だから、トンずらせずに最後までやれよというのはそう思う。7
no nameID: どうか竹中平蔵に天罰が下りますように。
no nameID: 竹中平蔵は元々そういうクズだから問題ないかと。竹中にバチが当たればいいのに。
no nameID: 竹中は非正規労働者2000万人を作って張本人です。
こいつはさらに、正社員をなくせ、100%非正規にしろとほざいているのです。
こいつは労働者の敵です。
no nameID: 竹中氏と創価学会に繋がりを感じる動きがみえたのですが、東洋大学の教授時代、生徒とのもめ事、他宗教への偽教義内容配布が疑われる。
名無しID: 目くそ鼻くそをそしる
no nameID: そんな貴方は、腹痛を理由に二度も政権を投げ出した人に媚びを売ってましたよね?
「正社員はいらない」“煽る人”竹中平蔵とは何者なのか?
規制緩和とともにある人の「変遷」をたどる
2018/07/01
ネット内では「対立を煽る書き方をすれば、読み手が過剰に反応する(=釣られる)」と、先日殺害されたネットウォッチャー・Hagexは著書『ネット釣り師が人々をとりこにする手口はこんなに凄い』(アスキー新書)に記す。その典型として「男女対立」、「理系文系」、「きのこの山・たけのこの里」、「能力や価値の相対化や序列化と対立煽り」などをあげている。
「生産性の低い人に残業代という補助金を出すのも一般論としておかしい」
「時間内に仕事を終えられない、生産性の低い人に残業代という補助金を出すのも一般論としておかしい」(東京新聞6.21)。これは竹中平蔵の言葉である。「経営者目線」の者と「社会のありようを問う」者の対立をうまいことアオり、ここまでくると、ネタで言っているのかと思ってしまう。過去にも「日本の正社員は世界一守られている労働者になった。だから非正規が増えた」(日経新聞2012.7.16)、「正社員をなくせばいい」(テレ朝2015.1.1)といった発言で、世のひとびとを虜にしてきた。
そんな竹中は自らの肩書でもネットを盛りあげる。上掲の東京新聞のインタビューでは、残業代ゼロ制度の異名をもつ高度プロフェッショナル制度について「個人的には、結果的に(対象が)拡大していくことを期待している」などと、「東洋大教授」の肩書で登場して語っている。これがまたいいネタフリになって、SNSには「東洋大教授でなく、パソナグループ会長と表記すべきじゃね?」との幾多の投稿が見られることになる。
学者大臣からパソナ、オリックスの企業人へ
稀代の釣り師ともいえる竹中だが、東洋大教授や人材派遣大手のパソナグループ会長のほか、オリックス社外取締役など肩書コレクターとしても有名だ。一介の経済学者であった竹中は小渕政権の諮問機関の委員となったのをきっかけに政治に入り込み、小泉内閣に入閣すると「学者大臣」と呼ばれ、選挙に当選して国会議員にもなり、やがて複数の大企業の取締役などになっていく。
「ちゃっかり経済財政大臣の椅子に座っていた」
週刊文春の見出しでこうした変遷をふり返ってみれば、小泉政権で経済財政政策担当大臣→「『変節漢ぶり』検証 竹中平蔵ってそういうことだったのか会議 御用学者と呼ばれる理由」(2001.9.6)、金融担当大臣→「竹中平蔵金融相登場 外資は栄え 日本は滅ぶ」(2002.10.10)、参院選に当選→「竹中平蔵 自爆告白『日銀やゴールドマン社員が選挙協力してくれた』」(2005.5.26)、パソナ取締役→「竹中平蔵『パソナ取締役』就任 南部社長とのただならぬ関係」(2009.8.13)という具合。そのときどきの肩書・立場に応じたネタを提供している。
これら記事の中に、こんな逸話がある。森政権の末期、竹中が、民主党議員らによる自民党を倒すための政策勉強会に参加させてほしいと頼んできた。しぶしぶそれを認めたところ、「しばらくして、勉強会で研究された、リナックス型社会、七つの改革 、といったアイデアを、いつのまにか竹中さんが別の場所で発表したんです」(永田町関係者・談)。おまけにそうした民主党の勉強会に参加していたのが「小泉政権の誕生と同時に、ちゃっかり経済財政大臣の椅子に座っていたこと」でさらに彼らを驚かす(週刊文春2001.9.6)。
規制緩和とともにある人
それでいえば、ときの政権に取り入って規制緩和を進めた竹中は、規制緩和による市場化で儲けるオリックスや、それこそ規制緩和ビジネスの人材派遣業の大手・パソナグループの取締役に“ちゃっかり”就いている。「“規制緩和の旗手”である竹中さんは、雇用問題について『派遣を含めて多様な雇用形態を実現すべき』と主張して」(文春2009.8.13)きたのである。釣り師としてばかりでなく、ちゃっかり者としても一流であった。
『サラリーマン政商 宮内義彦の光と影』(講談社2007)、『日本を壊す政商 パソナ南部靖之の政・官・芸能人脈』(文藝春秋2015)、これらは森功の著書名である。オリックスとパソナ、竹中が取締役に就いている会社の経営者が「政商」と呼ばれるゆえんは、政府による規制緩和の恩恵を受けていることにある。
小佐野賢治、小泉改革、人材派遣業をつなぐもの
政商といえば、もっとも有名なのが小佐野賢治であろう。小佐野は田中角栄の「刎頚の友」であった。そして田中の口利きで事業の利益を得ていく。土建国家、族議員、政・財・官の癒着、こうした政治風土のなかで、政治を介して特別の儲けを得る。これを支える体質を「古い自民党」と呼び、それを「ぶっ壊す」と叫んだのが小泉純一郎である。
小泉の有名なスローガンに「痛みをともなう構造改革」というのもある。不良債権などで経済が立ち行かなくなった90年代半ばに威勢を増したのが「構造改革」論で、それを突き進めたのだ。では、改革するとなにがどうなるのかといえば、規制緩和により、新たな市場が生まれたり、拡大したりするのである。
そうした市場のひとつが人材派遣業だ。小泉は「改革なくして成長なし」とも言ったが、まさに人材派遣業は「改革」によって成長をとげる。限られた業種にしか派遣できなかったのが、原則自由化され、製造業などへと拡大していく。そうした「法改正とともにそのときどきの政府の政策が、パソナの南部をここまで押しあげてきたのは、間違いない」(森功『日本を壊す政商』)。人材派遣業は「規制緩和ビジネス」なのだ。そして、これの推進役になったのが、オリックスの宮内が議長を務める政府の規制改革会議であった。
かつて竹中も属していた「経済戦略会議」の委員であった中谷巌は後年、構造改革が非正規雇用の増大を招いたと、自己批判する(「竹中平蔵君、僕は間違えた」文藝春秋2009.3)。この会議の答申が謳う労働市場の流動化が、その後に派遣業を拡大させたのだ。そして「あるべき社会とは何かという問いに答えることなく、すべてを市場まかせにしてきた『改革』のツケが、経済のみならず、社会の荒廃をも招いてしまった。それがこの十年の日本の姿であった」と中谷は懺悔するのであった。
それから更に10年近くが経とうとしている今日、正規雇用が破壊されつつある。あらたな分断を生もうとアオる竹中とともに、この荒廃はなおも拡大していく。
# 中国
竹中平蔵氏、中国社会でひそかに「大人気」になっていた
日中で共鳴する新自由主義の行方(1)
2020.09.20
あの竹中平蔵氏が、中国で大いに人気を集めているらしい。中国の人々はいったい竹中氏の何に惹かれ、彼から何を得ようとしているのか。その背景を追っていくと、日中で共振する「新自由主義」の動きが見えてきた。神戸大学・梶谷懐教授による全3回のレポート。
スーパーシティ法案成立の陰で
本年5月27日に、国家戦略特区法の改正案、いわゆる「スーパーシティ法案」が国会で成立した。新型コロナウイルス禍の拡大に伴う緊急事態宣言発令中の成立であり、報道などでは、遠隔医療の本格導入を始めスマート技術を用いた感染対策の進展に期待する声も多く聞かれた。
このスーパーシティ構想の背景としてAIやビッグデータを活用して社会のあり方を根本から変えるような都市設計を目指す動き、すなわちスマートシティの建設が、世界各地で本格化していることが指摘されている。
それを踏まえた上で(1)生活を支える複数のサービスが導入されている(2)複数のサービスがデータ連携を通じて相乗効果を発揮している(3)その成果が住民に評価されるような事業になっている――の3条件を満たす世界に類を見ない都市づくりを目指すのが「日本型スーパーシティ」構想の骨子だということらしい(「『スーパーシティ』構想について」『内閣府国家戦略特区ウェブサイト』2020年9月4日アクセス)。
そのようなスマートシティの代表的な例として、内閣府の資料にも挙がっているのが中国浙江省杭州市の「シティ・ブレイン(城市大脳)」である(内閣府地方創生推進事務局、2020)。シティ・ブレインは、市街を走行中の自動車の情報をライブカメラを用いて収集、そのビッグデータをAIで分析してドライバーにフィードバックすることで都市の混雑を解消し、交通事故の減少だけでなく、物流の高速化や市政サービスの簡便性の向上なども目的としている。
アリババ傘下のアリババ・クラウド社は、この「シティ・ブレイン」が目指すものについて、「ビッグデータそのものを都市インフラと位置付ける」ことによって、AIによるデータ活用が交通渋滞の解消、エネルギー損失の縮小、防犯体制の強化につながる、と述べている。
また同社は、自分たちのやっていることについて「ビッグデータの内部情報には一切触れずにアルゴリズム解析をし、要求された(あるいは、されているであろう)情報を自動的にアウトプットする」だけだ、と説明している(助川、2018)。
一方で、このようなスマートシティの導入に当たっては、政府による個人情報の大規模な収集が不可欠になることから、プライバシーが十分に保護されない「監視社会」化を招くのではないかという批判も生じている。特に、上記の杭州市のような中国のスマートシティには強権的な国家による「監視社会」に対する懸念がどうしてもつきまとうことになる。
さて、中国経済を専門とする筆者が、なぜスーパーシティ構想に興味をひかれたのか。そのきっかけは、この法案の参議院の審議過程で、日本共産党の大門実紀史議員が、「日本を中国のような監視社会に導き、個人のプライバシーと権利を侵害する重大な危険性がある」とし、法案に強く反対したことを知ったことである。大門議員の反対討論では、昨年9月に出版した拙著『幸福な監視国家・中国』も引用されていた、と聞く。
大門議員は、法案について次のように指摘している(「スーパーシティ法案 大門議員の反対討論(要旨)」『しんぶん赤旗』2020年5月29日、2020年9月6日アクセス)。
反対の最大の理由は、日本を中国のような「監視社会」に導き、個人のプライバシーと権利を侵害する重大な危険性があるからです」とし、中国では「政府・大企業が膨大なデータを分析し、国民への監視や統治に活用して、ウイグル族弾圧や民主化を求める活動家の拘束にも監視カメラや顔認証技術が用いられてきました。政府がスーパーシティ構想のお手本としてきた杭州市は、街全体のIT化が世界で一番進んでいますが、裏を返せば、街中に監視カメラが数千台もあるなど監視社会の最先端です。
これまで、政府が進めようとする規制緩和や都市開発の構想に対して、野党の政治家や政府に批判的なメディアが「アメリカの真似をするな」と批判を行うという現象はしばしば見られた。しかし、このスーパーシティ構想のように、自民党政権が進めようとするプロジェクトに対し、左派政党の政治家が「中国の真似をするな」という理由で強く反対する、という現象はこれまで見られなかったものである。この現象をどのように考えればよいだろうか。
竹中平蔵氏、中国で人気に
スーパーシティ構想を考える上で、キーパーソンの一人が「『スーパーシティ』構想の実現に向けた有識者懇談会」の座長であり、現パソナ会長の竹中平蔵氏であることは間違いないだろう。
竹中氏は周知のとおり、「聖域なき構造改革」の旗振り役として小泉政権経済に経済財政政策担当大臣、IT担当大臣、金融担当大臣、郵政民営化担当大臣を歴任した。第二次安部内閣の誕生に当たっては、日本経済再生本部の産業競争力会議の民間議員ならびに、国家戦略特区諮問会議の議員として、再びその動向が日本の政治に影響を与える存在としてクローズアップされてきた。スーパーシティ構想はその国家戦略特区の「目玉」として構想されたものである。
 |
| 慶応義塾大学教授:竹中平蔵 |
その竹中氏について筆者が以前から注目してきたのは、中国における評価の高さである。
特に小泉政権で閣僚に任命されたころから、その言動は特に中国の「改革派」知識人やメディアから常に高い注目を集めてきた。中国の代表的なIT企業、百度(パイドゥ)が運営する「百度百科(中国版ウィキペディア)」の「竹中平蔵」の項目では、彼が小泉政権時代に行ってきた様々な改革を中心に詳しい人物紹介がなされており、しかもその記述のほとんどは彼の経済改革の手腕を高く評価する内容で占められている(「竹中平蔵」『百度百科』、2020年9月4日アクセス)。
日本の著名な経済学者で「百度百科」で紹介されているのは故・宇沢弘文氏、故・青木昌彦氏、野口悠紀雄氏など数名しかおらず、いずれも竹中氏ほど詳しい記述はなされていない。さらに、彼が2007年に北京大学で行った講演録とその後の学生との対話が書籍化された『竹中平藏:解読日本経済与改革』(新華出版社、2010年)のほか、すでに多くの著作が中国語に翻訳されているほか、後述するように有力なメディアや、中国で開催された国際的なシンポジウムにも数多く登場している。
中国メディアが竹中氏を形容する際には「日本経済を最もよく知る人物」「改革の総指揮者」「経済改革の皇帝」「日本の王安石(中国宋代に大胆な改革を成功させた官僚)」「中国で最も人気の高い日本の経済学者」など、ほぼ絶賛といってよいほどのキャッチフレーズが冠せられることが多い。
周知のように竹中氏は日本において毀誉褒貶の極めて激しい人物であり、批判的なものも含めて彼を論じた書籍や報道はあまた存在するが、このような中国における彼の高い評価については筆者の知る限り日本ではほとんど知られておらず、そのことが持つ意味についてもほとんど考察されてこなかった。そこに浮かび上がった、竹中氏が旗振り役を務めるスーパーシティ構想と、その中国のAI監視社会との類似性の指摘。
これらの「点」と「点」を注意深くつなげることで、何かがつかめるかもしれない。そう考えたのが本稿を執筆した動機である。
中国改革派からのシンパシー
中国における竹中氏の高評価のキーパーソンといえるのが現在「財新メディア」グループの社長である胡舒立(こ・じょりつ)氏であろう。胡氏は、1998年に独立系の経済誌『財経』を創刊し、経済問題を主としながらも地方の汚職事件などにおける大胆な調査報道で「中国の真実」を描き出すメディアとして評価を高めていった。そして、2003年のSARS流行の際に政府の対応を批判する報道で国際的にも注目をあびた。
その後、『財経』誌への当局の規制が強まる中で2009年に同誌とは袂を分かち、「財新メディア」を創刊、同社が発行する『財新週刊』は中国経済や社会に関する鋭い分析で高い評価を得ている。
特に2020年のコロナ禍の際には、昨年末に武漢市における新型肺炎の流行にいち早く警鐘を鳴らし、自らも新型肺炎で命を落とした李文亮医師の独占インタビューを掲載したほか、都市封鎖の状況及び経済的な影響に関する精力的な調査報道を行った。その一連の調査報道は東洋経済オンラインや日経ビジネスで翻訳されるなど、海外でも大きな注目を集めた(陸、2019)。
報道の自由が大きく制限された中国社会において、胡氏は、政府ににらまれてつぶされてしまうような事態を独特の「嗅覚」で慎重に避けながら、できるだけ「事実」に迫るような質の高い報道を行ってきた。中国社会ができるだけリベラルな方向に向かうよう、ソフトな形で世論の喚起を図る、いわば体制内にとどまりながら中国社会の改革を権力者の耳にも入る形で行いながら社会を変えようとするのが胡氏のスタンスだと言ってよい。
さて、胡氏は『財経』誌の編集主幹だった時から竹中氏、および彼が行おうとする経済改革について注目し、記事としてたびたび取り上げるだけでなく、二度にわたるロングインタビューを行っている。特に、メルクマールとなったのが『財経』2006年1月23日号の「日本の改革を解読する」という日本経済の特集記事である。
この特集は、竹中氏以外にも田中直毅氏、加藤寛氏といった経済評論家、および何人もの財界人に対してインタビューを実施し、さらに胡氏らによる詳細な解説が加えられるという、非常にボリュームのある特集であった。この際の竹中氏に対するインタビューは、胡氏の後日の記述によると、2005年の暮れに彼女が日本を訪問した際に、彼女のたっての希望で行われたものだという(胡、2010)。
小泉内閣の時期、首相の靖国神社参拝などの問題もあり、中国各地で大規模な反日デモが起きるなど、日中関係は険悪なムードが支配した。また、日本人の対中感情も大きく悪化した。しかしその一方で、小泉内閣が進める「構造改革路線」への中国の「改革派」メディアや経済学者の関心はかなり高かった。中でも改革の先導役としての竹中平蔵氏に注目が集まっていたことは、すでに述べた通りである。
インタビューのトピックは、不良債権処理から郵政事業民営化まで多岐にわたっているが、特に1997年のアジア金融危機以降の日本経済に関する見解を問われた際の以下の発言に、現在にいたる竹中氏のスタンスがよく表れている(胡=林=法、2006)。
(この10年)日本経済の動きは非常に緩慢で、安定した停滞を経験してきました。 これはある意味で非常に危険なことです。 日本経済が(アジアの)他の国のような危機に陥らなかったことは、幸いでもあり、不幸でもあります。
(中略)もし日本が東南アジアのような危機に見舞われていたら、多くの政治家や国民は改革の重要性に気づいていたかもしれない。 しかし、日本にはそのような危機はなく、1990年代における「失われた10年」においてさえ、成長率は非常に低いものでしたが、とにかく日本経済は成長を続けていた。すなわち、危機が存在しないところに、改革への圧力は存在しないということです。
インタビューを実施した胡氏も、日本経済に関する竹中氏の見解を踏襲する形で、以下の様にまとめている(胡、2006)。
経済学者たちは、日本の経済衰退は周期的なものではなく、構造的なものであると明言している。構造改革が非常に困難であることが、日本経済の回復を遅らせてきたのだ。
(中略)日本は産業界・金融界・政府が一体化した、強大な社会的利益集団を形成してきた。また従来からの終身雇用制度が、日本国民の伝統的な体制への依存をもたらしてきた。このため、『小さな政府』を実現し、より一層の市場化を推進することが国家の長期的な経済発展にとって有益であるにもかかわらず、これまでは誰も改革のコストをだれ分担しようとせず、実行に移せなかったのである。
注意しなければならないのは、このような胡氏らによる竹中氏への高い評価は、あくまで中国国内の状況を念頭に置いたものである、ということだ。すなわち、上記のように胡氏が発言するとき、日本経済自体に対する興味もさることながら、やはり政府による市場への非効率な介入が横行する中国においても、市場志向的な「小さな政府」を目指す改革の断行が必要だ、という、中国国内の「改革派」としての主張が見え隠れする。
特に胡氏が、常に政府からの理不尽な介入により事実に基づく報道を脅かされてきた気骨のジャーナリストであることを考えれば、そこに込められた意図は明らかであろう。すなわち、胡氏のような中国国内の改革派はあくまでも、「市場から退場しようとしない国家」をメインのターゲットにしている。
なお、連載の第二回、第三回で詳しく触れる通り、それに対して、竹中氏がいう「構造改革」は、「国家の役割の縮小」を主張するだけではなく、それ以上に終身雇用制度や、特定郵便局制度に代表される、日本社会に残る様々な「古い慣習」や、中間団体の一掃をねらったものだ、という重要な違いがあることには注意しておいたほうがよい。
共振する竹中型の政策と中国型の政策
第一次安倍政権以降、竹中氏は政治の世界からは離れるが、その後も著名な経済学者として中国のメディアにはしばしば登場する。トピックも人民元の自由化問題であったり、財政再建問題であったりさまざまだが、竹中氏の発言が「小さい政府」を志向する改革派の経済学者の意見として取り上げられる状況は一貫している。
たとえば第二次安倍内閣における財政問題に関するインタビューでは、日本の法人税の高さが海外との競争力を低くしていることに言及し、財政再建は必要だが、そのためには増税よりも政府支出の抑制が重要だとする彼の発言が紹介されている(「竹中平藏:消費税増加不能徹底解决財政赤字」『新浪財経』2013年9月12日、、2020年9月4日アクセス)。
周知のように、2012年に成立した第二次安部政権で竹中氏は産業競争力会議の民間議員ならびに、国家戦略特区諮問会議の議員として、アベノミクスの「第3の矢」の旗振り役の一人として政治的なプレゼンスも増していく。それに伴い、再び中国のメディアでの登場も増えていく。その中で、竹中氏と中国との関係にも微妙な変化がうかがえるようになってくる。
もちろん、中国メディアが竹中氏を取り上げるときには、依然として中国の改革を進めていくうえでのヒントを彼の言説に探すものが多いことには変わりはないのだが、一方で竹中氏の経済思想や改革の方向性が、中国で現に行われていることとシンクロするような現象が目立つようになってくるのだ。
その際の重要なキーワードが、2015年より中国政府が、中国経済の持続的な成長を模索する中で提示された「供給サイドの改革」だろう。これは「過剰生産能力の削減、過剰在庫の削減、デレバレッジ(企業債務の削減)、企業のコストダウン、脆弱部分の補強」という一連の構造改革政策を通じて、経済の効率性を向上させ、これまでの資源投入型の成長に代わる持続的な経済成長を目指す、というものである(沈、2019)。
例えば、上海交通大学副教授の黄少卿(こう・しょうけい)氏は、習近平政権下の中国が「供給サイドの改革」を進めるにあたっては、国有企業を中心としたいわゆる「ゾンビ企業」の退出が必要だと述べたうえで、その際に財政投融資にメスを入れる、竹中氏が主導した小泉政権下の改革が参考になるのではないか、と指摘している(黄、2016)。
 |
| 田中真紀子から奇人変人と言われた首相:小泉純一郎 |
また、それより少し前のことになるが、2010年に竹中氏が中国を訪問した際に胡氏と行った対談で、彼が政府と市場との関係について述べた次のような発言も興味深い(胡、2010)。すなわち、政府支出には「救済型」と「根本治療型」があり、これまでの日本の財政支出は「救済型」であった。その代表的なものが失業者に対する給付金である。
しかしこのような「救済型」の支出を続けていく限り、財政収支が悪化するのは避けられない。したがって経済成長自体を加速させて自然に財政収入が増加するようにする「根本治療型」の財政支出を行うべきである。この点、中国は日本を反面教師にすべきだ、と。
なぜこの発言が注目すべきなのか。全世界がコロナ禍に見舞われた2020年、日本を含めた多くの主要国が、企業や個人への「救済型」の財政支出を積極的に行い、財政赤字を膨らませている一方で、武漢市での感染拡大を徹底した都市封鎖で抑え込んだ中国は、その後の経済対策において、竹中氏のいう「根本治療型」の政府支出を優先する政策によって、いち早くコロナ・ショックからの回復を実現しようとしているからである。
2020.09.27
# 企業・経営
# 中国
竹中平蔵氏の「雇用流動化」政策が、中国で人気になっている理由
日中で共鳴する新自由主義の行方(2)
2020.09.27
あの竹中平蔵氏が、中国で大いに人気を集めているらしい。中国の人々はいったい竹中氏の何に惹かれ、彼から何を得ようとしているのか。その背景を追っていくと、日中で共振する「新自由主義」の動きが見えてきた。神戸大学・梶谷懐教授による全3回のレポート。
第2回となる今回は、新型コロナウイルスの感染拡大によって深刻な失業率の上昇を経験した中国社会が、それでも不安定しなかったメカニズム、そして中国政府のコロナ対策と竹中氏が提唱する経済政策の類似について解説する。
中国政府のコロナ対応と労働の流動化
武漢市・湖北省をはじめとして、2020年初頭に中国全土を襲ったコロナ禍は、都市封鎖等を通じて人・モノの流れを停止させ、中国ならびに世界経済に大きな影響を与えた。
コロナ禍がもたらす需要・供給両面のショックに対して、中国政府がまず打った手は資金繰りに苦しむ企業への潤沢な流動性の供給である。2月1日には、中国人民銀行や財政部など経済政策を管轄する5つの部署が連名で、「新型肺炎流行の影響を最小限にするために金融政策を強化する通知」を発表した。
この通知を受けて、中国人民銀行は直ちに、湖北省など肺炎の流行が深刻な地域の企業、医療品や生活物資を生産する産業、さらには都市封鎖の影響が大きい小売り、宿泊、飲食などの産業、小型零細企業などを対象として、人民銀行が定める貸出市場報告金利(ローンプライムレート、LPR)の水準を大幅に下回る低金利融資を実施した。
さらに政府は、期限付きの社会保障費や住宅積立金の免除、さらに特にコロナ禍の影響が大きい地域などの中小企業を対象とした減税などの財政出動を次々と行った。そのほか、感染症防止のための財政出動、人民銀行再貸出に対する金利補填など、これまで行われたトータルの財政支出規模はGDPの1.2%とされる。
ただ、この財政支出のレベルは他の主要国の対応と比べると、極めて抑制されたものだと言わざるを得ない。2020年3月以降、全世界への感染の広がりを受けて、日本や米国も含め世界の主要国は相次いで市民の生活を支える現金給付や休業を余儀なくされた企業や店舗への補償をこれまでにない規模で行ってきた。一方で、中国政府は、そういった財政支出による市民や企業への直接補償をほとんど行っていない。
もちろん、さらなる財政出動の必要性は中国政府も認めている。例年よりも大幅に日程を遅らせて5月22日に全国人民代表大会が開幕した。5月28 日に報告された2020年の国家予算案では、コロナ禍に対応するためのさらなる財政支出拡大のために、地方特別債の発行枠を、昨年(2.15兆元)に比べて1兆6000 億元増やして3兆7500億元と大きく増加させることが明記された。
さらに、感染防止対策の費用に充てるための1兆元規模の特別国債を発行することも盛り込まれるなど、財政赤字は対GDP比の3.6%以上と、これまで事実上の「上限」と考えられていた3%を大きく上回り、財政赤字の額は2019年に比べ1兆元増加することが見込まれている(于=張=程、2020)。
また地方特別債の発行によって調達される資金は、5Gに代表される次世代情報ネットワークなど、いわゆる新型インフラの整備、新型都市化の建設の推進、都市部の古い住宅地の改築、交通・水利などにかかわる重要プロジェクトの建設などのような用途に用いられることが見込まれている(中国投資銀行部中国調査室、2020)。
中でも、景気刺激策の目玉になると考えられているのが、5Gなど高速通信網の整備、さらにはデータセンターやAI、スマートファクトリーなどのイノベーションが著しい分野を中心とした、いわゆる「新インフラ建設(新基建)」への投資である。
そこには、リーマン・ショックの際の4兆元規模の景気対策が、特に地方政府によるなりふり構わないインフラ建設と不動産バブルを招いたことの反省から、あくまでも供給サイドの効率性を重視し、成長部門に重点的に財政資金を投入しようという姿勢がみられる。
失業者が激増したが…
さて、以上のようなコロナ禍に対する中国政府の経済政策の特徴は、1.個人の所得補償よりも企業への低金利融資を重視する、2.供給面のショックが大きい局面では総需要を刺激する政策を控える、3.財政出動による景気刺激策では効率性に配慮したインフラ投資を重視する、などの点によって特徴づけられよう。これは、資源の効率性を重視し、需要面よりも供給面のショックへの対応を優先させる、経済学の主流派の考え方に沿った対応だといえる。その結果、6月の工業付加価値は対前年比4.8%の増加を記録するなど、文字通りのV字回復を遂げた。
たとえば、2020年3月にかつて竹中平蔵氏が理事長を務めたシンクタンク、東京財団研究所が発表した新型コロナウイルス対策に関する緊急提言でも、感染拡大が懸念され、供給面のショックが大きい局面と、感染が終息した後の局面を分けたうえで、個人への現金給付などの総需要刺激策は前者の局面では有効ではなく、後者の局面において、しかも生産性の向上が見込まれる分野にターゲットを絞って行うべきことを主張していた(「【経済学者による緊急提言】新型コロナウイルス対策をどのように進めるか? ―株価対策、生活支援の給付・融資、社会のオンライン化による感染抑止―」『東京財団研究所ウェブサイト』2020年3月17日)。
しかし、上記のような中国の対策は、資源配分の効率性を重視するあまり、失業率が大きく上昇する中、零細な事業者や不安定な雇用環境に置かれている労働者への救済が不十分になっている側面がある。生産が回復するなかでも、サービス産業などでは、むしろ失業や賃金カットなどの需要ショックが生じていた。
2020年2月の都市調査失業率の数字は6.2%と統計が公表されるようになってから最高の数値を記録したが、現実の失業をめぐる状況はこの数字をはるかに超える深刻なものだという指摘が相次いで行われている。民間エコノミストらの推計によると、3月期の都市における失業者数は7000万~8000万人、失業率にすると約20%に達していた。また、その70%以上は最もセーフティネットが脆弱な農民工であるという(張2020、李2020)。
サービス業を中心に、需要ショックに見舞われた産業、特に零細な中小企業は、政府からの援助を全く受けられない中で、高い技能を持たない、周辺的な労働者の雇用を減らすことで危機をしのいでいる、という構図が明らかになる。
中国の労働問題に詳しい石井知章氏は、「感染拡大の影響が比較的大きな飲食、ホテル、娯楽、卸売り、小売りなどの業界では、すでに大規模な人員削減が行なわれ」、 「違法な労働契約の解除や労働契約の解除の条件と手順に合致しないなどの事態に至って」おり、結果として労使間の紛争も頻発していると指摘している(石井、2020)。
社会が不安定化しない理由
ただ、このようにコロナの影響による深刻な雇用問題を抱えながらも、今のところ中国社会はそれほど顕著な社会の不安定化に見舞われてはいない。その背景には、もちろん政府による抑圧により問題が顕在化しないという可能性もあるが、それだけではない。中国社会における労働市場の流動性の著しい高さが、コロナ禍による失業問題の深刻さを覆い隠しているという側面を無視することはできない。
中国における労働市場の流動性の高さを象徴するのが、「従業員シェアリング」である。上述の石井氏によれば、コロナ化による労働市場の需給の矛盾が広がる中、「業務の爆発的拡大によって労働力不足に悩む企業の問題を解決すべく、「従業員シェアリング」モデルが生み出され、異業種間で直面する労働力の需給ギャップを一時的に解決する有効な手立てとなった」。
これは、製造業やIT系の大企業が、一時休業している飲食店、ホテル、大型スーパーなどの従業員を一時的に雇用するものであり、財政による休業補償が得られない中、労働者の生活を一定期間支える上では効果を上げた。一方で、一人の労働者が複数の雇用者と契約することで、労使間の矛盾がさらに複雑な形で顕在化しつつあることも指摘されている。
このような労働市場の流動性の高さが、失業問題がもたらす社会不安を和らげるカギであることは、中国の指導者層にもよく理解されている。例えば、5月には、李克強首相が山東省煙台を訪れた際に、露天商のたくましさを称賛し、「露店経済」すなわちインフォーマル・セクターが失われた雇用を吸収することに期待する発言を行った。
さらには、後述のように、ここ数年のシェアリングエコノミーの普及に伴うギグ・エコノミー、すなわちインターネット・プラットフォームを通じた短期的な雇用・労働形態の広がりも、コロナ禍の需要ショックに伴う失業者の増大のショックを緩和するのに寄与したと考えられる。
このような、労働市場のさらなる流動化の促進が、単にコロナ禍による一時的な失業問題の解決だけではなく、「供給サイドの改革」を掲げる今後の中国経済の持続的な経済成長のために要請されていることは、2020 年3月30日に中国共産党が発表した、「生産要素市場のより完全な配置体制とメカニズムの構築に関する意見」からも明らかである(リサーチ&アドバイザリー部中国調査室、2020)。
同意見書は、土地・労働・資本・技術・データといった5大生産要素について、(1)市場メカニズムに従い、効率性の高い配置を実現する、(2)要素のスムーズな移動を阻害する制度的要因を撤廃し、生産要素市場の構築と発展を促進する、という方向性を強調している。
要は、第1回で述べたような、中国が目指す(竹中氏の経済政策に似通った)「過剰生産能力の削減」を伴う「供給側の改革」の実施は、予想される多くの企業倒産によってあふれ出る失業者を、より効率よく吸収するための労働市場の流動化を必然的に要請する、ということである。すでに述べたようなコロナ禍における従業員のシェアリングやギグ・エコノミーによる雇用吸収は、そのための格好の予行演習といえるかもしれない。
いずれにせよ、コロナの前後を問わず、中国政府の労働問題への対応は雇用の流動化を重視するという意味で新自由主義的なものであり、後述するように竹中氏が、日本経済が真っ先に取り組むべき課題として雇用の流動化を挙げていることともシンクロしていることに注意しておきたい。
雇用の流動化とギグ・エコノミー
竹中氏は、小泉政権期から、折に触れ日本における雇用の流動化の必要性を語っており、自らも2003年の労働者派遣法成立に代表されるように、それを促進する政策の実現に関与してきた。近年では、その主張の重点は外国人労働者の受け入れの緩和にシフトしつつある。
このことは中国メディアによる取材によってもうかがえる。例えば、2018年に行われた財新ネットによるインタビュー(王、2018)の中で、竹中氏は日本経済が直面する問題として労働力不足を挙げ、労働市場を対外に開放して移民を受け入れることが今後の成長に必要だと語っている。移民労働の受け入れを積極的に行うべきだとの持論は、「政策工房」代表で元経済産業省の原英史氏との共著『日本の宿題』(竹中=原、2020)の中でもより詳しく述べられている。
さらに興味深い点は、竹中氏は、特に中国メディアの取材に答える際には、きわめて率直に、人材派遣会社パソナグループの経営者としての立場を前面に出した発言を行っていることだ。たとえば、上記の財新ネットのインタビューには、以下のような発言がある。
一般的に、人々は短期雇用を不安定なものだと考えています。しかし興味深いことに、システムに登録している人たちのうち、そう考えているのは全体の4%に過ぎません。70~80%の人々は自ら希望して短期の雇用形態を選んでいるのです。なぜなら、長期間雇用が固定されていなければ、引っ越しや旅行もできますし、子供の面倒も見ることができるからです。人々が短期雇用に対して抱いている印象や偏見は、その多くがマスメディアによる歪んだ報道によって作られたものです。
2017年に行われた英Financial Times紙の中国語版によるインタビューでも、竹中氏はほぼ同じようなニュアンスの発言を行っている(徐、2017)。ちなみに、このFT紙のインタビュー記事のサブタイトルは「日本は心地よすぎて変われない」である。要するに、人々が好きな時に好きな時間だけ働けるように、雇用はもっと流動化されるべきであり、そうした方が労働者の利益にもなる、しかし、現在の状況が「心地よすぎて変われない」のだ、というのが彼の主張である。
このような「雇用の流動化」を究極まで進めたものが、配車サービスの運転手もしくはウーバーイーツのようなデリバリーサービスの配達員といった、プラットフォームに登録しておいて空き時間を使って労働するような「ギグ・エコノミー」であろう。よく知られているように、この「ギグ・エコノミー」の世界的な先進地域の一つになっているのが中国である。
筆者と高口康太氏の共著である『幸福な監視国家・中国』で紹介したように、中国では4Gによるモバイル端末の通信環境向上と、政府の「インターネット+」に代表されるITを利用した新たなサービスを後押しする産業政策によって、ライドシェアや出前サービス代行に代表される都市内配送などのギグ・エコノミーが瞬く間に広がっていった(梶谷=高口、2019)。
労働者がプラットフォーム企業を通じてエントリーし、企業などと直接契約を結ぶわけではないギグ・エコノミーは、労使間の雇用契約を骨抜きにし、労災や超過労働のリスクを高めることが指摘されている。しかし、中国社会においてはギグ・エコノミーの広がりは基本的に肯定的にとらえられている。
その背景にあるのは第一にそれが高収入をもたらす、という点である。大卒のホワイトカラー層と非熟練労働者の給与にはもともと大きな格差があった中国において、場合によっては一般的な工場労働の二倍以上の収入をもたらすギグ・エコノミーの隆盛は非熟練労働者に新たな仕事の選択肢を与えて、生活水準を引き上げる効果を持ってきた。
第二に、もともと中国社会は短期雇用が労働契約に占める比重が高く、そこに「請負」、すなわち企業と労働者の間に仲介者が入ることも多かったということがあげられる。公務員や国有企業をのぞけば、中国の労働者は転職が多く、雇用の流動性が高い。農民工とよばれる出稼ぎ労働者も、春節の休みに地元に戻ったときに各地で働く仲間たちと情報交換し、より条件の良さそうな職場を求めて新たな土地に移動する、という光景はよく見かける。
さらに、李克強首相が称賛した屋台や露店商などの自営業、街の便利屋などの零細業者はさらに流動性が高いが、このようなインフォーマル・セクターの分厚さも、社会全体の雇用の流動性を高めている。
このように中国における労働の流動性の高さが、コロナ化による労働市場へのショックが社会問題として顕在化しないためのバッファーの役割を果たしていることはすでに見た通りである。ただ、だからと言って、日本がコロナのようなパンデミックに強い社会になるためには、中国なみに雇用の流動化を進めることが必要だ、と考えるのは短絡的に過ぎるだろう。そこには、日本と中国が、特に「中間団体」の果たす役割について全く異なる構成原理を持った社会である、という認識が欠けているからである。

竹中平蔵氏「5年で1000万円、政治家の不記載にガタガタ言うな」であふれる憤激「ならば国民も脱税を」
2024年3月4日
「年間200万円の不記載で大臣クラスがやめるのは海外だと驚かれる」と話した竹中平蔵氏
自民党の裏金問題について、経済学者・竹中平蔵氏の《年間200万円の不記載で過剰にガタガタすべきではない》という発言が物議を醸している。3月2日配信の「みんかぶマガジン」で、健全な社会には、グレーゾーンをある程度許容することが必要としたうえで、こう述べた。
松野博一前官房長官が5年間で作った1051万円の裏金は1年間だと200万円だとし、《年間200万円の不記載だけで大臣クラスが辞めるというのは、海外ではビックリされます》と綴った。
記事では《一切現金を配ってはいけないとルールを作ればいい》《全部デジタルで決算しなさい》と主張し、裏金問題の解決には、「政党法」によってガバナンスを効かせる仕組みが不可欠だと強調。

そうした提案を含めた記事なのだが、「過剰にガタガタ」という表現に違和感を覚えた読者も多かったようで、「X」では非難轟轟となった。
《国民を非正規に追いこんで貧乏にしまくってこの言い草》
《貧困を蔓延させて日本社会を壊したのがお前らだろ》
《裏金を放任しないと「成り立たたなく」なる社会とは》
《じゃあ国民も5年で1000万くらいの脱税をしてもいいって解釈でいいか?》
竹中氏は、2024年2月27日、YouTube「竹中平蔵の平ちゃんねる」で「裏金問題で揺れる自民党-派閥政治やめろ 企業献金やめろ-」と題した配信をおこなっている。
ここでは、献金は「政策を金で買うこと」であり、「いっさいお金は配ってはいけない」と語った。また、裏金は「脱税」と断じ、「国税がなぜ出てこないんでしょうか」と疑問を呈している。
「竹中氏も裏金は悪いことだと述べているので、発言の炎上は『切り取り』の感はあります。
ただ、竹中氏は、かつて閣僚として『労働の自由化』を推進し、その後、人材派遣大手・パソナ会長を長年務めた人物だけに、今でも『日本を壊した』『格差社会の元凶』というイメージを持つ人が少なくありません。
実際、さまざまなメディアでその点を突っ込まれる場面がしばしばあります。竹中氏自身は、『派遣拡大は厚労省がやったこと』だと反論しています。
また、『正社員が守られすぎている』とし、『同一労働同一賃金』を主張していますが、竹中氏のやったことは結果的に労働者の権利を縮小したことは間違いないでしょう」(経済担当記者)
小泉純一郎元首相の参謀として長期政権を支えた竹中氏。政治の世界を退いた今も、世論の風当たりは強いようだ。
Google社員、有給中の突然「レイオフ(一時解雇)」に唖然…終身雇用が崩壊しつつある日本でも普及しかねないレイオフに備えるためには
2024年3月4日
先月、Google勤務の日本人男性が、日本での有休中に突然解雇通知を受けたという話がXで大きな話題となった。それはアメリカのテック系企業で現在流行しているという「レイオフ」(一時解雇)だったそう。日本ではあまり知られていないレイオフとはいったいどういう制度なのか?
ゴールドマン・サックスなど金融業界にもレイオフの流れが波及
いま、欧米のテック系企業で流行している「レイオフ」という制度をご存知だろうか?
レイオフとは、業績が悪化した企業が人件費の削減を目的に、従業員を一時的に解雇すること。基本的には業績が回復した際には再雇用することを前提としているが、有休中や育休中などとは異なり、あくまで「解雇」なので給与は支給されなくなる。
アメリカでは新型コロナウイルス流行期に採用を拡大したところ、コロナの収束とともに、人員の過剰が目立つようになった。これがレイオフが流行した要因のひとつだと言われている。2022年後半から2023年初夏にかけて、主にテック系企業での大規模なレイオフが続き、今年に入ってからも再びレイオフ報道が相次いでいる。いまやGoogleやマイクロソフトといったテック系大企業のみならず、大手外資系のゴールドマン・サックスなど金融業界にもレイオフの流れが波及している状況だ。
そんななか今年2月、X上でGoogleのアメリカ本社に勤めていた日本人男性社員が、突然レイオフされたという内容のポストを投稿し、3.5万以上の“いいね”(2月末時点)を獲得し話題となった。
この男性は、なんの前触れもなく有休中に突然解雇されてしまい、いきなり無職に陥ったことに大きなショックを受けたようだ。
Xのポストの補足によれば、レイオフ後すぐにGoogle社員でなくなるわけではないようで、退職の準備期間は設けられていたそうだが、これには他のXユーザーから≪厳しい世界…≫≪外資はこんなにも冷酷なのですね…ビックリしました…≫と、企業のあまりのドライさに驚きの声が多く寄せられた。
この、日本ではあまり知られていないレイオフとはいったいどういう制度なのだろうか?
そこで、経営者側労働法専門弁護士として活躍し、多数の労働訴訟案件などを担当してきたKMM法律事務所の倉重公太朗弁護士に、レイオフについて法的な観点で解説してもらった。
そもそもレイオフって何? リストラとの違いは?
まず知っておきたいのは、アメリカにおけるレイオフの仕組みについてだ。
「アメリカの雇用の根底には『Employment-at-will』といって、雇用は雇用主と被雇用者との双方の自由意志によって成り立っているという考え方が存在します。よって、雇用主が従業員を解雇する際は、人種差別や性差別といったモラルに反するような理由でない限り、理由を問わず自由に解雇できる仕組みなのです。従業員もまた同じように予告や説明なしに仕事を辞めることが可能です。
今回話題になったGoogleのレイオフも突然解雇通知されたとのことで、日本とは真逆の価値観に驚く人も多く、こうして話題になったのでしょうが、アメリカでは割と普通のことなのです。
ちなみにレイオフは『一時帰休』とも訳されますが、あくまで一時的な解雇で再雇用の意思があるという姿勢を見せておくことで、労働者からの訴訟を避ける目的があると思われます。訴訟でもし企業が負けた場合には、多額の賠償金を支払う必要があるため、そうしたリスクは避けたいという意図がレイオフする理由のひとつとも考えられます」(以下、「」内は倉重氏のコメント)
そのほかにも、「一時的な解雇」にしておくことで優秀な人材の流出を抑制できることや、その人材が蓄積してきたノウハウなどの企業資産が損なわれないようにするといったことが、企業側のメリットとしてよく挙げらている。
日本とアメリカではそもそも雇用に対する基本的な考え方がまったく違うということだが、日本における解雇の特徴についても聞いてみた。
「日本ではいきなり解雇を通知するのではなく、社員への退職を段階的に促すことが多いです。一段階目が社内で退職者を募る『希望退職募集』、二段階目が社員を呼び出して退職を促す『退職勧奨』、それでも人員削減が追いつかない場合の最終段階として、はじめて一方的に解雇を通知する『整理解雇』が行われます。これらは一般的にリストラとも呼ばれています」
終身雇用が揺らぐ日本、レイオフが普及する可能性も…
現在日本ではレイオフはアメリカほど浸透していないが、それには解雇に対する労働法の厳しい規制が関係しているという。
「日本には『解雇濫用法理』といって、労働者を守るために会社からの一方的な解雇を制限する基本的なルールが存在します。このルールに違反した解雇は労働契約法16条によって無効とされます。長年、終身雇用が前提となっていた日本において、理由もなしに解雇を通達するようなことは不当解雇として扱われるのです」
しかし、倉重氏は日本の高度経済成長を支えた制度のひとつである終身雇用制が揺らぎかねない昨今の様子から、今後解雇のかたちが変わっていく可能性はゼロではないと指摘する。
「先ほど説明した『解雇濫用法理』は、企業が定年まで社員を雇う終身雇用制を想定して考えられたものです。しかし昨今の若者の間では転職が当たり前だったり、ずっと同じ企業に勤めることを逆に不安視したりする傾向が強いのです。高度経済成長期と違って経済状況も不安定ななか、大手企業にいれば一生安泰だという価値観も揺らいできています。
そういった背景もあるので、時代にそぐわない法やルールであれば、今後変わっていく可能性もゼロではない。とはいえ、政府が終身雇用を否定するような法改正をすれば支持率の低下に繋がるので、そう簡単には変わらないとは思う一方で、大手企業の崩壊が始まってから手を打つようでは遅いのではないかとも思います」
2019年に経団連の中西宏明会長やトヨタ自動車の豊田章男社長が、終身雇用制の維持が難しくなっていると発言し、これまでの雇用の価値観が揺らいできているのは明らかだ。
さらにはITやAIの進化で、長く働くことではなく、労働生産性や効率が重視される世の中になった。こうした働き方の価値観が変化している今、アメリカのようなレイオフが、今後日本で取り入れられるようになっていくこともあるのかもしれない。
Fullscreen button
終身雇用が揺らぐ日本、レイオフが普及する可能性も…
現在日本ではレイオフはアメリカほど浸透していないが、それには解雇に対する労働法の厳しい規制が関係しているという。
「日本には『解雇濫用法理』といって、労働者を守るために会社からの一方的な解雇を制限する基本的なルールが存在します。このルールに違反した解雇は労働契約法16条によって無効とされます。長年、終身雇用が前提となっていた日本において、理由もなしに解雇を通達するようなことは不当解雇として扱われるのです」
しかし、倉重氏は日本の高度経済成長を支えた制度のひとつである終身雇用制が揺らぎかねない昨今の様子から、今後解雇のかたちが変わっていく可能性はゼロではないと指摘する。
「先ほど説明した『解雇濫用法理』は、企業が定年まで社員を雇う終身雇用制を想定して考えられたものです。しかし昨今の若者の間では転職が当たり前だったり、ずっと同じ企業に勤めることを逆に不安視したりする傾向が強いのです。高度経済成長期と違って経済状況も不安定ななか、大手企業にいれば一生安泰だという価値観も揺らいできています。
そういった背景もあるので、時代にそぐわない法やルールであれば、今後変わっていく可能性もゼロではない。とはいえ、政府が終身雇用を否定するような法改正をすれば支持率の低下に繋がるので、そう簡単には変わらないとは思う一方で、大手企業の崩壊が始まってから手を打つようでは遅いのではないかとも思います」
2019年に経団連の中西宏明会長やトヨタ自動車の豊田章男社長が、終身雇用制の維持が難しくなっていると発言し、これまでの雇用の価値観が揺らいできているのは明らかだ。
さらにはITやAIの進化で、長く働くことではなく、労働生産性や効率が重視される世の中になった。こうした働き方の価値観が変化している今、アメリカのようなレイオフが、今後日本で取り入れられるようになっていくこともあるのかもしれない。
もしも、ある日突然レイオフされたらどうする?
もし日本でも今後レイオフが一般的になる未来が来るとしたら、レイオフ後どう対応すればいいのだろうか。
「レイオフは一時的解雇といえど、業績が回復して再雇用してもらえるのがいつになるのかわからない、先が見えない状態となります。そのためレイオフの期間中に転職することが一般的だと思いますが、その間収入が途絶えることに不安を覚える人も多いでしょう。しかし失業保険をもらうことで求職活動を続けられますし、レイオフは会社都合の解雇であるため退職金や一時金をもらえる場合もあります。
転職だけでなく、起業を考える方や、休職してゆっくり自身の今後のキャリアについて考える期間にする方など、レイオフ後の道はさまざまあると思います。これからの時代に大事なのは、突然解雇通知をされても困らないように、個人のスキルを高めて、企業に依存しない意識を持つことではないでしょうか」
取材・文/瑠璃光丸凪/A4studio 写真/shutterstock
地方公務員も非正規が増加、今年度74万2725人で最多…「5人に1人」の計算
2024年3月4日
地方自治体で働く非正規公務員の数が2023年度は74万2725人に上り、調査を開始した05年度以降で最も多くなったことが総務省のまとめで分かった。自治体の財政難の影響などもあり、正規公務員は近年、280万人前後で推移しており、働く5人に1人が非正規公務員になる計算だ。
総務省は2005年度から3~4年ごとに非正規公務員数を調査している。2005年度は45万5840人で、その後は増え続けている。前回調査の2020年度は69万4473人で、2023年度は6・9%の増加で74万2725人となった。
一方で、正規公務員数は1994年度の328万2492人をピークにその後は減少傾向になり、2010年度以降は270万~280万人で推移。最新の22年度は280万3664人だった。
自殺対策や児童虐待、生活困窮者支援など自治体が担う相談窓口業務が増えている。こうした対応にあたる必要があることから、非正規公務員が増加しているとの指摘が出ている。自治体側にも人件費を抑制したいという思惑があり、結果的に非正規公務員が増えているとみられる。
調査は、都道府県や市区町村などの任期6か月以上で1週間に19時間25分以上働く職員が対象。短時間勤務などを理由に、調査対象外の職員が47万6615人もいる。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
日本の「非正規雇用法(労働の不安定化政策)」の実態
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
「雇い止めは違法」非常勤講師が東海大学を集団提訴 “争点”を弁護士が解説
弁護士JPニュース - 2022年11月22日 12:14
東海大学に非常勤講師として勤務していた8人が、大学によってメール通知された「雇い止め」が違法だとして、地位の確認と来期以降の賃金の支払いを求め東京地裁に提訴、2022年11月21日会見を開いた。
原告の非常勤講師たちは、東海大学との間で契約期間1年の「有期労働契約」を締結し、毎年更新を行ってきた。契約の通算期間が5年を超えたことから、大学に対し「無期労働契約への転換」への申込権(労働契約法18条)を行使。
しかし、大学側は、「科学技術・イノベーション法」、「任期法」の特例を理由に、講師も研究者に該当、無期労働契約への転換には10年の通算期間を必要とすると主張、申し込みを認めなかった。その後、8人の原告全員に対し、「講座数を減らす」などとして、2022年度(2023年3月)限りの「雇い止め」を通告したことから提訴に至ったという。
「こんな形で終わるのは残念」
代理人の田淵大輔弁護士は、この裁判について、「任期法が最大の争点となるが、非常勤講師との関係で正面から判断した判決はない。特例の適用対象(労働契約法4条1項1号)にあたるのか。ただ、言い方が悪いが、大量に雇用し、多くの授業を回し、交代の要員が多くいるということであれば(専門分野の研究者の)要件にあたらないのではないか」と説明。できるだけ早く結論を出し、時間をかけないように進めたいと話した。
原告のひとり、河合紀子さん(非常勤講師・外国語)は、「全体の講座数が少なくなるので、4月に外国語の科目が選ばれなくなると告げられました。それは事情であって、理由ではないし、少しずつではなく、まったくなくなるということに納得できませんでした」と雇い止めに至る経緯を語った。
さらに、8月25日には「主体者が分からない」まま、来年の契約はないというメール通知を受けたという。「10年、20年以上働いている人にもメール1通。こんな形で終わるのは残念です。この大学で働く権利があると思いますし、正常な形で自分の科目に集中できる、無期雇用を認めていただきたい」(河合さん)
今回の提訴は8人であるが、今後その人数も増やしていくという。
「研究者」に“あたる”か“あたらない”か?
今回、「科学技術・イノベーション法」、「任期法」の特例など、やや耳なじみがないキーワードも多く、特殊な労働事件との印象も持ってしまう。しかし、普通の働く人たちにも関わる、軽視できない裁判と語るのは、労働問題の情報発信に注力している林孝匡弁護士。今回の裁判について、分かりやすく解説してもらった。(以上弁護士JP編集部)
━━━━━━━━
東海大から雇い止め通知を受けた非常勤講師8人が、東京地裁に提訴しました。提訴する理由は「無期転換を認めないことは違法だ」というものです。裁判では雇用継続を主張する模様です。
講師の8人は有期の雇用契約を繰り返し、通算で5年を超えていました。その後も繰り返し契約が更新されていたところ、今年2022年の春ごろ、大学から「来年2023年3月で雇用を打ち切る」とメール通知されたというもの。
裁判では、両者は以下のとおり主張を行うと考えられます。
■ 講師らの主張
契約期間が通算5年を超えているので無期転換を申し入れることができる。よって、雇用継続を求める。
■ 大学側の主張
この講師らは“研究者”にあたる。よって、5年ではなく、特例により10年である。10年を経過するのは、来年2023年の4月以降だ。
【研究者】にあたらなければ
もし“研究者”にあたらなければ、講師らは俄然優勢になるでしょう。
なぜなら、契約期間の通算が5年を越えていれば、無期転換への申し込みが認められているからです。
労働契約法 第18条
同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)が 5年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。
これを「無期転換ルール」と言います。
目的は、「有期契約という不安定な契約」から、「安定度の高い無期契約」への転換させようというものです(無期契約になれば雇い止めの心配はなく、解雇されるケースも相当制限されます)
【研究者】にあたれば
もし“研究者”にあたれば、上記の5年は適用されません。
なぜなら、下記法律によって、上記の5年ルールが【10年】に伸長されているからです。
・科学技術イノベーション創出の活性化に関する法15条の2第1号
・任期法7条1項
10年に伸長されていれば、論点は、雇い止めは合法か?に移ります。
講師らの契約がどれくらい繰り返されていたかなど、内容によりますが、大学の雇い止めが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められないものかどうかが争われることになるでしょう。
過去にもあった大学の“雇い止め”裁判
裁判所が「雇い止めは、社会通念上、相当ではない」と判断すれば、同じ条件での雇用継続が認められることになります。
労働契約法 第19条
有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
1 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。
2 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。
過去には、専修大学で類似の雇い止めの事件がありました。語学を教えていた非常勤講師が雇い止めの通知を受け、訴訟を提起したものです。
結果、講師は勝訴しました。〈学校法人専修大学(無期転換)事件:東京高裁 R4.7.20〉
大学側は「この講師は“研究者”にあたる」と主張したのですが、裁判所は「研究者にはあたらない」と判断し、契約期間が通算5年を超えている講師の無期転換を認めました。
裁判所が「研究者にあたらない」と判断した理由の骨子としては、この講師は語学の授業、試験その他の関連業務に従事してはいるが ”研究業務には従事していない” と言うものです。
今回の東海大の訴訟でも、この専修大の事件の【研究者】の定義を参考にして攻防が繰り広げられると考えられます。
雇い止めの空気を感じたら…
ちまたでは「直前のハシゴ外し」が横行しています。5年になる直前で雇い止めをしてくるケースが増えているんです。
企業は、
「5年を超えると、さらに同じ条件で雇わないとダメだからな〜」
「5年を超える前に雇い止めしちゃえ!」
と考え、近年、雇い止めしてくるケースが増えているということです。雇い止めの空気を感じたら、社外の労働組合や弁護士に相談しましょう。
労働組合は「あなたが住んでいる地名 ユニオン」でグーグル検索ででググれば出てきます。労働者の味方となって熱心に活動されているグループが多いので、一度相談してみましょう。
弁護士は、労働問題をウリにしている事務所が良いと思います。HPで判断しましょう。最近は、初回相談無料の事務所も多くなってきてます。
一度、突撃してみて相性が合わなかったら「また考えてみます」で退散してOKです。相性の合う弁護士さんを探してみてください。

岸田政権お前もか。竹中平蔵氏「デジタル田園都市構想」参画の波紋。マイナンバー頼みで目新しい政策なし=原彰宏
2021年11月11日
岸田首相の肝入りで設置した「デジタル田園都市国家構想実現会議」に参加する有識者のなかに竹中平蔵氏の名前が挙がったことが物議を醸しています。果たして日本のデジタル化は進むのでしょうか。世間からは「また中間業者がピンはねで潤うのか」と言った声が聞こえてきます。(『らぽーる・マガジン』原彰宏)
竹中平蔵氏「デジタル田園都市構想」参画決定にざわつく世間
岸田政権の成長戦略の一環である「デジタル田園都市構想」に関して、11日に、「デジタル田園都市国家構想実現会議」が初開催されることになりました。
議長は岸田首相が務め、関係閣僚・有識者も参加します。
その有識者として、竹中平蔵慶大名誉教授や増田寛也東大公共政策大学院客員教授らがメンバーに入ったと報じられました。そのほか、80代でスマートフォンアプリを開発した若宮正子氏ら14人が名を連ねたとのことです。若宮正子氏は、2017年に81歳でiPhoneアプリ「hinadan」を開発した世界最高齢のプログラマーです。
竹中平蔵氏がメンバーに入ることが報じられたことで、SNSでは大きな話題となっています。
竹中氏が動けば世間がざわつく……なぜかそのような構図になっている様子。ワイドショー的に捉えるのもどうかと思いますし、竹中氏に貼り付けられたレッテルだけで人物を判断するのもどうかとは思いますが、それだけ、政界において、いや政財界においての「キーパーソン」であることは間違いないようです。
小泉純一郎元総理が、金融再生・不良債権処理担当として抜擢してから、郵政民営化や雇用流動化政策など、竹中平蔵イコール「ミスター規制緩和」という印象が持たれ、その先が「利益誘導」ということになるイメージ誘導も、客観的に見て、ある意味すごいことだなという感じです。
事実として、小泉政権後は一時政界を離れながらも、有識者としてその後の政権が変わっても中央にお呼びがかかるという存在であることを、どのように理解すればよいのでしょうかね。
アメリカがどうとか、経済界代表とか、いろいろ言われますが、本当のところはわかりません。しかし、パソナ所属など「李下に冠を正さず」という思いは確かにあります。
かつて規制改革委員会の座長にオリックスの宮内義彦会長が就いたときも、散々なことを言われていましたね。
アベノミクス「第三の矢(成長戦略)」は岸田政権が放つ?
「デフレからの脱却」を旗印に出された“三本の矢”の経済政策(通称「アベノミクス」)では、以下が掲げられていました。
第一の矢:大胆な金融政策
第二の矢:機動性のある財政出動
第三の矢:民間需要を換気する成長戦略
“第一の矢”は放たれたものの、“第二の矢”はかなり中途半端で、“第三の矢”に至っては、放たれることもありませんでした。
国家戦略特構想という矢は、放たれましたかね。安倍総理は「“第三の矢”はIR事業」としましたが、カジノが成長戦略かと揶揄され、しかも矢を放つ前に、矢が折れた感じになってしまいましたね。東京五輪と大阪万博が「成長戦略」だとすると、もう“いわんや…をや”ですね。
当時の竹中氏は、「成長戦略」という安倍総理(当時)の言葉を聞いて、自分の経験では、「成長戦略」は役人が好んで使う表現で、よく提言で使われたが一度も実行した試しがなく、いいイメージがない……とおっしゃっておられたのを思い出します。その成長戦略の会議メンバーに、竹中氏が就くことになりました。岸田政権が、「アベノミクスの継承」として“第三の矢”を担当するのでしょうか。
金融緩和はもう十分ですし、財政出動はコロナ対策に向けられ(不十分だとは思いますが)、景気対策としての財政出動は、おそらくは「GoToキャンペーン」の再開だとは思いますが、成長戦略として「インフラのデジタル化」を置いているというメッセージなのかもしれませんね。
デジタルを軸に3つの成長戦略会議を新設
岸田政権の成長戦略に関して、3つの会議を新設します。
「デジタル田園都市国家構想実現会議」
「デジタル臨時行政調査会(臨調)」
「全世代型社会保障構築会議」
岸田首相は、8日の「新しい資本主義実現会議」の会合で、これら3つの会議での検討結果を統合した上で「来春にグランドデザインと、その具体化の方策を取りまとめ、世界に向けて発信する」と表明しています。
「デジタル田園都市国家構想」はその1つで、地方からデジタル化を進め、都市部との格差の是正を目指し、地方活性化へのビジョンを示す狙いとしています。「地方活性化+成長戦略」というもので、3人もの大臣が船頭になっているものですね。
ちなみに、牧島かれんデジタル担当大臣が取り仕切る「デジタル臨時行政調査会(臨調)」は16日に始動します。デジタル、規制、行政の改革を一体的に検討するもので、民間有識者8人を起用、ディー・エヌ・エー(DeNA)の南場智子会長やフューチャーの金丸恭文会長兼社長らが加わると報じています。
3つ目の、社会保障全般について議論する「全世代型社会保障構築会議」は、座長には日本私立学校振興・共済事業団の清家篤理事長が就き、傘下に増田氏が座長を務める「公的価格評価検討委員会」を置きました。9日に初会合を開き、看護師や介護士、保育士らの賃上げに向けた施策を練ったとのことです。
介護や看護の現場からは、もちろん賃上げは嬉しいですが、それだけで根本問題が解決するものではないという言葉も聞いています。
増田氏は「このままでは896の自治体が消滅しかねない」という東京一極集中に警鐘を鳴らす「地方消滅」という書籍を出すなど、地方分権に積極的な立場です。
果たして岸田政権で、これまで遅々として進まなかった成長戦略が一歩でも前に進むのか。
「デジタルが日本を救う」というお題目は果たして正解なのでしょうか。さらに、アベノミクス成長戦略継承なら、安倍政権下「国家戦略特区構想」はどうなっているのかを検証してもらいたい…などなど、今後とも目が離せないです。
これが岸田政権の通信簿の評価項目に入ることを、ここで指摘しておきたいです。
ここからは「デジタル田園都市構想」がどんなものなのかについて、解説していきます。
「デジタル田園都市構想」とは?関係する3名の大臣
前述の通り「デジタル田園都市国家構想」は、岸田文雄首相が成長戦略の柱の1つとして掲げているものです。つまり、地方のデジタル化によって、経済を発展させるというのです。
このプロジェクトに関わる大臣は3人です。
牧島かれんデジタル担当大臣は5日の閣議後記者会見で、若宮氏を中心に実現会議を開く方向で調整を進めていることに言及しました。
若宮健嗣内閣府特命担当相の担務は消費者及び食品安全、クールジャパン戦略、知的財産戦略および国際博覧会担当、共生社会担当、まち・ひと・しごと創生担当となっています。
牧島かれんデジタル担当大臣の他に、野田聖子地方創生担当大臣も関わってくるのでしょう。松野博一官房長官は5日の記者会見では、岸田内閣で地方創生分野は野田聖子地方創生担当相と若宮健嗣まち・ひと・しごと創生担当相が連携して取り組む方針を明らかにしています。
地方活性化を目指すデジタル社会構想会議
人口急減地域への支援強化、東京一極集中の是正に取り組む…。
首相と全閣僚で構成する「デジタル社会推進会議」や有識者会議「デジタル社会構想会議」など、デジタル社会の形成に向けた国の関連会議がそれぞれの役割を果たし、「デジタル田園都市」というものが、日本のそれぞれの地方で実装されていくことになるとしています。
昨年9月、平井担当大臣のもと「デジタル社会構想会議」を立ち上げました。
慶応義塾大学の村井純教授が座長を務めた構想会議は、有識者12人で構成、Zホールディングスの川邊健太郎社長、楽天グループの三木谷浩史会長兼社長、慶応大大学院政策・メディア研究科の夏野剛特別招聘教授らが参加しました。
昨年会合では、マイナンバーカードを生かした利便性の高い行政サービスの実現のほか、産業全体のデジタル化と、それを支えるインフラ整備を進める方針なども確認したとのことでした。
成長戦略の柱の一つなので、デジタル整備のためのインフラ設備に大きな予算を充てて、産業を活性化する狙いもあるのでしょう。
具体的には、5G網の整備に加え、インターネット用サーバーなどを集めた「データセンター」の設置、人工知能(AI)などを活用した最先端都市「スーパーシティ」の導入などを通じ、地方のデジタル化を進めるとしています。
政府は「デジタル実装加速化交付金」の創設などで、これらを後押ししたい考えだとしています。
デジタルデバイト(情報格差)の解消
誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化を……岸田総理が掲げるデジタル庁のミッションで、デジタルデバイド(情報格差)を解消し、全国津々浦々にデジタル化の恩恵を行き渡らせるための道筋を示すのだそうです。
デジタルデバイド(digital divide)とは、コンピュータやインターネットなどの情報技術(IT:Information Technology)を利用したり使いこなしたりできる人と、そうでない人の間に生じる、貧富や機会、社会的地位などの格差のことを言います。
コンピュータや通信ネットワークは、いまや職場や日常生活に深く入り込んでいて、それを活用できる者はより豊かで便利な生活や高い職業的、社会的地位を獲得できるのですが、情報技術の恩恵を受けられない人々は社会から阻害され、より困難な状況に追い込まれてしまうというのが現実にあります。
格差発生には様々な要因があり、以下などが挙げられます。
個人間:集団間:年齢・学歴・収入などの違いにより生まれる格差
国際間:先進国や発展途上国での国家間格差
地域間:都市部と地方部ということで生じる格差
問題は、情報技術の恩恵を受けられない「理由」にあります。「環境」と言い変えても良いでしょう。
たとえば「個人間・集団間」における年齢の問題。中高年や高齢者が新たにコンピュータの操作法などを覚えるのは困難な人が多いということです。
もちろんいまや高齢者のYouTuberもいるわけで、ネットがかなりフレンドリーな高齢者も増えてはきていますが、それでもやはり、少なからずもネットそのものを生活習慣に取り入れることに抵抗感があることが少なくない高齢者もいるということです。
深刻なのは、貧困のために情報機器の購入が困難だったり、身体機能の障害により機器の操作が困難だったり、情報技術の恩恵を受けられない場合があります。
地域や国家の単位での通信インフラの普及度合い
情報機器を購入できる所得水準か否か
技術の習得・利用の前提となる十分な教育が受けられるかどうか
インフラ整備や技術・機器の導入・教育を担う技術者などの人材が十分にいるか
などなど、地域ごと、国家ごとに格差が生じることもあります。
格差が生じる結果、デジタル知識がない層の孤立化があります。外部との情報手段が持てないということも考えられます。
デジタル知識が収入格差を生むことにもなります。DXの遅れは、企業の収益性にも影響があり、労働生産性の低下にも繋がります。セキュリティリスクも考えられます。
元々豊かな先進国や大都市が情報技術でさらに発展したり豊かになる一方、情報技術に十分アクセスできない発展途上国や農村部などが貧しいまま取り残されるという、格差の拡大・固定化の問題があるとされています。
岸田内閣では、このデジタルデバイト(情報格差)解消に取り組むとしているのです。お手並み拝見です。
現在のところ目新しい政策はまだ見えていない
牧島かれんデジタル大臣が述べている文章を読んでみても、「DX」とかお馴染みの言葉は出てきて「DN(デジタル・ニッポン)」という言葉も登場してきていますが、具体的にやることとなると「党内ペーパレス会議の実施」しか拾えないのですね。
地方活性化として、デジタライゼーションで地方にいても大都市並みに仕事ができ、収入が得られ、楽しく幸せに暮らせる……というのが「デジタル田園都市構想」だとしていますが、リモート会議、リモートワーク推進ということを言いたいのでしょうかね。
詳しいことは、自民党本部の制作ページから確認することができます。
https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/news/policy/200257_1.pdf
DXに関わる提言として、売買契約書、株主総会、医療診断、オンライン薬局、義務教育、試験制度、各種金融サービス党、行政サーボスや生活全般のデジタル化を徹底して、非対面、非接触、非(紙への)押印の手続きに変えるべき。
決済に関しても、顔認証を含め、非接触型への以降を進めるべき。
課題の指標化や、ベストプラクティス公開、DXサービス登録、DX銘柄の選定、DX投資への税制優遇等の検討。
すごい大量のページになっていますが、オンライン診療とオンライン教育、リモートワークしか目に止まらなかったのですが、特に新しい具体的なものがあるとは思えないのですがね。
オンライン診療やオンライン教育、リモートワークが揃えば、地方にいながら都会にアクセスすることができます。それが地方活性化だと言われれば、地方に住みながら都会のメリットを享受するということではあります。
限界集落や過疎地域における自動運転車の巡回、買い物補助や通院に利用してもらうというインフラ整備は、以前から考えられていたことです。
岸田内閣だけでなく、菅内閣でも、「デジタル」といえばマイナンバー、マイナポイント付与によるマイナンバーカード普及促進が、経済効果をもたらすというロジックは、そのまま継続されるのでしょう。
「新しい資本主義」を考える上での「デジタル田園都市構想」……何やら言葉だけが先行して、中身がさっぱりイメージできないというのが、岸田内閣の特徴なのでしょうかね。
日本社会は研究者を腐らせる?by経済評論家 加谷珪一
2021年のノーベル物理学賞真鍋氏「研究のために渡米した理由」、日本社会は研究者を腐らせる?
2021年のノーベル物理学賞に、気象学者で米国人の真鍋淑郎氏が選ばれたことが大きな話題となっている。真鍋氏の受賞はいろいろな意味で、日本という国のあり方について問いかけるものだった。真鍋氏の受賞から日本人は何を学べるだろうか。
 |
| 2021年のノーベル物理学賞に、気象学者で米国人の真鍋淑郎氏が選ばれた。彼の受賞から、日本の学術研究の問題点を考える |
●気象学の分野が受賞対象となった意味とは
今年のノーベル物理学賞は極めて大きな驚きを持って迎えられた。事前の予想を大きく裏切り、米プリンストン大学上席研究員で気象学者の真鍋淑郎氏が受賞した。これまでノーベル物理学賞は純粋な物理学の分野から選ばれることがほとんどだった。近年は青色発光ダイオードやリチウムイオン電池など物性の基礎理論を確立した研究者にも授与されており、工学的な要素も取り入れられているものの、物理学の範疇に入る研究業績が基本だった。
今回の受賞分野は気象学であり、物理学の分野以外では初めてのことである。気象学といっても真鍋氏の専門分野はコンピューターを使ったシミュレーションであり、計算科学に近い分野とも言えるが、少なくとも以前はノーベル賞の対象になる研究とは認識されていなかった。
新しい分野の業績に対して受賞が決まったのは、真鍋氏の学術業績が極めて高く評価されたからに他ならない。だが、ノーベル賞が特別な存在であることからも分かるように、政治的な意味合いも多分に含まれている。
受賞を発表したノーベル財団の記者会見では「今回の(気象学)の受賞は、世界の指導者に気候変動の深刻さを伝えるメッセージなのか」という質問に対して、選考委員から「いまだにメッセージを受け取っていないリーダーがいるのなら、今回も耳を貸さないでしょう」「気候モデリングが物理理論に基づいた事実であるということが私たちのメッセージです」という明確な説明があった。
選考委員によるこの発言はかなり踏み込んだものであり、事実上の政治的なメッセージであると判断して良い。しかも「いまだにメッセージを受け取っていないリーダーがいるのなら、今回も耳を貸さないでしょう」というかなり厳しい指摘も行っている。メッセージを受け取っていないリーダーが誰なのかは想像するしかないが、私たち日本人にとって耳の痛い話であることは言うまでもない。
 |
| 今回のノーベル物理学賞の受賞分野は気象学であり、物理学の分野以外では初めてのこと |
●日本の社会環境が独創的な研究の邪魔をする
分野が新しかったことに加え、真鍋氏が日系アメリカ人だったことも世間を驚かせた。米国には多くの日系アメリカ人が住んでいるが、ほとんどは二世や三世で親や祖父母が米国に渡った人たちの子孫である。真鍋氏は日本で生まれ、日本の大学を卒業した後に渡米し、わざわざ米国籍を取得している。
米国に渡る日本人研究者は少なくないが、学術分野でそれなりの実績があれば永住権(いわゆるグリーンカード)を比較的容易に取得できるので、研究生活を送る上での不便はほとんどない。それにもかかわらず米国籍まで取得したという現実を考えると、米国に骨を埋めたいという強い思いがあったと推察される。
米国籍を取得した理由について問われた真鍋氏は、日本の社会環境が研究成果にマイナスになるという現実について、冗談を交えながらも鋭く指摘した。
真鍋氏は会見で「日本では人々はいつも他人を邪魔しないようお互いに気遣っています」「日本で『はい』『いいえ』と答える形の質問があるとき、『はい』は必ずしも『はい』を意味しません。『いいえ』の可能性もあります」とし、日本における同調圧力について違和感を示した。
さらに「アメリカでは自分のしたいようにできます。他人がどう感じるかも気にする必要がありません」「アメリカでの生活は素晴らしいです。アメリカでは自分の研究のために好きなこと(中略)ができます」と述べ、米国籍を取得した理由について明確に説明した。
1997年には一度、日本に帰国し研究職に就いているが、結局は米国に戻り、米国での活動を続けている。日本の法律では二重国籍は認められないので、米国籍を取得すれば自動的に日本の国籍は失ってしまう。真鍋氏は日本で生まれ育った日本人であり、国籍の変更にはかなりの決断を要するはずだ。それでも真鍋氏は良好な研究環境を求めて国籍を変えた。
真鍋氏の行動について、研究者というのは独創性が必要な仕事なので特殊だという意見もあるが、そうではない。近年、日本の閉鎖的な社会慣習が学術研究はもとより、新しいビジネスの創出など経済面においてもマイナスになっているとの指摘は多い。こうした指摘に対しては「日本には独自の文化がある」といった反論が寄せられるが筆者はそうは思わない。
日本の文化というのはもっと柔軟なものであり、飛鳥時代から常に外国の良い習慣や技術を取り入れて独自の文化に昇華させてきたという歴史がある。明らかに日本にとってプラスとなる海外の習慣を取り入れないのは、むしろ本来の日本文化に反する行為といって良いだろう。
●科学技術を振興させるために本当に必要なこと
真鍋氏の経歴を見ると、日本と米国における科学技術に対するスタンスの違いにも驚かされる。近年、日本の科学技術が低迷していることから、研究開発への支援を強化すべきという意見をよく耳にする。だが現実はお寒い限りだ。
大学院を卒業して博士号を取得した人で、すぐに大学の教員や研究職に従事できる人はわずか1割強しかおらず。残りはポスドクと呼ばれ、任期付き採用という不安定な環境で研究を続けている。諸外国においても学術分野の競争は激しく、多くの博士号取得者がポスドクとなり、そこで必死に業績を上げて正規の研究職や大学教員のポストを手にしている。その点において、日本と諸外国が大きく変わるわけではない。
だが日本の場合、ポスドクに与えられる研究環境が極めて劣悪という特徴があり、研究成果を出そうにも、その環境自体が整わないという大きな問題がある。また正規の研究者になっても極度の予算不足という点では同じであり、研究を継続できなくなるケースも多い。このままでは、ポスドクは死ぬまでバイト…ということである。
人材の登用にも大きな課題がある。真鍋氏は東京大学大学院を卒業するとすぐに渡米したが、それは米国の気象局からオファーがあったからである。真鍋氏は大学院を出たばかりなので、当時は一人前の研究者とは言えない。米気象局は真鍋氏の大学院の博士論文を目に留め、内容が画期的であることから間髪入れずにオファーを出したものと考えられる。
日本の研究機関や行政組織が、海外の小国における学生の論文まで精査し、優秀な人材を即座にスカウトするなど、天地がひっくり返ってもあり得ないことだろう。日本にあてはめるならば、アジア各国の大学院生をすべてリサーチし、優秀な人は、次々と日本に呼び寄せるということを意味している。
●口で叫ぶのは簡単だが…
「日本の研究開発を強化せよ!」と勇ましく叫ぶことは簡単だが、実際に研究開発を強化するためには、こうした地道な努力が必要となる。
当時の米気象局では、成果を出せるかどうかも分からない大学院を出たばかりの外国人研究者を採用することで、米国人研究者の採用枠は1つ減ったはずである。国籍にかかわらず、優秀な人物の採用を優先するというコンセンサスが社会に出来上がっていなければ、研究開発の強化など不可能であり、米国や近年の中国ではこうした戦略が貫かれている(近年、良好な研究環境に魅力を感じ、中国に渡る優秀な日本人研究者が増えているし、有名な日本電産の開発部門の技術研究所も中国に移転した、また日本の家電の中心的技術者も軒並み中国へ引き抜かれ、アイデアが中国公営企業に渡ってしまった)。ひるがえって、日本社会や日本政府に、その覚悟があるだろうか。
予算配分についても問題が山積している。日本では研究予算を確保するにあたり、研究がどのように役に立つのか説明する計画書を提出しなければならない。だが、画期的な研究業績がどこから出てくるのか事前に予想するのは不可能であり、そもそも「社会の役に立つ研究」を支援するという概念自体が、学術の世界ではナンセンスである。役に立つのかどうかは、成果が出てから分かることであり、今役に立つことが分かっている理論というのは、もはや画期的とは言えない。
ちなみに真鍋氏は渡米後、一度も研究開発計画を書いたことがないという。画期的な学術成果を求めているのなら、潤沢な予算を確保し、優秀な人材にやりたいように研究をやらせるしか方法はない。支援した研究の多くが何も成果が出ずにムダに終わってしまうことについても社会的理解を得ておく必要がある。いわゆる日本型のムラ社会においては、外国人研究者の登用と同じく、こうした予算配分についても多くの反対意見が出るのではないだろうか。
これまでと同じように、非合理的で閉鎖的な研究環境を継続すれば、日本の科学技術の水準がさらに低下していくのは目に見えている。
経済評論家 加谷珪一
アメリカ西海岸からの緊急提言 2021年10月
激動の時代に日本はアメリカからどう見えているのか。スタンフォード大学アジア太平洋研究センター在籍の社会学部教授・筒井清輝氏と、カリフォルニア大学バークレー校ハース経営大学院ハース・エグゼクティブ・フェローの桑島浩彰氏による特別対談。アメリカ西海岸からの緊急提言がここに。
人文関係の「日本研究」で研究者としてやっていけるのか
桑島浩彰(以下:桑島) 私がここ数年で強く感じるのは、いまアメリカ国内で、アジアにおける関心が大きく中国に向かっているということです。日本が世界中から注目されていた時期は、アメリカの社会学者エズラ・ヴォーゲルが『ジャパン・アズ・ナンバーワン』を出版した後の1980年代でしょうか。
その後、日本のGDPの停滞と中国の台頭によって、アジア研究の中心は日本から中国へと移っていった。実際、日米関係という観点で見ても、アメリカでの日本研究にかけるリソースが大きく減っているのが現実のように見えます。スタンフォード大学ではいかがでしょうか。
筒井清輝(以下:筒井) それはこの10年、20年ほどの間に顕著になってきた傾向ですね。私が所属しているスタンフォード大学アジア太平洋研究センターは、まさに日本が経済成長を続けていた1983年に設立されました。
当時は、「なぜ日本が強いのか」というのが大きなテーマで、日本の企業や省庁が研究対象とされて、盛り上がりを見せていました。実際、アジア太平洋研究センターで所長を務めていたのは日本研究をしていたダニエル・オキモトでした。彼は、ハーバードのエズラ・ヴォーゲルと並ぶ日本研究者ですね。
他にも、著名な経済学者の青木昌彦もスタンフォードにいて、日本の経済や企業の仕組みが、どう日本経済の成長に貢献したのかを比較制度分析していました。
なぜ当時は、日本研究が盛んだったのか。それは、1980年代くらいに大学生だった人にとって、これからおもしろい国、これから伸びる国といえば日本という認識があったからなんです。それが今は完全に中国ですよね。
もちろん人文系の分野で日本のアニメや映画などのポピュラーカルチャーに興味を持つ学生や研究者はかなりの数います。ただ、政治経済の面では本当に少ない。
私が着任する前の年は、スタンフォード大学アジア太平洋研究センターで日本研究をやっている教授は1人もいませんでした。今でも私1人です。一方で中国研究は7人、韓国は3人と、日本研究には逆風の状況です。
桑島 私が懸念しているのは、これ以上アメリカでの日本研究者が減ると、アメリカの対日政策にマイナスの影響が出るんじゃないかということです。
たとえば、前述したエズラ・ヴォーゲルをはじめ、ハーバード大学の政治学者ジョセフ・ナイ、現米国家安全保障会議インド太平洋調整官のカート・キャンベルなどの日本にも明るい研究者が、米国の対東アジア政策に関わってきました。ところが、今後も日本研究者が減っていくと、必ずしも日本に明るくない人物が対東アジア政策を担うリスクがある。そんな心配をしています。
<独自>中国企業、帰化元社員に情報要求か 山村硝子の独自技術流出
2023年10月17日
ガラス瓶製造大手「日本山村硝子」(兵庫県尼崎市)の独自技術を中国企業に渡すため不正に入手したとして元社員ら夫婦が逮捕された事件で、山村硝子と中国企業の契約が打ち切られた後に技術情報が持ち出されていたことが16日、関係者らへの取材で分かった。また、夫婦とも元中国籍で日本に帰化していたことも判明。中国企業が元社員に漏洩(ろうえい)を持ちかけた疑いもあり、兵庫県警が詳しい経緯を調べている。

県警生活経済課などが不正競争防止法違反容疑で逮捕したのは、山村硝子元社員の小鷹瑞貴容疑者(57)=懲戒解雇=と、妻でガラス製造技術コンサルタント会社「アズインターナショナル」社長、青佳(せいか)容疑者(51)。平成28年、2016年6月、山村硝子のサーバーにアクセスし、ガラス瓶軽量化の技術に関するプログラムを私用メールアドレスに転送した疑いが持たれている。
山村硝子や関係者によると、瑞貴容疑者は平成15年に入社。平成25年5月~29年7月に海外チームに所属し、中国で技術契約に関する営業、通訳などに従事していた。もともとは中国籍で中国語が堪能といい、中国での営業を長く担当していたという。
同社は事件前、情報の流出先とされる中国のガラス瓶メーカーと技術支援契約を締結。瑞貴容疑者が担当していたが、契約が打ち切られたという。その後、瑞貴容疑者らが持ち出した情報は、ガラス瓶の超軽量化を図るためガラスを薄くする特殊な計算式で、二酸化炭素(CO2)削減などにつながる山村硝子の独自技術とされる。瑞貴容疑者は営業職として技術情報へのアクセス権限があった。
一方、青佳容疑者もかつて中国籍で、社長を務めるコンサル会社が事件約1カ月前の平成28年、2016年5月、この中国メーカーとライセンス契約を締結していた。同8月~令和3年4月には、中国メーカー側から20回にわたって計1億8960万円相当の入金があったという。営業秘密はコンサル会社を通じて中国側に提供されたとみられる。
山村硝子は東証スタンダード上場で、国内のガラス瓶生産シェアトップとされる。外部からの情報提供があり、社内調査で不正が発覚した。
相次ぐ流出、スパイ活動に高まる懸念
日本企業の営業秘密が中国などに持ち出される事件は度々起き、政府は近年、先端技術の海外流出を防ぐ経済安全保障対策に力を入れている。外国スパイによる情報流出も懸念されるが、日本にはスパイ活動自体を取り締まる法律がない。警察幹部は「流出は日本の技術的優位の低下を招く。企業は意識を高め、対策してほしい」と話す。
警察庁によると、全国の警察が昨年摘発した企業情報持ち出しといった営業秘密侵害事件は29件で、統計を取り始めた平成25年(2013年)以降で最多。中国などは先端技術などを獲得するため、民間人も活用した「情報戦」を展開しているとみられる。
令和2年(2020年)、液晶技術に関する情報を中国企業に漏洩したなどとして積水化学工業の元社員が書類送検された事件では、中国企業側がビジネス向けSNSを通じて元社員に接触。国立研究開発法人「産業技術総合研究所」の研究データを持ち出したとして今年(2023年)6月、逮捕された中国人研究員は、研究所に20年近く勤務する一方、中国人民解放軍と関係があるとされる「国防7校」の一つ、北京理工大教授にも就いていたと指摘される。
経済安全保障に詳しい明星大の細川昌彦教授は「技術力の高い日本は、特に半導体や基幹部品といった先端技術が狙われやすい。大企業だけでなく中小企業も警戒すべきだ」と指摘。漏洩対策について、「(情報に)アクセスできる人を限定するほか、重要な技術の管理サーバを他の情報と別にするなど、経営者らはコストをかけてでも対策に取り組むべきだ」としている。
「アメリカの企業、Intelは大きな脅威ではない!!」と台湾の半導体メーカーTSMCの創設者が発言、最先端技術の2nmプロセスの開発が順調に進んでいることも明かす!!(アメリの持っている先端技術は、もう知っている)
2023年10月17日
台湾に本拠を置く世界最大級の半導体メーカー「TSMC」の創設者であるモリス・チャン氏が、TSMCを取り巻く地政学的な変化と半導体産業における競争の激化により、TSMCが困難に直面していることを明かしました。一方で同じく半導体を製造するIntelについて、「TSMCに対する主要な脅威とは見なしていません」と主張しています。 Morris Chang Asserts Intel Foundry Will Remain in TSMC's Shadow | Tom's Hardware
示警地緣政治趨勢影響 張忠謀:台積電面臨嚴峻挑戰 | 產業熱點 | 產業 | 經濟日報
TSMC: Importance of Open Innovation Platform Is Growing, Collaboration Needed for Next-Gen Chips
Chip Development Is Nearing Completion
TSMCの創設社であるチャン氏は2023年10月14日に行われたイベントで、会社の将来的な課題と戦略的位置付けに関する見解を示しました。チャン氏は、TSMCが運用効率の向上と研究開発に多額の資金を投入していることを明かし、競合他社であるIntelに対して「Intelはアメリカ政府から多額の支援を受けているにもかかわらず、技術的なリーダーシップや半導体製品の質、適切な価格設定などの面で遅れているため、これらの課題を解消しない限りTSMCに実質的な脅威をもたらすことはありません」「たとえIntelが課題を克服し、成功をおさめたとしても、TSMCがトップシェアであることには変わりありません」と述べました。 一方で、チャン氏は「台湾に拠点を置くTSMCにとって地政学的な緊張は避けられず、競争環境に悪影響を及ぼす可能性があります。一方で、他の競合他社は地政学的にTSMCよりも競争上の優位性があるため、TSMCの半導体事業は今後これまで以上に多くの課題に直面する可能性があります」と指摘しています。 それでもTSMCは、最先端技術である2nmロジック半導体を2025年後半から量産する予定で、その開発が順調に進んでいることを明かしています。2023年10月に行われた
の中で、TSMCの設計インフラストラクチャの管理責任者であるダン・コッチパチャリン氏はTSMCの2nmロジック半導体「N2」「N2P」および「N2X」について「2021年からさまざまなパートナー企業と連携して開発を行っています」と報告しています。
コッチパチャリン氏によると、2nmロジック半導体にはナノシート技術を使用して製造されたトランジスタが搭載される予定で、従来のトランジスタであるFinFETとは異なる動作を示すとのこと。そのため、TSMCとともに2nmロジック半導体の製造に携わるパートナー企業は、2nmロジック半導体製品をゼロから開発する必要がありました。そこでTSMCは、AlphawaveやCadence、Credo、eMemory、GUC、Synopsysと連携して2021年頃から製品の開発を行う環境作りを行ってきました。しかし、2nmロジック半導体の不揮発性メモリやインターフェイスIP、チップレットIPなどの分野は依然として製造段階に至っておらず、一部のチップ設計におけるボトルネックになっているとのこと。 コッチパチャリン氏はイベントの中で、2nmロジック半導体をはじめとする次世代半導体技術や、高度なパッケージング技術を開発するにあたって、さまざまな企業が協力関係を結ぶ「Open Innovation Platform(OIP)」
と呼ばれるプログラムが非常に重要になることを主張しました。OIPには、2023年時点でのべ117もの企業が参加しています。
コッチパチャリン氏によると、OIPに参加することで、TSMCが新たな半導体製造技術の開発を開始してから、わずか数カ月後には製品の開発に参加できるようになり、最終的に市場投入までの時間が約15カ月短縮可能とのこと。コッチパチャリン氏は「半導体製造技術の高度化に伴って、ノードやチップの開発期間が長くなりつつある現代では、TSMCやOIPに参加した企業間でグローバルなコラボレーションを行うことが重要になっています」と述べています。また、OIPの利点として、市場投入までの時間が短縮されることや品質が向上するだけでなく、プログラムに参加した企業にかかる「チップの開発や製造、テスト、パッケージング」などの負担が軽減されることが主張されています。 TSMCがリーダー的役割を担って行われる半導体製造技術の開発では、6つのアライアンスに分けられた後、その企業が得意とする作業がTSMCから割り当てられ、個別に開発作業を行うことが可能です。さらにTSMCは2022年から
「3DFabric Alliance」「3DFabric Alliance」と呼ばれる高度なアライアンスを組織しており、関連企業への開発環境の提供や設計プロセスの合理化に取り組んでいます。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
日中、日台、日韓の経済協力、技術の提携を進め「日本の”蔵売り”」はどこまで続くのか!?
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
中国の“戦狼外交”はどこへ!?記者が見た終始“日本への気味の悪い友好モード”の習氏外遊
TBS NEWS DIG - 2022年11月22日 11:02
新型コロナの感染拡大以降、2年あまり国外に出ることは無かった習近平国家主席だったが、10月に行われた中国共産党大会で3期目入りを果たし、権力基盤を固めて以降は外交活動を本格化。インドネシア・バリで開かれたG20=主要20か国・地域の首脳会議と、タイ・バンコクで開かれたAPEC=アジア太平洋経済協力会議の首脳会議では、6日間で20人以上と会談した。
微笑外交
今回、私は北京支局の記者として習氏の動きを追いかけてきたが、なかでも目立ったのが、習氏の「笑顔」だった。“友好モード”が全面に出た外遊の背景にはいったい何があったのだろうか。
■“最大の懸案”アメリカとの会談では手応え
今回、習氏にとって最大の懸案だったのは、間違いなくアメリカとの会談だったに違いない。2022年11月14日にバリに到着して真っ先に会談したのがバイデン米大統領だった。
同時通訳を入れての議論は3時間にも及んだ。台湾問題については「核心的利益だ」とした上で、「越えてはならない最重要のレッドラインだ」と強くけん制。一方、意思疎通を維持して高官協議を再開し、ブリンケン米国務長官が年明け、中国を訪問することでは合意した。台湾問題をめぐる溝は埋まらなかったが、対立のエスカレートには一定の歯止めがかかった形だ。
習氏がこの会談をどう評価したのかは、5日後のAPECの会場でハリス副大統領に語った言葉からうかがえる。
「とても戦略的かつ建設的で、これからの中米関係を導く重要な意義があった」
習氏はこう話した上で関係改善への意欲を改めて示した。
■“友好モード”の背景に…対米対策やEUとの関係悪化への危機感?
バイデン米大統領との会談後、習氏は韓国の大統領や関係が悪化していたオーストラリアの首相とも相次いで会談し、いずれの場でも関係改善への意欲を示した。また、日本とも経済分野などでハイレベルの対話再開で合意するなど協調姿勢を見せている。韓国、オーストラリア、日本…一連の会談には、アメリカの同盟国にくさびを打ち込みたい狙いが透けて見える。
また、フランスやイタリア、オランダとの会談では、「ヨーロッパと中国の間の対話と協力を積極的に推進する上で重要な役割を果たしてほしい」などと述べていて、人権問題などで関係が悪化するヨーロッパ諸国との関係改善を模索していることが伺える。
さらに、太平洋島しょ国であるパプアニューギニアやこの地域で影響力が大きいニュージーランドに対しては「中国の太平洋島しょ国に対する政策は平和を目的としたものだ」などの立場を示した。この地域では、中国が安全保障の分野にまで影響力を拡大させようとしていることに対して懸念が高まっていて、それを払しょくしたい狙いとみられる。
中国の外交といえば「戦狼外交」と呼ばれる対外強硬姿勢が有名だが、今回の外遊では「戦狼外交」は影をひそめ、対話や協力を全面に出す穏やかな外交姿勢が目立った。
ただ、全ての会談が友好的に行われたわけではなかった。
■公開されなかった会談…残る課題
「ニュースは適切ではない。誠意があればうまくやっていけると思うが、そうでなければ、良い結果にはならない」
これは2022年11月16日に習氏がカナダのトルドー首相に語った言葉だ。いつも国営メディアの計算されつくした映像しか公開されない習氏だが、今回は珍しく習氏の素の表情がツイッターで拡散され、話題を呼んだ。会話は、この前日に行われた3年ぶりとなる中国とカナダの首脳会談の内容が報道されていることに苦言を呈したものとみられる。
実は、中国国内ではカナダとの会談の事実は公表されていない。中国とカナダをめぐっては、2018年に中国の通信機器大手ファーウェイの副会長兼最高財務責任者の孟晩舟氏がカナダで拘束され、その対抗措置として中国でカナダ人2人が拘束されたことなどから関係が悪化。最近もカナダの公共放送CBCの記者が中国政府から記者ビザの発給を受けられず、北京支局が閉鎖を余儀なくされるなど、両国のぎくしゃくした関係は続いている。
さらに、弾道ミサイルを相次いで発射している北朝鮮情勢やロシアによるウクライナ侵攻の問題では、西側諸国とは一線を画したままで、溝も埋まっていない。
■中国は失われた2年間を取り戻す“再出発”のための外遊
2020年1月、中国の武漢で初めて新型コロナの感染拡大が確認されて以降、中国と西側諸国との関係は悪化するばかりだったと言える。その間に西側諸国の中国への視線は厳しさを増し、一方で中国側は中国に向けられる批判に対して、外務省の報道官が厳しい表情で強硬に反論する「戦狼外交」を展開し、中国国民の西側に対する感情も悪化した。
今回、習氏があえて笑顔で会談に臨んだのは、今の中国がおかれている現状への危機感なのか、それとも笑顔の裏には隠された狙いがあるのか…。3期目を迎えた習氏のもと一連の会談で合意された様々な対話や交渉の再開がどこまで実現するのか、中国の本気度が今後試されることになる。
JNN北京支局・松井智史
1. 習近平の戦狼外交の実態、具体的な事例での中国による日本進出の手法が詳細に記されている。
日本にはスパイ防止法がない為、見つかってもお咎めなし
ましてや中国本土にある工場など接収するなど簡単なこと
技術と工場、取られて「さようなら」
2. 実質小学校レベルの頭の独裁者で毛沢東のやり方しか知らない阿保に何故馬鹿な日本人経営者はナビかねばならないのか?
3. 米国が戦後日本を警戒するあまりに日本とともに成長しようとせず、人間として躾も社会性も成ってないチャイナにお金をジャブジャブ注ぎ込んで、軍備拡張領土拡大を助けてしまったブーメランは、やはり米国に見る目が無かったとしか言えず、後悔先に立たずそのものだ
4.兎に角多くの常識ある日本人(玉城や山口那津男、林芳正、岸田、野党などの反日売国人はどうでも良いから)に本書を熟読理解して日本人の生命、財産、言論の自由、国家国土、独立国としてのプライドを守る気概を持ち行動してほしい
中国が仕掛ける超限戦に備えよ
2022年10月2日
中国による台湾及び尖閣を含む沖縄への侵攻が現実味を帯びる。だから、「中国が仕掛ける超限戦に備えよ!日本は準備不足だ」と筆者は言いたいのだろう。
中国企業が海外から資金を集めるVIEスキームを、本書で初めて理解した。ケイマン諸島のSPCを介してドル資金を集める手法だが、投資家は中国内企業には口を出せず、単なる融資にしてしまう方法だ。こうしたスキームで中国は海外からの干渉をブロックしている。
一方、中国企業は合弁やM &Aで海外企業から軍事転用技術を獲得している。これを米国を筆頭とした西側諸国が規制し、中国が対抗する構図なのだと言う。にも関わらず、日本の現状は、新幹線技術流失をはじめ、楽天とテンセンの資本業務提携やソフトバンクからアリババへのVIEスキーム出資で甘々だとしている。確かに、スパイ防止法もない日本は草刈り場になってしまう。しかも、中国には、戦時に外国企業資産を接収できる法律もあるのだと言う。トヨタを筆頭に1万社もある日本企業は全滅だろう。
トランプ氏 大統領就任なら日鉄のUSスチール買収を「即座に阻止する」
2024年2/1(木)
日本製鉄によるアメリカ鉄鋼大手「USスチール」の買収計画を巡り、トランプ前大統領は大統領に返り咲けば阻止すると表明しました。
記者
「あなたが大統領なら日本製鉄によるUSスチールの買収を阻止しますか?」
アメリカ トランプ前大統領
「阻止するだろう。恐ろしいことだと思う。日本がUSスチールを買収するなら私は即座に阻止する。絶対にだ」
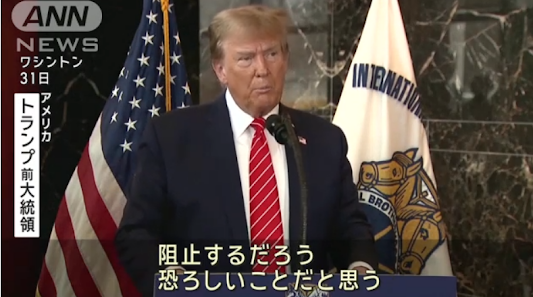
トランプ前大統領は1月31日、運輸業界の労働組合員との会談後にこう述べたうえで「我々は雇用をアメリカに戻したい」と強調しました。
この買収を巡っては、全米鉄鋼労働組合が反対を表明し、バイデン政権も安全保障などの観点から懸念を示しています。
大統領選挙が11月に迫るなか、共和党の候補者争いでトップを走るトランプ前大統領と2期目を狙うバイデン大統領がともに難色を示すのは労働者の票が激戦州での勝敗を左右するためです。

両者それぞれがアメリカ製造業の象徴ともいえる企業と国内の雇用を守る姿勢を打ち出すことで、労働組合や労働者の支持を取り付けようとする争奪戦に発展しています。

(C) CABLE NEWS NETWORK 2024
宮崎県知事選挙 各陣営の終盤戦の取り組みは 国内
宮崎県知事選挙、各陣営の終盤戦の取り組みを、取材にあたっている税田奈緒子記者に聞きます。
(聞き手:川野武文アナウンサー)
(川野AN)
選挙戦、終盤に入って、各陣営、熱が入っていますが、まず東国原氏の動きはどうでしょうか。
(税田記者)
東国原氏は政党や団体からの推薦をほとんど得ず、草の根の選挙戦を展開しています。
選挙戦の前半は、街頭演説などの冒頭で「1期で退任した理由」など過去の経緯を説明していましたが、選挙戦後半に入って自身の政策を訴えることを重視しています。
中でも、「宮崎のブランド力」「宮崎の存在感」を上げるというキーワードを多く使用していて、「県政の変革」を訴えています。
また、投票率の向上が当落のカギを握るとみていて、浮動票や若者の取り込みを図りたいとしています。
(川野AN)
続いて、河野氏の陣営は、いかがでしょうか。
(税田記者)
河野氏は、自民党、公明党、経済10団体や企業・団体などからおよそ400の推薦を取り付け、組織戦を展開しています。
河野氏は日本の長期政権である自民党とパイプ(ずぶずぶの関係、ポパイじゃない)を保っている!
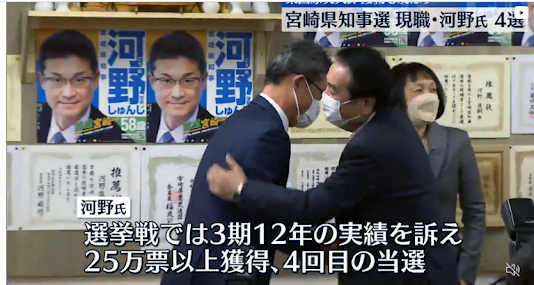 |
| 組織が、組織力が勝利した。その組織と河野氏が密接に抱き合う! |
選挙戦の前半は自身の3期12年の県政運営について「安定・堅実な県政」と表現し、「これは停滞ではなく、安定のもとでの成長をしてきた」と訴えています。
中盤に入り、陣営側は東国原氏の追い上げに危機感を感じていて、推薦を得た企業や団体の職員などに改めて支持をお願いしているということです。
また、県民の多くの支持を得たうえで当選したいとしていて、投票率50%を見据えたうえで高い得票率を目指したいとしています。
前回の知事選の投票率は「33.9%」と過去最低となりました。
これからの宮崎のかじ取り役を選ぶ大切な選挙です。
いま、候補者、SNSでも政策などを発信しています。それぞれの政策を確認して、投票に足を運んでほしいと思います。
選挙結果:
河野俊嗣氏「この瞬間は生涯忘れることがない、そういう思いがしています。政治家としての自信を強め、さらに力を発揮していきたい」
河野氏は旧自治省出身。2005年に総務部長として宮崎県に出向し、副知事を経て2010年に宮崎県知事に初当選しました。選挙戦で河野氏は、口蹄疫からの復興や、新型コロナウイルス対策など3期12年の実績を訴え、経済団体などの支援を受けて、25万票以上獲得し、4回目の当選となりました。4期16年の長期政権となった。宮崎県の景色が変わっていくでしょう。
一方、前の県知事の東国原氏は、草の根選挙で無党派層を取り込み、選挙戦の後半に猛烈な追い上げを見せましたが、わずかに及びませんでした。
東国原英夫氏「自分の資質・素養、そういったものが足りなかったということであります」
宮崎県知事選挙には、河野氏と東国原氏のほか、新人のスーパークレイジー君の計3人が立候補していました。新人のスーパークレイジー君も一万票近くを獲得したのは宮崎県民の凄い。
宮崎県選挙管理委員会によりますと、今回の宮崎県知事選の投票率は56.69%で、過去最低だった前回よりも22.79ポイント高くなりました。
陸の孤島と言われている宮崎県の地方選挙なのに、今回の宮崎県知事選が日本中で話題になっていることは、日本中の国民が宮崎から全国へ「何かの期待」をしているのか?若しくは「ひるおびの話題の一つ」に過ぎないのか?
悲報、新型コロナウイルスによる感染拡大が続く中、河野俊嗣宮崎県知事は「地産地消の旅」へ!
河野俊嗣宮崎県知事はコロナ対策にしても、宮崎県全体で重症病床17しかないし、病床数なんて鹿児島の半分以下、大分の6割程度で、専門家の意見を聞きながら対策したいといまだに言ってる。
【Vol. 9/ショートver】対話と協働を重視【河野しゅんじ(河野俊嗣)宮崎県知事】
【Vol. 6/ショートver】スポーツで地域活性化【河野しゅんじ(河野俊嗣)宮崎県知事】
宮崎県知事選挙の感想:
裏も表も隠さず正直者が馬鹿を見た?馬鹿者?⇔東国原力(メディアを知り尽くした力)が無くしたもの⇒宮崎の経済に不安⇒県民が安定を求める⇒大きい組織や企業に頼りたくなる⇒個人や店が衰退⇒犯罪が増えそうだ⇒警察力を高める⇒社会が安定する⇒このままが良いと考え始める⇔国債に頼った予算で国も県も「安定」したと考える⇒成長しない(経済のゼロ成長)ままか、マイナス(負)のサイクルになる⇒大きい組織や企業が内部に隠れて金(国民の税金)をため込む⇔真に国民が苦しむとき、遠い親戚(アメリカ、イギリス)より近くの友人を頼りたい(中国の資金力やロシアの資源力)⇒思想の無い人に悪漢は近寄り、何をするかは「歴史」が決めるでしょう。
宮崎県知事選で、現職の河野俊嗣氏(58)が4期目の当選確実を決めた後、前知事の東国原英夫氏(65)は宮崎市の事務所で、報道陣の取材に応じ、「
半数の人が『宮崎がこのままではいかん』と思った。一歩及ばなかったが、私はスポーツマンなので、これでノーサイド。みなさんは現職と力を合わせ(宮崎を)元気にするよう一丸となってください。私も微力ながらそんな活動を考えたい」と語った。2007年に初当選後、1期限りで退任したことへの批判については「完全に払拭(ふっしょく)はできなかったが、だいぶご理解が浸透したと思う」と語った。(大畠正吾)
「世の中を変えるの」は、若者か馬鹿者?のいずれか。(河野太郎)
 |
| 左が馬鹿者?(河野太郎)、右はロシアのロブロフ外相はただのゾンビ? |
河野太郎デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(デジタル改革、消費者及び食品安全)のインタビュー記事「デジタルから日本を変える」(聞き手・青山和弘)の一部を転載します(「文藝春秋」2023年1月号より)。
――まず旧統一教会問題への対応について伺います。河野太郎さんは消費者担当相として、岸田文雄政権が解散命令請求と被害者救済法案の策定に向かう流れを主導したと思います。そのカギとなったのが、河野太郎さんが消費者庁内に設置した「霊感商法等の悪質商法への対策検討会」です。検討会は8月12日の大臣就任後初の記者会見で立ち上げを宣言するという電光石火の対応でしたが、どういう考えだったのでしょうか。
河野太郎デジタル大臣 消費者担当相になるのは2015年以来2回目なので、やるべきことはある程度わかっていました。最初の時は、オーナー商法で問題になった「ジャパンライフ」の件で、消費者庁は明らかに後手に回った。もっと早く動いていれば被害は小さくて済んだのではという思いがあったので、旧統一教会への対応は「ちょっとのんびりしすぎている。すぐやるぞ」と言いました。直ちに第三者の検討会を作って「消費者庁としてちゃんと対応していたのかの検証と、これからどうすべきかの提案をしてください」と。また消費者庁は消費者安全法第三十九条で、他の役所にもモノを言えるわけですから、メンバーには「検討会は消費者庁に立ち上げるが、他の役所に不十分なところがあれば、それはそれで言ってください」と言いました。
――検討会のメンバーに長年教団と闘ってきた紀藤正樹弁護士と、元野党議員の菅野志桜里弁護士を入れました。この人選には、消費者庁内にも慎重意見があったそうですが、2人を選んだ理由は?
河野太郎デジタル大臣 菅野さんは、国会議員としての仕事ぶりを見て、能力のある方だと思っていました。紀藤さんはこの問題に一番詳しい方です。詳しい人が入って議論してもらわないと、意味がないと考えました。
――この人選ですと、旧統一教会に厳しい結論が出るのは想像がつきますね。当初から、解散命令請求の提言も視野に入っていたのですか?
河野太郎デジタル大臣 僕がああしろ、こうしろと言うつもりはありませんでしたし、実際に言いませんでした。専門家の皆さんに、「過去の消費者庁の対応がどうだったのかと、これからどうすればいいのかを言ってください」とだけお願いしました。
岸田総理「いいんじゃない」と
――検討会について、岸田総理に報告や相談はしたんですか?
河野太郎デジタル大臣 「こういうメンバーで行こうと思います」というところから、岸田総理とは話をしています。実は僕と岸田さんは1997年、2人で遺伝子組み換え食品の表示問題を担当した頃から、消費者問題に深く携わってきたんです。紀藤さんも岸田さんをよくご存じです。だから一応、「こういうメンツで行こうと思います」と報告して、「おお、いいんじゃない」という感じでした。
――10月に入ると検討会は、政府が解散命令請求を視野に宗教法人法に基づく質問権を行使するよう提言します。岸田総理はそれまで旧統一教会への解散命令請求には慎重な姿勢を見せていましたが、検討会の報告書が出た衆議院予算委員会の初日に、一転して質問権の行使を表明しました。岸田総理とはどんな話をしたのですか?
河野太郎デジタル大臣 (報告書が出る)前に検討会の議論の方向性を伝えました。「文化庁がこれまで、質問権を行使してこなかったのは甘いんじゃないかという意見が大半でした」と。たぶん、それから岸田さんが文化庁を呼んで話を聞いたりして、「じゃあ予算委員会で言うか」と決めたんだと思います。
――岸田総理は、河野さんに慎重な反応は見せなかったのですか?
河野太郎デジタル大臣 まったく。
――一方、専門家や政府与党の一部からは、「民法の不法行為」によって解散命令を出すのは、無理筋ではないかという意見も出ています。どう受け止めますか?
河野太郎デジタル大臣 最後は裁判所、司法の分野でお決めいただくことでしょう。政府としてはできることはやります。
――また報告書では被害者救済のための法整備も求めています。法案を巡って野党側からは、「マインドコントロール下の寄付の規制」や「寄付の上限設定」など、ハードルの高い内容が提案されていて、憲法で保障されている財産権の侵害や、寄付で成り立っている宗教界全体を揺るがすとの懸念も出ています。こうした状況をどう見ていますか?
河野太郎デジタル大臣 消費者庁は、検討会の報告書で「これはやろう」と言ったものを粛々とやります。そこから先は与野党協議で、必要なら議員立法などでやることになるでしょうから、そこでしっかり議論してもらえばいいと思います。
――自民党内には旧統一教会と関係の深い議員が多くいますし、一部の議員が選挙前に政策協定を結んでいた問題も浮上しています。今の党の対応を十分だと思いますか?
河野太郎デジタル大臣 党のことは党で考えてやっていることですので、あまり私がとやかく言う話ではないと思います。
一体化に2年の期限のワケ
――自分の職務以外の事は口を挟まないということですね。ではデジタル化の話に移りたいと思います。岸田総理は河野さんの突破力に期待して、デジタル相に任命したと伺っています。一方で、「担当を特化した大臣にした方がいい」という考えがあったと聞いています。河野さんはどのように受け止めていますか?
河野太郎デジタル大臣 「やれ」と言われたことをしっかりとやるのが仕事だと。
――そんな中で、マイナンバーカードと健康保険証との一体化について、2024年秋までにという期限を切りました。思い切った期限を設定したと思うのですが、どういう狙いなのですか?
河野太郎デジタル大臣 例えば僕はこの5年間で、閣僚としての担当省庁が変わるたびに保険証が切り替わりました。転職するのが当たり前の時代で、保険証の切り替えが頻繁になっています。だからマイナンバーカードとの一体化で、切り替えが一切要らなくなるのはメリットだと思います。また薬の情報を共有できるし、将来的には匿名化した情報をビッグデータで分析して、どういう医療が最適かという標準治療も変わっていくでしょう。データに基づいた医療が進むことで、医療の質は格段に上がります。そういう意味で、個人にも日本人全体にも大きなメリットがあると思います。
――メリットは分かるのですが、なぜ2年の期限を設けたのですか?
河野太郎デジタル大臣 ダラダラやるよりは、ピシッと目標を掲げてご説明したほうが、世の中が自分ごととして受け取ってくれると思います。要するに、「2年のうちに保険証をマイナンバーカードに切り替える」と言うと、「寝たきりの高齢者はどうしたらいいんだ?」とか、「赤ちゃんは2年で大きくなっちゃうのに、写真を撮らなきゃいけないの?」とか、いろんなことが気になってくる。今、そうした懸念を「どんどん寄せてください」と申し上げたら、もう5000件ぐらいご意見が来ています。すると行政側もやるべき課題がはっきりするので、非常に良いと思います。
◆
河野太郎デジタル大臣インタビュー「デジタルから日本を変える」全文は、月刊「文藝春秋」2023年1月号と、「 文藝春秋 電子版 」に掲載されている。
(河野 太郎/文藝春秋 2023年1月号)
潰す必要のない企業までハゲタカ外資に売り飛ばした…日本人を貧乏にした「小泉・竹中改革」の真実を語ろう
黒字企業が次々とワナにはめられ潰された
PRESIDENT Online
なぜ日本人はこんなにも貧しくなってしまったのか。経済アナリストの森永卓郎さんに『親子ゼニ問答』などの共著者でもある息子の森永康平さんが尋ねたところ、「小泉・竹中構造改革では『不良債権処理』という名目で、本来潰れる必要がない企業まで潰された。これが日本経済低迷の最大要因だ」という――。
※本稿は、YouTubeチャンネル『森永康平のビズアップチャンネル』の一部を再編集したものです。
タワマンとショッピングモールが日本人の暮らしを破壊した
【森永卓郎】グローバル資本主義は、金持ちをより豊かにしましたが、その一方、庶民の暮らしはどんどん悪くなっています。
その上、若者労働者は生産性向上の名のもとにつまらない仕事ばかり押し付けられる、ろくでもない世の中になってしまいました。
なぜそうなってしまったのか。わたしは規制緩和と構造改革が日本をボロボロにしたことこそ最大の理由だと思います。
タワマンがその一例です。
かつてタワマンは建築基準法で規制されていましたが、規制緩和でタワマンをどんどん建てた結果、人々の生活は良くなったでしょうか。
一部の富裕層が豊かな生活を享受する一方、タワマンによって電力消費量が増え、環境への負荷が大きくなっています。
タワマンは、人々をよりリスクの高い暮らしに追いやったと思います。
かつては日本中いたるところに商店街がありましたが、大店法の改正で郊外に大規模なショッピングモールが建設され、地元の商店街はことごとく叩きつぶされてしまいました。
商店街の店主は一国一城の主で、地域住民とのつながりを持っていました。
しかし、商店街が廃れ、店主さんたちは廃業して単なる労働者となり、地域社会が崩壊の危機に直面しています。
「生産性が上がった」と手放しで喜べるようなものではありません。
むしろ、人々の幸福が奪われてしまったのです。
こういう間違った政策をグローバル資本主義者たちが進めてきた結果、日本人の暮らしはちっとも良くなっていないのです。
「年収300万円時代」を作った構造改革
【森永康平】2003年に『年収300万円時代を生き抜く経済学』(光文社)という本を書かれていますが、その後日本経済は、非正規雇用が約4割、その賃金は約170万円という状況になりました。本の予想がある意味では的中したわけですが、2003年の時点でなぜ予見できたのでしょうか。
【森永卓郎】当時、小泉純一郎氏と竹中平蔵氏、木村剛氏が手を組み、構造改革を始めていたからです。いずれ日本をぶっ壊すのが目に見えていました。
彼らの手で、不良債権処理が進められていました。これがあたかも正しい政策であるかのようにメディアを通じて宣伝され、国民もこの政策を支持しました。
当時、わたしはニュースステーションという番組に出演していて、この不良債権処理プランがいかに危険かを、繰り返し説明していました。
しかし、メディアの人間は金融のことをまったく知らないので、なかなか理解してもらえませんでした。
その上、彼らはとんでもないルールを持ち込んで一気に不良債権処理を進めたので、国民からは一体何が行われているのかさっぱりわからなかったと思います。
「マグロの解体ショー」のように売り飛ばされた
【森永卓郎】彼らは不良債権処理の名目で、本来潰れる必要がない企業の資金を断ち切り、その資産を二束三文で売り飛ばしていったのです。
ほとんど、タダでくれてやったようなものでした。
100億円近くかけて開発したゴルフ場が、アメリカ系の投資銀行にわずか数千万円で売却される、といったケースが当たり前のように起きていました。
裏では以前から綿密なプランが練られていて、外資と、小泉構造改革(小泉純一郎&竹中平蔵&木村剛)に協力する企業だけが、日本の大切な資産を二束三文で買いあさったのです。
まるでマグロの解体ショーを見ているようでした。
半沢直樹も真っ青の逆粉飾決算が行われた
【森永卓郎】不動産は米国系の外資がほとんど持っていきましたし、当時世界最強の競争力を誇っていた日本の電機産業は中国や台湾に買われてしまいました。
日本経済を支えてきた大黒柱の産業を売り払ったのだから、日本経済が低迷するのは当たり前です。
そんなプランを、小泉・竹中・木村氏らが、あたかも正義の味方のような顔をして遂行していたのです。これが日本経済低迷の最大の原因だと思います。
【森永康平】私が少年時代を過ごした実家は所沢にありますけど、小さい頃地元のダイエーに行くと、ダイエーホークスの歌が流れていました。そのダイエーはその後破綻してしまいました。ダイエーの経営はすぐ潰れるような状態ではなかったのに、結局破綻処理されてしまったという記憶があります。
【森永卓郎】ダイエーは黒字だったんですよ。わずかな赤字を出した年もありましたが、潰す必要はありませんでした。
不良債権処理のターゲットとして狙われたから、破綻処理されたのです。
当時、不良債権処理を進めると、日本経済は回復すると言われていました。不良債権を持つ企業が銀行からの融資を塩漬けにしているので、そうした企業を破綻処理して資金を開放すれば、お金が中小企業に回り、一気に経済が良くなる、というわけです。
特に、流通・建設・不動産業界が不良債権処理のターゲットとなりました。こうした企業が駅前の一等地にいい不動産をたくさん持っていたからです。
彼らを追い詰め、不動産を二束三文で買うことができれば、買った企業は大儲けできます。
そんな中でも、UFJ銀行(当時)はダイエーを支援していました。しかし今度はUFJ銀行と東京三菱銀行との合併がしかけられました。
これは罠にはめられたようなものでした。半沢直樹も真っ青の世界です。
合併後の決算を見ると、不良債権の組み戻し益が1兆円近くも出ていました。
つまり、「不良債権」とされていたものの価値を再計算すると、もっと価値が高かったということです。
竹中・木村氏は、本来なら「正常な債権」とされるべきものを、片っ端から不良債権に計上していたということです。
いわば「逆粉飾決算」です。
安倍元首相は財務省との戦いに破れた
【森永康平】日本経済がダメになった原因は財務省にある、という意見も多いですが、むしろ構造改革のほうを主な原因に挙げられるんですね。
【森永卓郎】構造改革と緊縮財政の両方が日本をダメにしたと思います。
経済アナリストの森永卓郎氏(写真=YouTubeチャンネル『森永康平のビズアップチャンネル』より)
安倍政権の時、2013年度は少しだけ財政出動しましたが、その時は景気が良くなりました。
その後、財務省に説得されたのかは分かりませんが、安倍さんは消費税を2回も上げるという大失敗をしてしまった。あれがなければ日本はもっと良くなっていたと思います。
【森永康平】かつては構造改革の影響が大きく、2010年くらいから緊縮財政の影響が大きくなっているというお話でしたが、積極財政派はむしろ1997年くらいから緊縮財政による悪影響が始まっているという意見が多いと思います。
【森永卓郎】安倍さんは自民党の政治家のなかで唯一といっていいくらい、財務省と戦った政治家なんですよ。アベノミクスの3本の矢は、金融緩和、財政出動、成長戦略です。金融緩和の次には財政出動をしようとしていたんです。
財務省という組織は、増税はどんどんしたほうがいい、歳出はいくらでもカットするべきという、非常に強い教義を持っています。
その組織との戦いに、安倍さんは破れたのだと思います。
2023年は世界恐慌の可能性
【森永康平】安倍さんはあのような形で亡くなってしまいました(銃撃事件)。一方、アベノミクスを支えてきた日銀の黒田総裁は来年2023年春に退任します。来年4月以降は悲惨な状況になりそうな予感がします。
経済アナリストの森永康平氏
【森永卓郎】来年2023年は世界恐慌の可能性がきわめて高いと思います。
わたしは、マーガレット・サッチャー以来続いているグローバル資本主義が、ついに崩壊の時を迎えている、という現状認識を持っています。
「グローバル資本主義の罪」は大きくわけて3つあると思います。
1つ目の罪は地球環境をぶっ壊したこと。アメリカでハリケーンの被害が拡大したり、ヨーロッパも干ばつに苦しんだり、日本でも洪水被害が相次ぐなど、世界中ありとあらゆる場所で、地球環境を破壊した影響があらわれている。
資本主義の発展と温室効果ガスの排出はきれいにリンクしています。
ある経済学者によると、富裕層が排出する温室効果ガスの量は、庶民の1万倍にも上るそうです。
こうしたことを今すぐ止めないと地球が危ない、と考える人が増えたことが、グローバル資本主義が崩壊する要因となっていると思います。
グローバル資本主義は10年以内に崩壊する
【森永卓郎】2つ目の罪は、とてつもない格差を生み出したことです。
今、地球上に住んでいる人は約76億人と言われています。これを所得の順に並べて下から半分の約38億人が持つ金融資産は約153兆円。これは、上位26人が持つ金融資産の額と同じです。
この上位26人は額に汗して働いてはいません。金が金を生むしくみを利用し、巨万の富を得ているのです。その一方で、地球上では貧困が拡大しています。こういう状況はもはや限界に達していると思います。
3つ目は最大の罪だと思いますが、グローバル資本主義が仕事の楽しさを奪ったことです。
OECD諸国の中で、日本の生産性がぶっちぎりで最下位ということで、みんな生産性を上げようとしています。
ただ、生産性を上げ、所得を上げた結果、誰もが面白くない仕事を強いられるのです。
私がアナリストとして経済をずっと見てきた経験から確信しているのですが、生産性と仕事の楽しさは逆相関の関係にあります。
つまり、生産性を高めれば高めるほど、仕事はつまらなくなっていくのです。
こうしたグローバル資本主義の弊害がどんどん大きくなり、これを止めようという動きが加速している。日本人は大人しいので、あまりデモやストライキをしませんが、世界ではグローバル資本主義に反旗を翻す若者たちが増えています。
私はグローバル資本主義が10年以内に崩壊する可能性はきわめて高いと思います。
森永卓郎、森永康平『親子ゼニ問答』(角川新書)
働いても働いても貧乏から抜け出せない…経済大国ニッポンが「一億総貧国」に転落した根本原因
日本をダメにした「未熟な資本主義」という大問題
PRESIDENT Online
宮本 弘曉
なぜ日本の経済はよくならないのか。東京都立大学経済経営学部の宮本弘曉教授は「25年間も賃金は上がらず、日本人は貧困化している。その原因は『未熟な資本主義』にある」という。宮本さんの著書『51のデータが明かす日本経済の構造』(PHP新書)からお届けする――。
賃金は25年前のまま…日本の「一人負け」が続く根本原因
世界でインフレが高進するなか、国内の賃金が上がらなくては、日本は貧困化してしまいます。
日本の賃金はこの25年間ほとんど上がっていません。一方、他の先進国では賃金は大きく上昇しているので、日本だけが一人負けしている状況です。
賃上げは経営判断であり、その基本は労働生産性と経済の見通しです。日本で賃金が上がらない大きな理由は、労働生産性が低迷し、経済の見通しが明るくないからです。
つまり、賃金を上げるためには、労働生産性を高め、将来の展望を良くしなくてはいけません。これは、端的に言うと、経済を成長させるということにほかなりません。
賃金が過去25年間にわたり停滞しているというのは、日本経済が凋落していることの象徴です。日本経済を取り巻く環境が大きく変化するなか、日本は自己改革を行ってきませんでした。デジタル化や人への投資を怠り、企業経営者は安全運転経営に終始し、イノベーターではなくなりました。
その結果、生産性は低迷し、日本経済は30年にわたり停滞しています。
停滞を招いた未熟な資本主義
こうした閉塞へいそく状況を打破するために、労働市場の流動化を進め、経済の新陳代謝を高めることが重要です。日本の労働市場では特殊な雇用慣行によりマーケットメカニズムがうまく機能していません。これはなにも、労働市場に限った話ではありません。日本では資本主義が徹底されておらず、競争メカニズムがしっかりと働いていません。
競争不足の原因は、政府の政策にもあります。地域金融や中小企業政策など、旧来の日本の政策には、経済の新陳代謝を遅らせ、競争力にマイナスに働いたものが認められます。また、近年の大規模な金融緩和や大型の財政支援は、企業の生産性が十分でなくても、操業を続けられる状況を作り出してきました。
今、真に求められていることは、日本経済の衰退を止め、再び、発展軌道に乗せることです。競争的な市場環境で、企業が付加価値を増加させることが、生産性向上と経済成長につながります。本稿では、未来のために何をすべきかについて考えていくことにしましょう。
経済を復活させる2つの方法がある
経済全体の生産性を上げるには、2つのチャネルがあります。ひとつは各企業の生産性を上げることです。もうひとつは市場の競争メカニズムによるものです。市場で高生産性の企業が拡大し、低生産性の企業が縮小することで経済全体の生産性が向上します。
まずは、各企業で生産性を高めるために何ができるのかを考えていきましょう。
労働生産性は付加価値を労働投入量で割ったものなので、生産性を高めるには、付加価値を増やすか、労働投入量を節約するか、あるいはその両方を達成するかしかありません。
企業による資本や人への投資の停滞が、低生産性につながっています。生産性を高めるには、デジタル化を進めると同時に人的資本を高める必要があります。デジタル化を進める際には、単にパソコンなどのハードウェア、経理関係などのソフトウェアを導入するだけでなく、その利便性を活用するために組織の改善も必要となります。
ここで重要なのが、経営者の能力です。経営のあり方は経済状況や市場の力学に左右されることもあり、経営者の質を測ることは決して容易ではありません。しかしながら、最近の研究では、企業経営者の能力が生産性の違いをもたらすことが指摘されています。具体的には、経営者の能力が向上すると、生産性も高まるというものです。
悲観的な経営者はいらない
日本経済が長期にわたり停滞し、人口減少により国内市場が縮小するなかで、多くの企業経営者が今後の市場環境に対して悲観的な見通しを持っています。しかし、厳しい言い方になりますが、本来、経営者に求められているのはこうした消極的な経営姿勢ではありません。経営者には、いかなる環境でも勝ち抜く判断が求められます。
しかしながら、日本の経営者は海外の経営者と比べて、自社の将来展望について自信がない傾向にあります。この理由としては、日本の経営者には経営戦略に長けた人よりも、社内競争に勝ち残った人、ボイスが大きい人、営業や技術に長けていても経営が得意ではない人が少なくないことがあげられます。
図表1に示されているように、日本の経営者の97%は内部昇格によるもので、他企業で経営者としての経験を持たない人の割合も82%となっています。
諸外国に比べると、生え抜きの経営者の割合が高く、また、他企業での経験がない経営者の割合も著しく高くなっています。さらに、海外では経営者の多くがグローバルな経験を持っているのに対して、日本ではドメスティックな経営者が多いという調査結果もあります。
この国では「真面目に努力する人」ほど損をする…日本の「天才」が次々と海外へ流出してしまう根本原因
努力する人を引きずり下ろすニッポン
PRESIDENT Online
藤巻 健史
なぜ日本の経済はよくならないのか。モルガン銀行(現・JPモルガン・チェース銀行)元日本代表の藤巻健史さんは「日本は、結果の平等を重視する社会主義国家だ。稼いでも高い税金が取られるため真面目に働く人ほど損をする。これでは経済がよくなるはずがない」という――。
※本稿は、藤巻健史『超インフレ時代の「お金の守り方」』(PHPビジネス新書)の一部を再編集したものです。
資本主義のアメリカ、社会主義の日本
なぜ、かつては二大経済大国と称された日米に、これほどまでの差がついてしまったのでしょうか。
その理由を端的に示せば、「資本主義国家のアメリカに対して、日本が社会主義国家だから」ということになるでしょう。
社会主義国家が資本主義国家に敗北したのは、20世紀の歴史が示す厳然たる事実です。ソ連が崩壊し、中国は建前はともかく、とっくの昔に資本主義国家になっています。
しかし、日本はいまだに社会主義国家であり続けている。だから敗北するのは当然だということです。
もちろん、日本は建前としては資本主義国家です。とはいえ、その現実は社会主義国家以上に社会主義です。
「日本は社会主義国家」――これは、モルガン銀行時代に海外から日本に転勤でやってきた部下が帰国する際、口をそろえて指摘することでした。日本は大きな政府で、政府による規制が強く、「結果の平等」を重視する。それはまさに社会主義そのものではないか、と。
日本では稼げば稼ぐほど高額な税金を取られます。一方、低所得者への生活保護は充実している。つまり、頑張って稼いだ人がなかなかお金持ちになれない一方、頑張らなくてもある程度の生活はできてしまう、ということです。これはまさに「結果の平等」です。
もちろん、様々な理由で働きたくても働けない人も多く、そういった人たちの生活は保護されなくてはなりません。しかし、働いても働かなくてもそれほど生活に大きな差が出ない、ということになると、誰が真剣に働こうとするでしょうか。これはまさに、社会主義国家が踏んできた轍に他なりません。
アメリカには世界から「天才」たちが集まるワケ
私はモルガン銀行時代、ベルリンの壁崩壊直後の東ベルリンに入り、社会主義とはどういったものかを体験したことがあります。
ベルリンの壁崩壊直後の東ベルリンに入り、客のほとんどいないがらがらのレストランで、客より威張りくさったウエイトレスがやる気のなさそうに働いている。しかも、前菜、主食、デザートの3品コースが出てくるまで、なんと4時間もかかったのです。
でも、それは当然のことです。いくら愛想を良くしても料理を早く出しても、もらう給料は同じなのですから。
アメリカにももちろん累進課税はありますが、日本よりも高所得者の税率は低く抑えられています。相続税もないに等しい。だからこそ一獲千金を目指して世界中から人が集まり、必死に働くのです。そして、それが経済の活力を生んでいるのです。
2022年10月2日の日本経済新聞によると、資産10億ドル(約1400億円)以上の富豪(ビリオネア)が一番多いのはアメリカで719人、2位が中国で440人、3位がインドで161人でした。それに対して日本は27人で、台湾の45人、韓国の28人を下回るのだそうです。格差などないはずの共産主義国家である中国が世界第2位というのもおかしな話ですが、それより圧倒的に富豪が少ないのが日本なのです。
しかも、他国は相続税廃止・軽減の方向に進んでいるのに対し、日本はむしろ重税化の方向に向かっています。優秀な人材ほど、ますます日本を去っていくことでしょう。
トップ5%が仕組みを作り、残り95%を動かす
日本のリーダーあるいは資産家と呼ばれる人と話していると、相続税をどう節税しようかという話ばかりしていて愕然とします。貴重な時間やエネルギーをそんなことに費やしてしまうから、この国は発展しないのです。
それに対してアメリカでは、優秀な人は莫大ばくだいな資産を手にすることができます。だからこそ、世界中から天才たちが集まる。
GAFAM(ガーファ)をはじめとしたアメリカの優良企業のトップ層には天才の移民が数多くいます。グーグルCEOのサンダー・ピチャイ、マイクロソフトCEOのサティア・ナデラはインド出身、テスラのイーロン・マスクは南アフリカ出身の移民です。
そうした天才たちが成功すれば儲かり、税金もそこそこで済むアメリカに集まり、切磋琢磨せっさたくますることでさらに業績を上げていく。極論すれば、アメリカという国はそうしたトップ5%が動かしている国なのです。
そして、彼らが作ったシステムで残り95%の人が働くことで、社会が回っていくのです。
「残り95%のアメリカ人」よりも日本人は優秀だが…
その95%のアメリカ人と比べれば、ほとんどの日本人のほうが圧倒的に優れています。そのこともまた、今回アメリカに行って痛切に感じたことです。
私が借りたレンタカー店の受付の女性は、ジュースを飲みポテトチップスを食べながらダラダラと書類を作っていました。スーパーマーケットの有人レジはやたらと遅い。飛行機の荷物係は楽しそうにおしゃべりしながら客の荷物を乱暴に投げ付ける。ホテルのバイキングは10時までだというのに、9時45分の時点でもう何もなくなり、さっさと片付けを始めてしまう。
こんなこともありました。私が借りていたアパートを返却する際、金曜日の午前10時にチェックに来るというので待っていたのに、いつまでたっても現れない。午後3時すぎに電話を入れたのですが、オフィスの営業時間が終わっているらしく、つながらない。土日は当然休み。仕方なく月曜日に改めて電話したところ、「ごめんごめん。今日行くから」と、ほとんど悪びれずに言われたのです。
ある時はレンタカーを返却しようと店舗に行ったところ、返却予定どおりの時間だったにもかかわらず、店舗がすでに閉まっていました。
だからIT化が進み、国全体が豊かになった
仕方なく隣にあったホテルで聞いてみたところ、よくあることらしく、「そこにボックスがあるからカギを入れておいてくれ」とのこと。だったら借りる際に教えておいてくれよという話です。当然のことながら、返却時の車体チェックも何もなし。本当に大丈夫なのかと思ってしまいました。
どれも日本ではあり得ない話です。
だからこそ、ITが発達するのでしょう。レジを打つ人が遅いから、自動レジを導入する。注文をしょっちゅう間違えるから、タッチパネルやスマホでの注文システムが発達する。
もっとも、マクドナルドでは自動化されたシステムがあっても、3回に1回は注文したものと違うものを渡されるのはご愛敬。商品を入れる店員が注文をちゃんと読まないのです。いくらシステムが優れていても、限界はあるのです。
ともあれ、優秀な5%が、大したことのない95%をうまく動かすためのシステムを作ることで、社会も経済も回っていく。だからこそ国全体が豊かになり、95%の人たちもその恩恵を受けることができる。
それがアメリカという国であり、経済成長の原動力でもあるのです。
日本を脱出する一流が止まらない
そしてこの上位5%の人たちはもともと優秀なだけでなく、めちゃくちゃ働きます。だから、さらに稼ぐようになり、格差もどんどん広がっていくのです。
スポーツの世界を見ればそれがわかると思います。野球のメジャーリーグの一流選手がもらう金額は、日本のトッププレイヤーの10倍以上。だからこそ世界中から優秀な選手が集まり、日本からも大谷翔平やダルビッシュ有、菊池雄星などの超一流選手がみな、アメリカに行ってしまうのです。
日本の野球はレベルが高いなどと言われますが、年棒では世界の二流リーグと言わざるを得ません。ただし、その中ではみな平等。大谷、ダルビッシュ、菊池など超スーパースターで高給取りが抜けていくのですから、みな平等になるわけです。ある意味、今の日本社会を象徴しているのかもしれません。
確かにアメリカでも格差の拡大は問題視されています。しかし、金持ちが超金持ちになったから格差が広がったのです。日本では金持ちが超金持ちになどなっていないのです。日本の格差は金持ちがより金持ちになったから格差が開いたのではなく、中間層が没落していったから格差が拡大したのです。
アメリカの格差拡大の理由とはまったく違うというのは、格差を研究している研究者のほぼ一致した結論です。
努力をした人を「引き上げる米国」と「引きずり下ろす日本」
また、アメリカは国として優秀な人材を集めようとしています。移民に対する厳しい姿勢で知られたトランプ政権下でも、コロナでビザ発行を中止した時でも、研究者などの優秀な人材にだけはビザが発行されていました。
一方、日本でも移民政策が議論されていますが、その論点はあくまでも「労働力不足の解消」です。もちろん人手不足のアメリカにもそういう側面はあるにはありますが、より重要なのは高い報酬に惹かれて世界各国から集まってくる優秀な人材のほうです。
そもそも日本ではいくら仕事の環境を整えたところで、成功しても大して豊かになれないのだったら誰も来ないでしょう。アメリカに行けば環境も整っている上に、大金持ちになれるのですから。
いわば、アメリカは「努力をした人を引き上げる国」「天才を引き上げる国」。一方の日本は「努力をした人を引きずり下ろす国」「天才を引きずり下ろす国」。その差は極めて大きいと言わざるを得ません。
日本は「共同貧困」に向かっている
そもそも、日本にはアメリカのような真の富裕層などはほとんど存在しません。さらに、中間層すらいなくなりつつあります。そんな状況下で格差を是正しようとすると、どうなるか。国全体が平等に貧乏になっていくのです。
日本では経済の活性化を唱える政治家よりも、国民の格差是正を訴えるリーダーばかりが支持を集める傾向があります。それは国全体で貧しくなることだ、という一面があることも、理解していてほしいと思います。
中国の習近平国家主席は「共同富裕」というスローガンを打ち出していますが、日本の場合は「共同貧困」へ向かっていると思わざるを得ません。
イギリス経済を復活させた「鉄の女」マーガレット・サッチャー元首相は、「人のポケットに勝手に手を突っ込むな」という名言を残していますが、まさに、そのとおりなのです。政治家が税金を集めて、自分の票を集めるためにバラマキを行うことに対する警告です。
昨今、資本主義の終わりということが盛んに言われていますが、こと日本に関して言えば、「資本主義が終わろうとしている」のではなく、「資本主義でなかったから終わろうとしている」のです。
江戸時代の日本人は決して幸福ではなかった…明治維新を批判する人が誤解している「江戸時代の10大問題」
江戸時代では女性差別と部落差別が強化され、引っ越しや旅行は原則禁止
PRESIDENT Online
八幡 和郎
江戸時代の日本はどんな社会だったのか。評論家の八幡和郎さんは「安定した良い時代だったと評価する風潮があるが、実際は北朝鮮のような人権無視の社会だった。女性差別や部落差別、階級差別が深刻化したのも江戸時代だ」という――。
江戸時代と北朝鮮はとても似ている
2023年NHK大河ドラマは、松本潤主演の「どうする家康」だ。家康を描くのは「徳川家康」(1983年、滝田栄主演)、「葵 徳川三代」(2000年、津川雅彦主演)に次いで三度目である。
家康は「狸親父」として嫌われていたが、戦後になると辛抱強く困難を克服して出世していく姿がサラリーマンの共感を呼ぶようになった。また、江戸時代が再評価されて「江戸に学べ」という人が多くなると、家康が理想の経営者だという人も増えた。
環境重視・平和国家・地方分権だと賞賛されるのだが、江戸時代の人ははたして本当に幸福で、明治維新や文明開化のために日本は悪くなったのだろうか。
明治国家による近代化は、世界史上でもまれに見る偉業だと世界から評価されてきた。ところが、江戸時代を礼賛する人は明治以前の封建時代を褒めて学べというのである。この腑に落ちない賛辞は、「北朝鮮は地上の楽園」というのに似ている。
江戸時代と北朝鮮の現在はとても似ている。世襲権力による支配、鎖国体制、モノの不足がゆえのリサイクル、密告による体制維持などが同じだ。江戸や平壌の市民を優遇して、人々の不満が体制を脅かすのを避ける仕組みもそっくりだ。
確かに戦争のない、安定した時代だったが…
もちろん、いつの時代にも、貧しくとも安定し変化のない時代を懐かしむ人はいる。戦前の朝鮮半島での日本統治を批判して、「苦しかったけれどもそれなりに生活していた朝鮮の農民は、昔に比べてずっと不安定な生活に落としいれられた」という陳腐な前近代礼賛論を著名な左翼知識人が主張するのにはあきれたが、この人は北朝鮮擁護の急先鋒でもあった。
北朝鮮も悪く言われすぎかもしれない。体制は安定し、治安が悪いわけでもない。教育も普及しているし、韓国と違って海外に派兵したこともない。しかし、江戸時代も北朝鮮も、自由はなく身分は固定し、世界文明の進歩とともに歩まず、その成果を国民が受けられないでいる。
戦国時代が、貧農出身の豊臣秀吉が天下を取れるような自由な社会であり、宣教師たちが驚くほど女性が輝いていた時代だったのに(拙著『令和太閤記 寧々の戦国日記』ワニブックス)、江戸時代には李氏朝鮮から導入した朱子学を公式の学問とした結果、封建主義が徹底されたのである。
深刻化した女性差別と部落差別
江戸時代のどこが問題だったのか10点にまとめてみよう(拙著『日本人のための日中韓興亡史』さくら舎)。
①女性差別と部落差別は江戸幕府が深刻にした
戦国時代の日本女性は自由で男女差別も少ないと宣教師たちは報告しているが、江戸時代には隔離され表舞台での活躍もなくなった。穢れなどを理由とした身分差別はそれまでもあったが、厳格で服装まで区別するような極端な部落差別は江戸幕府がつくりだした。
②引っ越しや旅行は原則禁止され交通インフラは300年進歩せず
町人の旅行は比較的自由だったが、農民は引っ越しも旅行も原則禁止の藩が多く、交通インフラや通信も劣悪で、馬や馬車は使えず、関所も復活し、移動時間を短縮する方法もなかった。大型船建造が禁止されたので、岸から離れて航行できず瀬戸内海などを除いて客船もなかった。
「識字率が高かった」を信じてはいけない
③教育レベルは低かったし、識字率が高いのも嘘
科挙があった中国や朝鮮と違い武士は学問を軽視し、藩校が普及したのも幕末に近い時代になってから。しかも、漢学だけで九九も教えなかったので実務には役立たなかった。庶民が学べる中等学校(高校)もなかった。ヨーロッパの大学の学生が市民中心だったのとも大違いだ。
*ヨーロッパでは、学問や大学教育は市民層中心のもので、王侯貴族は軍人としての教育などを好んだ。イギリスのチャールズ国王は初の大卒の国王。ダイアナ妃のスイスの寄宿学校から保母さんというのこそ、伝統的な貴族のお嬢様の経歴といえる。
識字率が高いというのは、中国や朝鮮では数千字の漢字、日本では仮名だけができるかで計算した結果で比較しても意味がない。
④鎖国のために科学技術もほとんど進歩しなかった
日本人の海外渡航は全面的に禁止で、西洋のことを書いた漢籍の輸入も禁止されたので、科学技術はもちろん、それ以上に国際法や経済の知識も2世紀以上遅れることになった。
⑤鎖国のおかげで独立が保てたというのは嘘
スペイン・ポルトガルは各地に軍事拠点を確保したが、面での植民地支配は、国家未成立の地域や金属の武器がなかった中南米に限定しており、もともと日本に危険はなかった。むしろ、鎖国の結果、火縄銃の時代の軍事力のまま黒船来航を迎えたので、危うく植民地化されそうになった。
⑥武士道は明治時代になって生まれたもの
武士は戦国時代の先祖の遺族年金というべき禄を食んでいるだけに近く、軍人・官僚としての実務能力も使命感もなかった。武士道は明治になって西洋の騎士道に似たものがあったとして創造したもので、江戸時代の武士の実態とはかけ離れている。
米のモノカルチャーで飢饉が頻発
⑦士農工商より上級武士の権力独占が問題
適材適所でなく世襲が原則で、上級武士(馬に乗れて殿様に会える)とそれ以外が峻別されていた。福沢諭吉も中津藩で下級武士や庶民から上士に昇進したのは、300年で数例しかなかったとしている。
⑧北朝鮮なみに禿げ山だらけで環境先進国は嘘
ものを大事にしてリサイクルが発達したのは事実だが、物資不足の結果に過ぎず、いまの北朝鮮と同じだ。薪や炭を燃料にしたのでほとんどの山が禿げ山に近く、洪水が多かった。
⑨餓死者が続出し東日本では人口も停滞
鎖国のためトウモロコシ、芋類など新大陸原産の新しい作物導入が低調だったのと、米に偏った税制で極端な米のモノカルチャーになった。食料の流通も諸侯に任せたので、飢饉ききんが頻発し人口が停滞した。江戸時代中期と同時代の清国で、康熙帝こうきていなど賢帝が善政を敷き、経済も人口も伸びたのと対照的だった。
⑩裁判や警察など司法の前近代性と切り捨て御免
司法制度が恣意しい的だった。火あぶり、磔、牛裂き、釜煎り、獄門、石子責めなどサドマゾ刑罰に拷問もやり放題。切腹はお家断絶回避を餌に無実を主張させない制度として使われた。切り捨て御免も伝説ではなくまれでもなかった。
明治批判の裏返しとしての無理な江戸賛美
それでは、なぜ誤った江戸時代賛美論がはやるのだろうか。まず挙げられるのは、関ヶ原以前からの日本人の美点なのに、江戸時代に始まった長所と誤解しがちな点だ。民度の高さは『魏志倭人伝』も指摘しているし、仮名をほとんどの人が使うとザビエルの報告にもある。
江戸時代の日本として19世紀前半(天保期から幕末)の状況を持ち出す一方、18世紀以前(フランス革命や産業革命以前)の欧米と比べる不思議な比較が多い。
明治体制を誹謗ひぼうし、成果を矮小化する目的で江戸時代を褒める傾向もある。戦後史観では明治賛美は御法度らしいから、成果を矮小化するため江戸時代に日本はすでにかなり近代化されていたと強弁しがちだ。
家康が再征をちらつかせて派遣させた、一種の朝貢使節である朝鮮通信使を、対等の関係の象徴と歪曲して持ち上げる一方、むしろ、近代国際法に基づく対等の外交を提案しながら大院君に拒否された明治政府の対応を高圧的だと批判したがる。
保守と左翼がいずれもユートピアと褒める不思議
維新後に発展した日本文化を江戸時代からあったと誤解しているケースも多い。先ほども説明したように、武士道は新渡戸稲造が欧米人受けするように創ったものだし、陽明学も江戸時代に萌芽はあるが明治以降に流行したものだ。
江戸時代の民家は貧弱で、城下町の立派な町並みは明治後期から昭和初期にかけてのものだが、「小江戸」とかいって江戸時代のものと錯覚されている。時代劇は江戸の町ばかりだが、江戸は現在の平壌ピョンヤンと同じように別世界で、移動の自由がないなかで江戸の武士も町民も特権階級だったのに地方の惨めさが描かれない。
孔子が周王朝の初期を自分の理想を語るために理想郷としたのと同じで、理想社会を過去に求めることはよくあるが、日本では極端に顕著だ。保守は封建時代を美化し、左翼は貧しくとも安定を求むので、結果として江戸時代への賛美に収束するのだ。
極端な修正主義史観は国益を侵害する
この風潮は、日本だけで通用する世界史への特異な理解にもつながる。フランス革命が民主主義へ世界を導いた転換点であるのは世界の常識で、200周年となる1989年には、パリで「アルシュ・サミット」が開催され、世界の首脳が人類史における意義を再確認した。
パリのシャンゼリゼ通りで毎年行われている革命記念日(7月14日)のパレードには、あのトランプ大統領も主賓で招かれ、日本からは中曽根康弘首相が希望して出席して、歴史的偉業をフランス国民とともに祝ったことがある。2018年には安倍首相が主賓として招かれ自衛隊が先頭で旭日旗を掲げて行進した(首相は豪雨災害で出席中止)。
そもそも、明治維新もフランス革命やナポレオン、あるいはそれに触発されたビスマルクが創った近代国家をめざしたものである。にもかかわらず、フランス革命の時代に英国人として難癖をつけたエドモンド・バーグとかいう英国人の著書を保守主義のバイブルとか言って、フランス革命をネガティブな出来事として糾弾するのが日本の保守派の流行というのにはあきれるしかない。
そんなことを言っていると、世界から極端な修正主義史観だと受け取られかねないし、それは日本の政治に対する信頼を失わせ、国益を侵害するものだ。
江戸時代への過剰な賛美も同様だ。NHKが大河ドラマで江戸の社会をどのように描くのかも注目だが、人権無視で世界の文明に背を向けた江戸時代について、正しく科学的な評価がされるべきである。
出る杭は100%打つ…家康が「無能なトップに忠誠を誓う部下」を大量生産するために考え出した驚きの屁理屈
江戸時代が260余年も続いた本当の理由
PRESIDENT BOOKS
童門 冬二
約260年つづく維持管理体制を築き上げた天下人・徳川家康。家康は長くつづく体制をどう築いたのか。作家の童門冬二さんは「安定を最も重要視した家康は『出る杭を“必ず”打つ』ために、人間の欲望を理解し、巧みな支配で人を操った」という――。
※本稿は、童門冬二『徳川家康の人間関係学』(プレジデント社)の一部を再編集したものです。
人間の切実なニーズを逆用する
家康の、「人間の切実なニーズを逆用する方策」にはさまざまあるが、目に見えるものとしては藩をつくったことである。藩という言葉の意味は、もともと囲いとか垣根の意味だ。これは分断思想の表れである。
そうなると交通も自由にさせない。関所を設けた。川の渡しには番所を設けた。日本人が旅行するのにはそれぞれ目的が必要とされた。目的いかんによっては旅行を認めない。特に庶民は伊勢神宮に行くとか、高野山にお参りするとか信仰上の理由や家族に病人が出た、などという他は全く身動きできなくなった。
特に大都市の町々や各長屋では、入口に木戸が設けられた。午後6時に締まり翌朝午前6時に開けられる。したがって夜の12時間は完全に牢屋の中に入っているのと同じだ。檻の生活である。
家康はこうして日本中に檻をつくった。檻の中に人びとを閉じ込めた。これが徳川家康における、「日本の維持管理体制の確立」の実態である。
好都合な「武士の心構え」を植えつける
徳川家への忠誠度を物差しに、また人間の欲望を抑えつけてその逆エネルギーによって体制を維持する、ということは終始守られた。そのことを最も端的に表したのは、
「幕府の政策を批判してはならない」
ということである。
批判者はつぎつぎと罰された。もちろん、幕府に背くような大名は仮借なくその疑いだけで潰された。この物差しによって次々と滅ぼされた大名の家臣が失業して浪人問題を引き起こしたことは周知の通りだ。
こういう幕政への批判をあまねく食い止めるために徳川幕府は教育を重視した。教育といっても後代に教えるべきことはもう決まっていて、中国の朱子学である。
朱子学を持ち込んだ最大の理由は、
「武士の心構え」
が設定できたことである。
武士の心構えが設定できたというのは、徳川時代に入って新しく忠義の観念を植えつけたことだ。
「忠義」を生み出して乱世を統治
忠義の観念とは、
「君、君たらずとも、臣、臣たるべし」
という精神的な掟である。
つまり江戸時代の前は忠義という観念はあまりなかった。元禄年間にはいってさえ赤穂浪士の仇討ちが、堀部安兵衛によってはじめて君主の位置を父と同様に置き、仇討ちの対象にできるという理論構成をしたことでもわかる。
戦国の気風を多く残す江戸時代初期はまだ下剋上の論理が横行していて、
「部下の生活を保障できない主人は主人ではない」
という現実重視の考え方が支配的だった。
が、これでは困る。というのはもう日本の国を自由に切り取りできるような状況は去った。大名にしろ農民にしろ所有する土地は全部固定されてしまったのである。勝手に自由にはできない。そうなってくると、かつてあれほど一所懸命の思想で武士が目の色を変えていた土地を自由に与えたり取ったりすることもできない。全般が“固定社会”に移行しつつあった。
「トップに都合の良い」精神を教育するシステム
そういう中では物欲をおさえるためには精神力によらなければならない。その精神力をなににするか、という点で徳川幕府は、「武士における忠誠心」というものを考えだしたのである。それも、
「たとえ主人が能力を欠いていても、主人は主人だ。臣下は忠節を尽くさなければならない」
というトップにとってはなはだ都合の良い論理をつくりだした。
こうしておけばたとえ生活の保障能力を欠いているトップでも、仕える部下は全能力を発揮してこれを支えなければならない。トップが充分に能力を発揮できないのは部下が仕事を怠けているからだ、それは忠誠心が足りないからだ、という論法である。
この忠義を核にした武士道は武士だけに限らず、町人社会にも適用された。元禄期ころ、多くの商人が家訓をつくっているが、その根底にあるのは武士道と同じ考え方である。こうして子どものころからすべての日本人に、君に忠、親に孝という身分と長幼の序をシステム化した教育がおこなわれ、またそれを実行するシステムが強固につくられた。
したがって徳川幕府における進行管理は、物心両面によって蟻の這い出る隙間もないような緻密な制度によっておこなわれたといえる。
反乱者を挑発→弾圧して「見せしめ」
が、それだけで足りず幕府は時折、大名や旗本や浪人や庶民を挑発した。つまりこんながんじがらめの社会制度の中で、これでもかこれでもかと人間一人ひとりの自己主張や人格尊重欲を抑圧するような政策をとれば反発する人間も出てくる。
しかし幕府はそういう反発をすべて抑え込もうとして制度を厳しくしているわけではない。固い教育をしているわけではない。
ときには、「反乱者が出たほうがいい」と思っていた。鎮圧を大々的にPRして弾圧の実績が示せるからである。これにひっかかって由井正雪や多くの浪人たちが乱を起こした。島原の乱も考えようによってはその例だ。抑圧と疎外に対する反抗心の爆発である。
が、幕府はすでに強大な武力と権力を持っていたから、ものの見事にこれを鎮圧していよいよ幕府の勢威を固めた。
これは生きた国民へのテキストであった。日本人はこういう実例を次々と見せられて、大名も旗本も浪人も庶民もすべて抵抗心という牙を失っていった。皆丸く摩滅していったのである。徳川時代の太平はそれで保たれた。
足を引っ張りあう評価システムを確立
戦国時代と違って太平時代の業績評価は、やはり民をどのように平穏に治め、また幕府をどのように富ませ、いかに大過なく毎日を過ごせるか、そういう施策をおこなった人間が優遇された。
つまり人間を「小さく小さくなあれ」の境地に追い込み、また無事大過なく日常が過ごせるような連中が最も高く評価された。
ことを起こす人間は嫌われた。出る杭も必ず打たれた。後世のお粥社会が巧妙に形成されていった。
業績評価は鍋の中で煮られてアイデンティティを失ったふにゃふにゃのお粥たちがおこなうそれであった。お粥は米粒を嫌った。だから米粒が握り飯になるとすぐみんなで寄ってたかって足をひっぱった。徳川社会というのは、汁の中に権限と責任を吸いとられたふにゃふにゃの米粒の社会であった。
したがって業績評価は、
「無事大過なく生涯をまっとうできるかどうか」
という物差しによって判断されたのである。
常に全員を「慢性飢餓症」の状態にする
徳川家康は人間を、「慢性飢餓症」の状態に置いて、逆流してくるパワーを国家経営のエネルギーに使った。かれは日本人を決して満腹にはさせなかった。お腹が満たされるとろくなことは考えない。
「人間は常に飢えさせておくに限る、腹八分目にすべきだ」
という考えだ。かれ自身がいつも粥ばかり食っていたからそういうことを他人に強いてもなんとも思わなかったのだろう。
また、小さい時からかれは人質になって成人するまで他人の冷飯を食った。それだけに性格が暗くなり、他人をいじめてもあまり感じない人間になっていたのかもしれない。人質時代の報復を日本人全体に及ぼしたといってもいい。
この辺に、かれの組織力の限界、あるいはマイナス面の原因があった。
江戸幕府が260余年で限界を迎えた理由
たとえ二百六十余年間維持されたとしても、結局、徳川幕府は潰滅してしまった。
その原因は、幕末になって急に生じたのだろうか? そうではない。その原因ははじめからあったが、歴代の実権者がなんとか抑えてきたのだ。おもに制度と力によって。だから、「クサイものにはフタをする」という面もたくさんあった。
これはやはり、徳川家康の組織力の限界であると同時に、“組織される側”から見ると、万人が家康の組織力、あるいは人物を全面的に支持していなかったことを示している。家康の組織力の限界つまり徳川幕府のマイナス面である。
家康がつくりだした、日本の、「維持管理型組織」とは、「幕藩体制」である。幕府という親ガメと藩という子ガメで、日本の社会と人間を、中央=地方という体制内に全部封じこめようということだ。このため、家康は信長や秀吉が廃止した関所や番所を再び復活した。さらに藩をつくった。「藩」という「かこい」を列島上に二百数十つくった。
が、こういう“容れもの”だけで、それまでに高まっている国民のニーズを抑えることはできない。よりよい生活を求める。解放された人間の欲望は無限の増殖作用を起こす。
ハードとソフトで、欲望を抑え込む
制度というハードな“容れもの”(環境・社会)への制約だけで、民衆の欲望が抑えきれない、とみた家康は、そこで今度はソフト面に目を向けた。つまり、「人間の意識の抑圧」である。
このために、かれはどういう組織力を発揮したのか? 一言でいえば、そのためのかれの組織力は、「その時代に生きていた人々のニーズを逆に抑え込む」ということであった。
その時代に生きていた人々のニーズを逆に抑え込むというのは、ニーズを実現しないということである。ニーズを否定する方向で組織づくりをし、否定されたニーズが頭をもたげようと壁を破り土を起こせないように、壁を厚くし、覆土してしまうということである。
日本人の欲望を抑え込むことによって、「高密度管理社会」といわれる、「幕藩体制」を実現したのである。
中国「反日」暴徒化、日系企業〝襲撃〟に警戒 処理水放出めぐり大使館にレンガ片…岸田政権、早急な「脱中国」が必要
2023年8月29日
中国で尋常でない「反日」暴挙が続いている。東京電力福島第1原発処理水の海洋放出が始まってから、中国各地の日本人学校に石や卵が投げつけられていたが、北京の在中国日本大使館にレンガ片が投げ込まれていたことが分かった。香港では、岸田文雄首相の〝遺影〟のような写真を掲げた抗議デモも発生した。中国では過去にも「反日」が過熱し、暴徒化した群衆が日本大使館や日系企業などを襲撃したことがある。中国では不動産危機が金融危機に発展しつつあり、習近平政権が人民の不満を日本に向けさせた可能性もある。日本政府は在留邦人に警戒を呼び掛けているが、それで十分なのか。識者からは、非科学的「狂乱」への毅然(きぜん)とした対処と、早急な「脱中国」の必要性を指摘している。
◇
「中国発とされる多数の迷惑電話や、日本大使館、日本人学校への投石などが行われている。『遺憾なことである』と言わざるを得ない」「日本政府として邦人の安全確保に万全を期す」
岸田文雄首相は2023年28日夜、官邸で記者団に、中国政府の対応をこう批判した。外務省の岡野正敬事務次官も同日、呉江浩駐日中国大使を外務省に呼び出し抗議した。中国の暴挙は異常というしかない。
罪のない子供たちが通う日本人学校への攻撃だけでなく、北京の在中国日本大使館の敷地内に2023年24日、レンガ片が投げ込まれていた。日本政府関係者が28日に明らかにした。ネット上では、日本製品の不買運動を扇動する動画が数多く投稿されている。福島県内の飲食店や市役所などには、中国発信とみられる迷惑電話が相次いでいる。
在中国日本大使館は、中国に住む邦人らに対し、「外出の際、不必要に日本語で大きな声で話さない」などと注意を呼びかけた。外務省は、中国に滞在中だったり、訪問を予定している日本人への注意喚起を行っている。
宮崎氏「2012年は『反日』暴力デモ」
今回の「反日」暴挙をどう見るか。
中国事情に詳しい評論家の宮崎正弘氏は「共産党主導の『反日』行動だろう。日本への抗議電話も、ネットで具体的な連絡先や嫌がらせの手順などが指令として回っているようだ。現時点で、大規模なデモや襲撃はないが、同じように官製だった2012年の『反日』暴力デモでは、最終的なターゲットが日本から中国共産党に移る大騒動になった。民衆の一番の不満は、習国家主席の失政や独裁だ。共産党政権はそれを警戒して、慎重にガス抜きをはかっている」と分析する。
中国ではこれまでも、「反日」デモが繰り返されてきた。
中でも、民主党政権下の12年、沖縄・尖閣諸島の国有化などに反発した「反日」デモは、過去最大級にエスカレートした。デモ隊が日本大使館や日系スーパー、日系企業の工場や店舗を襲撃し、大規模な破壊・略奪行為が発生した。日本車を狙って襲撃する事件も相次いだ。
今回の暴挙について、違う背景を指摘する声がある。
M&Aのプロで、中国事情に詳しい経済安全保障アナリストの平井宏治氏は「中国の念頭にあるのは『半導体』ではないか。半導体分野での技術的躍進が、台湾侵略やアジアでの覇権確立をもくろむ中国の国家戦略の根幹となっている。処理水放出への抗議を装って日本に無理難題をふっかけ、中国の国家戦略の障害になっている『日米協調の半導体規制』を分断する狙いだ。現地の情報によると、雰囲気はかなり不穏だ。さらにエスカレートする恐れがある。『反日』攻撃は当分、やまないだろう」と語る。
共産党独裁で覇権拡大を進め、ウクライナ侵略を続けるロシアとも連携する中国とは違い、日本や米国は「自由」「民主」「人権」「法の支配」といった基本的価値観を共有している。
平井氏は「中国リスク」の高まりを受け、「中国デカップリング(切り離し)を急ぐべきだ」といい、説明する。
「いざとなれば、中国国内の日系工場は中国に接収されることを想定すべきだ。日本国内や東南アジアに製造拠点を移転することが急務だ。中国には『法の支配』という常識が通じず、経済で圧迫を加えてくる。今回、日本産水産物の禁輸で、日本が打撃をこうむる事態が懸念される。『脱中国』を推し進めなければならない」
外交は相互主義である。日本も経済的に中国へ反撃すべきではないか。それができない、日本人は、いじめ(出る杭は打たれる)にあうとただ黙っている、と中国人は見透かしている。それが「日本の失われた30年間」に表れている。
福井県立大学の島田洋一名誉教授は「中国共産党が重視するのは、何よりも『行動』だ。口先で反撃しても、相手に付け込まれるばかりだ。禁輸措置に対しては、同様の禁輸措置で対処するなど、〝痛み〟を感じるかたちで反撃しなければならない。(中国に政策は目には目を、歯には歯を、だ!)ただ、岸田政権にはそうした気配をまったく感じない」と危惧する。
島田氏「中国の経済的威圧があれば自由主義国が連携して対処」
親子2代で超党派の日中友好議員連盟会長を務め、「政界屈指の親中派」と呼ばれる林芳正外相だが、今回も目立たない。
公明党の山口那津男代表は2023年28日から訪中予定だったが、中国側から「当面の日中関係の状況に鑑み適切なタイミングではない」と連絡があり、訪中延期となった。
事態の長期化が予想されるが、日本は非科学的な中国に一歩も譲歩すべきではない。
島田氏は「中国の処理水放出への批判には科学的根拠がなく、『反日』カードの典型例だ。放出計画は、国際的な安全基準に基づき、世界保健機関(WHO)や、国際原子力機関(IAEA)の評価を受けている。中国の行為は経済的威圧だ。2023年5月の広島G7(先進7カ国)サミットでは、『中国の経済的威圧があれば、自由主義国が連携して徹底対処する』ことで合意した。今回は最初のケースであり、岸田首相はG7議長国として、自由主義国の対応を主導しなければならない」と語っている。
【北京=三塚聖平】中国政府は24日、東京電力福島第1原発処理水の海洋放出開始を受け、同日から日本産水産物の輸入を全面的に停止すると発表した。放出開始を受けた対抗措置の一環。習近平政権は処理水放出で対日圧力を増し、日中関係を巡る新たな不安定要素をつくりだしている。
中国税関総署が発表した。発表は、処理水放出が「食品安全に引き起こす放射性汚染リスク」を防ぐための措置だと主張。「中国の消費者の健康を守り、輸入食品の安全を確保する」と強調しており、水産物以外の食品についても検査を強化する可能性がある。中国は放出開始前の7月から日本産水産物などに事実上の輸入規制を敷いている。
生態環境省は24日、中国が管轄する海域におけるモニタリングを強化すると表明した。海洋放出による影響を調べるためとしており、中国独自のモニタリング結果を批判材料とすることが予想される。
中国外務省の汪文斌報道官は24日の記者会見で、海洋放出開始に「断固とした反対と強い非難」を表明。日本側に抗議したことを明らかにした。日本に対し「生態環境の破壊者、世界の海洋環境の汚染者」などと非難の言葉を連ねた。国際原子力機関(IAEA)が処理水の放出計画を「国際的な安全基準に合致する」と結論付けた包括報告書を出したことなどについては触れていない。
習政権が、歴史問題などと並ぶ新たな「対日カード」に処理水放出を位置付けているとの見方もある。汪氏は「日本は国際的な被告席に自らを置き、長期にわたって国際社会の非難を受けることになる」との見解を示し、長期的に問題視する姿勢を見せた。日中間では、8月中に公明党の山口那津男代表が訪中の予定ほか、9月にはインドネシアで岸田文雄首相と李強首相の会談も検討されている。中国側はそうした場で処理水放出について批判を展開するとみられる。習政権は東南アジア諸国連合(ASEAN)加盟国など各国政府にも懸念の共有を呼び掛けるが、現時点で広がりは見せていない。
中国の原発、処理水で上限超え トリチウム、7割の地点で
2023年8月8日
 |
| 「中国の原発の汚染水より数値が高いじゃないか!」 |
【北京共同】中国の原発から2021年に放出された排水に含まれる放射性物質トリチウムの量が計17カ所の観測地点のうち、7割を上回る13カ所で東京電力福島第1原発処理水の年間放出予定量の上限を超えていたことが8日、中国の公式資料で分かった。福島第1の処理水の最大10倍相当を排出した原発もあった。
福島第1の処理水は溶け落ちた炉心に触れており、中国は危険だと大々的に宣伝。7月ごろから日本の水産物に対する全面的な放射性物質検査を始め、放出前から事実上の輸入規制を課す対抗措置を開始した。日本は中国の原発から出る放射性物質の状況を把握しているが通関検査の強化などは行っておらず、中国の対応の不合理さが改めて鮮明になった。
原子力専門書「中国核能年鑑」が13原発から排水されたトリチウムなどの放射性物質に関する計17カ所の観測データを記載。浙江省の秦山原発は21年の1年に218兆ベクレルと、処理水の海洋放出計画が設ける年間上限「22兆ベクレル」の約10倍に当たるトリチウムを放出していた。トリチウムの除去は技術的に難しく、海外でも基準値以下に薄めてから海洋や大気中に放出している。中には、福島第1の排出量を大きく超過する事例も少なくない。
経済産業省によると、中国では秦山第3原発が約143兆ベクレルと福島第1が予定する6・5倍、陽江原発は5倍、紅沿河原発は4倍。韓国でも月城原発が3・2倍、古里原発が2・2倍に上る。
欧米では、数字がさらに跳ね上がる。フランスのラ・アーグ再処理施設は454・5倍。カナダのブルースA、B原発は54倍、英国のヘイシャム2原発は14・7倍とけた違いだ。
英国研究者ら「処理水のトリチウム濃度は、中国の放出の半分以下」
2023年8/24(木) 1:13配信
日本政府が早ければ24日に開始することを決めた福島第一原発の処理水の海洋放出をめぐり、イギリスの研究者らが23日、オンラインで会見を開きました。「トリチウム濃度は、中国の原発から放出される水の半分以下の数値であり、人体への大きな影響はない」として、科学的見地から問題はないとの見解を示しました。
23日に、オンラインで会見を開いたのは、イギリスで福島第一原発の事故について研究している大学教授らです。
会見で、チョルノービリ原発の事故と、福島第一原発の事故の環境への影響を研究しているポーツマス大学のジム・スミス教授は、「今回放出される予定の処理水のトリチウム濃度は、中国の原発から放出される水の半分以下の数値であり、人体への大きな影響はない」と述べ、放出について、科学的見地から問題はないとの見解を示しました。
また、「放射線の影響について研究している人々の中で、今回の処理水の放出に反対している人はいないと思う」とも述べた上で、中国の日本産の食品への規制強化について、「科学的理由は何もない。経済的影響は、健康への直接的な影響よりもはるかに深刻で、規制の強化は漁業関係者の生活を損なうものだろう」と批判しました。
さらに、処理水の放出計画の信頼性については「人々が東京電力の対応を信用していないようだが、IAEA(=国際原子力機関)が独立した研究所にサンプルを送り、問題がないことを確認しているため、中国、韓国のように隠蔽(いんぺい)するのは非常に難しいだろう」としています。
IAEA(=国際原子力機関)も22日、「放出は国際安全基準に合致していて、環境などへの影響は無視できるものだと結論付けている」とする声明を発表しています。
福島市に不審電話770件 98%が「中国発信」 「気味悪い」と飲食店主
2023/8/28
東京電力福島第1原発処理水の海洋放出開始以降、中国からとみられる不審な電話が多数入っている問題で、福島市は28日、市役所や市内の公立学校などに入った着信件数を公表した。それによると、24日から27日までの4日間で着信は770件。98・8%に当たる761件が中国の国番号「86」で始まる番号からの着信で、業務に支障をきたしたケースもあったという。
福島市危機管理室によると、4日間にあった770件の不審電話のうち「市役所・出先機関」に計584件、「学校・公共施設」には186件で、市内の公立小中学校にも75件の着信があった。
電話に出ると「もしもし」「こんにちは」などと片言の日本語を話した後、中国語などの音声が流れたり、中国語と思われる言語で一方的に話して切れたりするケースが大半。中国語ができる職員が偶然、電話にでると「処理水を何でみんなの海に流すのか」という意味の中国語を話していたという。通話の背後で笑い声がしたこともあった。
福島市では「仕事上、着信した電話は取らないといけないので困る。夜間、警備室のスタッフが寝られないこともあった」(危機管理室)といい、「28日も不審電話は入り続けている」(同)と話す。
一方、福島県内の飲食店にも迷惑電話が相次ぎ、県警では注意するよう呼び掛けている。福島市で飲食店を営む男性(38)の店の電話には、27日未明に不審な着信があった。閉店後で着信時には気付かず履歴で分かった。着信は午前2時28分から2分間で9回。7回は非通知、2回は中国を意味する国番号「86」が表示されていた。
男性は「話には聞いていたが、自分の店にかかってくるとは」といい「当事者になると不気味。店のホームページなどに電話番号を載せるのに抵抗はなかったが、今後は考えないと…」と困惑していた。
東京電力福島第1原発処理水の海洋放出開始後、放出とは無関係な日本国内の個人や団体に中国から迷惑電話が相次いでいる問題で、福島県でも飲食店や市役所などに中国の発信とみられる迷惑電話が相次いでいることが26日、県警などへの取材で分かった。被害者によると「ショリスイ」「バカ」などの発言があった。県警は県や市と連携して実態把握に努めているとした上で「必要な調査・捜査を行う」としている。
福島県内で複数の飲食店を経営する男性(42)によると、処理水放出のあった24日の翌25日に中国の国際電話の国番号「86」から迷惑電話が多発。多い時には1分ごとにあった。外国語中心だが「ショリスイ」「バカ」「シネ」などの単語も聞こえた。
福島市の木幡浩市長は26日、自身のフェイスブックで、市役所に約200件の「嫌がらせ電話」がかかってきたと表明。小中学校、ホテルや旅館にもあり「多いところは1事業所だけで100件以上」とした。多くは中国の番号だったといい、政府に対応を求めた。
福島市の木幡浩市長は26日、東京電力福島第1原発の処理水の海洋放出後、市役所などに中国語での迷惑電話が相次いでいると自身のフェイスブックに投稿した。「わが身の所業をわきまえぬ困った国だ。福島は原発事故の被害に加え、事後処理の負担も負わされている」と記し、政府に対応を求める考えを示した。
木幡氏は迷惑電話の実態について「市役所では2日間で約200件。小中学校にもかなり来ているようだ。飲食店やホテル・旅館も多く、多いところは1事業所だけで100件以上も。多くは+86(中国)発信で、中国語」と説明した。
【北京=三塚聖平】東京電力福島第1原発処理水の海洋放出開始後、放出とは無関係な日本国内の個人や団体に中国から迷惑電話が相次いでいることが26日、分かった。北京の在中国日本大使館が、中国の短文投稿サイト、微博(ウェイボ)で明らかにした。日本大使館は中国政府に対応を求めたとしている。
日本政府関係者によると、日本の一部施設などに中国の国番号「86」で始まる番号からの着信が相次いだ。東京都江戸川区の区総合文化センターのほか、医療機関、飲食店など放出とは無関係な施設などに電話が掛かってきていることが確認されている。海洋放出への抗議とみられる。
中国の交流サイト(SNS)では日本への抗議や、日本製品のボイコットを呼び掛ける投稿もみられる。
また、日本大使館は26日、大使館で同日に開催予定だった日本人ピアニストのイベントを延期した。「不測の事態を避けるため」と説明している。日本大使館周辺では、中国側の制服や私服の警察関係者による警備が強化されている。
日本大使館は在留邦人に対し「大使館を訪問する必要がある場合は、大使館周囲の様子に細心の注意を払う」といった注意を呼び掛けている。現時点で在留邦人が処理水放出に関連してトラブルに巻き込まれたり、日本大使館周辺で抗議デモが行われたりといったことは確認されていない。2012年には尖閣諸島(沖縄県石垣市)の国有化を受け、北京など中国各地で大規模な反日デモが起きた。
日本人の知らない旧満州「9.18」反日施設の実態
その建物には「勿忘"九・一八"」と記されていた
青沼 陽一郎 : 作家・ジャーナリスト
著者フォロー
2020/09/18
米中関係が悪化の一途をたどる中で、日本は複雑な立ち位置を迫られる。
いうまでもなく、アメリカは日本の同盟国だ。隣国の中国は、日本の最大の貿易相手国だ。
アメリカはあらゆる制裁を打ち出して、中国の覇権主義を切り崩しにかかる。9月15日から、中国の華為技術(ファーウェイ)への半導体輸出規制が発効されたのもその1つで、日本の半導体メーカーもファーウェイ向け出荷を停止している。
中国にしてみれば、本来ならば今年4月に予定されていた習近平国家主席の国賓としての来日にみられるように、昨今の日本との友好的な関係を維持して、強硬的な姿勢を貫くアメリカとの橋渡し役にしたい。そう考えていてもおかしくはない。
その日本では、安倍晋三内閣の長期政権が幕を下ろし、16日に菅義偉内閣が誕生したばかりだ。安倍前首相のように両国首脳と友好的な関係を演出できるか、定かではない。
そうした中で迎える9月18日。この日は、中国にとって忘れてはならない日だ。89年前に、満州事変の勃発した日だからだ。それを「反日」と結びつけて象徴する場所が中国にある。
「忘れる勿(なか)れ“九・一八”」
1931年9月18日、奉天(現在の瀋陽)郊外にある柳条湖付近の南満州鉄道の線路上で爆発があり、これを中国軍の犯行として関東軍が軍事行動に出る。いわゆる柳条湖事件だ。これをきっかけに、翌年には満州国が建国される。
満州国の首都「新京」は、現在の中国・吉林省長春にあたる。今、長春を訪れると、満州国の皇帝だった愛新覚羅溥儀の皇宮も残っていて、見学することができる。ただし中国では、これを「偽満州国皇宮」と呼んでいる。偽りの国ということだ。
しかも、そこは「偽満皇宮博物院」「長春溥儀研究会」と記された門と鉄条網に囲まれた中に管理されてある。
溥儀の皇宮は、三角屋根を載せた西洋風の2階建ての四角い建物が敷地の中にいくつも並んでいる。それぞれが、溥儀の居室であったり、執務や会見のためのものであったり、あるいは夫人の生活空間であったものだ。内装や家具は当時のものをそのまま保存している。溥儀専用の散髪室もある。
そこで中心になるのは、「緝熙楼(しょうきろう)」と呼ばれる溥儀の暮らした居住空間としての建物だった。ところが、その正面玄関前のスペースには、そこをすべて覆い尽くしてしまいそうなほど、巨大な黒色の石盤が増設されてあった。
「勿忘“九・一八” 江澤民」
そういう文字が金色で彫り抜かれている。署名のとおり、江沢民・元国家主席の揮毫だ。
「忘れる勿(なか)れ“九・一八”」
9月18日を中国人ならば忘れてはならない――。
もう1つの半日博物館の存在
歴史的保存物に、あえてこのようなものを置き、反日教育を推し進めた江沢民は、溥儀の皇宮の脇にもう1つ「東北淪陥史陳列館」という巨大な博物館を建てている。エントランスホールには、やはり「勿忘9・18」の文字を掲げ、その下に「日本侵略中国東北史実展覧」とあった。つまり、日本の中国侵略の歴史を伝えるものだ。
順路に従って最初の展示スペースに入ろうとすると、間口の脇の壁に中国語と英語とそれに日本語で文章が書かれていた。中国語で「前言」、日本語では「始めに」とあるそこには、こんな記載があった。あえてその全文を示してみる。
<炎帝と黄帝の子孫である中国人は、1931年9月18日、日本が凶暴にも内外を驚愕させる“九・一八事変”を引き起こし、武力で中国東北を侵略・占領して偽満州国をつくり、ファッショ的植民地支配を行って東北人民を奴隷化し、ほしいままに資源を収奪すること14年の長きにわたったことを、誰ひとりとして忘れるはずはない。
しかし、日本国内の一部の人々はこの時期の歴史を正視することが出来ず、甚だしくそれを歪曲・否認さえしている。そして、現在、中国(国内)の青少年の中には、日本が中国侵略で行ったファッショ的植民地支配の蛮行が分からず、日本軍国主義、偽満州国とは何ものであるかが分からず、銃剣による支配下でかつて中国人民が受けた屈辱と苦難が分からず、抗日戦争の困難さと比類のなさが分からない者がすでに少なくない。
それゆえ、私たちは大量の歴史的図面、文物、また、歴史証人の証言などの音声・画像資料をもって展示を作り、当時の歴史を再現したが、これは歴史とはいかなる人も書き替えることが出来ないものであることを証明するためである。すなわち、広範な人民にこの悲惨で苦痛な屈辱の歴史をしっかりと記憶させ、国の強化を図って中華民族の偉大な復興を実現し、歴史の悲劇の再演を許さないためである。>
反日の意図が見て取れる。
そこから順路に沿って進むと、いかに日本が中国東北部の人々を虐げ、略奪し、植民地支配を進めてきたか、教えられる。
例えば「教育」について資料を陳列した場所には、説明に日本語でこうある。
<植民地支配を一層強化するために、日「満」は“日満一徳一心”“五族協和”などのいわゆる建国精神を大宣伝し、日本語を国語と定め、奴隷化教育を強制的に推進して、東北人民、特に青少年の民族意識を滅ぼし、彼らを日本植民地支配の忠実な従僕に育てあげようとした。>
ほかにも「宗教」の解説。
<偽満皇帝溥儀はさらに、自ら日本に赴き、日本を象徴する“肇国の祖”である“天照大神”を偽満皇宮に招きいれ、それを“建国元神”として祭り、また東北人民に信奉・礼拝するよう強制した。東北人民は民族と祖先を失うという辱めを被った。>
それに見合った資料や写真が並べてある。
また、「白色恐怖」というコーナーでは、こう説明している。
<東北の人民には人身の自由と言論の自由は全くなく、少しのことにも嫌疑をかけられ、逮捕監禁されることになり、いわゆる“思想矯正”を受けたり、さらには殺害さえされた。銃剣が支配する東北の大地は極度の白色テロにさらされた。>
これをすべて日本がやったことだと強調して、敵視するように「忘れる勿れ」としている。その象徴が「9・18」なのだ。
現代中国の"映し鏡"という皮肉
しかしながら、ここに書かれていることは、まさに今、中国共産党が新疆ウイグル自治区で行っていることに当てはまる。そう思えるのは私だけだろうか。
一国二制度を約束していた香港も、国家安全維持法が6月末の成立施行と同時に、瞬く間にのみ込んでしまった。今の香港に言論の自由はあるだろうか。
4月には、かねて埋め立て、軍事拠点化してきた南シナ海の南沙(スプラトリー)諸島、西沙(パラセル)諸島を、新たな行政区「南沙区」「西沙区」としたことにも、「侵略・占領」という言葉が当てはまる。
それでも、この展示を私が1人で観て歩いたときのことだ。日本人に気づいた閲覧客の視線がだんだんと冷ややかになっていくのがわかった。私の姿を見た子どもは、親に寄り添って何事かをささやく。まるでこちらを蔑視するように、視線は逸らさない。
「日本人がいる……」
そうささやいていたのだろう。
そういう国を日本は相手にしているのだ。そんな国が今、アメリカと世界の覇権を争っている。そのことを忘れてはならない。(一部敬称略)青沼 陽一郎さんの最新公開記事
なぜ中国はヒステリックになったのか
中国が真のリーダーになるために必要なこと
中村 繁夫さんの最新公開記事
露骨になった中国
2021年11月10日、北京で安倍晋三首相と、中国の習近平・国家主席が初めて本格的な会談を行った。曲がりなりにも、首脳会談と呼べる対話が行われたのは約3年ぶりだという。10日の首脳会談をめぐる細かなやりとりは、専門家に任せるとして、長年、中国と向き合ってきたビジネスマンとしての立場から、ひとこと言わせていただく。
今回のコラムでいいたいのは、結論から言えば、昔の中国は思慮深かったが、最近の中国は子供っぽいところが目立つ、ということだ。「何を言っているんだ、いろいろ原因をつくったのは日本ではないか」と反論する向きもあるかもしれない。だが、35年ほど中国とのビジネスを行っている身からすると、今の中国は、昔とはすっかり変わってしまった。
もともと中国の外交的な手法とは、相手が弱いと見るや、カサにかかって責め立てる。多少の論理の飛躍があろうがなかろうが、強弁や詭弁はいわば、お手の物だ。だが、昔はそうした手法は、露骨には見せなかったものだ。
私が初めて中国の土地を踏んだのは1979年の春である。その前年の1978年の10月、鄧小平氏が初めて日本を訪問した。日中平和友好条約の批准書を交換するための訪日だったが、その存在感が一気に日中の歴史問題を越えて和解の合意まで成功させてしまった。
尖閣諸島の話もあったが、事実上、領土の話は、「時間を掛けて解決しましょう」とアッサリ「棚上げ」にしたうえで最も重要な国交回復を優先させた。百戦錬磨の老獪さを余すところなく発揮した形で、大所高所に立った決断を行った。日本中が沸き返ったのは言を待たないが、私自身も中国が大好きになって、中国貿易に本格的にのめり込むようになったのは、この時である。
日中友好条約がサインされた1979年前後の日中貿易では、年に2回の広州交易会で商談が行われ、大半の取引はその場で決まった。当時の貿易窓口は対外貿易部傘下の組織が行ったので全国から集まった優秀なエリートが貿易担当者であった。
当時の日本の対中輸入額は4000億円程度。一方で対中輸出は6000億円程度で、その差額は中国にとっての実質的な貿易赤字になるので、年間2000億円程度の協調融資を日本が行うといった仕組みだった。それ以外にも、実質的な戦後賠償の一環として多額のODA(政府開発援助)予算が中国に割り当てられた。技術ODAと称して日本の先端技術を「気前よく」供与したのもこの時期の支援策であった。従って、お互いの立場を理解し合い、双方とも相手を立てながら合理的な妥協点を模索したものだ。
こうした理想的な経済関係のバランスが崩れてきたのは、やはり1989年の天安門事件以降である。「社会主義市場経済政策」で中国の対外輸出が飛躍的に伸び、海外からの対中投資が加速するなか、中国は好調な経済を背景に外交姿勢も一層強気になっていったようにみえる。商売の交渉でも、言い方が良くないが、今まで猫をかぶっていた「化けの皮」が剥がれ始めた。日中友好ムードから一転して相手の足元を見透かすような商売が増えていった。
レアアース騒動に見る、日本の「オウンゴール」
ただ、2010年に尖閣諸島での中国漁船衝突事件が発生した当初は、レアアース(希土類)の禁輸と領土問題を絡めるという発想はなかったのである。この時、日本政府の訪中団(民主党の岡田外務大臣)があまりにレアアースにこだわり「手の内」を明かしたものだから「この手は使えるかもしれない」と反応を見るために輸出検査を強化したあたりから、問題は拡大していった。
中国政府は外交カードとして、レアアースの輸出禁止をした。日本の産業界は急にレアアース原料が輸入できなくなったので本当に困ったが、輸出許可制になっているから中国には幾らでも在庫があるのに入ってこないのである。その状況が半年以上続いた。
当然、日本の産業界は原料在庫も尽きて生産に支障が出てきたからパニック状態でレアアースの相場は10倍以上に跳ね上がった。当初は1キロ当たり10ドルのものが、何と150ドルまで高騰した話は、このコラムでも何度かふれた通りだ。私自身、レアアースを30年以上も取り扱っているが、単なる機能性素材の一種であるレアアースがニュースになり大騒ぎになったことには、本当に驚いた。
2011年の3月に東日本大震災が起こったのは、まさにそんな時である。だが、日本の国難という環境の中でも、中国は輸出政策を見直すどころか、さらに値上げをしてきた。戦国時代の上杉謙信のように「敵に塩を送る」のはどうかとしても、残念ながら、中国ビジネスはこうした発想はほとんどないことがわかる。「政治的に有利に交渉できるはずだ」と考える人々が優勢なのである。
戦前・戦中を知っている高齢の日本人なら、従来から「儒教の教えは中国から来たものだから」と中国に対するシンパシーが多少なりともある。だが日本の若い世代になると、東日本大震災という未曽有の国難の時を利用して「レアアース戦争」を仕掛けてくる中国の「いやらしさ」に反応せざるを得ないのだ。
だが皮肉なことに、結局、日本は代替材料を開発して、リサイクルの研究もできたし、新しい供給ソースも開発して、中国のレアアースの戦略的重要性は、ほぼ無くなりつつある。今や、インド政府との間で安定的レアアース供給の合意ができたので、逆に中国は「頭を下げて」原料を出したいとまで言ってきている。いわば中国のおかけで、日本はレアアース供給の多様化と、資源確保に成功しつつある、と言える。
「中国流」に惑わされるな
見方を変えれば、レアアースの一件でわかるように、日本のマスコミが考えるほど中国は戦略的な考え方を持っているわけではない。「石を池に投げて、その波紋を見て反応を測る」のが中国流なのだ。石を「ぽっちゃん」と池に落として、その波紋を見ながら決定する中国人の思考方法は、よく言えば柔軟性に富んでいるとも言える。だが短絡的で考えが浅いという見方もできる。
例えば、2014年8月の南沙諸島の海底油田を巡る問題について、中国はベトナムを舐めて、黙って探査船を送り込んだ。だが、その後中越艦船が衝突して一触即発の状況にまでなった。ベトナムの激しい反中デモとベトナム政府の外交力の前に、世界の世論がベトナム側についた風向きを見て、突如として事実上掘削作業を止めた。
この事件が典型的な中国流のやり口である。うまく行けば黙って実効支配をするし、調子が悪くなると、急きょ手を引くような手法が中国流なのだ。簡単に言えば、何事についても決めつけることはせず、融通無碍で、周りの影響を見ながら、「勝ち馬に乗る」思考方法である。
日本人と中国人は、同じ東洋人であり、歴史や伝統も共有している部分が多いので、よく思い違いをする。私が対中国を主体とするビジネスマンとして一番違和感を覚えるのは、平気で嘘をつく人が増えたことと、相手が困った時、自分の立場が弱ければ将来の見返りを期待して助けるが、自分の立場が強くなったと思えばカサにかかって叩いてくる発想である。
これは伝統的に競争社会の中で生き残る知恵であったから、仕方ないと思ってあげてほしい。彼らは地縁や血縁しか信じていない人も多く、相手の立場になって考える習慣が少ないのだ。
一方、日本人は「協調することが当たり前」だと思っているから、相手につけ込まれやすい。交渉になった時にも、まず日本側から妥協案が出てくることが多い。日本人は病的なほど揉めごとが嫌いで、交渉すること自体に慣れていない国民性がある。中国人はそれを知っているから、相手が下手(したて)に出ると、カサにかかってくるのだ。
外交やビジネスは「ギブアンドテーク」なのだから、何も「一歩も引くな」と言っているわけではない。だが、ビジネスの立場からも言わせてもらえば、ただ「下手に出ていればよい」、あるいは「もめたくはない」というスタンスで接していると、かえって結果は悪くなることのほうが多いということだ。
中国は日本の約26倍の国土に、13億人が暮らしている。一見大国に見えるが実際には沿海地域が開発されているだけで、内陸地方はまだまだ開発が進んでおらず、未成熟な国家である。日本人はついつい「中国の外交力は超一流」だと勘違いしている人が少なくないようだが、これは日本の大マスコミのミスリードである。
鄧小平の時代は、野心を隠しつつ、相手に近寄るという懐の深さがあった。逆にいえば、それだけ底知れぬ恐ろしさがあった。だが今の中国を見ていると、「国内の不平不満をそらすために、ヒステリックに相手に接しているとしか思えない」という外交のプロの意見は少なくない。
もちろん、底の深さ・浅さについては、日本も問われるところだ。だが、中国が真の世界のリーダーになるためには、足りないことだらけだ。こうした課題を克服して、中国は果たして鄧小平時代の懐の深さを取り戻すことができるのだろうか。
中村 繁夫さんの最新公開記事
 |
| 王毅外相とラジャパクリの腐った関係 |
巧妙化する「特殊詐欺」
「2023年ルフィ(渡辺優樹)事件」強盗事件、「失われた30年でフィリピンを悪党の天国」にしたのは誰か
実は、「悪党やグレーの輸出大国ニッポン」なのだ。
無知で弱い人間がルフィに騙される。
2023/02/03
マニラ首都圏パラニャーケ市ビクータンにある入管施設に日本のマスコミが押し寄せ、テレビカメラの放列ができている。日本で発生した連続強盗事件の指示役「ルフィ」が収容されているとみられているからだ。この10年ほどの間で、フィリピンにこれほど多くの日本メディアが殺到した例はない。中国の南シナ海の領有権問題にも、フィリピンの大統領選挙にもほとんど関心を示さない日本のテレビ局だが、日本人がらみの事件には時に強く反応する。
今に限ったことではない。かく言う私も新聞社勤務時代はフィリピンで事件を何度も追いかけた。紙面の扱いはだいたい、大統領に単独会見した時などよりよほどデカかった。
金さえあれば何でもできる
今回のきっかけは2023年1月19日、東京都狛江市で90歳の女性が殺害された事件だった。関東で強盗事件が相次いでいたが、死者が出たことで報道も一気にヒートアップした。連続強盗を指示していた「ルフィ(渡辺優樹)」を名乗る人物の通話履歴から、ビクータンに収容されている渡辺優樹容疑者(38)らが捜査線上に浮かんだ。
以後、テレビ局を中心に日本のマスコミが多数の記者やカメラマンを現場に送り込み、朝昼の情報番組、夜のニュース番組で収容所の様子や渡辺容疑者らの現地での行動を取り上げ、放映することになった。
フィリピンでは収容中に強盗や詐欺を指示できるのは、携帯電話が自由に使えるからだ。金さえあれば、携帯だけではなくさまざまな自由が手に入る。個室やエアコンを与えられ、収容所スタッフのエスコート付きで外食まで認められることが可能だ。そもそも日本への送還を回避するため、金を払って虚偽の事実で刑事告訴してもらったという報道もある。
こうしたことから日本の情報番組ではコメンテーターらが一様に「(フィリピンは)とんでもない国ですね」「腐敗は根深い」などと訳知り顔でコメントしている。
確かに、刑事司法がこの国でまっとうに機能しているとはいいがたい。1990年代半ばに私がマニラに駐在していたころ、刑務所や入管施設を取材した。収容されている日本人から支局に電話がかかってくることもあった。アジア太平洋戦争の戦犯として山下奉文将軍らが処刑され、BC級戦犯が長く収監されていたことでも有名なニュービリビッド刑務所(モンテンルパ刑務所)からの電話が多かった。
「面白い話があるからちょっと顔出さない」と言って、日本人受刑者が持ち掛けてくる。残留日本兵がどこそこで生きている、日本人の殺人事件の犯人を知っている、山下将軍が残したとされる「山下財宝」の地図を持っている――。こんな与太話がほとんどだ。面会ではお土産を要求されるのがつねだった。
機能不全のフィリピン司法
暇なときに刑務所に出向くと、私たち記者に限らず、受刑者の家族から売春婦までかなり自由に出入りしていた。当時も個室やエアコン、冷蔵庫を持つ囚人がいた。日本人死刑囚が刑務所内で現地の女性と知り合い、結婚した例もあった。看守を買収したり、なかには定期的に「手当」を払って部下のように使ったりしている「大物」受刑者もしていた。
私がそうであったように、初めてやってきた記者はその有様に驚き、「とんでもないこと」をレポートするが、収容施設の風紀は昔からほとんど変わっていない。今回の目新しさは「携帯電話で日本へ指示」というところだ。
このモンテンルパ刑務所が麻薬取引の国内の中心であるということは、フィリピン人の間ではなかば常識である。
所管する司法省は暴動などが起きたときだけ、通り一遍の対処をするが、本格的にメスを入れたことはない。定員の4倍とされる3万人近くが収容されており、数のうえでは囚人が看守を圧倒しているという説明もされるが、日本人には不思議なことだ。
看守で足りなければ、警察や軍を動員して一挙に内部を捜索し、個室や不要な設備などを一掃し、薬物や銃器を押収すればよさそうなものだが、「麻薬撲滅戦争」に力を入れた強面のドゥテルテ前大統領も手をつけなかった。
そのモンテンルパ刑務所が3カ月ほど前にも、地元で大きなニュースとなった。
発端は2022年10月3日夜、マニラ首都圏ラスピニャス市の住宅街の入り口で、帰宅中のジャーナリストのパーシバル・マバサ氏がバイクに乗った2人組に射殺された事件だった。ラジオ番組の人気キャスターでつねづね、ドゥテルテ前大統領やマルコス現大統領ら権力者を批判することで有名な人物だった。
マバサ氏殺害の実行犯は同月17日に逮捕された。近くの防犯カメラに映った自身の姿が公開されたために逃げ切れないと観念して出頭した。その男はモンテンルパ刑務所に収容されている仲介者から、55万ペソの報酬で殺害を依頼されたと供述したが、翌18日、この仲介者は刑務所内で不審死を遂げた。窒息死だった。
いわくつきの矯正局長
司法省は、国内の刑務所を統括するジェラルド・バンタグ矯正局長をマバサ殺しと仲介者殺害の容疑者として告発し、職を解いた。バンタグ氏の管理下にあった刑務所では、収監中の「麻薬王」らが相次いで死亡しており、マバサ氏はラジオでバンタグ氏の関与を指摘するとともに、矯正局長になってから豪勢な自宅に11台の車を所有するようになった汚職高官としても批判、豪邸を撮影するなどしていた。
バンタグ氏が解任された後、後任者がモンテンルパ刑務所を検査したところ、局長宿舎のプールの地下30メートルに長さ約200メートルにわたる未完成のトンネルが発見された。脱獄や禁制品の大量搬入も可能な規模だ。バンタグ氏は「潜水救助の訓練用」「山下財宝を探すため」などと弁明しているという。
さらに収容施設の1棟を抜き打ち検査したところ、携帯電話1142台のほか、銃器や刃物など武器類1324丁が押収された。缶ビール7512缶、現金5万5000ペソ、タバコ1019本、麻薬なども見つかった。まさに無法地帯の様相である。
バンタグ氏の矯正局長起用は当初から疑問視されていた。過去に首都圏で5カ所の刑務所長を務めてきたが、その間に未成年者の殺害を企てたり、飲食店で代金を払わずに発砲して起訴されたりしていた。
パラニャーケ刑務所時代には所長室で手榴弾が爆発し、10人の収容者が死亡する事件も起きていた。選任に際してドゥテルテ前大統領は「スキャンダルまみれの矯正局を管理できる『聖人』は見当たらなかった」と言い訳していた。
こうした司法現場の実態を知る大多数のフィリピン人にとって、日本人収容者が入管施設から携帯電話で日本に犯行を指示していたことなどさほどの驚きではない。ニュースとすれば、日本メディアが押しかけていることや司法省が対応に追われていることなのだ。
今回のビクータン収容所も日本のメディアが押しかけてから、抜き打ち検査をして収容者から携帯電話などを没収していたが、収容者が携帯電話を使っていることなど職員はみんな知っていたし、ほとぼりが冷めれば必ず復活するだろう。
それでは、なぜフィリピンの刑事司法はまっとうに機能しないのだろうか。
それは、途上国一般の事情として警官、検察官、刑務官、裁判官らの司法関係者をはじめとする公務員の給与が安く、それだけでは十分に生活できない状況がある。
給料の不足を権力で補う
為政者からすれば、給料は安いが、権力を与えているのだからそれで何とかしろという暗黙の含意があるともいえる。警官が交通違反者に賄賂を要求する姿は途上国ではよく見かける。裁判官も時に買収される。
私が社会部記者だった時に、暴力団員が航空機内に手榴弾を持ち込んで爆発させ、あわや墜落という事件がありフィリピンに出張した。現職や元職の警官、兵士らが関与していたこともあり、「元警官の犯行か」といった仮見出しを付けて原稿を送っていたが、地元の新聞では警官や兵士を見出しにとるケースはまれだった。誘拐や強盗といった犯罪に警官や兵士がからんでいても地元ではニュース価値がないことにしばらくして気づいた。
むしろ、こうした犯罪に手を染めるのは、銃器類の扱いに慣れていたり訓練を受けたりする警官や兵士であり、銃器も支給されているから珍しくはないというのだ。
ドゥテルテ前大統領は、任期中に警官と兵士の給与を倍に引き上げた。現在初任給は3万ペソ(約7万円)ほどとなり、一般の会社員より待遇はよくなったが、長年にわたり賄賂を当然視してきた悪習が一朝一夕に消えることはない。
途上国一般のこうした状況に加え、司法の機能不全の背景にはフィリピン特有の事情も垣間見える。罪に対する社会の寛容さ、当事者の悪びれなさが他国に比べても際立っているように思えるのだ。
国民の大多数を占めるカトリック教徒の「懺悔すれば赦される」といった精神が関係しているかもしれない。現場の公務員はもとより、政府の上層部からしてそうなのだ。
例えばマルコス大統領の母イメルダ氏は、不正蓄財などの罪で有罪判決を受けて保釈中の身だが、公衆の前に出ることに臆することもない。ファンポンセ・エンリレ元国防相は汚職で逮捕されたものの高齢を理由に釈放され、現在は大統領の法律顧問に収まっている。マルコス大統領自身、2030億ペソ(約4800億円)の相続税を未納のままだが、反マルコス派の人々を除けば、大多数の国民は気にする素振りもない。
政治家や公務員に限らず、国民の間にも「罪はあっても罰はなし」という不処罰の文化が根を張り、汚職や賄賂の広がりを助長しているように見受けられる。
フィリピンでの日本がらみの事件の多さについては、航空機で4時間足らずという距離の近さが大きな要因だし、ここ30年で日本の若者4割が非正規雇用で不安定な状態で独り者の孤独な独身者が多数いるのだ。最近の日本は武漢コロナ化で倒産したり、インフレと経済の停滞でお金に困った日本人は多い。素直で世の中の仕組みを知らない日本の若者は、犯罪の手口に騙されやすいし、フィリピン人から見れば格好のカモなのだ。さらにマニラ首都圏には日本人相手のカラオケや日本食店も多く、日本帰りで日本語をしゃべる人たちも歓楽街にたむろする。悪徳警官や収賄看守らの存在も含めて逃亡先としてのインフラが整っている。
これまでも多くの事件が日本で大々的に報道され、フィリピンは犯罪や逃亡先の「メッカ」としてのイメージが次の犯罪を呼び込んでいる面もある。1981年の旧・三和銀行茨木支店で女性行員が架空口座に1億8000万円を入金して横領後、マニラに逃亡した。
1986年には三井物産マニラ支店長が誘拐され多額の身代金が要求された。1995年の偽装水死保険金詐欺事件、1997年の
錢高組の所長が誘拐された事件なども耳目を集めた。日本人が被害者となった保険金殺人なら何件もあった。
日本とフィリピンの間で犯罪者引き渡し条約は結ばれていない。そのため、日本政府から引き渡しの要請があれば、その都度フィリピン政府が判断する。
マルコス大統領の訪日にらみ
フィリピンにとって日本は最大の援助国だ。中国などと比べて、援助に関する条件も寛容だ。両国間に大きな懸案もなく、フィリピン政府は日本政府の要請があれば大方は聞きいれる。容疑者引き渡しでも概して協力的といえる。
しかしながら、刑務所や拘置所側の事情もある。金を持つ容疑者や被告から賄賂を受け取っている刑務官や拘置所職員、その上司らからすれば金づるを失いたくない。そうした中で早期送還が実現するかどうかは、日本側の働きかけ次第となる。
今回の4人について、日本の警察はかねて強制送還を要請していた。渡辺容疑者(渡辺優樹)は2021年5月17日にマニラ首都圏パサイ市のホテルで国際手配犯として拘束され、9日後に強制送還が命じられた。ところが、女性・児童に対する暴力防止法違反の罪で起訴されていることが判明し、送還が延期されていた。
他に日本で逮捕状が出ている3人の日本人も、それぞれ現地の刑事事件で起訴されたため、収容が続いている。
日本でニュースが弾けて以降、送還へ向けた動きが急にスピードアップしたのは、2023年2月8日からマルコス大統領が日本を公式訪問するタイミングと重なったからだ。
収容所では金次第で自由が買えて、そこから犯罪が行われていたという「国の恥」が連日報道される中で、国家元首である大統領が訪日するのはフィリピン側はもとより日本政府にとってもいかにも間が悪い。ということで、送還協議が急速に進んだ。
強制送還するためには、地元裁判所で審理中の日本人容疑者ら(フィリピンでは被告)の事件を公訴棄却とする必要がある。三権分立ののりを超えて行政側が裁判所に認めさせようという話が進んでいるようだ。
送還逃れの偽りの告訴、それを取り上げて起訴する検察、行政の意向を汲んで公訴を棄却する裁判所……。残念ながらフィリピンの法治の現状だ。
「大統領訪日前の早期送還に努力する」とテレビカメラの前で話すレムリヤ法相は、2022年10月に長男が大麻所持の疑いで逮捕され、2023年1月に一部無罪となったものの道義的責任を取って辞任すべきだとの声も出ていた人物だ。4人の強制送還で仕事ぶりをアピールしたい事情もありそうだ。
フィリピンを「悪党の楽園」にしているのは誰か
収容所の実態からフィリピンを「悪党の楽園」と表現するテレビ局があった。法相に直接、そうぶつけるレポーターもいた。では悪党とは誰か。日本人である。
この国で日本人が殺人などの被害に遭うとき、加害側に日本人がいるケースがほとんどだ。逃亡先として選ぶ際に手引きするのも、多くは日本人だ。
こうした事件があると押しかける日本のマスコミの中には、地元で雇った助手やカメラマンだけではなく、時には官吏や囚人、容疑者にも多額の現金を渡してインタビューや情報を取る輩もいた。
フィリピンのよからぬ状況を上から目線で指弾するのはたやすい。しかしながら「犯罪の輸出」をしているのはほかならぬ日本である。実は、「悪党やグレーの輸出大国ニッポン」なのだ。天に唾せぬ謙虚さが報道にも求められるのではないか。
ルフィ(渡辺優樹)事件1
ルフィ(渡辺優樹)事件2
財務省公用車でひき逃げ、会社員逮捕 国会前、男性死亡―東京
時事通信 社会部2024年06月20日
 |
| 横断歩行者を引いて横転させた運転手は、突然興奮気味に「もう駄目だよ!この国は・・・」と発する。
|
 |
| 政府公用車で死亡事故を起こした運転手が、突然興奮気味に「もう駄目だよ!この国は・・・」と発する。 |
 |
| 政府関係者を長年乗車させていた運転手は、突然興奮気味に「もう駄目だよ!この国は・・・」と発するが、横断歩行者を引いたあなたがダメだった。東京都知事選まで後2週間だった。 |
2024年6月20日午後5時40分ごろ、東京都千代田区永田町の国会議事堂の南門前で、横断歩道を渡っていた男性が車にはねられ、病院に運ばれたが間もなく死亡した。
政府公用車は逃走し、約200メートル先の交差点付近で横転。警視庁は、自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)容疑などで、運転していたのは政府から委託されていた会社員濃畑宣秀容疑者(55)=中央区銀座=を現行犯逮捕した。濃畑宣秀は「パニックになった」と容疑を認めているという。
同庁によると、同容疑者は財務省の業務委託先の会社に勤務の運転手。乗っていた車は、財務省の政府公用車だった。
死亡したのは団体職員、大野泰弘さん(67)=新宿区四谷坂町。
濃畑容疑者は、大野さんをはねた後、官邸前の交差点を右折する際に横転し、車内にいるところを確保された。